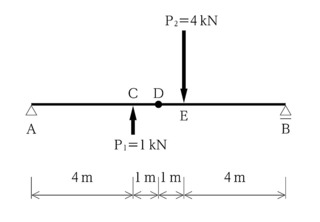第一次検定問題 [ No.28 ] 〜[ No.37 ] 解答解説
令和6年6月6日(日)
問題の解答の仕方は,次によってください。
ホ.[ No.28 ]から[ No.37 ]までの10問題は,全問題を解答してください。
[ No.28 ]
事前調査に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.山留め工事の計画に当たって,設計時の地盤調査が不十分であったため,ボーリング調査を追加して行うこととした。
2.鉄骨工事の計画に当たって,製作工場から現場までの搬入経路の調査を行うこととした。
3.鉄骨の建方の計画に当たって,日影による近隣への影響の調査を行うこととした。
4.解体工事の計画に当たって,発生する木くずを再生するため,再資源化施設の受入れ状況の調査を行うこととした。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.×
計画建築物が近隣に与える日影に関する影響は設計時に検討すべき事項であり、鉄骨建方計画においては関係が少ない。
4.◯
[ No.29 ]
仮設計画に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.仮囲いには,合板パネル等の木製材料を使用することとした。
2.仮囲いに設置する通用口の扉は,内開きとすることとした。
3.工事ゲートは,トラックアジテータが通行するため,有効高さを3.8mとすることとした。
4.仮囲いを設けなければならなかったため,その高さは周辺の地盤面から1.5mとすることとした。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.◯
4.×
仮囲いの高さは地盤面から 1.8m以上としなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)
[ No.30 ]
工事現場における材料の保管に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.ロール状に巻いたカーペットは,屋内の乾燥した場所に,縦置きにして保管した。
2.溶剤系のビニル床タイル用接着剤は,換気のよい場所に保管した。
3.ALCパネルは,台木を水平に置いた上に平積みで保管した。
4.左官用の砂は,周辺地盤より高い場所に,水はけをよくした置場を設置して保管した。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
ロール状に巻いたカーペットは、横置きにし、変形防止のため2〜3段までの俵積みで保管する。
2.◯
3.◯
4.◯
[ No.31 ]
建築工事の工程計画及び工程管理に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.基本工程表は,工事全体を一つの工程表としてまとめたもので,工事の主要な作業の進捗を表示する。
2.各作業の実働日数は,作業の総施工数量に1日当たりの施工数量を乗じて求める。
3.工程計画を立てるに当たり,その地域の雨天日や強風日等を推定して作業不能日を設定する。
4.暦日とは,実働日数に作業休止日を考慮した日数である。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
2.×
各作業の実働日数は,作業の総施工数量を1日当たりの施工数量を割って求める。
作業の総施工数量
= 1日当たりの施工数量 × 各作業の実働日数
3.◯
4.◯
[ No.32 ]
バーチャート工程表の一般的な特徴に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.各工事間の細かい作業工程の関連性が把握しにくい。
2.工程上で重点管理する必要がある作業が判断しやすい。
3.複雑な時間計算が不要であるため,作成しやすい。
4.各作業の開始時期,終了時期及び所要期間が把握しやすい。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
2.×
バーチャート工程表は、各作業の工程に対する影響がわかりにくく、重点管理作業やクリティカルパスが明確になりにくい。
3.◯
4.◯
[ No.33 ]
品質管理の検査に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.抜取検査は,ある程度の不良品の混入が許される場合に適用される。
2.抜取検査は,品物がロットとして検査できない場合に適用される。
3.全数検査は,不良品を見逃すと後工程に重大な影響を与える場合に適用される。
4.全数検査は,検査費用に比べて得られる効果が大きい場合に適用される。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
2.×
抜取検査とは、検品の方法で、生産、製造されたものの中から一部をサンプルとして抜き取って調べる方法のこと。一部検査ともいう。
品物がロットとして検査できない場合は、対称全部をくまなく調べる方法(全数検査)をする必要がある。
3.◯
4.◯
[ No.34 ]
品質管理のための試験及び検査に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.鉄筋工事において,ガス圧接部のふくらみの直径の確認は,デジタルノギスを用いて行った。
2.タイル工事において,タイルの浮きの確認は,テストハンマーを用いて行った。
3.木工事において,造作用木材の含水率の確認は,高周波水分計を用いて行った。
4.鉄骨工事において,隅肉溶接のサイズの確認は,マイクロメーターを用いて行った。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.◯
4.×
隅肉溶接部分の測定は、余盛高さ、角度測定、すき間測定、長さ測定がある。この測定には溶接用ゲージを用いる。
[ No.35 ]
コンクリートの試験及び検査に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.フレッシュコンクリートの荷卸し地点での検査におけるスランプ試験は,0.5cm単位で測定した。
2.フレッシュコンクリートの荷卸し地点での検査における普通コンクリートの空気量の許容差は,±2.5%とした。
3.コンクリートの打込み中に品質の変化が認められたため,再度スランプ試験を行った。
4.試験に用いる試料は,トラックアジテータから採取する直前に,アジテータで高速攪拌した。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
2.×
普通コンクリートの空気量の許容差は,± 1.5%である。
3.◯
4.◯
[ No.36 ]
工事現場の安全管理に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.新規入場者教育とは,新しく現場に入場した者に対して,作業所の方針,安全施工サイクルの具体的な内容,作業手順等を教育することである。
2.KY(危険予知)活動とは,作業に伴う危険性又は有害性に対し,作業グループが正しい行動を互いに確認し合う活動である。
3.TBM(ツールボックスミーティング)とは,職長を中心に,作業開始前の短時間で,当日の安全作業について話し合う活動である。
4.OJT(オンザジョブトレーニング)とは,施工の安全を図るため,毎日,毎週,毎月の基本的な実施事項を定型化し,継続的に実施する活動である。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.◯
4.×
OJT(オン ザ ジョブ トレーニング)とは、職場で実務をさせることで行う従業員の職業教育のこと。企業内で行われるトレーング手法、企業内教育の一種である。
[ No.37 ]
事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生規則」上,定められていないものはどれか。
1.高さが2m以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
2.高さが2m以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の時期,範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
3.型枠支保工の組立て等作業主任者を選任すること。
4.型枠支保工の組立て等の作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.◯
4.×
型枠支保工の組立て等作業主任者の職務について、労働安全衛生規則247条に記載されている。
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
よって、作業の方法を決定し、作業を直接指揮するのは、型枠支保工の組立て等作業主任者である。
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image