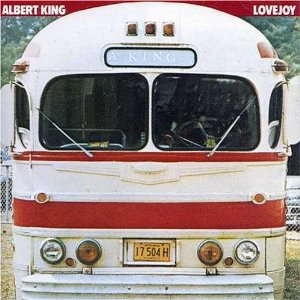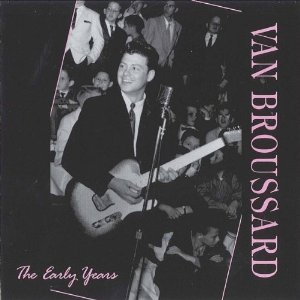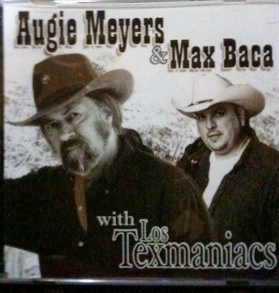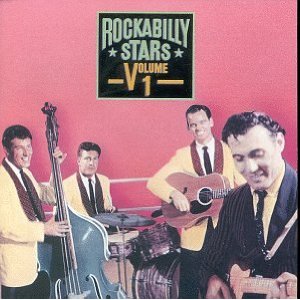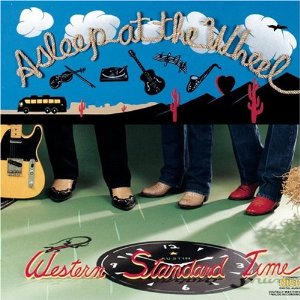2011年06月10日
鞍の上の生活へ帰ろう
今回は、Alvin Crowのカウボーイ・ソング集を聴きました。
まあ、ウエスタン・ソング集でも、アメリカーナ集と呼んでもいいと思います。
収録曲は、古くからの伝承曲と西部劇の劇中歌などが中心だと思われます。
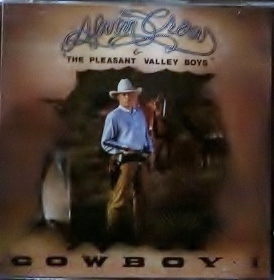
1. Big Iron (Marty Robbins)
2. Streets Of Larredo (P.D)
3. Riding Down The Canyon (Gene Autry, Smiley Burnett)
4. El Paso (Marty Robbins)
5. Ghost Riders In The Sky (Stan Jones)
6. High Noon (Dmitri Tiomkin, Ned Washington)
7. Back In The Saddle Again (Gene Autry, Ray Whitley)
8. Out On The Lonely Prairie (Harry S. Miller)
9. Coming Back To Texas (Kenneth Threadgill)
10. Bright Sherman Valley (P.D.Traditional)
11. Strawberry Roan (Curly Fletcher)
12. Patonia (P.D.Traditional)
13. Ruinning Gun (Tom Glasser, Jim Glasser)
Alvin Crowは、Takoma時代のSir Douglas Quintetのメンバーで、主にフィドルを弾いていた人です。
Quintetを離れてからは、ウエスタン・スイング・バンドを率いて活動していました。
本作は、録音時期は不明ですが、ホンキートンク・バー(?)"Brocken Spoke"でのライヴ録音をもとに、楽器やコーラスのダビングなどがなされているようです。
参加メンバーは、以下の通りです。
Alvin Crow : vocals, fiddle, guitar, mandocaster
Rick Crow : guitar, vocals
Don Bacoch : bass
John Chandler : drums
Scott Wall : Steel
James M. White : vocal
今回も、Bobby Earl Smithの参加はないようです。
私は、さほど西部劇に詳しくないのですが、"High Noon"の名前くらいは知っていました。
この曲は、邦題「真昼の決闘」のテーマです。
馬がトロットするような、随分とのどかな曲調です。
とても「決闘」とは結びつかない感じですね。
私は、かつてLP数枚組の「スクリーン・テーマ選集」みたいなのを持っていて、この曲も聴いていました。
(廃棄していないはずですが、所在不明です。)
"Streets Of Larredo"は、邦題「ラレド通り」でしょうか。
TV西部劇「ラレド」の主題歌らしいです。
「ラレド」は、メキシコとの国境近くの街で、国境を超えたメキシコには、ダグ・サーム作の曲名にもなった街「ヌエボ・ラレド」があるのでした。
リオ・グランデ川の流域にあり、ジョン・ウェインの映画「リオ・ブラボー」を連想します。
このアルバムには選ばれていませんが、「リオ・ブラボー」で、ディーン・マーチンとリッキー・ネルソンが弾き語りするシーンが好きでした。
特にリッキーの歌が好きで、曲名が思い出せないのが残念です。
"Ghost Riders In The Sky"は、「天駆けるカウボーイの亡霊」なのでしょうか。
イ・ピ・ヤー、エー、イ・ピ・ヤーオーのリフレインが耳に残ります。
ネオロカの(テッズのが正しいですか?)Matchboxのバージョンを思い出します。
ジーン・オートリーの曲が数曲チョイスされており、さすが歌うカウボーイを代表する存在だと思います。
私が知っているのは、やはり"Back In The Saddle Again"です。
多くのコンピにも選曲されている名作です。
ここでは、原曲よりテンポをあげて、ロッキン度が増したアレンジになっています。
出典の映画があるのか知りませんが、いろいろとイメージを膨らませてしまいます。
「また鞍に戻ろう」ですが、かってにストーリーを作ってみました。
酒浸りの初老のガンマンが、若い流れ者の無法に堪忍袋の緒を切って、一人無謀な闘いを挑む、というストーリーはいかがでしょう?
全くの思いつきをいってますが、私は、英国の作家、ギャビン・ライアルの「深夜プラス1」や「もっとも危険なゲーム」が大好きで、つい妄想を爆発させてしまうのでした。
彼が書く物語は、シニカルな面を差し引けば、西部劇の名作に通じるものがあると思います。
ライアルが得意としていたのが、「引退したプロと現役最高のアマチュアとの対決」といったシチュエーションでした。
さて、カウボーイ・ソングを代表するシンガーとして、マーティ・ロビンスの作品も2曲取り上げられケています。
"Big Iron"は、でっかい銃を指すのだと思いますが、無法者とテキサス・レンジャースの対決を描いた歌だったと思います。
テキサス・レンジャースは、もともとは自警団的なものだった(?)と聞いたことがあります。
ダグ・サームには、"Texas Rangers Man"という曲がありました。
そして、"El Paso"です。
この曲こそ、マーティのカウボーイ・ソングの代表曲でしょう。
美しいメキシコ娘をめぐる、恋のさや当てを描いた歌です。
思い余って、恋敵を射殺してしまったた主人公は、後ろ髪を引かれながら街を抜け出しますが、恋人への想いを断ちがたく、追手が迫る街へ続く道を引き換えしていくのでした。
原曲では、メキシカン風味たっぷりのトレモロ・ギターが素晴らしかったです。
ここでも、その雰囲気をだそうと頑張っています。
ところで、作者名に、P.Dとあるのは、パブリック・ドメイン(public domain)のことで、通常は著作権期限切れの楽曲を指すのだと思います。
単なるP.D.と、P.D.Traditionalとの区別が興味深いですね。
伝承曲は、もともと作者不詳だと思うのですが…。
いずれにしても、オールド・タイミーなスタイルの曲には和まされます。
関連記事はこちら
可愛い七つの子はフィドル弾き
ロッキン・レオンのふるさと
まあ、ウエスタン・ソング集でも、アメリカーナ集と呼んでもいいと思います。
収録曲は、古くからの伝承曲と西部劇の劇中歌などが中心だと思われます。
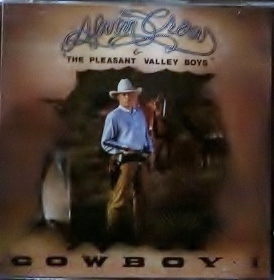
Cowboy 1
Alvin Crow & Pleasant Valley Boys
Alvin Crow & Pleasant Valley Boys
1. Big Iron (Marty Robbins)
2. Streets Of Larredo (P.D)
3. Riding Down The Canyon (Gene Autry, Smiley Burnett)
4. El Paso (Marty Robbins)
5. Ghost Riders In The Sky (Stan Jones)
6. High Noon (Dmitri Tiomkin, Ned Washington)
7. Back In The Saddle Again (Gene Autry, Ray Whitley)
8. Out On The Lonely Prairie (Harry S. Miller)
9. Coming Back To Texas (Kenneth Threadgill)
10. Bright Sherman Valley (P.D.Traditional)
11. Strawberry Roan (Curly Fletcher)
12. Patonia (P.D.Traditional)
13. Ruinning Gun (Tom Glasser, Jim Glasser)
Alvin Crowは、Takoma時代のSir Douglas Quintetのメンバーで、主にフィドルを弾いていた人です。
Quintetを離れてからは、ウエスタン・スイング・バンドを率いて活動していました。
本作は、録音時期は不明ですが、ホンキートンク・バー(?)"Brocken Spoke"でのライヴ録音をもとに、楽器やコーラスのダビングなどがなされているようです。
参加メンバーは、以下の通りです。
Alvin Crow : vocals, fiddle, guitar, mandocaster
Rick Crow : guitar, vocals
Don Bacoch : bass
John Chandler : drums
Scott Wall : Steel
James M. White : vocal
今回も、Bobby Earl Smithの参加はないようです。
私は、さほど西部劇に詳しくないのですが、"High Noon"の名前くらいは知っていました。
この曲は、邦題「真昼の決闘」のテーマです。
馬がトロットするような、随分とのどかな曲調です。
とても「決闘」とは結びつかない感じですね。
私は、かつてLP数枚組の「スクリーン・テーマ選集」みたいなのを持っていて、この曲も聴いていました。
(廃棄していないはずですが、所在不明です。)
"Streets Of Larredo"は、邦題「ラレド通り」でしょうか。
TV西部劇「ラレド」の主題歌らしいです。
「ラレド」は、メキシコとの国境近くの街で、国境を超えたメキシコには、ダグ・サーム作の曲名にもなった街「ヌエボ・ラレド」があるのでした。
リオ・グランデ川の流域にあり、ジョン・ウェインの映画「リオ・ブラボー」を連想します。
このアルバムには選ばれていませんが、「リオ・ブラボー」で、ディーン・マーチンとリッキー・ネルソンが弾き語りするシーンが好きでした。
特にリッキーの歌が好きで、曲名が思い出せないのが残念です。
"Ghost Riders In The Sky"は、「天駆けるカウボーイの亡霊」なのでしょうか。
イ・ピ・ヤー、エー、イ・ピ・ヤーオーのリフレインが耳に残ります。
ネオロカの(テッズのが正しいですか?)Matchboxのバージョンを思い出します。
ジーン・オートリーの曲が数曲チョイスされており、さすが歌うカウボーイを代表する存在だと思います。
私が知っているのは、やはり"Back In The Saddle Again"です。
多くのコンピにも選曲されている名作です。
ここでは、原曲よりテンポをあげて、ロッキン度が増したアレンジになっています。
出典の映画があるのか知りませんが、いろいろとイメージを膨らませてしまいます。
「また鞍に戻ろう」ですが、かってにストーリーを作ってみました。
酒浸りの初老のガンマンが、若い流れ者の無法に堪忍袋の緒を切って、一人無謀な闘いを挑む、というストーリーはいかがでしょう?
全くの思いつきをいってますが、私は、英国の作家、ギャビン・ライアルの「深夜プラス1」や「もっとも危険なゲーム」が大好きで、つい妄想を爆発させてしまうのでした。
彼が書く物語は、シニカルな面を差し引けば、西部劇の名作に通じるものがあると思います。
ライアルが得意としていたのが、「引退したプロと現役最高のアマチュアとの対決」といったシチュエーションでした。
さて、カウボーイ・ソングを代表するシンガーとして、マーティ・ロビンスの作品も2曲取り上げられケています。
"Big Iron"は、でっかい銃を指すのだと思いますが、無法者とテキサス・レンジャースの対決を描いた歌だったと思います。
テキサス・レンジャースは、もともとは自警団的なものだった(?)と聞いたことがあります。
ダグ・サームには、"Texas Rangers Man"という曲がありました。
そして、"El Paso"です。
この曲こそ、マーティのカウボーイ・ソングの代表曲でしょう。
美しいメキシコ娘をめぐる、恋のさや当てを描いた歌です。
思い余って、恋敵を射殺してしまったた主人公は、後ろ髪を引かれながら街を抜け出しますが、恋人への想いを断ちがたく、追手が迫る街へ続く道を引き換えしていくのでした。
原曲では、メキシカン風味たっぷりのトレモロ・ギターが素晴らしかったです。
ここでも、その雰囲気をだそうと頑張っています。
ところで、作者名に、P.Dとあるのは、パブリック・ドメイン(public domain)のことで、通常は著作権期限切れの楽曲を指すのだと思います。
単なるP.D.と、P.D.Traditionalとの区別が興味深いですね。
伝承曲は、もともと作者不詳だと思うのですが…。
いずれにしても、オールド・タイミーなスタイルの曲には和まされます。
Blues Brothers 2000でのGhost Riders in the Skyです。
関連記事はこちら
可愛い七つの子はフィドル弾き
ロッキン・レオンのふるさと
【カントリー、ブルーグラスの最新記事】
投稿者:エル・テッチ|01:25
|カントリー、ブルーグラス