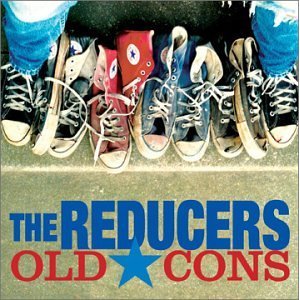2011年01月31日
シンディが好きなもの
Cyndi Lauperのアルバムを初めて買いました。
ハイスクールはダンステリアとか、トゥルー・カラーズとか、タイム・アフター・タイムとか、ヒット曲は知っていましたが、今まで一度もアルバムを買ったことはありません。
それが、なぜ?
その理由は、このアルバムの収録曲をご覧ください。

1. Just Your Fool (feat. Charlie Musselwhite)
2. Shattered Dreams (feat. Allen Toussaint)
3. Early in the Morning (feat. Allen Toussaint & B.B. King)
4. Romance in the Dark
5. How Blue Can You Get (feat. Jonny Lang)
6. Down Don't Bother Me (feat. Charlie Musselwhite)
7. Don't Cry No More
8. Rollin and Tumblin’ (feat. Kenny Brown and Ann Peebles)
9. Down So Low
10. Mother Earth (feat. Allen Toussaint)
11. Cross Roads (feat. Jonny Lang)
12. Wild Women Don't Get the Blues
13.I Don't Want To Cry (feat. Leo Gandelman)
このアルバムは、昨年にリリースされたものですが、何とタイトルどおりブルースのカバー集なのです。
驚きました。
私は、彼女のバックボーンを全く知らなかったので、なぜブルース?
なぜメンフィス? と思いました。
このアルバムは、数日前に手に入れて何度か聴いたのですが、ブルース・ロックではなく、普通にブルースとして楽しめました。
伴奏陣には、ドラムスでハワード・グライムズが、ベースでリロイ・ホッジズが参加しています。
私が不案内なだけでもっと有名人が参加している可能性もあります。
とはいっても、ハイ・サウンドを連想させるとまではいってないのが、少し残念です。
特定のサウンドを意識した音づくりではないということでしょう。
私などは、ついつい有名曲のそっくりフレーズとか期待してしまいがちですが、これはこれでよいのだと思います。
ゲストとして明記されている有名人は、B.B.キングとチャーリー・マッセルホワイト、アラン・トゥーサン、ジョニー・ラングなどです。
リズム隊よりもボーン陣のほうが、あのころの音を思い起こさせるかも知れません。
いい味を出しているホーン・リフが嬉しいです。
冒頭から、リトル・ウォルターのJust Your Foolでスタートします。
当然、チャーリーがハープで参加します。
この曲は、大好きなI Got Find My Babyのフリップ・サイドの曲ですが、実は原曲は未聴です。(だと思います。)
いい感じですが、欲を言えば、もう少しウォーキン・ベースとかで緊張感を出して、シカゴっぽくやってもよかったかなと思います。
Shattered Dreamsは、ローウェル・フルスンですね。
米ケント時代の曲で、多分、何度も繰り返しリイシューされていると思われる人気の時代の曲だと思います。
Early in the Morningは、ルイ・ジョーダンの有名曲ですが、ルイ大好きで、まるごと1枚ルイ・ソングで固めたアルバムを出しているB.B.キングが参加して、ボーカルも少しとっいます。
B.B.は私のヒーローなので、それだけでオールオーライです。
Romance in the Darkは、リリアン・グリーンとビッグ・ビルのペンになる曲で、リル・グリーンのバージョンが原曲のようです。
私は、今回初めて聴きました。
40年代の古い曲のようです。
How Blue Can You Getは、原曲が誰か知りませんが、もはやB.B.の曲で間違いないですね。
ここでのギターは、若干ロック寄りのトーンに聴こえ、やはりジョニー・ラングでした。
Down Don't Bother Me は、アルバート・キングのスタックス録音だと思いますが、チャーリーのハープが入っていて、少しダウンホームな雰囲気です。
ただ、シンディのボーカルがスタイリッシュなので、どっちつかずの感もあります。
Don't Cry No Moreは、もっとも期待していた曲です。
もちろん、原曲はデューク時代のボビー・ブランドですね。
あのジャンプ・グルーヴが出てくると、それだけでうれしくなります。
シンディは、まだ余力を残した歌い方です。
Rollin and Tumblin’は、誰が原曲ですか?
まあ、誰であってもマディ・ウォーターズで正解だと言いたい曲です。
ここでは、スライド・ギターが3分間を支配します。
Down So Lowは、トレイシー・ネルソンの1stソロ収録曲ですか。
白人の楽曲のカバーというのは、意表をつかれますね。
この曲を収録したトレイシーの日本盤をもっているはずですが、音は全く記憶にありません。
始めて出会った感じで聴きました。
この選曲は何か意味があるのかな。
Mother Earthは、メンフィス・スリムですね。
この原曲は、ピアノ・メインでしたっけ?
それとも、マット・マーフィーとのデュオ時代だったかな?
こちらも、どこかにCDがあるはずですが、ほとんど忘れてしまってます。
Cross Roadsは、クリーム盤ではなく、ウォーキン・ベースを使ったロバート・ジョンソン風です。
ジョニー・ラングがギターを弾いていますが、このあたりはブルース・ロックの雰囲気もあります。
Wild Women Don't Get the Bluesは、クラシック・ブルースのカバーだと思います。
私は全くうといのですが、原曲はベシー・スミスでしょうか?
それとも、作者のアイダ・コックス嬢ですか。
まあ、誰の代表曲かはともかく、このアルバムのライナーは、「ブルースの母、マ・レイニーに捧げる」というコメントで締められているので、マ・レイニー盤があるのかも知れません。
シンディのボーカルは、アンニュイな雰囲気を出していてうまく歌っていると思います。
ラストのI Don't Want To Cryは、今回の私の一押し曲です。
エタ・ジェイムズのような雰囲気の展開の曲で、ホーンがのっしのっしと進んでくるような、サザン・バラードです。
これは良いです。
アップ・テンポのチャック・ジャクソン盤とは同名異曲です。
オリジネイターは、サヴォイ時代のビッグ・メイベルだと思います。
メイベルは、オーケー時代のコンプリート集を聴いていましたが、サヴォイ時代はコンピで数曲きいただけなので、この曲は初体験でした。
ぜひ、原曲が収録されたアルバムが欲しいです。
ところで、皆さんはアマゾンでCDを購入していて、自然とMP3の楽曲ファイルのプレゼントがたまってませんか?
私は、もう何通もアマゾンからプレゼント通知メールが届いています。
このメイベルのサヴォイ音源なんか、試しにダウンロードしてみようかな、なんて考えたりしています。
まあ、考えるだけでなかなか実行に移さない、七回石橋を叩いてなお渡らない派なんですが…。
デジタル・データって、やっぱり形がないので、味気ないですよね。
新しいもの好きのわりに、アナログから逃れられない私は、仮にダウンロードしても、MP3プレイヤーのプレイリストを作って終わりではなく、CD-Rに焼きたい人かも知れません。
ただ、ものぐさなので口ばっかりなんですが。
今回、シンディ・ローパーという人に興味を持ちました。
ブルースが好きなんて、とにかく嬉しいです。
少し調べたところ、彼女はソロ・デビュー前に、Blue Angelというロカビリー系のバンドをやっていたらしいです。
なるほどというか、ますます好感を持ちました。
03年には、At Lastという、もう一枚のカバー集があるようです。
レヴューでは、スタンダード集のような書かれ方をされてますが、アルバム・タイトル曲は、エタ・ジェイムズの名バラードです。
モーリス・ウイリアムズ&ゾディアクスのStayとか、スモーキー・ロビンスンのあの曲とかもやっているようなので、興味は増す一方です。
企画盤が増えるのは、キャリアが長くなって、煮詰まっているとも言えなくありませんが、ロッド・スチュワートの成功の例もあります。
大の親日家で、ブルースやR&Bが好き、若いころはロカビリーもやってました、なんて素敵です。
今回、大いに見直したシンガーです。
なお、私が手に入れたアルバムは、多分ブラジル盤だと思われ、もっとも曲数が多いものです。
通常盤は全11曲で、トラック12が追加された米盤がありますが、トラック13は未収録です。
また、来月発売予定のDVD付き日本盤の説明文では、トラック13は日本盤のみ収録と謳われています。
歌詞対訳はともかく、各曲に関する詳細な日本語解説がつくのなら、ライナーは読んでみたいです。
ハイスクールはダンステリアとか、トゥルー・カラーズとか、タイム・アフター・タイムとか、ヒット曲は知っていましたが、今まで一度もアルバムを買ったことはありません。
それが、なぜ?
その理由は、このアルバムの収録曲をご覧ください。

Memphis Blues
Cyndi Lauper
Cyndi Lauper
1. Just Your Fool (feat. Charlie Musselwhite)
2. Shattered Dreams (feat. Allen Toussaint)
3. Early in the Morning (feat. Allen Toussaint & B.B. King)
4. Romance in the Dark
5. How Blue Can You Get (feat. Jonny Lang)
6. Down Don't Bother Me (feat. Charlie Musselwhite)
7. Don't Cry No More
8. Rollin and Tumblin’ (feat. Kenny Brown and Ann Peebles)
9. Down So Low
10. Mother Earth (feat. Allen Toussaint)
11. Cross Roads (feat. Jonny Lang)
12. Wild Women Don't Get the Blues
13.I Don't Want To Cry (feat. Leo Gandelman)
このアルバムは、昨年にリリースされたものですが、何とタイトルどおりブルースのカバー集なのです。
驚きました。
私は、彼女のバックボーンを全く知らなかったので、なぜブルース?
なぜメンフィス? と思いました。
このアルバムは、数日前に手に入れて何度か聴いたのですが、ブルース・ロックではなく、普通にブルースとして楽しめました。
伴奏陣には、ドラムスでハワード・グライムズが、ベースでリロイ・ホッジズが参加しています。
私が不案内なだけでもっと有名人が参加している可能性もあります。
とはいっても、ハイ・サウンドを連想させるとまではいってないのが、少し残念です。
特定のサウンドを意識した音づくりではないということでしょう。
私などは、ついつい有名曲のそっくりフレーズとか期待してしまいがちですが、これはこれでよいのだと思います。
ゲストとして明記されている有名人は、B.B.キングとチャーリー・マッセルホワイト、アラン・トゥーサン、ジョニー・ラングなどです。
リズム隊よりもボーン陣のほうが、あのころの音を思い起こさせるかも知れません。
いい味を出しているホーン・リフが嬉しいです。
冒頭から、リトル・ウォルターのJust Your Foolでスタートします。
当然、チャーリーがハープで参加します。
この曲は、大好きなI Got Find My Babyのフリップ・サイドの曲ですが、実は原曲は未聴です。(だと思います。)
いい感じですが、欲を言えば、もう少しウォーキン・ベースとかで緊張感を出して、シカゴっぽくやってもよかったかなと思います。
Shattered Dreamsは、ローウェル・フルスンですね。
米ケント時代の曲で、多分、何度も繰り返しリイシューされていると思われる人気の時代の曲だと思います。
Early in the Morningは、ルイ・ジョーダンの有名曲ですが、ルイ大好きで、まるごと1枚ルイ・ソングで固めたアルバムを出しているB.B.キングが参加して、ボーカルも少しとっいます。
B.B.は私のヒーローなので、それだけでオールオーライです。
Romance in the Darkは、リリアン・グリーンとビッグ・ビルのペンになる曲で、リル・グリーンのバージョンが原曲のようです。
私は、今回初めて聴きました。
40年代の古い曲のようです。
How Blue Can You Getは、原曲が誰か知りませんが、もはやB.B.の曲で間違いないですね。
ここでのギターは、若干ロック寄りのトーンに聴こえ、やはりジョニー・ラングでした。
Down Don't Bother Me は、アルバート・キングのスタックス録音だと思いますが、チャーリーのハープが入っていて、少しダウンホームな雰囲気です。
ただ、シンディのボーカルがスタイリッシュなので、どっちつかずの感もあります。
Don't Cry No Moreは、もっとも期待していた曲です。
もちろん、原曲はデューク時代のボビー・ブランドですね。
あのジャンプ・グルーヴが出てくると、それだけでうれしくなります。
シンディは、まだ余力を残した歌い方です。
Rollin and Tumblin’は、誰が原曲ですか?
まあ、誰であってもマディ・ウォーターズで正解だと言いたい曲です。
ここでは、スライド・ギターが3分間を支配します。
Down So Lowは、トレイシー・ネルソンの1stソロ収録曲ですか。
白人の楽曲のカバーというのは、意表をつかれますね。
この曲を収録したトレイシーの日本盤をもっているはずですが、音は全く記憶にありません。
始めて出会った感じで聴きました。
この選曲は何か意味があるのかな。
Mother Earthは、メンフィス・スリムですね。
この原曲は、ピアノ・メインでしたっけ?
それとも、マット・マーフィーとのデュオ時代だったかな?
こちらも、どこかにCDがあるはずですが、ほとんど忘れてしまってます。
Cross Roadsは、クリーム盤ではなく、ウォーキン・ベースを使ったロバート・ジョンソン風です。
ジョニー・ラングがギターを弾いていますが、このあたりはブルース・ロックの雰囲気もあります。
Wild Women Don't Get the Bluesは、クラシック・ブルースのカバーだと思います。
私は全くうといのですが、原曲はベシー・スミスでしょうか?
それとも、作者のアイダ・コックス嬢ですか。
まあ、誰の代表曲かはともかく、このアルバムのライナーは、「ブルースの母、マ・レイニーに捧げる」というコメントで締められているので、マ・レイニー盤があるのかも知れません。
シンディのボーカルは、アンニュイな雰囲気を出していてうまく歌っていると思います。
ラストのI Don't Want To Cryは、今回の私の一押し曲です。
エタ・ジェイムズのような雰囲気の展開の曲で、ホーンがのっしのっしと進んでくるような、サザン・バラードです。
これは良いです。
アップ・テンポのチャック・ジャクソン盤とは同名異曲です。
オリジネイターは、サヴォイ時代のビッグ・メイベルだと思います。
メイベルは、オーケー時代のコンプリート集を聴いていましたが、サヴォイ時代はコンピで数曲きいただけなので、この曲は初体験でした。
ぜひ、原曲が収録されたアルバムが欲しいです。
ところで、皆さんはアマゾンでCDを購入していて、自然とMP3の楽曲ファイルのプレゼントがたまってませんか?
私は、もう何通もアマゾンからプレゼント通知メールが届いています。
このメイベルのサヴォイ音源なんか、試しにダウンロードしてみようかな、なんて考えたりしています。
まあ、考えるだけでなかなか実行に移さない、七回石橋を叩いてなお渡らない派なんですが…。
デジタル・データって、やっぱり形がないので、味気ないですよね。
新しいもの好きのわりに、アナログから逃れられない私は、仮にダウンロードしても、MP3プレイヤーのプレイリストを作って終わりではなく、CD-Rに焼きたい人かも知れません。
ただ、ものぐさなので口ばっかりなんですが。
今回、シンディ・ローパーという人に興味を持ちました。
ブルースが好きなんて、とにかく嬉しいです。
少し調べたところ、彼女はソロ・デビュー前に、Blue Angelというロカビリー系のバンドをやっていたらしいです。
なるほどというか、ますます好感を持ちました。
03年には、At Lastという、もう一枚のカバー集があるようです。
レヴューでは、スタンダード集のような書かれ方をされてますが、アルバム・タイトル曲は、エタ・ジェイムズの名バラードです。
モーリス・ウイリアムズ&ゾディアクスのStayとか、スモーキー・ロビンスンのあの曲とかもやっているようなので、興味は増す一方です。
企画盤が増えるのは、キャリアが長くなって、煮詰まっているとも言えなくありませんが、ロッド・スチュワートの成功の例もあります。
大の親日家で、ブルースやR&Bが好き、若いころはロカビリーもやってました、なんて素敵です。
今回、大いに見直したシンガーです。
なお、私が手に入れたアルバムは、多分ブラジル盤だと思われ、もっとも曲数が多いものです。
通常盤は全11曲で、トラック12が追加された米盤がありますが、トラック13は未収録です。
また、来月発売予定のDVD付き日本盤の説明文では、トラック13は日本盤のみ収録と謳われています。
歌詞対訳はともかく、各曲に関する詳細な日本語解説がつくのなら、ライナーは読んでみたいです。
Don't Cry No Moreです。
投稿者:エル・テッチ|00:27
|リズム・アンド・ブルース