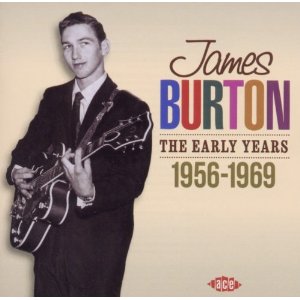2011年11月27日
シャーリー&カンパニー、しばしばジェシー
今回は、Shirley GoodmanとJesse Hillのデュオ・アルバムを聴きました。
制作はHeuy P. Meauxで、78年にCrazy Cajun Recordsからリリースされました。
これはちょっと意表をつく取り合わせですね。
さらに、アルバム・タイトルがBarbara Lynnの名作で、期待度のボルテージが高まります。

Side One
1. Ivory Tower
2. My Children (Malcom J. Rebenneck)
3. You'll Lose A Good Thing (Heuy P. Meaux)
4. (Oh Baby) We Got A Good Thing Going (Heuy P. Meaux)
5. Too Much Too Soon (Dale Ward)
Side Two
1. Certainly Hurting Me (Shirley Goodman)
2. I Dare You (Shirley Goodman)
3. Can't Fight Love (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)
4. Just A Little Ugly Part 1 (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)
5. Just A Little Ugly Part 2 (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)
まず、最初に確認しておきましょう。
ジャケをご覧ください。
アーティスト名ですが、Shirley & Jesseではなく、左上に大きくShirley & Co.、そしてその下段に少しフォントを抑えてJesse Hillと配置されています。
(アルバム・タイトルのフォントは更に小さいです。)
一般的には、Shirley Goodmanより、Jesse Hillの方が世間の認知度が高いと思うのですが、この当時はそうではなかったのでしょうか。
R&Bファンなら、Jesse Hillの名前は比較的有名だと思います。
もちろん、Allen Toussaint制作の"Ooh-Poo-Pah-Doo"ですね。
ただ、正直、私は彼の単独アルバムを持っていません。
ワン・ヒット・ワンダーの印象が強い人です。
"Ooh-Poo-Pah-Doo"は、Ray Charles好きのToussaintの趣味が出た一連の作品のひとつですね。
私の中では、"Mother In Law"とひとくくりにしてしまいがちな曲でした。
今回、70年代ものではありますが、Jesse Hillをまとめて聴くことが出来たいい機会でした。
そのボーカルは、例えるなら、Lee DoseyやRobert Parkerを連想させる、焼き芋をほおばったような発声で、どこかユーモラスな感じがします。
一方、Shirley Goodmanは、主として50年代にShirley & Leeとしてヒットを飛ばした、甲高い声が最大の個性になっている女性シンガーで、一度聴くと忘れられない印象を残す人です。
50年代にはいつくかのヒットがありますが、代表曲はやはり"Let The Good Time Roll"です。
そんなShirleyですが、相棒のLeonard Leeとコンビ解消したあと、72年のStonesの「メインストリートのならず者」では、バック・コーラスで参加しているらしいです。
そして、本盤の表記にある"Shirley & Co."名義で、75年に一発ヒットを出しました。
Shirley & Co.は、正確にはShirley & Companyです。
一部の曲を聴いた限りでは、別にグループという感じはしないです。
なぜ、こういうクレジットなのか私は知りません。
"Shame Shame Shame"というJimmy Reedのブルースをディスコ調でやって、それなりに注目されたようです。
それが、78年リリースの本盤で、Jesse Hillよりフォントが大きく表記されている理由だと理解しましょうか。
さて、中身を聴いていきましょう。
基本は二人のデュオですが、数曲ソロがあり、以下の通りです。
Shirley Goodmanのソロ
B2. I Dare You
Jesse Hillのソロ
A2. My Children
B4. Just A Little Ugly Part 1
B5. Just A Little Ugly Part 2
Jesse Hillの担当曲で、Dr. Johnがライター・クレジットされているのが目を惹きます。
Shirley & Co.名義を使っていますが、アルバム全体の印象はディスコではなく、古いR&Bのそれで嬉しいです。
ただ、往年のニューオリンズR&B調は希薄で、むしろ8ビートで快調に歌い飛ばす展開が爽快です。
70年代うんぬんもあまり意識にのぼりません。
冒頭のA1"Ivory Tower"は、ShirleyとJesseが交互にソロ・パートを歌い、徐々にデュエットして盛り上げていく8ビートの曲で、やはりShirleyが初登場する瞬間は、素直に「キター」とはしゃいでしまいます。
面白いのは、カスタネットの連打が印象に残ることで、まるで疑似スペクター・サウンドみたいです。
続くJesseのソロ曲"My Children"は、Jesseの個性がフルに発揮されたソウル・ダンス曲で、Lee Doseyを思わせるリッチな歌声で聴かせてくれます。
ミーターズ風ニューオリンズ・ファンクをイメージしているのかも知れません。
そして、アルバム・タイトル曲の"You'll Lose A Good Thing"です。
まともじゃないだろうとは予期していましたが、この飛びまくった仕上がりは、さすがShirleyです。
耳に馴染んだ、あの有名な歌詞が、とてつもなくハイ・ピッチなボーカルで歌われるこの感じ、予想以上でした。
そして、曲調は、原曲がもつセンチメントなスロー・バラードではなく、ここでもやはり快調に飛ばすミディアム・アップです。
Jesseの語り風のリードでスタートし、Shirleyにバトンを渡したあと、さらに交互に歌い継ぐ、ユニークというほかない構成です。
知らずに聴けば、「なにかどこかで聴いたような歌詞だなあ」と"You'll Lose A Good Thing"をすぐに連想できない可能性が高いです。
リズムは若干ノーザンに接近したアレンジかなと思いますが、Jesseのとぼけたキャラクターが全開で、対抗するようにニューオリンズ風味を発散しています。
ノーザンを連想するのは、インプレッションズ風(というか、"It's Alright"風)のリズム・ギターが印象に残るせいですね。
" (Oh Baby) We Got A Good Thing Going"は、ノーザン的な曲調がさらにはっきりしたアレンジで、これはシカゴではなくデトロイト調のダンス・ナンバーに仕上がっています。
とはいえ、Shirleyのワン・アンド・オンリーの個性は何物も飲み込んで突き進むのでした。
A面ラストの"Too Much Too Soon"は、ShirleyがShirley & Leeのあと、60年代に即席で組んだデュオ、Shirley & Alfredの吹き込みのセルフ・カバーです。
その時の相棒のAlfredは、実はBrenton Wood(本名Alfred Jesse Smith)のことで、日本での知名度は低いのではないかと思いますが、重要なアーリー・ソウル・シンガーだと思います。
Brenton Woodの67年の代表曲、"Gimmie Little Sign"は、チカーノの人気曲でもあります。
彼はルイジアナのシュリブポート出身ですが、ドゥワップからノーザンまで様々な曲調をこなせる、ユーティリティ・シンガーで、私は大好きです。
さて、少し脱線しましたので戻ります。
B面は、Shirleyをメインとする調子のいいノーザン・ダンサーで締める前半と、Jesseメインのニューオリンズ・ファンクでイナタく進行する後半に大別されます。
Shirleyのソロ、"I Dare You"では、カスタネットとタンバリンの連打が効果的に使われていて、再びウォール・オブ・サウンドを連想させるアレンジになっています。
"Can't Fight Love"は、Jesseに相性のいい(というかLee Doseyスタイル)のニューオリンズ・ファンクですが、ここではShirleyが最高の絡みをしていて、B面のハイライトです。
そして、"Just A Little Ugly"もまた、同種のニューオリンズ・ファンクで、やはりLee Doseyを連想します。
喧噪のSEを効果的に使った、くせになるグルーヴを持つ曲です。
よく転がるピアノと跳ねるベースのアンサンブルに、ブラスのブロウが切り込んでくるところが良く、繰り返し聴きたくなります。
70年代後半のこの時期にも、オールド・スタイルのR&Bをイナタく決めてくれた二人に拍手したいです。
(Jesse Hillにも、俄然興味がわいてきました。)
関連記事はこちら
シャーリー&リー、無類のデュオ
制作はHeuy P. Meauxで、78年にCrazy Cajun Recordsからリリースされました。
これはちょっと意表をつく取り合わせですね。
さらに、アルバム・タイトルがBarbara Lynnの名作で、期待度のボルテージが高まります。
You'll Lose A Good Thing
Shirley & Co.
Jesse Hill
Shirley & Co.
Jesse Hill
Side One
1. Ivory Tower
2. My Children (Malcom J. Rebenneck)
3. You'll Lose A Good Thing (Heuy P. Meaux)
4. (Oh Baby) We Got A Good Thing Going (Heuy P. Meaux)
5. Too Much Too Soon (Dale Ward)
Side Two
1. Certainly Hurting Me (Shirley Goodman)
2. I Dare You (Shirley Goodman)
3. Can't Fight Love (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)
4. Just A Little Ugly Part 1 (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)
5. Just A Little Ugly Part 2 (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)
まず、最初に確認しておきましょう。
ジャケをご覧ください。
アーティスト名ですが、Shirley & Jesseではなく、左上に大きくShirley & Co.、そしてその下段に少しフォントを抑えてJesse Hillと配置されています。
(アルバム・タイトルのフォントは更に小さいです。)
一般的には、Shirley Goodmanより、Jesse Hillの方が世間の認知度が高いと思うのですが、この当時はそうではなかったのでしょうか。
R&Bファンなら、Jesse Hillの名前は比較的有名だと思います。
もちろん、Allen Toussaint制作の"Ooh-Poo-Pah-Doo"ですね。
ただ、正直、私は彼の単独アルバムを持っていません。
ワン・ヒット・ワンダーの印象が強い人です。
"Ooh-Poo-Pah-Doo"は、Ray Charles好きのToussaintの趣味が出た一連の作品のひとつですね。
私の中では、"Mother In Law"とひとくくりにしてしまいがちな曲でした。
今回、70年代ものではありますが、Jesse Hillをまとめて聴くことが出来たいい機会でした。
そのボーカルは、例えるなら、Lee DoseyやRobert Parkerを連想させる、焼き芋をほおばったような発声で、どこかユーモラスな感じがします。
一方、Shirley Goodmanは、主として50年代にShirley & Leeとしてヒットを飛ばした、甲高い声が最大の個性になっている女性シンガーで、一度聴くと忘れられない印象を残す人です。
50年代にはいつくかのヒットがありますが、代表曲はやはり"Let The Good Time Roll"です。
そんなShirleyですが、相棒のLeonard Leeとコンビ解消したあと、72年のStonesの「メインストリートのならず者」では、バック・コーラスで参加しているらしいです。
そして、本盤の表記にある"Shirley & Co."名義で、75年に一発ヒットを出しました。
Shirley & Co.は、正確にはShirley & Companyです。
一部の曲を聴いた限りでは、別にグループという感じはしないです。
なぜ、こういうクレジットなのか私は知りません。
"Shame Shame Shame"というJimmy Reedのブルースをディスコ調でやって、それなりに注目されたようです。
それが、78年リリースの本盤で、Jesse Hillよりフォントが大きく表記されている理由だと理解しましょうか。
さて、中身を聴いていきましょう。
基本は二人のデュオですが、数曲ソロがあり、以下の通りです。
Shirley Goodmanのソロ
B2. I Dare You
Jesse Hillのソロ
A2. My Children
B4. Just A Little Ugly Part 1
B5. Just A Little Ugly Part 2
Jesse Hillの担当曲で、Dr. Johnがライター・クレジットされているのが目を惹きます。
Shirley & Co.名義を使っていますが、アルバム全体の印象はディスコではなく、古いR&Bのそれで嬉しいです。
ただ、往年のニューオリンズR&B調は希薄で、むしろ8ビートで快調に歌い飛ばす展開が爽快です。
70年代うんぬんもあまり意識にのぼりません。
冒頭のA1"Ivory Tower"は、ShirleyとJesseが交互にソロ・パートを歌い、徐々にデュエットして盛り上げていく8ビートの曲で、やはりShirleyが初登場する瞬間は、素直に「キター」とはしゃいでしまいます。
面白いのは、カスタネットの連打が印象に残ることで、まるで疑似スペクター・サウンドみたいです。
続くJesseのソロ曲"My Children"は、Jesseの個性がフルに発揮されたソウル・ダンス曲で、Lee Doseyを思わせるリッチな歌声で聴かせてくれます。
ミーターズ風ニューオリンズ・ファンクをイメージしているのかも知れません。
そして、アルバム・タイトル曲の"You'll Lose A Good Thing"です。
まともじゃないだろうとは予期していましたが、この飛びまくった仕上がりは、さすがShirleyです。
耳に馴染んだ、あの有名な歌詞が、とてつもなくハイ・ピッチなボーカルで歌われるこの感じ、予想以上でした。
そして、曲調は、原曲がもつセンチメントなスロー・バラードではなく、ここでもやはり快調に飛ばすミディアム・アップです。
Jesseの語り風のリードでスタートし、Shirleyにバトンを渡したあと、さらに交互に歌い継ぐ、ユニークというほかない構成です。
知らずに聴けば、「なにかどこかで聴いたような歌詞だなあ」と"You'll Lose A Good Thing"をすぐに連想できない可能性が高いです。
リズムは若干ノーザンに接近したアレンジかなと思いますが、Jesseのとぼけたキャラクターが全開で、対抗するようにニューオリンズ風味を発散しています。
ノーザンを連想するのは、インプレッションズ風(というか、"It's Alright"風)のリズム・ギターが印象に残るせいですね。
" (Oh Baby) We Got A Good Thing Going"は、ノーザン的な曲調がさらにはっきりしたアレンジで、これはシカゴではなくデトロイト調のダンス・ナンバーに仕上がっています。
とはいえ、Shirleyのワン・アンド・オンリーの個性は何物も飲み込んで突き進むのでした。
A面ラストの"Too Much Too Soon"は、ShirleyがShirley & Leeのあと、60年代に即席で組んだデュオ、Shirley & Alfredの吹き込みのセルフ・カバーです。
その時の相棒のAlfredは、実はBrenton Wood(本名Alfred Jesse Smith)のことで、日本での知名度は低いのではないかと思いますが、重要なアーリー・ソウル・シンガーだと思います。
Brenton Woodの67年の代表曲、"Gimmie Little Sign"は、チカーノの人気曲でもあります。
彼はルイジアナのシュリブポート出身ですが、ドゥワップからノーザンまで様々な曲調をこなせる、ユーティリティ・シンガーで、私は大好きです。
さて、少し脱線しましたので戻ります。
B面は、Shirleyをメインとする調子のいいノーザン・ダンサーで締める前半と、Jesseメインのニューオリンズ・ファンクでイナタく進行する後半に大別されます。
Shirleyのソロ、"I Dare You"では、カスタネットとタンバリンの連打が効果的に使われていて、再びウォール・オブ・サウンドを連想させるアレンジになっています。
"Can't Fight Love"は、Jesseに相性のいい(というかLee Doseyスタイル)のニューオリンズ・ファンクですが、ここではShirleyが最高の絡みをしていて、B面のハイライトです。
そして、"Just A Little Ugly"もまた、同種のニューオリンズ・ファンクで、やはりLee Doseyを連想します。
喧噪のSEを効果的に使った、くせになるグルーヴを持つ曲です。
よく転がるピアノと跳ねるベースのアンサンブルに、ブラスのブロウが切り込んでくるところが良く、繰り返し聴きたくなります。
70年代後半のこの時期にも、オールド・スタイルのR&Bをイナタく決めてくれた二人に拍手したいです。
(Jesse Hillにも、俄然興味がわいてきました。)
Can't Fight Love by Shirley & Jesse
関連記事はこちら
シャーリー&リー、無類のデュオ