2011年02月27日
ピアノ・ウーマン
この人は、何となく知っているつもりでしたが、実は初めてフル・アルバムを聴きました。
結論から先にに言いますが、印象はとてもいいです。
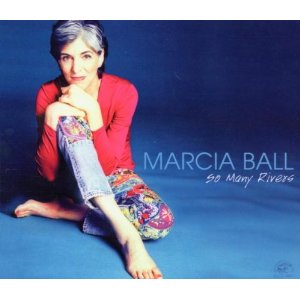
1. Foreclose On The House Of Love (John Lee Sanders)
2. Dance With Me (Danny Timms)
3. Baby, Why Not (Marcia Ball)
4. Honeypie (Danny Timms)
5. Give Me A Chance (Marcia Ball)
6. Didn't You Know (Marcia Ball, Sarah Brown)
7. Give It Up (Give In) (Marcia Ball)
8. So Many Rivers To Cross (Jodi Siegel, Daniel Moore)
9. The Storm (Marcia Ball)
10. The Lowdown (Marcia Ball)
11. Hurricane On The China Lake (Doanny Timms)
12. Three Hundred Pounds Of Hongry (Donnie Fritts, Eddie Hinton)
13. If It's Really Got To Be This Way (Donnie Fritts, Arthur Alexander, Gary Nicholson)
14. If It Ain't One Thing (Doug Duffey)
マーシア・ボールは、テキサス系のアンソロジーなどの常連というイメージを持っていて、多分探せばいろいろと出てくると思いますが、これまでまとまったものを聴いていませんでした。
これまで聴いたものでは、アントンズから、アンジェラ・ストレーリ、ルー・アン・バートンとトリオ名義で出した、91年のDreams Come True、そしてラウンダーから、アーマ・トーマス、トレイシー・ネルソンと、こちらもトリオ名義で出した、98年のSing It! が、それなりの曲数を聴いた数少ないアルバムでした。
そんな私が、初めて彼女のソロのフル・アルバムを聴こうと思ったのには、あるきっかけがありました。
それは、フリーダ&ファイアドッグスの幻の1stを聴いたためです。
フリーダこと、若き日のマーシアの瑞々しい歌声を聴いて、俄然関心を持つようになったのです。
それまでも、ブルースに傾倒するシンガー、ピアニストということは理解していました。
しかし、実のところ、R&Bを歌う白人女性シンガーには、頭から関心が薄かったというのが本当のところです。
ゴスペルは事情が違うようですが、ことディープ・ソウルに関しては、いわゆるレディ・ソウルというのは、層が薄いという思いこみがありました。
ましてや、白人となると…。
そういう予断がありました。
彼女は、ソウルというよりブルース系ではあるんですが…。
私が好きな白人女性R&Bシンガーは、Oo Tourでのボニー・ブラムレット、Reed My Lipsほかでのルー・アン・バートンといったところです。
他はすぐに頭に浮かびません。
また、先の二人にしても、すべてのアルバムが気に入っているわけではなかったのでした。
こういった先入観もあって、先にあげたトリオ名義の2枚にしても、あまり真剣に聴いていなかった気がします。
そんな意識を変える契機となったのが、フリーダ&ファイアドッグスでした。
ここでは、ブギを主体とした彼女のプレイを聴くことが出来ます。
そして、それはある程度、私のなかに折り込み済みのサウンドでした。
しかし、明らかに最近作よりも老成した歌声を聴かせているファイアドッグス盤では、彼女のカントリー・ルーツも、うかがい知ることが出来ました。
とりわけ、マーシアが歌う、ロレッタ・リンのナンバーに心を動かされました。
タミー・ワイネットのStand By Your Manも悪くないです。
ここには、私がずっと好み続けている雑種音楽の匂いが有りました。
カオスと言い換えてもいいです。
私が、ダグ・サームに夢中になった理由は、一人の音楽家の中に混然かつ違和感なく存在する、混成音楽の魅力です。
これは、私がテキサスやルイジアナの音楽を好む理由そのものです。
これらの地域が有するメキシコ文化やフランス文化との自然な混成が、私を惹きつけてやまない魅力なのでした。
私は、マーシアの音楽に同種の匂いを始めて感じることが出来、興味を持つようになりました。
さて、今回のアルバムです。
これは、03年にアリゲーターからリリースされたものですが、面白いのは、70年代の録音より、彼女の声が若く感じることです。
若い時は、静かに老成した音楽をやることがかっこよく感じられ、年齢を重ねるにつれ、力強い若さを表に出したくなる、そういうものかも知れません。
あるいは、単に「女性は恐い」ということに集約するのかもしれませんが…。
私が思うところ、アルバムの印象というのは、冒頭の1曲目が左右する場合が多いと思います。
本作では、1曲目のForeclose On The House Of Loveで、ガツンと頭を殴られるような衝撃を受けました。
いえ、例えがいまいちハズレていますね。
きつい炭酸飲料が喉元を一気に通ったような、そんな痛かゆい爽快感を感じたと言い直します。
私は、こういったホーンの鳴りが気持ちいいブギが大好きです。
この曲ですっかり気をよくした私は、一気に彼女の世界に身をゆだねることができたのでした。
このアルバムは、彼女自身によるピアノと、ホーン陣の印象が強いですが、実は、ラップ・スチール、マンドリン、フィドルなどもプレイされていて、全体のサウンドに深みを与えています。
ライターとしては、数曲で名前が出てくるダニー・ティムズという人が気になります。
2曲目のDance With Meは、ブルージーな曲ですが、イントロが、もろにニューオリンズR&Bを連想させるフレーズからスタートして、思わず「おっ」と耳をそばだててしまいます。
曲は、ブルージーにギターが切り込んできつつ、リズムはニューオリンズ・ファンク風なのでした。
また、Honeypieという曲では、出だしこそ隠し味的に使われるアコーディオンが、どんどん主役とになっていき、ごきげんなザディコか、ケイジャン風になります。
パーソネルを確認すると、なるほどWayne Toupsがアコを弾いていたのでした。
彼女の自作では、Baby, Why Notが、オールド・ディキシー・スタイルの演奏で、わくわくさせてくれます。
そして、続くGive Me A Chanceでは、ブルージーな出だしから徐々に荘厳な曲調に変化していき、ゴスペル・カルテットのような展開になっていくところが興味深いです。
このアルバムでは、彼女のカントリー・ルーツが表面化していませんが、彼女の抽斗はまだまだ色んな楽しみを蓄えているようです。
さて、カバー曲にも触れたいと思います。
まず、エディ・ヒントンのThree Hundred Pounds Of Hongryをやっています。
ただ、それほどいい曲という印象はないです。
この曲は、誰のバージョンが代表作なんでしょう。
トニー・ジョーですか?
ドニー・フリッツではないですね。
カーリーン・カーターは、もっと彼女に相応しい曲があると思います。
エディのバージョンは、99年のHard Luck Guyに収録されているようですが、残念ながら私は買い逃したアルバムです。
(…くよくよ)
そして、マーシアは、ドニー・フリッツとアーサー・アレクサンダーの名前が確認できる曲もやっていて、こちらの方か明らかに良いです。
If It's Really Got To Be This Wayです。
これは、ベン・ヴォーンが制作したアーサーのバージョンが忘れられません。
名作名演だと思います。
カバーでは、ロバート・プラント盤のボーカルが、セクシーな魅力に溢れていて良いです。
ここでのマーシアのバージョンも、なかなかの出来です。
しかし、これは雰囲気満点の伴奏と、曲そのものの力がかなりありますね。
マーシアのボーカルは、もう少し深みがあればなおいいです。
つらつらと感想を書き連ねてきましたが、もっと彼女を聴きたい、そう思わせてくれる1枚でした。
とりあえずは、トリオ名義の2枚を探すことから始めたいと思います。
関連記事はこちら
バックミラー越しの恋
回想のファイアドッグス
エドワード・ヒントンが好き
本家ヘタウマ
結論から先にに言いますが、印象はとてもいいです。
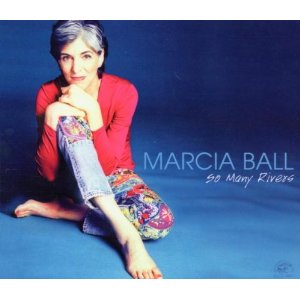
So Many Rivers
Marcia Ball
Marcia Ball
1. Foreclose On The House Of Love (John Lee Sanders)
2. Dance With Me (Danny Timms)
3. Baby, Why Not (Marcia Ball)
4. Honeypie (Danny Timms)
5. Give Me A Chance (Marcia Ball)
6. Didn't You Know (Marcia Ball, Sarah Brown)
7. Give It Up (Give In) (Marcia Ball)
8. So Many Rivers To Cross (Jodi Siegel, Daniel Moore)
9. The Storm (Marcia Ball)
10. The Lowdown (Marcia Ball)
11. Hurricane On The China Lake (Doanny Timms)
12. Three Hundred Pounds Of Hongry (Donnie Fritts, Eddie Hinton)
13. If It's Really Got To Be This Way (Donnie Fritts, Arthur Alexander, Gary Nicholson)
14. If It Ain't One Thing (Doug Duffey)
マーシア・ボールは、テキサス系のアンソロジーなどの常連というイメージを持っていて、多分探せばいろいろと出てくると思いますが、これまでまとまったものを聴いていませんでした。
これまで聴いたものでは、アントンズから、アンジェラ・ストレーリ、ルー・アン・バートンとトリオ名義で出した、91年のDreams Come True、そしてラウンダーから、アーマ・トーマス、トレイシー・ネルソンと、こちらもトリオ名義で出した、98年のSing It! が、それなりの曲数を聴いた数少ないアルバムでした。
そんな私が、初めて彼女のソロのフル・アルバムを聴こうと思ったのには、あるきっかけがありました。
それは、フリーダ&ファイアドッグスの幻の1stを聴いたためです。
フリーダこと、若き日のマーシアの瑞々しい歌声を聴いて、俄然関心を持つようになったのです。
それまでも、ブルースに傾倒するシンガー、ピアニストということは理解していました。
しかし、実のところ、R&Bを歌う白人女性シンガーには、頭から関心が薄かったというのが本当のところです。
ゴスペルは事情が違うようですが、ことディープ・ソウルに関しては、いわゆるレディ・ソウルというのは、層が薄いという思いこみがありました。
ましてや、白人となると…。
そういう予断がありました。
彼女は、ソウルというよりブルース系ではあるんですが…。
私が好きな白人女性R&Bシンガーは、Oo Tourでのボニー・ブラムレット、Reed My Lipsほかでのルー・アン・バートンといったところです。
他はすぐに頭に浮かびません。
また、先の二人にしても、すべてのアルバムが気に入っているわけではなかったのでした。
こういった先入観もあって、先にあげたトリオ名義の2枚にしても、あまり真剣に聴いていなかった気がします。
そんな意識を変える契機となったのが、フリーダ&ファイアドッグスでした。
ここでは、ブギを主体とした彼女のプレイを聴くことが出来ます。
そして、それはある程度、私のなかに折り込み済みのサウンドでした。
しかし、明らかに最近作よりも老成した歌声を聴かせているファイアドッグス盤では、彼女のカントリー・ルーツも、うかがい知ることが出来ました。
とりわけ、マーシアが歌う、ロレッタ・リンのナンバーに心を動かされました。
タミー・ワイネットのStand By Your Manも悪くないです。
ここには、私がずっと好み続けている雑種音楽の匂いが有りました。
カオスと言い換えてもいいです。
私が、ダグ・サームに夢中になった理由は、一人の音楽家の中に混然かつ違和感なく存在する、混成音楽の魅力です。
これは、私がテキサスやルイジアナの音楽を好む理由そのものです。
これらの地域が有するメキシコ文化やフランス文化との自然な混成が、私を惹きつけてやまない魅力なのでした。
私は、マーシアの音楽に同種の匂いを始めて感じることが出来、興味を持つようになりました。
さて、今回のアルバムです。
これは、03年にアリゲーターからリリースされたものですが、面白いのは、70年代の録音より、彼女の声が若く感じることです。
若い時は、静かに老成した音楽をやることがかっこよく感じられ、年齢を重ねるにつれ、力強い若さを表に出したくなる、そういうものかも知れません。
あるいは、単に「女性は恐い」ということに集約するのかもしれませんが…。
私が思うところ、アルバムの印象というのは、冒頭の1曲目が左右する場合が多いと思います。
本作では、1曲目のForeclose On The House Of Loveで、ガツンと頭を殴られるような衝撃を受けました。
いえ、例えがいまいちハズレていますね。
きつい炭酸飲料が喉元を一気に通ったような、そんな痛かゆい爽快感を感じたと言い直します。
私は、こういったホーンの鳴りが気持ちいいブギが大好きです。
この曲ですっかり気をよくした私は、一気に彼女の世界に身をゆだねることができたのでした。
このアルバムは、彼女自身によるピアノと、ホーン陣の印象が強いですが、実は、ラップ・スチール、マンドリン、フィドルなどもプレイされていて、全体のサウンドに深みを与えています。
ライターとしては、数曲で名前が出てくるダニー・ティムズという人が気になります。
2曲目のDance With Meは、ブルージーな曲ですが、イントロが、もろにニューオリンズR&Bを連想させるフレーズからスタートして、思わず「おっ」と耳をそばだててしまいます。
曲は、ブルージーにギターが切り込んできつつ、リズムはニューオリンズ・ファンク風なのでした。
また、Honeypieという曲では、出だしこそ隠し味的に使われるアコーディオンが、どんどん主役とになっていき、ごきげんなザディコか、ケイジャン風になります。
パーソネルを確認すると、なるほどWayne Toupsがアコを弾いていたのでした。
彼女の自作では、Baby, Why Notが、オールド・ディキシー・スタイルの演奏で、わくわくさせてくれます。
そして、続くGive Me A Chanceでは、ブルージーな出だしから徐々に荘厳な曲調に変化していき、ゴスペル・カルテットのような展開になっていくところが興味深いです。
このアルバムでは、彼女のカントリー・ルーツが表面化していませんが、彼女の抽斗はまだまだ色んな楽しみを蓄えているようです。
さて、カバー曲にも触れたいと思います。
まず、エディ・ヒントンのThree Hundred Pounds Of Hongryをやっています。
ただ、それほどいい曲という印象はないです。
この曲は、誰のバージョンが代表作なんでしょう。
トニー・ジョーですか?
ドニー・フリッツではないですね。
カーリーン・カーターは、もっと彼女に相応しい曲があると思います。
エディのバージョンは、99年のHard Luck Guyに収録されているようですが、残念ながら私は買い逃したアルバムです。
(…くよくよ)
そして、マーシアは、ドニー・フリッツとアーサー・アレクサンダーの名前が確認できる曲もやっていて、こちらの方か明らかに良いです。
If It's Really Got To Be This Wayです。
これは、ベン・ヴォーンが制作したアーサーのバージョンが忘れられません。
名作名演だと思います。
カバーでは、ロバート・プラント盤のボーカルが、セクシーな魅力に溢れていて良いです。
ここでのマーシアのバージョンも、なかなかの出来です。
しかし、これは雰囲気満点の伴奏と、曲そのものの力がかなりありますね。
マーシアのボーカルは、もう少し深みがあればなおいいです。
つらつらと感想を書き連ねてきましたが、もっと彼女を聴きたい、そう思わせてくれる1枚でした。
とりあえずは、トリオ名義の2枚を探すことから始めたいと思います。
Marcia Ballはこんな人
関連記事はこちら
バックミラー越しの恋
回想のファイアドッグス
エドワード・ヒントンが好き
本家ヘタウマ
【テキサス・ミュージックの最新記事】
投稿者:エル・テッチ|02:44|テキサス・ミュージック


この記事へのコメント