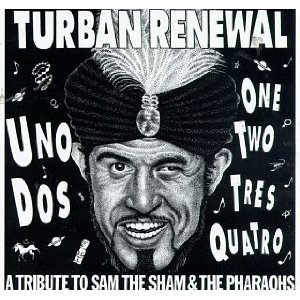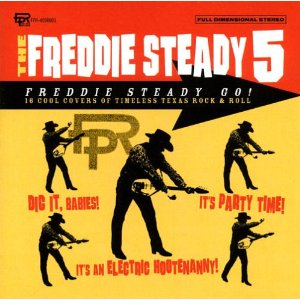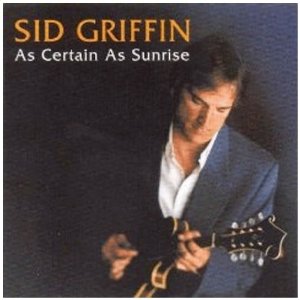2011年08月27日
メンフィスへの郷愁
これ、結構よくないですか?
私は、全く存在を知りませんでしたが、今年出た新作で、過去に1枚アルバムがあるらしいです。
私は、Otis Clayが好きなので、そのアンテナに引っかかって知りました。
このバンドは、基本的にソウル・インスト・バンドなので、ヴォーカル曲は、数人のゲストが参加して務めています。
私は未聴ですが、前作の1stは全編インストかも知れないです。

1. Hi Roller (Franklin, Bomar,Pitts)
2. Got To Get Back (To My Baby) (feat. Otis Clay) (Bomar, Carter, Franklin, Pitts)
3. Just Chillin' (Bomar, Gamble, Franklin, Pitts, Tuner)
4. Catch This Teardrop (feat. Percy Wiggins) (C.Reese, H.Reese)
5. Jack And Ginger (Bomar, Franklin, Pitts)
6. Sundown On Beale (Bomar, Franklin, Pitts)
7. Weak Spot (feat. William Bell) (Bell, Bomar, Franklin, Hall, Pitts)
8. 90 Days Same As Cash (Bomar, Franklin, Hall, Pitts)
9. I'm Going Home (feat. Charlie Musselwhite) (Conley)
10. Cauley Flower (Franklin, Bomar, Pitts)
11. Work That Sucker (feat. Charles "Skip" Pitts) (Pitts, Bomar, Franklin)
12. Got To Get Back (To My Baby) Pt. 2 (feat. Otis Clay) (Bomar, Carter, Franklin, Pitts)
私は、ソウル・ファンのつもりですが、Bar-keysにはほとんど関心を持っていませんでした。
確かOtis Reddingのツアー・バンドを務めたバンドじゃなかったですか?
Watstaxのビデオで見た気がします。
私には、サザン・ソウルより、Albert Kingのバックをやったファンキー・ブルースのアルバムの印象が強いです。
このBo-Keysは、そのBar-keysの残党をベースに、活きのいい若手を加えたバンドで、ざっくり言えば、60s70sの南部ソウル・サウンドのリバイバル・バンドです。
ファンキーな曲やジャズ・ソウル的な展開を得意としているようですが、本盤では黄金時代のメンフィス・ソウルを意識した音づくりに挑んでいるようです。
ゲストのメンツが、より一層、そう感じさせるのかも知れません。
私は、オリジナル・メンバーにうといんですが、参加メンツは以下のとおりです。
Scott Bomer : bass, percussion
Charles "Skip" Pitts : guitar
Howard Grimes : drums, percussion
Willie Hall : drums, percussion
Archie "Hubbie" Turner : keyboad
Al Gamble : keyboad
Mark Franklin : trumpet
Ben Cauley : trumpet
Kirk Smothers : tenor & baritone sax
Derrick Williams : tenor sax
Floyd Newman : baritone sax
Jim Spake : baritone sax
Spencer Wiggins & John Gary Williams : background vocals on "Catch That Teardrop"
Howard Grimesに反応してしまいますが、どうやらメインのドラムは、Willie Hallのようです。
それよりも、最後にチラッと出てくる、Spencer Wigginsの名前が気になりますね。
この人は、弟のPercy Wigginsがボーカルをとった、4曲目の"Catch This Teardrop"でコーラスとして参加しているようです。
(声の判別は、言われなけば困難です。)
Percy Wigginsは、兄貴が偉大すぎて影に隠れていますが、なかなか味のあるいい歌手です。
本盤でも、いい感じに歌っていて好感が持てます。
この人のヴィンテージ録音では、ずっと昔にアナログ盤で聴いた、"They Don't Know"が好きでした。
当時、ワーナーが出していた「ソウル・ディープ」の第2集に入っていたような気が…。(未確認です)
今なら、英KentのCD、"Sanctified Soul"で聴くことが出来ます。
(廃盤になっていなければ)
さて、お目当てのOtis Clayですが、私は現役のサザン・ソウル・シンガーでは、最も好きな人です。
オリジナル・アルバムこそ、ご無沙汰気味ですが、ときどき色んな企画盤に参加していたりするので、常にアンテナを張っておく必要があります。
本盤では、2曲に参加していますが、ラスト・ナンバーは同じ曲のPart2なので、実質は1曲ですね。
Otis Reddingを連想させる南部風ジャンプ・ナンバーで、「ガッタ、ガッタ」ならぬ「ガットゥ、ガットゥ」と連呼しています。
元気そうで、久しぶりに声が聴けただけでも嬉しかったです。
それよりも、やはりこのバンドは、インスト・ナンバーですね。
特に今回は意識してやっているのか、いくつかの曲では、MGsを思わせる曲があり、「おっ」と耳を惹かされます。
5曲目の"Jack And Ginger"が、出だしからしてMGs風で、これはよいです。
MGsは、グルーヴィーでねちっこいオルガンに、ギターが鋭くコンパクトに切り込んでくる曲が、ひとつの得意パターンでしたが、こちらはそんな雰囲気をうまく再現していて、嬉しくなります。
MGsのもうひとつのパターンとしては、イージーリスニング的なリラックス・チューンがあって、そういった要素が感じられる曲も見受けられます。
6曲目の"Sundown On Beale、"10曲目の"Cauley Flower"が、これまたいい雰囲気に決まっています。
ボーカル曲では、何といっても、Willam Bellが参加した、"Weak Spot"が素晴らしい出来だと思いました。
この曲の作者には、Bellの名前が共作者としてクレジットされていますが、メロディがいかにもBell風で、一音目が始まると同時に、一瞬世界がBell色に染まる感じを受けるのは、ひいきが過ぎるでしょうか。
William Bellは、メンフィス・ソウルのパイオニアであり、優れたソング・ライターでもありました。
ヴィンテージ期の名曲を、後年再録音するシンガーは少なくないですが、名作の新録音が素晴らしいと感じた人は、William Bellだけです。
Bell自身の会社、Wilbeから02年リリースされた、"Collectable Edition Greatest Hits"は、Stax時代の代表曲の新録音集で、タイトルが陳腐でジャケもしょぼいですが、中身はお奨めです。
生き生きとしたバックの演奏にのせて、Bellのジェントルなヴォーカルが、衰えない冴えを聴かせます。
さて、本盤唯一のカバー曲だと思われるのが、9曲目の"I'm Going Home"です。
Prince Conleyという無名のシンガーの曲ですが、Staxの9枚組Box、"The Complete Singles 1959-1968"のDisc1に収録されています。
この渋すぎる選曲は、南部音楽ヲタとしては、にやりとさせられます。
私は、先ほどから、本盤のテーマともいうべき、冒頭の"Hi Roller"をリピートして聴いています。
インストなんですが、中盤で出てくるCropper風のフレーズ(Sam & Daveのバックに出てきそうな、Otis Rush風にも聴こえるもの)が気に入って、繰り返し聴いているのです。
この曲と、"Jack And Ginger"が、特にお奨めです。
もちろん、Otis Clay、Percy Wiggins、William Bellが参加したヴォーカル曲は、60sソウル・ファンには必聴でしょう。
関連記事はこちら
愛なき世界で
ゴスペル・イン・マイ・ソウル
ヴァンソロジー
私は、全く存在を知りませんでしたが、今年出た新作で、過去に1枚アルバムがあるらしいです。
私は、Otis Clayが好きなので、そのアンテナに引っかかって知りました。
このバンドは、基本的にソウル・インスト・バンドなので、ヴォーカル曲は、数人のゲストが参加して務めています。
私は未聴ですが、前作の1stは全編インストかも知れないです。

Got To Get Back !
The Bo-Keys
The Bo-Keys
1. Hi Roller (Franklin, Bomar,Pitts)
2. Got To Get Back (To My Baby) (feat. Otis Clay) (Bomar, Carter, Franklin, Pitts)
3. Just Chillin' (Bomar, Gamble, Franklin, Pitts, Tuner)
4. Catch This Teardrop (feat. Percy Wiggins) (C.Reese, H.Reese)
5. Jack And Ginger (Bomar, Franklin, Pitts)
6. Sundown On Beale (Bomar, Franklin, Pitts)
7. Weak Spot (feat. William Bell) (Bell, Bomar, Franklin, Hall, Pitts)
8. 90 Days Same As Cash (Bomar, Franklin, Hall, Pitts)
9. I'm Going Home (feat. Charlie Musselwhite) (Conley)
10. Cauley Flower (Franklin, Bomar, Pitts)
11. Work That Sucker (feat. Charles "Skip" Pitts) (Pitts, Bomar, Franklin)
12. Got To Get Back (To My Baby) Pt. 2 (feat. Otis Clay) (Bomar, Carter, Franklin, Pitts)
私は、ソウル・ファンのつもりですが、Bar-keysにはほとんど関心を持っていませんでした。
確かOtis Reddingのツアー・バンドを務めたバンドじゃなかったですか?
Watstaxのビデオで見た気がします。
私には、サザン・ソウルより、Albert Kingのバックをやったファンキー・ブルースのアルバムの印象が強いです。
このBo-Keysは、そのBar-keysの残党をベースに、活きのいい若手を加えたバンドで、ざっくり言えば、60s70sの南部ソウル・サウンドのリバイバル・バンドです。
ファンキーな曲やジャズ・ソウル的な展開を得意としているようですが、本盤では黄金時代のメンフィス・ソウルを意識した音づくりに挑んでいるようです。
ゲストのメンツが、より一層、そう感じさせるのかも知れません。
私は、オリジナル・メンバーにうといんですが、参加メンツは以下のとおりです。
Scott Bomer : bass, percussion
Charles "Skip" Pitts : guitar
Howard Grimes : drums, percussion
Willie Hall : drums, percussion
Archie "Hubbie" Turner : keyboad
Al Gamble : keyboad
Mark Franklin : trumpet
Ben Cauley : trumpet
Kirk Smothers : tenor & baritone sax
Derrick Williams : tenor sax
Floyd Newman : baritone sax
Jim Spake : baritone sax
Spencer Wiggins & John Gary Williams : background vocals on "Catch That Teardrop"
Howard Grimesに反応してしまいますが、どうやらメインのドラムは、Willie Hallのようです。
それよりも、最後にチラッと出てくる、Spencer Wigginsの名前が気になりますね。
この人は、弟のPercy Wigginsがボーカルをとった、4曲目の"Catch This Teardrop"でコーラスとして参加しているようです。
(声の判別は、言われなけば困難です。)
Percy Wigginsは、兄貴が偉大すぎて影に隠れていますが、なかなか味のあるいい歌手です。
本盤でも、いい感じに歌っていて好感が持てます。
この人のヴィンテージ録音では、ずっと昔にアナログ盤で聴いた、"They Don't Know"が好きでした。
当時、ワーナーが出していた「ソウル・ディープ」の第2集に入っていたような気が…。(未確認です)
今なら、英KentのCD、"Sanctified Soul"で聴くことが出来ます。
(廃盤になっていなければ)
さて、お目当てのOtis Clayですが、私は現役のサザン・ソウル・シンガーでは、最も好きな人です。
オリジナル・アルバムこそ、ご無沙汰気味ですが、ときどき色んな企画盤に参加していたりするので、常にアンテナを張っておく必要があります。
本盤では、2曲に参加していますが、ラスト・ナンバーは同じ曲のPart2なので、実質は1曲ですね。
Otis Reddingを連想させる南部風ジャンプ・ナンバーで、「ガッタ、ガッタ」ならぬ「ガットゥ、ガットゥ」と連呼しています。
元気そうで、久しぶりに声が聴けただけでも嬉しかったです。
それよりも、やはりこのバンドは、インスト・ナンバーですね。
特に今回は意識してやっているのか、いくつかの曲では、MGsを思わせる曲があり、「おっ」と耳を惹かされます。
5曲目の"Jack And Ginger"が、出だしからしてMGs風で、これはよいです。
MGsは、グルーヴィーでねちっこいオルガンに、ギターが鋭くコンパクトに切り込んでくる曲が、ひとつの得意パターンでしたが、こちらはそんな雰囲気をうまく再現していて、嬉しくなります。
MGsのもうひとつのパターンとしては、イージーリスニング的なリラックス・チューンがあって、そういった要素が感じられる曲も見受けられます。
6曲目の"Sundown On Beale、"10曲目の"Cauley Flower"が、これまたいい雰囲気に決まっています。
ボーカル曲では、何といっても、Willam Bellが参加した、"Weak Spot"が素晴らしい出来だと思いました。
この曲の作者には、Bellの名前が共作者としてクレジットされていますが、メロディがいかにもBell風で、一音目が始まると同時に、一瞬世界がBell色に染まる感じを受けるのは、ひいきが過ぎるでしょうか。
William Bellは、メンフィス・ソウルのパイオニアであり、優れたソング・ライターでもありました。
ヴィンテージ期の名曲を、後年再録音するシンガーは少なくないですが、名作の新録音が素晴らしいと感じた人は、William Bellだけです。
Bell自身の会社、Wilbeから02年リリースされた、"Collectable Edition Greatest Hits"は、Stax時代の代表曲の新録音集で、タイトルが陳腐でジャケもしょぼいですが、中身はお奨めです。
生き生きとしたバックの演奏にのせて、Bellのジェントルなヴォーカルが、衰えない冴えを聴かせます。
さて、本盤唯一のカバー曲だと思われるのが、9曲目の"I'm Going Home"です。
Prince Conleyという無名のシンガーの曲ですが、Staxの9枚組Box、"The Complete Singles 1959-1968"のDisc1に収録されています。
この渋すぎる選曲は、南部音楽ヲタとしては、にやりとさせられます。
私は、先ほどから、本盤のテーマともいうべき、冒頭の"Hi Roller"をリピートして聴いています。
インストなんですが、中盤で出てくるCropper風のフレーズ(Sam & Daveのバックに出てきそうな、Otis Rush風にも聴こえるもの)が気に入って、繰り返し聴いているのです。
この曲と、"Jack And Ginger"が、特にお奨めです。
もちろん、Otis Clay、Percy Wiggins、William Bellが参加したヴォーカル曲は、60sソウル・ファンには必聴でしょう。
Got To Get Back by Bo-Keys feat. Otis clay
関連記事はこちら
愛なき世界で
ゴスペル・イン・マイ・ソウル
ヴァンソロジー
【ディープ・ソウルの最新記事】