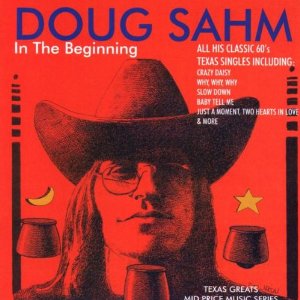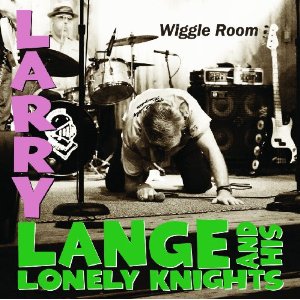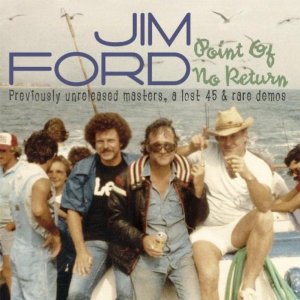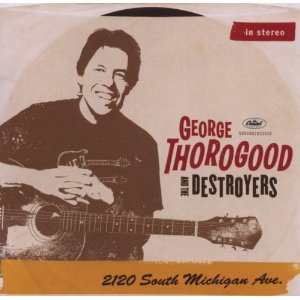2011年08月03日
メンフィス・ソウル、バイユー・スタイル
この人は、現役のSwamp Popシンガーの中で、最も精力的に活動している人ではないかと思います。
とはいえ、一般的には、全く無名ですよね。
私も知ったのは、それほど以前ではありません。
Don Richというと、Back Owensのバッカルーズのリード・ギターに同名の人がいて、アマゾンで検索すると、そちらが先にヒットしますが別人です。
90年代後半くらいにCDデビューしたと思われ、当初は自作中心でアルバム作りをしていましたが、いつごろからか、ステージで受けるようなカバー曲をまじえるスタイルが定着し、現在に至っているようです。
本作は、05年リリースの作品になります。

1. What Went Wrong (Don Rich)
2. Don't Be Afraid of Love (Otis Redding)
3. You Don't Miss Your Water (William Bell)
4. I'm a Fool to Care (Ted Daffan)
5. Sad Song (Steve Cropper, Otis Redding)
6. My Lover's Prayer (Otis Redding)
7. 'Tit Bayou (Trad. arr. Don Rich)
8. Cry Foolish Heart (J. A. Guillot)
9. Bony Maronie (Larry Williams)
10. Dreams to Remember (Otis Redding, Z. Redding, J. Rock)
11. It's Killing Me (Charles Guilbeau, Don Rich)
12. Lose the Blues (Tommy McLain)
13. Just a Dream (Jimmy Clanton)
14. Hey Mom (Don Rich)
Swamp Popは、ニューオリンズR&Bと付かず離れずの関係にあります。
例えば、Bobby Charlesなどは、一般的にニューオリンズR&Bの人と見られていますが、その音楽は、Swamp Popと呼んでも差支えないでしょう。
もともと、Swamp Popには明確な定義がないと思われ、米国のライターの中には、Fats DominoをSwamp Popの最大の成功者ととらえている人もいます。
まあ、これは広義の考え方ですね。
狭義には、ケイジャンやブラック・クリオールなど、出身文化にその定義を求める考えもあるようです。
この考え方によれば、ケイジャンやザディコに近い音楽性となるでしょう。
Johnnie Allanなどは、この考え方にぴったりの人ですね。
しかし、Swamp Popの表の顔は、あくまで黒人R&Bのイミテイト(それが不適切ならシュガー・コート)というイメージです。
しかも、しばしばセンチメントなメロを持つという特徴から、日本人に好まれてきました。
そんなSwanp Popですが、メンフィス・ソウルなど、サザン・ソウルのカバーも好んで取り上げられてきました。
本盤は、その典型といいますか、「どれだけOtisが好きなの?」と言いたくなる内容になっています。
なんとOtis Reddingを4曲もやっているのでした。
次の通りです。
2. Don't Be Afraid of Love
5. Sad Song
6. My Lover's Prayer
10. Dreams to Remember
このうち、"Don't Be Afraid of Love"は、未発表曲集、"Remember Me"収録曲で、レアな選曲ですね。
"Sad Song"は、一般的には"Fa-Fa-Fa-Fa-Fa"として知られている曲で、名盤"Dictionary Of Soul"収録曲です。
そして、同じ「ソウル辞典」収録曲でも、"My Lover's Prayer"が渋いチョイスで興味深いです。
私は、今回のOtisものでは、この曲の出来が一番好きです。
"Dreams to Remember"は、もちろん"I've Got Dream to Remember"で、カバーも多い人気曲ですね。
カバーでは、Delbert Mclinton盤を思い出します。
Don Richという人は、モダンなSwamp Popシンガーの中では、かなり歌える人だと思います。
Swamp Popでは、しばしばヘタうま系だったり、線の細い青白系のボーカリストが見受けられますが、この人は普通にうまい人です。
ただ、ここまでOtisの楽曲をやられると、Otisファンとしては、声に「Sad感」が足りない、などとつい言いたくなるのでした。
Don Richは、歌うだけでなく、ピアノとオルガンを弾いていて、バンドのサウンドの要でもあります。
バンドは、生のホーン陣を擁する編成で、往年のメンフィス・サウンドの再現を試みようと頑張っています。
そういえば、William Bellの名作、"You Don't Miss Your Water"は、Otisも"Otis Blue"でやっていますから、こちらもOtisのカバーと言えるかも知れません。
やはり、好きなんでしょう。
その他の曲も聴いていきましょう。
"I'm a Fool to Care"は、ヒルビリー・シンガーのTed Daffanの作品ですが、Swamp Popでは、Joe Barry盤が成功したことから、人気曲になっています。
カバーもかなりあると思います。
Freddy Fenderもやっていると思いますが、私はデビューしたてのJoe King Carrascoがやったバージョンが強く印象に残っています。
Ted Daffanという人は、他にも"Born To Lose"という人気曲があり、これまたカバーが多数あるはずです。
私がすぐに連想するのは、Ray Charles盤です。
"Cry Foolish Heart"は、初めて聴いた曲ですが、なかなかいい曲だと思いました。
この曲の作者は、J.A.Guillotとなっていますが、Johnnie Allanの本名です。
Johnnie Allan Guillotですね。
芸名には、フランス系の姓が伏せられていたわけです。
ファースト・ネームとミドル・ネームで芸名を名乗っている人は、少なくないですね。
Raymond Charles Robinsonがそうです。
Rayの場合は、有名なボクサー、Suger Ray Robinsonとの混同をさけるためだったらしいですが。
もう一人例をあげれば、Robert Charles Guidryさんがいますね。
もちろん、Bobby Charlesです。
この人のGuidryという姓は、やはりフランス系なのでしょうか?
英語系でないにしても、何となく違うような響きがしますが。
では、Don Richはどうでしょう。
Donald Richardとか、Richardsonかもしれないですね。
仮にDonald Richardなら、そのあとに、やはりフランス系の姓があってもおかしくなさそうです。
脱線しました。
私は、この手の名前の話が好きなのです。
Tommy MacLain作となっている"Lose the Blues"は、初めて聴く曲です。
Tommyは、今気になっているひとりなので、過去作を探したい気持ちがふつふつとわいてきています。
"Just A Dream"は、名作中の名作ですね。
作者は、Jimmy Clantonで、原曲は彼の自作自演です。
米Aceを代表する曲ですね。
私は、Sir Douglas Quintet盤で初めて聴いて以来、大好きな曲です。
Johnny Aceの"Predging My Love"と並ぶ永遠の名曲だと思います。
Don Richは、聴きがいのある歌い手だと思いました。
カバー曲の料理ぐあいをなぞるだけでも楽しいです。
もっと聴きたいシンガーです。
とはいえ、一般的には、全く無名ですよね。
私も知ったのは、それほど以前ではありません。
Don Richというと、Back Owensのバッカルーズのリード・ギターに同名の人がいて、アマゾンで検索すると、そちらが先にヒットしますが別人です。
90年代後半くらいにCDデビューしたと思われ、当初は自作中心でアルバム作りをしていましたが、いつごろからか、ステージで受けるようなカバー曲をまじえるスタイルが定着し、現在に至っているようです。
本作は、05年リリースの作品になります。

Bayou Soul
Don Rich
Don Rich
1. What Went Wrong (Don Rich)
2. Don't Be Afraid of Love (Otis Redding)
3. You Don't Miss Your Water (William Bell)
4. I'm a Fool to Care (Ted Daffan)
5. Sad Song (Steve Cropper, Otis Redding)
6. My Lover's Prayer (Otis Redding)
7. 'Tit Bayou (Trad. arr. Don Rich)
8. Cry Foolish Heart (J. A. Guillot)
9. Bony Maronie (Larry Williams)
10. Dreams to Remember (Otis Redding, Z. Redding, J. Rock)
11. It's Killing Me (Charles Guilbeau, Don Rich)
12. Lose the Blues (Tommy McLain)
13. Just a Dream (Jimmy Clanton)
14. Hey Mom (Don Rich)
Swamp Popは、ニューオリンズR&Bと付かず離れずの関係にあります。
例えば、Bobby Charlesなどは、一般的にニューオリンズR&Bの人と見られていますが、その音楽は、Swamp Popと呼んでも差支えないでしょう。
もともと、Swamp Popには明確な定義がないと思われ、米国のライターの中には、Fats DominoをSwamp Popの最大の成功者ととらえている人もいます。
まあ、これは広義の考え方ですね。
狭義には、ケイジャンやブラック・クリオールなど、出身文化にその定義を求める考えもあるようです。
この考え方によれば、ケイジャンやザディコに近い音楽性となるでしょう。
Johnnie Allanなどは、この考え方にぴったりの人ですね。
しかし、Swamp Popの表の顔は、あくまで黒人R&Bのイミテイト(それが不適切ならシュガー・コート)というイメージです。
しかも、しばしばセンチメントなメロを持つという特徴から、日本人に好まれてきました。
そんなSwanp Popですが、メンフィス・ソウルなど、サザン・ソウルのカバーも好んで取り上げられてきました。
本盤は、その典型といいますか、「どれだけOtisが好きなの?」と言いたくなる内容になっています。
なんとOtis Reddingを4曲もやっているのでした。
次の通りです。
2. Don't Be Afraid of Love
5. Sad Song
6. My Lover's Prayer
10. Dreams to Remember
このうち、"Don't Be Afraid of Love"は、未発表曲集、"Remember Me"収録曲で、レアな選曲ですね。
"Sad Song"は、一般的には"Fa-Fa-Fa-Fa-Fa"として知られている曲で、名盤"Dictionary Of Soul"収録曲です。
そして、同じ「ソウル辞典」収録曲でも、"My Lover's Prayer"が渋いチョイスで興味深いです。
私は、今回のOtisものでは、この曲の出来が一番好きです。
"Dreams to Remember"は、もちろん"I've Got Dream to Remember"で、カバーも多い人気曲ですね。
カバーでは、Delbert Mclinton盤を思い出します。
Don Richという人は、モダンなSwamp Popシンガーの中では、かなり歌える人だと思います。
Swamp Popでは、しばしばヘタうま系だったり、線の細い青白系のボーカリストが見受けられますが、この人は普通にうまい人です。
ただ、ここまでOtisの楽曲をやられると、Otisファンとしては、声に「Sad感」が足りない、などとつい言いたくなるのでした。
Don Richは、歌うだけでなく、ピアノとオルガンを弾いていて、バンドのサウンドの要でもあります。
バンドは、生のホーン陣を擁する編成で、往年のメンフィス・サウンドの再現を試みようと頑張っています。
そういえば、William Bellの名作、"You Don't Miss Your Water"は、Otisも"Otis Blue"でやっていますから、こちらもOtisのカバーと言えるかも知れません。
やはり、好きなんでしょう。
その他の曲も聴いていきましょう。
"I'm a Fool to Care"は、ヒルビリー・シンガーのTed Daffanの作品ですが、Swamp Popでは、Joe Barry盤が成功したことから、人気曲になっています。
カバーもかなりあると思います。
Freddy Fenderもやっていると思いますが、私はデビューしたてのJoe King Carrascoがやったバージョンが強く印象に残っています。
Ted Daffanという人は、他にも"Born To Lose"という人気曲があり、これまたカバーが多数あるはずです。
私がすぐに連想するのは、Ray Charles盤です。
"Cry Foolish Heart"は、初めて聴いた曲ですが、なかなかいい曲だと思いました。
この曲の作者は、J.A.Guillotとなっていますが、Johnnie Allanの本名です。
Johnnie Allan Guillotですね。
芸名には、フランス系の姓が伏せられていたわけです。
ファースト・ネームとミドル・ネームで芸名を名乗っている人は、少なくないですね。
Raymond Charles Robinsonがそうです。
Rayの場合は、有名なボクサー、Suger Ray Robinsonとの混同をさけるためだったらしいですが。
もう一人例をあげれば、Robert Charles Guidryさんがいますね。
もちろん、Bobby Charlesです。
この人のGuidryという姓は、やはりフランス系なのでしょうか?
英語系でないにしても、何となく違うような響きがしますが。
では、Don Richはどうでしょう。
Donald Richardとか、Richardsonかもしれないですね。
仮にDonald Richardなら、そのあとに、やはりフランス系の姓があってもおかしくなさそうです。
脱線しました。
私は、この手の名前の話が好きなのです。
Tommy MacLain作となっている"Lose the Blues"は、初めて聴く曲です。
Tommyは、今気になっているひとりなので、過去作を探したい気持ちがふつふつとわいてきています。
"Just A Dream"は、名作中の名作ですね。
作者は、Jimmy Clantonで、原曲は彼の自作自演です。
米Aceを代表する曲ですね。
私は、Sir Douglas Quintet盤で初めて聴いて以来、大好きな曲です。
Johnny Aceの"Predging My Love"と並ぶ永遠の名曲だと思います。
Don Richは、聴きがいのある歌い手だと思いました。
カバー曲の料理ぐあいをなぞるだけでも楽しいです。
もっと聴きたいシンガーです。
Heartache's Just Begun by Don Rich
【スワンプ・ポップの最新記事】