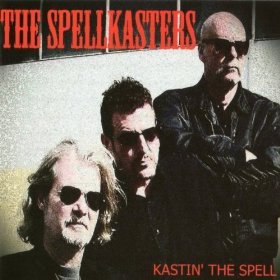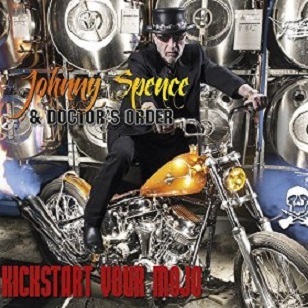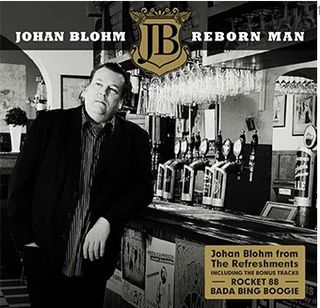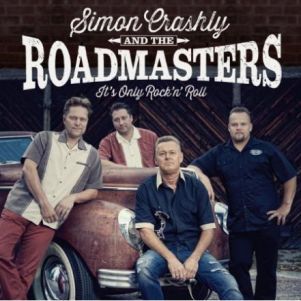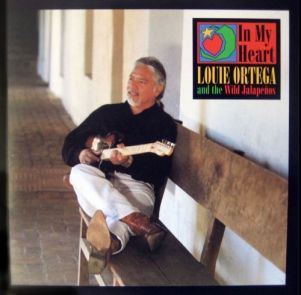2014年10月29日
ぼくの服が マッチ箱に入るなら
赤字追記しました。
久々に聴きました。
当時、好きだったんですよね。
実は私、この人たちのアナログLPを(多分、おそらく、少なくとも!)5枚は持っています。
そんな私ですが、CDは1枚も持っていませんでした。
今回、ちょっとしたことをきっかけに、CDを入手したのです。
The Magnet Records
Singles Collection
Matchbox
Singles Collection
Matchbox
Disc 1
1. Black Slacks (Bennet, Denton)
2. Mad Rush (Steve Bloomfield)
3. Rockabilly Rebel (Steve Bloomfield)
4. I Don't Wanna Boogie Alone (Steve Bloomfield)
5. Buzz Buzz A Diddle It (Slay, Crewe)
6. Everybody Needs A Little Love (Steve Bloomfield)
7. Palisades Park (As Cyclone) (Barris)
8. Crazy Haze (As Cyclone) (Major)
9. Midnite Dynamos (Steve Bloomfield)
10. Love Is Going Out Of Fashion (New Version) (Steve Bloomfield)
11. Scotted Dick (Matchbox)
12. When You Ask About Love (Curtis, Allison)
13. You've Made A Fool Of Me (Poke)
14. Over The Rainbow / You Belong To Me (Harburg, Arlen, King, Price, Stewart)
15. Don't Break Up The Party (Steve Bloomfield)
16. Stay Cool (Redhead, Scott, Callan, Poke)
Disc 2
1. Babe's In The Wood (Steve Bloomfield)
2. Tokyo Joe (Callan)
3. Love's Made A Fool Of You (Holly)
4. Springheel Jack (Fanton, Callan)
5. Angels On Sunday (Steve Bloomfield)
6. City Woman (Callan, Scott)
7. 24 Hours (Reed)
8. Arabella's On Her Way (Steve Bloomfield)
9. One More Saturday Night (Hodgson, Peters)
10. Rollin' On (Matchbox)
11. Riding The Night (Hodgson, Peters)
12. Mad Bad And Dangerous (Hodgson, Callan)
13. I Want Out (Featuring Kirsty Maccoll) (Hodgson, Peters, Colton)
14. Heaven Can Wait (Hodgson, Callan)
Bonus Japanese Single
15. I'm A Lover Man (Tadao Inoue, English lyrics by Bill Crutchfield)
16. Little Lonely Girl (Tadao Inoue, English lyrics by Bill Crutchfield)
正直、ほとんど覚えていませんでした。
ですので、かなり新鮮な気持ちで聴くことが出来ました。
ロカビリーではありますが、かなりポップです。
オールディーズ系のノスタルジー・バンドに近い楽しさがあります。
しかし、そのサウンドには(当時)新しさが感じられ、スラッピングの録り方など、すぐ近づいていたネオ・ロカビリーの萌芽を見る(聴く)ことが出来ます。
本盤は、本年14年に組まれた最新編集盤で、Magnet Records時代のシングルを2枚組にまとめた、大変お得なCDになっています。
オリジナルLPで言いますと、
Riders In The Sky (76年) Rockhouse (ニュージーランド?盤)
Settin' The Woods On Fire (78年) Chiswick (UK)
の2枚を経て
Matchbox (79年) CDにはボートラ3曲追加
Midnite Dynamos (80年) CDボートラ6曲追加
Flying Colours (81年) CDボートラ3曲追加
Crossed Line (82年)
以上4枚がMagnet Records(UK)のもので、本盤の対象の時代になります。
最初の2枚を含めた上記6枚の内、最後の"Crossed Line"のみ、私は持っていません。(これは間違いないです。)
また、その"Crossed Line"のみ、現時点では未だCD化されていません。
追記:どうやら、Bear Familyから、Flying Colours+Crossed Lineという2in1盤が出でいるようです。
ちなみに、この後、Magnetとの契約が切れ、次のアルバム、"Comin' Home"(98年)を出すまで、何と約16年のインターバルを要することになったのでした。(一旦解散、もしくは休業状態だったかも知れません。)
そして時代は移り、CD時代になっていくのでした。
私が今回、Matchboxに関心を寄せることになった原因は、2つあります。
まず、あるコンピCDで、"Seventeen"というMatchboxがカバーした曲の原曲を聴いて感激したこと。
(狙ったわけでもなく、不意打ちのように、こういう曲に出会うと興奮します。)
そして、スウェーデンのロカビリー、R&Rバンド、Simon Crashly & The Roadmastersの最新作で、"Harricane"のカバーを聴いたことです。
"Harricane"は、Matchbox"の中心人物、リード・ギターリストのSteve Broomfieldが書いたオリジナル曲です。
これら2つの出来事が相次いで起こったため、Matchboxを聴きたい症候群が発生していたのでした。
しかし、LPを引っ張りだすことは出来ればしたくありません。
(ここ2年ほど、LPは全く触っていないため…。ぶるる)
そんな時、この新しい編集盤の存在を知ったのでした。
あの懐かしい代表曲がズラリ並んでいて壮観です。
Disc 1
1. Black Slacks
3. Rockabilly Rebel
5. Buzz Buzz A Diddle It
6. Everybody Needs A Little Love
9. Midnite Dynamos
12. When You Ask About Love
Disc 2
3. Love's Made A Fool Of You
14. I'm A Lover Man
15. Little Lonely Girl
なかでも、"Rockabilly Rebel"、"Buzz Buzz A Diddle It"、"Midnite Dynamos"、"When You Ask About Love"などは、英本国での代表ヒットでしょう。
いずれもDisc1に収録されていますが、実はDisc2も、内容的に決して負けてはいません。
私は、これらを聴いて、久々に胸が熱くなりました。
しかも、他にも美味しい曲があるのです。
本盤未収録の曲では、The Blastersの"Marie Marie"、Joe Crayの"Sixteen Chicks"、Buddy Hollyの"Tell Me How"、Richie Valensの"C'mon Let's Go""なんかもレパートリーです。
"Marie Marie"は、本家やShakin' Stevens盤が上かも知れませんが、総じて良い出来の作品が多いです。
さて、Magnet時代のLP4枚プラスCDに追加収録されたボートラ12曲を含む全62曲のうち、本2枚組にはほぼ半数の曲が収録されています。
本盤はシングル・コレクションであるため、代表曲は網羅しています。
しかし、アルバムのみの収録曲に良曲があることはよくあることです。
ちなみに、前述した、"Seventeen"、"Harricane"は、いずれも3rdアルバム(Magnetの1枚目)、"Macthbox"収録曲ですが、本盤には未収録です。
逆に、本CDでしか聴けない曲もあります。
未CD化の"Crossed Line"からは5曲がセレクトされていて、現時点では貴重です。
この"Crossed Line"から、それまでの中心人物、Steve Broomfield(g)が脱退し、新加入したメンバー、Brian Hodgson(b)が作曲の中心を担っていて、これがなかなか良くて新鮮です。
1曲名前をあげるなら、"One More Saturday Night"でしょうか。
他の曲も良いです。
そして、日本盤LPにのみ追加収録されていた2曲が、本盤で聴くことが出来きるのですが、これは、あるいは英国初登場かもしれません。
I'm A Lover Man
Little Lonely Girl
の2曲です。
この2曲は、いずれも元ブルーコメッツの井上大輔(井上忠夫)氏の作品で、Bill Crutchfieldという人が英詞をつけているようです。
サントリー(Suntori Beerと表記)のCMソングだったと、ブックレットのライナーで触れられています。
また、日本語タイトルを"Bi Ri Te N Go Ku"だとして、Rockabilly Heavenという意味だと解説しています。
どこかで"Ro Ka"が行方不明になったようで面白いです。
この2曲も、やはり懐かしくて涙がでそうです。
とりわけ、"I'm A Lover Man"は、マンブル風の口ごもった歌い方から始まるのがかっこよく、怪しげなエコーの中、しゃくりあげるヒーカップ唱法まで、日本人がイメージするロカビリーの典型そのもので、最高にムネアツです。
このバンド、実は地味に現役のようで、しかも全盛期(Magnet時代)のメンバーが再結成しているようなので、またおっかけてみようか、なんて思いだしているこの頃です。
Rockabilly Rebel
by Matchbox
by Matchbox
Midnite Dynamos
by Matchbox
by Matchbox
I'm A Lover Man
by Matchbox
by Matchbox
関連記事はこちら
Shakin' Stevens
シェイキー、霧の中の結末
シェイキーの青空の使者
僕のシェイキーに何か
シェイキーのマンハッタン・メロドラマ
シェイキー、日の出に旅立つ
シェイキー、理由ある反抗
シェイキーの陽気にいこうぜ
シェイキーのロッキン・クリスマス
テイク・ワン
ジス・オール・ハウス
やっかいごとはごめんだよ
終わりだなんて言わないで
涙はほんの少しだけ
The Blasters
前門の爆風、後門の狼
Simon Crashly
ロック、スウェディッシュ・ロール
ロックパイルが北欧に残した芽