中世の山城をベースに近世城郭として設備された大多喜城を訪ねました。
<大多喜城>おおたき
こちらは本丸跡に建てられた天守をイメージした博物館です。現在の大多喜城のシンボルですね。
■上総武田氏の支配■
大多喜城は、上総武田氏の一族・真里谷(まりやつ)氏による築城から始まります(1521年)。上総武田氏は名の示す通り甲斐源氏の支族。房総半島に渡った名門ですね。
当時の地名は小田喜であったことから、小田喜城と呼ばれていました。のちの大多喜城は、この時代の城を元に築き直されたと考えられています。
2つは別の城という考え方もあるようです。確かに、初期の城の主郭は現在とは別の丘にありました。ただ、私は真里谷氏がこの付近を選んで拠点とした時をもって、城のはじまりと受け止めることにしました。
やがて上総武田氏の勢力は衰退し、築城者である真里谷信清の孫・朝信が、里見氏配下の正木氏に討ち取られたことで、大多喜城は里見氏の支配下におかれます。
<無料駐車場>
当日はここから本丸を目指しました。
<大多喜城址石柱>
駐車場から緩やかな坂道(メキシコ通り)を登ればそこはもう大多喜城跡です。むかしの大手は山の逆側ですので、裏から入ることになります。
<参考>
途中で左手に曲れば初期の大多喜城があった栗山地区です。こちらにも遺構があるようですが、私は直進して本丸跡を目指しました。参考まで
■里見氏の支配■
真里谷氏の所領を奪い取った正木氏は、この時点では里見氏配下ということになります(家臣と表現されることが多い)。ただ、もともとは里見氏同様に房総半島で地道に勢力を拡大していった独立した豪族です。諸説ありますが、三浦氏を祖とする一族とも言われています。里見氏との関係ですが、主従というより、利害が一致する同盟関係と考える方が妥当かと思われます(個人的な感覚です)。
真里谷氏を破った正木時茂は、里見氏の勢力の代表者として上杉謙信と交渉したりもしています。その上杉謙信による小田原城攻め(1561)にも参陣しており、単なる里見氏の家臣ではなく、かなり有能な武将として知られた人物でした。時茂は槍術にも優れていたことから、槍大膳と称されました。
正木氏の大多喜城支配は4代続き、上総国東部支配の拠点として機能しました。正木氏による継承が途切れたあとは、里見氏の代官が派遣されました。関東覇者となった小田原北条氏と、房総半島での覇権を争う里見氏にとって、引き続き重要な拠点であり続けたわけですね。
<入口付近>
入口付近には説明板が設置されています。右手に見えている丘は本丸下の出丸跡です。
<説明板>
ここに記載のある通り、私の訪問時は施設改修のため冒頭の画像の天守(博物館)は休館中でした。ただし展示物の一部が敷地内の別の建物に移されていたため、ありがたく見学させて頂きました。
右側には縄張り図が掲載されています。曲輪が西側から(この絵図だと上から)本丸・二の丸・三の丸と続く連郭式の城です。本丸の標高は73mで、南は崖と川、西には空堀、北と東は水堀です。明治まで続く近世城郭として仕上がってはいますが、基本は中世の山城だったことが見てとれます。
<堀切>
山を登り始めると右手に堀切跡が現れます。現地説明板の通り「空堀」に間違いありませんが、場所からして堀切と言った方が無難かと思います。登山道が整備されず斜面のままだったら、もっと分かり安かったと思います。
<堀切のスケール>
人と比較すると堀切のスケールが伝わると思います。
画像は同行した友人が背後から撮影してくれました。城跡巡りは基本的には独りですが、この日は会社の友人二人と探索しました。
■徳川氏の支配■
豊臣秀吉の小田原征伐により、戦国大名としての北条氏は滅びました(1590年)。この時、里見氏は小田原参陣に積極的ではなかったことから、広範囲にわたって所領を没収されてしまいます。ただし、もともとの所領である安房国はゆるされました。
関東を治めることになった徳川家康は、徳川四天王のひとり・本多忠勝を大多喜城に入城させました。所領が縮小されたといっても、地域に深く根を張っている房総半島南部の里見氏をけん制するためです。本多忠勝は1601年に伊勢国の桑名城に移るまでの約10年間、大多喜城の城主でした。
典型的な中世の山城だった大多喜城は、この時に近世に相応しい城として生まれ変わりました。
<幟>
歴史の長い城ですが、やはり徳川四天王のひとりである本多忠勝が推しのようですね。忠勝は10万石で大多喜城主となっています。
本多氏は3代で国替えとなり、城主は阿部氏・青山氏・稲垣氏と変わったあと、1703年からは松平氏が9代続き、廃藩置県を迎えます。最後の城主は松平豊前守正質でした。正質(まさただ)は、大多喜藩主というだけでなく、幕府の中核メンバーでした。鳥羽・伏見の戦いでは旧幕府軍を総督として指揮しています。敗北後に大喜多へ敗走し、新政府から官位などもはく奪されましたが、その後は許され、大多喜藩知事となっています。
<二之丸公園>
階段から更に上の区画に移動できます
<二之丸公園階段>
岩の層が目をひきます。泥岩の類でしょうか(不明)?
<鐘つき堂>
梵鐘が見えてきました。かつて大多喜城下に響き渡った歴史ある鐘とのこと
<平らな区画>
二之丸公園となっていますが、二の丸そのものはもっと広大であることから、ここは出丸的な場所と思われます(個人見解)。
<堀跡>
区画の柵から下を覗き込むと堀(堀切)が見えます
<堀切跡>
こちらは二之丸公園奥の堀切。尾根を切断した跡ですね
山中の遺構は豊富ですが頂上へ進みます
<模擬天守>
天守風の千葉県立中央博物館大多喜城分館。立派です。調査の結果、大多喜城跡に天守台は発見されていないそうです。実際に天守があったかは不明ですが、古絵図を元に復原とされています。
<本丸土塁跡>
本丸を囲む土塁です。土塁の向こう側は山の斜面を垂直に削った切岸になっています。
<研修館>
博物館は残念ながら休館ですが、こちらを見学させて頂きました
本丸から二の丸へ向かいます
<登山道>
こちらから丘を下りました
<丘陵>
二の丸側から見上げた本丸のある丘
<二の丸>
県立大多喜高校の校舎は二の丸御殿の跡、一段低くなったこのクラウンドも含めて二の丸跡です。かなり広い二の丸だったようです。近世城郭になってからは、ここが城の中心だったと思われます。縄張り図を参考にすると、左手の奥には水堀が、正面奥には水堀を挟んで三の丸が設けられていたようです。
<薬医門の説明板>
大多喜高校内には移築され現存する薬医門があります。実は、二の丸に降り立ったものの「ここは高校の敷地なのに、部外者が歩き回って良いものか…」と思い、実物は見ないまま撤収してしまいました。他の方のブログではしっかり撮影されているようです。このブログは管理者が小心者ということでご理解下さい。
<大井戸>
現地説明板によれば1590年に本多忠勝が城を改修した時に造られたことに始まる井戸のようです。通称は「底知らずの井戸」。ちなみに周囲17m、深さ20mとのことです。
城内の様子は以上です
<つわものどもが夢の跡>
中世から始まり、やがて近世の城となり、明治まで存在した城です。深い歴史の刻まれた大多喜城は、続日本100名城に選ばれています。
----------■ 大多喜城 ■----------
別 名: 大滝城
築城年:1512年頃
築城者:真里谷信清
城 主:真里谷武田氏 里見氏
本多氏 阿部氏
長沢松平家 他
改修者:本多忠勝 阿部正次
廃城年:1817年(明治4)
[千葉県夷隅郡大多喜町大多喜]
■参考及び出典
・現地説明板
(大多喜町教育委員会)
・Wikipedia:2023/7/15
・千葉県立中央博物館小冊子
・千葉県立中央博物館HP
(大多喜城分館)
http://www2.chiba-muse.or.jp/www/SONAN/contents/1517929898059/index.html
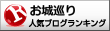
お城巡りランキング
タグ:千葉




