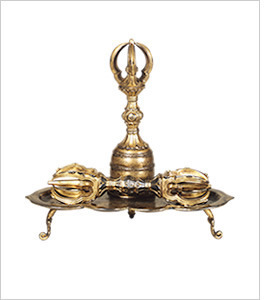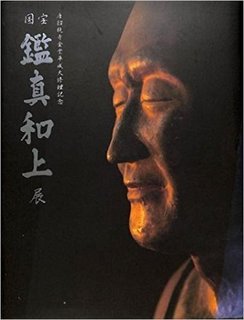2016年12月31日
第2回歴史第3部中世16【日本の古代・枕草子とポルノグラフイー源氏物語】
〈仮名による精神の飛翔・枕草子とポルノグラフイー源氏物語〉
道長は娘の彰子(あきこ)を一条天皇の中宮とし、外戚になる万全の体制をとった(道長の長兄道隆の子・定子(ていし)は既に一条天皇の皇后となり、ひとかたならぬ寵愛を受けていたが、男子を生むことなく他界し、道隆側は没落した)。この円融系の一条天皇の外戚となったのが道長で、その愛人で彰子の家庭教師が紫式部、冷泉系の一条皇后の定子に仕えたのが清少納言で、二人はライバルでした。清少納言は、後輩の紫式部に漢文の知識をひけらかし鼻持ちならないと痛烈に批判されているが、零落しても才智は衰えず、昂然たる品位を失わず、「枕草子」では、悲愴な皇后の生活に寄り添い、口固く「翳りのない明るさで、気高くも美しい皇后の日常を、鋭いしかも辛辣な観察で綴り、宮廷でのほほえましい挿話などを織り込ませた」。「なぜ清少納言は皇后の暗い運命や悲傷な心境に触れなかったのか。背後の事情を知る者には、明るく華やかな「枕草子」の陰(文体)から清少納言の無言の慟哭が聞こえて(97)」きます。まさしく、古代からの重苦しい漢文的素養が、仮名という触媒を得て、自由に表現の力を取り戻して飛翔する素晴らしさを示しているのです。これも、仮名によって蘇った「やまとごころ」なのです。勝ち組の紫式部とは違った、負け組であっても不運を嘆き引きずり続けない、優しいポジティブシンカーだったのです。
彼女の「小さきもの」「消えやすいもの」「移ろいやすいもの」への、温かい視線は、後の俳諧に表れる「しをり(98)」や「ほそみ(99)」に受け継がれます。
一方で紫式部は、律令制の完成と共に歴史書(正史)や昔物語の様な旧型物語の中に閉じ込められた「もの語り」を復興させ、私が本当の物語を書いてやるという意気込みで「源氏物語」創作に力を注いだ。その世界は肉体ばかりか、心の乱交パーティーさながらの、勧善懲悪を無視したアナーキーな物語でもあり、貴族社会の思いのたけを代弁してくれるベストセラーとなった。道徳に近いものと言えば、その場限りの「人笑われならず(人に笑われないような振る舞い)」という美学だけだった。重い道徳感による葛藤は見られない。
道長もたびたび紫式部のもとを訪れ、次巻を催促したり、小説の構成について口を挟んだ。
男心を引き留めるのは、顔の美しさや、あけっぴろげな性格ではないこと(当時は顔が美しいのは性格がいいから、前世の行いが良かったからと、顔にすべてが出るという考えだったから逆のことを言い且つ説得力があるこの物語に新鮮な驚きを持ったろう)、男色こそ「女にてみゆ」と、もし女だったら契りたいほどだ程度のもので、本格的なものは男性貴族の日記文学に任せたものの、それ以外は何でもありの、罪悪感の無い、男女の駆け引き溢れるフリーセックスや父帝の王妃が懐妊するまで続ける姦通(暴力に依らない父殺し)などタブー破りのニヒリズムに溢れている。
中でも、物語の中で、「意中の人」つまり本命の、「身代わり」と契りを交わすというパターンの多さは、裏を返せば、理想の人間などというものは存在しないのだ、だからこそ理想の人間は成るもの、思うものだという爽快なニヒリズムを思わせます。
TVドラマ・「逃げ・恥じ」では、ミクリの母親が、「(運命の人なんて出会うものじゃない)運命の人に、自分でするのよ」と言いました。(比較の目で)外から幸せそうに見えるひとに、幸せなんて無いよというメッセージですね(以上はおおよそ大塚ひかりさんから学んだ源氏の世界です。大塚さんは歴史的・集合的な目で源氏や平家を捉える貴重な方です)。
この思想は「物語」の本質を、ひいては人間の「欲望」の本質を垣間見させてくれます。
とても大事なところなので、よく考えてみてほしいのです。
人は皆、自分の意中の人・理想の人と一緒になりたがります。他の人・性格の悪い人・顔がすぐれない人・色の黒い人など様々ですが好みでない人とは契りたくはありません。これはどういうことでしょう。犬や猫などの動物が、そのような選り好みをするでしょうか。ただ盛がついたタイミングで用を澄ますだけで、あの人が嫌だとかではなく、より強いかどうかだけで選びます。イケメンかどうかなんて関係ありません。これは彼らが本能で動いているからです。人間も好みかどうかなんて関係なく盛に任せているだけなら、強姦されようが屈辱感など感じない筈です。ところが私たちはそんなことはとんでもない。許されない犯罪です。なぜ選り好みをするのでしょう。それは私たちが相手を、本能でなく、物語で見ているからなのです。自分の物語に合わない人と交わりたくないのです。つまりこれが犬や猫の本能でない、「欲望」の正体なのです(犬や猫には本能は合っても欲望は無いでしょう)。これを許しているのが現代社会で、個人の自由というものです。
これを突き詰めるとどうなっていくでしょうか。みんなが自分の物語に合う人を選びたいとすると、考えが浅い時はイケメンや美人を求めて多くの人間が殺到し、そうでない大部分は溢れて大きな偏りが出るでしょうし、更に経験を積んでくると、ふさわしい相手というものは「物」ではないのだから、見かけだけではすぐに飽きてしまう、又それを失うことに神経を使い疲弊することが判り(そこには長く続く物語がありませんから)、「自分の成長に合わせて変化していくこころ安らぐ人間性」を求めるようになるでしょう。つまり観賞用ではなく、自分の人生のパートナーとして=物語の共演者として、相手を見るようになるでしょう。両方揃った方がいい。しかしそんな理想の相手に巡り合う確率は何パーセントでしょうか。ゼロに近いですよね。だから結婚しない人は増え、出生率は下がるのは当然です。勘のいい人は、早く気づきます。自分が理想の物語(欲望)に囚われていることに。そんなものにぎゅうぎゅうにとらわれていては、自分の人生はすぐに終わってしまうと。だからと言って強姦でも構わないというのは行き過ぎですが、ある程度のところで、自分の物語(欲望の質)と妥協します。顔なんて一時のものに過ぎないと悟るわけです(勿論ラッキーにも理想の人と相思相愛の結びつきに出逢える人もあることはあるでしょうが、それとて、美男美女のカップルが、外から人形がかわいく見えるように何不自由なくお決まりの筋書きに動かされているように、お決まりの幸福とやらを演じているのを見るのは、かっこよさとかいう薄っぺらなものを後生大事に守り続けなきゃならない。額縁の中のおとぎ話の何と窮屈な人生であることか)。こうして本当の自分の物語にとって、顔や性格はマストではないことが、年を重ねるうちに判ってくるのです。源氏物語は、(宮中という狭いながらも)社会全体が先にその結論を出してルール化してしまった、ある意味進んだ大人社会だったわけです。
だから強姦は、源氏物語では日常茶飯事でした。更には好みを品定めする顔や性格は皆隠されて夜陰に紛れての行為がルールでした。相手が実際がどのような顔をしていようが関係ない。男も女も「引目鉤鼻(ひきめかぎばな)」で充分だったのです。

問題はどのような出会いの条件かではなく、どんな条件であっても、その与えられた条件を如何に演じるか(切実さ・情愛)にあったのです。いつまでも結婚できないとか、いい人に巡り合えないとか悩んでいる人は、自分の欲望を、つまり物語をすこし変えてやれば、広い世界が見えてくるのに、もったいないと思いますよ。何も平安時代に戻れと言っている訳ではないのですから。物(顔やカッコよさ)はやっぱり見世物に過ぎません。そこにこだわるより、コト(出来事)にこだわらなきゃ。自分の生きるドラマの質に。
又さらには、もっと視界を広げてみると、紫式部が意識していたとは思いませんが、源氏の世界は、「平和とはこういうものか」という一種の到達点と、頂点が故の「転げ落ちる不安」を見せているのではという自問に行きつきます。それは平安という一つの文化の爛熟点に達した(と言っても貴族社会だけですが)からこそたどり着いた平和(100)と、それを維持するために(我慢し)犠牲となった人間の、ぶちまけずにはいられなかった怨念と時代を生きる心の不安や息苦しさが行きつく先を、愛ではなく性を、心ではなく外見をテーマとせざるを得ない、物語という大河(時代の様式)に乗せて語り繋ぎ、図らずも来るべき将来を予測した一人の天才の生きざまでもあったと思います(まるで千年後の現代の市民(当時の貴族程度の生活水準には達しているし、メールやネットで意思疎通をするのは、貴族の手紙や使用人を介しての会話・間接的な伝達方式と似た感触を持つ)の生きざまを予知していたかのように。更には次に来る中世の分裂志向が、現代のトランプ現象に代表される時代の方向が、ポピュリズムで小児的で、遠心力の働く中世の始まりに酷似しているのは、不気味な予感さえ抱かせます)。
このような、権威と権力を分けて、天皇と上皇と女院との間で、均衡をとり生き延びる、「混沌(曖昧)」とした藤原流物語(神話)というものを理解できず、中国風の白黒はっきりし、大義名分論や法家的論理を振り回し、再び社会を混乱に引き戻す(保元の乱)のが、同じ藤原家の信西(しんぜい)入道なのは何という時代の皮肉でしょう。
結局、古代貴族や律令国家の終焉という社会構造の解体期に、氏や共同体的制約から解放され、未だ「家」の縛りには束縛されていない人々(貴族だけですが)が自分の言葉で語り始めるさきがけが、日記であり、手紙であり、物語だったのでしょう。
※皆さん、ここまで読んでくださってありがとうございます。これで今年は最後です。来年も命の続く限り頑張ります。
どうか、良いお年をお迎えください。
注97) 角田文衛「平安の春」講談社学術文庫P55
注98) しをり
蕉風俳諧の根本理念で、題材が哀憐であるのをいうのでなく、人間や自然に哀憐の情をもって眺める心から流露したものが、自ずから句の姿に表れたもの。〈萎(しを)る〉の連用形というのが通説である。
注99) ほそみ
作者の心が対象にかすかに深く入り込んでとらえる美、およびそれが繊細微妙に表現される句境。
注100) 平和とタブー
平和とは、苦しくてつまらないものです。争いを避けて、我慢の連続だ。陰湿ないじめや、噂だけで人の人生を葬ることもできる息苦しい世界だ。ターゲットのされようものなら、ありもしない噂で非難の的にされ、悲惨な人生を送ることにもなりかねない。いつ何時身に覚えのない咎で、罪人になっているかもしれない恐怖を抱えることになる。
そんな中で、弱い人間はことに、周囲や見た目を気にし、「笑われないように振る舞う」のが、自分を貫くよりも、重要な心掛けになる。悲しくても笑みを浮かべ、嬉しくても自制し、言いたいことも言えず(言えば人も自分も傷つくし、自分も傷つきたくない)、そのストレスは知らず知らずに内面に膨れ上がり、自身の肉体や精神を蝕むという形で昇華される。内に向かっては、拒食症や自死、外に向かっては人を騙して陥れたり、更には怨霊となって姿・形を鬼の面相にしたり、それを信じる他人(噂や動揺)の手を借りては、瞬く間に標的に辿り着く。或いは本人の直接ではない手によって(使用人を介した手紙・伝言など)行う通信・伝達によって、時代の常識や世間体に検閲された言葉によるの為の気持ちの「曖昧さ」、「個の埋没」にストレスは溜まる。逆に発信元が誰ともわからないが為に発せられる「噂」は反動で内容は過激で大きく人のこころを傷つけ、人生を左右するまでの力を持つ。傷ついた心を人形で癒すのはペットブームの先駆けかもしれません。
まるで現代のネット社会のようですが、これが源氏物語の描く貴族たちの生活なのです。千年も前に、20世紀の人間たちが悩み恐れていた人間関係が描かれていたという奇跡が、ヨーロッパ人を驚かせたのです。更にはフリーセックスの域を超えて、姦通はざらで、男色も珍しくない(流石に紫式部は女だったのでこの辺りはあまり踏み込みませんが)世界は、「爽快なニヒリズム」を見せて、欧米人の気持ちをわしづかみにしました。今はもう、このような苦しみに我慢ができず、人々が言いたいことを吐き出して我慢しない、収拾のつかない新しい中世に向かって着実に進み始めていますね(怒りも憎しみも現世の内に済ましてしまうから後味もさっぱりして精神衛生上はいい)。中世のきっかけは異民族の侵略でしたが、現在の中世化(遠心力の働く時代)のきっかけは難民や核でしょう。もうお体裁や人助けなんてまっぴらだ、みんな我慢するのはやめて自己主張をするのだ、自分のことは自分でやれというわけです。トランプ現象ですね。「宗教戦争」ならぬ「信念戦争」はもうあちこちで起きていますが、これが今まで平和だった世界各地でも起きてくるでしょう。大江健三郎さんは、ノーベル文学賞の授賞式で、日本の「曖昧さ」が戦争を引き起こしたと言って、川端康成の「美しい日本の私」を批判したようですが、この批判は当たっているでしょうか。これは大江さんだけの問題ではないですが、又森有正にも言えることですが、この世代の人たちには日本の伝統が、西欧の論理のもとに否定されるだけで、正しく理解されていなかったこともあのようなことが言える原因でもあるのです。更には、この否定された日本の伝統の代わりに拠り所にした「ヨーロッパ近代」が、本物の伝統に基づくものではなく、明治・大正が「誤解したヨーロッパ近代」だったのです。いわばゴッホではなく「額縁に入ったゴッホ」だったのです。ヨーロパの貪欲且つ排除主義の上澄みのところだけを見た合理性や美や宗教性が、彼らの新しい様式になったのです。西洋人からすれば大江は、自分たちの論理で話せるかわいいやつと思うでしょう。大江も森も真面目で良心的な人間です。そして川端は少女・屍体なぶりの変態爺さんです。しかしそれでも大江も森も勘違いしていると思います。西洋流の「自我」主義と平和は矛盾しているよと言いたいのです。平和は、女々しくとも、都合のいいように自己正当化をしていない川端の方にあると思います。
先の戦争では、欧米コンプレックスを持つ自閉的な内面を自己正当化しようとして、現実感覚を喪失してしまった日本国民の深層心理が、軍部の自己正当化の精神的な後押しをしたのではないでしょうか。そうなら、彼は何故軍部ばかり批判して、後押しした日本国民を批判しないのでしょうか。
或いは外圧に弱い「曖昧性」を批判するのではなく、それを自我中心の合理しか介しない外国に解らせる道に挑戦しないのでしょうか。元を正せば侵略と排除主義の欧米が、平和に暮らしていた人の家に、正義の名のもとに(文明とやらを教えてやるという)押しかけてきたことが始まりなんですから。その屈辱に対し、仮面を被って(欧米化)その場しのぎで対処したものの、我慢しきれなくなってコンプレックスが爆発して、同じ被害者の本来味方の筈の近隣アジアのまで敵に回して、倒錯した攻撃性を持つに至ったことは責められても当然で、決して正当化はできない犯罪であることは間違いないでしょう。しかしそれは、押しかけて来た西欧(アメリカ)も、攻撃性を剝きだしにした日本も、共に正義の名のもとにやったことで、これが共に悪なんだということです。何も曖昧性を現実と受け留め、そのまま平和に生きてきた民族を、(対外的な)抵抗力が無いからと言って、曖昧だからといって責めるような問題ではないでしょう。
欧米の合理・自我中心の思考が行き詰まり、その先に来るものはやはり「曖昧性(矛盾)」の受容だと思うからです。
源氏物語が示唆するものが、理想的な社会だなどというつもりはありません。
というのも、人々は世間の目を気にし、言いたいこともしたいことも我慢し、感情を押し殺し、コミュニケーション能力は低下し、陰湿ないじめや噂や怨霊にに振り回され人生を台無しにされることもあり、物の怪を恐れ迷信に振り回され、多くの時間を祈りや儀式に割き、個人の心からの欲望は発露されず、常に世間という超自我に抑圧され、そこに辛うじて「もののあわれ」が読み取られるような息苦しい世界だからです。
それでも物の怪など恐れもせずバッタバッタと切り倒してしまう武士の様な暴力勢力の台頭はまだ見られず、まして外国に正義を押しつけるようなことも無く、平和の一つの形を見せたわけです。平家物語が、男性的なるものを著したとすれば、源氏は女性的なるものを示しているんです。
女性的なるものは、自然そのもので、宇宙全体と繋がっていますから、基本的に怖いものは無い。子どもも産めるし、本来は肉体的暴力とは無縁です。だからタブーなんていらないんです。近親相姦なんて、社会の様な幻想を持つ必要が無いから、怖くもなんともない。所有欲も本来はなく、一夫多妻だって何ともない。自我や個人のアイデンティティーなんていらないからです(現代の女性は、近代的な男女平等など、男たちの作り出した所有制度や平等という思想に手なずけられていますから、俄かには信じられないと思いますが)。基本的に自閉の世界なんです。
それを女性とは反対の男が、不安や寂しさから、肉体を、権利を独り占めしたいから、所有権などを持ちたがり、他を縛り付けようとするから争い(奪い合い)が起きるのです。男は子どもも産めないし、女性に利用されてやっと少しは親の気分を頂くくらいが関の山の、自然から疎外された存在なんです。だから声を荒立て(源氏の時代は未だ肉体派ではなく、観念的を弄ぶ風潮の為、遠回しに周囲を気にしながらですが)、自分の存在を主張したがる。その自己主張を様々な形に変化させて(制度や時代の雰囲気・ムードとして)、社会をかき回す。立派な理想や政治的理念や、スポーツの純粋さ、正義の戦争、自衛の為の戦争などなどいくらでも作り上げることができる。もし、平和が善だと言い張るなら、やれオリンピックだの、球児たちの純粋な夢を支援する高校野球だの、未開の可愛そうな民族を文明化させてあげる正義感に満ちた植民地政策や大東亜戦争だの、アメリカの仕掛けたイラク戦争だの、それに抵抗することからかじまったイスラム国のテロだの、ベトナム戦争だの、それに抵抗したべトコンゲリラだの、ナチのアーリア主義を振りかざす虐殺と侵略だの、それに抵抗するレジスタンスだの、
「どんな理想にせよ、ある理想のために真面目に真剣に戦うということは、立派なことだと思われているけれど、そういうことはそれ自体が悪なんだ(*)」ということを知らなければならないということです。これは、何度強調しても足りないくらい重要な言葉だと思います。
とても賛同できないという人は多いと思います。ナチとレジスタンスが共に悪だなんて誰が肯定するものかと思われるでしょう。でもこれを、どちらが悪でどちらが善というふうに分けると、「正義の奪い合い」が始まり、古代の神々から現代までずーーと続く、サディスティックな憎しみの連鎖から抜け出られないわけです。源氏物語は、このような一代しか考えられない男たちの正義に基づく争いに目もくれず、「自我と敵対するものを攻撃する」という呪縛から自由で、いちゃいちゃ生理的に生きているわけです。自我なんかいらない世界なんです。これが人間のできる平和の一つの姿なんです。ねちねちと女々しいと思われるでしょうし、いじめも、えこひいきも、チャッカリもこずるさもありますが、それが嫌なら、心にもない平和を叫ばず、修羅の道を行けばいいのです。但し、正義の名のもとによそを巻き込まないでいただきたいものですが、もうそんな神業の様なことも難しい。込み入ったグローバルとやらの魔力をがっちりと掛けられていて、困ったものです。
平安時代同様、外圧から比較的自由となり、平和のもう一つの形を作り出せた江戸時代と、その平和をぶち破る外圧に揺れた幕末に話を進めるのは行き過ぎですが、やはりここでも攘夷を主張する朝廷と、密貿易で私腹を肥やしていた(実は自分たち主導の条件付き開国派だった)薩長の、心にもない攘夷賛同による朝廷利用作戦に対する、幕府主導の屈辱開国やむ無し派との、「正義奪い合い」の権力闘争で江戸(東京)が火の海になるのを防いだ、即ち正義しか、一代限りしか考えられない男たちの後始末をして、次世代へのバトンタッチをして、権力の座を退かせたのも、天璋院篤姫や皇女和宮などの女たちの決断だったのです。東京が残ったことが良かったのか悪かったのかは言えませんが、少なくとも明治の近代化とやらを遅らせる、或いはもっとひどい植民地化を齎す要因を潰したことだけは事実でしょう。
トルストイの暗示するように、戦争と平和は同じものなんです。身体で戦争しているか、こころで戦争しているかの違いだけなんです。
(*) 伊丹十三、岸田秀「哺育器の中の大人」ちくま文庫2011年11月p39
さて、話を戻しますが、何故平安の貴族たちは、かように平気で強姦や姦通や男色など、タブーとされていることを罪悪感もなく、寧ろ日常時のようにあからさまにするのでしょうか。皆さんは、彼らが単に文化の爛熟の末に、狂っていたというだけで納得できますか?
自然を(本能を)飛び越えた人間にとって、家族が原初のアイデンティティー(自分であることの一貫性)を獲得する場であり、このアイデンティティーが自我であり、これが壊れると人格は成立しない。一旦出来上がった家族を他人とするような行為(例えば近親相姦)は自分自身を崩壊させることで恐ろしくてできない。そうなったら人格(自我)が壊れてしまう恐れがある。これがタブーです(自我のアイデンティティーが親子間の縦軸のものとすれば、社会人としての人格は、国家との間の横軸のアイデンティティーです。これの崩壊を特に恐れるのは愛国主義者です)。これらは、精神分析家岸田秀さんの著書から学び、勝手に再構成した私の考えです。
当時の貴族社会は、女性を軸に構成された社会で、家も財産も娘に与えられ、男は成人として生きていくには、どこかの貴族の娘の家に転がり込むしかなかったのです。子どもが生まれても、母親側でしかも、乳母(めのと)という他人に育てられ、実の父母との近親関係は育ちにくい。子どもは自分が初めて作り上げる自我の物語に、乳母やその子供を近親として入れるのです。実の親は他人なのです。だから、親子の関係を破ってもタブー破りにならないのです。
特に父親は実際に産んでもらってないから他人感がさらに強い。それで光源氏は平気で父帝の王妃である藤壺の宮が懐妊するまで密会し続ける。武力に訴えなかっただけで、姦通による政権転覆の試みです。それを罪悪感もなく実行し続ける。後から源氏は、自身の妻・女三宮が、頭の中将の息子に姦通されることでしっぺ返しを受ける。
しかも当時の性交渉は闇の中で行われるもので、顔や肉体を見られることを極端に嫌いました。それは女性ばかりでなく男性も同様でした。身分が上の人間は人から顔をじかに見られるということがほとんど無く、自分は相手を一方的に見るだけの接し方が日常になります。意思疎通さえ、部下を通しての伝言や手紙を通じてになり、何時しか、自分が生々しい自分でなく、観念的になります。女性は顔を見られたということが、犯されたことと同じに感じます。生々しい自分(現実)を見られたのですから。むしろ兄の家にいた時、男と間違えられて殺されそうになった時、迷わず清少納言は股間を丸出しにして女としての証明をすることで暗殺を免れたといいます。股間も生々しいとは思いますが、顔の知らない人間の股間は、唯の「もの」に過ぎなかったのかもしれません。いきおい、恋と言っても「高貴な人の娘だからさぞかし美しいだろう」のうわさや想像で物語的行為に及ぶわけです。自分も相手も想像ですから、何でもありで、お互いが見られることのないガードのかかった中での観察だから、タブー破りも、現実に囚われない想像逞しい文学も可能だったのでしょう。そして行為の後には、後朝(きぬぎぬ)の歌を交わすことが必須なのです。物語の仕上げです。動物的発散だけではないことの証拠です。
実はお前の顔は、こんな顔なんだと突きつけられる、「はしたない」リアリズムの世界は、後の武者の世です。社会全体が共同で見ていた夢を引っ剥がして、現実に引きずり下ろしたのです。
では、男色はどうでしょう。同じアイデンティティの問題でも、インセスト・タブーが「自我」の樹立に関わる問題であるのに対し、男色は自己の「(身体的ではなく)精神的な性別の選択」に対する問題です。あまりに長い脱線でしたので、これは後程、中世の〈政治手法としての男色〉のところで話します。
道長は娘の彰子(あきこ)を一条天皇の中宮とし、外戚になる万全の体制をとった(道長の長兄道隆の子・定子(ていし)は既に一条天皇の皇后となり、ひとかたならぬ寵愛を受けていたが、男子を生むことなく他界し、道隆側は没落した)。この円融系の一条天皇の外戚となったのが道長で、その愛人で彰子の家庭教師が紫式部、冷泉系の一条皇后の定子に仕えたのが清少納言で、二人はライバルでした。清少納言は、後輩の紫式部に漢文の知識をひけらかし鼻持ちならないと痛烈に批判されているが、零落しても才智は衰えず、昂然たる品位を失わず、「枕草子」では、悲愴な皇后の生活に寄り添い、口固く「翳りのない明るさで、気高くも美しい皇后の日常を、鋭いしかも辛辣な観察で綴り、宮廷でのほほえましい挿話などを織り込ませた」。「なぜ清少納言は皇后の暗い運命や悲傷な心境に触れなかったのか。背後の事情を知る者には、明るく華やかな「枕草子」の陰(文体)から清少納言の無言の慟哭が聞こえて(97)」きます。まさしく、古代からの重苦しい漢文的素養が、仮名という触媒を得て、自由に表現の力を取り戻して飛翔する素晴らしさを示しているのです。これも、仮名によって蘇った「やまとごころ」なのです。勝ち組の紫式部とは違った、負け組であっても不運を嘆き引きずり続けない、優しいポジティブシンカーだったのです。
彼女の「小さきもの」「消えやすいもの」「移ろいやすいもの」への、温かい視線は、後の俳諧に表れる「しをり(98)」や「ほそみ(99)」に受け継がれます。
一方で紫式部は、律令制の完成と共に歴史書(正史)や昔物語の様な旧型物語の中に閉じ込められた「もの語り」を復興させ、私が本当の物語を書いてやるという意気込みで「源氏物語」創作に力を注いだ。その世界は肉体ばかりか、心の乱交パーティーさながらの、勧善懲悪を無視したアナーキーな物語でもあり、貴族社会の思いのたけを代弁してくれるベストセラーとなった。道徳に近いものと言えば、その場限りの「人笑われならず(人に笑われないような振る舞い)」という美学だけだった。重い道徳感による葛藤は見られない。
道長もたびたび紫式部のもとを訪れ、次巻を催促したり、小説の構成について口を挟んだ。
男心を引き留めるのは、顔の美しさや、あけっぴろげな性格ではないこと(当時は顔が美しいのは性格がいいから、前世の行いが良かったからと、顔にすべてが出るという考えだったから逆のことを言い且つ説得力があるこの物語に新鮮な驚きを持ったろう)、男色こそ「女にてみゆ」と、もし女だったら契りたいほどだ程度のもので、本格的なものは男性貴族の日記文学に任せたものの、それ以外は何でもありの、罪悪感の無い、男女の駆け引き溢れるフリーセックスや父帝の王妃が懐妊するまで続ける姦通(暴力に依らない父殺し)などタブー破りのニヒリズムに溢れている。
中でも、物語の中で、「意中の人」つまり本命の、「身代わり」と契りを交わすというパターンの多さは、裏を返せば、理想の人間などというものは存在しないのだ、だからこそ理想の人間は成るもの、思うものだという爽快なニヒリズムを思わせます。
TVドラマ・「逃げ・恥じ」では、ミクリの母親が、「(運命の人なんて出会うものじゃない)運命の人に、自分でするのよ」と言いました。(比較の目で)外から幸せそうに見えるひとに、幸せなんて無いよというメッセージですね(以上はおおよそ大塚ひかりさんから学んだ源氏の世界です。大塚さんは歴史的・集合的な目で源氏や平家を捉える貴重な方です)。
この思想は「物語」の本質を、ひいては人間の「欲望」の本質を垣間見させてくれます。
とても大事なところなので、よく考えてみてほしいのです。
人は皆、自分の意中の人・理想の人と一緒になりたがります。他の人・性格の悪い人・顔がすぐれない人・色の黒い人など様々ですが好みでない人とは契りたくはありません。これはどういうことでしょう。犬や猫などの動物が、そのような選り好みをするでしょうか。ただ盛がついたタイミングで用を澄ますだけで、あの人が嫌だとかではなく、より強いかどうかだけで選びます。イケメンかどうかなんて関係ありません。これは彼らが本能で動いているからです。人間も好みかどうかなんて関係なく盛に任せているだけなら、強姦されようが屈辱感など感じない筈です。ところが私たちはそんなことはとんでもない。許されない犯罪です。なぜ選り好みをするのでしょう。それは私たちが相手を、本能でなく、物語で見ているからなのです。自分の物語に合わない人と交わりたくないのです。つまりこれが犬や猫の本能でない、「欲望」の正体なのです(犬や猫には本能は合っても欲望は無いでしょう)。これを許しているのが現代社会で、個人の自由というものです。
これを突き詰めるとどうなっていくでしょうか。みんなが自分の物語に合う人を選びたいとすると、考えが浅い時はイケメンや美人を求めて多くの人間が殺到し、そうでない大部分は溢れて大きな偏りが出るでしょうし、更に経験を積んでくると、ふさわしい相手というものは「物」ではないのだから、見かけだけではすぐに飽きてしまう、又それを失うことに神経を使い疲弊することが判り(そこには長く続く物語がありませんから)、「自分の成長に合わせて変化していくこころ安らぐ人間性」を求めるようになるでしょう。つまり観賞用ではなく、自分の人生のパートナーとして=物語の共演者として、相手を見るようになるでしょう。両方揃った方がいい。しかしそんな理想の相手に巡り合う確率は何パーセントでしょうか。ゼロに近いですよね。だから結婚しない人は増え、出生率は下がるのは当然です。勘のいい人は、早く気づきます。自分が理想の物語(欲望)に囚われていることに。そんなものにぎゅうぎゅうにとらわれていては、自分の人生はすぐに終わってしまうと。だからと言って強姦でも構わないというのは行き過ぎですが、ある程度のところで、自分の物語(欲望の質)と妥協します。顔なんて一時のものに過ぎないと悟るわけです(勿論ラッキーにも理想の人と相思相愛の結びつきに出逢える人もあることはあるでしょうが、それとて、美男美女のカップルが、外から人形がかわいく見えるように何不自由なくお決まりの筋書きに動かされているように、お決まりの幸福とやらを演じているのを見るのは、かっこよさとかいう薄っぺらなものを後生大事に守り続けなきゃならない。額縁の中のおとぎ話の何と窮屈な人生であることか)。こうして本当の自分の物語にとって、顔や性格はマストではないことが、年を重ねるうちに判ってくるのです。源氏物語は、(宮中という狭いながらも)社会全体が先にその結論を出してルール化してしまった、ある意味進んだ大人社会だったわけです。
だから強姦は、源氏物語では日常茶飯事でした。更には好みを品定めする顔や性格は皆隠されて夜陰に紛れての行為がルールでした。相手が実際がどのような顔をしていようが関係ない。男も女も「引目鉤鼻(ひきめかぎばな)」で充分だったのです。

問題はどのような出会いの条件かではなく、どんな条件であっても、その与えられた条件を如何に演じるか(切実さ・情愛)にあったのです。いつまでも結婚できないとか、いい人に巡り合えないとか悩んでいる人は、自分の欲望を、つまり物語をすこし変えてやれば、広い世界が見えてくるのに、もったいないと思いますよ。何も平安時代に戻れと言っている訳ではないのですから。物(顔やカッコよさ)はやっぱり見世物に過ぎません。そこにこだわるより、コト(出来事)にこだわらなきゃ。自分の生きるドラマの質に。
又さらには、もっと視界を広げてみると、紫式部が意識していたとは思いませんが、源氏の世界は、「平和とはこういうものか」という一種の到達点と、頂点が故の「転げ落ちる不安」を見せているのではという自問に行きつきます。それは平安という一つの文化の爛熟点に達した(と言っても貴族社会だけですが)からこそたどり着いた平和(100)と、それを維持するために(我慢し)犠牲となった人間の、ぶちまけずにはいられなかった怨念と時代を生きる心の不安や息苦しさが行きつく先を、愛ではなく性を、心ではなく外見をテーマとせざるを得ない、物語という大河(時代の様式)に乗せて語り繋ぎ、図らずも来るべき将来を予測した一人の天才の生きざまでもあったと思います(まるで千年後の現代の市民(当時の貴族程度の生活水準には達しているし、メールやネットで意思疎通をするのは、貴族の手紙や使用人を介しての会話・間接的な伝達方式と似た感触を持つ)の生きざまを予知していたかのように。更には次に来る中世の分裂志向が、現代のトランプ現象に代表される時代の方向が、ポピュリズムで小児的で、遠心力の働く中世の始まりに酷似しているのは、不気味な予感さえ抱かせます)。
このような、権威と権力を分けて、天皇と上皇と女院との間で、均衡をとり生き延びる、「混沌(曖昧)」とした藤原流物語(神話)というものを理解できず、中国風の白黒はっきりし、大義名分論や法家的論理を振り回し、再び社会を混乱に引き戻す(保元の乱)のが、同じ藤原家の信西(しんぜい)入道なのは何という時代の皮肉でしょう。
結局、古代貴族や律令国家の終焉という社会構造の解体期に、氏や共同体的制約から解放され、未だ「家」の縛りには束縛されていない人々(貴族だけですが)が自分の言葉で語り始めるさきがけが、日記であり、手紙であり、物語だったのでしょう。
※皆さん、ここまで読んでくださってありがとうございます。これで今年は最後です。来年も命の続く限り頑張ります。
どうか、良いお年をお迎えください。
注97) 角田文衛「平安の春」講談社学術文庫P55
注98) しをり
蕉風俳諧の根本理念で、題材が哀憐であるのをいうのでなく、人間や自然に哀憐の情をもって眺める心から流露したものが、自ずから句の姿に表れたもの。〈萎(しを)る〉の連用形というのが通説である。
注99) ほそみ
作者の心が対象にかすかに深く入り込んでとらえる美、およびそれが繊細微妙に表現される句境。
注100) 平和とタブー
平和とは、苦しくてつまらないものです。争いを避けて、我慢の連続だ。陰湿ないじめや、噂だけで人の人生を葬ることもできる息苦しい世界だ。ターゲットのされようものなら、ありもしない噂で非難の的にされ、悲惨な人生を送ることにもなりかねない。いつ何時身に覚えのない咎で、罪人になっているかもしれない恐怖を抱えることになる。
そんな中で、弱い人間はことに、周囲や見た目を気にし、「笑われないように振る舞う」のが、自分を貫くよりも、重要な心掛けになる。悲しくても笑みを浮かべ、嬉しくても自制し、言いたいことも言えず(言えば人も自分も傷つくし、自分も傷つきたくない)、そのストレスは知らず知らずに内面に膨れ上がり、自身の肉体や精神を蝕むという形で昇華される。内に向かっては、拒食症や自死、外に向かっては人を騙して陥れたり、更には怨霊となって姿・形を鬼の面相にしたり、それを信じる他人(噂や動揺)の手を借りては、瞬く間に標的に辿り着く。或いは本人の直接ではない手によって(使用人を介した手紙・伝言など)行う通信・伝達によって、時代の常識や世間体に検閲された言葉によるの為の気持ちの「曖昧さ」、「個の埋没」にストレスは溜まる。逆に発信元が誰ともわからないが為に発せられる「噂」は反動で内容は過激で大きく人のこころを傷つけ、人生を左右するまでの力を持つ。傷ついた心を人形で癒すのはペットブームの先駆けかもしれません。
まるで現代のネット社会のようですが、これが源氏物語の描く貴族たちの生活なのです。千年も前に、20世紀の人間たちが悩み恐れていた人間関係が描かれていたという奇跡が、ヨーロッパ人を驚かせたのです。更にはフリーセックスの域を超えて、姦通はざらで、男色も珍しくない(流石に紫式部は女だったのでこの辺りはあまり踏み込みませんが)世界は、「爽快なニヒリズム」を見せて、欧米人の気持ちをわしづかみにしました。今はもう、このような苦しみに我慢ができず、人々が言いたいことを吐き出して我慢しない、収拾のつかない新しい中世に向かって着実に進み始めていますね(怒りも憎しみも現世の内に済ましてしまうから後味もさっぱりして精神衛生上はいい)。中世のきっかけは異民族の侵略でしたが、現在の中世化(遠心力の働く時代)のきっかけは難民や核でしょう。もうお体裁や人助けなんてまっぴらだ、みんな我慢するのはやめて自己主張をするのだ、自分のことは自分でやれというわけです。トランプ現象ですね。「宗教戦争」ならぬ「信念戦争」はもうあちこちで起きていますが、これが今まで平和だった世界各地でも起きてくるでしょう。大江健三郎さんは、ノーベル文学賞の授賞式で、日本の「曖昧さ」が戦争を引き起こしたと言って、川端康成の「美しい日本の私」を批判したようですが、この批判は当たっているでしょうか。これは大江さんだけの問題ではないですが、又森有正にも言えることですが、この世代の人たちには日本の伝統が、西欧の論理のもとに否定されるだけで、正しく理解されていなかったこともあのようなことが言える原因でもあるのです。更には、この否定された日本の伝統の代わりに拠り所にした「ヨーロッパ近代」が、本物の伝統に基づくものではなく、明治・大正が「誤解したヨーロッパ近代」だったのです。いわばゴッホではなく「額縁に入ったゴッホ」だったのです。ヨーロパの貪欲且つ排除主義の上澄みのところだけを見た合理性や美や宗教性が、彼らの新しい様式になったのです。西洋人からすれば大江は、自分たちの論理で話せるかわいいやつと思うでしょう。大江も森も真面目で良心的な人間です。そして川端は少女・屍体なぶりの変態爺さんです。しかしそれでも大江も森も勘違いしていると思います。西洋流の「自我」主義と平和は矛盾しているよと言いたいのです。平和は、女々しくとも、都合のいいように自己正当化をしていない川端の方にあると思います。
先の戦争では、欧米コンプレックスを持つ自閉的な内面を自己正当化しようとして、現実感覚を喪失してしまった日本国民の深層心理が、軍部の自己正当化の精神的な後押しをしたのではないでしょうか。そうなら、彼は何故軍部ばかり批判して、後押しした日本国民を批判しないのでしょうか。
或いは外圧に弱い「曖昧性」を批判するのではなく、それを自我中心の合理しか介しない外国に解らせる道に挑戦しないのでしょうか。元を正せば侵略と排除主義の欧米が、平和に暮らしていた人の家に、正義の名のもとに(文明とやらを教えてやるという)押しかけてきたことが始まりなんですから。その屈辱に対し、仮面を被って(欧米化)その場しのぎで対処したものの、我慢しきれなくなってコンプレックスが爆発して、同じ被害者の本来味方の筈の近隣アジアのまで敵に回して、倒錯した攻撃性を持つに至ったことは責められても当然で、決して正当化はできない犯罪であることは間違いないでしょう。しかしそれは、押しかけて来た西欧(アメリカ)も、攻撃性を剝きだしにした日本も、共に正義の名のもとにやったことで、これが共に悪なんだということです。何も曖昧性を現実と受け留め、そのまま平和に生きてきた民族を、(対外的な)抵抗力が無いからと言って、曖昧だからといって責めるような問題ではないでしょう。
欧米の合理・自我中心の思考が行き詰まり、その先に来るものはやはり「曖昧性(矛盾)」の受容だと思うからです。
源氏物語が示唆するものが、理想的な社会だなどというつもりはありません。
というのも、人々は世間の目を気にし、言いたいこともしたいことも我慢し、感情を押し殺し、コミュニケーション能力は低下し、陰湿ないじめや噂や怨霊にに振り回され人生を台無しにされることもあり、物の怪を恐れ迷信に振り回され、多くの時間を祈りや儀式に割き、個人の心からの欲望は発露されず、常に世間という超自我に抑圧され、そこに辛うじて「もののあわれ」が読み取られるような息苦しい世界だからです。
それでも物の怪など恐れもせずバッタバッタと切り倒してしまう武士の様な暴力勢力の台頭はまだ見られず、まして外国に正義を押しつけるようなことも無く、平和の一つの形を見せたわけです。平家物語が、男性的なるものを著したとすれば、源氏は女性的なるものを示しているんです。
女性的なるものは、自然そのもので、宇宙全体と繋がっていますから、基本的に怖いものは無い。子どもも産めるし、本来は肉体的暴力とは無縁です。だからタブーなんていらないんです。近親相姦なんて、社会の様な幻想を持つ必要が無いから、怖くもなんともない。所有欲も本来はなく、一夫多妻だって何ともない。自我や個人のアイデンティティーなんていらないからです(現代の女性は、近代的な男女平等など、男たちの作り出した所有制度や平等という思想に手なずけられていますから、俄かには信じられないと思いますが)。基本的に自閉の世界なんです。
それを女性とは反対の男が、不安や寂しさから、肉体を、権利を独り占めしたいから、所有権などを持ちたがり、他を縛り付けようとするから争い(奪い合い)が起きるのです。男は子どもも産めないし、女性に利用されてやっと少しは親の気分を頂くくらいが関の山の、自然から疎外された存在なんです。だから声を荒立て(源氏の時代は未だ肉体派ではなく、観念的を弄ぶ風潮の為、遠回しに周囲を気にしながらですが)、自分の存在を主張したがる。その自己主張を様々な形に変化させて(制度や時代の雰囲気・ムードとして)、社会をかき回す。立派な理想や政治的理念や、スポーツの純粋さ、正義の戦争、自衛の為の戦争などなどいくらでも作り上げることができる。もし、平和が善だと言い張るなら、やれオリンピックだの、球児たちの純粋な夢を支援する高校野球だの、未開の可愛そうな民族を文明化させてあげる正義感に満ちた植民地政策や大東亜戦争だの、アメリカの仕掛けたイラク戦争だの、それに抵抗することからかじまったイスラム国のテロだの、ベトナム戦争だの、それに抵抗したべトコンゲリラだの、ナチのアーリア主義を振りかざす虐殺と侵略だの、それに抵抗するレジスタンスだの、
「どんな理想にせよ、ある理想のために真面目に真剣に戦うということは、立派なことだと思われているけれど、そういうことはそれ自体が悪なんだ(*)」ということを知らなければならないということです。これは、何度強調しても足りないくらい重要な言葉だと思います。
とても賛同できないという人は多いと思います。ナチとレジスタンスが共に悪だなんて誰が肯定するものかと思われるでしょう。でもこれを、どちらが悪でどちらが善というふうに分けると、「正義の奪い合い」が始まり、古代の神々から現代までずーーと続く、サディスティックな憎しみの連鎖から抜け出られないわけです。源氏物語は、このような一代しか考えられない男たちの正義に基づく争いに目もくれず、「自我と敵対するものを攻撃する」という呪縛から自由で、いちゃいちゃ生理的に生きているわけです。自我なんかいらない世界なんです。これが人間のできる平和の一つの姿なんです。ねちねちと女々しいと思われるでしょうし、いじめも、えこひいきも、チャッカリもこずるさもありますが、それが嫌なら、心にもない平和を叫ばず、修羅の道を行けばいいのです。但し、正義の名のもとによそを巻き込まないでいただきたいものですが、もうそんな神業の様なことも難しい。込み入ったグローバルとやらの魔力をがっちりと掛けられていて、困ったものです。
平安時代同様、外圧から比較的自由となり、平和のもう一つの形を作り出せた江戸時代と、その平和をぶち破る外圧に揺れた幕末に話を進めるのは行き過ぎですが、やはりここでも攘夷を主張する朝廷と、密貿易で私腹を肥やしていた(実は自分たち主導の条件付き開国派だった)薩長の、心にもない攘夷賛同による朝廷利用作戦に対する、幕府主導の屈辱開国やむ無し派との、「正義奪い合い」の権力闘争で江戸(東京)が火の海になるのを防いだ、即ち正義しか、一代限りしか考えられない男たちの後始末をして、次世代へのバトンタッチをして、権力の座を退かせたのも、天璋院篤姫や皇女和宮などの女たちの決断だったのです。東京が残ったことが良かったのか悪かったのかは言えませんが、少なくとも明治の近代化とやらを遅らせる、或いはもっとひどい植民地化を齎す要因を潰したことだけは事実でしょう。
トルストイの暗示するように、戦争と平和は同じものなんです。身体で戦争しているか、こころで戦争しているかの違いだけなんです。
(*) 伊丹十三、岸田秀「哺育器の中の大人」ちくま文庫2011年11月p39
さて、話を戻しますが、何故平安の貴族たちは、かように平気で強姦や姦通や男色など、タブーとされていることを罪悪感もなく、寧ろ日常時のようにあからさまにするのでしょうか。皆さんは、彼らが単に文化の爛熟の末に、狂っていたというだけで納得できますか?
自然を(本能を)飛び越えた人間にとって、家族が原初のアイデンティティー(自分であることの一貫性)を獲得する場であり、このアイデンティティーが自我であり、これが壊れると人格は成立しない。一旦出来上がった家族を他人とするような行為(例えば近親相姦)は自分自身を崩壊させることで恐ろしくてできない。そうなったら人格(自我)が壊れてしまう恐れがある。これがタブーです(自我のアイデンティティーが親子間の縦軸のものとすれば、社会人としての人格は、国家との間の横軸のアイデンティティーです。これの崩壊を特に恐れるのは愛国主義者です)。これらは、精神分析家岸田秀さんの著書から学び、勝手に再構成した私の考えです。
当時の貴族社会は、女性を軸に構成された社会で、家も財産も娘に与えられ、男は成人として生きていくには、どこかの貴族の娘の家に転がり込むしかなかったのです。子どもが生まれても、母親側でしかも、乳母(めのと)という他人に育てられ、実の父母との近親関係は育ちにくい。子どもは自分が初めて作り上げる自我の物語に、乳母やその子供を近親として入れるのです。実の親は他人なのです。だから、親子の関係を破ってもタブー破りにならないのです。
特に父親は実際に産んでもらってないから他人感がさらに強い。それで光源氏は平気で父帝の王妃である藤壺の宮が懐妊するまで密会し続ける。武力に訴えなかっただけで、姦通による政権転覆の試みです。それを罪悪感もなく実行し続ける。後から源氏は、自身の妻・女三宮が、頭の中将の息子に姦通されることでしっぺ返しを受ける。
しかも当時の性交渉は闇の中で行われるもので、顔や肉体を見られることを極端に嫌いました。それは女性ばかりでなく男性も同様でした。身分が上の人間は人から顔をじかに見られるということがほとんど無く、自分は相手を一方的に見るだけの接し方が日常になります。意思疎通さえ、部下を通しての伝言や手紙を通じてになり、何時しか、自分が生々しい自分でなく、観念的になります。女性は顔を見られたということが、犯されたことと同じに感じます。生々しい自分(現実)を見られたのですから。むしろ兄の家にいた時、男と間違えられて殺されそうになった時、迷わず清少納言は股間を丸出しにして女としての証明をすることで暗殺を免れたといいます。股間も生々しいとは思いますが、顔の知らない人間の股間は、唯の「もの」に過ぎなかったのかもしれません。いきおい、恋と言っても「高貴な人の娘だからさぞかし美しいだろう」のうわさや想像で物語的行為に及ぶわけです。自分も相手も想像ですから、何でもありで、お互いが見られることのないガードのかかった中での観察だから、タブー破りも、現実に囚われない想像逞しい文学も可能だったのでしょう。そして行為の後には、後朝(きぬぎぬ)の歌を交わすことが必須なのです。物語の仕上げです。動物的発散だけではないことの証拠です。
実はお前の顔は、こんな顔なんだと突きつけられる、「はしたない」リアリズムの世界は、後の武者の世です。社会全体が共同で見ていた夢を引っ剥がして、現実に引きずり下ろしたのです。
では、男色はどうでしょう。同じアイデンティティの問題でも、インセスト・タブーが「自我」の樹立に関わる問題であるのに対し、男色は自己の「(身体的ではなく)精神的な性別の選択」に対する問題です。あまりに長い脱線でしたので、これは後程、中世の〈政治手法としての男色〉のところで話します。