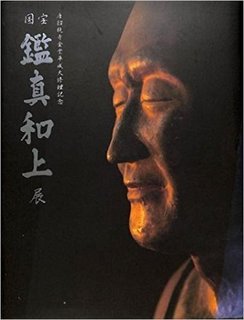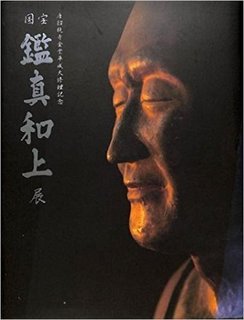6・長く深く沈潜する西ヨーロッパ中世
〈ヨーロッパの風土と民族〉
ヨーロッパ(28)は大きく地中海地方、西ヨーロッパ、東ヨーロッパに区分されています。地中海地方は、地形的によく似た我が国の瀬戸内海とよく似て夏季に雨が少なく温暖な気候です。それに加えて、石灰岩質の痩せた土地でオリーブなどの果樹栽培に適した半面、小麦不足の為交易や植民が欠かせず地中海・黒海沿岸に都市が発達した。一方でアルプス以北の西ヨーロッパは、陽光は少ないが、西岸海洋性気候の、南からの暖流である北大西洋海流や偏西風のおかげで、冬は緯度に比して温暖で降水量も平均しており広汎な農作物が栽培や酪農も可能な環境だった。唯当時は、内陸は広葉樹・針葉樹の森林におおわれて、寒冷で開発は遅れていた。ただ地味も肥えていた為、後の大開墾や農業技術の進歩(三圃式農法・後述)などで、有畜農業(29)が行われた。交通は道路が舗装されておらず、雨となれば通れたものではなく、勢い河川が動脈として利用され、そこに沿って都市が発達した。東ヨーロッパは、雨量は少なく寒暖の差の大きい大陸性気候で、草原地帯が広がり、黒海北岸は肥沃な黒土で地中海の穀倉として知られ、東方からの遊牧民の侵入に脅かされた。
一方、この広大なヨーロッパ(イベリア半島からアルプス以北)に古くから住み着いたのはケルト人(30)でした。彼らはイベリア半島やアルプス以北を活動の拠点としていましたが、北方のゲルマン系民族中、西ゲルマンと東ゲルマンがライン・ドナウ両川以北に拡がり、4~6世紀にゲルマン民族移動により一部は自然の障壁アルモリカン山脈に守られたブルターニュ地方へ、一部は北方に追いやられ、アイルランドなどに駆逐されてしまいました(実はそのもっと前には、紀元前6000年~1800年には巨石文化を持つ先住民族が住んでいました。巨大な石を太陽である神に捧げたと言われます。どうやって動かしたのかは不明のようですが、もしこれが花崗岩なら節理に沿って雨で割れた可能性もあります)。
ケルト文化は縄文の日本人と似て、文字を持たなかった民族なので、伝承や音楽や芸術的なものからしか推し量ることができないのですが、アイルランドなど一部の地域では(科学的な見地では当時の資料たりうる伝統は残りうるはずもないのですが)、僅かな言い伝えや遺跡やアイルランドの昔話などから、想像力を借りてのケルト世界の一端を垣間見ることは可能です。なぜケルト文化にこだわるのかというと、そこには、辺境ヨーロパの根っこの部分や、大陸からの辺境の地・日本との共通の風土が匂うからなのです。特に森の中の木の住居は我々に親しい。縄文土器に見られる観念の渦巻く模様は、ケルトの渦巻き模様思わせますし、昔話における変身譚において、グリム童話などのように呪文や魔法などの操作を挟まないで、ごく当たり前に変身は行われます。これは人間と動植物の境界が無いというか、隔たりの無い同等の関係にあるので、会話したり変身したり、特別な操作無く可能なんです。おそらくこれは日本とケルトだけということでは無く、原始の人類共通の能力であり、会話自体がもともとそういうものであり、認識や視覚自体も、現代の写真というものがクリアー過ぎて、覆ってしまっている向こう側まで見えたりするものだったのだろうと思います。つまり現代人が自分と切り離そうとしている、非合理な無意識やカオスとの連絡が取れているからこそ見える・感じられる豊かな世界を持っていたろうと思われるからなのです。「古代から渦は、偉大なる母の子宮の象徴と考えられてきた。それは、生まれてくるという意味と、そこに引き込まれて死ぬという二つの意味を併せ持っている。・・まさに輪廻転生を象徴するものなのだ。・・つまり母性の象徴なのである(31)」。これは後にヨーロッパを席巻するキリスト教の父性と対立するものなのです。遂には「赦す」存在、神へのとりなしをしてくれるマリアの必要性を認めたカトリックよりも更に父性の強い、プロテスタントと対立するものです。ヨーロッパの優れた文学でケルト文化に影響を受けた人たちはアイルランドのイエーイツ、ジョイス、フランスのマルセル・プルーストなど20世紀の代表的な作家がいますし、ワグナーの「トリスタンとイズー」伝説もアイルランドに源泉があります。墓の中から蘇る愛の「嵐が丘」の結末もアイルランド起源です。もっと言えば、ケルトの場所の一つであるアイルランドは、ノルマンの侵略から始まり、12世紀から続いたイギリスによる修道院文化の破壊、弾圧と圧政から、新大陸に避難したアメリカのルーツでもあるのです。今日でもアイルランドへの観光客の多くはアメリカ人です。自分のルーツを探しているのです。ケネディーもレーガンも同じルーツでした。
いずれにしても、ケルトは日本の縄文のように、ローマや古代ゲルマン族らによって(縄文人は弥生人たちによって)、跡形もなく破壊されてしまったのです。フランスのブルターニュやアイルランドに僅かに残るのみです。(ヨーロッパの)石の文化は残りますが、森(木)の文化は断片しか残りません。歴史家の木村尚三郎さんは、パリに行くといつも訪ねるところがあるといいます。それはサン・ジェルマン・アン・レイにあるフランス古代博物館の、銀でできたケルトの木々の葉のコレクションです。
病気や怪我の治癒に感謝して、ケルトの神々に捧げた奉納板であり、その空中に舞うがごとき美しい光からは森の歌が、大自然への畏怖と森の木々に神秘を見た彼らの豊かな情感がこみ上げてくる感動を覚えるといいます。曰くヨーロッパ版縄文の歌だそうです。
もともとローマ帝国の辺境だった西ヨーロッパは地中海と比べると寒冷で、森に覆われた未開の地だった。麦の収穫も少なかった。ローマ人がケルト人を森の人と呼んだのはその為だった。そこでは森が神々の住まう神域として敬われ、その神々は聖なる木・カシ(32 )の木に宿るとされたのです。カシは寿命は2000年に及ぶと言われ、新しい葉が生えるまで古い葉は残り、日本でも一族の繁栄のシンボルとして子どもの日にカシワ餅が食されます。銀の葉もおそらくカシワでしょう。実物を見てみたいものですね。
長くなりましたが、ゲルマン人は征服民とはいえ、ヨーロッパという同じ風土で育ったという点でケルトの民と底では繋がっています(我々も大陸からの稲作や渡来人の弥生に染まっているとはいえ、地中奥深くには縄文の熱い血潮が渦巻いているのと同じです。土俗の盆踊りはその情念を「をどり」によって踏みしめ・吸収する行事です)。後に一神教であるキリスト教によって否定され変化を強要され、地中深く埋められたこの多神教の世界は、ゲルマンの神々と共に、ことあるごとに対抗の炎を燃やし各地で噴火するのです。(クリスマスツリーやハロウゥンの)ケルトはヨーロッパの底辺なのです。縄文が日本の底辺であるように。
こうしてヨーロッパは、中世前期に、地中海にラテン系民族、西ヨーロッパにはゲルマン系民族(33)、東ヨーロッパにはスラブ系民族(34)という分布が出来上がりました。唯、ハンガリーとフィンランドだけはウラル・アルタイ語系(アヴァール・マジャール・モンゴル・トルコ人)の言語を持ちます。彼らはアジア方面から移住してきた遊牧民の子孫だったのです。
〈ゲルマン民族大移動・375~476年〉
ゲルマン人は、ローマ人からすれば随分と素朴で荒々しい牧畜と狩猟と小規模の農業とで暮らしをたてていた部族集団だった。それでも、貴族・平民・奴隷の階級と民会という意志決定機関を持っていた。ゲルマン人の信仰していた神々の名は自然現象から来ていて、曜日の呼称として残っている。主神オーディンはWednesday、その妻フリッグはFridayなど。
ゲルマン民族大移動とは、ローマから見ればそうなりますが、ゲルマン民族から見れば、農業進歩と人口増による土地不足と、匈奴の末裔・フン族からの逃走であり、フン族から見れば中国(鮮卑系の北魏)の圧力からの逃走でもあったわけです。
そして西ヨーロッパ世界の形成は、ローマから見れば、地中海世界に進出したイスラム勢力からの逃亡とゲルマン勢力であるフランク王国との提携でもあったのです。当時のイスラム勢力とフランク王国の力の差は、首都バクダードの人口150万人に対し、フランクの首都アーヘンは、僅かに3000人という差から見ても歴然としたものでした。ど田舎の農村から出発したヨーロッパは、イスラムの大征服圧力に、けなげにも連帯し、北方の「ゲルマン人のローマ帝国」を辛うじて確保したのです。両方から挟まれた西ローマ帝国は、攻撃的なイスラムよりも、素朴で一神教を持たない、比較的平和的な移住をしてきたゲルマン人との提携の方を選んだのです。ローマ人の都落ちですね(395年ローマ帝国は東西に分裂しました。東ローマ帝国(ビザンチン帝国)は、古い伝統を受け継ぎ、皇帝と教皇一体主義の体制(帝権と教権の分離をしない)をとり、昔ながらの制度国家を維持しました。一方でゲルマン人と組んだ西ローマ帝国は、ゲルマンの諸王国が群雄割拠し、強大さを競う状態でした。
西部に建設された諸国の中でゲルマン人の人口比率は僅かなもの(3%程度)でした。にもかかわらず軍事的主導権を握った為、やがてゲルマン傭兵隊長オドアケルが、476年西ローマ帝国を滅ぼし、東ローマ帝国(ビザンチン帝国)の臣下となった。以降ゲルマン諸民族の王は東ローマ皇帝に従属し権威を利用した。ここに西ローマ帝国という国は滅亡したのです(ローマ教会は、東ローマ帝国とは別に生き残ります)。時に、倭王「讃」(仁徳天皇?)が東晋に使者を出し、中国では北魏と東晋がしのぎを削り、ビザンツ帝国と朝が対立する時代でした。
そうした中で西ヨーロッパ最大の勢力になったのがフランク王国(メロヴィング朝)でした。5世紀末のゲルマン部族は、カトリックではなく異端とされたアリウス派(35)を信仰していたが、フランク王国のクローヴィスは諸国に先駆けて496年に臣下と共に正統のアタナシウス派に改宗し、旧ローマ貴族やローマ教会の支持を取り付け勢力を伸ばした。その後次第に衰え宮宰(宮廷の家政を取り仕切る役人)一族に実権は移ったが、7~8世紀にかけての、シリア・エジプト・ササン朝までもを倒したアラブ人民族大移動である「イスラム大征服運動(後述)」により、イベリア半島(現スペイン)まで征服され西ゴート王国も滅ぶに及び、危機感は一気に高まった。フランク王国宮宰でカロリング家のカール・マルテルは救援の要請に、国土の3分の1を没収し騎士に与えることで強力な重装騎兵を組織し、既にポワチエが落とされた後、キリスト教の聖地のひとつであるトゥールでイスラム軍と激突し、勝利した。マルタン修道院も守られた(トゥール・ポワティエ間の戦い)。しかし、イベリア半島と地中海一帯は長らくイスラムの支配に置かれたことを考えると大勝利などと言えるものではなかった。それでもこの勝利が無ければ、今のヨーロッパは無く、イスラム世界になっていたことは確実でしょう。
これをきっかけにカロリング家は台頭し、カール・マルテルの子ピピンはカロリング朝を起こした。ピピンは教皇領を寄進し、この機にビザンツ皇帝と対立していたローマ教皇は、カロリング朝と接近し権威確立に利用した。ピピンの子・カール大帝は800年ローマ教皇から、ローマ皇帝の帝冠を授けられた。こうしてローマ帝国は、ローマ人ではなく、「ゲルマン人のローマ帝国」として復活しました。
〈カール大帝の戴冠と西欧世界の誕生・486~870年〉
カール大帝がキリスト教に戴冠(たいかん)したことが、なぜヨーロッパ世界の誕生につながるのでしょうか。その背景には、遡ること300年、メロビング朝のクローヴィス(クロードヴィッヒ)がカトリック(正統のアタナシウス派)に改宗し、塗油(油または脂を人または物に塗ってそれらのものが神聖なものとの新しい関係を得たことを象徴する儀式)の儀式によって、王がゲルマンの神々にではなく、キリスト教の神に贈り物をし、民衆の平和を祈らなければならなくなったことに象徴されます。つまり、従前の、家臣に戦利品を気前よく配ったり、生活の隅々まで浸透していた贈与慣行(36)
は保ちつつ、王がもっていた民衆の病を治し、収穫を増加させるという力の行使を教会に移し、もって民衆に対しては伝道を進めることに絞る代わりに、死者への贈与(生前・死後を問わず自己の幸運を保証してもらう為の取引)として財宝を地下に埋める慣習をやめさせ、教会に寄進させることで、つまり神への贈与に換えることで、天国で報われることを聖職者の祈りで保証する形に転換させた。
こうすることで、教会は寄進された財産で大聖堂を建て、権威を高め、王は名誉という社会的権威も、聖堂の周囲に立つ市の開催による収入も確保できた。貨幣は埋められて腐ることなく市井に循環し始めたのです。贈与経済体制から、売買による(利潤を目的とする)貨幣経済への移行期にいたのです。勿論、カトリックを信仰していた旧ローマ人との障害も少なくなったことは言うまでもありません。こうしてヨーロッパは教権と帝権のバランス(聖俗2つの中心を持つ楕円のような)のもとに一体となる独特の共同体を形成していくのです。これは後のヨーロッパ文化の特色であるバロック(ヴィヨンやヴェルニーニなどに見られる二律背反な「敬虔」と「猥雑」の2つの中心を持つ、楕円構造の持つダイナミックな)文化をも生み出すのです。それはやがて、現世での善行や教会への寄進は、天国での救いを約束するものではないと、教会の欺瞞を暴いたルターの登場まで続くのです。
フランク族には、子が財産を分割して相続するという慣習があり、843年のヴェルダン条約などを経て、カペー朝(フランス)、イタリア王国、神聖ローマ帝国(ドイツ)の3国に分裂しました。これが「帝権はドイツに、教権はイタリアに、そして学芸はフランス(パリ)にという3つの中心を持つユニークな文化圏となった(37)」のです。彼らはナショナリズム一辺倒ではなく、この時代から王侯貴族同士の通婚を認めたり、市民や農民も地域社会の特色を認め合い、国の如何に関わらず同一身分の同格性など相認め合う意識も持っていたようです。
少なくともヨーロッパ内に限って言えば、最初から異なった文化を認め合った上で統合していこうという国際的な自覚を持った集団でした(勿論ヨーロッパ連合の、外に対しては傲慢で、鼻持ちならない優越意識が、多くの犠牲を強いたことも事実ですが)。
〈カロリングルネッサンス〉
アーヘン(森の中の小さな町に過ぎない)を中心としたルネッサンスと言っても、同時期のバクダードや長安(両方とも100万都市)と比べたら、本当に月とスッポンぐらいみじめな差があったことは述べました。それでも、「ゲルマン人のローマ帝国」を復活させたカール大帝は、国造りの為のインフラ整備に加え、自らは文字の読み書きはできなかったものの文教政策に力を入れ、各地の修道院や教会に付属学校を設置させ、各地からアルクインなどの高名な学者を招き、当時の俗化したラテン語に対し、古典を模範にした正しいラテン語の復興や文化の研究に当たらせた。その結果修道院では、それまでの文字が「アンシャル体」という荘重なローマ字中心だったものを、カロリング小文字(アルファベットの小文字)という独特の書体で多くの写本が作成され、古典文化の継承がしやすくなった。
カール大帝の西ローマ帝国は、単なる古代帝国の復活ではなく、古代の古典文化に加え、キリスト教、ゲルマン的要素の融合した新しい世界の誕生を象徴するものでした。アルクイン(735~804)は古典学芸とキリスト教信仰の調和につとめ、カロリングルネサンスの中心人物となりました。
〈ヴァイキングと東西ヨーロッパ9~11世紀〉
9世紀から11世紀にかけては、ノルマン人・ヴァイキング(ノルウェーの入り江=ヴィークに住むところからこう呼ばれた)と呼ばれる北ゲルマン(スウェーデン人・ノルウェー人・デンマーク人=ディーン人)は、スカンジナヴィア半島やユトランド半島で農業に従事していたが、気候は悪く農地不足で、人口増を賄うことができず、彼らは巧みな航海技術で川や海を往来し、横波に強く、左右どちらからでも岸に付けることが可能で、帆で航海し河川をオールで遡るヴァイキング船を駆使し、交易や移住や略奪を行い、その勢力を広げた。
これを、ゲルマン民族大移動の落ち着いた後の、第二次民族大移動と言います。
スウェーデン系ヴァイキングは、バルト海から南下する川を遡り、ヴォルガ川やドニエプル川を下り、カスピ海・黒海に至る交易路を開発し、イスラムやビザンツ帝国との交易をおこなった。イスラム商人との交易ではアラブ銀貨が流入し、北欧から西欧にヨーロッパの貨幣経済をもたらした。トルコ系遊牧民がヴォルガ川下流の草原地帯を占拠すると、孤立したヴァイキングはスラブ人と混血し、森林地帯の集落を集めて毛皮の集散地だったノヴゴロドに、「ノヴゴロド公国」を建国、更に交易の中継都市キエフに南下して、「キエフ公国」を誕生させた。これがロシアの始まりです。
ノルウェー系バイキングは、征服した国々の習俗・宗教には関心を払わず、村を焼き払い、墓をほりかえし、無防備な修道院の十字架などの貴金属を奪い、人々を虐殺し、残虐で荒々しい方法でアイルランドやスコットランド、フランク王国など沿岸各地を襲い、略奪の限りを尽くしました。カペー朝(フランス)は彼らに海沿いの領地を与え(西フランクとイングランドの間)、ノルマンディー公国とし、同族のヴァイキングの撃退に当たらせたが、飼い馴らし作戦はうまくいかず却って1066年ノルマンディー公は、イングランドに攻め入り、ノルマン朝を開いた(イングランドには、ゲルマン民族移動期にアングル人・サクソン人が住み着いていた。イングランドはアングル人の土地という意味)。その為14~15世紀にわたる英仏間の百年戦争が終わるまでは、イギリスの公用語はフランス語だった。英語でフランス語由来の単語は多い。
注28) ヨーロッパ
ギリシャ神話の、ゼウスが白い牡牛に変身して、恋に落ちたテュロスの王女エウローペーを誘惑した話にちなんで名づけられており(牡牛座もここから来ています)、そのラテン語形であるというのは有名ですが、セム語(アッカド語)の「エレブ」(夕暮れ=西方)が由来になっているとする説の方が信憑性が高いとされます。ヨーロッパは国の名前ではありません。各国の統合名称です。これが示すように、ある時は民族の自決を主張して分裂の力が強く、ある時は外圧(イスラムなどの強大な外圧や日本などの経済的進出の外圧)に逢って団結してこれに当たり、膨張力と求心力のダイナミックな力を持つ稀に見る自治統合体なのです。決して一つの領土国家ではなく、帝国でもないのです。EUが経済統合したからと言って、将来一つの国になろうなんて、これっぽっちも考えてなどいないのです。
世界の社会体制が、古代から中世にかけて、「世間」という集団体制を普遍としたとき、ヨーロッパだけは、11・12世紀を境に、そうした「人間が集団の中に埋没して相互に依存しあう、世間体制」から離脱し、「個人を単位としながら、結合する」という社会の実現に成功したのです。これを可能としたのは、(阿部勤也さんから学びましたが)カソリック・キリスト教の父性的性格や、個人に対する「告解(告白)」の強制です。これが「自分自身を見つめること」を覚えさせ、社会から孤独な「個人」の自立をもたらしたのです。やがて自意識を生み、身体から離れた客観主義や、自然を人間に奉仕する存在と見る「自然科学」の見方を生みます(これは、キリスト教の発生のところで、アウグスチヌスと共に説明しました)。これが様々な文化や技術を生み、産業革命も起こしました。18世紀から19世紀にかけての「ヨーロッパの優位」を生み出した要因です。勿論様々な副作用も生まれました。それが鬼子であるアメリカも、怨念のイスラム過激派も、パレスチナ問題も、そして魔法のような「自由と民主主義」も生んだのです。現代はその魔法が解け、新しい中世(豊かな中世)に向けての長く苦しい模索の時代に入っています。新しい古代ではありません。新しい古代(=近代国家・帝国主義・共産主義)を目指した動きは悉く自壊しています。せいぜい遅れてやってきた今の中国位でしょうか。中央政府を脅かす勢力などどこにも見当たりませんから。未だに日本以上に贈与の経済が民間では盛んで、人権問題など非難するのは、彼らには理解できないでしょう。その素朴に世界は振り回されているのです。やがて時間は、資本主義を経験している彼らに観念の中世をもたらすでしょう。
ヨーロッパとその子であるアメリカには新しい体制をリードする可能性があります。しかし彼らは嘗て、ひどく手を汚してしまいました。これが致命的な問題です。残念ながら、今のところ、素朴が先進文明を滅ぼすという、古代的な動きが優勢です。逆戻りですが仕方ありません。優越意識が墓穴を掘ったのです。日本も、それを覆す智慧もあるのですが、やはり過去に手を汚してしまいました。警戒心は根深いものがあります。辛抱しきれずに積極的平和主義などという訳の分からないことも言い出しています。何をビビってるんでしょうか。日本の本当の力はハードではありません。本当に平和を望むなら(リスクを潰すなどという安易な排除の論理では太刀打ちできないのです)、危機を逃げてはやってきません。そう、平和は掴むのではなく、やってくるものなんです。ソフトなのです。急がば回れです。
しかし、もっともっと巨大な問題・地球環境が既に取り返しの利かない状態になってしまっているという問題がのしかかっています。にもかかわらず、目を閉じて、これを見ようともせず、目先の豊かさばかりにうつつを抜かし、未だナショナリズムにあくせくこだわるのは如何でしょうか。地球温暖化が齎す環境の変化は、もしかしたら生物全体が望んでいたことなのではないか。もう20年も前に、松井孝典さんは喝破されています。人類のことしか頭にない身勝手な人類主義で考えれば、困ったことかもしれません。しかしそんな人類団結主義すら、もう通用しない時代なのです。ミミズが何億年もかけて岩を砕き土にしているのは、誰の為なのでしょうか。人間が利用して耕すため?とんでもない思い違いですよね。
注29)有畜農業
作物の栽培と家畜の飼育を組合せた農業形態。ヨーロッパの三圃式農業より発展した。狭義では,家畜飼養が商品生産部門として未確立の段階にあるものをいう。混合農業や酪農はその代表的なもの。家畜の飼育はそれが現金収入をもたらすだけでなく,地力維持のための肥料を生産する(ブリタニカ国際大百科事典)。
注30)ケルト人
インド・ヨーロッパ語族のうち西方系の民族。ギリシャ語でケルトイ、ラテン語でケルタエ、ガリーとも。原住民は南ドイツ地方。紀元前8世紀頃、鉄製武器と戦車で前2世紀ごろまでにイベリア半島からブリテン諸島、小アジアまで広大な地が彼らの世界となったが、前1世紀からローマ人に、前5世紀からゲルマンに圧迫・征服された(角川世界史辞典)。ガリア人、ブリトン人、スコット人はケルト系民族。
注31)河合隼雄「ケルトを巡る旅」講談社α文庫2010年7月 P75
注32)カシとカシワとOAK
カシはカシの木で、カシワはカシの葉のことを指したが、いつの間にか別の植物のように使われることもあった。更にカシワはカシの葉ばかりか、食事の際に使う葉を総称して、カシワというようになったと、本居宣長の「古事記伝」にあるようです。
加之波(かしは)(かしは)といふは、もと一樹の名には非ず。何樹にまれ、飲食に用ひる葉をいへり。・・すべて上代には飲食の具に、多くの葉を用ひしことにて、・・・飯を炊くにも甑(こしき)(こしき)に葉を敷きもし、覆(おほ)(おほ)ひもして、炊きつるものから、炊(かし)葉(は)(かしは)の意にて加志波(かしは)とはいへるなり。
カシワは一樹の名前ではない。何の樹であれ、飲食に用いる葉をカシワといったという説です。
又明治のころ、oakを誤ってカシと訳していた頃があり、時に英和辞典にも未だその名残があります。正解は楢です。これは、昔日本では木材 としてのナラ(楢)の評価が低く、ヨーロッパでありがたがられている oak が楢であるはず がないとの思い込みから誤ってカシ(樫)と訳されたのが原因のようです。
冬になりカシの葉が落ちると、丸くボールのように固まった常緑の大きな寄生植物・「宿り木(ギイ)」が(鳥に実を啄ばんでもらうために)カシの枯れ木につく。その光景は灰色の空に浮かび上がった濃緑色のオブジェのように妖気漂う雰囲気を醸し出す。フランス人はこのギイを見ると、幼いころ祖父母から聞かされたケルトの伝承を思い出す。霊魂の不滅や輪廻転生を信じた太古のケルト人たちにとり、このギイは、枯れて死んだ木の命がそこに移り住んだ神の住まいであり、天からの贈り物と考えたという。フランス語には今も「木に触れる(トゥーシェ・ドゥ・ボワ)」という表現があり、お守りの意味だそうです(*)が、木肌に触れることで、そこに「気」を感じ取っているのでしょうか。
(*)木村尚三郎「成熟の時代」日本経済新聞社P202
注33)ゲルマン民族
インド・ヨーロッパ語族で、ゲルマン諸派に属する言語(英語、ドイツ語、スウェーデン語、デンマーク語、アイスランド語、オランダ語など)を話し、オーディンを主神とする神話や習俗を持つバルト海沿岸を原住地としていた人々の総称。東(東ゴート、西ゴート、ヴァンダル人、ブルグント人、ロンバルト人)、西(アングロ・サクソン人、フランク人など)、北(ディーン人、ノルマン人)に大別される。ゲルマン系民族が支配する国はドイツ、オーストリア、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、またイギリスのアングロサクソン人、ベルギーのフランデン人などのゲルマン系の血を引いているが混血で、特に民族の意識は弱いようです。外見的特徴も、白色人種で、髪の色は金髪が一般的といわれていますが、ゲルマン系ドイツ人の過半数は黒髪や茶髪であり、必ずしも金髪が多いとは言えない。又長身、青い目、頬が角ばっているなどの特徴があるようです。
注34)スラブ民族
ゲルマン人と同様のインド・ヨーロッパ語族で、スラブ諸語(ロシア語・ポーランド語など)を話す人々の総称。外見では白色人種であり、髪型は薄い茶色・亜麻色~黒、ゲルマン民族と比べて顔が丸く彫が浅く、身長は高くないとされるが、そうでない人も見られ、混血が進んでいるので、特に意識は強くない。宗教面で、東方正教会に帰依した東スラブ(ロシア人、ウクライナ人、ベラルーシ人)、南スラブ(ブルガリア人、セルビア人、マケドニア人)と、ローマ・カトリックに帰依した西スラブ(ポーランド人、チェコ人、スロヴァキア人)、南スラブ(スロヴェニア人、クロアチア人)に大別される。ゲルマン民族のうち移動せずにライン川以東に留まったものをスラブ人という大きな分類の仕方もある。
注35)アリウス派
子たるキリストは父なる神に従属するとする考え方。父と子は同質とし、後に
父と子と精霊の「三位一体説」を確立したアタナシウス派と争い、コンスタンティヌス帝が招集したニカイア公会議で異端とされた(よって東ローマ帝国内でも異端だった)。イエスも神と同格で無ければ、キリスト教の特徴はなくなってしまい、イエスの言葉である聖書も、神の言葉になり、他の一神教と変わらなくなってしまいますものね。神が身を借りて、この世に「出現」したというリアリティイーがなくなってしまう。ここは譲れないでしょう。
注36)贈与慣行
贈与慣行は中世ヨーロッパに限ったことではありませんが、商業活動や貨幣経済の近代経済を理解する上でも重要なキーワードです。
古代から労働は徳ではなく、楽園から追放された罰として与えられた苦役とされ、富を蓄積するために労働することは罪人や奴隷のすることとして否定されていた。
それでも11世紀ごろから、都市も教会も多くの富を集積していた。これを正当化する理屈はどのようなものかというに、まずは当時の人たちの富に対する考え方を認識しておく必要があります。
当時の首長や戦士たちは略奪行を行い戦利品や財宝を手に入れても、これを自分の為に貯えずに、宴会を開き、戦利品を配り見栄を張り、自身の権威を高め、優越性・勇敢さを示すための手段と考え、吝嗇は軽蔑され、人間関係を破滅に導くものだった。金の切れ目が縁の切れ目ではありませんが、贈るものが無くなれば家臣たちは離れていった。又貨幣に換えたとしてもこれを支払い手段としてはあまり用いられず、寧ろ装飾品・財宝と捉えられ、自分の人格(魂)が籠った「モノ」として、他者の所有に帰するのを嫌い(幸運を他者に奪われないように)、死を予期した人は地中に埋めることが多かった。だから物を贈るという行為は、贈与自体に意味があるのではなく、相手と付き合いたいという希望表明であり、贈るものの人格が刻み込まれている物を受け取った場合は、相応のお返しをしなければならない。それができなければ贈り主に対し奉仕・隷属関係を結ばなければならなくなる。悪意をもってそれが為されることもあったという。
「贈与は単に財産・動産・不動産など物の交換であったばかりか、饗宴・軍事奉仕・婦女子・祭礼なども交換され、宗教・法・道徳・政治・経済の全制度を包含する全体的社会現象だった(*)」わけです。従って「人格的触れ合いを求めず(モノに籠った魂を抜き取った金銭で)物のみの交換に終始する商人とは、対等な人間関係を結べない( **)」として軽蔑された。
こうした背景を理解したうえで、正当化の理屈を見ていくと、まずは、商業は富を蓄積する為の便利な手段だったことが挙げられる。その貨幣経済は、貨幣の「匿名性」と「価値基準の一元性」により瞬く間に都市に浸透した(便利なのです。アシもつかない)。しかし世間や神の厳しい目に耐えられず、良心の呵責にさいなまれる商人たちもいた。こうした矛盾の橋渡しをしたのがカトリック教会だったと阿部勤也さんは言います。
どうしたかというと、贈与慣行を否定したのではなく転換したのです。労働という賤しい手段によって蓄えた富も、見ず知らずの人間関係を持たない人々への饗応を行うなどの手間のかかる(商人としての)贈与をしなくても、お返しするものの代表、つまり公的な機関・教会や聖所・巡礼の宿坊等に贈与することで、教会側からお返しなしに贈与が成立するとしたのです。これによって、冨者の贈与に対する教会からの=神からのお返しは、死後の救いが賭けられるものだから、彼岸によって成立するものとなる。よって現世においては何の見返りも求めないことになる。即ちこれが「無償の贈与」の成立になるというわけです(***)。こうした考え方が民衆まで浸透してくると、この贈答の慣習は、クリスマスと誕生日や復活祭以外はほとんど行われなくなっていく。この変化は経済的な話だけでなく、時空意識の変化ともつながっており、家(安心な小宇宙)の周囲の森に象徴される(危険・恐怖に満ちた)大宇宙の区別は取り払われ、神のもとに拡がる一つの宇宙のみの空間と、永遠に続く循環する時間でなく、始まりと終わりを持つ、即ち原因と結果を持つ「意味」を持つ直線的な時間に変わった。ここに今まで個人や村の為に大宇宙との橋渡しをしていた職業、迷信と言われる観念の上に成り立っていた職業、即ち死とかかわる職業(刑吏、墓掘人、塔守りなど)・動物とかかわる職業(皮剥ぎ、豚の去勢人など)・大地や水や火とかかわる職業(道路、煙突掃除人、煉瓦工、粉ひきなど)・性に関わる職業(娼婦)などの特殊な能力をもって畏敬のまなざしをもたれていた人たちは、徐々に仕事がなくなっていくのです(****)。会社が合併すれば、中間管理職はそんな何人も必要ないわけです。やがて残ったとしても賤しい職業として、賤民扱いに至り、差別発生に向かいます。普通じゃない人間はいらなくなってくるのです。もっと大切なことは、神という超越的な存在を証人とすることで、例え共同体や家や縁の介在なしの1対1の関係ですら、「公」的な意識が介在したということです。「打つならお打ちなさい、神様が見ていらっしゃるよ」と大きな鞭を持った番人に毅然と見合った少年時代のアンデルセンの、底冷えするほど孤独な心を一人一人が知るに至ったということです。自覚を持った「個人」の誕生です。
贈与経済から貨幣経済への移行は、(土地ごとに異なり、個々の人間関係で出来上がっている、癖のある)「文化」から、(地上の全てが神の視点から一義的に説明可能な)「文明」への移行でした。
日々の気持ちの籠った文(ふみ)や発声による挨拶から、贈与互酬を伴う、思い思われるいたわりの人間関係を過ごし、自然の姿に人間の立ち位置を日々確認して生きられる文化は、携帯やメールによる匿名性を持つ伝達手段や、神の視点でドラマをわがものとするテレビジョンによる「三人称的生活感」の占拠、時間の壁を限りなく破壊した交通手段、病気という病気を次々に排除の論理で撃破していく(その実ますますウイルスを強靭に鍛えているわけですが)医学、悩みや葛藤を引き起こす現実の人間関係をバーチャルに置き換え人工の幸福に満足してしまう科学技術などにズームインした「文明」に占拠・浸食されてしまうのです。焦点の合っていない周辺は気にしない。「いい悪いは別にして」のおまじないで、無かったことにしてしまうのです。
(*)阿部勤也「中世の星の下で」--カテドラルの世界-ちくま学芸文庫P256
( **)同P262
(***)阿部勤也「中世選民の宇宙」ちくま学芸文庫p121
(****)同p260
注37)増田史郎「ヨーロッパとは何か」岩波新書1967年7月 P196