<千歳神社>ちとせじんじゃ
富山市の千歳神社です。佐々成政が戦勝祈願をした神社と伝わります。
<説明板(御由緒)>
情報が少ないので、現地説明板(御由緒)を参考にさせて頂きます。下記に一部を転記させて頂きます。(『』内は原文の写しです)
『天正九年(一五八一)佐々成政公が、越中五十四万石を領して富山城主となった時、敬神の念が厚かったので、この神明社を産土大神として崇め、城下町富山を東西に二分し、東は北の神明、西は南の神明と称し、それぞれ富山の守護神とした。』
佐々成政というと、とても荒々しく、勇猛果敢に戦うイメージが強いですね。しかしその一方で、神を敬うことを大切にしていました。
若い頃から織田信長に仕えて、徐々に頭角を現していった佐々成政が、ここ越中で一国を任されたのが40代の半ばのこと。越中54万石ですからね。これはかなり凄いことです。そのまま何事なければ、更に飛躍できたことでしょう。しかし、そうはなりませんでした。
成政が柴田勝家らとともに上杉方の魚津城を攻めている真っ最中に、主君が本能寺で討たれてしまいます。これ以降、状況は激しく変化。成政は時代の流れに激しく抵抗しますが、良い結果は得られませんでした。
終わってみれば、越中を領し、この神社を保護した頃が、出世のピークだったのかもしれません。
<千歳神社鳥居>
勢いに乗っていた佐々成政が大切にした地元の神明社。富山の土地神としては最も古いとされています。
説明板によれば、当初は別の場所に鎮座していたようです。説明文をそのまま転記させて頂くと『当神社は北の神明にあたり、当時は蛯町の地に鎮座していましたが、富山藩祖前田利次公が入城後、寛文年間城下の町割に際し現在地に移った。』とのこと。江戸時代になって移転したわけですね。
また、神明社が千坂神社と改称されたのは明治になってからとのこと。説明文には、越中富山藩の第10代藩主である前田利保が、富山城の出丸に隠居所として千歳御殿を造り、城の近くを流れる神通川の下流を千歳川と名づけたことが記されています。神社の改称も、千歳御殿に因んだのでしょう。
<千歳橋>
千歳神社近くの千歳橋です。川はかつての神通川の流路とほぼ一致します。
<佐々成政ゆかりの神社>
現在の社殿は昭和になって再建されたものです。しかし神社の始まりは古く、長い歴史のなかには、
、戦国武将・佐々成政も深く関わっています。
以上、富山市にて佐々成政ゆかりの神社を訪ねたというお話でした。拙ブログにお付き合い頂き、ありがとうございます。
■訪問:千歳神社
[富山県富山市千歳町]2丁目
■参考及び抜粋
現地説明板(千歳神社由緒)
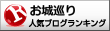
お城巡りランキング
タグ:富山




