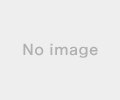新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2021年05月31日
カッコウ
5月最後の日は快晴の朝になった。
久しぶりの快晴だ。
私の住む田舎町では、耳を澄ますと、カッコウが鳴く。
ホトトギスも鳴く。
そしてトンビが大空で歌う。
その中で、抜けるような青空のもと、近くの山々が朝日に輝く…。
間もなく蛍も飛び交うだろう…。
学校では明日から中間考査。
運動会の日程で、例年より遅くなったが、中1にとっては初めての定期考査。
緊張とプレッシャーで潰れそうになってしまう生徒もいるが、皆が乗り越えてきた道でもある。
入学試験で大きな試験は経験しているとは言え、今は中学生。一人で立ち向かわなければならない。
初めての経験を、重ね、繰り返し、繰り返し成長して、大人への道へ進んでいくのだ。
あと一月もすれば、ヒグラシの季節だ。
季節は巡り、時は流れ、子どもたちは成長していく。
と、同時に、我々も齢を重ねていく…。
私にとって、かつてのバイタリティは減りつつある。
ギラギラ感が薄れ、おおらかになったとも言えるが、老獪になったとも言える。
それでいて、かつての経験と異なり、思い通りならないと、少なからず傷つく…。
早朝から勉強している生徒に、「頑張れよ!」と、心の中で声援を送る。
みんな来た道。そしてこの先も、若者が歩んでいく道。
教室の外では、何事もなかったかのように、小鳥たちが歌を歌っている。


久しぶりの快晴だ。
私の住む田舎町では、耳を澄ますと、カッコウが鳴く。
ホトトギスも鳴く。
そしてトンビが大空で歌う。
その中で、抜けるような青空のもと、近くの山々が朝日に輝く…。
間もなく蛍も飛び交うだろう…。
学校では明日から中間考査。
運動会の日程で、例年より遅くなったが、中1にとっては初めての定期考査。
緊張とプレッシャーで潰れそうになってしまう生徒もいるが、皆が乗り越えてきた道でもある。
入学試験で大きな試験は経験しているとは言え、今は中学生。一人で立ち向かわなければならない。
初めての経験を、重ね、繰り返し、繰り返し成長して、大人への道へ進んでいくのだ。
あと一月もすれば、ヒグラシの季節だ。
季節は巡り、時は流れ、子どもたちは成長していく。
と、同時に、我々も齢を重ねていく…。
私にとって、かつてのバイタリティは減りつつある。
ギラギラ感が薄れ、おおらかになったとも言えるが、老獪になったとも言える。
それでいて、かつての経験と異なり、思い通りならないと、少なからず傷つく…。
早朝から勉強している生徒に、「頑張れよ!」と、心の中で声援を送る。
みんな来た道。そしてこの先も、若者が歩んでいく道。
教室の外では、何事もなかったかのように、小鳥たちが歌を歌っている。
2021年05月30日
草刈り
地元の草刈りがあった。
十数人の部落民が、一斉に草刈りをすると、あっという間に、道路脇の草は刈られていく。
私は、草刈りが下手くそで、時間もかかるので、この日に合わせて、何日も前から少しずつ私の担当エリアを刈っていたのだ。
お陰で、今日も慌てることなく終えることができた。
草刈りの開始時間は朝の6時。
だが私は、その30分前から始める。
私が草刈りを始めて、程なく他の人も草刈りを始める。
順調にいけば、6時半には「終わりだべ」と解散になる。
何となく集まってきて、何となく解散するスタイルにも慣れてきた。
草刈りだって、気づいたら、気づいた人がやる。
それが農家を中心として営む地域の、古来からの助け合いの精神だ。
しかし彼等は、誰がやったをちゃんと知っている。
どこで見ているのだろうか、と思うのだが、地域のたいていの出来事は、皆が把握しているのだ。
恐らく、畑や田んぼ仕事をしながら見ているのだろう。
ある種の共同体だから、いざというときは、助け合って生き抜いてきたのだ。
「ありゃ、駄目だ。あいつは信用できねぇ…。」
今は亡き、私が住んでいる家のもと住人に対して、そんな言葉を聞いたことがある。
私自身が、「あいつは駄目だ」と言われないように努力しなくてはなるまい…。
基本的には優しい人たちばかりだ。
飲み会があっても、楽しく時を過ごせる。
私自身、新参者には違いないが、そうしたコミュニティにいられることを嬉しく思う…。
以前はもっと厳しい方がいらしたと聞く。
今の重鎮たちは、その人の指導のもと、生きてきたと言う。
そんな中で、今も田舎の部落は生き抜いている…。


十数人の部落民が、一斉に草刈りをすると、あっという間に、道路脇の草は刈られていく。
私は、草刈りが下手くそで、時間もかかるので、この日に合わせて、何日も前から少しずつ私の担当エリアを刈っていたのだ。
お陰で、今日も慌てることなく終えることができた。
草刈りの開始時間は朝の6時。
だが私は、その30分前から始める。
私が草刈りを始めて、程なく他の人も草刈りを始める。
順調にいけば、6時半には「終わりだべ」と解散になる。
何となく集まってきて、何となく解散するスタイルにも慣れてきた。
草刈りだって、気づいたら、気づいた人がやる。
それが農家を中心として営む地域の、古来からの助け合いの精神だ。
しかし彼等は、誰がやったをちゃんと知っている。
どこで見ているのだろうか、と思うのだが、地域のたいていの出来事は、皆が把握しているのだ。
恐らく、畑や田んぼ仕事をしながら見ているのだろう。
ある種の共同体だから、いざというときは、助け合って生き抜いてきたのだ。
「ありゃ、駄目だ。あいつは信用できねぇ…。」
今は亡き、私が住んでいる家のもと住人に対して、そんな言葉を聞いたことがある。
私自身が、「あいつは駄目だ」と言われないように努力しなくてはなるまい…。
基本的には優しい人たちばかりだ。
飲み会があっても、楽しく時を過ごせる。
私自身、新参者には違いないが、そうしたコミュニティにいられることを嬉しく思う…。
以前はもっと厳しい方がいらしたと聞く。
今の重鎮たちは、その人の指導のもと、生きてきたと言う。
そんな中で、今も田舎の部落は生き抜いている…。
2021年05月29日
小学生と中学生
中学生になって一番最初の試練は、もしかしたら、「先輩と良好な関係を築く」ことかも知れない。
どこの学校でも、小学校から中学校へ進学した際にはギャップがあって(中1ギャップ)、そのギャップにうまく適応できない生徒がいるようだ。
近隣の学校では、そのために中学校と小学校が積極的に交流している。
いままで友達だと思っていた人が、急に先輩として見なくてはいけなくなり、呼び捨てからさん付けや、先輩と呼ぶ。敬語も使う。
楽しく先生と関わっていたのに、中学の先生は怖い。
話しかけにくい。
すぐに職員室に帰ってしまう。
遊んでくれない…。
確かに小学校とのギャップは大きい。
それでも、私立学校に来るくらいだから、相応の覚悟の元に入学してきたかつての生徒たちは、それほどそのギャップを感じることはなかった。
だが、昨今は違う。
あからさまに幼いのである。
成績も下がったという面もあるが、成績が低いということは、基本的な生活習慣の確立ができておらず、勉強に対する意欲や集中力も低いという傾向がある。
行動も刹那的で、考えて行動するというよりも、反射的に動く。
発言も、思いついたことを言い、その場の雰囲気や、状況を把握できない。
そんな中で、思い通りにならないことが、ギャップになるのだろう。
中学当初は、先輩から優しく接してもらえ、言葉遣いなども大目に見られるのだろうが、だんだんと、先輩たちの目は厳しくなる。
逆に、それが理解できずに先輩になった場合、今度は後輩の行動や発言に傷つく…。
学力低下は、生活面にも大きな影響を与え、教員としての仕事の柱をさらに何本も打ち立てる。
変わらない中に、変わって行く姿に対処していくのが教員だが、老体にはやや重い…。


どこの学校でも、小学校から中学校へ進学した際にはギャップがあって(中1ギャップ)、そのギャップにうまく適応できない生徒がいるようだ。
近隣の学校では、そのために中学校と小学校が積極的に交流している。
いままで友達だと思っていた人が、急に先輩として見なくてはいけなくなり、呼び捨てからさん付けや、先輩と呼ぶ。敬語も使う。
楽しく先生と関わっていたのに、中学の先生は怖い。
話しかけにくい。
すぐに職員室に帰ってしまう。
遊んでくれない…。
確かに小学校とのギャップは大きい。
それでも、私立学校に来るくらいだから、相応の覚悟の元に入学してきたかつての生徒たちは、それほどそのギャップを感じることはなかった。
だが、昨今は違う。
あからさまに幼いのである。
成績も下がったという面もあるが、成績が低いということは、基本的な生活習慣の確立ができておらず、勉強に対する意欲や集中力も低いという傾向がある。
行動も刹那的で、考えて行動するというよりも、反射的に動く。
発言も、思いついたことを言い、その場の雰囲気や、状況を把握できない。
そんな中で、思い通りにならないことが、ギャップになるのだろう。
中学当初は、先輩から優しく接してもらえ、言葉遣いなども大目に見られるのだろうが、だんだんと、先輩たちの目は厳しくなる。
逆に、それが理解できずに先輩になった場合、今度は後輩の行動や発言に傷つく…。
学力低下は、生活面にも大きな影響を与え、教員としての仕事の柱をさらに何本も打ち立てる。
変わらない中に、変わって行く姿に対処していくのが教員だが、老体にはやや重い…。
2021年05月28日
定期試験と大会
時に、定期試験前後に大会がある場合がある。
今回も、試験の二日前の日曜日が高校サッカーのインターハイ予選。
高校テニスも土日に大会だ。
今日は水泳の大会も行われている。
幸い中間考査では、中学校は大会と重なっていないが、期末考査のときに苦しい…
実は、期末考査の翌日が、中学総体なのだ。
こんな風に試験と大会が近いと、通常考査一週間前で部活動が活動しなくなる、という原則が崩れ、試験前であっても、練習をしなくてはならなくなるわけだ。
考査と考査前一週間を加えると約10日。
この間、何も身体を動かさなければ、当然試合どころではなくなってしまう。
私が担当している野球部では、練習のない日でも自主練をするきおとが習慣化されているが、何もしなければ、大会で怪我をしたり、思うように身体が動けなかったりするだろう。
試験前に勉強していない人には、大会前の部活があろうがなかろうが、あまり関係ないのかも知れないが、本気で勉強をしている人にとっては、とても大変な状況になる。
私が以前勤めていた学校では、こうした場合、「放課後一時間のみ」活動が許されたのだが、今の学校ではそうした既定はない。
それでも、彼等の勉強時間の確保は担保しなくてはいけないのだろう。
中学総体が試験と近づいてしまったのは、本来7月下旬に行われていた総体が、何年か前の猛暑で前倒しになったからだ。
それに加えて、今年は、私の学校の期末考査が少し遅くなった。
これにより、結局生徒に負担をかけることになってしまっている。
「勉強しなくては…」、と思いつつも、大会がある。
総体は中3は最後の大会である。
昨年はコロナで中止になったが、今年は今のところ実施の見込みである。
「中間考査で点数を稼いでおきなさい!」
という私の言葉も虚しく、中間考査前でありながら、彼等はそれほど勉強しているとも思えないのだが…。
私はせっせと試験問題を作っている…。
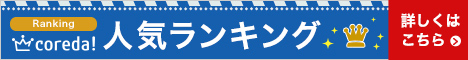

今回も、試験の二日前の日曜日が高校サッカーのインターハイ予選。
高校テニスも土日に大会だ。
今日は水泳の大会も行われている。
幸い中間考査では、中学校は大会と重なっていないが、期末考査のときに苦しい…
実は、期末考査の翌日が、中学総体なのだ。
こんな風に試験と大会が近いと、通常考査一週間前で部活動が活動しなくなる、という原則が崩れ、試験前であっても、練習をしなくてはならなくなるわけだ。
考査と考査前一週間を加えると約10日。
この間、何も身体を動かさなければ、当然試合どころではなくなってしまう。
私が担当している野球部では、練習のない日でも自主練をするきおとが習慣化されているが、何もしなければ、大会で怪我をしたり、思うように身体が動けなかったりするだろう。
試験前に勉強していない人には、大会前の部活があろうがなかろうが、あまり関係ないのかも知れないが、本気で勉強をしている人にとっては、とても大変な状況になる。
私が以前勤めていた学校では、こうした場合、「放課後一時間のみ」活動が許されたのだが、今の学校ではそうした既定はない。
それでも、彼等の勉強時間の確保は担保しなくてはいけないのだろう。
中学総体が試験と近づいてしまったのは、本来7月下旬に行われていた総体が、何年か前の猛暑で前倒しになったからだ。
それに加えて、今年は、私の学校の期末考査が少し遅くなった。
これにより、結局生徒に負担をかけることになってしまっている。
「勉強しなくては…」、と思いつつも、大会がある。
総体は中3は最後の大会である。
昨年はコロナで中止になったが、今年は今のところ実施の見込みである。
「中間考査で点数を稼いでおきなさい!」
という私の言葉も虚しく、中間考査前でありながら、彼等はそれほど勉強しているとも思えないのだが…。
私はせっせと試験問題を作っている…。
2021年05月27日
愛するということ
つくづく、「自分は駄目な奴だなぁ」と思う。
平凡かそれ以下で、優れた能力を発揮している同僚たちと比べると、勝っているのは年齢くらいで、とても太刀打ちできるものではない。
生徒たちだって優秀で、将来彼等が世の中のリーダーになった時、その足下にも及ばず、霞んで見えるくらいの存在。
それが今の私である。
そうは言っても、私にも、心の奥底に僅かながらの『愛』があるのだろう。
私が教員生活として残された時間は、それほど多くない。
だが、私の『愛』で、生徒たちを導くことは、まだまだ出来るかも知れない。
最近、そんな風に考えるようになった。
野に咲く花を見て、美しいと感じる心は、幸せな気持ち。
無邪気な子どもたちを見て、微笑ましく思う気持ちも、幸せな気持ち。
溢れる笑顔で駆け回る子ども立ちを見るのも、幸せな気持ち。
一生懸命問題を解く子どもたちの姿は美しい。
遠くに見える山々の雄大さと同じくらい美しい。
たとえ、答えを間違えても、もう一度チャレンジして、「できること」を目指す彼等の姿を見て、私の人生を顧みる。
教師という権威にたよらず
歳をとったベテランという姿に甘んじず
いつも新鮮な気持ちで
生徒と関わることができたならば
いつまでもこの仕事を続けることができるのだろうか。
子どもたちが成長していく姿は
青空を見て美しいと思う心
懸命に生きている虫たち
夜空に輝く無数の星々
これらの美しさと同じ
元気に走る子どもたちの姿を見るのも
学んで知識を得て嬉しそうな姿を見るのも
勝負に負けて泣きじゃくる子どもたちの姿を見るのも
すべて教育者の醍醐味
さあ、もう一踏ん張りしようか。


平凡かそれ以下で、優れた能力を発揮している同僚たちと比べると、勝っているのは年齢くらいで、とても太刀打ちできるものではない。
生徒たちだって優秀で、将来彼等が世の中のリーダーになった時、その足下にも及ばず、霞んで見えるくらいの存在。
それが今の私である。
そうは言っても、私にも、心の奥底に僅かながらの『愛』があるのだろう。
私が教員生活として残された時間は、それほど多くない。
だが、私の『愛』で、生徒たちを導くことは、まだまだ出来るかも知れない。
最近、そんな風に考えるようになった。
野に咲く花を見て、美しいと感じる心は、幸せな気持ち。
無邪気な子どもたちを見て、微笑ましく思う気持ちも、幸せな気持ち。
溢れる笑顔で駆け回る子ども立ちを見るのも、幸せな気持ち。
一生懸命問題を解く子どもたちの姿は美しい。
遠くに見える山々の雄大さと同じくらい美しい。
たとえ、答えを間違えても、もう一度チャレンジして、「できること」を目指す彼等の姿を見て、私の人生を顧みる。
教師という権威にたよらず
歳をとったベテランという姿に甘んじず
いつも新鮮な気持ちで
生徒と関わることができたならば
いつまでもこの仕事を続けることができるのだろうか。
子どもたちが成長していく姿は
青空を見て美しいと思う心
懸命に生きている虫たち
夜空に輝く無数の星々
これらの美しさと同じ
元気に走る子どもたちの姿を見るのも
学んで知識を得て嬉しそうな姿を見るのも
勝負に負けて泣きじゃくる子どもたちの姿を見るのも
すべて教育者の醍醐味
さあ、もう一踏ん張りしようか。
2021年05月26日
ピアノレッスン
高1のS君にピアノレッスンをしてみた。
「自分で音楽練習室の予約をとるのだったら、教えてあげるよ…。」
と言っておいたら、きちんと予約していた。
S君は、多少はピアノを弾けるようだが、習ったことはなかったようだ。
かく言う私も、それほど長い期間レッスンを受けた訳ではない。
世界的ピアニストの方と知り合いだったので、その方のレッスンが、私にとって最後のレッスンだ。
ここ半年近く、私は一切ピアノを触らなかった。
ピアノを弾く時は、一種の瞑想状態になる。
心が落ち着くのである。
もちろん、弾けない曲が弾けるようになるには、かなりの時間と努力を要するし、飽きっぽい性格の私の場合、なかなか練習時間が作れない。
それでも、ピアノは好きだ。
いつかは自宅に、グランドピアノを置いてみたい。
そんな訳で、今回、初めて生徒に教えてみた。
指使いやら音階やら、教えるべきことは多いが、一番大切にしたいことは、自分の音を自分で聞くということだ。
自分で弾いた音を、自分で確認しながら、音楽性を高めていくのだ。
そこに思いを込めることができる。
その思いが、音楽の調べとなって、人に感動を生む。
そのためには、「ただ弾ける」だけではいけないわけだ。
根気を出して、訓練を重ねなくてはいけない…。
最近の若者は楽譜を読めない人が多い。
サイトの鍵盤が流れる動画で練習しているらしい…。
確かに、どの鍵盤を弾けばいいかが分かるが、これではいつまで経っても楽譜は読めるようにならないだろう。
それに強弱記号や微妙な速度調整はどうするのだろう…。
この先、レッスンが続くのかどうか分からないが、私も、ちょっと一歩を踏み出した感じだ。


「自分で音楽練習室の予約をとるのだったら、教えてあげるよ…。」
と言っておいたら、きちんと予約していた。
S君は、多少はピアノを弾けるようだが、習ったことはなかったようだ。
かく言う私も、それほど長い期間レッスンを受けた訳ではない。
世界的ピアニストの方と知り合いだったので、その方のレッスンが、私にとって最後のレッスンだ。
ここ半年近く、私は一切ピアノを触らなかった。
ピアノを弾く時は、一種の瞑想状態になる。
心が落ち着くのである。
もちろん、弾けない曲が弾けるようになるには、かなりの時間と努力を要するし、飽きっぽい性格の私の場合、なかなか練習時間が作れない。
それでも、ピアノは好きだ。
いつかは自宅に、グランドピアノを置いてみたい。
そんな訳で、今回、初めて生徒に教えてみた。
指使いやら音階やら、教えるべきことは多いが、一番大切にしたいことは、自分の音を自分で聞くということだ。
自分で弾いた音を、自分で確認しながら、音楽性を高めていくのだ。
そこに思いを込めることができる。
その思いが、音楽の調べとなって、人に感動を生む。
そのためには、「ただ弾ける」だけではいけないわけだ。
根気を出して、訓練を重ねなくてはいけない…。
最近の若者は楽譜を読めない人が多い。
サイトの鍵盤が流れる動画で練習しているらしい…。
確かに、どの鍵盤を弾けばいいかが分かるが、これではいつまで経っても楽譜は読めるようにならないだろう。
それに強弱記号や微妙な速度調整はどうするのだろう…。
この先、レッスンが続くのかどうか分からないが、私も、ちょっと一歩を踏み出した感じだ。
2021年05月25日
採密
昨年春から育てている日本ミツバチの採密を実験的に行った。
近所に住むミツバチの師匠が、「軽いから蜜入ってねぇかも知れんぞ」、というものだから、本当に入っていないのかを調べるため、重層式の巣箱の最上段を切り離してみた。
実際は、そのうちの半分より下に蜜がたまっており、少しハチミツをいただくことができた。
何もかもが初めてで、試行錯誤やら失敗の連続だったが、なんとか、あまりミツバチたちの犠牲者を出さずにできたと思う。
まずは一晩、垂れ蜜を取り、明日は巣蜜を採ったり、搾ってみようと思う。
本当は高1のT君に手伝ってもらおうと思ったのだが、最近、あまり私に寄りつかないので、高3のM君に手伝ってもらった。
「丹澤先生、防護服の中にミツバチが入ってきちゃいました…。」
と、焦るM君。
「大丈夫だ…。」
と、私はさっと蜂を払いのける。
蜜の匂いに誘われているだけで、攻撃中ではないので、凶暴ではない。
一度、蜜の状態を確認しようと、天板を開けたとき、防護服を着ていなかった私に、数匹が猛攻をかけてきたことがあったが、今回はそんなこともなかった。
アレルギー反応のこともあるので、あまり刺されない方がいい…。
「ほれ、なめてみろ」
と、採りたてのハチミツをM君になめてもらう。
いわゆる百花蜜である。
昨年からの二年越しの蜜でもある。
かなりの美味であったことは間違いあるまい。
日本ミツバチのハチミツは、100グラム1000円以上で取引される。
売れるほど取れるか分からないが、自然の恵みをしばし楽しませていただくことにしようと思う。
何と言っても、一年育てた(勝手に育った)、人生最初のミツバチなのだから…、
近所に住むミツバチの師匠が、「軽いから蜜入ってねぇかも知れんぞ」、というものだから、本当に入っていないのかを調べるため、重層式の巣箱の最上段を切り離してみた。
実際は、そのうちの半分より下に蜜がたまっており、少しハチミツをいただくことができた。
何もかもが初めてで、試行錯誤やら失敗の連続だったが、なんとか、あまりミツバチたちの犠牲者を出さずにできたと思う。
まずは一晩、垂れ蜜を取り、明日は巣蜜を採ったり、搾ってみようと思う。
本当は高1のT君に手伝ってもらおうと思ったのだが、最近、あまり私に寄りつかないので、高3のM君に手伝ってもらった。
「丹澤先生、防護服の中にミツバチが入ってきちゃいました…。」
と、焦るM君。
「大丈夫だ…。」
と、私はさっと蜂を払いのける。
蜜の匂いに誘われているだけで、攻撃中ではないので、凶暴ではない。
一度、蜜の状態を確認しようと、天板を開けたとき、防護服を着ていなかった私に、数匹が猛攻をかけてきたことがあったが、今回はそんなこともなかった。
アレルギー反応のこともあるので、あまり刺されない方がいい…。
「ほれ、なめてみろ」
と、採りたてのハチミツをM君になめてもらう。
いわゆる百花蜜である。
昨年からの二年越しの蜜でもある。
かなりの美味であったことは間違いあるまい。
日本ミツバチのハチミツは、100グラム1000円以上で取引される。
売れるほど取れるか分からないが、自然の恵みをしばし楽しませていただくことにしようと思う。
何と言っても、一年育てた(勝手に育った)、人生最初のミツバチなのだから…、
2021年05月24日
最後の砦
昨今は、「質問があります。教えて下さい」、と私を訪ねてくる生徒も少なくなった。
もしかしたら、私が潜在的に拒否しているのかも知れない。
と同時に、彼等と年齢が離れすぎて、聞きずらいのだろう。
そう考えると、教える先生の年齢は、生徒たちと近い方がいい。
私が彼等に寄り添おうとしても、彼等から見れば、自分の親よりも年齢が高い先生に違いなく、怖れのようなものを感じることだってあるだろう。
私自身の中学、高校時代を振り返っても、印象に残っているのは若手の先生だった。
年配の先生は、それなりに面白かったが、やっぱり少し距離があり、話しかけにくく、親しく話をするにはほど遠い存在であったように思う。
今、自分がそうした年齢になって、生徒との距離が年々離れていくのは仕方のないことだ。
だからこそ、引退時期があるのだろうが、それを感じる年齢になってしまったことに、悲しみを感じる。
年配の教師たちがよく言う、「あの頃はね…」という口癖も、私の口から頻繁に出てくるようにもなった。
そんな中で、今でも中学時代の教え子である何人もの高校生が、私の姿を見るたびに、満面の笑顔で挨拶をしてくれる。
そんなとき、「あぁ、教員でよかったなぁ…」、とひととき幸せな気持ちになる。
もしかしたら、これが『最後の砦』で、こうした情景すら失われた時には、私は潔く引退すべきなのだろう。
確かに、年々、そうした生徒が減っていくようにも思える。
つまり、『最後の砦』は、少しずつ崩壊し、砦としての形態を失いつつあるようでもある。
もし、私自身が、生徒から話しかけてもらえない教師となったとき、私は、淋しくて孤独死してしまうかもしれない。
それほどまでに私は寂しがり屋であったのだろうか。
かつて私に、「丹澤先生は、生徒と結婚したようなものだからな…」、と言った校長がいたことを思い出す…。
もしかしたら、私が潜在的に拒否しているのかも知れない。
と同時に、彼等と年齢が離れすぎて、聞きずらいのだろう。
そう考えると、教える先生の年齢は、生徒たちと近い方がいい。
私が彼等に寄り添おうとしても、彼等から見れば、自分の親よりも年齢が高い先生に違いなく、怖れのようなものを感じることだってあるだろう。
私自身の中学、高校時代を振り返っても、印象に残っているのは若手の先生だった。
年配の先生は、それなりに面白かったが、やっぱり少し距離があり、話しかけにくく、親しく話をするにはほど遠い存在であったように思う。
今、自分がそうした年齢になって、生徒との距離が年々離れていくのは仕方のないことだ。
だからこそ、引退時期があるのだろうが、それを感じる年齢になってしまったことに、悲しみを感じる。
年配の教師たちがよく言う、「あの頃はね…」という口癖も、私の口から頻繁に出てくるようにもなった。
そんな中で、今でも中学時代の教え子である何人もの高校生が、私の姿を見るたびに、満面の笑顔で挨拶をしてくれる。
そんなとき、「あぁ、教員でよかったなぁ…」、とひととき幸せな気持ちになる。
もしかしたら、これが『最後の砦』で、こうした情景すら失われた時には、私は潔く引退すべきなのだろう。
確かに、年々、そうした生徒が減っていくようにも思える。
つまり、『最後の砦』は、少しずつ崩壊し、砦としての形態を失いつつあるようでもある。
もし、私自身が、生徒から話しかけてもらえない教師となったとき、私は、淋しくて孤独死してしまうかもしれない。
それほどまでに私は寂しがり屋であったのだろうか。
かつて私に、「丹澤先生は、生徒と結婚したようなものだからな…」、と言った校長がいたことを思い出す…。
2021年05月23日
泣けなかった運動会
今年の運動会は、ほとんど泣けなかった。
いつもは、彼等の姿に感動し、涙ながら写真撮影をしているのだが、今年はそんなことはなかった。
彼等の雄姿に心を揺さぶられないと言うことは、「もう、この世界から引退すべきなのではないか…」、とも思う。
リーダー学年が、昔、私を苦しめた代であるということも、あまり親近感を持てなかった理由の一つではあるが、それでも自ら教育者を名乗る以上、そんなわだかまりを、何年も引きずってはいけないのだ。
あの頃のダメージが大きすぎたということもある。
だが、それを乗り越えるだけの時間も経っていることも事実。
唯一、高校三年生の演舞だけは、涙が流れた。
だが、それだけだった。
「運動会よ、早く終わってくれ」、とも思わなかったし、自らの役割を果たすため、今年も五千枚以上の写真は撮影している。
だが、彼等との距離を作り、一歩引いて見ている自分自身がいる。
リーダー学年である高2は、当初高1からも、中3からも煙たがられていたが、運動会の練習が進むにつれて、それも弱まり、最終的には、どの団も一つになった。
だが、どれだけ高2とのわだかまりが溶けたのかは分からない。
「一緒の団になって話したら、結構いい先輩でした。」
そんな声もチラホラ聞いた。
学校行事としては成功した運動会だったと思う。
見て下さった七百名以上の保護者も、概ね満足してお帰りいただけたことだろう。
だが、何となく私自身に充実感がない。
子供らに感動出来なくなった時が、この仕事を終える時期なのだろう。
ともあれ、今年も感動をありがとう。


いつもは、彼等の姿に感動し、涙ながら写真撮影をしているのだが、今年はそんなことはなかった。
彼等の雄姿に心を揺さぶられないと言うことは、「もう、この世界から引退すべきなのではないか…」、とも思う。
リーダー学年が、昔、私を苦しめた代であるということも、あまり親近感を持てなかった理由の一つではあるが、それでも自ら教育者を名乗る以上、そんなわだかまりを、何年も引きずってはいけないのだ。
あの頃のダメージが大きすぎたということもある。
だが、それを乗り越えるだけの時間も経っていることも事実。
唯一、高校三年生の演舞だけは、涙が流れた。
だが、それだけだった。
「運動会よ、早く終わってくれ」、とも思わなかったし、自らの役割を果たすため、今年も五千枚以上の写真は撮影している。
だが、彼等との距離を作り、一歩引いて見ている自分自身がいる。
リーダー学年である高2は、当初高1からも、中3からも煙たがられていたが、運動会の練習が進むにつれて、それも弱まり、最終的には、どの団も一つになった。
だが、どれだけ高2とのわだかまりが溶けたのかは分からない。
「一緒の団になって話したら、結構いい先輩でした。」
そんな声もチラホラ聞いた。
学校行事としては成功した運動会だったと思う。
見て下さった七百名以上の保護者も、概ね満足してお帰りいただけたことだろう。
だが、何となく私自身に充実感がない。
子供らに感動出来なくなった時が、この仕事を終える時期なのだろう。
ともあれ、今年も感動をありがとう。
2021年05月22日
M君暴れる…
「Sさん、パソコン室でエッチな画面見ていたよ。」
おしゃべりの中1Mが、中2のSの様子を皆に言いふらそうとしたのを、Sが先輩風を吹かせて止めた。
だが、Mは、「Sさん、長くパソコンを使っていたよ」、などと言いふらして回った。
言いふらされたと勘違いして、怒ったSは、Mとその友人たちを追い回す。
「許さん。殴ってやる!」と、暴れ回った。
最近、Mは情緒不安定である。
入学時から、自分の衝動を抑えきれないことに苦しんでおり、今は、大分コントロールできるようにはなったが、まだ感情が爆発すると、行動を抑えきれない。
「このままだと、本当に暴行事件になりますよ。」
同学年の生徒たちも、Mの行動を怖れ、彼と距離を取る。
だが、その疎外感とも孤立感とも言える状況が、ますますMを追い込んでいるようにも見える。
と言って、Mが受け入れられる状況でもない。
昨今は、後輩たちにもその噂と言動は広がり、ますます孤立しているのが現状だ。
発達の偏りとひとくくりにするのは簡単だが、そうした生徒も育て、かつ、他の生徒にいい意味で学びの場を提供できるはずだ。
検査をすれば、支援学級に入るべき生徒なのかも知れないが、うちの学校では、そういう生徒も、これまで何度も受け入れ、卒業させてきた。
学校の教育力と、生徒たちと先生たちの愛の力が、Mを善導してゆくことを信じたい。
「話しても、理解できないみたいですよ…。」
若手の先生たちはそう言うが、結局は、その指導を自分の中で受け入れる状況には到っていないのと、叱られたことへの照れ隠しが、素直さを妨げているのだろう。
根気強く繰り返しの指導で、Mが成長していくことを願うばかりだ。
良くなることを信じて疑わなければ、必ずや変わっていくだろう。
それが教育の効果だ。


おしゃべりの中1Mが、中2のSの様子を皆に言いふらそうとしたのを、Sが先輩風を吹かせて止めた。
だが、Mは、「Sさん、長くパソコンを使っていたよ」、などと言いふらして回った。
言いふらされたと勘違いして、怒ったSは、Mとその友人たちを追い回す。
「許さん。殴ってやる!」と、暴れ回った。
最近、Mは情緒不安定である。
入学時から、自分の衝動を抑えきれないことに苦しんでおり、今は、大分コントロールできるようにはなったが、まだ感情が爆発すると、行動を抑えきれない。
「このままだと、本当に暴行事件になりますよ。」
同学年の生徒たちも、Mの行動を怖れ、彼と距離を取る。
だが、その疎外感とも孤立感とも言える状況が、ますますMを追い込んでいるようにも見える。
と言って、Mが受け入れられる状況でもない。
昨今は、後輩たちにもその噂と言動は広がり、ますます孤立しているのが現状だ。
発達の偏りとひとくくりにするのは簡単だが、そうした生徒も育て、かつ、他の生徒にいい意味で学びの場を提供できるはずだ。
検査をすれば、支援学級に入るべき生徒なのかも知れないが、うちの学校では、そういう生徒も、これまで何度も受け入れ、卒業させてきた。
学校の教育力と、生徒たちと先生たちの愛の力が、Mを善導してゆくことを信じたい。
「話しても、理解できないみたいですよ…。」
若手の先生たちはそう言うが、結局は、その指導を自分の中で受け入れる状況には到っていないのと、叱られたことへの照れ隠しが、素直さを妨げているのだろう。
根気強く繰り返しの指導で、Mが成長していくことを願うばかりだ。
良くなることを信じて疑わなければ、必ずや変わっていくだろう。
それが教育の効果だ。