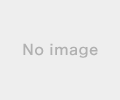新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2021年02月21日
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,58
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,58
私は今でもあの時の教師の言葉を胸に浮かべ、みんなと一緒にゲラゲラ笑った自分の姿を思い出すことが在るのです。
そして思い出すたびに、もう自分では笑う資格が無いことをつくづくと感じます。
なぜなら私は、どういう訳で羅馬(ローマ)の英雄が馬鹿になったか、アントニーともいわれる者が何故たわいなく妖婦の手管に巻き込まれてしまったか、その心持ちが現在と鳴ってはハッキリ頷けるばかりでなく、それに対して同情を禁じ得ないくらいですから。
よく世間では「女が男を欺(だま)す」と言います。しかし私の経験によると、これは決して最初から欺すのではありません。
最初は男が自ら進んで「欺される」のを喜ぶのです。
惚れた女が出来て見ると、彼女の言うことが嘘であろうと真実であろうと、男の耳にはすべて可愛い。
たまたま彼女が空涙を流しながら凭れかかってきたりすると、
「ははあ、此奴(こやつ)、この手で己を欺そうとしているな。でもお前はおかしな奴だ。可愛い奴だ、己にはちゃんとお前の腹は分ってるんだが、折角だから欺されてやるよ。まあまあたんと己をお欺し・・・・・・」
と、そんな風に男は大腹中(たいふくちゅう)に構えて、いわば子供を嬉しがらせるような気持で、わざとその手に乗ってやります。
ですから男は女に欺される積りはない。
かえって女を欺してやっているのだと、そう考えて心の中で笑っています。その証拠に私とナオミとがやはりそうでした。
「あたしの方が譲治さんより悧巧だわね」
引用書籍
谷崎潤一郎「痴人の愛」
角川文庫刊
次回に続く。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
三国志演義朗読第57vol,1(全7回)
(^_-)-☆アスカミチル
オモロかったら、
チャンネル登録
たのんだよーーーーーーんんんん(*´ε`*)チュッチュ
三国志演義朗読第57vol,1(全7回)
https://youtu.be/Dt2u9KmWVQU
2021年02月20日
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,57
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,59
が、大切なのはここの処です。私は当時、アントニーともあろう者がどうしてそんな薄情な女に迷ったのか、不思議でなりませんでした。いや、アントニーばかりではない、直ぐその前にもジュリアス・シーザーの如き英雄が、クレオパトラに引っ掛かって器量を下げている。
そういう例はまだその他にもいくらでもある。徳川時代の御家騒動や、一国の治乱興廃の跡を尋ねると、必ず蔭に物凄い妖婦の手管がないことはない。ではその手管というものは、一旦それに引っ掛かれば誰でもコロリと欺(だま)されるほど、非常に陰険に、巧妙に仕組まれているかと言うのに、どうもそうではない様な気がする。
クレオパトラがどんなに悧巧な女だったにした所で、まさかシーザーやアントニーより知恵が在ったとは考えられない。
たとい英雄でなくっても、その女に真心が在るか、彼女の言葉が嘘かほんとかぐらいなことは、用心すれば洞察できるはずである。
にもかかわらず、現に自分の身を亡ぼすのが分かっていながら、欺されてしまうというのは、餘りと言えば腑甲斐ないことだ、事実その通りだったとすると、英雄なんて何もそれほど偉い者ではないかもしれない。
私は密かにそう思って、マーク・アントニーが、「古今部類の物笑いの種」であり、「この位歴史に馬鹿を曝した人間は無い」
という教師の批評を、そのまま肯定したものでした。
引用書籍
谷崎潤一郎「痴人の愛」
角川文庫刊
次回に続く。
が、大切なのはここの処です。私は当時、アントニーともあろう者がどうしてそんな薄情な女に迷ったのか、不思議でなりませんでした。いや、アントニーばかりではない、直ぐその前にもジュリアス・シーザーの如き英雄が、クレオパトラに引っ掛かって器量を下げている。
そういう例はまだその他にもいくらでもある。徳川時代の御家騒動や、一国の治乱興廃の跡を尋ねると、必ず蔭に物凄い妖婦の手管がないことはない。ではその手管というものは、一旦それに引っ掛かれば誰でもコロリと欺(だま)されるほど、非常に陰険に、巧妙に仕組まれているかと言うのに、どうもそうではない様な気がする。
クレオパトラがどんなに悧巧な女だったにした所で、まさかシーザーやアントニーより知恵が在ったとは考えられない。
たとい英雄でなくっても、その女に真心が在るか、彼女の言葉が嘘かほんとかぐらいなことは、用心すれば洞察できるはずである。
にもかかわらず、現に自分の身を亡ぼすのが分かっていながら、欺されてしまうというのは、餘りと言えば腑甲斐ないことだ、事実その通りだったとすると、英雄なんて何もそれほど偉い者ではないかもしれない。
私は密かにそう思って、マーク・アントニーが、「古今部類の物笑いの種」であり、「この位歴史に馬鹿を曝した人間は無い」
という教師の批評を、そのまま肯定したものでした。
引用書籍
谷崎潤一郎「痴人の愛」
角川文庫刊
次回に続く。
三国志演義朗読第56回ラストvol,9
(^_-)-☆アスカミチル
オモシロかったら、
チャンネル登録
頼んだよーーーーーーーーっ
三国志演義朗読第56回ラストvol,9
https://youtu.be/S2ksP3VFnYI
2021年02月19日
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,56
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,56
「呆れたもんだね、すっかり僕を一杯食わせていたんだね」
「どう?あたしの方が少し悧巧でしょ」
「うん、悧巧だ、ナオミちゃんには敵(かな)わないよ」
すると彼女は得意になって、腹を抱えて笑うのでした。
読者諸君よ。ここで私が突然妙な話をし出すのを、どうか笑わないで聞いて下さい。
というのは、嘗て私は中学校にいた時分、歴史の時間にアントニーとクレオパトラの条(くだり)を教わったことがあります。
諸君も御承知の事でしょうが、あのアントニーがオクタヴィアヌスの軍勢を迎えてナイルの河上で船戦(ふないくさ)をする、と、アントニーに附いてきたクレオパトラは、味方の形勢が非と見るや、忽ち中途から船を返して逃げ出してしまう。
然るにアントニーはこの薄情な女王の船が自分を捨てて去るのを見ると、危急存亡の際であるにもかかわらず、戦争などはそっちのけにして、自分も直ぐに女のあとを追いかけて行きます。
「諸君」と、歴史の教師はその時私たちに言いました。
「このアントニーと言う男は女の尻を追っかけまわして、命を落としてしまったので、歴史の上にこの位馬鹿を曝した人間は無く、実にどうも、古今無類の物笑いの種であります。
英雄豪傑も、いやはやこうなってしまっては、・・・・・・」
その言い方がおかしかったので、学生たちは教師の顔を眺めながら、一度にどっと笑ったものです。
そして私も、笑った仲間の一人であったことは言うまでもありません。
引用書籍
谷崎潤一郎「痴人の愛」
角川文庫刊
次回に続く。
2021年02月18日
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,55
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,55
私は無理にそういう風に考えて、それで満足するように自分の気持ちを向けて行きました。
「譲治さんは此の頃英語の時間にも、あんまり私を馬鹿馬鹿ッて言わないようになったわね」
と、ナオミは早くも私の心の変化を看て取ってそう言いました。
学問の方には疎くっても、私の顔色を読むことにかけては彼女は実に敏かったのです。
「ああ、あんまり言うとかえってお前が意地を突っ張るようになって、結果が良くないと思ったから、方針を変えることにしたのさ」
「ふん」
と、彼女は鼻先で笑って、
「そりゃあそうよ、あんなに無暗に馬鹿馬鹿ッて言われりゃ、あたし決して言う事なんか聴きゃしないわ、あたしほんとうはね、大概な問題はちゃんと考えられたんだけれど、わざと譲治さんを困らしてやろうと思って、出来ないふりをしてヤッタの、それが譲治さんには分からなかった?」
「へえ、ほんとうかね?」
私はナオミの言うことが空威張りの負け惜しみであるのを知っていながら、故意にそう言って驚いて見せました。
「当り前さ、あんな問題が出来ない奴はありゃしないわ。それを本気で出来ないと思っているんだから、譲治さんの方がよっぽど馬鹿だわ。あたし譲治さんが怒るたんびに、おかしくッておかしくッて仕方がなかったわ」
引用書籍
谷崎潤一郎「痴人の愛」
角川文庫刊
次回に続く。
2021年02月17日
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,54
スポンサードリンク
「痴人の愛」本文 角川文庫刊vol,54
自分が選択を誤ったこと、ナオミは自分が期待していたほど賢い女ではなかったこと、もうこの事実はいくら私のひいき目でも否むに由なく、彼女が他日立派な婦人になるであろうというような望みは、今となっては全く夢であったことを悟るようになったのです。
やっぱり育ちの悪い者は争われない、千束町(せんぞくまち)の娘にはカフェエの女給が相当なのだ、柄に無い教育を授けた所で何にもならない。
わたしはしみじみそういうあきらめを抱く様になりました。が、同時に私は、一方においてあきらめ乍ら、他の一方ではますます強く彼女の肉体に惹きつけられていったのでした。
そうです、私は特に『肉体』と言います、なぜならそれは彼女の皮膚や、歯や、唇や、髪や、瞳や、その他あらゆる姿態の美しさであって、決してそこには精神的の何物もなかったのですから。
つまり彼女は頭脳の方では私の期待を裏切りながら、肉体の方ではいよいよますます理想通りに、いやそれ以上に、美しさを増して行ったのです。
「馬鹿な女」「仕様のない奴(やつ)だ」と、思えば思うほど尚意地悪くその美しさに誘惑される。
これは実に私にとって不幸なことでした。
私は次第に彼女を「仕立ててやろう」という純な心持を忘れてしまって、むしろあべこべにずるずる引き擦(ず)られるようになり、これではいけないと気が付いた時には、既に自分でもどうすることも出来なくなっていたのでした。
「世の中の事は全て自分の思い通りに行くものではない。自分はナオミを、精神と肉体と、両方面から美しくしようとした。
そして精神の方面では失敗したけれど、肉体の方面では立派に成長したじゃないか。
自分は彼女がこの方面でこれほど美しくなろうとは思い設けていなかったのだ。
そうして見ればその成功は他の失敗を補って餘りあるのではないか」
引用書籍
谷崎潤一郎「痴人の愛」
角川文庫刊
次回に続く。
スポンサードリンク
三国志演義朗読第56回vol,6(ラストvol,9)
スポンサードリンク
(^_-)-☆アスカミチル 当チャンネル目標は、
ユーザーさんを 短期間で 文学通
にすること!!
★毎日更新の動画視聴で、
必ず文学通に
なれるのですよーーーーーっっっっ。









★2021(令和3年)
2/1(月)から 以下の更新スタイルね。
●毎日P.M.4:00までに 更新アプロード。
YOUTUBEチャンネル 「動画文学通」
https://www.youtube.com/channel/UCTZ5GnDOX9JTi8NHODbF26A
【三国志演義】朗読 1動画(約15分朗読)
&
●毎日P.M.4:00までに更新アプロード。
ブログ「3分読むだけ文学通」
http://14highschool.jugem.jp/
【痴人の愛】本文掲載 1日1記事(約800字掲載)
どんぞーーーーーーーー。
三国志演義朗読第56回vol,6(ラストvol,9)
https://youtu.be/3m-8AgVAwg4
スポンサードリンク
(^_-)-☆アスカミチル 当チャンネル目標は、
ユーザーさんを 短期間で 文学通
にすること!!
★毎日更新の動画視聴で、
必ず文学通に
なれるのですよーーーーーっっっっ。
★2021(令和3年)
2/1(月)から 以下の更新スタイルね。
●毎日P.M.4:00までに 更新アプロード。
YOUTUBEチャンネル 「動画文学通」
https://www.youtube.com/channel/UCTZ5GnDOX9JTi8NHODbF26A
【三国志演義】朗読 1動画(約15分朗読)
&
●毎日P.M.4:00までに更新アプロード。
ブログ「3分読むだけ文学通」
http://14highschool.jugem.jp/
【痴人の愛】本文掲載 1日1記事(約800字掲載)
どんぞーーーーーーーー。
三国志演義朗読第56回vol,6(ラストvol,9)
https://youtu.be/3m-8AgVAwg4
スポンサードリンク
2021年02月16日
「現代日本の開花」講演本文 1/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 1/18
はなはだお暑いことで、こう暑くては多人数お寄り合いになって演説などお聴きになるのは定めしお苦しいだろうと思います。
ことに承れば昨日も何か演説会があったそうで、そう同じ催しが続いてはいくら中(あた)らない保証のあるものでも、多少は流行りすぎの気味で、お聴きになるのもよほどご困難だろうとご察し申します。
が、演説をやるほうの身になって見てもそう楽ではありません。
ことにただ今牧君の紹介で漱石君の演説は紆余曲折の妙があるとか何とかいう広告めいた賛辞を頂戴した後に出て、同君の吹聴通りを遣ろうとすると、あたかも紆余曲折の妙を極めるための芸当を御覧に入れるために登壇したようなもので、いやしくもその妙を極めなければ降りることができないような気がして、いやが上に遣りにくい羽目に陥ってしまうわけであります。
実はここへ出て参る前ちょっと先番の牧君に相談を掛けたことがあるのです。
これは内々ですが、思い切って打ち明けてお話ししてしまいます。
というほどの秘密でもありませんが、全くのところ、今日の講演は、長時間諸君に対してお話をする材料が不足のような気がしてならなかったから、牧さんにあなたの方は少しは伸ばせますかと聞いたのです。
すると牧君は自分の方は伸ばせばいくらでも伸びると気丈夫な返事をしてくれたので、たちまち親船に乗ったような心持になって、それじゃア、少し伸ばして戴きたいと頼んでおきました。
その結果として、冒頭だか序論だかに私の演説の短評を試みられたのは、もともと私の注文から出たことではなはだありがたいことには違いないけれども、その代わり、厭に遣りにくくなってしまったこともまた争われない事実です。
元来がそういう情けない依頼を敢えてするくらいですから、曲折どころではない、真直に行き当たってピタリと終(しま)いになるべき演説です。
なかなかもって、抑揚頓挫(とんざ)波乱曲折の妙を極めるだけの材料などは薬にしたくてももちあわせておりません。
引用書籍
夏目漱石著【私の個人主義】
講談社学術文庫刊
スポンサードリンク
はなはだお暑いことで、こう暑くては多人数お寄り合いになって演説などお聴きになるのは定めしお苦しいだろうと思います。
ことに承れば昨日も何か演説会があったそうで、そう同じ催しが続いてはいくら中(あた)らない保証のあるものでも、多少は流行りすぎの気味で、お聴きになるのもよほどご困難だろうとご察し申します。
が、演説をやるほうの身になって見てもそう楽ではありません。
ことにただ今牧君の紹介で漱石君の演説は紆余曲折の妙があるとか何とかいう広告めいた賛辞を頂戴した後に出て、同君の吹聴通りを遣ろうとすると、あたかも紆余曲折の妙を極めるための芸当を御覧に入れるために登壇したようなもので、いやしくもその妙を極めなければ降りることができないような気がして、いやが上に遣りにくい羽目に陥ってしまうわけであります。
実はここへ出て参る前ちょっと先番の牧君に相談を掛けたことがあるのです。
これは内々ですが、思い切って打ち明けてお話ししてしまいます。
というほどの秘密でもありませんが、全くのところ、今日の講演は、長時間諸君に対してお話をする材料が不足のような気がしてならなかったから、牧さんにあなたの方は少しは伸ばせますかと聞いたのです。
すると牧君は自分の方は伸ばせばいくらでも伸びると気丈夫な返事をしてくれたので、たちまち親船に乗ったような心持になって、それじゃア、少し伸ばして戴きたいと頼んでおきました。
その結果として、冒頭だか序論だかに私の演説の短評を試みられたのは、もともと私の注文から出たことではなはだありがたいことには違いないけれども、その代わり、厭に遣りにくくなってしまったこともまた争われない事実です。
元来がそういう情けない依頼を敢えてするくらいですから、曲折どころではない、真直に行き当たってピタリと終(しま)いになるべき演説です。
なかなかもって、抑揚頓挫(とんざ)波乱曲折の妙を極めるだけの材料などは薬にしたくてももちあわせておりません。
引用書籍
夏目漱石著【私の個人主義】
講談社学術文庫刊
スポンサードリンク
「現代日本の開花」講演本文 2/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 2/18
とそう言った所で何もただボンヤリ教壇に登ったわけでもないので、ここへ出て来るだけの用意は、多少準備して参ったには違いないのです。
もっとも私がこの和歌山へ参るようになったのは、当初からの計画ではなかったのですが、私のほうで近畿地方を所望したので、社のほうでは和歌山をその中(うち)へ割り振ってくれたのです。
お陰で私もまだ見ない土地や名所などを探る便宜を得ましたのは好都合です。
そのついでに演説をする、のではない演説のついでに玉津島だの紀三井寺などを見たわけですから、これらの故跡や名勝に対しても、空手では帰れません。
お話をする題目は、ちゃんと東京表で極(き)めて参りました。
その題目は「現代日本の開花」というので、現代という字は下へもってきても、上へ持ってきても同じことで、「現代日本の開花」でも、「日本現代の開花」でも大して私のほうでは構いません。
「現代」という字があって、「日本」という字があって、「開花」という字があって、その間へ「の」の字が入っていると思えば、それだけの話です。
何の造作もなく、ただ現今の日本の開花という、こういう簡単なものです。
その開花をどうするのだと聞かれれば、実は私の手際ではどうもしようがないので、私はただ開花の説明をして、後はあなた方の御高見にお任せするつもりであります。
では開花を説明して何になる?とこうお聞きになるかも知れないが、私は現代の日本の開花ということが、諸君によくお分かりになっておるまいと思う。
お分かりになっていなかろうと思うというと、失礼ですけれども、どうもこれが一般の日本人に能(よ)く呑み込めていないように思う。
私だってそれほど分かってもいないのです。
けれども先ず諸君よりもそんな方面に余計頭を使う余裕のある境遇におりますから、こういう機会を利用して、自分の思ったところだけをあなた方に聞いて頂こうというのが主眼なのです。
どうせあなた方も私も日本人で、現代に生まれたもので、過去の人間でも未来の人間でも何でもない上に、現に開花の影響を受けているのだから、現代と日本と開花という三つの言葉は、どうしても諸君と私とに切っても切れない離すべからざる密接な関係があるのは分かりきったことですが、それにもかかわらず、お互いに現代の日本の開花について無頓着であったり、または余りハッキリした理会を有(も)っていなかったならば、万事に都合が悪いわけだから、まあ互いに研究もし、また分かるだけは分からせておく方が、都合が好かろうと思うのであります。
引用書籍
夏目漱石講演記録文
「現代日本の開花」
講談社学術文庫
スポンサードリンク
とそう言った所で何もただボンヤリ教壇に登ったわけでもないので、ここへ出て来るだけの用意は、多少準備して参ったには違いないのです。
もっとも私がこの和歌山へ参るようになったのは、当初からの計画ではなかったのですが、私のほうで近畿地方を所望したので、社のほうでは和歌山をその中(うち)へ割り振ってくれたのです。
お陰で私もまだ見ない土地や名所などを探る便宜を得ましたのは好都合です。
そのついでに演説をする、のではない演説のついでに玉津島だの紀三井寺などを見たわけですから、これらの故跡や名勝に対しても、空手では帰れません。
お話をする題目は、ちゃんと東京表で極(き)めて参りました。
その題目は「現代日本の開花」というので、現代という字は下へもってきても、上へ持ってきても同じことで、「現代日本の開花」でも、「日本現代の開花」でも大して私のほうでは構いません。
「現代」という字があって、「日本」という字があって、「開花」という字があって、その間へ「の」の字が入っていると思えば、それだけの話です。
何の造作もなく、ただ現今の日本の開花という、こういう簡単なものです。
その開花をどうするのだと聞かれれば、実は私の手際ではどうもしようがないので、私はただ開花の説明をして、後はあなた方の御高見にお任せするつもりであります。
では開花を説明して何になる?とこうお聞きになるかも知れないが、私は現代の日本の開花ということが、諸君によくお分かりになっておるまいと思う。
お分かりになっていなかろうと思うというと、失礼ですけれども、どうもこれが一般の日本人に能(よ)く呑み込めていないように思う。
私だってそれほど分かってもいないのです。
けれども先ず諸君よりもそんな方面に余計頭を使う余裕のある境遇におりますから、こういう機会を利用して、自分の思ったところだけをあなた方に聞いて頂こうというのが主眼なのです。
どうせあなた方も私も日本人で、現代に生まれたもので、過去の人間でも未来の人間でも何でもない上に、現に開花の影響を受けているのだから、現代と日本と開花という三つの言葉は、どうしても諸君と私とに切っても切れない離すべからざる密接な関係があるのは分かりきったことですが、それにもかかわらず、お互いに現代の日本の開花について無頓着であったり、または余りハッキリした理会を有(も)っていなかったならば、万事に都合が悪いわけだから、まあ互いに研究もし、また分かるだけは分からせておく方が、都合が好かろうと思うのであります。
引用書籍
夏目漱石講演記録文
「現代日本の開花」
講談社学術文庫
スポンサードリンク
「現代日本の開花」講演本文 3/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 VOL,3/18
それについては少し学究めきますが、日本とかいう現代とか特別な形容詞に束縛されない一般の開花から出立して、その性質を調べる必要があると考えます。
お互いに開花という言葉を使っておって、日に何遍も繰り返しているけれども、果たして開花とはどんなものだと煎じ詰めて聞き糺(ただ)されて見ると、今まで互いに了解し得たとばかり考えていた言葉の意味が存外喰い違っていたり、あるいはもってのほかに漠然と曖昧であったりするのはよくあることだから、私は先ず開花の定義から極めて懸かりたいのです。
もっとも定義を下すについては、よほど気を付けないと、飛んでもないことになる。
これを難しく言いますと、定義を下せばその定義のために定義を下されたものがピタリと糊細工のように硬張ってしまう。
複雑な特性を簡単にまとめる学者の手際と脳力とには敬服しながらも、一方においてその迂闊(うかつ)を惜しまなければならないようなことが、彼らの下した定義を見ると、よくあります。
その弊所を極く分かりやすく一口にお話すれば、生きたものをわざと四角四面の棺の中へ入れて、殊更に融通が利かないようにするからである。
もっとも幾何学などで中心から円周に至る距離が、ことごとく等しいものを円というというような定義はあれで差し支えない、定義の便宜があって、弊害のない結構なものですが、これは実世間に存在する円いものを説明するといわんよりむしろ理想的に頭の中にある円というものをかく約束上取り決めたまでであるから、古往今来変わりっこないので、どこまでもこの定義一本で押して行かれる。
その他四角だろうが三角だろうが、幾何的に存在している限りは、それぞれの定義で一旦纏めたら決して動かす必要もないかもしれないが、不幸にして現実世の中にある円とか四角とか三角とかいうもので、過去現在未来を通じて動かないものは甚だ少ない。
ことにそれ自身に、活動力を具(そな)えて存在するものには、変化消長がどこまでも付き纏っている。
今日の四角は明日の三角にならないとも限らないし、明日の三角がまたいつ円く崩れ出さないともいえない。
要するに幾何学のように定義があってその定義から物を拵(こしら)えだしたのでなくって、物があってその物を説明するために定義を作るとなると、勢いその物の変化を見越してその意味を含ましたものでなければ、いわゆる杓子定規(しゃくしじょうぎ)とかで一向気の利かない定義になってしまいます。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社学術文庫刊
それについては少し学究めきますが、日本とかいう現代とか特別な形容詞に束縛されない一般の開花から出立して、その性質を調べる必要があると考えます。
お互いに開花という言葉を使っておって、日に何遍も繰り返しているけれども、果たして開花とはどんなものだと煎じ詰めて聞き糺(ただ)されて見ると、今まで互いに了解し得たとばかり考えていた言葉の意味が存外喰い違っていたり、あるいはもってのほかに漠然と曖昧であったりするのはよくあることだから、私は先ず開花の定義から極めて懸かりたいのです。
もっとも定義を下すについては、よほど気を付けないと、飛んでもないことになる。
これを難しく言いますと、定義を下せばその定義のために定義を下されたものがピタリと糊細工のように硬張ってしまう。
複雑な特性を簡単にまとめる学者の手際と脳力とには敬服しながらも、一方においてその迂闊(うかつ)を惜しまなければならないようなことが、彼らの下した定義を見ると、よくあります。
その弊所を極く分かりやすく一口にお話すれば、生きたものをわざと四角四面の棺の中へ入れて、殊更に融通が利かないようにするからである。
もっとも幾何学などで中心から円周に至る距離が、ことごとく等しいものを円というというような定義はあれで差し支えない、定義の便宜があって、弊害のない結構なものですが、これは実世間に存在する円いものを説明するといわんよりむしろ理想的に頭の中にある円というものをかく約束上取り決めたまでであるから、古往今来変わりっこないので、どこまでもこの定義一本で押して行かれる。
その他四角だろうが三角だろうが、幾何的に存在している限りは、それぞれの定義で一旦纏めたら決して動かす必要もないかもしれないが、不幸にして現実世の中にある円とか四角とか三角とかいうもので、過去現在未来を通じて動かないものは甚だ少ない。
ことにそれ自身に、活動力を具(そな)えて存在するものには、変化消長がどこまでも付き纏っている。
今日の四角は明日の三角にならないとも限らないし、明日の三角がまたいつ円く崩れ出さないともいえない。
要するに幾何学のように定義があってその定義から物を拵(こしら)えだしたのでなくって、物があってその物を説明するために定義を作るとなると、勢いその物の変化を見越してその意味を含ましたものでなければ、いわゆる杓子定規(しゃくしじょうぎ)とかで一向気の利かない定義になってしまいます。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社学術文庫刊
「現代日本の開花」講演本文 4/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 VOL,4/18
丁度汽車がゴーッと駆けてくる、その運動の一瞬間、すなわち運動の性質の最も現れにくい刹那の光景を写真に撮って、これが汽車だ汽車だといって、あたかも汽車のすべてを一枚のうちに写しえたごとく吹聴すると一般的である。
なるほどどこから見ても、汽車に違いありますまい。
けれども汽車に見逃してはならない運動というものが、この写真のうちには出ていないのだから、実際の汽車とは到底比較のできないくらい懸絶しているといわなくてはなりますまい。
ご存知の琥珀というものがありましょう。
琥珀の中に時々蠅が入ったのがある。
透かして見ると蠅に違いありませんが、要するに動きの取れない蠅であります。
蠅でないとは言えぬでしょうが、生きた蠅とはいえますまい。
学者の下す定義には、この写真の汽車や琥珀の中の蠅に似て、鮮やかに見えるが死んでいると評しなければならないものがある。
それで注意を要するというのであります。
つまり変化をするものを捉えて、変化を許さぬがごとくピタリと定義を下す。
巡査というものは、白い服を着て、サーベルを下げているものだなどと天から極められた日には、巡査もやりきれないでしょう。
家へ帰って浴衣も着替えるわけにいかなくなる。
この暑いのに、剣ばかり下げていなければならないのは可哀そうだ。
騎兵とは馬に乗るものである。
これもご尤もに違いないが、いくら騎兵だって年が年中馬に乗り続けに乗っているわけにも行かないじゃありませんか。
少しは下りたいでさア。
こう例を挙げれば、際限がないから、いい加減に切り上げます。
実は開花の定義を下すお約束をしてしゃべっていたところが、いつの間にか開花はそっちのけになって、むつかしい定義論に迷い込んではなはだ恐縮です。
がこのくらい注意をした上で、さて開花とは何者だと纏(まと)めてみたら、幾分か学者の陥りやすい弊害を避け得られるし、またその便宜をも受けることが出来るだろうと思うのです。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社文庫刊
丁度汽車がゴーッと駆けてくる、その運動の一瞬間、すなわち運動の性質の最も現れにくい刹那の光景を写真に撮って、これが汽車だ汽車だといって、あたかも汽車のすべてを一枚のうちに写しえたごとく吹聴すると一般的である。
なるほどどこから見ても、汽車に違いありますまい。
けれども汽車に見逃してはならない運動というものが、この写真のうちには出ていないのだから、実際の汽車とは到底比較のできないくらい懸絶しているといわなくてはなりますまい。
ご存知の琥珀というものがありましょう。
琥珀の中に時々蠅が入ったのがある。
透かして見ると蠅に違いありませんが、要するに動きの取れない蠅であります。
蠅でないとは言えぬでしょうが、生きた蠅とはいえますまい。
学者の下す定義には、この写真の汽車や琥珀の中の蠅に似て、鮮やかに見えるが死んでいると評しなければならないものがある。
それで注意を要するというのであります。
つまり変化をするものを捉えて、変化を許さぬがごとくピタリと定義を下す。
巡査というものは、白い服を着て、サーベルを下げているものだなどと天から極められた日には、巡査もやりきれないでしょう。
家へ帰って浴衣も着替えるわけにいかなくなる。
この暑いのに、剣ばかり下げていなければならないのは可哀そうだ。
騎兵とは馬に乗るものである。
これもご尤もに違いないが、いくら騎兵だって年が年中馬に乗り続けに乗っているわけにも行かないじゃありませんか。
少しは下りたいでさア。
こう例を挙げれば、際限がないから、いい加減に切り上げます。
実は開花の定義を下すお約束をしてしゃべっていたところが、いつの間にか開花はそっちのけになって、むつかしい定義論に迷い込んではなはだ恐縮です。
がこのくらい注意をした上で、さて開花とは何者だと纏(まと)めてみたら、幾分か学者の陥りやすい弊害を避け得られるし、またその便宜をも受けることが出来るだろうと思うのです。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社文庫刊
「現代日本の開花」講演本文 5/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 VOL,5/18
でいよいよ開花に出戻りをいたしますが、開花というものも、汽車とか蠅とか巡査とか騎兵とかいうようなものの如くに動いている。
それで開花の一瞬間を取って、カメラにピタリと入れて、そうしてこれが開花だと提げて歩くわけにはいきません。
私は昨日和歌の浦を見物しましたが、あすこを見た人のうちで、和歌の浦はたいへん浪の荒いところだという人がある。
かと思うと、非常に静かなところだという人もいる。
どっちが宜いのか分からない。
だんだん聞いてみると、一方は浪の非常に荒い時に行き、一方は非常に静かな時に行った違いから話がこう表裏して来たのである。
固より見た通りなんだから、両方とも嘘ではない。
が両方とも本当でもない。
これに似よりの定義は、あっても役に立たぬことはない。
が、役に立つと同時に害をなすことも明らかなんだから、開花の定義というのも、なるべくはそういう不都合を含んでいないようにいたしたいのが、私の希望であります。
が、そうすると、ボンヤリしてくる。
恨むらくは、ボンヤリしてくる。
けれどもボンヤリしても、外のものと区別ができればそれで宜いでしょう。
さっき牧君の紹介があったように夏目君の講演は、その文章のごとく、時とすると門口から玄関へ行くまでにうんざりすることがあるそうで、誠にお気の毒だが、なるほど遣ってみるとその通り、これまでようやく玄関まで着きましたから、思い切って本当の定義に移りましょう。
開化は、人間活力の発言の経路である。
と私はこういいたい。
私ばかりじゃない、あなた方だってそういうでしょう。
もっともそういった所で、別に書物に書いてあるわけでも何でもない、私がそう言いたいまでのことであるが、その代わり珍しくもなんともない。
がこれすこぶる漠然としている。
前口上を長々述べ立てた後で、このくらいの定義をご吹聴に及んだだけではあまり人を馬鹿にしているようですが、まあそこから定めて掛からないと曖昧になるから、実は已(や)むを得ないのです。
それで人間の活力というものが、いま申す通り時の流れを沿うて発現しつつ開花を形作って行くうちに私は根本的に性質の異なった二種類の活動を認めたい、否(いな)確かに認めるのであります。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社文庫刊
でいよいよ開花に出戻りをいたしますが、開花というものも、汽車とか蠅とか巡査とか騎兵とかいうようなものの如くに動いている。
それで開花の一瞬間を取って、カメラにピタリと入れて、そうしてこれが開花だと提げて歩くわけにはいきません。
私は昨日和歌の浦を見物しましたが、あすこを見た人のうちで、和歌の浦はたいへん浪の荒いところだという人がある。
かと思うと、非常に静かなところだという人もいる。
どっちが宜いのか分からない。
だんだん聞いてみると、一方は浪の非常に荒い時に行き、一方は非常に静かな時に行った違いから話がこう表裏して来たのである。
固より見た通りなんだから、両方とも嘘ではない。
が両方とも本当でもない。
これに似よりの定義は、あっても役に立たぬことはない。
が、役に立つと同時に害をなすことも明らかなんだから、開花の定義というのも、なるべくはそういう不都合を含んでいないようにいたしたいのが、私の希望であります。
が、そうすると、ボンヤリしてくる。
恨むらくは、ボンヤリしてくる。
けれどもボンヤリしても、外のものと区別ができればそれで宜いでしょう。
さっき牧君の紹介があったように夏目君の講演は、その文章のごとく、時とすると門口から玄関へ行くまでにうんざりすることがあるそうで、誠にお気の毒だが、なるほど遣ってみるとその通り、これまでようやく玄関まで着きましたから、思い切って本当の定義に移りましょう。
開化は、人間活力の発言の経路である。
と私はこういいたい。
私ばかりじゃない、あなた方だってそういうでしょう。
もっともそういった所で、別に書物に書いてあるわけでも何でもない、私がそう言いたいまでのことであるが、その代わり珍しくもなんともない。
がこれすこぶる漠然としている。
前口上を長々述べ立てた後で、このくらいの定義をご吹聴に及んだだけではあまり人を馬鹿にしているようですが、まあそこから定めて掛からないと曖昧になるから、実は已(や)むを得ないのです。
それで人間の活力というものが、いま申す通り時の流れを沿うて発現しつつ開花を形作って行くうちに私は根本的に性質の異なった二種類の活動を認めたい、否(いな)確かに認めるのであります。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社文庫刊
「現代日本の開花」講演本文 6/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 VOL,6/18
その二通りのうち、一つは積極的のもので、一つは消極的のものである。
何か月並のような講釈をしてすみませんが、人間活力の発現上、積極的という言葉を用いますと、勢力の消耗を意味することになる。
またもう一つのほうは、これとは反対に、勢力の消耗をできるだけ防ごうとする活動なり工夫なりだから、前のに対して消極的と申したのであります。
この二つの互いに食い違って反りの合わないような活動が、入り乱れたりコンガラカッたりして、開花というものが出来上がるのであります。
これでもまだ抽象的で、能(よ)くお分かりにならないかも知れませんが、もう少し進めば、私の意味は自ら明瞭になるだろうと信じます。
元来人間の命とか生とか称するものは、解釈次第でいろいろな意味にもなり、またむつかしくもなりますが、要するに、前(ぜん)申したごとく、活力の示現とか進行とか持続とか評するより外に致し方のないものである以上、この活力が外界の刺激に対してどう反応するかという点を細かに観察すれば、それで吾人(ごじん)人類の生活状態も、ほぼ了解ができるようなわけで、その生活状態の多人数の集合して過去から今日に及んだものがいわゆる開花に外ならないのは今更申し上げるまでもありますまい。
さて我々の活力が外界の刺激に反応する方法は、刺激の複雑である以上、固(もと)より多種多様千差万別に違いないが、要するに刺激の来るたびに、吾が活力の成るべく制限節約して、できるだけ使いまいとする工夫と、また自ら進んで適意の刺激を求め能(あた)うだけの活力を這裏(しゃり)に消耗して快を取る手段との二つに帰着してしまうよう私は考えているのであります。
で前のを便宜のため活力節約の行動はどんな場合に起こるかといえば、現代の吾々が普通用いる義務という言葉を冠して形容すべき
性質の刺激に対して起こるのであります。
従来の徳育法及び現今とても教育上では好んで義務を果たす敢為邁往(かんいまいおう)の気象を奨励するようですが、これは道徳上の話で、道徳上しかなくてはならぬ若しくはしかする方が社会の幸福だというまでで、人間活力の示現を観察して、その組織の経緯一つを司る大事実からいえば何(ど)うしても今私が申し上げたように、解釈するより外、仕方がないのであります。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社文庫刊行
その二通りのうち、一つは積極的のもので、一つは消極的のものである。
何か月並のような講釈をしてすみませんが、人間活力の発現上、積極的という言葉を用いますと、勢力の消耗を意味することになる。
またもう一つのほうは、これとは反対に、勢力の消耗をできるだけ防ごうとする活動なり工夫なりだから、前のに対して消極的と申したのであります。
この二つの互いに食い違って反りの合わないような活動が、入り乱れたりコンガラカッたりして、開花というものが出来上がるのであります。
これでもまだ抽象的で、能(よ)くお分かりにならないかも知れませんが、もう少し進めば、私の意味は自ら明瞭になるだろうと信じます。
元来人間の命とか生とか称するものは、解釈次第でいろいろな意味にもなり、またむつかしくもなりますが、要するに、前(ぜん)申したごとく、活力の示現とか進行とか持続とか評するより外に致し方のないものである以上、この活力が外界の刺激に対してどう反応するかという点を細かに観察すれば、それで吾人(ごじん)人類の生活状態も、ほぼ了解ができるようなわけで、その生活状態の多人数の集合して過去から今日に及んだものがいわゆる開花に外ならないのは今更申し上げるまでもありますまい。
さて我々の活力が外界の刺激に反応する方法は、刺激の複雑である以上、固(もと)より多種多様千差万別に違いないが、要するに刺激の来るたびに、吾が活力の成るべく制限節約して、できるだけ使いまいとする工夫と、また自ら進んで適意の刺激を求め能(あた)うだけの活力を這裏(しゃり)に消耗して快を取る手段との二つに帰着してしまうよう私は考えているのであります。
で前のを便宜のため活力節約の行動はどんな場合に起こるかといえば、現代の吾々が普通用いる義務という言葉を冠して形容すべき
性質の刺激に対して起こるのであります。
従来の徳育法及び現今とても教育上では好んで義務を果たす敢為邁往(かんいまいおう)の気象を奨励するようですが、これは道徳上の話で、道徳上しかなくてはならぬ若しくはしかする方が社会の幸福だというまでで、人間活力の示現を観察して、その組織の経緯一つを司る大事実からいえば何(ど)うしても今私が申し上げたように、解釈するより外、仕方がないのであります。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社文庫刊行
「現代日本の開花」講演本文 7/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 VOL,7/18
吾々もお互いに義務は尽くさなければならんものと始終思い、また義務を果たした後は、大変心持が良いのであるが、深くその内面に立ち入って内省してみると、願わくはこの義務の束縛をのがれて早く自由になりたい、人から強いられて止むを得ずする仕事は出来るだけ分量を圧搾して、手軽に済ましたいという根性が、常に胸の内に付き纏っている。
その根性が取りも直さず活力節約のくふうとなって、開花なるものの一大原動力を構成するのであります。
かく消極的に活力を節約しようとする奮闘に対して、一方ではまた、積極的に活力を任意随所に消耗しようという精神がまた開花の一半を組み立てている。
その発言の方法も、また世が進めば進むほど、複雑になるのは当然であるが、これをごく約(つづ)めてどんな方向に現れるかと説明すれば、まず普通の言葉で道楽という名の付く刺激に対し、おこるものだとしてしまえば、一番早わかりであります。
道楽といえば、だれも知っている。
釣魚をするとか玉を突くとか、碁を打つとか、または鉄砲を担いで猟に行くとか、いろいろのものがありましょう。
これらは説明するがものはない悉く自ら進んで強いられざるに、自分の活力を消耗して、嬉しがる方でございます。
なお進んではこの精神が文学にもなり、科学にもなり、または哲学にもなるので、ちょっと見ると、はなはだ難し気なものも、皆道楽の発現に過ぎないのであります。
この二用の精神、すなわち義務の刺激に対する反応としての、消極的な活力節約と、また道楽の刺激に対する反応としてもの、積極的な活力消耗とが互いに並び進んで、コンガラカッて変化して行って、この複雑極まりなき開花というものが出来るのだと私は考えています。
その結果は現に吾々が生息している社会の実況を目撃すればすぐわかります。
活力節約のほうからいえば、出来るだけ労働を少なくして、なるべくわずかな時間に多くの働きをしようしようと工夫する。その工夫が積もり積もって、汽車汽船はもちろん、電信、電話、自動車、大変なものになりますが、元を糺(ただ)せば面倒を避けたい横着審心の発達した便法に過ぎないでしょう。
この和歌山市から、和歌の浦までちょっと使いに行って来いと言われた時に、出来得るなら誰しも御免こうむりたい。
がどうしても行かなければならないとすれば、なるべく楽に行きたい。
そうして早く帰りたい。
出来るだけ体は使いたくない。
そこで人力車も出来なければならないわけになります。
その上に贅沢をいえば、自転車にするでしょう。なお我慢を言い募れば、これが電車にも変化し、自動車または飛行器にも化けなければならなくなるのは自然の数であります。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社学術文庫刊行
吾々もお互いに義務は尽くさなければならんものと始終思い、また義務を果たした後は、大変心持が良いのであるが、深くその内面に立ち入って内省してみると、願わくはこの義務の束縛をのがれて早く自由になりたい、人から強いられて止むを得ずする仕事は出来るだけ分量を圧搾して、手軽に済ましたいという根性が、常に胸の内に付き纏っている。
その根性が取りも直さず活力節約のくふうとなって、開花なるものの一大原動力を構成するのであります。
かく消極的に活力を節約しようとする奮闘に対して、一方ではまた、積極的に活力を任意随所に消耗しようという精神がまた開花の一半を組み立てている。
その発言の方法も、また世が進めば進むほど、複雑になるのは当然であるが、これをごく約(つづ)めてどんな方向に現れるかと説明すれば、まず普通の言葉で道楽という名の付く刺激に対し、おこるものだとしてしまえば、一番早わかりであります。
道楽といえば、だれも知っている。
釣魚をするとか玉を突くとか、碁を打つとか、または鉄砲を担いで猟に行くとか、いろいろのものがありましょう。
これらは説明するがものはない悉く自ら進んで強いられざるに、自分の活力を消耗して、嬉しがる方でございます。
なお進んではこの精神が文学にもなり、科学にもなり、または哲学にもなるので、ちょっと見ると、はなはだ難し気なものも、皆道楽の発現に過ぎないのであります。
この二用の精神、すなわち義務の刺激に対する反応としての、消極的な活力節約と、また道楽の刺激に対する反応としてもの、積極的な活力消耗とが互いに並び進んで、コンガラカッて変化して行って、この複雑極まりなき開花というものが出来るのだと私は考えています。
その結果は現に吾々が生息している社会の実況を目撃すればすぐわかります。
活力節約のほうからいえば、出来るだけ労働を少なくして、なるべくわずかな時間に多くの働きをしようしようと工夫する。その工夫が積もり積もって、汽車汽船はもちろん、電信、電話、自動車、大変なものになりますが、元を糺(ただ)せば面倒を避けたい横着審心の発達した便法に過ぎないでしょう。
この和歌山市から、和歌の浦までちょっと使いに行って来いと言われた時に、出来得るなら誰しも御免こうむりたい。
がどうしても行かなければならないとすれば、なるべく楽に行きたい。
そうして早く帰りたい。
出来るだけ体は使いたくない。
そこで人力車も出来なければならないわけになります。
その上に贅沢をいえば、自転車にするでしょう。なお我慢を言い募れば、これが電車にも変化し、自動車または飛行器にも化けなければならなくなるのは自然の数であります。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社学術文庫刊行
「現代日本の開花」講演本文 8/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 VOL,8/18
これに反して、電車や電話の設備があるにしても、是非今日は向こうまで歩いて行きたいという道楽心の増長する日も年に二度や三度は怒らないとは限りません。
好んで体を使って疲労を求める。
吾々が毎日やる散歩という贅沢も、要するにこの活力消耗の部類に属する積極的な命の取り扱い法の一部分なのであります。
がこの道楽気の増長した時に幸いに行って来いという命令が下れば丁度好いが、まあ大抵はそううまくはいかない。
いいつかった時は、多く歩きたくない時である。
だから歩かないで用を足す工夫をしなければならない。
となると、勢い、訪問が郵便になり、その電報が電話になる理屈です。
詰まるところは、人間存在上の必要上、何か仕事をしなければならないのを、なろうことならしないで用を足して、そうして満足に生きていたいという我儘な了見、と申しましょうかまたはそうそう身を粉(こ)にしてまで働いて生きているんじゃ割に合わない、馬鹿にするねえ、冗談じゃねえという発奮の結果が、怪物のように辣腕(らつわん)な器械力と豹変したのだとみれば、差し支えないでしょう。
この怪物の力で距離が縮まる、時間が縮まる、手数が省ける、すべて義務的の労力が最小低額に切り詰められた上に、また切り詰められて、どこまで押していくかわからないうちに、彼の反対の活力消耗と名付けておいた道楽根性のほうも、また自由我儘の出来る限りを尽くして、これまた瞬時の絶え間なく、天然自然と発達しつつ、とめどもなく前進するのである。
この道楽根性の発展も、道徳家に言わせると、怪しからんとか言いましょう。
がそれは徳義上の問題で、事実上の問題にはなりません。
事実の大局からいえば、活力を吾好む所に、消費するというこの工夫精神は二六時中休みなく働いて、休みっこなく発展しています。
元々社会があればこそ義務的の行動を余儀なくされる人間も、放り出しておけばどこまでも自我本位に立脚するのは、当然だから、自分の好いた刺激に精神なり身体なりを消費しようとするのは、致し方もない仕儀(しぎ=やり方)である。
もっとも好いた刺激に反応して、自由に活力を消耗すると言ったって、何も悪いことをするとは限らない。
道楽だって女を相手にするばかりが道楽じゃない。
好きな真似をするとは、開花の許す限りのあらゆる方面にわたっての話であります。
自分が画がかきたいと思えば、出来るだけ画ばかりかこうとする。
本が読みたければ、差し支えない以上、本ばかり読もうとする。
或いは学問が好きだといって、親の心も知らないで、書斎に入って青くなっている子息(むすこ)がある。
傍(はた=そば)から見れば何のことか分からない。
親父が無理算段の学資を工面して、卒業の上は月給でも取らせて、早く隠居でもしたいと思っているのに、子供のほうでは、活計(くらし)の方なんかまるで無頓着で、ただ天地の真理を発見したいなどと太平楽を並べて、机にもたれて苦り切っているのもある。
親は生計のための修行と考えているのに、子供は道楽のための学問とのみ合点している。
こういうようなわけで、道楽の活力は、いかなる道徳学者も杜絶(とぜつ)するわけにはいかない。
現にその発現は、世の中にどんな形になって、どんなに表れているかということは、この競争激甚(げきじん)の世に、道楽なんどとてんでその存在の権利を承認しないほど家業に励精(れいせい)な人でも、少し注意されれば、肯定しないわけに行かなくなるでしょう。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社学術文庫刊行
これに反して、電車や電話の設備があるにしても、是非今日は向こうまで歩いて行きたいという道楽心の増長する日も年に二度や三度は怒らないとは限りません。
好んで体を使って疲労を求める。
吾々が毎日やる散歩という贅沢も、要するにこの活力消耗の部類に属する積極的な命の取り扱い法の一部分なのであります。
がこの道楽気の増長した時に幸いに行って来いという命令が下れば丁度好いが、まあ大抵はそううまくはいかない。
いいつかった時は、多く歩きたくない時である。
だから歩かないで用を足す工夫をしなければならない。
となると、勢い、訪問が郵便になり、その電報が電話になる理屈です。
詰まるところは、人間存在上の必要上、何か仕事をしなければならないのを、なろうことならしないで用を足して、そうして満足に生きていたいという我儘な了見、と申しましょうかまたはそうそう身を粉(こ)にしてまで働いて生きているんじゃ割に合わない、馬鹿にするねえ、冗談じゃねえという発奮の結果が、怪物のように辣腕(らつわん)な器械力と豹変したのだとみれば、差し支えないでしょう。
この怪物の力で距離が縮まる、時間が縮まる、手数が省ける、すべて義務的の労力が最小低額に切り詰められた上に、また切り詰められて、どこまで押していくかわからないうちに、彼の反対の活力消耗と名付けておいた道楽根性のほうも、また自由我儘の出来る限りを尽くして、これまた瞬時の絶え間なく、天然自然と発達しつつ、とめどもなく前進するのである。
この道楽根性の発展も、道徳家に言わせると、怪しからんとか言いましょう。
がそれは徳義上の問題で、事実上の問題にはなりません。
事実の大局からいえば、活力を吾好む所に、消費するというこの工夫精神は二六時中休みなく働いて、休みっこなく発展しています。
元々社会があればこそ義務的の行動を余儀なくされる人間も、放り出しておけばどこまでも自我本位に立脚するのは、当然だから、自分の好いた刺激に精神なり身体なりを消費しようとするのは、致し方もない仕儀(しぎ=やり方)である。
もっとも好いた刺激に反応して、自由に活力を消耗すると言ったって、何も悪いことをするとは限らない。
道楽だって女を相手にするばかりが道楽じゃない。
好きな真似をするとは、開花の許す限りのあらゆる方面にわたっての話であります。
自分が画がかきたいと思えば、出来るだけ画ばかりかこうとする。
本が読みたければ、差し支えない以上、本ばかり読もうとする。
或いは学問が好きだといって、親の心も知らないで、書斎に入って青くなっている子息(むすこ)がある。
傍(はた=そば)から見れば何のことか分からない。
親父が無理算段の学資を工面して、卒業の上は月給でも取らせて、早く隠居でもしたいと思っているのに、子供のほうでは、活計(くらし)の方なんかまるで無頓着で、ただ天地の真理を発見したいなどと太平楽を並べて、机にもたれて苦り切っているのもある。
親は生計のための修行と考えているのに、子供は道楽のための学問とのみ合点している。
こういうようなわけで、道楽の活力は、いかなる道徳学者も杜絶(とぜつ)するわけにはいかない。
現にその発現は、世の中にどんな形になって、どんなに表れているかということは、この競争激甚(げきじん)の世に、道楽なんどとてんでその存在の権利を承認しないほど家業に励精(れいせい)な人でも、少し注意されれば、肯定しないわけに行かなくなるでしょう。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社学術文庫刊行
「現代日本の開花」講演本文 9/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 VOL,9/18
私は昨晩和歌の浦に泊まりましたが、和歌の浦に行ってみると、さがり松だの権現様だの紀三井寺だのいろいろのものがありますが、その中に東洋第一海抜二百尺と書いたエレベーターが宿の裏から小高い石山の頂へ絶えず見物を上げたり下げたりしているのを見ました。
実は私も動物園の熊のように、あの鉄の格子の檻の中に入って、山の上へ上げられた一人であります。
があれは生活上別段必要のある場所にあるわけでもなければ、またそれほど大切な器械でもない、まあ物好きである。
ただ上がったり下ったりするだけである。
疑いもなく道楽審の発現で、好奇心兼広告欲も手伝っているかもしれないが、まあ活計向とは関係の少ないものです。
これは一例ですが、開花が進むにつれて、こういう贅沢なものの数が殖えて来るのは、だれでも認識しないわけにはいかないでしょう。
如之(しかのみならず)この贅沢が日に増し細かくなる。
大きなものの中に、輪がいくつもできて、漏斗(じょうご)みたようにだんだん深くなる。
と同時に、今まで気の付かなかった方面へ、だんだん発展して範囲が年々広くなる。
要するにただいま申し上げた二つの入り乱れた経路、すなわち出来るだけ労力を節約したいという願望から出てくる種々の発明とか、器械力とかいう方面と、出来るだけ気ままに精力を費やしたいという娯楽の方面、これが経となり緯となり千変万化錯綜して、現今のように混乱した開花という不可思議な現象が出来るのであります。
そこでそういうものを開花とすると、ここに一種妙なパラドックスとでもいいましょうか、ちょっと聞くと可笑(おか)しいが、実は誰しも認めねばならない現象が起こります。
元来、なぜ人間が開花の流れに沿うて、以上二種の活力を発現しつつ、今日に及んだかといえば、生まれながらそういう傾向を持っていると答えるより外に仕方がない。
これを逆に申せば、吾人(ごじん)の今日あるは全くこの本来の傾向あるがためにほかならんのであります。
なお進んで言うと、元のままで懐手をしていては、生存上どうしてもやり切れぬから、それからそれへと順々に押され押されてかく発展を遂げたと言わなければならないのです。
してみれば、古来何千年の労力と、歳月を挙げて、ようやくの事現代の位置まで進んできたのであるからして、いやしくもこの二種類の活力が、上代から今に至る長い時間に工夫し得た結果として、昔よりも生活が楽になっていなければならないはずであります。
夏目漱石「現代日本の開花」
明治44年、和歌山での講演記録文
講談社学術文庫刊行
私は昨晩和歌の浦に泊まりましたが、和歌の浦に行ってみると、さがり松だの権現様だの紀三井寺だのいろいろのものがありますが、その中に東洋第一海抜二百尺と書いたエレベーターが宿の裏から小高い石山の頂へ絶えず見物を上げたり下げたりしているのを見ました。
実は私も動物園の熊のように、あの鉄の格子の檻の中に入って、山の上へ上げられた一人であります。
があれは生活上別段必要のある場所にあるわけでもなければ、またそれほど大切な器械でもない、まあ物好きである。
ただ上がったり下ったりするだけである。
疑いもなく道楽審の発現で、好奇心兼広告欲も手伝っているかもしれないが、まあ活計向とは関係の少ないものです。
これは一例ですが、開花が進むにつれて、こういう贅沢なものの数が殖えて来るのは、だれでも認識しないわけにはいかないでしょう。
如之(しかのみならず)この贅沢が日に増し細かくなる。
大きなものの中に、輪がいくつもできて、漏斗(じょうご)みたようにだんだん深くなる。
と同時に、今まで気の付かなかった方面へ、だんだん発展して範囲が年々広くなる。
要するにただいま申し上げた二つの入り乱れた経路、すなわち出来るだけ労力を節約したいという願望から出てくる種々の発明とか、器械力とかいう方面と、出来るだけ気ままに精力を費やしたいという娯楽の方面、これが経となり緯となり千変万化錯綜して、現今のように混乱した開花という不可思議な現象が出来るのであります。
そこでそういうものを開花とすると、ここに一種妙なパラドックスとでもいいましょうか、ちょっと聞くと可笑(おか)しいが、実は誰しも認めねばならない現象が起こります。
元来、なぜ人間が開花の流れに沿うて、以上二種の活力を発現しつつ、今日に及んだかといえば、生まれながらそういう傾向を持っていると答えるより外に仕方がない。
これを逆に申せば、吾人(ごじん)の今日あるは全くこの本来の傾向あるがためにほかならんのであります。
なお進んで言うと、元のままで懐手をしていては、生存上どうしてもやり切れぬから、それからそれへと順々に押され押されてかく発展を遂げたと言わなければならないのです。
してみれば、古来何千年の労力と、歳月を挙げて、ようやくの事現代の位置まで進んできたのであるからして、いやしくもこの二種類の活力が、上代から今に至る長い時間に工夫し得た結果として、昔よりも生活が楽になっていなければならないはずであります。
夏目漱石「現代日本の開花」
明治44年、和歌山での講演記録文
講談社学術文庫刊行
「現代日本の開花」講演本文 10/18
夏目漱石「現代日本の開花」明治44,8月和歌山講演 VOL,10/18
けれども実際は同(ど)うか?打ち明けて申せばお互いの生活は甚だ苦しい。
昔の人に対して一歩も譲らざる苦痛のもとに生活しているのだという自覚がお互いの中にある。
否開花が進めば進むほど競争がますます激しくなって、生活はいよいよ困難になるような気がする。
なるほど以上二種の活力の猛烈な奮闘で開花は勝ち得たに相違ない。
しかしこの開化は一般に生活の程度が高くなったという意味で、生存の苦痛が比較的和らげられたという意味ではありません。
ちょうど小学校の生徒が学問の競争で苦しいのと、大学の学生が学問の競争で苦しいのと、その程度は違うが、比例に至っては同じである如く、昔の人間と今の人間が、どのくらい幸福の程度において違っているかといえば、あるいは不幸の程度において違っているかといえば、活力消耗、活力節約の両工夫において大差はあるかもしれないが、生存競争から生ずる不安や努力に至っては、決して昔より楽になっていない。
否(いな)昔よりかえって苦しくなっているかも知れない。
昔は死ぬか生きるかのために争ったものである。
それだけの努力を敢えてしなければ死んでしまう。
止むを得ないからやる。
加之(しかのみならず)道楽の念はとにかく道楽の途はまだ開けていなかったから、こうしたい、ああしたいという方角も程度も至って微弱なもので、たまに足を押したり手を休めたりして、満足していたくらいのものだろうと思われる。
今日は死ぬか生きるかの問題は大分超越している。
それが変化してむしろ生きるか生きるかという競争になってしまったのであります。
生きるか生きるかというのは、可笑(おか)しゅうございますが、Aの状態で生きるか、Bの状態で生きるかの問題に腐心しなければならないという意味であります。
活力節減の方で例を引いてお話をしますと、人力車を挽(ひ)いて渡世にするか、または自動車のハンドルを握って暮らすかの競争になったのであります。
どっちを家業にしたって命に別状は無いに決まっているが、どっちに行っても労力は同じだとはいわれません。
人力車を挽(ひ)く方が汗がよほど多分にでるでしょう。
自動車の御者になってお客を乗せれば、(もっとも自動車を有(も)つくらいならお客を乗せる必要もないが、)短い時間で長いところが走れる。
糞力はちっとも出さないで済む。
活力節約の結果、楽に仕事が出来る。されば自動車の無い昔はいざ知らず、いやしくも発明される以上、人力車は自動車にまけなければならない。
負ければ追いつかなければならない。
というわけで、少しでも労力を節減し得て、優勢なるものが地平線上に現れて、ここに一つの波瀾を誘うと、ちょうど一種の低気圧と同じ現象が、開花の中に起こって、各部の比例がとれ、平均が回復されるまでは、動揺して已(や)められないのが人間の本来であります。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社学術文庫刊
けれども実際は同(ど)うか?打ち明けて申せばお互いの生活は甚だ苦しい。
昔の人に対して一歩も譲らざる苦痛のもとに生活しているのだという自覚がお互いの中にある。
否開花が進めば進むほど競争がますます激しくなって、生活はいよいよ困難になるような気がする。
なるほど以上二種の活力の猛烈な奮闘で開花は勝ち得たに相違ない。
しかしこの開化は一般に生活の程度が高くなったという意味で、生存の苦痛が比較的和らげられたという意味ではありません。
ちょうど小学校の生徒が学問の競争で苦しいのと、大学の学生が学問の競争で苦しいのと、その程度は違うが、比例に至っては同じである如く、昔の人間と今の人間が、どのくらい幸福の程度において違っているかといえば、あるいは不幸の程度において違っているかといえば、活力消耗、活力節約の両工夫において大差はあるかもしれないが、生存競争から生ずる不安や努力に至っては、決して昔より楽になっていない。
否(いな)昔よりかえって苦しくなっているかも知れない。
昔は死ぬか生きるかのために争ったものである。
それだけの努力を敢えてしなければ死んでしまう。
止むを得ないからやる。
加之(しかのみならず)道楽の念はとにかく道楽の途はまだ開けていなかったから、こうしたい、ああしたいという方角も程度も至って微弱なもので、たまに足を押したり手を休めたりして、満足していたくらいのものだろうと思われる。
今日は死ぬか生きるかの問題は大分超越している。
それが変化してむしろ生きるか生きるかという競争になってしまったのであります。
生きるか生きるかというのは、可笑(おか)しゅうございますが、Aの状態で生きるか、Bの状態で生きるかの問題に腐心しなければならないという意味であります。
活力節減の方で例を引いてお話をしますと、人力車を挽(ひ)いて渡世にするか、または自動車のハンドルを握って暮らすかの競争になったのであります。
どっちを家業にしたって命に別状は無いに決まっているが、どっちに行っても労力は同じだとはいわれません。
人力車を挽(ひ)く方が汗がよほど多分にでるでしょう。
自動車の御者になってお客を乗せれば、(もっとも自動車を有(も)つくらいならお客を乗せる必要もないが、)短い時間で長いところが走れる。
糞力はちっとも出さないで済む。
活力節約の結果、楽に仕事が出来る。されば自動車の無い昔はいざ知らず、いやしくも発明される以上、人力車は自動車にまけなければならない。
負ければ追いつかなければならない。
というわけで、少しでも労力を節減し得て、優勢なるものが地平線上に現れて、ここに一つの波瀾を誘うと、ちょうど一種の低気圧と同じ現象が、開花の中に起こって、各部の比例がとれ、平均が回復されるまでは、動揺して已(や)められないのが人間の本来であります。
引用書籍
夏目漱石「現代日本の開花」
講談社学術文庫刊