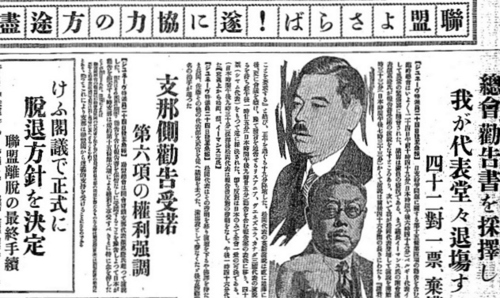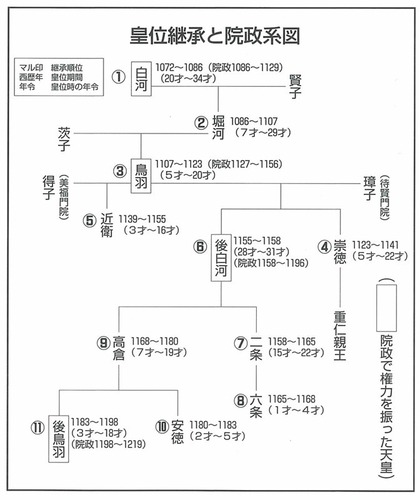2020年01月03日
新時代の幕開け 鳥羽伏見の戦い
明けまして おめでとうございます
令和二年(2020年)最初の投稿です。
皆さんお正月はいかがお過ごしですか?
人それぞれお正月の楽しみ方はあると思うのですが、僕は毎年、初日の出を見に行くのが正月の楽しみの一つです。
しかし、残念ながら今年は見れなかったのです!(泣)
毎年、神奈川の西湘あたりの海岸に行って初日の出を拝んでいるのですが、今年は水平線のかなり上の方まで厚い雲に覆われていて・・・。
海に初日の出を見に行くと、晴れそうでも水平線上にだけ雲が垂れ込めているのはよくあることなのですが、日の出予定時刻から20分以上待っても太陽は現れず、しばらく雲も動きそうになかったので諦めました。
それなのに、昼間になるとやけに天気良かったのが恨めしかったですね。
きれいな初日の出の写真をここに載せたかったので残念です!
さて、今日1月3日は鳥羽伏見の戦いが行われた日です。(慶応四年 1868年)※改元前
鳥羽伏見の戦いとは、前年10月に大政奉還した徳川方の旧幕府軍と、薩摩・長州藩を中心とした新政府軍が最初に激突した戦いです。
旧幕府軍と新政府軍の争いは鳥羽伏見の戦いを皮切りに翌年5月まで約1年5ヶ月に渡って行われ、これらの戦いを総称して戊辰戦争(ぼしんせんそう)といいます。
大政奉還により政権を返上したはずの徳川が、なぜ新政府と戦うことになったのでしょうか?
というわけで、今回は戊辰戦争の火蓋を切った鳥羽伏見の戦いについて語りたいと思います。
薩長の逆襲
慶応三年(1867年)10月14日に行われた大政奉還(10月14日付ブログ参照)により、討幕派の薩摩・長州藩の機先を制した最後の将軍・徳川慶喜は、政権返上後も徳川家の権力維持を目論んでいました。
しかし、徳川家の権力維持を認めず、武力行使による巻き返しを画策していた薩長ら討幕派は、慶応三年(1867年)12月9日、公家の岩倉具視・薩摩藩の大久保利通らを中心に朝廷を巻き込んだクーデターを決行し、天皇より王政復古の大号令が発せられました。
これにより、それまでの征夷大将軍や摂政・関白を廃止、新たに総裁・議定・参与の三職を制定し、朝廷と薩長を中心とした天皇親政を確立するため新政府が発足しました。
さらに、その夜に行なわれた三職による小御所会議では、天皇の名において慶喜に辞官納地(官位の辞職と幕府領を朝廷へ返還すること)を命じ、徳川家の権力を剥奪しました。
ほとんど一方的に官位や幕府領を奪われてしまった慶喜は、この決定にとうてい納得できるはずはなく、急遽大坂城に入り、幕府の軍勢を集め臨戦態勢を整えました。
そして各国の公使に対し慶喜は「諸外国との交渉権はあくまでも幕府にあり、薩長が勝手に決めた王政復古は無効である」と通達します。
この状況に全国の諸大名は幕府側と新政府側のどちらに従うべきか、態度を決めかねていました。
無料体験授業
決起する旧幕府軍
このどっちつかずの状況を打開し、武力により一気に決着をつけたい薩摩の西郷隆盛(9月24日付ブログ参照)は、江戸で薩摩藩が暴動を起こすことで幕府側を挑発し、決起を誘発するという作戦に出ました。
隆盛の作戦は見事に当たり、江戸における薩摩藩の暴挙を知った幕府側に「薩長許すまじ!」の機運が高まり、ついに幕府軍は立ち上がります。
慶応四年(1868年)1月3日、京都南部の鳥羽・伏見において、会津・桑名を主力とする旧幕府軍1万5千と薩摩藩を主力とする新政府軍5千が激突しました。
数の上では勝る旧幕府軍でしたが、新政府軍の装備する近代兵器に圧倒され敗れてしまいます。
翌日、緒戦の勝利で勢いづいた新政府軍は嘉彰親王(よしあきしんのう)を征討大将軍に奉り、朝廷の「錦の御旗」を掲げることで自分たちを「官軍」と称し、旧幕府軍を「朝敵」としました。

錦の御旗
錦の御旗とは、天皇の命令を受けた正式な朝廷軍であることを示すものです。
新政府軍が錦の御旗を掲げたことで、いよいよ朝廷が旧幕府軍討伐の旗色を明確にしたため、態度を決めかねていた諸藩は旧幕府軍から続々と離反していきました。
人気コミック絶賛発売中!【DMM.com 電子書籍】
敵前逃亡した慶喜
緒戦で敗れた旧幕府軍ですが、1月6日に慶喜は大坂城内で「たとえ千騎が一騎になっても退却するな。もし、ここ関西で敗れても関東がある。関東で敗れても水戸がある。決して戦うことをやめてはならない!」と、幕兵たちに檄を飛ばし、徹底抗戦を促しました。
ところがその夜、思いもよらない事態が起こります。
徹底抗戦を宣言していた慶喜が、会津藩主・松平容保らわずかな側近を連れて大坂城を脱出、大阪湾に停泊する幕府の旗艦・開陽丸にに乗り込んで海路江戸へ逃げ帰ってしまったのです。
しかもこの時、慶喜は家康以来の徳川家の象徴である金扇の旗印を大坂城に置き忘れるという失態をも犯しています。
この慶喜の体たらくに幕兵たちは呆れ返り、完全に戦意を喪失してしまいました。
旧幕府軍の総大将でありながら、なぜ慶喜は“敵前逃亡”してしまったのでしょうか?
鳥羽伏見の戦いはあくまで局地戦であり、ここで敗れても慶喜が改めて全国の諸大名に号令すれば、数に勝る幕府軍に勝ち目もあったと思われますが、慶喜はそうはしませんでした。
また、敵前逃亡の理由についても生涯語ることはありませんでした。
こうした理由には、慶喜の生い立ちに起因している可能性があります。
水戸出身の慶喜は、幼少の頃から水戸学の中核をなす「尊王論」(天皇を絶対的権威として尊崇する思想)の教えを受けてきました。
その慶喜にとって、徳川家が「朝敵」の汚名を着せられることだけは避けたかったのではないでしょうか?
つまり、たとえ敵であろうと「錦の御旗」を掲げた朝廷軍に弓を引くことはできなかったと考えられるのです。
まとめ
- 大政奉還後も武力討幕にこだわった薩長は王政復古の大号令を起こし、徳川家の権力を剥奪した
- 巻き返しを図る旧幕府軍は鳥羽・伏見で新政府軍と戦うが敗れた
- 徳川慶喜が敵前逃亡した理由は、徳川家が朝敵となることを避けたかったからと考えられる
本日からの始動となりましたが、今年もよろしくお願い致します。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9533309
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック