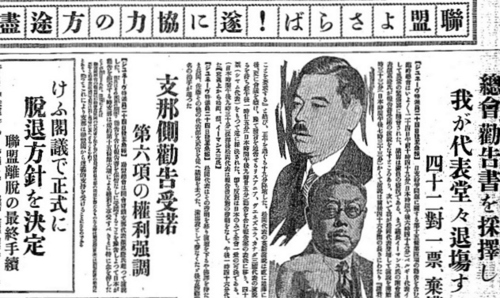2019年09月10日
龍虎相打つ宿命の対決
川中島合戦のクライマックス
昨日関東に大きな爪跡を残した台風15号は、まさに”風雲急を告げる”台風でしたね。
何しろ、先週前半まで発生もしていなかった台風が、日曜の夜中に関東を直撃するとは思いませんでした。
しかも、強い勢力を保ったまま上陸したので各地で記録的な強風が吹き荒れ、昨日の朝は関東各地の鉄道が計画運休していたので、多くの駅周辺は大混雑でした。
最近よく口にしている言葉ですが、やはり地球温暖化の影響で日本列島周辺の海水温が高いので、台風が日本に接近しても衰えず強い勢力を保ったまま上陸してしまうんでしょうね。
そう考えると近い将来、日本にどれだけ強大な台風が直撃してしまうのか恐ろしい限りです。
さて、今日9月10日は、越後の龍・上杉謙信(3月13日付ブログ参照)と、甲斐の虎・武田信玄(4月10日付ブログ参照)が激闘を繰り広げた川中島の戦いがあった日です。(永禄四年 1561年)

川中島の戦いは天文二十二年(1553年)から永禄七年(1564年)までの間に合計5度にわたって行われましたが、最も激戦だったのがこの永禄四年に行われた四度目の合戦でした。
今回はこの永禄四年の川中島の戦いについて語りたいと思います。
雌雄を決するべく両雄が出陣!
そもそも川中島の戦いが行われることになった理由は、信濃(長野県)の守護大名であった小笠原長時と、北信濃を支配していた村上義清の二人が、甲斐(山梨県)の武田信玄の信濃侵攻に抗えず、越後(新潟県)の上杉謙信の元に逃げ込んで助けを求めたことがきっかけでした。
謙信は自分を頼ってきた二人の旧領地を取り返すことと、信玄を自らの領地である越後にまで攻め込んで来させないための楔(くさび)を打つため、対する信玄はせっかく勝ち取った信濃の地を謙信に奪われないためで、両雄の思惑が交錯する場所が北信濃の川中島だったというわけです。
ちなみに、川中島という地名は、犀川(さいがわ)と千曲川の二つの大きな川に挟まれた島のような土地だったからといわれています。
まず、先に動いたのは謙信でした。
8月14日、謙信は1万8千の兵を率いて居城の春日山を出陣します。
同15日に信濃の善光寺に到着した謙信は兵5千をここに残し、同16日に1万3千の軍勢で千曲川を渡り、川中島の南に位置する妻女山に布陣します。
川中島から近い海津城(武田方の城)の城主・高坂昌信は、謙信の出陣を狼煙(のろし)で甲府の信玄に知らせます。
この知らせを受けた信玄も甲府の躑躅ヶ崎を出陣し、同24日に2万の軍勢を率いて川中島の西方にある茶臼山に布陣します。
ここで、両軍はそれぞれ妻女山と茶臼山から千曲川を挟んで対峙する形となりました。
【見放題chライト】7000本以上の動画を無料お試し
名軍師の奇策 ”キツツキの戦法”
対峙から5日後の同29日、信玄は突如全軍を海津城に移動させます。
謙信と対峙したものの相手がなかなか動かないので、作戦を立て直し兵を休ませるために城に移ったものと考えられます。
しかし、それでも謙信は妻女山から一向に動く気配がありません。
そこで、信玄の軍師・山本勘助(10月30日付ブログ参照)により提案されたのがキツツキの戦法です。
これは、キツツキが木の穴に入っている虫を獲る時、穴の裏側をくちばしでつついて驚いた虫が表の穴から出てきたところを捕食する習性を兵法に応用したものです。
つまりこの場合、武田軍を二手に分け、妻女山(=木)にいる上杉軍(=虫)を、別働隊が後方から奇襲(=くちばしでつつく)して追い出し、山から下りてきたところを正面から本隊が迎え撃ち、別働隊とともに挟み撃ちにするという作戦です。
信玄はこの作戦を採用し、2万の軍勢を本隊8千と別働隊1万2千に分け、9月9日深夜にまず別働隊が行動を開始します。
おいしさと、食べる喜びを、食のそよ風にのせて【食のそよ風】
激闘! 八幡原の戦い
ここまでの上杉軍と武田軍の動きを見てみましょう。

妻女山から動かない上杉軍を討つ作戦としては見事ですが、山本勘助が名軍師なら、上杉謙信は戦の天才と謳われた名将です。
この戦いにおいては謙信の方が一枚上手でした。
妻女山から海津城を見下ろしていた謙信は、海津城からさかんに煙が立ち上るようすを見て、今夜武田軍が奇襲を仕掛けてくることをいち早く察知し、武田軍の別働隊が襲ってくる前に全軍で山を下りてしまったのです。
信玄率いる本隊8千は同10日未明に海津城を出て、川中島の八幡原に布陣し、別働隊が上杉軍を追い立ててくるのを待ち構えていました。
しかし、深夜だったことに加え、この時期特有の濃霧が発生していたので周囲は全く見えませんでした。
夜が明けると同時に濃霧も消え、視界が開けた信玄の眼前の現れたのは1万3千の上杉軍でした。
講談『川中島の戦い』の名セリフ「鞭声粛々(べんせいしゅくしゅく)夜河を渡る」の如く、上杉軍は武田軍に気付かれぬよう妻女山を下り、静かに夜の千曲川を渡っていたのです。
奇襲を仕掛けるつもりでいた信玄が逆に仕掛けられてしまったのですから、信玄はさぞ度胆を抜かれたことでしょう。
先手を取った上杉軍は車懸りの陣(くるまがかりのじん)で武田軍を攻撃します。
車懸りの陣とは、水車が回転するような動きで各部隊が入れ替わりながら攻め立てる戦法で、台風の外側の強風が何度も当たってくるイメージです。
対する武田軍は鶴翼の陣(かくよくのじん)で応戦します。
鶴翼の陣とは、文字通り鶴が翼を広げたような形に部隊を左右に分け敵を包み込む陣形で、攻めにも守りにも強い陣形といわれています。
最初に両軍が激突した時点では、上杉軍1万3千に対し武田軍8千(本隊のみ)だったので上杉軍が優勢で武田軍は苦戦を強いられます。
しかし、妻女山を奇襲しようとしていた武田軍の別働隊1万2千がようやく八幡原に追いつくと形勢は逆転、劣勢になった上杉軍は犀川を渡り善光寺方面へ撤退して戦いは終わりました。
まとめ
- 上杉謙信は自分を頼ってきた武将の領地を取り返すため、武田信玄は勝ち取った領地を奪われないために川中島で戦った
- 妻女山から動かない上杉軍を討つ作戦として山本勘助はキツツキの戦法を提案した
- 八幡原の戦いでは上杉軍は車懸りの陣で攻撃し、武田軍は鶴翼の陣で応戦した
次回は、川中島の戦いに残る「謎」について語っていきますので、引き続きご期待下さい。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9179725
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック