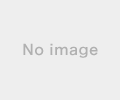2004年以来となる新紙幣の登場が刻々と迫ってきた。
偽札対策の為には新たな製造技術の導入が欠かせないが、物価高や人手不足と言った逆風に晒される企業にとっては追加の出費がずしりと嵩む。
三重苦の様相に、悲鳴が漏れる。
第一生命経済研究所の永浜利広首席エコノミストは、小規模な店舗では高価な機械の更新を諦め、導入費用の少ないキャッシュレス決済に切り替える動きを予想。
「今回を切っ掛けに普及が進む可能性がある」として、新紙幣登場の「副産物」を予言した。
愛媛新聞 記事から
正に副産物だ。
光ファイバーに掛かる歪から地震を観測する技術を使えるらしい。
将来的には海底光ケーブルによる観測を津波の緊急速報などに活用できる可能性があるらしい。
2024年06月07日
規正法 一層の充実期待
今国会中の成立は確実だ。
修正後の改正案は、猶足らざる所があるにしても、先ずは成立させてから、更なる充実を期する水準には達したと言える。
裏金事件の様な問題の再発を防ぐには先ず、パーティー券購入代金の支払いは開催者の預貯金口座への振り込みに限り、収入記録と会計帳簿を突き合わせる事が必要だ。
この点は自民党の当初案から取り入れられていた。
パーティー券購入者の公開基準額引き下げも、政治資金収支報告所の記載内容をチェックし易くなり、透明性を高める効果がある。
議員に聞かれなかったから会計責任者は報告しなかったと言うケースに関しては、再発防止策が講じられた事になる。
だが、要求水準の高い野党案があったから、公明党は自民党に安易な妥協をせず、譲歩を引き出せたとも考えられる。
本当にパーティーや企業・団体献金を禁止したいのなら、自ら政権を取って実行すればいい。
候補者本位の政治から政党本位の政治への移行を謳いながら、肝心の政党自体がガバナンスの確立を怠ってきた事に病根がある。
東京大教授 谷口 将紀 1970年神奈川県生まれ。 東京大法学部卒。 博士(法学)。
専門は現代日本政治論。
愛媛新聞 視標から
自民党推薦の教授だから自民党に甘い。
専門家が皮肉る様に、自民党にとって痛くも痒くもない案が通ったと思う。
修正後の改正案は、猶足らざる所があるにしても、先ずは成立させてから、更なる充実を期する水準には達したと言える。
裏金事件の様な問題の再発を防ぐには先ず、パーティー券購入代金の支払いは開催者の預貯金口座への振り込みに限り、収入記録と会計帳簿を突き合わせる事が必要だ。
この点は自民党の当初案から取り入れられていた。
パーティー券購入者の公開基準額引き下げも、政治資金収支報告所の記載内容をチェックし易くなり、透明性を高める効果がある。
議員に聞かれなかったから会計責任者は報告しなかったと言うケースに関しては、再発防止策が講じられた事になる。
だが、要求水準の高い野党案があったから、公明党は自民党に安易な妥協をせず、譲歩を引き出せたとも考えられる。
本当にパーティーや企業・団体献金を禁止したいのなら、自ら政権を取って実行すればいい。
候補者本位の政治から政党本位の政治への移行を謳いながら、肝心の政党自体がガバナンスの確立を怠ってきた事に病根がある。
東京大教授 谷口 将紀 1970年神奈川県生まれ。 東京大法学部卒。 博士(法学)。
専門は現代日本政治論。
愛媛新聞 視標から
自民党推薦の教授だから自民党に甘い。
専門家が皮肉る様に、自民党にとって痛くも痒くもない案が通ったと思う。
政活費維持 自民固執
専門家は、選挙費用に充てられる政策活動費の廃止は、自民党にとって死活問題になると指摘。
「裏金事件を切っ掛けに改正議論が始まったのに、多くの課題が先送りされ、自民党にとって痛くも痒くもない案が通った」と皮肉った。
政策活動費は政治団体ではなく政治家個人に支出される為、使途を明らかにする必要がない。
野党などはこの点を強く問題視してきた。
政策活動費は不記載の言い訳にもなった。
政策活動費は、領収書を受け取れない選挙費用や飲食代などに使われてきたとされている。
或る元自民党議員は「例えば派閥に入って貰う為に新人候補に渡すと言う使われ方はある」と明かす。
高崎経済大の増田正教授(’政治学)も、政策活動費は選挙対策に使われる事が多いと見る。
透明化は各議員の力の源泉を失わせるリスクを孕む為、自民党は最後まで制度温存に拘ったと指摘する。
「10年後に不正が発覚しても(規制法違反の)時効が成立している可能性が高い」との指摘が上がった。
増田氏も「10年後では適切に使われたのか如何か検証のしようがない」と批判する。
その上でこう力を込めた。
「この改正案を国民が『問題あり』と考えるか如何かだ」
愛媛新聞 記事から
問題ありと考えるか如何からしい。
なしと考える人がいるとすれば、自民党支持か、状況判断の甘い人だと思う。
これこそ問題ありだ。
「裏金事件を切っ掛けに改正議論が始まったのに、多くの課題が先送りされ、自民党にとって痛くも痒くもない案が通った」と皮肉った。
政策活動費は政治団体ではなく政治家個人に支出される為、使途を明らかにする必要がない。
野党などはこの点を強く問題視してきた。
政策活動費は不記載の言い訳にもなった。
政策活動費は、領収書を受け取れない選挙費用や飲食代などに使われてきたとされている。
或る元自民党議員は「例えば派閥に入って貰う為に新人候補に渡すと言う使われ方はある」と明かす。
高崎経済大の増田正教授(’政治学)も、政策活動費は選挙対策に使われる事が多いと見る。
透明化は各議員の力の源泉を失わせるリスクを孕む為、自民党は最後まで制度温存に拘ったと指摘する。
「10年後に不正が発覚しても(規制法違反の)時効が成立している可能性が高い」との指摘が上がった。
増田氏も「10年後では適切に使われたのか如何か検証のしようがない」と批判する。
その上でこう力を込めた。
「この改正案を国民が『問題あり』と考えるか如何かだ」
愛媛新聞 記事から
問題ありと考えるか如何からしい。
なしと考える人がいるとすれば、自民党支持か、状況判断の甘い人だと思う。
これこそ問題ありだ。
2,3,2 訴訟手続
(1) 当事者
民事訴訟では、原告と被告が裁判所の面前で口頭弁論を行い、裁判所が判決を下す事によって紛争が解決される。
この時の原告と被告は、当事者と呼ばれる。
当事者は、法律について素人である事も多く、その様な場合には訴訟代理人が当事者の訴訟追行を助ける事になる(原則として、訴訟代理人は弁護士のみがなる事ができる)。
(2) 裁判所
裁判所には、最高裁判所の他下級裁判所として4種類が存在している(高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所)。
地方裁判所と一部の高等裁判所には支部が設置されている。
我が国では審級制度が採用され、民事訴訟における第一審は、簡易裁判所と地方裁判所が扱う。
訴額が90万円以下であれば、原則として簡易裁判所が第一審を受け持つ事になる。
実際に裁判を行うのは、裁判機関としての裁判所である。
裁判は 、合議制で行われる場合と単独で行われる場合がある。
簡易裁判所は常に単独性であるが、地方裁判所では、合議制・単独性が併用されている。
高等裁判所・最高裁判所は常に合議制である。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
訴額は変わっているかも知れない?。
法律はちょくちょく変わる。
民事訴訟では、原告と被告が裁判所の面前で口頭弁論を行い、裁判所が判決を下す事によって紛争が解決される。
この時の原告と被告は、当事者と呼ばれる。
当事者は、法律について素人である事も多く、その様な場合には訴訟代理人が当事者の訴訟追行を助ける事になる(原則として、訴訟代理人は弁護士のみがなる事ができる)。
(2) 裁判所
裁判所には、最高裁判所の他下級裁判所として4種類が存在している(高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所)。
地方裁判所と一部の高等裁判所には支部が設置されている。
我が国では審級制度が採用され、民事訴訟における第一審は、簡易裁判所と地方裁判所が扱う。
訴額が90万円以下であれば、原則として簡易裁判所が第一審を受け持つ事になる。
実際に裁判を行うのは、裁判機関としての裁判所である。
裁判は 、合議制で行われる場合と単独で行われる場合がある。
簡易裁判所は常に単独性であるが、地方裁判所では、合議制・単独性が併用されている。
高等裁判所・最高裁判所は常に合議制である。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
訴額は変わっているかも知れない?。
法律はちょくちょく変わる。