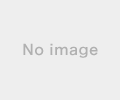国際ジャーナリストの堤末果さんが「国民の違和感は9割正しい」( PHP 新書)を出版した。
「こうしたショックな出来事の裏で、何時も大事な法律が通されてきたからです」と明かす。
例えば政府は3月、殺傷能力の高い戦闘機の輸出に踏み切った。
日本は「平和主義」の精神から、武器輸出三原則に基付いて事実上の全面禁輸が基本だったが安倍内閣で方針転換。
「憲法の精神を守ると言う原則を捻じ曲げてしまったんです」
岸田内閣も路線を継承し、昨年末に防衛装備移転三原則と運用指針の改定を閣議などで決定した。
「戦争を知らない世代の国会議員は憲法改正や武器輸出を進め乍ら、食料や水道、通信インフラを外資へ開放し、日本の安全保障を脅かしている」と堤さん。
「刻々と戦争前夜に似てくる現状を、戦争を知る世代と、これからの社会を担う若い世代の両方に読んで、知って欲しかったから」と理由を語る。
堤さんは地方自治法の改正も地方分権に逆行すると強く警鐘を鳴らす。
「新型コロナウイルス禍では、山梨県が飲食店の経営を支える為の独自の制度を作りました。
国からの指示権を強化する事で、そうした地方の裁量が制限される懸念があります」
「国や社会の動きを見る中で、何か可笑しいなと違和感を覚えたら、立ち止まって考えて欲しい。
そうすると、社会への注意の向き方が変わってきます」と堤さん。
自身、情報収集する際は同じテーマについて立場の異なる著者が書いた本を複数読む事で理解を深めると言う。
「ネットでは事実が歪められて伝えられる事もある。自分で調べて考える『知力』が、これから自分と国を守る為に最も大切になるでしょう」
国際ジャーナリスト 堤 未果さん
愛媛新聞 文化から
立場の異なる著者が書いた本を複数読む事で理解を深めるらしい。
知力、大切らしい。
自民党政府には違和感を感じる。
戦争前夜に似るらしい。
2024年05月10日
視力回復の7つのトレーニング
ビジョンテラピーの目的は、あなたのはっきり見える領域を拡大し、ぼんやり見える領域を縮小させる事にあります。
そして、その基本的トレーニングの方法としては、以下の7つがあります。
1 エッジング:物の縁をなぞって見る
2 ポンピング:はっきり見える物とぼんやり見える物を交互に見る
3 ブルアーゾーニング:はっきり見える領域を広げる
4 アイストレッチング:眼筋を解す
5 スクイーズブリンキング:上下の瞼を、きつく閉じて瞬きする
6 ファーストブリンキング:早い瞬きをする
7 スローブリンキング:ゆっくりと瞬きをする
視力回復トレーニング講座から
良くなると信じて繰り返し練習する事が大切らしい。
そして、その基本的トレーニングの方法としては、以下の7つがあります。
1 エッジング:物の縁をなぞって見る
2 ポンピング:はっきり見える物とぼんやり見える物を交互に見る
3 ブルアーゾーニング:はっきり見える領域を広げる
4 アイストレッチング:眼筋を解す
5 スクイーズブリンキング:上下の瞼を、きつく閉じて瞬きする
6 ファーストブリンキング:早い瞬きをする
7 スローブリンキング:ゆっくりと瞬きをする
視力回復トレーニング講座から
良くなると信じて繰り返し練習する事が大切らしい。
事務管理・不当利得・不法行為
私人間に債権債務関係が発生するのは、契約だけではない。
民法は、契約以外で債権債務関係が発生する場合として、事務管理・不当利得・不法行為を定めている。
(1) 事務管理
事務管理とは、法的義務がないのに他人の為の事務を行った場合に、法律関係が発生する事を認めた相互扶助の考えに基付く制度である。
事務管理とは、一定の要件の元で義務なくして他人の事務の管理を始める事であり、これに要した費用の償還請求権が認められている(民法702条)。
(2) 不当利得
不当利得とは、法律上の原因なくして利得を受け、それにより他人に損失を与えた場合、その利得の返還を求める制度である(民法703条)。
例えば、売買契約が取消された場合、売主が代金を受け取っているとすれば、その利得は取消によって法律上の原因を失う事になるから、代金は不当利得となり、買主に返還する義務を負う事になる。
(3) 不法行為
故意又は過失によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う(民法709条)。
過失責任・自己責任の原則を理念としている。
然し、此れを修正した特殊的不法行為の規定も置かれている(民法714条〜719条)。
使用者責任や土地工作物の占有者・所有者の責任等である。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
事務管理の例として、Y が家族総出で旅行中、自宅の屋根が台風で壊れた。
このままでは雨漏りで家財道具が駄目になってしまうと気の毒に思った隣人の X は、職人に依頼して、屋根を修繕し、その費用を支払った。
この場合、X は、事務管理の規定によって、支出した修繕代金を Y に請求する事ができると言うものらしい。
民法は、契約以外で債権債務関係が発生する場合として、事務管理・不当利得・不法行為を定めている。
(1) 事務管理
事務管理とは、法的義務がないのに他人の為の事務を行った場合に、法律関係が発生する事を認めた相互扶助の考えに基付く制度である。
事務管理とは、一定の要件の元で義務なくして他人の事務の管理を始める事であり、これに要した費用の償還請求権が認められている(民法702条)。
(2) 不当利得
不当利得とは、法律上の原因なくして利得を受け、それにより他人に損失を与えた場合、その利得の返還を求める制度である(民法703条)。
例えば、売買契約が取消された場合、売主が代金を受け取っているとすれば、その利得は取消によって法律上の原因を失う事になるから、代金は不当利得となり、買主に返還する義務を負う事になる。
(3) 不法行為
故意又は過失によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う(民法709条)。
過失責任・自己責任の原則を理念としている。
然し、此れを修正した特殊的不法行為の規定も置かれている(民法714条〜719条)。
使用者責任や土地工作物の占有者・所有者の責任等である。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
事務管理の例として、Y が家族総出で旅行中、自宅の屋根が台風で壊れた。
このままでは雨漏りで家財道具が駄目になってしまうと気の毒に思った隣人の X は、職人に依頼して、屋根を修繕し、その費用を支払った。
この場合、X は、事務管理の規定によって、支出した修繕代金を Y に請求する事ができると言うものらしい。