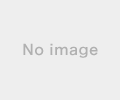眼球の仕組み:
眼球は、直径25mm にも満たない生きた細胞でできている袋の様なものです。
その中には、ゼリー状のものと圧縮された液体が入っていて、此れが袋を風船の様に膨らませています。
そして、この前面の部分に角膜があります。
これは、透明な膜でできていて、光の取り入れ口となっています。
角膜の裏側には、虹彩と言う光の量を調節する筋肉の隔壁があります。
虹彩の後ろには、レンズ、則ち、軟らかくて透明な細胞が集まってできている水晶体があります。
この水晶体によって、網膜上に光の焦点が合わされ、光はそこで電気的な刺激に変えられて、視神経を通じて脳に伝わります。
水晶体の周りの毛様体筋と言う筋肉は、焦点を変える役割を果たしています。
これが収縮すると水晶体が引っ張られて薄くなり焦点は遠くになります。
逆に、これが弛緩すると、水晶体は厚くなり焦点が近くなって、近い所のものが見える様になります。
眼球の周りには、6つの筋肉(外眼筋と総称します)があり、この働きによって目が動き、一つのものから他のものへと視線を移したり、動いているものを目で追う事ができるわけです。
両目の間は数cm 空いている為、夫々多少異なった像を平面的に捉えます。
そして、脳がこの2つの異なった像を合成して立体的な像を作り出します。
若し毛様体筋に欠陥があると、網膜上の像がぼやける事になります。
又、外眼筋が正しく機能しない場合には、ものが二重に見え、仕事や学業やスポーツなどに支障をきたします。
視力回復トレーニング講座から
眼球は、ゼリー状のものと液体が膨らませている袋の様なものらしい。
2024年05月07日
格差是正 求める根拠に
憲法は14条で「法の下の平等」を定めるが、日常生活で不平等や不公平を感じる場面は多い。
格差を是正する為に、憲法を活用する事はできるのだろうか。
----------憲法が定める「平等」はどんなものか。
教育や就労などの機会が全ての人に開かれている「機会の平等」を定めていると解されているが、それだけでは参加できないグループが生まれる。
弱い立場にいる人たちに便宜を図る事で参加の機会を生かせる様にする「実質的平等」の意味も含まれる。
只何を平等とするかの考え方は人により多種多様で、時代によっても変化する。
不平等と感じても裁判で平等権違反の判決を勝ち取るのはハードルが高い。
違憲判決が示されたのは「在外者の選挙権」など、差別により重要な権利の侵害が起きた場合に限られる。
何が平等かについて合意を形成するのは本来、司法ではなく政治の役割だ。
----------差別を是正する措置として、差別是正措置(アファーマティブ・アクション、A A )が日本でも注目されている。
近年は男女差別是正策として議論される例が多い。
合理的な目的を掲げ社会的に合意を得て実施されるなら合憲と考えられる。
只社会的、経済的弱者の救済策として、薔薇色の物ではない。
特定グループを優先する事で、新たな構造的差別が生まれる恐れは常に生じる。
「多様性の確保」を根拠に A A 導入を求める例が多いが、人によって捉え方が全く異なる。
----------格差が広がっているが、憲法の平等原則から是正策を導く事はできないか。
格差や分断が進めば他者に無関心になり、国民の一体感が失われる。
災害時でも助け合い、法を順守する日本人のモラルの高さが失われる恐れもある。
不公平や不平等の不満が溜まれば、憲法が描く健全な社会から遠ざかる。
平等原則を定める14条は裁判で権利を勝ち取る根拠とするのは難しいが、理念として幅広く解釈できる。
全ての人に健康で文化的な生活を保障する生存権を規定した25条と組み合わせる事で、国に格差を是正する法制度や政策を求める根拠として活用できる。
限られたパイを奪い合って過酷な椅子取りゲームをする状態では、格差の本質的な解消には繋がらない。
全体が底上げされる様な経済成長策を含め、社会資源が貧しい人にも配分される政策が必要だ。
桐蔭横浜大法学部 茂木 洋平准教授
愛媛新聞 平等って何ですか?から
14条と25条を組み合わせると根拠として活用できるらしい。
国に求めるべきだ。
格差を是正する為に、憲法を活用する事はできるのだろうか。
----------憲法が定める「平等」はどんなものか。
教育や就労などの機会が全ての人に開かれている「機会の平等」を定めていると解されているが、それだけでは参加できないグループが生まれる。
弱い立場にいる人たちに便宜を図る事で参加の機会を生かせる様にする「実質的平等」の意味も含まれる。
只何を平等とするかの考え方は人により多種多様で、時代によっても変化する。
不平等と感じても裁判で平等権違反の判決を勝ち取るのはハードルが高い。
違憲判決が示されたのは「在外者の選挙権」など、差別により重要な権利の侵害が起きた場合に限られる。
何が平等かについて合意を形成するのは本来、司法ではなく政治の役割だ。
----------差別を是正する措置として、差別是正措置(アファーマティブ・アクション、A A )が日本でも注目されている。
近年は男女差別是正策として議論される例が多い。
合理的な目的を掲げ社会的に合意を得て実施されるなら合憲と考えられる。
只社会的、経済的弱者の救済策として、薔薇色の物ではない。
特定グループを優先する事で、新たな構造的差別が生まれる恐れは常に生じる。
「多様性の確保」を根拠に A A 導入を求める例が多いが、人によって捉え方が全く異なる。
----------格差が広がっているが、憲法の平等原則から是正策を導く事はできないか。
格差や分断が進めば他者に無関心になり、国民の一体感が失われる。
災害時でも助け合い、法を順守する日本人のモラルの高さが失われる恐れもある。
不公平や不平等の不満が溜まれば、憲法が描く健全な社会から遠ざかる。
平等原則を定める14条は裁判で権利を勝ち取る根拠とするのは難しいが、理念として幅広く解釈できる。
全ての人に健康で文化的な生活を保障する生存権を規定した25条と組み合わせる事で、国に格差を是正する法制度や政策を求める根拠として活用できる。
限られたパイを奪い合って過酷な椅子取りゲームをする状態では、格差の本質的な解消には繋がらない。
全体が底上げされる様な経済成長策を含め、社会資源が貧しい人にも配分される政策が必要だ。
桐蔭横浜大法学部 茂木 洋平准教授
愛媛新聞 平等って何ですか?から
14条と25条を組み合わせると根拠として活用できるらしい。
国に求めるべきだ。
債権の確保
債権者が債務者の将来の資力に不安を抱いた時、或いは債務者が引当となっている財産の保全に不熱心である場合、債権者を保護する為、民法は、債権の確実な履行を確保する為の制度を用意している。
その一つは、担保物件や保証に関する制度であり、もう一つは、責任財産を保全する為の債権者代位権や債権者取消権である。
(1)担保制度
債権の確実な回収を実現する為に、債権者が予め講じておく手段を担保と言う。
担保には、物的担保と、人的担保がある。
① 物的担保
担保力の根源を目的物の経済的価値に置くものを物的担保と言う。
留置権、先取特権、質権、抵当権が挙げられる。
② 人的担保
担保力の根源を保証人の一般財産に置くものを人的担保と言う。
保証には、通常の保証と連帯保証の区別がある。
(2) 責任財産保全の為の制度
債務者が、債権の履行を拒む場合、債権者は強制執行により債権の弁済を受ける事になる。
然し、債務者が、債権の引当となる財産の保全に不熱心であるか、或いは債権者を害する意図で処分してしまう様な場合、強制執行は十分に功を奏しない事になる。
そこで民法は、強制執行に備えて、引当となる財産(’責任財産)を保全する為の制度として、債権者代位権(民法423条)、債権者取消権(民法424条)を規定している。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
債権者平等原則があるらしい。
その一つは、担保物件や保証に関する制度であり、もう一つは、責任財産を保全する為の債権者代位権や債権者取消権である。
(1)担保制度
債権の確実な回収を実現する為に、債権者が予め講じておく手段を担保と言う。
担保には、物的担保と、人的担保がある。
① 物的担保
担保力の根源を目的物の経済的価値に置くものを物的担保と言う。
留置権、先取特権、質権、抵当権が挙げられる。
② 人的担保
担保力の根源を保証人の一般財産に置くものを人的担保と言う。
保証には、通常の保証と連帯保証の区別がある。
(2) 責任財産保全の為の制度
債務者が、債権の履行を拒む場合、債権者は強制執行により債権の弁済を受ける事になる。
然し、債務者が、債権の引当となる財産の保全に不熱心であるか、或いは債権者を害する意図で処分してしまう様な場合、強制執行は十分に功を奏しない事になる。
そこで民法は、強制執行に備えて、引当となる財産(’責任財産)を保全する為の制度として、債権者代位権(民法423条)、債権者取消権(民法424条)を規定している。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
債権者平等原則があるらしい。