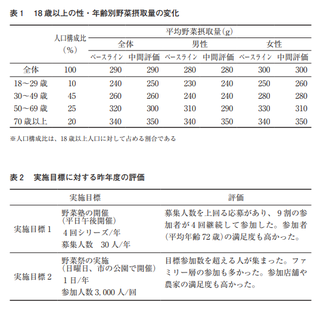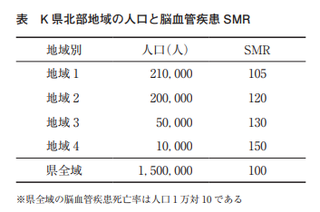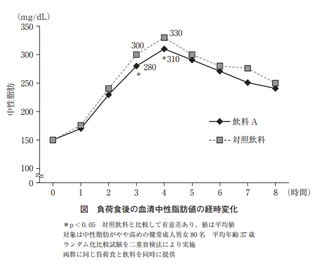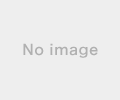2018年12月19日
国家試験解説「応用力試験(No.191,192)」~社会・環境と健康、公衆栄養学~
K市の健康増進課に勤務する管理栄養士である。K市では高血圧の有病率が全国より高いため、中高年で正常高値血圧の者を対象とした栄養教室(月1回、通年)を企画した。特定健康診査の際に収縮期血圧が130~139mmHgであった者に周知し、参加希望を募った。教室参加者は40名となった。対照群を設けることができず、教室の評価は前後比較で行うことになった。教室終了時の事後調査に協力が得られた者は22名であった。
Q191.食塩摂取量について、対象者の負担が少なく、かつ精度の高い方法で測定した。最も適切なのはどれか。1つ選べ。
(1)連続した普段の日の2日間の写真法による食事記録
(2)普段の1日の目安量法による食事記録
(3)普段の日の翌日1回の随時尿による推定
(4)塩蔵食品、汁物、麺類の摂取頻度の調査
【解説】…正答(3)
(1)適切でない。写真法は対象者の負担は少ないが、尿検査による食塩摂取量の推定に比べて精度が劣る。
(2)適切でない。1日の食事記録では、対象者の習慣的な食事摂取量を把握できない。
(3)適切。1回の尿検査で、随時尿に含まれるナトリウム(Na)とクレアチニン(Cr)から
24時間尿中Na排泄量を求めることで1日食塩摂取量の推定が可能であり、
対象者の負担が少なく、かつ最も制度の高い方法であるといえる。
(4)適切でない。食物摂取頻度調査法は1回の調査で簡便に対象者の習慣的な食事摂取量を把握できるが、 塩蔵食品、汁物、麺類以外の食品にも食塩は含まれており、
これらに限定した食物摂取頻度調査法では精度に欠ける。
Q192.食塩摂取量を教室の前後で比較したところ、統計的に有意な減少が認められた。この結果の解釈である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。
(1)統計的に有意な減少があったため、教室の減塩効果があった。
(2)対照群を設定していないため、教室の減塩効果があったとはいえない。
(3)性別を調整していないため、教室の減塩効果があったとはいえない。
(4)事後調査の人数が少ないため、教室前後の変化を過小評価している。
【解説】…正答(2)
前後比較試験では、選択バイアスなどの種々のバイアスが生じやすいため、プログラム実施の前後で評価指標に差がみられたとしても、それがプログラムの実施によるものであると結論付けるには多くの検討が必要である。対象群を設定して介入群とのプログラム実施の前後における評価指標の差を比較することで、評価の信頼性を高めることが可能になる。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8038357
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック