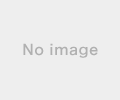新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2020年02月19日
出題予測問題<臨床栄養学>がん患者
昨日の問題の解説です。
(2)たんぱく質摂取量は、60g/日とする。
(3)水分摂取量は、1,300mL/日とする。
(4)リン摂取量は、1,700mg/日とする。
(5)透析間の体重増加量は、6㎏までとする。
【解説】正答(2)
以下、「慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版」に基づく。
(1)誤り。エネルギー摂取量は、30~35kcal/標準体重/日とする。
この患者の標準体重56㎏(1.6(m)2✕22)を代入すると、1,680~1,960kcal/日となる。
2,400kcal/日では多い。
(2)正しい。たんぱく質摂取量は、0.9~1.2g/㎏標準体重/日とする。
この患者の標準体重56㎏を代入すると、50.4~67.2g/日となる。
60g/日は適正量である。
(3)誤り。水分摂取量は、できるだけ少なくする。
(4)誤り。リン摂取量は、(たんぱく質(g)✕15)㎎/日以下とする。
(2)のたんぱく質摂取量60g/日を代入すると、900㎎/日以下となる。
1,700mg/日では多い。
(5)誤り。透析間の体重増加量は、ドライウエイトの3~5%以内(次の透析まで中1日で3%以内、
中2日で5%以内)を目安とする。
この患者のドライウエイトは54㎏であるため、増加量は1.62~2.7㎏以内を目安とする。
(2)血液透析では、原則、カリウム制限の必要はない。
(3)長期にわたる血液透析では、不均衡症候群が起こりやすい。
(4)腹膜透析では、シャントを造設する必要がある。
(5)腹膜透析では、たんぱく質の喪失が大きい。
【解説】正答(5)
(1)誤り。血液透析ではなく、腹膜透析においてである。
腹膜透析では、透析液中のブドウ糖が腹膜を介して体内に一部吸収されることを考慮した
総エネルギーとする。
(2)誤り。原則、カリウム制限がないのは、腹膜透析においてである。
腹膜透析は、間欠的療法ではないため、常に排液中へのカリウム排出が持続しているからである。
血液透析では、カリウムは2,000mg/日以下に制限する。
ただし、腹膜透析の場合でも、高カリウム血症を認める場合には血液透析同様に制限する。
(3)誤り。不均衡症候群は、血液透析に体が慣れていない透析導入期にしばしばみられる合併症である。
(4)誤り。シャントを造設する必要があるのは、血液透析である。
血液透析では大量の血液を取り出す必要があり、その経路として内シャントが用いられる。
動脈と静脈を吻合することにより、穿刺しやすく大量の血液を取り出すことができるようになる。
腹膜透析では、透析液を出し入れするためのカテーテルが必要である。
(5)正しい。腹膜透析では、長期間腹腔内に貯留された透析液を排液する際に、
5~10g/日のたんぱく質の喪失がある。
今日は、「がん患者」の問題です。
診療報酬では、「がん」に関する栄養食事指導での加算が認められるようになりましたね。
それを受けて国家試験でも「がん」に関する出題が増えています。
がんの特性を理解し、どんな問題が出題されても解けるようにしておいてください。
(2)大腸がん術後のストーマ(人工肛門)は、空腸に造設する。
(3)化学療法施行時には、食欲が低下する。
(4)疼痛緩和に用いられるモルヒネ塩酸塩の副作用として、便秘がある。
(5)緩和ケアでは、患者と家族のQOL向上を考慮する。
明日解説します。
Q1.65歳、男性。身長160㎝、ドライウェイト54㎏。週3回血液透析を受けている。この患者の栄養管理に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)エネルギー摂取量は、2,400kcal/日とする。(2)たんぱく質摂取量は、60g/日とする。
(3)水分摂取量は、1,300mL/日とする。
(4)リン摂取量は、1,700mg/日とする。
(5)透析間の体重増加量は、6㎏までとする。
【解説】正答(2)
以下、「慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版」に基づく。
(1)誤り。エネルギー摂取量は、30~35kcal/標準体重/日とする。
この患者の標準体重56㎏(1.6(m)2✕22)を代入すると、1,680~1,960kcal/日となる。
2,400kcal/日では多い。
(2)正しい。たんぱく質摂取量は、0.9~1.2g/㎏標準体重/日とする。
この患者の標準体重56㎏を代入すると、50.4~67.2g/日となる。
60g/日は適正量である。
(3)誤り。水分摂取量は、できるだけ少なくする。
(4)誤り。リン摂取量は、(たんぱく質(g)✕15)㎎/日以下とする。
(2)のたんぱく質摂取量60g/日を代入すると、900㎎/日以下となる。
1,700mg/日では多い。
(5)誤り。透析間の体重増加量は、ドライウエイトの3~5%以内(次の透析まで中1日で3%以内、
中2日で5%以内)を目安とする。
この患者のドライウエイトは54㎏であるため、増加量は1.62~2.7㎏以内を目安とする。
Q2.透析療法に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)血液透析では、透析液から吸収されるエネルギー分を考慮する。(2)血液透析では、原則、カリウム制限の必要はない。
(3)長期にわたる血液透析では、不均衡症候群が起こりやすい。
(4)腹膜透析では、シャントを造設する必要がある。
(5)腹膜透析では、たんぱく質の喪失が大きい。
【解説】正答(5)
(1)誤り。血液透析ではなく、腹膜透析においてである。
腹膜透析では、透析液中のブドウ糖が腹膜を介して体内に一部吸収されることを考慮した
総エネルギーとする。
(2)誤り。原則、カリウム制限がないのは、腹膜透析においてである。
腹膜透析は、間欠的療法ではないため、常に排液中へのカリウム排出が持続しているからである。
血液透析では、カリウムは2,000mg/日以下に制限する。
ただし、腹膜透析の場合でも、高カリウム血症を認める場合には血液透析同様に制限する。
(3)誤り。不均衡症候群は、血液透析に体が慣れていない透析導入期にしばしばみられる合併症である。
(4)誤り。シャントを造設する必要があるのは、血液透析である。
血液透析では大量の血液を取り出す必要があり、その経路として内シャントが用いられる。
動脈と静脈を吻合することにより、穿刺しやすく大量の血液を取り出すことができるようになる。
腹膜透析では、透析液を出し入れするためのカテーテルが必要である。
(5)正しい。腹膜透析では、長期間腹腔内に貯留された透析液を排液する際に、
5~10g/日のたんぱく質の喪失がある。
今日は、「がん患者」の問題です。
診療報酬では、「がん」に関する栄養食事指導での加算が認められるようになりましたね。
それを受けて国家試験でも「がん」に関する出題が増えています。
がんの特性を理解し、どんな問題が出題されても解けるようにしておいてください。
Q1.がん患者に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
(1)胃がんによる胃全摘術後には、骨粗鬆症のリスクが高まる。(2)大腸がん術後のストーマ(人工肛門)は、空腸に造設する。
(3)化学療法施行時には、食欲が低下する。
(4)疼痛緩和に用いられるモルヒネ塩酸塩の副作用として、便秘がある。
(5)緩和ケアでは、患者と家族のQOL向上を考慮する。
明日解説します。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
2019年07月31日
出題予測問題【食べ物と健康⑯】
16.食品のアレルギー表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)特定原材料として、5品目が定められている。(2)そばを原材料とする食品には、表示が推奨されている。
(3)大豆を原材料とする食品には、表示が義務付けられている。
(4)うずら卵を原材料とする食品には、表示をしなくてよい。
(5)「小麦粉」は、小麦の代替表記として認められる。
【解説】 正答(5)
(1)誤り。特定原材料として、7品目が定められている。
(2)誤り。そばを原材料とする食品には、表示が義務付けられている。
(3)誤り。大豆を原材料とする食品には、表示が推奨されている。
(4)誤り。うずらの卵を原材料とする食品には、表示が義務付けられている。
(5)正しい。
2019年07月30日
出題予測問題【食べ物と健康⑮】
15.食品の表示に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
(1)分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品には、「非遺伝子組換え食品」の表示が義務付けられている。
(2)分別生産流通管理をしていない非遺伝子組換え食品には、
「遺伝子組換え不分別」の表示が義務付けられている。
(3)ビタミンCを栄養強化の目的で使用する場合は、
「栄養強化剤(ビタミンC)」の表示が義務付けられている。
(4)さば、大豆を原材料として加工食品に使用する場合は、アレルギー表示が義務付けられている。
(5)そば、落花生は、特定原材料としての表示が義務付けられている。
【解説】 正答(2)(5)
(1)誤り。分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品には、
「非遺伝子組換え食品」の表示が任意で認められている。
(2)正しい。
(3)誤り。ビタミンCを栄養強化の目的で使用する場合は、
「栄養強化(ビタミンC)」などの表示は必要ではない。
(4)誤り。さば、大豆を原材料として加工食品に使用する場合は、
アレルギー表示が義務付けられていない。
(5)正しい。
2019年07月29日
出題予測問題【食べ物と健康⑭】
14.食品添加物に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)食品添加物は、健康増進法で定義されている。(2)指定添加物は、消費者庁長官が指定する。
(3)既存添加物は、天然添加物として使用実績があったものである。
(4)天然香料は、指定添加物に含まれる。
(5)一般飲食物添加物は、既存添加物に含まれる。
【解説】 正答(3)
(1)誤り。食品添加物は、食品衛生法で定義されている。
(2)誤り。指定添加物は、厚生労働省が指定する。
(3)正しい。
(4)誤り。天然香料は、指定添加物に含まれない。
(5)誤り。一般飲食物添加物は、既存添加物に含まれない。
2019年07月28日
出題予測問題【食べ物と健康⑬】
13.放射線物質に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)セシウム137の就籍部位は、甲状腺である。(2)ストロンチウム90の沈着部位は、骨である。
(3)ヨウ素131の集積部位は、筋肉である。
(4)放射線の透過能力は、α線が最も強い。
(5)生物学的半減期は、元素によらず一定である。
【解説】 正答(2)
(1)誤り。セシウム137の集積部位は、筋肉、全身である。
(2)正しい。
(3)誤り。ヨウ素131の集積部位は、甲状腺である。
(4)誤り。放射線の透過能力は、γ線が最も強い。
(5)誤り。生物学的半減期は、元素によって異なる。
2019年07月27日
出題予測問題【食べ物と健康⑫】
12.フグ毒に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)ベロ毒素である。
(2)加熱により無毒化される。
(3)中毒症状は、激しい下痢である。
(4)毒性は、ハウユニット(HU)で表される。
(5)卵巣や肝臓に蓄積している。
【解説】 正答(5)
(1)誤り。テトロドトキシンである。
(2)誤り。加熱により無毒化されない。
(3)誤り。中毒症状は、しびれ、麻痺などである。
(4)誤り。毒性は、マウスユニット(MU)で表される。
(5)正しい。
2019年07月26日
出題予測問題【食べ物と健康⑪】
11.腸管出血性大腸菌による食中毒に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)細菌性食中毒の原因菌として、最も多い。(2)主な症状は発熱である。
(3)重篤な場合、溶血性尿毒症症候群を引き起こす。
(4)真空包装食品が主な原因となる。
(5)食後数時間で発症する。
【解説】 正答(3)
(1)誤り。細菌性食中毒の原因菌として、毎年報告されている。
(2)誤り。主な症状は、出血性大腸炎である。
(3)正しい。
(4)誤り。加熱不十分な食肉が主な原因となる。
(5)誤り。食後4~9日で発症する。
2019年07月25日
出題予測問題【食べ物と健康⑩】
10.細菌性食中毒の原因菌と主な発生源となる食品の組合せである。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)腸炎ビブリオー野菜(2)カンピロバクターーきのこ類
(3)サルモネラー鶏卵
(4)ブドウ球菌ー二枚貝
(5)ウェルシュ菌ーはちみつ
【解説】 正答(3)
(1)誤り。腸炎ビブリオの発生源は、海産鮮魚介類である。
(2)誤り。カンピロバクターの発生源は、鶏肉である。
(3)正しい。
(4)誤り。ブドウ球菌の発生源は、にぎりめしである。
(5)誤り。ウェルシュ菌の発生減は、大量調理のシチューである。
2019年07月24日
出題予測問題【食べ物と健康⑨】
9.食品衛生法に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的としている。(2)食品とは、医薬品・医薬部外品を含むすべての飲食物をいう。
(3)新開発食品の販売を禁止することが出来るのは、農林水産大臣である。
(4)食品または、添加物の規格・基準を定めることができるのは、厚生労働大臣である。
(5)輸入された食品について、登録検査機関の行う検査を命じることが出来るのは、都道府県知事である。
【解説】 正答(4)
(1)誤り。飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的としている。
(2)誤り。食品とは、医薬品・医薬部外品を除くすべての飲食物をいう。
(3)誤り。新開発食品の販売を禁止することができるのは、厚生労働大臣である。
(4)正しい。
(5)誤り。輸入された食品について、登録検査機関の行う検査を命じることが出来るのは、厚生労働大臣である。
2019年07月23日
出題予測問題【食べ物と健康⑧】
8.食品の色素成分に関する記述である。正しいのはどれか、1つ選べ。
(1)クロロフィルが褐色になるのは、マグネシウムの離脱による。(2)アントシアニンが赤色を呈するのは、アルカリ性の条件下である。
(3)えびやかにをゆでると赤色になるのは、アスタシンの分解による。
(4)ミオグロビンが褐色になるのは、ヘム鉄の還元による。
(5)のりを加熱すると青緑色になるのは、フィコシアニンの分解による。
【解説】 正答(1)
(1)正しい。
(2)誤り。アントシアニンが赤色を呈するのは、産生の条件下である。
(3)誤り。えびやかにをゆでると赤色になるのは、アスタシンの生成による。
(4)誤り。ミオグロビンが褐色になるのは、ヘム鉄の酸化による。
(5)誤り。のりを加熱すると青緑色になるのは、フィコシアニンが残るためである。