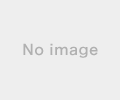政治の劣化が著しい。
国会の審議にしても政治資金の在り方にしても、何も変わらないままだ。
国会議員に改革しようと言う気持ちがないからで、突き詰めえいくと、こう言うやる気のない議員しか選べない選挙制度の問題に行き着く。
今の制度は衆参両院共に問題がある。
現代国家で国政の主体となるのは、一貫した政策を持つ政党だ。
衆院は中選挙区の比例代表制にしたら如何か。
選挙区の規模は5、6人で、非拘束式名簿を徹底し、個人名だけで投票する様にしたらいい。
個人票を合算して政党の得票として計算するのだ。
参院は、民主党政権時代に当時の西岡武夫参院議長が示した私案が参考になる。
都道府県単位の選挙区を廃し、全国比例を北海道など9ブロックに分けるのが柱だ。
個人名での投票を可能にすれば、地域代表も選出できる。
「1票の格差」問題は解消され、良い事尽くめではないか。
地方議会の選挙制度改革も重要だ。
多くがこの悪循環に陥り、議会は何処も地域や団体の顔役の様な高齢男性ばかりだ。
選挙制度を制限連記制に変えたら如何か。
定数より少ない範囲で複数の候補者を選べる制度だ。
制度が変わればガラッと変わるものだ。
改革をしないと落選すると思わせる事ができれば、議員は動き出す。
若者は選挙に行かないと言うが、投票率を上げるには選挙制度を変えるのが一番だ。
「こんなに選べるんだ」と言う気持ちになれば、意識も変わる。
そうすれば政治も変わるのではないか。
大山玲子 駒沢大前教樹 1954年東京都生まれ。 一橋大大学院修士課程修了。 博士(法学)。
2003年に駒沢大教授。 専門は政治制度論。 著書に「政治を再建する、幾つかの方法」など。
愛媛新聞 記事から
兎に角、政治を再建しなければならない。
その為には選挙制度を変えなけらばならない。
自民党政権では選挙制度を変えられないので政権交代をしなければならない。
改革をしないと落選すると思わせないといけない。
制度を変えないと落選すると思わせよう。
2024年05月11日
老視
我々の目の調節する力は年齢と共に減少していくもので、ピントを合わせる事のできる範囲は狭くなり、調節できる一番近くの点が遠ざかります。
普通物を見るのに最も適した距離は、目から30cm 程度の所とされていますが、この位置の物も良く見えなくなると愈々凸レンズ(老眼鏡)の助けを借りなければならなくなります。
此れを老視と呼びます。
勿論老視となっても、それ以前に使用していた近視や遠視の眼鏡も必要で、老視用の眼鏡(老眼鏡)には、調整力の低下にそれまでの眼鏡の度をプラスした物が必要となります。
全科家庭の医学から
遠方用と近方用の眼鏡を別々に作ると視野も広く、像も綺麗に見えるらしい。
遠近両用よりも良いらしい。
普通物を見るのに最も適した距離は、目から30cm 程度の所とされていますが、この位置の物も良く見えなくなると愈々凸レンズ(老眼鏡)の助けを借りなければならなくなります。
此れを老視と呼びます。
勿論老視となっても、それ以前に使用していた近視や遠視の眼鏡も必要で、老視用の眼鏡(老眼鏡)には、調整力の低下にそれまでの眼鏡の度をプラスした物が必要となります。
全科家庭の医学から
遠方用と近方用の眼鏡を別々に作ると視野も広く、像も綺麗に見えるらしい。
遠近両用よりも良いらしい。
遠視
無調節状態(何もせずに、ぼんやりした状態)では何処にもピントが合っていない目、無限大の距離にある物を見るにも調節をしなければならない目、此れが遠視です。
普通幼児は遠視である事が多く、体の成長と共に近視の方へ変化し、多くは正視で止まるものです。
遠視のままですと、絶えず人一倍調節の努力が必要なので、目が疲れ易く、子供では寧ろ調節のやり過ぎで、一見近視の様になったり、斜視になったりしますし、年を取ると早く老視が起こります。
見付かったら、早くから凸レンズの眼鏡を掛ける事です。
全科家庭の医学から
無調節状態で無限大の距離の物にピントが合っているのが正視らしい。
遠視はややこしい様だ。
普通幼児は遠視である事が多く、体の成長と共に近視の方へ変化し、多くは正視で止まるものです。
遠視のままですと、絶えず人一倍調節の努力が必要なので、目が疲れ易く、子供では寧ろ調節のやり過ぎで、一見近視の様になったり、斜視になったりしますし、年を取ると早く老視が起こります。
見付かったら、早くから凸レンズの眼鏡を掛ける事です。
全科家庭の医学から
無調節状態で無限大の距離の物にピントが合っているのが正視らしい。
遠視はややこしい様だ。