�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B
�L��
�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B
posted by fanblog
2013�N02��03��
���������n���������w�����ɗ^����S�Ɓx�̓G���{�������i�P�j�@
zeranium�̃u���O�@���]��
*******************************************************************************
���������n���������w�����ɗ^����S�Ɓx�̓G���{�������@�E
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/index.html#entry-83670623
�@�@�@1198�N�ɃC���m�P���e�B�E�X3�������[�}�@���̈ʂɂ��ƁA�J�^���h�ւ̒e�������߁A1209�N�A���ɓ�t�����X�ɓ����R�𑗂邱�Ƃ����肵�܂����B
�ނ͓����R��g�D����ɂ�����A���[�}�s���̂Ȃ��Ɉْ[�ɑ���{����I�݂ɐ��肽�āA����œ����R�ɂْ͈[�҂̗̒n�ƍ��Y��^���邱�Ƃ�����̂ł��B
���ƘV�ԁi�낤�����j�Ȑ����Ƃł��傤���B�܂�R�l��l�ЂƂ�ɍł����͓I�Ɉْ[�����s�Ȃ킹����@�́A�ނ�̗~�ɉ����邱�Ƃ��ƐS���Ă����̂ł��B
�@�@�@�@���̖��ɂ���đ���ꂽ���̌R���́A�A���r�\���R�ƌĂ�܂����B
�@�@�@����͂͂��߂����t�����X�̃J�^���h�Ƃ����A�L���X�g���k�̓�����ړI�Ƃ��đg�D���ꂽ�ŏ��̏\���R�ł����B
�����Ĉْ[�����́A���̌�20�N�Ԃɓn���ČJ��L����ꂽ�̂ł��B
�A���r�\���R���e�n�ōs�Ȃ����̂́A�Z���̑�s�E�ł����B
�����ł̓J�^���h�������łȂ����Ƃ������Ƃ́A���͂�W������܂���ł����B
�Ȃ��Ȃ�A�����������D���邱�Ƃ��ړI�ɂȂ��Ă����̂ŁA�E�C�ɖ����̓��荞�ޗ]�n�͂Ȃ��A�ނ�͂ނ��낻��������ł��܂����B
���Ƃ��Ζ�����˂ɗ��Ƃ��A���̏ォ�玟�X�Ƒ傫�Ȑ𓊂����ނƂ����؍s���s�Ȃ�ꂽ�̂����̓T�^�ł��傤�B
�@�@�@���̎�����\���R���A���̖ړI�͗̓y�ƍ��Y�̎��D�ł����B
�@�@�@�ނ炪�f�����ً��k��łڂ��Ƃ�����`�������A�����ɓs���̂������R�ł����������A�A���r�\���R�͗Y�قɕ�����Ă��܂��B
�Ȃ��Ȃ�A�����L���X�g���k�ɑ��Ă��A���炩�Ɉْ[�ł͂Ȃ������l�X�ɑ��Ă��A�ς��Ȃ��ڗ�Ȕ؍s���s�Ȃ�ꂽ����ł��B
��ɏq�ׂ��悤�ɁA�u�L���v�Ɓu�}�[�_�[�v�͈Ⴄ�Ɣ�����������̏@���w���҂̘b���Љ�܂������A�A���r�\���R�ɂ����Ă͂��������ǂ����Ⴄ�Ƃ����̂ł��傤���B
�ł�����u������Ƒ҂āI�A���͑��v���H�v�ƁA�����������˂����݂���ꂽ���Ȃ����̂́A���̂悤�ȗ��j�I�j����m���Ă�������ł��B
�@�@�@13���I�̓�t�����X�ōs�Ȃ�ꂽ�s�E�̖c��ȃG�s�\�[�h������܂����A�����ł��̘b�ɕ������邱�Ƃ͂�߂Ă����܂��傤�B
�����āA1229�N�̐푈�I���܂łɁA��t�����X�̂�����s�s�͂��ׂĊח������̂ł��B
�@�@�@�푈�I���̔N�A�J�^���h�ɑ���ْ[�R�₪�n�܂�܂����B
�@�@�@�������ʂ����āA�R��̖@��Ɉ�������o���ꂽ�l�X���A�{���ɐ����c�����J�^���h�������̂��A�����̎s���������̂��͍��ƂȂ��Ă͂킩��܂���B
����Ɏ�������ɂ���āA�u���͐_�̋����ɔw���܂����v�Ƃ����ْ[�̎�������������܂����B
�Ȃ��ɂ͎��疳����i��������s���̐l�����܂������A���������l�͍�������ɂ���Đ▽���܂����B�������Ă����Ȃ��Ă��A�Ƃɂ��������҂��Ă����̂ł��B
�@�@�@���ꂪ�c�s�ȍ���Ə��Y���J��Ԃ����A�����̈Í��ٔ��̎n�܂�������鍆�C�ł������Ƃ������Ƃ��ł��܂��B
�����ăJ�^���h�ւْ̈[�R������������Ƃ��āA�ْ[�R��Ƃ������x�����܂�邱�ƂɂȂ����̂ł��B
���̐��x�̓����́A�u�P�v�I�v�u���g�D�v�u�S���ϔC�v�Ƃ����_�ł��B
�܂�ْ[�R��Ƃ����̂́A�ŏ�����A�u���ׂĂ̌����������A�i���Ɉْ[�������܂�v�Ƃ������̂ł����B
�ْ[�R�⊯���ʂ������\�͍ٔ��������ł͂Ȃ��A����̎i�@���x�ł����A�ނ�͌��@�ł���A�x�@�ł���A���Y���ł���A�������ƌ�������߂Đl���E�����߂́A�l�ގj��ő�̎v�z�x�@�Ƃ������ׂ����݂ł����B
�@�@�@���c�O���S���E�X9���́A���̑g�D���҈Ђ�U�邤���߂́u���v���A�����ƒ������邱�Ƃ��Y��܂���ł����B
������ْ[�R�⊯�̊������x����������̒��ɁA�R��ɂ���ď��Y�����ْ[�҂̖v�����Y���܂߂��̂ł��B
����͂��Ă̋��c�C���m�P���e�B�E�X3�����A���r�\���R�ɗp�������@�ł������A���������c�O���S���E�X9���́A���ꂪ�P�v�I�ɓ����悤�ɐ��x�̒��ɖ��ߍ��̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u����Ł@�����̓S�Ɓv�@�ϕĒn�p�l���@�t�H���X�g�o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
*******************************************************************************
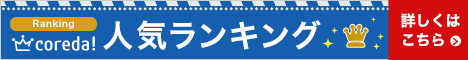

*******************************************************************************
���������n���������w�����ɗ^����S�Ɓx�̓G���{�������@�E
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/index.html#entry-83670623
�@�@�@1198�N�ɃC���m�P���e�B�E�X3�������[�}�@���̈ʂɂ��ƁA�J�^���h�ւ̒e�������߁A1209�N�A���ɓ�t�����X�ɓ����R�𑗂邱�Ƃ����肵�܂����B
�ނ͓����R��g�D����ɂ�����A���[�}�s���̂Ȃ��Ɉْ[�ɑ���{����I�݂ɐ��肽�āA����œ����R�ɂْ͈[�҂̗̒n�ƍ��Y��^���邱�Ƃ�����̂ł��B
���ƘV�ԁi�낤�����j�Ȑ����Ƃł��傤���B�܂�R�l��l�ЂƂ�ɍł����͓I�Ɉْ[�����s�Ȃ킹����@�́A�ނ�̗~�ɉ����邱�Ƃ��ƐS���Ă����̂ł��B
�@�@�@�@���̖��ɂ���đ���ꂽ���̌R���́A�A���r�\���R�ƌĂ�܂����B
�@�@�@����͂͂��߂����t�����X�̃J�^���h�Ƃ����A�L���X�g���k�̓�����ړI�Ƃ��đg�D���ꂽ�ŏ��̏\���R�ł����B
�����Ĉْ[�����́A���̌�20�N�Ԃɓn���ČJ��L����ꂽ�̂ł��B
�A���r�\���R���e�n�ōs�Ȃ����̂́A�Z���̑�s�E�ł����B
�����ł̓J�^���h�������łȂ����Ƃ������Ƃ́A���͂�W������܂���ł����B
�Ȃ��Ȃ�A�����������D���邱�Ƃ��ړI�ɂȂ��Ă����̂ŁA�E�C�ɖ����̓��荞�ޗ]�n�͂Ȃ��A�ނ�͂ނ��낻��������ł��܂����B
���Ƃ��Ζ�����˂ɗ��Ƃ��A���̏ォ�玟�X�Ƒ傫�Ȑ𓊂����ނƂ����؍s���s�Ȃ�ꂽ�̂����̓T�^�ł��傤�B
�@�@�@���̎�����\���R���A���̖ړI�͗̓y�ƍ��Y�̎��D�ł����B
�@�@�@�ނ炪�f�����ً��k��łڂ��Ƃ�����`�������A�����ɓs���̂������R�ł����������A�A���r�\���R�͗Y�قɕ�����Ă��܂��B
�Ȃ��Ȃ�A�����L���X�g���k�ɑ��Ă��A���炩�Ɉْ[�ł͂Ȃ������l�X�ɑ��Ă��A�ς��Ȃ��ڗ�Ȕ؍s���s�Ȃ�ꂽ����ł��B
��ɏq�ׂ��悤�ɁA�u�L���v�Ɓu�}�[�_�[�v�͈Ⴄ�Ɣ�����������̏@���w���҂̘b���Љ�܂������A�A���r�\���R�ɂ����Ă͂��������ǂ����Ⴄ�Ƃ����̂ł��傤���B
�ł�����u������Ƒ҂āI�A���͑��v���H�v�ƁA�����������˂����݂���ꂽ���Ȃ����̂́A���̂悤�ȗ��j�I�j����m���Ă�������ł��B
�@�@�@13���I�̓�t�����X�ōs�Ȃ�ꂽ�s�E�̖c��ȃG�s�\�[�h������܂����A�����ł��̘b�ɕ������邱�Ƃ͂�߂Ă����܂��傤�B
�����āA1229�N�̐푈�I���܂łɁA��t�����X�̂�����s�s�͂��ׂĊח������̂ł��B
�@�@�@�푈�I���̔N�A�J�^���h�ɑ���ْ[�R�₪�n�܂�܂����B
�@�@�@�������ʂ����āA�R��̖@��Ɉ�������o���ꂽ�l�X���A�{���ɐ����c�����J�^���h�������̂��A�����̎s���������̂��͍��ƂȂ��Ă͂킩��܂���B
����Ɏ�������ɂ���āA�u���͐_�̋����ɔw���܂����v�Ƃ����ْ[�̎�������������܂����B
�Ȃ��ɂ͎��疳����i��������s���̐l�����܂������A���������l�͍�������ɂ���Đ▽���܂����B�������Ă����Ȃ��Ă��A�Ƃɂ��������҂��Ă����̂ł��B
�@�@�@���ꂪ�c�s�ȍ���Ə��Y���J��Ԃ����A�����̈Í��ٔ��̎n�܂�������鍆�C�ł������Ƃ������Ƃ��ł��܂��B
�����ăJ�^���h�ւْ̈[�R������������Ƃ��āA�ْ[�R��Ƃ������x�����܂�邱�ƂɂȂ����̂ł��B
���̐��x�̓����́A�u�P�v�I�v�u���g�D�v�u�S���ϔC�v�Ƃ����_�ł��B
�܂�ْ[�R��Ƃ����̂́A�ŏ�����A�u���ׂĂ̌����������A�i���Ɉْ[�������܂�v�Ƃ������̂ł����B
�ْ[�R�⊯���ʂ������\�͍ٔ��������ł͂Ȃ��A����̎i�@���x�ł����A�ނ�͌��@�ł���A�x�@�ł���A���Y���ł���A�������ƌ�������߂Đl���E�����߂́A�l�ގj��ő�̎v�z�x�@�Ƃ������ׂ����݂ł����B
�@�@�@���c�O���S���E�X9���́A���̑g�D���҈Ђ�U�邤���߂́u���v���A�����ƒ������邱�Ƃ��Y��܂���ł����B
������ْ[�R�⊯�̊������x����������̒��ɁA�R��ɂ���ď��Y�����ْ[�҂̖v�����Y���܂߂��̂ł��B
����͂��Ă̋��c�C���m�P���e�B�E�X3�����A���r�\���R�ɗp�������@�ł������A���������c�O���S���E�X9���́A���ꂪ�P�v�I�ɓ����悤�ɐ��x�̒��ɖ��ߍ��̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u����Ł@�����̓S�Ɓv�@�ϕĒn�p�l���@�t�H���X�g�o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
*******************************************************************************
2013�N02��02��
13���I��t�����X�̑�s�E�@�ْ[�����O��
zeranium�̃u���O�@���]��
******************************************************************************
13���I��t�����X�̑�s�E�@�ْ[�����O��@�D
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/index.html#entry-83656962
�@�@�@���[���b�p�����̖����ٔ��̑O�ɂ́A�ْ[�R��Ƃ����Í��ٔ��̑O�j������܂��B�@
�@�@�@�ْ[�Ƃ́A��������O��Ă���Ƃ����Ӗ��ł����A���E�ْ̈[����ْ[�̉Ȋw�҂Ȃǂ̗p�����������錻��ł́A�u�ْ[�v�Ƃ͂���قLj����C���[�W�ł͂���܂���B
�������@���ňْ[�Ƃ����ꍇ�A����͏d��ȈӖ��������Ă���A�Ƃ��Ƀ��[���b�p�����ł͂���͐����ɂ��������ł������̂ł��B
�@�@�@�ْ[�Ƃ������t�������܂ꂽ�̂��肩�ł͂���܂��A�L���X�g�������̂���ɂ��łɈْ[�_�����s�Ȃ��Ă������Ƃ͐���������M�����Ƃ��ł��܂��B
���łɏЉ���悤�ɁA�R���X�^���e�B�k�X���̎���ɃA���E�X�h���ْ[�Ƃ��ꂽ���Ƃ͂��̓T�^�ł��B
�܂苳�`�ɑ��l�ȍl��������߂����邱�Ƃ����e�����A�����Ƃ�����̈ȊO��o�ł��悤�Ƃ��邱�Ƃł��B
��������ŁA���������ł��邩�Ɍ���������̂́A��ɐM�ł͂Ȃ������͂ł��B
�@�@�@�R���X�^���e�B�k�X��邪�A�O�ʈ�̂�������A�^�i�V�E�X�h��i�삵���̂������ł��B
�@�@�@����͎O�ʈ�̂̋��`����A����̈ʊi���_�Ɠ����Ƃ������ƂɂȂ�A����̏h�����p�E���̌��t���A����c�̋c�����A�_�̌��t�ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���̂Ő����I�ɔ��ɗ��p���₷�������Ƃ����܂��B
�@�@�@�R���X�^���e�B�k�X���̖ړI�́A����4�ɕ�������Ă������[�}�鍑���܂Ƃ߁A�����ŗB��̍c��Ƃ��Đꐧ�N�吧���m�����邱�Ƃł����B
���̂��߂ɓ����A�l�C�̏㏸���Ă����L���X�g���𗘗p�����̂ł��B
���̈Ӗ��ŃR���X�^���e�B�k�X��邪�L���X�g���ɋ��߂��̂́A����ւ̒����Ƌ��S�͂ł������͂��ł��B
�O�ʈ�̘_�c�ňْ[�Ƃ��ꂽ�A���E�X�h���A���̌�ǂ̂悤�Ȉ����������͂킸�������L�^�ɂ͎c����Ă��܂��A����ɂ��ƁA�̓y���ɂ����Č��������Q���A�Ƃ���A�\�͂�U����A�E���ꂽ�肵�A���[�}�鍑��ǂ��Ă����܂����B
�@�@�@���Ȃ݂ɓ����A�R���X�^���e�B�k�X���ɑ��铌�̐���ł��������L�j�E�X�́A���̃R���X�^���e�B�k�X�̓����Ɍ������������܂����B
���������|�I�ȕs�l�C�̒��ŁA�킢�ɔs�ꂽ���L�j�E�X�́A�R���X�^���e�B�k�X�ɂ����324�N�ɏ��Y����܂����B
����ɂ�胍�[�}�鍑�͓��ꂳ��A325�N�Ƀj�P�A����c���R���X�^���e�B�k�X����ɂŊJ����A�L���X�g�������[�}�Ŋm�����܂����B
���̂悤���@���ƌ��͂����т��A���ꂪ�����������Ƃ������Ƃ́A���Ȃ킿�@�������͎҂̌��͓����̓���Ƃ��č̗p����邱�Ƃ��Ӗ����܂��B
�@�@�@���[�}�J�g���b�N����̗��j��U��Ԃ�ƁA12���I���܂ł́A�ނ�ɂْ͈[�o�ł��s�Ȃ����ʂȎ�������Ȃ������悤�Ɍ����܂��B
�����������I�ɂ�࣏n���̌�̑��A�ޔp�����K��Ă��܂����B
�����͎s����̖��̐������ڂ݂邱�ƂȂ��A�����͂͒����������Ă��܂����B
����������ŏ@���̖ʂ��猩��ƁA���̎����͋���̌��Ђ����ĂȂ����܂�������ł���A��ʂɁA�@�����̑S������ƌ����鎞�オ�n�܂��Ă��܂����B
�@�@�@�����Ă������������܂��A�Ђǂ����Ƒޔp�̒��ɂ���܂����B
�@�@�@���E�̔�����E�҂���w���͂����Ƃ͓��풃�ю��ł���A����̏������͓�m�Ə����M�k�Ƃ̏�̏�Ɖ����A���E�҂͎������₷���Ƃ���ɔM�S�ł����B
�_���e��13���I�ɁA�w�_�Ȓn���ҁx�ŋt���܂ɒ݂邳�ꂽ���c�j�R���E�X3���i�݈�1277�|1280�j��`���A�_���e�Ɠ�����̋��c�{�j�t�@�e�B�E�X8�����ނƓ����^�������ǂ邾�낤�Ɨ\�����܂����B
�܂�_���e�͂��̈�߂ɁA����̌��͂ւ̍������\�����̂ł��B
�_���e�́u�_�Ȓn���ҁv�́A���O�������̋���ɑ��ĕ����Ă����{��̋������A����ɓ`���Ă��܂��B
�@�@�@�����̕�����ނɂƂ������l�b�T���X�̊G��́A�_�ɋ~�������߂�l�Ԃ̌�������Y��`�������̂������������܂��B
�Ȃ������������悤�ȃe�[�}�ŁA���������ǂ남�ǂ낵���^�b�`�̊G���肪�`���ꂽ�̂��A�s�v�c�Ɏv���Ă����l�������ł��傤�B
���̗��R���A���l�b�T���X�G��̍�҂������A���S�Ƀ_���e�Ɠ����悤�ȓ{�������A�����n�쓮�@�ɏ����ĊG�M�������Ă�������ł��B
�@�@�@���̂悤�ȏ�ԂŐl�X�������オ��A�@�����v�^�����N����͓̂��R�̗���ƌ���˂Ȃ�܂���B
���ْ͈[�R��Ə@�����v�́A���Ă���Ȃ��W�ɂ���܂��B
����Ȃ��ْ[�R����s�Ȃ��̂��Ƃ����A���̖ړI�͋���̌��Ђ����A�g�D��h�q���邱�Ƃł��B
����͋���ɕs���������ْ[�҂Ƃ����M�k�������A����̑���������悤�Ȃ��Ƃ��咣���Ă�������ł����B
��������Ƃ����ƌ��͂������������́A�����ɋ�������Ƃ��ېg�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł�����܂����B
�@�@�@�c���ȍ���Ɛ��܂����s�E�̍s�Ȃ�ꂽ�����ْ̈[�R��́A12���I�̓�t�����X�Ŏn�܂�܂����B
�����̓�t�����X�ł́A�̎��s���̓��[�}�@���̌��Ђ���͋�����u���A���玩�R�ȕ��������ł��܂����B
���̒n�Ől�X�̊ԂɐZ�����Ă����̂��A�J�^���h�Ƃ�����L���X�g���̈�h�ł����B
�J�^���h�́u�J�^���v�Ƃ́A�M���V����Łu����Ȃ���́v���Ӗ����܂��B
�n��ɂ���Ă̓A���r�h�Ƃ��o�^���j�h�Ƃ��Ă�Ă��܂����B
�J�^���h���̂��̂����ł��Ă��܂����̂ŁA�ނ�̎v�z�̏ڍׂ͂킩��܂��A�����ے肵�A�ǂ��ŋF���Ă��M�ɕς��͂Ȃ��Ƃ���M���������Ă��܂����B
�@�@�@���[�}�J�g���b�N����ł́A�F��͋���ōs�Ȃ����̂ƒ�߂Ă��܂����B
�@�@�@�܂�V���͓T��ɑ���A�����͏@���w���҂ɂ���Ď���s������̂ƌ��߂��Ă����̂ł��B
���ꂪ����̍������Ђ��ے����Ă���A�M�҂ւ̎x�z�����������i�ł�����܂����B
���̌��ʁA�_�ւ̐M�̂͂������̊Ԃɂ�����ɑ����]�ւƕώ����A�����ɁA�M�̏�ł���͂��̋���`������̐M�Ƌ��ׂ��A���邢�͐����̏�ւƑ��Ă��܂��܂����B
�@�@�@�J�^���h���͂��߂Ƃ���@�����v�h�́A������������̂�������M��c�߂�Ƃ������̖{���ɁA��������C�Â��Ă��܂����B
���m�̗��j�m���t�B�N�V�����Ȃǂł́A�@�����v�^�����u�����ے肷��^���v�Ƃ����悤�ɁA������1�s�ŕЂÂ���L�q���������߂ɓ����̏��킩�炸�A�^������������Ă͂��Ȃ��悤�ł��B
�܂��@�����v�́A�M����邱�ƂƁA����Ƃ�����ŋF�邱�ƂƂ̖����ɋC�Â����l�X�ɂ��A�M�̌��_��A���o���_�ɂȂ��Ă����̂ł��B
�M�̖{���ɂ��čl����A�F��ꏊ�͊W�Ȃ��͂��ł��B
�����Ă��̍s��������́A������������͕K�v�Ȃ��Ƃ����I�_�Ȃ̂ł��B���ꂪ�A�u�@�����v�^���������ے肵���v�Ƃ����Ă���v���Ȃ̂ł��B
�@�@�@���[�}�J�g���b�N����ɂƂ��āA���������@�����v�҂����̘_���́A���ɓs���̈������̂ł����B
�F��̏�Ƃ��Ă̋�����^���M�҂�������ƁA����̌��Ђ͕���Ă��܂��܂��B
�M�������ƂƋ���͉��̊W���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA����܂ʼnc�X�Ǝ���s���Ă����V���͉��̂��߂��Ƃ������ƂɂȂ�A�M�̎ז������Ă���̂͋���̂ق��ł͂Ȃ����Ƃ����ɘ_�����藧���܂��B
����ɂ��̘_���̌��ɖ��O�I�N���N����A�L���X�g���������Ƃ��鐭�����͂̌��Ђ�����Ă��܂��܂��B
�@�@�@�����Ə@���͋��͂������A���O�����߁A���Ƃ����Ă��܂����B
�@�@�@���ꂪ�R���X�^���e�B�k�X���ȗ��������Ă��������V�X�e���ł����B
����������̕��s�Ɣ��肪���������Ȃ��ŁA�M�̌��_�ɗ����Ԃ�Ƃ����_�������܂�A���ꂪ���k�ɍ��グ���Ă�������̃V�X�e���̕ǂɋT�����ꂽ�̂ł��B
�M�̖{�������߂���߂�قNj���ے肳���킯�ł�����A���̘_�������j��͎͂��ɋ��͂ł��B
���}�Ɍ����A����������ƁA�����Ə@���ɂ�铝���V�X�e��������̂ł��B
������A���͎҂��ق��Č��Ă���͂��͂���܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u����Ł@�����̓S�Ɓv�@�ϕĒn�p�l���@�t�H���X�g�o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
�@�@�@
*******************************************************************************

@Petit_Soleil17 ����̃c�C�[�g
******************************************************************************
13���I��t�����X�̑�s�E�@�ْ[�����O��@�D
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/index.html#entry-83656962
�@�@�@���[���b�p�����̖����ٔ��̑O�ɂ́A�ْ[�R��Ƃ����Í��ٔ��̑O�j������܂��B�@
�@�@�@�ْ[�Ƃ́A��������O��Ă���Ƃ����Ӗ��ł����A���E�ْ̈[����ْ[�̉Ȋw�҂Ȃǂ̗p�����������錻��ł́A�u�ْ[�v�Ƃ͂���قLj����C���[�W�ł͂���܂���B
�������@���ňْ[�Ƃ����ꍇ�A����͏d��ȈӖ��������Ă���A�Ƃ��Ƀ��[���b�p�����ł͂���͐����ɂ��������ł������̂ł��B
�@�@�@�ْ[�Ƃ������t�������܂ꂽ�̂��肩�ł͂���܂��A�L���X�g�������̂���ɂ��łɈْ[�_�����s�Ȃ��Ă������Ƃ͐���������M�����Ƃ��ł��܂��B
���łɏЉ���悤�ɁA�R���X�^���e�B�k�X���̎���ɃA���E�X�h���ْ[�Ƃ��ꂽ���Ƃ͂��̓T�^�ł��B
�܂苳�`�ɑ��l�ȍl��������߂����邱�Ƃ����e�����A�����Ƃ�����̈ȊO��o�ł��悤�Ƃ��邱�Ƃł��B
��������ŁA���������ł��邩�Ɍ���������̂́A��ɐM�ł͂Ȃ������͂ł��B
�@�@�@�R���X�^���e�B�k�X��邪�A�O�ʈ�̂�������A�^�i�V�E�X�h��i�삵���̂������ł��B
�@�@�@����͎O�ʈ�̂̋��`����A����̈ʊi���_�Ɠ����Ƃ������ƂɂȂ�A����̏h�����p�E���̌��t���A����c�̋c�����A�_�̌��t�ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���̂Ő����I�ɔ��ɗ��p���₷�������Ƃ����܂��B
�@�@�@�R���X�^���e�B�k�X���̖ړI�́A����4�ɕ�������Ă������[�}�鍑���܂Ƃ߁A�����ŗB��̍c��Ƃ��Đꐧ�N�吧���m�����邱�Ƃł����B
���̂��߂ɓ����A�l�C�̏㏸���Ă����L���X�g���𗘗p�����̂ł��B
���̈Ӗ��ŃR���X�^���e�B�k�X��邪�L���X�g���ɋ��߂��̂́A����ւ̒����Ƌ��S�͂ł������͂��ł��B
�O�ʈ�̘_�c�ňْ[�Ƃ��ꂽ�A���E�X�h���A���̌�ǂ̂悤�Ȉ����������͂킸�������L�^�ɂ͎c����Ă��܂��A����ɂ��ƁA�̓y���ɂ����Č��������Q���A�Ƃ���A�\�͂�U����A�E���ꂽ�肵�A���[�}�鍑��ǂ��Ă����܂����B
�@�@�@���Ȃ݂ɓ����A�R���X�^���e�B�k�X���ɑ��铌�̐���ł��������L�j�E�X�́A���̃R���X�^���e�B�k�X�̓����Ɍ������������܂����B
���������|�I�ȕs�l�C�̒��ŁA�킢�ɔs�ꂽ���L�j�E�X�́A�R���X�^���e�B�k�X�ɂ����324�N�ɏ��Y����܂����B
����ɂ�胍�[�}�鍑�͓��ꂳ��A325�N�Ƀj�P�A����c���R���X�^���e�B�k�X����ɂŊJ����A�L���X�g�������[�}�Ŋm�����܂����B
���̂悤���@���ƌ��͂����т��A���ꂪ�����������Ƃ������Ƃ́A���Ȃ킿�@�������͎҂̌��͓����̓���Ƃ��č̗p����邱�Ƃ��Ӗ����܂��B
�@�@�@���[�}�J�g���b�N����̗��j��U��Ԃ�ƁA12���I���܂ł́A�ނ�ɂْ͈[�o�ł��s�Ȃ����ʂȎ�������Ȃ������悤�Ɍ����܂��B
�����������I�ɂ�࣏n���̌�̑��A�ޔp�����K��Ă��܂����B
�����͎s����̖��̐������ڂ݂邱�ƂȂ��A�����͂͒����������Ă��܂����B
����������ŏ@���̖ʂ��猩��ƁA���̎����͋���̌��Ђ����ĂȂ����܂�������ł���A��ʂɁA�@�����̑S������ƌ����鎞�オ�n�܂��Ă��܂����B
�@�@�@�����Ă������������܂��A�Ђǂ����Ƒޔp�̒��ɂ���܂����B
�@�@�@���E�̔�����E�҂���w���͂����Ƃ͓��풃�ю��ł���A����̏������͓�m�Ə����M�k�Ƃ̏�̏�Ɖ����A���E�҂͎������₷���Ƃ���ɔM�S�ł����B
�_���e��13���I�ɁA�w�_�Ȓn���ҁx�ŋt���܂ɒ݂邳�ꂽ���c�j�R���E�X3���i�݈�1277�|1280�j��`���A�_���e�Ɠ�����̋��c�{�j�t�@�e�B�E�X8�����ނƓ����^�������ǂ邾�낤�Ɨ\�����܂����B
�܂�_���e�͂��̈�߂ɁA����̌��͂ւ̍������\�����̂ł��B
�_���e�́u�_�Ȓn���ҁv�́A���O�������̋���ɑ��ĕ����Ă����{��̋������A����ɓ`���Ă��܂��B
�@�@�@�����̕�����ނɂƂ������l�b�T���X�̊G��́A�_�ɋ~�������߂�l�Ԃ̌�������Y��`�������̂������������܂��B
�Ȃ������������悤�ȃe�[�}�ŁA���������ǂ남�ǂ낵���^�b�`�̊G���肪�`���ꂽ�̂��A�s�v�c�Ɏv���Ă����l�������ł��傤�B
���̗��R���A���l�b�T���X�G��̍�҂������A���S�Ƀ_���e�Ɠ����悤�ȓ{�������A�����n�쓮�@�ɏ����ĊG�M�������Ă�������ł��B
�@�@�@���̂悤�ȏ�ԂŐl�X�������オ��A�@�����v�^�����N����͓̂��R�̗���ƌ���˂Ȃ�܂���B
���ْ͈[�R��Ə@�����v�́A���Ă���Ȃ��W�ɂ���܂��B
����Ȃ��ْ[�R����s�Ȃ��̂��Ƃ����A���̖ړI�͋���̌��Ђ����A�g�D��h�q���邱�Ƃł��B
����͋���ɕs���������ْ[�҂Ƃ����M�k�������A����̑���������悤�Ȃ��Ƃ��咣���Ă�������ł����B
��������Ƃ����ƌ��͂������������́A�����ɋ�������Ƃ��ېg�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł�����܂����B
�@�@�@�c���ȍ���Ɛ��܂����s�E�̍s�Ȃ�ꂽ�����ْ̈[�R��́A12���I�̓�t�����X�Ŏn�܂�܂����B
�����̓�t�����X�ł́A�̎��s���̓��[�}�@���̌��Ђ���͋�����u���A���玩�R�ȕ��������ł��܂����B
���̒n�Ől�X�̊ԂɐZ�����Ă����̂��A�J�^���h�Ƃ�����L���X�g���̈�h�ł����B
�J�^���h�́u�J�^���v�Ƃ́A�M���V����Łu����Ȃ���́v���Ӗ����܂��B
�n��ɂ���Ă̓A���r�h�Ƃ��o�^���j�h�Ƃ��Ă�Ă��܂����B
�J�^���h���̂��̂����ł��Ă��܂����̂ŁA�ނ�̎v�z�̏ڍׂ͂킩��܂��A�����ے肵�A�ǂ��ŋF���Ă��M�ɕς��͂Ȃ��Ƃ���M���������Ă��܂����B
�@�@�@���[�}�J�g���b�N����ł́A�F��͋���ōs�Ȃ����̂ƒ�߂Ă��܂����B
�@�@�@�܂�V���͓T��ɑ���A�����͏@���w���҂ɂ���Ď���s������̂ƌ��߂��Ă����̂ł��B
���ꂪ����̍������Ђ��ے����Ă���A�M�҂ւ̎x�z�����������i�ł�����܂����B
���̌��ʁA�_�ւ̐M�̂͂������̊Ԃɂ�����ɑ����]�ւƕώ����A�����ɁA�M�̏�ł���͂��̋���`������̐M�Ƌ��ׂ��A���邢�͐����̏�ւƑ��Ă��܂��܂����B
�@�@�@�J�^���h���͂��߂Ƃ���@�����v�h�́A������������̂�������M��c�߂�Ƃ������̖{���ɁA��������C�Â��Ă��܂����B
���m�̗��j�m���t�B�N�V�����Ȃǂł́A�@�����v�^�����u�����ے肷��^���v�Ƃ����悤�ɁA������1�s�ŕЂÂ���L�q���������߂ɓ����̏��킩�炸�A�^������������Ă͂��Ȃ��悤�ł��B
�܂��@�����v�́A�M����邱�ƂƁA����Ƃ�����ŋF�邱�ƂƂ̖����ɋC�Â����l�X�ɂ��A�M�̌��_��A���o���_�ɂȂ��Ă����̂ł��B
�M�̖{���ɂ��čl����A�F��ꏊ�͊W�Ȃ��͂��ł��B
�����Ă��̍s��������́A������������͕K�v�Ȃ��Ƃ����I�_�Ȃ̂ł��B���ꂪ�A�u�@�����v�^���������ے肵���v�Ƃ����Ă���v���Ȃ̂ł��B
�@�@�@���[�}�J�g���b�N����ɂƂ��āA���������@�����v�҂����̘_���́A���ɓs���̈������̂ł����B
�F��̏�Ƃ��Ă̋�����^���M�҂�������ƁA����̌��Ђ͕���Ă��܂��܂��B
�M�������ƂƋ���͉��̊W���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA����܂ʼnc�X�Ǝ���s���Ă����V���͉��̂��߂��Ƃ������ƂɂȂ�A�M�̎ז������Ă���̂͋���̂ق��ł͂Ȃ����Ƃ����ɘ_�����藧���܂��B
����ɂ��̘_���̌��ɖ��O�I�N���N����A�L���X�g���������Ƃ��鐭�����͂̌��Ђ�����Ă��܂��܂��B
�@�@�@�����Ə@���͋��͂������A���O�����߁A���Ƃ����Ă��܂����B
�@�@�@���ꂪ�R���X�^���e�B�k�X���ȗ��������Ă��������V�X�e���ł����B
����������̕��s�Ɣ��肪���������Ȃ��ŁA�M�̌��_�ɗ����Ԃ�Ƃ����_�������܂�A���ꂪ���k�ɍ��グ���Ă�������̃V�X�e���̕ǂɋT�����ꂽ�̂ł��B
�M�̖{�������߂���߂�قNj���ے肳���킯�ł�����A���̘_�������j��͎͂��ɋ��͂ł��B
���}�Ɍ����A����������ƁA�����Ə@���ɂ�铝���V�X�e��������̂ł��B
������A���͎҂��ق��Č��Ă���͂��͂���܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u����Ł@�����̓S�Ɓv�@�ϕĒn�p�l���@�t�H���X�g�o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
�@�@�@
*******************************************************************************
@Petit_Soleil17 ����̃c�C�[�g
�@���̋��`�͏�Ɍ��͎҂̓s���ō����@
zeranium�̃u���O ���]��
*******************************************************************************
�@���̋��`�͏�Ɍ��͎҂̓s���ō����@�C
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/index.html#entry-83635885
�@�@�@�����N���̊Ԃɐ����́A�p����͂��߂��܂��܂Ȑ��E�̌��t�ɖ|��Ă����܂����B
�@�@�@�C�O�̗��s��̃z�e���Ȃǂɒu���Ă��鐹���́A�����Ă��͉p��̂��̂ł��B
�L���X�g���ɓ���݂̂Ȃ����{�l�͂��̗��R���A�u�p��l�����������炾�낤�v�ƍl���邩������܂��A�p��̐������������Ă��邱�Ƃɂ́A�����ƍ��{�I�ȗ��R������̂ł��B
�@�@�@�p��̐����Ƃ����̂́A����͒ʏ�C�M���X������̐����̂��ƂŁAKJV�����Ƃ����܂��B
�v���e�X�^���g�̐����͉p��ŏ����ꂽ���̂ł���A����ȊO�͐����������ł͂Ȃ��Ƃ���������̂ł��B
�����Ď��̓J�g���b�N�̐������A�p��̐�����KJV�������x�[�X�ɂ��Ă��܂��B
����KJV�Ƃ�King James Version �̗��ł��B
���Ƃ��Ɓw�V���x�̓M���V����ŏ�����Ă��܂������A���ꂪ���e����ɖ|��čL�܂��Ă����܂����B
���������[�}�J�g���b�N�������ɐ����ƒ�߂Ă���̂́A���܂ł����e����ŏ����ꂽ�����ł��B
����Ɠ����Ӗ��ŁA�����̃v���e�X�^���g��������ƒ�߂Ă���̂́A�p��ŏ����ꂽ�����݂̂Ȃ̂ł��B
���Ƃ���A�N���p��̐�����|�A�Ҏ[�����̂����d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ�܂��B
�@�@�@�v���e�X�^���g�̉p�ꐹ�����������̂́A�X�R�b�g�����h��C���O�����h�A�A�C�������h�����߂��W�F�[���Y1���i�`���[���Y�E�W�F�[���Y�E�X�`�����[�g�j�ł��B
�ނ�1611�N�ɁA�C�M���X������̓T��Ɏg���Ƃ������R����A�w�Ԓ���x�iKJV�����j������܂����B
���ꂪ������ȑO�܂ł́A�C�M���X�ɂ́u�W���l�[�u�����v�ƌĂ��p��������y���Ă���A�l�X�ɐe���܂�Ă��܂����B
����͏@�����v�^���ւ̔��Q��ăW���l�[�u�ɓn�����A�J�����@���h�̐_�w�҂����ɂ���Ė|�ꂽ���̂ł��B
�@�@�@�����̉p��ɂ������̐s���Ȃ����j������܂��B
�@�@�@�ŏ��̉p��́A�W�����E�E�B�N���t�ɂ��p���i1408�N�j�A���̎����E�B���A���E�e�B���_���ɂ��p���i1525�N�j�ł��B
�E�B�N���t�ƃe�B���_���͂Ƃ��ɏ@�����v�̃��[�_�[�I���݂ł����B
����Ȍ�́A�w�}�V���[�Ő����x�A�w�W���l�[�u�����x�A�Ǝ��X���s����܂������A�w�Ԓ���x�̓e�B���_���Ő����ɑ傫�ȉe�����Ă��܂��B
�@�@�@�W�F�[���Y1���ɁA���炽�߂ĉp�������邱�Ƃ����ӂ��������̂����ł��������A�ڂ�������͂킩��܂���B
�������̍����������A�����ɕ��]���Ȃ��Ɗ������W�F�[���Y1���́A����܂ł̐������Ђǂ��������Ƃ����Ă��܂��B
����͂܂��ɏ@�����v�̔g�ɐ���A�C�M���X�̐����̎��Ԃ��傫�ȉ��ƂƂ��ɉ��n�߂Ă��܂����B
�ł������W�F�[���Y1�����A����̗͂ŐV�����������߂邱�Ƃ����͂�����Ɋg�傷�铹�ł���A�ƍl�������Ƃ͑z���ɓ����܂���B
�L���O�E�W�F�[���Y1���̈���
�@�@�@54�l�̐_�w�҂������A�ǂ�قǐ��T�̋����ɒ����ł��낤�Ƃ����ɂ���A�ނ�̓W�F�[���Y1���̐����I��]�̎�̕��ŗx�炳��Ă����ɂ����܂���B
�����Ď��ۂɃW�F�[���Y1���́A�����ɓs���̂������t���u�����Ɓv�����ɔE�э��܂����̂ł��B
���Ƃ��A�u���A�E�����ƂȂ���v�Œm����}�^�C19�F18�́A�J�g���b�N�̐����ł́AThou shalt do not kill �ƂȂ��Ă��܂����A�w�Ԓ���x�ł́AThou shalt do not murder �ƂȂ��Ă���Akill �� murder �ɕς���Ă��܂��B
���Ƃ��Ƃ̃M���V����ł́@�Ӄ̓˃Ã҃ցiphoneuo�j�Ƃ����P��� kill�@��\����ʖ����ł��B
���������̐_���F�߂� kill �� murder �ł͂Ȃ��Ƃ�����̂ŁA�܂��ɖ�������\���R�̘_���ł���A���ꂪ�����̕����ɕ\���ꂽ�̂ł��B
�@�@�@�����ăC�M���X�̍������A�����J�ɈڏZ�����s���[���^���܂ł��A���̐������g���܂����B
�A�����J�C���f�B�A���̋s�E���܂��� murder�ł͂Ȃ� kill �ł����_�� murder �͋ւ��Ă��Ă��A kill �͋ւ��Ă��Ȃ��Ƃ����_���ōs�Ȃ�ꂽ�̂ł��傤�B
�������A���������̘_���������������܂��B
�@�@�@�u����Ȕn���ȁv�Ǝv����������܂��A�����[�E�L���O�E���C���̃g�[�N�ԑg�ōs�Ȃ�ꂽ�c�_�������悤�ɁA�����͊m���ɂ����Ȃ��Ă��܂��B
�����ďA�C���ɗՂޗ��̃A�����J�哝�̂́u�L���v���m�肷��o�C�u���ɕЎ��u���A�u�w���v�E�~�[�E�S�b�h�v�Ɛ鐾���s�Ȃ��̂ł��B
�܂��A���Ƃ��Ɓu����v�͉p��� congregation�@�ƌ����܂����A������C�M���X����������� church�@�ɕς����̂̓W�F�[���Y1���ł��B
�ł�����v���e�X�^���g�̊J�c�́A�W�F�[���Y1���ƌ����Ă������̂ł��B
���̓W�F�[���Y1���ɂ������ς̗��R���A�ނ̌l�I���R���琶�܂ꂽ�ƍl���Ă���̂ł����A����͌�Ŗ��炩�ɂ��Ă����܂��B
�@���͌�����Ȃ�
�@�@�@���āA�����܂ł̘b�ŏd�v�ȓ_�́A�@���̋��`�Ƃ������̂́A���̎���ɂ����͎҂ɓs���̂����悤�ɏ����c����Ă���Ƃ������Ƃł��B
�����ĕ����Ƃ��ď����ꂽ���`�́A�Ȋw�_���̂悤�ɍ��ǂ���A������邱�ƂȂ��A���̊Ԃɂ��l�X�̐S�ɍ��܂�Ă����܂��B
�Ȃ������Ȃ����Ƃ����A�@���͂��Ƃ��ƌ��ł��Ȃ����̂ł���A�u���̕����͐��������ǁA�S�̓I�ɂ͊Ԉ���Ă���v�Ƃ������ƂɂȂ�A���͂₻��͐M��������̂ł͂Ȃ��A�ӏ]����M�҂����̋��߂ɉ���������̂ł͂Ȃ�����ł��B
�@�@�@�~�������߂�l�قǁA�x���₷�����̂͂���܂���B
�@�@�@���ɍ���A�̂ǂ���肪�o��قǂ������~�����Ǝv���Ă���l�قǁA���\���x����₷���Ƃ����̂͂��̎�����ς��܂���B
�������Ƃ��@���ɋ~�������߂�l�ɂ�������̂ł��B
�Ȃ������ꂽ���`��ӖړI�ɐM�p���邩�Ƃ����A����͑��l��M���Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�M�p�ł���Ώۂ��~�����ƍl���Ă��邩��ł��B
�܂��ŏ��ɁA���ׂĂ̂��Ƃ��^��
�S�����ĂA���̂悤�ȐȋC�����͂����ɏ����ĂȂ��Ȃ�܂��B
�����Ȃ�ƁA����̔��f�ŐM�p�ł�����̂�����悤�ƑO�ɏo�鎩�M���A�t�ɐS�ɖ����Ă���͂��ł��B
�@�@�@��������Ȃ��S�ɍ�p����̂́A����܂ł���ɏ@���ł���A���t�ł����B
�@�@�@�����Ă��̍�p���������A�����������̂��A�����ꂽ���t�ł���A������ꂽ���t�ł����B
�O�[�e���x���N�̈���p�ɂ�锭���́A�l�Ԃ��m�����l�����邤���ŁA����͋ɂ߂đ傫�Ȗ������ʂ������͎̂����ł��B
���������̔��ʁA����p�́A�����̃��[���b�p�̐l�X�̐S�Ɍ�܂����Œ�ϔO��A���t����������ʂ������̂ł��B
�w�����ɗ^����S�Ɓx�Ƃ����������J��Ԃ���������邱�Ƃɂ���āA��܂����Œ�ϔO���L�߂��Ă����Ƃ����A���̑��ʂ����݂��܂����B
���͎҂Ə@���͂��̌��ʂ𗘗p���A���̏������ł��d�˂�ɂ�āA������肪���悢��҈Ђ�U����Ă������̂͋��R�ł͂���܂���B
�@�@�@�w�����ɗ^����S�Ɓx���x�X�g�Z���[�ɂȂ�ƁA�����Ɋւ��鏑���͎��X�Ɛ��ݏo����Ă����A���̈���W�F�[���Y1���̎�ɂȂ�w�f���m���W�[�x�i�����w�j�ł��B
19���I�ɂȂ�Ɩ������͏I�����܂������A�f���m���W�[�̗���͎c��܂����B
�{�[�h���[���́w���̉x�Ȃǂ̈������w�́A�܂��ɂ�����p�����̂ł����B
�܂��t���C�g���A���_���͊w���m�������̂��A�����������ł���Ǝ��̂���l�X�̐S�����A�𖾂��悤�ƍl�������Ƃ����[�ł������̂ł��B
���̈Ӗ��ŁA�������̓��[���b�p�Љ�̌`�������E�������ɑ傫�Ȏ����������A�Ƃ����w�E������܂��B
�@�@�@���āA����ɂ�����IT�̔����́A�O�[�e���x���N�ɂ�����p�ɕC�G����Ƃ����Ă��܂��B
���̉��b�ɗ����鎄�����́A�O���̐��{��V���A���W�I�A�e���r�A�܂��l���B�e�����f���Ɏ���܂ŁA�D���Ȃ悤�ɐڂ��A�ۑ����A���H���邱�Ƃ܂łł���悤�ɂȂ�܂����B
�����������́A���Ƃ��܂ޑ吨�̐l�X�̖ڂƂ����t�B���^�[��ʂ��āA��܂������͏C������A��������Ă����܂��B
���̌��ʎ�������IT�ȑO�ɔ�ׂ�ƁA�͂邩�ɐ����������m������������ɕ�点��悤�ɂȂ�܂����B
���̎���������s�Ȃ��l�Ԃ�����
�@�@�@�������Ȃ���A����͕\�̘b�ł���A�����ɂ͕K�����\�����݂��܂��B
�@�@�@���[���b�p�̒����ɃO�[�e���x���N�̈���p�������炳�ꂽ���Ƃ��\���Ƃ���ƁA���̈���p�ɂ���āw�����ɗ^����S�Ɓx�����������炵�����̂����̐��E�ł���A����͌���ɂ����Ă����݂��Ă��܂��B
����́A���Ƃ��܂ߑ吨�̐l�X�ɂ���Č�����Ȃ����ł���A�Ȃ��ł��Ӑ}�I�Ȍ�U����A���]����ތ��͎҂ɂ���čs�Ȃ���g�D�I�ȏ��̐��E�ł��B
�@�@�@�]������A�C���^�[�l�b�g�̐��E�ŋN���邱���������ɑ��āA����1���\�[�X���m�F������A���Έӌ��╡���̈ӌ����ᖡ�����e���V�[�̃L�����y�[�����s�Ȃ��Ă��܂����B
��������e���V�[�́A�����ȃT�C�g����K�g���u���Ɋ������܂�Ȃ��Ƃ������x�̂��Ƃɂ͖𗧂Ƃ��Ă��A���͎҂ɂ��Ӑ}�I�ȏ��ɑ����ł��ł�����̂ł͂���܂���B
�Ȃ��Ȃ���̐��E�́A��₂��ꂽ1���\�[�X��A�ꌩ����Ɣ��Έӌ��̂悤�ɓǂ߂�u�U�������^���ӌ��v��A���邢�͈ꌩ����Ǝ^���ӌ��̂悤�ɓǂ߂�u�U���������Έӌ��v�Ȃǂ���������A����Ԑ��E������ł��B
�@�@�@�������c�C�b�^�[�̓o��ɂ���āA���������U�����͂Ȃ�����I���ɗ��ʂ�����܂��B
�_�����������A����ɑi����u�Ԃ₫�v�́A���_�┽���قƂ�ǎt���܂���B
��܂��Ă��邱�Ƃ��Ƃ��߂Ă��A�u�Ԃ₢�������Ȃ���A���������v�A�ŏI���ł��B
����͌���ɖ�����肪���s����A���ɑ傫�Ȋ��I�����ł��B
����𗘗p���錠�͎҂͂��łɌ���Ă��邵�A���̓����͍���v�X�����ɂȂ��Ă����ł��傤�B
����ɂ��Ă͖��炩�ɂ��Ă����܂����A���̂��߂ɂ����[���b�p�����ɋN�������������ɂ��āA���������[���l�@��i�߂�K�v������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u����Ł@�����̓S�Ɓv�@�ϕĒn�p�l���@�t�H���X�g�o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
*******************************************************************************


*******************************************************************************
�@���̋��`�͏�Ɍ��͎҂̓s���ō����@�C
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/index.html#entry-83635885
�@�@�@�����N���̊Ԃɐ����́A�p����͂��߂��܂��܂Ȑ��E�̌��t�ɖ|��Ă����܂����B
�@�@�@�C�O�̗��s��̃z�e���Ȃǂɒu���Ă��鐹���́A�����Ă��͉p��̂��̂ł��B
�L���X�g���ɓ���݂̂Ȃ����{�l�͂��̗��R���A�u�p��l�����������炾�낤�v�ƍl���邩������܂��A�p��̐������������Ă��邱�Ƃɂ́A�����ƍ��{�I�ȗ��R������̂ł��B
�@�@�@�p��̐����Ƃ����̂́A����͒ʏ�C�M���X������̐����̂��ƂŁAKJV�����Ƃ����܂��B
�v���e�X�^���g�̐����͉p��ŏ����ꂽ���̂ł���A����ȊO�͐����������ł͂Ȃ��Ƃ���������̂ł��B
�����Ď��̓J�g���b�N�̐������A�p��̐�����KJV�������x�[�X�ɂ��Ă��܂��B
����KJV�Ƃ�King James Version �̗��ł��B
���Ƃ��Ɓw�V���x�̓M���V����ŏ�����Ă��܂������A���ꂪ���e����ɖ|��čL�܂��Ă����܂����B
���������[�}�J�g���b�N�������ɐ����ƒ�߂Ă���̂́A���܂ł����e����ŏ����ꂽ�����ł��B
����Ɠ����Ӗ��ŁA�����̃v���e�X�^���g��������ƒ�߂Ă���̂́A�p��ŏ����ꂽ�����݂̂Ȃ̂ł��B
���Ƃ���A�N���p��̐�����|�A�Ҏ[�����̂����d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ�܂��B
�@�@�@�v���e�X�^���g�̉p�ꐹ�����������̂́A�X�R�b�g�����h��C���O�����h�A�A�C�������h�����߂��W�F�[���Y1���i�`���[���Y�E�W�F�[���Y�E�X�`�����[�g�j�ł��B
�ނ�1611�N�ɁA�C�M���X������̓T��Ɏg���Ƃ������R����A�w�Ԓ���x�iKJV�����j������܂����B
���ꂪ������ȑO�܂ł́A�C�M���X�ɂ́u�W���l�[�u�����v�ƌĂ��p��������y���Ă���A�l�X�ɐe���܂�Ă��܂����B
����͏@�����v�^���ւ̔��Q��ăW���l�[�u�ɓn�����A�J�����@���h�̐_�w�҂����ɂ���Ė|�ꂽ���̂ł��B
�@�@�@�����̉p��ɂ������̐s���Ȃ����j������܂��B
�@�@�@�ŏ��̉p��́A�W�����E�E�B�N���t�ɂ��p���i1408�N�j�A���̎����E�B���A���E�e�B���_���ɂ��p���i1525�N�j�ł��B
�E�B�N���t�ƃe�B���_���͂Ƃ��ɏ@�����v�̃��[�_�[�I���݂ł����B
����Ȍ�́A�w�}�V���[�Ő����x�A�w�W���l�[�u�����x�A�Ǝ��X���s����܂������A�w�Ԓ���x�̓e�B���_���Ő����ɑ傫�ȉe�����Ă��܂��B
�@�@�@�W�F�[���Y1���ɁA���炽�߂ĉp�������邱�Ƃ����ӂ��������̂����ł��������A�ڂ�������͂킩��܂���B
�������̍����������A�����ɕ��]���Ȃ��Ɗ������W�F�[���Y1���́A����܂ł̐������Ђǂ��������Ƃ����Ă��܂��B
����͂܂��ɏ@�����v�̔g�ɐ���A�C�M���X�̐����̎��Ԃ��傫�ȉ��ƂƂ��ɉ��n�߂Ă��܂����B
�ł������W�F�[���Y1�����A����̗͂ŐV�����������߂邱�Ƃ����͂�����Ɋg�傷�铹�ł���A�ƍl�������Ƃ͑z���ɓ����܂���B
�L���O�E�W�F�[���Y1���̈���
�@�@�@54�l�̐_�w�҂������A�ǂ�قǐ��T�̋����ɒ����ł��낤�Ƃ����ɂ���A�ނ�̓W�F�[���Y1���̐����I��]�̎�̕��ŗx�炳��Ă����ɂ����܂���B
�����Ď��ۂɃW�F�[���Y1���́A�����ɓs���̂������t���u�����Ɓv�����ɔE�э��܂����̂ł��B
���Ƃ��A�u���A�E�����ƂȂ���v�Œm����}�^�C19�F18�́A�J�g���b�N�̐����ł́AThou shalt do not kill �ƂȂ��Ă��܂����A�w�Ԓ���x�ł́AThou shalt do not murder �ƂȂ��Ă���Akill �� murder �ɕς���Ă��܂��B
���Ƃ��Ƃ̃M���V����ł́@�Ӄ̓˃Ã҃ցiphoneuo�j�Ƃ����P��� kill�@��\����ʖ����ł��B
���������̐_���F�߂� kill �� murder �ł͂Ȃ��Ƃ�����̂ŁA�܂��ɖ�������\���R�̘_���ł���A���ꂪ�����̕����ɕ\���ꂽ�̂ł��B
�@�@�@�����ăC�M���X�̍������A�����J�ɈڏZ�����s���[���^���܂ł��A���̐������g���܂����B
�A�����J�C���f�B�A���̋s�E���܂��� murder�ł͂Ȃ� kill �ł����_�� murder �͋ւ��Ă��Ă��A kill �͋ւ��Ă��Ȃ��Ƃ����_���ōs�Ȃ�ꂽ�̂ł��傤�B
�������A���������̘_���������������܂��B
�@�@�@�u����Ȕn���ȁv�Ǝv����������܂��A�����[�E�L���O�E���C���̃g�[�N�ԑg�ōs�Ȃ�ꂽ�c�_�������悤�ɁA�����͊m���ɂ����Ȃ��Ă��܂��B
�����ďA�C���ɗՂޗ��̃A�����J�哝�̂́u�L���v���m�肷��o�C�u���ɕЎ��u���A�u�w���v�E�~�[�E�S�b�h�v�Ɛ鐾���s�Ȃ��̂ł��B
�܂��A���Ƃ��Ɓu����v�͉p��� congregation�@�ƌ����܂����A������C�M���X����������� church�@�ɕς����̂̓W�F�[���Y1���ł��B
�ł�����v���e�X�^���g�̊J�c�́A�W�F�[���Y1���ƌ����Ă������̂ł��B
���̓W�F�[���Y1���ɂ������ς̗��R���A�ނ̌l�I���R���琶�܂ꂽ�ƍl���Ă���̂ł����A����͌�Ŗ��炩�ɂ��Ă����܂��B
�@���͌�����Ȃ�
�@�@�@���āA�����܂ł̘b�ŏd�v�ȓ_�́A�@���̋��`�Ƃ������̂́A���̎���ɂ����͎҂ɓs���̂����悤�ɏ����c����Ă���Ƃ������Ƃł��B
�����ĕ����Ƃ��ď����ꂽ���`�́A�Ȋw�_���̂悤�ɍ��ǂ���A������邱�ƂȂ��A���̊Ԃɂ��l�X�̐S�ɍ��܂�Ă����܂��B
�Ȃ������Ȃ����Ƃ����A�@���͂��Ƃ��ƌ��ł��Ȃ����̂ł���A�u���̕����͐��������ǁA�S�̓I�ɂ͊Ԉ���Ă���v�Ƃ������ƂɂȂ�A���͂₻��͐M��������̂ł͂Ȃ��A�ӏ]����M�҂����̋��߂ɉ���������̂ł͂Ȃ�����ł��B
�@�@�@�~�������߂�l�قǁA�x���₷�����̂͂���܂���B
�@�@�@���ɍ���A�̂ǂ���肪�o��قǂ������~�����Ǝv���Ă���l�قǁA���\���x����₷���Ƃ����̂͂��̎�����ς��܂���B
�������Ƃ��@���ɋ~�������߂�l�ɂ�������̂ł��B
�Ȃ������ꂽ���`��ӖړI�ɐM�p���邩�Ƃ����A����͑��l��M���Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�M�p�ł���Ώۂ��~�����ƍl���Ă��邩��ł��B
�܂��ŏ��ɁA���ׂĂ̂��Ƃ��^��
�S�����ĂA���̂悤�ȐȋC�����͂����ɏ����ĂȂ��Ȃ�܂��B
�����Ȃ�ƁA����̔��f�ŐM�p�ł�����̂�����悤�ƑO�ɏo�鎩�M���A�t�ɐS�ɖ����Ă���͂��ł��B
�@�@�@��������Ȃ��S�ɍ�p����̂́A����܂ł���ɏ@���ł���A���t�ł����B
�@�@�@�����Ă��̍�p���������A�����������̂��A�����ꂽ���t�ł���A������ꂽ���t�ł����B
�O�[�e���x���N�̈���p�ɂ�锭���́A�l�Ԃ��m�����l�����邤���ŁA����͋ɂ߂đ傫�Ȗ������ʂ������͎̂����ł��B
���������̔��ʁA����p�́A�����̃��[���b�p�̐l�X�̐S�Ɍ�܂����Œ�ϔO��A���t����������ʂ������̂ł��B
�w�����ɗ^����S�Ɓx�Ƃ����������J��Ԃ���������邱�Ƃɂ���āA��܂����Œ�ϔO���L�߂��Ă����Ƃ����A���̑��ʂ����݂��܂����B
���͎҂Ə@���͂��̌��ʂ𗘗p���A���̏������ł��d�˂�ɂ�āA������肪���悢��҈Ђ�U����Ă������̂͋��R�ł͂���܂���B
�@�@�@�w�����ɗ^����S�Ɓx���x�X�g�Z���[�ɂȂ�ƁA�����Ɋւ��鏑���͎��X�Ɛ��ݏo����Ă����A���̈���W�F�[���Y1���̎�ɂȂ�w�f���m���W�[�x�i�����w�j�ł��B
19���I�ɂȂ�Ɩ������͏I�����܂������A�f���m���W�[�̗���͎c��܂����B
�{�[�h���[���́w���̉x�Ȃǂ̈������w�́A�܂��ɂ�����p�����̂ł����B
�܂��t���C�g���A���_���͊w���m�������̂��A�����������ł���Ǝ��̂���l�X�̐S�����A�𖾂��悤�ƍl�������Ƃ����[�ł������̂ł��B
���̈Ӗ��ŁA�������̓��[���b�p�Љ�̌`�������E�������ɑ傫�Ȏ����������A�Ƃ����w�E������܂��B
�@�@�@���āA����ɂ�����IT�̔����́A�O�[�e���x���N�ɂ�����p�ɕC�G����Ƃ����Ă��܂��B
���̉��b�ɗ����鎄�����́A�O���̐��{��V���A���W�I�A�e���r�A�܂��l���B�e�����f���Ɏ���܂ŁA�D���Ȃ悤�ɐڂ��A�ۑ����A���H���邱�Ƃ܂łł���悤�ɂȂ�܂����B
�����������́A���Ƃ��܂ޑ吨�̐l�X�̖ڂƂ����t�B���^�[��ʂ��āA��܂������͏C������A��������Ă����܂��B
���̌��ʎ�������IT�ȑO�ɔ�ׂ�ƁA�͂邩�ɐ����������m������������ɕ�点��悤�ɂȂ�܂����B
���̎���������s�Ȃ��l�Ԃ�����
�@�@�@�������Ȃ���A����͕\�̘b�ł���A�����ɂ͕K�����\�����݂��܂��B
�@�@�@���[���b�p�̒����ɃO�[�e���x���N�̈���p�������炳�ꂽ���Ƃ��\���Ƃ���ƁA���̈���p�ɂ���āw�����ɗ^����S�Ɓx�����������炵�����̂����̐��E�ł���A����͌���ɂ����Ă����݂��Ă��܂��B
����́A���Ƃ��܂ߑ吨�̐l�X�ɂ���Č�����Ȃ����ł���A�Ȃ��ł��Ӑ}�I�Ȍ�U����A���]����ތ��͎҂ɂ���čs�Ȃ���g�D�I�ȏ��̐��E�ł��B
�@�@�@�]������A�C���^�[�l�b�g�̐��E�ŋN���邱���������ɑ��āA����1���\�[�X���m�F������A���Έӌ��╡���̈ӌ����ᖡ�����e���V�[�̃L�����y�[�����s�Ȃ��Ă��܂����B
��������e���V�[�́A�����ȃT�C�g����K�g���u���Ɋ������܂�Ȃ��Ƃ������x�̂��Ƃɂ͖𗧂Ƃ��Ă��A���͎҂ɂ��Ӑ}�I�ȏ��ɑ����ł��ł�����̂ł͂���܂���B
�Ȃ��Ȃ���̐��E�́A��₂��ꂽ1���\�[�X��A�ꌩ����Ɣ��Έӌ��̂悤�ɓǂ߂�u�U�������^���ӌ��v��A���邢�͈ꌩ����Ǝ^���ӌ��̂悤�ɓǂ߂�u�U���������Έӌ��v�Ȃǂ���������A����Ԑ��E������ł��B
�@�@�@�������c�C�b�^�[�̓o��ɂ���āA���������U�����͂Ȃ�����I���ɗ��ʂ�����܂��B
�_�����������A����ɑi����u�Ԃ₫�v�́A���_�┽���قƂ�ǎt���܂���B
��܂��Ă��邱�Ƃ��Ƃ��߂Ă��A�u�Ԃ₢�������Ȃ���A���������v�A�ŏI���ł��B
����͌���ɖ�����肪���s����A���ɑ傫�Ȋ��I�����ł��B
����𗘗p���錠�͎҂͂��łɌ���Ă��邵�A���̓����͍���v�X�����ɂȂ��Ă����ł��傤�B
����ɂ��Ă͖��炩�ɂ��Ă����܂����A���̂��߂ɂ����[���b�p�����ɋN�������������ɂ��āA���������[���l�@��i�߂�K�v������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u����Ł@�����̓S�Ɓv�@�ϕĒn�p�l���@�t�H���X�g�o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
*******************************************************************************
2013�N01��31��
�W�����k�E�_���N�Ƃ͒N�������̂��H
�ǂݕ��Ƃ��ẮA�ʔ������b�I(߁��)
zeranium�̃u���O�@���]��
*******************************************************************************
�W�����k�E�_���N�Ƃ͒N�������̂��H
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/index.html#entry-83697455
�@�@�@�y�h���͑����Ęb�����B
�@�@�@�u�n���ł͌��͎҂ɂ���Đl�����D��ꑱ���Ă���A����炪�n���̕�������W���Ă����B
������15���I�̒������[���b�p�ŌJ��L�����Ă������̑����ɁA���͏I�~����łƂ��Ƃ��Ă����B
���͒n���̔N���10�ɂȂ����Ƃ��A�W�����k�E�_���N�Ƃ����n���l�̒��ɑ��݂��Ă����B
�܂��ŏ��ɁA���̕��e�i�W�����k�̕��e�j�̗z�����ɒ��肷�邱�Ƃ���n�߂��B
�@�@�@�����Ȃ��u�h��v�Ƃ��Ĕ_�Ƃ̖���I���Ƃ����A�����̏ꍇ�A�n���l�̐i���ƕ������̂��߂ɂ́A���M�Ȑ��܂�̎҂����A�Ⴂ����ɂ���҂̒�����a�����邱�Ƃ��K�v�ł���A�L���Ȏ�i�ɂȂ邩�炾�B
�������邱�ƂŁA�l�Ԃ̔����́A�Ⴂ�g���ł��ꍂ�M�ȗ���ł��ꓯ�����Ƃ������Ƃ��������Ƃ��ł���̂��B
���҂̈Ⴂ�́A�P�Ȃ邨���ł���A��������悷��҂Ƃ����҂ɐU�蕪���Ă��܂��̂��B
�@�@�@�W�����k�E�_���N�̕�e�́A���ӂŕn�������_���l�������B
�@�@�@�������ޏ��́A���̂ǂ�ȋM���̏��������A��X�A�v���l���h��₷��������L���ɔ����Ă����B
�������W�����k�̕��e�́A�t�ɉA���������B
���W�����k�́A���e�ɂ��ꂩ��N���邳�܂��܂ȗ\����b���ĕ����������A�ނ͂�����Ƌ�����Ȃ��Ă��܂����B
�����Ă�����A�ނ͍Ȃ��ɌĂяo���Č������A�u�킵��̖��ɂ͈������߂��Ă���B
������X�ɘA��čs���Ēu������ɂ��A���Ƃ̓I�I�J�~�ƌF�ɖ��̂��Ƃ��܂����悤�Ǝv���v�@
�@�@�@���������e�͋����ċ����n�߁A�v�̑O�ɂЂ��܂Â��A�ނ̑��ɂ����݂��č��肵���B
���������e�͔ޏ����R����ƉƂ̒��ɓ������B
���̎�10�̃W�����k�͒�ƗV��ł����B
���͔ޏ���A��o���A�܂�Œ��ł��S���悤�Ȋi�D�ŃW�����k�����ɏ悹��ƐX�Ɍ������ĕ����n�߂��B
���̓r���A�n�ɓS���t���Ă���Œ��̗F�l�ɏo������B
����ƃW�����k�̕��e�͔ޏ��𑐂ނ�ɕ���o���A�n�̓S���t����F�l����`�����B
��Ƃ��I���ƕ��e�́A�����F���t�̂Ƃ���ɘA��Ă��������̂ŁA�n��݂��Ă����悤�ɗ��ݍ��B���͕a�C�Ŗ��@�ɂ������Ă���ƌ������̂��B
�@�@�@�����ėF�l�͈���Ɏv���A�n��݂����Ƃɂ����B
�@�@�@���e�͔ޏ�������������Ĕn�ɏ��ƁA�M�����b�v�ŋ삯�o�����B
��l�͈Â��Ȃ�܂ŃM�����b�v�Ŏ��������B������ꂽ���A�R�̂قڒ����܂ŗ���ƁA���e�͖���n����~�낵�A�ނ͂��̂܂ܔn�ő��苎���Ă��܂����B
�������W�����k�ɂ͎����h���Ă����̂ʼn������͂Ȃ������B
���̓I�I�J�~�Ɉ͂܂��ƁA�I�I�J�~�����Ƀv���X�C�I�����Ǝ˂����B
�����Ă��̒��ł���ԋ����I�I�J�~�̔w���ɏ��ƁA�^�������ƂɋA�����B
���̕��e�́A�����Ƃɖ߂��ė��Ă���̂�����ƁA�����đ��|�������ɂȂ����B
�ނ͍ȂɁA�����������������b���Ȃ��������A���̏o�����ŁA�����̖��͕��ʂł͂Ȃ��Ɣ[�������̂������B
�@�@�@1�T�Ԍ�A�W�����k�̕��e�́A���ޗp�̔��o�����߂ɐX�ւƌ��������B
�@�@�@�ނ͂��̒n���̔_���̑�َ҂ƂȂ邱�Ƃ����܂�A�t�����X���V������7���̓��ʂȉ������ď��������Ă邱�ƂɂȂ����̂��B
��������Ƃ̍Œ��ɕs�K�ɂ��A�ނ͎�������o�����ޖ�����Ă��̉��~���ɂȂ��Ă��܂����B�����10���̋����g���čޖ��ړ������Ȃ�����A�ނ������o�����Ƃ͏o���Ȃ��������B
�@�@�@���̎��A���W�����k�͎R�r�̌Q����Ă������A���Ɋ댯�������Ă���Ƃ����\���������B
�����Ŏ��͕��̂���ꏊ�Ɍ������đ���A�����ɒ����Ƒ�ʂ̃v���X�C�I�����W�߂čޖ��N�����A���������o�����̂��B
�����Ă���ȍ~�A�W�����k�̕��e�͖��̒����ȗF�l�ƂȂ����B
�������Ď��́A�t�����X�c���q�ɋ߂Â����߂̎菕�����Ă����悤�ɔނ���������邱�Ƃ��ł����B�����āA�ނ̂������Ŏ��̉y���͎������邱�ƂɂȂ����B
�@�@�@����11�ɂȂ������A���͗F�l�̌R�l�̂Ƃ���ɘA��čs���Ă��ꂽ�B
�@�@�@�����ĕ��ƌR�l�͘A�ꗧ���āA�����t�����X�c���q�̌��ֈē����Ă���邱�ƂɂȂ����B
���ɂƂ��čc���q�̐����͈�ԓ���A����ԏd�v�Ȃ��Ƃ������B
�c���q�͎��̖ڂ����߁A�B�R�Ƃ����ԓx�Ō������B
�@�@�@�u��͂��O���N�ŁA�������߂Ă��邩�͒m��ʂ��A���O�͘b������S���Ă���B
���O�̓t�����X�������Ă���B���̎��������ŁA���O�̒����S��M���邱�Ƃ��ł��悤�B
�������Ȃ���A�R�������O�̎w�����ɒu���Ƃ����̂́A����ǂ��s�ׂ��B
����Ȃ��Ƃ͕s�\���B���ӂʼn��̒m�����Ȃ����O�̂悤�ȔN�Ⴂ�����A�R�����w���ł���Ǝv���̂��H�@
��̂����Ƃ��D�G�Ȑ�m�ł����A�P�����ꂽ�C�M���X�̎ˎ�ɂ���ĝˁi�����j����Ă��܂����B
����ɂ��Ă��E�E�E�E�A���O�͂����������҂Ȃ̂��H�v
�@�@�@�u�ł͓a���A���͂ǂ̂悤�ȏؖ��������낵���̂ł��傤���H�v
�@�@�@�u���O�̉b�q�ƍU���v��������B
�@�@�@�@����ɁA�Ȃ������܂ŏ������m�M�ł���̂����m�肽���B
���ł��悢���玄�Ɋ�Ղ������Ă݂�B�����ŁA�������ɂ��v
�@�@�@���͔ނɍU���v�������������A�C�ɓ����Ă͂��炦�Ȃ������B
�@�@�@����Ŏ��͔ނɐq�˂��B�����炱���ōc���q���{�l�Ɋւ���u��Ձv������I���邪�A���Ȃ��͗�Â���ۂ��Ă����܂����A�ƁB
�����Ĕނ͑��v���Ɠ����A���߂̎m���ƎQ�������ɑގ�����悤�ɂƖ������B
�������͎������œ�l����ɂȂ����B�����Ŏ��͏W�����ăv���X�C�I�����W�߁A�ǂɃ^�C���E�X�N���[�����o�������āA�������B
�@�@�@�u�a���A���̕����ō����炨�ڂɂ�������̂��A�N�ɂ��������Ȃ��Ƃ����Ă��������܂����H�v
�@�@�@�u���悤�A������v�A�ƍc���q�͌��R�Ƃ����ԓx�œ������B
�@�@�@�u�ł͂����������v�A�Ǝ��͌������B
�@�@�@�ނ̓X�N���[�������߁A�t�����X�����G�̏�ǂɉ�������l�q��ڂ̓�����ɂ����B
�@�@�@��ʂł͎����ނɐ��������v��ǂ���A�p�j�b�N��ԂɂȂ����C�M���X���͑ދp���čs�����B
�˔@�A��ʂ͕ς�A���ɔނ̑Պ����̗l�q���f���o���ꂽ�B
����ɉ�����Ղ��A�{�a�̐l�X�Ɉ͂܂�č����Ă��鎩���̎p�ɋC�Â����Ƃ��A�c���q�͊��������ɔ��B�����Ă��ɔނ́A���̎�����A�����悤�Ɍ������̂��B
�@�@�@�u������A��̌R�����D���ɂ��邪�悢�v
�@�@�@����͂ق�̐����̏o�������������A�c���q���������m�M���A��m���������ɏ]���悤�ɖ��߂��Ă��炤���߂ɂ͏[���������̂��B
�@�@�@�W�����k�́u���Ԃ�v��Ƃ��K�v�͂����Ȃ������B
�@�@�@�Ȃ��Ȃ�W�����k�Ƃ����z���̐l�Ԃ̐l�i�́A����̃~�b�V�����������S���������炾�B
�@�@�@�C���m�������W�����k�E�_���N�ɉ��Ԃ�̌Y��鍐�����̂́A�ޏ��̎��傫�ȗ͂̂��߂ł���A���������̐l�X�ւ̐��@�̉e���͂��A���̂��߂ɂȂ��Ȃ邱�Ƃ�|�ꂽ���߂������B
�����Ĕނ炪�A�W�����k�̑����̂��������ς܂ꂽ�d�ɉ���������A�ޏ��ł��鎄�́������������̂��B
�����ĉ����痣��A���ėZ���������̂ŁA���͂܂����������Ă���B
���̌�����N�ԁA�푈�͑��������A�Ŋ��ɂ͕��a�������̓����K�ꂽ�B
���̑b�i���������j�ƂȂ����̂��A�u�W�����k�v�̗z���ȉ����������B�v
�@�u�A�v���Ō��āA�m���āA�̌��������Ƈ@�v�@�����h�E�J�y�^�m���B�b�`��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
*******************************************************************************
�r�W�l�X��Ƃ����w�T���_�C�������h�x���������ł܂��͂S���w�ǁI�i��P�����j

zeranium�̃u���O�@���]��
*******************************************************************************
�W�����k�E�_���N�Ƃ͒N�������̂��H
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/index.html#entry-83697455
�@�@�@�y�h���͑����Ęb�����B
�@�@�@�u�n���ł͌��͎҂ɂ���Đl�����D��ꑱ���Ă���A����炪�n���̕�������W���Ă����B
������15���I�̒������[���b�p�ŌJ��L�����Ă������̑����ɁA���͏I�~����łƂ��Ƃ��Ă����B
���͒n���̔N���10�ɂȂ����Ƃ��A�W�����k�E�_���N�Ƃ����n���l�̒��ɑ��݂��Ă����B
�܂��ŏ��ɁA���̕��e�i�W�����k�̕��e�j�̗z�����ɒ��肷�邱�Ƃ���n�߂��B
�@�@�@�����Ȃ��u�h��v�Ƃ��Ĕ_�Ƃ̖���I���Ƃ����A�����̏ꍇ�A�n���l�̐i���ƕ������̂��߂ɂ́A���M�Ȑ��܂�̎҂����A�Ⴂ����ɂ���҂̒�����a�����邱�Ƃ��K�v�ł���A�L���Ȏ�i�ɂȂ邩�炾�B
�������邱�ƂŁA�l�Ԃ̔����́A�Ⴂ�g���ł��ꍂ�M�ȗ���ł��ꓯ�����Ƃ������Ƃ��������Ƃ��ł���̂��B
���҂̈Ⴂ�́A�P�Ȃ邨���ł���A��������悷��҂Ƃ����҂ɐU�蕪���Ă��܂��̂��B
�@�@�@�W�����k�E�_���N�̕�e�́A���ӂŕn�������_���l�������B
�@�@�@�������ޏ��́A���̂ǂ�ȋM���̏��������A��X�A�v���l���h��₷��������L���ɔ����Ă����B
�������W�����k�̕��e�́A�t�ɉA���������B
���W�����k�́A���e�ɂ��ꂩ��N���邳�܂��܂ȗ\����b���ĕ����������A�ނ͂�����Ƌ�����Ȃ��Ă��܂����B
�����Ă�����A�ނ͍Ȃ��ɌĂяo���Č������A�u�킵��̖��ɂ͈������߂��Ă���B
������X�ɘA��čs���Ēu������ɂ��A���Ƃ̓I�I�J�~�ƌF�ɖ��̂��Ƃ��܂����悤�Ǝv���v�@
�@�@�@���������e�͋����ċ����n�߁A�v�̑O�ɂЂ��܂Â��A�ނ̑��ɂ����݂��č��肵���B
���������e�͔ޏ����R����ƉƂ̒��ɓ������B
���̎�10�̃W�����k�͒�ƗV��ł����B
���͔ޏ���A��o���A�܂�Œ��ł��S���悤�Ȋi�D�ŃW�����k�����ɏ悹��ƐX�Ɍ������ĕ����n�߂��B
���̓r���A�n�ɓS���t���Ă���Œ��̗F�l�ɏo������B
����ƃW�����k�̕��e�͔ޏ��𑐂ނ�ɕ���o���A�n�̓S���t����F�l����`�����B
��Ƃ��I���ƕ��e�́A�����F���t�̂Ƃ���ɘA��Ă��������̂ŁA�n��݂��Ă����悤�ɗ��ݍ��B���͕a�C�Ŗ��@�ɂ������Ă���ƌ������̂��B
�@�@�@�����ėF�l�͈���Ɏv���A�n��݂����Ƃɂ����B
�@�@�@���e�͔ޏ�������������Ĕn�ɏ��ƁA�M�����b�v�ŋ삯�o�����B
��l�͈Â��Ȃ�܂ŃM�����b�v�Ŏ��������B������ꂽ���A�R�̂قڒ����܂ŗ���ƁA���e�͖���n����~�낵�A�ނ͂��̂܂ܔn�ő��苎���Ă��܂����B
�������W�����k�ɂ͎����h���Ă����̂ʼn������͂Ȃ������B
���̓I�I�J�~�Ɉ͂܂��ƁA�I�I�J�~�����Ƀv���X�C�I�����Ǝ˂����B
�����Ă��̒��ł���ԋ����I�I�J�~�̔w���ɏ��ƁA�^�������ƂɋA�����B
���̕��e�́A�����Ƃɖ߂��ė��Ă���̂�����ƁA�����đ��|�������ɂȂ����B
�ނ͍ȂɁA�����������������b���Ȃ��������A���̏o�����ŁA�����̖��͕��ʂł͂Ȃ��Ɣ[�������̂������B
�@�@�@1�T�Ԍ�A�W�����k�̕��e�́A���ޗp�̔��o�����߂ɐX�ւƌ��������B
�@�@�@�ނ͂��̒n���̔_���̑�َ҂ƂȂ邱�Ƃ����܂�A�t�����X���V������7���̓��ʂȉ������ď��������Ă邱�ƂɂȂ����̂��B
��������Ƃ̍Œ��ɕs�K�ɂ��A�ނ͎�������o�����ޖ�����Ă��̉��~���ɂȂ��Ă��܂����B�����10���̋����g���čޖ��ړ������Ȃ�����A�ނ������o�����Ƃ͏o���Ȃ��������B
�@�@�@���̎��A���W�����k�͎R�r�̌Q����Ă������A���Ɋ댯�������Ă���Ƃ����\���������B
�����Ŏ��͕��̂���ꏊ�Ɍ������đ���A�����ɒ����Ƒ�ʂ̃v���X�C�I�����W�߂čޖ��N�����A���������o�����̂��B
�����Ă���ȍ~�A�W�����k�̕��e�͖��̒����ȗF�l�ƂȂ����B
�������Ď��́A�t�����X�c���q�ɋ߂Â����߂̎菕�����Ă����悤�ɔނ���������邱�Ƃ��ł����B�����āA�ނ̂������Ŏ��̉y���͎������邱�ƂɂȂ����B
�@�@�@����11�ɂȂ������A���͗F�l�̌R�l�̂Ƃ���ɘA��čs���Ă��ꂽ�B
�@�@�@�����ĕ��ƌR�l�͘A�ꗧ���āA�����t�����X�c���q�̌��ֈē����Ă���邱�ƂɂȂ����B
���ɂƂ��čc���q�̐����͈�ԓ���A����ԏd�v�Ȃ��Ƃ������B
�c���q�͎��̖ڂ����߁A�B�R�Ƃ����ԓx�Ō������B
�@�@�@�u��͂��O���N�ŁA�������߂Ă��邩�͒m��ʂ��A���O�͘b������S���Ă���B
���O�̓t�����X�������Ă���B���̎��������ŁA���O�̒����S��M���邱�Ƃ��ł��悤�B
�������Ȃ���A�R�������O�̎w�����ɒu���Ƃ����̂́A����ǂ��s�ׂ��B
����Ȃ��Ƃ͕s�\���B���ӂʼn��̒m�����Ȃ����O�̂悤�ȔN�Ⴂ�����A�R�����w���ł���Ǝv���̂��H�@
��̂����Ƃ��D�G�Ȑ�m�ł����A�P�����ꂽ�C�M���X�̎ˎ�ɂ���ĝˁi�����j����Ă��܂����B
����ɂ��Ă��E�E�E�E�A���O�͂����������҂Ȃ̂��H�v
�@�@�@�u�ł͓a���A���͂ǂ̂悤�ȏؖ��������낵���̂ł��傤���H�v
�@�@�@�u���O�̉b�q�ƍU���v��������B
�@�@�@�@����ɁA�Ȃ������܂ŏ������m�M�ł���̂����m�肽���B
���ł��悢���玄�Ɋ�Ղ������Ă݂�B�����ŁA�������ɂ��v
�@�@�@���͔ނɍU���v�������������A�C�ɓ����Ă͂��炦�Ȃ������B
�@�@�@����Ŏ��͔ނɐq�˂��B�����炱���ōc���q���{�l�Ɋւ���u��Ձv������I���邪�A���Ȃ��͗�Â���ۂ��Ă����܂����A�ƁB
�����Ĕނ͑��v���Ɠ����A���߂̎m���ƎQ�������ɑގ�����悤�ɂƖ������B
�������͎������œ�l����ɂȂ����B�����Ŏ��͏W�����ăv���X�C�I�����W�߁A�ǂɃ^�C���E�X�N���[�����o�������āA�������B
�@�@�@�u�a���A���̕����ō����炨�ڂɂ�������̂��A�N�ɂ��������Ȃ��Ƃ����Ă��������܂����H�v
�@�@�@�u���悤�A������v�A�ƍc���q�͌��R�Ƃ����ԓx�œ������B
�@�@�@�u�ł͂����������v�A�Ǝ��͌������B
�@�@�@�ނ̓X�N���[�������߁A�t�����X�����G�̏�ǂɉ�������l�q��ڂ̓�����ɂ����B
�@�@�@��ʂł͎����ނɐ��������v��ǂ���A�p�j�b�N��ԂɂȂ����C�M���X���͑ދp���čs�����B
�˔@�A��ʂ͕ς�A���ɔނ̑Պ����̗l�q���f���o���ꂽ�B
����ɉ�����Ղ��A�{�a�̐l�X�Ɉ͂܂�č����Ă��鎩���̎p�ɋC�Â����Ƃ��A�c���q�͊��������ɔ��B�����Ă��ɔނ́A���̎�����A�����悤�Ɍ������̂��B
�@�@�@�u������A��̌R�����D���ɂ��邪�悢�v
�@�@�@����͂ق�̐����̏o�������������A�c���q���������m�M���A��m���������ɏ]���悤�ɖ��߂��Ă��炤���߂ɂ͏[���������̂��B
�@�@�@�W�����k�́u���Ԃ�v��Ƃ��K�v�͂����Ȃ������B
�@�@�@�Ȃ��Ȃ�W�����k�Ƃ����z���̐l�Ԃ̐l�i�́A����̃~�b�V�����������S���������炾�B
�@�@�@�C���m�������W�����k�E�_���N�ɉ��Ԃ�̌Y��鍐�����̂́A�ޏ��̎��傫�ȗ͂̂��߂ł���A���������̐l�X�ւ̐��@�̉e���͂��A���̂��߂ɂȂ��Ȃ邱�Ƃ�|�ꂽ���߂������B
�����Ĕނ炪�A�W�����k�̑����̂��������ς܂ꂽ�d�ɉ���������A�ޏ��ł��鎄�́������������̂��B
�����ĉ����痣��A���ėZ���������̂ŁA���͂܂����������Ă���B
���̌�����N�ԁA�푈�͑��������A�Ŋ��ɂ͕��a�������̓����K�ꂽ�B
���̑b�i���������j�ƂȂ����̂��A�u�W�����k�v�̗z���ȉ����������B�v
�@�u�A�v���Ō��āA�m���āA�̌��������Ƈ@�v�@�����h�E�J�y�^�m���B�b�`��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
*******************************************************************************
�r�W�l�X��Ƃ����w�T���_�C�������h�x���������ł܂��͂S���w�ǁI�i��P�����j
2013�N01��24��
���{�̐N���ҁF�S�ϐl�ɖ��E���ꂽ�ꕶ�l�̖���B
�\�̐^���|�^����ǂ����߂āi�A���u���Łj�@���]��
************************************************************************************
http://ameblo.jp/bishamonten337/entry-11258864088.html
��Z���ł������y�w偁E�F�P�E�ڈ̏l���ƍ���
�h�剻�̉��V�h�͓��{���A�S�ω����ł��铡���ꑰ�̎����ƂȂ邫�������������̂ł��B

************************************************************************************
http://ameblo.jp/bishamonten337/entry-11258864088.html
��Z���ł������y�w偁E�F�P�E�ڈ̏l���ƍ���
�h�剻�̉��V�h�͓��{���A�S�ω����ł��铡���ꑰ�̎����ƂȂ邫�������������̂ł��B

�y�w偁i�������j�E�E�E�E�E���{��Z�����̑��́B
�F�P�i���܂��j�E�E�E�E�E�E�E�E�E��B�암�����͌��̓ꕶ�l����B
���Ȃ݂ɔ��l���Ƃ́A�����ꑰ�̌R��ɉ������F�P�̈ꕔ�ƌ����Ă���܂��B
�ڈi���݂��E�����j�E�E�E�E�֓��Ȗk�̓����{�S�悪���͌��̓ꕶ�l����B
�ڈƍ������ꂪ�������A�A�C�k�����͖k���n�Ƃ̍����Ƃ������A���[�c�͓ꕶ�B
��X�̏Z�ޓ��{�̏Z�l�̃��[�c�͈ȉ��̗l�ɂȂ�܂��B
�P�D�嗤�ł̌��͓����ɔs�ꂽ�l�X�B�i���͎҈ꑰ�j
�Q�D�嗤�┼��������Ă����l�X�B
�R�D���Ñ����Z���Ă����ꕶ�l�̖���B�B
�S�D������[�g�y�сA�����m���ړ����ė����l�X�B
�܂�A���{�l�Ƃ͗l�X�ȃ��[�g����ړ����ė����l�X�̏W����
�Ñ�V�c�Ƃ���S�����A��a������f���ē��{�𐧈������S�ω����̓����ꑰ�B
���͓����ɔs�ꂽ�V���n�⍂���n�����{�ɂȂ��ꍞ�݂܂��B
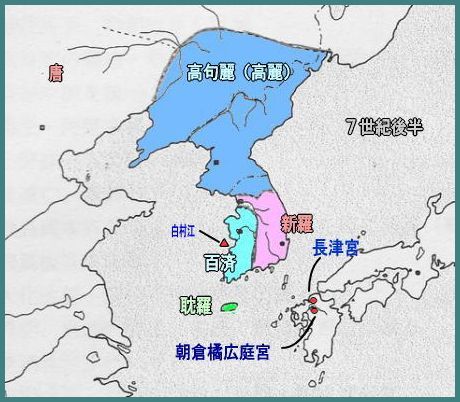
���̍\�}�́A����ɂ����Ă��S���ω��͂���܂���B
���{�̐N���҂̐��̂́A���Ȓ��S�I�ȗ��Ȏ�`���琶���錠�͗~�Ǝx�z�~�B
�⍓�Ŏc�s�ȁA������H�̓����{�\���������h�����h�ɂ������l�ԂƂ͎v���Ȃ������̂��ƌ�����̂ł͖����ł��傤���H
************************************************************************************
�Z���Ԃʼnp��̔����������o����I�����C�����ށi�����\�����j

