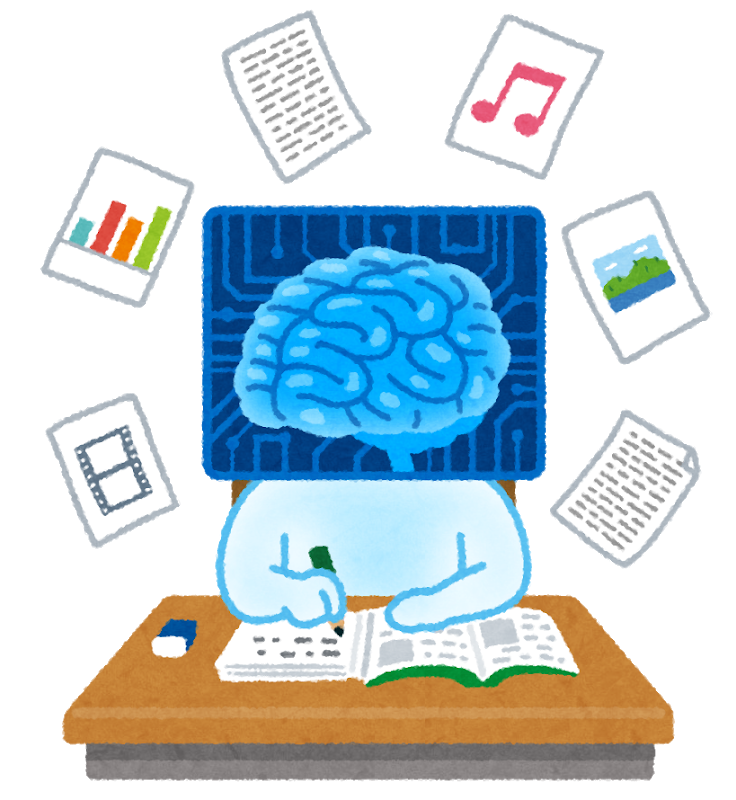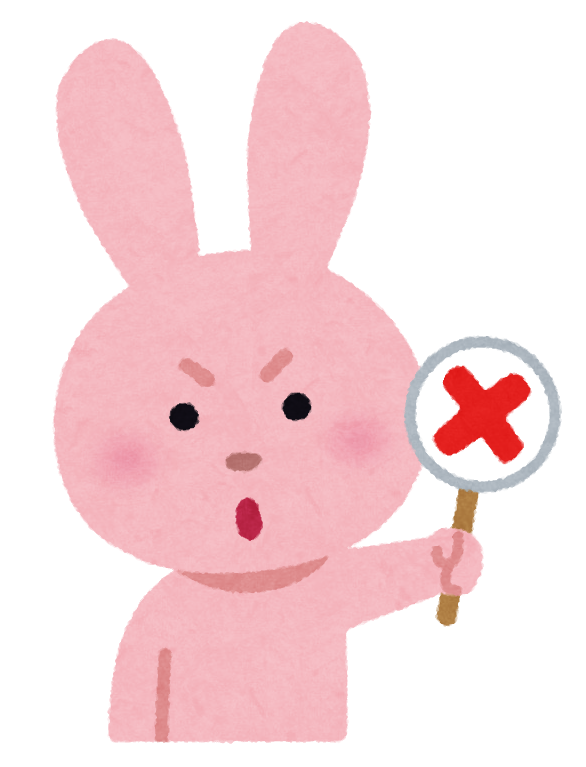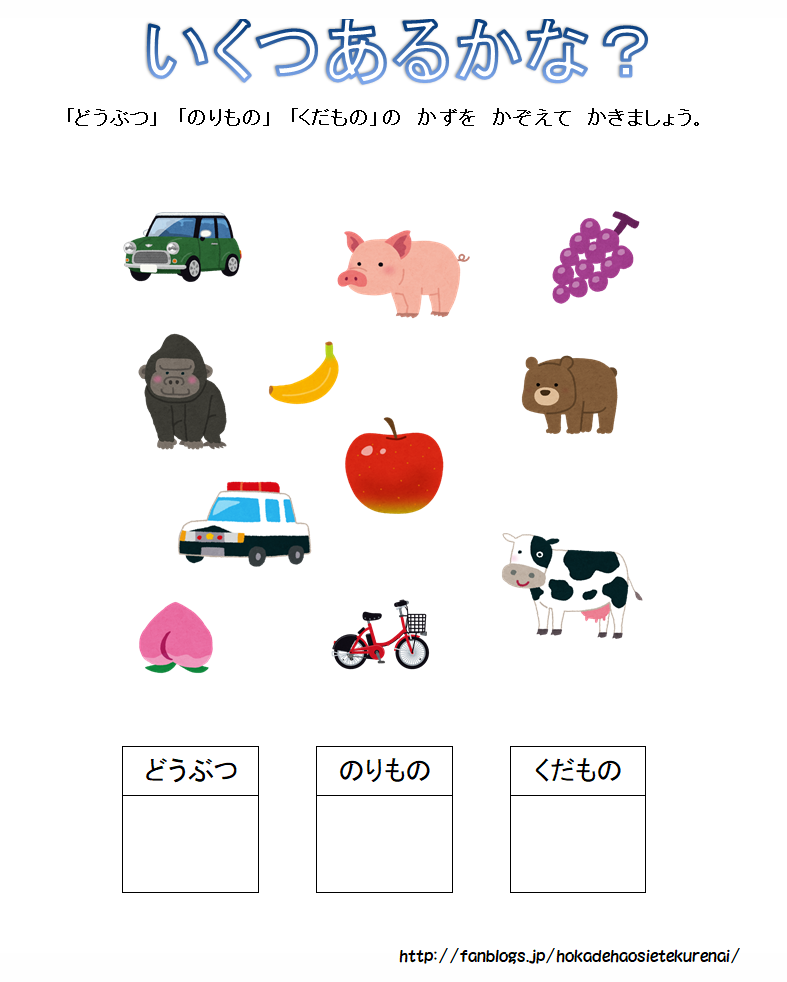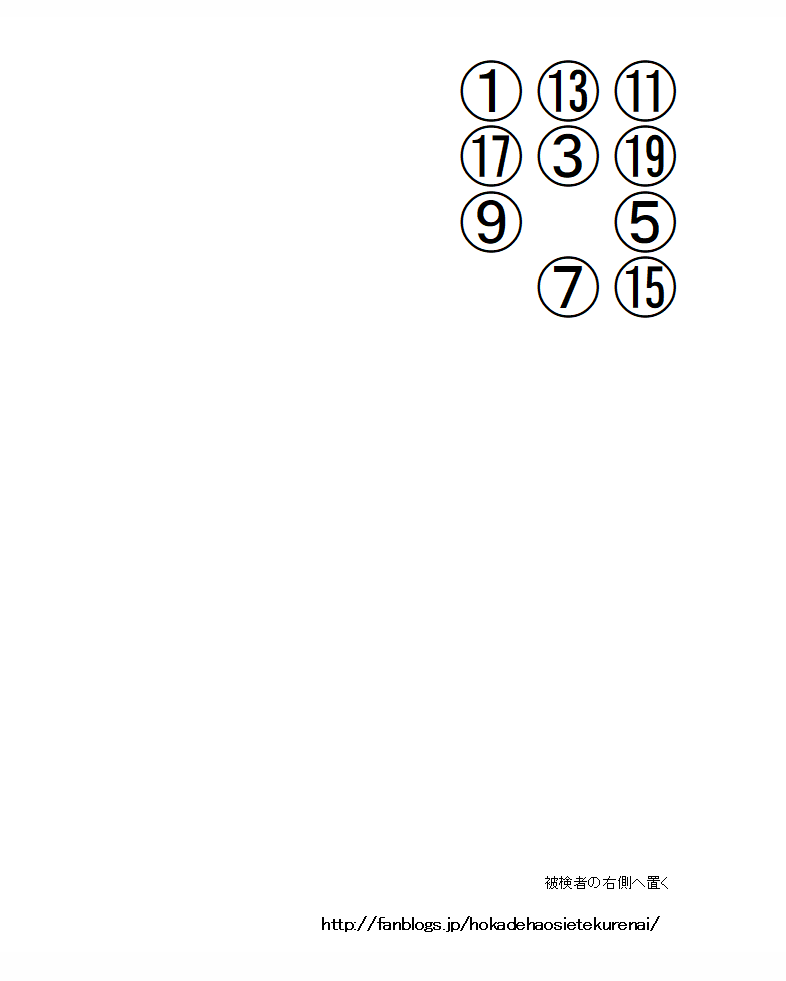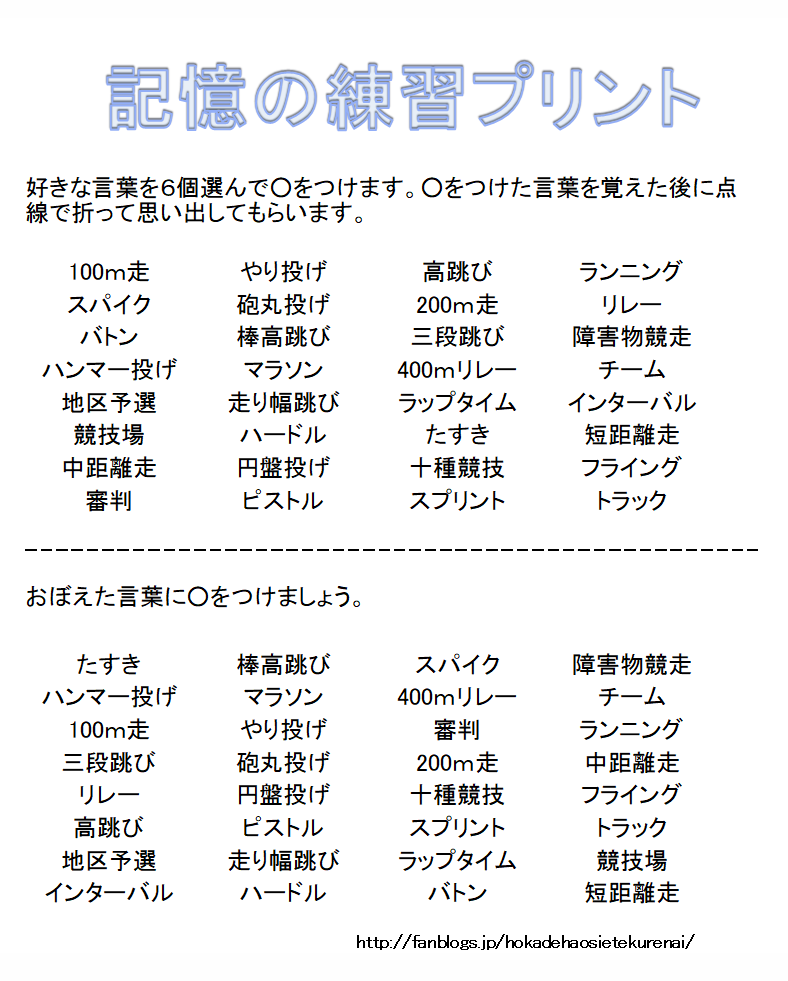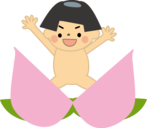2018年05月03日
口腔ケアで口を開いてくれない!対処法! 〜看護師、介護士向け〜
皆さんこんにちは。
言語聴覚士の桃の助です
本日のテーマは、「口腔ケアで口を開いてくれない」についてです。
主に看護師、介護士の人に見て頂けたらと思います。
私たち医療従事者、介護従事者にとって口腔ケアは必ずしなくてはいけない介助ですよね。
一般の歯科治療を行うように、全ての方が協力的で開口保持してくれればいいのですが、実際の現場ではそうもいきませんよね?
なかなか口を開いてくれずにケアでお困りの方もいるのではないでしょうか?
そこで、本日は口腔ケアの時に開口してくれないのはなぜか?どうすればいいのか?についてお話ししたいと思います!


 スポンサードリンク
スポンサードリンク
顎関節症になると十分に口を開くことが難しくなり、途中までしか開くことができません。
また、口角(唇の端)が乾燥で切れて出血している場合も開口しにくい原因となります。
医療現場では気管内挿管なども開口できない状態となります。
よく見落とされがちなのが、患者・利用者の心理面です。
「何をされるのか分からない」
「自分の口臭が気になる」
「口腔ケアに対する痛みが不安だ」
といった心理的な不安を持つ方がいらっしゃいます。
そういった方に対しては十分な説明が必要です。
認知症などによって理解力が低下した方に対しては、説明も必要ですが、実際に痛みを与えないように軽いケアから開始する必要があります。
軽い痛みを伴わないケアを行う事で、痛みに対する不安感や口腔ケアが苦痛でない事を体で理解してもらう必要があります。
そうする事で口腔ケアに対する受け入れは格段に良くなってきます。
上に書いた通り、機能的問題であったり、心理的問題、理解力の低下であったりと開口しないことに対する理由は様々です。
鑑別のポイントとしては、
あくびをして大きく口を開けている場合は、心理的問題や理解力低下によって開口しない場合が多いです。逆にあくびの時も大きく口を開けれない場合は、機能的問題の可能性があります。
当たり前の事ですが、開口しない理由を尋ねる事も必要です。
認知症の方に理由を尋ねた場合であっても意外と適切な回答が得られる事があります。
「口の中が痛い」
「恥ずかしい」
「口を人に見せたくない」
などと言った理由を話される事もあるので、理由は必ず尋ねた方がいいと思います。
 スポンサード リンク
スポンサード リンク

簡単に説明すると、奥歯の奥の粘膜に刺激を入れる方法です。
この方法については、歯科医師、言語聴覚士に指導を受けるとスムーズにできる可能性があります。
詳しくは相談してみてください。
私たちにとって歯磨きは当たり前の事です。
しかし、1人1人生活環境が違うので、歯磨きをあまりしていなかった方もいらっしゃいます。
また、歯磨きが必要な事と思わない、または思えなくなった方もいます。
そういった方に対して十分に説明をして理解してもらう必要があります。
臨床場面で患者さんと触れ合っていると、この人がいい!この人は嫌い!なんて言葉を耳にする事があります。
そういった場合、信頼関係が出来ている方の言う事は比較的スムーズに受け入れてくれる事が多いです。
もし、口腔ケアに対する拒否がある場合は信頼関係を築くことから始めてみるといいかもしれないですね。
唇にあたった感覚、口腔内で歯ブラシが動いている感覚に対して過敏になっている方もいます。
そういった方に対しては、磨くというより触れるという感覚で口腔ケアを導入する必要があります。
触れる状態から徐々に磨く状態へゆっくりと移行していきましょう。
意外と多いのが、ケア用品を歯磨きの道具と認識できない方です。
そういった方に対しては、ケア用品を目の前に見せて、ゆっくりと口へと運びます。
その際に「歯磨きしますよ。あーん。」といった具合に声掛けも一緒にお願いします。
1度では習慣化しないので、何度もチャレンジしてみてください。
私も臨床の現場で何度も開口拒否をされた経験があります。
そのたびに、「なぜ開けてくれなかったのか?」「どうすれば開けるようになるのか?」といった風に考えています。
根気強く、適切な対応をする事で徐々に口腔ケアに対する拒否はなくなっていくと思います。
数日で拒否が無くなる方もいれば、数か月がかりで拒否がなくなった方もいます。
皆さんも気長に試してみてください。
それではまた。
桃の助でした

ブログランキング参加中です。もしよければクリックしてください。活動の励みになります
 スポンサード リンク
スポンサード リンク
言語聴覚士の桃の助です
本日のテーマは、「口腔ケアで口を開いてくれない」についてです。
主に看護師、介護士の人に見て頂けたらと思います。
私たち医療従事者、介護従事者にとって口腔ケアは必ずしなくてはいけない介助ですよね。
一般の歯科治療を行うように、全ての方が協力的で開口保持してくれればいいのですが、実際の現場ではそうもいきませんよね?
なかなか口を開いてくれずにケアでお困りの方もいるのではないでしょうか?
そこで、本日は口腔ケアの時に開口してくれないのはなぜか?どうすればいいのか?についてお話ししたいと思います!

なぜ口を開けない?
器質的・機能的問題がある
顎関節症になると十分に口を開くことが難しくなり、途中までしか開くことができません。
また、口角(唇の端)が乾燥で切れて出血している場合も開口しにくい原因となります。
医療現場では気管内挿管なども開口できない状態となります。
心理的な不安がある
よく見落とされがちなのが、患者・利用者の心理面です。
「何をされるのか分からない」
「自分の口臭が気になる」
「口腔ケアに対する痛みが不安だ」
といった心理的な不安を持つ方がいらっしゃいます。
そういった方に対しては十分な説明が必要です。
理解力の低下
認知症などによって理解力が低下した方に対しては、説明も必要ですが、実際に痛みを与えないように軽いケアから開始する必要があります。
軽い痛みを伴わないケアを行う事で、痛みに対する不安感や口腔ケアが苦痛でない事を体で理解してもらう必要があります。
そうする事で口腔ケアに対する受け入れは格段に良くなってきます。
鑑別ポイント
上に書いた通り、機能的問題であったり、心理的問題、理解力の低下であったりと開口しないことに対する理由は様々です。
鑑別のポイントとしては、
あくび
あくびをして大きく口を開けている場合は、心理的問題や理解力低下によって開口しない場合が多いです。逆にあくびの時も大きく口を開けれない場合は、機能的問題の可能性があります。
理由を尋ねる
当たり前の事ですが、開口しない理由を尋ねる事も必要です。
認知症の方に理由を尋ねた場合であっても意外と適切な回答が得られる事があります。
「口の中が痛い」
「恥ずかしい」
「口を人に見せたくない」
などと言った理由を話される事もあるので、理由は必ず尋ねた方がいいと思います。
どうすれば口を開くの?

k−point刺激法(けーぽいんとしげきほう)
簡単に説明すると、奥歯の奥の粘膜に刺激を入れる方法です。
この方法については、歯科医師、言語聴覚士に指導を受けるとスムーズにできる可能性があります。
詳しくは相談してみてください。
説明を十分に
私たちにとって歯磨きは当たり前の事です。
しかし、1人1人生活環境が違うので、歯磨きをあまりしていなかった方もいらっしゃいます。
また、歯磨きが必要な事と思わない、または思えなくなった方もいます。
そういった方に対して十分に説明をして理解してもらう必要があります。
信頼関係を育む
臨床場面で患者さんと触れ合っていると、この人がいい!この人は嫌い!なんて言葉を耳にする事があります。
そういった場合、信頼関係が出来ている方の言う事は比較的スムーズに受け入れてくれる事が多いです。
もし、口腔ケアに対する拒否がある場合は信頼関係を築くことから始めてみるといいかもしれないですね。
優しいケアを
唇にあたった感覚、口腔内で歯ブラシが動いている感覚に対して過敏になっている方もいます。
そういった方に対しては、磨くというより触れるという感覚で口腔ケアを導入する必要があります。
触れる状態から徐々に磨く状態へゆっくりと移行していきましょう。
口腔ケア用品を歯磨きの道具と認識してもらう
意外と多いのが、ケア用品を歯磨きの道具と認識できない方です。
そういった方に対しては、ケア用品を目の前に見せて、ゆっくりと口へと運びます。
その際に「歯磨きしますよ。あーん。」といった具合に声掛けも一緒にお願いします。
1度では習慣化しないので、何度もチャレンジしてみてください。
おわりに
私も臨床の現場で何度も開口拒否をされた経験があります。
そのたびに、「なぜ開けてくれなかったのか?」「どうすれば開けるようになるのか?」といった風に考えています。
根気強く、適切な対応をする事で徐々に口腔ケアに対する拒否はなくなっていくと思います。
数日で拒否が無くなる方もいれば、数か月がかりで拒否がなくなった方もいます。
皆さんも気長に試してみてください。
それではまた。
桃の助でした
ブログランキング参加中です。もしよければクリックしてください。活動の励みになります
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/7613577
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック