どうも~。「黄昏」最終話の前に、ちょっと一息。
半分の月がのぼる空二次創作「想い歌」7話掲載です。
結構長くなりましたね。今のファンブログはこの文量でも受け入れてくれるので重宝しています。
今回から、かなり改変があります。
人によっては好き嫌いが分かれる内容と思われるので、どうぞご承知ください。
ではでは。
―15―
頭の中が、グチャグチャだった。
(・・・アンタ“達”は、いつもそう・・・。)
(今生きてる人の・・・これから生きてく人の・・・何もかもをかっさらっていってしまう・・・。)
(心も、夢も、希望も、未来までも奪い去って、それで自分だけ消えてしまう!!)
(“有限”の時間しかもたないアンタと、“無限”の未来を持ってる先輩と・・・)
(釣り合うと思ってるの?ホ・ン・ト・ウに。)
あの娘の言葉が、壊れたスピーカーみたいに頭の中でくわんくわん響いては消えていく。
いくら耳を塞いでも、いくら目を瞑っても、その声は響くのを止めてくれない。
やめて。
やめて。
まるで嵐の夜、風の音に怯える子供の様に、あたしはただただ、貝の様に縮こまる事しか出来なかった。
そうしているうちに、冷たい風が吹いてきて身体が冷えてきた。
このままでは、本当に風邪をひいてしまう。
そんな、半分現実逃避的な考えが浮かんできた。
それでもいい。
とにかく思考を逸らさないと、どうにかなってしまいそうだった。
ふらつく足で、立ち上がる。
学校の中に戻ろうと、屋上の戸をくぐったら、踊り場に誰かがいた。
薄暗い校舎の中じゃあ、それが誰なのか、何をしているのかすぐには分からなかった。
誰なのだろう。
一人じゃない。
二人?
この暗い中、くっついて何をしているのだろう。
分からない。
ただ、何か近寄りがたい雰囲気だけが漂っていた。
その空気に押されて、あたしは降りていく事を躊躇する。
そうこうするうちに、暗さに目が慣れてきた。
目を凝らす。
・・・裕一と、あの娘が一緒にいた。
あの娘は裕一の首に手を回して、いっぱいに背伸びをして、そして―
自分が何を見ているのか、分からなかった。
けれど、時間が経つにつれて“それ”は頭に染みていく。
そして―
身体から、力が抜けていくのが分かった。
崩れる体勢。
腕が、開いたまんまのドアに当たった。
ガタンッ
腕が当たったドアが、大きな音を立てる。
二人の顔が、いっせいにこっちを向いた。
裕一は驚いた顔。そしてあの娘は―
「――っ!!」
何かを考える前に、身体が動いていた。
ドンッ
自分の肩が、二人のうちのどちらかにぶつかる。
裕一の叫ぶ声が聞こえる。
けど、それに構う余裕もない。
今までに経験した事がない位の速さで、視界が過ぎていく。
もう、何がどうなってもいい。
いっそ、何もかも壊れてしまえ。
そんな事を考えながら、あたしは走っていた。
そう。あたしは“走って”いた。
「・・・気付いて、いたんですか・・・?」
自分の手を握る如月蓮華の母親に向かって、吉崎多香子は茫然と呟いた。
「・・・一応、あの娘の親よ。あの娘が転校してこんなに早く、友達を作れる様な娘かくらい、分かってるわ。」
そう言うと、如月蓮華の母親は掴んでいた手を離す。
「・・・ごめんなさいね。急に変なお願いして・・・」
「いえ・・・最初に妙な事をしたのはこちらですから・・・。」
よほど強く握られていたのか、赤く痕のついた手を見ながら吉崎多香子は姿勢を正す。
「だまそうとして、申し訳ありませんでした。」
そう言って、頭を下げる。
「・・・あの娘、何かをしようとしてるのね・・・。」
「・・・はい。」
「それは、誰かを・・・傷つける様な事・・・?」
「そうなるかも、しれません。」
頷く吉崎多香子を見て、如月蓮華の母親は大きく息をついた。
「わかったわ。」
「!?」
その言葉に、吉崎多香子は思わず顔を上げる。
「何の助けになるかも、分からないけれど・・・」
そして、話は始まった。
何も考えられなかった。
気がつけば、僕の首には蓮華の腕が回され、唇は蓮華に塞がれていた。
密着する身体の柔らかさと、鼻腔を満たす甘い香りに、ただただ、頭が真っ白になった。
その時―
ガタンッ
大きな音が響いて、僕を現実に引き戻した。
ハッとして蓮華の身体を突き放すと、音のした方を見た。
・・・上を向けた視線の先に、大きく目を見開いた里香の姿があった。
「り・・・」
思わず声をかけそうになった時、僕の前に立つ蓮華の顔が目に入った。
瞬間、怖気が走る。
笑っていた。
嘲るでも。
勝ち誇るでもなく。
その顔は、笑っていた。
“邪悪”という言葉がある。
その言葉を、寸分の違いもなく体現する。
そんな、笑顔だった。
だけど、僕が蓮華に気をとられたその瞬間―
ドンッ
何かが、僕の肩に当たった。
我に帰って見ると、階段を“駆け下りて”いく里香の姿が見えた。
そう、里香は“走って”いた。
その事を理解すると同時に、僕は叫んだ。
「ばっ・・・里香、走るなっ!!」
だけど、里香の足は止まらない。
その姿は、見る見る階下へと消えていく。
「くそっ!!」
急いで後を追おうとすると、ガクンと身体が止まった。
振り返って見れば、僕の右腕に蓮華が絡み付いていた。
「何処行くんですか?先輩。」
その顔にあの笑みを張り付かせたまま、蓮華は言う。
「ねえ、どこにも行かないで。ここにいて。」
甘く誘うような言葉。
僕は、それを振り切る様に怒鳴る。
「うるせえ!!放せ!!」
「いやです。放しません。」
そう言って、腕にぶら下がったまま離れない。
苛立ちと、焦りがつのる。
「里香は心臓が悪いんだぞ!!それで手術もしてるんだ!!走ったりしたら、どうなるか分からないんだぞ!!」
「それが?」
なんでもない事の様に、そう言われた。
絶句する僕に、蓮華は言う。
「良いじゃないですか。別に。もし“そうなった”ら何も考えずに走った秋庭さんが悪いんです。先輩の事を責める人なんて、誰もいないし、あたしがさせません。」
「・・・お前、何言ってんだ・・・?」
「いい機会だと思いません?この際、秋庭さんにはいなくなってもらいましょう。」
平然と言い放つその言葉には、微塵の躊躇もない。
「先輩、今なら間に合います。」
何?何を言ってるんだ?こいつは?
「今なら間に合います。先輩の未来には。だから、だから・・・。」
―“今度こそ”、あたしを選んで。―
薄い花弁の様な唇が、確かにそう紡いだ。
「二人の関係がおかしくなったのは、あの娘達が中学に入ってからの時の事だったわ。」
お互いの湯飲みに二杯目のお茶を注ぎながら、如月蓮華の母親は静かに話す。
「それまでには、休みの日には欠かさず会ってたのに、だんだんとそれが途切れ途切れになって、ついには全然会わなくなってしまった・・・。」
時折お茶で喉を湿らせながら、如月蓮華の母親の話は続く。
―二人で会う事がなくなってから、如月蓮華は目に見えて塞ぎ込むようになってしまった。
心配した母親は、双子の片割れである如月鈴華の保護者。つまり二人の父親に連絡をとった。
返って来た答えは驚くべきものだった。
鈴華に、恋人が出来たのだという。
相手は、通っていた中学の同級生。
ただし、その少年は普通の少年ではなかった。
彼は、病を患っていた―
訳が分からなかった。
蓮華(こいつ)の言っている事が。
蓮華(こいつ)の求めている事が。
僕には、全く分からなかった。
選ぶ?
今度こそ?
一体何の事だ?
何を言っているんだ?
狼狽する僕の目を、蓮華はじっと見つめてくる。
まるで、何かを求める様に。まるで、何かにすがる様に。
けれど、その暗く燃える瞳はそのままに。
僕らの時間が、凍った様に止まる。
その間は、どれほどだっただろう。
10秒?5秒?それとも、もっと―
ハッと気付いた時、僕の耳に飛び込んできたのは、カッカッカッという靴が床を蹴る固い音。
―里香が、走っている―
その事が頭に浸透したその瞬間、僕は力いっぱい蓮華を突き飛ばしていた。
床に突き倒された蓮華が短く悲鳴を上げたが、そんな事に構っている暇はなかった。
僕は蓮華を顧みる事もなく、里香の足音を追って走り出していた。
如月鈴華がその少年に会ったのは、中学に入学して最初の週末。
先生に頼まれて学校のプリントを届けに行った時の事。
行き先は、少年の家ではなく市立病院の一室。
ノックをして入った先で、その少年は待っていた。
「一目惚れだったらしいわ。」
手にした茶碗をコトリ、と置きながら、如月蓮華の母親はそう言ってフフ、と笑った。
「本人に会った事があったけど、別にどうって事のない子だったのよ。特別に美形だった訳でもないし。本当、何処にでもいる様な、普通の男の子。でも、あの娘は、鈴華は夢中だった。」
少年は、心臓の病を抱えていた。
小学生の時にリウマチ熱に罹り、それによって「大動脈弁狭窄症」を併発したらしい。
手術の必要があったが、幼い頃から病と闘ってきた少年の体力は弱く、手術(それ)に耐えられる見込みは少なかった。
そして何より、長年の闘病生活に少年自身が疲れきり、手術という大事に向き合う気力を失っていた。
そんな少年を、如月鈴華は懸命に励ました。
学校の放課後、休日、夏休みに冬休み。足しげく病院に通い、少年の側に寄り添い続けた。
そんな二人に、やがて変化が現れる。
塞ぎ込みがちだった少年が、如月鈴華に興味を持ち出したのだ。
少年は鈴華の話に耳を傾け、鈴華が笑えば、笑顔でそれに応じた。
そうして二人の間は、急速に縮まっていった―
「・・・そんな二人の事を、蓮華は良く思っていなかったわ。何度も、そんな明日をも知れない相手に入れ込むのはやめろって言ってた。自分で心臓病の勉強をしては、その事を教えたりもしてたみたい。だけど、それでも鈴華の気持ちは変わらなかった・・・。」
当然だろうな、と吉崎多香子は思う。
人が人を想う気持ちは、そんな事で変わるものではない。
秋庭里香と戎崎裕一が良い例だ。
第三者がどれだけ口を挟もうが、どんな事実が立ち塞がろうが、一度つながった二人の心を分ける事など、出来はしない。
たとえ、それが同じ血を分けた片割れの言葉であったとしても。
一人の人間が持つ心は、あくまでその人間のものなのだ。
青臭い考えだと思われるかもしれないが、今のあの二人を知る吉崎多香子にとっては、それはまごう事なき真実だった。
―そして、事態は少なからずの進展を見せ始めた。
何に対しても消極的だった少年が、行動を起こし始めたのだ。
自ら進んで体力作りに励み、出される食事も全部食べる様になった。
そしてその傍らには、いつも伴侶の様に寄り添う如月鈴華の姿があった。
時間はゆっくりと過ぎていき、やがて彼女達が三年生になる頃、少年の身体は手術に耐えうるだけの体力があると判断されるまでに持ち直していた。
そして、手術の日が決まった。
「よっぽど、嬉しかったのね。わたし達の所にも、電話をかけてきたわ。彼が治るって。治ったら、一緒にいっぱい遊ぶんだって。海にも、動物園にも、遊園地にも行くんだって。本当に、子供みたいにはしゃいでた。」
・・・同じだな、と吉崎多香子は思った。
秋庭里香も、戎崎裕一という存在を得てから“生きる”という事に対して貪欲になったのだと聞いた。
人が人を想う気持ちは、それほどまでに強い。一人の人間を、死の影から引っ張り上げるほどに。
吉崎多香子は、その事を再確認した様な思いでいた。
如月蓮華の母親の、次の言葉を聞くまでは―
「・・・良い話だと思った・・・?」
「え・・・あ、はい、その・・・」
不意に飛んできたその問いに、吉崎多香子は思わず頷く。
しかし―
「でもね、神様って、そんなに優しくないのよ。」
能面の様に無表情な顔で、如月蓮華の母はそう言った。
その手の中の湯飲みが小さく震えて、カタタ、と鳴った。
“それ”は、あまりにも唐突に訪れた。
手術まであと数日という日の朝、彼の心臓は突然その動きを止めた。
緊急の処置が、それこそ考えられうる全ての手が施された。
けれど、彼の心臓が再び動く事は二度となかった。
「大動脈弁狭窄症」による心不全。
それが、医者から遺された者達に告げられた、最後の言葉だった。
僕は必死で走っていた。
耳には、相変わらず走る里香の足音が響いている。
その音が、僕には終わりを告げるカウントダウンの様に聞こえていた。
馬鹿な!!
そんな事、あってたまるか!!
僕は、走る足に力を込める。
どれくらい走っただろう。
実際の時間にしたら、ほんの数十秒くらいのものだろう。
それでも僕には、とてつもなく長い時間の様に感じられた。
やがて、僕の目に走る里香の後姿が見えてくる。
それからは、あっという間だった。
いくら先に走り出したとはいっても、里香の足は僕よりずっと遅い。
僕達の距離はどんどん縮まっていく。
僕は里香に向けて、いっぱいに右手を伸ばす。
そして―
僕の右手が、里香の肩を掴んだ。
そのまま、力いっぱい抱き寄せる。
「放して!!」
腕の中で荒い息をつきながら、里香がもがく。
身体越しに、彼女の鼓動が伝わってくる。
速い。
まるで、今にも破裂しそうな程に激しく波打っている。
それを押さえ込もうとする様に、僕は抱き締める腕に力を込める。
「落ち着けよ!!里香!!落ちつけったら!!」
「うるさい!!放してったら!!放せ!!」
怒鳴る僕に、里香が怒鳴り返す。
こんなに錯乱した里香を見たのは、初めてだった。
伝わってくる心臓の鼓動は、相変わらず早い。
とにかく、落ち着かせなければ。
しかし、どうすればいいのだろう。
言葉で言っても、今の里香は聞いてはくれない。
それなら、どうすればいい?
言葉で、通じないなら―
「はな・・・んっ――!?」
ぼくは咄嗟に、里香の唇を塞いでいた。
「んっ、んんっ!!」
里香がもがくが、僕は放さない。
一分。
二分。
腕の中で、里香の抵抗が弱まってくる。
それに合わせる様に、早鐘の様に波打っていた鼓動が静かになっていく。
やがて、里香がすっかり大人しくなると、僕はやっと唇を放した。
「「はぁ・・・」」
二人同時に、大きく息をつく。
僕は廊下の壁に背中をつけると、里香を抱き締めたまま、ズルズルと床に崩れ落ちた。
当然、里香の身体もそれについてくる。
「里香・・・大丈夫か?どうも・・・なってないか?」
「・・・気持ち悪い・・・。」
その答えに、僕はドキリとする。
慌てて里香を見ると、
「あの娘とした口で、キスした・・・。」
そう言って、口をゴシゴシと擦っていた。
「気持ち悪いって、そっちの気持ち悪いかよ・・・」
ホッと胸を撫で下ろす僕に、だけど里香は視線を合わせようとしない。
「・・・ごめん・・・。」
他に、かける言葉が思いつかなかった。
「・・・・・・。」
里香は、何も言わない。
「・・・・・・。」
僕も、何も言えない。
すっかり日が落ちて暗くなった廊下に、僕達の息遣いだけが響く。
淡々と続く沈黙。
いい加減、それに耐えかねて、僕がもう一度謝ろうとした時―
ガバッ
突然、里香が僕の首にしがみついてきた。
「うわっ!?わっ!!」
不意の事に、崩れる体勢。
そのまま、僕達はもつれる様に床に倒れ込んだ。
「痛・・・」
起き上がろうとしたけれど、それは出来なかった。
僕の首には、里香の腕がしっかりと絡みついていたから。
そんな里香の身体は、僕の下にある。
丁度、僕の身体が彼女に覆い被さっている様な状態だ。
「あ・・・」
自分達の体勢に気づいた僕は、慌てて里香の上から退けようとした。
けれど、やっぱりそれは叶わなかった。
僕を束縛する里香の力は、本当に彼女のものかと思える位に強かった。
「里香・・・どうし・・・!!」
言いかけた言葉を、僕は呑み込んだ。
首に絡んでいた腕が一本、離れていた。
その腕はそのまま僕の右手を掴み、自分の左胸に押し当てていた。
柔らかなふくらみの奥で、命を刻む鼓動を感じる。
それはとても温かくて、優しくて、そして蠱惑的な感触だった。
僕の全身で、血液が一気に沸騰した。
「り、里香!!お前、何やって・・・!?」
「裕一・・・」
里香が、呟く様に言った。
「・・・あの娘にも、されたの・・・?こんな事・・・。」
「え・・・?」
答えに窮する僕の胸に、里香が顔を埋めてくる。
甘い香とともに、長い髪が顔をくすぐった。
「・・・いいよ・・・」
微かな艶を絡めた声が、静かに囁く。
「・・・裕一になら、いい・・・」
「――――っ!!」
思わず見下ろすと、見上げる里香の瞳と視線が合った。
里香の目。強さと儚さを併せ持った瞳。
それが、ユラユラと揺れていた。
艶っぽい熱をもって潤む眼差し。
ドクン
里香の意図を察した瞬間、心臓が大きく跳ねた。
「・・・暗くなったわね。」
如月蓮華の母親はそう言うと、立ち上がって部屋の電灯の紐を引いた。
カチリ
小さな音が鳴って、薄闇に沈んでいた部屋がパッと明るくなる。
けれど、それでも部屋に漂う闇は消えない。
むしろ、中途半端な光はそこにある闇をより濃く浮き上がらせる。
客間の隣、深い闇に沈んだ仏間。
それを、視界の隅に入れながら、吉崎多香子は知らず知らずのうちにその身を竦ませていた。
「吉崎さん・・・」
電灯を点けたその姿勢のままで、如月蓮華の母親が言う。
その声につられて、吉崎多香子は顔を上げる。
こちらを見下ろす如月蓮華の母親。
電灯の光を背に受けるその顔も、闇に彩られていた。
闇。
闇。
闇。
いつしか、この家の全てに闇が満ちていた。
空気。空間。そして、人間(ひと)に至るまで。
「吉崎さん、知ってる・・・?」
人の形をとった闇が囁く。
「神様って、酷いのよ・・・。」
闇色の声が、闇の中に響いて消える。
「本当に、本当に、酷いの・・・。」
悲傷とも、怨嗟ともとれる声。
吉崎多香子は、その声に不吉なものを感じる。
それは、この後語られる事がどんなものなのか、薄々感じ取っていたからかもしれない。
如月鈴華が愛した少年は、もうこの世にいない。
けど、その如月鈴華も、もうこの世にはいない。
何故、彼女はその命を失ったのか。
何が、彼女の命を奪ったのか。
一つの“答え”が、頭を過ぎる。
その“答え”に身体の芯から、震えが沸き起こる。
聞くべきなのだろうか。
いや、聞く事は許されるのだろうか。
自分が。
この家族に。
この姉妹に。
何の縁もゆかりもない自分が。
恐らくは彼女達が孕む、もっとも深い闇の事を。
知ってしまって、いいのだろうか。
それが、酷く罪深い事の様に思えて、吉崎多香子は思わず席を立とうとした。
しかし―
腰を浮かしかけたところで、その動きは止まった。
いつの間にか元通りに座った如月蓮華の母親が、こちらを見ていた。
じっと。
逸らす事なく。
見つめてくる瞳。
それを見た瞬間、吉崎多香子は悟った。
もう、逃げられないのだと。
・・・こんな事を、想像した事がない訳じゃなかった。
いつかはこう言う時が来るかもしれない、と思った事もあった。
けど、それはいつも霞がかかった様に曖昧で。
手を伸ばしても、届きそうで届かない所にあった。
何より、実際に里香を前にすると、そんな荒々しい衝動は形を潜めた。
それくらい、里香は神聖で大事な宝物だった。
汚しちゃいけない。
壊しちゃいけない。
里香と一緒にいる。
それだけで、全ては満たされていた。
その筈だった。
けど。
だけど。
僕は、気づいてしまった。
自分の中で、燃えている”それ”に。
焔だった。
それは、あいつの中にあったもの。
蓮華の身体に灯っていた、焔。
昏く、熱く燃える灯火。
彼女と身体を重ねた、ほんの一時。
それが。
僕の中にも、燃え移っていた事を。
まずい。
そう思いかけた瞬間、それが僕の脳漿に引火した。
嫌だった。
絶対に、嫌だった。
彼を。
裕一を。
失う事が、嫌だった。
今なら分かる。
”彼女”の想いの形が。
それは、巨大な蛇だった。
虚ろにのたうつそれは、あたしの心に巻き付き、締め上げる。
責め立てる。
いいのかと。
奪われて、いいのかと。
心が軋む。
悲鳴を、上げる。
耐えられなかった。
耐えられる筈がなかった。
だから、決めた。
何をしても。
何を壊そうとも。
つなぎ止めると。
「裕一・・・」
里香が、言う。
「いいから・・・あたしは、いいから・・・」
脳が、熱に浮かされる。
「だから・・・」
腕が、華奢な身体を抱き寄せる。
「だから・・・」
視界に入る、白い首筋。
「お願い・・・」
次の言葉を聞く事なく、僕はそこに顔を埋めた。
口付けた舌先に広がる、甘い肌の味。
「んっ・・・!!」
か細い声とともに、里香の身体がビクリと震える。
首に絡まる腕が、戦慄く。
戦慄きながら、抱き寄せる。
まるで、すがり求める様に。
耳元で、今にも絶えそうな声が言った。
「行かないで・・・」、と。
―16―
闇の帳が降りた校舎。
冷たい夜気が満ち始めた舎内。
その中で、僕は熱に浮かされた様に里香を抱きしめていた。
欲しかった。
里香が、欲しかった。
ここが学校だという事も。
誰かに見られるかもしれないという懸念も。
もう、どうでも良かった。
僕は、貪りたかった。
里香の身体を。
里香の心を。
里香の全てを。
貪り尽くしたかった。
里香の身体。
細くて華奢な、精巧なガラス細工の様な身体。
それが砕けんばかりの力で抱きしめ、白いうなじに唇を押し付ける。
舌を這わせる度、腕の中で里香が震える。
彼女の吐息が、耳に触れる。
それだけで、ゾクゾクする様な快感が走った。
もう、止める事は叶わなかった。
闇に満たされた部屋。
その中で、吉崎多香子は身動ぎする事もままならず、ただ“彼女”の言葉を聞いていた。
「ねぇ、吉崎さん・・・」
手にした遺影を愛しげに撫でながら、如月蓮華の母親は言う。
「あなた、分かってるんじゃない?」
「・・・・・・。」
吉崎多香子は答えない。
否、答えられない。
如月蓮華の母親の目が、それまで遺影に落とされていた視線が、再び彼女の方を向く。
「ねぇ、分かってるんでしょう・・・?」
繰り返される言葉。
その“答え”に行き着いてしまった事を、責める様に。
その“答え”に怯える事を、嘲る様に。
吉崎多香子は、大きく息を吸う。
呼吸が、苦しかった。
まるで、肺の中まで闇に満たされたかの様に。
狭い鉢の中、空気を求める金魚の様に口をパクパクさせる彼女を見つめながら、如月蓮華の母親は、言葉を続ける。
「・・・そうよ・・・。」
疲れたような、それでいてどこか高揚した様な、奇妙な声。
吉崎多香子は、心の内で叫ぶ。
聞きたくはなかった。
もう、分かっている。
もう、理解している。
だから。
だから、言わないで。
だけどその叫びは、言葉の体を成しはしない。
乾いた口が、ただパクパクと動くだけ。
「あの娘は・・・鈴華はね・・・」
そして、“彼女”はゆっくりと、噛み締める様に言った。
―“自殺”したの―
予想していた筈のその言葉は、酷くハッキリと耳へと突き刺さった。
熱が冷めるのは、一瞬だった。
滾る衝動のまま、右手を里香の服の中に潜り込ませようとしたその時、
ポタン
温かい、けれど冷たい感触が頬に落ちた。
ハッと顔を上げる。
そこで、僕は初めて里香の顔を見た。
綺麗な顔が、怯える様に震えていた。
ギュッと閉じた目尻には涙が浮かび、噛み締めた唇には薄らと赤いものが滲んでいた。
瞬間、僕の内で猛犬の様に荒ぶっていた衝動が、それこそ水でもぶっかけられたみたいに静まった。
何だ!?
何をしようとしてたんだ!?
熱を急激に冷やされた頭が混乱する。
沸き起こる後悔と罪悪の念に引き剥がされる様に、僕は里香の身体を離していた。
そのまま、里香の視線から逃れる様に後ろを向く。
「裕一・・・?」
戸惑う様な声で、里香が言う。
「どうしたの・・・?」
問いかける声。
答えなんか、出やしない。
里香に背を向けたまま、「ごめん。」と呟く。
「・・・どうして、謝るの?」
里香は言う。
「いいって言ったのは、あたしだよ・・・?」
「違う・・・。」
「裕一は、ああしたかったんでしょ?」
「違うんだ・・・。」
「だから・・・」
「違うんだよ!!」
思わず、大きな声が出た。
背後で、里香がビクリと竦む気配がした。
「・・・・・・。」
「・・・・・・。」
僕達の間に、沈黙が降りる。
さっきまでの熱が嘘の様な、肌寒い沈黙。
頭の中が、ぐるぐる回る。
どうして、こんな事になったのだろう。
こんな事、望んでいた筈じゃなかったのに。
里香が、いいって言ったから?
違う。
僕が里香を。
彼女を、そこまで追い込んでしまったのだ。
蓮華なんか、関係ない。
結局は、僕が弱かったから。
その結果が、これ。
二回も、里香を傷つけてしまった。
心も。
身体までも。
馬鹿だ。
本当の、本当に、大馬鹿だ。
何だか、鼻の奥がツンとする。
目頭が、熱くなってきた。
気づくと、目から涙が溢れていた。
ああ、何泣いてんだよ。
そんな立場じゃないだろうが。
こらえようとすればするほど、こみ上げてくるものが止まらなくなる。
いっそ、舌でも噛んでしまおうかと思ったその時、
ふわり
温かい感触が、背中を包んだ。
・・・「抜け殻になる」という言葉がある。
少年を亡くした後の如月鈴華が、まさにそんな状態だった。
学校に行かなくなり、趣味だった歌や作曲にも興味を示さなくなり、一日中部屋に閉じ篭って虚空を見つめて過ごすようになった。
それはまるで、心も、気力も、残りの人生も、その全てを少年に持っていかれた様な有様だった。
そんな彼女を、周りの者も手をこまねいて見ていた訳ではない。
特に、如月蓮華は必死だった。
まるで鈴華自身が少年にそうした様に、毎日彼女の元に通ってはその隣に寄り添い続けた。
幼い頃の思い出を話し、かつて共に思い描いた未来の夢を語った。時には二人で作った歌を歌って聞かせ、そして部屋には小さい頃に一緒に摘み遊んだ花を飾った。
しかし、それでも如月鈴華の瞳に光が戻る事はなかった。
もう、このまま時の流れがその傷を癒してくれるのを待つしかないのではと、皆が思い出した矢先―
如月鈴華が、如月蓮華に家族一緒に遊びに行こうと誘いをかけた。
その事に、如月蓮華はもちろん、二人の両親も喜びに沸いた。
・・・その日、昔家族で訪れた遊園地で、如月鈴華は久方ぶりの笑顔を見せた。
それを見て、如月蓮華とその両親も心から喜んだ。
この時、二つに解れていた家族の心は、如月鈴華を通して確かに繋がっていた。
懐かしい、そして暖かい一日だった。
―そしてその夜、如月鈴華は己の命を絶った。
冷たい浴槽の中。切り開いた手首に、真っ赤な華を咲かせて―
・・・その温もりの正体は、すぐに分かった。
里香が、僕を背中から抱き包んでいた。
「裕一。」
里香が、僕を呼ぶ。
答える声は、出せなかった。
「裕一。」
また、呼ばれた。
でも、やっぱり声は出ない。
答える術もないまま、垂れる鼻水を拭おうとしたその時、
「裕一!!返事しろ!!」
バンッ
大きな声と一緒に、背中を思いっきり叩かれた。
「イッテー!!」
堪らず飛び上がる。
「な、何すんだよ!?」
怒鳴りながら振り返ると、こっちを見つめていた里香と目があった。
思わず、固まってしまう。
しばしの間。
そして―
「アハ、アハハハハ。」
里香が、笑いだした。
「裕一、顔すごい。ぐちゃぐちゃ。」
言いながらハンカチを取り出すと、僕の顔を拭う。
「ほら、これでいい。」
そう言って微笑む顔はとても綺麗で、思わずドキリと心臓が鳴った。
「ほら、ハンカチ、ちゃんと洗って返してよね。」
里香の手が、ベトベトになったハンカチを握らせてくる。
「わ、分かった・・・」
ハンカチを受け取る瞬間、手が重なる。
瞬間、
クンッ
そのまま、里香の手が僕の手に絡んできた。
ハンカチが、床に落ちる。
僕達は、自然と抱き合っていた。
さっきの、荒々しい感情はもう湧かなかった。
とても静かで、優しい抱擁。
すぐ近くに、里香の鼓動を感じる。
里香もきっと、僕を感じている筈だった。
「・・・裕一。」
里香が言った。
呟く様に。
小さな声で。
「・・・何だ?」
「そんなに、長くはないよ・・・。」
その言葉を聞いたとき、僕はまたドキリとした。
それは、あの夜の言葉。
あの半月の下、暗い病室で交わした、あの言葉。
「でも、短くもないよ・・・。」
僕の腕の中で、僕に身を委ねながら里香は続ける。
「あたしのために、何もかも諦めなくちゃいけなくなるよ・・・。」
「・・・・・・。」
「いいの?」
それは何かを恐れる様な、そして何かに怯える様な、そんなか細い声だった。
「本当に、いいの?」
また、言った。
細い肩が、震えていた。
里香は屋上で、蓮華に何をされたのだろう。
蓮華に、どんな言葉をぶつけられたのだろう。
その心が、酷く傷ついている事がその肩の震えから察せられた。
僕の心に、改めて怒りが湧き起こる。
今すぐ蓮華のところに戻って、ぶん殴ってやりたい衝動に駆られる。
だけど、今はその時じゃない。
今しなきゃいけない事は、たった一つだった。
里香を抱き締める腕に、もう一度力を込める。
その肩が、ビクリと震えた。
その耳元で、僕はささやく。
「わかってる。」
里香と同じ様に、僕もあの時の言葉を繰り返す。
「全部、わかってる。」
俯いていた里香の顔が、僕の方を見る。
僕を見つめる目が、濡れていた。
「ずっと、いっしょだろ。里香。」
「・・・うん。」
細い腕が、僕の背に回る。ギュッと抱きしめられる感覚。
里香が目を閉じ、顔を寄せてくる。
それに答える様に、僕も顔を寄せる。
廊下の窓から差し込む月明かりの中で、僕らの影が重なる。
いつの間にか、窓の外には大きな半月が浮かんでいた。
秋庭里香と戎崎裕一は気付かない。
自分達を包む月の光の外。
廊下の端。階段。その、踊り場。
暗い、暗い闇の澱み。
その中から、自分達を見つめる目があった事を。
如月蓮華。
闇の中、彼女は光の中の秋庭里香と戎崎裕一を見つめていた。
その目に、暗く冷たい炎を燻らせながら。
ジッと。
ジッと見つめていた。
空には、大きな半月が浮かんでいた。
月明かりの差し込む廊下。
その光の中で、僕達は抱き合っていた。
里香の細い腕が、僕の身体をギュウと抱き締めてくる。
トクン
トクン
ピッタリとくっついた身体を通して、里香の鼓動が伝わってくる。
さっきまで、千々に乱れ、早鐘の様に鳴っていたそれは、今はすっかり平穏を取り戻している。
それを確かめる様に、僕もギュウと里香を抱き締める。
「里香・・・大丈夫か?」
さっきから何度もした問いを、僕はまた繰り返す。
「・・・うん。」
里香も、何度も繰り返した答えを繰り返す。
「裕一、少ししつこいよ?」
半ば呆れた様な顔で、里香が言う。
「だってさ・・・」
僕の言いたい事を悟る様に、里香はコツンとおでこを僕の胸につけた。
「ゴメンね・・・。」
「・・・お前があやまることじゃないだろ。」
「・・・そうかな?」
「そうだろ。」
いつになくしおらしい里香。それがたまらなく愛おしくて、僕は彼女の頭をクシャクシャと撫でた。
すると、里香がウフフ、と笑った。
くすぐったかったのか、それとも別の理由なのかは分からないけれど、とにかく笑った。
それは、ここしばらく見たことのなかった里香の笑顔。
それが嬉しくて、僕もウハハ、と笑った。
ウフフ、ウハハと僕達は笑い合う。
笑いながら、僕は如月蓮華の事を考えていた。
蓮華(あいつ)に対する怒りは、まだ胸の中でグラグラと滾っている。
だけど、今はそれ以上に、勝ち誇る気持ちの方が強かった。
ざまあみろと言う気持ちだった。
これが、僕と里香だ。
お前なんかの割り込む隙間なんか、ありゃしないんだ。
ふと、僕に突き飛ばされた時の、あいつの顔が目に浮かぶ。
親を見失った子供の様な、捨てられた子犬の様な、悲しげな顔。
だけど、憐憫の情は少しも起きない。
あいつは里香を傷つけた。
あれくらい、当然の報いだ。
そう言えば、あいつはまだ、学校(ここ)にいるのだろうか。
あいつの事だ。ひょっとしたら、またどこかで見ているかもしれない。
構うもんかと思った。
この様を見て、とことん思い知ればいいんだ。
僕は、何処かにいる蓮華を思いっきり嘲笑った。
「忘れ物、ないか?」
「うん。大丈夫。」
教室から鞄を持って出てきた里香は、僕の問いにそう答えて頷いた。
「じゃ、帰ろうぜ。」
そう言って、僕は手を差し出す。
その手を、当たり前の様にとる里香。
「暗いから、足元気をつけろよ。」
「分かってるよ。」
僕達の会話は、もうすっかりいつもの調子に戻っていた。
それがたまらなく嬉しくて、僕は月明かりの差し込む廊下を里香の手を取り歩きながら、ニタニタとわらった。
「裕一、何ニタニタしてるの?」
そんな僕の顔を見て、里香が気味悪そうに言う。
「そうか?ニタニタなんてしてたか?」
しれっとしながら、そんな事を言ってみる。
「してた。あ、ほら、またしてる。気持ち悪い。」
里香がそう言いながら、顔をしかめる。
うん。いつもの里香だ。
さっきまでのしおらしい里香もいいけど、里香はやっぱりこうでなくちゃ。
僕はニタニタと笑いながら、気味悪がる里香の手を引いて歩いた。
「・・・・・・。」
「・・・・・・。」
話し終わった如月蓮華の母親が、冷めたお茶で口を湿らした。
「それ以来、蓮華もすっかり変ってしまった・・・。」
如月鈴華を、自分の半身を失った彼女は、次第に攻撃的になっていった。
外界からの干渉を拒絶し、否定し、侮蔑した。
そしてそれは、他人だけに納まらず、彼女自身の親、親類にさえも及んでいた。
如月蓮華は孤立し、そしてその孤独の中で、心の刃をますます研ぎ澄ませていった。
・・・おそらく、と吉崎多香子は考える。
今の如月蓮華にとっては、この世の全てが敵なのだろう。
自分達姉妹を別った両親も。
それを良しとした親類縁者も。
如月鈴華の全てを持ち去った少年も。
そして、愛する姉をこの世に繋ぎとめられなかった自身さえも。
自分から如月鈴華を奪った世界の全てを、彼女は敵視し、拒絶しているのだ。
孤独という、闇色の殻に閉じ篭りながら。
「ねぇ、吉崎さん・・・」
言いながら、如月蓮華の母親が、持っていた湯飲みをテーブルに置く。
コトリ
湯飲みがテーブルに置かれる音が、妙に大きく聞こえた。
「わたし達は、一体何を間違っちゃったのかしら・・・?」
問いかけてくる、闇色の言葉。
「・・・あの夜、あの娘を一人にしてしまった事・・・?あの日、あの子の心を読み違えてしまった事・・・?あの娘が、“彼”を選んでしまうのを、止められなかった事・・・?あの娘を、あの学校に入れてしまった事・・・?あの娘達を、別けてしまった事・・・?親(わたし達)が、別れてしまった事・・・?」
そう。この女(ひと)も同じ。
己の娘を、救えなかった自分。
もう一人の娘を、救えない自分。
それを嫌悪し、呵責し、苦しんでいる。
終わりのない自責と言う、闇の泥濘に溺れながら。
「ねぇ、何?何かしら・・・?」
続けられる問いかけ。
答えはない。
答えられる筈もない。
吉崎多香子は思い知る。
死に寄り添われる者と共に生きる。
それが、何を意味するのか。
その事を、自分がいかに安易に考えていたのか。
吉崎多香子の前には、戎崎裕一と秋庭里香という存在がある。
彼らの物語を知ってから、秋庭里香と近しい仲になってから、自分は“その事”に関して他の人間よりも理解があるつもりになっていた。
しかし、それはただの幻想だったのかもしれない。
丁度、世間を知らぬ小娘が、テレビの中のスターに憧れる様に。
その表の眩さだけに魅せられて、その影にある闇から目を逸らしていたのかもしれない。
そして、改めて認識する。
この闇は、あの戎崎裕一と秋庭里香の影にも、確かに潜んでいるのだと。
あの光の中にある様な輝きは、闇の上に置かれた平均台を、二人三脚で渡っている様なもの。
一歩でも足を踏み外せば、闇は何の容赦もなく、“彼ら”を呑み込んでしまうのだろう。
背筋が震えた。
考えたくない。
考えたくもない。
けれど、それが事実なのだ。
どうしようもなく冷酷な、だけど歴然たる事実なのだ。
・・・気付けば、如月蓮華の母親は泣いていた。
如月鈴華の遺影を、赤ん坊でも抱くように腕に持ち、その上にポロポロと涙を落としながら。
そこにあるのは、平均台から落ち、闇に呑まれた者達の姿。
いつかは、“彼ら”がたどり着いてしまうだろう場所。
“その時”が来た時、彼はどの道を辿るのだろう。
如月鈴華の様に、全てを捨ててしまうのか。
この母親の様に、ただ遺され、涙にくれるのか。
それとも・・・
そこで、吉崎多香子はある事に思い至る。
「―っ!!おばさん!!」
思わず、吉崎多香子は叫んでいた。
「?」
突然の呼びかけに、如月蓮華の母親が顔を上げる。
「さっき、言ってましたよね!?如月さんは、心臓病の勉強もしてたって!!」
「ええ・・・。鈴華に教えるために、それはもう、一生懸命・・・」
「鈴華さんのお相手に、会った事は・・・!?」
「何度かあるわ・・・。鈴華が、あの娘達を馴染ませようとして・・・。」
やっぱり。
吉崎多香子は確信する。
“彼女”は、学校の中では目立つ存在だ。
他の生徒から、病気を持ってるらしい事や、体育関係の授業や行事はいつも見学している事ぐらい、聞きだすのは容易だろう。
加えて。
それほど知識があるのなら。
それだけ近くで、実際の患者を見た事があるのなら。
分かるのかもしれない。
その所作から。
そのそぶりから。
そう。
彼女は、如月蓮華は気付いたのだ。
秋庭里香の病に。
戎崎裕一が選んだ運命に。
それが、意味するものに。
たどり着いた。
そう確信した。
如月蓮華の想い。その、彼女の真意に。
何故、あんなにも戎崎裕一に執着するのか。
何故、あんなにも秋庭里香に敵意を持つのか。
そう、彼女はやり直そうとしているのだ。
あの時、渡りそこねた平均台。
それをもう一度、たどり直すために。
「すっかり遅くなっちゃったね。」
月明かりと外灯の光の中、自転車置場から自転車を引っ張り出す僕に向かって、里香がそう声をかけてきた。
「そうだな。」
自販機で買ったパックのジュースを啜りながら、僕は答える。
実際、全くもってその通りだった。
いつもなら、そろそろ夕食の時間。
さっきから、腹がグウグウ鳴っている。
ジュースでも飲まなきゃ、やってられない。
「叱られるかな。」
「適当に誤魔化しちゃえよ。」
ちょっと心配そうな里香に、僕はそう言った。
「適当って?」
「日直で先生に用事を頼まれたとか言ってさ。」
「嘘つくの?」
里香が、少し嫌そうな顔をする。
里香は、あまり嘘が好きじゃないのだ。
「仕方ないだろ。本当の事なんて、説明のしようがないし。」
「そうでもないよ。」
僕の言葉に、里香がニヤリと笑ってそう言った。
・・・何か、嫌な笑いだ。
「・・・なんて言うんだよ?」
「裕一に襲われてたって言う。」
ブッ
思わず、含んでたジュースを噴出してしまう。
って言うか、少し気管に入った。
盛大にむせてしまう。
そんな僕を見て、里香はケタケタと笑う。
いやいや、笑い事じゃないぞ。
せきが止まらない。
マジで死にそうだ。
「い・・いや、お前、あれは・・・その・・・その・・・」
涙目で弁解する僕に、里香が笑いながら言った。
「ウソウソ、そんな事、言わないから。」
お前、嘘嫌いなんじゃなかったのかよ。
心の中で抗議しながら、僕はもう一つ、ゲホリとせきをした。
「遅くまで、お邪魔しました。」
玄関口まで送りに出てきた如月蓮華の母親に向かってそう言うと、吉崎多香子はペコリとお辞儀をした。
「いいのよ。それよりも・・・」
如月蓮華の母親はそこで言葉を区切り、吉崎多香子の顔をじっと見る。
「わたしのお願い・・・聞いてくれる?」
その言葉に吉崎多香子はしばし逡巡し、そしてこう答えた。
「約束はできません・・・。でも、善処してみます・・・。」
まるで、何処ぞの官僚の様な、見方によっては無責任とも言える返答。
しかし、その言葉に如月蓮華の母親はその表情を緩ませる。
「・・・それで十分よ。ありがとう・・・。」
そうして、吉崎多香子の長い時間は終わりを告げた。
「じゃ、行くぞ。」
「うん。」
荷台に乗った里香に、そう声をかける。
しっくりと、落ち着く感触。
ああ、やっぱりここは“里香の場所”だ。
そんな事をしみじみと思いながら、こぎ出す前に僕はもう一度里香の方を確認した。
・・・里香は、じっと校舎の方を見ていた。
夜闇の中、月明かりに浮かびあがるそのシルエットは、昼間とはまるで違う印象をうける。
学校の怪談なんか信じるたちじゃないけど、なんて言うか気味が悪い。
一階の、職員室の辺りはまだ灯りが点いているけれど、それ以外の場所はもう真っ暗だ。
そんな校舎を、里香はじっと見つめていた。
いや、見つめていたのは、校舎だろうか。
僕には何となく、校舎のもっと上の方。そう、屋上の辺りを見つめている様に見えた。
僕もつられて、目を凝らしてみる。
月明かりの屋上。そこを覆う転落防止用のフェンス。その上に―
・・・ちょこんと座る、人影が見えた様な気がした。
気付いた瞬間、その人影もこちらを見ている様な気がして、思わず総毛が立った。
まさか。
いくらなんでも。
けれど―
「里香、行くぞ!!」
里香の答えを待たず、僕は勢いよくペダルをこぎ出した。
驚いた里香が抗議の声を上げるが、それにも構わず無我夢中でペダルをこぐ。
背中に感じる視線。
それから逃げる様に、僕は必死にペダルをこぎ続けた。
・・・人気の失せた学校。
月明かりに照らし出される、無人の屋上。
「♪・・・君は王女 僕は召使い・・・♪」
そこに、何処からともなく、たおやかな歌声が流れる。
「♪・・・運命分かつ 哀れな双子・・・♪」
青い月の下、白と黒の陰影だけに支配された世界。
その中で、如月蓮華は一人フェンスに座り、“その歌”を歌っていた。
「♪・・・君を守る そのためならば・・・♪」
誰が聞くでもなく、誰に聞かせるでもなく、歌はただ、無人の屋上に流れては消える。
「♪・・・僕は悪にだってなってやる・・・♪」
無造作に投げ出された足が、テンポをとる様にカツンカツンとフェンスを鳴らす。
「♪・・・もしも・・・♪」
虚ろな眼差しが見つめるのは、“彼ら”が去っていったその方向。
けれど、見つめるその場所に、もう求める人の姿はない。
「♪・・・生まれ変われるならば・・・♪」
虚空を見つめる瞳。
一滴の雫が、その頬をすべる。
「♪・・・その時はまた遊んでね・・・♪」
言葉の結びと共に、こぼれた滴が闇の中へと落ちて消えた。
続く
タグ:半分の月がのぼる空
【このカテゴリーの最新記事】

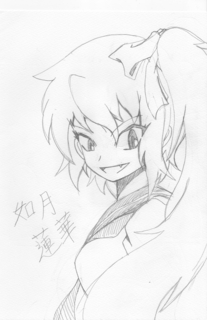


.jpg?2023-01-2212:27:19)
