「想い歌」、これにて終幕です。
前身の「恋文」が納得できる出来ではなかったので、修正作となった今作ですが、正直、やっぱり満足のいくものは出来ませんでした。
二次創作と、オリキャラの扱いの難しさを改めて痛感する作となりました。
この次は、従来のスタイルに戻して、原作のキャラ達だけの作品を書きたいなぁとか思っています。
まあ、まずはネタが浮かばねば話になりませんが・・・・・・。
ではでは。
―28―
......~~♪♪♪♪♪♪~~♪♪♪♪♪♪~~♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪~~......
「何、聴いてるの?」
イヤホンから流れる調べに浸っていたあたしは、不意にかけられた声に閉じていた瞳を開けた。
明るくなった視界の中で、長く黒い髪が舞う。
いつの間に来たのか。秋の日差しを背負った先輩があたしを見下ろしていた。
「あ、先輩」
慌てて立ち上がろうとすると、手振りで制された。思わず動きを止めると、先輩はそのままあたしの隣りに腰を下ろした。
「いい天気だね」
「ですね」
心持ち高くなった空を見上げながらそんな事を言う先輩。あたしも相槌を打っておく。
ここは、昼休みの屋上。
ここしばらくのゴタゴタに気を取られていた間に、季節はすっかり変わっていた。時折、秋の香りをたっぷり含んだ風が、あたし達の間を流れていく。
でも、その白い季節に傾いた風は少し冷たい。
あまり長く当たっていると、身体に毒ではないだろうか。
早く用を済まさせて、校舎の中に戻ってもらおう。
そう思い、「用は何ですか」と訊こうとした時、
「吉崎さん、ありがとう」
先に飛んできた言葉に、思わずポカンとしてしまった。って言うか、何の事か分からない。
「何がですか?」
訊くと、先輩は微笑みながら言った。
「如月さんの事」
「!!」
その名に、思わず胸が跳ねた。
「何か、ありました?」
恐る恐る、訊いてみる。
「さっきね、会った」
「!!」
もう一度、ギョッとする。
「また、ちょっかい出してきたんですか!?」
けど、そんなあたしの言葉に対して、先輩は静かに首を振る。
「ううん。廊下歩いてた時、行き逢っただけ」
「じゃあ、何か言われたとか?」
けれど、先輩はやっぱり首を振る。
「あたしの事、じっと見て。その後、ペコリってお辞儀して行っちゃった」
「......それだけですか?」
「うん。それだけ」
どうやら、余計な心配だったらしい。あの”敗北”宣言を、彼女は確かに履行していたのだ。
もっとも、あれだけの想いがそう簡単に消えるとも思えない。しばらくは、悶々とした時が続くのではないだろうか。
そんな事を考えていると、また先輩が話しかけてきた。
「如月さんね、変わってたよ」
「え?」
「とても、すっきりした顔してた」
「すっきり......?」
訳が分からない。あたしが小首を傾げていると、先輩が言った。
「きっと、何かの思いが晴れたんだと思う」
「思い......?」
「そう。思い」
そして、先輩はまたあたしに微笑みかける。
「吉崎さんが、何かしてあげたんだよね」
「え?」
「あの日、一緒に帰ったんでしょう?如月さんと」
見通されていたらしい。エスパーか何かか?この女(ひと)は。
「何してあげたの?如月さんに」
微笑みながら訊いてくるその顔に、好事(こうず)の色はない。ただ何となく、訊いてみてるだけなのだろう。だから、あたしもお茶を濁しておく。
「まあ、ちょっとお節介はしましたけど......」
「お節介したんだ」
「はい」
「そうなんだ」と言って、先輩はクスクス笑う。
あたしも、「そうです」と言って笑っておいた。
「で、」
「はい?」
「何、聞いてたの?」
話が、元に戻った。
「また、ボーカロイド?」
こっちの方は、声音に思いっきり好奇心が満ちている。今回の件で、結構気に入ったのかもしれない。
「はい」
答えながら、ふとあたしは手の中のウォークマンに視線を落とした。
確か、今流れているこの曲は......。
ああ。そうか。
運命の導きなんて大層なものじゃないし、信じる口でもないけれど。今ここに、先輩がいる意味が分かった様な気がした。
手の中のイヤホンを、先輩に差し出す。
「聞いてください」
何か、有無を言わさぬ調子になったけど、先輩は気にしなかった。素直にあたしの手からイヤホンを受け取る。
「何て言う曲?」
当然の問いかけ。あたしも、当然の様に答える。
「『Re_birthday』です」
「どんな曲?」
「聞けば、分かります」
そして、あたしは再生ボタンを押した。
♪~~♪♪~♪
微かな振動が、曲の始まりを教えてくれる。見てみれば、先輩は目を閉じて曲に聞き入っている。
しばし流れる、静かな時間。
やがて、ウォークマンのから伝わるリズムが静かに消える。曲が、終わったのだ。
先輩が、イヤホンを外してあたしを見た。
「吉崎さん、これって......」
「作者は明言してませんけどね。そう言う、事です」
「そっか......」
そう言うと、先輩は愛しげにイヤホンを胸に抱く。
「”あの娘”は、この歌を歌うのかな?」
「分かりません。少なくとも、あたしは聞いてません」
「そうか......」
そう呟くと、先輩はフェンスに背もたれて、空を仰いだ。
「歌える日、来ますかね?」
あたしが問うと、先輩は大きく頷く。
「来るよ......。きっと、ううん。必ず、来る」
どこか確信を持った声で、そう言った。
「そう、ですね」
反論する理由などない。あたしも頷くと、先輩と同じ様にフェンスにもたれて、空を仰いだ。
「吉崎さん」
先輩が言う。
「もう一度、聞こう。今度は、一緒に」
そして、イヤホンの片方を差し出してきた。
思わず、「ええ?」と声が出た。
「嫌ですよ」
「どうして?」
いや、どうしても何もあるものか。一本のイヤホンを二人でなんて、恋人同士がやるものだろう。普通。って言うか、恋人がいる身なのに、そういう事は気にならないのだろうか。この女(ひと)は。
「そんな硬い事言わないでいいから。ほら」
結局、半ば強引に押し切られた。
渋々、イヤホンの片側を耳にはめる。
近くに寄せられる、先輩の顔。サラリとした髪が頬をくすぐって、微かに甘い香りが漂う。一瞬、ドギマギしてしまった。
それを誤魔化す様に、ウォークマンを操作する。
「それじゃ、始めますよ」
「うん」
先輩が頷くのを見計らって、再生ボタンを押す。
♪......♪♪......♪......♪♪♪......
静かに流れ始める伴奏。
ふと横をみると、先輩はもう、目を閉じて聞き入っている。
それに倣う様に、あたしも目を閉じると歌に身を委ねる。
白い世界の中で、調べは紡ぐ。
悪と呼ばれた姉弟。その最後の物語を。
歌は綴る。
罪が許される事はない。けれど、未来はあるのだと。
今のあの娘は、きっとこの歌は歌えない。
受け入れる事も出来ない。
でも、きっといつかはたどり着ける。
今は、暗闇の中でたった一人。
でも、小瓶のメッセージは繋いでくれた筈。
一度は途切れた、想いと絆を。
それなら、彼女はきっと歩み出せる。
そして、歩みつづけた先にはきっと......。
歌が終わる。
止まっていたゼンマイを巻き終える様に。
あたしは願う。
きっと、先輩も願っている。
いつの日か、あの娘がこの曲を奏でられる日がくる事を。
あの娘のゼンマイが、動き出す日を。
優しい調べの中、意識が眠りへと落ちていく。
意識を手放すその間際。
見えた気がした。
暗闇の中、白く染まる道。
その上を、固く手を繋いで歩く、二人の少女の姿が。
終わり
【このカテゴリーの最新記事】

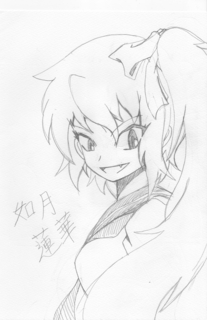


.jpg?2023-01-2212:27:19)
