こんばんは。
今日も「想い歌」、更新です。
―13―
「~♪君は王女 僕は召使い♪~」
綺麗な夕焼けに照らされる、放課後の屋上。誰もいないその空間に、涼やかな歌声が流れる。
歌の主は如月蓮華。
彼女は転落防止用のフェンスの上に座り、足を外に投げ出して歌っていた。
先にも言った様に、場所は屋上。投げ出された足の先には当然、何もない。しかし、そんな事は意も介さず、如月蓮華は朱に染まる空を見上げながら歌っていた。
宙に浮かんだ足をトントンとフェンスに打ちつけてリズムをとりながら、如月蓮華は歌い続ける。
と、
「歌、上手なんだね。」
不意にかけられた声に、如月蓮華は歌うのを止め、後ろを振り向いた。
「だけど、そんな事してると、危ないよ。」
屋上を通る風に、長い黒髪が舞う。
「少し、話したい事があるの。」
降り注ぐ朱光の中、如月蓮華を見上げる様に立った秋庭里香が、静かな声でそう言った。
それより少し前、一年三組の教室では吉崎多香子が下校準備をしていた。
教科書やノートを鞄に詰め、さて帰ろうと廊下に出たところ、その廊下で困った様にウロウロしている一人の女生徒が目に入った。
知らない顔ではない。一年二組の大森芳子だ。
吉崎多香子とは家が割合近く、小学校の時からクラスこそ違えど、同じ学校に通い続けている腐れ縁の仲でもある。
「何してんの?あんた。」
吉崎多香子がそう声をかけると、大森芳子は初めて気がついた様にこちらを向いた。
「あ、多香子~。ちょっと、聞いてよ。」
大森芳子は情けない声を出して、話し始めた。
彼女が帰ろうとしていた時、教室に顔を出した担任の田島に声をかけられたのだという。
彼は教室に入ってくるとキョロキョロし、如月蓮華はもう帰ったのかと聞いてきた。
教室の中に姿がなかったので、多分そうなんじゃないですかと答えたのがまずかった。
田島はそれならと彼女に話をふってきたのだ。
何でも、如月蓮華に渡す書類(転校関係の何からしい)を、彼女の家に届けて欲しい、との事だった。
何であたしが、と大森芳子が訊くと、彼女の家は君の帰り道の近くだから、と住所を書いた紙を書類と一緒に渡されたらしい。
その紙を見せてもらうと、なるほど。大森芳子の家と学校の中間辺りの住所だ。
「参っちゃったよ。」
と、大森芳子は溜息をつく。
何がそんなに「参った」なのかを訊くと、「だって、あたし、あの娘苦手なんだもん。」などと言ってきた。
確かに、生徒の間における如月蓮華の評判は良いとは言えない。
仲の良いカップルの片割れを略奪愛しようとしている事に対して、道義的な憤慨を抱く者もいるが、それ以上にその普段の所作から滲み出る得体の知れなさを気味悪がる声が多かった。
無理もないかもしれない、と吉崎多香子は思う。
そもそも、学校という集団生活の空間において、一人の人間がその本質を隠し通すのは至難の業だ。
何しろ、何百人と言う人間の目に毎日晒されるのだ。遅かれ早かれ、多かれ少なかれ、その人間の本質は知れていく。
そしてその暴かれた本質を通して、同じ方向性の本質を持った者同士は友人やカップルとなり、全く反対の 本質を持つ者同士はただの他人となっていく。
学校というのは、そうやって出来た無数のコミュニケーションの塊だ。
つまり、その本質が同調を得難いものであればあるほど、その人物は学校の中に出来た無数のコミュニケーション体の中から弾かれ、孤立していく。
かつて、そう言ったコミュニケーションの形成に入念だった吉崎多香子は、その事を良く知っていた。
普通に隠そうとしていてさえ、そうなのだ。
それが、如月蓮華に至ってはそれを隠そうすらしない。
むしろ、その特異性をさらけ出し、自分の武器として使っている。
昨日の、瀬良姫子達の化け物でも見る様な目が思い出される。
あの類の視線を、如月蓮華は自ら望んで受けているのだ。
如月蓮華は、孤独だった。
そして、それを凌駕するほどに、強かった。
「あ~ん。もう、どうしよう~!?」
真剣に悩んでいる、大森芳子。
まあ、あたしには関係ない事だ。とそのままスルーしかけた吉崎多香子だが、ふとその足が止まる。
自分と大森芳子の家は近い事は先に言った。と言う事は、その役目は自分でも担えると言う事である。
一つの考えが、思いつく。
それが頭に浸透すると同時に、吉崎多香子は大森芳子に向かって手を伸ばしていた。
「それ、ちょうだい。」
「え?」
「あたしが、届けてあげる。」
そう言って、吉崎多香子は微笑んだ。
「・・・何しに来たんですか?秋庭さん。」
肩越しに秋庭里香を見下ろしながら、如月蓮華は言う。
「言ったでしょ?話したい事があるの。」
その視線を真っ直ぐに受け返しながら、秋庭里香も言う。
「話したい事?」
クルリ
フェンスの上で、平行棒でもやる様に手で身体を反転させると、如月蓮華はポンと3mの段差を飛び降りた。
「だから、危ないよ。落ちたらどうするの?」
「大丈夫ですよ。慣れてますから。」
そう言って、着地の態勢から立ち上がると如月蓮華はパンパンと制服についた埃を掃う。
「・・・で、話って何ですか?わざわざそっちから来なくても、今から自転車置場に行くつもりだったんですけど。あ、それともひょっとして・・・」
如月蓮華、両手を合わせて目をキラキラさせる。
「敗北宣言ですか?とうとう戎崎先輩を渡す気になったとか・・・」
「あたし、真面目に話してるんだけど・・・。」
「心外な!あたしはいつも真面目です!!」
そんな、どこまでが本気か分からない如月蓮華の視線を、しかし秋庭里香は真正面から受け止める。
その様子に、如月蓮華の顔からもふざけた調子が消えていく。
代わりに張り付くのは、あの能面の様な、無表情な顔。
「・・・何なんですか?一体・・・。」
「・・・歌、ほんとに上手だった。習ってたの?」
「習ってないですよ。独学・・・って程でもない。下手の横好きってやつです。」
「聞いた事ない歌だった。何て歌?」
「『悪ノ召使』・・・ボカロの歌ですよ。」
「ボカロ?」
「ボーカロイド・・・。人の代わりに歌ってくれるPCソフトです。知らないんですか?」
「パソコン、持ってないから。」
「はぁ、そうですか。」
「声楽部とか、入ればいいのに。」
「嫌いなんですよ・・・。群れるの。ウザッたいから。」
「もったいないなぁ・・・。」
「余計なお世話です。何ですか?世間話しにきたんですか?」
苛立つ如月蓮華を見つめると、秋庭里香は静かに、だけど声に力を込めて言った。
「これ以上、裕一に付き纏わないで。」
「!」
その言葉に、如月蓮華は目を細める。
「以外ですね。秋庭さんがともあろう人が、そんなそこらの一般女性みたいな面白味のない台詞、口にするなんて。」
その嘲る様な調子の言葉にも構わず、秋庭里香は話を続ける。
「別に、今の話を面白くしようなんて思ってないし。」
「そうですか?」
「聞いたよ。昨日の放課後の事・・・」
細まった目が、ますます細くなる。
薄い唇から、ククッという笑い声が洩れる。
「ああ、“アレ”ですか?誰から聞きました?そういえば、一人見学者がいたっけ。あの娘、秋庭さんと仲よかったですよね?そこですか?漏洩元は。」
クックッと笑う如月蓮華。
その様子に、秋庭里香は眉をひそめる。
「・・・本当なんだ。」
「本当ですよ?それがどうかしましたか?何か悪い事でも?振りかかった火の粉を払っただけです。被害者なんですけど?あたし。」
「悪いとは言わない。だけど、やっぱり裕一には近づかないで。」
重ねられる言葉。
如月蓮華が、秋庭里香をじっと見つめる。
「・・・その心は?」
「やりすぎだよ。何もかも。そんな事してたら、あなたの周りには誰もいなくなっちゃう。」
「構いませんよ。言ったでしょう?群れるのは嫌いだって。」
「あなたはそうでも、裕一はそうじゃない!!」
語気を強めた言葉が、如月蓮華を打つ。
「あなたが側にいたら、裕一からも人が離れていっちゃう!!それは駄目!!裕一はこれからもっと沢山の人と関わって、友達になって、世界を広げていくの!!それを、あなたは一人で無茶苦茶にしちゃう!!」
投げ付けられる言葉を、如月蓮華は全て受け止めた。しかし、その能面の様な表情はピクリとも動かない。
「裕一の事、好きなんでしょう?」
「・・・・・・。」
「だったら、分かるよね?」
「・・・・・・。」
「それでも離れないっていうなら、あたしが許さない。」
突きつける、最後通告。
二人の間に、しばしの間流れる沈黙。
それがどれ程の間だったのかは、分からない。
いつしか辺りを朱に染めていた夕日は山の陰に隠れかけ、屋上を薄い夜闇が覆い始めていた。
と、
「ク・・・クク・・・」
続いていた沈黙に、異音が混じる。
「・・・・・・?」
怪訝そうな顔をする秋葉里香。
その彼女の前で、如月蓮華の肩が震えていた。
一瞬、泣いているのかとも思ったが、そうではない。
「クク・・・ククク・・・クックックックッ・・・」
笑っていた。
その細い肩を震わせ、如月蓮華は笑っていた。
「ククク・・・何ソレ?心配してるって訳?戎崎先輩の将来を・・・?よりにもよって、“アンタ”が・・・?」
沈みかけ、色の濃くなった陽光を背に受けたその顔は、暗く沈んで表情を読み取る事は出来ない。だけど―
「クク・・・ククク・・・」
歪な笑みの形に歪んだその口だけが、闇に沈んだ顔の中で妙にハッキリと見えた。
そして―
「アハ!!アハハハハハハッ!!」
―闇が、弾けた―
その頃、吉崎多香子は住所を片手に如月蓮華の家を探していた。
「え・・・と、多分この辺り・・・」
と、その目が一軒の木造建屋の貸家に止まる。
表札には、「如月」の文字。
「・・・ここか。」
正直、自分が何をしたいのかよく分からない。
ただ、ここにくれば、如月蓮華の事が何か分かるかもしれないという漠然とした思いがあった。
じゃあ、如月蓮華の事を知ってどうしたいのかと問われれば、やっぱりそこに明確な答えはない。
秋庭里香のため?
戎崎裕一のため?
それともその二人のため?
馬鹿げてる。
自分が、あの二人にそうまでしてやる義理などあろうか?
昼休みにした、あの忠告で十分ではないか。
そうは思うものの、吉崎多香子の足は止まらない。
疑問符を繰り返す頭に反して、足はスッスッと進んでいく。
家の玄関は、もう目の前だ。
吉崎多香子は腹を決めた。
どうせ、請け負った仕事を放り出す訳にはいかないのだ。
入ってしまえば、自分が何をどうしたいのか、見当くらいつくだろう。
そう自分を納得させ、吉崎多香子は目の前の戸に手をかけた。
ガララ・・・
古びた引き戸が、重い音を立てて開く。
「ごめんくださーい。」
薄暗い、家の中に呼びかける。
しばしの間。
もう一度叫ぼうかと思ったその時、家の奥の方から「はーい。」という声が返ってきた。
やがて、出てきたのは一人の女性。
年恰好から察するに、如月蓮華の母親だろう。
「どちら様?」
そう訊かれて、鞄の中から件の書類を取り出し、差し出す。
「如月さんの・・・えと、“友達”です。先生からお使いを頼まれてきました。」
その言葉に、如月蓮華の母親の顔が綻んだ。
「まあ、蓮華の・・・」
嬉しそうな声で言うその様を見て、吉崎多香子はある種の手ごたえを感じた。
書類を受け取りながら、如月蓮華の母親は申し訳なさそうな顔をして言う。
「ごめんなさい。蓮華、まだ帰ってきてないの。良かったら、上がって待っていてくれない?もう少しで帰ってくると思うから。」
・・・予想通りの言葉だった。
「・・・そうですか?じゃあ、お言葉に甘えて・・・」
そう言って玄関に上がると、「さあ、どうぞ」と来客用らしいスリッパが差し出された。
如月蓮華の母親が、心から歓迎している事がよく分かる。
娘に友達が出来たという事が、よっぽど嬉しいらしい。
後ろめたい気持ちがチクリと胸を刺したが、とりあえず気付かないふりをした。
実際、途中で如月蓮華本人が帰ってきたら少々面倒な事になりそうだが、その時はその時である。
これも全てはうら若き恋人達の平穏を護るため・・・と言う事にしておこう。
全くもって、柄ではないが。
いずれ、この貸しはキッチリ払って貰おう。
心にそう決めながら、吉崎多香子は案内されるまま廊下を歩く。
よく掃除が行き届いているのか、家の見た目のわりに綺麗な廊下がスリッパに擦られる度、キュッキュッと音がなる。
その代わりの様に家の壁からは、見た目通り古い木の匂いが微かにした。
やがて通されたのは、小さな客間。
そこに入ると、隣にもう一つ部屋がある。
客間よりもこじんまりとしたそこは仏間らしく、仏壇が置いてあった。
何気なく見ると、その仏壇にはまだ真新しい遺影が飾られている。
(あ、誰か最近、亡くなったんだ。)
そんな事を思いながら、その遺影を見る。
―瞬間、吉崎多香子は硬直した―
「アハ、アハハハハハ、アハハハハハハハ!!」
薄暗い屋上に、甲高い笑い声が響き渡る。
何かのタガが外れたかの様に笑うその様を、秋庭里香は茫然と眺めていた。
「アハ、ハハ、あー可笑しい・・・。」
一頻り笑うと、その眦に浮かんだ涙を指で拭い、如月蓮華は秋庭里香に向き直る。
「・・・何が可笑し・・・!!」
言いかけた言葉が、思わず飲み込まれる。
如月蓮華の眼差しが、変わっていた。
それは戎崎裕一に見せる軽い小娘のものでもなければ、先ほどまで見せていた色のない、無表情な眼差しでもなかった。
それは、暗い、どこまでも暗い焔に彩られた眼差し。
そこに込められるのは、紛れもなき憎悪の念。
秋庭里香の背筋に、怖気が走る。
如何に秋庭里香と言えど、その生きてきた時間は短い。
いくら密度が高いとは言え、経験した事のない事象はいくらでもある。
妬みでも嫉みでもない。
そんな薄っぺらな感情など、ものの数に入らない。
明確な、憎悪。
それを向けられるのは、彼女の人生においてまさに初めての事。
冷たい雫が頬を伝うのを感じながら、秋庭里香は乾いた口で唾を飲み下す。
と、如月蓮華の左手が上がり、サイドで纏めていた髪へとかかった。
シュッ
鋭い音と共に髪を纏めていたリボンが引き抜かれ、長い髪がバサリと広がる。
薄闇の中、暗い陽光を受けて烏の濡れ羽の様に輝くそれは、まるで黒い翼の様に見えた。
「あ~あ、もうヤメヤメ!!やーめたっと!!」
風に舞う髪を鬱陶しげに払いながら、如月蓮華は言う。
「ったく、折角人が幾らかでも傷つかない様にって気を使ってやってんのに、何で自分でぶち壊す様な真似するかなぁ?」
「・・・どういう事?」
突然の豹変に驚きながらも、秋庭里香は問う。
「言ったままよ。大体、今まで何であたしが直接“アンタ”の所に乗り込んで行かなかったと思ってる?変じゃない?隣のクラスだってのに。」
「?????」
混乱する秋庭里香に向かって、如月蓮華はズイと詰め寄る。その迫力に押され、後ずさる秋庭里香。
「自分を抑えるため。アンタとさしで向かい会っちゃあ、こうなるって分かってたから。」
ドンッ
秋庭里香の背が、フェンスに当たった。その顔をかすめる様に腕が伸び、フェンスの金網をガシャンと掴んだ。
「人の将来を心配する?アンタが?笑わせないで。」
己に向けられる憎悪の瞳に竦みそうになりながらも、秋庭里香は声を絞り出す。
「何を、言って・・・!!」
絞り出そうとした声が詰まった。
フェンスを掴むのとは、反対の手が、秋庭里香の左胸をなぞっていた。
いや、なぞっていたのは胸ではなく―
「手術痕だよね?これ。」
声のトーンを落として、如月蓮華は言う。
「!!」
その言葉に、秋庭里香は目を見開く。
「確認済みよ。“この間、触った時”に。」
如月蓮華が、歪に笑う。心の底から、怖気を誘う笑い。
「“ここ”にあるって事は、心臓だよね?九割方。」
胸に当てられた指が、ゆっくりとなぞる事を繰り返す。その感覚に、秋庭里香は思わず身を震わせた。
「病気は何?突発性拡張型心筋症?心室中隔欠損?それとも・・・」
そこで、如月蓮華は少し考える素振りを見せる。そして―
「“先天性心臓弁膜症”?」
パシッ
己の胸をなぞっていた手を、秋庭里香の手が払っていた。
「ビンゴ?」
払われた手を大げさにブラブラさせながら、嬉しそうに言う。
「手術、したんでしょ?どう?完治した?」
歪に歪んだ口が、歪んだ言葉を吐き出す。そこに満ちる悪意を隠す事無く。
「治ってないよね?だから、あんなに“大事に生きてる”んだよね。色んな意味で。」
クックッ、と笑う如月蓮華。絶句する、秋庭里香。
「じゃあ、聞くけど・・・」
如月蓮華の顔が、ぐっと寄せられる。耳朶に、吐息がかかる。それを酷く冷たく感じたのは、気のせいだろうか。
「聞くけどね・・・」
もう一度、言う。念を押すように。いたぶる様に。そして―
「アンタは、いつ“死ぬ”の?」
最後の言葉を、その口はゆっくりと紡いだ。
続く
タグ:半分の月がのぼる空
【このカテゴリーの最新記事】

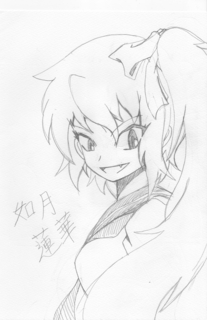


.jpg?2023-01-2212:27:19)
