こんばんは。土斑猫です。
最近、更新が滞り気味で申し訳ないです。
実は、最近在宅ワークを始めまして、時間のやりくりが上手くいかないのです。
仕事に慣れれば、それなりに繰れる様になると思いますので、しばしお待ちください。
という訳で、短いですが「想い歌」更新です。
―22―
「・・・落ち着いた?」
蓮華の嗚咽が止むのを見計らって、あたしはそう声をかけた。
「・・・・・・。」
彼女は黙ったまま服の袖でグイッと顔を拭うと、開口一番、
「屈辱・・・。」
と言い放った。
「何よ?それ。」
「秋庭さんにならともかく、あんたにごときにまで泣かされるなんて。」
「泣かされたんだ。」
「訂正。勝手に泣いただけ。」
そう言いながら、蓮華はゴシゴシと目を擦る。
今日泣くのは2回目だというその目は、幾分腫れぼったく見えた。
やがて、ヨロリと立ち上がると制服についた埃をパンパンと払いながら、あたしを睨む。
「この借りは、いつか返すからね・・・。」
そう言う声は、言葉とは裏腹に酷く弱々しかった。
「まあ、それもいいんじゃない?」
あたしがそう言うと、蓮華が怪訝そうな顔をした。
「何が?」
と訊いてきたので、
「泣くのもさ。」と言った。
「泣きなよ。そして、流しちゃいな。鈴華さんへの想いも、相手の男の子とやらへのわだかまりも。」
全く、我ながららしくない。
まるで、古い演歌の文句みたいだ。
けど、他に気の利いた文句も浮かばない。そのまま、勢いに任せる。
「でないと、あんたはずっとそのまんま。鈴華さんを傷つけ続けるよ。」
そう。この娘に必要なのは、鈴華さんの事を、そしてその相手の少年の事をすっぱり割り切る事。
それが出来た時、初めてこの娘の世界は開かれる。
「・・・・・・。」
「・・・・・・。」
蓮華は、何も言わない。
あたしも、もう何も言わない。
しばしの間。
そして―
「・・・くく・・・」
蓮華の肩が、小刻みに震え始める。
「・・・?」
「くくく・・・あは、ははははは・・・」
笑い出した。
唐突に。
「ちょ・・・ちょっと?」
「ははは、ははははははは!!」
夜闇に響く笑い声。
壊れた様に鳴り響くそれが、あたしの背筋を怖気させる。
「ちょっと!!どうしたのよ!?」
湧き上がる恐怖を振り払う様に、問いかける。
けれど、笑いは止まらない。
壊れた嬌声はしばらくの間、夜を震わせ続けた。
「・・・・・・。」
「ん?どうした?」
帰ろうと自転車を引っ張り出していると、里香が空を見上げている事に気がついた。
「何か、見えるのか?」
もう一度訊くと、里香は「ううん。」と首を振った。
「何かね、如月さんの声が聞こえた様な気がした。」
「うえっ!?」
思わず飛び上がりながら、周りを見回す。
辺りには、すっかり夜闇が堕ちている。
自転車置き場に建てられた外灯だけが、唯一の光源だ。
その光の外の暗闇に、あの幽鬼の様な姿が佇んでいる様に思えて背筋が冷えた。
「そんな気がしただけだよ。裕一、馬鹿みたい。」
キョロキョロと明らかに挙動不審な僕を見て、里香が呆れた様に言う。
「いや、そんな事言うけどな・・・」
「如月さんは、もうあたし達に関わってこないよ。さっき、さよなら言った。」
「お前、信じてんのか?あんな奴の事。」
「如月さん、嘘つかないよ。」
あっさり、言い切った。
「いや、俺散々騙されたんだけど・・・。」
「何、怯えてるの?」
呆れた様な視線が痛い。
だって、仕方ないじゃないか。どんな目に会わされたと思ってんだ。
そんな僕から視線を外して、里香はまた夜空を見上げる。
「如月さんが色々したのは知ってるけど、あの言葉は嘘じゃない。それは、絶対。」
そう言う里香の目は、不思議な確信に満ちている。
僕としては色々と言いたい事はあるけれど、里香がそう言うのならどうしようもない。
里香と蓮華。その有り様に違いはあるけれど、僕達とは違う世界を見ている二人。何か通じるものがあるのかもしれない。里香との世界を蓮華(あいつ)なんかに専有されるのは非常に癪だけど。
「でも・・・」
「ん?」
「それだけ。」
夜空を見つめながら、里香は言う。
「あの娘はまだ、抜けてない。」
「へ?」
意味の分からない言葉。
思わずポカンとする。
「あの娘は、まだ昏いトンネルの中にいる。」
「里香・・・?」
「一人じゃ抜けれない。誰かが手を引いてあげなくちゃ。」
言葉の真意を取りかねてる僕を、里香が見た。
「ねえ、裕一。」
「え?」
「あの娘の手を引いてくれるのは、誰なのかな?」
戸惑う僕を、里香が見つめる。
その瞳は、夜空に瞬く星の様に澄んだ光に満ちていた。
「くく・・・ふふふ・・・」
永遠に続くかと思われた、笑い声。けれど、それもやがて細まって、夜の闇へと溶けていった。
「ふふふ・・・ああ、可笑しい・・・。」
嬌声とともに吐き出したものを取り戻す様に、蓮華は大きく息をついだ。
「・・・何が、可笑しいの・・・?」
半ば呆然としながら、あたしは問う。
そんなあたしを横目で見ると、その顔に笑いの余韻を貼り付けたまま、蓮華は言った。
「だって、同じなんだもの。」
「え・・・?」
「母さんと同じ。あんた、何にも分かってない。」
「どう言う・・・事・・・?」
絞り出した声に返るのは、白い仮面に貼り付けた亀裂の様な笑み。
「あんた・・・まだそう思ってんの?」
言葉の意が、捉えられない。
あたしの戸惑いを無視する様に、蓮華は続ける。
「鈴華があいつの・・・光貴(みつき)のせいで死んだって、そう思ってんの?」
”光貴”。
それが、件の少年の名だろうか?
けれど、それに思考を向ける余裕は、今のあたしにはなかった。
「ホント、揃いも揃って、馬鹿ばっかり。」
ゾクリ
ゾクリ
蓮華が言葉を紡ぐ度、背中を悪寒が走る。
何だ?
この娘は、何を言おうとしているのだ?
「教えてあげるよ・・・。」
響く声は、酷く冷えている。
死者が声を発するとしたら、こんなではなかろうか?
そう思わせる、声だった。
「鈴華を死なせたのは、光貴じゃない・・・。」
「え・・・?」
瞬間、月が陰る。
堕ちる影が、蓮華の顔を闇に落とす。
「鈴華が死んだのは・・・」
顔型の闇が揺れる。
冷えた声が、闇に響く。
「鈴華を死なせたのは・・・」
闇の中で、赤い口がパクパクと動く。
紡ぎ出す言葉は、まるで怨嗟の様に流れて溶ける。
「殺したのは・・・」
ヒクリ
喉が、引き連れる様に鳴いた。
次の言葉を、忌避する様に。
でも、流れる呪歌は止まらない。
そして、最後の言葉が紡がれる。
「あ・た・し・だ・よ。」
辺りを染める闇が、怯える様に震えた。
続く
【このカテゴリーの最新記事】

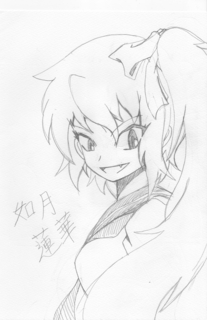


.jpg?2023-01-2212:27:19)
