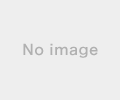現行民法の規定による、相続人・相続分は以下の通りである。
第1順位=配偶者と子が相続人。配偶者が2分の1、子が2分の1。
第2順位=配偶者と直系尊属が相続人。配偶者が3分の2、尊属が3分の1。
第3順位=配偶者と兄弟姉妹が相続人。配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
代襲相続人=相続人である子、又は相続開始以前に死亡・排除等により相続できない時、その者の子が代わって相続人となる(正し、兄弟姉妹の場合は、その子までしか代襲相続できない)。
非摘出子=相続分は、摘出子の2分の1。
③ 遺産分割
相続人の間で、相続財産を配分する事を遺産分割と言う。
遺言があればそれに従い(民法908条)、それがなければ協議によって行う(民法907条1項)。
分割が終了すれば、遺産分割協議書を作成する。
又、協議が纏まらなければ、家庭裁判所に遺産分割の審判を求める事ができる(民法907条2項)。
④ 相続の放棄・承認
相続人が、相続財産の継承を受諾する意思表示を相続の承認と言う。
全面的に相続を承認する場合が単純承認であり、相続人が相続財産の限度でのみ、被相続人の債務を弁済すると言う留保条件を付して行う承認を限定承認と言う(民法912条)。
限定承認は、相続人全員で申立てを行わなければならない(民法923条)。
又、財産を相続したくない何らかの事情があれば、相続財産の承認を全面的に放棄する事ができる。
放棄は、自己の為に相続の開始があった事を知った時から三箇月以内に家庭裁判への申述によって行い、放棄者は、最初から相続人でなかった事になる(民法939条)。
⑤ 遺留分
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有する(民法1028条)。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の時は、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1である。
遺留分は、被相続人死亡後の、相続人の生活を保障する為に認められた制度である。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
遺留分は、直系卑属・尊属と配偶者のみに認められるらしい。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image