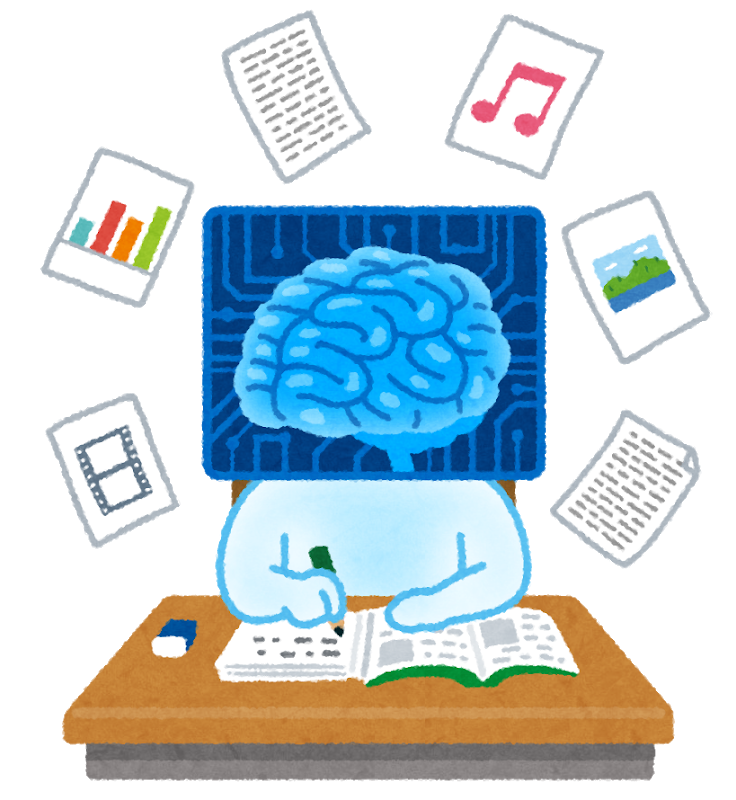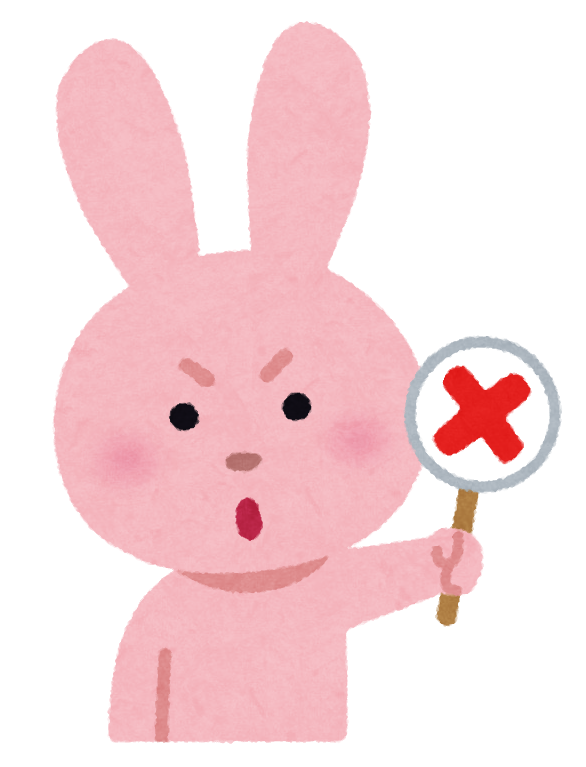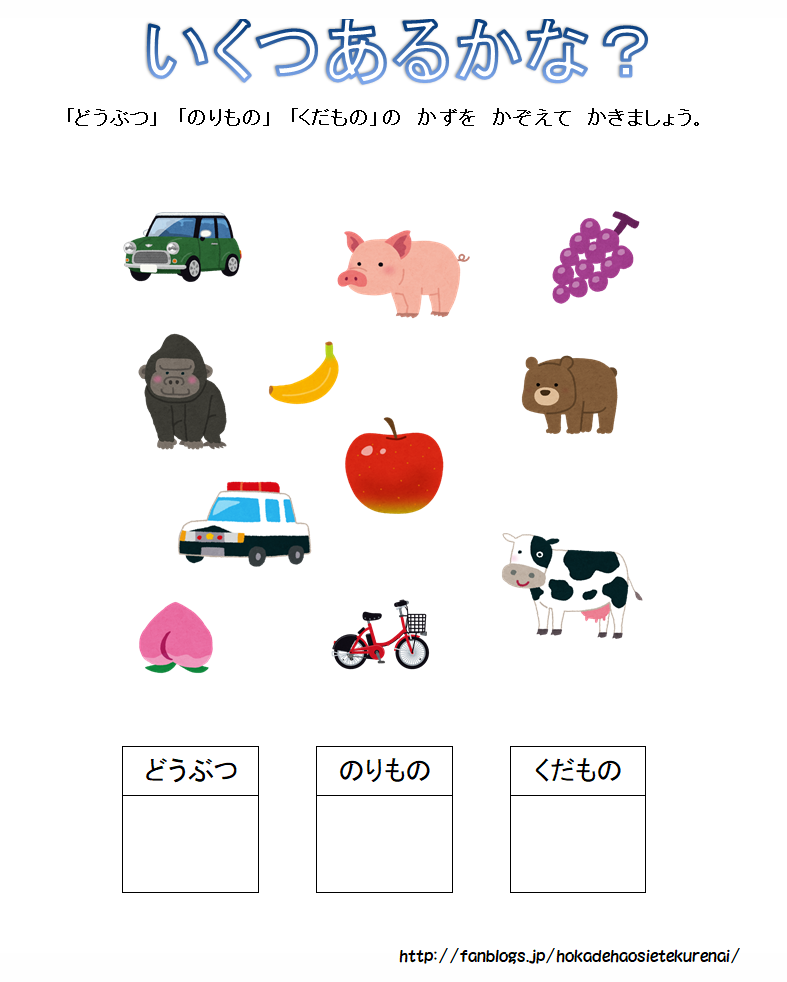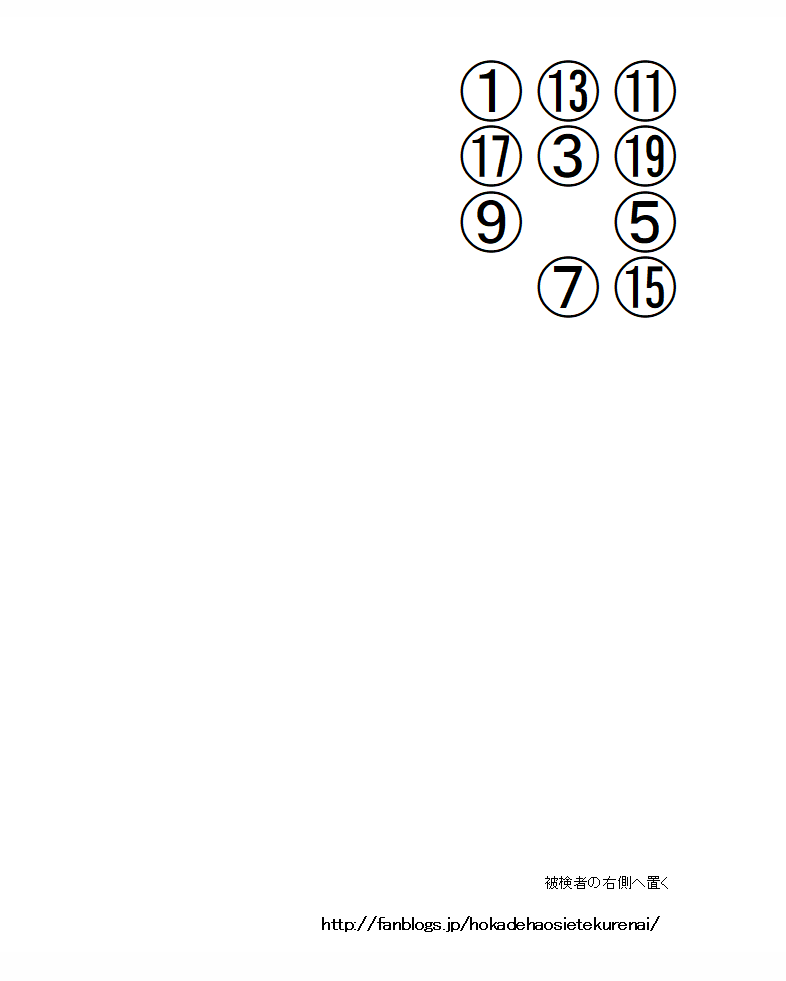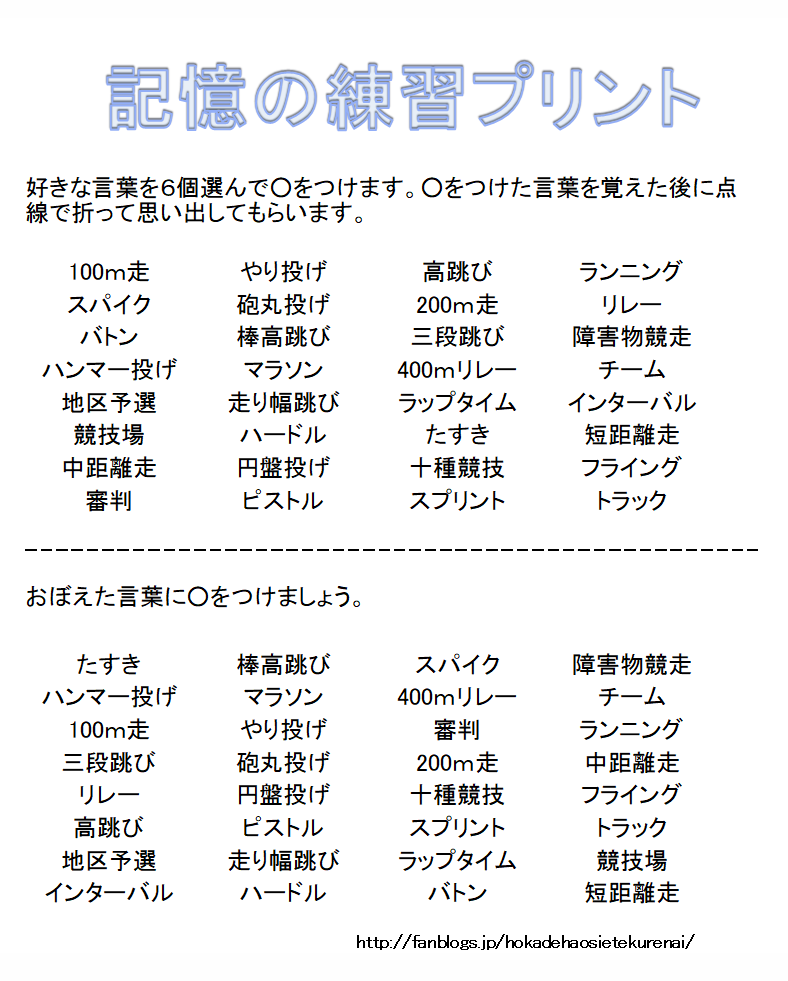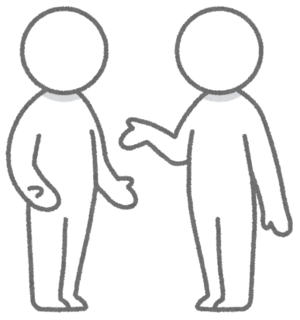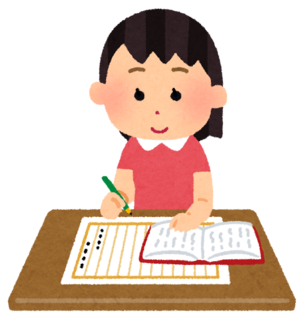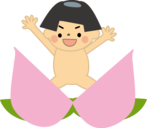2018年10月13日
学生に身につけてもらいたい”力” 臨床実習生について part2
皆さんこんにちは!
当サイトを運営している桃の助です!
本日は、昨日の続きの「学生に身につけてもらいたい”力”」についてお話ししたいと思います。
昨日の内容をまだご覧になっていない方はそちらからぜひご覧ください。
・学生に身につけてもらいたい”力” part1
もう読んだよ!という方は、このまま下へお進みください。
 スポンサード リンク
スポンサード リンク
さて、それでは本題に入りたいと思います。
昨日は、「疑問を持つ習慣」「探究心」についてお話ししましたが、実際に学生に対してどういった指導をすれば、そういった習慣がつくのかについてお話ししたいと思います。
まず第一に、何度も掘り下げることが大切です。
CCSでの教育プログラムでは、見学、模倣が基本となります。
CCSでの教育でいい点は、担当した療法士の訓練を直接実施できる点です。
でも、逆を言えば、教えてもらえる分、あまり深く考えなくても訓練が出来てしまうという難点もあります。
そこは、担当した療法士の腕の見せ所です。
学生を生かすも殺すも指導する療法士次第!
そのまま訓練だけ見せるスタイルでは、学生が就職してから苦労することでしょう。
なので、学生に深く考える習慣を身につけさせる必要があります。
では、どうすればいいかと言うと、
何度も何度も学生に質問をして下さい。
・これをやっている意味はどうしてだと思うか?
・どうしてこれをしなくてはいけないのか?
・どのタイミングでやらなくてはいけないのか?
・この症状から予想される病気は何か?
小さなことでも考えさせることが大切です。
そして、学生から返ってきた答えに対して、理由も尋ねましょう。
もし、間違った答えであれば、正してあげましょう。
もし、正しい答えであれば、さらに深く尋ねましょう。
どんどん掘り下げて質問していくことが大切です!

でも、ここで一つ注意が必要です!
よくありがちな誤った指導方法があります。
それは、
一つの答えに対して、長々と指導することです。
学生が答えた一つの答えに対して、全てを教えてしまう療法士がいます。
これは誤りです。
学生は、分からないながらも絞り出した答えです。
回答するだけで物凄く緊張しているかもしれません。
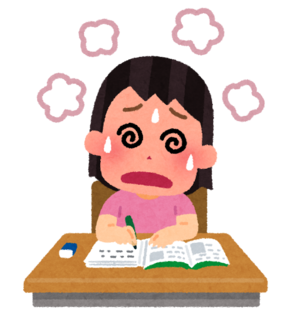
それに対して指導者がさらに深く説明しても、学生の頭はいっぱいになることでしょう!
一つの質問に対して、一つの回答。
さらに、また一つ質問をして、学生が答えにたどり着きやすくしていきます。
そのために指導者が気を付けることは、
スモールステップでの質問を心がけること!です。
これはとても技術がいることです。
指導者が明確な答えを分かっていなければいけませんし、それまでの道筋を順序立てて理解していなければなりません。
この点については、指導者自身が、技術を磨かなければなりません。
私は、学生が来ることを「面倒だ」「大変だ」とは全く思いません。
むしろ、たくさん私のところに来てほしいとおもっています。
学生に質問をする時には、自分も試されている場だと感じています。
学生が臨床実習で来てくれる事で、私自身も成長させてもらっているように感じています。
私自身、「死ぬまで勉強」と思っています。
なんでか分からないですが、この記事を書いていたら、学生の指導が楽しみになってきました! 笑
笑
この記事を読んだ皆さんも、ぜひ参考にされてみてくださいね
そうは言ったものの、日ごろから疑問に思う習慣はなかなか身につくものではありません。
それまでの育ってきた環境で違いますが、人はなかなか変われないものなのです。
でも、リハビリの実習期間は長ければ2か月ほど療法士と行動を共にします。
2カ月もの間、一緒に行動できれば、考え方も少しは変える事はできるでしょう!
学生も指導者の方も頑張りましょう!
それでは今日はこのへんで。
桃の助でした!

ブログランキング参加中です。クリックをお願いします。

 スポンサード リンク
スポンサード リンク
当サイトを運営している桃の助です!
本日は、昨日の続きの「学生に身につけてもらいたい”力”」についてお話ししたいと思います。
昨日の内容をまだご覧になっていない方はそちらからぜひご覧ください。
・学生に身につけてもらいたい”力” part1
もう読んだよ!という方は、このまま下へお進みください。
さて、それでは本題に入りたいと思います。
昨日は、「疑問を持つ習慣」「探究心」についてお話ししましたが、実際に学生に対してどういった指導をすれば、そういった習慣がつくのかについてお話ししたいと思います。
まず第一に、何度も掘り下げることが大切です。
CCSでの教育プログラムでは、見学、模倣が基本となります。
CCSでの教育でいい点は、担当した療法士の訓練を直接実施できる点です。
でも、逆を言えば、教えてもらえる分、あまり深く考えなくても訓練が出来てしまうという難点もあります。
そこは、担当した療法士の腕の見せ所です。
学生を生かすも殺すも指導する療法士次第!
そのまま訓練だけ見せるスタイルでは、学生が就職してから苦労することでしょう。
なので、学生に深く考える習慣を身につけさせる必要があります。
では、どうすればいいかと言うと、
何度も何度も学生に質問をして下さい。
・これをやっている意味はどうしてだと思うか?
・どうしてこれをしなくてはいけないのか?
・どのタイミングでやらなくてはいけないのか?
・この症状から予想される病気は何か?
小さなことでも考えさせることが大切です。
そして、学生から返ってきた答えに対して、理由も尋ねましょう。
もし、間違った答えであれば、正してあげましょう。
もし、正しい答えであれば、さらに深く尋ねましょう。
どんどん掘り下げて質問していくことが大切です!

でも、ここで一つ注意が必要です!
よくありがちな誤った指導方法があります。
それは、
一つの答えに対して、長々と指導することです。
学生が答えた一つの答えに対して、全てを教えてしまう療法士がいます。
これは誤りです。
学生は、分からないながらも絞り出した答えです。
回答するだけで物凄く緊張しているかもしれません。
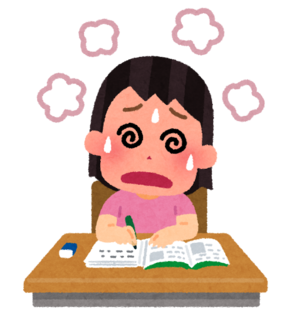
それに対して指導者がさらに深く説明しても、学生の頭はいっぱいになることでしょう!
一つの質問に対して、一つの回答。
さらに、また一つ質問をして、学生が答えにたどり着きやすくしていきます。
そのために指導者が気を付けることは、
スモールステップでの質問を心がけること!です。
これはとても技術がいることです。
指導者が明確な答えを分かっていなければいけませんし、それまでの道筋を順序立てて理解していなければなりません。
この点については、指導者自身が、技術を磨かなければなりません。
私は、学生が来ることを「面倒だ」「大変だ」とは全く思いません。
むしろ、たくさん私のところに来てほしいとおもっています。
学生に質問をする時には、自分も試されている場だと感じています。
学生が臨床実習で来てくれる事で、私自身も成長させてもらっているように感じています。
私自身、「死ぬまで勉強」と思っています。
なんでか分からないですが、この記事を書いていたら、学生の指導が楽しみになってきました!
この記事を読んだ皆さんも、ぜひ参考にされてみてくださいね
そうは言ったものの、日ごろから疑問に思う習慣はなかなか身につくものではありません。
それまでの育ってきた環境で違いますが、人はなかなか変われないものなのです。
でも、リハビリの実習期間は長ければ2か月ほど療法士と行動を共にします。
2カ月もの間、一緒に行動できれば、考え方も少しは変える事はできるでしょう!
学生も指導者の方も頑張りましょう!
それでは今日はこのへんで。
桃の助でした!
ブログランキング参加中です。クリックをお願いします。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8197688
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック