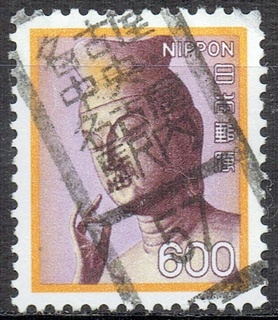新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2022年01月23日
旧キク15円の分室局櫛型印(名古屋中央局豊田ビル内分室)
旧キク15円は定形書状額面用として昭和41年7月に発行されましたが、1年後に色検知用として新キク15円が発行されました。発行枚数は約24億枚ですが現在となっては満足できる消印を収集するのには難しくなるようです。発行当時は産業図案の女工15円や五重塔航空円位15円は窓口にあり、そちらを優先して処分されています。消印は昭和43年のD欄分室名入りの櫛型印、名古屋中央局豊田ビル内分室です。
(局の変遷)
・1955年11月1日~1973年12月9日=名古屋中央郵便局 豊田ビル内分室
・1973年12月10日~2012年10月9日=名古屋中央郵便局 第二豊田ビル内分室
(局の変遷)
・1955年11月1日~1973年12月9日=名古屋中央郵便局 豊田ビル内分室
・1973年12月10日~2012年10月9日=名古屋中央郵便局 第二豊田ビル内分室
2022年01月20日
風神90円赤茶の分室局櫛型印(松山中央局郵政局内分室)
昭和46年7月の郵便料金改定に伴い、速達加貼り料金が70円に値上げになったため、定形書状速達1枚貼り用として発行されたのが風神90円赤茶です。風神90円金茶を速達色検知用として赤系の色へ改色して発行されました。この切手も特定局や簡易局などの窓口での押印が多いため、分室局の櫛型印もありますが新はにわの馬65円ほど多くはありません。消印は昭和47年、松山中央局郵政局内分室の櫛型印です。
(局の変遷)
・1944年8月6日~1949年7月15日=松山郵便局 逓信局内分室
・1949年7月16日~1967年5月31日=松山郵便局 郵政局内分室
・1967年6月1日~1989年7月2日=松山中央郵便局 郵政局内分室
・1989年7月3日~=松山宮田郵便局
(局の変遷)
・1944年8月6日~1949年7月15日=松山郵便局 逓信局内分室
・1949年7月16日~1967年5月31日=松山郵便局 郵政局内分室
・1967年6月1日~1989年7月2日=松山中央郵便局 郵政局内分室
・1989年7月3日~=松山宮田郵便局
2022年01月16日
新はにわの馬65円の分室局櫛型印(東京中央局日活ビル内分室)
新はにわの馬65円切手は定形書状の速達便、簡易書留便の1枚貼り用額面として発行されたため、特定局や簡易局などの無集配郵便局の窓口での押印が多かったため、分室局の櫛型印は比較的多く見かけます。ハガキへの速達加貼り使用なども多いため、機械印の消印も多いが分室では配備されていないため存在してはいません。消印は昭和44年の東京中央局日活ビル内分室の櫛型印です。
(局の変遷)
・1952年4月1日~1971年1月31日=東京中央郵便局 日活ビル内分室
・1971年2月1日~2003年3月29日=東京中央郵便局 日比谷パークビル内分室
(局の変遷)
・1952年4月1日~1971年1月31日=東京中央郵便局 日活ビル内分室
・1971年2月1日~2003年3月29日=東京中央郵便局 日比谷パークビル内分室
2022年01月13日
新丹頂鶴100円田型の分室局和文ローラー印(東京中央局日比谷パークビル内分室)
昭和38年7月発行のタンチョウヅルを改色して入り検知枠を入れて発行されたのが新タンチョウヅル100円です。適応額面の郵便料金は無く、キリの良い金額での様々な郵便物に対応できるように発行された切手です。消印は昭和51年の東京中央局日比谷パークビル内分室の和文ローラー印ですが、田型4枚使用済みですのでおそらく小包か定形外の特殊郵便に使用されたものと推測されます。
(局の変遷)
・1952年4月1日~1971年1月31日=東京中央郵便局 日活ビル内分室
・1971年2月1日~2003年3月29日=東京中央郵便局 日比谷パークビル内分室
(局の変遷)
・1952年4月1日~1971年1月31日=東京中央郵便局 日活ビル内分室
・1971年2月1日~2003年3月29日=東京中央郵便局 日比谷パークビル内分室
2022年01月09日
ニホンジカ10円の分室局櫛型印(大阪中央局高等裁判所内分室)
2022年01月06日
梵鐘60円ペアの分室局櫛型印(大阪中央局高等裁判所内分室)
今回の消印は以前整理しました、昭和60年代初期のキロボックスからのモノです。梵鐘60円の使用済みが大量に出てきましたが、企業内では定形郵便用として封書額面の切手はある程度買って保管していたようです。従って封書額面切手の複数枚貼りが多い理由はそのような点にあるようです。現在でも状況は同じなのですが、84円と言う半端な額面のため複数枚使用は計算が紛らわしくなります。梵鐘ペアへの消印は定形外や特殊料金に使用されたのでしょう。大阪中央局高等裁判所内分室の櫛型印です。
(局の変遷)
・1929年4月21日~1947年5月31日=大阪中央郵便局 控訴院内分室
・1947年6月1日~2007年7月29日=大阪中央郵便局 高等裁判所内分室
・2007年7月30日~=北浜郵便局 高等裁判所内分室
(局の変遷)
・1929年4月21日~1947年5月31日=大阪中央郵便局 控訴院内分室
・1947年6月1日~2007年7月29日=大阪中央郵便局 高等裁判所内分室
・2007年7月30日~=北浜郵便局 高等裁判所内分室
2022年01月02日
新はにわの馬65円の分室局櫛型印(札幌中央局丸井内分室)
2022年 新年あけましておめでとうごさいます。本年もよろしくお願いします。
新はにわの馬65円は速達と簡易書留の定形書状用に発行されたため、櫛型印の消印は多く存在しています。当時のエンタイヤでは速達を多く見かけるため、簡易書留の需要は少なかったものと推測されます。発行年は京浜地区と都内南部局のみだったため、昭和42年の消印は非常に少なくなります。消印は札幌中央局丸井内分室の櫛型印です。
(局の変遷)
・1950年6月1日~1959年6月14日=札幌郵便局 丸井内分室
・1959年6月15日~1990年5月9日=札幌中央郵便局 丸井内分室
・1990年5月10日~=札幌丸井内郵便局
新はにわの馬65円は速達と簡易書留の定形書状用に発行されたため、櫛型印の消印は多く存在しています。当時のエンタイヤでは速達を多く見かけるため、簡易書留の需要は少なかったものと推測されます。発行年は京浜地区と都内南部局のみだったため、昭和42年の消印は非常に少なくなります。消印は札幌中央局丸井内分室の櫛型印です。
(局の変遷)
・1950年6月1日~1959年6月14日=札幌郵便局 丸井内分室
・1959年6月15日~1990年5月9日=札幌中央郵便局 丸井内分室
・1990年5月10日~=札幌丸井内郵便局
2021年12月30日
弥勒菩薩像50円赤の分室局和文ローラー印(大阪中央局毎日ビル内分室)
色検知式郵便物自動取り揃え機用に切手に色検知枠を入れて発行された切手のひとつが、弥勒菩薩像50円赤になります。色検知では赤色が速達用になるため、弥勒菩薩像小豆を改色して発行されました。速達以外に簡易書留加貼り用としても多用されています。発行年は実用実験で発売局が限られていたため、初期使用印は稀少です。
(局の変遷)
・1956年8月1日~1999年3月31日=大阪中央郵便局 毎日ビル内分室
・1999年4月1日~=堂島アバンザ郵便局
(局の変遷)
・1956年8月1日~1999年3月31日=大阪中央郵便局 毎日ビル内分室
・1999年4月1日~=堂島アバンザ郵便局
2021年12月26日
埴輪の兵士200円赤の分室局櫛型印(名古屋中央局第二豊田ビル内分室)
昭和51年1月の郵便料金改正に伴い発行されたのが、はにわの兵士200円赤で茶を速達用の赤色に改色して発行されました。定形郵便速達用や簡易書留加貼り用の額面であったため、発行初期から大量に使用されました。また、200円と言うキリの良い数字額面であったことから、小包や特殊郵便を含めて様々な郵便物にも使用されました。消印は名古屋中央局第二豊田ビル内分室の櫛型印です。
(局の変遷)
・1955年11月1日~1973年12月9日=名古屋中央郵便局 豊田ビル内分室
・1973年12月10日~2012年10月9日=名古屋中央郵便局 第二豊田ビル内分室
(局の変遷)
・1955年11月1日~1973年12月9日=名古屋中央郵便局 豊田ビル内分室
・1973年12月10日~2012年10月9日=名古屋中央郵便局 第二豊田ビル内分室
2021年12月23日
梵鐘60円の分室局櫛型印(新宿北局落合長崎分室)
梵鐘60円切手はスイセン60円を引き継いだ切手ですが、スイセン60円は封書額面50円時代に定形重量品用の切手として発行されました。封書額面が50円から60円に値上げされたのが昭和56年1月ですが、梵鐘60円は前年の11月に料金改正の準備として発行されています。料金値上げの頃にはスイセンは殆ど梵鐘へと切り替わっていました。消印は新宿北局落合長崎分室の櫛型印です。
(局の変遷)
・1946年3月11日~1976年6月20日=新宿郵便局 落合長崎分室
・1976年6月21日~1995年7月30日=新宿北郵便局 落合長崎分室
・1995年7月31日~=落合郵便局
(局の変遷)
・1946年3月11日~1976年6月20日=新宿郵便局 落合長崎分室
・1976年6月21日~1995年7月30日=新宿北郵便局 落合長崎分室
・1995年7月31日~=落合郵便局
2021年12月19日
新タンチョウヅル100円の分室局和文ローラー印(天王寺局貯金局内分室)
今回の消印も昭和50年代半ばのキロボックスからの物で、昭和40年代の使用済みもかなり含まれていました。新タンチョウヅル100円は昭和43年8月に発行され、昭和56年7月の銀鶴100円発行まで約14年間発行されたため使用済みのバラエティ、量ともに多い切手です。発行当時は適応額面がなく、キリの良い額面切手としての役割がほとんどです。消印は昭和44年の天王寺局貯金局内分室、和文ローラー印です。
(局の変遷)
・1952年10月16日~1984年6月30日=天王寺郵便局 貯金局内分室
・1984年7月1日~2007年7月29日=天王寺郵便局 貯金事務センター内分室
・2007年7月30日~2021年1月9日=大阪南郵便局 城南寺町分室
(局の変遷)
・1952年10月16日~1984年6月30日=天王寺郵便局 貯金局内分室
・1984年7月1日~2007年7月29日=天王寺郵便局 貯金事務センター内分室
・2007年7月30日~2021年1月9日=大阪南郵便局 城南寺町分室
2021年12月16日
梵鐘60円の分室局和文ローラー印(名古屋中央局柳橋分室)
今回の消印も昭和50年代半ばのキロボックスから出てきたものですが、愛知県内の消印が多くありました。切手は梵鐘60円の消印が大量にある切手ですが、消印は前回の弥勒菩薩像600円同様に見栄えのする和文ローラー印です。梵鐘60円切手は定形額面であり、昭和56年1月から平成元年3月まで発行されたために使用済みは本当に大量にあります。満月印も豊富に残っていますが、特殊な消印でルックスの良い物は思ったほどありません。消印は昭和57年、名古屋中央局柳橋分室印です。
(局の変遷)
・1939年3月11日~1945年9月20日=名古屋柳橋郵便局
・1945年9月21日~1952年8月31日=中村郵便局 柳橋分室
・1952年9月1日~2012年10月9日=名古屋中央郵便局 柳橋分室
(局の変遷)
・1939年3月11日~1945年9月20日=名古屋柳橋郵便局
・1945年9月21日~1952年8月31日=中村郵便局 柳橋分室
・1952年9月1日~2012年10月9日=名古屋中央郵便局 柳橋分室
2021年12月12日
弥勒菩薩像600円の分室局和文ローラー印(名古屋中央局名古屋駅内分室)
今回の消印は、昭和50年代半ばのキロボックスから出てきた物ですが、斜めに押印された和文ローラー印で見栄えの大変良いものです。弥勒菩薩像600円切手は昭和56年3月に発行されましたが、この当時は郵便料金改正が続いたため高額切手の需要増を予測して発行されたものです。従って、他の切手との混貼りが多いのですが満月印収集となると難しく、高額なため注文消しも極端に少ない切手です。平成元年4月の料金改正後は需要が少なくなり整理券種になっています。消印は昭和57年、名古屋中央局名古屋駅内分室印です。
(局の変遷)
・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室
・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局
・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局
・2015年12月14日~名古屋柳橋郵便局
(局の変遷)
・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室
・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局
・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局
・2015年12月14日~名古屋柳橋郵便局
2021年12月09日
郵便番号宣伝4次7円ペアの分室局和文ローラー印(名古屋中央局貯金局内分室)
郵便番号宣伝切手は1968年7月1日より使用開始された「郵便番号」を広く周知するために1次から6次まで発行された切手です。切手カタログでは記念切手のカテゴリーに分類されていますが、実質的には普通切手同様に使用されてました。ハガキ額面切手の発行枚数より封書額面の発行枚数は3倍になり、ハガキ額面の使用済みの方が収集は難しくなります。今回の消印は4次7円ペアの和文ローラー印ですが、おそらく別納からのペアだと思われます。名古屋中央局貯金局内分室印です。
(局の変遷)
・1950年12月1日~1984年6月30日=名古屋中央郵便局 貯金局内分室
・1984年7月1日~2015年12月6日=名古屋中央郵便局 貯金事務センター内分室
・2015年12月7日~2019年12月31日=名古屋西郵便局 名古屋貯金事務センター内分室
(局の変遷)
・1950年12月1日~1984年6月30日=名古屋中央郵便局 貯金局内分室
・1984年7月1日~2015年12月6日=名古屋中央郵便局 貯金事務センター内分室
・2015年12月7日~2019年12月31日=名古屋西郵便局 名古屋貯金事務センター内分室
2021年12月05日
平成切手コアウハナムグリ10円の分室局丸型印(西東京局保谷分室)
平成19年10月1日の郵政民営化に伴い前倒しでその準備が進められ、分室については「貯金・保険会社の支店が設けられる局は分室ではいけない」という規約に基づいて、保谷・福生・稲城若葉台・長野栗田・坂本・瀬田・北浜東・朝里の8分室が同年7月30日より普通局となりました。西東京局保谷分室もそのひとつですが、この局の消印は実逓ではほとんど見かけません。
(局の変遷)
・~2004年3月28日=保谷郵便局(廃止)
・2004年3月29日~2007年7月30日=西東京郵便局 保谷分室
(局の変遷)
・~2004年3月28日=保谷郵便局(廃止)
・2004年3月29日~2007年7月30日=西東京郵便局 保谷分室
2021年12月02日
平成切手ホトトギス3円の分室局丸型印(大崎局NTT関東病院内分室)
今回の切手も前回同様の目的で発行された切手の一つです。この切手は発行の発表もなく突然郵便局で現れています。5円と比較して3円の使用頻度が少ないため消印も少なく、満月印は同様に注文消しがほとんどになります。大崎局NTT関東病院内分室の丸型印で年号部にアンダーバーが入った窓口での消印です。
(局の変遷)
・1959年10月1日~199911年11月30日=大崎郵便局 関東逓信病院内分室
・1999年12月1日~2014年6月28日=大崎郵便局 NTT関東病院内分室
(局の変遷)
・1959年10月1日~199911年11月30日=大崎郵便局 関東逓信病院内分室
・1999年12月1日~2014年6月28日=大崎郵便局 NTT関東病院内分室
2021年11月28日
平成切手コブハクチョウ5円の分室局丸型印(麹町局東京逓信病院内分室)
平成22年頃に大量の郵便物を処理できるインクジェット式の機械印押印機を大型の区分局へ設置するため、郵便物の切手を貼った位置を読み取るため切手の上下にバーを入れた切手を6種類発行しました。そのひとつが平成コブハクチョウ5円ですが結局押印機の機能が向上しバーは必要がなくなりました。実逓での使用済みは少なく満月印は注文消しがほとんどです。消印は麹町局東京逓信病院内分室の丸型印です。
(局の変遷)
・1938年2月21日~2014年7月26日
(局の変遷)
・1938年2月21日~2014年7月26日
2021年11月25日
観音菩薩像350円の分室局櫛型印(大阪中央局高等裁判所内分室)
昭和51年1月の郵便料金改正で書留料金が300円となり、定形書留料金が350円になりましたが該当する額面切手がありませんでした。改正の5ヶ月のにようやく350円の観音菩薩像が発行されました。初めて発行される額面であり初日から全国の郵便局で発売されました。この切手はその後小包や定形外などにも利用されています。消印は昭和61年4月の櫛型印、大阪中央局高等裁判所内分室の消印です。
(局の変遷)
・1929年4月21日~1947年5月31日=大阪中央郵便局 控訴院内分室
・1947年6月1日~2007年7月29日=大阪中央郵便局 高等裁判所内分室
・2007年7月30日~=北浜郵便局 高等裁判所内分室
(局の変遷)
・1929年4月21日~1947年5月31日=大阪中央郵便局 控訴院内分室
・1947年6月1日~2007年7月29日=大阪中央郵便局 高等裁判所内分室
・2007年7月30日~=北浜郵便局 高等裁判所内分室
2021年11月21日
ミズバショウ45円ペアの分室局櫛型印(大阪中央局郵政局内分室)
今回の消印はミズバショウ45円への分室印ですが、この切手は定形外100~150グラムまでの適応額面を主に発行された切手です。昭和42年5月に発行されましたが昭和46年と47年の郵便料金改正で該当する料金は無くなっていますが、昭和60年頃までは一部の局では販売されていました。消印は昭和45年のペアですが他の切手と混貼りで特殊料金に使用されたのでしょうか。大阪中央局郵政局内分室の櫛型印です。
(局の変遷)
・1927年1月16日~1949年6月30日=大阪中央郵便局 逓信局内分室
・1949年7月1日~2003年3月31日=大阪中央郵便局 郵政局内分室
・2003年4月1日~2007年7月29日=大阪中央郵便局 北浜東分室
・2007年7月30日~=北浜東郵便局
(局の変遷)
・1927年1月16日~1949年6月30日=大阪中央郵便局 逓信局内分室
・1949年7月1日~2003年3月31日=大阪中央郵便局 郵政局内分室
・2003年4月1日~2007年7月29日=大阪中央郵便局 北浜東分室
・2007年7月30日~=北浜東郵便局
2021年11月18日
1985年/国際職業訓練競技大会の分室局櫛型印(名古屋中央局第二豊田ビル内分室)
今回の消印は記念切手への分室印で切手発行日より3か月後の消印になります。昭和60年代になると記念切手の発行枚数は3000万枚前後と多くなり、また記念切手を通信用に使用する場合も増えてきています。またシリーズ切手に関しても封書額面50円時代から増え続けいます。とは言え、記念切手への実逓での満月印は稀少で今回の消印は名古屋中央局第二豊田ビル内分室の櫛型印です。
(局の変遷)
・1955年11月1日~1973年12月9日=名古屋中央郵便局 豊田ビル内分室
・1973年12月10日~2012年10月9日=名古屋中央郵便局 第二豊田ビル内分室
(局の変遷)
・1955年11月1日~1973年12月9日=名古屋中央郵便局 豊田ビル内分室
・1973年12月10日~2012年10月9日=名古屋中央郵便局 第二豊田ビル内分室
検索
カテゴリーアーカイブ
動植物国宝切手(605)
記念切手(144)
産業図案切手(8)
昭和切手(8)
慶弔切手(14)
平成切手(144)
航空切手(41)
年賀切手(13)
エンタイヤ(10)
ふるさと切手(10)
その他(3)
記念切手(144)
産業図案切手(8)
昭和切手(8)
慶弔切手(14)
平成切手(144)
航空切手(41)
年賀切手(13)
エンタイヤ(10)
ふるさと切手(10)
その他(3)
プロフィール