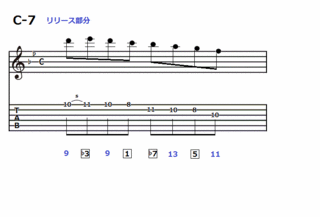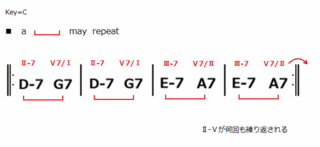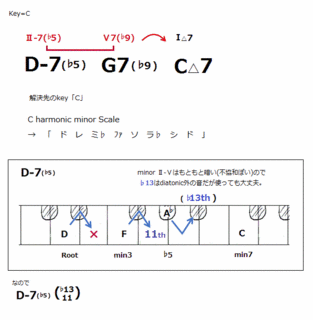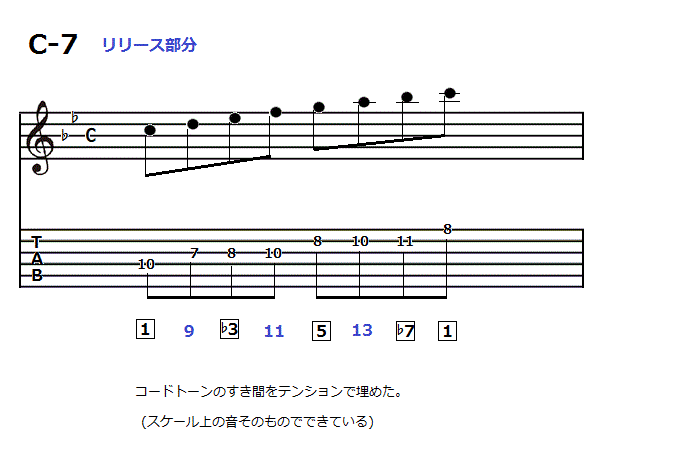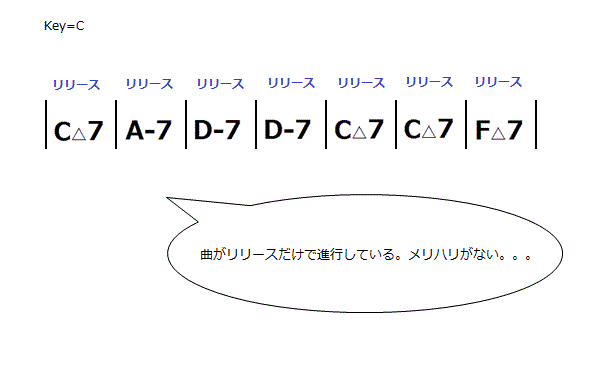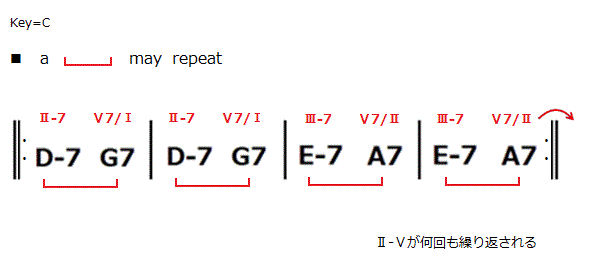新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2015年05月28日
0062.Related Ⅱ-7 コードの使い方とその進行のおぼえ方の説明。あとⅤ7とⅡ-Ⅴ進行の分割とまとめかた。その解釈についてふれました。
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
♪♪今回はrelated Ⅱ-7 chordについてです
Full cadenceのサブドミナントである
ⅣをⅡ-7にすることで、
より強い終止感を与えることができる。
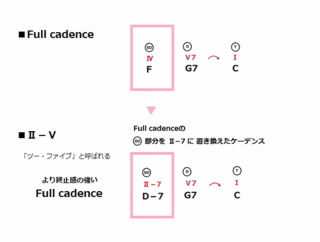
これはPrimary Ⅴ7に対して
Ⅱ-7 コードがⅡ-Ⅴ(Full cadence)で
つながっている状態です
このようなⅡ-7 コードを
→ related Ⅱ-7 といいます
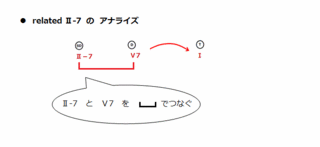
このrelated Ⅱ-7を利用して
各secondary Ⅴ7に対しても
Ⅱ-Ⅴ進行することができます
それぞれのⅡ-Ⅴの進行と
related Ⅱ-7のアナライズを紹介します
説明上
Ⅱ-Ⅴから各diatonic chordまでの進行で書きます
①Ⅴ7/Ⅱに対してのrelated Ⅱ-7

key=Cでいうと
A7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chordのE-7と同一のコードになります
この場合のアナライズはそのまま
diatonic chordのⅢ-7を書きます
②Ⅴ7/Ⅲに対してのrelated Ⅱ-7
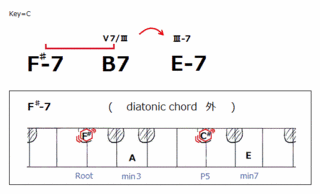
key=Cでいうと
B7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chord 外 のF♯-7コードになります
diatonic chordでない場合のアナライズは、
ディグリーは書かかず
relatedの線だけ書いてつなぎます
③Ⅴ7/Ⅳに対してのrelated Ⅱ-7
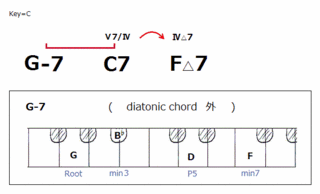
key=Cでいうと
C7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chord 外 のG-7コードになります
diatonic chordでない場合のアナライズは、
ディグリーは書かかず
relatedの線だけ書いてつなぎます
④Ⅴ7/Ⅴに対してのrelated Ⅱ-7
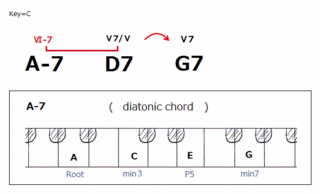
key=Cでいうと
D7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chordのA-7と同一のコードになります
この場合のアナライズはそのまま
diatonic chordのⅥ-7を書きます
⑤Ⅴ7/Ⅵに対してのrelated Ⅱ-7
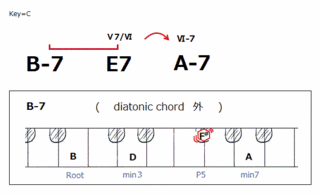
key=Cでいうと
E7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chord 外 のB-7コードになります
diatonic chordでない場合のアナライズは、
ディグリーは書かかず
relatedの線だけ書いてつなぎます
次のはなし。
■すべてのdominant7thはⅡ-Ⅴに分割可能
PrimaryⅤ7だけでなくsecondaryⅤ7などの
すべてのⅤ7コードは、自由に
分割可能
(逆にまとめることも可能)です
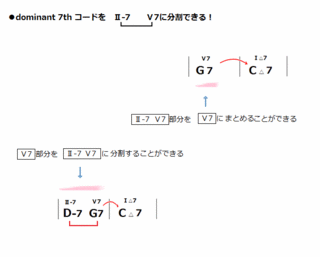
Point!!)
この考えを利用して
解釈のしかたを広げることができます
たとえば)Ⅱ-Ⅴに対して、
Ⅱ-ⅤはFull cadenceなので
サブドミナント【Ⅱ-7】部分
ドミナント【Ⅴ7】部分と
それぞれを分けて解釈することもできるし
今回の
「Ⅱ-7とⅤ7をまとめてⅤ7とできる」ことから
【Ⅱ-7 Ⅴ7部分】は、どちらも合わせて
ドミナント【Ⅴ7】部分と解釈することもできます
こうした解釈はほかにも
考え方が広がるたびに増えてくるけど、
いろんな見方ができるほど
狙いにあった
使うテンションの選択や
コードスケールの選択に生かされていきます
おくぶかし(●´∀`)ノ+゜*
こんかいはひとまずここまで
次回からもしばらくは
related Ⅱ-7についてふれていきます
お楽しみに。
♪♪今回はrelated Ⅱ-7 chordについてです
Full cadenceのサブドミナントである
ⅣをⅡ-7にすることで、
より強い終止感を与えることができる。
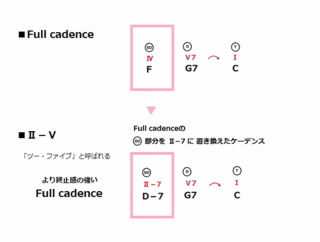
これはPrimary Ⅴ7に対して
Ⅱ-7 コードがⅡ-Ⅴ(Full cadence)で
つながっている状態です
このようなⅡ-7 コードを
→ related Ⅱ-7 といいます
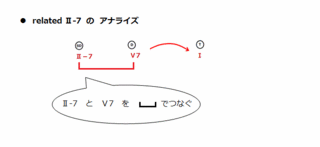
このrelated Ⅱ-7を利用して
各secondary Ⅴ7に対しても
Ⅱ-Ⅴ進行することができます
それぞれのⅡ-Ⅴの進行と
related Ⅱ-7のアナライズを紹介します
説明上
Ⅱ-Ⅴから各diatonic chordまでの進行で書きます
①Ⅴ7/Ⅱに対してのrelated Ⅱ-7

key=Cでいうと
A7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chordのE-7と同一のコードになります
この場合のアナライズはそのまま
diatonic chordのⅢ-7を書きます
②Ⅴ7/Ⅲに対してのrelated Ⅱ-7
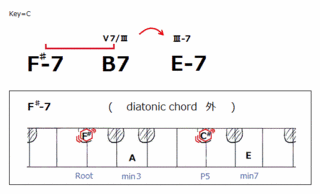
key=Cでいうと
B7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chord 外 のF♯-7コードになります
diatonic chordでない場合のアナライズは、
ディグリーは書かかず
relatedの線だけ書いてつなぎます
③Ⅴ7/Ⅳに対してのrelated Ⅱ-7
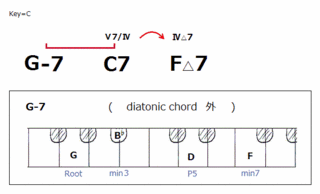
key=Cでいうと
C7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chord 外 のG-7コードになります
diatonic chordでない場合のアナライズは、
ディグリーは書かかず
relatedの線だけ書いてつなぎます
④Ⅴ7/Ⅴに対してのrelated Ⅱ-7
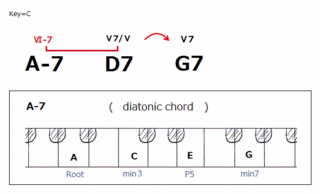
key=Cでいうと
D7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chordのA-7と同一のコードになります
この場合のアナライズはそのまま
diatonic chordのⅥ-7を書きます
⑤Ⅴ7/Ⅵに対してのrelated Ⅱ-7
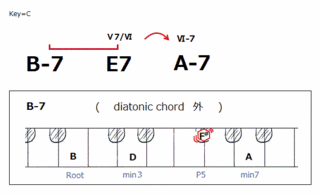
key=Cでいうと
E7につながるⅡ-Ⅴ進行ですが
related Ⅱ-7 コードは
diatonic chord 外 のB-7コードになります
diatonic chordでない場合のアナライズは、
ディグリーは書かかず
relatedの線だけ書いてつなぎます
次のはなし。
■すべてのdominant7thはⅡ-Ⅴに分割可能
PrimaryⅤ7だけでなくsecondaryⅤ7などの
すべてのⅤ7コードは、自由に
分割可能
(逆にまとめることも可能)です
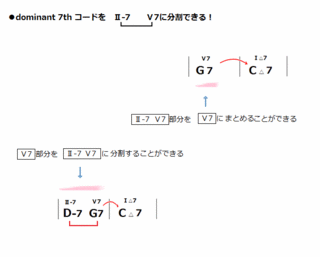
Point!!)
この考えを利用して
解釈のしかたを広げることができます
たとえば)Ⅱ-Ⅴに対して、
Ⅱ-ⅤはFull cadenceなので
サブドミナント【Ⅱ-7】部分
ドミナント【Ⅴ7】部分と
それぞれを分けて解釈することもできるし
今回の
「Ⅱ-7とⅤ7をまとめてⅤ7とできる」ことから
【Ⅱ-7 Ⅴ7部分】は、どちらも合わせて
ドミナント【Ⅴ7】部分と解釈することもできます
こうした解釈はほかにも
考え方が広がるたびに増えてくるけど、
いろんな見方ができるほど
狙いにあった
使うテンションの選択や
コードスケールの選択に生かされていきます
おくぶかし(●´∀`)ノ+゜*
こんかいはひとまずここまで
次回からもしばらくは
related Ⅱ-7についてふれていきます
お楽しみに。
2015年05月25日
0061.セカンダリードミナントのテンションのつけ方の違いから、コードのねらいにあわせた音の選び方が出来るようになるための話にすこしふれます。使える音楽理論をめざしてます
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
この先いろいろと曲を
アウトさせたりするための技法入ってくるので
ここでは
セカンダリードミナントのテンションが
なぜプライマリードミナントと違うのか
ってところにふれつつ
今までの内容をちょっとまとめます
こんかいは息抜き回です
ではまず復習) diatonic chordは ■トライアド部分のmajor9th上の音で ■そのkeyのdiatonic scale上にない音は避ける その中でもⅤ7とⅤ7(sus4)は altered tension(maj9th上以外の音)も使えます →Ⅴ7(sus4)での仕様は、響きを損なうので稀 このⅤ7コードは keyの「Ⅰ」コードへ完全5度ダウンする ドミナントモーションが可能なコードで →プライマリードミナントといい もっとも優先されるドミナントモーションです それに対して セカンダリー ドミナントは 「Ⅰ」以外のdiatonic chordに解決する ドミナントモーションです (例外。「Ⅶ」へもセカンダリーはない) セカンダリーのテンションは ■トライアド部分のmajor9th上の音を考えながら ■chord toneの隙間をkeyのdiatonic音で埋める ■11thはⅤ7(sus4)と区別する意味で除きます |
詳しくは
→プライマリーⅤ7のavailable tensionはこちら
→セカンダリーⅤ7のavailable tensionはこちら
この違いを理解するうえで
Keyの調性に対して
インサイドする(もしくはアウトサイドする)
って部分をしっかり意識したいので
→ 調性について説明します
今回の話では、
この調性は
そのkeyのTonic(key=CならC音が中心音)として
終止感を持ち続けているかどうかが基準とします
ドミナントモーションによる解決だけに限らず、
他のコードも、各スケール音も
それぞれすべてが
●keyのTonicで終われる。もしくは
●連なってkeyのTonicに向かって終れる感じがある
この状態があれば調性が保たれている状態です
つまり調性とは、
→すべての音が、調性の引力で
中心音に引っ張られている状態のことをいいます
例)極端にいうと key=Cで
その調性上のコードなら
どんなコードを鳴らしても、
次でCコードを鳴らせば、曲は終止するし
その調整上のメロディなら
どんなメロディを歌っても
最後にC音を伸ばせば、そこでメロディは終わる
Tonicつえーヾ(*・ω・)ノ゜+.
そしてこの性質とても便利。
これを踏まえて
プライマリーとセカンダリーの違いをみると
Primary Ⅴ7は、diatonic chordなので
完全にkeyにインサイドしています。
仮に
オルタードテンションを付けた場合でも
テンションの音はkeyからアウトしても
コード自体がもつコードの進行感や、
ドミナントモーションの機能によって
特につよくTonicに終止します
→keyにインサイドしている
●ドミナントモーションの機能
例)key=Cでいうと
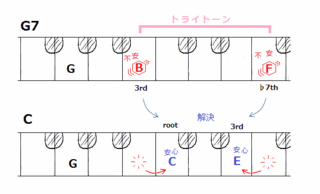
なのでⅤ7コードは
Primaryとしての役割を持つときがもっとも
keyにインサイドし、Tonicを印象付けます
それに対して
secondary Ⅴ7は、
Root自体は、keyにはまっているけど
diatonic外のコードであり、
そのKeyの調性は守ってないし、
また
Ⅴ7系のコードは、本来
Primary Ⅴ7として向かいたいkeyがあるので
たとえば) A7は
key=C の調性上なら
セカンダリーのⅤ7/Ⅱとしての役割をだしますが、
A7はKey=Dのプライマリー Ⅴ7としての響きも
強く持っています
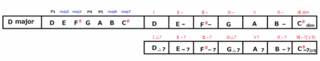
なので
仮にkey=Cの調性上にあっても
このA7が鳴ると
一瞬的には、A7がPrimary Ⅴ7として本来向かう
Key=Dの調性へOutした感じがでます
ここがポイント)
しかし、A7がそのまま進行して
「D」に解決してみると
その「D」のコードは
key=Dの調性上のⅠではなく
key=Cの調性上のⅡ-の役割だったので
(この場合はコードの違いより役割の違いが重要)
セカンダリーで一瞬Outした調性は
またすぐに元の調性に戻ることができます。
このしくみを前提に
次の表をみてください
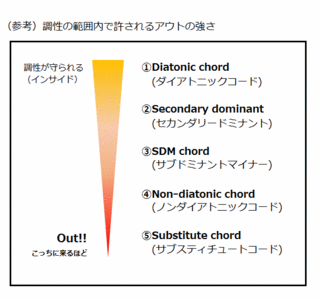
この
セカンダリードミナントは
Outな響きを感じさせる機能ですが
調性の範囲内では
そのOut性の弱いです
逆にいうと
Ⅴ7の中でも、
プライマリーの次に
よりインサイドに戻りやすい性質が
セカンダリーの特徴であり
セカンダリーはむしろ
インサイドを狙うためのコードと解釈できます。
●secondary dominantの条件の
①RootがKeyのdiatonicの音であることや
②解決先のコードに不安定な響きは避ける、
などの条件も、
セカンダリーが
よりインサイドしやすくなるための条件です
つまり
セカンダリードミナントとは
一瞬、Outしたような雰囲気を出しながらも
すぐに調性にインサイドさせるためのコードなので
あまりOutさせないように
使うのがポイントといえます
ドミナントモーションもその意味で
機能するように
フレーズやテンションなどを
考える必要があります
その意味で、
テンションのつけ方を考えると
まず
①プライマリー的なテンションのつけ方だと
■major9th上の音で
■keyのdiatonic音以外は調性を守る意味で避ける
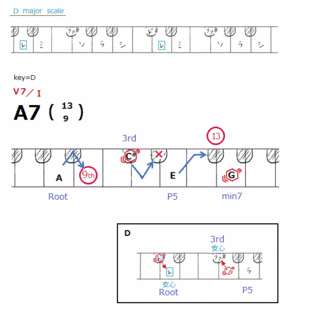
このテンションのつけ方は
解決先「Ⅰ」に対して調性を守るためのものなので
この場合はKey=Dに向かう感じが強まります
→A7(9,13)
とくにこの13thの「ファ♯」音は、
次のコードがDであることを予感させるで
よりKey=CからOutした感じに響きます
Point!)
セカンダリードミナントに
プライマリー的なテンションのつけ方をすると
コードの響きは自然に響きますが
元のkeyに対してはOutした感じが強まります
それに対して
②セカンダリーのテンションのつけ方だと
■トライアド部分のmajor 9th上の音を考えながら
■chord toneのすき間をkeyのdiatonic音で埋めます
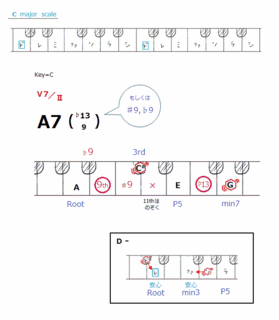
keyのdiatonicの音で埋めるのは、
その音がすべて元のkeyの調性内の音だからです
Point!)
それらの音がテンションとして加わると
オルタードの音も含まれてくるため
コードの響きは不協和が増すけど
調性としては、逆に
元のkeyが予感される音が増えるので
調性にはまって聞こえる
セカンダリードミナントの狙いは
インサイドなので、
available tensionは、後者②のつけ方になります
説明は以上です
ただし! 音楽では調性よりも その前後の流れを重視することも多いので これはあくまでも理論としての まとめ方であり 音楽としては、そこにしばられないという 捉え方もとても大事です ルールは自由になるために使うほうがいいと思う |
今回、大事なのは
いろんな技法の中で、
セカンダリーにはセカンダリーの
狙いがあるっていうのを分かったうえで
それに合わせてテンションなどを
選べるようになるかって部分です。
たとえば、
曲をOutさせようとしたとき
セカンダリーにあえてOutな音を加えて
表現をするのもいいし、
もっとOutする技法に選択し直すのも
ありだと思う
それぞれに違う効果があるので
ここもねらいなのだけど
よし。あえてセカンダリーを
Outさせるぞおおおってなった場合
どんな音を使えば、
よりアウトさせれるのか?
それが
今回の話から
みえてきますよね
ヾ(*・ω・)ノ゜+.ここなんです。
こうした考え方は、
テンションのつけ方の話だけで終わらず
たとえば、フレーズにおいても
スケールに何か1音を加えることで
何か雰囲気を足そうとした場合、
→エッセンシャルトーン(後日)
その1音が、
曲においてどんな効果になるのかを
分かったうえで狙って使えたら
とても便利ですよね
そういうのが分かる内容に
ここを作っていけたらなって思います
(●´∀`)ノ+゜
さいごに)
こんかいは
ちょっと反省するところも多くて
次からは気をつけようと思うのだけど
これからも
知る音楽理論じゃなくて
使える音楽理論になるよう
がんばって内容進めていくので
どうぞおつきあいください
それでは次回。
2015年05月23日
0060. セカンダリードミナントのavailable tensionのつけ方を説明します。これでぜんぶのセカンダリードミナントにテンションがつけれるよ。各Ⅴ7ごとに絵でまとめたからおぼえやすいと思う。
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
♪♪今回はセカンダリードミナントのつづき
available tensionのつけ方についてです
セカンダリードミナントに
available tensionをつける方法は
今までのtensionのつけ方とは
ちょっと方法が違うので気をつけてね
(なぜこのつけ方になるかは重要なので後日)
【スポンサーリンク】
■secondary dominantsのavailable tensions
①chord toneのmaj9th上を考えながらも
chord toneの隙間をkeyのdiatonicの音で埋める
②その音から
11thを除いた音群がavailable tensionとなる
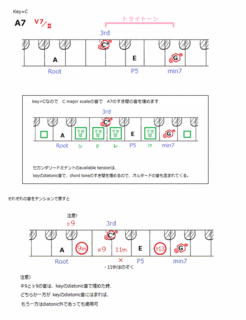
●すき間を埋めた音のテンションの数え方
手順① トライアドの音からそれぞれ
Natural tension音(maj9th上の音)の場所を確認
Root → 9th
3rd → ♯11th
5th → 13th
手順② 9thの前後のすき間に♭9と#9を書く
ポイント!!)
このとき、♭9もしくは#9の音で
すき間を埋めた場合は、
もう一方がkeyのdiatonic音以外でも
使用可能となるので、どちらも書く
手順③ ♯11thの1つ前の「11th」は消す
♯11thは、Keyのdiatonic上にあれば使える
ただし不協成分を持つので使い方には注意。
手順④ 13thの前に隙間があれば♭13を書く
これでかんぺきです
(●´艸`)フ゛ハッ
手順⑤ これらのテンションのうち
どれをavailable tensionと呼ぶかは、
書くセカンダリーごとで暗記するしかないので
以下の図でがんばっておぼえてください
じつは
かんたんなおぼえかたも
いちおうあるので
各図の説明のあとに紹介します
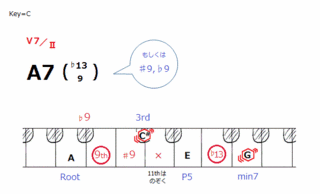
Ⅴ7/Ⅱのavailable tensionは 9と♭13 です
♯9や♭9は、available tensionではないですが
(♭9はkeyのdiatonic外の音でもあるけど)
使用可能です。
→ ただし下記の9thのルール参照のこと
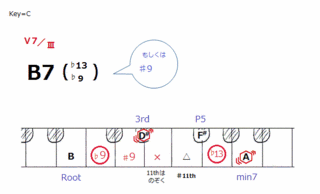
Ⅴ7/Ⅲのavailable tensionは ♭9と♭13 です
♯11thは、available tensionですが
不協成分を持つので使い方に注意する
♯9は、available tensionではないですが
使用可能です。
→ 下記の9thのルール参照のこと
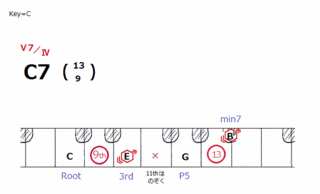
Ⅴ7/Ⅳのavailable tensionは 9と13 です
♭9と♯9の使用は避ける
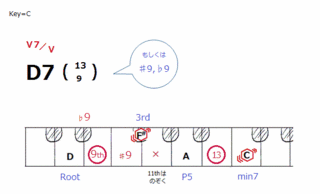
Ⅴ7/Ⅴのavailable tensionは 9と13 です
♯9や♭9は、available tensionではないですが
(♭9はkeyのdiatonic外の音でもあるけど)
使用可能です。
→ ただし下記の9thのルール参照のこと
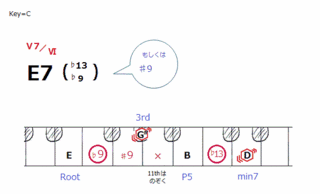
Ⅴ7/Ⅵのavailable tensionは ♭9と♭13 です
♯9は、available tensionではないですが
使用可能です。
→ 下記の9thのルール参照のこと
■かんたんなおぼえかた
次の点に着目するとおぼえやすくなります
●どの9thをavailable tensionとするかを
おぼえやすくする方法
基本9thがkeyのdiatonicにあるときは
♭9や#9ではなく、「9th」が
available tensionになる
逆に9thがkeyのdiatonicに無く、
♯9と♭9があるときは、
「♭9」のほうがavailableになる
●available tensionの組み合わせを
かんたんにおぼえれるようにする方法
メジャー系のコードに解決する
ドミナントコード
・プライマリーのⅤ7/Ⅰ
・セカンダリーⅤ7/Ⅳ、Ⅴ7/Ⅴの3種は
ぜんぶavailavle tensionは(9,13)になるので
おぼえるのが かんたん
たすかる
゜*。(*´Д`)。*°
あともう1こ
トニックの仲間である
Ⅲ- およびⅥ-に解決する
セカンダリー Ⅴ7/ⅢとⅤ7/Ⅵの2種は
どちらもavailable tensionが(♭9,♭13)なので
これもおぼえやすい
まだこれだと
それぞれのセカンダリーに
♭9や♯9があるのかないのかを
かんぜんには判断できないんだけど
上記の方法があればたしょうは楽になるかな??
がんばって覚えてみてください
(●´∀`)ノ+゜*。
次回は、
なぜセカンダリードミナントが
このすき間を埋める方法でテンションを
考えないといけないのか
その理由についてふれてみます
こうした
音楽の骨組みにあたる部分の
理由を知ることは、
すごく応用性のある音楽理論の利用につながるので、
とても大事です
更新、楽しみにまっててね
それではおやすみなさい
♪♪今回はセカンダリードミナントのつづき
available tensionのつけ方についてです
セカンダリードミナントに
available tensionをつける方法は
今までのtensionのつけ方とは
ちょっと方法が違うので気をつけてね
(なぜこのつけ方になるかは重要なので後日)
【スポンサーリンク】
■secondary dominantsのavailable tensions
①chord toneのmaj9th上を考えながらも
chord toneの隙間をkeyのdiatonicの音で埋める
②その音から
11thを除いた音群がavailable tensionとなる
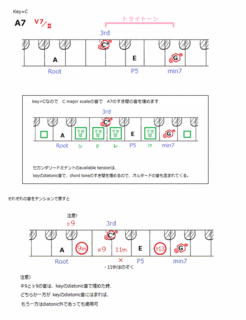
●すき間を埋めた音のテンションの数え方
手順① トライアドの音からそれぞれ
Natural tension音(maj9th上の音)の場所を確認
Root → 9th
3rd → ♯11th
5th → 13th
手順② 9thの前後のすき間に♭9と#9を書く
ポイント!!)
このとき、♭9もしくは#9の音で
すき間を埋めた場合は、
もう一方がkeyのdiatonic音以外でも
使用可能となるので、どちらも書く
手順③ ♯11thの1つ前の「11th」は消す
♯11thは、Keyのdiatonic上にあれば使える
ただし不協成分を持つので使い方には注意。
手順④ 13thの前に隙間があれば♭13を書く
これでかんぺきです
(●´艸`)フ゛ハッ
手順⑤ これらのテンションのうち
どれをavailable tensionと呼ぶかは、
書くセカンダリーごとで暗記するしかないので
以下の図でがんばっておぼえてください
じつは
かんたんなおぼえかたも
いちおうあるので
各図の説明のあとに紹介します
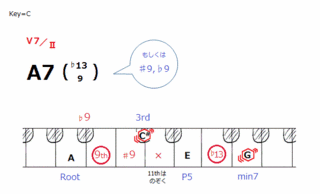
Ⅴ7/Ⅱのavailable tensionは 9と♭13 です
♯9や♭9は、available tensionではないですが
(♭9はkeyのdiatonic外の音でもあるけど)
使用可能です。
→ ただし下記の9thのルール参照のこと
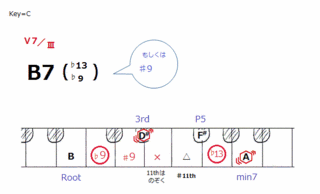
Ⅴ7/Ⅲのavailable tensionは ♭9と♭13 です
♯11thは、available tensionですが
不協成分を持つので使い方に注意する
♯9は、available tensionではないですが
使用可能です。
→ 下記の9thのルール参照のこと
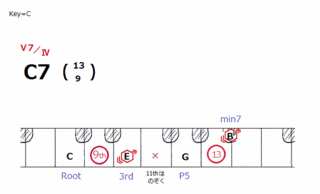
Ⅴ7/Ⅳのavailable tensionは 9と13 です
♭9と♯9の使用は避ける
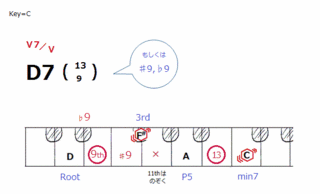
Ⅴ7/Ⅴのavailable tensionは 9と13 です
♯9や♭9は、available tensionではないですが
(♭9はkeyのdiatonic外の音でもあるけど)
使用可能です。
→ ただし下記の9thのルール参照のこと
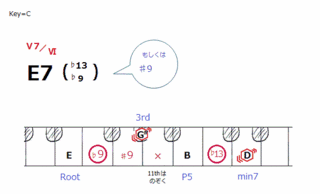
Ⅴ7/Ⅵのavailable tensionは ♭9と♭13 です
♯9は、available tensionではないですが
使用可能です。
→ 下記の9thのルール参照のこと
■9th使用のルール 9thの音は、 diatonicの音に#9(もしくは♭9)がれば、 どちらか一方を選んで使うこと つまり 9th ← or → ♯9(もしくは♭9) ( 9thとの同時使用はダメ ) * ♯9と♭9はintervalがwhole tone(全音)のため → 同時使用は可能 |
■かんたんなおぼえかた
次の点に着目するとおぼえやすくなります
●どの9thをavailable tensionとするかを
おぼえやすくする方法
基本9thがkeyのdiatonicにあるときは
♭9や#9ではなく、「9th」が
available tensionになる
逆に9thがkeyのdiatonicに無く、
♯9と♭9があるときは、
「♭9」のほうがavailableになる
●available tensionの組み合わせを
かんたんにおぼえれるようにする方法
メジャー系のコードに解決する
ドミナントコード
・プライマリーのⅤ7/Ⅰ
・セカンダリーⅤ7/Ⅳ、Ⅴ7/Ⅴの3種は
ぜんぶavailavle tensionは(9,13)になるので
おぼえるのが かんたん
たすかる
゜*。(*´Д`)。*°
あともう1こ
トニックの仲間である
Ⅲ- およびⅥ-に解決する
セカンダリー Ⅴ7/ⅢとⅤ7/Ⅵの2種は
どちらもavailable tensionが(♭9,♭13)なので
これもおぼえやすい
まだこれだと
それぞれのセカンダリーに
♭9や♯9があるのかないのかを
かんぜんには判断できないんだけど
上記の方法があればたしょうは楽になるかな??
がんばって覚えてみてください
(●´∀`)ノ+゜*。
次回は、
なぜセカンダリードミナントが
このすき間を埋める方法でテンションを
考えないといけないのか
その理由についてふれてみます
こうした
音楽の骨組みにあたる部分の
理由を知ることは、
すごく応用性のある音楽理論の利用につながるので、
とても大事です
更新、楽しみにまっててね
それではおやすみなさい
タグ:ポピュラーミュージック 音楽理論 セカンダリードミナント available tension Ⅴ7 V7 かんたんなおぼえ方 オルタードテンション コードトーンのすき間を埋める keyのdiatonic音 音楽教室
2015年05月22日
5001. 今回は演奏技術についてふれます。耳の使い方を音楽用の耳にすると、リズム感はよくなるし、感情の操作をしやすい音がつくれたらグルーヴも作りやすくなるので、1音にこだわるための話ししますね
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
今回はちょっと
音楽理論から外れるんですが
演奏面についても
触れる機会があれば記事書きたいなって思ってたので
不定期ではありますが、
ときどきこういうのもはさませてください。
はしやすめな(人´∀`).☆.。.:*
理論の内容が遅々として進んでないですけど ←
【スポンサーリンク】
以下の内容は、レッスンを受けた内容を踏まえて
実際に自分がバンドや楽器をクリニックしている経験から
生み出したものです
ちなみにじぶんじたいは
楽器を演奏できません
教えてるだけ
それでもたくさん効果はでているので
もしよかったら参考にしてみてください
■リズム感について
リズム感を良くするっていうと
リズム感とは何かって定義をきめて、
それを改善していくって流れになるんですけど
今回は、リズムについての要素を
斜めの方向から解釈して
耳の使い方と、あと感情の操作という面から、
成長の方法を紹介します
このリズムの感覚は
リズム感って枠を超えて、
グルーヴづくりにも役立ちます
一般的にリズムってきくと
一定のテンポに対する、
何かしらの正確なリズムの操作ってとらえがちだけど
ビート感のある音楽の場合は
一定のテンポのある拍にたいして
質的にはリズムは一定ではないので、
(質的に意味は後述)
必ずしも
正確にリズムを割れるってことが
リズム感の良さにはつながりません
→音楽を聞いた人がいいリズムだね
って言ってくれるのがいいリズム感って捉えた場合ね
これは
それぞれのジャンルを
1つの「ファッション」としてとらえて、
そのジャンルはリズムをどう割るのが
「ぽい」かが分かるかってのがすごく大事で
そのジャンルの音楽が好きで
お約束を感じれるリズムの良さがわかる耳があるか
ってのがまず重要になります
で、それを前提にしたうえで
より正確なリズムを、
演奏でつくるための練習方法を紹介します
正確なリズムを生み出すためには
クリックのタイミングに合わせるのは後で大丈夫
それよりも
まず、先にすべきは、そのタイミングで鳴らす
「音の質づくり」からはじめましょう
質が一定に定まったら
クリックのタイミングを狙うのがたやすくなります
逆に、質があやふやだと
各拍ごとでの音の意味が違い過ぎて、
ノリや、場合によってはテンポさえ一定で
表現できなくなったりします。
では質とは何かってことですが、
今回はその質の要素として、
①耳の使い方の操作と
②曲にあった感情を込めるだけの時間(溜め)を
つくるための意識の使い方を挙げます
これをきっちり狙って出せるようになれば、
音の質が定まった状態とかんがえてください。
Point!)
リズムは、音を鳴らす前の気持ちを込める
ところからすでに始まっていると認識する
どのくらいの熱量で、その拍を狙いに行くかが
音の立ち上がりのアタック感や
鳴らした音の重さ、長さなど
いろいろなものを
狙って作れるって意味で大事なんですが
今回は、
●シンプルに耳の使い方としてだけ考えて
まず、おおきく2パターンにわけます。
パターン①
その拍で鳴らしたい せーの!→ 拍
って狙う気持ちを作った音は
耳の使い方的には、
この思いが強いほど、鳴らした音を長く聞けず
→つぶの細かい短い音や、その場に押しつぶすような、
→ぐっとブレーキのかかる音にきこえます
反対に、
パターン②
↓ここから鳴らしたい
拍ぶーーーーん → 次の拍
って感じの、拍のはじまりの場所から
音を鳴らしたいって気持ちでつくる場合は
耳の使い方的には、
この気持ちが強いほど、音は長くなり、
鳴らした音の終わりを聞きに行きやすく
さっきとは逆で、音のはじまりへの意識が弱まります
■練習法
ここで、クリックを4分でならして
1拍目 四分音符
2拍目 休符
3拍目 四分音符
4拍目 休符 ってサイクルで鳴らす場合
ここでパターン①とパターン②の
感覚の違いをおぼえてください
パターン①が
ブツ切れにリズムを区切れるのに対して
(身体が縦に踏ん張る感じ)
パターン②は
粘っこくリズムを引っ張る感覚になります
(身体が横にもってかれる感じ)
この必然的に起こる音の長さの違いが
耳の使い方です
またこの2つの違いが生み出す
次の休符拍の質の違いも味わいましょう
パターン①は休符拍が、
次の音を狙うきっかけに感じると思います
餅つきの相づちみたいなかんじで。
それに対してパターン②は休符拍が、
自分の伸ばす音の終わりを教えてくれる感じがしますね
次のクリックで、はっ( ゚д゚ )!!ってする感覚
休符拍がくると、ちょっと解放感があり
一定のテンポをまもっていた感じが薄らぎます
この違いが、
感情の込め方の違いに利用できて、また
次の拍までの時間的な溜め感も操作できます
パターン①は次の拍を意識的に
つくって時間を一定で流します
(意識の空間的には狭い)
パターン②は次の拍を意識的に
消して時間をちょっと止めます
(意識の空間的には広い)
この感覚は、自分のなかでの時間の操作ですが
わかりやすく確認する方法として
「アナログ時計の秒針を止める」練習をします
(1秒ごとに、秒針がとまるタイプの時計で行う)
眼で見ながら、意識を変化させると
1秒が長く感じたり、
一定で動いたりが自由に操作できるようになります
ためしに、
秒針がカチってなった瞬間にハッ( ゚д゚ )!!てしてみて
意識の空間が広がると
時間がゆっくり流れますね
すごくないですか
人間て時間をそうさできるんです
ざわーるどですよ(●´艸`)フ゛ハッ
ちなみに実際は
パターン①も強く次の拍に狙っていくと
それが強いほど、次の拍は急ブレーキかかるから
すごく長く時間を止めてしまうんだけど、
意識がその長さを認識できない。
空間が狭いから。
でも意識すれば、めちゃ時間止めれます
(こっちは意識的に止めてるって感じがでますね)
この2つは、
パターン①のほうが
リズムへの意識が一定で保たれているので
いっけんすると、音楽ではこちらのリズムだけで
演奏をし続けるのが、良きって感じもしますが
実はそうじゃなくて
Point!)
■音楽はそのジャンルにあわせて
■リズムのスピード変化を操作できるのが大事です
しかも。
■そのリズムのスピードが変化しても
■テンポ的には一定な状態でおこっているって不思議が、
音楽の質を高めます
→なぜかっていうと演奏は合奏なので、
テンポが一定であれば、いろいろな重なりが表現しやすいので
(これをわざとずらすのも技術の1つという意味も含めて)
■なので練習法としてはこうです。
耳の使い方と意識の使い方を
クリックにあわせて、
数回ずつ徐々に音の長さ(意識)を変化させていく
パターン① → → → パターン②へ
(その逆も)
コツ)
はじめは耳の使い方を変化させずに
それぞれの同じ質の音で、
一定のテンポを表現できるように
4分を鳴らす練習をして
慣れたら、
耳の使い方を徐々に変化させていっても
テンポが一定であり続けられるようにしていきます
これが出来てくると
あいまいな耳の使い方によっておこる、
自分の音につられてテンポがずれるっていうのが
減ってくるし、
耳で音楽のノリが感じやすくなるので
より感情でリズムを表現しやすくなります
ちょっと不思議な話をしているように
おもうかもしれないけど
これ自体が感覚的に楽しめるものだと思うので
遊びがてら
一度ためしてみてね
音の質の変化にびっくりすると思う
あと、これらは
あくまでもリズム感の1要素なんで
これだけできればリズム感は完ぺきて話じゃないよ
スキルとして身に着けないといけない技術は多い。
きっちり音符を割る技術とか
テンポ感を維持できる能力とか
その他いろいろあるので、どれも練習ですね
演奏者の皆様がんばってください
じぶんはどうしても
そうした努力が演奏に対してはできません
向き不向きですね、、
じぶんは理論べんきょうします
たくさんいい演奏聞かせてくださいね
それではおやすみなさい。
今回はちょっと
音楽理論から外れるんですが
演奏面についても
触れる機会があれば記事書きたいなって思ってたので
不定期ではありますが、
ときどきこういうのもはさませてください。
はしやすめな(人´∀`).☆.。.:*
理論の内容が遅々として進んでないですけど ←
【スポンサーリンク】
以下の内容は、レッスンを受けた内容を踏まえて
実際に自分がバンドや楽器をクリニックしている経験から
生み出したものです
ちなみにじぶんじたいは
楽器を演奏できません
教えてるだけ
それでもたくさん効果はでているので
もしよかったら参考にしてみてください
■リズム感について
リズム感を良くするっていうと
リズム感とは何かって定義をきめて、
それを改善していくって流れになるんですけど
今回は、リズムについての要素を
斜めの方向から解釈して
耳の使い方と、あと感情の操作という面から、
成長の方法を紹介します
このリズムの感覚は
リズム感って枠を超えて、
グルーヴづくりにも役立ちます
一般的にリズムってきくと
一定のテンポに対する、
何かしらの正確なリズムの操作ってとらえがちだけど
ビート感のある音楽の場合は
一定のテンポのある拍にたいして
質的にはリズムは一定ではないので、
(質的に意味は後述)
必ずしも
正確にリズムを割れるってことが
リズム感の良さにはつながりません
→音楽を聞いた人がいいリズムだね
って言ってくれるのがいいリズム感って捉えた場合ね
これは
それぞれのジャンルを
1つの「ファッション」としてとらえて、
そのジャンルはリズムをどう割るのが
「ぽい」かが分かるかってのがすごく大事で
そのジャンルの音楽が好きで
お約束を感じれるリズムの良さがわかる耳があるか
ってのがまず重要になります
で、それを前提にしたうえで
より正確なリズムを、
演奏でつくるための練習方法を紹介します
正確なリズムを生み出すためには
クリックのタイミングに合わせるのは後で大丈夫
それよりも
まず、先にすべきは、そのタイミングで鳴らす
「音の質づくり」からはじめましょう
質が一定に定まったら
クリックのタイミングを狙うのがたやすくなります
逆に、質があやふやだと
各拍ごとでの音の意味が違い過ぎて、
ノリや、場合によってはテンポさえ一定で
表現できなくなったりします。
では質とは何かってことですが、
今回はその質の要素として、
①耳の使い方の操作と
②曲にあった感情を込めるだけの時間(溜め)を
つくるための意識の使い方を挙げます
これをきっちり狙って出せるようになれば、
音の質が定まった状態とかんがえてください。
Point!)
リズムは、音を鳴らす前の気持ちを込める
ところからすでに始まっていると認識する
どのくらいの熱量で、その拍を狙いに行くかが
音の立ち上がりのアタック感や
鳴らした音の重さ、長さなど
いろいろなものを
狙って作れるって意味で大事なんですが
今回は、
●シンプルに耳の使い方としてだけ考えて
まず、おおきく2パターンにわけます。
パターン①
その拍で鳴らしたい せーの!→ 拍
って狙う気持ちを作った音は
耳の使い方的には、
この思いが強いほど、鳴らした音を長く聞けず
→つぶの細かい短い音や、その場に押しつぶすような、
→ぐっとブレーキのかかる音にきこえます
反対に、
パターン②
↓ここから鳴らしたい
拍ぶーーーーん → 次の拍
って感じの、拍のはじまりの場所から
音を鳴らしたいって気持ちでつくる場合は
耳の使い方的には、
この気持ちが強いほど、音は長くなり、
鳴らした音の終わりを聞きに行きやすく
さっきとは逆で、音のはじまりへの意識が弱まります
■練習法
ここで、クリックを4分でならして
1拍目 四分音符
2拍目 休符
3拍目 四分音符
4拍目 休符 ってサイクルで鳴らす場合
ここでパターン①とパターン②の
感覚の違いをおぼえてください
パターン①が
ブツ切れにリズムを区切れるのに対して
(身体が縦に踏ん張る感じ)
パターン②は
粘っこくリズムを引っ張る感覚になります
(身体が横にもってかれる感じ)
この必然的に起こる音の長さの違いが
耳の使い方です
またこの2つの違いが生み出す
次の休符拍の質の違いも味わいましょう
パターン①は休符拍が、
次の音を狙うきっかけに感じると思います
餅つきの相づちみたいなかんじで。
それに対してパターン②は休符拍が、
自分の伸ばす音の終わりを教えてくれる感じがしますね
次のクリックで、はっ( ゚д゚ )!!ってする感覚
休符拍がくると、ちょっと解放感があり
一定のテンポをまもっていた感じが薄らぎます
この違いが、
感情の込め方の違いに利用できて、また
次の拍までの時間的な溜め感も操作できます
パターン①は次の拍を意識的に
つくって時間を一定で流します
(意識の空間的には狭い)
パターン②は次の拍を意識的に
消して時間をちょっと止めます
(意識の空間的には広い)
この感覚は、自分のなかでの時間の操作ですが
わかりやすく確認する方法として
「アナログ時計の秒針を止める」練習をします
(1秒ごとに、秒針がとまるタイプの時計で行う)
眼で見ながら、意識を変化させると
1秒が長く感じたり、
一定で動いたりが自由に操作できるようになります
ためしに、
秒針がカチってなった瞬間にハッ( ゚д゚ )!!てしてみて
意識の空間が広がると
時間がゆっくり流れますね
すごくないですか
人間て時間をそうさできるんです
ざわーるどですよ(●´艸`)フ゛ハッ
ちなみに実際は
パターン①も強く次の拍に狙っていくと
それが強いほど、次の拍は急ブレーキかかるから
すごく長く時間を止めてしまうんだけど、
意識がその長さを認識できない。
空間が狭いから。
でも意識すれば、めちゃ時間止めれます
(こっちは意識的に止めてるって感じがでますね)
この2つは、
パターン①のほうが
リズムへの意識が一定で保たれているので
いっけんすると、音楽ではこちらのリズムだけで
演奏をし続けるのが、良きって感じもしますが
実はそうじゃなくて
Point!)
■音楽はそのジャンルにあわせて
■リズムのスピード変化を操作できるのが大事です
しかも。
■そのリズムのスピードが変化しても
■テンポ的には一定な状態でおこっているって不思議が、
音楽の質を高めます
→なぜかっていうと演奏は合奏なので、
テンポが一定であれば、いろいろな重なりが表現しやすいので
(これをわざとずらすのも技術の1つという意味も含めて)
■なので練習法としてはこうです。
耳の使い方と意識の使い方を
クリックにあわせて、
数回ずつ徐々に音の長さ(意識)を変化させていく
パターン① → → → パターン②へ
(その逆も)
コツ)
はじめは耳の使い方を変化させずに
それぞれの同じ質の音で、
一定のテンポを表現できるように
4分を鳴らす練習をして
慣れたら、
耳の使い方を徐々に変化させていっても
テンポが一定であり続けられるようにしていきます
これが出来てくると
あいまいな耳の使い方によっておこる、
自分の音につられてテンポがずれるっていうのが
減ってくるし、
耳で音楽のノリが感じやすくなるので
より感情でリズムを表現しやすくなります
ちょっと不思議な話をしているように
おもうかもしれないけど
これ自体が感覚的に楽しめるものだと思うので
遊びがてら
一度ためしてみてね
音の質の変化にびっくりすると思う
あと、これらは
あくまでもリズム感の1要素なんで
これだけできればリズム感は完ぺきて話じゃないよ
スキルとして身に着けないといけない技術は多い。
きっちり音符を割る技術とか
テンポ感を維持できる能力とか
その他いろいろあるので、どれも練習ですね
演奏者の皆様がんばってください
じぶんはどうしても
そうした努力が演奏に対してはできません
向き不向きですね、、
じぶんは理論べんきょうします
たくさんいい演奏聞かせてくださいね
それではおやすみなさい。
2015年05月19日
実例おまけ。かえるのうたリハモ おんがくりろんでごはんver.
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
今回はおまけです。
かえるのうたでリハモをたのしみます
リハモの過程は以下より。
■■スポンサーリンク■■
まずリハモの前に
原型として、
ふつうにメロディに対しての
コードづけだけはしておきます
で、音価をねらっていこうと思うんですが
【原型】
C C
|ド ミ |ミ ド |
C C
|ミ ソ |ソ ミ |
C C
|ド ド |ド ド |
C C
|ド ミ |ミ ド |
終点
あ??(●゚ー゚●)なにこれ...
チェンジできない。笑
かえるの歌って、ちょっと変わってて
フレーズが全部順次的にながれるので
(順次的→音階の順に沿ったフレーズ)
音の頭だけに音価を感じていくと、
各拍ごとがトニック「C」の構成音からの
フレーズなので、
すべてがCだけの曲になりそうな
べったり感になっちゃう
うまく動き秘めてつくってあるよな
すごくいいメロディだと思う。
そんなわけで、
メロディが動きたがってる部分だけ
ドミナントやサブドミナントの進行で動きだします
point!)
曲中「C」をならして進行すると
メロディが動きたがってる場所が分かりやすいです
てことで
リハモ パターン①
SD、D進行利用
C G C
|ド ミ |ミ ド |
C F C
|ミ ソ |ソ ミ |
C C G
|ド ド |ド ド |
C G C
|ド ミ |ミ ド |
ちょっと動き出しましたね
(ノД`)・゜・。
リハモ パターン②
もうちょっとうごき頂戴
C F G C
|ド ミ |ミ ド |
C F C
|ミ ソ |ソ ミ |
C G
|ド ド |ド ド |
C F C G C
|ド ミ |ミ レ ド |
あと、おまけで
リハモ パターン③
かえるのうたって、フレーズの流れ的には
1,3拍ごとにというより、
12拍は3拍目に向かってる感じあるので
その投げれにトニックを置いて動かしたら
こんな感じもありやとおもう
T T
F C G C
|ドレ ミ |ミレ ド |
T T
F C G C
|ミファ ソ |ソファ ミ |
T T
C C G C
|ド ド |ド ド |
T
F G C G
|ド レ ミ ファ |
T
F G C
|ミ レ ド |
で、
なんかこんな感じでいろいろやった結果
Ⅱ-Ⅴとsecondaryとかいろいろいれるために
【原型②】
C F G C
①|ド ミ |ミ ド |
C
②|ミ ソ |ソ ミ |
③|ド ド |ド ド |
C
④|ド ミ |ミ レ ド |
ここだけ、大筋で残してリハモします。
うあー( ゚д゚ )これだともっと
メロディも遊びたいいいい
が、ひとまず1こ完成
前半はひかえめなのは
①段目で
曲の大筋が伝わるようにする狙いと
④段目からの進行が華やかに聞こえるように
なるべくシンプルにしてます
じゃ流れはなるべくそのままで
前半もなにかしらのドラマを考えます
F♯ー7(♭5) F-6 E-7 E♭dim7
①|ド ミ |ミ ド |
D-7(♭5) C♯-7 C6 A7/C#
②|ミ ソ |ソ ミ |
A- A-(△7) A- 7 A-6
③|ド ド |ド ド |
D-7 E-7 F△7 F-6
④|ド レ ミ ファ |
D-7(9) D♭△7 C△7
|ミ レ ド |
前半①②はベースのラインで半音進行押し
③段目はラインクリシェ
④段目はさっきと同じです
コードチェンジのリズム的な
緩急もついたと思う
ついでなんでその緩急でさらに
意表を突く意味で
④段目の終了を1小節、
コードだけ進行ずらしてみます
④|ドレミファ|ミレド | |
(さいご×)→(こっちへ)
というわけで
こまごまとしたところの進行感も修正しつつ
2こめ完成
(●´艸`)フ゛ハッ
んー(゜д゜)
やりすぎて迷子という感もあるな
響き増やすことに目が行き過ぎてるかも
かえる歌ってる感じでてますか?
ま(●´∀`)ノ+゜*
いいだすときりがないので
完成です
今回はおまけです。
かえるのうたでリハモをたのしみます
■かえるのうたリハモ完成版 (おんがくりろんでごはんver.) F♯ー7(♭5) F-6 E-7 E♭dim7 ①|ド ミ |ミ ド | D-7 C♯-7(♭5) C6 E7 ②|ミ ソ |ソ ミ | A- A-(△7) A- 7 A-6 ③|ド ド |ド ド | D-7 E-7 F△7 F-6 ④|ド レ ミ ファ | D-7(9) G7 D♭△7 C△7 |ミ レ ド | | |
リハモの過程は以下より。
■■スポンサーリンク■■
まずリハモの前に
原型として、
ふつうにメロディに対しての
コードづけだけはしておきます
で、音価をねらっていこうと思うんですが
【原型】
C C
|ド ミ |ミ ド |
C C
|ミ ソ |ソ ミ |
C C
|ド ド |ド ド |
C C
|ド ミ |ミ ド |
終点
あ??(●゚ー゚●)なにこれ...
チェンジできない。笑
かえるの歌って、ちょっと変わってて
フレーズが全部順次的にながれるので
(順次的→音階の順に沿ったフレーズ)
音の頭だけに音価を感じていくと、
各拍ごとがトニック「C」の構成音からの
フレーズなので、
すべてがCだけの曲になりそうな
べったり感になっちゃう
うまく動き秘めてつくってあるよな
すごくいいメロディだと思う。
そんなわけで、
メロディが動きたがってる部分だけ
ドミナントやサブドミナントの進行で動きだします
point!)
曲中「C」をならして進行すると
メロディが動きたがってる場所が分かりやすいです
てことで
リハモ パターン①
SD、D進行利用
C G C
|ド ミ |ミ ド |
C F C
|ミ ソ |ソ ミ |
C C G
|ド ド |ド ド |
C G C
|ド ミ |ミ ド |
ちょっと動き出しましたね
(ノД`)・゜・。
リハモ パターン②
もうちょっとうごき頂戴
C F G C
|ド ミ |ミ ド |
C F C
|ミ ソ |ソ ミ |
C G
|ド ド |ド ド |
C F C G C
|ド ミ |ミ レ ド |
あと、おまけで
リハモ パターン③
かえるのうたって、フレーズの流れ的には
1,3拍ごとにというより、
12拍は3拍目に向かってる感じあるので
その投げれにトニックを置いて動かしたら
こんな感じもありやとおもう
T T
F C G C
|ドレ ミ |ミレ ド |
T T
F C G C
|ミファ ソ |ソファ ミ |
T T
C C G C
|ド ド |ド ド |
T
F G C G
|ド レ ミ ファ |
T
F G C
|ミ レ ド |
で、
なんかこんな感じでいろいろやった結果
Ⅱ-Ⅴとsecondaryとかいろいろいれるために
【原型②】
C F G C
①|ド ミ |ミ ド |
C
②|ミ ソ |ソ ミ |
③|ド ド |ド ド |
C
④|ド ミ |ミ レ ド |
ここだけ、大筋で残してリハモします。
■リハモ パターン④ 完成1 C D-7 G7 C ①|ド ミ |ミ ド | C C7 F A7 ②|ミ ソ |ソ ミ | D-7 G7 E-7(♭5) A7 ③|ド ド |ド ド | D-7 E-7 F△7 F-6 ④|ド レ ミ ファ | D-7 D♭△7 C△7 |ミ レ ド | |
うあー( ゚д゚ )これだともっと
メロディも遊びたいいいい
が、ひとまず1こ完成
前半はひかえめなのは
①段目で
曲の大筋が伝わるようにする狙いと
④段目からの進行が華やかに聞こえるように
なるべくシンプルにしてます
じゃ流れはなるべくそのままで
前半もなにかしらのドラマを考えます
F♯ー7(♭5) F-6 E-7 E♭dim7
①|ド ミ |ミ ド |
D-7(♭5) C♯-7 C6 A7/C#
②|ミ ソ |ソ ミ |
A- A-(△7) A- 7 A-6
③|ド ド |ド ド |
D-7 E-7 F△7 F-6
④|ド レ ミ ファ |
D-7(9) D♭△7 C△7
|ミ レ ド |
前半①②はベースのラインで半音進行押し
③段目はラインクリシェ
④段目はさっきと同じです
コードチェンジのリズム的な
緩急もついたと思う
ついでなんでその緩急でさらに
意表を突く意味で
④段目の終了を1小節、
コードだけ進行ずらしてみます
④|ドレミファ|ミレド | |
(さいご×)→(こっちへ)
というわけで
こまごまとしたところの進行感も修正しつつ
2こめ完成
(●´艸`)フ゛ハッ
■リハモ パターン⑤ 完成2 F♯ー7(♭5) F-6 E-7 E♭dim7 ①|ド ミ |ミ ド | D-7 C♯-7(♭5) C6 E7 ②|ミ ソ |ソ ミ | A- A-(△7) A- 7 A-6 ③|ド ド |ド ド | D-7 E-7 F△7 F-6 ④|ド レ ミ ファ | D-7(9) G7 D♭△7 C△7 |ミ レ ド | | |
んー(゜д゜)
やりすぎて迷子という感もあるな
響き増やすことに目が行き過ぎてるかも
かえる歌ってる感じでてますか?
ま(●´∀`)ノ+゜*
いいだすときりがないので
完成です
タグ:nonーdiatonic
2015年05月16日
0059. 実例 セカンダリードミナントを使ったいろんなパターンのコードづけ ⑥童謡「かたつむり」 少しだけもっと先で触れる内容のコードやフレージングのアレンジとかいろいろおまけつけてます。よかったら参考にしてね
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
【スポンサーリンク】
今回はセカンダリーの使い方の実例です
まだテンションのつけ方に
ふれてないので
コードづけはやや制限きつめ
縛りプレイになりますよ
d(○´Д`○)b
→セカンダリーについてはまずここから
こんかいもこの曲
同じ曲なので
違いがわかりやすいとおもう

Key=Cです
①|ソ |ド |ミ |レ |
②|ミ |ソ |レ |ミ |
③|ソ |ミ |ド |ド |
今日は一段目①だけに注目して
いろんなパターンを試してみますね
ちなみに以下説明中の
ドミナントモーションは
コード進行に対して「→」をつけて表記します

■パターン1)
冒頭①は3コードでコードをつけました
あと終点②の1小節目を「C」にして
Primary Ⅴ7でつないであります。
【原案】
C F G7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Primary)
C
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
ここにセカンダリーをつけてみます
①段目の4小節目がⅤ7「G7」なので
Ⅴ7/Ⅴの「D7」をつけて
ドミナントモーションさせます
【完成】
C F D7 → G7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(secondary) (Prim.)
→C
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
解説)
コード進行としては、D→G→Cと
P5度downで進行しているので
終点「C」までスムーズに流れます
進行感的には
C F D-7 G7
①|ソ |ド |ミ |レ |
D-7→G7 の Ⅱ-Ⅴ進行と同じ流れです
聞き比べてみてください
セカンダリーを使うと
Outした感じがでますね
かっこいいです(●´艸`)フ゛ハッ
セカンダリーをつけた時は
chord toneとメロディーのぶつかりも
確認しましょう
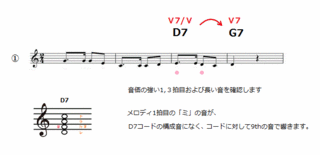
今回は、セカンダリーD7のChord tone内に
メロディーの音価にあたる音がないので、
多少、独立してしまう感じはありますが
これ自体は問題ないです
→歌いにくいなどの場合は、tensionなどで修正
セカンダリーのテンションのつけ方は
後日説明します

ではでは他のパターンも。
■パターン2)
①段目3小節目に小さい終点として
トニックの仲間「Ⅲ-」置きました。
あとひと区切りの終点を
②段目の1小節目とし「Ⅵ-」にして
暗い解決を目指します。
【原案】
E-
①|ソ |ド |ミ |レ |
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
では、ここにコードづけをしていきます
セカンダリーは「E-」「A-」コードの
どちらにもつけれます。
ドミナントモーションには
deceptive resolutionが可能なので、
暗い解決で「A-」にはdominant motion
「E-」へはdeceptiveをしかけてみました
【完成】
D-7(11) G7 E- E7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Prim.) (Sec.)
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
解説)
D-7は音価に対してtensionで修正。
①段目1,2小節目はⅡ-Ⅴ進行になっている。
G7はトニックの仲間「Ⅲ-」へのdeceptive
→deceptive感は弱め。
(G7は本来「C」へ解決するPrimary)
→ドミナントモーションはしていない。
セカンダリーE7からA-の進行で
暗さがいっきに引き立てられた。

ちなみに
■パターン3)
「E-」に対してセカンダリーB7をつける場合
【原案】
B7 → E- E7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Sec.) (Sec.)
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
セカンダリーB7のchord toneに対して、
①段目2小節目のメロディ「C」音は
♭9のオルタードテンションの響きとなり
かなり暗い雰囲気をつくります
なのであえて、
より暗さが強まる進行にしてみます
【完成】
C△7 B7 ⇒ B-7(♭5) E7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Sec.) (Sec.)
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
いっけんすると
セカンダリーB7はdeceptiveしてそうですが
じつはこれもドミナントモーションしてて
interpolatedして解決してます
あと、
マイナーⅡ-Ⅴという進行を利用して
セカンダリー「E7」から「A-」の
暗さを引き立ててます
これらはまだ触れてない内容なので
ここでは説明は飛ばしますが、
しくみはこんなかんじ。
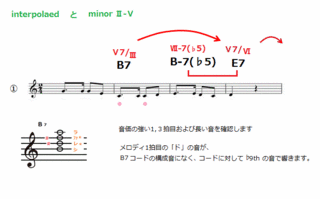
かなりテクニカルしょ?
(●´艸`)フ゛ハッ

せっかくなんで
最後におまけでもう1つ変わったやつ
今度はメロディをコードにあわせて
ちょっと変えて、雰囲気をだしてみる
■パターン4)
【原案】
E-7 A7 F△7 E7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Sec.) (Sec.)
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
ねらい①
各コード基本7thの音を強調するように
コードづけをしてみる
E-7 は 「レ」音
F△7 は 「ド」音
E7 は 「レ」音
ねらい②
A7 はとくに、コードの3rd「ド♯」と
メロディ「ド」が(半音「下」だけど)
ぶつかるので
そこをあえて活かすために
メロディをいじります
ねらい③
コード進行感とあわせて
メロディの順次的な流れが生きるように修正
その他つめこんで以下。
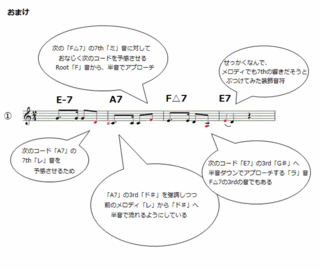
あんまやりすぎると
何の曲か分からなくなるから
先にでんでんむしって分かってる前提で
崩してます
アレンジ的要素やね
今回はいろいろ
まだやってない内容とかも
入れてしまったけど、
この先いろんなことが出来るようになってくるので
それを先取りする意味で
それぞれのパターンを味わってみてください
それではまた次回
(●´∀`)ノ+


【スポンサーリンク】
今回はセカンダリーの使い方の実例です
まだテンションのつけ方に
ふれてないので
コードづけはやや制限きつめ
縛りプレイになりますよ
d(○´Д`○)b
→セカンダリーについてはまずここから
こんかいもこの曲
同じ曲なので
違いがわかりやすいとおもう

Key=Cです
①|ソ |ド |ミ |レ |
②|ミ |ソ |レ |ミ |
③|ソ |ミ |ド |ド |
今日は一段目①だけに注目して
いろんなパターンを試してみますね
ちなみに以下説明中の
ドミナントモーションは
コード進行に対して「→」をつけて表記します
ジャズ・スタンダード・セオリー ~名曲から学ぶジャズ理論の全て (CD付) 新品価格 |  |
■パターン1)
冒頭①は3コードでコードをつけました
あと終点②の1小節目を「C」にして
Primary Ⅴ7でつないであります。
【原案】
C F G7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Primary)
C
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
ここにセカンダリーをつけてみます
①段目の4小節目がⅤ7「G7」なので
Ⅴ7/Ⅴの「D7」をつけて
ドミナントモーションさせます
【完成】
C F D7 → G7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(secondary) (Prim.)
→C
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
解説)
コード進行としては、D→G→Cと
P5度downで進行しているので
終点「C」までスムーズに流れます
進行感的には
C F D-7 G7
①|ソ |ド |ミ |レ |
D-7→G7 の Ⅱ-Ⅴ進行と同じ流れです
聞き比べてみてください
セカンダリーを使うと
Outした感じがでますね
かっこいいです(●´艸`)フ゛ハッ
注意)ちなみに この曲では①段目の3小節目は、 不安感が弱い小節なので、 D7からG7への解決感は、 テンポや演奏の印象のつけ方によっては 弱くなるかもしれません。 →詳しくはHarmonic rhythmで(後日説明) |
セカンダリーをつけた時は
chord toneとメロディーのぶつかりも
確認しましょう
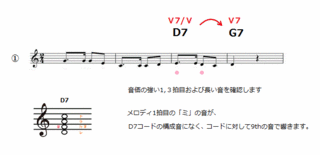
今回は、セカンダリーD7のChord tone内に
メロディーの音価にあたる音がないので、
多少、独立してしまう感じはありますが
これ自体は問題ないです
→歌いにくいなどの場合は、tensionなどで修正
セカンダリーのテンションのつけ方は
後日説明します
■コードとメロディのぶつかりで気にする部分 diatonic chord & secondary dominantのとき ①メロディの音価の強い部分に対し コードトーンにその音がない場合、 歌ものは歌いづらいことがあるので、 その音を加えるなど修正します。 ②ただし、音価の強いメロディの音が 必ずしもコードトーンにないと いけないわけではない。 Point! ③コードトーンの3rdの音に対して、 半音上の音価の強いメロディは避ける →コードの明暗や機能を壊してしまう →メロディも汚く響いてしまう たとえば) key=Cのとき 「C」のコード(ドミソ)に対する 「F」音を長く伸ばすメロディは× ただしトニックの音は例外 「G」コード(ソシレ)のとき 「C」音を長く伸ばすメロディは 「C」がトニックの音なので○ とくにセカンダリーは 音が汚く響いても keyのdiatonic音を選んで フレージングすることも多いので 音のぶつかり方には注意する ただし耳で聞いて問題がなければ可能。 |
ジャズ・スタンダード・バイブル ~セッションに役立つ不朽の227曲 (CD付き) 新品価格 |  |
ではでは他のパターンも。
■パターン2)
①段目3小節目に小さい終点として
トニックの仲間「Ⅲ-」置きました。
あとひと区切りの終点を
②段目の1小節目とし「Ⅵ-」にして
暗い解決を目指します。
【原案】
E-
①|ソ |ド |ミ |レ |
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
では、ここにコードづけをしていきます
セカンダリーは「E-」「A-」コードの
どちらにもつけれます。
ドミナントモーションには
deceptive resolutionが可能なので、
暗い解決で「A-」にはdominant motion
「E-」へはdeceptiveをしかけてみました
【完成】
D-7(11) G7 E- E7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Prim.) (Sec.)
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
解説)
D-7は音価に対してtensionで修正。
①段目1,2小節目はⅡ-Ⅴ進行になっている。
G7はトニックの仲間「Ⅲ-」へのdeceptive
→deceptive感は弱め。
(G7は本来「C」へ解決するPrimary)
→ドミナントモーションはしていない。
セカンダリーE7からA-の進行で
暗さがいっきに引き立てられた。
ジャズ・スタンダード・バイブル2 in B♭ セッションをもっと楽しむ不朽の227曲 (CD付) 新品価格 |  |
ちなみに
■パターン3)
「E-」に対してセカンダリーB7をつける場合
【原案】
B7 → E- E7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Sec.) (Sec.)
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
セカンダリーB7のchord toneに対して、
①段目2小節目のメロディ「C」音は
♭9のオルタードテンションの響きとなり
かなり暗い雰囲気をつくります
なのであえて、
より暗さが強まる進行にしてみます
【完成】
C△7 B7 ⇒ B-7(♭5) E7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Sec.) (Sec.)
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
いっけんすると
セカンダリーB7はdeceptiveしてそうですが
じつはこれもドミナントモーションしてて
interpolatedして解決してます
あと、
マイナーⅡ-Ⅴという進行を利用して
セカンダリー「E7」から「A-」の
暗さを引き立ててます
これらはまだ触れてない内容なので
ここでは説明は飛ばしますが、
しくみはこんなかんじ。
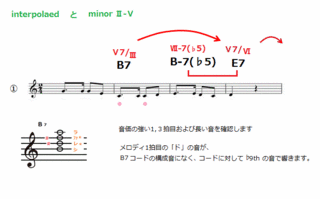
かなりテクニカルしょ?
(●´艸`)フ゛ハッ
ジャズ・スタンダード・バイブル2 in E♭ セッションをもっと楽しむ不朽の227曲 (CD付) 新品価格 |  |
せっかくなんで
最後におまけでもう1つ変わったやつ
今度はメロディをコードにあわせて
ちょっと変えて、雰囲気をだしてみる
■パターン4)
【原案】
E-7 A7 F△7 E7 →
①|ソ |ド |ミ |レ |
(Sec.) (Sec.)
A-
②|ミ |ソ |レ |ミ |
(終点)
ねらい①
各コード基本7thの音を強調するように
コードづけをしてみる
E-7 は 「レ」音
F△7 は 「ド」音
E7 は 「レ」音
ねらい②
A7 はとくに、コードの3rd「ド♯」と
メロディ「ド」が(半音「下」だけど)
ぶつかるので
そこをあえて活かすために
メロディをいじります
ねらい③
コード進行感とあわせて
メロディの順次的な流れが生きるように修正
その他つめこんで以下。
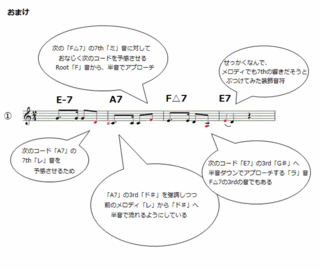
あんまやりすぎると
何の曲か分からなくなるから
先にでんでんむしって分かってる前提で
崩してます
アレンジ的要素やね
今回はいろいろ
まだやってない内容とかも
入れてしまったけど、
この先いろんなことが出来るようになってくるので
それを先取りする意味で
それぞれのパターンを味わってみてください
それではまた次回
(●´∀`)ノ+
2015年05月14日
0058. セカンダリードミナントをおぼえて曲にアウト感をじょうずにくわえましょう。ドミナントモーション先がかんたんにわかる方法も紹介。
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
♪♪今回はドミナントモーションのつづき
secondary dominantについてです
セカンダリードミナントとは
「Ⅰ」以外のdiatonic chordに解決する
ドミナントモーションのことをいう
【スポンサーリンク】
確認)
Key=C のdiatonic chord
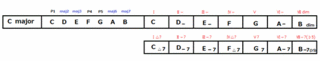
上記ダイアトニックコード中、
「Ⅰ」へドミナントモーションするのは
→ G7(Ⅴ7)コード
これをプライマリードミナントという。
→プライマリードミナントについてはここ
「Ⅰ」以外のdiatonic chord、
「Ⅱー」「Ⅲ-」「Ⅳ」「Ⅴ」「Ⅵ-」へ
解決するのがセカンダリードミナント。
(解決先はそれぞれセブンスコードでも良い)
注意)
「Ⅶdim」に対しての
セカンダリードミナントは無い。
*このページ最後に触れる
secondary dominantのルールを
参照してください
■各diatonic chordに対するsecondary dominants
①「Ⅱ-」に対するセカンダリー
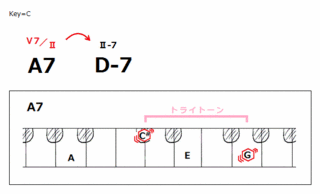
Ⅱ-7に対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅱ(ファイブセブン・オブ・ツーと言う)
②「Ⅲ-」に対するセカンダリー
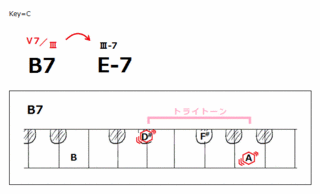
Ⅲ-7に対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅲ(ファイブセブン・オブ・スリー)
③「Ⅳ」に対するセカンダリー
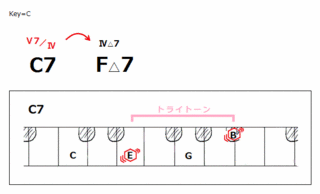
Ⅳに対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅳ(ファイブセブン・オブ・フォー)
④「Ⅴ」に対するセカンダリー
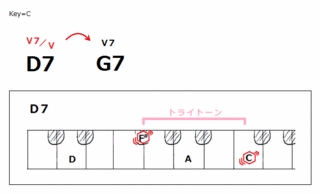
Ⅴに対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅴ(ファイブセブン・オブ・ファイブ)
⑤「Ⅵ」に対するセカンダリー
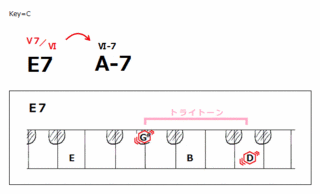
Ⅵに対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅵ(ファイブセブン・オブ・シックス)
Point!!)
●セカンダリードミナントの「Ⅴ7」は、
chord toneにKeyのdiatonic音以外の音が混じる
この響きが瞬間的に
→違うKeyにいるような緊張感をだし
Outするサウンドになっている
でも各diatonic chordのRootに対して
解決することで、
しっかりkey=Cにインサイドできる
とてもおしゃれな機能です
!(●´∀`)ノ+
詳しくはまた後日ふれます。
●P5度ダウンの関係でおぼえるとかんたん。
それぞれのsecondary dominantは
解決先のdiatonic chordに対して
完全5度ダウンするので、
cycle of fifthの関係を思い出すと
かんたんにおぼえられます。
これはべんりすぎ。(●´艸`)フ゛ハッ
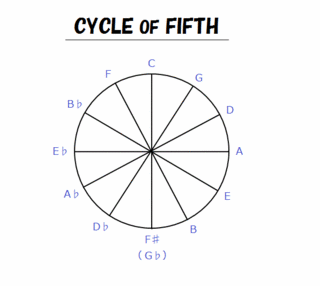
逆時計回りに
Ⅴ7とdiatonic chordの関係が並んでいる
セカンダリードミナントが
上手に使えるようになると
メロディにもコード進行にも
diatonic外の音が使えるようになるので
急に世界が広がった感じがでますね
次回、実例いきますかねヾ(*・ω・)ノ゜+
ひとまず今回はこのへんで。


♪♪今回はドミナントモーションのつづき
secondary dominantについてです
セカンダリードミナントとは
「Ⅰ」以外のdiatonic chordに解決する
ドミナントモーションのことをいう
【スポンサーリンク】
確認)
Key=C のdiatonic chord
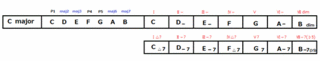
上記ダイアトニックコード中、
「Ⅰ」へドミナントモーションするのは
→ G7(Ⅴ7)コード
これをプライマリードミナントという。
→プライマリードミナントについてはここ
「Ⅰ」以外のdiatonic chord、
「Ⅱー」「Ⅲ-」「Ⅳ」「Ⅴ」「Ⅵ-」へ
解決するのがセカンダリードミナント。
(解決先はそれぞれセブンスコードでも良い)
注意)
「Ⅶdim」に対しての
セカンダリードミナントは無い。
*このページ最後に触れる
secondary dominantのルールを
参照してください
■各diatonic chordに対するsecondary dominants
●アナライズをしっかり覚えること セカンダリードミナントは Ⅴ7の後ろに、 進行先のdiatonic chordの度数を書きます 例えば) Ⅴ7 / Ⅱ (diatonic chordの「Ⅱ-」に進行するⅤ7という意味) ちなみに かくセカンダリードミナントから 伸びている矢印は、 Ⅴ7が「完全5度ダウン」で解決したときにつける ドミナントモーションのアナライズ (deceptive resolutionした場合はつけない) |
①「Ⅱ-」に対するセカンダリー
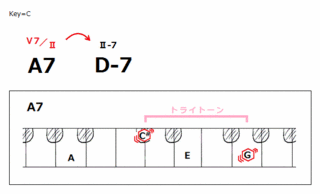
Ⅱ-7に対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅱ(ファイブセブン・オブ・ツーと言う)
②「Ⅲ-」に対するセカンダリー
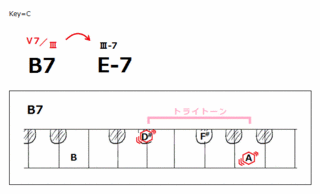
Ⅲ-7に対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅲ(ファイブセブン・オブ・スリー)
③「Ⅳ」に対するセカンダリー
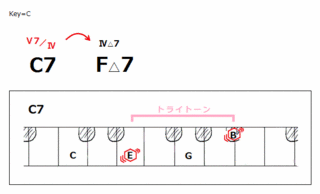
Ⅳに対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅳ(ファイブセブン・オブ・フォー)
④「Ⅴ」に対するセカンダリー
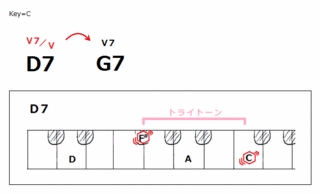
Ⅴに対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅴ(ファイブセブン・オブ・ファイブ)
⑤「Ⅵ」に対するセカンダリー
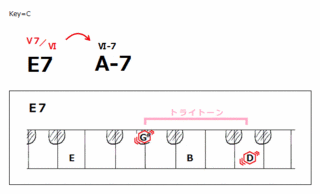
Ⅵに対してP5度ダウンする
→Ⅴ7/Ⅵ(ファイブセブン・オブ・シックス)
Point!!)
●セカンダリードミナントの「Ⅴ7」は、
chord toneにKeyのdiatonic音以外の音が混じる
この響きが瞬間的に
→違うKeyにいるような緊張感をだし
Outするサウンドになっている
でも各diatonic chordのRootに対して
解決することで、
しっかりkey=Cにインサイドできる
とてもおしゃれな機能です
!(●´∀`)ノ+
詳しくはまた後日ふれます。
●P5度ダウンの関係でおぼえるとかんたん。
それぞれのsecondary dominantは
解決先のdiatonic chordに対して
完全5度ダウンするので、
cycle of fifthの関係を思い出すと
かんたんにおぼえられます。
これはべんりすぎ。(●´艸`)フ゛ハッ
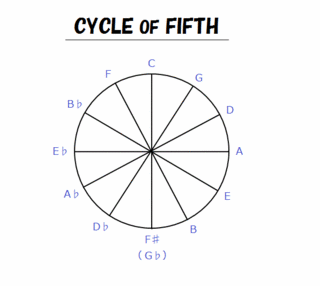
逆時計回りに
Ⅴ7とdiatonic chordの関係が並んでいる
■secondary dominantのルール ①解決先は、必ずdiatonic chordでないとダメ ②またセカンダリーは一瞬Outするので 解決先にのコードは不安定な響きはさける →不安定な響きのコードが解決先だと、 ドミナントモーションの働きが活きないから。 ディミニッシュ7thコードは、 セカンダリードミナントの解決先から除く。 ③「Ⅴ7」のRootはkeyのdiatonic音であること 「Ⅶ」に対しての「Ⅴ7」のRootは keyのdiatonic外の音になるので セカンダリーとは呼べない たとえば) Key=Cのとき Ⅴ7/Ⅶ Ⅶ-7(♭5) F♯7 → B-7(♭5) となり Ⅴ7/ⅦのRoot音「F♯」が、 keyのdiatonic音以外になるので セカンダリードミナントとは呼ばない。 余談)セカンダリーとは呼べないだけで。 耳で聞いてよければ、「Ⅶ」に対しても ドミナントモーションはしてもよい ただし、この進行は セカンダリードミナントとは呼べないので Ⅴ7/Ⅶとはアナライズしない |
セカンダリードミナントが
上手に使えるようになると
メロディにもコード進行にも
diatonic外の音が使えるようになるので
急に世界が広がった感じがでますね
次回、実例いきますかねヾ(*・ω・)ノ゜+
ひとまず今回はこのへんで。
タグ:ポピュラーミュージック 音楽理論 セカンダリードミナント アウト感 ドミナントモーション 完全5度ダウン ファイブセブン・オブ・ツー ファイブセブン・オブ・スリー ファイブセブン・オブ・フォー ファイブセブン・オブ・ファイブ ファイブセブン・オブ・シックス
2015年05月13日
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)のもくじ①
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
音楽理論は
好きなところをつまみ食いで
知っているだけでも
じゅうぶん使えるところはあるのだけど
このサイトは
より理解がしやすいように
レッスンで習った順に、内容を紹介しています
そのぶん時間はかかりますけど
よければ初めから
おつきあいしてもらえたらって思います
→音楽の基礎知識(さいしょ)
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/1/0
(●´∀`)ノ+゜
最新の記事→
https://fanblogs.jp/musictheory/
その他、よく読まれている記事。
■音楽理論の使い方(実例)
(1) 3コードだけのコードづけ
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/44/0
(2) C以外のキーでのコードづけ
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/64/0
(3) 7thやtensionを加えるコードづけ
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/65/0
(4) reharmonizationによるコードづけ
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/74/0
(5) ケーデンスを利用したコードづけ
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/77/0
(6) セカンダリーを利用したコードづけ
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/81/0
(7) テンション&リリースのフレーズ例①
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/96/0
(8) テンション&リリースのフレーズ例②
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/97/0
おまけ)かえるのうたリハモ
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/82/0
演奏について)
■ジャンルごとにアドリブしてみる
(1) ブルース
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/21/0
(2) ロックとか
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/22/0
(3) ロックンロールとか
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/23/0
(4) ジャズ
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/24/0
■楽器のスキルとはまた違う角度から
(1) 耳の使い方でリズム感をよくする①
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/84/0
(2) 耳の使い方でリズム感をよくする②
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/94/0
音楽理論について)
■メジャーkeyの曲作り
→もくじ(現在作成中)
メジャーkeyの曲作りの最初
→ダイアトニックコードについて
https://fanblogs.jp/musictheory/archive/41/0
これからもよろしくお願いします
Twitter::@music_pecopeco
おんがくりろんでごはん(灬╹ω╹灬)ただの豚足
2015年05月11日
0057. ドミナントモーションのしくみを説明してます。あとドミナントモーションを使う狙いも。短いけどとても大事なはなし(プライマリードミナント)
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
更新遅くなってごめんね
なかなか時間がなくて、
短くしか説明できないけど
今回もとても重要な内容です
がんばっておぼえておいてください
【スポンサーリンク】
♪♪ドミナントモーションのおはなし
ドミナントモーションとは
不安から安心へと解決する働きのことで、
次のようなねらいで使われる
①終止感
②推進力(スピード感)
③連結
④解決先を引き立てる
補足説明)
→①終止感
ドミナントモーションすると
解決先で落ち着いた感じがするので、
ひと区切りついた感じがする
これが終止感
→②推進力
Ⅴ7コードはとても不安なので
気持ち的に速く次の音へ
つながっていく気がする
これが推進力
→③連結
そうした効果を利用して、
解決先のコードとの
つながりを強めることができる
→④解決先を引き立てる
不安から安心へと解決することで
より安心感が増し、解決先が引き立つ
■Primary dominant
プライマリードミナントは
ドミナントモーションの基本形
KeyのⅤ7からⅠへ、
rootが完全5度Downする
ドミナントモーションを
→ プライマリードミナントという
もっとも優先されるドミナントモーション
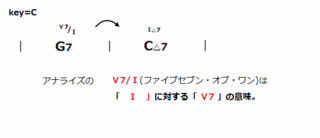
今回は以上です。
次回を待っててね
゜*。(*´Д`)。*°


更新遅くなってごめんね
なかなか時間がなくて、
短くしか説明できないけど
今回もとても重要な内容です
がんばっておぼえておいてください
【スポンサーリンク】
♪♪ドミナントモーションのおはなし
ドミナントモーションとは
不安から安心へと解決する働きのことで、
次のようなねらいで使われる
①終止感
②推進力(スピード感)
③連結
④解決先を引き立てる
補足説明)
→①終止感
ドミナントモーションすると
解決先で落ち着いた感じがするので、
ひと区切りついた感じがする
これが終止感
→②推進力
Ⅴ7コードはとても不安なので
気持ち的に速く次の音へ
つながっていく気がする
これが推進力
→③連結
そうした効果を利用して、
解決先のコードとの
つながりを強めることができる
→④解決先を引き立てる
不安から安心へと解決することで
より安心感が増し、解決先が引き立つ
■Primary dominant
プライマリードミナントは
ドミナントモーションの基本形
KeyのⅤ7からⅠへ、
rootが完全5度Downする
ドミナントモーションを
→ プライマリードミナントという
もっとも優先されるドミナントモーション
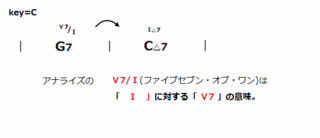
●ドミナントモーションのしくみ 【G7】 「B」と「F」がトライトーンをつくる 不協和な響きとなっている(不安) 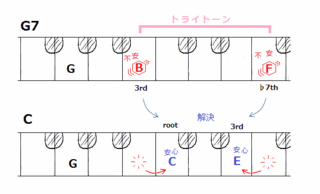 それがドミナントモーションにより 【C】 不協和なトライトーンの音が それぞれRootと3rdの音に 半音で解決している(安心) |
今回は以上です。
次回を待っててね
゜*。(*´Д`)。*°
2015年05月07日
0056. 実例 ケーデンスを使ったいろんなパターンのコードづけ ⑤童謡「かたつむり」
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
今回はまた息抜き回。
ケーデンスつかったコードづけします
けっこうややこしい話もでてくるので
まずはしっかりケーデンスのところを
おぼえてから読んでね
この2つは必須かな
(●´∀`)ノ+゜
→ケーデンスの種類についてはここ
→リハモニゼーションの実例はここ
【スポンサーリンク】
じゃこんかいもこの曲で。

Key=Cです
①まだコードは抜いてます
|ソ |ド |ミ |レ |
|ミ |ソ |レ |ミ |
|ソ |ミ |ド |ド |
ケーデンスを意識したコードづけは
メロディが、小節ごとのコード感に
はまるかどうかよりも
メロディが流れていく「感じ」にそって
つけていきます
なのでフレーズの終点(解決先)が
先に決まります
Point!!)
コードをつけるとき
慣れるまでは1小節目から順番に
つけていきたくなると思いますが、
作曲の段階ではむしろ
虫食い状態で部分的にコードが決まって
そこから順に
→後ろからつけていくほうが多くなります


②’ では終点決めます
ここで一番大事なのは曲のさいごです
(エンディング部分でなく、本編のさいご)
(key=C)
|ソ |ド |ミ |レ |
|ミ |ソ |レ |ミ |
C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
曲にはkeyがあるので
この最後が調性としていちばん
言いたかった部分です
なので
C major の調性で曲をつくるなら
→ ここは「C」です
たとえば)
仮に曲が最後のさいごまで
A minorの調性で進んできたように
感じるマイナーぽい曲としても
さいごが「C」で終われば
最終的に「C」を伝えるために
前半にマイナーの感じを持ってきた
メジャーの曲って解釈が一般的
暗い物語の最後をわざわざ
ハッピーエンドにするってことは
伝えたかったのは、
本質的には何かの救いを秘めたかった故の
暗い物語ってことですよね
ヾ(*・ω・)ノ゜+
ちなみに
→keyの判断は「さいご」で決まる。
逆に言うと、曲の最初ではkeyはまだ読めない


②'’ じゃ他の終点も決めましょう
フレーズの終点って、
言い方変えると、
次のフレーズのスタートともいえます
今回はケーデンスするために
TonicⅠを終点って考えているので
あえて長めのフレーズで
大きな終点だけ。
ここにしました
(key=C)
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
③ じゃケーデンスつけるよ
●さいごまでの進行を決める
前回のアレンジが
Subdominant cadenceだったので
違うパターンで考えてみる
【案1】 dominant cadence
G7 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
メロディの音価に対して
コード感はあわせてないけど
流れとしてはぜんぜん自然です
仮にメロディとぶつかることがあっても
Ⅴ7は、不安感をあおるコードなので
それが逆に
Ⅰでの安心感になったりもします
ただし、この3小節目の1拍目は
印象の強い場所なので、
不安感があまり強く出ない
それならあえてしっくり狙いで
「G」コードもいいかもね
せっかくなので
よりしっくりくるように
メロディの音価を意識して
コードや進行を修正してみます
【案2】dominant cadence
Gsus4 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
小節前半はすっきりしたけど
後半の終止感が弱いので
ドミナントモーションを少し強めるなら
【案3】dominant cadence
G7sus4 G7 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
あら自然
(●´艸`)フ゛ハッ
ならどんどん終始感つよめますか
Ⅴ7(sus4)→Ⅴ7は分けて考えると
SD D ともいえるので
次はFull cadenceのパターンで。
【案4】Full cadence
F G7 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
Full cadenceにしました
「F」コードはchord tone 5thが「ド」だし
しっくり感がそうとうきましたね
よし。ここまで来たら
Ⅱ-Ⅴ進行のパターンも挙げときます
【案5】Ⅱ-Ⅴ
D-7 G7 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
D-7にもchord toneに
「ド」の音を持つのでしっくりきますね
これらの進行は音価にもはまるし
ケーデンスによって進行感もいいので
すごく自然に曲が流れます
こーいうの
いいコードづけです( ̄ー ̄)ニヤリッ


じゃ逆に
進行感があっても
音価にはまらないとダメなのかっていうと
そんなこともなく
進行感はさいごの終止先で
!!( ゚д゚ )あーって納得できるので
変な状況も
逆にありって場合もあります
ま、無理なときもあるけどね
→ そんな時は
とりあえず
好きな進行を当てはめてみて
進行の流れがあっても
まだ響きがコードに違和感があれば
メロディと照らし合わせて
コードのなかみを修正すれば
だいたい大丈夫になります
ポイントは
7thやtensionが使えること
あとchord toneの微調整ができること
コード単体が、
その場所にがっちり
合うか合わないかって判断だけで
合うコードをひたすら探す
そんな生活は
これで終了ですね(●´艸`)フ゛ハッ
では前半部分
強引さだけで突き進んで
ケーデンス後の着地を目指します
あそびすぎ注意
(●´∀`)ノ+゜
参考)
→ダイアトニックのよくある進行について
→7thやtensionのつけ方の実例はここ


●前半部分の進行を決める
【案1】 Ⅱ-Ⅴ進行
(key=C)
E-7 A-7 D-7 G7
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
あんちょくにⅡ-Ⅴの進行を
5度ダウンの進行でつないだパターン
よく言われる「3625」進行
1小節目をⅠにして「1625」進行も多い
とても自然に流れる。
【案2】 Subdominant cadence
(key=C)
C D- E- F6
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
Subdominant cadenceを狙って
4小節目にFを置いたら
小節数がちょうど4小節だったので
1こずつ2度で動かしてみたよパターン
テキトーすぎるか(-ε-)笑
でもわかりやすい進行感になってます。
4小節目のメロディの音価が
Fコードには強すぎて
SDの響きにはちょっとキツかったので
ここをF6に修正した。
(Fのままとの違い味わってみて)
これであり得る進行になったよね。
2,3小節目も7thにすれば
さらにメロディにははまるけど
2度進行がくっきりみえるように
ここでは
あえてトライアドで
進行を目立たせるほうを選択しました
じゃもう1つ
同じ発想で
【案3】 Full cadence
(key=C)
D-7(11) C△7/E F△7 G7
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
今度は4小節目にⅤ7を置いて、
1小節目から順番にD-,E-,F,Gと
並べてみたが、今回の進行は
メロディとのぶつかりが強かったので
それぞれ修正した
注意)
E-にドの音は
テンションとしても無理なので
構成音が同じのC△7のonEにしている
表記上はこうなるけど
伴奏は演奏上
D- E- F G7でも良い
ただしメロディが歌いづらいので
これは主旋が楽器の場合。
さらに進行を遊んでみる
【案4】 deceptive resolutionも。
(key=C)
D-7(11) G7(sus4) E-7 F6
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
案2のSubdominant cadence前の
3小節目がⅢ-(Tonicの仲間)だったので
そこを小さな着地地点(Ⅰ代理)とみて
1,2小節で、Ⅱ-Ⅴでつなげて
あえて
deceptive resolutionを狙ったパターン
Tonicの仲間へのdeceptiveかつ、
Ⅴ7(sus4)コードからなので、
deceptiveの印象は弱め
でも流れとしてはよいかな


やりだすときりはないのだけど
長くなるとややこしくなるので
今回はこのへんで終了です。
\(○^ω^○)/
後半遊びすぎて
逆にわかりづらくなってる気もするので
ポイントだけまとめると
コード進行はただ
コードの組み合わせを選ぶんじゃなくて
コードの中身も考えながら
つくっていくほうが
自由に進行が選べるようになるよ
ってところが大事です
です( ゚д゚ )」
メロディに対して
コードの響きも進行感も
意識しながら、
狙ってつくれるように
練習をしてみてね
(key=C)
E-7(11) A-7 B-7(♭5)Gsus4G
|ソ |ド |ミ |レ |
Cadd13 F △(#11) B-7(♭5) E-7
|ミ |ソ |レ |ミ |
A-7(9) B-7(♭5) G7(sus4) G7 Cadd9
|ソ |ミ |ド |ド |
さいごははっぴーえんどで。
それではまた次回。
ドミナントモーションについてを予定してます
重要です
でわ。(o→ܫ←o)♫


今回はまた息抜き回。
ケーデンスつかったコードづけします
けっこうややこしい話もでてくるので
まずはしっかりケーデンスのところを
おぼえてから読んでね
この2つは必須かな
(●´∀`)ノ+゜
→ケーデンスの種類についてはここ
→リハモニゼーションの実例はここ
【スポンサーリンク】
じゃこんかいもこの曲で。

Key=Cです
①まだコードは抜いてます
|ソ |ド |ミ |レ |
|ミ |ソ |レ |ミ |
|ソ |ミ |ド |ド |
ケーデンスを意識したコードづけは
メロディが、小節ごとのコード感に
はまるかどうかよりも
メロディが流れていく「感じ」にそって
つけていきます
なのでフレーズの終点(解決先)が
先に決まります
Point!!)
コードをつけるとき
慣れるまでは1小節目から順番に
つけていきたくなると思いますが、
作曲の段階ではむしろ
虫食い状態で部分的にコードが決まって
そこから順に
→後ろからつけていくほうが多くなります
②’ では終点決めます
ここで一番大事なのは曲のさいごです
(エンディング部分でなく、本編のさいご)
(key=C)
|ソ |ド |ミ |レ |
|ミ |ソ |レ |ミ |
C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
曲にはkeyがあるので
この最後が調性としていちばん
言いたかった部分です
なので
C major の調性で曲をつくるなら
→ ここは「C」です
たとえば)
仮に曲が最後のさいごまで
A minorの調性で進んできたように
感じるマイナーぽい曲としても
さいごが「C」で終われば
最終的に「C」を伝えるために
前半にマイナーの感じを持ってきた
メジャーの曲って解釈が一般的
暗い物語の最後をわざわざ
ハッピーエンドにするってことは
伝えたかったのは、
本質的には何かの救いを秘めたかった故の
暗い物語ってことですよね
ヾ(*・ω・)ノ゜+
ちなみに
→keyの判断は「さいご」で決まる。
逆に言うと、曲の最初ではkeyはまだ読めない
②'’ じゃ他の終点も決めましょう
フレーズの終点って、
言い方変えると、
次のフレーズのスタートともいえます
今回はケーデンスするために
TonicⅠを終点って考えているので
あえて長めのフレーズで
大きな終点だけ。
ここにしました
(key=C)
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
③ じゃケーデンスつけるよ
●さいごまでの進行を決める
前回のアレンジが
Subdominant cadenceだったので
違うパターンで考えてみる
【案1】 dominant cadence
G7 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
メロディの音価に対して
コード感はあわせてないけど
流れとしてはぜんぜん自然です
仮にメロディとぶつかることがあっても
Ⅴ7は、不安感をあおるコードなので
それが逆に
Ⅰでの安心感になったりもします
ただし、この3小節目の1拍目は
印象の強い場所なので、
不安感があまり強く出ない
それならあえてしっくり狙いで
「G」コードもいいかもね
せっかくなので
よりしっくりくるように
メロディの音価を意識して
コードや進行を修正してみます
【案2】dominant cadence
Gsus4 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
小節前半はすっきりしたけど
後半の終止感が弱いので
ドミナントモーションを少し強めるなら
【案3】dominant cadence
G7sus4 G7 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
あら自然
(●´艸`)フ゛ハッ
ならどんどん終始感つよめますか
Ⅴ7(sus4)→Ⅴ7は分けて考えると
SD D ともいえるので
次はFull cadenceのパターンで。
【案4】Full cadence
F G7 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
Full cadenceにしました
「F」コードはchord tone 5thが「ド」だし
しっくり感がそうとうきましたね
よし。ここまで来たら
Ⅱ-Ⅴ進行のパターンも挙げときます
【案5】Ⅱ-Ⅴ
D-7 G7 C
|ソ |ミ |ド |ド |
さいご
D-7にもchord toneに
「ド」の音を持つのでしっくりきますね
これらの進行は音価にもはまるし
ケーデンスによって進行感もいいので
すごく自然に曲が流れます
こーいうの
いいコードづけです( ̄ー ̄)ニヤリッ
じゃ逆に
進行感があっても
音価にはまらないとダメなのかっていうと
そんなこともなく
進行感はさいごの終止先で
!!( ゚д゚ )あーって納得できるので
変な状況も
逆にありって場合もあります
ま、無理なときもあるけどね
→ そんな時は
とりあえず
好きな進行を当てはめてみて
進行の流れがあっても
まだ響きがコードに違和感があれば
メロディと照らし合わせて
コードのなかみを修正すれば
だいたい大丈夫になります
ポイントは
7thやtensionが使えること
あとchord toneの微調整ができること
コード単体が、
その場所にがっちり
合うか合わないかって判断だけで
合うコードをひたすら探す
そんな生活は
これで終了ですね(●´艸`)フ゛ハッ
では前半部分
強引さだけで突き進んで
ケーデンス後の着地を目指します
あそびすぎ注意
(●´∀`)ノ+゜
参考)
→ダイアトニックのよくある進行について
→7thやtensionのつけ方の実例はここ
●前半部分の進行を決める
【案1】 Ⅱ-Ⅴ進行
(key=C)
E-7 A-7 D-7 G7
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
あんちょくにⅡ-Ⅴの進行を
5度ダウンの進行でつないだパターン
よく言われる「3625」進行
1小節目をⅠにして「1625」進行も多い
とても自然に流れる。
【案2】 Subdominant cadence
(key=C)
C D- E- F6
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
Subdominant cadenceを狙って
4小節目にFを置いたら
小節数がちょうど4小節だったので
1こずつ2度で動かしてみたよパターン
テキトーすぎるか(-ε-)笑
でもわかりやすい進行感になってます。
4小節目のメロディの音価が
Fコードには強すぎて
SDの響きにはちょっとキツかったので
ここをF6に修正した。
(Fのままとの違い味わってみて)
これであり得る進行になったよね。
2,3小節目も7thにすれば
さらにメロディにははまるけど
2度進行がくっきりみえるように
ここでは
あえてトライアドで
進行を目立たせるほうを選択しました
じゃもう1つ
同じ発想で
【案3】 Full cadence
(key=C)
D-7(11) C△7/E F△7 G7
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
今度は4小節目にⅤ7を置いて、
1小節目から順番にD-,E-,F,Gと
並べてみたが、今回の進行は
メロディとのぶつかりが強かったので
それぞれ修正した
注意)
E-にドの音は
テンションとしても無理なので
構成音が同じのC△7のonEにしている
表記上はこうなるけど
伴奏は演奏上
D- E- F G7でも良い
ただしメロディが歌いづらいので
これは主旋が楽器の場合。
さらに進行を遊んでみる
【案4】 deceptive resolutionも。
(key=C)
D-7(11) G7(sus4) E-7 F6
|ソ |ド |ミ |レ |
C
|ミ |ソ |レ |ミ |
案2のSubdominant cadence前の
3小節目がⅢ-(Tonicの仲間)だったので
そこを小さな着地地点(Ⅰ代理)とみて
1,2小節で、Ⅱ-Ⅴでつなげて
あえて
deceptive resolutionを狙ったパターン
Tonicの仲間へのdeceptiveかつ、
Ⅴ7(sus4)コードからなので、
deceptiveの印象は弱め
でも流れとしてはよいかな
やりだすときりはないのだけど
長くなるとややこしくなるので
今回はこのへんで終了です。
\(○^ω^○)/
後半遊びすぎて
逆にわかりづらくなってる気もするので
ポイントだけまとめると
コード進行はただ
コードの組み合わせを選ぶんじゃなくて
コードの中身も考えながら
つくっていくほうが
自由に進行が選べるようになるよ
ってところが大事です
です( ゚д゚ )」
メロディに対して
コードの響きも進行感も
意識しながら、
狙ってつくれるように
練習をしてみてね
(key=C)
E-7(11) A-7 B-7(♭5)Gsus4G
|ソ |ド |ミ |レ |
Cadd13 F △(#11) B-7(♭5) E-7
|ミ |ソ |レ |ミ |
A-7(9) B-7(♭5) G7(sus4) G7 Cadd9
|ソ |ミ |ド |ド |
さいごははっぴーえんどで。
それではまた次回。
ドミナントモーションについてを予定してます
重要です
でわ。(o→ܫ←o)♫