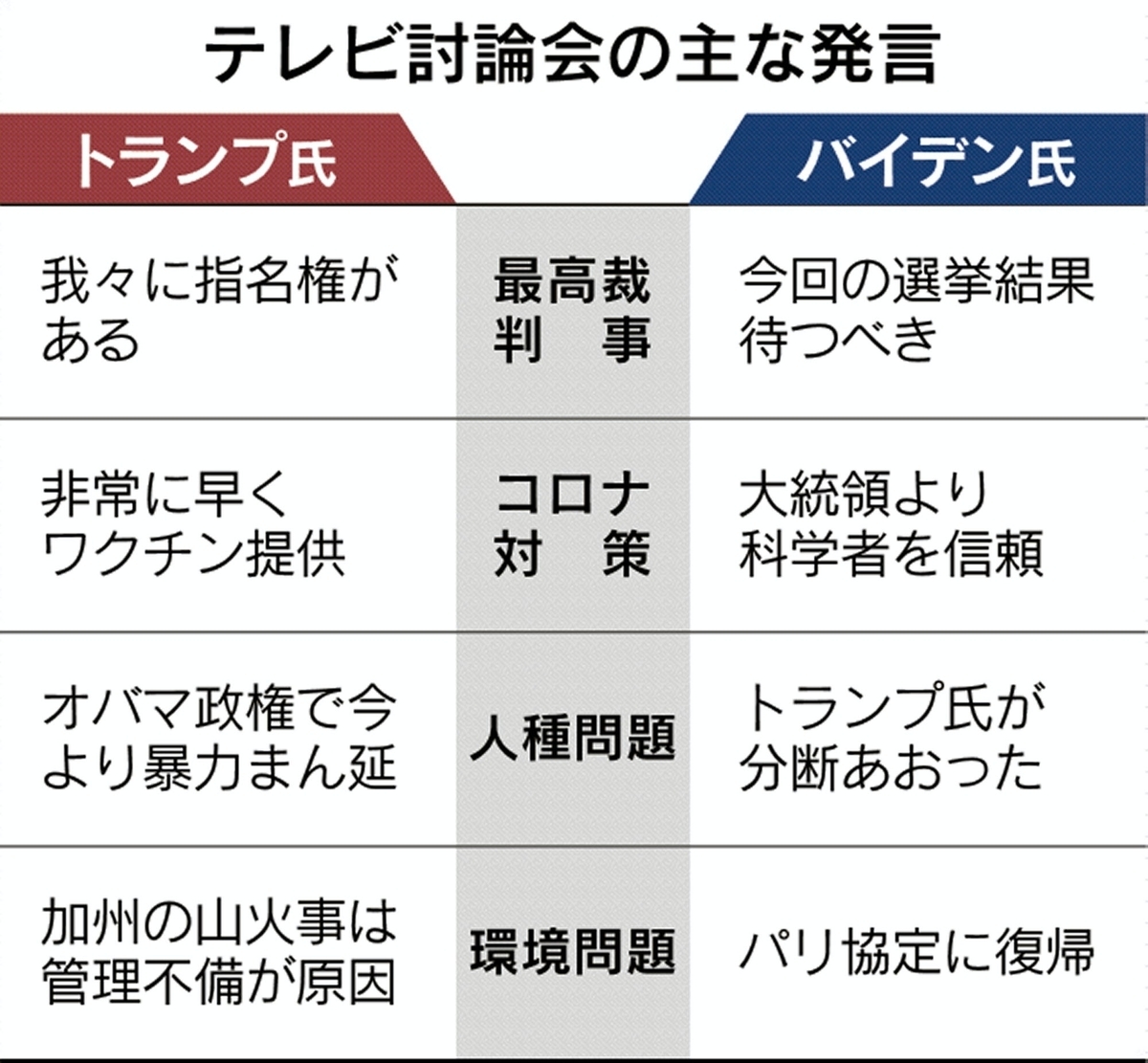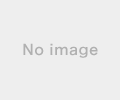新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2020年06月19日
【経済ニュース 6/19 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
1.ユニクロのマスク発売 店舗に行列、ネット購入殺到
2.製造業景況感、11年ぶり低水準 6月短観の民間予測
3.日銀、ドル供給を週3回に減少 1週間物で7月から
4.日経平均反発、終値123円高の2万2478円
5.豪の政府機関にサイバー攻撃 中国関与と現地報道
6.中国軍機、4日連続で台湾空域侵入 米接近をけん制か
7.米最高裁、リベラル寄り判決相次ぐ トランプ氏に痛手
2.製造業景況感、11年ぶり低水準 6月短観の民間予測
3.日銀、ドル供給を週3回に減少 1週間物で7月から
4.日経平均反発、終値123円高の2万2478円
5.豪の政府機関にサイバー攻撃 中国関与と現地報道
6.中国軍機、4日連続で台湾空域侵入 米接近をけん制か
7.米最高裁、リベラル寄り判決相次ぐ トランプ氏に痛手
1.ユニクロのマスク発売 店舗に行列、ネット購入殺到
ファーストリテイリング傘下のユニクロは19日、速乾性や通気性に優れる機能性肌着「エアリズム」の素材でつくったマスクを発売した。エアリズムに細菌や花粉などの粒子をブロックするフィルターなどを合わせた構造で機能と肌ざわりを両立させた。ユニクロ銀座店(東京・中央)では整理券を配布して対応したが行列ができたほか、ネット販売ではアクセスが集中してつながりにくくなるなど購入が殺到している。
商品名はエアリズムマスク。3枚組で税別990円。自宅の洗濯機で洗って、繰り返し使うことができる。東京都内に住む30代の女性会社員は「毎日健康のために10キロ歩いているが、通常の不織布では息苦しかったので購入するのが楽しみだった」と話した。
2.製造業景況感、11年ぶり低水準 6月短観の民間予測
日銀が7月1日に公表する6月の全国企業短期経済観測調査(短観)の民間エコノミストによる予測がほぼ出そろった。大企業製造業の業況判断指数(DI)はマイナス31と前回の3月から23ポイント悪化し、約11年ぶりの低水準になる見通しだ。新型コロナウイルスの打撃の大きさが鮮明になる。
QUICKが19日までに公表された17社の予測(中心値)を集計した。
3.日銀、ドル供給を週3回に減少 1週間物で7月から
日銀は19日、金融機関に米ドルを1週間貸し出すオペ(公開市場操作)の頻度を7月以降、毎日から週3回に減らすと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で強まったドルの調達不安が足元で和らいだと判断した。米連邦準備理事会(FRB)などドル供給の枠組みに参加する5つの中央銀行間で協議して決めた。
日銀は国債などを担保にドルを金融機関に貸し出している。ドル調達への懸念が高まった3月にそれまで週1回だった1週間物のドル供給の頻度を毎日に増やしていた。頻度を減らすのはコロナ禍への対応後で初めて。3カ月物のドル供給は週1回の頻度を維持する。
日銀から金融機関への1週間物のドル供給は、19日まで3日連続で利用がゼロだった。市場で円を元手にドルを調達する際のコストも3月に一時リーマン危機時以来の高水準まで上昇したが、足元では新型コロナの流行前の水準まで下がった。ドルの需給緩和を踏まえ、オペの頻度を減らす。
6月末は多くの国内企業の四半期末にあたり、海外でも半期末となるため、ドル需要が再び強まる可能性もある。日銀は今後、市場の状況をみながらドルの供給頻度を柔軟に増減させる構えだ。
4.日経平均反発、終値123円高の2万2478円
19日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反発し、前日比123円33銭(0.55%)高の2万2478円79銭で終えた。19日から国内で都道府県をまたぐ移動制限が全面解除となり、景気回復への期待感が高まるなか買いが優勢だった。後場にかけては日銀の株価指数連動型上場投資信託(ETF)買い観測も支援材料となった。もっとも、新型コロナウイルス感染「第2波」への警戒感から上値は抑えられ、日経平均は下げに転じる場面もあった。
ボラティリティー(変動率)が高い相場が続いた後とあって、相場の落ち着きどころを見定めたいとの見方から、中長期の投資家の積極的な売買は手控えられたようだ。日中は方向感を欠く展開が続いた。
JPX日経インデックス400は3日ぶりに小幅反発。終値は前日比2.31ポイント(0.02%)高の1万4263.59だった。東証株価指数(TOPIX)は3日続落し、0.29ポイント(0.02%)安の1582.80で終えた。業種別TOPIXは空運、精密機器が上昇した。半面、鉄鋼、非鉄金属は下落した。
東証1部の売買代金は概算で2兆8398億円。売買高は15億5593万株だった。英FTSEが算出する指数の構成銘柄の調整(リバランス)に伴い、機関投資家などによる大引けでの取引が膨らんだ。東証1部の値上がり銘柄数は1043銘柄だった。値下がりは1033、変わらずは90銘柄だった。
2021年3月期の増収増益見通しを発表した東エレクが7%上昇。アドテスト、ディスコなどその他の半導体関連にも上げが目立った。塩野義、JAL、JR東海も上昇。半面、MS&AD、三菱ケミHD、日本製鉄は売られた。第一生命HD、三井不も下落した。
5.豪の政府機関にサイバー攻撃 中国関与と現地報道
オーストラリアのモリソン首相は19日、豪州の政府機関や企業を標的に外国政府が関与するサイバー攻撃が起きた事実を明らかにした。特定の国の名指しは避けた。豪公共放送ABCは政府高官の話として、足元で2国間関係が冷え込む中国の関与が疑われると報じた。
モリソン氏はレイノルズ国防相と共同で記者会見を開き、「政府機関や産業界、教育や保健、重要インフラの運営企業」といった幅広い企業や機関が攻撃を受けたと主張した。「強大な能力を持つ国家を基盤とした組織が実行したことは明らかだ」とも指摘。「これだけの攻撃ができる組織は多くない」と述べた。
豪中関係は急速に悪化している。4月にモリソン氏が、新型コロナウイルスの発生源や感染拡大を巡り、独立した調査が必要だと表明した。これに対し、感染拡大が世界で初めて確認された中国が反発。5月には豪産食肉の一部の輸入を停止し、大麦に80%超の追加関税を課した。6月には中国市民に豪州への旅行や留学の中止を勧告した。
豪州では2019年2月にも連邦議会を標的としたサイバー攻撃が発生した。その際も、モリソン氏は外国政府の関与を指摘していた。
6.中国軍機、4日連続で台湾空域侵入 米接近をけん制か
台湾の国防部(国防省)は19日、中国軍の戦闘機が台湾南西の防空識別圏に一時入ったと発表した。中国軍機による侵入は同日まで4日連続で、6月に入ってからは6回目となる。中国は直近で米国と台湾の関係緊密化に反発。米台へのけん制を強めているとみられ、偶発的な軍事衝突を懸念する声も出ている。
国防部によると、19日正午に中国軍の戦闘機「殲10」が台湾の防空識別圏に入った。台湾の偵察機による警告を受け飛び去ったという。6月に入ってからは9日と12日、16〜19日にそれぞれ中国軍の戦闘機や輸送機が一時侵入し、活動が常態化している。
台湾では9日、米軍のC40A輸送機が台湾当局の許可を得て上空を飛行した。中国で対台湾政策を所管する国務院(政府)台湾事務弁公室は11日、「強烈な不満と断固とした反対を表明する」「中国の領土を完全に守る決意を低くみるな」と反発していた。
台湾の蔡英文(ツァイ・インウェン)政権は中国による統一を拒む姿勢を鮮明にし、安全保障を頼る米と関係強化を図っている。中国と対立を深める米側も台湾に肩入れしている。エスパー米国防長官は15日、ツイッターの投稿で「民主主義的な台湾への約束を果たし続ける」と言及。台湾の安全保障への関与を維持する姿勢を示した。
中台の軍事に詳しい淡江大学の黄介正・准教授は米軍輸送機の台湾上空での飛行について、「米台の高度な信頼関係の証しだ」と指摘する。一方で台湾を巡り米中の対立がエスカレートする恐れがあり、「偶発的な軍事衝突を警戒する必要がある」と指摘した。
7.米最高裁、リベラル寄り判決相次ぐ トランプ氏に痛手
米連邦最高裁判所でリベラル派の主張を認める判決が相次いでいる。最高裁は政策全般の是非を判断し、判決内容には国民の関心も高い。トランプ大統領は最高裁で支持基盤である保守派の影響力を高めたと成果を訴えてきただけに、痛手となりそうだ。
最高裁は18日、幼少期に親と米国に不法入国した若者の強制送還を猶予する制度「DACA」に関し、撤廃を当面認めない判決を下した。不法移民の保護を訴えるリベラル派の主張に沿ったものだ。オバマ前政権が導入し、これまでに約80万人が保護を受けたとされる。トランプ氏はDACAの対象に犯罪者が紛れているなどと主張し、撤廃を求めていた。
11月の大統領選で民主党の候補指名を固めたバイデン前副大統領は18日、判決を歓迎したうえで大統領就任初日に1100万人の不法移民に市民権を付与する工程表をつくるよう議会に求めるとツイッターで約束した。リベラル派の代表格であるバーニー・サンダース上院議員も「トランプ氏が移民を傷つけるために講じた全てのひどい措置を覆そう」と支持者に訴えた。
他にも最高裁ではリベラル派の主張を認める判決が目立つ。15日には職場でのLGBT(性的少数者)差別は、性別に基づく差別を禁じた連邦法に違反するとの判断を示した。LGBTの権利向上につながる判決だ。5月末には新型コロナウイルスの感染防止を理由に教会での礼拝者の人数を制限することは認められないとする西部カリフォルニア州の教会の訴えを退けた。
いずれの判決でもカギを握ったのはジョン・ロバーツ長官だ。2005年に共和党のブッシュ(子)元大統領に任命されて保守派判事とみられたが、3つの判決ではリベラル派を支持する立場に回った。最高裁判事9人のうち保守派とリベラル派は4人ずつに分かれており、ロバーツ氏の一票が判決の行方を決めるケースが増えてきた。
ロバーツ氏の行動はトランプ氏にとって誤算だ。トランプ氏は18年10月、中道派のアンソニー・ケネディ判事の後任に保守派のブレット・カバノー氏を任命。ロバーツ氏を含む保守派の判事を5人そろえて、最高裁の保守化を進めたと成果を強調してきた。最高裁は個人の銃保有や人工妊娠中絶の是非など日常生活に深く関わるテーマに判断を下し、その動向には国民の関心が極めて高い。
トランプ氏は18日、ツイッターで「最高裁は私のことを嫌いになったように見えないか?」と書きこんで、ロバーツ氏を念頭に不満を漏らした。三権分立が確立した米国で最高裁は政権から独立した立場で判決を下すが、トランプ氏は16年の大統領選の際にも「ロバーツ氏は保守派にとって悪夢だ」と批判したことがある。
トランプ氏の公約実現が滞るリスクも高まる。トランプ氏は保守派に肩入れした政策を打ち出して提訴されても最高裁で勝利して政策を実現してきた。「イスラム圏への偏見だ」と激しい批判を浴びたイスラム諸国などからの入国制限措置は最高裁が支持する判決を下した。トランプ氏が不法移民対策として推進するメキシコとの国境沿いの壁建設の財源に国防費を充てることも最高裁が認めた。
トランプ氏は18日、大統領2期目に向けて最高裁判事候補のリストを9月1日までに公表するとした。最高裁では高齢のクラレンス・トーマスやルース・ギンズバーグ両判事の去就に注目が集まる。判事は終身制だが、退任を決意すれば即座に保守派を起用する構えを見せて支持基盤をつなぎとめる思惑がある。
今後も最高裁では大きな懸案をめぐる判決が相次ぐ見通しだ。トランプ氏の財務や納税記録の開示をめぐる判決が6月中にも下される。民主党はトランプ氏に不正な資金取引などがないか追及している。人工妊娠中絶を困難にする目的だとの批判がある南部ルイジアナ州の制度への判決にも関心が高まっている。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
2020年06月18日
【経済ニュース 6/18 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
1.東京都内で新たに41人感染 新型コロナ
2.みずほ・ソフトバンク、スマホ融資提携 ペイペイ活用
3.中国「香港国家安全法」審議入り G7、試される結束
4.ビジネス往来、開国手探り 7月にもベトナムとタイ
5.NYダウ続落、一時200ドル超安 コロナ感染拡大を懸念
6.衆院解散「時がくればちゅうちょなく」 首相会見
7.Zoom、強固な暗号化技術を無料で 7月から試験提供
8.米中、対話継続を確認 外交トップがハワイで会談
9.英中銀が追加緩和、資産購入枠を13兆円増
10.中銀デジタル通貨、FRB議長が「真剣に研究する」
11.米、ウイグル人権法成立 中国は反発「強烈な憤慨」
12.米、デジタル税の交渉打ち切り 欧州に課税撤回要求
1.東京都内で新たに41人感染 新型コロナ
東京都は18日、新型コロナウイルスの感染者を新たに41人確認したと発表した。感染経路が特定されていない人が22人に上り、10〜30代が28人と全体の約7割を占めた。都内の感染者は計5674人になった。
41人のうち10人はホストクラブやキャバクラの従業員などで「夜の繁華街」での感染とみられる。既に複数の感染者が出ている武蔵野中央病院(小金井市)では新たに5人の感染が確認され、同院に関連した感染者は計58人となった。
都内では14、15日に新宿エリアを中心とした夜の街で多くの感染が確認され、40人を超える高い水準となっていた。いずれの日も、新宿区が感染者を確認した店舗の全従業員を検査する「集団検査」の数を含むため増加した。
18日の確認分に集団検査で判明した感染者は入っていない。新規感染が40人を超え、都福祉保健局は「どこにでも感染リスクはあるので、注意して感染防止に努めていただきたい」と呼びかけた。
小池百合子知事は同日、都庁で記者団に「この後、いくつかの店で関係者が多く(検査を)受けているので、また来週は多い数字が出てくる可能性がある」と話した。
19日にはスナックなどの接客飲食業に対する休業要請が解除される予定で、都は夜の街での感染防止策を呼びかけている。
2.みずほ・ソフトバンク、スマホ融資提携 ペイペイ活用
みずほフィナンシャルグループとソフトバンクがスマートフォンを使う金融サービスで提携する。ソフトバンクグループのスマホ決済「PayPay」(ペイペイ)の顧客に対し、個人の信用力を人工知能(AI)ではかる信用スコアを使った個人向け融資などのサービスを提供する。
ペイペイはスマホ決済の国内最大手で、登録者数は約2800万人に達する。
3.中国「香港国家安全法」審議入り G7、試される結束
中国の国会にあたる全国人民代表大会(全人代)は18日に常務委員会を開き、香港で反体制活動を禁じる「香港国家安全法」の審議に入った。主要7カ国(G7)が17日に「重大な懸念」を示す共同声明を発表するなか、習近平(シー・ジンピン)指導部が強行突破する構えをみせた。G7の結束が問われている。
「中国政府が再考するよう強く求める」。
4.ビジネス往来、開国手探り 7月にもベトナムとタイ
政府は18日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて制限している出入国をビジネス目的に限定して緩めると決めた。出入国時のPCR検査が条件になる。まずベトナム、タイを対象に7月にも実施する。入国者は最大でも1日250人で米国や中国、韓国、台湾は秋以降になる可能性がある。日本は検査の拡充が遅れており、手探りの開国となる。
5.NYダウ続落、一時200ドル超安 コロナ感染拡大を懸念
18日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続落して始まった。午前9時35分現在、前日比234ドル41セント安の2万5885ドル20セントで推移している。新型コロナウイルス感染の再拡大への懸念が強まり、売りが先行した。朝方発表の週間の米新規失業保険申請件数が市場予想より増え、雇用回復が遅れるとみた売りも出た。
今週に入り、テキサス州やアリゾナ州などで新型コロナの入院者数が最高水準となり、多くの州で感染者数の増加ペースが高まっていると米ウォール・ストリート・ジャーナルが18日に報じた。経済活動の正常化が遅れる可能性が意識され、投資家がリスク回避姿勢を強めた。
米新規失業保険申請件数は前週比150万8000件と前週からやや減ったが、市場予想(130万件)より多かった。市場では「申請件数の減少ペースがかなり鈍ってきた」(パンセオン・マクロエコノミクス)との指摘が多かった。
朝方発表の2020年1〜3月期決算が大幅な最終赤字となったクルーズ船のカーニバルが下落し、クルーズ船銘柄が軒並み下げている。アメリカン航空グループなど空運株にも売りが先行した。航空機のボーイングやクレジットカードのアメリカン・エキスプレスの下げも目立つ。
6.衆院解散「時がくればちゅうちょなく」 首相会見
安倍晋三首相は18日、首相官邸で記者会見を開いた。衆院解散・総選挙に関して「昨日、通常国会が終わったばかりで頭の片隅にもない」と述べた。「様々な課題に真正面から取り組む中で国民の信を問うべき時がくれば、ちゅうちょなく解散を断行する考えに変わりはない」とも語った。
■河井夫妻逮捕「大変遺憾」
記者会見の冒頭で前法相の河井克行容疑者と妻の案里容疑者が公職選挙法違反(買収)容疑で逮捕されたことを陳謝した。
「大変遺憾だ。かつて法相に任命した者としてその責任を痛感している。国民の皆さんに深くおわび申し上げる」と述べた。「国民の厳しいまなざしをしっかり受け止め、国会議員は自ら襟を正さなければならない」とも強調した。
■「改憲、任期内に」
憲法改正に関する議論について「各党各会派の意見を伺いながら深化させたい」と述べた。「目の前の課題を先送りせず解決していく。これは私たち政治家の責任だ」と強調した。
「(2021年9月までの)総裁任期の間に憲法改正をなし遂げていく決意は変わらない」と明言した。党総裁4選や任期の延長は「全く考えていない」と述べた。
■「後継者は育つもの」
「ポスト安倍」を巡り「後継者は育てるものではなく、育ってくるものだ」との認識を示した。佐藤栄作政権の「三角大福中」の例を挙げて「ポストを生かしてチャンスをつかんできた」と指摘した。
「成果を地味に出す人もいれば、うまく発信している人もいる。それぞれが立場、立場でがんばってもらいたい。国のために全力を尽くす結果、そういう立場に立っていく」と訴えた。
■安保戦略「夏に新しい方向性」
首相は「安全保障戦略のありようについて今夏に国家安全保障会議(NSC)で徹底的に議論し新しい方向性を打ち出し、すみやかに実行に移していきたい」と言明した。
防衛大綱と中期防衛力整備計画(中期防)の見直しに関して「全く考えていない」と述べた。「国民の命と平和な暮らしを守るために何をなすべきか基本からしっかりと議論すべきだ」と話し、NSCで方向性を協議する意向を示した。
地上配備型の迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の計画停止を巡り「わが国の防衛に空白を生むことはあってはならない。平和は人から与えられるものではなく我々自身の手で勝ち取るものだ」と話した。
北朝鮮との緊張が高まる韓国からの在外邦人退避を巡り「日米、日韓、日米韓でプランを協議していくことは重要だ。在外邦人の安全を確保するために様々なことに対応していかなければいけない」と指摘した。
■検査強化、2次感染防止に有効
新型コロナウイルスの感染者が東京の「夜の繁華街」で働く人の間で相次いだことに関して、PCR検査の強化によるものだと強調した。「二次感染を防止する上で有効だ」とも述べた。
クラスター(感染者集団)対策として、社会・経済活動の引き上げと感染防止を両立する上で必要だとの考えを示した。
新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した可能性を通知するスマートフォン向けアプリを19日に配信すると明らかにした。「個人情報はまったく取得しない。多くの人にダウンロードしていただきたい」と話した。
■PCR検査「一層強化する」
19日に社会経済活動のレベルを「もう一段引き上げる」と表明した。「都道府県をまたぐ移動も全て自由になる。観光旅行も人との間隔を取ることに留意しながら出かけてもらいたい」と呼びかけた。
プロ野球やJリーグ、コンサートの再開などに触れ「感染予防策を講じながら社会経済活動を本格化してもらいたい。新たな日常を作り上げていく」と語った。
感染の有無を調べるPCR検査や抗原検査などの態勢について「一層強化していく」と強調した。
■ビジネス往来緩和、客観的な基準置かず
首相はビジネス目的に限定した往来緩和の対象国について「感染再拡大を防止する観点も踏まえながら、協議が整ったところから順次措置をとる」と表明した。「『日本はこういう基準ですよ』『クリアしたからどうぞ』ではない」として、客観的な基準を置くことには否定的な考えを示した。
出入国制限をめぐり「グローバル化が進化した世界になって現在の鎖国状態を続けることは、島国の貿易立国日本にとっては致命的だ」と述べた。感染状況が落ち着いている国を対象に、ビジネス上の往来が必要な国から段階的に解除する方針を示した。今後の往来再開に向け「とにかく検査能力の拡充が必要だ」とも話し、新たなPCRセンターの設置を検討すると表明した。
■五輪円滑実施へワクチン開発
首相は2021年夏の東京五輪・パラリンピックの開催に向け、新型コロナのワクチン開発を進めると訴えた。「円滑に実施するためにも我が国、世界の英知を結集して開発に取り組みたい」と語った。国際オリンピック委員会(IOC)理事会が示した簡素化などの方向性に関しては「原点に戻った大会にしようということだと理解した」と述べた。
■未来投資会議、メンバーを拡大
政府の未来投資会議について、メンバーを拡大した上で来月から議論を開始すると明らかにした。新型コロナの影響でテレワークが普及し、地方への転勤希望者が増加した背景などから「集中から分散へ日本列島のあり方を変えていく大きなきっかけだ」と強調した。「新しい日本の姿、ポストコロナの未来についてもしっかり描いていかなければならない」と語った。
■拉致問題解決「私の使命」
首相は横田めぐみさんの父、滋さんら日本人拉致被害者の家族が亡くなったことについて「痛恨の思いだ。大変責任を痛感している」と述べた。拉致問題に関し「今後も政権の最重要課題、私の使命として取り組んでいく」と語った。
7.Zoom、強固な暗号化技術を無料で 7月から試験提供
ビデオ会議サービス「Zoom」を運営する米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズは17日、通信の秘匿性が高い「エンド・ツー・エンド(端末間)」の暗号化技術を無料ユーザーも使えるようにすると発表した。有料プランの利用者向けとする計画だったが、データ保護への関心が高まるなかで全員が使えるようにする。
安全性をめぐる様々な問題が発覚した3月以降、ズームはソフトウエアの改良による対策を進めてきた。通信データをすべて暗号にし、参加者の端末でのみ閲覧できるエンド・ツー・エンドの暗号化もその一つ。製品として提供する時期は決まっていないが、7月から「テスト版」を試せるようにする。
無料の利用者も強固な暗号化技術を使えるように方針を変えたのは、米グーグルや米マイクロソフトなどがビデオ会議サービスを強化しているためだ。競争が激しくなるなかで、ズームの利用者らにくすぶるデータ保護への疑念を払拭する狙いがある。
8.米中、対話継続を確認 外交トップがハワイで会談
ポンペオ米国務長官は17日、訪問先のハワイで中国外交担当トップの楊潔篪(ヤン・ジエチー)中国共産党政治局員と会談した。国務省の発表によると、ポンペオ氏は新型コロナウイルスの感染拡大を巡り、完全な透明性の確保と情報共有の必要性を強調した。中国メディアは今後も対話を続ける方針で一致したと伝えた。
米中対立が先鋭化して以降、両国の高官が直接対面して本格協議する初の機会となった。緊張緩和に向けた転換点となるかは見通せない。
協議はホノルルの米空軍基地で現地時間17日午前9時(日本時間18日午前4時)ごろに始まり、午後5時までに終わった。ポンペオ氏は米国の重要な国益を主張し、商業や安全保障、外交分野で完全に互恵的な関係が必要だと訴えた。これらは中国による香港への統制強化や中国による米国人記者の追放などが念頭にあるとみられる。
トランプ政権は中国が新型コロナ対処の初動を誤り、発生源などの情報開示も不十分だと批判を強めてきた。中国側が直接協議でどう応じたかが焦点となる。
緊迫している北朝鮮情勢も懸案に急浮上している。北朝鮮は韓国に軍事的な挑発を強める構えを示し、米中は事態の沈静化に向けた対応を話し合った可能性がある。
日米欧の主要7カ国(G7)外相の共同声明が中国が制定作業を進める「香港国家安全法」に「重大な懸念」を示したことに対し、楊氏はポンペオ氏との会談で「断固とした反対」を表明。「立法の決心は揺るがない」と発言した。中国外務省が18日に発表した。
中国共産党の機関紙、人民日報(電子版)は18日、会談について「中米関係やお互いに関心を持っている国際問題と地域の問題で深く意見交換した」と伝えた。「お互いの立場を十分に明らかにした」と指摘し、米中の対立点の多さをうかがわせた。米国の政治専門紙ポリティコによると、会談は中国側が要請した。
9.英中銀が追加緩和、資産購入枠を13兆円増
英イングランド銀行(中央銀行)は18日、量的金融緩和策の拡大を発表した。国債や社債の買い入れ枠を1000億ポンド(約13.4兆円)増やし、総額7450億ポンドに引き上げる。金融市場に大規模な資金供給を続け、新型コロナウイルスのまん延で打撃を受けた経済を下支えする。
17日まで開いた定例の金融政策委員会で、政策委員9人のうち8人の賛成多数で決めた。チーフエコノミストのハルデーン委員は、経済の回復ペースが想定よりも速いとして据え置きを主張した。政策金利は過去最低の年0.1%に維持することを全会一致で決めた。
イングランド銀は3月、2度の緊急会合で政策金利を0.75%から引き下げるとともに、資産の購入枠を2000億ポンド増やした。4月以降は毎週140億ポンド程度の債券を買い入れており、今のペースでは7月初めにも上限に達する見通しだった。今回の声明では、新たな上限に達する時期を「年が変わるころ」と説明し、購入ペースは減速するとの想定を示した。
足元の英経済については、行動制限の一部緩和を受けて「個人消費やサービス業が上向く兆しがある」と指摘した。4〜6月期の国内総生産(GDP)は、前回5月に想定していたほどは悪化しないとの見方を示した。ただ「世界経済の下方リスクは残っている」とし、新型コロナの新興国での感染拡大などを挙げて慎重な立場を維持した。
英国では3月下旬に導入した外出制限が響き、4月の実質GDPは前月比20%減となった。6月15日から多くの小売店の再開が認められたが、感染状況の厳しさから制限緩和は欧州内で遅れている。経済協力開発機構(OECD)は2020年の実質GDPは前年比11.5%減と、主要7カ国(G7)で最も落ち込みが厳しいと予測する。
市場ではイングランド銀が今後、マイナス金利政策を導入するとの予想が広がった。今回の議事要旨では、マイナス金利に関する議論の形跡はなかった。3月に就任したベイリー総裁はこれまで「支持しない」と表明していたが、5月20日の英下院財務委員会の公聴会では「立場を少し変えた」と述べ、選択肢から排除せずに是非を検討していく方針を示していた。
10.中銀デジタル通貨、FRB議長が「真剣に研究する」
米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は17日の米下院委員会で、中央銀行が発行するデジタル通貨(CBDC)を「真剣に研究していく案件の1つだ」と述べた。FRBはドルのデジタル化に慎重な姿勢だったが、同氏は「世界の基軸通貨としての地位を保つ必要がある」と強調した。
パウエル氏は前日の上院に続き、下院金融サービス委員会で半期ごとの議会証言に臨んだ。CBDCは欧州中央銀行(ECB)や日銀が共同研究を開始している。パウエル氏も「デジタル通貨は、我々が最も先端で、最も深く理解しなければいけない」と述べ、FRBとして「デジタルドル」の独自研究を進める考えを強調した。
FRBはこれまで、CBDCはサイバー攻撃などのリスクが大きいとして、独自発行に極めて慎重だった。ただ、中国が「デジタル人民元」の実証実験を進めるなど、技術の変化が加速。パウエル氏は17日の議会証言で「ドルは(各国が保有する)準備通貨であり続ける必要がある」と強調し、各国への対抗姿勢を鮮明にした。
米ドルは各国が貿易決済などに使う世界の基軸通貨で、パウエル氏も16日の上院委で「ドルは基軸通貨なので、米国は多大な借り入れ能力がある」と、その利点を主張していた。ただ、トランプ米政権はドルを使って各国に経済制裁を仕掛ける動きを強めており、中国などは「脱ドル」を模索し始めている。
11.米、ウイグル人権法成立 中国は反発「強烈な憤慨」
トランプ米大統領は17日、中国の新疆ウイグル自治区で少数民族ウイグル族への弾圧に関与した中国の当局者への制裁に道を開くウイグル人権法に署名し、同法が成立した。ホワイトハウスが発表した。ハワイで米中高官協議が開かれるタイミングでの成立となった。
同法は米政府にウイグル族への弾圧や人権侵害に関わった人物のリストを180日以内に作成して議会に報告するよう求め、それらの人物にビザ(査証)発給の停止や資産凍結などの制裁を科せるようにする内容だ。上下両院では圧倒的多数の支持で可決されていた。
米でウイグル人権法が成立したことについて、中国外務省は18日に声明を出し「乱暴に中国の内政に干渉するもので、中国政府と人民は強烈な憤慨と断固とした反対を表明する」と反発した。
通常の報道官談話よりも格上の声明で「いかなる外国の干渉も受け入れないと米国に忠告する」と強調。「一切の悪い結果はすべて米国が負うことになる」と指摘した。
12.米、デジタル税の交渉打ち切り 欧州に課税撤回要求
トランプ米政権は17日、英国やフランスなど欧州勢に対し、各国が導入する「デジタルサービス税」をめぐる国際交渉を打ち切ると伝達したと明らかにした。欧州各国にデジタル税の課税撤回を強硬に求めたもので、報復関税を発動する可能性もある。経済協力開発機構(OECD)による国際課税のルールづくりも停滞が避けられない。
米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表が17日の米下院公聴会で証言した。主要国はデジタル課税をめぐり、ITサービスの消費地に税収を分配する国際課税ルールを検討している。ライトハイザー氏は「現時点で交渉は行き詰まっており、ムニューシン米財務長官は欧州勢に『交渉から離脱する』と伝えている」と話した。
トランプ米政権は英国、フランス、イタリア、スペインの欧州4カ国のデジタルサービス税について「米企業を狙い撃ちした不当な措置」と反発。USTRはブラジルやインドなどデジタル税を検討する新興国も含め、報復関税の発動を視野に実態調査を進めている。ライトハイザー氏は17日の公聴会でも「米産業界への不公正な措置を許してはならない」と強調した。
欧州を中心に各国が独自のデジタル課税に動くのは、米国の強硬姿勢で国際ルールづくりが進まないためだ。OECDは1月末、巨大グローバル企業への課税強化案をまとめたが、米国は「現行ルールと新ルールのどちらかを企業が選択できる」という独自案を提案。日欧や新興国は「骨抜き」と一斉に反発し、国際合意は遅れている。
巨大IT企業は知的財産権を低税率国に置き、営業所や工場などがない消費地で課税を回避してきた。節税規模は世界で1000億〜2400億ドルに達するともされ、欧州を中心に不満が強い。そのため英国やフランスは各国に先駆けて独自のデジタル課税を導入し、アップルなど巨大IT企業が集中する米国の反発を招く悪循環になっている。
米欧の対立が深まれば、20年中の合意をめざすOECDの国際ルールづくりも実現が遠のく。ライトハイザー氏は17日の公聴会で「交渉の余地はあり、アイデアもある」とも述べており、交渉撤退や関税発動を振りかざしながら、欧州勢に課税の撤回を促す交渉姿勢を貫いている。
【経済ニュース 6/17 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
1.NYダウ、もみ合いで始まる 新型コロナ「第2波」重荷に
2.2019年度税収60兆円割れ コロナ響き、20年度も下振れ
3.中印衝突で45年ぶり死者、緊張高まる
4.英、TPP加盟の意向再表明 申請に向け本格調整へ
5.OPEC、年後半は石油需要の回復を予測 減少幅640万バレル
6.東証大引け 反落、新型コロナ感染再び増加の懸念 売り優勢
7.米国債「大量に発行可能」 FRB議長が追加歳出促す
8.米国務長官、中国高官と会談へ ハワイ訪問を発表
9.北朝鮮、止まらぬ挑発 軍事緊張、1990年代に逆戻り
10.トランプ氏、警察改革で民主と火花 大統領令に署名
2.2019年度税収60兆円割れ コロナ響き、20年度も下振れ
3.中印衝突で45年ぶり死者、緊張高まる
4.英、TPP加盟の意向再表明 申請に向け本格調整へ
5.OPEC、年後半は石油需要の回復を予測 減少幅640万バレル
6.東証大引け 反落、新型コロナ感染再び増加の懸念 売り優勢
7.米国債「大量に発行可能」 FRB議長が追加歳出促す
8.米国務長官、中国高官と会談へ ハワイ訪問を発表
9.北朝鮮、止まらぬ挑発 軍事緊張、1990年代に逆戻り
10.トランプ氏、警察改革で民主と火花 大統領令に署名
1.NYダウ、もみ合いで始まる 新型コロナ「第2波」重荷に
17日の米株式市場でダウ工業株30種平均はもみ合いで始まった。午前9時40分現在、前日比23ドル84セント安の2万6266ドル14セントで推移している。米景気回復や大型の経済対策を期待した買いが続き、取引開始直後は100ドル近く上昇する場面があった。半面、新型コロナウイルス感染の第2波への懸念はくすぶり、相場の重荷になっている。
早期の経済再開を実施したテキサスやフロリダなどでは日々の感染者数の大幅増加が続いている。ホワイトハウスで新型コロナ対策の中心的な役割を担うファウチ国立アレルギー感染症研究所長が「複数の州での感染急増は検査数の増加では説明できない」と警鐘を鳴らしたことが伝わった。
朝方発表の5月の米住宅着工件数は前月比4.3%増と大幅な減少だった4月から回復した。住宅着工許可件数は14.4%増と大きく伸びた。「先行きの住宅着工が一段と増加することを示している」(アマースト・ピアポントのスティーブン・スタンレー氏)
航空機のボーイングや建機のキャタピラーは安い。一方、ソフトウエアのマイクロソフトやスマートフォンのアップルなどハイテク株は買いが先行している。
2019年度税収60兆円割れ コロナ響き、20年度も下振れ
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国の2019年度の税収が2年ぶりに60兆円を割り込む見通しだ。企業活動の停滞に加え、収入が急減した場合に納税を1年猶予する措置を導入したことも響く。20年度も不透明感が強く、民間では50兆円台前半まで落ち込むとの試算もある。
3.中印衝突で45年ぶり死者、緊張高まる
インド北部ラダック地方にある中国との係争地域で中印両軍が衝突し、インド軍の20人が死亡、中国軍も死傷者を出した。両国の衝突で死者が出たのは1975年以来、45年ぶりで極めて異例だ。双方とも対話を探る姿勢は示すが領土問題で譲歩する兆しはなく、緊張が高まる危うさをはらむ。
インドのモディ首相は17日、「兵士の犠牲は無駄にしない」と語り2分間の黙とうをささげた。「インドは平和を求めている。ただ刺激されれば適切な対応を取る」とも強調した。インド外務省は16日夜の声明で「中国と緊張緩和のために会談してきたが、中国側が合意を破った」と非難した。インド軍は「領土と主権を断固として守る」と一歩も引かない構えだ。
一方、中国外務省の趙立堅副報道局長は17日の記者会見で「インド軍は約束に違反して2回実効支配線を越えた」と主張。領土を巡る問題で譲らない姿勢を強調した。
インド軍によると衝突は15日夜〜16日未明に起きた。当初の発表で死者は3人だった。現場は高地で、新たに死亡が確認された17人は衝突で負傷後、気温が氷点下になるなどの影響で死亡したという。中国側は発表していないが、43人が死傷したとの現地報道がある。
両軍は5月から両国の実効支配線のある湖パンゴン・ツォ周辺など数カ所でにらみ合い小競り合いが起きていた。中国軍が兵士5千〜6千人を増強し、インド軍も同数を配置していた。
中国外務省によると王毅(ワン・イー)外相とインドのジャイシャンカル外相は17日、電話協議し、現地情勢を沈静化し地域の平和と安定を守る認識で一致した。電話は中国側からかけたとみられる。習近平(シー・ジンピン)指導部は衝突を巡る報道を抑えている。人民解放軍の機関紙、解放軍報は17日付紙面で衝突を伝えなかった。
中国はトランプ米政権からの圧力が強まるなか、インドとまで対立関係に陥るのは避けたいのが本音とみられる。ただ対外的に領土問題で譲歩する余地はない。インドも経済成長が鈍るなか、モディ政権には外交で弱腰の姿勢を見せづらい事情がある。領土を巡る争いでナショナリズムが高まればなおさらだ。
中印の政府・軍関係者は6月6日に協議し「平和的解決」をめざす方針で一致していた。北京の軍事筋は「上層部の交渉は順調だったが、現場でうまくいかなかった」との見方を示す。部隊同士が対立感情から不測の衝突に至るリスクはくすぶる。今回の衝突が殴り合いや投石などによるものだったとの報道もある。
トランプ米大統領は5月27日、「米国は両国の激しい国境紛争を仲介する用意があると伝えた」と表明し、仲介に意欲を示した。インドを引き寄せ対中圧力を強める狙いがあるとみられるが、現時点で中印とも米国の仲介に否定的だ。ロシアのプーチン大統領もモディ印首相との関係改善に乗り出している。中印対立を機に影響力を強める狙いが透ける。
4.英、TPP加盟の意向再表明 申請に向け本格調整へ
英政府は17日の声明で、環太平洋経済連携協定(TPP)への加盟を目指す方針を改めて表明した。欧州連合(EU)離脱後の通商戦略の柱に位置づけ、新型コロナウイルスで傷ついた経済の再建につなげる。今後、日本などの加盟国との協議や英へのメリットを分析する国内議論を本格化し、参加申請するかを最終判断する。
トラス国際貿易相は17日の英議会下院での演説でTPPについて「貿易と供給網のパートナーを多様化し、英国経済を強固にできる」と加盟のメリットを説明した。政府の声明ではTPPを通じて、日本やオーストラリアなど自由貿易を推進する国との連携を深め、コロナの影響で台頭しつつある保護主義に対抗する姿勢も強調した。
離脱したEUとの貿易が全体のほぼ半分を占める英国は、域外との通商関係の強化が重要課題で、日米豪やニュージーランドとも2国間の自由貿易協定(FTA)締結を目指している。足元でEUとの新たなFTAなどを交渉中だが難航している。国内では香港問題を受けて中国への経済的依存を弱めるべきだとの声も強く、TPP参加の意義は高まっている。
英国は2018年7月にTPPの参加検討を表明してから、加盟国との協議や情報収集を進めてきた。英政府によると、TPPの現加盟国の国内総生産(GDP)の合計は2018年時点で世界全体の13%を占めており、英国が加われば16%に拡大する。
5.OPEC、年後半は石油需要の回復を予測 減少幅640万バレル
石油輸出国機構(OPEC)は17日、2020年7〜12月の世界の石油需要は前年同期に比べ日量640万バレルの減少にとどまるとの見通しを発表した。1〜6月は新型コロナウイルスの世界的な流行で前年比で日量1190万バレル落ち込んだ。
OPECとロシアなどは過去最大の日量970万バレルの協調減産による原油価格の下支えを続ける。感染防止のための行動制限の解除が各国で進むことに期待を寄せているもようだ。
OPECの5月の減産量は日量630万バレルで、ロイター通信の計算によると合意の順守率は84%。サウジやアラブ首長国連邦(UAE)、クウェートが合意をほぼ完全に履行したのに対し、イラクなどが合意を大きく上回って生産した。
6.東証大引け 反落、新型コロナ感染再び増加の懸念 売り優勢
17日の東京株式市場で日経平均株価は反落し、前日比126円45銭(0.56%)安の2万2455円76銭で終えた。新型コロナウイルスの新規感染者数が米国や中国で増えていることへの懸念から売りが優勢だった。前日の大幅高からの反動で、短期筋らによる利益確定売りに押された。北朝鮮情勢への警戒感も高まり、積極的な投資が手控えられた。
朝方から売りが先行した。朝鮮半島の情勢悪化や感染者の増加を手掛かりに、1000円超高となった前日の相場を受けた利益確定売りが出て、一時264円安まで下げた。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が議会証言で景気の先行き不透明感に触れたことも投資心理を冷やした。
ただ、米国の消費の回復や米トランプ政権によるインフラ整備計画への期待などは根強く残った。国内でも新興株が堅調に推移したことを安心材料に一方向に売りを急ぐ展開にはならなかった。ここ数日、東京時間中に世界的に相場が動くことが多かったが、この日の取引では目立った材料も出ず、もみ合いが続いた。
7.米国債「大量に発行可能」 FRB議長が追加歳出促す
米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は16日の米上院委員会で、「米国は基軸通貨国で、大いに国債発行能力がある。財政悪化を懸念するのではなく、今は歳出増で経済再生を優先すべきだ」と主張した。早期の財政立て直しを意識する米議会に対して、追加の新型コロナウイルス対策を求めた発言だ。
パウエル氏は上院銀行委員会で、半期ごとの議会証言に臨んだ。新型コロナによる経済活動の制限で、4〜6月期の経済成長率は「過去例のない過酷な落ち込みとなるだろう」と指摘した。失業率の改善など米景気には底入れ感もあるが「雇用も生産も危機前の水準を大きく下回っている」と強い懸念を表明した。
米政権と議会は既に3兆ドル弱の新型コロナ対策を発動したが、パウエル氏は「生活者が新型コロナの封じ込めに確信が持てるようになるまで、経済は完全には復元しないだろう」と指摘。失業の長期化など経済の停滞を避ける必要があると強調した。
米議会には「FRBとともに追加対策の発動余地がある」と指摘し、歳出の一段の積み増しを求めた。共和党の財政保守派を中心に追加対策に慎重な意見もあるが「経済成長こそが将来の債務返済を手助けするものになる」と主張した。
FRBは量的緩和で大量の米国債を購入しており、中央銀行が連邦政府の債務を穴埋めする「財政ファイナンス」との指摘も出た。パウエル氏は「国債購入は市場の円滑な取引を支えるための手段」と述べ、禁じ手とされる財政ファイナンスを否定した。ただ、国債利回りが上昇する際には「それを抑える必要がある」とも述べた。
トランプ米政権は追加対策として、1兆ドル規模のインフラ投資や中間層減税を検討している。ただ、与党・共和党は失業率の改善で景気に底入れ感が出てきたため、大型の財政出動に慎重な意見が出てきた。7月末には失業給付の特例加算が打ち切られる方向で、市場では「財政の崖」による景気の下押しを不安視する声もある。
8.米国務長官、中国高官と会談へ ハワイ訪問を発表
米国務省は16日、ポンペオ国務長官が16、17両日にハワイを訪問すると発表した。訪問の理由は公表していない。米外交筋は16日、ポンペオ氏が現地滞在中に中国の外交担当トップ、楊潔篪(ヤン・ジエチー)中国共産党政治局員と会談する見通しだと明らかにした。
新型コロナウイルスの感染拡大や中国による香港への統制強化などを受けて米中対立は先鋭化しており、今回の高官協議は両国の緊張緩和に向けた機会となる可能性もある。これらに加え、北朝鮮や貿易、軍縮といった幅広い案件が議題になりそうだ。
ポンペオ氏には北朝鮮担当特別代表を兼ねるビーガン国務副長官が同行する。スティルウェル国務次官補(東アジア・太平洋担当)も随行するもようだ。米メディアは会談が中国側の要望を受けたもので、ハワイにある空軍基地で実施される見通しだと伝えている。
海外を含めた国務長官の出張には米メディアの同行が通例だ。米ポリティコによると、今回は同行記者団がいないという。
9.北朝鮮、止まらぬ挑発 軍事緊張、1990年代に逆戻り
北朝鮮による相次ぐ韓国への挑発行動で、南北間の軍事緊張は1990年代の状況へと逆戻りした。2000年以降に進んだ南北融和は大きく後退する。挑発が続く見通しで、韓国側では強硬姿勢で応じるべきだとする声も出ている。
朝鮮人民軍総参謀部が発表した軍事行動計画によると、軍は開城と金剛山に連隊級の部隊と火力区分隊を展開する。2004年に開城工業団地が稼働する以前、開城にはソウルを狙う高射砲や装甲車部隊が配置されていた。金剛山近くには90年代まで軍港が置かれていた。
開城、金剛山の両地は南北が冷戦時代の対立から「和解」の時代へと入った融和の象徴だった。98年から10年間続いた韓国人の金剛山観光と、開城工業団地で得る労働者の賃金は、北朝鮮の重要な外貨収入源となった。
北朝鮮軍はさらに、軍事境界線付近の緊張緩和をうたった18年の軍事合意を事実上の白紙にする行動を予定している。境界線の南北に幅2キロメートルにわたって広がる非武装地帯(DMZ)内の監視所を復活させ、陸海の前線で部隊を増強し軍事訓練を再開するという。
海上の境界線である北方限界線(NLL)では、過去にも艦艇の侵犯に伴う衝突がたびたび起きている。前線の一部で、対韓国の「ビラ散布闘争」を展開するとも主張している。挑発行動の発端となった韓国の脱北者団体は、北朝鮮に近い江華島からのビラまきを予告しており、報復に出る可能性がある。
朝鮮労働党第1副部長の金与正(キム・ヨジョン)氏は17日付の談話で、韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領を「根深い事大主義の根性に苦しみ自滅に走っている」と直接批判した。
文氏が15日に「対話で知恵を寄せ、ともに乗り越えたい」などと発言したことに「ずうずうしい詭弁(きべん)だ」などと反発。「信頼が根元まで崩れ嫌悪は極に達したのに、うわべだけの言葉で北南関係を反転できるのか」と強調した。
文氏と金正恩(キム・ジョンウン)委員長は18年4月と9月の会談で、北朝鮮の体制保障と経済協力をめざすと約束した。文氏は米朝の仲介役を自任したが、米国の反対を前に具体策を実行に移せなかった。
北朝鮮は軍の行動計画を実行に移しながら、一段と緊張を高める方針とみられる。朝鮮中央通信は17日の論評で「口を慎まなければ『ソウル火の海』説が再び浮上するかもしれない」と主張した。94年の南北実務協議で、北朝鮮の首席代表は韓国側に「戦争が起きれば、ソウルは火の海になる」と発言したことがある。
専門家の多くは、北朝鮮が南北関係を実際に破綻させる意思はないと見ている。独裁体制を苦しめている経済制裁が解かれるメドが立たないままでは、指導部はかえって窮地に追い込まれる恐れがあるからだ。韓国議会の過半数は、北朝鮮に融和的な革新勢力で占められており、政策を有利な方向に引き込む環境は整っている。
韓国側は、特使の派遣を打診し拒まれたことまで暴露され反発を強めた。大統領府の尹道漢(ユン・ドハン)国民疎通首席秘書官は17日に「無礼だ。常識外れの行為だ」と発表し、与党「共に民主党」の李海●(たまへんに贊)(イ・ヘチャン)代表も「北朝鮮の行動は度を超えた」と語った。
もっとも、南北融和を最大の成果と誇る文氏が、対話方針を改めることは考えにくい。文氏は17日、政権の外交安全保障の担当者を集めて対応を協議した。
文政権は今後、南北融和の理想と、安全保障の間で難しい判断を迫られる。夏の米韓合同軍事演習を実施するかどうかや、8月には米国が延長を望む日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の更新が問われる。在韓米軍の駐留経費問題も米国と交渉がまとまっていない。
10.トランプ氏、警察改革で民主と火花 大統領令に署名
トランプ米大統領が16日公表した警察改革を野党・民主党が一斉に批判した。トランプ氏は中西部ミネソタ州で起きた黒人暴行死事件の死因となった警官による首絞め行為を原則禁止したが、一部条件付きで認めており、警察組織の抜本改革にはほど遠いと反発している。
トランプ氏は16日、警官に親族が殺害された遺族とホワイトハウスで面会した。マクナニー大統領報道官によると、子どもが命を落とした事件の説明などがあり参加者が涙を流したり感情的になったりして「大統領も打ちひしがれていた」という。トランプ氏は「こうした家族を助けなければならない」と話した。
トランプ氏は声明で、首絞め行為を「警官の命が危険にさらされない限り禁止する」とした。ただニューヨーク州などは首絞めを全面禁止し、実施した場合に厳罰を科す。これに比べてトランプ氏が署名した警察改革の大統領令は拘束力が弱いとの見方が多い。
大統領令では警察の訓練充実を目的として助成金制度を設け、過剰な暴力行為をした警官を把握するデータベースをつくるとしたが、白人警官による黒人の取り締まりが厳しい実態の是正などには切り込んでいない。
民主党のペロシ下院議長は16日の声明で、大統領令に関し「黒人殺害の原因である人種間の不公平や警官の残忍さをなくすには悲しいほどに力不足だ」と批判した。民主党は暴力行為をした警官を起訴しやすくすることを柱とした警察改革法案を公表し、米メディアによると下院は来週にも本会議で採決する構えだ。民主上院トップのシューマー院内総務も大統領令を「包括的で意義のある変革をもたらさない」と断じた。
一方で大統領選の民主候補に確定したバイデン前副大統領にも、リベラル派からの風当たりが厳しい。左派の代表格であるサンダース上院議員を大統領選で支持したグループを含む約50のリベラル派団体は、バイデン氏が提案した各地域の警察の訓練充実に向けた補助金支給を取り下げるよう求めた。多くの左派団体は警察予算の削減を求めており、バイデン氏の取り組みは不適切だとみる。
2020年06月16日
【経済ニュース 6/16 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
さて日銀の追加緩和がまさかすぎる額・・・
そしてFRBの個人企業の国際買い上げも始まり
相場は相変わらずインチキ爆上げムードです
今日の見出しです
1.「2022年度でも利上げ遠い」 日銀総裁、経済の厳しさ続く
2.北朝鮮、南北連絡事務所を爆破 韓国「厳重に警告」
3.日経平均が大幅反発 終値1051円高の2万2582円
4.ユーグレナ、一時11%高 抗体検査開発に期待(話題の株)
5.対アマゾンで新旧タッグ ウォルマートとショッピファイ
6.英・EU首脳「移行期間延長なし留意」 交渉加速は合意
7.トランプ氏「駐独米軍を3割削減」 負担不足に不満
8.FRB、6千億ドルの企業融資始動 未経験の損失リスク
9.米、ファーウェイと議論容認 5Gの基準作りで
2.北朝鮮、南北連絡事務所を爆破 韓国「厳重に警告」
3.日経平均が大幅反発 終値1051円高の2万2582円
4.ユーグレナ、一時11%高 抗体検査開発に期待(話題の株)
5.対アマゾンで新旧タッグ ウォルマートとショッピファイ
6.英・EU首脳「移行期間延長なし留意」 交渉加速は合意
7.トランプ氏「駐独米軍を3割削減」 負担不足に不満
8.FRB、6千億ドルの企業融資始動 未経験の損失リスク
9.米、ファーウェイと議論容認 5Gの基準作りで
1.「2022年度でも利上げ遠い」 日銀総裁、経済の厳しさ続く
日銀は16日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和政策の維持を決めた。黒田東彦総裁は会合後に記者会見し、日本経済について「厳しい状態が続く」との認識を示した。少なくとも2022年までゼロ金利を維持するとしている米連邦準備理事会(FRB)より先に日銀が利上げに踏み切ることは難しいとの見方について「正直、そうだと思う」と明言した。
黒田総裁は物価上昇が低い水準で推移するとの見方を示したうえで「21年度であれ、22年度であれ、金利を引き上げる状況には遠い」として、金融緩和を粘り強く続ける姿勢を強調した。
経済の先行きについて新型コロナウイルスの影響で抑制された需要が出てくる半面、感染症の行方や内外経済への影響の大きさは「極めて不確実性が大きい」と語った。
決定会合は15日から2日間、開いた。企業の資金繰り支援は政府の2020年度第2次補正予算を受け、総枠が75兆円から110兆円になる。
短期政策金利マイナス0.1%、10年物国債金利を0%近辺に誘導する長短金利操作(イールドカーブコントロール)の枠組みは維持した。
黒田総裁は様々な対策の効果で年後半にかけて景気が改善していくとの基本認識は変えていないと述べた。そのうえで「企業や家計の中長期的な成長期待が大きく低下せず、金融システムの安定性が維持されるもとで金融仲介機能が円滑に発揮されるかについて注意が必要だ」と警戒した。
今後の政策運営について「必要があればちゅうちょなく追加的な金融緩和措置を講じる」と強調した。追加緩和の具体策をめぐり、企業の資金繰り支援策について「必要に応じて拡充、拡大を検討していく」と言明。さらに長短金利のさらなる引き下げ、上場投資信託(ETF)の買い入れ額の増額などを挙げた。
物価の動向を巡っては「2%の物価安定の目標は堅持していく。経済を持続的な成長経路に戻し、その下で物価上昇率を徐々に高めていくことを実現する」と述べた。新型コロナの影響については「一部の新興国で感染の拡大が止まらないこといがリスクになっている」との懸念を表明した。
日銀は新型コロナ対応ですでに大きく3種類の政策を打ち出している。一つが企業の資金繰り支援。金融機関にゼロ金利で資金を供給し、コロナ禍で苦しむ企業への融資を後押しする。二つ目がETFの買い入れ、三つ目は国債買い入れとドル資金の供給だ。年80兆円としていたメドを4月になくし制限なく国債を買えるようにした。
2.北朝鮮、南北連絡事務所を爆破 韓国「厳重に警告」
韓国統一省は16日、北朝鮮が同日午後2時49分ごろ、開城(ケソン)にある南北共同連絡事務所を爆破したと発表した。
北朝鮮は韓国の脱北者団体がまいたビラに強く反発しており、対韓工作を担う金与正(キム・ヨジョン)朝鮮労働党第1副部長が13日、同事務所の爆破を予告していた。
韓国大統領府は同日夕、鄭義溶(チョン・ウィヨン)国家安保室長が国家安全保障会議(NSC)常任委員会を招集。「朝鮮半島の平和定着を望むすべての人々の期待を裏切る行為」と強い遺憾を表明し「これにより発生するあらゆる事態の責任は全面的に北朝鮮側にある。状況を悪化させる措置を続ければ、我々は強力に対応すると厳重に警告する」と発表した。
北朝鮮の朝鮮中央通信も同日、同事務所が「完全に破壊された」と報じた。韓国国防省が公開した映像では、爆発とともに建物が崩壊する様子が確認された。
同事務所は2018年4月の南北首脳会談で文在寅(ムン・ジェイン)大統領と金正恩(キム・ジョンウン)委員長が交わした「板門店宣言」に基づき同年9月に開設した。開城工業団地にある南北交流協力協議事務所の建物を約100億ウォン(約9億円)を投じて改修した。
南北双方が人員を派遣したが、19年2月にハノイで開かれた2回目の米朝首脳会談が決裂してからは事実上、機能不全に陥っていた。北朝鮮が新型コロナウイルスの「国家非常防疫体制」を敷いた今年1月に南北双方が人員を撤収した。
脱北者団体が5月31日に軍事境界線付近で金正恩体制を非難するビラを風船で飛ばすと、体制動揺を警戒する北朝鮮は猛反発。6月9日には韓国との通信回線を完全遮断した。
16日には朝鮮中央通信が朝鮮人民軍総参謀部による報復方針として、南北合意で非武装化された地域に軍隊を再進出させて前線を要塞化する措置を検討すると報じた。
3.日経平均が大幅反発 終値1051円高の2万2582円
16日の東京株式市場で日経平均株価は4営業日ぶりに大幅反発し、前日比1051円26銭(4.88%)高の2万2582円21銭で終えた。上げ幅は今年3番目で、3月25日(1454円)以来の大きさ。米連邦準備理事会(FRB)の金融政策を受けて前日の米株式相場が上昇したことや、米景気刺激策を巡る一部報道を支えに海外投資家が株価指数先物に買いを入れた。東証1部の値上がり銘柄数は2104と全体の97%に達し、2018年12月27日(2112銘柄)以来の多さだった。
米株式市場では新型コロナウイルス感染拡大の「第2波」を警戒した売りが先行したものの、FRBが個別企業の社債購入を開始すると発表したことで、ダウ工業株30種平均は上げに転じた。
米ブルームバーグ通信が日本時間16日昼ごろ、「トランプ米政権は景気てこ入れ策の一環として1兆ドル(約107兆円)に近いインフラ計画の提案を準備している」と報じた。米シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)で米株価指数先物が上げ幅を拡大し、今晩の米株式相場が上昇するとの期待が高まった。
日銀はきょうまで開いた金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の維持を決めた。市場予想通りの結果となったが、緩和姿勢の継続は買い安心感をもたらした。
東証1部の売買代金は概算で2兆7542億円。売買高は15億5476万株だった。
JPX日経インデックス400は6営業日ぶりに大幅反発した。終値は前日比565.98ポイント(4.10%)高の1万4367.07だった。東証株価指数(TOPIX)も6営業日ぶりの大幅反発となり、62.67ポイント(4.09%)高の1593.45で終えた。
4.ユーグレナ、一時11%高 抗体検査開発に期待(話題の株)
16日の東京株式市場でユーグレナ株が4営業日ぶりに大幅反発した。一時は前日比81円(11%)高の843円まで上昇した。前日の取引終了後にスタートアップ支援のリバネス(東京・新宿)と新型コロナウイルスの抗体検査に関する共同開発を始めると発表した。将来的な収益貢献への期待が高まり、個人投資家を中心とした買いが入った。
終値は75円(10%)高の837円だった。売買代金は3.7倍に膨らんだ。
共同開発は新型コロナの感染症の原因であるウイルスに対する抗体を検査対象者が持っているかどうかを判別することを目的とする。ボランティアによるサンプルを用いた試験では、陽性者を判別する抗体検査ができることを確認したといい、今後、精度を高めていく。
ユーグレナの業績は低迷が続く。5月に発表した2019年10月〜20年3月期の連結決算では、最終損益が1億4300万円の赤字(前年同期は64億円の赤字)だった。広告費の抑制を背景に主力の食品・化粧品販売が苦戦した。新型コロナの感染拡大で事業環境には不透明感が漂っており、20年9月期通期の業績予想は未定とした。
ユーグレナは今年、ミドリムシから搾った油を活用した航空機向けのバイオ燃料の国際規格を世界で初めて取得した。早期に実際の航空機での導入を目指している。次の成長事業としての期待は高いが、現状は先行投資がかさむ。市場では「本業は振るわず、株価の上昇は一時的なものにとどまる可能性が高い」(岡三証券の小川佳紀日本株式戦略グループ長)との声が聞かれた。
5.対アマゾンで新旧タッグ ウォルマートとショッピファイ
米ウォルマートとカナダの電子商取引(EC)サービス業者ショッピファイが15日に業務提携を発表した。小売業の巨人と「アマゾン・キラー」として注目される新興勢力のタッグは、米アマゾン・ドット・コムが独り勝ちを続けるネット通販市場を大きく変える可能性がある。
■手数料かからない手軽さ人気
ショッピファイは2004年創業の新興企業で、通販サイトの作成や配送・決済の支援を手掛ける。サービスは月額29ドル(約3100円)から3段階の定額制で、アマゾンなどと異なり販売手数料がかからない手軽さから中小企業の人気を集め、175カ国で100万社以上が利用する。
今回の提携により、ショッピファイの登録業者はウォルマートの通販サイト「ウォルマート・ドット・コム」に出品できるようになる。出品費用はかからず、売れた分だけウォルマートに手数料を支払う。
ショッピファイは月間1億2000万人が閲覧するウォルマートの通販サイトの集客力を利用できる。ウォルマートはショッピファイの多彩な通販業者を取り込んで品ぞろえを充実できる。ウォルマートは年内に1200社を自社サイトにつなぐ計画だ。
ウォルマートはここ数年、アマゾンに対抗するためネット通販の分野でM&A(合併・買収)を加速してきた。16年に米ジェット・ドット・コムを33億ドルで買収したのを皮切りに、若者向けアパレルやアウトドア用品の通販事業を相次ぎ買収。18年にはインドの最大手フリップカートを傘下に収めた。
■順調ではなかった買収戦略
買収戦略は順調だったわけではない。自社サービスや店舗との相乗効果が限られ、20年5月にはジェット・ドット・コムのサービスを廃止を決めた。ショッピファイとの業務提携にとどめるのはウォルマートにとって新たな取り組みで、投資リスクを負わずに品ぞろえを広げ、ノウハウの吸収を狙う。ショッピファイは19年12月期の売上高が約15億ドルとウォルマートの300分の1以下だが、時価総額は800億ドル超と3割近くまで膨らんでいる。
カナダ・ナショナルバンクのアナリスト、リチャード・ツェー氏は「ウォルマートの集客力は大きく、ショッピファイ側の利点も大きい」と指摘する。15日の米株式市場でショッピファイの株価は前日比8%上昇した。
新型コロナウイルスの影響で在宅消費の習慣が定着し、ネット通販市場はさらなる成長が期待される。両社の提携が通販サイトの場所貸しにとどまるなら効果は限定的だ。在庫管理や物流など通販の心臓部にも踏み込めば、アマゾン1強の構図を崩す強力な組み合わせになりそうだ。
6.英・EU首脳「移行期間延長なし留意」 交渉加速は合意
英国のジョンソン首相と欧州連合(EU)のフォンデアライエン欧州委員長らEU首脳は15日のテレビ会談で、英とEUの新たな自由貿易協定(FTA)など将来関係を巡る交渉を7月以降、加速させることで合意した。2020年末に終わる「移行期間」については、共同声明に「延長しないという英国の決定を留意する」と記した。
7.トランプ氏「駐独米軍を3割削減」 負担不足に不満
トランプ米大統領は15日、米軍のドイツ駐留規模を3割減らす計画を明らかにした。北大西洋条約機構(NATO)の軍事費の支出目標をあげて「ドイツが義務を履行していない」と理由を説明した。欧州諸国が反発し、米欧同盟の溝が一段と広がる公算が大きい。
トランプ氏がホワイトハウスで記者団に対し、NATO加盟国が軍事費を国内総生産(GDP)比の2%に増やす目標に関し、ドイツが達していないと指摘。「ドイツが支払うまで米兵を大幅に減らす」と表明した。国防総省によるとドイツには3月末時点で3万4674人が駐留しているが、これを2万5000人に減らす見通しだ。
トランプ氏は削減の実施時期は明らかにしなかった。部隊をドイツから米国本土に戻すのか、欧州内で再配置するのかにも言及していない。こうした詳細が示されずに駐留部隊の削減だけが先行するのは異例だ。17〜18日にはNATO国防相理事会が予定されており、米軍縮小が議論になる見通し。
駐独米軍をめぐっては複数の米メディアが6月上旬にトランプ氏が削減を指示したと報道。独政府や議会が強く反発した経緯があり、米独で綿密に計画を擦り合わせた形跡は乏しい。トランプ氏が率いる米与党・共和党内からもロシアにつけいる隙を与えるとして削減に反対する意見が相次ぎ、トランプ氏の意向に注目が集まっていた。
欧州米軍を巡ってはブッシュ(子)政権、オバマ政権もそれぞれ削減する方針を打ち出してきた。だがオバマ政権ではロシアが2014年にウクライナ領クリミア半島に侵攻したことを受け、欧州へ一時的に米軍を派遣するローテーションという形式で、対ロ抑止力の強化を図ってきた。
「米国第一」を掲げるトランプ氏は同盟国からも米軍の撤収・縮小を進める考えを示してきたが、計画が具体化するのは今回が初めてとみられる。韓国は在韓米軍の駐留経費をめぐる交渉が長期化し、日本も在日米軍の負担についての交渉がこれから本格化する。負担不足を理由にした独駐留の縮小は日韓との交渉に向けても強い圧力になりそうだ。
8.FRB、6千億ドルの企業融資始動 未経験の損失リスク
米連邦準備理事会(FRB)は15日、中小・中堅企業向けの「メインストリート融資制度(MSLP)」を開始した。新型コロナウイルス対策としての緊急資金支援はこれですべて始動。総額4兆ドル(約430兆円)超と、中央銀行として経験のない損失リスクも抱えることになる。
MSLPの実務を担うボストン連銀が15日、融資の受け付けを始めたと発表した。対象は従業員1万5000人以下の中堅・中小企業で、資本市場で資金を直接調達できない多くの米企業が、FRBの支援を受けられるようになる。資金枠は最大6000億ドルで、4兆ドル弱ある米企業(非金融)のローン残高の15%近くに相当する規模だ。
直接的な融資は民間銀行が担うが、その95%はFRBが設立するSPV(特別目的事業体)が買い取る。形式的には間接融資だが、損失リスクの大部分はFRBが抱えることになる。融資期間は5年間で、当初の2年間は元金の返済すら不要だ。新型コロナで売り上げが減少した企業は当面の運転資金を確保できる。
FRBは通常、融資などの取引を民間銀行に限っている。ただ、根拠法である連邦準備法では「異常かつ緊急時」に限って、FRBが企業や個人にも資金を出すことが認められている。今回の事業会社への融資は、2008年の金融危機時にも踏み込まなかった極めて異例の措置となる。
前例のない施策のため、3月に構想を発表してから始動するまで3カ月かかった。その間、対象企業は従業員1万人以下から1万5000人以下へと拡大。百貨店など規模が比較的大きい企業が相次いで経営破綻し、水面下でFRBへの支援要請が相次いだためだ。
3月以降に公表した緊急資金支援は、これでほぼすべてが始動した。大企業向けには社債やコマーシャルペーパー(CP)の購入を開始。FRBの支援で社債利回りが低下し、米企業の3月の社債発行額は2370億ドルと過去最高になった。
連邦政府が中小企業(従業員500人以下)の給与支払いを肩代わりする「給与保護プログラム(PPP)」も、FRBが側面支援している。地方債を購入する支援策も発動した。失業給付などで州・地方政府の財政が悪化しているためだ。
FRBの緊急支援の総額は4.2兆ドルとなる。量的緩和で米国債なども月1200億ドル買い入れており、FRBのバランスシート(6月10日時点で7.2兆ドル)は20年末には10兆ドルを超えそうだ。コロナ危機前の資産規模は4.5兆ドルが最大で、その2倍を超す「極めて巨大な中央銀行」となる。
懸念は損失リスクだ。FRBの緊急支援策には、米財務省も損失バッファとして一定の額を拠出する。例えば6000億ドルのMSLPには、米財務省が750億ドルを出資。同額まで損失が出てもFRBのバランスシートは傷まない仕組みだ。4.2兆ドルある緊急支援全体でみても、米財務省が計2000億ドル強を拠出し、中銀と通貨の信認を守る一定の工夫がある。
もっとも、その損失リスクは今後の経済動向で大きく変わる。新型コロナの感染第2波などで景気がさらに悪化すれば、企業融資の焦げ付きは米財務省の損失負担を超えかねない。パウエル議長は一連の緊急支援を、危機回避へ必要な措置としつつも「レッドラインを超えた」とも認める。
「小さな政府」を志向する米国は、日本のような政策金融機関を持たない。FRBの企業支援はその空白を埋める措置だ。ただ、事業会社への資金支援は商業銀行が担う「産業金融」そのもので、世界の中銀のモデルケースとはなりにくい。
9.米、ファーウェイと議論容認 5Gの基準作りで
米商務省は15日、中国の通信機器最大手、華為技術(ファーウェイ)が参加する次世代通信規格「5G」などの国際基準づくりの議論に、米企業が参加するのを認めると発表した。事実上の禁輸措置は続けるが、基準作りの目的に限って一定の技術開示を認める。
新規則は国際機関で5Gや人工知能(AI)など最先端技術の規格を決める過程に限り、商務省の許可なしでもファーウェイに一部技術を開示するのを認める。それ以外の輸出は引き続き商務省の許可が必要で、企業の申請は原則却下する。
商務省は2019年5月、事実上の禁輸対象企業を並べた「エンティティー・リスト」にファーウェイを加えた。5Gなどの国際基準作りにファーウェイが参加することが多く、米企業が出席できなければ国際基準作りで取り残されるとの懸念が産業界や議会で広がっていた。
ロス商務長官は声明で「米国は世界のイノベーション(革新)の主導権を渡さない」とあくまで米企業を支援する取り組みだと強調した。ファーウェイに対する厳しい姿勢は変えていない。
【経済ニュース 6/15 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
株式相場は続落ですね
明日は自律反発狙いたい所ですね
1.接触検知アプリ、週内にも投入 マイクロソフトなど開発
2.東京、新たに48人感染 2日連続で40人超
3.北京、第2波回避へ厳戒 卸売市場で集団感染
4.英BP、減損最大1.9兆円 原油価格の停滞を想定
5.NYダウ反落、一時700ドル安 コロナ「第2波」警戒
6.ユニクロ、「エアリズムマスク」19日から販売
7.トランプ氏、健康不安説再燃も
8.日経平均終値、774円安の2万1530円 感染「第2波」警戒
9.独政府、ワクチン新興に360億円出資 海外からの買収防止
10.中国、雇用回復鈍く 小売り・飲食不振
11.米国で警察対応に批判高まる アトランタで黒人男性射殺
1.接触検知アプリ、週内にも投入 マイクロソフトなど開発
新型コロナウイルス感染者との濃厚接触を検知するスマホ向けアプリが週内にも日本で投入される。マイクロソフトなどに作成を依頼した。だが政府の開発方針の迷走で予定が1カ月以上遅れ、運用面の課題も多い。普及率を6割以上に高め、アプリからの通知を自宅待機などにつなげる仕組みも整えなければ、感染の第2波を防ぐのが難しくなる。
2.東京、新たに48人感染 2日連続で40人超
東京都は15日、新型コロナウイルスの感染者が新たに48人確認されたと発表した。2日連続で40人を上回った。都内の感染者は計5592人になった。
都内では6月から新規感染が1日あたり20人を超える日が目立ち、14日には「夜の繁華街」に関連した32人を含む47人の感染が確認された。
15日に確認された48人のうち、23人は接客飲食業の従業員など夜の繁華街での感染とみられる。うち20人は同じ店舗で働く20〜30代のホストクラブの従業員。新宿区が感染者を確認した店舗の関係者全員を検査して判明した。
友人などとの会食で感染したと疑われる人も13人に上った。都福祉保健局の担当者は「外出して友人と会ってお酒を飲むなど『密』になりがちな時に感染したと思われる」と分析。その上で「人の動きが出れば陽性者が増えるのは織り込み済みだが、店に行っても感染防止策をとって気を付けてほしい」と訴えた。
3.北京、第2波回避へ厳戒 卸売市場で集団感染
食品卸売市場を巡る新型コロナウイルスの集団感染が判明した中国・北京市で、当局が再び厳戒態勢を敷いた。首都・北京で感染「第2波」が生じれば、習近平(シー・ジンピン)指導部の足元を揺るがしかねない。14日に7.6万人超をPCR検査するなど感染者の把握と隔離を急いでいる。
4.英BP、減損最大1.9兆円 原油価格の停滞を想定
英石油大手BPは15日、2020年4〜6月期に最大175億ドル(約1兆9千億円)の減損損失を計上する見通しだと発表した。新型コロナウイルスのまん延を受け、原油価格の長期見通しを引き下げる。低炭素エネルギーへの移行も進むとみて、資産価値を抜本的に洗い直す。他の石油メジャーでも、化石燃料の需要の長期停滞に備える構造改革が広がりそうだ。
BPは新型コロナをきっかけに「エネルギー需要は継続して弱まる」との見通しを示した。世界経済に長期で影響を与え「低炭素の経済やエネルギーシステムへの移行が加速する」とも指摘した。石油関連を中心に、既存の設備や無形資産の収益力を保守的に見直す。
原油価格は国際指標である北海ブレント原油で、21〜50年の平均が1バレル55ドルとの前提を新たに置く。従来は40年ごろまでに平均70ドルとのシナリオを掲げていたが、期間を延ばしたうえで2割強下方修正する。天然ガス価格の想定も3割程度下げる。この結果、4〜6月期に計130億〜175億ドルの資産の評価減が生じるという。
巨額減損には、石油依存から脱却する構造改革を一気に進める狙いもある。バーナード・ルーニー最高経営責任者(CEO)は2月の就任直後に、自社の事業活動で出る温暖化ガスを「50年までに実質ゼロ」にする目標を掲げた。同氏はこの日の声明で、新型コロナで目標を再確認したとして「エネルギー転換を通じて競争力を高められる」と強調した。
8日には、全従業員の15%近くにあたる約1万人を世界で削減する方針を明らかにしていた。設備投資やコスト全般の圧縮も進めている。20年12月期の最終赤字幅は、米メキシコ湾の原油流出事故に伴う引当金や原油安に見舞われた15年12月期(64億ドル)を大幅に上回るのは確実だ。
コロナ危機は他の欧米石油メジャーにも影響を及ぼしている。米エクソンモービルは石油生産設備などで29億ドルの減損損失を計上し、1〜3月期は6億1000万ドルの最終赤字に陥った。20年の設備投資を230億ドルと当初計画から約100億ドル削減する。米シェブロンも米天然ガス資産の評価減などで106億ドルの減損処理を迫られた。
5.NYダウ反落、一時700ドル安 コロナ「第2波」警戒
15日の米国株式市場でダウ工業株30種平均は反落し、前週末比の下げ幅は一時700ドルを上回った。米国では一部州で新型コロナウイルスの新規感染者数や入院者数の増加が顕著になってきた。感染の「第2波」を警戒する動きが強まっている。
ダウ平均は米東部時間午前9時45分時点で、前週末比560ドル安の2万5040ドル近辺で推移している。
米国が経済再開に動くなか、感染の「第2波」が広がりつつある。カリフォルニア州やフロリダ州、アラバマ州などで新規感染者数の増加が顕著となるほか、ノースカロライナ州やテキサス州では入院者数が過去最高を更新。米バンダービルト大学医学部のウィリアム・シャフナー教授は15日、米CNBCのインタビューで「第2波は始まった」と警戒感を示した。
個別銘柄では、経済再開の恩恵を受ける企業が売られた。空運大手のユナイテッド航空やアメリカン航空、クルーズ船大手のカーニバルやロイヤル・カリビアンなどが大幅下落した。
6.ユニクロ、「エアリズムマスク」19日から販売
ファーストリテイリング傘下のユニクロは15日、速乾性や通気性に優れる機能性肌着「エアリズム」の素材でつくったマスクを19日から発売すると発表した。エアリズムに細菌や花粉などの粒子をブロックするフィルターと、紫外線をカットするメッシュを合わせた3層構造とし、性能と肌ざわりを両立させた。新型コロナウイルスの感染拡大により、年間を通してマスクを着用する新しい生活スタイルに対応する。
商品名は「エアリズムマスク」。19日から国内のユニクロ店舗と電子商取引(EC)サイトで発売する。3枚組で税別990円。色は白のみで3サイズを展開する。
生産地は中国で当面は毎週50万パックの生産を計画している。海外のユニクロ店舗でも順次発売する予定だ。
自宅の洗濯機で洗って、繰り返し使うことができる。肌に触れるマスクの内側にエアリズムを使い、外側は紫外線を90%カットするメッシュ素材にする。ユニクロの試験では、中間部のフィルターがバクテリアの飛沫や花粉の粒子を99%取り除く効果があったとするが、新型コロナを含めたウイルスの侵入を完全に防ぐものではないという。
7.トランプ氏、健康不安説再燃も
トランプ米大統領の健康不安を指摘する声が出ている。13日に陸軍士官学校での演説後に階段を降りる際におぼつかない足取りを見せたからだ。トランプ氏は「スロープがとても長いうえ手すりもなく、とても滑りやすかった」と説明し、健康不安説を否定している。
トランプ氏を巡っては2019年11月に予告せずに健康診断を受けるなど健康不安説がたびたび出ている。14日には74歳の誕生日を迎えた。一方でバイデン前副大統領(77)にも健康を不安視する見方が目立ち、11月の大統領選では両氏の健康に関しても注目が集まりそうだ。
8.日経平均終値、774円安の2万1530円 感染「第2波」警戒
15日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落し、前週末比774円53銭(3.47%)安の2万1530円95銭ときょうの安値付近で引けた。5月29日以来、約2週間ぶりに2万2000円を下回った。米国に加え、他国に先駆けて拡大が収束したとみられていた中国で新型コロナウイルスの新規感染者数が増加したのを受け、「第2波」リスクが改めて意識された。中長期の投資家は買いを手控えるなか、短期筋による先物主導の売りに押された。
日本時間15日午後の米ダウ先物が下げ幅を広げるなか、日経平均は心理的節目の2万2000円を割り込むと個人投資家やヘッジファンドなどの短期筋の見切り売りを伴って急速に下落し、200日移動平均(2万1755円、同日時点)を割り込んだ。日経平均の下げ幅は4月1日以来の大きさだった。
9.独政府、ワクチン新興に360億円出資 海外からの買収防止
ドイツ政府は15日、同国でワクチンを開発する未上場企業のキュアバク(CureVac)に対して、3億ユーロ(約360億円)を出資し株式の23%を取得すると発表した。同社は新型コロナウイルスのワクチン開発を進めており、今年3月には米国のトランプ政権が買収などを狙って接近していると報じられていた。
ドイツ政府がキュアバクに投資するのは、有力なワクチン開発企業をつなぎ留め、ワクチンの国内調達の可能性を広げるためだ。アルトマイヤー経済相は15日に「これらの重要な研究成果や技術はドイツと欧州に必要なもので、産業政策として大きな意味がある」と意義を強調した。
ドイツなどの各国は経済活動の再開を進めているが、ワクチンが開発されない限りは感染の第2波のリスクは免れない。ドイツ政府は月内に臨床試験を始めるキュアバクに必要な資金を供給して研究開発を後押しし、海外からの買収の脅威を退ける狙いがある。
出資は政府系のドイツ復興金融公庫(KfW)を通じて実施し、経営には介入しない方針だ。大手ソフトウエア会社、SAPの共同創業者でキュアバクのオーナーであるホップ氏も同日、出資を歓迎する意向を示した。
ドイツ政府はフランス、イタリア、オランダとの欧州連合で、英製薬大手のアストラゼネカから少なくとも3億回分のワクチンを調達する契約を結んだばかりだ。世界では100を超えるワクチンの開発計画が進んでおり、ドイツ政府は確実にワクチンが手に入るように幅広く検討を進めていく構えだ。
欧州連合(EU)もキュアバクに対してはすでに8千万ユーロの資金供給を表明している。ドイツ政府は今回の出資について、EUの競争当局から認可を得る必要はないとの考えを示した。
10.中国、雇用回復鈍く 小売り・飲食不振
中国の雇用回復が鈍い。2020年5月の都市部の新規雇用は前年同月より23%減り、減少幅が拡大した。生産、投資、消費の指標はいずれも改善したが、雇用に結びついていない。新型コロナウイルスの「第2波」への警戒も高まり、先行きの不透明感が強まってきた。
新規雇用は106万人にとどまり、4月より19万人減った。2月の39万人を底に増えてきたが回復が止まった。前年同月比の減少幅も4月は7%まで縮まったが拡大に転じた。5月の失業率も5.9%と4月から0.1ポイントしか改善しなかった。
李克強(リー・クォーチャン)首相は5月の政府活動報告で成長率目標を示さなかった一方、「雇用」に過去最多の39回も言及した。国務院(政府)の劉桓参事は11日に「しばらく成長率には注目せず、雇用対策に注目してほしい」と語った。
最重要のはずの雇用の回復が鈍いのは、中国経済の構造変化に政策が追いついていないためだ。
製造業や建設業の大手国有企業を政府が補助金や融資、発注で強く支援し、下請けや孫請けに恩恵を波及させるのが伝統的な中国の景気対策だ。官僚の評価のものさしである国内総生産(GDP)と税収を増やすには一番手っ取り早いからだ。
経済センサス調査によると、18年末の製造業の就業者は1億2100万人と5年で1300万人減った。逆に卸小売りや飲食の就業者は18年末に1億3400万人と5年で4200万人も増えて製造業を逆転した。急速に経済のサービス化が進んでおり、新規雇用も中小零細企業や個人事業主が生むが、従来型の景気対策は届きにくい。
11.米国で警察対応に批判高まる アトランタで黒人男性射殺
米南部ジョージア州アトランタで飲酒運転を摘発しようとした白人警官が抵抗した黒人男性を射殺する事件が起き、その余波が広がっている。事件翌日の13日には同市内で警察の行き過ぎた対応に抗議する批判が高まった。現場近くのハンバーガー店は放火されて炎上した。
ジョージア州の捜査当局などによると、事件は12日夜にアトランタ市のハンバーガーチェーン「ウェンディーズ」の駐車場で起きた。
ドライブスルーの通路に駐車し眠っている男性がいるとの通報を受け、駆けつけた警官が呼気検査を実施したところ、基準値を超えるアルコールを検出した。男性が拘束に抵抗して逃走したため、警官が銃を発砲。男性は病院に運ばれ、死亡が確認された。米メディアによると、男性は逃走の際に警官からスタンガンを奪ったという。
事件を受け、アトランタ市内では翌13日、警官の対応に抗議するデモが起きた。夜には事件現場周辺にも大勢の人だかりができ、催涙ガスなどを使ってデモ隊を解散させようとする警官隊と一時もみ合いになった。デモ参加者の一部がウェンディーズの入る建物に火を放ったとみられ、建物が激しく燃えるようすが報じられた。ロイター通信によると、地元警察は放火した疑いのある白人女性を追跡している。
アトランタ市のボトムズ市長は13日、男性への発砲について正当な武器使用ではなかったと市警の対応を非難し、シールズ本部長の引責辞任を発表した。同市警は事件に関与した2人の白人警官のうち、発砲した警官を解雇したことも明らかにした。
5月下旬には米中西部ミネソタ州で起きた白人警官による黒人男性暴行死事件の動画がSNS(交流サイト)を通じて拡散し、全米を揺るがせたばかり。全米規模の抗議デモが続く中で発生した新たな黒人殺害事件によって、警察への不信感は各地で強まっている。今後、警察による武器使用を制限しようとする議論に拍車がかかる可能性がある。
2020年06月12日
【経済ニュース 6/12 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です。
昨晩はコロナ第ニ波の懸念からダウは1400ドル近く下げ
史上4番目の下げ幅を記録しました
ただFOMC金融緩和措置の継続や一度コロナ相場を経験してる事も踏まえ
前回のような大きな下落はあまり考えにくくまだまだリスクオン継続で
インチキ上げ相場の押し目にすぎないのかな?とも思いますw
では見出しです。
1.NYダウ反発、上げ幅800ドル超 前日の急落の反動で
2.2次補正予算が成立 20年度の歳出、160兆円超に
3.EU、7月から段階的に渡航解禁 観光業回復狙う
4.英EU、15日に首脳会談へ FTAなど交渉の打開探る
5.米、イラク駐留軍の削減を継続へ 戦略対話で確認
1.NYダウ反発、上げ幅800ドル超 前日の急落の反動で
12日の米株式市場でダウ工業株30種平均は4日ぶりに反発して始まった。上げ幅は一時、800ドルを超える場面もあった。前日に1861ドル(6.9%)下落した後とあって、自律反発狙いの買いが先行している。ドイツやフランスなど欧州の主要株式相場が上昇していることも米国株の買いにつながっている。
投資家心理を測る指標とされ「恐怖指数」と呼ばれる米株の変動性指数(VIX)は大幅に低下している。前日は5割近く上昇し40台に急上昇した。20を超えると不安心理が高まった状態とされる。
一方、新型コロナウイルスの感染「第2波」で経済活動の早期正常化が順調に進まないとの警戒は根強い。ロイター通信によるとテキサスやアリゾナを含む6つの州で感染者の増加が顕著だという。
金融のゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェース、クレジットカードのアメリカン・エキスプレス(アメックス)などの上昇が目立っている。エクソンモービルやシェブロンといった石油株も買われている。航空機のボーイングも高い。
2.2次補正予算が成立 20年度の歳出、160兆円超に
新型コロナウイルス対策を盛る2020年度第2次補正予算が12日、参院本会議で自民、公明両党や立憲民主党など野党共同会派などの賛成多数で可決、成立した。当初予算、第1次補正予算と合わせた20年度の歳出は160兆円を超える。成立後は迅速な予算執行が課題になる。
安倍晋三首相は同日、首相官邸で記者団に、2次補正に盛り込んだ家賃補助などに触れ「一日も早く届け、事業継続と雇用・生活を守り抜く」と述べた。中小企業対策の持続化給付金について「無駄遣いがあってはならない。厳正に執行するのは当然だ」とも語った。
2次補正の一般会計からの歳出は31兆9114億円で補正で過去最大だ。財源は全額を国債の追加発行で賄う。当初予算の歳出は102兆6580億円、1次補正は25兆6914億円だった。
緊急事態宣言による外出自粛で影響を受けた企業への支援に重点を置いた。雇用調整助成金の日額上限1万5千円への引き上げや最大600万円のテナントの家賃支援が柱となる。
従業員が企業を介さずに申請・受給できる給付金制度も設ける。自治体が新型コロナ対策に活用できる地方創生臨時交付金は2兆円増額する。
感染拡大の備えとして使い道を事前に定めない予備費を10兆円積み増した。立民など野党からの批判を受け、5兆円については大まかな使途を説明した。(1)雇用維持や生活支援に約1兆円(2)中小企業の事業継続に約2兆円(3)医療体制強化に約2兆円――を充てる。
新型コロナ対策は遅れが指摘されている。厚生労働省によると、雇調金の11日時点の申請件数は15万5553件に対して支給決定件数は8万7195件にとどまる。
予算審議では大幅に減収となった中小企業に最大200万円を支給する「持続化給付金」の委託費や資金の流れが論点になっており、野党は説明責任を求めていた。
3.EU、7月から段階的に渡航解禁 観光業回復狙う
欧州連合(EU)の欧州委員会は新型コロナウイルスの感染拡大で原則禁止している欧州30カ国への渡航を、7月1日から段階的に解除するよう加盟国に提案した。年間7億人が訪れる欧州にとって観光は重要産業だ。世界の主要国で先んじて規制を解除することで、低迷する経済の再生につなげたい考えだ。
「国際的な旅行(の解禁)は観光とビジネスにとってカギだ」。EUのヨハンソン欧州委員(内務担当)は11日の会見で力説した。渡航制限は3月半ばに始まり、欧州経済に大きな傷痕を残した。経済活動の早期の活性化への思いがにじむ。
EUはまず6月中に域内の移動を全面的に再開する。これまで国境検問などが設けられていたが、今後は原則、自由に往来できる。EUや域内の移動の自由を保障した「シェンゲン協定」に加盟する30カ国が対象だ。7月からは域外からの渡航者を段階的に受け入れる構えだ。まずはバルカン諸国からはじめ、感染状況が安定している国を対象に徐々に解禁する。
制限の解除を急ぐのは域内の感染が落ち着いたことに加え、経済への影響を最小限に抑える狙いがある。夏は観光産業にとってかき入れ時だ。EUにとって観光関連産業が生み出す域内総生産(GDP)は全体の10%弱。クロアチアでは25%、スペインは15%弱だ。
国連機関によると、EUへの旅行者は2018年に7億人超に達したが、20年の国際旅行者数は6〜8割落ち込む可能性がある。多くの企業が破綻しかねないと、南欧を中心に早期の解除を求める声が強まっていた。
ただ欧州委の提案に拘束力はなく、出入国管理は加盟国の権限だ。観光業が主力のギリシャは15日、日本や中国など約30カ国からの観光客の受け入れを再開する方針だ。一方、感染者の多いロシアと国境を接するフィンランドは渡航禁止措置を7月半ばまで延長するよう主張したもようだ。ヨハンソン氏は制限の緩和に慎重な国もあることを認めつつ、7月1日の緩和を「多くの国が支持している」と説明した。
シェンゲン協定の加盟国内にいったん入ると、原則、パスポートの審査なしで行き来できる。解除のタイミングにばらつきが出ると、加盟国が一体で出入国を管理する意味が薄れてしまう。「共通で協調された対応が必要」。欧州委は加盟国に呼び掛けている。
EU各国は今後、どの国からの入国を認めるのかを協議する。感染の水準がEUと同程度に抑えられていることや、感染抑制策の実施の有無、EUからの渡航を受け入れるか、といった条件を考慮する。スペインは既に独自に、7月に日本からの観光客の受け入れを再開すると表明済みだ。EU全体としても、日本からの渡航が早期に認められるのか注目される。
4.英EU、15日に首脳会談へ FTAなど交渉の打開探る
欧州連合(EU)と英政府は11日、新たな自由貿易協定(FTA)など英・EUの将来関係を巡って、15日に首脳会談を開くと発表した。EUのフォンデアライエン欧州委員長とミシェル大統領らがジョンソン英首相とテレビ会議で直接会談し、膠着する交渉の打開策を協議する。
英国の1月末のEU離脱以来、両者間で3月から交渉官レベルで4回の協議を重ねた。だが「英が税制などのEUルールを順守するか」や「英海域でのEU加盟国の漁業権を認めるか」などの点で紛糾し進展していない。
英国は現在、EU離脱の激変緩和のため2020年末までの移行期間中で、関税ゼロでの貿易などEU加盟国とほぼ同じ扱いを受けている。交渉が決裂してFTAなしの結論となれば、21年初から関税などが発生して企業活動への打撃は避けられない。双方は首脳会談で打開策を探り、経済への影響を回避したい考えだ。
英・EUで結んだ離脱協定は6月末までに両者の同意があれば、移行期間を2年延長することを認めている。EU側は経済への打撃回避のため、延長も選択肢に入れる。英はEU域外とのFTAが発効できないなどデメリットが多いことから、移行期間の延長を強く拒否している。
5.4月の英GDP20%減、新型コロナで最大の悪化
英国の政府統計局が12日発表した4月の英国内総生産(GDP)は、物価変動を除く季節調整済みの実質で前月比20.4%減だった。新型コロナウイルス対策として3月下旬に始まった外出制限で経済活動が全土で停止したため、統計を遡れる1997年以降で最大の落ち込みを記録した。
英国は月次でGDPを公表している。減少率は3月の5.8%から急拡大し、市場予想の「18%程度」を上回る悪化だった。新型コロナの感染拡大が深刻化する以前の2月と比べると25.1%縮み、2002年7月以来17年9カ月ぶりの水準に落ち込んだ。2〜4月期でみると、前の3カ月と比べ10.4%減だった。
4月のGDPの内訳をみると、全体の8割を占めるサービス業が前月比19.0%減だった。製造業は24.3%、建設は40.1%それぞれ落ち込んだ。主な項目別で最も悪化したのは「宿泊・サービス業」で、88.1%の減少を記録した。
英国は3月23日にロックダウン(都市封鎖)に踏み切り、生活必需品を売るスーパーや薬局などを除くほとんどの商業施設が営業を休止した。4月の自動車生産台数は前年同月比99.7%減の197台にとどまるなど、外出制限で製造業にも甚大な影響が出た。
ジョンソン英政権は外出や行動制限の段階的な緩和を始めた。6月15日に小売業の営業許可を百貨店などに広げ、7月からは飲食店の再開も目指している。5月の企業の景況感指標は4月比で改善した。だが、制限緩和はドイツやフランスなど他の欧州主要国と比べて出遅れている。感染「第2波」への懸念もくすぶるなか、景気回復の道のりは不透明だ。
5.米、イラク駐留軍の削減を継続へ 戦略対話で確認
米国務省が共同声明を発表し、「米国はイラクでの恒久的な基地使用や駐留を求めない」と強調した。イラク議会は1月、駐留米軍の撤退を求めていた。米側は撤退を否定したものの、米メディアによると、その後、一部の部隊はイラクを離れていた。トランプ政権には海外駐留経費を削減したいとの考えがある。
過激派組織「イスラム国」(IS)掃討を目的とした米軍のイラク駐留は約5千人規模とされ、隣国イランににらみをきかせる狙いもある。1月には米軍がイラク国内でイラン革命防衛隊のソレイマニ司令官を殺害したことがきっかけで、イラクを主な舞台に、米とイランの関係が一触即発の危機に陥った。
戦略対話では、米企業がエネルギー分野でイラクに投資するなど、ビジネス分野での協力の可能性も議論した。トランプ政権は中東でイランの影響力拡大を抑えるため、イラクとの協力強化に意欲を示している。
2020年06月11日
【経済ニュース 6/11 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です

さて昨日FOMCで政策金利は据え置き
そしてYCCは実施されませんでしたね
2022年年まではゼロ金利政策の継続の発表もあり
ドル円は108円を割れています。
日経平均も調整局面に入り大きく下落しました。
明日のSQの関係もあると思います。
ただ低金利継続が明確化したので今後の株式市場も
下がったら買いという目線は変えていません。
では見出しです。
1.東京都、19日に休業要請を全面解除へ
2.FRB、中長期金利抑制策を検討 経済復元は23年以降
3.都内で新たに22人感染 新型コロナ
4.東証大引け 大幅反落、2カ月半ぶり下げ幅 高値警戒感根強く
5.中国が豪に圧力、留学禁止など 新型コロナ調査けん制
1.東京都、19日に休業要請を全面解除へ
東京都は11日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業要請について、19日に全面的に解除する方向で最終調整に入った。感染リスクが高いとされるライブハウスや接待を伴う飲食店も、感染防止策をとった上で再開を認める。感染状況は落ち着きつつあると判断し経済再開をさらに進める。
現在は午後10時までの時短営業を求めている飲食店も、19日からは営業時間の制限を撤廃する。イベントは規模に応じて会場への入場者数制限などを残す。
政府は19日に都道府県をまたぐ移動や、接待を伴う飲食店に対する自粛要請を全国的に解除する予定で、都も国と足並みをそろえる。
都は感染再拡大の恐れがあるとして2日に発動した独自の警戒情報「東京アラート」を、11日に解除する。あわせて12日午前0時から、休業要請の段階的な緩和措置を、現状の「ステップ2」から「ステップ3」へ移行する。ステップ3ではカラオケ店や遊園地、ゲームセンターなど遊興・遊戯施設への休業要請が解かれる。
足元の新規感染者数に大きく増える傾向がみられないことから、19日からはさらに解除の対象範囲を広げる。
都内では夜の街での感染が問題になっている。都は休業要請の解除後も、引き続き感染拡大防止策を求めていく方針だ。
2.FRB、中長期金利抑制策を検討 経済復元は23年以降
米連邦準備理事会(FRB)は10日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、少なくとも2022年末までゼロ金利政策を維持する方針を表明した。雇用回復に時間がかかり、米経済の再生も23年以降にずれ込むと警戒する。米国債の大増発で長期金利に上昇懸念も浮上しており、新たな金利目標など3つの追加策を検討する。
「2000万人以上の雇用が失われ、回復の道のりは長い。22年まで利上げはない」。パウエル議長は10日の記者会見で、ゼロ金利の長期据え置きを表明した。同日のFOMCでは参加者17人が3年間分の政策方針をそれぞれ提示し、15人が「22年末までゼロ金利を維持する」とした。
5月の米失業率は13.3%と前月(14.7%)から改善した。パウエル議長も「労働市場は底入れした可能性がある」と話したが、FOMCは20年10〜12月期の失業率が9.3%と高止まりすると予測した。22年末でも5.5%と、コロナ危機前の3〜4%台に戻るのは23年以降とみる。
米経済は4〜6月期の成長率が年率換算で40%ものマイナスになると予測され「これまでで最も過酷な落ち込みとなる」(パウエル氏)。7月以降は持ち直しに転じるとみるが、感染第2波などのリスクも拭えず、先行きは「不透明感が極めて強い」と指摘した。
「政策金利が下限に達した現在、金融政策をどう運営するか。今回の会合でも(ゼロ金利を長期間続けると約束する)フォワードガイダンスと資産購入という手段を議論した」。パウエル議長は冒頭発言で、追加策に言及してみせた。
「フォワードガイダンス」は08年の金融危機後に採用したことがあり、11年には声明文にゼロ金利を2年続けると明示した。今回も22年末までのゼロ金利維持を表明したが、あくまで「政策見通し」で公式な約束ではない。FOMC内には「完全雇用と物価目標を1年間続けて達成できればゼロ金利を解除する」と明記する案がある。
量的緩和の拡大も検討する。10日のFOMCではこれまで「必要量」としていた米国債の購入規模を月800億ドル(約8兆5千億円)、住宅ローン担保証券(MBS)は同400億ドルと新たな目安を示した。足元の米国債の購入量は1日40億ドルで、ペースそのものは変わらない。目標を明示したのは、先行きの緩和拡大に備え「発射台」の数値をつくるためだ。
「先行きの新たな景気動向をにらみ、イールドカーブ・コントロール(YCC)は次回以降も議論する」。パウエル議長は微妙な言い回しで、日銀のように長期金利に誘導目標をつくるYCCの採用も示唆した。FRBが警戒する「新たな動き」とは、米国債の大増発による利回り上昇だ。
米政権と議会はすでに3兆ドル弱の新型コロナ対策を発動。財政赤字は4兆ドル規模と前年の4倍に膨らむ可能性がある。国債増発で赤字を埋めるしかなく、市場には常に金利上昇圧力がかかる。米10年物国債利回りは5日、一時2カ月半ぶりの水準に上昇していた。
パウエル氏は「利回り曲線に沿って、金利目標を定める」ことを検討していると表明した。日銀は10年債利回りをゼロ近辺にする誘導目標を持つが、FRBは1年物の短期国債(TB)や5年物国債など、中短期の利回りにいくつか上限目標を置く案を検討する。
念頭に置くのはFRBが自ら1940年前後に取り組んだ「国債管理政策」だ。第2次世界大戦の戦費調達に協力するため、FRBは長期金利の上限を2.5%と定め、3カ月物と1年物にも誘導目標を設定。大量の国債を買い入れて中長期金利を抑え込んだ。
一方、今回のFOMCでマイナス金利政策の導入を検討する参加者はゼロだった。銀行など間接金融が中心の欧州や日本と異なり、MMF(マネー・マーケット・ファンド)の存在が大きい米国でマイナス金利を導入すれば市場に混乱が広がりかねないとの判断もあるとみられる。
「生活者が安全を確信しなければ経済は完全回復しない」。ナスダック総合株価指数が最高値を更新するなど株式市場には早期の景気回復に楽観論も広がるが、パウエル議長は米経済の復元には長期間かかるとの見通しを示した。
3.都内で新たに22人感染 新型コロナ
東京都は11日、新型コロナウイルスの感染者が新たに22人確認されたと発表した。1日あたりの新規感染が10人以上確認されるのは11日連続。都内の感染者は計5448人になった。
都は独自の警戒情報「東京アラート」を11日夜に解除する。解除直後の12日午前0時からは、休業要請の緩和対象を広げてカラオケ店などの営業再開も認める「ステップ3」に移行する。
都によると、11日に確認された22人のうち「夜の街」に関連した感染者はホストの男性6人だった。2日に東京アラートが発動した後、3日以降に感染が確認された165人のうち59人が夜の街での感染とみられる。新宿エリアが半数程度を占めるという。
4.東証大引け 大幅反落、2カ月半ぶり下げ幅 高値警戒感根強く
11日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に反落し、前日比652円04銭(2.82%)安の2万2472円91銭で終えた。下げ幅は4月1日(851円)以来2カ月半ぶりの大きさ。円高・ドル安に振れるなか、高値警戒感も手伝って景気敏感株を中心に利益確定売りが広がった。米ダウ先物が午後に下げ幅を広げると、国内市場にも売りが波及した。
米連邦準備理事会(FRB)は10日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で金融緩和を長期にわたり続ける方針を示した。米長期金利の低下が円高・ドル安を招いて輸出関連株を中心に売りが先行した。金融緩和の長期化方針が「かえって実体経済の回復の遅れを意識させた」との見方もあった。
米国で新型コロナウイルスの感染者数が200万人を突破したと伝わると、感染再拡大や経済活動再開の遅れが懸念され、米ダウ先物が午後に下げ幅を拡大。国内市場でも一段と景気敏感株などへの売りが強まった。
5.中国が豪に圧力、留学禁止など 新型コロナ調査けん制
中国が新型コロナウイルスの感染源などの独立調査を求めたオーストラリアに、次々と圧力をかけている。農畜産物の輸入を制限し、留学や渡航の禁止を自国民に勧告した。中国経済に依存する豪州を狙い撃ちし、独立調査に同調する国が広がらないようにする思惑がありそうだ。
2020年06月10日
【経済ニュース 6/10 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
いよいよ今晩FOMCです!!
EPS 純利益
PEPP パンデミック緊急購入プログラム
1.「夜の繁華街」入店時に連絡先確認 接待伴う店に指針
2.孫氏、ファンド「止血」急ぐ 10兆円運用は袋小路に
3.オンライン診療急拡大、1万5000施設に LINEも参入
4.都内で新たに18人感染 新型コロナ
5.20年の世界成長率、感染再拡大ならマイナス7.6%予測
6.コロナ感染、米14州で再拡大 デモ下で「第2波」現実味
7.東証大引け 小幅反発 下値では押し目買い 代金は2週ぶり低水準
8.2次補正予算案が衆院通過 政府・与党、12日成立めざす
9.航空業界、9兆円の赤字に 2020年IATA見通し
1「夜の繁華街」入店時に連絡先確認 接待伴う店に指針
.繁華街で接待を伴う夜間営業をする飲食店に向けて業界団体がつくった指針案が10日、分かった。新型コロナウイルスの感染が発生しても濃厚接触者を追跡できるよう、客にアンケートを実施して連絡先の届け出を求める。政府はこうした店への営業自粛要請を19日に解除するため、事前に指針を示して準備を促す。
キャバレー、ホストクラブ、スナックなどが対象になる。ナイトクラブにも別途、同様の指針を示す。
2.孫氏、ファンド「止血」急ぐ 10兆円運用は袋小路に
ソフトバンクグループ(SBG)が傘下の10兆円ファンドで初のリストラに踏み切る。新型コロナウイルスで運用成績が悪化し、人員の15%を削減して「止血」を急ぐ。ファンドの世界では投資先の価値急落を好機とみて投資を再開する動きもあるが、SBGの「ビジョン・ファンド」は資金余力が乏しく反転は難しい。有力なユニコーンなどを総取りする異形の投資戦略は袋小路に入り込んでいる。
3.オンライン診療急拡大、1万5000施設に LINEも参入
病院へ足を運ばなくてもスマートフォンで医師の診察を受けられる「オンライン診療」が急速に広がってきた。これまでは規制が厳しかったため消極的な医師が多かったが、新型コロナウイルスの感染拡大が状況を一変させた。規制緩和もあり、導入する医療機関が急増。LINEなど大手も参入し、医療機器やサービスとの連携も始まった。一方で「医療の質が低下しないか」と懸念する声もある。
4.都内で新たに18人感染 新型コロナ
東京都は10日、新型コロナウイルスの感染者が新たに18人確認されたと発表した。1日あたりの新規感染が10人以上確認されるのは10日連続。都内の感染者は計5426人になった。
10日に確認された18人のうち、夜の街に関連した感染者は7人だった。ホスト3人と、接客飲食業の客などを含む。直近1週間あたりの感染者数は131人で、夜の街での感染とみられているのは46人に上った。都によると、約半数が新宿エリアでの感染という。
都内では若い世代や夜の繁華街に関連した感染者が増えている。都は2日に独自の警戒情報「東京アラート」を初めて発動。都民らに夜の街への外出を控えるように呼びかけている。
5.20年の世界成長率、感染再拡大ならマイナス7.6%予測
経済協力開発機構(OECD)は10日、新型コロナウイルスの感染が年内に再び拡大した場合、2020年の世界の実質経済成長率がマイナス7.6%に落ち込むとの予測を公表した。感染がこのまま収束するシナリオでは20年にマイナス6.0%まで落ち込んだ後、21年にプラス5.2%に回復すると見込んだ。
予測は(1)今年の10〜12月期に感染が再び拡大する(2)このまま感染が収束に向かう――の2パターンを示した。OECDは「どちらのシナリオも同じぐらい起こる可能性がある」とみている。
日本の成長率は感染がこのまま落ち着いた場合で20年にマイナス6.0%となると予測。21年もプラス2.1%にとどまるとみている。OECDは「潜在成長率が低く、経済の回復力が主要国より弱い」との見方を示した。感染が再拡大すると20年にマイナス7.3%、21年もマイナス0.5%と、2年連続のマイナス成長に陥ると見込む。
20年の落ち込みはより厳しい感染拡大防止措置をとった米欧で一段と大きくなりそうだ。20年の成長率は感染が再拡大しない場合でも、米国はマイナス7.3%、欧州でマイナス9.1%を見込む。中国はマイナス2.6%と予測した。
OECDは失業率が各国で上昇すると懸念。「最も脆弱な人々が大きな影響を被る」と指摘し、各国に労働者が新たな仕事に移るためのサポートや、見込みのある企業の事業継続を支援するように求めた。
OECDは3月上旬時点の予測では、20年の実質経済成長率を世界全体でプラス2.4%、日本はプラス0.2%と見込んでいた。この時点では感染症は中国を中心としたアジアでの流行にとどまり、米国などには大きな影響を与えないとみていた。
6.コロナ感染、米14州で再拡大 デモ下で「第2波」現実味
米国で新型コロナウイルスの感染者数が再び拡大してきた。全50州で経済再開を進める時期に、白人警官による黒人暴行死への抗議デモが重なった。テキサス州では入院者数が過去最高になるなど、14州で感染者が再び上向いている。感染「第2波」の現実味が増しており、専門家や研究機関は警戒感を強めている。
7.東証大引け 小幅反発 下値では押し目買い 代金は2週ぶり低水準
10日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に反発し、前日比33円92銭(0.15%)高の2万3124円95銭で終えた。経済が早期に立ち直るとの期待感や、各国の金融・経済政策が株価を支えるとの見方は根強く、下げた局面では押し目買いが入った。割安株を売って成長株を買う投資家が増えたことも株価を支えた。
もっとも、日本時間11日未明に予定されている米連邦公開市場委員会(FOMC)の内容を見極めたいとの見方が強く、持ち高を一方向に傾ける市場参加者は限られた。
JPX日経インデックス400は続落。終値は前日比39.35ポイント(0.27%)安の1万4636.97だった。東証株価指数(TOPIX)も続落し、3.72ポイント(0.23%)安の1624.71で終えた。
東証1部の売買代金は概算で2兆2934億円と5月25日以来2週間ぶりの低水準にとどまった。売買高は12億5774万株だった。東証1部の値上がり銘柄数は943銘柄と全体の43%だった。値下がりは1142、変わらずは84銘柄だった。
8.2次補正予算案が衆院通過 政府・与党、12日成立めざす
新型コロナウイルス対策を盛り込んだ2020年度第2次補正予算案が10日午後、衆院本会議で自民、公明両党や立憲民主党など野党共同会派などの賛成多数で可決し衆院を通過した。参院での審議を経て、政府・与党は12日の参院本会議での成立をめざす。
一般会計からの追加歳出が31兆9114億円と補正予算で過去最大となる。必要な財源は全額を国債の追加発行で賄う。事業規模は117兆1千億円程度を見込む。
雇用調整助成金の日額上限の1万5千円への引き上げや最大600万円の家賃支援が柱となる。従業員が企業を介さずに申請・受給できる給付金制度も設ける。自治体が新型コロナ対策に使える臨時交付金は2兆円増額する。
政府は感染拡大の長期化に備え、使い道を事前に定めない予備費を10兆円積み増した。立民など野党は「国会審議を経る必要のない予備費としては巨額すぎる」などと批判した。
これを受け、麻生太郎財務相は衆参両院での財政演説で5兆円のおおまかな使途を説明した。(1)雇用維持や生活支援に約1兆円(2)中小企業の事業継続に約2兆円(3)医療体制強化に約2兆円――を充てる。
9日に実質的な審議が始まった衆院予算委では大幅に減収となった中小企業に最大200万円を配る「持続化給付金」の委託費や資金の流れが論点になった。
野党は参院で引き続き追及を続ける。旅行や外食などの割引券やクーポンを配る「Go Toキャンペーン」の委託費も高額だと指摘していく。
立民など野党共同会派と共産党は衆院本会議での採決に先立ち、衆院予算委員会に10兆円の予備費を1.5兆円に圧縮する組み替え動議を提出し、否決された。立民などは「予算案自体は国民生活に必要だ」との考えから2次補正予算案の委員会採決で賛成し、共産党は反対した。
9.航空業界、9兆円の赤字に 2020年IATA見通し
国際航空運送協会(IATA)は9日、新型コロナウイルスの影響で2020年の世界の航空会社の最終損益が843億ドル(約9兆800億円)の赤字になるとの見通しを発表した。売上高が19年の半分に落ち込むのに対し、費用の減少が追いつかないためだ。21年は改善するものの、158億ドルの赤字が残る見通しだ。
IATAは世界の航空便の8割以上を占める約290の航空会社が加盟している。20年の旅客需要は19年比半減の22億5千万人と06年並みの水準になるとみており、売上高は4190億ドルになる。
燃料費などのコストは減るが乗客1人あたりの費用は増え、全体では35%しか減らない。固定費に加え、航空券の払戻費用も重なり4〜6月期だけで610億ドルの資金が消失する。
危機を乗り切るため航空各社はこれまでに各国政府の支援で1230億ドルを手当てした。だが、このうちの半分以上は返済する必要がある。民間からの借り入れなどを合わせた負債額は20年末で5500億ドルを見込む。積み上がる負債が航空会社の経営を圧迫するおそれもある。
IATAのアレクサンドル・ド・ジュニアック事務総長は声明で「20年は航空史上で最悪の年だ。1日に2億3千万ドルずつ損失が膨らんでいる」と述べた。一方で「(新型コロナ感染の)第2の波が来ないという前提で、需要落ち込みの最悪期は脱した」と今後の回復に期待を示した。
2020年06月09日
【経済ニュース 6/9 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
さて明日FOMCを控えて市場はYCCの実施について注目です
長期金利の抑制を債券購入により行い低金利を維持し株価上昇維持
そしてドル安に動くのか
はたまた長期金利上昇によりドル高に動き株価の調整に働くのか
かなりの注目材料になりそうです。
では見出しです。
1.NYダウ反落で始まる、一時400ドル超安 利益確定売り優勢
2.東京都、新たに12人の感染確認 新型コロナ
3.マイナンバーのひも付け義務化、1口座に 総務相方針
4.富士フイルム、バイオ薬製造で1000億円投資 生産能力2倍に
5.LIXILグループ、ホームセンター売却後も残る経営課題
6.英コルトCEO「コロナで5G加速」 デジタルサミット閉幕
7.楽天が「1円スマホ」ばらまきも、狭まる大手の包囲網
8.香港国家安全法、詳細詰め 18日から全人代常務委
9.ホンダ、サイバー攻撃でシステム障害 北米は生産停止
10.東芝、オンライン授業を自動で字幕化 85%の正確さ
2.東京都、新たに12人の感染確認 新型コロナ
3.マイナンバーのひも付け義務化、1口座に 総務相方針
4.富士フイルム、バイオ薬製造で1000億円投資 生産能力2倍に
5.LIXILグループ、ホームセンター売却後も残る経営課題
6.英コルトCEO「コロナで5G加速」 デジタルサミット閉幕
7.楽天が「1円スマホ」ばらまきも、狭まる大手の包囲網
8.香港国家安全法、詳細詰め 18日から全人代常務委
9.ホンダ、サイバー攻撃でシステム障害 北米は生産停止
10.東芝、オンライン授業を自動で字幕化 85%の正確さ
11.東証大引け 7日ぶり反落、円高で利益確定売り 2万3000円台は維持
12.米国の人出、コロナ前迫る 経済再開と抗議デモで
13.日銀、社債オペで初の下限利回り設定
12.米国の人出、コロナ前迫る 経済再開と抗議デモで
13.日銀、社債オペで初の下限利回り設定
1.NYダウ反落で始まる、一時400ドル超安 利益確定売り優勢
9日のダウ工業株30種平均は7営業日ぶりに反落して始まった。午前9時35分現在は前日比323ドル70セント安の2万7248ドル74セントで推移している。下げ幅は一時400ドルを超えた。前日はナスダック総合株価指数が過去最高値を更新し、機関投資家が運用の指標にするS&P500種株価指数が年初来でプラスに転じた。相場上昇に一定の達成感が出ており、利益確定売りが優勢になった。欧州株相場が軒並み下げていることも売りを促した。
米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を10日に控え、買いに傾いた持ち高を調整する売りも出ているようだ。
旅客需要の回復期待から前日までに大きく上げたユナイテッド航空ホールディングスが15%安を付けるなど、空運やクルーズ船株が軒並み急落。航空機のボーイングも利益確定売りに押され、大幅安になっている。化学のダウのほか、石油のエクソンモービルの下げも目立つ。
一方、決算と同時に営業再開した店舗の業績が予想以上だと明らかにした百貨店のメーシーズは急伸。アナリストが目標株価を引き上げた交流サイト(SNS)のフェイスブックやネット通販のアマゾン・ドット・コムは買いが先行している。
2.東京都、新たに12人の感染確認 新型コロナ
東京都は9日、新型コロナウイルスの感染者が新たに12人確認されたと発表した。1日当たりの感染者が10人以上となるのは9日連続。都内の感染者は累計で5408人になった。
9日に確認された12人のうち、10〜30代が6人と半数を占めた。都内では若い世代や、夜の繁華街に関係した感染者が増えている。
福祉保健局の担当者は「孫から同居している祖母に感染したケースが複数含まれている。若い方が家庭内での感染を広めている例が増えると非常に心配だ」と話した。
都は6月2日に独自の警戒情報「東京アラート」を発動し、夜の繁華街などで感染に注意するよう呼び掛けている。
3.マイナンバーのひも付け義務化、1口座に 総務相方針
高市早苗総務相は9日の閣議後の記者会見で、マイナンバーと預貯金口座のひも付けについて、国民1人について1口座の登録義務化を目指す考えを明らかにした。災害時などの給付金の迅速な支給に向け、来年の通常国会に関連法改正案の提出を目指す。高市総務相は当初、個人が持つ全口座の登録を目指していたが「希望者のみとする」として方針を見直した。
現行制度ではマイナンバーを利用できる事務は社会保障、税、災害対策の3分野に限られている。このため緊急経済対策の柱の1つである家計向け10万円給付では、住民が郵送やオンラインで振込先の口座を届け出る手続きが発生した。自治体が口座番号などの確認作業に追われ、給付までに時間がかかっている。
口座登録の義務化は、新型コロナウイルス対策などの給付金のほか、福祉目的の支援策などへの活用を目指す。高市総務相は「行政から様々な給付を行うために利用する一生ものの口座情報を登録して頂ければ、迅速な給付や行政コストの削減に資する」と話した。
政府は当初、個人が所有する全ての口座と、マイナンバーとのひも付けの義務化を検討していた。相続時に親族の資産の所在を把握しやすくするなどの狙いがあったが、国や自治体に資産を把握されることを危惧する声も上がっていた。
マイナンバーと口座のひも付けを巡っては、自民、公明両党と日本維新の会が、個人の申し出に基づきマイナンバーと口座番号、氏名などをまとめて管理できる名簿を作成できるようにする法案を衆院に提出している。
4.富士フイルム、バイオ薬製造で1000億円投資 生産能力2倍に
富士フイルムホールディングスは約1000億円を投じ、デンマーク工場でバイオ医薬品の製造受託の生産能力を増強する。原薬をつくる培養タンクの容量を2倍に増やす。バイオ薬は高い治療効果が見込める一方、副作用も少ないとされ、需要が伸びている。開発が増加するバイオ薬は供給体制が普及の課題になっており、製造受託会社が投資を急いでいる。
5.LIXILグループ、ホームセンター売却後も残る経営課題
住宅設備大手LIXILグループは9日、ホームセンターを展開する上場子会社のLIXILビバを売却すると発表した。2019年6月にLIXILグループの最高経営責任者(CEO)に返り咲いた瀬戸欣哉氏はイタリア子会社に続き、国内でもLIXILブランドの事業を手放し経営改革を加速させる。新型コロナウイルスの感染拡大で主力と位置づける建材や水回り関連は需要停滞が見込まれる。
6.英コルトCEO「コロナで5G加速」 デジタルサミット閉幕
次世代通信規格「5G」などデジタル技術の革新について議論する「世界デジタルサミット2020」(日本経済新聞社主催)が9日、閉幕した。世界のIT(情報技術)大手の幹部からは、新型コロナウイルスの感染拡大がデジタル変革を促し、5Gがイノベーションのインフラになるとの声が相次いだ。
7.楽天が「1円スマホ」ばらまきも、狭まる大手の包囲網
楽天の携帯電話事業会社、楽天モバイルが往年の「0円ケータイ」をほうふつとさせるキャンペーンを5月27日に始めてから1週間ほど。申込数は非公表だが「好評で入荷待ちになっている」(同社)という。
このキャンペーンでは、楽天モバイルの自社回線サービス「Rakuten UN-LIMIT」を新規契約すると、税別1万7000円のスマートフォン「Rakuten Mini」をわずか1円で購入できる。現在は出荷まで1カ月程度かかるとアナウンスしている。
4月に自社回線サービスを始めた楽天モバイルは、月2980円(税別)かかる月額料金を1年間無料にするとともに、ウェブ経由の申込者なら契約時にかかる手数料3000円(税別)をポイントで還元するキャンペーンを実施した。ところが、想定通りには契約者数が増えていないもようだ。
通信料金が無料なのに契約に二の足を踏む人が多い理由の1つは、端末の問題だ。楽天モバイルの回線を使うには、「楽天モバイル対応」と検証された端末の購入が求められているからだ。
NTTドコモとau、ソフトバンクの3大キャリアや、その回線を利用するMVNO(仮想移動体通信事業者)の場合、使っているスマホのSIMロックを解除すれば別の通信会社に乗り換えられる。しかし、楽天モバイルは自らが販売している端末の利用を推奨する。「音声通話などで端末メーカー側の調整が必要」(楽天モバイルの山田善久社長)だからだ。
楽天モバイルも手をこまぬいていたわけではない。当初から、自社回線の契約と同時に対応端末を購入する場合、1万〜1万5000円相当のポイントを還元するキャンペーンを行ってきた。さらに4月9日からは、楽天市場で対応端末を最大50%ポイント還元で販売するセールも断続的に実施している。例えば4月時点では、税込み9万9800円の「Galaxy S10」(韓国サムスン電子製)を買うと、40%分の3万9920ポイントが還元されていた。
ただしこのセールは、楽天モバイルの自社回線サービスを契約しなくても端末だけ購入できるものだ。2019年10月の電気通信事業法改正で、通信契約を条件とした場合の2万円以上の値引きができなくなった。上記のような4万円近い実質値引きは、この規制に抵触する。大幅値引きによる端末の普及を優先するか、それとも契約の獲得を優先するか。楽天モバイルは端末の普及を選択したわけだ。その結果、高額還元した端末が個人間取引サイトで転売される副作用も生じている。
そして行き着いたのが、冒頭のRakuten Miniの大幅値引きだった。価格が税別1万7000円と安価なため、価格を1円にしても値引き幅は2万円の枠内に収まる。ただし、画面サイズは3.6型と小さく、性能も価格相応。今回のキャンペーンが楽天モバイルを継続的に利用するユーザーの大量獲得につながるかどうかは疑問が残る。
■UQもワイモバイルも
端末と並ぶ楽天モバイルの弱点が、自社回線エリアの狭さだ。東名阪などの都市部の一部にとどまり、都市部でも地下鉄のトンネル内などの整備が遅れ気味だ。自社回線が使えないエリアではKDDIの回線を借りている。「データ量無制限」を売りに掲げる楽天モバイルだが、KDDIの回線利用分はその範囲外。月間データ容量の上限を超過すると通信速度を制限する。
その弱点を狙い撃ちにしたかのような料金プランをKDDI傘下の格安スマホ「UQモバイル」が打ち出した。6月1日から提供を開始した「スマホプランR」は、楽天モバイルと同じ月額2980円(税別)。月間データ容量の上限は楽天モバイルにおけるKDDI回線利用時の2倍に設定しており、超過後の通信速度は楽天モバイルと同じだ。
UQモバイルを運営するUQコミュニケーションズ(東京・港)の担当者は「楽天モバイルが自社回線エリアを整備するには数年かかるだろう。全国どこでも同じ条件で利用できるぶん優位性がある」と話す。UQモバイル事業は10月から運営をKDDI本体に移管する予定。サブブランドとしてauショップでも取り扱いが広がり、営業力が飛躍的に高まる。KDDIは回線を楽天モバイルに貸し出すパートナーである一方、UQモバイルの吸収で低価格プランを充実させ、ユーザーの流出を防ぐ構えだ。
UQに対抗する形で、ソフトバンクの格安サブブランド「ワイモバイル」も同様のプランを7月1日から始めると発表。サブブランドを通じた楽天包囲網が築かれつつある。
スマホが広く普及してから参入した楽天モバイルが勢力を拡大するためには、大手キャリアの顧客を奪うしかない。自社回線エリアを早急に広げ、「データ量無制限」のサービスを言葉通りに提供できるかが鍵になる。1円スマホによるユーザー獲得で安堵している暇はなさそうだ。
8.香港国家安全法、詳細詰め 18日から全人代常務委
中国の国会に相当する全国人民代表大会(全人代)常務委員会の委員長会議が9日、北京市で開かれ、18〜20日に全人代常務委員会を開くと決めた。習近平(シー・ジンピン)指導部は全人代常務委で反体制活動を禁じる「香港国家安全法」の制定手続きを進める考えで、18日にも具体的な法律の条文や運用の仕組みを策定する可能性が高まっている。
中国国営中央テレビ(CCTV)が伝えた。国家安全法は香港で国家分裂や中央政府の転覆、テロ行為、外部による内政干渉など反体制活動を禁じ、中国が香港に国家安全機関を設置することも可能。全人代常務委で法案を審議し、可決後、香港政府が施行する流れだ。
香港では高度な自治を保障する「一国二制度」がある。ただ今回は香港の憲法にあたる香港基本法の例外規定を使うことで、香港立法会(議会)では審議・採択することなく中国本土の法律が適用できるようになる。
国家安全法は5月末に閉幕した全人代で導入を決めたが、具体的に反体制活動に対する罰則や取り締まりについては明らかになっていなかった。習指導部は9月の香港立法会選で民主派が過半数の議席を占めるのを阻止するため、同法の施行を急いでいるとの見方が強い。一部の香港紙は6月中に可決し、月内に施行する可能性も伝えている。
9.ホンダ、サイバー攻撃でシステム障害 北米は生産停止
ホンダは9日、サイバー攻撃が原因で社内のネットワークシステムに8日に障害が発生したことを明らかにした。ウイルスが拡散された影響で8日に国内工場では一時、完成車の出荷業務を見合わせたほか、北米では7つの四輪車工場など全拠点で生産を停止した。パソコンでのメールのやり取りは9日時点でも支障が出ている。情報漏洩の問題はないとしている。
8日、寄居工場(埼玉県寄居町)などで、出荷前に完成車に不具合がないかどうかを確認する検査システムと工場のコンピューターが接続できなくなった。その影響で、出荷業務を一時取りやめた。既に復旧したがパソコンを使った業務は制限されたままだ。社員の一部は9日に有給休暇を取ったという。
海外では北米で8日、ウイルス問題の確認のため全拠点で生産を停止した。9日は一部を除き生産を再開する予定だ。中国の工場では影響が見られなかったという。ホンダの広報担当者は「今回のサイバー攻撃による顧客などの情報漏洩はない」としている。
ホンダは2017年、世界の複数拠点でランサムウエア「WannaCry(ワナクライ)」に感染した。当時も工場の生産を一時停止させるなどの影響が出た。国内では三菱電機など複数の大手企業もサイバー攻撃を受けており、セキュリティー対策の重要性が増している。
10.東芝、オンライン授業を自動で字幕化 85%の正確さ
東芝は、音声認識の人工知能(AI)を活用し、オンライン授業での教員の声を自動で字幕化するシステムを開発したと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大に伴ってオンライン授業を取り入れる大学などが増えているため。字幕をつけることで学生の授業の理解度を高める。月内にも慶応義塾大や法政大で実証実験を始め2021年をメドの実用化を目指す。
発言内容を約85%の正確さで認識できるといい、専門用語を事前に登録しておけば、より精度を高められる。資料を読み込ませることで専門用語を一括して認識させることができるという。開発した音声自動字幕システムは、既存のオンライン会議システムで使え、リアルタイムで音声を字幕化する。東芝が会議・講演の字幕化のために開発してきた技術をオンライン授業用に特化させた。
新型コロナ感染抑止のため、授業をオンライン化する学校は増えている。東芝は、字幕化システムによりオンライン授業を理解・復習しやすくし、教員や学生の支援につなげたい考えだ。
11.東証大引け 7日ぶり反落、円高で利益確定売り 2万3000円台は維持
9日の東京株式市場で日経平均株価は7営業日ぶりに反落し、前日比87円07銭(0.38%)安の2万3091円03銭で終えた。これまでの急ピッチな上昇に対する警戒感が漂い、利益確定を目的とした売りが優勢となった。外国為替市場で円相場が上昇したのも重荷だった。
前日に1ドル=109円台半ばだった円相場が一時107円台後半の水準まで円高に振れ、自動車などの輸出関連株の売りを誘った。日経平均は前日までの6日続伸で上げ幅が1300円に達し、25日移動平均との乖離(かいり)も広がっていたため、短期的な相場の過熱感が意識された。
直近で上げていた鉄鋼や海運、銀行などの業種への売りも目立った。日経平均の下げ幅は200円を超え、2万3000円の心理的な節目を割り込む場面があった。
ただ、アジアの主要株価指数が堅調に推移するなか、これまでの上昇局面で買いそびれていた投資家や、海外勢の先物の買い戻しなどが入り、取引終了にかけて下げ幅を縮小した。
JPX日経インデックス400は7日ぶりに反落。終値は前日比17.80ポイント(0.12%)安の1万4676.32だった。東証株価指数(TOPIX)も7日ぶりに反落し、2.29ポイント(0.14%)安の1628.43で終えた。業種別TOPIXは鉄鋼、海運業、非鉄金属などが大きく下げた。
東証1部の売買代金は概算で2兆5070億円。売買高は15億2158万株だった。東証1部の値下がり銘柄数は1219銘柄だった。値上がりは853、変わらずは97銘柄だった。
12.米国の人出、コロナ前迫る 経済再開と抗議デモで
米国の人出が急速に回復している。経済の一部再開に加え、5月下旬からは全米で人種差別への抗議が相次いだ。米アップルの集計では徒歩や車の移動は新型コロナウイルスの流行前の水準に迫る。8日にはニューヨーク市も2カ月半ぶりに経済を部分的に再開。経済活動が持ち直す半面、コロナの感染が再拡大するおそれもある。
ミネソタ州での白人警官による黒人暴行死から2度目の週末となった6〜7日、事件後で最大規模のデモが全米で起きた。首都ワシントンの中心部では大統領就任式のような人出となり、大規模な行進が繰り広げられた。アトランタやフィラデルフィアなど、数千人以上のデモが全米各地であった。
アップルが集計する地図アプリの利用状況で人の動きの回復が鮮明だ。車や徒歩の移動は2月平均の水準を回復した。一部の州で経済再開が始まった4月下旬から右肩上がりで増えた。
徒歩での移動を都市別に集計すると、デモの影響が顕著だ。暴行事件のあった5月25日以降、現場のミネアポリスでは徒歩の移動が急増した。デトロイトも増加が目立ち、直近は2月平均より5割近く多い。ワシントンも大規模デモのあった6日に大幅に増えた。
一時は略奪や放火が各地で相次いだが、この数日間で暴動は沈静化しつつある。警備強化や逮捕者が増えたことで、大半のデモは平和裏に実施されている。ただ、人種差別だけでなく、格差や警察への不満も噴出しており、デモは収束の兆しがみえていない。
経済再開も人出に影響している。ニューヨーク市は8日、経済再開の第1弾に踏み切った。対象は建設業などに限られるが、車の移動は徐々に回復している。レストランを再開する都市も増えている。大手レストラン予約のオープンテーブルによると、5月の全米の予約数は前年同月比92%減だったが、6月は79%減(7日まで)に回復した。
エネルギー情報局(EIA)の集計では1日時点のレギュラーガソリンの全米小売価格は1ガロン1.974ドルと4月下旬の安値から11%上昇した。経済再開に加え、ドライブシーズンに入ったことでガソリンの需要が持ち直している。株式市場でも経済再開への期待で、株価は連日のように上昇を続けている。
ただ、新型コロナの感染が再び急増するおそれもある。カリフォルニア州やテキサス州、アリゾナ州などは6月に入り、新規感染者数がピークを更新している。特に抗議デモでは大人数で密集しており、感染リスクは高まっている。感染拡大の第2波を招けば経済再開は頓挫し、景気だけでなく国民の生活や感情にも再びストレスがかかるおそれがある。
13.日銀、社債オペで初の下限利回り設定
保存 共有 印刷その他
日銀は9日に実施した社債の買い入れオペ(公開市場操作)で、2013年の異次元緩和開始後で初めて下限の利回りを設定した。下限はマイナス0.14%にした。国債よりも低い利回りで社債を買うことで、特定の市場参加者が過度な利益を上げることを防ぐ狙いがあったとみられる。
9日のオペは残存期間が1年超3年以下の社債が対象で、買い入れ予定額3000億円に対して3757億円の応募があった。落札額は3003億円だった。最低落札利回りはマイナス0.14%で下限利回りと同じだった。
アセットマネジメントOneの加藤晴康ファンドマネジャーは日銀の狙いについて「社債買い入れの拡大で市場機能をゆがめないように下限利回りを設定した」と指摘する。マイナス0.14%は年限が近い国債の利回りと同水準で、社債を国債よりも低い利回りでは買わないという意思表示だとの見方を示す。
日銀が下限利回りの設定に動いたことは、社債購入を継続するための工夫でもある。加藤氏は「日銀が買い入れ額を簡単には減らさないという投資家の安心感につながった」と話す。
【経済ニュース 6/8 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
今日は帰宅が遅く更新あまりできません。
すみません。
NYダウ続伸、200ドル超上昇 米経済の正常化期待で
8日の米株式市場でダウ工業株30種平均は6日続伸して始まった。午前9時35分現在、前週末比233ドル88セント高の2万7344ドル86セントで推移している。前週末発表の米雇用統計で雇用者数が市場予想に反して急増し、米経済が早期に正常化に向かうとの楽観論が買いを後押ししている。
旅客需要の回復見込みからユナイテッド航空ホールディングスなど空運株が軒並み大幅高となり、連動して航空機のボーイングも買われている。業績が景気に左右されやすいJPモルガン・チェースなど金融株も総じて上げている。クルーズ船や外食なども高い。
ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は続伸し、前週末比13.09ポイント高の9827.17と、2月19日に付けた過去最高値(9817)を上回って推移している。アナリストが目標株価を引き上げた通販のアマゾン・ドット・コムが買われている。