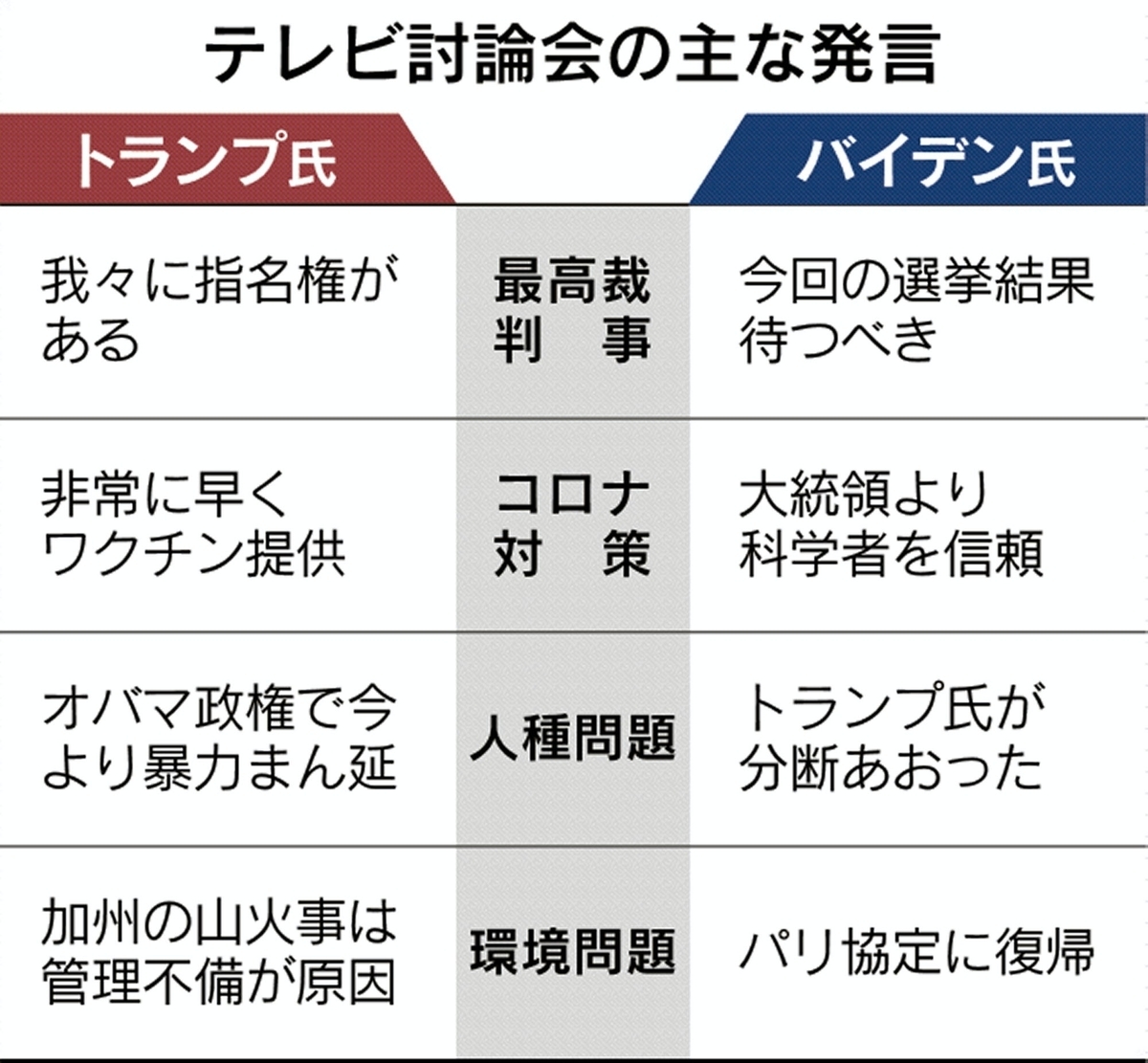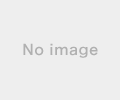新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2020年06月05日
【経済ニュース 6/5 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
さて米国のお祭り指標とも言える雇用統計が終わりました
気になる結果は・・・
1.米失業率、5月は13%に一転改善 就業者も250万人増
2.NYダウ先物650ドル高 米雇用、予想外の増加で
3.ビデオ会議市場争奪 AmazonとSlack提携、MSに対抗
4.トヨタ、中国5社と燃料電池を共同開発 合弁設立へ
5.日本株、上げ一服でも視線は「上」 生保が警戒解除
6.トランプ氏批判、米軍元高官から続出 軍動員に懸念
7.OPECプラス、6日に会合 協調減産延長の見通し
8.日経平均終値、167円高の2万2863円 5日続伸
9.豪印、防衛協力で新協定 対中けん制 首脳が合意
10.インド、新型コロナで1億2千万人が失職 民間調べ
11.香港取引所、中国・京東の上場承認 米ナスダックと重複
2.NYダウ先物650ドル高 米雇用、予想外の増加で
3.ビデオ会議市場争奪 AmazonとSlack提携、MSに対抗
4.トヨタ、中国5社と燃料電池を共同開発 合弁設立へ
5.日本株、上げ一服でも視線は「上」 生保が警戒解除
6.トランプ氏批判、米軍元高官から続出 軍動員に懸念
7.OPECプラス、6日に会合 協調減産延長の見通し
8.日経平均終値、167円高の2万2863円 5日続伸
9.豪印、防衛協力で新協定 対中けん制 首脳が合意
10.インド、新型コロナで1億2千万人が失職 民間調べ
11.香港取引所、中国・京東の上場承認 米ナスダックと重複
1.米失業率、5月は13%に一転改善 就業者も250万人増
米労働省が5日発表した5月の雇用統計(速報値、季節調整済み)は、失業率が13.3%となり、戦後最悪だった4月(14.7%)から一転して改善した。市場は20%程度の失業率を見込んでいたが、経済活動の一部再開で人材の職場復帰が進んだとみられる。景気動向を敏感に映す非農業部門の就業者数も、前月から250万人増えた。
4月は就業者の減少幅が過去最大の2070万人に達したが、5月は一転して大きく持ち直した。市場は就業者数が約800万人減少すると予測していた。就業者数の伸び幅を業種別にみると、新型コロナで一時的に休業を迫られていた飲食業が137万人増と、大きく持ち直した。小売業も37万人増えた。
米政権は企業の雇用維持を条件に、6600億ドル(約72兆円)という巨額の枠を設けて、従業員の給与支払いを肩代わりする異例の資金供給を続けている。再雇用でも企業は資金を受け取れるため、職場復帰が加速した可能性がある。実際、4月の失業者(2300万人)のうち、職場への早期復帰を前提とした「一時解雇」が8割近くあった。5月でみても失業者(約2100万人)の7割強が「一時解雇」だ。
ただ、それでも失業率は金融危機時のピーク(2009年10月、10.0%)を超えたままで、戦後最悪の水準が続く。飲食店などでは新型コロナによる営業制限が残っており、収束が遅れれば一時解雇が「恒久解雇」になる可能性もある。
雇用統計の予想外の改善を受けて、5日のニューヨーク株式市場では、ダウ工業株30種平均が前日比700ドルほど上昇して始まった。米10年物国債の利回りも上昇し、円相場も2カ月ぶりの円安・ドル高水準となった。
2.NYダウ先物650ドル高 米雇用、予想外の増加で
】5日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均の先物が急上昇した。5日朝発表の米雇用統計が市場予想に反し、雇用者数が増加したことに反応した。前日比の上昇幅は650ドルを超え、2万6900ドル程度と2月下旬以来の高値を付けた。
株式以外の市場でも投資家心理は改善している。米10年物国債の利回りは0.9%台に上昇し、円相場は109円60銭台と約2カ月ぶりの円安・ドル高水準となった。ニューヨーク原油先物期近物は1バレル39ドル台に上昇した。
米雇用統計は事前の市場予想では前月比800万人程度の減少が見込まれていた。失業率は4月の14.7%から20%近くへの上昇が見込まれていたが、実際は13.3%へと低下した。
3.ビデオ会議市場争奪 AmazonとSlack提携、MSに対抗
米アマゾン・ドット・コムがビジネスチャットで台頭してきた米スラック・テクノロジーズとの提携を決めた。アマゾンが力を入れるクラウド部門のライバルである米マイクロソフト(MS)に対抗する。焦点は新型コロナ禍で急成長するビデオ会議サービスだ。「Zoom」を運営する米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズも含め、新興勢力が巨大企業を動かす新たな競争の構図が浮かび上がってきた。
4.トヨタ、中国5社と燃料電池を共同開発 合弁設立へ
トヨタ自動車は中国大手自動車など5社と燃料電池を開発する合弁会社を設立する。同社が開発した燃料電池車(FCV)のシステムを2022年をめどに、北京汽車集団などの自動車メーカーが開発するトラックやバスに提供していく。新エネルギー車へのシフトを進める中国政府はトヨタが持つFCV技術への関心を強めており、共同開発をてこにFCVの普及に向け弾みをつける。
5.日本株、上げ一服でも視線は「上」 生保が警戒解除
5日の東京株式市場で、日経平均株価は前日比78円(0.4%)安の2万2616円で午前の取引を終えた。前週からほぼ休みなしで急騰してきただけに、上げ一服の展開だったが、市場関係者の目線はさらに「上」を向いている。二番底を警戒していた生命保険会社も先物ヘッジ売りの解除に動いたとみられ、早くも「相場は長期上昇トレンドに回帰する」との声が聞かれ始めた。
6.トランプ氏批判、米軍元高官から続出 軍動員に懸念
黒人暴行死事件の抗議デモに対してトランプ米大統領が連邦軍動員を検討していることに、元軍高官から批判が相次いでいる。退役後も政治的発言を控えることが多い軍OBが、最高司令官である現職大統領を非難するのは異例だ。国防総省は4日に首都近郊の連邦軍の一部撤収を決めたが、トランプ氏が「強い指導者」の演出に軍を私物化するとの懸念は消えていない。
「彼は立派な人物だ」。トランプ政権で大統領首席補佐官を務めたケリー元海兵隊大将は4日、米紙ワシントン・ポストのインタビューでマティス前国防長官への支持を表明した。マティス氏は前日、トランプ氏のデモ対応を「軍と市民社会に誤った紛争を生む」と痛烈に批判。反発するトランプ氏が「過大評価された大将」とマティス氏をこき下ろしていた。
米軍制服組トップを務めたマイク・マレン元統合参謀本部議長も米誌への寄稿で「軍最高司令官(であるトランプ氏)による命令の健全性に信頼が置けなくなっている」と批判。ジェームズ・スタブリディス元北大西洋条約機構(NATO)欧州連合軍最高司令官も政権がホワイトハウス前のデモ隊を排除したことに触れて「天安門のようにしてはならない」と苦言を呈した。
トランプ政権はデモがさらに暴徒化した場合に備えて首都ワシントンの近郊に米兵1600人を集めたが、エスパー国防長官は4日、一部の撤収を決めた。武力を見せつけてデモ隊を威圧してきたトランプ氏も容認したとされる。ただ完全撤収については「状況次第だ」(国防総省高官)としており、動員の可能性は完全には消えていない。
共和党系の政治コンサルタントのダグラス・ヘイ氏は「トランプ氏は(軍を通じて)法と秩序を重視する姿勢を示し、混乱を容認するかのような民主党と対比しようとしている」と指摘する。11月の大統領選に向けて米軍が政治利用されているとの見方は多い。
軍にとって人種問題は敏感な問題だ。ピュー・リサーチ・センターによると、2017年時点の人種構成は、非白人が43%と04年に比べて7ポイント上昇した。非白人の貧困家庭出身者が経済的理由で入隊するケースもある。エスパー氏が3日まで公然と黒人差別問題を批判しなかったことにも疑問の声があがっている。
国防長官時代のマティス氏のスピーチライターを務めたガイ・スノッドグラス氏は、国内の混乱が長引けば、中国やロシア、北朝鮮につけいる隙を与えかねないとの懸念が軍OBにはあると指摘する。中国は香港への統制を強める「香港国家安全法」の施行を急ぎ、台湾統一への意欲も隠さない。ロシアは新たな核兵器使用の指針で、通常兵器に対しても核兵器で対抗する可能性を示した。
多くの世論調査では抗議デモや新型コロナウイルスへの対応が不適切だとして、トランプ氏は11月の大統領選で民主党の候補指名を固めたバイデン前副大統領に支持率で引き離されている。米メディアによるとトランプ氏は4日、選対幹部と世論動向に関して協議。今後の対応を話し合ったとみられている。
7.OPECプラス、6日に会合 協調減産延長の見通し
石油輸出国機構(OPEC)とロシアなど非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」は6日に協調減産の継続をめぐる会合を開くことを決めた。4月の合意では、日量970万バレルの協調減産を7月からゆるめるとしていた。新型コロナウイルスの感染拡大にともなう需要消失が深刻で、サウジアラビアやロシアは、現状の規模の減産を少なくとも1カ月延長するよう求める見通しだ。
会合では、イラクやナイジェリアなど決められた減産目標に届かなかった国の合意順守に向けた改善が要求される見通しだ。OPECプラスの5月の合意順守率は90%程度にとどまったとみられている。
一時1バレル20ドルを下回った国際指標の北海ブレント先物は現在、40ドル前後まで回復している。しかし、感染がピークを越えたとみられる中国の需要回復が遅れるなど、年後半の市況をめぐって産油国の不安は根強い。消費国は価格の急落時に貯蔵を一気に増やしたもようで、原油の供給過剰は早期に解消しにくくなっている。
OPECプラスは当初、9、10日の会合を予定していたが、OPEC議長国アルジェリアの要請などで前倒し開催となった。前回と同様、出席者の感染防止のためオンラインの会合となる。
8.日経平均終値、167円高の2万2863円 5日続伸
5日の東京株式市場で日経平均株価は5日続伸した。前日比167円99銭(0.74%)高の2万2863円73銭とほぼ高値引けとなり、2月21日(2万3386円)以来、およそ3カ月半ぶりの高値で終えた。5日以上続伸するのは、2019年10月18〜29日に7日続伸して以来。朝方は短期的な過熱感が意識され利益確定売りが先行したが、米国での経済活動の根強い再開期待などから昼に米ダウ先物が上げ幅を拡大し、日経平均も後場に上昇に転じた。
市場では今晩発表の5月の米雇用統計をめぐり「最近は米経済指標の改善が買い材料になるケースが多かったため、今回も改善を評価して株高で反応すると見越した買いが入った可能性がある」(国内証券)との見方もあった。午前の相場の底堅さを受け、短期筋が午後に買い戻しを進めたのも相場を押し上げた。
欧州中央銀行(ECB)が4日に開いた理事会で、市場予想を上回る規模の追加金融緩和を決定したことも投資家心理の支えになった。
9.豪印、防衛協力で新協定 対中けん制 首脳が合意
オーストラリアとインドがインド太平洋での防衛協力を拡大させる。両国は4日、オンラインで首脳会談を開いた。両国軍の相互運用能力を高める協定で合意し、共同声明を発表した。通商や領土を巡り中国との緊張が高まる中、豪印は日米主導で中国に対抗する「自由で開かれたインド太平洋」構想に賛同、対中けん制で足並みをそろえる。
豪州のモリソン首相とインドのモディ首相は豪印関係を従来の戦略パートナーシップから包括的戦略パートナーシップに格上げすると決めた。相互後方支援協定の締結でも合意した。ロイター通信によると、この協定で両国の軍隊が互いの艦船や航空機に燃料補給したり、整備施設を利用したりできるようになる。
インド太平洋地域での海洋協力に関する共同宣言では「(豪印には)インド太平洋地域で航行の自由を確保する共通利益がある」と指摘した。両国が同地域で「安全保障などの課題に対し共通の懸念を抱いている」とも表明し、南シナ海とインド洋を結ぶシーレーン(海上交通路)の確保を目指す中国を強くけん制した。
両首脳は海軍間の協力を深め、情報交換を進めることも確認した。米印海軍と日本の海上自衛隊による共同訓練「マラバール」への豪州の参加も協議されたとみられる。豪州は2007年マラバールに参加したが、中国が不快感を表明したため、その後は参加していない。外務・防衛担当閣僚協議(2プラス2)に関しても、少なくとも2年ごとに開催し、日米との連携も進める方針だ。
両首脳は貿易や投資活動の拡大に向けた協力も協議した。豪州の投資家向けにインドのインフラ部門についての情報提供を行うなどの連携を進める。
豪印がここにきて中国へのけん制を強める背景には、中国と摩擦や緊張が高まっていることがある。
豪州は今年4月、新型コロナウイルス感染拡大の経緯に関する独立調査を求め、中国の強い反発を受けた。中国は5月、一部の豪産食肉の輸入停止に踏み切り、大麦にも80%超の追加関税を課すと発表した。18年には豪州は安全保障上の懸念から次世代高速通信規格「5G」から中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)を排除している。インドと中国の国境付近では、1カ月ほど前から両国軍の小競り合いが続く。
中国と対立が続く米国は、豪印に秋波を送る。中国が広域経済圏構想「一帯一路」を掲げ、南シナ海やインド太平洋へ進出することに米は非難を続け、通商でも対立する。トランプ米大統領は9月以降に米国で開く主要7カ国首脳会議(G7サミット)に豪印も招待し、対中包囲網の構築につなげる考えで豪印も参加に前向きだ。
もっとも、豪印両国は中国に対し、明確な対決姿勢を示すのは難しい。経済上の関係が深いからだ。中国は豪州にとって輸出の3割超を占める最大の貿易相手国だ。牛肉や大麦など農産物は中国への輸出額の1割程度だが、中国からの「報復」が液化天然ガス(LNG)など資源分野にも及べば影響は大きい。
インドにとっても中国は米国、アラブ首長国連邦(UAE)に次ぐ主要の輸出先だ。両国とも安全保障と経済のバランスで難しいかじ取りが続きそうだ。
10.インド、新型コロナで1億2千万人が失職 民間調べ
首都ニューデリーなどインド都市部の失業率が5月、26%となったもようだ。新型コロナウイルスの感染予防として3月末に全土封鎖を始め、経済活動が停止し、全国では1億2千万人が職を失った。インドは都市部で失職した出稼ぎ労働者が農村に帰らざるを得ず、その過程で感染者が広がる構図となっている。8日から経済活動を段階的に再開するが、感染拡大のペースが速まる恐れもある。
11.香港取引所、中国・京東の上場承認 米ナスダックと重複
香港取引所が中国ネット通販2位の京東集団(JDドットコム)の株式上場を承認したことが5日分かった。米ナスダック市場との重複上場となる。調達目標額は明らかになっていないが、30億ドル(約3300億円)程度になる可能性がある。
香港取引所が同日公開した京東の上場申請資料によると、調達する資金はIT(情報技術)システムや物流などの開発に投じる方針。中国メディアによると、上場時期は6月中となる見通しだ。
一方、香港紙は香港取引所に上場予定の中国ゲーム大手、ネットイースの公募価格が1株あたり123香港ドル(約1700円)になると報じた。上場日は11日で、調達額は210億香港ドル(約2900億円)程度となる見通し。同社も米ナスダック市場との重複上場となる。
2019年11月にアリババ集団が香港で重複上場するなど米上場の中国企業による「香港回帰」が続いている。米中対立が続くなか、中国への理解が深い投資家が多い香港市場を選ぶ中国企業が増えたとみられる。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
【経済ニュース 6/4 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
さて東京のコロナ新規感染者が2桁を続けています
また昨晩発表の欧州の政策金利は据え置きに
米国の新規失業保険申請件数は予想を上回るなど
まだまだコロナの猛威が止まりません
今一度不要不急の外出の自粛頑張っていきましょう
そもそもなぜそんなに外出が出来ないだけでイライラするのでしょうか??
散歩とかはもちろん許されてますしね
たまたま他の人生のストレスをコロナ自粛のストレスを言い訳にしてしまってるだけの気も
お店の経営や夜の仕事などの方は本当にお辛い状況かと思います。
それ以外の個人であれば発信が出来ないストレスを
在宅で発信をする大きなチャンスに変えられる時期でもあります。
色々試行錯誤してアクセス数を伸ばしる方も増えているので頑張る事で
自粛にもなり同居の家族がいる方は家族を守る事にも繋がりますね
家族と職場を壊すリスクを取って外出してコロナになりに行く可能性を作るメリットが分かりません。
いまだにそれをわかってない発達障害のような精神コントロールが出来ないお子様がいるのが不思議・・・
さて今日の見出しです
1.ビジネス渡航にPCR検査 行動計画も義務付け
2.東京、新たに28人の感染を確認 新型コロナ
3.欧州中銀が追加緩和、資産買い取り枠を拡大
4.日米欧、追加対策200兆円 日本、執行速度見劣り
5.NYダウ反落で始まる 利益確定売りが先行
6.抗マラリア薬、新型コロナ予防できず トランプ氏服用
7.コロナ下の米株価上昇「経済反映せず」63%、5月FT・米財団世論調査
8.香港立法会、国歌条例が成立 侮辱行為を禁止
9.米、4月の輸出入が過去最大の下落 新型コロナで
10.中国当局、国際線週2往復を容認 米国への配慮も
2.東京、新たに28人の感染を確認 新型コロナ
3.欧州中銀が追加緩和、資産買い取り枠を拡大
4.日米欧、追加対策200兆円 日本、執行速度見劣り
5.NYダウ反落で始まる 利益確定売りが先行
6.抗マラリア薬、新型コロナ予防できず トランプ氏服用
7.コロナ下の米株価上昇「経済反映せず」63%、5月FT・米財団世論調査
8.香港立法会、国歌条例が成立 侮辱行為を禁止
9.米、4月の輸出入が過去最大の下落 新型コロナで
10.中国当局、国際線週2往復を容認 米国への配慮も
1.ビジネス渡航にPCR検査 行動計画も義務付け
政府が検討中の出入国の緩和策が4日、分かった。ビジネス目的の往来の際に、新型コロナウイルスへの感染を判断するPCR検査の陰性証明書と、行動計画の提出を求める。審査を通れば入国時に長期間の待機を免除する。産業医らの診断で無症状の渡航希望者へのPCR検査も認める方針だ。どれだけ検査を拡充できるかが経済再開の規模を左右する。
2.東京、新たに28人の感染を確認 新型コロナ
東京都は4日、新型コロナウイルスの感染者が新たに28人確認されたと発表した。5月25日に緊急事態宣言が解除されて以降、1日当たりの感染者数としては6月2日(34人)に次ぐ多さだった。都内の感染者は計5323人となった。また1人の死亡を確認し、死者は計307人となった。
都によると4日に確認した感染者28人のうち、夜の繁華街での感染者は9人。うち4人は同じパーティーに参加して感染したという。また、4日までの1週間の128人の感染者のうち3割超の43人が「夜の街」関連で、うち十数人がホストクラブの従業員という。
都内の1日当たりの感染者数は4月中旬にピークを迎えた後に減少し、5月中旬には10人を下回る日が続いた。5月下旬から徐々に増加傾向に転じ、都は6月2日に独自の警戒情報「東京アラート」を発動し、警戒を呼びかけていた。
都はアラート発動後に(1)直近1週間平均の1日当たりの新規感染者が50人以上(2)感染経路不明者の割合が直近1週間平均で50%以上(3)週単位での感染者数が前週の倍以上――の複数を満たした場合、医療提供体制なども加味しながら、専門家の判断を踏まえて再度の休業要請を判断するとしている。
4日時点では(3)が2.03倍で満たしている。都は「1日の感染者が50人を超えるような場合に、他の指標も含めて慎重に判断する」と説明している。
3.欧州中銀が追加緩和、資産買い取り枠を拡大
欧州中央銀行(ECB)は4日開いた理事会で、追加金融緩和を決めた。3月に新設した7500億ユーロ(約90兆円)の資産買い取り枠を1兆3500億ユーロへ6000億ユーロ(約70兆円)拡大する。少なくとも2020年末までとしていた政策の期限も21年6月末までに半年延長した。新型コロナウイルスの欧州経済への悪影響が長期化するなか、大規模な金融緩和を粘り強く続ける。
4.日米欧、追加対策200兆円 日本、執行速度見劣り
新型コロナウイルス対策で主要国が財政出動を一段と積み増している。日米欧主要国の対策追加額はこの1カ月あまりで少なくとも200兆円規模と4割近く増えた。ドイツは投資や消費を刺激する第2弾の対策をまとめ、米国も中小企業の雇用維持策を大幅に拡大する方針だ。日本は主要国でも大型の対策をまとめたものの、給付金の執行の遅れやコロナ対策と関連の薄い事業の予算計上も目立ち、速度や効果に課題がある。
5.NYダウ反落で始まる 利益確定売りが先行
4日の米株式市場でダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落して始まった。午前9時35分時点では、前日比62ドル32セント安の2万6207ドル57セントで推移している。直近3日間で900ドル近く上げ、前日は3カ月ぶりの高値を付けていた。朝方発表の週間の米新規失業保険申請件数が市場予想を上回ったこともきっかけとなり、利益確定売りが先行している。
新規失業保険申請件数は5月30日までの1週間で187万7000件と市場予想(180万件)より多かった。失業手当の継続受給件数も前の週に比べて増えた。経済活動の再開が景気を押し上げるとの期待がやや後退した。
個別では医薬・日用品大手のジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)や建機のキャタピラーが売られている。前日に上昇した銀行株も下げて始まった。
ただ、下値は堅い。アメリカン航空グループは4日、需要の増加を受けて夏の国内便を増便すると発表した。米経済が正常化に向かっているとの見方は続いており、相場を下支えしている。
6.抗マラリア薬、新型コロナ予防できず トランプ氏服用
トランプ米大統領が新型コロナウイルス感染症の予防や治療に有望だと推奨してきた抗マラリア薬ヒドロキシクロロキンについて、感染者と近くで接した人の発症を予防する効果はみられなかったとする臨床試験の結果を米ミネソタ大などのチームが米医学誌電子版に3日、発表した。指摘される心臓への深刻な副作用はみられなかった。
トランプ氏はホワイトハウスのスタッフの感染が相次いだ5月、予防目的で自ら服用していた。ホワイトハウスはこの日、2週間服用したが副作用はなかったとする担当医の所見を公表。これまでに19回感染検査をしたが全て陰性だったとしている。
ミネソタ大などのチームの臨床試験は、職場や家庭で、感染者と約2メートル以内で10分よりも長く接した医療従事者など、米国とカナダの821人が対象。接触から4日以内にヒドロキシクロロキンと、比較用の偽薬を投与した。
その結果、14日以内に陽性判定を受けたか、新型コロナとみられる症状が出た人の割合は、ヒドロキシクロロキンのグループは約12%、偽薬は約14%で、予防の効果があるといえるだけの違いはなかった。
7.コロナ下の米株価上昇「経済反映せず」63%、5月FT・米財団世論調査
英フィナンシャル・タイムズ(FT)と米ピーター・G・ピーターソン財団は5月20〜26日、11月の米大統領選に関する世論調査を実施した。新型コロナウイルスの影響下で続く株価上昇は「(今後の)米経済回復を示していない」との回答が63%に上った。市場は経済活動の再開期待で持ち直すが、有権者の慎重な姿勢との乖離(かいり)が浮き彫りになった。
ダウ工業株30種平均は2月下旬以降に急落したが、足元では経済が早期に立て直すとの見立てから直近のピークの9割まで戻った。トランプ大統領は有権者に株高をアピールするが、実態を反映していないとの見方が多く、再選の追い風となるかは不透明だ。
新型コロナから米経済が完全回復するまでに「1年以上かかる」との回答は59%と3ポイント上昇した。ワクチンや有効な治療薬が登場するまでの長期戦を覚悟しているようだ。解雇されたり一時帰休となったりした人は21%で、そのうち14%が元の職場に戻れるとみる。
5月以降に全米各地で経済再開が進むなか、悪影響の拡大はひとまず歯止めがかかっている。「個人やビジネスの決断に影響を与えている」との回答は前月に比べ8ポイント減の66%。2月以降の調査で初めて減少した。「公共の場所を避けている」人は55%と10ポイント減少した。「旅行計画を中止・変更した」「大型の買い物を延期した」との回答はそれぞれ8ポイント、7ポイント減った。
経済再開のスピードを巡っては支持政党の違いで温度差がある。不要不急のビジネスへの規制を続ける地方政府に対し、民主党支持者は90%が賛同したが、共和党支持者は54%にとどまった。トランプ氏は共和党支持者の意識をくみ取って経済再開に前のめりだ。
新型コロナの感染が再び広がる「第2波」への警戒感は消えていない。自分たちが暮らす地域で新型コロナを巡る状況が今後1カ月で「改善する」との回答は1ポイント増の39%、悪化するは3ポイント減の35%だった。ソーシャル・ディスタンス(社会的距離)などの規制を「3カ月以内に解除すべきだ」との意見は61%と前月から5ポイント減った。
足元の景気悪化はトランプ氏の政策評価には大きな影響を与えていない。同氏の経済政策が「経済を改善させた」との回答は48%と前月と変わらず、「悪化させた」は41%と2ポイント低下した。トランプ氏は20年後半にかけて経済が大幅に回復すると主張しており、有権者は様子見を続けている。
FTと同財団による世論調査は19年10月に始めた。5月20〜26日にインターネットを使って全米で調査し、1000人から有効回答を得た。このうち760人が中西部ミシガン州や東部ペンシルベニア州など激戦州の有権者だった。
8.香港立法会、国歌条例が成立 侮辱行為を禁止
香港の立法会(議会)で4日、中国国歌「義勇軍行進曲」を侮辱する行為を禁じる国歌条例が親中派の賛成多数で成立した。民主派は審議妨害などで抵抗したが、最後は数で押し切られた。月内にも施行される見通し。反体制活動を禁じる「香港国家安全法」と合わせて、政治活動や表現の自由への締め付けが強まっている。
国歌条例は立法会の議員宣誓などの際に国歌斉唱を義務付け、替え歌を歌うなどの侮辱行為を禁止する。違反すると最長で3年の禁錮刑を科す。中国が2017年に国歌法を施行し、香港にも適用すると決めた。民主派は「何が違法行為にあたるのか曖昧で、恣意的に運用される可能性がある」と反発していた。
ここ数年、香港では若者を中心に反中国の機運が強まっている。サッカーの国際試合などで中国国歌斉唱の際にブーイングをしたり、グラウンドに背を向けたりする人が相次いでいた。国歌条例に反対する抗議活動も起きていた。
9.米、4月の輸出入が過去最大の下落 新型コロナで
米商務省が4日発表した4月の貿易統計(季節調整済み、国際収支ベース)によると、モノの貿易赤字は718億3700万ドル(約7兆8千億円)と前月に比べて8.8%増えた。新型コロナウイルスの影響で輸出が25.2%減と2009年9月以来、約10年半ぶりの低水準。輸入も13.6%減少した。輸出入とも落ち込み幅は1992年の集計開始以来、過去最大となった。
通関ベースの統計によると、自動車関連の輸出がおよそ28年ぶりの水準に落ち込んだ。新型コロナで海外需要が停滞し、国内生産も滞った。輸入も消費意欲が低迷して10年11月以来、約9年半ぶりの低水準となった。
対中国のモノの貿易赤字は260億ドルと前月に比べて52.8%増えた。新型コロナの影響で縮小していた輸入が中国の生産活動再開で急拡大した。対中輸出も持ち直しているが、トランプ政権が「第1段階の合意」で求める水準にはまだ遠い。
対中輸入は45.7%増えて352億ドルだった。カナダやメキシコ、日本など主要な貿易相手国からの輸入が軒並み減るなかで突出して伸びた。新型コロナの震源地である中国では電子機器などの工場が一時停止して供給に制約がかかったが、感染を押さえ込んで早期に生産を再開していた。
対中輸出は93億ドルと28.8%増えた。ただ1〜4月期でみると前年同期実績より8%少ない。第1段階合意では中国が農産品やエネルギーの購入を増やし、20年通年の米国の対中輸出は前年比で8割増やす約束だ。新型コロナによる出遅れの挽回はなお難しい。トランプ氏は対中輸出が伸びないことに不満を示し、協定破棄も示唆しながら合意の順守を求めている。
10.中国当局、国際線週2往復を容認 米国への配慮も
中国の航空当局は4日、新型コロナウイルスの世界的流行後に乗り入れを制限してきた国際旅客便を、最大で現状の2倍の週2往復まで認める方針を発表した。また暫定的に止めていた米系航空会社などの運航も許可する。米運輸省が3日発表した中国系航空による定期旅客便の乗り入れ禁止措置への対応という側面もありそうだ。
海外の航空会社が中国に乗り入れる国際線の定期旅客便は現在、1社1路線、週1往復だけの運航に原則制限されている。8日からは乗客の新型コロナの感染有無でフライトの上限数を増減させる。3週間続けて感染者がゼロなら週2往復まで認める。一方で感染者が5人に達した路線は1週間の運航停止に、10人に達した場合は4週間の運航停止にする。
中国航空当局は5月下旬、国際旅客チャーター便のフライト申請を簡略化する方針も打ち出している。中国政府は国際線の制限緩和で、母国に戻った外資系メーカーの技術者などを呼び戻して経済の再起動を急ぐ。
また今回の新方針からは米国への配慮も透ける。中国当局が3月下旬に実施した1社1路線、週1往復のルールの対象は、この時に中国に乗り入れるフライトを設けていた航空会社に限っていた。ただ米国などの航空会社は3月中旬までに中国へのフライトをやめていたためルールから漏れていた。6月4日の方針ではこうした航空会社も今後は乗り入れを許可するとした。
米運輸省は3日、中国の航空会社による米中間の定期旅客便の運航を16日から禁止すると発表した。米系航空会社が6月上旬からの中国便再開を中国当局に申請していたが認められていないためだ。米運輸省は中国当局が対応を改めれば決定を見直すことを示唆している。
2020年06月04日
【経済ニュース 6/3 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です

さてドル円が109円目前
雇用統計も予想よりも良い結果という事もあり株もイケイケムードです
1.日本電産、中国にEVモーター開発拠点 日本級の規模
2.中国、国家安全法施行へ準備加速 香港長官「支持」
3.「東京アラート」生活への影響は? 解除はいつ?
4.NYダウ続伸で始まる 221ドル高、米雇用指標を好感
5.カナダ中銀、政策金利を年0.25%で据え置き 2会合連続
6.米国防長官、連邦軍動員に反対 トランプ氏に反旗
7.欧州、雇用情勢に南北間格差 観光低迷が打撃に
8.豪、29年ぶり景気後退へ 入国禁止など響く
9.米、中国航空会社の米国便運航を禁止 16日から対抗措置
10.ロシア、8兆円で経済復興 改憲投票前に企業支援
2.中国、国家安全法施行へ準備加速 香港長官「支持」
3.「東京アラート」生活への影響は? 解除はいつ?
4.NYダウ続伸で始まる 221ドル高、米雇用指標を好感
5.カナダ中銀、政策金利を年0.25%で据え置き 2会合連続
6.米国防長官、連邦軍動員に反対 トランプ氏に反旗
7.欧州、雇用情勢に南北間格差 観光低迷が打撃に
8.豪、29年ぶり景気後退へ 入国禁止など響く
9.米、中国航空会社の米国便運航を禁止 16日から対抗措置
10.ロシア、8兆円で経済復興 改憲投票前に企業支援
1.日本電産、中国にEVモーター開発拠点 日本級の規模
日本電産は中国に駆動モーターの開発拠点を新設する。成長の柱と位置づける電気自動車(EV)用が中心で、2021年に稼働させる計画。人員規模は約1千人と日本の中核拠点と同規模になる見通し。米国との政治対立や新型コロナウイルスの感染問題で中国展開に慎重な企業も増えるなか、日本電産は中国を重要市場と位置づけている。米国も含めた複数の拠点整備で、現地の需要を取り込む。
2.中国、国家安全法施行へ準備加速 香港長官「支持」
中国政府は3日、香港政府トップの林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官を北京に呼び、香港で反中国共産党などの活動を禁じる「香港国家安全法」の施行への準備を加速すると伝達した。香港の高度な自由を保障する「一国二制度」を揺るがしかねないとして国際社会の批判を集めている同法だが、6月中の施行も視野に強行突破する構えだ。
3.「東京アラート」生活への影響は? 解除はいつ?
東京都は2日夜、新型コロナウイルスの感染再拡大の兆候があるとして都独自の警戒情報「東京アラート」を初めて発動した。東京湾のレインボーブリッジ、新宿の都庁を赤くライトアップし、都民らに感染防止対策の継続を求めた。東京アラートの意味や基準を整理する。
――東京アラートはなぜ必要なのか。
都内では4月中旬をピークに感染者が減少し、5月25日に政府による緊急事態宣言が解除された。ただ、大都市で人が動き始めると、瞬く間に感染が再拡大するおそれがある。再拡大すれば営業を再開した施設や店舗が再び休業に追い込まれ、経済的な打撃も大きくなるため、早期に警戒情報を出して再拡大を防ぐのが狙いだ。
――アラート発動の基準は?
都は発動にあたって(1)直近1週間平均の1日当たりの新規感染者数が20人以上(2)感染経路不明者の割合が50%以上(3)週単位の感染者数が増加――の3つの指標を設けている。いずれかの指標に当てはまった場合、病床の逼迫状況なども考慮して発動を判断することになっている。
都内では、緊急事態宣言が解除された5月25日前後から感染者が再び増加傾向になり、同29日以降は指標の(2)と(3)を満たしていた。感染が再拡大する「第2波」への兆候が見られるとして、都は6月2日に専門家の意見を聞いたうえで発動に踏み切った。
――生活への影響はあるのか。
発動によって都民の生活が具体的に制限されることはなく、あくまでも都による警戒の呼び掛けにとどまる。手洗いの徹底や3密(密閉、密集、密接)の危険がある場所に近づかないなどの対策を求め、事業者にはテレワークや時差出勤を行うよう呼び掛ける。
――休業要請の緩和措置は今後変わるのか。
都は緊急事態宣言の解除を受けて5月26日に事業者に対する休業要請の段階的緩和をスタートした。「ステップ1」として図書館や学校などの一部施設の再開を可能とし、6月1日には「ステップ2」として百貨店やショッピングモール、映画館など幅広い業種で休業要請を解除した。アラートの発動によって現在のステップ2の状況が変わることはない。
ただ、アラートが発動されている間、ネットカフェやカラオケ店など感染リスクが高いとされる施設・店舗への休業要請を解除する「ステップ3」には移行しない。
――アラートはいつ解除されるのか。
都によると、アラートを数日で解除することはなく、3つの指標を下回るなど感染者数が低水準で安定することが必要となる。週単位で感染状況を見極め、専門家の意見も聞いたうえで解除を決めるという。
逆に感染が再拡大した場合は再び施設や店舗に休業を要請し、緊急事態宣言の解除前の状態に戻る。都は(1)1日の新規感染者が50人以上(2)感染経路不明者の割合が50%以上(2)週単位で感染者が2倍になる――という目安を設けている。目安を超えた場合は専門家の見解を聞いたうえで再要請を判断する。
4.NYダウ続伸で始まる 221ドル高、米雇用指標を好感
3日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続伸して始まった。午前9時35分現在は前日比221ドル21セント高の2万5963ドル86セントで推移している。取引開始前に発表された民間の米雇用統計が市場予想ほど悪化せず、経済活動の再開で米景気が改善に向かっているとの見方が強まった。
雇用サービス会社ADPが発表した5月の全米雇用リポートでは、非農業部門の雇用者数が前月比276万人減となり、減少幅は市場予想(875万人減)を大きく下回った。経済活動の再開で、失業の拡大に歯止めが掛かりつつあると受け止められた。
白人警官による黒人暴行死事件を巡る抗議デモは2日夜も続いた。ただ、AP通信が3日、トランプ米大統領はデモ沈静化に向けた連邦軍の派遣を強行しないようだと報じ、衝突が一段と激化するとの懸念は和らいでいる。
ダウ平均の構成銘柄では業績が景気の影響を受けやすい化学のダウ、金融のJPモルガン・チェースが高い。航空機のボーイングやクレジットカードのアメリカン・エキスプレス(アメックス)も上げている。
5.カナダ中銀、政策金利を年0.25%で据え置き 2会合連続
カナダ銀行(中央銀行)は3日、政策金利である翌日物金利の誘導目標を現行の年0.25%で据え置くと発表した。据え置きは2会合連続。声明では新型コロナウイルスの世界経済への影響について「どのように回復できるか不透明感は強いままだが、ピークに達したようだ」との見解を示した。「金融状況は改善し、商品価格は過去数週間で上昇している」と説明した。
新型コロナウイルスのまん延と原油安を受け、カナダ中銀は3月に3回の0.5%の利下げに踏み切った。市場では経済活動の再開に伴ってカナダ景気が回復に向かうとの見方から、政策金利を据え置くとの予想が多かった。3日付で同中銀の総裁にマックレム氏が就いた。
6.米国防長官、連邦軍動員に反対 トランプ氏に反旗
米国で起きた白人警官の暴行による黒人死亡事件への抗議デモの一部が暴徒化していることへの対応を巡り、エスパー国防長官は3日の記者会見で連邦軍の動員に反対する考えを表明した。トランプ大統領が「強い大統領」を演出するために米軍を政治利用しているとの批判に配慮したものだ。トランプ氏は「デモ制圧」を目指しており、エスパー氏に反発する可能性がある。
エスパー氏は「(連邦軍の)現役部隊を治安維持の役割で使うのは最終手段であり、最も緊急かつ差し迫った状況に限られるべきだ」と指摘。「いまはそういう状況にはない」と断じた。トランプ氏は1日、デモ鎮圧に向けて州知事による州兵動員が不十分と判断すれば、自身の指揮下にある連邦軍を派遣する考えを示していた。
米メディアによると、エスパー氏は1日の州知事とのテレビ会議で抗議デモの状況を「戦場」と位置づけてトランプ氏による強硬措置に賛同する発言をしたが軌道修正した。国防総省によると、連邦軍に属する米兵1600人がすでに首都ワシントンの近郊に移動した。デモがいっそう暴徒化した場合に備えているが、これまでに治安維持活動は始めていない。
トランプ氏が1日にホワイトハウス前の教会を訪れて聖書を片手に写真撮影をした際にはエスパー氏も付き添った。写真撮影は保守派を支持基盤とするトランプ氏の選挙活動の一環で、同行は政治から中立であるべき国防長官として不適切だとの声が広がった。エスパー氏は3日の記者会見で「写真撮影があることは知らなかった」と釈明した。
7.欧州、雇用情勢に南北間格差 観光低迷が打撃に
欧州連合(EU)統計局が3日発表した4月のユーロ圏の失業率(速報値)は7.3%と前月から0.2ポイント上昇し、高止まりした。新型コロナウイルスの影響は、観光などサービス業への雇用依存度が高い南欧が大きく、統計に表れない失業者も増えており、南北間の格差が広がる傾向にある。各国は雇用対策を急ぐが、社会不安につながりかねない。
「外出制限をすぐやめろ」「政権は辞職せよ」。スペインのマドリードやバルセロナでは、サンチェス政権を批判するデモが散発している。同政権は21日まで非常事態宣言を延長する方針で、実現すれば3カ月超になる。国民は自らの生活基盤を揺るがす規制に不満を募らす。
スペイン労働省が2日発表した5月の失業者数は前月から約2万7千人増えた。5月は経済活動の一部が再開され、3、4月がそれぞれ30万人、28万人増えたのに比べると落ち着きつつはある。だが地元メディアによると、5月としては2008年以来の悪い水準だ。
ユーロ圏の失業率は3月の7.1%を直近の底に上昇に転じた。欧州委は20年通年で9.6%になると予測しており、各国とも一段と悪化する見通しだ。4月の国別をみると、スペインやフランス、キプロスやマルタなど南欧は悪化。一方、ドイツやオーストリアは3月と同水準だった。休業や勤務時間の短縮で減る就業者の賃金を補助するといった政府支援策が奏功したようだ。
雇用環境は公表値よりも悪いとみるのが一般的だ。例えばイタリアは3月の8.0%から6.3%に改善しているが、求職活動ができなかったり、就職を当面諦めたりした場合は失業者に算入されない。
伊国家統計局によると、労働人口に占める就職活動をしていない人の比率は4月に38.1%と11年以来の高水準に達した。イタリアだけでなく、新型コロナの影響で「学校閉鎖による子供の世話や求人激減で労働市場から一時的に離れる人は多い」(欧州系証券)。統計に反映されない事実上の失業者は多いとみられる。
南欧の失業率が北部欧州より高い要因は主に2つある。1つは外出制限や店舗閉鎖といった厳しい規制が長期間続いたことだ。ドイツは3月半ばに外出制限などの厳しい規制を導入し、4月下旬には緩和に動いた。一方、イタリアやスペインの厳格な規制は2カ月前後。外出制限や店舗休業が長引けば長引くほど景気は落ち込み、休業による収入減や企業の資金繰り悪化につながる。
2つ目は経済構造の違いだ。南欧では観光や小売り、飲食などが雇用の大きな受け皿になっている。世界旅行ツーリズム協議会によると、観光関連産業が全雇用に占める割合はギリシャが21.7%。イタリアとスペインもそれぞれ15%弱なのに対し、ドイツが13%、オランダは10%。新型コロナの影響は製造業よりサービス業が大きいため、失業率は上がりやすい。
とりわけ若者の失業率が上がりやすい。ユーロ圏の24歳以下の失業率は15.8%と3月から0.7ポイント上昇した。イタリアやスペインでは若者の職場の3〜4割が外食などのサービス関連という。同産業は有期雇用が多く「スキルの乏しい若者から契約を解除される」(欧州政策研究所のグロス調査部長)。マッキンゼー・アンド・カンパニーは4月下旬の報告書で、欧州の若者の41%に失業のリスクがあると警告した。
南欧では公式統計に反映されない「地下経済」で働く若者も多いとされる。イタリアでは350万人以上が社会保障制度に加入しなかったり、納税をしない地下経済で働いているとされ、安全網の枠外に置かれている。
失業した若者は反EUや反移民などの思想に走り、社会不安につながるリスクがある。シンクタンク「ブリューゲル」のジョルト・シニアフェローは「若者の失業はスキルが損なわれるのに加え、出生率と教育費にも影響する。長期的にも経済にマイナスになる」と懸念する。
8.豪、29年ぶり景気後退へ 入国禁止など響く
世界最長の経済成長を記録してきたオーストラリアが29年ぶりに景気後退に入ることが確実な情勢となった。3日発表の1〜3月期の国内総生産(GDP、実質)は前期比0.3%減と9年ぶりのマイナスとなった。新型コロナウイルス対策として導入した入国禁止や外出制限により、4〜6月期は一段の落ち込みが避けられない。
3日記者会見したフライデンバーグ財務相は「4〜6月期の減少幅は1〜3月期よりずっと大きくなる」と認めた。英調査会社、キャピタル・エコノミクスは4〜6月期の成長率がマイナス9%まで落ち込むと予想している。
豪州が一般的な景気後退の定義とされる「2四半期連続のマイナス成長」を最後に経験したのは1991年4〜6月期まで遡る。2000年代以降は中国がけん引した資源ブーム、その後は住宅ブームによる住宅関連事業が経済を下支えし、景気後退を回避してきた。
1〜3月期は新型コロナに加え、2019年末から深刻化した森林火災も響いた。GDPの約6割を占める個人消費は外食やレジャーサービスを中心に減少し、前期比1.1%減。34年ぶりの落ち込みを記録し、GDPを0.6ポイント押し下げた。
外国人の入国禁止も打撃となった。旅行サービスの輸出は19.9%減少し、輸出全体も3.5%低下した。豪州の大学連盟に当たる「ユニバーシティーズ・オーストラリア」は3日、留学生の減少などにより23年までの4年間で160億豪ドル(約1兆2千億円)の減収を見込むと発表した。
豪政府は3月以降、雇用維持や中小企業支援のため豪準備銀行と併せ、GDPの13%に相当する計2600億豪ドルの経済対策を打ち出した。7月末までには経済活動を再開する方針だ。オーストラリア・ニュージーランド銀行のシニアエコノミスト、フェリシティ・エメット氏は「V字回復は考えにくい。来年以降の成長のためにはさらなる景気刺激策が必要」と指摘する。
9.米、中国航空会社の米国便運航を禁止 16日から対抗措置
米運輸省は3日、中国の航空会社による米中間の運航便を16日から禁止すると発表した。米航空会社が新型コロナウイルスの影響で停止していた中国便の再開を中国政府に申請していたが、中国側が認めないため対抗措置を取るという。米中の対立が一段と激しくなっている。
中国の航空会社4社は、新型コロナの感染が拡大した後も大幅に減便したものの、米国との運航を一部続けてきた。運航を止めれば米中間の人の往来が一段と厳しく制限されることになる。
米国は新型コロナの感染抑制策のため中国に過去14日間滞在した外国人の入国を禁止している。ただ米国人は対象外となっている。
10.ロシア、8兆円で経済復興 改憲投票前に企業支援
ロシア政府は新型コロナウイルスで悪化した経済をテコ入れする。プーチン大統領に2日報告した2021年までの経済復興計画で、企業支援などに5兆ルーブル(8兆円弱)を投じる方針を盛りこんだ。プーチン氏の5選に道を開く憲法改正法案の是非を問う7月1日の全国投票を前に、景気底上げと生活の改善を国民に訴える狙いがある。
2020年06月02日
【経済ニュース 6/2 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です

さて何も言いません
株のバブル到来です・・・
買えーーーーwww
さて見出しです。
1.都、「東京アラート」発動 新たに34人が感染
2.キャッシュレス決済、手数料の開示義務化 競争促す
3.トランプ氏、軍投入辞さず 「暴動はテロ」州兵増員迫る
4.日経平均が続伸、終値263円高の2万2325円 買い戻し
5.米国株、ダウ続伸で始まる 米景気の回復期待根強く
6.英でファーウェイ排除論、新型コロナで中国に不信感
7.米GDP、11年間で7.9兆ドル下振れ CBOが長期予測
8.ロシアが内政締め付け、プーチン氏再選の憲法改正控え
9.中国、米産農産品輸入停止も 米報道 香港巡り瀬踏みか
10.中国外務省「米は内政干渉やめよ」、香港問題で対抗示唆
2.キャッシュレス決済、手数料の開示義務化 競争促す
3.トランプ氏、軍投入辞さず 「暴動はテロ」州兵増員迫る
4.日経平均が続伸、終値263円高の2万2325円 買い戻し
5.米国株、ダウ続伸で始まる 米景気の回復期待根強く
6.英でファーウェイ排除論、新型コロナで中国に不信感
7.米GDP、11年間で7.9兆ドル下振れ CBOが長期予測
8.ロシアが内政締め付け、プーチン氏再選の憲法改正控え
9.中国、米産農産品輸入停止も 米報道 香港巡り瀬踏みか
10.中国外務省「米は内政干渉やめよ」、香港問題で対抗示唆
1.都、「東京アラート」発動 新たに34人が感染
東京都は2日、新型コロナウイルスの感染者34人を新たに確認したと発表した。新規感染者が増加傾向にあることから、都は感染再拡大の兆候があるとして独自の警戒情報「東京アラート」を初めて発動した。
都は都民に求めていた外出自粛などを5月26日から段階的に緩和、6月1日には劇場や映画館、学習塾など幅広い業種への休業要請を解除したばかりだった。
小池百合子知事は2日の都議会で「より一層外出を、特に夜の街への外出を控えてもらうことをお願いする」と述べた。
都はアラートを発動するに当たり、直近1週間平均の1日当たりの新規感染者数が20人以上▽感染経路不明者の割合が50%以上▽週単位の感染者数が増加――を主な指標としている。
指標のいずれかを満たせば発動の検討に入り、医療提供体制や感染拡大の兆候を加味しながら要否を判断する。5月29日には3つの主な指標のうち、感染経路不明者の割合と週単位の感染者数で基準を超えていた。
感染者数も同月下旬以降は増加傾向で、20〜30代などの若い世代が夜の繁華街で感染する事例が目立っている。6月2日までの1週間の感染者114人のうち約3割に当たる32人が夜の繁華街での感染者だった。
アラートの発動で、百貨店やショッピングモール、スポーツジムなどに対する休業要請の緩和措置が即座に取り消されるわけではない。都はさらなる感染の拡大を防ぐため、まずは都民に外出自粛などを呼び掛けて警戒を求める。
それでも感染者数の増加に歯止めがかからず、直近1週間平均の1日当たりの新規感染者数が50人以上▽感染経路不明者の割合が50%以上▽週単位の感染者数が2倍以上――などとなった場合は、専門家の見解も聞いたうえで、飲食店の短縮営業や商業施設の休業を再要請する。
2.キャッシュレス決済、手数料の開示義務化 競争促す
政府はキャッシュレス決済の事業者が加盟店から受け取る手数料について開示するよう義務付ける。消費税増税にあわせて導入したポイント還元制度は手数料に上限を設けたが、同制度は月内に終わる。7月以降は再び手数料が上がる可能性が高い。決済業者間の差を開示させることで競争を促し、小売店が比較や選別をしやすくする狙いだ。
3.トランプ氏、軍投入辞さず 「暴動はテロ」州兵増員迫る
トランプ米大統領は1日、ホワイトハウスで全米向けに演説し、白人警官の暴行による黒人死亡事件をきっかけに全米で起きる暴動の鎮圧に向け「各州知事に街頭を占拠するのに必要な数だけ州兵を出動させるよう求めた」と明らかにした。州兵の投入が不十分と判断すれば大統領の指揮下にある連邦軍を派遣する考えを示した。一段と強硬な姿勢を示せば、デモ参加者らがかえって反発し、事態の収拾が見通せなくなる可能性はある。
演説は約6分間。トランプ氏は「私は法と秩序を尊重する大統領だ」と主張した。「米国はプロの無政府主義者や暴力集団、略奪者らに支配されている」と語り、各州の知事によるデモへの対処は弱腰だと批判した。暴徒化した一部のデモ参加者を「国内テロ活動だ」と糾弾し、徹底的に取り締まる考えを示した。
ニューヨーク州のクオモ知事はトランプ氏の演説を「恥ずべきこと」とツイッターで非難した。
トランプ氏は演説に先立ち、全米の州知事とテレビ会議に臨んだ。複数の米メディアによるとトランプ氏は「抗議デモを制圧せよ」と繰り返し強調した。「そうしないとあなたがたはひどい愚か者になる。(暴徒化した抗議者を)逮捕し、裁判にかけ、長期にわたり刑務所で拘束すべきだ」と主張した。「石を投げた者は銃を発砲した者と同じ。そうした人に報復すべきだ」とも指摘した。
首都ワシントンでは5月31日に続き、米東部時間1日午後7時(日本時間2日午前8時)に外出禁止令が発効。ニューヨーク市も午後11時から外出を禁止。米メディアによると、抗議デモはこれまでに少なくとも140都市に広がり、一部のデモ隊が暴徒化して店舗の略奪も起きている。
米国防総省によると、1日午前時点で州知事の監督下にある1万7000人以上の州兵(ナショナルガード)が23州と首都ワシントンで動員された。動員規模は前日に比べて3.4倍に増えたが、トランプ氏はさらに増やすよう求めた形だ。
議会調査局によると、連邦政府の指揮下にある連邦軍は原則として国内の治安維持活動をできないが、暴動法は公民権擁護などを目的とした派遣を例外的に認めている。トランプ氏は州政府の対応が手ぬるいと判断すればこの法律を使って軍を派遣する構えだ。この法律が適用されれば1992年に白人警官による黒人暴行などをきっかけに起きたロサンゼルス暴動に対処して以来だ。
ワシントンではトランプ氏の演説直前、警官隊らがホワイトハウス前で活動していたデモ隊に対して催涙弾を相次いで発射。一帯の道路を一気に制圧した。トランプ氏は演説を終えるとホワイトハウスから徒歩で近くの教会を訪れた。記者団に対し、聖書を片手に「安全を守る」と語った。危機下での教会訪問は支持基盤の保守派の求心力を保つ狙いがありそうだ。
4.日経平均が続伸、終値263円高の2万2325円 買い戻し
2日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、前日比263円22銭(1.19%)高の2万2325円61銭と2月26日以来、約3カ月ぶりの高値水準で終えた。5月の米製造業景況感指数が前月比で4カ月ぶりに上昇したことで、米国などの景気が回復に向かうとの見方が強まった。新型コロナウイルスの「第2波」を予想して株式を売り持ちしていたヘッジファンドなど、海外投資家による日本株の買い戻しが継続した。後場にかけては一段高となり、上げ幅は一時300円を超えた。
きょうの日本株は、アジアの主要株価指数や日本時間2日のシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の米株価指数先物との比較でも強さが目立った。「欧米などと比較した経済活動再開の遅れから日本株は売られてきただけに、買い戻しの動きも強い」(国内証券のストラテジスト)との指摘が聞かれた。
一方、白人警官の暴行による黒人死亡事件を巡る米国の抗議デモが、経済活動回復の遅れや新型コロナの感染再拡大につながるとの見方は、相場で一定の重荷となった。
JPX日経インデックス400は続伸した。終値は前日比169.18ポイント(1.20%)高の1万4301.63だった。東証株価指数(TOPIX)も続伸し、18.93ポイント(1.21%)高の1587.68で終えた。業種別TOPIXは証券商品先物や不動産業、機械などの景気敏感業種が上昇した。
5.米国株、ダウ続伸で始まる 米景気の回復期待根強く
2日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸して始まった。午前9時35分現在、前日比117ドル72セント高の2万5592ドル74セントで推移している。米経済活動が段階的に再開して景気が回復に向かうとの期待が根強く、買いが先行した。白人警官の暴行による黒人死亡事件を巡る抗議デモが続いているが、現時点では企業収益を圧迫する要因になるとはみなされていない。
米経済再開への期待から、内需の景気敏感株である金融株への買いが続いている。旅客需要が改善するとの見方から空運株も軒並み上昇し、航空機のボーイングも買いが先行した。石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアなど非加盟国が協調減産を延長する方針と伝わり、原油先物相場が上昇して石油株のエクソンモービルなども高い。
全米で拡大している抗議デモは一部が暴徒化し、1日はニューヨーク市も夜間外出禁止令を出した。トランプ米大統領は1日、抗議デモの鎮圧にあたって連邦軍の投入も辞さない方針を示した。現時点では売り材料にはなっていないが、混乱が夏にかけても続くようなら、経済再開に水を差しかねないとの警戒感も出ている。
6.英でファーウェイ排除論、新型コロナで中国に不信感
英国政府内で、次世代通信規格「5G」から中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)を排除すべきだとの声が高まっている。新型コロナウイルスの感染拡大で、中国への不信感が急速に増しているためだ。一度は押しのけた米からのファーウェイ排除要請に応じる形になれば、同社製品を採用する欧州各国の判断にも影響しそうだ。
7.米GDP、11年間で7.9兆ドル下振れ CBOが長期予測
米議会予算局(CBO)は1日、新型コロナウイルスによる景気悪化で、2030年までの実質国内総生産(GDP)が11年間の累積で当初予測比7.9兆ドル(約850兆円)下振れするとの試算を公表した。累積GDPの3%分に相当する。米GDPは20年に戦後最大のマイナス成長が予測されるが、10年かけても傷痕を完全に穴埋めできないと指摘する。
CBOは5月19日に、新型コロナの影響を織り込んだ経済見通しを公表し、20年の成長率をマイナス5.6%と予測した。1月時点の予測では20年がプラス2.2%としていた。19年の米GDPは約21兆ドルだった。
CBOが1日公表した長期試算では、2030年までの米経済の回復経路を分析。1月時点では20年から30年までの11年間分の累積GDPを290兆ドル強とみていたが、20年の大幅な落ち込みが影響して、3%に相当する7.9兆ドル分下振れすると予測した。一度小さくなったGDPは、すぐには完全復元しないことを示している。
生活実感に近い名目GDPは、さらに下振れ幅が大きい。20年のインフレ率が0.6%にとどまると予測され、物価の上昇圧力も当初予測に比べて大幅に弱まるためだ。名目GDPの下振れ幅は、11年間の累積で5.3%分に相当する15.7兆ドルに達するという。
CBOは党派中立の組織で、試算は連邦議会の予算編成に使われる。GDPの急回復が見込めないため、議会ではインフラ投資や大型減税など、追加経済対策の議論が始まった。一方で名目GDPが大きく落ち込めば、税収の回復も見込めず、財政悪化の懸念は強まる。CBOは1日の長期予測を基に、さらに税収など歳出入の試算も近く公表する見通しだ。
8.ロシアが内政締め付け、プーチン氏再選の憲法改正控え
ロシアのプーチン政権が内政の締め付けを強化している。議会が有力な野党候補の排除や警察の権限強化を可能にする法改正を急ぐ一方、警察は1日までにモスクワで抗議行動の参加者30人以上を拘束した。プーチン大統領の5選出馬に道を開く憲法改正法案の全国投票を7月1日に控え、反政権運動が広がることに警戒を強めている。
9.中国、米産農産品輸入停止も 米報道 香港巡り瀬踏みか
米ブルームバーグ通信は1日、中国政府が大豆や豚肉など米国産農産品の輸入を一時的に停止するよう中国国有企業に命じたと報じた。米トランプ政権の香港問題での出方を中国側が瀬踏みしている可能性がある。
報道によると、複数の大手国有企業が大豆を含む米国産農産品の輸入を一時停止するよう命じられたほか、一部のバイヤーは米国産豚肉の輸入を取り消した。トランプ米大統領が29日に「香港国家安全法」の制定方針を批判し、香港に認めている関税などの優遇措置を取り消す考えを示したことが背景にあるという。
ただ、トランプ氏の29日の演説について、中国では「予想したほど強硬ではなかった」との受け止めが少なくない。関税や査証(ビザ)などの優遇措置をいつからどう取り消すかなど具体策に言及しなかったほか、市場が「最悪の事態」と懸念していた貿易協議の「第1段階合意」の破棄も口にしなかったからだ。
貿易協議の経緯を知る国務院(政府)関係者は「全米での暴動問題もあり、いまは強硬姿勢を取るのに最適な時期ではないとトランプ氏も判断したのではないか」とみる。今回も香港問題で厳しい対中制裁を打ち出さないようけん制するため、米国にゆさぶりをかける戦術の一環とみられる。
米中は現時点では第1段階合意を履行する方針を崩していない。新型コロナウイルスで中国側の輸入の進展は遅れるが、米通商代表部と米農務省は5月21日、中国の対応を評価する声明を出した。中国の李克強(リー・クォーチャン)首相も政府活動報告で「第1段階合意を米中共同で実行する」と述べていた。
第1段階合意では中国側の輸入が目標に達しなければ、米国がいつでも制裁関税をかけられる。トランプ氏は票田である農家の支持を左右する農産物の動きに敏感で、中国側も輸入を全面停止すれば厳しい報復を受ける覚悟を迫られる。今回の報道を主要な中国メディアは転電しておらず、国内で反米感情が高まりすぎないよう神経を使っていることもうかがえる。
10.中国外務省「米は内政干渉やめよ」、香港問題で対抗示唆
中国外務省の趙立堅副報道局長は1日の記者会見で、トランプ米大統領が香港優遇措置の廃止を打ち出したのは「内政干渉で中米関係を損なう」と反発した。「中国側の利益を損なう米国の言動は断固たる反撃に遭うだろう」と話した。対抗措置を示唆したものの、具体的内容には触れなかった。
トランプ米大統領が29日に記者会見して、中国政府として反応を示したのは初めて。これまでの中国外務省のコメントから大きな変更はなく、米国への対応を慎重に検討しているとみられる。
米国が世界保健機関(WHO)脱退を宣言したことについて「自分勝手に責任から逃れるもので、感染症対応の国際協力を壊す行為だ」と非難した。
米白人警官の暴行による黒人死亡事件で米国で抗議活動が拡大していることに関し「なぜ米国は香港の暴徒を英雄として美化し、自国の抗議活動への参加者を暴徒と呼ぶのか」と指摘した。中国の国営メディアなどは米国での抗議活動を大々的に伝えている。
2020年06月01日
【経済ニュース 6/1 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんわ
ひも子です
さてミネアポリスでの暴動が騒がれていますが市場への影響は限定的ですね。
今日の見出しです。
1.NYダウ続落で始まる 抗議デモ拡大、経済再開に不透明感
2.米デモ、40超の都市で夜間外出禁止 50年ぶり規模
3.コロナ債、世界で13兆円規模 10カ国が国債で費用調達
4.中国景況感、回復鈍る 5月、輸出が不振
5.英・EU、「移行期間」の延長焦点 2日から山場の交渉
6.G7サミット延期、9月以降に トランプ氏意向
2.米デモ、40超の都市で夜間外出禁止 50年ぶり規模
3.コロナ債、世界で13兆円規模 10カ国が国債で費用調達
4.中国景況感、回復鈍る 5月、輸出が不振
5.英・EU、「移行期間」の延長焦点 2日から山場の交渉
6.G7サミット延期、9月以降に トランプ氏意向
1.NYダウ続落で始まる 抗議デモ拡大、経済再開に不透明感
1日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続落して始まった。午前9時35分現在、前週末比118ドル83セント安の2万5264ドル28セントで推移している。白人警官の暴行による黒人死亡事件への抗議デモが全米で広がっており、経済再開に水を差すとの見方が出た。米中対立も投資家心理の悪化つながっている。
抗議デモは全米の140都市以上に拡大し、首都ワシントンやサンフランシスコなど40超の都市で夜間外出禁止令が出された。小売り大手ウォルマートやターゲットは店舗の一時閉鎖や営業時間の短縮を迫られた。
米ブルームバーグ通信は1日、中国政府が国営企業に対して大豆や豚肉など米国産農産品の輸入を一時的に停止するように命じたと報じた。トランプ米大統領が香港に認めている関税などの優遇措置を取り消す考えを示したことへの対抗措置という。米中は現時点では1月の貿易協議の第1段階の合意を履行する方針を崩していないが、米中関係の不透明感が高まった。
ただ、下値は堅く、ダウ平均は小幅高に転じる場面もあった。各国での経済再開に伴う景気回復期待が相場を支えている。
新型コロナウイルスの治験薬で治験の最終段階である第3相試験で優位な結果が出なかったと発表したギリアド・サイエンシズは下落した。製薬のファイザーも大幅安。
2.米デモ、40超の都市で夜間外出禁止 50年ぶり規模
白人警官の暴行による黒人死亡事件への抗議デモが5月31日、全米でさらに広がった。米メディアによると、抗議デモは少なくとも140都市におよび、首都ワシントンやサンフランシスコなど40超の都市で夜間外出禁止令が出された。外出禁止令の広がりは公民権運動を主導したキング牧師の暗殺が起きた1968年以来、約50年ぶりの規模だという。
首都ワシントンではホワイトハウス周辺の教会や労組ビルが相次いで放火された。警察隊はデモ隊に催涙弾を発射し、ペットボトルを投げた人々が次々と拘束された。シークレットサービスは31日、ホワイトハウス周辺を警護していた警官60人以上が負傷したと明らかにした。
各州は治安維持に向けて州兵(ナショナルガード)の動員に乗り出した。国防総省によると、31日午前時点で首都と15州で5000人が動員された。トランプ大統領は連邦政府の軍に属する憲兵隊の派遣も視野に入れる。国内の治安維持目的での連邦軍派遣は1807年に成立した暴動法で認められている。同法の適用に踏み切れば黒人に暴行した白人警官が無罪となり1992年に起きたロサンゼルス暴動に対処して以来となる。
3.コロナ債、世界で13兆円規模 10カ国が国債で費用調達
世界的な金融緩和の中で、新型コロナウイルス対策を掲げる債券(コロナ債)に資金が集まっている。医療体制の整備や企業の資金繰り支援などを目的に、発行は国際機関から国家へと広がる。ESG(環境・社会・企業統治)重視に変わりつつある機関投資家にとっても投資しやすく、世界での発行額は13兆円を超えたが、実際の使い道の監視など課題もある。
4.中国景況感、回復鈍る 5月、輸出が不振
中国国家統計局と中国物流購入連合会が31日発表した2020年5月の製造業の購買担当者景気指数(PMI)は、前月比0.2ポイント低い50.6だった。拡大・縮小の節目となる「50」は3カ月連続で上回ったが、水準は2カ月連続で下がった。輸出不振などで景況感の回復ペースが鈍っている。
PMIは製造業3千社へのアンケート調査で算出する。生産や新規受注の指数が50を上回れば前月と比べて拡大、50を下回れば縮小を示す。
PMIは新型コロナウイルスで2月に35.7と過去最低を記録したが、3月は52まで回復した。4、5月と2カ月連続で水準を切り下げており、景況感は回復しているが、その勢いは鈍っていることを示唆している。
5月は柱の生産が53.2と前月より0.5ポイント下がった。もう1つの柱の新規受注は前月より0.7ポイント高い50.9に上昇したものの、依然として生産を大きく下回る。
国務院発展研究センターの張立群研究員は「需要不足が生産の足かせであることをはっきり示している」と指摘する。今回の調査でも企業が直面する課題を聞くと「需要不足」と答えた企業の割合は50%を超え、比率が最も高かった。
とくに海外需要の不振が鮮明だ。輸出に限った新規受注は前月比1.8ポイント高い35.3だった。20年1月から5カ月連続で節目の50を下回った。外需が縮小し続けていることを示しており、今後の輸出は大幅に落ちこむことが予想される。
気がかりなのは3、4月と50を上回った従業員の指数が、5月は49.4と再び50を下回ったこと。従業員の数が前月よりも減ったことを示唆しており、雇用保持を経済政策の筆頭に掲げる習近平(シー・ジンピン)指導部には試練になる。
一方、同時に発表した非製造業のPMIは前月比0.4ポイント高い53.6に上昇した。節目の50を上回るのは3カ月連続で、PMIの水準自体も3カ月連続で上昇した。もっとも、内訳をみると建設業のPMIが前月比1.1ポイント高い60.8と大幅に改善した一方、小売りや飲食などサービス業のPMIは同0.2ポイント高い52.3にとどまった。
建設業には景気対策でインフラ工事が拡大した恩恵が及ぶ一方、新型コロナの打撃が最も深刻なサービス業は景況感の回復が鈍いままだ。
5.英・EU、「移行期間」の延長焦点 2日から山場の交渉
欧州連合(EU)を離脱した英国とEUによる自由貿易協定(FTA)など将来関係を巡る山場の第4回交渉が2日から開かれる。交渉妥結の見通しは立っておらず、新型コロナウイルスで悪化した経済への新たなリスクを防ぐために、移行期間を延ばすかどうかが焦点になる。英・EUの取り決めで6月末までに延長の是非の判断が必要だが、英国は延長拒否の姿勢を貫いている。
6.G7サミット延期、9月以降に トランプ氏意向
トランプ米大統領は30日、6月下旬にワシントンでの開催をめざしていた主要7カ国首脳会議(G7サミット)を9月に延期する意向を明らかにした。ロシアと韓国、オーストラリア、インドの招待も計画していると表明し「G10、G11になるかもしれない」と述べた。G7の枠組みを巡る議論が再燃しそうだ。
大統領専用機内で記者団に語った。2020年は米国がG7の議長国を務める。安倍晋三首相は出席の意向を表明したが、ドイツのメディアによるとメルケル独首相は訪米しない方針を示した。
トランプ氏はG7の枠組みについて「世界を適切に代表しているとは思えない。時代遅れの集まりだ」と述べ、枠組みの拡大が必要との認識を示した。ウクライナのクリミア半島併合への対抗措置として14年に主要8カ国(G8)から追放されたロシアを復帰させるべきだとかねて主張してきた。
開催時期に関しては、国連総会が予定される9月中旬ごろの可能性に言及した。ただ、11月3日投開票の米大統領選の後になるかもしれないとも述べた。
トランプ氏周辺によると、今回の枠組み拡大には中国にどう対処するかを議論する狙いもあるという。同氏は米国で多数の死者を出している新型コロナウイルスの感染拡大で中国責任論を唱えており、大統領選の集票狙いで対中強硬に傾斜している。選挙に近い時期に有権者に自らの姿勢をアピールする狙いもうかがえる。
G7サミットは6月10〜12日にワシントン近郊の大統領山荘「キャンプデービッド」で開く予定だったが、新型コロナの影響でテレビ会議方式による開催に変更された。その後、トランプ氏が再び対面式の開催に意欲を示して6月25、26両日にホワイトハウスで開く方向で調整が進んでいた。
2020年05月29日
【経済ニュース 5/29 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
さて今日は月末でしかも週末という事で投資家も持ち高整理の売りが考えられます
ただこの無限の金融緩和の相場の中では来週もイエイケムードを考えて持ち越しする人も
多いのかもしれませんね
では今日の見出しです。
1.米欧企業が配当抑制 当局、コロナの支援対象に要請
2.コロナ、雇用・生産直撃 鉱工業過去最大の9.1%低下
3.年金改革法が成立
4.米、香港優遇見直し焦点に 金融・貿易地位揺らぐか
5.日経平均5日ぶり反落、終値38円安 米中関係悪化を警戒
6.英、香港住民の滞在期間拡充へ 国家安全法に抗議
7.NYダウ続落、一時100ドル超安 米中関係の悪化警戒
8.トランプ氏、SNS規制強化へ大統領令 投稿監視けん制トランプ政権 ネット・IT 北米
1.米欧企業が配当抑制 当局、コロナの支援対象に要請
米欧の政府や中央銀行が株主還元に厳しい目を向けている。新型コロナウイルスによる資金繰りの悪化で政府支援を受けた企業の配当を禁止するほか、銀行には融資のために資本を厚く保つよう株主還元の停止を要請している。各国のコロナ対策費が株主に流れるのを防ぐ狙いがある。従業員の給与や手元資金より還元を重視する株主至上主義からの転換をコロナが強める側面があり、増加してきた世界の配当は今年度に2〜3割減少する
2.コロナ、雇用・生産直撃 鉱工業過去最大の9.1%低下
新型コロナウイルスの感染拡大による影響が雇用や生産を直撃している。総務省が29日発表した4月の休業者数は597万人と過去最多だった。非正規の職員・従業員数(実数ベース)は前年同月比で97万人減少した。経済産業省が29日発表した4月の鉱工業生産指数速報(2015年=100、季節調整済み)は前月比9.1%低下し87.1と大幅に低下した。
4月の休業者数は597万人で、前年同月比で420万人増えた。リーマン・ショック直後の休業者数は100万人程度で異例の伸び幅だった。休業者は失業には至っていないが、仕事を休んでいる人を指す。
4月の完全失業率(季節調整値)は2.6%で前月から0.1ポイント悪化した。完全失業者数は178万人で6万人増えた。就業者数は非正規労働者を中心に前月に比べ107万人減少した。1963年1月以来の下げ幅となった。
景気の悪化が長引けば、企業は休業者を雇い続けるのは難しくなる。失業していても新型コロナウイルスの感染拡大の影響で求職活動をしていない人も多い。2.6%にとどまっている失業率は今後、跳ね上がる可能性がある。
厚生労働省が29日発表した4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.32倍で前月から0.07ポイント低下した。16年3月以来、4年1カ月ぶりの低水準となった。景気の先行指標となる新規求人は前年同月比で31.9%減と09年5月以来、10年11カ月ぶりの下げ幅となった。
生産指標も大幅に悪化した。4月の鉱工業生産は現行基準で最大の下げ幅だった。基準年が異なるため単純比較はできないものの、下げ幅はリーマン・ショック後の8.8%低下(09年1月)より大きかった。東日本大震災発生時の16.5%低下(11年3月)よりは小さかった。経産省は基調判断を「生産は急速に低下」に下方修正した。
15業種中14業種が低下した。自動車は前月比33.3%低下した。国内外で需要が低迷し、部品調達の停滞や工場の稼働停止も影響した。自動車メーカーの減産などが波及し、鉄鋼・非鉄金属工業も14.3%低下した。航空機部品を含む輸送機械工業は25%低下した。
メーカーの先行き予測をまとめた製造工業生産予測調査によると、5月は前月比4.1%の低下、6月は同3.9%の上昇を見込む。輸送機械工業などを中心に増産が予想されている。経産省は「先行きを見通すのは難しく、少なくとも6月までは低い生産水準で推移する」と分析している。
3.年金改革法が成立
公的・私的年金の改革法が29日の国会で成立した。公的年金では繰り下げ受給開始時期の選択肢拡大、私的年金では個人型確定拠出年金(イデコ)の拡充など、長寿化の中で個人の老後資金に大きな影響を与える項目が目白押し。
パートなど短時間労働者への厚生年金適用拡大を柱とした年金制度改革関連法が29日の参院本会議で、与野党の賛成多数で可決、成立した。加入義務がある企業の規模を、現在の「従業員数501人以上」から2022年10月に「101人以上」、24年10月に「51人以上」まで段階的に拡大。全世代型社会保障の実現に向け、高齢者や女性を念頭に制度の支え手を増やす狙い。
また、高齢者の就労を後押しするため、60〜70歳の間で選べる年金の受給開始時期について、22年4月から60〜75歳に広げる。66歳以降に繰り下げ受給すると月0・7%ずつ上乗せされ、75歳まで繰り下げた場合は月額で84%増となる。
一定以上の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金」は、60〜64歳で「月収28万円超」から65歳以上と同じ「月収47万円超」に引き上げる。高齢者の働く意欲をそいでいるとの指摘を受けて見直す。
4.米、香港優遇見直し焦点に 金融・貿易地位揺らぐか
トランプ米大統領は29日、中国への米国の対応措置について発表する。中国が香港への統制強化を決めたのを受け、制裁を含めた対応を明らかにする可能性がある。米国が一国二制度に基づく「高度な自治」を前提に香港に認めてきた優遇措置の見直しに踏み込むかどうかが焦点だ。ヒトやモノの流れに打撃を与えれば、アジアの金融・貿易のハブとしての地位が揺らぐ。
中国が香港国家安全法の制定を決めたのを受け、トランプ政権は香港が「高度な自治」を維持できていないと判断。香港の優遇措置は継続困難との見解を米議会に伝達した。
優遇措置は主に関税と査証(ビザ)発給の2つがある。
影響が大きいのはビザ発給の見直しだ。香港には米国企業約1300社が拠点を構え、アジア全域を統括する機能を持つケースも少なくない。香港在住者は中国本土と比べて簡単に米国ビザを取得できる。香港から米国への渡航者は2019年に15万人に上った。人の往来が制限されれば、企業活動に打撃になる。
貿易への影響は複雑だ。米国は「香港政策法」で香港を「経済・貿易面で(中国本土とは)別の地域として扱う」と明記し、対中制裁関税を適用していない。
ただ、香港から米国への輸出額3040億香港ドル(約4兆2千億円、19年)のうち77%は中国本土から香港を経由して米国に向かう再輸出だ。大半は原産地が中国だとして、すでに制裁関税の対象になっているとみられる。輸出に占める米国向けの割合は約8%で、米国が関税を上げたとしても「マクロ経済への影響は大きくない」(英調査会社オックスフォード・エコノミクス)。
一方、米国から香港への輸入額は2129億香港ドルで、電子機器などが多い。軍事技術に転用可能な半導体などを香港経由で仕入れる中国企業が多い。米国が香港への輸出管理を厳しくすれば、こうした取引に影響が出る。
「香港と中国を決済ネットワークから締め出すべきだ」(中国に関する現在の危機委員会)。米国の保守派の団体には、国際的な資金決済のネットワークである国際銀行間通信協会(SWIFT)の利用停止などを求める声もある。金融制裁に踏み込めば、アジアの金融センターである香港への影響は甚大だ。
香港は金融市場に強みを持つ。新規株式公開(IPO)を通じた企業の資金調達額は18、19年に世界1位だった。仏ナティクシスによると、10〜18年の中国企業のオフショア市場での資金調達のうち株式は73%、債券は60%が香港市場だ。香港の金融機能を止めれば世界の金融市場は混乱が必至だ。市場で存在感を高める中国企業への打撃にとどまらず、米金融機関のビジネスにも大きな影響が及ぶ。
香港は北朝鮮やイランと違って、世界経済と密接につながる。香港への制裁は中国企業だけでなく、香港企業や香港で活動する米企業にも影響が及ぶため、トランプ政権は慎重に検討するとみられる。
これとは別に、中国の政府当局者や企業への資産凍結などの制裁なども浮上している。スティルウェル米国務次官補は「対応措置には長大なリストがある」と述べ、経済制裁や中国当局者へのビザ停止などを具体例に挙げる。
米国の対中強硬姿勢は強まるばかりだ。米紙ニューヨーク・タイムズによると、トランプ政権は米国に滞在する中国人の留学生や研究者のビザの効力の停止を検討している。大学院生ら約3千人が対象になるという。
米議会では中国・新疆ウイグル自治区で少数民族への弾圧に関わった中国の当局者に制裁を科すよう米政権に求めるウイグル人権法案が可決済みだ。
5.日経平均5日ぶり反落、終値38円安 米中関係悪化を警戒
29日の東京株式市場で日経平均株価は5営業日ぶりに反落し、前日比38円42銭(0.18%)安の2万1877円89銭で終えた。反体制活動を禁じる「香港国家安全法」の制定方針を中国が28日に採択したのを受け、米中関係が一段と冷え込むとの警戒感から下げ幅は一時200円を超えた。
29日にはトランプ米大統領が対中政策に関する記者会見を開く見通しで、制裁強化で世界経済の回復が遅れるとの不安が投資家心理の重荷となった。日経平均は28日までの4営業日で1500円超上昇していたため、短期的な過熱感から利益確定売りが出やすい面もあった。
東京都が6月から新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業要請を緩和する方向となり、経済活動の再開期待が支えとなった。海外の短期筋などによる買い戻しも下値を支え、日経平均は上昇に転じる場面もあった。ファーストリテイリングと中外製薬、第一三共の3銘柄で日経平均を100円超下支えした。
JPX日経インデックス400は5営業日ぶりに反落し、終値は前日比116.63ポイント(0.82%)安の1万4078.89だった。東証株価指数(TOPIX)も5営業日ぶりに反落し、13.67ポイント(0.87%)安の1563.67で終えた。
東証1部の売買代金は概算で4兆6423億円に達した。株価指数を開発・算出するMSCIによる株価指数への採用銘柄変更に伴う売買が膨らんだ。売買高は23億8386万株だった。東証1部の値下がり銘柄数は1438と、全体の6割超だった。値上がりは674銘柄、変わらずは58銘柄だった。
前日に決算を発表した日産自が10%を超える下落となったほか、トヨタやホンダ、三菱自などほかの自動車株も売られた。ニコンやコニカミノル、川崎汽や商船三井も大幅安。半面、エーザイや塩野義が買われた。ヤマトHDも高い。
6.英、香港住民の滞在期間拡充へ 国家安全法に抗議
英政府は28日、中国政府が香港の自治への関与につながる「香港国家安全法」を撤回しない場合、英国発行のパスポートを持つ香港住民の英滞在可能期間を、現行の6カ月から1年に延ばす方針を明らかにした。英国での就職などの機会を増やし、市民権取得につなげる。香港の自治崩壊に備えて住民の受け入れ姿勢を示すことで、国家安全法へ抗議する狙いだ。
7.NYダウ続落、一時100ドル超安 米中関係の悪化警戒
29日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続落して始まった。午前9時35分現在、前日比114ドル98セント安の2万5285ドル66セントで推移している。トランプ米大統領は中国への米国の対応措置について29日に発表する。中国による香港への統制強化を受けた措置に関した内容になる可能性があり、米中対立への懸念から売りが出ている。
中国が28日に全国人民代表大会で反体制活動を禁じる「香港国家安全法」の制定方針を採択したことに伴い、米政権は対中制裁を科す見通しだ。トランプ氏が中国の責任論を唱える新型コロナウイルスの感染拡大への報復も念頭にあるとみられている。中国は米国が制裁に動けば報復措置をとる構えで、米中対立が一段と激しさを増す。
朝方に米商務省が発表した4月の個人所得は前月比10.5%増だった。新型コロナの影響で失業者が大きく増えたものの、失われた労働所得を上回る失業保険の給付が影響した。もっとも、感染抑制のための外出規制や店舗の一時休業で個人消費支出(PCE)は13.6%減少し、統計開始の1959年以来過去最大の下げ幅だった。所得増加と消費減少で個人貯蓄率は33%に急上昇した。「経済再開で夏にかけ個人消費は強含む」(CIBCキャピタル・マーケッツ)との指摘もあった。
建機のキャタピラーと化学のダウが下落した。金融のゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェースも安い。一方、ソフトウエアのマイクロソフトや半導体のインテルなど主力ハイテク株は高い。
8.トランプ氏、SNS規制強化へ大統領令 投稿監視けん制トランプ政権 ネット・IT 北米
トランプ米大統領は28日、ツイッターなどのSNS(交流サイト)の規制強化に向けた大統領令に署名した。SNS運営企業が政治的理由などから投稿を制限したり、削除したりした場合に、利用者らが企業に法的責任を問えるようにする案を検討する。SNS企業による利用者の監視をけん制する狙いがある。ただ実効性は不透明なうえ、言論の自由を侵害するとみなされて、政府に対する訴訟が起きる公算が大きい。
トランプ氏は同日、ホワイトハウスで記者団に対し、SNS企業を念頭に「最大の脅威の一つから言論の自由を守るために我々はここにいる」と強調した。ツイッターがトランプ氏の投稿に事実誤認の疑いがあるとして注意喚起したことに関し「政治的行動だ」と主張し、トランプ氏の信頼をおとしめるための工作活動だとの見方を示した。
米でSNSでの投稿を巡っては、「通信品位法」でSNS企業による不適切な投稿の閲覧制限や削除など内容を精査する権限を付与している。投稿削除などで利用者から訴訟を起こされた場合も法的責任を問われることがないよう企業は原則保護されている。
トランプ氏が今回署名した大統領令では、こうした免責の対象を狭めることを意図している。SNS企業に対する訴訟を起こしやすい環境をつくり、利用者の投稿や活動に対する介入を抑える狙いがある。
ただ大統領令だけでは通信品位法を覆すことはできず、トランプ氏が期待するような実効性が担保できるかは不明だ。トランプ氏も抜本的な制度の見直しには議会による新たな立法措置が必要だと認め、議会に規制強化に協力するよう求めていくと説明しているが、民主党の協力を得るのも容易ではない。
2020年05月28日
【経済ニュース 5/28 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
さて全人代が閉幕して国家安全法が採決されてしまいました
これにより香港でもの悪化や米欧からの反発は強まりそうですね
そしてEUではユーロボンドの発行
様々な事が起こっております
そんな今晩は米国のGDPと新規失業保険申請件数と失業保険継続受給者数発表
株価指数もその様子見といった静まりです。
では見出しです。
1.日産最終赤字6712億円、20年ぶり規模 「生産2割減」
2.中国、香港に「国家安全法」導入方針決定 全人代閉幕
3.韓国、29日から再び外出自粛要請 ソウル首都圏新型コロナ 朝鮮半島
4.人民元急落 揺れる一国二制度、世界に影響
5.ファーウェイ、米半導体先端品の在庫を2年分確保
6.日経平均4日続伸、終値497円高 景気刺激策に期待
7.米ディズニー再開へ 「夢の国」もタッチレス
8.ロシアとサウジ、減産巡り調整継続で一致
9.米経済「急激に悪化」 FRB、失業給付が再雇用の妨げも
10.トランプ氏「SNS閉鎖も辞さず」 ツイッターに反発
2.中国、香港に「国家安全法」導入方針決定 全人代閉幕
3.韓国、29日から再び外出自粛要請 ソウル首都圏新型コロナ 朝鮮半島
4.人民元急落 揺れる一国二制度、世界に影響
5.ファーウェイ、米半導体先端品の在庫を2年分確保
6.日経平均4日続伸、終値497円高 景気刺激策に期待
7.米ディズニー再開へ 「夢の国」もタッチレス
8.ロシアとサウジ、減産巡り調整継続で一致
9.米経済「急激に悪化」 FRB、失業給付が再雇用の妨げも
10.トランプ氏「SNS閉鎖も辞さず」 ツイッターに反発
1.日産最終赤字6712億円、20年ぶり規模 「生産2割減」
日産自動車が28日発表した2020年3月期の連結決算は、最終損益が6712億円の赤字(前の期は3191億円の黒字)だった。赤字は09年3月期以来11年ぶり。赤字額は00年3月期(6843億円の赤字)に迫る規模で、20年ぶりの規模だ。新型コロナウイルスの感染拡大で世界の販売が減った。構造改革費用や固定資産の減損損失なども収益を圧迫した。
2.中国、香港に「国家安全法」導入方針決定 全人代閉幕
北京で開いた全国人民代表大会(全人代、国会に相当)は28日、反体制活動を禁じる「香港国家安全法」の制定方針を採択して閉幕した。中国が国家安全に関する機関を香港に設置して直接取り締まりができるようになる。香港で言論の自由が中国本土並みに制限され、高度な自治を認める「一国二制度」が揺らぐとして、米国や香港の民主派は反発を強めている。
北京の人民大会堂で習近平(シー・ジンピン)国家主席らが出席して採決し、賛成2878、反対1、棄権6で可決した。方針には「外国勢力が香港に干渉することに断固反対し、必要な措置をとって反撃する」と明記。中国の分裂や共産党政権の転覆、組織的なテロ活動、外部勢力による内政干渉を禁止する。「中央政府の機関が香港政府に組織を設置し、国家安全に関連する職責を果たす」とした。
李克強(リー・クォーチャン)首相は全人代後の記者会見で「決定は一国二制度を確保して香港の長期繁栄を守るものだ」と述べた。6月にも全人代常務委を開き、立法作業を進める。9月に香港立法会(議会)の選挙を予定しており、夏までに成立させるとの見方が強い。中国共産党序列3位の栗戦書(リー・ジャンシュー)全人代常務委員長(国会議長)は「香港の同胞を含む中国人全体の利益となる」と述べた。
香港の憲法といわれる香港基本法は23条で香港政府が自ら国家分裂や政権転覆などを禁じる法律を制定しなければならないと定める。香港政府は2003年に立法を試みたが大規模な反対活動にあい条例案の撤回に追い込まれた。
19年には香港に逃げた容疑者を中国本土に引き渡せるようにする「逃亡犯条例」を巡り香港でデモ活動が長期間続いた。このため習指導部は香港政府が自力で国家安全に関する立法措置を進めるのは難しいと判断し、自ら制定に乗り出した。
習指導部は香港基本法の例外規定を使い、中国本土の法律を直接適用する立法措置をとる。国家安全法の施行で、香港の抗議活動への締めつけがさらに厳しくなるのは確実とみられる。中国国営中央テレビ(CCTV)によると、中国軍の香港駐留部隊の司令官は同法に関して「分裂勢力や外部の干渉勢力を震え上がらせる」と強調した。
全人代は例年3月5日に開幕するが、今回は新型コロナウイルスの影響で2カ月半遅れた。22日採択した政府活動報告では、20年の経済成長率の目標設定は見送り、景気対策として財政出動を拡大する方針を示した。
3.韓国、29日から再び外出自粛要請 ソウル首都圏新型コロナ 朝鮮半島
韓国政府は28日、新型コロナウイルスの感染者が再び増加ペースを強める可能性があるとして、29日からソウルを含む首都圏で外出自粛を要請すると明らかにした。公共施設の運営も中断する。6日に制限を緩めたが集団感染が相次ぎ、制限緩和の基準とした「1日50人」の感染者数を3週間ぶりに上回った。
28日には新たに79人の感染が判明した。5月6日には1日あたりの感染者を2人まで抑え込んだが、直後に繁華街のナイトクラブで集団感染が発覚し、全国に拡散した。最近ではソウル近郊の物流センターでも集団感染が発生した。
政府は6月14日までの約2週間、外出自粛や在宅勤務を呼びかける。首都圏の美術館や公園などの公共施設は閉鎖し、塾やインターネットカフェの運営者に防疫対策の徹底を義務付ける。29日以降に1週間連続で感染者が50人を超えたら制限を一段と強める方針だ。
一般の飲食店などは日本と同様、市民に自粛を促す。防疫当局は6日の緩和後も、バスやタクシーがマスクを着用していない客の乗車拒否を認める措置などを相次ぎ打ち出していた。
感染者の増加は、学校の再開にも影響する。20日以降に高校3年生から順次登校を始めたが、生徒の感染や地域での感染拡大で中止や延期を決めた例も多い。
4.人民元急落 揺れる一国二制度、世界に影響
香港の高度な自治を認めた中国の一国二制度が「香港国家安全法」によって動揺し、中国本土と香港の金融市場に衝撃が波及している。中国通貨の人民元が急落し、本土マネーが香港に逃避。本土投資家による香港株買いは記録的な水準に膨らんでいる。今後、香港を「中継地」として、欧米に資本が流出するようだと人民元安が加速して中国経済が危機に陥るリスクが高まる。景気と金融の両面で世界経済への影響も大きくなる。
5.ファーウェイ、米半導体先端品の在庫を2年分確保
中国通信機器最大手の華為技術(ファーウェイ)が半導体の先端品の確保を急いでいる。米政府による取引規制に対抗するのが狙いで、既に米有力半導体メーカーの先端品の在庫を最大2年分確保したことが、28日までに分かった。主力事業の通信機器に使う半導体で、米大手のザイリンクスやインテルなどが手掛ける先端品を優先的に確保している。
6.日経平均4日続伸、終値497円高 景気刺激策に期待
28日の東京株式市場で日経平均株価は4日続伸し、前日比497円08銭(2.32%)高の2万1916円31銭で終えた。欧米で景気刺激策の議論が進み、経済活動の再開への期待感から短期筋による買いが集まった。国内要因では政府が2020年度第2次補正予算案を決めたことが投資心理の改善を促し、2月27日以来、約3カ月ぶりの高値となった。上げ幅は一時500円を超えた。
JPX日経インデックス400は4日続伸。終値は前日比262.29ポイント(1.88%)高の1万4195.52だった。東証株価指数(TOPIX)も4日続伸で、27.87ポイント(1.80%)高の1577.34で終えた。
欧州で経済下支えのための基金を創設する計画が打ち出された。米連邦準備理事会(FRB)が金利を低く抑える方策の検討を始めたと伝わった。欧米で景気刺激策が相次いで議論されていることで経済活動の再開への期待感が高まった。日本政府は一般会計歳出などの「真水」で33兆円を用意して企業支援を進める方針で、投資家の安心感を誘った。
これまで売りに回っていた短期筋の買い戻しが急速に入ったことで、市場で節目とされてきた200日移動平均線(2万1655円)を超えてもなお上昇。出遅れ銘柄の物色が強まったほか、新規の買い持ちが始まったとの指摘も市場の一角で聞かれた。
中国の全国人民代表大会(全人代)で香港国家安全法の策定方針が採択される見込みとあって米中関係の悪化懸念がくすぶり、午後は上げ幅を縮める場面もあった。
東証1部の売買代金は概算で3兆3816億円で、3兆円を超えたのは4月30日以来。金額としては3月27日(3兆9093億円)以来の大きさだった。売買高は20億8753万株。東証1部の値上がり銘柄数は1530と、全体の7割を占めた。値下がりは583、変わらずは53銘柄だった。
7.米ディズニー再開へ 「夢の国」もタッチレス
新型コロナウイルスの影響で休業していた米国のテーマパークが再び門を開く。米ウォルト・ディズニーは27日、南部フロリダ州にある「ディズニーワールド」を7月から再開する計画を明らかにした。非接触決済やパレードの見送りなどでタッチレスとなる「夢の国」の姿は、再開の道を探る日本の娯楽産業にも影響を与えそうだ。
「迎えられるゲストの人数は少なくなるが、妥協のないディズニーの体験を届けると確約する」。27日に米経済番組に出演したディズニーのボブ・チャペック最高経営責任者(CEO)は3月中旬以来、約4カ月ぶりとなるディズニーワールドの再オープンに自信をのぞかせた。
5月に先行して中国・上海のディズニーランドを開いたが、「マジックキングダム」や「アニマルキングダム」など4つのテーマパークからなるディズニーワールドの再開は別格だ。総面積は約110平方キロメートルで埼玉県川越市と同規模。コロナ前は1日あたり約16万人が訪れ、従業員は7万7千人に上る。ディズニーの2020年1〜3月期の純利益は前年同期比9割減っており、業績回復にも欠かせない存在だ。
とはいえ、再開でコロナの集団感染が起これば評判は地に落ちる。そのため世界で最も大きな夢の国は、4カ月前とは異なる姿で7月11日の再開を迎える。ディズニーが立地自治体に提出した資料に並ぶのは、コロナ感染を防ぐ対策の数々だ。
まずはゲストに、マスクやフェイスカバーの着用とテーマパークの入り口での検温を求める。熱がある場合は入園を控えてもらう。来場者を迎えるキャストも皆、マスク姿だ。
園内のアトラクションやレストラン、モノレールなどでの体験も変わる。具体的な数は明かしていないが、来場者が互いに約2メートルの距離を取れるよう一度に利用できる人数を絞る。レストランでは「マジックバンド」と呼ぶ腕輪型の独自端末や、「アップルペイ」などスマートフォンでの非接触決済を促す。スマホからメニューを注文できる店舗の数も一段と増やす。
一方で、安全を優先して諦める催しもある。例えば、花火やパレードといったディズニーの目玉イベントは再開後も当面開催しない。人混みを防ぐのが難しいとみるためだ。握手やハグなどキャラクターとの触れ合いも控えてもらう。テーマパークの「新常態」に対する理解を促すため、園内に新しいルールを示す看板を設置する。
夢の国にいても「コロナの現実」を思い出さざるを得ない再開計画を、市場はまだ評価しきれずにいる。27日の米市場でディズニーの株価は前日比で0.48%の小幅上昇にとどまった。SNS(交流サイト)でも再開を喜ぶファンと、夏場のマスク着用を嫌がる声が交錯する。チャペック氏が宣言するように「妥協のない体験」を提供できるかどうかが試される。
多くのテーマパークが集積するフロリダ州では、米コムキャスト系の企業が運営する「ユニバーサル・スタジオ」も6月5日から部分的に再開する。プールを中心とする「シーワールド」の運営会社は6月11日の再オープンをめざす。
日本の東京ディズニーリゾート(TDR)を運営するオリエンタルランドは現時点で再開時期を明らかにしていない。日本でテーマパークを訪れる人は年5280万人(18年)と、国別では米国に次いで多い。小規模な娯楽施設も含め、米国での再開の道のりから学べることは多そうだ。
8.ロシアとサウジ、減産巡り調整継続で一致
ロシアのプーチン大統領は27日、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話協議し、石油輸出国機構(OPEC)とロシアなど非加盟国の主要産油国で構成する「OPECプラス」の協調減産を巡り、緊密な調整を続けることで一致した。6月10日にOPECプラスのテレビ会議を控え、7月以降の減産量の維持を協議した可能性がある。
ロシア大統領府が発表した。プーチン氏とムハンマド皇太子は世界のエネルギー市場の状況について意見交換、4月のOPECプラスによる減産合意の意義を確認した。
タス通信は27日、複数の関係者の話として、OPECプラスが7月以降の減産を現行の日量970万バレルで維持する方向で議論していると報じた。4月の合意では7月から2020年末まで日量770万バレルに減らす計画だった。ロシアは原油安の長期化で経済への打撃が深刻になっており、サウジと連携して減産強化を探るとみられる。
9.米経済「急激に悪化」 FRB、失業給付が再雇用の妨げも
米連邦準備理事会(FRB)は27日発表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で、米経済は「新型コロナウイルスによって、大半の地域で急激に悪化している」と総括判断した。5月は失業率が20%を超える可能性もあり、各地区とも雇用情勢の悪さを指摘した。ただ、連邦政府の潤沢な失業給付が「かえって再雇用の障害になる」などとの指摘も目立った。
4月上旬から5月中旬までの経済情勢を、12地区連銀がそれぞれ報告した。同期間は新型コロナで経済活動を大幅に制限しており、総括では「レジャー・接客業は厳しい状況に置かれ、旅行サービスはほとんど活動がない」とした。自動車販売も大幅に減少し、各地区とも「製造活動が急落した」と指摘した。
もっとも厳しい報告が上がったのは雇用情勢だ。ダラス連銀はテキサス州の400社を調査したところ「47%が従業員の一時解雇や恒久解雇に踏み切った」という。フィラデルフィア連銀も「4月中旬までに5割超の企業が雇用を減らした」と報告。同地区では製造業の3分の1が、30%を超す売り上げ減に見舞われているという。
5月は失業率が20%に達する可能性があり、大恐慌時並みの厳しさとなる。パウエルFRB議長は7月以降に失業率は持ち直しに転じると予測するが、焦点はその回復スピードだ。ニューヨーク連銀は「多くの企業が解雇は一時的で、再雇用を予想している」と指摘するが、クリーブランド連銀は「従業員を減らした企業のうち、営業再開後に雇用を元のレベル近くに戻す予定なのは3分の1だけ」と悲観的だ。
雇用回復を阻むのは、新型コロナの感染リスクが完全に拭えたわけではないためだ。飲食店は営業再開後も客同士の距離を空ける「ソーシャル・ディスタンシング」を求められるが、ボストン連銀は「飲食店の供給能力の35〜45%しか発揮できず、採算が合わない」と断じる。学校の再開も遅れており「子供のケアで職場復帰できない従業員が多い」(リッチモンド連銀)との指摘もある。
多くの連銀から挙がったのは、失業給付の潤沢さが、かえって離職を招いているとの指摘だ。連邦政府は3月末に決めた2.2兆ドル(約236兆円)の経済対策で、失業給付を通常より週600ドル積み増す特例措置を発動している。
そのため、失業者は当面は手元資金の不安がなくなり「職場復帰をためらっている」(ニューヨーク連銀)という。シカゴ連銀も管轄区内の企業が「寛大な失業給付を上回るような給与を支払うのが難しい」と指摘し、従業員の再雇用の妨げになるとみている。
同報告書は6月8〜9日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の討議資料となる。FRBは関連法で「雇用の最大化」を政策遂行の使命と定められており、追加の資金供給策などの議論に入る。
トランプ氏「SNS閉鎖も辞さず」 ツイッターに反発
トランプ米大統領は27日、ツイッターやフェイスブックなどのSNS(交流サイト)について「強力に規制するか、閉鎖させる」とツイッターに書きこんだ。ツイッターが自身の投稿に関し、閲覧者に事実確認を促す注記をしたことに反発したものだ。「SNSが保守派の意見を完全に黙殺しようとしていると共和党員は感じている」と不満をぶちまけた。
米メディアによると、マクナニー大統領報道官は27日に記者団に対し、トランプ氏がSNSを対象とした大統領令に28日に署名すると明らかにした。詳細は明らかにしなかった。ツイッターは26日、トランプ氏による郵便投票に関する書き込みが誤解を招く恐れがあると注記し、同社として事実関係を確認したページに誘導する措置を講じていた。
トランプ氏は11月の大統領選に向けてツイッターが民主党の味方をしていると批判している。27日も「SNSの2016年の(大統領選で民主党を勝たせる)試みは失敗した。さらに高度な試みを再び許してはならない」と強調した。
トランプ氏は米主要メディアを「フェイクニュース」とみなし、国民に主張を直接伝える手段としてツイッターを16年の大統領選のころから多用してきた。27日時点のフォロワー数は8000万人を超える。仮にツイッターを閉鎖させるような措置を講じればむしろ情報発信の手段を失って大統領選でトランプ氏に不利に働く可能性がある。
2020年05月27日
【経済ニュース 5/27 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
1.米住宅ローン申請、2カ月ぶりプラス コロナ前水準に
2.香港統制、世界が懸念 28日に国家安全法方針採択
3.EU経済再生に89兆円基金案 欧州委、南北対立で難航も
4.NYダウ続伸で始まる、300ドル超高 経済正常化に期待
5.米大統領、対中制裁を示唆 香港統制強化に不快感
6.海にプールに… 米「自粛疲れ」でヒト殺到 感染増懸念
7.ルノー会長「日産と統合必要なし」構想棚上げ協業急ぐ
1.米住宅ローン申請、2カ月ぶりプラス コロナ前水準に
米国で住宅ローンの申し込みが復調してきた。米抵当銀行協会(MBA)が27日発表した5月22日までの週間の購入向け住宅ローン申請件数は、前年同期比で8%増だった。約2カ月ぶりのプラスで、低金利と外出制限の緩和を追い風に3月上旬の水準まで回復した。ただ足元の失業急増で、住宅市場の先行きはなお不透明だ。
1990年を100として指数化した申請件数は18〜22日で281となり、3月2〜6日と同水準まで回復した。MBAで経済予測を担当するジョエル・カン氏は「州の経済活動の再開で、家探しを再び始める人が増えた」と述べた。
新型コロナウイルスの感染を防ぐための外出制限により、ローン申請件数は5月15日まで9週連続で前年の同時期を下回っていた。特に4月上旬は3割超の落ち込み幅だった。物件保有者が内見を断るケースが多く、住宅供給も滞った。4月の中古住宅販売件数は前年同月比17%減の433万戸で、8年半ぶりの低水準に沈んだ。販売減に伴いローン申請も低調だった。
4月下旬以降は経済活動が各地で一部再開し、「物件の広告も入るようになった」(不動産関係者)。インターネット不動産仲介のレッドフィンがまとめる住宅需要の指数は5月4〜10日に、新型コロナの感染が広がる前と比べて約5%増の水準まで回復。連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)によると、30年固定の住宅ローン金利は5月15〜21日の期間平均で3.24%と遡れる1971年以来で過去最低水準に下がった。ローンの借りやすさが申請の増加につながった。
ただ、従来のように金利の低下が住宅購入を継続的に後押しするかどうかは不透明だ。経済再開で住宅の供給不足が解消されても、失業増や収入減による需要サイドの問題が残る。米国野村証券の雨宮愛知氏は「ローンの延滞増や銀行による審査の厳格化で、住宅需要の回復は鈍る可能性もある」と指摘する。
2.香港統制、世界が懸念 28日に国家安全法方針採択
香港問題に国際社会が懸念を強めている。トランプ米大統領は26日、「週末までにとても強力な内容を知らせる」と制裁の可能性を示唆した。米国は制裁カードを武器に、中国の翻意を促したい考えだ。ただ中国は強硬姿勢を変えていない。中国による28日の「香港国家安全法」制定方針採択を前に香港では27日、1千人以上が参加する抗議デモが起きた。
トランプ政権が想定するのは、2019年11月に成立した香港人権・民主主義法に基づく制裁措置だ。同法は大きくわけて2つの制裁手段がある。一つは香港の人権弾圧に関わった中国共産党の関係者らの米国内の資産凍結や査証(ビザ)の発給停止措置だ。
こうした制裁は形式的な側面が強く、比較的発動しやすい。米国が重視する民主主義や法の支配を揺るがしかねない事態に断固たる対応をとる姿勢を示すことになる。
もう一つは米国が香港に与えている関税やビザ発給などの優遇措置の見直しだ。米国は香港を中国本土と異なる関税地域と位置づけ、対中国の制裁関税や厳格な輸出管理の対象外としている。
同法は香港が一国二制度に基づく「高度な自治」を維持できているかどうかの検証を米政府に義務付け、議会への毎年の報告を求めている。一国二制度に問題があると判断すれば、香港に与えている優遇を見直す。
米シティグループは米国が香港の優遇を取りやめた場合、「モノの貿易に大きな影響が出る可能性は小さいものの、輸送や旅行などのサービス貿易に目に見えた影響が及ぶ」と分析する。中国企業は軍事技術に転用可能なハイテク製品などを香港を通じて輸入するケースがあり、米国の制裁の一環でこうした抜け穴がふさがれる可能性もある。
米国勢調査局によると、19年に米国にとって最大の貿易黒字国・地域が香港(約260億ドル)だった。米国は電気製品などを香港に輸出しているが、貿易中継地としての色彩が強い。また米投資銀行などは香港をアジアの統括拠点と位置づけて多くの人材を配置しており、香港への制裁は米国企業への打撃となりかねない。
米国が制裁に踏み切れば、中国は報復に動く可能性が高い。中国外務省の趙立堅副報道局長は27日、トランプ氏の発言に「いかなる外部勢力の干渉も許さず、必要な反撃措置をとる」と反発した。制裁は米国にとっては「もろ刃の剣」といえる。
欧州連合(EU)のミシェル大統領は26日、「我々は中国の行動について甘くない」と中国に警告した。英国、オーストラリア、カナダの3カ国は、「香港市民が直接参加せずに法律を導入すれば、一国二制度の原則を明らかに損なう」との共同声明を発表した。
日本では、菅義偉官房長官が27日の記者会見で、香港情勢に関して「政府として強く懸念している」と語り、「日本の懸念は外交ルートを通じて中国にしっかり伝えている」と明らかにした。
菅氏は「一国二制度のもと従来の自由で開かれた体制が維持され、民主的、安定的に発展することが重要だ」と主張。「主要7カ国(G7)をはじめ関係国の動向などを情報収集し適切に対応したい」と述べた。
香港では27日、国家安全法への抗議が呼びかけられ、昼すぎから繁華街に若者が集まった。複数の繁華街で次々に抗議デモが起き、1千人以上が参加した。香港は新型コロナウイルス対策で9人以上の集会を禁止しており、武装警察官が出動して解散を命じるなど街は物々しい雰囲気に包まれた。午後4時半(日本時間5時半)までに300人以上が逮捕された。
3.EU経済再生に89兆円基金案 欧州委、南北対立で難航も
欧州連合(EU)の欧州委員会は27日、新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ経済の復興計画案を公表した。新たに補助金と融資からなる7500億ユーロ(約89兆円)の基金を創設する。すでに合意した支援策と合わせ、総額は1.85兆ユーロ規模になる。基金にはオランダなどが反対しており、危機克服に向けてEUが団結できるかの試金石となる。
計画案は復興基金が核となり、18日に仏独首脳が合意した提案におおむね沿った内容だ。EUが5千億ユーロ分の債券を発行して市場からお金を調達し、被害が大きいイタリアなど南欧に回す。補助金となるため、返済の必要はない。欧州委はこれに2500億ユーロの融資枠を設ける案を加えた。
基金は2021〜27年のEUの中期予算に組み込むため、実際にお金が届くのは21年からとなる。年内は緊急対応として合意済みの5400億ユーロの対策で雇用維持や企業の資金繰りを後押しする。このほか、これまでの環境政策や地域振興策も復興計画の一部とした。
フォンデアライエン欧州委員長は27日の声明で「復興計画は経済の回復だけでなく将来に投資することで、我々が直面する困難を機会に変える」と述べ、環境やデジタルといった成長分野に投資する考えを表明した。
今回の債券はコロナ対応に限った一時的な措置で「ユーロ共同債」との表現は使っていないが、大規模な共通債券の発行は初めてとなる。これまで慎重だったドイツが容認し、EUの中核国として南欧支援に乗り出す姿勢に転じた。共通債券の発行が実現すれば「財政共通化の一歩」(仏ソシエテ・ジェネラル)と評価する声もある。
復興計画は全加盟国の同意が必要となる。欧州委は基金について6月11日のユーロ圏財務相会合で大筋で合意し、同18日のEU首脳会議で承認する青写真を描くが、財政規律を重視する「倹約4カ国」(オランダ、オーストリア、デンマーク、スウェーデン)は23日、反対を表明した。
「債務の共通化やEU予算の大幅な増額につながるあらゆる手段に同意できない」と補助金ではなく、返済が前提の融資でのみ支援を実施すべきだと訴えた。
共通債務は財政に余裕がある北部欧州が南欧の借金を肩代わりする面があり、有権者の理解を得にくい。オランダのルッテ首相は26日、「我々は(計画は)融資からなるべきだと信じている」と強調した。EUは全加盟国の同意を得ながら、大胆な景気対策をまとめる難題に挑むことになる。
市場から調達した資金をどう返すのかも定まっていない。欧州委によると、債券の償還期間は30年を想定する。償還には加盟国によるEU予算への拠出額を増やすのに加え、デジタル課税や排出量取引制度の対象拡大などEU独自の新規財源を確保する案が出ている。
ユーロ圏の実質成長率は20年に前年比7.7%マイナスに沈んだ後、21年は6.3%のプラスに転じると、欧州委は予測する。EUの意思決定は賛成派と反対派の中間をとりながら合意形成することが多く、景気対策が中途半端になれば、反転シナリオにも影を落としかねない。
4.NYダウ続伸で始まる、300ドル超高 経済正常化に期待
27日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸して始まった。午前9時35分現在、前日比326ドル04セント高の2万5321ドル15セントで推移している。米経済が早期に正常化に向かうとの楽観論が買いを誘っている。欧州の主要株式相場が軒並み上昇し、米国株にも買いが波及している面もある。
米国では経済再開に伴う景気改善期待が高まっている。ニューヨーク市のデブラシオ市長は26日、6月前半から段階的な経済再開に入る可能性を示唆した。ロサンゼルス市のガルセッティ市長は26日夜、米メディアで27日から市内のすべての小売店での営業再開を認める方針を示した。ウォルト・ディズニーは27日、フロリダ州のテーマパーク「ディズニーワールド」の再開計画を提出する見込みだ。
欧州株高も投資家心理の改善につながった。スペインなど欧州の一部が国外からの観光客受け入れの方針を示した。欧州連合(EU)の欧州委員会は27日、新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ経済の復興計画案を公表。補助金と融資からなる7500億ユーロの基金を創設する。すでに合意した支援策と合わせ総額は1兆8500億ユーロになる。
業績が景気に連動しやすい金融のゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェースが大幅に上昇した。クレジットカードのアメリカン・エキスプレス(アメックス)も高い。一方、ソフトウェアのマイクロソフトは下落している。
5.米大統領、対中制裁を示唆 香港統制強化に不快感
トランプ米大統領は26日の記者会見で、中国が香港への統制強化をめざす香港国家安全法の施行を強行すれば、週内にも中国に強力な制裁を科す可能性を示唆した。中国に強い警告を改めて発したものだ。マクナニー米大統領報道官は26日の記者会見で「大統領は中国の試みを不快に思っている」と述べた。
トランプ氏は制裁を科すかどうかを問われ「いま取り組んでいるところだ。週末までにとても強力な内容を知ることになるだろう」と語った。詳細は明らかにしなかった。米ブルームバーグ通信は26日、トランプ政権が中国の政府当局者や企業に制裁を検討していると報じた。
中国は開会中の全国人民代表大会で28日に制定方針を採択する運びだ。トランプ氏は採択されれば制裁に動く可能性を示したものとみられる。これに関連し、マクナニー氏は「もし中国が香港を乗っ取ることになれば、香港が金融のハブ(中核)の地位を維持するのは難しい」と指摘した。
2019年11月にトランプ氏が署名して成立した香港人権・民主主義法は、香港で人権弾圧があれば中国共産党の関係者らの米国内の資産を凍結したり、査証の発給を止めたりできる。
一方、マクナニー氏は6月下旬をめざす主要7カ国(G7)首脳会議を対面式で開く場合、場所はホワイトハウスになるとの見通しを示した。
6.海にプールに… 米「自粛疲れ」でヒト殺到 感染増懸念
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限が全50州で一部解除された米国で、「自粛疲れ」の反動が顕著になっている。夏の行楽シーズンの到来を告げる「メモリアルデー」の3連休には、各地のプールや海辺に人々が殺到した。米国の新規感染者や死者数はピークの2〜5割の水準に落ち着いているが、経済再開を機に感染者数が再拡大する懸念も強まっている。
米中部ミズーリ州のリゾート地オザークス湖。5月23〜25日の3連休、湖畔のプールで数百人が集まって楽しむ様子がツイッターなどで伝えられた。マスク姿の人は皆無で、感染を防ぐため人との距離を保つ「ソーシャル・ディスタンシング」を気にする様子はない。
ミズーリ州では4月6日に外出禁止令が発令され、5月4日に一部解除されるまで多くの州民が自宅待機を余儀なくされた。ある観光客は「みんな楽しむことに夢中だった」と地元メディアに語っている。同州の新規感染者数は5月中旬以降、再び増加傾向にある。地元自治体はオザークス湖を訪れた人に2週間の自主隔離を求めた。
米国では20日に東部コネティカット州が自宅待機命令を解除し、全50州で感染抑制のための行動制限が一部緩和された。多くの州では店舗の収容人数を従来の半分以下に抑えるなど慎重に再開を進めるが、人々の「自粛疲れ」も顕著で、ミズーリ州以外にもカリフォルニア州やメリーランド州など至る所で人々が密集する様子が伝えられた。
7.ルノー会長「日産と統合必要なし」構想棚上げ協業急ぐ
日産自動車と仏ルノー、三菱自動車の3社連合は27日、新たな中期経営計画を発表した。ルノーのジャンドミニク・スナール会長は同日のオンライン会見で日産との統合構想について問われ「統合は必要ない。提携の強みを発揮して結果を出していく」と話した。互いの不信感の原因となっていたルノー・日産の経営統合構想を棚上げして協業を急ぐ考えを示した。
3社連合を率いたカルロス・ゴーン被告失脚後の混乱に加え、新型コロナウイルス感染拡大に伴う需要減で3社の業績は悪化している。27日の会見でスナール会長は提携効果の発揮を強調した。
目標時期を設定しない新中計の具体策として、部品や車台の共通化などを通じて1車種あたりの開発・生産に必要な投資額を最大40%減らす。3社が展開する車種の数も25年までに19年比で20%減らす。これまで不十分だった3社提携を深掘りすることで、需要に応じたコスト構造を構築する。「これからは数量よりも効率と競争力を(戦略として)前面に出す」(スナール会長)
2016年に日産が三菱自に出資して3社連合の世界販売台数は1千万台規模となり、独フォルクスワーゲン(VW)やトヨタ自動車と肩を並べた時期があった。拡大路線のゴーン被告主導による中計では22年に1400万台を販売目標に掲げたが、達成が困難になっていた。
2020年05月26日
【経済ニュース 5/26 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
日銀の国債買い入れや経済再開の期待により
日経がとうとう21000円を突破しましたね!!
NYダウも25000ドルを上抜けしてきました
1.東証大引け 大幅続伸、一時580円高 緊急事態解除で2カ月半ぶり高値
2.「1メートル以内15分以上」で濃厚接触 アプリ通知
3.中国・百度、自動運転の開発拠点 早期の収益化目指す
4.日EU首脳、WHO検証開始を テレビ会議
5.香港混乱「基本法」が起点 中国、例外規定で強行
6.新型コロナ「世界は第1波のまっただ中」 WHO警告
7.中国「デジタル人民元」、22年北京冬季五輪までに発行か
8.サウジファンド、米欧株底値買い 8千億円投資
9.英、対EU「FTAなし」準備加速 関税率表や閣僚会議も
10.テンセント、クラウドなどに7兆円超投資 今後5年で
1.東証大引け 大幅続伸、一時580円高 緊急事態解除で2カ月半ぶり高値
26日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸し、前日比529円52銭(2.55%)高の2万1271円17銭で終えた。心理的な節目の2万1000円を上回り、3月5日以来、約2カ月半ぶりの高値を付けた。新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言が全面的に解除されたことで、経済活動が再開に向かうとの期待が高まった。株価指数先物を売り持ちする海外投資家の断続的な買い戻しが相場を押し上げた。
安倍晋三首相が緊急事態宣言を全国で解除すると25日夜の記者会見で表明し、経済対策の効果で景気が底入れに向かうとの見方が広がった。
米バイオ企業ノババックスが新型コロナウイルスのワクチン候補でヒト治験を始めたと発表し、米株価指数先物が大幅に上昇したのも相場の支えとなった。「売り方の買い戻しが中心」(国内証券ストラテジスト)の展開で、日経平均の上げ幅は一時580円を超えた。
東証1部の売買代金は概算で2兆5326億円。売買高は14億7246万株だった。
JPX日経インデックス400は大幅続伸。終値は前日比298.24ポイント(2.21%)高の1万3807.61だった。東証株価指数(TOPIX)も大幅続伸し、32.53ポイント(2.17%)高の1534.73で終えた。業種別TOPIXは33業種全て上昇。空運や海運などの上げが目立った。
東証1部の値上がり銘柄数は1734と全体の約8割を占めた。値下がりは384、変わらずは52銘柄だった。
2.「1メートル以内15分以上」で濃厚接触 アプリ通知
政府は26日、新型コロナウイルスの感染者と濃厚接触した可能性を知らせるスマートフォンアプリの詳しい仕様を公開した。近距離無線通信のブルートゥースを使い、使用者同士が近づいたことを記録。陽性者と1メートル以内に15分以上一緒いた人に通知する。プライバシーに配慮して個人情報の登録なしで利用できるようにする。
厚生労働省が民間企業に委託し、6月中旬の運用開始を目指す。多くの人が使わないと機能が発揮できないため6割程度の普及率を目指す。多言語対応や高齢者にわかりやすい操作法も求める。
アプリはスマホ上で最小限の電力消費で常時動いている状態になる。利用者同士の接触データは14日間保存する。陽性と診断された利用者が保健所からのメールなどで届く専用の番号を入力すると、過去14日間に濃厚接触した可能性がある人に通知が届く。
アプリは米アップルと米グーグルの技術を用いる。日本独自に、1日に陽性者と何回接触したか分かる機能を付けることも検討している。両社の技術を使うアプリは22カ国が導入済みで、将来の連動も視野に入れる。
政府はプライバシーやセキュリティーの留意事項も公表した。アプリやデータを新型コロナ対策以外に使うことは禁じる。刑事捜査の追跡や証拠収集、企業のマーケティング活動や宣伝などへの転用は認めない。厚労省が新型コロナが終息したと判断すればアプリの機能は停止させる。
3.中国・百度、自動運転の開発拠点 早期の収益化目指す
中国インターネット大手の百度(バイドゥ)は26日、北京市内に自動運転技術の開発拠点を開設したと発表した。200台余りの試験車両を配置し、道路や信号など交通インフラと連携した先端技術の開発を進める計画。主力のネット検索事業が低迷するなか、自動運転技術分野で早期の収益化を目指す。
開発拠点「アポロ・パーク」は北京市南部の亦庄経済開発区にこのほど完成した。敷地面積は1万3500平方メートルで、試験車両のほか、道路上にセンサーなどを設けてデータを測定・解析し、先端技術を開発するという。同社によると、同様の施設としては「世界最大」としている。
百度は2013年に自動運転技術の開発に乗り出した。今年4月には湖南省長沙市の限定された公道で、人が操作しない「レベル4」のロボタクシーの試験サービスを一般の利用者を対象に始めた。今回の拠点設置をテコに、技術開発をさらに加速する方針だ。
中国政府も同社の自動運転技術のプロジェクトを支援し、トヨタ自動車やホンダ、独フォルクスワーゲン(VW)、米フォード・モーターなどの自動車大手に加え、米インテル、米エヌビディアなども参加している。
百度の1〜3月期の売上高は前年同期比で7%減に落ち込んだ。新型コロナウイルスの感染拡大で多くの広告主が出稿を控えたことが響いた。主力となるネット検索の広告収入が減少するなか、新たな事業の育成が課題となっている。
4.日EU首脳、WHO検証開始を テレビ会議
安倍晋三首相は26日、欧州連合(EU)のミシェル大統領、フォンデアライエン欧州委員長とテレビ会議を開いた。新型コロナウイルスについて、治療薬とワクチンの開発や国際協調、途上国支援の重要性で一致した。
3者は共同報道発表をまとめた。世界保健機関(WHO)の対応に関し「公平で独立した包括的な検証の段階的な作業」の開始を求めた。
首相は「将来的な感染症の世界的な流行を防ぐ観点からWHOを含む関係の国際機関の改革や効率化の実現が喫緊の課題だ」と述べた。フォンデアライエン氏は「WHOを含む国際機関の感染症への対応能力の強化が必要だ」と語った。
医療用品などの流通維持と貿易円滑化の必要性も確かめた。感染状況が落ち着き次第、定期首脳協議を調整することも話し合った。
日本政府によると、2019年12月のEU新指導部の発足後、3首脳の枠組みで協議するのは初めて。
5.香港混乱「基本法」が起点 中国、例外規定で強行
北京で開催中の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)は28日、反体制活動を禁じる「香港国家安全法」の制定方針を採択する。今夏にも香港立法会(議会)の手続きを経ずに施行される見通し。香港の憲法にあたる香港基本法の例外規定を使い、中国本土の法律を直接適用する。基本法が定めた例外規定によって香港に高度の自治を認めた「一国二制度」は存亡の機に立たされている。
6.新型コロナ「世界は第1波のまっただ中」 WHO警告
新型コロナウイルスの勢いが衰えない。世界保健機関(WHO)は25日の記者会見で、世界全体では感染拡大の「第1波のまっただ中だ」と警鐘を鳴らした。特に南米など新興国で患者が急増しているほか、規制を緩和し始めた先進国も第2波が到来するリスクがくすぶっている。
米ジョンズ・ホプキンス大の集計によると、世界の累計感染者数は550万人を超えた。ブラジルとロシアはそれぞれ感染者数が36万人以上と、米国(約166万人)に次いで多い。新興国では検査や医療態勢が不十分な国も多く、感染者は統計よりもさらに多い可能性がある。
欧米などの先進国は、外出規制や店舗閉鎖などの規制の解除に動き出した。ただ、WHOで緊急事態対応を統括するマイク・ライアン氏は25日、依然として感染は拡大している段階として、「患者はいつでも急増する可能性がある」と警告した。流行がいったん落ち着いたドイツや韓国では再び感染拡大が生じた。
日本は25日に緊急事態宣言を全面的に解除した。WHOのテドロス事務局長は日本は新たな感染者が大幅に減少し、死者も少ないとして「(ウイルスの封じ込めに)成功した」と評価した。ひとまず爆発的な感染拡大は回避できたが、今後は人々の気の緩みも懸念される。WHOは1メートル以上の対人距離の確保や、患者の隔離など「すべての国は厳戒態勢を維持する必要がある」(感染症専門家マリア・ファンケルクホーフェ氏)とする。
一部では、新型コロナはインフルエンザのように冬に再燃するとの声もある。ただ、季節や気温とコロナの関連性は解明されておらず、ライアン氏は10月や11月に次の波が来ると推測するのは「危険」と一蹴した。一部の国で感染者が減少しているのは季節が理由ではなく、徹底した公衆衛生対策を打った成果だと強調した。
7.中国「デジタル人民元」、22年北京冬季五輪までに発行か
中国が「デジタル人民元」を2022年2月に北京で開く冬季五輪までに発行する方針であることが26日、わかった。中国人民銀行(中央銀行)の易綱総裁が同日公開した中国メディアのインタビューで、五輪会場で実証実験をしていると明かした。新型コロナウイルスで現金を敬遠する動きが発行に追い風となっており、準備を加速する。
易氏は「広東省深圳、江蘇省蘇州、河北省雄安新区、四川省成都、冬季五輪の会場で利用者を限って実験中」と語った。五輪会場での実験が判明したのは初めて。易氏は「発行に向けた時間表はない」と述べたが、冬季五輪での発行を目指していることがわかった。
デジタル人民元に詳しい国務院(政府)関係者は「年末までに実験結果をまとめ、習近平(シー・ジンピン)指導部が満足すれば来年に発行する。満足しなければ来年さらに実験する」と話す。
新型コロナでもともと利用者が減っていた現金はさらに敬遠される。香港金融管理局の余偉文総裁は4月の討論会で「(決済分野で)科学技術の応用、普及を進めやすくなった」と語った。
デジタル人民元は携帯電話番号にひもづけて発行され、携帯電話にアプリを取り込んで使う。4月には中国のインターネット上でデジタル人民元を表示したとされる携帯電話の写真が出回った。アリババ集団傘下の電子決済サービス「支付宝」(アリペ
イ)と似ており、QRコードを読み取って決済したり、逆に相手にQRコードやバーコードを表示したりできる。
8.サウジファンド、米欧株底値買い 8千億円投資
世界屈指の政府系ファンドであるサウジアラビアのパブリック・インベストメント・ファンド(PIF)が、米欧の石油会社や金融機関などに大型投資を実行したことが明らかになった。新型コロナウイルスの打撃から業績が早期回復するとの判断から、株価急落局面での「底値買い」に動いたもようだ。ただ、PIFに傾斜した改革姿勢は地道な産業育成などを遅らせる懸念もある。
9.英、対EU「FTAなし」準備加速 関税率表や閣僚会議も
欧州連合(EU)を離脱した英国とEUによる自由貿易協定(FTA)などの将来関係の交渉が難航する中、英国が「FTAなし」の結末に向けた準備を加速している。山場となる6月の交渉前にEUからよい条件を引き出すための戦術とみられるが、英国内では強硬論も強まる。新型コロナウイルスによる景気失速に加え、経済に混乱を及ぼす「FTAなし」となるのか。国民や産業界は不安を募らせる。
10.テンセント、クラウドなどに7兆円超投資 今後5年で
中国のネットサービス大手、騰訊控股(テンセント)は26日、クラウドなどのIT(情報技術)インフラ整備について、今後5年間で5千億元(約7兆5千億円)を投じると発表した。クラウド投資を積極化する競合のアリババ集団に対抗するとともに、中国政府が打ち出している全国的なITインフラの整備方針にも応える。
テンセントが同日、自社のSNS(交流サイト)内で投資方針を明らかにした。クラウドや人工知能(AI)、ブロックチェーン、あらゆるモノがネットにつながるIoT、量子計算といった設備や研究開発へ重点的に資金を投入するという。
クラウドを巡っては、中国市場でシェアトップのアリババが3年間で2千億元を投資する計画を4月に発表したばかり。クラウド事業はデータの受け皿となるサーバーを大量調達してコストを抑え、顧客へのサービス価格を下げることが求められる。シェア2位のテンセントは今回の投資でコスト競争力を高め、アリババに対抗する狙いがあるようだ。
中国政府は5月22日に開幕した全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で「新型インフラ」の建設を進める方針を強調した。新型インフラには高速通信規格「5G」の基地局や高速鉄道、データセンター、IoTなどの設備が含まれる。設備や機械投資で経済を活性化しながら産業や社会の高度化を目指す。
2020年05月25日
【経済ニュース 5/25 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ついに緊急事態宣言解除が来ましたね
これにより日経平均先物も20900円代タッチ
あとはワクチンが供給整えばいったんコロナでの大きな心配は消え
2波3波の確認までは米中問題が鍵になりそうですね。
では見出しです。
1.緊急事態を全面解除、首相表明 事業規模200兆円の対策
2.コロナ研究の「武漢コネクション」 米が支援打ち切り
3.衰えるバフェット氏の手腕 指数に勝てず含み益も急減
4.東証大引け 反発 宣言解除見通し、2カ月半ぶり高値
5.中国外相、香港で米欧に譲歩せず 「新冷戦」に警戒も
6.人民元基準値、12年ぶり安値 香港巡る米中対立懸念
7.G7サミット、6月下旬に 米大統領補佐官
8.ドイツ経済は底入れか 景況感改善、正常化は遠く
9.英首相側近、制限中に親類宅へ EU離脱の参謀、首相は擁護
10.アマゾン、インドでも5万人短期雇用 配送拠点向け
1.緊急事態を全面解除、首相表明 事業規模200兆円の対策
安倍晋三首相は25日の記者会見で、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を全国で解除すると表明した。一時は全47都道府県に発令していた宣言は残る東京と埼玉、千葉、神奈川、北海道の5都道県も対象から外し全面解除となる。打ち出す経済対策の事業規模は2020年度第1次と第2次の補正予算を合わせて200兆円を超えると明らかにした。
■「厳しい基準クリア」
首相は宣言の全面解除について「世界的にも極めて厳しいレベルで定めた解除基準を全国的にクリアしたと判断した」と述べた。
「わずか1カ月半で今回の流行をほぼ収束させることができた。日本モデルの力を示した」と語った。人口当たりの感染者数や死亡者数が主要7カ国(G7)の中で少なく抑え込めていると説明した。
「これまでの社会、経済活動を厳しく制限したやり方では、私たちの生活は立ちゆかなくなる」とも述べた。その上で「緊急事態宣言の解除をもってウイルスの存在、新規感染者がゼロになったわけではない。ウイルスとの戦いは長い道のりになる」とクギをさした。
■経済再開は段階的に
「社会・経済活動を厳しく制限するのではなく、段階的にレベルを引き上げてコロナ時代の新たな日常を作り上げる」と強調した。
業界ごとに作成する指針に沿った感染防止の取り組みには全額を補助すると打ち出した。「ガイドラインに沿った感染防止の取り組みに100%を補助するなど最大150万円の補助金で街の飲食店を始め中小小規模事業者の事業再開を応援する」と訴えた。
クラスター(感染者集団)が発生した接待を伴う飲食店やナイトクラブなど夜の繁華街の事業再開に関しても、6月中旬にも指針を策定する方針だ。政府の補助金を活用して「有効な感染防止策が講じられるよう支援する」という。
プロ野球は来月から無観客の状態で再開し、段階的に拡大していくと紹介した。コンサートや各種イベントも100人程度から始め、感染状況をみながら収容人数の50%まで順次拡大していく方針を表明した。
■資金繰りに130兆円
追加経済対策として27日に2020年度第2次補正予算案を閣議決定する。「(第1次)補正予算とあわせ事業規模は200兆円を超える」との数字を示した。「総額130兆円を超える強力な資金繰り支援をする。空前絶後の規模だ。100年に一度の危機から日本経済を守り抜く。事業と雇用は何としても守り抜いていく」と訴えた。
金融政策は「政府と日銀が一体となって事態を収束するためにあらゆる手段を講じていく。圧倒的な資金を供給し、企業の資金繰りを支えていく」と明言した。「コロナ時代の新たな日常のために強力な3本の矢を打ち出す」と新たな経済政策を提起する構えだ。
人件費への助成は1万5000円まで引き上げる方針を出した。店舗の家賃負担を軽減するため最大600万円の給付金を新たに創設する。最大200万円の持続化給付金の対象もベンチャー企業などにも広げる。
施行が始まった経済対策にも触れた。持続化給付金はすでに「45万の中小企業に6000億円近い金額を届けている」との実績を上げた。
「実質無利子、最大5年間返済据え置きの融資についても3週間で1兆円を超える融資を行った。公庫と合わせれば7兆円を超える融資が行われた」と明らかにした。一人あたり一律10万円の給付は「1300を超える8割近い自治体で実際の給付が始まっ
2.コロナ研究の「武漢コネクション」 米が支援打ち切り
米国立衛生研究所(NIH)は4月下旬、米国のNPO法人へのコロナウイルス研究資金の支援を突然打ち切った。研究資金の一部が中国科学院・武漢ウイルス研究所への支援にも使われていると米メディアから指摘を受けた直後のことだ。新型コロナウイルス感染症の拡大を中国の責任だと非難するトランプ米大統領の指示があったとみられる。米中の研究者の連携がコロナウイルス研究を先導してきた。
3.衰えるバフェット氏の手腕 指数に勝てず含み益も急減
バークシャー・ハザウェイを率いる米著名投資家、ウォーレン・バフェット氏が運用成績の悪化に悩まされている。2020年1〜3月期の米株式相場の急落を受け、34歳のころから積み上げてきた株式含み益の47%を吐き出すことになったからだ。態勢立て直しのため、足を引っ張った航空株などを慌てて売却し、銀行株にも距離を置き始めた。しかし、投資の神様も8月30日には90歳になる。再び先見力を発揮する日が来るのだろうか。
4.東証大引け 反発 宣言解除見通し、2カ月半ぶり高値
25日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反発し、前週末比353円49銭(1.73%)高の2万0741円65銭と高値引けした。3月6日以来、約2カ月半ぶりの水準を回復した。緊急事態宣言の全面的な解除方針を受け、経済活動再開への期待感から買いが優勢だった。政府の2020年度第2次補正予算案の事業規模が100兆円を超えるとの報道も一部で材料視された。
25日は米国や英国の株式市場が休場で海外投資家の売りが出にくいとの声もあった。米中対立や香港情勢を巡る不透明感から売り方の買い戻しが中心で、東証1部の売買代金は概算1兆7371億円と4月13日以来、約1カ月ぶりの低水準だった。売買高は10億0257万株と1月24日以来約4カ月ぶりの少なさだった。東証1部の値上がり銘柄数は1857、値下がりは259、変わらずは54銘柄だった。
JPX日経インデックス400は3営業日ぶりに反発。終値は225.42ポイント(1.70%)高の1万3509.37だった。東証株価指数(TOPIX)も3営業日ぶりに反発し、24.40ポイント(1.65%)高の1502.20で終えた。業種別TOPIXはパルプ・紙を除く32業種すべてが上昇した。空運業、不動産業、陸運業、サービス業などの上げが目立った。
5.中国外相、香港で米欧に譲歩せず 「新冷戦」に警戒も
中国の王毅(ワン・イー)外相は24日の記者会見で、中国政府が香港の社会統制を強める「香港国家安全法」の制定を進めていることについて「一刻の猶予も許されない。必然的な流れだ」と話した。法案に反発する香港の民主派や米欧諸国などに譲歩しない姿勢を示した形だ。一方で、米国と対立を深めて「新冷戦」に至ることには警戒感も見せた。
王氏の記者会見は、開幕中の中国の国会に相当する全国人民代表大会に合わせて実施した。新型コロナウイルスがくすぶる中で、テレビ電話を使って質問に答えた。
香港国家安全法を巡り、米欧は香港に高度な自治を保障する「一国二制度」の崩壊につながると批判を強めている。これに対して王氏は「香港のことは中国の内政で外部の干渉を許さない」と猛反発した。「香港の高度な自治には影響を与えない」とも主張した。
「一国二制度」は国防や外交を除く行政管理権や立法権を香港政府に与える仕組み。香港では本来、中国本土の法律は適用されないが、全人代常務委員会が香港基本法の付属文書に国家安全法を追加して、例外扱いとする方向で準備している。
王氏は2019年6月から続く香港のデモに関して「中国と香港を分裂させようとする勢力の暴力活動がエスカレートしている」と主張した。「中央政府が香港における国家の安全に最も大きく最終的な責任を負っている」と述べ、国家安全法の制定を正当化した。同法は8月にも成立させ、9月の香港立法会(議会)選挙で民主派を抑え込む狙いがあるとの見方が出ている。
王氏は悪化する対米関係について「警戒すべきは一部の政治勢力が中米関係を人質に取り、新冷戦に向かわせようとしていることだ」と話し、「これは歴史を後退させる危険なやり方だ」と述べた。
新型コロナの発生で外交・経済の両面で課題を抱える習近平(シー・ジンピン)指導部にはトランプ政権を過度に刺激し、直接対決に陥る事態は避けたいとの思惑があるようだ。
ただ、米政府は新型コロナウイルスの世界的な拡大について、中国当局が自国での感染が確認された当初に情報を隠蔽したとして批判を強めている。米国では市民団体などが中国共産党などを相手取って賠償請求する動きがあり、米政府が追加の対中関税をちらつかせ、中国に対応を迫っている。
王氏は中国のウイルス発生を巡る責任と賠償論に声を荒らげて反論した。「中国もウイルス感染の被害者だ」と発言し、中国の責任を追及することは「事実に合わず、理屈も通らず、法にかなわない」と反発した。
6.人民元基準値、12年ぶり安値 香港巡る米中対立懸念
中国人民銀行(中央銀行)は25日、人民元取引の基準値を1ドル=7.1209元に設定した。2008年2月以来、12年3カ月ぶりの安値となる。前週来、香港問題や新型コロナウイルスを巡って米中対立が一段と激しくなるとの懸念から主に海外市場で元安が進んでいた。人民銀が容認する形で基準値に反映した。
基準値は毎朝、人民銀が公表する。大手銀行などの報告をもとに算出するという形式をとっているが、実際には通貨当局の意思を反映しているとの見方が一般的だ。元安を批判するトランプ米政権へのけん制も念頭に、輸出下支えにもなる元安を一歩進めた。
25日午前の取引では国内市場で一時1ドル=7.14元、海外では同7.15元まで元安が進んだ。19年秋には突破しなかった1ドル=7.2元台の元安を当局が認めるかが当面の注目点になる。
7.G7サミット、6月下旬に 米大統領補佐官
オブライエン米大統領補佐官(国家安全保障担当)は24日のCBSニュースのインタビューで、主要7カ国(G7)首脳会議(サミット)を対面式で開く場合は時期が6月下旬になるとの見通しを示した。「トランプ大統領は招待状を出し、これまでとてもいい反応が返っている」と語った。
G7サミットは当初、6月10〜12日にワシントン近郊の大統領山荘「キャンプデービッド」で開く方針だったが、新型コロナウイルスの影響で3月にテレビ会議方式にいったん変更が決まった。その後、トランプ氏が再び対面式の開催に意欲を示し調整が進んでいる。オブライエン氏は「各国首脳はテレビ会議ではなく、直接会いたいと考えている」と述べた。
また、オブライエン氏はNBCニュースの番組で中国政府が香港の統制強化に向けて議論する香港国家安全法について「香港が『高度な自治』を維持できなくなれば、中国と香港に制裁を科すことになるだろう」と述べ、中国を強くけん制した。
「中国が香港を乗っ取れば、香港がアジアの金融センターとしての地位を守るのは困難だろう」との見方を示した。もし中国が香港を通じて西側諸国の資本にアクセスできなくなれば「習近平(シー・ジンピン)政権と中国共産党には打撃となる」と警告した。
8.ドイツ経済は底入れか 景況感改善、正常化は遠く
ドイツのIfo経済研究所が25日発表した5月の企業景況感指数は前月を5.3ポイント上回る79.5となり、3カ月ぶりに上昇に転じた。ドイツでは4月から徐々に新型コロナウイルスの感染拡大に対する行動制限の緩和が進んでおり、景気の底入れが鮮明になってきた。ただ、感染の第2波への懸念が残り、回復は力強さを欠いている。正常化はなお遠いのが現状だ。
「制限緩和がかすかな希望をもたらした」(同研究所のフュースト所長)。ドイツ企業の景況感の急落にようやく歯止めがかかり、持ち直しに転じた。ドイツでは5月に大規模店舗や飲食店も再開され、制限緩和が今後も順調に進むとの期待が企業心理の改善につながったといえる。
もっとも、企業の現状判断は4月よりわずかに悪化しており、先行きへの期待が景況感全体を押し上げたというのが実態だ。製造業からサービス業までそろって景況感が改善したが、企業の期待通りに制限緩和が進まなければ、企業心理は再び冷え込みかねない。
欧州経済全体をけん引する力強さにも欠ける。ドイツの国内総生産(GDP)に対する輸出の割合は47.4%で、米国や日本の1割台と比べ高い。世界経済が停滞感を強める限り、ドイツ経済の回復には限界がある。
ドイツ政府は3月にGDPの2割に相当する総額7500億ユーロ(約90兆円)の経済対策を示し、景気の底割れ回避に努めてきた。6月初めにも新たに大規模な経済対策を打ち出し、景気回復を後押ししていく方針だ。対策の規模や具体的な中身が今後の焦点になる。
ドイツ連邦統計庁が25日公表した1〜3月のGDPの改定値は前期比マイナス2.2%と大きく落ち込んだ。2019年10〜12月のマイナス0.1%に続く2期連続のマイナスで、ドイツ経済は景気後退局面に入っている。
9.英首相側近、制限中に親類宅へ EU離脱の参謀、首相は擁護
英国のジョンソン首相の側近のドミニク・カミングス上級顧問が、外出制限中に400キロ以上移動し親類を訪問していたことが英メディアの報道で明らかになり、批判が高まっている。政権側はカミングス氏の妻に新型コロナウイルスの症状が出たため、子供を親類に預ける必要があったと反論。ジョンソン氏も24日の記者会見で「合法的で誠実な行動だった」と擁護した。
ただ野党だけでなく与党・保守党の中堅議員からも辞任を求める声が出ており、このままカミングス氏の去就問題が沈静化するかは不透明だ。
カミングス氏は2016年の欧州連合(EU)離脱を問う国民投票で、離脱陣営の戦略立案を担当したEU離脱の立役者だ。ジョンソン政権発足後は上級顧問に就任し、政権運営全体や19年末の総選挙の戦略を練るなどジョンソン氏の懐刀として動いてきた。カミングス氏を失えば政権へのダメージは大きい。
一方で英政府は国民に対し外出制限中は「親類にも会ってはいけない」と訴えており、カミングス氏の行動はこれに矛盾する。だがジョンソン氏は記者会見で「彼は父親としての本能に従った」と述べ、更迭などの処分は下さない考えを強調した。野党は「首相はエリートの友人にだけ特別なルールを適用した」と強く批判している。
10.アマゾン、インドでも5万人短期雇用 配送拠点向け
米アマゾン・ドット・コムはこのほど、インドで約5万人を短期雇用すると発表した。外出制限などを伴う都市封鎖でネット通販の需要が高まっており、配送センターでの梱包作業や宅配といった業務に充てる。米国で4月末までに17万5千人を追加で雇用したのに続くものだ。
アマゾンが公式ブログで発表した。インドでの社員数は明らかにしていないが、2019年10月時点のアジア全体の社員数は約9万5千人だった。インドでの5万人の雇用期間は不明だが、同国では配車サービス大手のオラなどが人員を削減しており、雇用の受け皿になりそうだ。
インドでは新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるため、3月下旬から外出制限などが続く。食品など生活必需品の買い出しのための外出は容認されているが、感染を避けるために外出を控える傾向は強く、必需品をネット通販で買う需要が高まっている