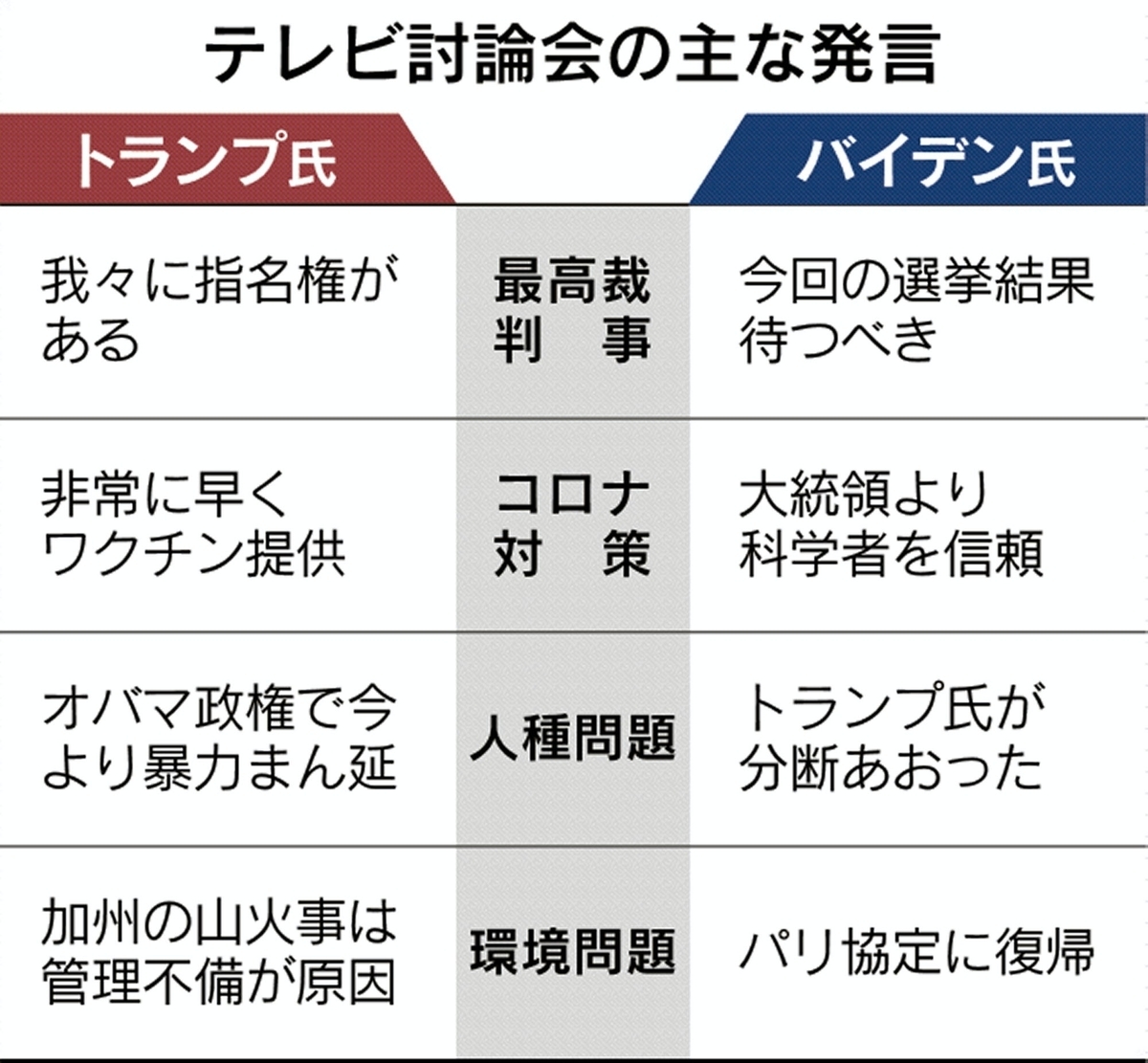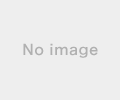2020年06月05日
【経済ニュース 6/5 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
ひも子です
さて米国のお祭り指標とも言える雇用統計が終わりました
気になる結果は・・・
1.米失業率、5月は13%に一転改善 就業者も250万人増
2.NYダウ先物650ドル高 米雇用、予想外の増加で
3.ビデオ会議市場争奪 AmazonとSlack提携、MSに対抗
4.トヨタ、中国5社と燃料電池を共同開発 合弁設立へ
5.日本株、上げ一服でも視線は「上」 生保が警戒解除
6.トランプ氏批判、米軍元高官から続出 軍動員に懸念
7.OPECプラス、6日に会合 協調減産延長の見通し
8.日経平均終値、167円高の2万2863円 5日続伸
9.豪印、防衛協力で新協定 対中けん制 首脳が合意
10.インド、新型コロナで1億2千万人が失職 民間調べ
11.香港取引所、中国・京東の上場承認 米ナスダックと重複
2.NYダウ先物650ドル高 米雇用、予想外の増加で
3.ビデオ会議市場争奪 AmazonとSlack提携、MSに対抗
4.トヨタ、中国5社と燃料電池を共同開発 合弁設立へ
5.日本株、上げ一服でも視線は「上」 生保が警戒解除
6.トランプ氏批判、米軍元高官から続出 軍動員に懸念
7.OPECプラス、6日に会合 協調減産延長の見通し
8.日経平均終値、167円高の2万2863円 5日続伸
9.豪印、防衛協力で新協定 対中けん制 首脳が合意
10.インド、新型コロナで1億2千万人が失職 民間調べ
11.香港取引所、中国・京東の上場承認 米ナスダックと重複
1.米失業率、5月は13%に一転改善 就業者も250万人増
米労働省が5日発表した5月の雇用統計(速報値、季節調整済み)は、失業率が13.3%となり、戦後最悪だった4月(14.7%)から一転して改善した。市場は20%程度の失業率を見込んでいたが、経済活動の一部再開で人材の職場復帰が進んだとみられる。景気動向を敏感に映す非農業部門の就業者数も、前月から250万人増えた。
4月は就業者の減少幅が過去最大の2070万人に達したが、5月は一転して大きく持ち直した。市場は就業者数が約800万人減少すると予測していた。就業者数の伸び幅を業種別にみると、新型コロナで一時的に休業を迫られていた飲食業が137万人増と、大きく持ち直した。小売業も37万人増えた。
米政権は企業の雇用維持を条件に、6600億ドル(約72兆円)という巨額の枠を設けて、従業員の給与支払いを肩代わりする異例の資金供給を続けている。再雇用でも企業は資金を受け取れるため、職場復帰が加速した可能性がある。実際、4月の失業者(2300万人)のうち、職場への早期復帰を前提とした「一時解雇」が8割近くあった。5月でみても失業者(約2100万人)の7割強が「一時解雇」だ。
ただ、それでも失業率は金融危機時のピーク(2009年10月、10.0%)を超えたままで、戦後最悪の水準が続く。飲食店などでは新型コロナによる営業制限が残っており、収束が遅れれば一時解雇が「恒久解雇」になる可能性もある。
雇用統計の予想外の改善を受けて、5日のニューヨーク株式市場では、ダウ工業株30種平均が前日比700ドルほど上昇して始まった。米10年物国債の利回りも上昇し、円相場も2カ月ぶりの円安・ドル高水準となった。
2.NYダウ先物650ドル高 米雇用、予想外の増加で
】5日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均の先物が急上昇した。5日朝発表の米雇用統計が市場予想に反し、雇用者数が増加したことに反応した。前日比の上昇幅は650ドルを超え、2万6900ドル程度と2月下旬以来の高値を付けた。
株式以外の市場でも投資家心理は改善している。米10年物国債の利回りは0.9%台に上昇し、円相場は109円60銭台と約2カ月ぶりの円安・ドル高水準となった。ニューヨーク原油先物期近物は1バレル39ドル台に上昇した。
米雇用統計は事前の市場予想では前月比800万人程度の減少が見込まれていた。失業率は4月の14.7%から20%近くへの上昇が見込まれていたが、実際は13.3%へと低下した。
3.ビデオ会議市場争奪 AmazonとSlack提携、MSに対抗
米アマゾン・ドット・コムがビジネスチャットで台頭してきた米スラック・テクノロジーズとの提携を決めた。アマゾンが力を入れるクラウド部門のライバルである米マイクロソフト(MS)に対抗する。焦点は新型コロナ禍で急成長するビデオ会議サービスだ。「Zoom」を運営する米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズも含め、新興勢力が巨大企業を動かす新たな競争の構図が浮かび上がってきた。
4.トヨタ、中国5社と燃料電池を共同開発 合弁設立へ
トヨタ自動車は中国大手自動車など5社と燃料電池を開発する合弁会社を設立する。同社が開発した燃料電池車(FCV)のシステムを2022年をめどに、北京汽車集団などの自動車メーカーが開発するトラックやバスに提供していく。新エネルギー車へのシフトを進める中国政府はトヨタが持つFCV技術への関心を強めており、共同開発をてこにFCVの普及に向け弾みをつける。
5.日本株、上げ一服でも視線は「上」 生保が警戒解除
5日の東京株式市場で、日経平均株価は前日比78円(0.4%)安の2万2616円で午前の取引を終えた。前週からほぼ休みなしで急騰してきただけに、上げ一服の展開だったが、市場関係者の目線はさらに「上」を向いている。二番底を警戒していた生命保険会社も先物ヘッジ売りの解除に動いたとみられ、早くも「相場は長期上昇トレンドに回帰する」との声が聞かれ始めた。
6.トランプ氏批判、米軍元高官から続出 軍動員に懸念
黒人暴行死事件の抗議デモに対してトランプ米大統領が連邦軍動員を検討していることに、元軍高官から批判が相次いでいる。退役後も政治的発言を控えることが多い軍OBが、最高司令官である現職大統領を非難するのは異例だ。国防総省は4日に首都近郊の連邦軍の一部撤収を決めたが、トランプ氏が「強い指導者」の演出に軍を私物化するとの懸念は消えていない。
「彼は立派な人物だ」。トランプ政権で大統領首席補佐官を務めたケリー元海兵隊大将は4日、米紙ワシントン・ポストのインタビューでマティス前国防長官への支持を表明した。マティス氏は前日、トランプ氏のデモ対応を「軍と市民社会に誤った紛争を生む」と痛烈に批判。反発するトランプ氏が「過大評価された大将」とマティス氏をこき下ろしていた。
米軍制服組トップを務めたマイク・マレン元統合参謀本部議長も米誌への寄稿で「軍最高司令官(であるトランプ氏)による命令の健全性に信頼が置けなくなっている」と批判。ジェームズ・スタブリディス元北大西洋条約機構(NATO)欧州連合軍最高司令官も政権がホワイトハウス前のデモ隊を排除したことに触れて「天安門のようにしてはならない」と苦言を呈した。
トランプ政権はデモがさらに暴徒化した場合に備えて首都ワシントンの近郊に米兵1600人を集めたが、エスパー国防長官は4日、一部の撤収を決めた。武力を見せつけてデモ隊を威圧してきたトランプ氏も容認したとされる。ただ完全撤収については「状況次第だ」(国防総省高官)としており、動員の可能性は完全には消えていない。
共和党系の政治コンサルタントのダグラス・ヘイ氏は「トランプ氏は(軍を通じて)法と秩序を重視する姿勢を示し、混乱を容認するかのような民主党と対比しようとしている」と指摘する。11月の大統領選に向けて米軍が政治利用されているとの見方は多い。
軍にとって人種問題は敏感な問題だ。ピュー・リサーチ・センターによると、2017年時点の人種構成は、非白人が43%と04年に比べて7ポイント上昇した。非白人の貧困家庭出身者が経済的理由で入隊するケースもある。エスパー氏が3日まで公然と黒人差別問題を批判しなかったことにも疑問の声があがっている。
国防長官時代のマティス氏のスピーチライターを務めたガイ・スノッドグラス氏は、国内の混乱が長引けば、中国やロシア、北朝鮮につけいる隙を与えかねないとの懸念が軍OBにはあると指摘する。中国は香港への統制を強める「香港国家安全法」の施行を急ぎ、台湾統一への意欲も隠さない。ロシアは新たな核兵器使用の指針で、通常兵器に対しても核兵器で対抗する可能性を示した。
多くの世論調査では抗議デモや新型コロナウイルスへの対応が不適切だとして、トランプ氏は11月の大統領選で民主党の候補指名を固めたバイデン前副大統領に支持率で引き離されている。米メディアによるとトランプ氏は4日、選対幹部と世論動向に関して協議。今後の対応を話し合ったとみられている。
7.OPECプラス、6日に会合 協調減産延長の見通し
石油輸出国機構(OPEC)とロシアなど非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」は6日に協調減産の継続をめぐる会合を開くことを決めた。4月の合意では、日量970万バレルの協調減産を7月からゆるめるとしていた。新型コロナウイルスの感染拡大にともなう需要消失が深刻で、サウジアラビアやロシアは、現状の規模の減産を少なくとも1カ月延長するよう求める見通しだ。
会合では、イラクやナイジェリアなど決められた減産目標に届かなかった国の合意順守に向けた改善が要求される見通しだ。OPECプラスの5月の合意順守率は90%程度にとどまったとみられている。
一時1バレル20ドルを下回った国際指標の北海ブレント先物は現在、40ドル前後まで回復している。しかし、感染がピークを越えたとみられる中国の需要回復が遅れるなど、年後半の市況をめぐって産油国の不安は根強い。消費国は価格の急落時に貯蔵を一気に増やしたもようで、原油の供給過剰は早期に解消しにくくなっている。
OPECプラスは当初、9、10日の会合を予定していたが、OPEC議長国アルジェリアの要請などで前倒し開催となった。前回と同様、出席者の感染防止のためオンラインの会合となる。
8.日経平均終値、167円高の2万2863円 5日続伸
5日の東京株式市場で日経平均株価は5日続伸した。前日比167円99銭(0.74%)高の2万2863円73銭とほぼ高値引けとなり、2月21日(2万3386円)以来、およそ3カ月半ぶりの高値で終えた。5日以上続伸するのは、2019年10月18〜29日に7日続伸して以来。朝方は短期的な過熱感が意識され利益確定売りが先行したが、米国での経済活動の根強い再開期待などから昼に米ダウ先物が上げ幅を拡大し、日経平均も後場に上昇に転じた。
市場では今晩発表の5月の米雇用統計をめぐり「最近は米経済指標の改善が買い材料になるケースが多かったため、今回も改善を評価して株高で反応すると見越した買いが入った可能性がある」(国内証券)との見方もあった。午前の相場の底堅さを受け、短期筋が午後に買い戻しを進めたのも相場を押し上げた。
欧州中央銀行(ECB)が4日に開いた理事会で、市場予想を上回る規模の追加金融緩和を決定したことも投資家心理の支えになった。
9.豪印、防衛協力で新協定 対中けん制 首脳が合意
オーストラリアとインドがインド太平洋での防衛協力を拡大させる。両国は4日、オンラインで首脳会談を開いた。両国軍の相互運用能力を高める協定で合意し、共同声明を発表した。通商や領土を巡り中国との緊張が高まる中、豪印は日米主導で中国に対抗する「自由で開かれたインド太平洋」構想に賛同、対中けん制で足並みをそろえる。
豪州のモリソン首相とインドのモディ首相は豪印関係を従来の戦略パートナーシップから包括的戦略パートナーシップに格上げすると決めた。相互後方支援協定の締結でも合意した。ロイター通信によると、この協定で両国の軍隊が互いの艦船や航空機に燃料補給したり、整備施設を利用したりできるようになる。
インド太平洋地域での海洋協力に関する共同宣言では「(豪印には)インド太平洋地域で航行の自由を確保する共通利益がある」と指摘した。両国が同地域で「安全保障などの課題に対し共通の懸念を抱いている」とも表明し、南シナ海とインド洋を結ぶシーレーン(海上交通路)の確保を目指す中国を強くけん制した。
両首脳は海軍間の協力を深め、情報交換を進めることも確認した。米印海軍と日本の海上自衛隊による共同訓練「マラバール」への豪州の参加も協議されたとみられる。豪州は2007年マラバールに参加したが、中国が不快感を表明したため、その後は参加していない。外務・防衛担当閣僚協議(2プラス2)に関しても、少なくとも2年ごとに開催し、日米との連携も進める方針だ。
両首脳は貿易や投資活動の拡大に向けた協力も協議した。豪州の投資家向けにインドのインフラ部門についての情報提供を行うなどの連携を進める。
豪印がここにきて中国へのけん制を強める背景には、中国と摩擦や緊張が高まっていることがある。
豪州は今年4月、新型コロナウイルス感染拡大の経緯に関する独立調査を求め、中国の強い反発を受けた。中国は5月、一部の豪産食肉の輸入停止に踏み切り、大麦にも80%超の追加関税を課すと発表した。18年には豪州は安全保障上の懸念から次世代高速通信規格「5G」から中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)を排除している。インドと中国の国境付近では、1カ月ほど前から両国軍の小競り合いが続く。
中国と対立が続く米国は、豪印に秋波を送る。中国が広域経済圏構想「一帯一路」を掲げ、南シナ海やインド太平洋へ進出することに米は非難を続け、通商でも対立する。トランプ米大統領は9月以降に米国で開く主要7カ国首脳会議(G7サミット)に豪印も招待し、対中包囲網の構築につなげる考えで豪印も参加に前向きだ。
もっとも、豪印両国は中国に対し、明確な対決姿勢を示すのは難しい。経済上の関係が深いからだ。中国は豪州にとって輸出の3割超を占める最大の貿易相手国だ。牛肉や大麦など農産物は中国への輸出額の1割程度だが、中国からの「報復」が液化天然ガス(LNG)など資源分野にも及べば影響は大きい。
インドにとっても中国は米国、アラブ首長国連邦(UAE)に次ぐ主要の輸出先だ。両国とも安全保障と経済のバランスで難しいかじ取りが続きそうだ。
10.インド、新型コロナで1億2千万人が失職 民間調べ
首都ニューデリーなどインド都市部の失業率が5月、26%となったもようだ。新型コロナウイルスの感染予防として3月末に全土封鎖を始め、経済活動が停止し、全国では1億2千万人が職を失った。インドは都市部で失職した出稼ぎ労働者が農村に帰らざるを得ず、その過程で感染者が広がる構図となっている。8日から経済活動を段階的に再開するが、感染拡大のペースが速まる恐れもある。
11.香港取引所、中国・京東の上場承認 米ナスダックと重複
香港取引所が中国ネット通販2位の京東集団(JDドットコム)の株式上場を承認したことが5日分かった。米ナスダック市場との重複上場となる。調達目標額は明らかになっていないが、30億ドル(約3300億円)程度になる可能性がある。
香港取引所が同日公開した京東の上場申請資料によると、調達する資金はIT(情報技術)システムや物流などの開発に投じる方針。中国メディアによると、上場時期は6月中となる見通しだ。
一方、香港紙は香港取引所に上場予定の中国ゲーム大手、ネットイースの公募価格が1株あたり123香港ドル(約1700円)になると報じた。上場日は11日で、調達額は210億香港ドル(約2900億円)程度となる見通し。同社も米ナスダック市場との重複上場となる。
2019年11月にアリババ集団が香港で重複上場するなど米上場の中国企業による「香港回帰」が続いている。米中対立が続くなか、中国への理解が深い投資家が多い香港市場を選ぶ中国企業が増えたとみられる。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9904518
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック