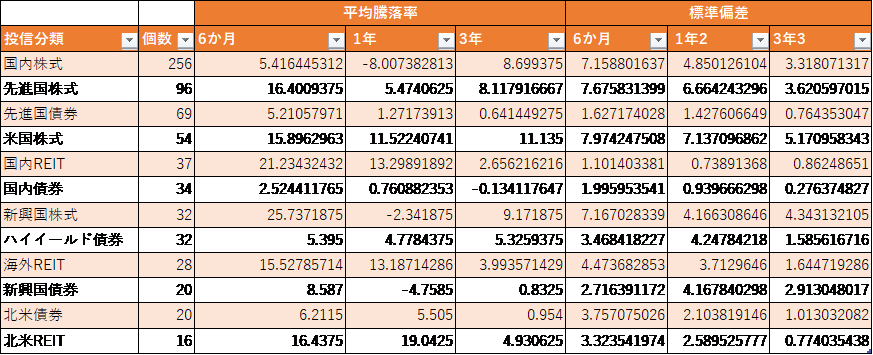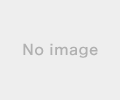2019年02月03日
おすすめ本の紹介(FACTFULLNESS)
「人間は、ドラマチックに考えたがる生き物である」
今回は、最近読んだ本の中で面白いなと思った本に関して紹介して行きたいと思います。
その本は、2019年1月11日に販売された、ハンス・ロスリング著の「FACTFULLNESS 10の思い込みを乗り越え、出たをもとに世界を正しく見る習慣」という本です。
この本は世界で100万部のベストセラーになったことからも、読んでおいて損はないと思うような本であったと思います。
この本の要旨を説明しますと、
この本では、まず人間の生活水準を4つのレベルに区分し、実際に世界の現状はどうなっているのかを国連の様々なデータを用いて説明し、それに対して我々はどれほど勘違いをしているのかに関して説明しています。そして、その勘違いの原因は、人間は良いニュースよりも、悪いニュースのほうがよく目に留まり、記憶に残りやすいという性質があるからであると説明しています。そして、最後に世界を正しく見るためにはどのように物事をとらえる必要があるのか(FACTFULLNESS=事実に基づいて物事の理解しよう)ということを説明しています。
この本の感想を書いていこうと思います。
この本を読んでいく中で、人間がどのように勘違いを起こしていくのかに関しては詳述しているので、そこは非常に勉強になったし、面白いところでした。しかし、データの選択に対して若干の恣意性を感じざるを得ませんでした。具体的には、これ以降で述べますが、著者は世界を所得レベルで4つに分けているのですが、この区別の仕方に関して根拠が薄いような気がするということなど、あたかもその区別の仕方が当たり前ではないかと言わんばかりに唐突に区分が出てくるので、データ選択の恣意性を感じました。そして、じゃあ、データをもとに正しく世界を見るためにはどうしたらいいのかということに関する主張がちょっと中小すぎるのではないかと感じました。これはしょうがないことなのかもしれませんが、読んだ後に「じゃあどうすればいいんだよ」とつい思ってしまいました。しかし、物事の構造に関して自分が知らなかった新たな見方があるということや、ニュース報道等で盛んに言われていることが必ずしも最も適切なものではないということの示唆を与えてくれるという意味でも一読してみることを進めます。
これ以降、この本の内容に関して詳しく書いていこうと思います。
まず人間の生活水準の4つの区分に関してですが、これは一日の平均所得で分類しています。レベル1の人々は一日の平均所得が1ドル程度で、このような生活をしている人々は絶対的な貧困であると称しています。毎日同じような穀物しか食べることしかできず、移動手段は徒歩しかなく、そして、水を汲みに行くにもかなりの時間を要しているのに、その水は汚染されているという生活を送っている人々のことです。
次に、レベル2の人々は、一日の平均所得が4ドル程度の生活をしている人々で、この生活水準にいる人々の主な移動手段は移転者などレベル1と比べた時に多少進化しています。なので、レベル1と同じような水を確保するために自転車を使うことでかなり時間を短縮することができ、ほかの労働に時間を割くことができるようになっている状態であるといえます。
次にレベル3です。レベル3の人々の生活水準は、移動手段が主にバイクになり、水の確保もある程度インフラとして整備されているので簡単にできます。何より一日の平均所得が16ドル程度で、移動手段はここから人力からバイクに代わります。
そして、最後にレベル4です。レベル4の生活水準に暮らす人々は一日の平均所得は32ドル程度になります。もちろん自動車が移動手段の主役になります。説明しなくてもわかると思いますが、今この記事を読んでいる人々はほとんど場合にはレベル4に該当します。
さて、次に人々が世界の現状をいかに勘違いしているかに関して説明をします。
ここでは、三択のクイズ形質の問題が13問与えられる形で、自分たちがどれくらい世界に関して勘違いをしているのかということや、なぜそのような勘違いを起こすのかに関して説明をしています。
ここではすべては紹介できなきので、いくつか印象に残ったものを紹介していきます。
まずこんな質問です。「世界で最も多くの人が住んでいるのはどこでしょう? A低所得国、B中所得国、C高所得国」皆さんはどれが正解だと思いますか? 正解はBの中所得国が成果なのですが、この本によると意外にもAの低所得国に住んでいる人が最も多いと考えている人々が多いようです。なぜこのような考え方が、多く生まれてしまうのかに関して著者は以下のような考え方をしています。それは、人間というのは物事を「二項対立」で考えるのが好きであるということです。二項対立で物事を考えるとは、正義と悪、富者と貧者というようにその物事の間を考えずに、物事を二つの命題に分けて考えようとすることである。この考え方には、物事を構造を簡略化するという利点もありますが、中間層を見ないことになってしまうので、場合によっては構造を把握することを大きく損なってしまうことがあります。特に今回紹介しました質問では、実際には中所得国(レベル2と3)に暮らす人々が最も多いにもかかわらず、レベル1にような低所得国に暮らす人々が最も多いというような勘違いを起こしてしまうのです。さらに、二項対立による考え方は、構造を把握するのに簡単なだけではなく、特に貧富の差に関しては世界の1%の人々が99%の富を占有するなどのようなに劇的な主張を混ぜることができます。なので、余計にこの間が肩に傾倒ししまうのはないでしょうかと筆者は伝えています。
もう一つ紹介します。次はこんな質問です。
「国連の予測によると、2100年には今よりも人口が40億人増える言われています。人口が増える最も大きな理由は何でしょう? A子供が増えるから B大人が増えるから C高齢者が増えるから」
このクイズの答えは、Bの大人の数が増えるからというのが正解です。一方で一般の人々は、子供の数が増えるから人口が増加すると考えているようです。このような勘違いを起こす理由として著者が挙げていることは、「人々は一般的に物事を線形でとらえがちである」ということを挙げています。特に今回のクイズでは、「こどもの数が年数立つごとに線形に増加し続けるのではないか」という勘違いから来ていると主張しています。子供の数はその親の所得に依存しますが、所得が低いような家庭では子供は重要な労働力であると同時に衛生環境が悪いためにすぐに亡くなってしまう可能性が高いです。なので、低所得国ほど一人の女性に対してのこども数が多くなりますが、所得が多くなって安定的に暮らすことができるようになるにつれて、子供は労働力として不要になり、それよりも教育をしっかり受けさせるようにするためにも少数になっていきます。なので、経済が成長していき、所得の底上げがなされるといわゆる合計特殊出生率の数は低下していきます。なので、こども数はある程度は増加し続けますが、ある期間を過ぎるとほとんど増えない状況になると考えることができます。その一方で、医療の発達等で現在は平均寿命はますます高くなっています。なので、より長く生きる子tのできる人が増えているので、大人になる前に死ぬ人が減少していくと同時に、高齢者になるまで生きている人々も増加していきます。このクイズでは、物事が推移する状況を線形で把握しようというのは構造を把握するのが最も簡単であるために、そのような勘違いが起こるのだと説明されています。もちろん線形に推移していくものもありますが、推移の仕方に関しては大きく分けて5つあり、線形型、S字型、逆S字型、こぶ型、指数関数型です。物事委の性質を把握し、その推移の仕方はいったいどのようになるのかをしっかり見極める力が必要になります。
このように、この本では10章に分けて、物事の構造を把握するときにどのように勘違いを起こすのかに関して、説明しています。私の文章力ではなかなか面白さが伝わりにくいかもしれませんが、興味を持った方は是非読んでみてはいかがでしょうか? Amazonでもベストセラーのビジネス書になっており大変面白いと思います。
今回は、最近読んだ本の中で面白いなと思った本に関して紹介して行きたいと思います。
その本は、2019年1月11日に販売された、ハンス・ロスリング著の「FACTFULLNESS 10の思い込みを乗り越え、出たをもとに世界を正しく見る習慣」という本です。
この本は世界で100万部のベストセラーになったことからも、読んでおいて損はないと思うような本であったと思います。
この本の要旨を説明しますと、
この本では、まず人間の生活水準を4つのレベルに区分し、実際に世界の現状はどうなっているのかを国連の様々なデータを用いて説明し、それに対して我々はどれほど勘違いをしているのかに関して説明しています。そして、その勘違いの原因は、人間は良いニュースよりも、悪いニュースのほうがよく目に留まり、記憶に残りやすいという性質があるからであると説明しています。そして、最後に世界を正しく見るためにはどのように物事をとらえる必要があるのか(FACTFULLNESS=事実に基づいて物事の理解しよう)ということを説明しています。
この本の感想を書いていこうと思います。
この本を読んでいく中で、人間がどのように勘違いを起こしていくのかに関しては詳述しているので、そこは非常に勉強になったし、面白いところでした。しかし、データの選択に対して若干の恣意性を感じざるを得ませんでした。具体的には、これ以降で述べますが、著者は世界を所得レベルで4つに分けているのですが、この区別の仕方に関して根拠が薄いような気がするということなど、あたかもその区別の仕方が当たり前ではないかと言わんばかりに唐突に区分が出てくるので、データ選択の恣意性を感じました。そして、じゃあ、データをもとに正しく世界を見るためにはどうしたらいいのかということに関する主張がちょっと中小すぎるのではないかと感じました。これはしょうがないことなのかもしれませんが、読んだ後に「じゃあどうすればいいんだよ」とつい思ってしまいました。しかし、物事の構造に関して自分が知らなかった新たな見方があるということや、ニュース報道等で盛んに言われていることが必ずしも最も適切なものではないということの示唆を与えてくれるという意味でも一読してみることを進めます。
これ以降、この本の内容に関して詳しく書いていこうと思います。
まず人間の生活水準の4つの区分に関してですが、これは一日の平均所得で分類しています。レベル1の人々は一日の平均所得が1ドル程度で、このような生活をしている人々は絶対的な貧困であると称しています。毎日同じような穀物しか食べることしかできず、移動手段は徒歩しかなく、そして、水を汲みに行くにもかなりの時間を要しているのに、その水は汚染されているという生活を送っている人々のことです。
次に、レベル2の人々は、一日の平均所得が4ドル程度の生活をしている人々で、この生活水準にいる人々の主な移動手段は移転者などレベル1と比べた時に多少進化しています。なので、レベル1と同じような水を確保するために自転車を使うことでかなり時間を短縮することができ、ほかの労働に時間を割くことができるようになっている状態であるといえます。
次にレベル3です。レベル3の人々の生活水準は、移動手段が主にバイクになり、水の確保もある程度インフラとして整備されているので簡単にできます。何より一日の平均所得が16ドル程度で、移動手段はここから人力からバイクに代わります。
そして、最後にレベル4です。レベル4の生活水準に暮らす人々は一日の平均所得は32ドル程度になります。もちろん自動車が移動手段の主役になります。説明しなくてもわかると思いますが、今この記事を読んでいる人々はほとんど場合にはレベル4に該当します。
さて、次に人々が世界の現状をいかに勘違いしているかに関して説明をします。
ここでは、三択のクイズ形質の問題が13問与えられる形で、自分たちがどれくらい世界に関して勘違いをしているのかということや、なぜそのような勘違いを起こすのかに関して説明をしています。
ここではすべては紹介できなきので、いくつか印象に残ったものを紹介していきます。
まずこんな質問です。「世界で最も多くの人が住んでいるのはどこでしょう? A低所得国、B中所得国、C高所得国」皆さんはどれが正解だと思いますか? 正解はBの中所得国が成果なのですが、この本によると意外にもAの低所得国に住んでいる人が最も多いと考えている人々が多いようです。なぜこのような考え方が、多く生まれてしまうのかに関して著者は以下のような考え方をしています。それは、人間というのは物事を「二項対立」で考えるのが好きであるということです。二項対立で物事を考えるとは、正義と悪、富者と貧者というようにその物事の間を考えずに、物事を二つの命題に分けて考えようとすることである。この考え方には、物事を構造を簡略化するという利点もありますが、中間層を見ないことになってしまうので、場合によっては構造を把握することを大きく損なってしまうことがあります。特に今回紹介しました質問では、実際には中所得国(レベル2と3)に暮らす人々が最も多いにもかかわらず、レベル1にような低所得国に暮らす人々が最も多いというような勘違いを起こしてしまうのです。さらに、二項対立による考え方は、構造を把握するのに簡単なだけではなく、特に貧富の差に関しては世界の1%の人々が99%の富を占有するなどのようなに劇的な主張を混ぜることができます。なので、余計にこの間が肩に傾倒ししまうのはないでしょうかと筆者は伝えています。
もう一つ紹介します。次はこんな質問です。
「国連の予測によると、2100年には今よりも人口が40億人増える言われています。人口が増える最も大きな理由は何でしょう? A子供が増えるから B大人が増えるから C高齢者が増えるから」
このクイズの答えは、Bの大人の数が増えるからというのが正解です。一方で一般の人々は、子供の数が増えるから人口が増加すると考えているようです。このような勘違いを起こす理由として著者が挙げていることは、「人々は一般的に物事を線形でとらえがちである」ということを挙げています。特に今回のクイズでは、「こどもの数が年数立つごとに線形に増加し続けるのではないか」という勘違いから来ていると主張しています。子供の数はその親の所得に依存しますが、所得が低いような家庭では子供は重要な労働力であると同時に衛生環境が悪いためにすぐに亡くなってしまう可能性が高いです。なので、低所得国ほど一人の女性に対してのこども数が多くなりますが、所得が多くなって安定的に暮らすことができるようになるにつれて、子供は労働力として不要になり、それよりも教育をしっかり受けさせるようにするためにも少数になっていきます。なので、経済が成長していき、所得の底上げがなされるといわゆる合計特殊出生率の数は低下していきます。なので、こども数はある程度は増加し続けますが、ある期間を過ぎるとほとんど増えない状況になると考えることができます。その一方で、医療の発達等で現在は平均寿命はますます高くなっています。なので、より長く生きる子tのできる人が増えているので、大人になる前に死ぬ人が減少していくと同時に、高齢者になるまで生きている人々も増加していきます。このクイズでは、物事が推移する状況を線形で把握しようというのは構造を把握するのが最も簡単であるために、そのような勘違いが起こるのだと説明されています。もちろん線形に推移していくものもありますが、推移の仕方に関しては大きく分けて5つあり、線形型、S字型、逆S字型、こぶ型、指数関数型です。物事委の性質を把握し、その推移の仕方はいったいどのようになるのかをしっかり見極める力が必要になります。
このように、この本では10章に分けて、物事の構造を把握するときにどのように勘違いを起こすのかに関して、説明しています。私の文章力ではなかなか面白さが伝わりにくいかもしれませんが、興味を持った方は是非読んでみてはいかがでしょうか? Amazonでもベストセラーのビジネス書になっており大変面白いと思います。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8528107
この記事へのトラックバック