�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B
�L��
�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B
posted by fanblog
2021�N03��06��
�w���ߑ��x���ĕ��Q��������ˁB���Ęb��
��肽�����Ƃ�����̂ɁA���ꂱ��ƒ��n�߂���L�����Ȃ��Ȃ��āA���Ǔ����Ȃ��Ȃ�l���Ă��邶��Ȃ�
�Ő�[�����œ��������ꂽ�u�l�������Ȃ��v�l�̍l�����iamazon�j�̒��҂Ŗ�����w�����E�x�c�G�ᎁ���A�I�����_�̃��h�o�E�h��w�̐S���w�҃_�C�N�X�^�[�n�E�X�炪�s�����A���ÎԂ��g����2�̎������ʂɂ��ĉ�����Ă��܂��B
�ŏ��̎����ł�4��̒��ÎԂ�p�ӂ��A���̂���1�䂾�������ɂ��������ȁu������v�̎ԂɂȂ��Ă��܂��B�����̎Q���҂����ɂ��ꂼ��̎Ԃ̃X�y�b�N��������A�ʂ����ē�����̎Ԃ�I�ׂ邩�ǂ����A�Ƃ��������ł��B�Q���҂͑傫���A�ȉ���2�ɕ������܂����B
�@�悭�l���đI�ԃO���[�v
�A�I�Ԃ��߂̎��Ԃ����Ȃ��i�������Ԃ��ݒ肳��A���̑O�Ƀp�Y���������ۑ�����Ă��猈�߂Ȃ�������Ȃ��j�O���[�v
�ǂ���̃O���[�v�ɂ��u�R��v�u�G���W���v�Ȃ�4�̃J�e�S���[�ɂ��ĎԂ̐��������܂����B
���̌��ʁA�@�u�悭�l���đI�ԃO���[�v�v�̂قƂ�ǂ��u������v�̎Ԃ�I�Ԃ��Ƃ��ł��A�A�u�I�Ԃ��߂̎��Ԃ����Ȃ��O���[�v�v�������ȏオ�u������v��I�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B
�������A���̎����͑O�t���B�{���͎��̑�2�i�ł��B
��2�i�������V�`���G�[�V�����ŁA4��̂���1�䂪�u������v�B�@�u�悭�l���đI�ԃO���[�v�v�ƇA�u�I�Ԃ��߂̎��Ԃ����Ȃ��O���[�v�v��2�O���[�v�ōs���܂��B
�������ŏ��Ƃ̈Ⴂ�́A�u��������ʁv�ł��B���ꂼ��̎Ԃɂ��Đ�������J�e�S���[�𑝂₵�A���ڂ��������������̂ł��B�Ⴆ�A�g�����N�̑傫����h�����N�z���_�[�̐��Ȃǂɂ��Ă��`���܂����B
���̌��ʂǂ��Ȃ������Ƃ����ƁA�@�u�悭�l���đI�ԃO���[�v�v�̒��Łu������v��I�l��25�����܂����B���������u������v��4�䒆1��i��25���j�Ȃ̂ŁA���Ă����ۂ��ɑI�̂Ƒ卷�Ȃ��Ƃ������ʂł��B
�Ƃ��낪�A�A�u�I�Ԃ��߂̎��Ԃ����Ȃ��O���[�v�v��60���̐l���u������v��I�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B
�����ł������W�߁A�ł������Ǝv������̂�I�т����I�����l����l�������Ǝv���ł��傤���ǁA���́u�x�X�g�ȑI���v�����邽�߂ɂ�������̏����W�߂�A���Ԃ������邱�Ƃ́A�������Ă悭�Ȃ��I�������邱�ƂɂȂ��邱�Ƃ�����܂��B���������ǂ��������Ƃł��傤���H
�������ԍl���Ă��A���܂�Ӗ����Ȃ�
���ߑ��ł������č������Ă��܂��A�ׂ����Ƃ���Ɉӎ����s���߂��āA�����Ȍ��_��}�C�i�X�v�����A�傫�Ȗ��̂悤�Ɍ����Ă��܂��B
���̂��߂ɁA�������V���v���ɑ�ǓI�ɍl�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A��������f�����Ă��������ł��B
���������Ԃ�������A���������f���o����Ƃ͌���Ȃ��̂ł��B
�Z���ԂŌ��߂��O���[�v�̐��𗦂������Ƃ������ʂ̗��R�Ƃ��āA�Z���ԂŌ��߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��O���[�v�́A���Ԃ��Ȃ����A���ɐ������D�揇�ʂ����āA�����I�ɑI���ł����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B
�D�揇�ʂ����Ă����A�ׂ����Ƃ���ɂ͖ڂ������Ȃ��i���Y��Ă����j�B���̂悤�ȏK�����v�l�̃��_���Ȃ��A���f�����s���ɂȂ����Ă���̂ł��B
����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����Ƃ�����
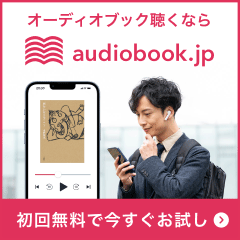

�u�����I�ɂ�肽���v�Ƃ����l��������ƁA�s������O�ɁA�Ȃ�ׂ������̏����W�߂Ă���łȂ��ƍs���ł��Ȃ��Ǝv���Ă��܂�����ł��B��������ďW�߂����̂����ł������č������āA�s���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B
�������A�ǂ̂����������ɍ����Ă��邩�́A���ۂɂ���Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂���B �����ŔY��ʼn������Ȃ����炢�Ȃ�A�Ƃ肠��������Ă݂�����̂ł��B�ǂ̂����ɂ���A��������������ʂ�����̂͊ԈႢ�Ȃ��̂ł�����B
�ł��A�l�͂Ȃ�ׂ����N�����Đg�ɕt�������Ǝv���������ł��B���N�����悤�Ƃ��邱�Ǝ��͈̂������Ƃł͂���܂��A���͂��̂����ł��B
�Ⴆ�Ήp��͂Ȃǂ̃X�L���n�̂��̂͂قƂ�ǁA�K�i��ɐ������܂��B���炭�������������Ȃ����Ԃ������āA������O�b�ƐL�тĂ���̂ł����A�����̐l�͂����������ς݊��Ԃɑς���܂���B���������߂āA���ꂱ��V����������͍����܂����A���ꂪ�������Ď����𐬒����Ԃɓ��B���邱�Ƃ��牓�����Ă���̂ł��B
�厖�Ȃ̂͌����������p���̂��₷���ŁA�����̂�т�Ƃ����y�[�X�ł����Ă��A�܂��͐����������ł���i�K�ɓ��B���邱�Ƃ�D�悷�ׂ��Ȃ̂ł��B�p�����邽�߂̍H�v�Ƃ��ẮA�u�����ɂƂ��ĐS���I�ȃn�[�h���̒Ⴂ�A�ł��邾���ȒP�Ȃ��Ƃ���n�߂�v�u������x�̌����I�Ȃ���������������A�Ë����Č��蔭�Ԃ���v�Ƃ��������̂�����܂��B
�l���x��ĉ������n�߂悤�Ƃ���l�́A�u�����ƌ����I�ɂ��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��v�Əł肪���ł����A�܂��͂��̍l�������߂Ă��������B
��ʓI�ɂ́A�I�����������ق�����������`�����X���L����Ǝv��ꂪ���ł��B�������A�l�́A�I�����������ƍs�����Â炭�Ȃ�̂ł��B�������ŁA����ނ̃��C���i�b�v�̏��i�ƁA���\��ނ̃��C���i�b�v�̏��i�Ƃ��r�����ꍇ�A��ނ����Ȃ����i�̂ق����͂邩�ɔ���₷���Ƃ����������ʂ�����܂��B
�����͂����Ă��A�I���������Ȃ��ƕs���ł���ˁB�s������O�ɂ܂����������W�����Ȃ��̂͂ǂ����Ǝv���܂����A������x�����W�߂��i�K�ŁA�s���Ɉڂ����Ƃ���Ȃ̂ł��B
������ڎw���Ă��A���͖��ʂȘJ�͂Ɏ��Ԃ��₵�Č��ʂ�����Ȃ����Ƃ������̂ł��B
���낢��l���āA�����̗ǂ�������͍�����O�ɁA�܂��͍s�������Ă���Y�ނ悤�ɂ��Ă����܂��傤�B


�ŒZ3�T�ԂŎ��i���擾�ł���ʐM���i�y���[�L�����z

�����L���O�ɎQ�����Ă܂�
��낵�����������|�`�b��
���Ă���������Ɨ�݂ɂȂ�܂� ��

�ɂق�u���O��

�����a�����L���O
�Ő�[�����œ��������ꂽ�u�l�������Ȃ��v�l�̍l�����iamazon�j�̒��҂Ŗ�����w�����E�x�c�G�ᎁ���A�I�����_�̃��h�o�E�h��w�̐S���w�҃_�C�N�X�^�[�n�E�X�炪�s�����A���ÎԂ��g����2�̎������ʂɂ��ĉ�����Ă��܂��B
�ŏ��̎����ł�4��̒��ÎԂ�p�ӂ��A���̂���1�䂾�������ɂ��������ȁu������v�̎ԂɂȂ��Ă��܂��B�����̎Q���҂����ɂ��ꂼ��̎Ԃ̃X�y�b�N��������A�ʂ����ē�����̎Ԃ�I�ׂ邩�ǂ����A�Ƃ��������ł��B�Q���҂͑傫���A�ȉ���2�ɕ������܂����B
�@�悭�l���đI�ԃO���[�v
�A�I�Ԃ��߂̎��Ԃ����Ȃ��i�������Ԃ��ݒ肳��A���̑O�Ƀp�Y���������ۑ�����Ă��猈�߂Ȃ�������Ȃ��j�O���[�v
�ǂ���̃O���[�v�ɂ��u�R��v�u�G���W���v�Ȃ�4�̃J�e�S���[�ɂ��ĎԂ̐��������܂����B
���̌��ʁA�@�u�悭�l���đI�ԃO���[�v�v�̂قƂ�ǂ��u������v�̎Ԃ�I�Ԃ��Ƃ��ł��A�A�u�I�Ԃ��߂̎��Ԃ����Ȃ��O���[�v�v�������ȏオ�u������v��I�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B
�������A���̎����͑O�t���B�{���͎��̑�2�i�ł��B
��2�i�������V�`���G�[�V�����ŁA4��̂���1�䂪�u������v�B�@�u�悭�l���đI�ԃO���[�v�v�ƇA�u�I�Ԃ��߂̎��Ԃ����Ȃ��O���[�v�v��2�O���[�v�ōs���܂��B
�������ŏ��Ƃ̈Ⴂ�́A�u��������ʁv�ł��B���ꂼ��̎Ԃɂ��Đ�������J�e�S���[�𑝂₵�A���ڂ��������������̂ł��B�Ⴆ�A�g�����N�̑傫����h�����N�z���_�[�̐��Ȃǂɂ��Ă��`���܂����B
���̌��ʂǂ��Ȃ������Ƃ����ƁA�@�u�悭�l���đI�ԃO���[�v�v�̒��Łu������v��I�l��25�����܂����B���������u������v��4�䒆1��i��25���j�Ȃ̂ŁA���Ă����ۂ��ɑI�̂Ƒ卷�Ȃ��Ƃ������ʂł��B
�Ƃ��낪�A�A�u�I�Ԃ��߂̎��Ԃ����Ȃ��O���[�v�v��60���̐l���u������v��I�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B
�����ł������W�߁A�ł������Ǝv������̂�I�т����I�����l����l�������Ǝv���ł��傤���ǁA���́u�x�X�g�ȑI���v�����邽�߂ɂ�������̏����W�߂�A���Ԃ������邱�Ƃ́A�������Ă悭�Ȃ��I�������邱�ƂɂȂ��邱�Ƃ�����܂��B���������ǂ��������Ƃł��傤���H
�������ԍl���Ă��A���܂�Ӗ����Ȃ�
���ߑ��ł������č������Ă��܂��A�ׂ����Ƃ���Ɉӎ����s���߂��āA�����Ȍ��_��}�C�i�X�v�����A�傫�Ȗ��̂悤�Ɍ����Ă��܂��B
���̂��߂ɁA�������V���v���ɑ�ǓI�ɍl�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A��������f�����Ă��������ł��B
���������Ԃ�������A���������f���o����Ƃ͌���Ȃ��̂ł��B
�Z���ԂŌ��߂��O���[�v�̐��𗦂������Ƃ������ʂ̗��R�Ƃ��āA�Z���ԂŌ��߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��O���[�v�́A���Ԃ��Ȃ����A���ɐ������D�揇�ʂ����āA�����I�ɑI���ł����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B
�D�揇�ʂ����Ă����A�ׂ����Ƃ���ɂ͖ڂ������Ȃ��i���Y��Ă����j�B���̂悤�ȏK�����v�l�̃��_���Ȃ��A���f�����s���ɂȂ����Ă���̂ł��B
����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����Ƃ�����
�u�����I�ɂ�肽���v�Ƃ����l��������ƁA�s������O�ɁA�Ȃ�ׂ������̏����W�߂Ă���łȂ��ƍs���ł��Ȃ��Ǝv���Ă��܂�����ł��B��������ďW�߂����̂����ł������č������āA�s���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B
�������A�ǂ̂����������ɍ����Ă��邩�́A���ۂɂ���Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂���B �����ŔY��ʼn������Ȃ����炢�Ȃ�A�Ƃ肠��������Ă݂�����̂ł��B�ǂ̂����ɂ���A��������������ʂ�����̂͊ԈႢ�Ȃ��̂ł�����B
�ł��A�l�͂Ȃ�ׂ����N�����Đg�ɕt�������Ǝv���������ł��B���N�����悤�Ƃ��邱�Ǝ��͈̂������Ƃł͂���܂��A���͂��̂����ł��B
�Ⴆ�Ήp��͂Ȃǂ̃X�L���n�̂��̂͂قƂ�ǁA�K�i��ɐ������܂��B���炭�������������Ȃ����Ԃ������āA������O�b�ƐL�тĂ���̂ł����A�����̐l�͂����������ς݊��Ԃɑς���܂���B���������߂āA���ꂱ��V����������͍����܂����A���ꂪ�������Ď����𐬒����Ԃɓ��B���邱�Ƃ��牓�����Ă���̂ł��B
�厖�Ȃ̂͌����������p���̂��₷���ŁA�����̂�т�Ƃ����y�[�X�ł����Ă��A�܂��͐����������ł���i�K�ɓ��B���邱�Ƃ�D�悷�ׂ��Ȃ̂ł��B�p�����邽�߂̍H�v�Ƃ��ẮA�u�����ɂƂ��ĐS���I�ȃn�[�h���̒Ⴂ�A�ł��邾���ȒP�Ȃ��Ƃ���n�߂�v�u������x�̌����I�Ȃ���������������A�Ë����Č��蔭�Ԃ���v�Ƃ��������̂�����܂��B
�l���x��ĉ������n�߂悤�Ƃ���l�́A�u�����ƌ����I�ɂ��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��v�Əł肪���ł����A�܂��͂��̍l�������߂Ă��������B
��ʓI�ɂ́A�I�����������ق�����������`�����X���L����Ǝv��ꂪ���ł��B�������A�l�́A�I�����������ƍs�����Â炭�Ȃ�̂ł��B�������ŁA����ނ̃��C���i�b�v�̏��i�ƁA���\��ނ̃��C���i�b�v�̏��i�Ƃ��r�����ꍇ�A��ނ����Ȃ����i�̂ق����͂邩�ɔ���₷���Ƃ����������ʂ�����܂��B
�����͂����Ă��A�I���������Ȃ��ƕs���ł���ˁB�s������O�ɂ܂����������W�����Ȃ��̂͂ǂ����Ǝv���܂����A������x�����W�߂��i�K�ŁA�s���Ɉڂ����Ƃ���Ȃ̂ł��B
������ڎw���Ă��A���͖��ʂȘJ�͂Ɏ��Ԃ��₵�Č��ʂ�����Ȃ����Ƃ������̂ł��B
���낢��l���āA�����̗ǂ�������͍�����O�ɁA�܂��͍s�������Ă���Y�ނ悤�ɂ��Ă����܂��傤�B
�ŒZ3�T�ԂŎ��i���擾�ł���ʐM���i�y���[�L�����z
�����L���O�ɎQ�����Ă܂�
��낵�����������|�`�b��
���Ă���������Ɨ�݂ɂȂ�܂� ��
�ɂق�u���O��

�����a�����L���O
2021�N02��16��
��������藧�Ă�S�̖��߂��Ęb��
�l�̖ڂ��C�ɂȂ錴���ƂR�̉����@

�l�̖ڂ��C�ɂ��邱�Ƃ͈������Ƃ���Ȃ���ˁB
�g�����Ȃ݂⋤�����͑�����ˁB
�����ǁA�l�̖ڂ��C�ɂ��߂���l���āu���Ȓ��S�I�v�Ƃ������邻�����B
���́A�ȑO�u���O�ɂ����������ǁA�l���l�̖ڂ��������C�ɂ���^�C�v�B
���������l���ĈӊO�ɑ�����������Ȃ��ȁB
���Ȓ��S�I���g����ꂽ���Ȃ��h �g�{��ꂽ���Ȃ��h�Ƃ����C�����͎��������̖�肾����ˁB
�S���w�p��ł́A���̂悤����������藧�Ă�S�̖��߂��u�h���C�o�[�v���Ă������Ă��B
�X�|���T�[�����N
���̃h���C�o�[�ɂ́A�ȉ��̂T�����B
- ���S�ł���iBe Perfect�j
- ���l�������iPlease Others�j
- �w�͂���iTry Hard�j
- ��������iBe Strong�j
- �}���iHurry Up�j
���̃h���C�o�[�̌����ˑΏ��@��m�邱�ƂŁA�C�ɂ��߂��������Ƃ́A��������悤���Ă��ƁB
�X�|���T�[�����N
�����F�c�����̃W���b�W
���l�̖ڂ��C�ɂȂ�l�̋��ʓ_�́A�c�����ɂ₽��W���b�W���Ă���l��A�ߊ����Ă���l���ƒ��w�Z�ɂ����Ƃ������Ƃ��B
����Ȋ��Ɉ炿�A�{���̎��������炯�o����o�������ĂȂ��ƁA�u���l�͎����ɕ]���������ď����鑶�݁v�Ƃ��ĔF�����Ă��܂��B
������A�������Ȃ��悤���u���l�̖ځv���C�ɂ���h���C�o�[�����悤�ɂȂ���Ă��B
�̂P �����̋C�����ƂȂ���
�u�`���Ȃ���v�Ƃ����h���C�o�[�͖����̂��Ƃ���ˁB
���̃h���C�o�[�i��̂��Ɓj���ɂ����u�����݂̎����̋C�����v�Ɉӎ����W�����Ă݂悤�B
�}�C���h�t���l�X�i�O�ɏ������u���O�j���A�u�����݁v���ɂ����ґz�@�Ȃ�B
�X�|���T�[�����N
�̂Q �{���̑��l������
�u���l�̖ڂ��C�ɂ���v��Ԃ́A����u�����̒��̏������o�������Ƃɂ����A�z����̑����v���C�ɂ��Ă����ԂȂ�ˁB
������A����̖{���̋C�������āA����̂܂܂̑��������邱�Ƃ��ӎ����Ă݂悤�B
��R ���ۂɍs�����Ă݂悤
���l�̖ڂ��C�ɂ��߂���l�́A�����ɕs���ɂȂ邱�Ƃ�������ˁB
�s���ɂ͗ǂ��s���ƈ����s���Ă̂������ĂˁA
�ǂ��s���̏������u�����s���ɂ����s���v
�����s���Ƃ́A�Ȃ��Ȃ��u���P�s���ֈڂ��ɂ����s���v
�s���Ɉڂ��ɂ����̂́A�u�ߋ��̏��v�ւ̋��ꂪ�����̂悤���ˁB
�����ǁA�S�z��s���͍s���𑣂����߂̊���Ȃ�ŁA���ۂɍs�����n�߂�A�ȁ`�債�����ƂȂ�������ˁH�ƂȂ��ĕs���͂Ȃ��Ȃ��B
���̂R�̕��@�������āA�l�̖ڂ��C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�Ƃ����ˁB
�l���撣��ׁI
�����L���O�ɎQ�����Ă܂�
��낵�����������|�`�b��
���Ă���������Ɨ�݂ɂȂ�܂� ��
�ɂق�u���O��

�����a�����L���O
2021�N02��09��
�V���N�}�̃��o�E���h���ʁH
�V���N�}�̃��o�E���h���ʂ��Ēm���Ă܂��H
�w�������l���Ȃ��悤�ɓw�͂������قǁA�������Ă��̂��Ƃ������痣��Ȃ��Ȃ�x�Ƃ������ۂ�������闝�_�̂��ƁB
����́A�A�����J�̐S���w�҃_�j�G���E�E�F�O�i�[���炪�����ɂ���Ė��炩�ɂ��ꂽ���ۂ̂��ƂŁA�S���w�̐��E�ł͗L���ȗ��_�Ȃ����ȁB
����́A�팱�҂��R�̃O���[�v�ɕ����ăV���N�}�̉f�����ςĂ��炤�����̂��ƂŁA
�P�N��A���̂R�̃O���[�v�ɃV���N�}�̂��Ƃ����₵���Ƃ���A��ԃV���N�}�̂��Ƃ��o���Ă����̂́A�Ȃ�ƂP�̃O���[�v�����������ł��B
�u�o���Ȃ��ł��������v�ƌ���ꂽ�팱�҂́A�V���N�}�̂��Ƃ��l���Ȃ��悤�ɓw�͂���B
�������A�w�͂������قLjӎ����Ă��܂��V���N�}�̂��Ƃ����ɕ�����ł��܂��B
���̌��ʁA�������ē����痣��Ȃ��Ȃ�A�K�R�I�Ɋo���Ă��܂��Ă���킯�ł���B
���̂��Ƃ��g�V���N�}�̃��o�E���h���ʁh���Č�����ł��ˁB
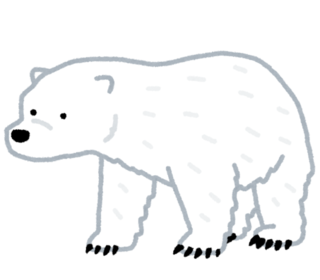
������Ă͂����Ȃ��ɔ������遄
�l�͗}�������ƁA����ɑR����悤�ɔ�������B
�֎~�����Ƃ�肽���Ȃ銴����Ă���܂���ˁB
�l�̏ꍇ�́A�w�֎��x�ł��B
�z���g�h���ł����ۂ߂Ȃ����čl����ƁI
�����ǁA�l�̎d�����i�g���b�N�h���C�o�[�j�����Ɏd�����T���Ă鎞�͋֎����Ă܂��B
�o���_�Ď��̃A���R�[���`�F�b�N�ň���������Ȃ����߂ł��B
�Ȃ���Ȃ�ɂ��v���h���C�o�[�ł�����ˁB
���̎d������܂ł́A��������̔ӎނ͌������܂���ł�����A��D���ł�����B
����Ɠ����悤�ɁA
�Ƃ��ˁB
���\�}�����������Ă�ł���H
���ꂪ����Ȃ��ƂɃ��o�E���h��������ł��B
�ł́A���̑�͂ǂ����邩�Ƃ����Ɓw�֎~�ɂ��}���������x�ł��B
��̓I�ɂ́A�u���Ȃ��v�ł͂Ȃ��u������ɉ�������v�����߂邱�ƁB
�։��Ȃ�A�u�^�o�R���z��Ȃ��v�ł͂Ȃ��u�^�o�R���z������ɃK�����������v�Ƃ��ł��ˁB
�֎~�ł͂Ȃ��ʂ̉���������E�E�E������ȃ��o�E���h���ʂ������L���Ȏ�i�Ȃ�ł��B
�悭�A�l�K�e�B�u�Ȕ�����l����������l�Ɂw�|�W�e�B�u�ɍl����I�x�Ƃ��A�w�|�W�e�B�u�Ȕ���������I�x�Ƃ��������������A�l�b�g�����ĂĂ��|�W�e�B�u�v�l�Ȃ��A�A�A�Ƃ��₽��Ƃ͂т����Ă��邯�ǁA���̗��_���炷��������ċt���ʂ��Ă��Ƃł��ˁB
�l�K�e�B�u�Ȋ����v�l��}�������ɁA���̂܂���Ĕg������̂�҂̂����������ł��B
���ꂪ�A������Ɏ��グ���Ă���w�}�C���h�t���l�X�x�Ƃ������z�ł��B
�}�C���h�t���l�X�ґz�Ƃ����̂�����܂��ˁB
�l�Ȃ́A�l�K�e�B�u�̂����܂�݂����Ȑl�ԂȂ̂ŁA��Ɉ��������ɕ������Ƃ炦�Ă��܂��Ȃ������Ď����������ɂȂ��ˁB
���������l���������鎩����S���Ђ�����߂āA���̂܂����Ă݂悤���Ȃ��Ďv���Ă܂���B
�Ȃ��Ȃ�������Ƃ����ǂˁB
�܂��b�����܂Ƃ߂�ƁA�������ے肵�ė}�����Ă��ǂ����ƂȂ���B�f���Ɏ���ĕʂ̕�����l���悤���Ă��Ƃ��ˁB
���Љ���֘A�{�͂��ꁫ
�����L���O�ɎQ�����Ă܂�
��낵�����������|�`�b��
���Ă���������Ɨ�݂ɂȂ�܂� ��

�ɂق�u���O��

�����a�����L���O
�w�������l���Ȃ��悤�ɓw�͂������قǁA�������Ă��̂��Ƃ������痣��Ȃ��Ȃ�x�Ƃ������ۂ�������闝�_�̂��ƁB
����́A�A�����J�̐S���w�҃_�j�G���E�E�F�O�i�[���炪�����ɂ���Ė��炩�ɂ��ꂽ���ۂ̂��ƂŁA�S���w�̐��E�ł͗L���ȗ��_�Ȃ����ȁB
����́A�팱�҂��R�̃O���[�v�ɕ����ăV���N�}�̉f�����ςĂ��炤�����̂��ƂŁA
- �V���N�}�̂��Ƃ͊o���Ȃ��ł��������B�ƌ����ςĂ��炤�B
- �V���N�}�̂��Ƃ��o���Ă��������B�ƌ����ςĂ��炤�B
- �V���N�}�̂��Ƃɂ��āA���ɉ������킸�ɊςĂ��炤�B
�P�N��A���̂R�̃O���[�v�ɃV���N�}�̂��Ƃ����₵���Ƃ���A��ԃV���N�}�̂��Ƃ��o���Ă����̂́A�Ȃ�ƂP�̃O���[�v�����������ł��B
�u�o���Ȃ��ł��������v�ƌ���ꂽ�팱�҂́A�V���N�}�̂��Ƃ��l���Ȃ��悤�ɓw�͂���B
�������A�w�͂������قLjӎ����Ă��܂��V���N�}�̂��Ƃ����ɕ�����ł��܂��B
���̌��ʁA�������ē����痣��Ȃ��Ȃ�A�K�R�I�Ɋo���Ă��܂��Ă���킯�ł���B
���̂��Ƃ��g�V���N�}�̃��o�E���h���ʁh���Č�����ł��ˁB
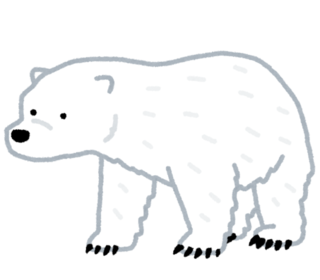
������Ă͂����Ȃ��ɔ������遄
�l�͗}�������ƁA����ɑR����悤�ɔ�������B
�֎~�����Ƃ�肽���Ȃ銴����Ă���܂���ˁB
�l�̏ꍇ�́A�w�֎��x�ł��B
�z���g�h���ł����ۂ߂Ȃ����čl����ƁI
�����ǁA�l�̎d�����i�g���b�N�h���C�o�[�j�����Ɏd�����T���Ă鎞�͋֎����Ă܂��B
�o���_�Ď��̃A���R�[���`�F�b�N�ň���������Ȃ����߂ł��B
�Ȃ���Ȃ�ɂ��v���h���C�o�[�ł�����ˁB
���̎d������܂ł́A��������̔ӎނ͌������܂���ł�����A��D���ł�����B
����Ɠ����悤�ɁA
- �_�C�G�b�g�ł͐H������
- �։��ł̓^�o�R���z���Ă͂����Ȃ�
�Ƃ��ˁB
���\�}�����������Ă�ł���H
���ꂪ����Ȃ��ƂɃ��o�E���h��������ł��B
�ł́A���̑�͂ǂ����邩�Ƃ����Ɓw�֎~�ɂ��}���������x�ł��B
��̓I�ɂ́A�u���Ȃ��v�ł͂Ȃ��u������ɉ�������v�����߂邱�ƁB
�։��Ȃ�A�u�^�o�R���z��Ȃ��v�ł͂Ȃ��u�^�o�R���z������ɃK�����������v�Ƃ��ł��ˁB
�֎~�ł͂Ȃ��ʂ̉���������E�E�E������ȃ��o�E���h���ʂ������L���Ȏ�i�Ȃ�ł��B
�悭�A�l�K�e�B�u�Ȕ�����l����������l�Ɂw�|�W�e�B�u�ɍl����I�x�Ƃ��A�w�|�W�e�B�u�Ȕ���������I�x�Ƃ��������������A�l�b�g�����ĂĂ��|�W�e�B�u�v�l�Ȃ��A�A�A�Ƃ��₽��Ƃ͂т����Ă��邯�ǁA���̗��_���炷��������ċt���ʂ��Ă��Ƃł��ˁB
�l�K�e�B�u�Ȋ����v�l��}�������ɁA���̂܂���Ĕg������̂�҂̂����������ł��B
���ꂪ�A������Ɏ��グ���Ă���w�}�C���h�t���l�X�x�Ƃ������z�ł��B
�}�C���h�t���l�X�ґz�Ƃ����̂�����܂��ˁB
�l�Ȃ́A�l�K�e�B�u�̂����܂�݂����Ȑl�ԂȂ̂ŁA��Ɉ��������ɕ������Ƃ炦�Ă��܂��Ȃ������Ď����������ɂȂ��ˁB
���������l���������鎩����S���Ђ�����߂āA���̂܂����Ă݂悤���Ȃ��Ďv���Ă܂���B
�Ȃ��Ȃ�������Ƃ����ǂˁB
�܂��b�����܂Ƃ߂�ƁA�������ے肵�ė}�����Ă��ǂ����ƂȂ���B�f���Ɏ���ĕʂ̕�����l���悤���Ă��Ƃ��ˁB
���Љ���֘A�{�͂��ꁫ
�����L���O�ɎQ�����Ă܂�
��낵�����������|�`�b��
���Ă���������Ɨ�݂ɂȂ�܂� ��
�ɂق�u���O��

�����a�����L���O
2021�N02��08��
�����^�����ア�H
�����^�����ア�A�X�g���X���瓦�������Ǝv���Ă邠�Ȃ��A���̖{��ǂ�ł݂�ׂ��ł���
���̖{�́A�X�g���X���y��������@�A�����ă����^�����������邽�߂ɃX�g���X�𖡕��ɕt������@�� �A������Ղ�������Ă��B
���̖{��ǂ�ŁA�����Ȃ����������^�������Ȃ��̂��̂ɂ��ĉ������ˁB
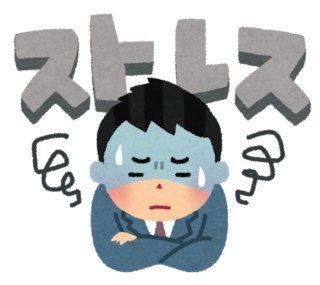
�����B�������̖l���܂��ɁA�����^���Ŏ㉤�I
���l�̖ڂ��C�ɂ���
�����s����������
�����̂������S�z��
�����h������
���C���ア
�S���A�z�炵�������B
����Ȏ��Ƀ����^���X�gDaiGo�́w�X�g���X�𑀂郁���^�������p�x�ɏ��荇���āA�ڂ���E���R���Č����̂��ȁH
�g�X�g���X���ē������Ȃ����āA����Ȃ�����Ȃ��h���ċC�t�����Ă��ꂽ�ˁB
�l���������������ǁA��ʓI�ɃX�g���X�͗��߂����Ȃ��āA�����Ȃ��Ⴂ���Ȃ������Ďv���Ă���ȁB
�����ǃX�g���X�́A�����Ă����ĉ��̉����ɂ��Ȃ�Ȃ���ȁB
���̖{�ǂ�Ŋw�̂́A�X�g���X����������Ȃ��āA�������Ă��ƁB
���ł������̂��̂ɂ͂��ĂȂ���I
�ۑ���Ă������h��݂����Ȃ��ȁB
������͏��z���Ȃ�������Ȃ����A�������Ȃ���Ή��̉����ɂ��Ȃ�Ȃ�����ˁB
�l�Ƃ����l�i���́A�D���ɂȂ�Ȃ��̂͌��ݐi�s�`�Ȃ�B
�z���g�̘b���ˁB
�����ǂ��A���̂܂܂��ች�̉����ɂ��Ȃ�Ȃ��͕̂�������Ă�̂��B
�ǂ��ɂ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��I
�����āA�ς�肽����ł���H
�����Ǝ�����O�����ɕς�������ł���H
�l�����āA�����Y�݂Ȃ���߂��������Ȃ�����ˁB
�|�W�e�B�u�ɉ߂�����������ˁB
�Ǝv���Ă����ɏ��荇�����{�����̖{
�����^���X�gDaiGo�w�X�g���X�𑀂郁���^�������p�x
���̃u���O���A�g�ނ�h���Ǝv���Ȃ�ʂɑE�߂Ȃ�������S���āB
���������������͂Ȃ�����ˁB
�����̐��i�����Ō��ł��傤���Ȃ��A�l�݂����Ȑl������Ȃ�A
�x���ꂽ�Ǝv���ēǂ�ł݂鉿�l�͂����Ȃ����ȁH���Ďv�����̂��B
���̖{�ǂ�ŁA�����炩�ł��C�������y�ɂȂ������ǂ����Ȃ��ĂˁB
�l�́A�Ǐ����z�������̐̂����肾��������A���̖{�̃��r���[�Ȃ�Ĉ̂����Ȃ��Ə����ĂȂ����ǂ��A�C�������~��ꂽ����A�Љ���������̂ˁB
�����������āA�ǂ�ł݂����Ȃ������Đl�����ǂ�ł݂āB
���̖{�ł���
�����^���X�gDaiGo���M
�w�X�g���X�𑀂郁���^�������p�x
���̖{�́A�X�g���X���y��������@�A�����ă����^�����������邽�߂ɃX�g���X�𖡕��ɕt������@�� �A������Ղ�������Ă��B
���̖{��ǂ�ŁA�����Ȃ����������^�������Ȃ��̂��̂ɂ��ĉ������ˁB
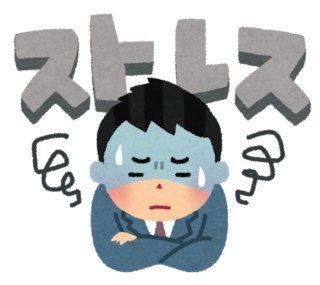
�����B�������̖l���܂��ɁA�����^���Ŏ㉤�I
���l�̖ڂ��C�ɂ���
�����s����������
�����̂������S�z��
�����h������
���C���ア
�S���A�z�炵�������B
����Ȏ��Ƀ����^���X�gDaiGo�́w�X�g���X�𑀂郁���^�������p�x�ɏ��荇���āA�ڂ���E���R���Č����̂��ȁH
�g�X�g���X���ē������Ȃ����āA����Ȃ�����Ȃ��h���ċC�t�����Ă��ꂽ�ˁB
�l���������������ǁA��ʓI�ɃX�g���X�͗��߂����Ȃ��āA�����Ȃ��Ⴂ���Ȃ������Ďv���Ă���ȁB
�����ǃX�g���X�́A�����Ă����ĉ��̉����ɂ��Ȃ�Ȃ���ȁB
���̖{�ǂ�Ŋw�̂́A�X�g���X����������Ȃ��āA�������Ă��ƁB
���ł������̂��̂ɂ͂��ĂȂ���I
�ۑ���Ă������h��݂����Ȃ��ȁB
������͏��z���Ȃ�������Ȃ����A�������Ȃ���Ή��̉����ɂ��Ȃ�Ȃ�����ˁB
�l�Ƃ����l�i���́A�D���ɂȂ�Ȃ��̂͌��ݐi�s�`�Ȃ�B
�z���g�̘b���ˁB
�����ǂ��A���̂܂܂��ች�̉����ɂ��Ȃ�Ȃ��͕̂�������Ă�̂��B
�ǂ��ɂ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��I
�����āA�ς�肽����ł���H
�����Ǝ�����O�����ɕς�������ł���H
�l�����āA�����Y�݂Ȃ���߂��������Ȃ�����ˁB
�|�W�e�B�u�ɉ߂�����������ˁB
�Ǝv���Ă����ɏ��荇�����{�����̖{
�����^���X�gDaiGo�w�X�g���X�𑀂郁���^�������p�x
���̃u���O���A�g�ނ�h���Ǝv���Ȃ�ʂɑE�߂Ȃ�������S���āB
���������������͂Ȃ�����ˁB
�����̐��i�����Ō��ł��傤���Ȃ��A�l�݂����Ȑl������Ȃ�A
�x���ꂽ�Ǝv���ēǂ�ł݂鉿�l�͂����Ȃ����ȁH���Ďv�����̂��B
���̖{�ǂ�ŁA�����炩�ł��C�������y�ɂȂ������ǂ����Ȃ��ĂˁB
�l�́A�Ǐ����z�������̐̂����肾��������A���̖{�̃��r���[�Ȃ�Ĉ̂����Ȃ��Ə����ĂȂ����ǂ��A�C�������~��ꂽ����A�Љ���������̂ˁB
�����������āA�ǂ�ł݂����Ȃ������Đl�����ǂ�ł݂āB
���̖{�ł���
�����^���X�gDaiGo���M
�w�X�g���X�𑀂郁���^�������p�x


