2016年05月13日
青紙鋼のナイフ鍛造をしてきました。
焦がれていた鍛造
これまで研ぎに明け暮れる生活が、一変しそうです。
家族の仕事の都合で、長きにわたる大阪の暮しから、香川県高松市に居を移す事になりました。
突然と言えば突然なのですが、昨年の暮れからなんとなくそんな予感がありました。関東かもという可能性もあったのですが、意外な着地点となり、驚いています。
還暦もとっくに過ぎているので、新天地高松にはなんだか期待感の方が強くなってきています。
高松は、訪れた事もなく両親も青森と丹波がルーツなので土地勘がゼロの地域だったのでどうなる事やら。
で、これまで勤めていた研ぎ工房を退職し、高松での研ぎの環境が出来るまでの間、しばし休息。以前から興味を持っていた刃物作りを体験しに福井県武生市へ行ってきました。

武生はちょうど桜の季節。満開で出迎えてくれました。
小ぶりの蒲鉾板を薄くしたような青紙鋼を高温炉に入れ、焼入れ槌打ちを繰返し、鋼を鍛え形を整え刃つけの行程です。刃つけは、さておいて1400度の炉の作業は、興奮物でした。
炉の温度調整をしながら、槌打ちも鍛冶屋の心地よい(かなりの騒音でした)響きに酔いしれるひと時でした。

焼入れ前の青紙鋼

1400度の炉の中は、古代の熱さが詰まっている

鋼を鍛える
材料の鋼が、みるみる特有の力強さが宿って行く様は、神懸りのような神秘さがありました。
古来より、製法が基本的にはなにも変わっていない普遍的かつ伝統的な鍛造法のルーツは、個人的見解ではありますが、隕石を手にした人が、地球上にはない貴重な硬質の素材を、地球上の素材で再現する際、成層圏を焼かれながら海岸に落下し(地面でも充分に冷える)た様子を、焼入れと言う方法で再現したのではと常々思っています。
焼入れの技法には、そんな先人達の超思考の贈り物と、解釈しています。
炉の作業中、そんな思いを巡らせながら神秘のひと時を満喫できました。

なんとか仕上がりました。
炉の作業を終え、大型の回転砥で裏スキと成形を施し、最後は手研ぎで仕上げました。
日本には、まだまだ古式鍛造の鍛冶場が残っています。後何年続くのか、後継者はいるのか、貴重な和式の鍛造の現場を存続される事を願っています。
高松の周辺にも、高知県の土佐や岡山県の備前なども有数の鍛造が継承されています。
機会を作って、そちらも訪れたいと願っています。
これまで研ぎに明け暮れる生活が、一変しそうです。
家族の仕事の都合で、長きにわたる大阪の暮しから、香川県高松市に居を移す事になりました。
突然と言えば突然なのですが、昨年の暮れからなんとなくそんな予感がありました。関東かもという可能性もあったのですが、意外な着地点となり、驚いています。
還暦もとっくに過ぎているので、新天地高松にはなんだか期待感の方が強くなってきています。
高松は、訪れた事もなく両親も青森と丹波がルーツなので土地勘がゼロの地域だったのでどうなる事やら。
で、これまで勤めていた研ぎ工房を退職し、高松での研ぎの環境が出来るまでの間、しばし休息。以前から興味を持っていた刃物作りを体験しに福井県武生市へ行ってきました。
小ぶりの蒲鉾板を薄くしたような青紙鋼を高温炉に入れ、焼入れ槌打ちを繰返し、鋼を鍛え形を整え刃つけの行程です。刃つけは、さておいて1400度の炉の作業は、興奮物でした。
炉の温度調整をしながら、槌打ちも鍛冶屋の心地よい(かなりの騒音でした)響きに酔いしれるひと時でした。



材料の鋼が、みるみる特有の力強さが宿って行く様は、神懸りのような神秘さがありました。
古来より、製法が基本的にはなにも変わっていない普遍的かつ伝統的な鍛造法のルーツは、個人的見解ではありますが、隕石を手にした人が、地球上にはない貴重な硬質の素材を、地球上の素材で再現する際、成層圏を焼かれながら海岸に落下し(地面でも充分に冷える)た様子を、焼入れと言う方法で再現したのではと常々思っています。
焼入れの技法には、そんな先人達の超思考の贈り物と、解釈しています。
炉の作業中、そんな思いを巡らせながら神秘のひと時を満喫できました。
炉の作業を終え、大型の回転砥で裏スキと成形を施し、最後は手研ぎで仕上げました。
日本には、まだまだ古式鍛造の鍛冶場が残っています。後何年続くのか、後継者はいるのか、貴重な和式の鍛造の現場を存続される事を願っています。
高松の周辺にも、高知県の土佐や岡山県の備前なども有数の鍛造が継承されています。
機会を作って、そちらも訪れたいと願っています。
タグ:刃物製作
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/5058643
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック




















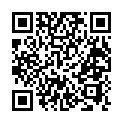
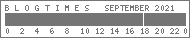
メールで、詳細等連絡致しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
研ぎの検索からこちらを拝見させていただきました。
実は、私の祖母が使っていた花鋏があるのですが、
研いでいただける方を探しているのです。
なかなか鋏を研げる方は見つけられませんで困っています。
もし、可能性があるようでしたらご連絡いただけると
嬉しいです。急な不躾なコメントですみません。
よろしくお願いいたします。