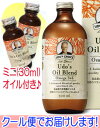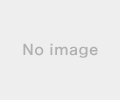2015年06月08日
587. 野村萬斎② ロックバンド・黒澤明との出会い・狂言の伝統 「サワコの朝」
狂言師の家に生まれ、4人兄弟の唯一の男子。姉と妹に挟まれ、家を継ぐ重圧を感じながら幼少期を過ごしました。
「稽古が終わらないです」と野村さん。「出来るようになるまで稽古が終わらない」
「嫌いになりませんか?」と阿川さん。
「泣いているどころではない」「とにかく必死になってやらないと終わらない」「辞めた!やりたくない!って逃げだしゃいいんでしょうけど、そうすると、『多分親子の関係は切られるんだろうな』っていうプレッシャーは感じてましたですね」
帰宅してお父さんの靴があると「奈落の底に落とされたような…」。
野村さん自身は、狂言よりもバンドやバスケットに惹かれていたそうです。ただ、それほどギターが上手いわけでもなく、背も高くはない…。
 |
黒澤明との出会い
マイケルジャクソンに憧れた17歳の時に、野村さんは「三番叟」という舞踊曲を舞い、「これはマイケルに対抗できる唯一の僕らのダンスではないか」と感じたそうです。「これはカッコいい」
その「三番叟」の写真が黒澤明監督の目に留まり、映画「乱」への出演が決まります。黒澤監督からは「狂言の表現を使って演じてください」という指示。
「今まで自分がプログラミングされていたことが表現に繋がるんだ、ということが…。回路が繋がるというか…」
自分が嫌がりながらも受けてきた修業の成果を、黒澤明は求めていたのです。
また祖父の演技が世界的に評価されていることも知り、「世界に通じるんだ、と」
 |
狂言の本質はモノマネ
お能も狂言も本質はモノマネにある、と野村さん。
「お能と狂言は一卵性双生児みたいなものですけれども、狂言はモノマネの対象が日常的・一般な方なんですけれども、お能は、どちらかというと、平家物語とか源氏物語、ロングセラーの(笑)、みんなが知っている人が出てくるものに典拠を求めてる…」
確かに狂言は「この辺りの者でござる」から始まります。あれは一般人を真似していると。
3歳から始まる狂言師の修業、最初に演じるのは猿の役だとか。
様々な型が身につくまで何度も練習する。たとえば「泣く」を練習するとなると「朝から晩までひたすら泣き続ける」(笑)
 |
同じ道を歩む息子
NHKの朝ドラ「あぐり」で有名になったのは31歳のとき。NHKとは縁があって、現在は「にほんごであそぼ」という番組で長男の裕基くんと共演しています。
裕基くんは小学校の低学年のころ、萬斎さんに「どうして狂言をやらなくちゃいけないの?」と率直に聞いてきたそうです。「僕も分からない」と答えた萬斎さん。(笑)「僕はそれにずっと悩んでいたので…」
自分の中に埋め込まれた狂言師としてのチップを他と違うものとして証明するためには狂言師として生きていくしかない、という野村さん。
「自分がチップを息子に埋め込むことになったとき、自分にとってはショックでしたね、息子に本当にやらせていいのかどうか、自分も苦しんだので…」ただ「(息子が)自分でやろうという気にならなければ難しいんじゃないですかね、芸が許さないですから…」
型を叩きこむことはできる、ただそこから先は自分の意志、ということでしょうか…。
最新の舞台「敦ー山月記・名人伝ー」ではお父さんの万作さんも出演。演出も行う萬斎さんがお父さんに演技を指示します。
世襲制の芸能がなぜ、現在も命脈を保っていられるのか、私は素朴な疑問をもっていたのですが、受け継がれたDNAと長年に渡る稽古、そして覚醒してからの情熱、ということでしょうか…。
 |
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image