2024年04月09日
和歌山広川町 廣八幡宮
和歌山県広川町にある廣八幡宮に行ってきました


廣八幡宮は、約1500年前の欽明天皇の頃に建立されました
境内にある本殿や楼門、拝殿などの建物と
鎌倉時代に作られたの短刀が国の重要文化財に指定されています
この地域は古くから幾多の津波被害に遭ってきました
高台にある神社には、「津波には、ただ足早に宮参り」という言い伝えがあります
安政元年、大津波が広川町を襲った際
濱口梧陵が稲むらに火を放ち、村人を避難させた場所です
梧陵の判断によって多くの村人の命が救われました
神社もまた、蔵の貯蔵米を炊きだして避難民を飢えから救うなど
梧陵と協力して急場をしのぎ、復興の足掛かりとなるよう人々を支えました
それ以来、避難場所として、また心の支えとして
人々の暮らしの中に存在してきました
10月第三土曜に開催される稲むらの火祭りは
広川町役場から廣八幡宮まで、約2kmの松明行列が行われます
以下記載しています↓
https://fanblogs.jp/sunflower0623/daily/202310/23
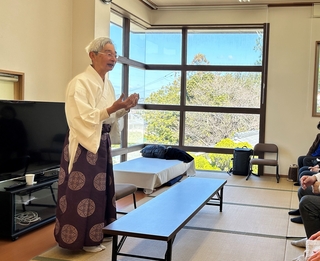
当神社の宮司で、稲むらの火祭り実行委員長である
佐々木さんにお話をいただきました
濱口梧陵の「稲むらの火」の話を単に津波の教訓として
記憶しておけばいいのではなく
日常の生活で活かさないといけないことは何か
災害が起きる前にできることは、災害時の適切な行動とは...
それらを意識し行動することなんですね
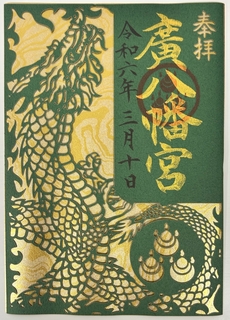


廣八幡宮は、約1500年前の欽明天皇の頃に建立されました
境内にある本殿や楼門、拝殿などの建物と
鎌倉時代に作られたの短刀が国の重要文化財に指定されています
この地域は古くから幾多の津波被害に遭ってきました
高台にある神社には、「津波には、ただ足早に宮参り」という言い伝えがあります
安政元年、大津波が広川町を襲った際
濱口梧陵が稲むらに火を放ち、村人を避難させた場所です
梧陵の判断によって多くの村人の命が救われました
神社もまた、蔵の貯蔵米を炊きだして避難民を飢えから救うなど
梧陵と協力して急場をしのぎ、復興の足掛かりとなるよう人々を支えました
それ以来、避難場所として、また心の支えとして
人々の暮らしの中に存在してきました
10月第三土曜に開催される稲むらの火祭りは
広川町役場から廣八幡宮まで、約2kmの松明行列が行われます
以下記載しています↓
https://fanblogs.jp/sunflower0623/daily/202310/23
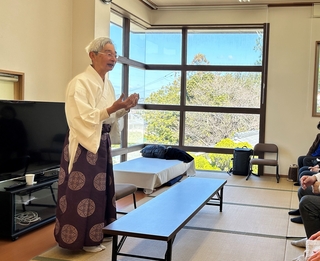
当神社の宮司で、稲むらの火祭り実行委員長である
佐々木さんにお話をいただきました
濱口梧陵の「稲むらの火」の話を単に津波の教訓として
記憶しておけばいいのではなく
日常の生活で活かさないといけないことは何か
災害が起きる前にできることは、災害時の適切な行動とは...
それらを意識し行動することなんですね
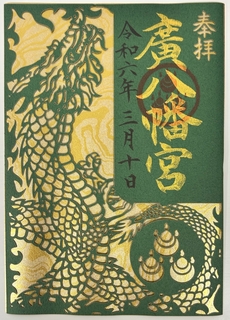
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12504207
この記事へのトラックバック














