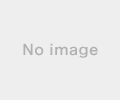新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2020年06月28日
山下和仁 「展覧会の絵」
山下和仁は、おそらく日本人で初めて世界に名の知れたギタリスト。その登場は衝撃的でした。
で、その山下和仁がギター一本で展覧会の絵を弾いたアルバム。おそろしいです。曲芸です。ため息しか出ません。そして、困った事に楽譜が出版されていて(今でもあるのかな)、出てる以上は買ったんですが、1ページめから手も足も出ません。
山下和仁という人、とにかくギターが好きで、小学校の時は登校する直前まで弾いて玄関に置いていき、帰ってきたらその置いてあるギターを玄関で弾いていたというエピソードの持ち主。努力の人というよりキ印です。
そんな人なので、服とかファッションには無頓着で、大事なリサイタルなのに寝癖で現れたりとか、言うなれば将棋の羽生さんみたいな人。結婚してからは、奥さんのおかげでこざっぱりしてみんなを安心させたというのも羽生さんっぽい。
とにかく、日本人ギタリストに世界への道を開いたという意味で偉大な人です。
ギターという楽器の可能性を極限まで突き詰めたアルバムです。たしかレコードは展覧会の絵だけだったと思うんですが、CDはストラヴィンスキーの火の鳥もカップリングされてます。まったく、無茶する人だなあ。
 | 山下和仁(g) / RCA Red Seal THE BEST 75 展覧会の絵&火の鳥 ギター版 ムソルグスキー 山下編: 組曲 展覧会の絵 ストラヴィンスキー 山下編: 組曲 火の鳥 [CD] 価格:1,385円 |
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
ベルリオーズ 「幻想交響曲」
そのベルリオーズの代表作がこの「幻想交響曲」。ヘンな曲です。まあ、失恋して投薬自殺を企てた若者が見た悪夢を描写した曲とされているので、ヘンな曲なのは当たり前といえば当たり前なんですが。
まず、編成がデカイ。当時の標準的な編成の二管編成だとだいたい50人くらいなんですが、「幻想」の編成は軽く100人を超えます。それに、今では楽器博物館でしかお目にかかれない、オフィクレイドやサックバットといった楽器も編成に入ってます。また、標準的な交響曲は四楽章形式なのに、「幻想」は五楽章形式。独自性がありまくりです。
書法的にもかなり突拍子のないことをやってます。五楽章の冒頭でフルートにグリッサンドダウン指定があるんですが、グリッサンドアップならまだしも(ラプソディインブルーのクラリネットとかあるからね)、管楽器にグリッサンドダウンは無理。どの録音を聴いても、ここのフルートは苦労してます。変ちくりんな伸びるフルートを使った演奏もあるほど。
ヘンな曲はヘンな曲なんですが、素晴らしい曲です。かなり時代を先取っていて、リヒャルト・シュトラウスやワーグナーの曲かと思っちゃうくらい。私は、二楽章のワルツが好きなんですが、四楽章から五楽章にたたみかけていく様は圧巻の一言。終盤の、シンコペーションの連打から突然テーマが戻ってくるところなんかゾクゾクします。
長い曲なので、時間のある時にじっくりお聴きください。
 | クラウディオ・アバド(cond) / ベルリオーズ:幻想交響曲(SHM-CD) [CD] 価格:1,410円 |
ブーレーズ 「ル・マルトー・サン・メートル」
ブーレーズはメシアンの弟子で、そのスタイルはクールで理知的、難解で演奏至難。ピアノソナタなんかは、どこがソナタなのかわかんないし、演奏不可能な箇所が何ヶ所かあって、録音を聴いても譜面通りに演奏してるのか聴き取れません。とんでもない曲です。
同時に非常にヤリ手で、フランス国立音響音楽研究所IRCAM(私は現代音楽マニアですからイルカムと読みます)を自分で創設して初代所長におさまっちゃう。国立の機関ですから、フランスのシリアスなクラシック音楽の頂点に立ったようなものです。とんでもない人です。
指揮活動も活発で、もともとはマイナーな作曲家エドガー・ヴァレーズを紹介したり、フランス現代音楽を振ったりするために始めたんですが、ドビュッシーやバルトーク、ストラヴィンスキーらの曲を指揮すると、これが非常に精緻で明晰。録音した途端にその曲のベスト演奏になっちゃうくらい。とんでもない音楽頭です。
そんなトンデモ人のブーレーズですが、実はとんでもないロマンチストで、トータル・セリーというガッチガチの技法を使いながら、聴き慣れてくるとそこかしこにポエジーが感じられます。
で、この「ル・マルトー・サン・メートル」ですが、ガッチガチなのに実に美しい。アルバン・ベルクの「叙情組曲」と双璧を成す美しさです。
ブーレーズは、残念なことに2016年に亡くなってしまいました。このニュースを聞いて、ひとつの時代が終わったと感じた人も多かったでしょう。そんな巨人です。
 | ブーレーズ、ピエール(1925-2016) / ル・マルトー・サン・メートル、デリーヴ1、デリーヴ2 ブーレーズ&アンサンブル・アンテルコンタンポラン、サマーズ 輸入盤 【CD】 価格:1,822円 |
 | アルバン・ベルク四重奏団 / ベルク:弦楽四重奏曲 抒情組曲(UHQCD) [CD] 価格:1,306円 |
ロドリーゴ 「アランフェス協奏曲」
ギターとオーケストラという珍しい編成ですが、よくこんな編成、思いつきましたよね。だってギターですよ。フルオーケストラの中で聞こえるわけがありません。で、実際どうしてるかというと、アンプで増幅して演奏します。クラシックの演奏会でスピーカーから聞こえるって、ちょっと違和感ですよね。
この曲、レヒーノ・サインス・デ・ラ・マーサ(どれが名前でどれが苗字なんだろう)の独奏ギターとバルセロナ・フィルで初演されました。その話を聞いた大ギタリストのセゴビアは、独奏ギターの依頼が自分に来るだろう、もしかしたら自分に曲を献呈されるかもと待ってたんですが、いつまでたってもロドリーゴから連絡がない。そのうちに、「禁じられた遊び」で名を売ったイエペスがリサイタルで取り上げて大好評を受けちゃったもんだから、すねちゃったセゴビアはこの曲を生涯演奏しなかったそうです。子供か。
第一楽章も第三楽章も民族的で陽気で明るいいい曲なんですが、全曲聴くと実は第二楽章が一番盛り上がります。静かな曲のイメージがあるのでびっくりしますね。ライブで聴いたらカッコいいでしょうね。
 | ナルシソ・イエペス(g) / ロドリーゴ:アランフエス協奏曲 ある貴紳のための幻想曲(SHM-CD) [CD] 価格:1,410円 |
 | Chick Corea/Return To Forever / Light As A Feather 【SHM-CD】 価格:1,518円 |
メシアン 「トゥーランガリラ交響曲」
この曲、現代音楽の傑作のひとつとも言われますが、最初聴いた時、なんかよくわかんなかったんですよね。派手派手しくてなんかエロくて、独特なのはわかるけどなんでそうなるのかわかんない。
で、せっかくなんでメシアンの全集CDを買ってみたものの、やっぱりとっつきにくい。
こりゃ私にはわかんない音楽なのかなあ、と思ってしばらくほっといたんですが、テレビのN響アワーで、エサ・ペッカ・サロネンが振ってたのを見てスッと理解できました。
要するに、愛の音楽なんですね。愛っていっても、形而上のものではなくて、わりと下世話な愛。くんずほずれつしたりするようなもの。
一回理解しちゃうと、どんどんいろんなことが見えてきます。愛こそすべて、エロこそ真理。メシアンってすごく真面目な人なんですけど、真面目に愛について考えてここに行き着いたんですね。
使われてる技法とか難しい話はおいといて、慣れてくると脳髄にビリビリくる音楽です。現代音楽って頭でっかちなものが多いですが、ここまできてやっと、さすがメシアンと思いました。いや、これもメシアンの仕組んだ迷路かもしれませんが。
 | リッカルド・シャイー(cond) / メシアン:トゥーランガリラ交響曲(SHM-CD) [CD] 価格:1,410円 |
モーツァルト 「交響曲41番ジュピター」
まあ、間違いなく天才ですよね、この人は。でも、過大評価されてる気もするするんですよね。若くして亡くなったというのも、それに輪をかけてるんでしょうが。
ハイドンがいなければモーツァルトはいなかったはずだし、孤高の天才というイメージは無くて、なんとなく楽しい事をやってたらそれが評価されちゃったラッキーな人という感じ。
もともとは、ハイドンの影響の下で厳格な音楽を書こうと思ってたんですが、いかんせん溢れ出るものが多すぎてその枠をはみだしちゃう。ところが、ハイドンみたいな型にはまった音楽よりも、モーツァルトの自由な音楽がウケちゃうんですね。
でまあ、モーツァルトもいい気になっちゃうわけですが、晩年(といっても30代)にこれじゃあいかんとでも思ったんですかね、いろんなチャレンジをしていきます。
まず、曲調から能天気な明るさが減っていきます。このへんは、世界情勢とも関係してるんでしょう。ちょうどフランス革命が起こって、貴族社会が没落し始めた頃ですから、宮廷に雇われてたモーツァルトも身の振り方を考えたんでしょうね。なにせ、次の才能ベートーヴェンが後ろに迫ってきてましたし。
で、交響曲40番なんて、およそモーツァルトらしくない曲を書いちゃうあたり逡巡してますね。
技法的にもソナタ形式一辺倒だったのが、対位法やフーガに色気を見せ始めます。なんか、おもちゃに飽きた子供が別のおもちゃで遊び始めるみたい。
で、そのモーツァルトのフーガの最高峰と言われているのが、交響曲41番ジュピターの終楽章なんですが、これが実に中途半端。厳密にはフーガじゃなくてフガートなんですが、やっぱりモーツァルトなので厳格なフーガを始めると何かが邪魔するんでしょうね、自分の中で。
いや、いい曲なんですよ、ジュピター。なんというか、モーツァルトの人間味が感じられるというか。なんか音楽サイボーグみたいな印象もあるモーツァルトが、人間だと主張するような感じがして。
 | レナード・バーンスタイン(cond) / モーツァルト:交響曲第40番&第41番「ジュピター」他(期間生産限定盤) [CD] 価格:816円 |
バッハ 「ロ短調ミサ」
で、そんなにバッハがでかい顔できるのかというと、実はそうでもなかったりします。
時代的には、バッハは後期バロックになるんですが、他の作曲家と一線を画していました。というか、バッハみたいなことをやってる人がいなかったんですね。他の作曲家が、華やかだったり軽やかだったり、いわゆる宮廷音楽として貴族にウケる曲を書いてたのに、バッハだけはしかめっ面して、対位法だのフーガだのの技法を追求していました。
そのうちに、バッハの技法はどんどん厳格なものになっていきましたが、それはそれは窮屈なものでした。娯楽だったはずのパズルが、パズルのためのパズルになってっちゃって面白くなくなっていくみたいな。要するにやりすぎちゃったわけですね。
バッハのせいでどん詰まり状態になっちゃったバロックに先は無いと、なんとかせんといかんとハイドンが古典派をぶち上げました。これが後のモーツァルト、ベートーヴェンに受け継がれて、そのままロマン派になだれ込みます。そういう意味では、「音楽の父」ってハイドンなんじゃね?と思いますね。
そんな音楽殺しのA級戦犯のバッハですが、バッハの前にバッハ無しバッハの後にバッハ無しで、一人でどうしてここまでできちゃうの?というくらい独自の音楽を構築しています。孤高の天才ですね。
この「ロ短調ミサ」は、バッハの集大成です。バッハの会得したあらゆる技法が使われています。そりゃ、こんなもん見せられたら作曲なんてやる気なくすわなあ、って感じ。バッハの怨念さえ感じられる曲です。
 | ペーター・シュライアー(cond) / CREST 1000 497::J.S.バッハ:ミサ曲 ロ短調 BWV232(廉価盤) [CD] 価格:1,224円 |
ホルスト 組曲「惑星」
ホルストは、音楽大学などに職を得ずに、ロンドン近郊のセントポール女学院の音楽教師を生涯勤めて、学校の休みの時に作曲をしていたそうです。言ってみれば、アマチュア作曲家ですね。
そんなアマチュア作曲家のこんな編成のでかい曲がよく初演できたなー、と思いますよね。金もかかるし。
実はイギリスは、ヘンデル、パーセルあたりのバロック期から大した作曲家が出てこず、音楽の辺境地に成り下がっていました。そこで、第一次世界大戦あたりの時期に、ヘンリー・バルフォア・ガーディナーという人が大スポンサーに名乗りを上げて、イギリスの近代音楽の紹介を始めました。いい人ですね。で、その
演奏会で「惑星」を取り上げてもらったんですね。
初演は好評だったようです。でも、いかんせん、アマチュア作曲家の作品。演奏される機会も少ないまま忘れ去られていきました。1960年代に、カラヤンがウイーン・フィルと録音したのをきっかけに大ヒット曲の仲間入りをしたそうです。もちろん、その時にはホルストは亡くなっています。
この「惑星」は、間違いなくホルストの最高傑作です。というか、本当にホルストが作ったの?って感じ。他のホルストの曲を聴くと、イギリスの民謡を素材にした素朴なものが多いのに、この「惑星」だけ豪華絢爛で大げさ。何があったんでしょうね。
まあ、とにかく名曲です。
 | ズービン・メータ(cond) / ホルスト:組曲≪惑星≫ ジョン・ウィリアムズ:≪スター・ウォーズ≫組曲(SHM-CD) [CD] 価格:1,410円 |
 | 価格:1,200円 |
 | ホルスト:吹奏楽のための組曲第1番・第2番 他/フェネル(フレデリック)[CD]【返品種別A】 価格:1,093円 |
富田勲 「宇宙幻想」
田舎の中学生にも、富田勲の新しさはなんとなくわかりました。なんせ、富田勲の写真のバックに写ってるモーグのシンセサイザーが、どう見ても楽器に見えない。このわけのわからないケーブルだらけの箱から、あの豪華絢爛な音楽が出て来ちゃう。しかも富田勲一人で。
聴きましたねー、カセットテープが伸びちゃうくらいに。今調べると、オネゲルのパシフィック231とかアイヴズの答えのない質問とかが入ってるので、音楽の素養が全く無かった田舎の中学生に理解できたのかしらんとも思いますが、富田勲のオーケストレーションが凄かったんでしょうね。
このアルバム、スターウォーズも入ってて、確かR2D2とC3POの会話をシンセサイザーでシミュレートしてたんですが、シンセサイザーってなんでもできるんだと思いましたね。20年後に、才能と努力とアイデアが必要だと思い知るんですが(笑)。
富田勲のおかげで、ドビュッシーやリヒャルト・シュトラウス、ムソルグスキーなんかを知らず知らずに聴いていたという人は多いはず。そう考えると、富田勲の功績は計り知れないですね。
 | 価格:816円 |
スクリャービン 「法悦の詩」
一応ソナタ形式だけど、全然交響曲っぽくない。最初から最後までゆらゆらふわふわして、響きを味わう曲。一時は、聴衆の劣情を煽るという理由で上演禁止になったほどなんですが、今聴くと、まあそうかなって感じ。
スクリャービン自身が開発した「神秘和音」なるものが使われていて、それによって独特の雰囲気を醸し出しています。技法的にはドビュッシーと似てるんですが、より偏執狂的なところが表れて、終わりのない世界になっちゃってます。
このスクリャービン、なかなかいっちゃってる人で、家族を捨てて弟子と愛人関係になっちゃうし、哲学に傾倒して自分は超人だとか言い出すし、神秘主義を標榜して独自の世界を突っ走ったり。なかなかに研究肌の人でもあったようで、音と色の関係の研究をしてた時に、弾いた音に対応した色のビームを発するオルガンを開発したりしてたようです。
ピアノが超達者で、10曲あるピアノソナタは名曲揃い。中でもピアノソナタ第1番は後期ロマン派の傑作。
あまりにも独自性が強かったために、その後フォローワーが出てこなかったのが残念と言えば残念。音楽史的にも、片隅に追いやられてる感じでかわいそう。孤高の人って感じですね。
 | ユージン・オーマンディ(cond) / ラフマニノフ:交響曲第2番、合唱交響曲「鐘」 スクリャービン:法悦の詩、プロメテウス他 [CD] 価格:1,470円 |
 | ウラディーミル・アシュケナージ(p) / スクリャービン:ピアノ・ソナタ全集(SHM-CD) [CD] 価格:1,867円 |