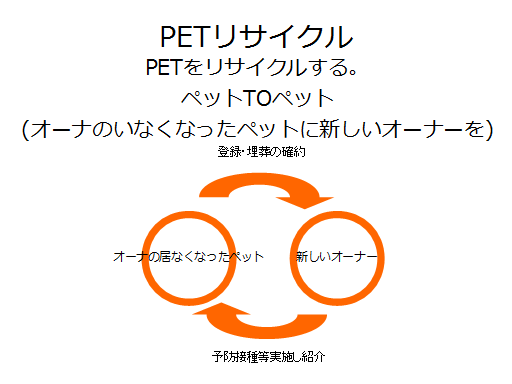老化というのは徐々に進行するので気がつきにくいものの、いわば健常者ほどの能力がないという時点で、若干の障がいを持つ者と言っていいと思う。
塩見さんの場合は、実際に障がい者となったわけだが、病気でそのようになることについて正直に述べていて我が身のこととして障がいを考えるには良いと思う。また、病気がきっかけで自身の老いを感じたということも述べとり、然りと思うところ。
そして、世間はまだまだバリアフリーには程遠いという現実についてもさらっと触れてくれている。
あとは、やはり妻は若い方が良いということか・・・
Yahoo!より、
俳優・塩見三省「脳出血で人生を中断されて。元に戻るのは不可能とわかったとき、声をあげて泣いた」
11/15(月) 12:01配信
婦人公論.jp
https://news.yahoo.co.jp/articles/dd9d3fcb5df211536e45811f893a0794e2624723
記事より、
66歳で病気をするまで、どちらかと言えば私は健康に自信があるほうでした。ジムに通ったりランニングをしたりするのは性に合わなかったけれど、40代後半で始めたテニスは暇さえあればコートに立つくらい好きで。年齢を重ねて続けられるのがテニスのよいところだ、とも思っていました。
俳優はチームワークによって成り立つ仕事ですから、たとえ一人でも欠ければ周りに大きな迷惑がかかります。特に私は長いスパンで取り組む仕事が好きでしたので、数ヵ月から1年といった長丁場の間に体調を崩すようなことがあっては困る。年に一度の人間ドックはもちろん、現場に入る前の健康チェックも欠かさず、問題なく過ごしていたのです。
確かに、倒れるまでの1年ほどは、それまでにない忙しさではありました。理由は、どの仕事も「ほかのヤツがやるのは嫌だな」という魅力的なものばかりだったから(笑)。映画が2本、大河ドラマなどの連続ドラマが3本、CMが2本、アート展用の銅版画制作……。
夢中で取り組んだことに、後悔はありません。ただ毎週のように新幹線で東京と2つの地方を往復したこと、その年の厳しい冬の寒さなども重なったのでしょう。今思えば、血圧も少々高かったのかもしれない。でも血圧ってちょっと高いくらいが「お、調子がいいな」と感じたりするものじゃないですか。
自宅で倒れ、救急搬送された私は生死を彷徨った末、一命を取り留めました。手術はせず、降圧剤を服用して10日ほど入院。そしてリハビリ専門の病院に移りました。
期間としては約5ヵ月。当時の気持ちを一言で言うなら、果てしのない恐怖と絶望です。リハビリは現状維持を目指すものにすぎません。すでに66歳、完全に元の身体に戻るのは不可能とわかったときは声をあげて泣きました。死を考えたこともあります。
しかし7年経った今、私は病を得たことを神様からのギフトだと思うに至りました。倒れる前の生活は確かに順調でしたが、すでに私の生命力はすり減り、意外と弱っていたのだと思います。
倒れてからの毎日は、「生きている」という実感しかありません。そりゃあ私だって、できれば健常者でいたかったですよ。悲しいことやつらいこと、悔しいことは数えきれないほどありますし、生き残ったからこその苦悩もあります。でもそれを超えて余りあるギフトを私は受け取っている――そう思えるようになったのは、この7年の道のりを『歌うように伝えたい』という本に書いたことが大きいでしょう。
きっかけは、ドラマで共演した星野源君の、「シオミさん、何か書けばいいのに」という言葉でした。彼も病気の経験を、「書く」ことで一区切りつけられたそうです。
書くための時間は、膨大にありました。何もしないでいると考えなくてもいいことまで考えてしまうから、妻にお古のiPadをもらって旧作映画や音楽で気を紛らわしていたんです。そのiPadに、人差し指一本で病気のこと、リハビリの苦しさなどを打ち込み始めました。
もどかしいようなスピード。それはパソコンで原稿を書いていたら決して味わえないものでした。ああ、これはペンで文字を書くスピードに似ているじゃないか、と思いました。言葉一つでも、こうじゃない、もっと違う表現があるはず、と吟味する面白さ。私は次第に書くことにのめり込んでいきました。
退院した日に感じた「オレって、社会の異物じゃん」という強烈な感覚は、今も忘れることができません。病院にいれば、周りはみんな病を抱えているか、そのことを専門に考える人たちばかり。
でも一歩病院の外に出れば、手すりはない、段差はある、周りはこちらの事情など知らない相手ばかり。そのことでうつになってしまう人も多いと聞きますが、私がなんとか気持ちを保ってこられたのは、社会の異物としての自分を受け入れ、そして自らの老いを受け入れ、この体で生きていくんだと覚悟できたからなのでしょう。
定年のない俳優という仕事は、その気になれば一生現役でいられるので、老いるという感覚が希薄になりがちです。でも私は、わが身に起きた老いをそのまま画面に出すしかない、と決めました。
何より、一番の頼りは妻です。彼女がいなければ、とうてい生きてこられなかった。歳が離れているから私のほうが先に老いる覚悟くらいはあっただろうけれど、こんなに早く介助生活が始まるとは想像していなかったでしょう。退院した直後、脳出血の後遺症と慣れないリハビリ生活で私の精神状態がおかしくなっていたときは、彼女もつらかったと思います。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image