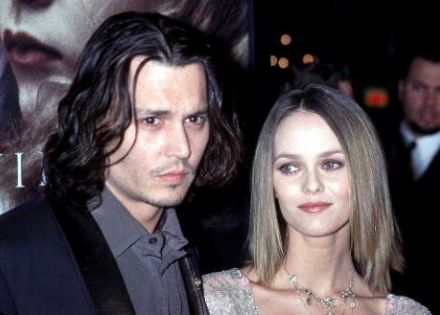2018年11月06日
スペイン巡礼記⑱ 18日目:心を乱すヤンとの再会
Pilgrimage in Spain ⑱ Day18: Reunion with Jan disturbing my heart【4.2011】
4月17日(巡礼17日目)Boadilla del Camino ボアディリャ・デル・カミーノ ~ Villalcazar de Sirga ヴィラルカサール・デ・シルガ (19.5km)
4月18日(巡礼18日目)Villalcazar de Sirga ヴィラルカサール・デ・シルガ~ Ledigos レディゴス (28.5km)
「ヤンとの再会 Reunion with Jan」
見知らぬ女性に「ハイ、Izumi!」と肩を叩かれたのは、ギラギラと照りつける太陽の下、果てしなく続く麦畑の中のまっすぐな一本道をひたすら歩いている時だった。
驚いて振り向くと、そのショートカットの女性の数歩後ろには、トレードマークの黒いカウボーイハットをかぶったあのヤンが、少々照れ臭そうに俯いて笑っているではないか。
ヴィラルカサール・デ・シルガの町を出た頃の朝日
「ヤン!」
てっきり先を歩いていると思っていたヤンに再会できた嬉しさで思わず叫んで立ち止まると、女性二人を従えて近付いてきたヤンが杖代わりにしている右手のスキーストックを少し上げ、「ハロー、アゲイン!」と歯並びのよい白い歯を見せて言った。
ブルゴスで思いがけず再会したドイツ人女性二人と合流したため、ゆっくり歩いているのだという。先ほど私に声をかけた女優トニ・コレット似の男勝りな雰囲気を持った女性と、赤いジャージ姿の欧米人にしては小柄な女の子が、興味深げに私を見つめている。
「あなたが彼のお気に入りのIzumiね、あなたのことはヤンから全部聞いてるわ。こんな小さな体でこんな大きな荷物背負って、一人で歩いるなんてすごいわね」
トニ・コレット女史が英語でそう言ってから、ドイツ語でヤンと赤いジャージの女の子に何やら話しかけ、頷きあっている。
「やだ、ほんとに38には見えないわね」
そんなことを言っているのかと想像してしまうほど、彼女たちは無遠慮に、上から下へとなめ回すように私を観察していた。トニ・コレット女史が英語で続ける。
「ヤンとの経緯も聞いてるわ。ブルゴスでホステルを探して歩き回ったのよね。そして最後までヤンがあなたに付き添ってホステルの部屋まで送り届けた」
accompaniedという単語に、親が子供に付きそうような保護者的な響きを感じ、その上から目線に内心カチンとしながらも、その折りのお礼をヤンに向かって言う。あのとき彼はわざわざ辞書で調べたescortという単語を使ったのに。
あんなにフレンドリーだったヤンだが、なぜかこの時はあらぬ方向を向いたり俯いたりして、サングラスごしにではあるが私と目線を合わせようとしなかったのが気になった。この二人の女性に洗いざらい私のことを喋っていることに対する負い目だろうか、どこか他人行儀な態度…。
私は心の中で毒づく。ログローニョの前で初めて会った時そう言ったのは自分じゃないの、と。
もっと私をいじりたかったらしいコレット女史は「ア、ハーン」と両手を上げる欧米人独特の動作をして、心底残念そうに首を振ると、じゃぁお菓子をあげる、とリュックから何かをゴソゴソと取り出した。
それは小麦バーで、イギリスの朝食でよく食べられるまずいシリアルバーだったので、一瞬正直に固まってしまった私にヤンが「彼女の好意だからもらっておきなよ」と横から口を挟んだので、仕方なく礼を言って受け取る。
満足そうに微笑んだ彼女が、「じゃ、またね」と私の肩を親しげに叩き、二人の女と一人の男は足早に私を追い越していった。長い足で着実に私より早く歩を進める彼らの姿があっという間に遠のいていくのを眺めながら、私はどこか釈然としない気分に侵されていた。
初めて会ったとき、ヤンは言っていたのだ。他人と一緒に歩くとペースを合わせるのに苦労するから疲れる、巡礼の始めの頃、同じドイツ人の女の子たちと歩いていたけど、一人になりたくなって途中で別れたんだ、と。
そのヤンが、ブルゴスで彼女たちと再会してからもう5日、一緒に歩いている。
ヤンの嘘つき。ブルゴスには泊まらない、と言ったくせに。ヤンのお喋り。私のことをあんなに事細かにいろんな人たちに喋りまくるなんて。
彼はブルゴスで交わした私との会話の内容まで彼女たちに話したのだろうか。ホステルを探し求めてさまよう間、私達はいろんな話をした。
ヤンが日本人に対して世界一リッチな国だという印象を持っていること。時間に正確、という日本とドイツの共通点。(スペイン人の時間に対するルーズさやシエスタに伴う不都合などで意見が一致!)
シュトゥットガルトから来たというヤンの、巡礼に来るまでの仕事と都会での生活。私の東京での生活。(夜、映画を見ながらのカウチ・ポテトが懐かしいと言ったヤンに同感!)
ヤンに再会したことで余計な雑念に付きまとわれながら歩く私の耳に、後ろから大きな歌声が聞こえてきた。振り向くと、髭もじゃのまるで浮浪者のような見てくれのオジサンが、木の杖を振り回しながら歩いてくる。
私に気付いた彼は隣りを歩きながら「やぁ、お嬢さん、どこから来たのかな?」と、まるで舞台俳優が台詞をしゃべるような調子で大げさな身振りの挨拶をしながら尋ねた。彼はアイルランドから来た自称詩人で、さっきから大声で歌っているのはアイルランドを称えた歌なのだという。
「いやぁ、なんと素晴らしい太陽に満ちたこの世界!神に祝福されたこの道!」などと聞き取りにくいアイルランド訛りの強い英語で話しながらしばらく歩調を合わせて歩いていたが、やがてカリヨン・デ・ロスコンデスの町に着くと、踊るようにフラフラと歩きながら「さらば!」と手を振り、バルの中へと吸い込まれていった。
「彼の態度に戸惑いを隠せない自分
I can not hide embarrasment in his attitude」
カリヨン・デ・ロスコンデスを抜けると、この日の道は本当にひたすら平地が続いていた。行けども行けども同じような麦畑の緑が左右に果てしなく広がり、土埃を舞い上げる微風が時たま吹きすぎるだけで、陽炎の立つような暑い日だった。
それでいて道の両側に休憩を取るようなベンチや大きな石などもほとんど見当たらず、どこまで歩けば休めるのだろう、と挫けそうになっていた頃、行く手にピクニック・エリア(木のテーブルと椅子が何セットか設置された巡礼者のための休憩エリア)があることを示すサインが現れた。
「やった、やっとこの重いリュックを下ろせる!」
と思った矢先、その休憩場所で寛ぐ先客の赤いジャージと黒いカウボーイハットが目に飛び込んできた。
ヤンたちだ。その瞬間、止まろうとしていた私の足は何故か歩を早め始めた。休みたいという意思とは逆に、頑固に歩き続ける足に戸惑う私に、トニ・コレット女史が手を振る。
「Izumi! 一緒に休まなーい?」と大声で呼んでくれる。喉はカラカラだし、足だって今にももつれて転びそうに疲れていたにも関わらず、私の口は意思とは真逆の言葉を叫んでいた。
「止まれない!今ここで止まったら二度と歩けなくなりそうだから!」
なんて馬鹿みないなセリフ、とその時も私の顔は暑さと恥ずかしさで真っ赤になっていた気がする。
幸い休憩場所は歩道から10メートル以上奥まった木陰にあったので、私の顔色までは彼らには見えなかっただろう。
私は、声をかけてくれたお礼の気持ちをこめて力なくではあるが、彼らに手を振った。ヤンはその時もあらぬ方向を眺め、我関せずのどこかよそよそしい態度だった。
この日はこんな道が延々と続いていた
さて、本当に休みたかったタイミングで休めなかった私は、自らの言葉通りその先どこかで立ち止まって座ったが最後、本当に二度と立ち上がれなくなりそうな気がして、意地になって歩き続けた。
デラ・クエサのバルでアイリッシュの詩人に呼び止められて初めて足を止めた時には、炎天下で約十七キロ歩き続けた私は、砂埃と汗にまみれて息も絶える寸前だった。
そこでバックパックの重みから4時間ぶりに解放され、太陽の光を遮るパラソルの下で一気に飲み干したレモネードの美味しかったこと!
体に染み渡るとはまさにこの時のことをいうのだろう。干からびた砂漠にこぼしたコップ一杯の水が大地に吸い込まれていくように、身体の隅々まで冷たいレモネードが行き渡り、私は息を吹き返した。
アイリッシュの髭もじゃ詩人と、何度か顔を合わせたことのある夫婦が席に呼んでくれて、心地よい風の吹き抜けるオープンエアで椅子に背中を預け、スペイン風オムレツでお腹を満たし、楽しいおしゃべりに身を任せる幸せ。満ち足りた午後がゆっくりと過ぎていった。
ヤンとの再会によってモヤモヤした気持ちも忘れかけた約1時間後、アイリッシュ詩人や夫婦が先に出発し、私もさて、もうひと頑張りするぞ、と出立する前にトイレへと立った。
そして再び遭遇したのだ、あのヤンに。
高い梁を巡らせた宿屋も兼ねた木造のかわいらしいバルの片隅で、トイレから出てきた私とバルに入ってきたヤンは、まさにバッタリと鉢合わせた。
そして驚いたことに、彼は先ほどまでのよそよそしさはどこへ行ったのかという勢いでつかつかと歩み寄り、私の両手を取ると口づけせんばかりに胸の前で握りしめ、ぐっと顔を寄せて「Are you OK?」と尋ねた。眉間に皺を寄せ、真剣そのもので真っすぐに私の目を見つめながら。
(イメージ的にはこんな感じ?)
外へ出ると、ヤンの連れの二人の女性が待ち構えていて、ちょうど私だけになっていたテーブルに移ってきた。
が、私はすでに一時間ほど休憩を取っていたのでちょうど出発しようとしたところへ彼らがきた訳である。出立準備を始めると、コレット女史が「私たちが来るといつも逃げるのね」と冗談めかして言った。
カウボーイハットからサングラス、そして上着まで脱ぎ捨てて、黒いランニングシャツ一枚になったヤンが私の隣りにどかっと腰を下ろし、今日はどこまで行くつもりかと聞いてきた。
あと6キロ先のレディゴスに泊まるつもりだというと彼は、「レディゴス、レディゴス…」と口の中で唱えながら「I’ll follow you.」と言ってウィンクを投げてきた。
あああぁ、なんて軽いヤン!
女性たちに囲まれ、意外にも鍛えられた筋肉美を晒して片目をつぶって見せるヤンはまるで「だからオレがオマエに追いつくのを楽しみに待ってな」とでも言いたげに私には映った。
返事はせずに渇いた笑いを返した私は、どこかで本当に彼が私を追いかけてきてくれることを期待しつつ、あとたった6キロを歩いて止まるようなヤンではないことを知っていた。
事実、レディゴスの宿で過ごした夜、私はヤンに会ってはいない。ただ、彼は来たのだ、レディゴスで私が泊まったアルベルゲに。
彼らを残して出立した私がレディゴスのアルベルゲに着いてシャワーを浴び終え、さっぱりしたところで部屋で髪を乾かしていた時、中庭がにぎやかになったかと思うと、彼の連れの小さい方の女の子が、「Izumi!」と嬉しそうに声をかけて部屋に入ってきたのだ。
そしてくるりと踵を返すと「She’s here!」とヤンへ報告に行ったらしい。その後私はすぐに洗濯物を干しに裏庭へ行き、心地よい風に洗いたての髪をなぶられながら椅子に腰かけ、うたた寝などして過ごしていたので、ヤン達3人がどうしたのかは知らない。ヤンは部屋には顔を出さなかったからだ。
「スペインオヤジ達との焼肉パーティ
Barbrcue party with Spanish uncles」
その夜、私より先に着いてずっと中庭で椅子を円形に並べてお喋りしていたドイツ人のメガネの女の子と、アメリカ人の男の子、スペイン人のおじさん達が夕食に誘ってくれた。アルベルゲのキッチンで自分たちが買ってきた肉を焼いたりするのだという。
まるでコメディ映画でも見ているかのように分担された絶妙な流れ作業で、フライパンやナイフを手に料理を楽しむスペインのオヤジ4人組は皆とても陽気で声も大きく、時にはオペラのようにセリフを歌にのせながら喋るのでその賑やかさに圧倒され、私はヤンのことをしばし忘れて、久々の大勢での食事を楽しんだ。
マドリードで英語教師をしながらスペイン語を勉強中のアメリカ人の若い男の子が、英語の話せないオジサンたちとスペイン語を解さない私とドイツ人の女の子のために通訳として活躍してくれた。
しかし、人と人とを繋ぐのは時に言葉ではなく、音楽だったり美味しい料理だったり、お酒だったりする。とことん陽気なオジサン達に囲まれて、飲めや歌えやのどんちゃん騒ぎの様相を呈した楽しい夕食にかかった費用はたったの3ユーロ。若者の負担を軽くしてくれたオジサン達は、見た目も気持ちも太っ腹なのだった。
夕食を待っている間に若者3人で話しているとき、ドイツの女の子が首を傾げていた。
「あなたの少し後に来たドイツ人女性二人と男性一人のうち男性だけここに残ったんだけど、あの人どこへ行ったのかしら」と…。
4月17日(巡礼17日目)Boadilla del Camino ボアディリャ・デル・カミーノ ~ Villalcazar de Sirga ヴィラルカサール・デ・シルガ (19.5km)
4月18日(巡礼18日目)Villalcazar de Sirga ヴィラルカサール・デ・シルガ~ Ledigos レディゴス (28.5km)
「ヤンとの再会 Reunion with Jan」
見知らぬ女性に「ハイ、Izumi!」と肩を叩かれたのは、ギラギラと照りつける太陽の下、果てしなく続く麦畑の中のまっすぐな一本道をひたすら歩いている時だった。
驚いて振り向くと、そのショートカットの女性の数歩後ろには、トレードマークの黒いカウボーイハットをかぶったあのヤンが、少々照れ臭そうに俯いて笑っているではないか。
ヴィラルカサール・デ・シルガの町を出た頃の朝日
「ヤン!」
てっきり先を歩いていると思っていたヤンに再会できた嬉しさで思わず叫んで立ち止まると、女性二人を従えて近付いてきたヤンが杖代わりにしている右手のスキーストックを少し上げ、「ハロー、アゲイン!」と歯並びのよい白い歯を見せて言った。
ブルゴスで思いがけず再会したドイツ人女性二人と合流したため、ゆっくり歩いているのだという。先ほど私に声をかけた女優トニ・コレット似の男勝りな雰囲気を持った女性と、赤いジャージ姿の欧米人にしては小柄な女の子が、興味深げに私を見つめている。
「あなたが彼のお気に入りのIzumiね、あなたのことはヤンから全部聞いてるわ。こんな小さな体でこんな大きな荷物背負って、一人で歩いるなんてすごいわね」
トニ・コレット女史が英語でそう言ってから、ドイツ語でヤンと赤いジャージの女の子に何やら話しかけ、頷きあっている。
「やだ、ほんとに38には見えないわね」
そんなことを言っているのかと想像してしまうほど、彼女たちは無遠慮に、上から下へとなめ回すように私を観察していた。トニ・コレット女史が英語で続ける。
「ヤンとの経緯も聞いてるわ。ブルゴスでホステルを探して歩き回ったのよね。そして最後までヤンがあなたに付き添ってホステルの部屋まで送り届けた」
accompaniedという単語に、親が子供に付きそうような保護者的な響きを感じ、その上から目線に内心カチンとしながらも、その折りのお礼をヤンに向かって言う。あのとき彼はわざわざ辞書で調べたescortという単語を使ったのに。
あんなにフレンドリーだったヤンだが、なぜかこの時はあらぬ方向を向いたり俯いたりして、サングラスごしにではあるが私と目線を合わせようとしなかったのが気になった。この二人の女性に洗いざらい私のことを喋っていることに対する負い目だろうか、どこか他人行儀な態度…。
| せっかく再会したんだから一緒に歩きましょうよ、と提案したコレット女史に、私は歩くのが遅くて皆に迷惑をかけるから遠慮せず先に行ってと答えると、ヤンがこちらを向いて頷きながら「君はは人にペースを合わせて歩くのが苦手だったね」と意味ありげに呟いた。 |
私は心の中で毒づく。ログローニョの前で初めて会った時そう言ったのは自分じゃないの、と。
もっと私をいじりたかったらしいコレット女史は「ア、ハーン」と両手を上げる欧米人独特の動作をして、心底残念そうに首を振ると、じゃぁお菓子をあげる、とリュックから何かをゴソゴソと取り出した。
それは小麦バーで、イギリスの朝食でよく食べられるまずいシリアルバーだったので、一瞬正直に固まってしまった私にヤンが「彼女の好意だからもらっておきなよ」と横から口を挟んだので、仕方なく礼を言って受け取る。
満足そうに微笑んだ彼女が、「じゃ、またね」と私の肩を親しげに叩き、二人の女と一人の男は足早に私を追い越していった。長い足で着実に私より早く歩を進める彼らの姿があっという間に遠のいていくのを眺めながら、私はどこか釈然としない気分に侵されていた。
初めて会ったとき、ヤンは言っていたのだ。他人と一緒に歩くとペースを合わせるのに苦労するから疲れる、巡礼の始めの頃、同じドイツ人の女の子たちと歩いていたけど、一人になりたくなって途中で別れたんだ、と。
そのヤンが、ブルゴスで彼女たちと再会してからもう5日、一緒に歩いている。
ヤンの嘘つき。ブルゴスには泊まらない、と言ったくせに。ヤンのお喋り。私のことをあんなに事細かにいろんな人たちに喋りまくるなんて。
彼はブルゴスで交わした私との会話の内容まで彼女たちに話したのだろうか。ホステルを探し求めてさまよう間、私達はいろんな話をした。
ヤンが日本人に対して世界一リッチな国だという印象を持っていること。時間に正確、という日本とドイツの共通点。(スペイン人の時間に対するルーズさやシエスタに伴う不都合などで意見が一致!)
シュトゥットガルトから来たというヤンの、巡礼に来るまでの仕事と都会での生活。私の東京での生活。(夜、映画を見ながらのカウチ・ポテトが懐かしいと言ったヤンに同感!)
| あの時ヤンに巡礼を始めた理由を聞かれ、私は両親の死について触れた。そのことも、彼は彼女たちに話したのだろう。だからあんなにエライと感心するのだ。もっと若いのに一人で歩いている女の子だってたくさんいるはずなのに。 |
ヤンに再会したことで余計な雑念に付きまとわれながら歩く私の耳に、後ろから大きな歌声が聞こえてきた。振り向くと、髭もじゃのまるで浮浪者のような見てくれのオジサンが、木の杖を振り回しながら歩いてくる。
私に気付いた彼は隣りを歩きながら「やぁ、お嬢さん、どこから来たのかな?」と、まるで舞台俳優が台詞をしゃべるような調子で大げさな身振りの挨拶をしながら尋ねた。彼はアイルランドから来た自称詩人で、さっきから大声で歌っているのはアイルランドを称えた歌なのだという。
「いやぁ、なんと素晴らしい太陽に満ちたこの世界!神に祝福されたこの道!」などと聞き取りにくいアイルランド訛りの強い英語で話しながらしばらく歩調を合わせて歩いていたが、やがてカリヨン・デ・ロスコンデスの町に着くと、踊るようにフラフラと歩きながら「さらば!」と手を振り、バルの中へと吸い込まれていった。
「彼の態度に戸惑いを隠せない自分
I can not hide embarrasment in his attitude」
カリヨン・デ・ロスコンデスを抜けると、この日の道は本当にひたすら平地が続いていた。行けども行けども同じような麦畑の緑が左右に果てしなく広がり、土埃を舞い上げる微風が時たま吹きすぎるだけで、陽炎の立つような暑い日だった。
それでいて道の両側に休憩を取るようなベンチや大きな石などもほとんど見当たらず、どこまで歩けば休めるのだろう、と挫けそうになっていた頃、行く手にピクニック・エリア(木のテーブルと椅子が何セットか設置された巡礼者のための休憩エリア)があることを示すサインが現れた。
「やった、やっとこの重いリュックを下ろせる!」
と思った矢先、その休憩場所で寛ぐ先客の赤いジャージと黒いカウボーイハットが目に飛び込んできた。
ヤンたちだ。その瞬間、止まろうとしていた私の足は何故か歩を早め始めた。休みたいという意思とは逆に、頑固に歩き続ける足に戸惑う私に、トニ・コレット女史が手を振る。
「Izumi! 一緒に休まなーい?」と大声で呼んでくれる。喉はカラカラだし、足だって今にももつれて転びそうに疲れていたにも関わらず、私の口は意思とは真逆の言葉を叫んでいた。
「止まれない!今ここで止まったら二度と歩けなくなりそうだから!」
なんて馬鹿みないなセリフ、とその時も私の顔は暑さと恥ずかしさで真っ赤になっていた気がする。
幸い休憩場所は歩道から10メートル以上奥まった木陰にあったので、私の顔色までは彼らには見えなかっただろう。
私は、声をかけてくれたお礼の気持ちをこめて力なくではあるが、彼らに手を振った。ヤンはその時もあらぬ方向を眺め、我関せずのどこかよそよそしい態度だった。
この日はこんな道が延々と続いていた
さて、本当に休みたかったタイミングで休めなかった私は、自らの言葉通りその先どこかで立ち止まって座ったが最後、本当に二度と立ち上がれなくなりそうな気がして、意地になって歩き続けた。
デラ・クエサのバルでアイリッシュの詩人に呼び止められて初めて足を止めた時には、炎天下で約十七キロ歩き続けた私は、砂埃と汗にまみれて息も絶える寸前だった。
そこでバックパックの重みから4時間ぶりに解放され、太陽の光を遮るパラソルの下で一気に飲み干したレモネードの美味しかったこと!
体に染み渡るとはまさにこの時のことをいうのだろう。干からびた砂漠にこぼしたコップ一杯の水が大地に吸い込まれていくように、身体の隅々まで冷たいレモネードが行き渡り、私は息を吹き返した。
アイリッシュの髭もじゃ詩人と、何度か顔を合わせたことのある夫婦が席に呼んでくれて、心地よい風の吹き抜けるオープンエアで椅子に背中を預け、スペイン風オムレツでお腹を満たし、楽しいおしゃべりに身を任せる幸せ。満ち足りた午後がゆっくりと過ぎていった。
ヤンとの再会によってモヤモヤした気持ちも忘れかけた約1時間後、アイリッシュ詩人や夫婦が先に出発し、私もさて、もうひと頑張りするぞ、と出立する前にトイレへと立った。
そして再び遭遇したのだ、あのヤンに。
高い梁を巡らせた宿屋も兼ねた木造のかわいらしいバルの片隅で、トイレから出てきた私とバルに入ってきたヤンは、まさにバッタリと鉢合わせた。
そして驚いたことに、彼は先ほどまでのよそよそしさはどこへ行ったのかという勢いでつかつかと歩み寄り、私の両手を取ると口づけせんばかりに胸の前で握りしめ、ぐっと顔を寄せて「Are you OK?」と尋ねた。眉間に皺を寄せ、真剣そのもので真っすぐに私の目を見つめながら。
| 日本ではほぼ起こりえないシチュエーションに目の前で星が飛ぶのを感じながら、筋肉痛にはなっていないか、どこか足を痛めていないか、などとまるで保護者のように矢継ぎ早に訊いてくるヤンに向かって首を縦に何度も振ることで必死に答える。内心「近い! 近いよ、ヤン!」と叫びつつ…。 |
外へ出ると、ヤンの連れの二人の女性が待ち構えていて、ちょうど私だけになっていたテーブルに移ってきた。
が、私はすでに一時間ほど休憩を取っていたのでちょうど出発しようとしたところへ彼らがきた訳である。出立準備を始めると、コレット女史が「私たちが来るといつも逃げるのね」と冗談めかして言った。
カウボーイハットからサングラス、そして上着まで脱ぎ捨てて、黒いランニングシャツ一枚になったヤンが私の隣りにどかっと腰を下ろし、今日はどこまで行くつもりかと聞いてきた。
あと6キロ先のレディゴスに泊まるつもりだというと彼は、「レディゴス、レディゴス…」と口の中で唱えながら「I’ll follow you.」と言ってウィンクを投げてきた。
あああぁ、なんて軽いヤン!
女性たちに囲まれ、意外にも鍛えられた筋肉美を晒して片目をつぶって見せるヤンはまるで「だからオレがオマエに追いつくのを楽しみに待ってな」とでも言いたげに私には映った。
返事はせずに渇いた笑いを返した私は、どこかで本当に彼が私を追いかけてきてくれることを期待しつつ、あとたった6キロを歩いて止まるようなヤンではないことを知っていた。
事実、レディゴスの宿で過ごした夜、私はヤンに会ってはいない。ただ、彼は来たのだ、レディゴスで私が泊まったアルベルゲに。
彼らを残して出立した私がレディゴスのアルベルゲに着いてシャワーを浴び終え、さっぱりしたところで部屋で髪を乾かしていた時、中庭がにぎやかになったかと思うと、彼の連れの小さい方の女の子が、「Izumi!」と嬉しそうに声をかけて部屋に入ってきたのだ。
そしてくるりと踵を返すと「She’s here!」とヤンへ報告に行ったらしい。その後私はすぐに洗濯物を干しに裏庭へ行き、心地よい風に洗いたての髪をなぶられながら椅子に腰かけ、うたた寝などして過ごしていたので、ヤン達3人がどうしたのかは知らない。ヤンは部屋には顔を出さなかったからだ。
「スペインオヤジ達との焼肉パーティ
Barbrcue party with Spanish uncles」
その夜、私より先に着いてずっと中庭で椅子を円形に並べてお喋りしていたドイツ人のメガネの女の子と、アメリカ人の男の子、スペイン人のおじさん達が夕食に誘ってくれた。アルベルゲのキッチンで自分たちが買ってきた肉を焼いたりするのだという。
| ドイツ人の女の子に案内されて、ピザを焼くためのかまどがある古いキッチンへ行くと、スペインのオヤジ達4人が賑やかに肉を焼いたりポテトを揚げたりサラダを作ったりしている。セッティングされたテーブルについた私達若者3人の前には、素晴らしいチームワークで盛り付けられたステーキやポテトやサラダ、パンなどの皿があっという間に並んだ。 |
まるでコメディ映画でも見ているかのように分担された絶妙な流れ作業で、フライパンやナイフを手に料理を楽しむスペインのオヤジ4人組は皆とても陽気で声も大きく、時にはオペラのようにセリフを歌にのせながら喋るのでその賑やかさに圧倒され、私はヤンのことをしばし忘れて、久々の大勢での食事を楽しんだ。
マドリードで英語教師をしながらスペイン語を勉強中のアメリカ人の若い男の子が、英語の話せないオジサンたちとスペイン語を解さない私とドイツ人の女の子のために通訳として活躍してくれた。
しかし、人と人とを繋ぐのは時に言葉ではなく、音楽だったり美味しい料理だったり、お酒だったりする。とことん陽気なオジサン達に囲まれて、飲めや歌えやのどんちゃん騒ぎの様相を呈した楽しい夕食にかかった費用はたったの3ユーロ。若者の負担を軽くしてくれたオジサン達は、見た目も気持ちも太っ腹なのだった。
夕食を待っている間に若者3人で話しているとき、ドイツの女の子が首を傾げていた。
「あなたの少し後に来たドイツ人女性二人と男性一人のうち男性だけここに残ったんだけど、あの人どこへ行ったのかしら」と…。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8267904
この記事へのトラックバック