�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B
�L��
�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B
posted by fanblog
2017�N03��21��
�t�̂��Ƃ���@�G���͐����͂����܂���
�@��T�A��ɍ炢������ƃz�g�P�m�U���Љ�܂����B
����A�ߏ����U�����ɁA�y�̂Ȃ��Ƃ���ɐ����Ă���G���������܂����̂ŏЉ�܂��B
�ʐ^�͓��H�̃A�X�t�@���g������u���b�N�����B���Ă��܂��B
���ƉE�̃u���b�N�̋�����ꊔ�i�t���N�₩�j�ƁA�E�̃u���b�N���̖ڒn����ꊔ�ł��B

�t��2�����݂��Ⴂ�Ɂi�s�̒f�ʂ��l�p�`�j�o�Ă��邱�ƁA�Ԃ�����ƃz�g�P�m�U�i���̍��j�̌`�ł��邱�Ƃ���A���̎G���̓z�g�P�m�U���Ǝv���܂��B
��ɐ������z�g�P�m�U�Ɣ�ׂ�Ɨt�̐F��A�Ԃ̑N�₩�����܂���������܂��A�悭������ȂƂ���ɐ������Ǝv���܂��B
���̌s�͉E�ƍ��̃u���b�N�̌��Ԃ���������̂ŁA�����ɗ��܂����y�����n�ʂ̑�������Ă���Ǝv���܂��B
�E�̌s�Ɏ����Ă̓u���b�N���̖ڒn�Ȃ̂łǂ�����Ď킪�����āA�������������h�{�Ɉ�����̂��͑z�������܂���B
�܂��������ォ�痬�ꗎ����r���ň�����̂��i�Ⴆ�|�g�X�̂悤�ɐ������ň�����̂��j�H
��q�����ƍ����o�āA���͌s���x���Ă���͂��̂ŁA�ǂ���̌s���������������u���b�N�̉���܂ł���̂ł͂Ƒz�����܂��B
������̂��炢�����͂�����ƋQ����������ł���̂��Ȃ��A�Ǝv���܂����B
�����������疡��A�����ڂ��C�ɂ��Ȃ��̂Ȃ����������炢�̐����͂�����̂�������܂���B
��ƎG������ʂ��Ă���̂͐l�ԂŁA�ق��̐����ɂƂ��Ă͓����A���Ȃ̂ŁB
����A�ߏ����U�����ɁA�y�̂Ȃ��Ƃ���ɐ����Ă���G���������܂����̂ŏЉ�܂��B
�ʐ^�͓��H�̃A�X�t�@���g������u���b�N�����B���Ă��܂��B
���ƉE�̃u���b�N�̋�����ꊔ�i�t���N�₩�j�ƁA�E�̃u���b�N���̖ڒn����ꊔ�ł��B
�t��2�����݂��Ⴂ�Ɂi�s�̒f�ʂ��l�p�`�j�o�Ă��邱�ƁA�Ԃ�����ƃz�g�P�m�U�i���̍��j�̌`�ł��邱�Ƃ���A���̎G���̓z�g�P�m�U���Ǝv���܂��B
��ɐ������z�g�P�m�U�Ɣ�ׂ�Ɨt�̐F��A�Ԃ̑N�₩�����܂���������܂��A�悭������ȂƂ���ɐ������Ǝv���܂��B
���̌s�͉E�ƍ��̃u���b�N�̌��Ԃ���������̂ŁA�����ɗ��܂����y�����n�ʂ̑�������Ă���Ǝv���܂��B
�E�̌s�Ɏ����Ă̓u���b�N���̖ڒn�Ȃ̂łǂ�����Ď킪�����āA�������������h�{�Ɉ�����̂��͑z�������܂���B
�܂��������ォ�痬�ꗎ����r���ň�����̂��i�Ⴆ�|�g�X�̂悤�ɐ������ň�����̂��j�H
��q�����ƍ����o�āA���͌s���x���Ă���͂��̂ŁA�ǂ���̌s���������������u���b�N�̉���܂ł���̂ł͂Ƒz�����܂��B
������̂��炢�����͂�����ƋQ����������ł���̂��Ȃ��A�Ǝv���܂����B
�����������疡��A�����ڂ��C�ɂ��Ȃ��̂Ȃ����������炢�̐����͂�����̂�������܂���B
��ƎG������ʂ��Ă���̂͐l�ԂŁA�ق��̐����ɂƂ��Ă͓����A���Ȃ̂ŁB
�y���̃J�e�S���[�̍ŐV�L���z
-
no image
2017�N03��20��
����@�S�������܂����B
�@�V�O�N�㖖����W�O�N��ɓǂu�ĂJ�b�v���i���݂��j�v�́A�����̐l���ςɉe����^�����{�Ƃ����܂��B
����ɉe�����ꂽ�̂́A�l���o���̕s���Ɗ������������炾�Ǝv���܂��B���͋t�Ɍo���͖L�x�ł����A
���͏��Ȃ��Ȃ芴�������肷��@�������܂����B
�u�D��S�i���j���������͔̂N���Ƃ��Ă��N�ł���v�Ƃ́A�^���̂悤�ȋC�����܂��B
�ĂJ�b�v���͏��N�}�K�W���i�u�k�Ёj�ɘA�ڂ���Ă��܂����B�P�s�{�Ƃ��đS�P�T���ł��B
����́A�c�ɂ��瓌���Ɉ����z���Ă�����l���i�j�j���f���̈ꌬ�Ƃ���l�Ŏ�邱�ƂɂȂ�A�������̂��߂ɕs���Y���ɒj�̓����ҕ�W�����肢���܂��B
�����z���Ă����̂́A���Z�̔��l�ȓ������ł����B
�w�Z�ɒm���Ȃ��悤�ɂ���킯�ł����A�O�p�W����̃h�^�o�^����������R���f�B�ł��B
�ŏ��̂ق��̓M���O����Ȃ̂ł����A
������ǂ�...
����ɉe�����ꂽ�̂́A�l���o���̕s���Ɗ������������炾�Ǝv���܂��B���͋t�Ɍo���͖L�x�ł����A
���͏��Ȃ��Ȃ芴�������肷��@�������܂����B
�u�D��S�i���j���������͔̂N���Ƃ��Ă��N�ł���v�Ƃ́A�^���̂悤�ȋC�����܂��B
�ĂJ�b�v���͏��N�}�K�W���i�u�k�Ёj�ɘA�ڂ���Ă��܂����B�P�s�{�Ƃ��đS�P�T���ł��B
����́A�c�ɂ��瓌���Ɉ����z���Ă�����l���i�j�j���f���̈ꌬ�Ƃ���l�Ŏ�邱�ƂɂȂ�A�������̂��߂ɕs���Y���ɒj�̓����ҕ�W�����肢���܂��B
�����z���Ă����̂́A���Z�̔��l�ȓ������ł����B
�w�Z�ɒm���Ȃ��悤�ɂ���킯�ł����A�O�p�W����̃h�^�o�^����������R���f�B�ł��B
�ŏ��̂ق��̓M���O����Ȃ̂ł����A
������ǂ�...
2017�N03��19��
�����@�S�Ɏc����
�@�u�S�Ɏc���ʁv�����鏬���ɏo��̂͂T���ʂ��ȂƎv���܂��B
�����悻�X�T���̏����͐S�Ɏc��܂��ǂ�ł���Ƃ��́A�����A�ʔ����A�Ƃ����莞�Ԃ̉߂���̂�Y�ꂳ���Ă����l���ɂȂ����悤�ȋC�����ɂ����Ă���܂��B
�nj㊴�͗ǂ��̂ł����N�����o���Ă��u�S�Ɏc���ʁv�����鏬���ɏo����͂Ȃ��Ȃ�����܂���B
�Ⴂ����͌o�����Ȃ����߁A�������邱�Ƃ����������C�����܂��B
�S�Ɏc���ʂ����鏬�����Љ�܂��B�P�O�ォ��Q�O��ɓǂ����ł��B
�@�����蕨��i�i�n�ɑ��Y�j�F�֓����O�i��������Y�j�����Z�̍����̒�ł��闊�|�̈����A�[�F�����ɓ���邽�߁A�������ő��ɂ��Ղ̊G�̊���˔�����ʂł��B
���̎��̋L�q���A�����̒[���瑄�Ŏh���G�܂ł�
�u�����B�����ɂ������v
�Ə�����r�����Ȃ�����ȏ�i�����܂��B
�A�O�l�Y�i�Ėڟ��j�F�O�l�Y�����H�q����肽������Ԃ������̓�l�̂����ł��B
�u����́c�v�u���Ȃc�v
�Ɠ�l�Ƃ��D���Ȃ̂Ɍ����o���Ȃ��Ȃ����ɂ��ݏo�Ă���Ǝv���܂��B
�@�X�g���C���V�[�v�ƌ��ɏo���V�[�������A���݂��Ɍ��ɏo���Ȃ����ǂ��������������܂��B
�B���������i�R��L�q�j�F�����ɂȂ������O�������ՏI���}������A���̉���
�u��͓������a�@���r�a����U�ɂ��Ă̋����v
�Ƃ������O�����̏���������������܂����B
�F�͍��O���A����ł��邱�Ƃ��B���ʂ����Ǝv���Ă��܂����B
���������O�͎���������ł��邱�Ƃ��킩���Ă����A�Ƃ�����ʂł��B
��w���̋������S���Ȃ�Ɖ�U����邱�Ƃ������Ă���̂Ŏ����Ȃ�̏�����`�����������Ƃ������Ƃł��B
���͑����A�ٔ��A�w��ł̔��\�Ƃ��낢�날��܂������A�Ō�̊ԍۂɌ����҂Ƃ��Ă����������߂����Ƃ�����i�������ъ������܂��B
�C�����e�N���X�g���i�A���N�T���h���E�f���}�j�F�D���̃_���e�X��23�N�ヂ���e�E�N���X�g���Ɩ����悤�ɂȂ莩�����̍߂ŘS�ɓ��ꂽ�W�҂ɕ��K���Ă�������ł��B
����҂����������Z�f�X���_���e�X���ׂꂽ�t�F���i���̍ȂɂȂ��Ă��܂����B
�t�F���i���̉Ƃŕ�������Â��܂��������Z�f�X�������e�E�N���X�g���ɉ������߂Ă����ɓ���Ȃ���ʂŁA
�@�u�킽���͐���Ⴑ�����������ׂ܂���̂Łv�ƁA�����e�E�N���X�g�����������B
�Ƃ���A���Ȃ������Z�f�X���D���Ȃ̂ł����G�̉Ƃł͂��̂�H�ׂȂ��Ƃ����ӎu�̋��������ݓ���܂����B
�N��ƌo�����d�˂�ɏ]���A�Ȃ��Ȃ��������鏬���ɂ͏o��܂���B
�����������������Ă��܂����炩������܂��A�N����̊�����ꂽ�����ɏo�����Љ�����Ǝv���܂��B
�����悻�X�T���̏����͐S�Ɏc��܂��ǂ�ł���Ƃ��́A�����A�ʔ����A�Ƃ����莞�Ԃ̉߂���̂�Y�ꂳ���Ă����l���ɂȂ����悤�ȋC�����ɂ����Ă���܂��B
�nj㊴�͗ǂ��̂ł����N�����o���Ă��u�S�Ɏc���ʁv�����鏬���ɏo����͂Ȃ��Ȃ�����܂���B
�Ⴂ����͌o�����Ȃ����߁A�������邱�Ƃ����������C�����܂��B
�S�Ɏc���ʂ����鏬�����Љ�܂��B�P�O�ォ��Q�O��ɓǂ����ł��B
�@�����蕨��i�i�n�ɑ��Y�j�F�֓����O�i��������Y�j�����Z�̍����̒�ł��闊�|�̈����A�[�F�����ɓ���邽�߁A�������ő��ɂ��Ղ̊G�̊���˔�����ʂł��B
���̎��̋L�q���A�����̒[���瑄�Ŏh���G�܂ł�
�u�����B�����ɂ������v
�Ə�����r�����Ȃ�����ȏ�i�����܂��B
�A�O�l�Y�i�Ėڟ��j�F�O�l�Y�����H�q����肽������Ԃ������̓�l�̂����ł��B
�u����́c�v�u���Ȃc�v
�Ɠ�l�Ƃ��D���Ȃ̂Ɍ����o���Ȃ��Ȃ����ɂ��ݏo�Ă���Ǝv���܂��B
�@�X�g���C���V�[�v�ƌ��ɏo���V�[�������A���݂��Ɍ��ɏo���Ȃ����ǂ��������������܂��B
�B���������i�R��L�q�j�F�����ɂȂ������O�������ՏI���}������A���̉���
�u��͓������a�@���r�a����U�ɂ��Ă̋����v
�Ƃ������O�����̏���������������܂����B
�F�͍��O���A����ł��邱�Ƃ��B���ʂ����Ǝv���Ă��܂����B
���������O�͎���������ł��邱�Ƃ��킩���Ă����A�Ƃ�����ʂł��B
��w���̋������S���Ȃ�Ɖ�U����邱�Ƃ������Ă���̂Ŏ����Ȃ�̏�����`�����������Ƃ������Ƃł��B
���͑����A�ٔ��A�w��ł̔��\�Ƃ��낢�날��܂������A�Ō�̊ԍۂɌ����҂Ƃ��Ă����������߂����Ƃ�����i�������ъ������܂��B
�C�����e�N���X�g���i�A���N�T���h���E�f���}�j�F�D���̃_���e�X��23�N�ヂ���e�E�N���X�g���Ɩ����悤�ɂȂ莩�����̍߂ŘS�ɓ��ꂽ�W�҂ɕ��K���Ă�������ł��B
����҂����������Z�f�X���_���e�X���ׂꂽ�t�F���i���̍ȂɂȂ��Ă��܂����B
�t�F���i���̉Ƃŕ�������Â��܂��������Z�f�X�������e�E�N���X�g���ɉ������߂Ă����ɓ���Ȃ���ʂŁA
�@�u�킽���͐���Ⴑ�����������ׂ܂���̂Łv�ƁA�����e�E�N���X�g�����������B
�Ƃ���A���Ȃ������Z�f�X���D���Ȃ̂ł����G�̉Ƃł͂��̂�H�ׂȂ��Ƃ����ӎu�̋��������ݓ���܂����B
�N��ƌo�����d�˂�ɏ]���A�Ȃ��Ȃ��������鏬���ɂ͏o��܂���B
�����������������Ă��܂����炩������܂��A�N����̊�����ꂽ�����ɏo�����Љ�����Ǝv���܂��B
2017�N03��18��
�G���h�E���i�Q�j�@�P������
�@�挎�P�X���ɃG���h�E���̕c���ڐA���āA�P�����o���܂����B
�Q���͕��������ւ��A�c���܂�邩�ƐS�z�����܂������A�K���ꊔ����Q�ɂ����܂���ł����B
���X�A����������ȊO�������Ă��܂���B
�����P�����O�A�E�������̏�Ԃł��B
���̎ʐ^�ł͂Q���i�w�����P�|�b�h�ɂQ�������Ă����̂ł��̂܂܈ڐA���܂����j�ʂ��Ă��܂��B
�P�����ʼnE���̊����L�тĂ��܂������̊��͂��܂萬�����Ă��܂���B
���Ə����܂������A�܂��c�̂悤�ŁA�ߏ��̉ƒ�؉�������Ă�����̃G���h�E�Ɣ�ׂ�ƁA���炩�ɐ������x���ł��B
�挎�������K�̎}�̂����Ȃ̂��A�y�������̂������s���ł��B
��������͂悭�A��ؗp�̓y���g�p���Ă���̂ł����Ȃ��ł��傤���H
��ĕ����������Ƃ����́A�͂����肵�Ă��܂��B
�ΊD���T�����A�ǔ�����邩�A�h���̘m��~�����A���𗣂��Ă��܂����A���̗��Ē��������Ȃ��Ǝ��n�܂ł��ǂ蒅���Ȃ��C�����܂��B
���|�̖{�ƁA�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ���ĕ��ł́A�����ÂႤ�̂Ő����͂Ȃ��̂�������܂���B
�������ꂼ��قȂ�̂ł�����A��͂�m���ƌo����ς�ł��������Ȃ��̂ł��傤�B
�Q���͕��������ւ��A�c���܂�邩�ƐS�z�����܂������A�K���ꊔ����Q�ɂ����܂���ł����B
���X�A����������ȊO�������Ă��܂���B
�����P�����O�A�E�������̏�Ԃł��B
 |
���̎ʐ^�ł͂Q���i�w�����P�|�b�h�ɂQ�������Ă����̂ł��̂܂܈ڐA���܂����j�ʂ��Ă��܂��B
�P�����ʼnE���̊����L�тĂ��܂������̊��͂��܂萬�����Ă��܂���B
���Ə����܂������A�܂��c�̂悤�ŁA�ߏ��̉ƒ�؉�������Ă�����̃G���h�E�Ɣ�ׂ�ƁA���炩�ɐ������x���ł��B
�挎�������K�̎}�̂����Ȃ̂��A�y�������̂������s���ł��B
��������͂悭�A��ؗp�̓y���g�p���Ă���̂ł����Ȃ��ł��傤���H
��ĕ����������Ƃ����́A�͂����肵�Ă��܂��B
�ΊD���T�����A�ǔ�����邩�A�h���̘m��~�����A���𗣂��Ă��܂����A���̗��Ē��������Ȃ��Ǝ��n�܂ł��ǂ蒅���Ȃ��C�����܂��B
���|�̖{�ƁA�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ���ĕ��ł́A�����ÂႤ�̂Ő����͂Ȃ��̂�������܂���B
�������ꂼ��قȂ�̂ł�����A��͂�m���ƌo����ς�ł��������Ȃ��̂ł��傤�B
2017�N03��17��
���Ɛ��@�H��
�@25�N�قǑO�A���[���b�p�̓c�ɂɏZ��ł������Ƃ�����܂��B
300�����قǗ��ꂽ�s�s�܂ōs���Γ��{�H���X�g�����A���{�H�ޓX������܂������Z��ł���Ƃ���ɂ́A���{�H�ޓX�͂���܂���ł����B
�ߏ��ɒ��ؐH�ޓX������قƂ�ǂ̓���̐H�ނ��w�����Ă��܂����B
��Ԃ����b�ɂȂ����̂́A�������ȓ��{��̖��O���܂Ɉ�����ꂽ�C�^���A�Y�̕Ăł��i���{�̃R�����l�S�肪�o�܂��j�B
���[���b�p�̃R���͍ג����C���f�B�J�Ăł��B������͂ς��ς��ŁA���Ă��͂�Ƃ͌����܂���B���������Ă𐆂��Ƃ��������ł͂Ȃ��̂Ŏd��������܂���B
���N�Ɉ�x���炢��s�s�܂ōs���H�ނ����߂�̂ł����A�Ƃ̍ɂ��Ȃ��Ȃ������͎����ʼn��_�����܂����̂ŏЉ�܂��B
�@�h�g�F�邾���Ȃ̂ŊȒP�B
�C���߂��̂ŏT�Ɉ�x�A�s���J���V�N�ȋ��������Ă��܂����B
���Ƀ}�O���͌��n�ł̓\�e�[�ɂ��ĐH�ׂ邽�߁A�g���̕����͐l�C������܂���B
��ōw�����A�����ɂ��Ă���邾���ł��B
�z�^�e�L�͐������܂ܕ��ׂ��Ă���̂ł�����J���Đ邾���B
�C�J���Ƃꂽ�Ă����ׂ��Ă���̂Ń��^������Ĕ���ނ��Đ邾���B
�^�R�͂���܂���B�G�r�͐����Ă���̂ł����A���{�ł͌��Ȃ���ނȂ̂ŁA�h�g�ɂ͂��܂���B
���Ƃ̓A�{�K�h�𔖂����Ďh�g�ɓY���܂��B
�卪�͓��{�Ƃ͎�ނ��Ⴄ�̂ł����A�h�g�̂܂ɂ͂Ȃ�܂����B
�A�[���F����ł��B
�哤�͒��ؐH�ޓX�ōw���A�[���ۂ͓��{���玝�Q�B�̔��ɓd�������40���ʂɂȂ�悤�ȕ����쐬�B
��Ӑ��ɂ��A�_�炩���Ȃ�܂Ŏϋl�߂܂��B��߂��琴���ȗe��ɂ���[���ۂ����������܂��A
���̂܂܁A������x�Ǘ����Ȃ���u���ƁA5���1�炢�͂܂Ƃ��Ȕ[�����ł��܂����B
�B��₵���F�ȒP�ł��B
�˂̓X�p�Q�b�e�B�A����͏ݖ��A�����A�}�X�^�[�h�A�|�ł܂��܂��ł��B
���[���b�p�Y�̑傫�ȃL���E���A���n���A���Ă����肵�����̂��ڂ���Əo���オ��B
�C���ȕ��F�ȒP�ł����d�J���ł��B
�哤���u���Ă��蔫�ŕ��ɂ��܂��i���{�̎s�̕i���ǂ�����ɂȂ�܂��j�B
�D�����F�ȒP�ł��B
���ؐH�ޓX�ɓ��{���̓����̂��Ɓi�哤�̕��Ƃɂ��肪���ɓ����Ă���j�������Ă����̂ŁA���������ʂ�ɍ��Ώo���オ��B
�E���g���F�D�̓����𔖂����Đ��C������Ė��ŗg���ďo���オ��B���g���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������B
�F�花���卪�F�卪����ɂ��ăx�����_�Ŋ��������B
���̍��́A���肠�킹�̂��̂œ��{�H���ۂ������ɂ������̂ŏ\���������������܂����B
���ł́A�ƂĂ��H�ׂ�Ȃ���������܂���B
�܂��A���y���݂�����܂����B
���͎�ԉɂ�������C���^�[�l�b�g�Œ��������ق������S�A���Ԃ̐ߖ�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�������v���o�͎c��܂��B
300�����قǗ��ꂽ�s�s�܂ōs���Γ��{�H���X�g�����A���{�H�ޓX������܂������Z��ł���Ƃ���ɂ́A���{�H�ޓX�͂���܂���ł����B
�ߏ��ɒ��ؐH�ޓX������قƂ�ǂ̓���̐H�ނ��w�����Ă��܂����B
��Ԃ����b�ɂȂ����̂́A�������ȓ��{��̖��O���܂Ɉ�����ꂽ�C�^���A�Y�̕Ăł��i���{�̃R�����l�S�肪�o�܂��j�B
���[���b�p�̃R���͍ג����C���f�B�J�Ăł��B������͂ς��ς��ŁA���Ă��͂�Ƃ͌����܂���B���������Ă𐆂��Ƃ��������ł͂Ȃ��̂Ŏd��������܂���B
���N�Ɉ�x���炢��s�s�܂ōs���H�ނ����߂�̂ł����A�Ƃ̍ɂ��Ȃ��Ȃ������͎����ʼn��_�����܂����̂ŏЉ�܂��B
�@�h�g�F�邾���Ȃ̂ŊȒP�B
�C���߂��̂ŏT�Ɉ�x�A�s���J���V�N�ȋ��������Ă��܂����B
���Ƀ}�O���͌��n�ł̓\�e�[�ɂ��ĐH�ׂ邽�߁A�g���̕����͐l�C������܂���B
��ōw�����A�����ɂ��Ă���邾���ł��B
�z�^�e�L�͐������܂ܕ��ׂ��Ă���̂ł�����J���Đ邾���B
�C�J���Ƃꂽ�Ă����ׂ��Ă���̂Ń��^������Ĕ���ނ��Đ邾���B
�^�R�͂���܂���B�G�r�͐����Ă���̂ł����A���{�ł͌��Ȃ���ނȂ̂ŁA�h�g�ɂ͂��܂���B
���Ƃ̓A�{�K�h�𔖂����Ďh�g�ɓY���܂��B
�卪�͓��{�Ƃ͎�ނ��Ⴄ�̂ł����A�h�g�̂܂ɂ͂Ȃ�܂����B
�A�[���F����ł��B
�哤�͒��ؐH�ޓX�ōw���A�[���ۂ͓��{���玝�Q�B�̔��ɓd�������40���ʂɂȂ�悤�ȕ����쐬�B
��Ӑ��ɂ��A�_�炩���Ȃ�܂Ŏϋl�߂܂��B��߂��琴���ȗe��ɂ���[���ۂ����������܂��A
���̂܂܁A������x�Ǘ����Ȃ���u���ƁA5���1�炢�͂܂Ƃ��Ȕ[�����ł��܂����B
�B��₵���F�ȒP�ł��B
�˂̓X�p�Q�b�e�B�A����͏ݖ��A�����A�}�X�^�[�h�A�|�ł܂��܂��ł��B
���[���b�p�Y�̑傫�ȃL���E���A���n���A���Ă����肵�����̂��ڂ���Əo���オ��B
�C���ȕ��F�ȒP�ł����d�J���ł��B
�哤���u���Ă��蔫�ŕ��ɂ��܂��i���{�̎s�̕i���ǂ�����ɂȂ�܂��j�B
�D�����F�ȒP�ł��B
���ؐH�ޓX�ɓ��{���̓����̂��Ɓi�哤�̕��Ƃɂ��肪���ɓ����Ă���j�������Ă����̂ŁA���������ʂ�ɍ��Ώo���オ��B
�E���g���F�D�̓����𔖂����Đ��C������Ė��ŗg���ďo���オ��B���g���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������B
�F�花���卪�F�卪����ɂ��ăx�����_�Ŋ��������B
���̍��́A���肠�킹�̂��̂œ��{�H���ۂ������ɂ������̂ŏ\���������������܂����B
���ł́A�ƂĂ��H�ׂ�Ȃ���������܂���B
�܂��A���y���݂�����܂����B
���͎�ԉɂ�������C���^�[�l�b�g�Œ��������ق������S�A���Ԃ̐ߖ�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�������v���o�͎c��܂��B
2017�N03��16��
����g���@�p�ӂ��܂����B
�@���i�A����g�������Ƃ��͎s�̂̓��g�������g�p���Ă��܂��B
����͎��̎��Ƃ̕ꂪ����Ă����Ǝv������@�ō���Ă݂܂����B
�g����O�̒i�K��2�p�^�[������̂ł����A�ǂ��炾������������ɂ͕����Ȃ��̂ł킩��܂���B
�@�������炦�́A��������|�����Ńv�v�Ƃ����Č��������܂��i����͌������Y��܂����j�B
�A�����ɐ�A�{�[���ɓ����B
�B���傤��K�ʁi�ʐ^�ł͂������Q���ő���R���炢�j�A�����K�ʁi�ʐ^�ł͏������P���炢�j�A���萶�I���X�����A��ō������킹�܂��B���̂܂�30���`�R���ԁi�K���ł��j�Ȃ��܂��B

������ǂ�...
����͎��̎��Ƃ̕ꂪ����Ă����Ǝv������@�ō���Ă݂܂����B
�g����O�̒i�K��2�p�^�[������̂ł����A�ǂ��炾������������ɂ͕����Ȃ��̂ł킩��܂���B
�@�������炦�́A��������|�����Ńv�v�Ƃ����Č��������܂��i����͌������Y��܂����j�B
�A�����ɐ�A�{�[���ɓ����B
�B���傤��K�ʁi�ʐ^�ł͂������Q���ő���R���炢�j�A�����K�ʁi�ʐ^�ł͏������P���炢�j�A���萶�I���X�����A��ō������킹�܂��B���̂܂�30���`�R���ԁi�K���ł��j�Ȃ��܂��B

������ǂ�...
2017�N03��14��
����w���܂����B�@�i�O�c�@�j
�@��T�͎Q�c�@�̍���w�����܂������A�{���͏O�c�@�̍���w�����܂����B
��t��̏W���ꏊ�͎Q�c�@�ƈقȂ肠�܂�d�X����������܂���B
3��11���̎ʐ^�Ɣ�ׂĂ݂Ă��������B

����͏W���ꏊ�Ɏ����̔��@�������܂����B�Ȃ�ƒʏ�̒l�i�������Ȃ��Ă��܂��B
���w���͈��H�֎~�ł��B

���w�J�n���ԂɂȂ�Ǝ�ו���������n�܂�͎̂Q�c�@�Ɠ����ł��B
���O�~�̊K�i��n���P�K����R�K�܂ŏグ��܂��B
�Q�c�@�Ɠ����悤�ɘL���̕Б��Ɋe�}�̕��������є��Α��͒���ł��B
������ǂ�...
��t��̏W���ꏊ�͎Q�c�@�ƈقȂ肠�܂�d�X����������܂���B
3��11���̎ʐ^�Ɣ�ׂĂ݂Ă��������B

����͏W���ꏊ�Ɏ����̔��@�������܂����B�Ȃ�ƒʏ�̒l�i�������Ȃ��Ă��܂��B
���w���͈��H�֎~�ł��B

���w�J�n���ԂɂȂ�Ǝ�ו���������n�܂�͎̂Q�c�@�Ɠ����ł��B
���O�~�̊K�i��n���P�K����R�K�܂ŏグ��܂��B
�Q�c�@�Ɠ����悤�ɘL���̕Б��Ɋe�}�̕��������є��Α��͒���ł��B
������ǂ�...
2017�N03��13��
�}�E�X�@�`�ԕϑJ
�@�p�\�R����ς��邽�тɃ}�E�X�������Ă��܂��i���[�J�[���ł�BTO�ł��}�E�X���w�����Ă���̂Łj�B
���������Ă���ł��Â��}�E�X�́A1995�N��PC9801�����芷�������ɖ{�̂ƂƂ��ɍw���������̂ł��B
PC-9801�͈����z�����ɂ��ׂĔp�����Ă��܂����̂Ń}�E�X���ǂ�Ȃ��̂��������Y��Ă��܂��܂����B
��헪�ŗV�̂Ń}�E�X�͂������Ǝv���̂ł����A�������Ȃ��̂ŏЉ�ł��܂���B
�Q�{�^�����Ń}�E�X�̉��ɂ̓S���{�[�������Ă��܂��B�p�b�h��łȂ��ƃ{�[���̉�]�����ǂ��������Ƃ�����܂����B
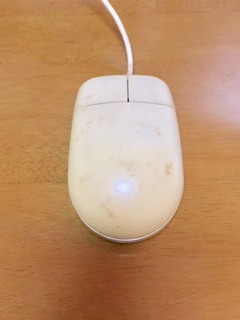
���ɍw�������{�̂̎��̓z�C�[���t���ł��B������ǂ�...
���������Ă���ł��Â��}�E�X�́A1995�N��PC9801�����芷�������ɖ{�̂ƂƂ��ɍw���������̂ł��B
PC-9801�͈����z�����ɂ��ׂĔp�����Ă��܂����̂Ń}�E�X���ǂ�Ȃ��̂��������Y��Ă��܂��܂����B
��헪�ŗV�̂Ń}�E�X�͂������Ǝv���̂ł����A�������Ȃ��̂ŏЉ�ł��܂���B
�Q�{�^�����Ń}�E�X�̉��ɂ̓S���{�[�������Ă��܂��B�p�b�h��łȂ��ƃ{�[���̉�]�����ǂ��������Ƃ�����܂����B
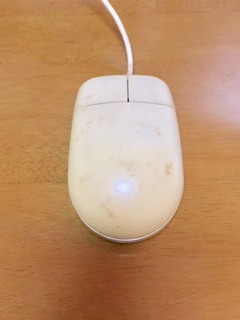
���ɍw�������{�̂̎��̓z�C�[���t���ł��B������ǂ�...
2017�N03��12��
2017�N03��11��
����w���܂����B�@�i�Q�c�@�j
�@�����̃X�J�C�c���[���w��A����c�����i�Q�c�@�j���w�ɍs���܂����B
�����Œ�8������P���Ԗ��Ɏ�t���A�N�ł��Q���ł��܂��B
�Ŋ��̒n���S�w�́A�u����c�����O�w�v�u�i�c���v�ɂȂ�܂��B�ǂ���������Đ����ł��B
����40��������t���J�n�A55���Ɏ�t�I���ɂȂ�A�������Ɍ��w�X�^�[�g�ł��B
��t��A�W���ꏊ�͎Q�σ��r�[�ɂȂ�܂��B

�ʐ^�B�e�͂����ȍ~�͋֎~�ɂȂ�܂��B
�i�O�c�@�͖{��c��̎B�e�j
���w���͏��w���̃O���[�v��20���ƈ�ʎҖ�20���̖�40���ł����B
�Q�σ��r�[����2��ɂȂ�A����֎~�ō���c��������������Ă����܂��B
�@�L���͂��ׂĐԂ��イ����A�{��c��Ɍ������ʘH�̕Б��Ɋe�}�h�̍T���A�ψ����������ł���ؑ��̃h�A���Â��܂܂ł��B���Α��͒�ɂȂ��Ă���O���������Ă��܂��B
���ǂ���͎Q�c�@�{��c��A��x���A�����L�ԁi�Q�c�@�ƏO�c�@�̊Ԃɂ���Ƃ��������̕����j�ł��B
�嗝�A�w���ӂ�Ɏg�p����A�Â߂������d���A�����g�p���Ă���Ƃ͎v���Ȃ��d���Ŋi��������܂��B
������ǂ�...
�����Œ�8������P���Ԗ��Ɏ�t���A�N�ł��Q���ł��܂��B
�Ŋ��̒n���S�w�́A�u����c�����O�w�v�u�i�c���v�ɂȂ�܂��B�ǂ���������Đ����ł��B
����40��������t���J�n�A55���Ɏ�t�I���ɂȂ�A�������Ɍ��w�X�^�[�g�ł��B
��t��A�W���ꏊ�͎Q�σ��r�[�ɂȂ�܂��B
�ʐ^�B�e�͂����ȍ~�͋֎~�ɂȂ�܂��B
�i�O�c�@�͖{��c��̎B�e�j
���w���͏��w���̃O���[�v��20���ƈ�ʎҖ�20���̖�40���ł����B
�Q�σ��r�[����2��ɂȂ�A����֎~�ō���c��������������Ă����܂��B
�@�L���͂��ׂĐԂ��イ����A�{��c��Ɍ������ʘH�̕Б��Ɋe�}�h�̍T���A�ψ����������ł���ؑ��̃h�A���Â��܂܂ł��B���Α��͒�ɂȂ��Ă���O���������Ă��܂��B
���ǂ���͎Q�c�@�{��c��A��x���A�����L�ԁi�Q�c�@�ƏO�c�@�̊Ԃɂ���Ƃ��������̕����j�ł��B
�嗝�A�w���ӂ�Ɏg�p����A�Â߂������d���A�����g�p���Ă���Ƃ͎v���Ȃ��d���Ŋi��������܂��B
������ǂ�...
