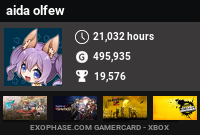|
The Elder Scrolls IV:オブリビオン Game of the Year Edition プラチナコレクション |
おはようございます。あるへです。
今回はこちら「The Elder Scrolls IV:OBLIVION」をレビューします。
言わずと知れた超有名ゲーム、プレイしたことがなくても「観た」ことはある、という人もかなり多いのではないでしょうか。
観たことがあるだけの人、やらなきゃ損ですよ。
公式サイト
ただし、今回レビューするのは私がプレイしたXbox360版、ひいては家庭用ソフトのことですので、PCの利点をフル活用した、MODを始めとする様々なユーザーコンテンツには触れないことご了承ください。また、IVとナンバリングされている通り、前作が存在しますが、さらに人を選ぶゲームになっています。前作との繋がりはほとんどありませんので、気にしなくても大丈夫です。
さて、オープンワールドゲーと言ったらロックスター(GTA)かベセスダ(オブリビオン、スカイリム、フォールアウト)か、というくらいの今では老舗のオープンワールドRPGですが、現在の視点で眺めてみると、「古臭い」という感覚は否めません。
バタ臭く、まったく日本人受けしそうにないキャラモデル、GTAとは違い一人称視点ということで、背景から小物まで細部まで観察できるのですが、それが仇となりグラフィックは汚く見えてしまうのではないでしょうか。GTA5やスカイリムなどを経験している方なら、「スカスカしている」と感じることもあるかもしれません。戦闘も多少の駆け引きは作れるとはいえ、基本的には単調な部類です。
ではいったいこのゲームは何を楽しめばいいのかというと、それはもう皆さんお分かりのように、この広大な世界を思うがままに過ごす、というのが最大の醍醐味です。
最近まで(というか今も)GTA4をプレイしていまして、どうしても比べがちになってしまって恐縮ですが、たとえばGTA4のストーリーというのはかなり受動的なシステムであり、たいていマップに表示されたアイコンの場所へ行けば自動的にストーリーが始まります。ストーリー展開的にも「あれをやってこい」だのお使いが大部分です。ストーリー分岐が少ないかわりに演出やセリフ回しに手が込んでおり、見ていて惹き込まれるものになっています。
対してオブリビオンは、困っている人を見つけ、自分から話しかけてクエストを発生させます。また、頼まれごとを引き受けるか拒絶するかはプレイヤーの選択に委ねられますし、クエストの過程で裏切ったり、宝を手に入れてとんずらすることだって出来ます。
GTAでは街の再現に力を尽くしており、遠くから見るほど美しいと感じられる反面、数少ない特定の建物にしか入れなかったり、街ゆくNPCはあくまでNPCで、コミュニケーションをとることはできませんでした。
そういう風に見てみると、オブリビオンは大抵の建物には入れますし、ほぼ全てのNPCには彼ら専用のセリフが用意されています。
ただ街を練り歩くだけだったGTAと比べれば、オブリビオンでは花も摘めますし、机の上のパンを盗み食いすることだって出来ます。
あくまでGTAとの比較で見ればオブリビオンのストーリーは「自分で作る」、かなり能動的なシステムとなっています。ストーリーの内容そのものはRPGのお約束ですけどね。
GTA4では最初こそグラの粗さに目が行きましたが、膨大なコンテンツを攻略するうちに大して気にならなくなりました。三人称視点であり、やや遠距離から物事を「マクロ」に捉え、膨大な要素を一つのまとまりとして考えることでGTAの世界観を楽しめると思います。様々な物や人、要素が絡まりあう、ということはストーリー内容の話題にも転換できます。多くの人がニコの物語に絡んできますよね?
逆にオブリビオンを始めとするベセスダRPGは、やはりグラフィックのキメは粗いものの、多くのクエストをこなし、広い世界を練り歩くうちにどうでもよくなります。GTAとは異なり、古臭いながらもさっぱりとしたテクスチャ、風味づけですので、よく見えます。水に潜ればその下の地面も見えますし、花が咲いていればその一輪一輪を観察できます。扉があれば十中八九その中に入れますし、部屋の中の意匠もこれでもかってくらいに中世王道ファンタジーです。
このように、GTAとは逆にオブリビオンでは「ミクロ」な視点で様々な、小さく些細な要素に感動し、その蓄積によってこの世界観を感じる、というコンセプトなのかもしれません。一つのストーリーラインに大人数が参加するというのはまずありませんし、派手な演出などもほとんどありません。あくまで主人公=自分というスタンスで、自分が見た物事しか把握できず、GTAのように深い余韻を残すことはほとんどないと思います。むしろ、今まで淡々と積み上げてきたクエスト履歴、経験や知識などが、あとで思い返すことで自分だけのストーリーとなって思い出に残る、そんなゲームですよね。
いかがでしょうか。一例としてGTA4を引き合いに出し、比較することでオブリビオンの魅力を探してみました。
なんだかんだ言って、オブリビオンはまだ典型的な洋モノRPGから抜け出しているとは言い切れません。むしろフォールアウトやスカイリムを経てようやく垢抜けてきた感じがします。
ですので、スカイリムは万人にお勧めしやすいのですが、オブリビオンを勧める場合にはいくつか注釈がついてしまいます。
不細工なキャラモデル、様々な世界観用語、もっさり殴りあい戦闘、何をするにもまず会話、宿屋で寝て初めてレベルアップ、等々ゲームの魅力にとりつかれた人を迎える懐の広さは文句なしに広いですが、反面そこに至るまでに若干の辛抱が必要なゲームでもあります。
動画や攻略サイトなどでさらっと予習した上でプレイするのがベターかもしれません。
*注意*
オブリビオンには無印版とGOTY(ゲームオブザイヤー)エディションの二種類が存在します。
追加コンテンツ「シヴァリング・アイルズ」は、技術上の問題からオンライン配信されていません。ですので、このコンテンツを遊びたい場合は最初から「シヴァリング・アイルズ」がインストールされているGOTY版を検討してください。無印版では遊ぶことができません。
攻略サイト