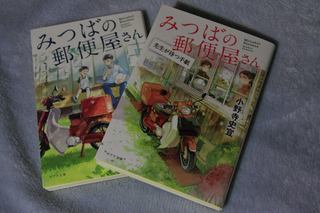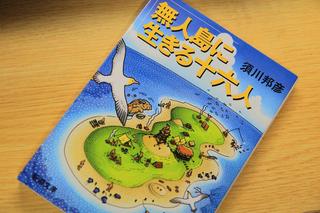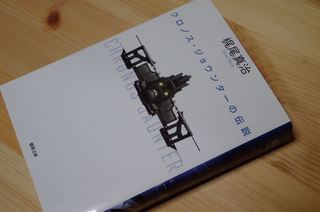2020年12月12日
竈門炭治郎の故郷、明治・大正期の雲取山に想いを馳せる話
「登山」昭和中期に入り大衆レジャーとして流行り出した登山。それからも何度かブームの波を越え、今に至ります。それよりも前の時代、近代日本の登山は生活の一部として山に分け入る、国策として地形把握のために入山する。軍事演習、修験者の修行など、レジャーとしてのそれは欧州の文化が明治期に日本に入り、当時はごく一部の富裕層の間で流行った道楽であったそうです。

そんな登山ですが、僕も好きで山に足を運びます。登山をしない人々からは
「なんで辛い思いをしてまで山に登りたいのか?」
という質問をもらうこともありますが、
「そこに山があるから!!」
というものでもなく、かといって登頂した時の達成感というわけでもないなと思うのです。だから返事に困ってしまします。今日はそんなお話。その中でも秩父山系の好きな山、雲取山についてお話して行きますね。
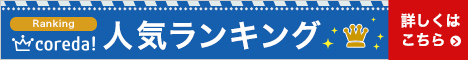
 その前に少しだけ、雲取山に限らず、山に登ることの楽しさの一つに、その山の歴史や、そこで垣間見る生活の跡、麓の集落とその山との関係、山小屋の歴史、などなど自然と人が関わってきた文化を知りたいと言う登山文化的な欲求と言うものがあります。
その前に少しだけ、雲取山に限らず、山に登ることの楽しさの一つに、その山の歴史や、そこで垣間見る生活の跡、麓の集落とその山との関係、山小屋の歴史、などなど自然と人が関わってきた文化を知りたいと言う登山文化的な欲求と言うものがあります。

僕の登山欲求はそれなのかもしれません。もちろん、街では出会えない美しい自然に出逢いに行くというのも大切な目的です。
そう言ったことをあえて一言で言うならば
「その山の記憶に想いを馳せて見たいから!」
とでも言いましょうかね。そういうことなのです。
そんなこともあり、自分の足で山に登ること以外にも、昔の登山の記録を読むことも、日常の楽しみの一つであります。
ここ40年くらいの山の記録は、山岳雑誌やその時代の登山小説などで目にすることはできますが、それより以前の明治大正期の登山記録は少ないですね。やはりレジャーとして大衆に浸透していなかったこと、山で生活している人々の間で、口頭や一緒に暮らす経験で受け継がれる歴史はあっても、それを書き物として記録に書き残すということがなかったため、代が変わり、生活も変わり、伝える必要がなくなれば、段々とその記録は失われてしまったと言うのが、その頃の登山または山での生活の記録があまり残っていない原因ではないかと思います。

そんな明治大正期において田部重治さんと言う方が、貴重な、特に関東の秩父山系を中心に山岳の記録を残しており、当時の書物が今でも復刻、編集されて販売されております。
北アルプスなどの雄大な自然の山岳地帯も好きですが、この秩父山系の魅力は自然の豊かさはもちろんですが、もう少し、麓の街との関わりやその山での生活など、人々の生活に息づいた山であると言うところに、山岳文化の探究心をくすぐる何かがあるのだと思うのです。

そんな秩父山系、東京都最高峰である雲取山は日本100名山の一つであります。この山の主な登山道は埼玉県側の三峰からと、東京都側の奥多摩地区からの二つのルートがあります。
どちらのルートも、かかる時間や難易度はさほど変わらないかと思います。
明治から大正期にかけてこの辺りは炭焼きが盛んで、この山で炭を作り、その袂で暮らし、街場にその炭を売りに行くと言うのがこの地域の材を切り出す林業に並ぶ経済の一つだったそうです。
田部重治さんの山の記録には、ただ山を登ってと言う登山記録だけではなく、山で暮らす人々の文化も描かれています。
登山中、山の中にポツンと建っていた炭焼きの家族の小屋で水を頂いたことや、その麓には炭焼きで生計を立てている人々の集落があり、仕事終わりに外の薪風呂を沸かして疲れを癒す住人や、炭を束ねた俵をいくつも背負って街まで運ばんとする人々の姿など、その山での生活ぶりも細かく描かれています。
最近、流行りの「鬼滅の刃」の主人公の「竈門炭治郎」も生家は炭焼きを生業としており、出身は雲取山ということだそうです。
 話の舞台も大正時代なので、その辺りはなるほどと思わせるところがあります。冒頭の生活のシーンでは雪の積もる山の中の一軒家に炭治郎が家族と住んでいて、麓の街に炭を売りに行くと言うのがあり、最初は東北あたりの出身なのかと思っておりましたが、なんとまさか東京の山だったとは。
話の舞台も大正時代なので、その辺りはなるほどと思わせるところがあります。冒頭の生活のシーンでは雪の積もる山の中の一軒家に炭治郎が家族と住んでいて、麓の街に炭を売りに行くと言うのがあり、最初は東北あたりの出身なのかと思っておりましたが、なんとまさか東京の山だったとは。
確かに雲取山も冬は雪が積もります。
冬の雲取山は綺麗です。そういう物語に想いを馳せて訪れるのもいいでしょう。しかし、そこは登山です!!ちょっとした観光のつもりで登ると取り返しのつかないことになります。

冬は雪崩こそ起きないものの、登山道は凍結箇所もありますし、山頂近くはマイナス10度を下回ります。

樹林帯では日差しの届かないことで寒さが増し、樹林帯を抜けた尾根では風に体温を奪われます。そんなところです。
無理だなと思ったら、無理して行かずに、その頃の書籍で知を肥やし、そこに想いを馳せると言うのも楽しみの一つではないでしょうか。

そんな登山ですが、僕も好きで山に足を運びます。登山をしない人々からは
「なんで辛い思いをしてまで山に登りたいのか?」
という質問をもらうこともありますが、
「そこに山があるから!!」
というものでもなく、かといって登頂した時の達成感というわけでもないなと思うのです。だから返事に困ってしまします。今日はそんなお話。その中でも秩父山系の好きな山、雲取山についてお話して行きますね。

僕の登山欲求はそれなのかもしれません。もちろん、街では出会えない美しい自然に出逢いに行くというのも大切な目的です。
そう言ったことをあえて一言で言うならば
「その山の記憶に想いを馳せて見たいから!」
とでも言いましょうかね。そういうことなのです。
そんなこともあり、自分の足で山に登ること以外にも、昔の登山の記録を読むことも、日常の楽しみの一つであります。
ここ40年くらいの山の記録は、山岳雑誌やその時代の登山小説などで目にすることはできますが、それより以前の明治大正期の登山記録は少ないですね。やはりレジャーとして大衆に浸透していなかったこと、山で生活している人々の間で、口頭や一緒に暮らす経験で受け継がれる歴史はあっても、それを書き物として記録に書き残すということがなかったため、代が変わり、生活も変わり、伝える必要がなくなれば、段々とその記録は失われてしまったと言うのが、その頃の登山または山での生活の記録があまり残っていない原因ではないかと思います。
 |
新品価格 |
そんな明治大正期において田部重治さんと言う方が、貴重な、特に関東の秩父山系を中心に山岳の記録を残しており、当時の書物が今でも復刻、編集されて販売されております。
北アルプスなどの雄大な自然の山岳地帯も好きですが、この秩父山系の魅力は自然の豊かさはもちろんですが、もう少し、麓の街との関わりやその山での生活など、人々の生活に息づいた山であると言うところに、山岳文化の探究心をくすぐる何かがあるのだと思うのです。

そんな秩父山系、東京都最高峰である雲取山は日本100名山の一つであります。この山の主な登山道は埼玉県側の三峰からと、東京都側の奥多摩地区からの二つのルートがあります。
どちらのルートも、かかる時間や難易度はさほど変わらないかと思います。
明治から大正期にかけてこの辺りは炭焼きが盛んで、この山で炭を作り、その袂で暮らし、街場にその炭を売りに行くと言うのがこの地域の材を切り出す林業に並ぶ経済の一つだったそうです。
田部重治さんの山の記録には、ただ山を登ってと言う登山記録だけではなく、山で暮らす人々の文化も描かれています。
登山中、山の中にポツンと建っていた炭焼きの家族の小屋で水を頂いたことや、その麓には炭焼きで生計を立てている人々の集落があり、仕事終わりに外の薪風呂を沸かして疲れを癒す住人や、炭を束ねた俵をいくつも背負って街まで運ばんとする人々の姿など、その山での生活ぶりも細かく描かれています。
最近、流行りの「鬼滅の刃」の主人公の「竈門炭治郎」も生家は炭焼きを生業としており、出身は雲取山ということだそうです。
 |
新品価格 |
確かに雲取山も冬は雪が積もります。
冬の雲取山は綺麗です。そういう物語に想いを馳せて訪れるのもいいでしょう。しかし、そこは登山です!!ちょっとした観光のつもりで登ると取り返しのつかないことになります。

冬は雪崩こそ起きないものの、登山道は凍結箇所もありますし、山頂近くはマイナス10度を下回ります。

樹林帯では日差しの届かないことで寒さが増し、樹林帯を抜けた尾根では風に体温を奪われます。そんなところです。
無理だなと思ったら、無理して行かずに、その頃の書籍で知を肥やし、そこに想いを馳せると言うのも楽しみの一つではないでしょうか。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10402781
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック