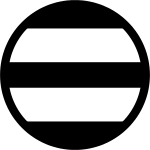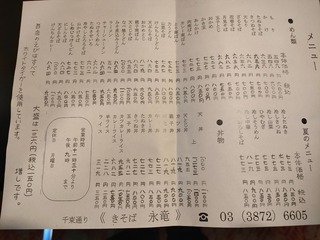新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2019年12月21日
一条房家
一条 房家(いちじょう ふさいえ)
戦国時代の公卿(土佐国の国司)、大名。
土佐一条氏の第2代当主。
関白・一条教房の次男。
戦国時代の公卿(土佐国の国司)、大名。
土佐一条氏の第2代当主。
関白・一条教房の次男。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
一条兼良
一条 兼良(いちじょう かねよし)
室町時代前期から後期にかけての公卿・古典学者。名は一般には「かねら」と読まれることが多い。関白左大臣・一条経嗣の六男。官位は従一位・摂政、関白、太政大臣、准三宮。一条家8代当主。桃華叟、三関老人、後成恩寺などと称した。名の兼良は「かねよし」であるが、「かねら」とも呼ばれる。
室町時代前期から後期にかけての公卿・古典学者。名は一般には「かねら」と読まれることが多い。関白左大臣・一条経嗣の六男。官位は従一位・摂政、関白、太政大臣、准三宮。一条家8代当主。桃華叟、三関老人、後成恩寺などと称した。名の兼良は「かねよし」であるが、「かねら」とも呼ばれる。
一条教房
一条 教房(いちじょう のりふさ)
室町時代後期から戦国時代の公卿(関白)で、
土佐一条氏の祖。一条兼良の長男。
室町時代後期から戦国時代の公卿(関白)で、
土佐一条氏の祖。一条兼良の長男。
一条内政
一条 内政(いちじょう ただまさ)
安土桃山時代の大名・公家。土佐一条氏第6代当主。権中納言・一条兼定の嫡男。
生涯
一条兼定の嫡男として土佐国幡多郡中村に生まれる。名の「内」は宗家の一条内基(うちもと)からの偏諱とされる。ただし「内」の読みは異なる。
天正元年(1573年)9月、長宗我部元親に擁立されて父・兼定を追放して家督を継ぎ土佐国司となる。長岡郡大津城に移り、大津御所と称された。天正2年12月(1575年1月)従五位上・左近衛少将に叙任され、天正5年(1577年)従四位下・左近衛中将に至る。傀儡当主といわれるが、元親の娘を娶っていたためかある程度の領国経営を行い、弱体化した土佐一条家領の立て直しを図った。
『信長公記』天正8年6月26日条に明智光秀を介して織田信長に献上した長宗我部元親のことを「土佐国捕佐せしめ候長宗我部土佐守」と表現しているが、これは信長の織田政権が一条内政を土佐国主と認識していた、もしくは意図的に国主と認定することで陪臣である長宗我部元親の土佐支配を否認して信長ー内政ー元親の秩序に服従するように要求したと解する秋澤繁の説がある。
ところが天正9年(1581年)2月に、長宗我部氏家臣の波川清宗の謀叛に加わった嫌疑で伊予法華津に追放。同国の法華津氏や豊後大友氏に援助を求めるが、その地で病死したとも、元親によって毒殺されたともいう。あるいは天正8年(1580年)5月に伊予国邊浦に放たれて殺害されたともされる。前述の秋澤説では長宗我部側からすれば信長が認めた土佐国主・一条内政の追放によって、元親は織田政権への服属拒否の姿勢を示し、両者の関係は断絶・交戦状態に入ったと解している。
続きを読む...
安土桃山時代の大名・公家。土佐一条氏第6代当主。権中納言・一条兼定の嫡男。
生涯
一条兼定の嫡男として土佐国幡多郡中村に生まれる。名の「内」は宗家の一条内基(うちもと)からの偏諱とされる。ただし「内」の読みは異なる。
天正元年(1573年)9月、長宗我部元親に擁立されて父・兼定を追放して家督を継ぎ土佐国司となる。長岡郡大津城に移り、大津御所と称された。天正2年12月(1575年1月)従五位上・左近衛少将に叙任され、天正5年(1577年)従四位下・左近衛中将に至る。傀儡当主といわれるが、元親の娘を娶っていたためかある程度の領国経営を行い、弱体化した土佐一条家領の立て直しを図った。
『信長公記』天正8年6月26日条に明智光秀を介して織田信長に献上した長宗我部元親のことを「土佐国捕佐せしめ候長宗我部土佐守」と表現しているが、これは信長の織田政権が一条内政を土佐国主と認識していた、もしくは意図的に国主と認定することで陪臣である長宗我部元親の土佐支配を否認して信長ー内政ー元親の秩序に服従するように要求したと解する秋澤繁の説がある。
ところが天正9年(1581年)2月に、長宗我部氏家臣の波川清宗の謀叛に加わった嫌疑で伊予法華津に追放。同国の法華津氏や豊後大友氏に援助を求めるが、その地で病死したとも、元親によって毒殺されたともいう。あるいは天正8年(1580年)5月に伊予国邊浦に放たれて殺害されたともされる。前述の秋澤説では長宗我部側からすれば信長が認めた土佐国主・一条内政の追放によって、元親は織田政権への服属拒否の姿勢を示し、両者の関係は断絶・交戦状態に入ったと解している。
続きを読む...
国司
国司(こくし)
昔、朝廷から諸国に赴任させた地方官。
国司(こくし、くにのつかさ)は、古代から中世の日本で、地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された官吏で、四等官である守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)たちを指す。守の唐名は刺史、太守など。中央では中級貴族に位置する。
郡の官吏(郡司)は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので(詳細は古代日本の地方官制を参照)、中央からの支配のかなめは赴任した国司たちにあった。任期は6年(のちに4年)であった。国司たちは国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、管内では絶大な権限を持った。
沿革
『日本書紀』には、大化の改新時の改新の詔において、穂積咋が東国国司に任じられるなど、国司を置いたことが記録されている。このとき、全国一律に国司が設置されたとは考えられておらず、また当初は国宰(くにのみこともち)という呼称が用いられたと言われており、国宰の上には数ヶ国を統括する大宰(おほ みこともち)が設置されたという(「大宰府」の語はその名残だと言われている)。その後7世紀末までに令制国の制度が確立し、それに伴って国司が全国的に配置されるようになったとされている。
8世紀初頭の大宝元年(701年)に制定された大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織である国郡里制に編成され、地方分権的な律令制が布かれることとなった。律令制において、国司は非常に重要な位置に置かれた。律令制を根幹的に支えた班田収授制は、戸籍の作成、田地の班給、租庸調の収取などから構成されていたが、これらはいずれも国司の職務であった。このように、律令制の理念を日本全国に貫徹することが国司に求められていたのである。
国司は中央の官人が任命されて家族を連れて任国に赴くことが認められていた。また、公務の都合などで在任中もたびたび上京しており、在任中ずっと帰京できなかった訳ではなかった[1]。
国司は通常は国府に設けられた国衙の中にある国庁で政務を行っているが、郡司の業務監査や農民への勧農などの業務を果たすために責任者である守が毎年1回国内の各郡を視察する義務があった。これを部内巡行という[2]。
平安時代の天長3年(826年)からは親王任国の制度が始まった。桓武天皇や平城天皇、嵯峨天皇は多くの皇子・皇女に恵まれたため充てるべき官職が不足し、親王の官職として親王任国の国司が充てられ、親王任国の国司筆頭官である守には必ず親王が補任されるようになった。親王任国の守となった親王は太守と称し、任国へ赴任しない遥任だったため、実務上の最高位は次官の介であった。
また平安時代になると、朝廷は地方統治の方法を改め、国司には一定の租税納入を果たすことが主要任務とされ、従前の律令制的な人民統治は求められなくなっていった。それは、律令制的な統治方法によらなくとも、一定の租税を徴収することが可能になったからである。9世紀〜10世紀頃には田堵と呼ばれる富豪農民が登場し、時を同じくして、国衙(国司の役所)が支配していた公田が、名田という単位に再編された。国司は、田堵に名田を経営させ、名田からの租税納付を請け負わせることで、一定の租税額を確保するようになった(これを負名という)。律令制下では、人民一人ひとりに租税が課せられていたため、人民の個別支配が必要とされていたが、10世紀ごろになると、上記のように名田、すなわち土地を対象に租税賦課する体制(名体制(みょうたいせい))が確立したのである。
一定の租税収入が確保されると、任国へ赴任しない遥任国司が多数現れるようになった。そして国司(守、介、掾、目)の中の実際に現地赴任する最高責任者を受領と呼ぶようになった。王朝国家体制への転換の中で、受領は一定額の租税の国庫納付を果たしさえすれば、朝廷の制限を受けることなく、それ以上の収入を私的に獲得・蓄積することができるようになった。
平安時代中期以降は開発領主による墾田開発が盛んになり、彼らは国衙から田地の私有が認められたが、その権利は危ういものであった。そこで彼らはその土地を荘園公領制により国司に任命された受領層である中級貴族に寄進することとなる。また、受領層の中級貴族は、私的に蓄積した富を摂関家などの有力貴族へ貢納することで生き残りを図り、国司に任命されることは富の蓄積へ直結したため、中級貴族は競って国司への任命を望み、重任を望んだ。『枕草子』には除目の日の悲喜を描いている[3]。平安中期以降、知行国という制度ができた。これは皇族や大貴族に一国を指定して国司推薦権を与えるもので、大貴族は親族や家来を国司に任命させて当国から莫大な収益を得た。
新しく国司に任ぜられる候補としては、蔵人、式部丞、民部丞、外記、検非違使などが巡爵によって従五位に叙せられたものから選ばれる[4]ほか、成功、院宮分国制などもあった。
国司の選任に当たっては、その国に住み所領を持つ者は、癒着を防止するという観点から任命を避けるという慣例があった。寛弘3年(1006年)1月28日の除目において、右大臣藤原顕光が伊勢守に平維衡を推挙したが、藤原道長が「維衡はかつて伊勢国で事件を起こしたものである」ことを理由に反対している[5]。この「事件」とは、かつて維衡が伊勢において平致頼と合戦を起こしたことである[6]。なお道長は8年後の長和3年2月の除目で、清和源氏である源頼親を摂津守に推挙するという矛盾した行動をとっている[7]。
鎌倉時代にも国司は存続したが、鎌倉幕府によって各地に配置された地頭が積極的に荘園、そして国司が管理していた国衙領へ侵出していった。当然、国司はこれに抵抗したが、地頭は国衙領へ侵出することで、徐々に国司の支配権を奪っていった。
室町時代になると、守護に大幅な権限、例えば半済給付権、使節遵行権などが付与された。これらの権限は、国司が管理する国衙領においても強力な効力を発揮し、その結果、国司の権限が大幅に守護へ移ることとなった。
こうして国司は名目だけの官職となり、実体的な支配は守護(守護大名)が執行するようになった。ここに至り、国司は単なる名誉職となり、被官される人物の実効支配地に関係なく任命された。戦国時代の武将の中には国司を自称、あるいは僭称する者も多かった(百官名)。政治の実権が幕府等の武家にあるうちは、単なる名誉職に過ぎなかった国司であったが、下克上が頻発した戦国時代では守護や守護代等の幕府役職者以外の出自の大名が、自国領土支配もしくは他国侵攻の正当性を主張するために任官を求める事が増加した。この時代では国司職を求めて戦国大名が朝廷へ盛んに献金などを行った。これは、天皇の地位が再認識される契機ともなった[8]。また、一部の戦国大名(大内義隆の周防介・伊予介、織田信秀・今川義元・徳川家康の三河守など)は名目的な国司職ではなく実質的な目的を持って申請を行っている[9]。
江戸幕府成立以降は、大名や旗本、一部の上級陪臣が幕府の許可を得た上で、家格に応じて国司名を称することが行われた(武家官位)。しかしこれらの「名乗り」は名目上のものであったため、同時期に複数の人物が同じ国司名を名乗ることも多かった[10]。ただし、国持大名が自分の領国の国司を名乗るのは一種の特権とされており、小倉藩から熊本藩へ加増転封されて肥後国主となった細川忠利は息子光尚の元服時に「肥後守」を名乗れるよう運動している[11]。
明治維新後、律令制度の廃止とともに国司は廃止された。
昔、朝廷から諸国に赴任させた地方官。
国司(こくし、くにのつかさ)は、古代から中世の日本で、地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された官吏で、四等官である守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)たちを指す。守の唐名は刺史、太守など。中央では中級貴族に位置する。
郡の官吏(郡司)は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので(詳細は古代日本の地方官制を参照)、中央からの支配のかなめは赴任した国司たちにあった。任期は6年(のちに4年)であった。国司たちは国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、管内では絶大な権限を持った。
沿革
『日本書紀』には、大化の改新時の改新の詔において、穂積咋が東国国司に任じられるなど、国司を置いたことが記録されている。このとき、全国一律に国司が設置されたとは考えられておらず、また当初は国宰(くにのみこともち)という呼称が用いられたと言われており、国宰の上には数ヶ国を統括する大宰(おほ みこともち)が設置されたという(「大宰府」の語はその名残だと言われている)。その後7世紀末までに令制国の制度が確立し、それに伴って国司が全国的に配置されるようになったとされている。
8世紀初頭の大宝元年(701年)に制定された大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織である国郡里制に編成され、地方分権的な律令制が布かれることとなった。律令制において、国司は非常に重要な位置に置かれた。律令制を根幹的に支えた班田収授制は、戸籍の作成、田地の班給、租庸調の収取などから構成されていたが、これらはいずれも国司の職務であった。このように、律令制の理念を日本全国に貫徹することが国司に求められていたのである。
国司は中央の官人が任命されて家族を連れて任国に赴くことが認められていた。また、公務の都合などで在任中もたびたび上京しており、在任中ずっと帰京できなかった訳ではなかった[1]。
国司は通常は国府に設けられた国衙の中にある国庁で政務を行っているが、郡司の業務監査や農民への勧農などの業務を果たすために責任者である守が毎年1回国内の各郡を視察する義務があった。これを部内巡行という[2]。
平安時代の天長3年(826年)からは親王任国の制度が始まった。桓武天皇や平城天皇、嵯峨天皇は多くの皇子・皇女に恵まれたため充てるべき官職が不足し、親王の官職として親王任国の国司が充てられ、親王任国の国司筆頭官である守には必ず親王が補任されるようになった。親王任国の守となった親王は太守と称し、任国へ赴任しない遥任だったため、実務上の最高位は次官の介であった。
また平安時代になると、朝廷は地方統治の方法を改め、国司には一定の租税納入を果たすことが主要任務とされ、従前の律令制的な人民統治は求められなくなっていった。それは、律令制的な統治方法によらなくとも、一定の租税を徴収することが可能になったからである。9世紀〜10世紀頃には田堵と呼ばれる富豪農民が登場し、時を同じくして、国衙(国司の役所)が支配していた公田が、名田という単位に再編された。国司は、田堵に名田を経営させ、名田からの租税納付を請け負わせることで、一定の租税額を確保するようになった(これを負名という)。律令制下では、人民一人ひとりに租税が課せられていたため、人民の個別支配が必要とされていたが、10世紀ごろになると、上記のように名田、すなわち土地を対象に租税賦課する体制(名体制(みょうたいせい))が確立したのである。
一定の租税収入が確保されると、任国へ赴任しない遥任国司が多数現れるようになった。そして国司(守、介、掾、目)の中の実際に現地赴任する最高責任者を受領と呼ぶようになった。王朝国家体制への転換の中で、受領は一定額の租税の国庫納付を果たしさえすれば、朝廷の制限を受けることなく、それ以上の収入を私的に獲得・蓄積することができるようになった。
平安時代中期以降は開発領主による墾田開発が盛んになり、彼らは国衙から田地の私有が認められたが、その権利は危ういものであった。そこで彼らはその土地を荘園公領制により国司に任命された受領層である中級貴族に寄進することとなる。また、受領層の中級貴族は、私的に蓄積した富を摂関家などの有力貴族へ貢納することで生き残りを図り、国司に任命されることは富の蓄積へ直結したため、中級貴族は競って国司への任命を望み、重任を望んだ。『枕草子』には除目の日の悲喜を描いている[3]。平安中期以降、知行国という制度ができた。これは皇族や大貴族に一国を指定して国司推薦権を与えるもので、大貴族は親族や家来を国司に任命させて当国から莫大な収益を得た。
新しく国司に任ぜられる候補としては、蔵人、式部丞、民部丞、外記、検非違使などが巡爵によって従五位に叙せられたものから選ばれる[4]ほか、成功、院宮分国制などもあった。
国司の選任に当たっては、その国に住み所領を持つ者は、癒着を防止するという観点から任命を避けるという慣例があった。寛弘3年(1006年)1月28日の除目において、右大臣藤原顕光が伊勢守に平維衡を推挙したが、藤原道長が「維衡はかつて伊勢国で事件を起こしたものである」ことを理由に反対している[5]。この「事件」とは、かつて維衡が伊勢において平致頼と合戦を起こしたことである[6]。なお道長は8年後の長和3年2月の除目で、清和源氏である源頼親を摂津守に推挙するという矛盾した行動をとっている[7]。
鎌倉時代にも国司は存続したが、鎌倉幕府によって各地に配置された地頭が積極的に荘園、そして国司が管理していた国衙領へ侵出していった。当然、国司はこれに抵抗したが、地頭は国衙領へ侵出することで、徐々に国司の支配権を奪っていった。
室町時代になると、守護に大幅な権限、例えば半済給付権、使節遵行権などが付与された。これらの権限は、国司が管理する国衙領においても強力な効力を発揮し、その結果、国司の権限が大幅に守護へ移ることとなった。
こうして国司は名目だけの官職となり、実体的な支配は守護(守護大名)が執行するようになった。ここに至り、国司は単なる名誉職となり、被官される人物の実効支配地に関係なく任命された。戦国時代の武将の中には国司を自称、あるいは僭称する者も多かった(百官名)。政治の実権が幕府等の武家にあるうちは、単なる名誉職に過ぎなかった国司であったが、下克上が頻発した戦国時代では守護や守護代等の幕府役職者以外の出自の大名が、自国領土支配もしくは他国侵攻の正当性を主張するために任官を求める事が増加した。この時代では国司職を求めて戦国大名が朝廷へ盛んに献金などを行った。これは、天皇の地位が再認識される契機ともなった[8]。また、一部の戦国大名(大内義隆の周防介・伊予介、織田信秀・今川義元・徳川家康の三河守など)は名目的な国司職ではなく実質的な目的を持って申請を行っている[9]。
江戸幕府成立以降は、大名や旗本、一部の上級陪臣が幕府の許可を得た上で、家格に応じて国司名を称することが行われた(武家官位)。しかしこれらの「名乗り」は名目上のものであったため、同時期に複数の人物が同じ国司名を名乗ることも多かった[10]。ただし、国持大名が自分の領国の国司を名乗るのは一種の特権とされており、小倉藩から熊本藩へ加増転封されて肥後国主となった細川忠利は息子光尚の元服時に「肥後守」を名乗れるよう運動している[11]。
明治維新後、律令制度の廃止とともに国司は廃止された。
安並和泉守
安並和泉守(あなみ いずみのかみ) 生没年不詳
土佐・一条氏家老。遊興に耽る当主兼定を他の家臣と共に豊後へ追放するが、その後専横な振る舞いが目立ち、これに反発した国人衆の攻撃をうけて奮戦するも討たれた。
土佐・一条氏家老。遊興に耽る当主兼定を他の家臣と共に豊後へ追放するが、その後専横な振る舞いが目立ち、これに反発した国人衆の攻撃をうけて奮戦するも討たれた。
加久見左衛門
加久見 左衛門(かぐみ さえもん)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。土佐一条氏の家臣。実名は不明。土佐国幡多郡加久見城主。
時代
戦国時代 - 安土桃山時代
生誕
不明
死没
不明
主君
一条兼定
氏族
加久見氏
出自
加久見氏は古くから幡多郡を根拠としていた国人。土佐一条氏の祖・一条教房が幡多荘に下った際、当時の当主・加久見宗孝はこれを迎え入れた。宗孝はその功労によって応仁2年(1468年)12月に一条家家司がしばしば任じられていた土佐守に補任され、近侍していた娘は、教房に愛されて一条房家を生むなど、一条氏傘下の国人領主の中でも特別な地位を占めていたとされる。
略歴
天正元年(1573年)9月に一条兼定を隠居させ兼定の子・内政を擁立し、実権を握った羽生道成・為松若狭守・安並和泉守ら家老に反感を抱いていた大岐左京進、大塚八木右衛門、江口玄蕃、橋本和泉守らと挙兵、中村を襲撃し家老らを討伐した。しかし、この事が敵対する長宗我部元親の介入を招き、結果的に土佐一条氏の衰亡を早める結果となった。
時代
戦国時代 - 安土桃山時代
生誕
不明
死没
不明
主君
一条兼定
氏族
加久見氏
出自
加久見氏は古くから幡多郡を根拠としていた国人。土佐一条氏の祖・一条教房が幡多荘に下った際、当時の当主・加久見宗孝はこれを迎え入れた。宗孝はその功労によって応仁2年(1468年)12月に一条家家司がしばしば任じられていた土佐守に補任され、近侍していた娘は、教房に愛されて一条房家を生むなど、一条氏傘下の国人領主の中でも特別な地位を占めていたとされる。
略歴
天正元年(1573年)9月に一条兼定を隠居させ兼定の子・内政を擁立し、実権を握った羽生道成・為松若狭守・安並和泉守ら家老に反感を抱いていた大岐左京進、大塚八木右衛門、江口玄蕃、橋本和泉守らと挙兵、中村を襲撃し家老らを討伐した。しかし、この事が敵対する長宗我部元親の介入を招き、結果的に土佐一条氏の衰亡を早める結果となった。
藤原氏
藤原氏(ふじわらうじ)
日本の氏族のひとつ。
姓は朝臣。略称は藤氏(とうし)。

家紋
下がり藤(代表的な家紋)
各、藤原氏によって異なる。
氏姓
藤原朝臣
始祖
天児屋命
出自
中臣氏
氏祖
藤原鎌足
種別
神別(天神)
本貫
大和国高市郡藤原
著名な人物
藤原氏の人物一覧参照
後裔
藤原南家
藤原北家
藤原式家
藤原京家
奥州藤原氏
飛鳥時代の藤原鎌足を祖とする神別氏族で、多くの公家を輩出したほか、日本各地に支流がある。1200年以上もの間、廷臣の一大勢力であった。
飛鳥時代の藤原鎌足を祖とする神別氏族で、多くの公家を輩出したほか、日本各地に支流がある。1200年以上もの間、廷臣の一大勢力であった。
概要
姓の代表的なものの一つとして源氏・平氏・橘氏とともに「源平藤橘」(四姓)と総称され、その筆頭名門氏族である。
中臣鎌足が大化の改新の功により天智天皇に賜った「藤原」の姓が、子の藤原不比等の代に認められたのに始まる。鎌足が中臣氏の出身であるため、祖は中臣氏と同じく天児屋命と伝える。
奈良時代に南家・北家・式家・京家の四家に分かれ、平安時代には北家が皇室と姻戚関係を結んで摂関政治を行った。藤原氏の一族は、奈良時代から平安時代までは本姓の「藤原」を称したが、鎌倉時代以降は姓の藤原ではなく、「近衛」「鷹司」「九条」「二条」「一条」などの苗字に相当する家名を名のり、公式な文書以外では「藤原」とは名乗らなかった。これらをあわせると特に朝廷における比率は圧倒的であり、地方に散った後裔などもふくめ、日本においては皇室(およびその流れを汲む源平など)に次いで大きな広がりと歴史を持つ家系である。江戸時代の朝廷において大臣就任の資格を持つ上位公卿17家系(摂家、清華家、大臣家)のうち14家系が藤原家、残り3家系が源氏であり、徳川をはじめとした主要武家の多くも源平や藤原流を称していることを併せると、皇統と藤原家の二つだけの血流が支配階級をほぼ独占するという世界でも稀な状態であった。
出自
藤原氏の祖である中臣鎌足は、中大兄皇子(天智天皇)とともに乙巳の変から大化の改新に至る諸改革に携わった。その後功績を称えられ、死の直前に天智天皇から藤原朝臣姓を与えられたとされる。藤原の名は鎌足の生地・大和国高市郡藤原(のちの藤原京地帯、現 橿原市)にちなむ[1]。通説では、鎌足の子である不比等がその姓を引き継ぎ、以後不比等の流が藤原朝臣と認められたとされる。
他方、この時に与えられた藤原の姓は鎌足一代のものであり、後に改めて鎌足の遺族に藤原朝臣の姓が与えられたとする説[2]もある。この見解は、鎌足の死後中臣氏を率いた右大臣・中臣金が壬申の乱で大友皇子(弘文天皇)方について敗北し処刑されたため、乱とは無関係の鎌足流も一時衰亡の危機を迎えたことを一因とする。乱平定ののち、天武天皇13年(684年)に八色の姓が定められた際には、朝臣を与えられた52氏の中に「藤原」の姓は登場せず、鎌足の嫡男である不比等を含めた鎌足の一族は「中臣連(後に朝臣)」と名乗っていたとする。そして『日本書紀』に鎌足没後最初に「藤原」が登場する翌天武天皇14年(685年)9月以前に、鎌足の遺族に対してあらためて「藤原朝臣」が与えられその範囲が定められた、とするものである。
いずれにしても、当時不比等がまだ若かったこともあって不比等以外の成員にも藤原朝臣が与えられ、鎌足の一族であった中臣大嶋や中臣意美麻呂(鎌足の娘婿でもある)が、不比等が成長するまでの中継ぎとして暫定的に「氏上」(うじのかみ)に就いていたとみられている[2]。
のちに不比等が成長して頭角を現すと、藤原氏が太政官を、中臣氏が神祇官を領掌する体制とするため、文武天皇2年(698年)8月鎌足の嫡男である不比等の家系以外は元の「中臣」姓に戻された。
藤原氏分離後の中臣氏
中臣意美麻呂は中臣姓に復帰後に不比等の推薦で中納言となり、その七男の清麻呂は右大臣まで昇った。そのため、以後はこの子孫が中臣氏の嫡流とされて特に「大中臣朝臣」と称されるようになった。平安時代以降になると他の中臣氏も大中臣氏を名乗るようになるが、清麻呂の系統が嫡流であることは変わらず、藤波家として堂上公家に列する。
日本の氏族のひとつ。
姓は朝臣。略称は藤氏(とうし)。

家紋
下がり藤(代表的な家紋)
各、藤原氏によって異なる。
氏姓
藤原朝臣
始祖
天児屋命
出自
中臣氏
氏祖
藤原鎌足
種別
神別(天神)
本貫
大和国高市郡藤原
著名な人物
藤原氏の人物一覧参照
後裔
藤原南家
藤原北家
藤原式家
藤原京家
奥州藤原氏
飛鳥時代の藤原鎌足を祖とする神別氏族で、多くの公家を輩出したほか、日本各地に支流がある。1200年以上もの間、廷臣の一大勢力であった。
飛鳥時代の藤原鎌足を祖とする神別氏族で、多くの公家を輩出したほか、日本各地に支流がある。1200年以上もの間、廷臣の一大勢力であった。
概要
姓の代表的なものの一つとして源氏・平氏・橘氏とともに「源平藤橘」(四姓)と総称され、その筆頭名門氏族である。
中臣鎌足が大化の改新の功により天智天皇に賜った「藤原」の姓が、子の藤原不比等の代に認められたのに始まる。鎌足が中臣氏の出身であるため、祖は中臣氏と同じく天児屋命と伝える。
奈良時代に南家・北家・式家・京家の四家に分かれ、平安時代には北家が皇室と姻戚関係を結んで摂関政治を行った。藤原氏の一族は、奈良時代から平安時代までは本姓の「藤原」を称したが、鎌倉時代以降は姓の藤原ではなく、「近衛」「鷹司」「九条」「二条」「一条」などの苗字に相当する家名を名のり、公式な文書以外では「藤原」とは名乗らなかった。これらをあわせると特に朝廷における比率は圧倒的であり、地方に散った後裔などもふくめ、日本においては皇室(およびその流れを汲む源平など)に次いで大きな広がりと歴史を持つ家系である。江戸時代の朝廷において大臣就任の資格を持つ上位公卿17家系(摂家、清華家、大臣家)のうち14家系が藤原家、残り3家系が源氏であり、徳川をはじめとした主要武家の多くも源平や藤原流を称していることを併せると、皇統と藤原家の二つだけの血流が支配階級をほぼ独占するという世界でも稀な状態であった。
出自
藤原氏の祖である中臣鎌足は、中大兄皇子(天智天皇)とともに乙巳の変から大化の改新に至る諸改革に携わった。その後功績を称えられ、死の直前に天智天皇から藤原朝臣姓を与えられたとされる。藤原の名は鎌足の生地・大和国高市郡藤原(のちの藤原京地帯、現 橿原市)にちなむ[1]。通説では、鎌足の子である不比等がその姓を引き継ぎ、以後不比等の流が藤原朝臣と認められたとされる。
他方、この時に与えられた藤原の姓は鎌足一代のものであり、後に改めて鎌足の遺族に藤原朝臣の姓が与えられたとする説[2]もある。この見解は、鎌足の死後中臣氏を率いた右大臣・中臣金が壬申の乱で大友皇子(弘文天皇)方について敗北し処刑されたため、乱とは無関係の鎌足流も一時衰亡の危機を迎えたことを一因とする。乱平定ののち、天武天皇13年(684年)に八色の姓が定められた際には、朝臣を与えられた52氏の中に「藤原」の姓は登場せず、鎌足の嫡男である不比等を含めた鎌足の一族は「中臣連(後に朝臣)」と名乗っていたとする。そして『日本書紀』に鎌足没後最初に「藤原」が登場する翌天武天皇14年(685年)9月以前に、鎌足の遺族に対してあらためて「藤原朝臣」が与えられその範囲が定められた、とするものである。
いずれにしても、当時不比等がまだ若かったこともあって不比等以外の成員にも藤原朝臣が与えられ、鎌足の一族であった中臣大嶋や中臣意美麻呂(鎌足の娘婿でもある)が、不比等が成長するまでの中継ぎとして暫定的に「氏上」(うじのかみ)に就いていたとみられている[2]。
のちに不比等が成長して頭角を現すと、藤原氏が太政官を、中臣氏が神祇官を領掌する体制とするため、文武天皇2年(698年)8月鎌足の嫡男である不比等の家系以外は元の「中臣」姓に戻された。
藤原氏分離後の中臣氏
中臣意美麻呂は中臣姓に復帰後に不比等の推薦で中納言となり、その七男の清麻呂は右大臣まで昇った。そのため、以後はこの子孫が中臣氏の嫡流とされて特に「大中臣朝臣」と称されるようになった。平安時代以降になると他の中臣氏も大中臣氏を名乗るようになるが、清麻呂の系統が嫡流であることは変わらず、藤波家として堂上公家に列する。
2019年12月19日
片岡氏
片岡氏(かたおかし)
家紋

揚羽蝶/三つ巴
醍醐源氏/桓武平氏
片岡氏は土佐国高吾北地方を地盤とした、土佐の有力国人領主であった。その出自は、醍醐源氏、宇多源氏、あるいは桓武平氏とするなど諸説があり、『姓氏家系大辞典』では、醍醐源氏から出た系図を掲載し、古代壬生氏の末裔ではないかとしている。『片岡系譜』『片岡盛衰記』などによれば、上野国片岡郷を名字の地とし、室町時代に直綱が土佐へ下向したと伝えられるが、実際のところは不詳というしかない。
戦国時代における片岡氏に関していえば、諸社の棟札などから壬生姓で光の字を通字としていたことが知られる。すなわち、永禄元年(1558)、文禄四年(1595)にかけての棟札に、茂光・光綱・親光らの片岡氏の名が散見している。
片岡氏は法巌城を本拠として、最盛期には吾川・高岡両郡を支配し、仁淀川上流の別府山五名・大川五名・ 小川八名の山間部から、越知・黒岩・佐川の盆地を経て加茂・北地の平野部まで千町歩におよぶ広大な領地を有していた。
室町時代から戦国時代初めにかけての土佐は、安芸・本山・山田・長宗我部・大平・吉良・津野の七守護と国司一条氏らが割拠し、それに準じる存在として、波川・三宮・中村・米森・和田、そして片岡氏らが勢力を築いていた。片岡氏が勢力を拡大したのは、茂光の代で、茂光は国司一条氏から守護代格として高岡郡の監視を託された。
土佐の戦乱
戦国時代たけなわの十六世紀になると、七守護らは互いに戦いを繰り返し、永正五年(1508)長宗我部氏が吉良・大平連合軍に敗れて没落した。その後、長宗我部氏は遺児国親の活躍で勢力を挽回し、片岡茂光は国親に見込まれて妹を室とし、長宗我部氏の有力な味方となった。
その後、長宗我部氏は土佐国内の対抗勢力を次々と滅ぼし、または降すなどして土佐統一に邁進した。そして、国親のあとを継いだ元親の代になると、本山氏を滅ぼし、国司一条氏と対立するようになった。この間、片岡氏では茂光が死去し、嫡男の光綱が家督を継ぎ、長宗我部氏の有力武将として活躍した。光綱は父茂光に優る資質の持ち主で、長宗我部氏に属して片岡氏の勢力を拡大していった。
土佐の諸勢力を滅ぼし、国司一条氏まで討って土佐一国を統一した長宗我部元親は、四国統一に乗り出すのである。かくして、長宗我部軍の「一領具足」と呼ばれる軍団が四国を席巻することになる。そして元親は、伊予の河野氏、阿波の十河氏らと戦って、天正十年(1582)には四国をほぼ統一することに成功した。ところが、織田信長の死後、信長の事業を受け継いだ豊臣秀吉が長宗我部元親の前に立ちはだかったのである。
秀吉は元親に奪った土地を返すように迫ったが、元親はそれを拒否したため、ついに秀吉の遠征軍を迎え撃つことになった。秀吉は、弟の秀長をはじめ小早川隆景・毛利輝元・吉川元家らの諸将に命じ、天正十三年、四国攻めを開始した。秀吉軍は四国攻めのさきがけとして、まず長宗我部氏に通じる伊予金子城主金子備後守を攻撃させた。
相次ぐ当主の戦死
この金子の陣に長宗我部元親は片岡光綱らを大将とする援軍を送って、秀吉勢を迎え撃ったのである。戦いは激戦であったが、結果は金子勢は壊滅し片岡光綱も討死するという長宗我部勢の大敗となった。その後も秀吉軍の攻勢にさらされ、長宗我部元親は降伏し辛うじて土佐一国を安堵された。光綱の戦死したのちの片岡氏は、一族の台住民部が継いで片岡民部大夫光政を名乗った。のちに元親から一字をもらって親正と名乗ったともいわれる。
四国征伐を終えた秀吉は、天正十四年、九州征伐に着手し、長宗我部氏・十河氏らの四国勢に大友氏と協力して島津軍を討つように命じた。四国勢はただちに九州に渡海し、豊後の戸次川において島津軍と戦った。しかし、島津軍の巧妙な作戦に敗れ、長宗我部元親の嫡子信親をはじめ、十河存保らが討死し、片岡光政も奮戦の末に討死した。
世に「戸次川の戦い」と呼ばれる合戦で、片岡氏は前年の光綱の戦死、そして九州での光政の死によって大きく勢力を失墜し、ついには没落の運命となるのである。
いまに伝えられる各種片岡氏系図によると、光政の長男は久助といい、江戸時代に至って土佐藩主となった山内氏に仕え庄屋職についたという、また二男の熊之助は讃岐金毘羅宮の多聞院主の祖になったと伝えられている。さらに、片岡氏の庶流は、山内氏や山内氏家老深尾氏に仕えて、片岡氏旧領内の庄屋職などになって、土佐に片岡一族は繁衍したのである。
家紋

揚羽蝶/三つ巴
醍醐源氏/桓武平氏
片岡氏は土佐国高吾北地方を地盤とした、土佐の有力国人領主であった。その出自は、醍醐源氏、宇多源氏、あるいは桓武平氏とするなど諸説があり、『姓氏家系大辞典』では、醍醐源氏から出た系図を掲載し、古代壬生氏の末裔ではないかとしている。『片岡系譜』『片岡盛衰記』などによれば、上野国片岡郷を名字の地とし、室町時代に直綱が土佐へ下向したと伝えられるが、実際のところは不詳というしかない。
戦国時代における片岡氏に関していえば、諸社の棟札などから壬生姓で光の字を通字としていたことが知られる。すなわち、永禄元年(1558)、文禄四年(1595)にかけての棟札に、茂光・光綱・親光らの片岡氏の名が散見している。
片岡氏は法巌城を本拠として、最盛期には吾川・高岡両郡を支配し、仁淀川上流の別府山五名・大川五名・ 小川八名の山間部から、越知・黒岩・佐川の盆地を経て加茂・北地の平野部まで千町歩におよぶ広大な領地を有していた。
室町時代から戦国時代初めにかけての土佐は、安芸・本山・山田・長宗我部・大平・吉良・津野の七守護と国司一条氏らが割拠し、それに準じる存在として、波川・三宮・中村・米森・和田、そして片岡氏らが勢力を築いていた。片岡氏が勢力を拡大したのは、茂光の代で、茂光は国司一条氏から守護代格として高岡郡の監視を託された。
土佐の戦乱
戦国時代たけなわの十六世紀になると、七守護らは互いに戦いを繰り返し、永正五年(1508)長宗我部氏が吉良・大平連合軍に敗れて没落した。その後、長宗我部氏は遺児国親の活躍で勢力を挽回し、片岡茂光は国親に見込まれて妹を室とし、長宗我部氏の有力な味方となった。
その後、長宗我部氏は土佐国内の対抗勢力を次々と滅ぼし、または降すなどして土佐統一に邁進した。そして、国親のあとを継いだ元親の代になると、本山氏を滅ぼし、国司一条氏と対立するようになった。この間、片岡氏では茂光が死去し、嫡男の光綱が家督を継ぎ、長宗我部氏の有力武将として活躍した。光綱は父茂光に優る資質の持ち主で、長宗我部氏に属して片岡氏の勢力を拡大していった。
土佐の諸勢力を滅ぼし、国司一条氏まで討って土佐一国を統一した長宗我部元親は、四国統一に乗り出すのである。かくして、長宗我部軍の「一領具足」と呼ばれる軍団が四国を席巻することになる。そして元親は、伊予の河野氏、阿波の十河氏らと戦って、天正十年(1582)には四国をほぼ統一することに成功した。ところが、織田信長の死後、信長の事業を受け継いだ豊臣秀吉が長宗我部元親の前に立ちはだかったのである。
秀吉は元親に奪った土地を返すように迫ったが、元親はそれを拒否したため、ついに秀吉の遠征軍を迎え撃つことになった。秀吉は、弟の秀長をはじめ小早川隆景・毛利輝元・吉川元家らの諸将に命じ、天正十三年、四国攻めを開始した。秀吉軍は四国攻めのさきがけとして、まず長宗我部氏に通じる伊予金子城主金子備後守を攻撃させた。
相次ぐ当主の戦死
この金子の陣に長宗我部元親は片岡光綱らを大将とする援軍を送って、秀吉勢を迎え撃ったのである。戦いは激戦であったが、結果は金子勢は壊滅し片岡光綱も討死するという長宗我部勢の大敗となった。その後も秀吉軍の攻勢にさらされ、長宗我部元親は降伏し辛うじて土佐一国を安堵された。光綱の戦死したのちの片岡氏は、一族の台住民部が継いで片岡民部大夫光政を名乗った。のちに元親から一字をもらって親正と名乗ったともいわれる。
四国征伐を終えた秀吉は、天正十四年、九州征伐に着手し、長宗我部氏・十河氏らの四国勢に大友氏と協力して島津軍を討つように命じた。四国勢はただちに九州に渡海し、豊後の戸次川において島津軍と戦った。しかし、島津軍の巧妙な作戦に敗れ、長宗我部元親の嫡子信親をはじめ、十河存保らが討死し、片岡光政も奮戦の末に討死した。
世に「戸次川の戦い」と呼ばれる合戦で、片岡氏は前年の光綱の戦死、そして九州での光政の死によって大きく勢力を失墜し、ついには没落の運命となるのである。
いまに伝えられる各種片岡氏系図によると、光政の長男は久助といい、江戸時代に至って土佐藩主となった山内氏に仕え庄屋職についたという、また二男の熊之助は讃岐金毘羅宮の多聞院主の祖になったと伝えられている。さらに、片岡氏の庶流は、山内氏や山内氏家老深尾氏に仕えて、片岡氏旧領内の庄屋職などになって、土佐に片岡一族は繁衍したのである。
土佐一条氏
土佐一条氏(とさ いちじょうし)
日本の武家の一つ。本姓は藤原氏で、五摂家の一条家の分家。

家紋
いちじょうふじ
一条藤
概要
土佐国幡多郡を拠点とした戦国大名で、
五摂家の一条家が、応仁の乱を避けて中央から下向したことに始まる。
土着後も土佐国にありながら高い官位を有し、戦国時代の間、土佐国の主要七国人(「土佐七雄」)の盟主的地位にあった。次第に武家化し伊予国への外征も積極的に行うが、伸長した長宗我部氏の勢いに呑まれ、断絶した。
明治時代に入って一条家により土佐一条家の再興が行われ、一条家から分家して男爵が授けられている。
歴史
初代土佐一条氏は、1468年(応仁2年)に一条兼良の子で前関白の一条教房が、応仁の乱の混乱を避け、京都から所領であった土佐幡多荘(現在の四万十市中村)に下向したことに起源を有する。鎌倉時代末期から室町時代にかけて敷地氏・布氏・入野氏などが幡多荘の押領をもくろみ、更に戦乱による所務不振に悩まされることになり、その安定化を図る目的もあったと考えられる。教房は幡多郡を中心とした国人領主たちの支持を得ることに成功し、文明年間には拠点として「中村館」を置き、以後「中村御所」と称された。また、教房とともに公家や武士、職人なども幡多荘に下向するなど、中村繁栄の基礎を築いた。
戦国時代
2代 房家
土佐で誕生した教房の次男一条房家は京都に戻らずに幡多荘の在地領主となり、中村御所を拠点に土佐の中村に京都さながらの街を築き上げ、官位も正二位まで昇進した。房家の時代に土佐一条氏は管領細川氏(土佐守護を兼ねる)と土佐を二分する勢力[3]となり、公家としての権威を維持したまま同国に勢力をもつ大名として存在感を高めた。嫡男房冬の正室に伏見宮邦高親王の娘、側室には大内義興の娘を迎え、更に娘を伊予の西園寺公宣に嫁がせるなど、公武の有力者との婚姻を通じて土佐一条氏の安定を図っている。また、房家の次男一条房通は京都の一条家の婿養子となって関白に昇進している。
永正の錯乱(1507年(永正4年))により細川氏が中央に引き上げてその影響が消えると、土佐国は「土佐七雄」と呼ばれる七国人が割拠する状態となった。土佐一条氏はその上位に立ち、盟主的存在を担った。
初代 一条教房
二代 一条房家
三代 一条房冬
四代 一条房基
五代 一条兼定
六代 一条内政
俗に土佐一条氏と呼んでいる。
一条家は京都五摂家の名門として、政治的社会的に高い地位にあった。この一条氏が中世において土佐の幡多荘を領有していたのである。
応仁元年(1467)7月、京都を中心に起った応仁の乱は、その後11年の間合戦が続き、京都は一面の焼野が原となった。この戦乱で貴族といわれた公家も生活に窮して地方の荘園を目指して京都を去るものが多かった。前関白左大臣一条教房(房家の父)も乱が起るとその年8月25日京都の兵火を避けて、初め奈良の興福寺に身を寄せていた。興福寺の住職尋尊大僧正が教房の弟に当たる関係である。教房は、翌応仁2年9月6日奈良をたち、同25日泉州堺から土佐の豪族大平氏の船に便乗して、翌26日に神浦(安芸郡東洋町甲ノ浦)に着き、10月1日に神浦を出帆、翌2日大平氏の居城蓮池に近い高岡郡猪ノ尻(宇佐町井ノ尻)に着き、ここでも数日間滞在してから、幡多の本庄中村に来国されたと伝えられている。
教房一行が大平氏の知行船に乗船して来国されたのは、大平氏の女房が教房夫人の宣旨殿と縁者であったためである(『大乗院寺社雑事記』)といわれているが、『土佐物語』や『古城略史』には、長宗我部文兼の父元親が京都にいた頃、教房の祖父に仕えて厚い恩遇を得ていた。それで、文兼は京都の乱を聞き、今こそ父の恩に報ゆるときと、船を艤して卿を兵庫浦から土佐国甲浦に渡し、自分の居城長岡郡岡豊に迎えたとある。
また、一説には、下国の理由について、京の戦乱によって畿内や付近の荘園からの年貢が入らなくなって、苦しい一家の経済を少しでも豊かにするために、有名無実となっていた幡多庄を回復して、荘園としての実績を挙げようとした為であろうともいわれている。
下国の理由はともあれ、京の絢燗たる文化を携え伝え、公卿大名というより戦国武将として数代百余年を土佐に勢力を張り、多くの影響を及ぼしたのである。
中村に来国した教房は、荘園内の土豪を支配下に組織して基礎経営に専念したのである。中村の町作りを京都に模し、風景も鴨川、東山に見たてて御所を設営したり、更に、下田を対明貿易の中継地とし、商業貿易の拠点として利益を挙げ、朝廷へも珍品を献納したり、石山(大阪)本願寺造営に土佐木材を送るなど、財力獲得にも成功し、凡庸の公家育ちを脱したものがあったようである。しかし、父兼良より先に文明12年(1480)58歳で死去した。国人十余人は、この主人を慕って出家したとも伝えられている。中村市妙華寺谷(奥御前谷)に教房の墓がある。
さて、教房の第2子で中村生まれの房家を、初代として房冬、房基、兼定、内政の5代を俗に土佐一条氏と呼んでいる。
一条房家は、文明9年(1477)父教房の没する3年前に生まれた。母は幡多の武将加久見宗孝の娘である。
一条家の家督は京都の叔父冬良(教房の弟)が継ぎ、房家は奈良の大乗院の叔父尋尊の孫弟子として出家することに決められていた。しかし、父教房の死を契機に内訌が起き、房家7、8才の頃母と共に、中村御所から足摺岬金剛福寺へ移リ、更に、清水へ逃れたこともあったのである幼い房家を中村に置くことに危険を感じた為であろう。
それより10年が過ぎ、明応3年(1494)18才で出家をやめて元服し、正五位下、左近衛少将になり土佐国司に任ぜられた。これによって、土佐一条氏は房家をもって初代としている。教房の死後、その後を継ぐようになった背景には、国人土豪が、房家の在国を望んで、働き掛けた為だともいわれている。
房家は土佐中村で飛騨の姉小路、伊勢の北畠と並んで公卿三国司と称せられ、いわゆる公卿大名として戦国の世に臨んでいった。そしてよく土佐の豪族を抑えて治安を獲得し、その威令は隣国の南予にまで及んだのである。また、都風の文化を移すと共に、通商を盛んにして財政の裕福も計った。一条家の一門並びに家老は、
「御所一人と申すは一条殿をいう。幡多郡一万六千貫(約五万三千三百石)の主にて中村に在城なり。御一門というは東小路、西小路、入江、飛鳥井、白河なり。家老は土居、羽生、為松、安並の4人なり」。(『土佐物語』)このほかに一条殿衆と呼ばれる53人の家臣団がいた。宿毛には、一条家兵伏随身武者所判官二宮房資をニノ宮城に置いて、宿毛城番とした。房家の治世45年間が土佐一条氏の最も栄えたときであった。
房家は寛仁の心の持主であった。永正5年(1508)9月、長宗我部兼序が吾川郡北部の本山茂宗、同郡南部の弘岡の吉良、香美都の山田、高岡郡の大平等の連合軍に急襲され兼序は防ぎかねて自殺したが、この岡豊落城の際、兼序は一子千雄(王)丸を家臣に托して幡多郡中村御所に送リ、一条房家の保護を求めた。
房家は、これを庇護成長させ、10年の後、永正15年に元服させて長宗我部国親と名乗らせ、父の旧領岡豊城を取り返して国親に与えた。長宗我部家再興の恩人でもあったのである。ところが、この温情が土佐一条氏滅亡の因をつくるようになったのはあまりにも皮肉てある。
房家は、正二位権大納言にまで進み、天文8年(1539)11月13日63才で中村城で死去され、法名を藤林寺殿正二品東泉大居士といい、藤林寺に葬られた今も、藤林寺境内にこけむしたる卵塔の墓石二基と五輪塔一基があるが、中央が初代房家の墓で、左右はその縁者の墓であろう。
日本の武家の一つ。本姓は藤原氏で、五摂家の一条家の分家。

家紋
いちじょうふじ
一条藤
概要
土佐国幡多郡を拠点とした戦国大名で、
五摂家の一条家が、応仁の乱を避けて中央から下向したことに始まる。
土着後も土佐国にありながら高い官位を有し、戦国時代の間、土佐国の主要七国人(「土佐七雄」)の盟主的地位にあった。次第に武家化し伊予国への外征も積極的に行うが、伸長した長宗我部氏の勢いに呑まれ、断絶した。
明治時代に入って一条家により土佐一条家の再興が行われ、一条家から分家して男爵が授けられている。
歴史
初代土佐一条氏は、1468年(応仁2年)に一条兼良の子で前関白の一条教房が、応仁の乱の混乱を避け、京都から所領であった土佐幡多荘(現在の四万十市中村)に下向したことに起源を有する。鎌倉時代末期から室町時代にかけて敷地氏・布氏・入野氏などが幡多荘の押領をもくろみ、更に戦乱による所務不振に悩まされることになり、その安定化を図る目的もあったと考えられる。教房は幡多郡を中心とした国人領主たちの支持を得ることに成功し、文明年間には拠点として「中村館」を置き、以後「中村御所」と称された。また、教房とともに公家や武士、職人なども幡多荘に下向するなど、中村繁栄の基礎を築いた。
戦国時代
2代 房家
土佐で誕生した教房の次男一条房家は京都に戻らずに幡多荘の在地領主となり、中村御所を拠点に土佐の中村に京都さながらの街を築き上げ、官位も正二位まで昇進した。房家の時代に土佐一条氏は管領細川氏(土佐守護を兼ねる)と土佐を二分する勢力[3]となり、公家としての権威を維持したまま同国に勢力をもつ大名として存在感を高めた。嫡男房冬の正室に伏見宮邦高親王の娘、側室には大内義興の娘を迎え、更に娘を伊予の西園寺公宣に嫁がせるなど、公武の有力者との婚姻を通じて土佐一条氏の安定を図っている。また、房家の次男一条房通は京都の一条家の婿養子となって関白に昇進している。
永正の錯乱(1507年(永正4年))により細川氏が中央に引き上げてその影響が消えると、土佐国は「土佐七雄」と呼ばれる七国人が割拠する状態となった。土佐一条氏はその上位に立ち、盟主的存在を担った。
初代 一条教房
二代 一条房家
三代 一条房冬
四代 一条房基
五代 一条兼定
六代 一条内政
俗に土佐一条氏と呼んでいる。
一条家は京都五摂家の名門として、政治的社会的に高い地位にあった。この一条氏が中世において土佐の幡多荘を領有していたのである。
応仁元年(1467)7月、京都を中心に起った応仁の乱は、その後11年の間合戦が続き、京都は一面の焼野が原となった。この戦乱で貴族といわれた公家も生活に窮して地方の荘園を目指して京都を去るものが多かった。前関白左大臣一条教房(房家の父)も乱が起るとその年8月25日京都の兵火を避けて、初め奈良の興福寺に身を寄せていた。興福寺の住職尋尊大僧正が教房の弟に当たる関係である。教房は、翌応仁2年9月6日奈良をたち、同25日泉州堺から土佐の豪族大平氏の船に便乗して、翌26日に神浦(安芸郡東洋町甲ノ浦)に着き、10月1日に神浦を出帆、翌2日大平氏の居城蓮池に近い高岡郡猪ノ尻(宇佐町井ノ尻)に着き、ここでも数日間滞在してから、幡多の本庄中村に来国されたと伝えられている。
教房一行が大平氏の知行船に乗船して来国されたのは、大平氏の女房が教房夫人の宣旨殿と縁者であったためである(『大乗院寺社雑事記』)といわれているが、『土佐物語』や『古城略史』には、長宗我部文兼の父元親が京都にいた頃、教房の祖父に仕えて厚い恩遇を得ていた。それで、文兼は京都の乱を聞き、今こそ父の恩に報ゆるときと、船を艤して卿を兵庫浦から土佐国甲浦に渡し、自分の居城長岡郡岡豊に迎えたとある。
また、一説には、下国の理由について、京の戦乱によって畿内や付近の荘園からの年貢が入らなくなって、苦しい一家の経済を少しでも豊かにするために、有名無実となっていた幡多庄を回復して、荘園としての実績を挙げようとした為であろうともいわれている。
下国の理由はともあれ、京の絢燗たる文化を携え伝え、公卿大名というより戦国武将として数代百余年を土佐に勢力を張り、多くの影響を及ぼしたのである。
中村に来国した教房は、荘園内の土豪を支配下に組織して基礎経営に専念したのである。中村の町作りを京都に模し、風景も鴨川、東山に見たてて御所を設営したり、更に、下田を対明貿易の中継地とし、商業貿易の拠点として利益を挙げ、朝廷へも珍品を献納したり、石山(大阪)本願寺造営に土佐木材を送るなど、財力獲得にも成功し、凡庸の公家育ちを脱したものがあったようである。しかし、父兼良より先に文明12年(1480)58歳で死去した。国人十余人は、この主人を慕って出家したとも伝えられている。中村市妙華寺谷(奥御前谷)に教房の墓がある。
さて、教房の第2子で中村生まれの房家を、初代として房冬、房基、兼定、内政の5代を俗に土佐一条氏と呼んでいる。
一条房家は、文明9年(1477)父教房の没する3年前に生まれた。母は幡多の武将加久見宗孝の娘である。
一条家の家督は京都の叔父冬良(教房の弟)が継ぎ、房家は奈良の大乗院の叔父尋尊の孫弟子として出家することに決められていた。しかし、父教房の死を契機に内訌が起き、房家7、8才の頃母と共に、中村御所から足摺岬金剛福寺へ移リ、更に、清水へ逃れたこともあったのである幼い房家を中村に置くことに危険を感じた為であろう。
それより10年が過ぎ、明応3年(1494)18才で出家をやめて元服し、正五位下、左近衛少将になり土佐国司に任ぜられた。これによって、土佐一条氏は房家をもって初代としている。教房の死後、その後を継ぐようになった背景には、国人土豪が、房家の在国を望んで、働き掛けた為だともいわれている。
房家は土佐中村で飛騨の姉小路、伊勢の北畠と並んで公卿三国司と称せられ、いわゆる公卿大名として戦国の世に臨んでいった。そしてよく土佐の豪族を抑えて治安を獲得し、その威令は隣国の南予にまで及んだのである。また、都風の文化を移すと共に、通商を盛んにして財政の裕福も計った。一条家の一門並びに家老は、
「御所一人と申すは一条殿をいう。幡多郡一万六千貫(約五万三千三百石)の主にて中村に在城なり。御一門というは東小路、西小路、入江、飛鳥井、白河なり。家老は土居、羽生、為松、安並の4人なり」。(『土佐物語』)このほかに一条殿衆と呼ばれる53人の家臣団がいた。宿毛には、一条家兵伏随身武者所判官二宮房資をニノ宮城に置いて、宿毛城番とした。房家の治世45年間が土佐一条氏の最も栄えたときであった。
房家は寛仁の心の持主であった。永正5年(1508)9月、長宗我部兼序が吾川郡北部の本山茂宗、同郡南部の弘岡の吉良、香美都の山田、高岡郡の大平等の連合軍に急襲され兼序は防ぎかねて自殺したが、この岡豊落城の際、兼序は一子千雄(王)丸を家臣に托して幡多郡中村御所に送リ、一条房家の保護を求めた。
房家は、これを庇護成長させ、10年の後、永正15年に元服させて長宗我部国親と名乗らせ、父の旧領岡豊城を取り返して国親に与えた。長宗我部家再興の恩人でもあったのである。ところが、この温情が土佐一条氏滅亡の因をつくるようになったのはあまりにも皮肉てある。
房家は、正二位権大納言にまで進み、天文8年(1539)11月13日63才で中村城で死去され、法名を藤林寺殿正二品東泉大居士といい、藤林寺に葬られた今も、藤林寺境内にこけむしたる卵塔の墓石二基と五輪塔一基があるが、中央が初代房家の墓で、左右はその縁者の墓であろう。