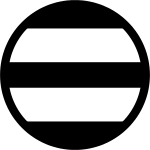җVӢKӢLҺ–ӮМ“ҠҚeӮрҚsӮӨӮұӮЖӮЕҒA”с•\ҺҰӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЕӮ·ҒB
ҚLҚҗ
җVӢKӢLҺ–ӮМ“ҠҚeӮрҚsӮӨӮұӮЖӮЕҒA”с•\ҺҰӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЕӮ·ҒB
posted by fanblog
2020”N01ҢҺ19“ъ
Ң№ҺҒ
Ң№ҺҒҒiӮЭӮИӮаӮЖӮӨӮ¶ҒAӮ°ӮсӮ¶Ғj
“ъ–{ӮМҺҒ‘°ӮМӮРӮЖӮВҒBҗ©ӮН’©җbҒB

үЖ–дҒ@Қщ—і’_ӮіӮіӮиӮсӮЗӮӨ
Ғ@Ғ@Ғi‘г•\“IӮИүЖ–дҒj
ҠeҒAҢ№ҺҒӮЙӮжӮБӮДҲЩӮИӮйҒB
ҺҒҗ©
Ң№’©җb
ҺҒ‘c
“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨ
Ӣ{үЖӮМҸ”үӨ
Һн•К
Қc•К
’ҳ–јӮИҗl•Ё
‘әҸгҢ№ҺҒҒF
Ң№’Кҗe
–k”©җe–[
җҙҳaҢ№ҺҒҒF
Ң№—Ҡ’©
‘«—ҳ‘ёҺҒ
“ҝҗмүЖҚNҒiҺ©ҸМҒj
Ӯ»ӮМ‘јӮНҢ№ҺҒӮМҗl•ЁҲк——ӮрҺQҸЖ
Ңгеб
ҚөүгҢ№ҺҒ
‘әҸгҢ№ҺҒ
җҙҳaҢ№ҺҒ
үФҺRҢ№ҺҒ
үF‘ҪҢ№ҺҒ
җіҗe’¬Ң№ҺҒ
ӮИӮЗ
Ӯ»ӮМ‘јӮМҢ№ҺҒӮЙӮВӮўӮДӮНҒA“сҸ\Ҳк—¬ӮрҺQҸЖ
“ъ–{ӮЙӮЁӮўӮДҚc‘°ӮӘҗbүәӮМҗРӮЙҚ~ӮиӮйҒiҗbҗРҚ~үәҒjҚЫӮЙ–јҸжӮйҺҒӮМӮРӮЖӮВӮЕҒA‘Ҫҗ”ӮМ—¬”hӮӘӮ ӮйҒBҢ№ҺҒӮр“қӮЧӮйҢ№ҺҒ’·ҺТӮНҺә’¬Һһ‘гӮЬӮЕ‘әҸг“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ Ӯй‘әҸгҢ№ҺҒӮӘ“ЖҗиӮөҒAҢҡӢvҺө”NӮМҗӯ•ПӮЕҗЫҠЦүЖӮрүzӮҰӮйҢ —НӮрҺиӮЙӮөӮҪҢ№’КҗeӮвҒAҢг‘зҢн“VҚc‘жҲкӮМ‘ӨӢЯӮЖӮөӮД“м’©ӮрҺwҠцӮөӮҪ–k”©җe–[ӮИӮЗӮӘӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҗҙҳa“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮйҗҙҳaҢ№ҺҒӮН•җүЖӮМ“Ҹ—АӮр‘ҪӮӯ”yҸoӮөҒAҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҢ№—Ҡ’©ӮвҺә’¬–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪ‘«—ҳ‘ёҺҒӮИӮЗӮӘӮўӮйҒBҗнҚ‘Һһ‘гӮМ•җҸ«Ҹј•ҪҢіҚNӮаҢг”јҗ¶ӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҺ©ҸМӮөӮД“ҝҗмүЖҚNӮЖ–јҸжӮиҒAҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҒB
ҠT—v
җ©ӮМ‘г•\“IӮИӮаӮМӮМҲкӮВӮЖӮөӮДҒA•ҪҺҒҒE“ЎҢҙҺҒҒEӢkҺҒӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢ№•Ҫ“ЎӢkҒvҒiҺlҗ©ҒjӮЖ‘ҚҸМӮіӮкӮДӮўӮйҒB
Қөүг“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҚөүгҢ№ҺҒӮвҗҙҳa“VҚcӮ©ӮзӮМҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҠЬӮЯҒA“сҸ\ҲкӮМ—¬”hҒi“сҸ\Ҳк—¬ҒjӮӘӮ ӮйӮЖӮіӮкӮДӮўӮй[’ҚҺЯ 1]ҒB’ҶӮЕӮаүЖҠiӮӘҚЕӮаҚӮӮўӮМӮН‘әҸгҢ№ҺҒӮЖӮіӮкҒAҺә’¬–Ӣ•{ӮМҗ¬—§ӮЬӮЕҢ№ҺҒ’·ҺТӮр—LӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA•ҪҲАҲИҚ~җbҗРҚ~үәӮӘ•p”ӯӮ·ӮйӮЖҢ№ҒE•ҪӮМ“сҗ©ӮОӮ©ӮиӮЙӮИӮйӮӘҒAҚЕӢЯӮМҢӨӢҶӮЕҒuҲкҗўүӨҒA“сҗўүӨӮӘҢ№ҒAҺOҗўҲИҚ~ӮӘ•ҪҒvӮҫӮБӮҪҺ–ӮӘ”»–ҫӮөӮДӮўӮйҒBҢ№җ©Ғi–{җ©ӮӘҢ№ҺҒҒjӮМүЖҢnӮНӮ»ӮкӮјӮк•КӮМ•cҺҡӮрҚҶӮөӮДӮўӮйӮҪӮЯҒAҢ»ҚЭҒuҢ№ҒvӮрҚЎ“ъ“IӮИҲУ–ЎӮМҗ©ӮЖӮөӮД–јҸжӮй—бӮН‘ҪӮӯӮИӮӯҒAҗ„’иҗlҢыӮН4,000җl’цӮЕӮ ӮйҒB
‘г•\“IӮИүЖ–дӮЕӮ ӮйҒuҚщ—і’_ҒvӮН“ъ–{ҚЕҢГӮМүЖ–дӮЕӮ ӮйӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒB
ӢNҢ№
Қөүг“VҚcӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҺqӮзӮЙҢ№җ©Ӯр—^ӮҰӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮйҒBҚcҺәӮЖ‘cҒiҢ№—¬ҒjӮр“ҜӮ¶ӮӯӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ–ј—_ӮМҲУ–ЎӮрӮұӮЯӮД—^ӮҰӮзӮкӮҪҒB
ҢіҒXӮН’ҶҚ‘ӮМҢЬҢУҸ\ҳZҚ‘Һһ‘гҒA“м—БүӨӮМҺqӮМ“Г”Ҝ”jгіӮӘҒA“м—Б–Е–SҢгӮЙ–kй°ӮЙҺdӮҰӮҪҚЫҒA‘ҫ•җ’йӮ©Ӯз“Г”ҜҺҒӮЖ‘сжлҺҒҒi–kй°ӮМ’йҺәӮМҗ©ҒjӮНҢ№ӮӘ“ҜӮ¶ӮЕӮ ӮйӮЖӮөӮДҢ№ӮМҗ©Ӯр—^ӮҰӮзӮкҒAҢ№үкӮЖ–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮЙ—R—ҲӮ·ӮйҒB
‘јӮЙӮаҒAҒuҢ№ҒvӮНҒuҗ…ҢіҒvӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҗаӮаӮ ӮйҒB—бӮҰӮОҒAҒwҳaҢPһxҒxҒi’JҗмҺmҗҙҒjӮЕӮНҒuӮЭӮИӮаӮЖҒAҢ№ӮрӮжӮЯӮиҒBҗ…ҢіӮМӢ`ӮИӮиҒvӮЖӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAҒwҗ_‘гҠӘ‘”ү–‘җҒxҒiӢК–ШҗіүpҒjӮЕӮНҒuҢ№ғmҢPғnҗ…Ңі–зҒvӮЖӮ ӮйҒB
Қөүг“VҚcӮЙҚcҺqҚcҸ—ӮӘ‘қӮҰҒA’©’мӮМҚаҗӯӮр•N”—ӮіӮ№ӮйҠоӮЙӮаӮИӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA‘ҒӮӯӮЙҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҚcҲыӮЙӮЖӮБӮДҺq‘·”ЙүhӮМ“№ӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗeүӨӮИӮӘӮзҚcҲКӮр–]ӮЯӮИӮўҸкҚҮӮвҒAҸ”үӨӮЙӮ ӮБӮДҗeүӨҗйүәӮр–]ӮЯӮИӮўҚc‘°ӮӘҺ©ӮзҚ~үәӮрӢҒӮЯӮйҸкҚҮӮЖҒA’©’мӮ©ӮзҲк•ы“IӮЙҚ~үәӮіӮ№ӮйҸкҚҮӮЖӮӘӮ ӮиҚc•КҺҒ‘°ӮрҺжӮиҠӘӮӯҸуӢөӮН’©’мӮМҚаҗӯҺ–ҸоӮЖҸнӮЙҳA“®Ӯ·Ӯй—v‘fӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪҒB
Қөүг“VҚcӮМҢгӮМ“VҚcӮа“xҒXҚc‘°ӮрҢ№ҺҒӮЖӮөӮДҗbҗРӮЙүәӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҚөүг“VҚcӮр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№ҺҒӮрҚөүгҢ№ҺҒӮЖҸМӮ·Ӯй—lӮЙӮИӮиҒAҲИҢгҢ№ҺҒӮНӮ»ӮкӮјӮкӮМ‘cӮЖӢВӮ®“VҚcӮМҚҶӮрӮаӮБӮДҺҒ‘°ӮМҸМӮЖӮөӮҪҒiҗm–ҫҢ№ҺҒҒA•¶“ҝҢ№ҺҒҒAҗҙҳaҢ№ҺҒҒAүF‘ҪҢ№ҺҒӮИӮЗҒjҒB
җbҗРӮЙҚ~үәӮ·ӮйӮЖҢҫӮБӮДӮа“VҚcӮМҺАҺqӮЕӮ ӮйҲкҗўҢ№ҺҒӮН“БҺкӮИ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮ鑶ҚЭӮЕӮ ӮБӮҪҒBҚөүг“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№’иҒEҢ№—ZҒAҗm–ҫ“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№—вӮН•ғ“VҚcӮМҲУҢьӮЕҗeүӨӮМ—бӮЙҸҖӮ¶ӮД“а— ӮЙӮЁӮўӮДҢі•һӮрҚsӮБӮДӮЁӮиҒAҗeүӨӮЙҸҖӮ¶ӮҪ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒA—zҗ¬“VҚcӮМ‘ЮҲКҢгӮМҢгҢp‘I’иӮЕ“ЎҢҙҠоҢoӮӘҢ№—ZӮр‘ЮӮҜӮДҢхҚF“VҚcӮр‘ҰҲКӮіӮ№ҒAҢхҚF“VҚcӮӘ•цҢдӮ·ӮйӮЖӮ»ӮМҠоҢoӮӘҗbҗРӮЙҚ~үәӮөӮҪҢ№’иҸИӮр•ңҗРӮіӮ№ӮДүF‘Ҫ“VҚcӮЖӮөӮД‘ҰҲКӮіӮ№ӮйӮИӮЗҒA“ҜӮ¶“VҚcӮМҺqӮЕӮаҗeүӨӮЖҲкҗўҢ№ҺҒӮМӢж•КӮМ–ҫҠmү»Ӯр”—ӮзӮкӮйҺ–‘ФӮӘ”ӯҗ¶ӮөҒAүF‘Ҫ“VҚcҲИҚ~ӮМӢVҺ®Ҹ‘ӮЕӮНҗeүӨӮМҢі•һӮЖҲкҗўҢ№ҺҒӮМҢі•һӮЕӮНҲЩӮИӮйҚм–@ӮӘӢLӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮМҢгӮаӢK–НӮрҸ¬ӮіӮӯӮөӮИӮӘӮзӮа“а— ӮЕҢі•һӮрҚsӮўҒA“а‘ —ҫӮ©ӮзӢАүғӮвҲшҸo•ЁӮӘ—pҲУӮіӮкӮҪ‘зҢн“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№ҚӮ–ҫҒEҢ№Ң“–ҫӮМҢі•һӮИӮЗҲкҗўҢ№ҺҒӮМ“БҺкҗ«ӮӘҠ®‘SӮЙ”rҸңӮіӮкӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒi“а‘ —ҫӮН“VҚcӮМҺ„“IӮИҺxҸoӮрҲөӮӨҠҜҺiӮЕӮ ӮиҒAҲкҗўҢ№ҺҒӮМҢі•һӮрҢц“IҚsҺ–Ӯ©Ӯз“VҚcҺеҚГӮМҺ„“IҚsҺ–ӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮйӮұӮЖӮЕ“БҺкҗ«ӮрҲЫҺқӮөӮҪӮЖӮЭӮзӮкӮйҒjҒBҒwҢ№ҺҒ•ЁҢкҒxӮЙӮЁӮўӮДҒAӢЛҡв’йӮӘҲкҗўҢ№ҺҒӮЕӮ ӮйҢхҢ№ҺҒӮМҢі•һӮрҺ©ӮзҺе“ұӮөӮДҒAҲшҸo•ЁӮаҺ©ӮзҸҖ”хӮөӮДӮўӮйҒi”п—pӮаӢЛҡв’йӮМ•ү’SӮЖҚlӮҰӮзӮкӮйҒjӮМӮаҒAҲкҗўҢ№ҺҒӮМ“БҺкҗ«ӮӘ•`Ӯ©ӮкӮҪҸк–КӮЖҢҫӮҰӮй[2]ҒB
ӮЬӮҪҒA’©’мӮӘҚc‘°ӮрҗbҗРҚ~үәӮіӮ№Ң№ҺҒӮЖӮөӮҪ”wҢiӮЖӮөӮДӮНҸгӢүӢM‘°ӮЖӮөӮДҚcҺәӮМ”Л•»ӮЖӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮўӮӨ—қ—RӮаӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҺАҚЫӮЙӮН3‘г–ЪҲИҚ~ӮаҸгӢүӢM‘°ӮЕӮ Ӯи‘ұӮҜӮҪ—бӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮӯҒA‘е”јӮНҺу—МҠKӢүӮЖӮөӮД’n•ыӮЦ•Ӣ”CӮөӮ»ӮұӮЕ“y’…ӮөӮД•җҺmү»Ӯ·ӮйӮ©ҒA’ҶүӣӮЕ’ҶүәӢүӢM‘°ӮЖӮөӮДҚЧҒXӮЖҗ¶Ӯ«ү„ӮСӮҪҒB‘јӮЙҚc‘°ӮЙ‘ОӮөӮДҺ’ӮБӮҪҗ©ӮЖӮөӮДӮНҒAҚЭҢҙ’©җbҒE•Ҫ’©җbӮИӮЗӮӘӮ ӮйҒB
•җүЖҢ№ҺҒӮЖҢцүЖҢ№ҺҒ
җҙҳaҢ№ҺҒӮНҒA“сҸ\Ҳк—¬Ӯ ӮйӮЖӮўӮнӮкӮйҢ№ҺҒӮЙӮЁӮҜӮйҲкүЖҢnӮЕӮ ӮйӮӘҒA•җүЖҢ№ҺҒӮЖӮөӮД—рҺjҸгӮЙ–јӮр’yӮ№ӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮрӮөӮДҢ№ҺҒӮЖҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўҒB
ӮұӮМҲк‘°ӮНҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqӮр‘cӮЖӮ·ӮйҒB•җүЖҢ№ҺҒӮЖӮөӮД–јӮр’yӮ№ӮҪҗҙҳaҢ№ҺҒӮЙӮЁӮўӮДӮНӢE“аӮЙҺnӮЬӮиҠe’nӮЙ“y’…ӮөӮДӮЁӮиҒAҢ№–һ’ҮӮМҺqӮ©ӮзҗЫ’ГҢ№ҺҒҒA‘еҳaҢ№ҺҒҒAүН“аҢ№ҺҒӮЖӮЙ•ӘӮ©ӮкӮҪҒBүН“аҚ‘Ӯр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪүН“аҢ№ҺҒӮМҢ№Ӣ`үЖҒi”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖҒjӮНӮ»ӮМҺе—¬ӮЕҒAӮ»ӮМҺq‘·ӮНҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҢ№—Ҡ’©ӮЙ‘г•\ӮіӮкӮй•җ–еӮЖӮөӮДүhӮҰӮҪҒBӮіӮзӮЙүН“аҢ№ҺҒӮ©ӮзӮНҗОҗмҢ№ҺҒҒAҚb”гҢ№ҺҒҒAҸн—ӨҢ№ҺҒҒAүә–мҢ№ҺҒҒi‘«—ҳҺҒҒjҒAҸг–мҢ№ҺҒҒiҗV“cҺҒҒjӮИӮЗӮӘ•Ә”hӮөӮДӮўӮйҒBҗЫ’ГҚ‘Ӯр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪҗЫ’ГҢ№ҺҒӮ©ӮзӮН‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒA”ь”ZҢ№ҺҒӮ»ӮМ‘јӮӘ•Ә”hӮөӮДӮЁӮиҒAӮўӮёӮкӮаҗҙҳaҢ№ҺҒҲк–еӮЕӮ ӮиҒAӮўӮнӮдӮйҒu•җүЖҢ№ҺҒҒvӮЕӮ ӮйҒB
җҙҳaҢ№ҺҒҲИҠOӮЙ•җүЖӮЖӮИӮБӮҪҢ№ҺҒӮЖӮөӮДӮНҒAҚөүгҢ№ҺҒӮМҢ№—ZӮр‘cӮЖӮ·ӮйҒu—Z—¬ҚөүгҢ№ҺҒҒvӮӘӮ ӮйҒBҚөүгҢ№ҺҒӮМ•җүЖӮЖӮөӮДҢn•ҲӮр“`ӮҰӮҪ‘г•\ӮНҒAҗЫ’ГҚ‘ӮрҠо”ХӮЖӮөӮҪ“n•УҺҒӮЖӮ»ӮМ•Ә—¬ӮМҸјүYҺҒӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAүF‘ҪҢ№ҺҒӮМ’ҶӮЕ•җүЖӮЖӮөӮДӢЯҚ]Қ‘ӮрҠо”ХӮЖӮөӮҪҢn“қӮНӢЯҚ]Ң№ҺҒҒiҚІҚІ–ШҢ№ҺҒҒjӮЖҸМӮөҒAҚІҒX–ШҺҒӮЖӮөӮД—L—Н•җҺm’cӮЙҗ¬’·ӮөӮДӮўӮӯҒB
’ҶүӣӢM‘°ӮЖӮөӮДүhӮҰӮҪҢ№ҺҒӮЖӮөӮД‘әҸг“VҚcӮМҚcҺqӮр‘cӮЖӮ·Ӯй‘әҸгҢ№ҺҒӮӘӮ ӮйҒB“ҜӮ¶Ң№ҺҒӮЕӮаҢцӢЁӮЖӮөӮД”ЙүhӮ·ӮйҢn“қӮвҒA•җҺmӮвҗ_ҠҜӮЖӮИӮйҢn“қӮЙ•КӮкӮйӮМӮНҒAҗӯҺЎҸоҗЁӮвҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйҺТҒA•к•ыӮМҗЁ—НӮвҗg•ӘӮӘӮ»ӮМҢгӮМҠҜ“rӮЙ‘еӮ«ӮӯҚ¶үEӮ·ӮйҲЧӮЕӮ ӮйҒB“БӮЙ“VҚcӮМҚcҺqӮӘҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒAҒuҲкҗўӮМҢ№ҺҒҒvӮЖӮўӮўҒA”CҠҜӮМҸгӮЕ‘еӮўӮЙ—DӢцӮіӮкӮҪҒBҚc‘·ӮЙҺҠӮБӮДҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒu“сҗўӮМҢ№ҺҒҒvӮЖӮўӮўҒAҲкҗўӮМҢ№ҺҒӮжӮиӮаүЖҢn“IӮЙӮН•s—ҳӮр–ЦӮБӮҪҒB
•ҪҲАҢгҠъҲИҚ~ҒAҚcҲКҢpҸіӮЖӮНҠЦӮнӮиӮМӮИӮўҚcҺqҚcҸ—ӮҪӮҝӮНҸoүЖӮ·ӮйҠө—бӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪӮҪӮЯҒAҺ’җ©Ң№ҺҒӮНӮЩӮЖӮсӮЗ“rҗвӮҰӮДӮўӮҪҒBҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙ“ьӮБӮДҲкүЖӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҒiҚL”ҰүЖҒjӮӘҒAӮ»ӮкӮрҚЕҢгӮЙҢ№ҺҒҺ’—^ӮН“rҗвӮҰӮҪҒB
Ң№ҺҒӮМҲк——
Ң№ҺҒӮН‘S•”ӮЕ21ӮМ—¬”hҒiҒu“сҸ\Ҳк—¬ҒvҺQҸЖҒjӮӘӮ ӮйӮЖӮіӮкӮйӮӘҒAӮ»ӮМӮӨӮҝ18—¬ӮрҲИүәӮЙҺҰӮ·ҒB
ҚөүгҢ№ҺҒ
52‘гҚөүг“VҚcӮМҺq‘·ҒBҸЪҚЧӮНҒuҚөүгҢ№ҺҒҒvӮрҺQҸЖҒB
Қөүг“VҚcӮН‘ҪӮӯӮМҚcҺqҚcҸ—ӮЙҢ№ҺҒҗ©ӮрҺ’ӮиҗbҗРҚ~үәӮіӮ№ӮҪҒBӮұӮМ“аҒAҢ№җMҒEҢ№ҸнҒEҢ№—ZӮНҚ¶‘еҗbӮЖӮИӮиҒA•ҪҲАҺһ‘гҸүҠъӮЙ’©’мӮМҲк‘еҗЁ—НӮрӮИӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҢ№—ZӮМҢn“қӮН’n•ыӮЙ“y’…ӮЖӮөӮД•җүЖӮЖӮИӮБӮҪҒB
ҺҒ‘°ҒF“n•УҺҒҒAҸјүYҺҒҒAҠ—’rҺҒӮИӮЗ
ҚөүгҢ№ҺҒ Ңnҗ}
Қөүг“VҚcҸ”ҚcҺqҒEҚcҸ—Ңn•Ҳ
Ҹ—ҺqӮНҗ”ӮрҢАӮБӮДӢLҚЪҒB
“ъ–{ӮМ‘ж52‘г“VҚc
Қөүг“VҚc
“ъ–{ӮМ‘ж54‘г“VҚc
җm–ҫ“VҚcҒ@Қөүг“VҚcӮМ‘ж“сҚcҺq
ҸG—ЗҗeүӨ
ӢЖ—ЗҗeүӨ
’ү—ЗҗeүӨ
Ҡо—ЗҗeүӨ
Ҹ~үӨ
Ң№җMҒ@Ң№җM—¬ӮЦ
Ң№ҚOҒ@Ң№ҚO—¬ӮЦ
Ң№ҸнҒ@Ң№Ҹн—¬ӮЦ
Ң№’иҒ[Ң№ҺҠҒ[Ң№Ӣ“Ғ[Ң№ҸҮ
Ң№–ҫҒ@Ң№–ҫ—¬ӮЦ
Ң№җ¶Ғ[Ң№үБҒ[Ң№•Ӯ
Ғ@Ғ@Ғ@Ң№Ң©
“ъ–{ӮМҺҒ‘°ӮМӮРӮЖӮВҒBҗ©ӮН’©җbҒB

үЖ–дҒ@Қщ—і’_ӮіӮіӮиӮсӮЗӮӨ
Ғ@Ғ@Ғi‘г•\“IӮИүЖ–дҒj
ҠeҒAҢ№ҺҒӮЙӮжӮБӮДҲЩӮИӮйҒB
ҺҒҗ©
Ң№’©җb
ҺҒ‘c
“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨ
Ӣ{үЖӮМҸ”үӨ
Һн•К
Қc•К
’ҳ–јӮИҗl•Ё
‘әҸгҢ№ҺҒҒF
Ң№’Кҗe
–k”©җe–[
җҙҳaҢ№ҺҒҒF
Ң№—Ҡ’©
‘«—ҳ‘ёҺҒ
“ҝҗмүЖҚNҒiҺ©ҸМҒj
Ӯ»ӮМ‘јӮНҢ№ҺҒӮМҗl•ЁҲк——ӮрҺQҸЖ
Ңгеб
ҚөүгҢ№ҺҒ
‘әҸгҢ№ҺҒ
җҙҳaҢ№ҺҒ
үФҺRҢ№ҺҒ
үF‘ҪҢ№ҺҒ
җіҗe’¬Ң№ҺҒ
ӮИӮЗ
Ӯ»ӮМ‘јӮМҢ№ҺҒӮЙӮВӮўӮДӮНҒA“сҸ\Ҳк—¬ӮрҺQҸЖ
“ъ–{ӮЙӮЁӮўӮДҚc‘°ӮӘҗbүәӮМҗРӮЙҚ~ӮиӮйҒiҗbҗРҚ~үәҒjҚЫӮЙ–јҸжӮйҺҒӮМӮРӮЖӮВӮЕҒA‘Ҫҗ”ӮМ—¬”hӮӘӮ ӮйҒBҢ№ҺҒӮр“қӮЧӮйҢ№ҺҒ’·ҺТӮНҺә’¬Һһ‘гӮЬӮЕ‘әҸг“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ Ӯй‘әҸгҢ№ҺҒӮӘ“ЖҗиӮөҒAҢҡӢvҺө”NӮМҗӯ•ПӮЕҗЫҠЦүЖӮрүzӮҰӮйҢ —НӮрҺиӮЙӮөӮҪҢ№’КҗeӮвҒAҢг‘зҢн“VҚc‘жҲкӮМ‘ӨӢЯӮЖӮөӮД“м’©ӮрҺwҠцӮөӮҪ–k”©җe–[ӮИӮЗӮӘӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҗҙҳa“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮйҗҙҳaҢ№ҺҒӮН•җүЖӮМ“Ҹ—АӮр‘ҪӮӯ”yҸoӮөҒAҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҢ№—Ҡ’©ӮвҺә’¬–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪ‘«—ҳ‘ёҺҒӮИӮЗӮӘӮўӮйҒBҗнҚ‘Һһ‘гӮМ•җҸ«Ҹј•ҪҢіҚNӮаҢг”јҗ¶ӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҺ©ҸМӮөӮД“ҝҗмүЖҚNӮЖ–јҸжӮиҒAҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҒB
ҠT—v
җ©ӮМ‘г•\“IӮИӮаӮМӮМҲкӮВӮЖӮөӮДҒA•ҪҺҒҒE“ЎҢҙҺҒҒEӢkҺҒӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢ№•Ҫ“ЎӢkҒvҒiҺlҗ©ҒjӮЖ‘ҚҸМӮіӮкӮДӮўӮйҒB
Қөүг“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҚөүгҢ№ҺҒӮвҗҙҳa“VҚcӮ©ӮзӮМҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҠЬӮЯҒA“сҸ\ҲкӮМ—¬”hҒi“сҸ\Ҳк—¬ҒjӮӘӮ ӮйӮЖӮіӮкӮДӮўӮй[’ҚҺЯ 1]ҒB’ҶӮЕӮаүЖҠiӮӘҚЕӮаҚӮӮўӮМӮН‘әҸгҢ№ҺҒӮЖӮіӮкҒAҺә’¬–Ӣ•{ӮМҗ¬—§ӮЬӮЕҢ№ҺҒ’·ҺТӮр—LӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA•ҪҲАҲИҚ~җbҗРҚ~үәӮӘ•p”ӯӮ·ӮйӮЖҢ№ҒE•ҪӮМ“сҗ©ӮОӮ©ӮиӮЙӮИӮйӮӘҒAҚЕӢЯӮМҢӨӢҶӮЕҒuҲкҗўүӨҒA“сҗўүӨӮӘҢ№ҒAҺOҗўҲИҚ~ӮӘ•ҪҒvӮҫӮБӮҪҺ–ӮӘ”»–ҫӮөӮДӮўӮйҒBҢ№җ©Ғi–{җ©ӮӘҢ№ҺҒҒjӮМүЖҢnӮНӮ»ӮкӮјӮк•КӮМ•cҺҡӮрҚҶӮөӮДӮўӮйӮҪӮЯҒAҢ»ҚЭҒuҢ№ҒvӮрҚЎ“ъ“IӮИҲУ–ЎӮМҗ©ӮЖӮөӮД–јҸжӮй—бӮН‘ҪӮӯӮИӮӯҒAҗ„’иҗlҢыӮН4,000җl’цӮЕӮ ӮйҒB
‘г•\“IӮИүЖ–дӮЕӮ ӮйҒuҚщ—і’_ҒvӮН“ъ–{ҚЕҢГӮМүЖ–дӮЕӮ ӮйӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒB
ӢNҢ№
Қөүг“VҚcӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҺqӮзӮЙҢ№җ©Ӯр—^ӮҰӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮйҒBҚcҺәӮЖ‘cҒiҢ№—¬ҒjӮр“ҜӮ¶ӮӯӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ–ј—_ӮМҲУ–ЎӮрӮұӮЯӮД—^ӮҰӮзӮкӮҪҒB
ҢіҒXӮН’ҶҚ‘ӮМҢЬҢУҸ\ҳZҚ‘Һһ‘гҒA“м—БүӨӮМҺqӮМ“Г”Ҝ”jгіӮӘҒA“м—Б–Е–SҢгӮЙ–kй°ӮЙҺdӮҰӮҪҚЫҒA‘ҫ•җ’йӮ©Ӯз“Г”ҜҺҒӮЖ‘сжлҺҒҒi–kй°ӮМ’йҺәӮМҗ©ҒjӮНҢ№ӮӘ“ҜӮ¶ӮЕӮ ӮйӮЖӮөӮДҢ№ӮМҗ©Ӯр—^ӮҰӮзӮкҒAҢ№үкӮЖ–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮЙ—R—ҲӮ·ӮйҒB
‘јӮЙӮаҒAҒuҢ№ҒvӮНҒuҗ…ҢіҒvӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҗаӮаӮ ӮйҒB—бӮҰӮОҒAҒwҳaҢPһxҒxҒi’JҗмҺmҗҙҒjӮЕӮНҒuӮЭӮИӮаӮЖҒAҢ№ӮрӮжӮЯӮиҒBҗ…ҢіӮМӢ`ӮИӮиҒvӮЖӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAҒwҗ_‘гҠӘ‘”ү–‘җҒxҒiӢК–ШҗіүpҒjӮЕӮНҒuҢ№ғmҢPғnҗ…Ңі–зҒvӮЖӮ ӮйҒB
Қөүг“VҚcӮЙҚcҺqҚcҸ—ӮӘ‘қӮҰҒA’©’мӮМҚаҗӯӮр•N”—ӮіӮ№ӮйҠоӮЙӮаӮИӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA‘ҒӮӯӮЙҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҚcҲыӮЙӮЖӮБӮДҺq‘·”ЙүhӮМ“№ӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗeүӨӮИӮӘӮзҚcҲКӮр–]ӮЯӮИӮўҸкҚҮӮвҒAҸ”үӨӮЙӮ ӮБӮДҗeүӨҗйүәӮр–]ӮЯӮИӮўҚc‘°ӮӘҺ©ӮзҚ~үәӮрӢҒӮЯӮйҸкҚҮӮЖҒA’©’мӮ©ӮзҲк•ы“IӮЙҚ~үәӮіӮ№ӮйҸкҚҮӮЖӮӘӮ ӮиҚc•КҺҒ‘°ӮрҺжӮиҠӘӮӯҸуӢөӮН’©’мӮМҚаҗӯҺ–ҸоӮЖҸнӮЙҳA“®Ӯ·Ӯй—v‘fӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪҒB
Қөүг“VҚcӮМҢгӮМ“VҚcӮа“xҒXҚc‘°ӮрҢ№ҺҒӮЖӮөӮДҗbҗРӮЙүәӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҚөүг“VҚcӮр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№ҺҒӮрҚөүгҢ№ҺҒӮЖҸМӮ·Ӯй—lӮЙӮИӮиҒAҲИҢгҢ№ҺҒӮНӮ»ӮкӮјӮкӮМ‘cӮЖӢВӮ®“VҚcӮМҚҶӮрӮаӮБӮДҺҒ‘°ӮМҸМӮЖӮөӮҪҒiҗm–ҫҢ№ҺҒҒA•¶“ҝҢ№ҺҒҒAҗҙҳaҢ№ҺҒҒAүF‘ҪҢ№ҺҒӮИӮЗҒjҒB
җbҗРӮЙҚ~үәӮ·ӮйӮЖҢҫӮБӮДӮа“VҚcӮМҺАҺqӮЕӮ ӮйҲкҗўҢ№ҺҒӮН“БҺкӮИ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮ鑶ҚЭӮЕӮ ӮБӮҪҒBҚөүг“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№’иҒEҢ№—ZҒAҗm–ҫ“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№—вӮН•ғ“VҚcӮМҲУҢьӮЕҗeүӨӮМ—бӮЙҸҖӮ¶ӮД“а— ӮЙӮЁӮўӮДҢі•һӮрҚsӮБӮДӮЁӮиҒAҗeүӨӮЙҸҖӮ¶ӮҪ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒA—zҗ¬“VҚcӮМ‘ЮҲКҢгӮМҢгҢp‘I’иӮЕ“ЎҢҙҠоҢoӮӘҢ№—ZӮр‘ЮӮҜӮДҢхҚF“VҚcӮр‘ҰҲКӮіӮ№ҒAҢхҚF“VҚcӮӘ•цҢдӮ·ӮйӮЖӮ»ӮМҠоҢoӮӘҗbҗРӮЙҚ~үәӮөӮҪҢ№’иҸИӮр•ңҗРӮіӮ№ӮДүF‘Ҫ“VҚcӮЖӮөӮД‘ҰҲКӮіӮ№ӮйӮИӮЗҒA“ҜӮ¶“VҚcӮМҺqӮЕӮаҗeүӨӮЖҲкҗўҢ№ҺҒӮМӢж•КӮМ–ҫҠmү»Ӯр”—ӮзӮкӮйҺ–‘ФӮӘ”ӯҗ¶ӮөҒAүF‘Ҫ“VҚcҲИҚ~ӮМӢVҺ®Ҹ‘ӮЕӮНҗeүӨӮМҢі•һӮЖҲкҗўҢ№ҺҒӮМҢі•һӮЕӮНҲЩӮИӮйҚм–@ӮӘӢLӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮМҢгӮаӢK–НӮрҸ¬ӮіӮӯӮөӮИӮӘӮзӮа“а— ӮЕҢі•һӮрҚsӮўҒA“а‘ —ҫӮ©ӮзӢАүғӮвҲшҸo•ЁӮӘ—pҲУӮіӮкӮҪ‘зҢн“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№ҚӮ–ҫҒEҢ№Ң“–ҫӮМҢі•һӮИӮЗҲкҗўҢ№ҺҒӮМ“БҺкҗ«ӮӘҠ®‘SӮЙ”rҸңӮіӮкӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒi“а‘ —ҫӮН“VҚcӮМҺ„“IӮИҺxҸoӮрҲөӮӨҠҜҺiӮЕӮ ӮиҒAҲкҗўҢ№ҺҒӮМҢі•һӮрҢц“IҚsҺ–Ӯ©Ӯз“VҚcҺеҚГӮМҺ„“IҚsҺ–ӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮйӮұӮЖӮЕ“БҺкҗ«ӮрҲЫҺқӮөӮҪӮЖӮЭӮзӮкӮйҒjҒBҒwҢ№ҺҒ•ЁҢкҒxӮЙӮЁӮўӮДҒAӢЛҡв’йӮӘҲкҗўҢ№ҺҒӮЕӮ ӮйҢхҢ№ҺҒӮМҢі•һӮрҺ©ӮзҺе“ұӮөӮДҒAҲшҸo•ЁӮаҺ©ӮзҸҖ”хӮөӮДӮўӮйҒi”п—pӮаӢЛҡв’йӮМ•ү’SӮЖҚlӮҰӮзӮкӮйҒjӮМӮаҒAҲкҗўҢ№ҺҒӮМ“БҺкҗ«ӮӘ•`Ӯ©ӮкӮҪҸк–КӮЖҢҫӮҰӮй[2]ҒB
ӮЬӮҪҒA’©’мӮӘҚc‘°ӮрҗbҗРҚ~үәӮіӮ№Ң№ҺҒӮЖӮөӮҪ”wҢiӮЖӮөӮДӮНҸгӢүӢM‘°ӮЖӮөӮДҚcҺәӮМ”Л•»ӮЖӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮўӮӨ—қ—RӮаӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҺАҚЫӮЙӮН3‘г–ЪҲИҚ~ӮаҸгӢүӢM‘°ӮЕӮ Ӯи‘ұӮҜӮҪ—бӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮӯҒA‘е”јӮНҺу—МҠKӢүӮЖӮөӮД’n•ыӮЦ•Ӣ”CӮөӮ»ӮұӮЕ“y’…ӮөӮД•җҺmү»Ӯ·ӮйӮ©ҒA’ҶүӣӮЕ’ҶүәӢүӢM‘°ӮЖӮөӮДҚЧҒXӮЖҗ¶Ӯ«ү„ӮСӮҪҒB‘јӮЙҚc‘°ӮЙ‘ОӮөӮДҺ’ӮБӮҪҗ©ӮЖӮөӮДӮНҒAҚЭҢҙ’©җbҒE•Ҫ’©җbӮИӮЗӮӘӮ ӮйҒB
•җүЖҢ№ҺҒӮЖҢцүЖҢ№ҺҒ
җҙҳaҢ№ҺҒӮНҒA“сҸ\Ҳк—¬Ӯ ӮйӮЖӮўӮнӮкӮйҢ№ҺҒӮЙӮЁӮҜӮйҲкүЖҢnӮЕӮ ӮйӮӘҒA•җүЖҢ№ҺҒӮЖӮөӮД—рҺjҸгӮЙ–јӮр’yӮ№ӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮрӮөӮДҢ№ҺҒӮЖҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўҒB
ӮұӮМҲк‘°ӮНҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqӮр‘cӮЖӮ·ӮйҒB•җүЖҢ№ҺҒӮЖӮөӮД–јӮр’yӮ№ӮҪҗҙҳaҢ№ҺҒӮЙӮЁӮўӮДӮНӢE“аӮЙҺnӮЬӮиҠe’nӮЙ“y’…ӮөӮДӮЁӮиҒAҢ№–һ’ҮӮМҺqӮ©ӮзҗЫ’ГҢ№ҺҒҒA‘еҳaҢ№ҺҒҒAүН“аҢ№ҺҒӮЖӮЙ•ӘӮ©ӮкӮҪҒBүН“аҚ‘Ӯр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪүН“аҢ№ҺҒӮМҢ№Ӣ`үЖҒi”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖҒjӮНӮ»ӮМҺе—¬ӮЕҒAӮ»ӮМҺq‘·ӮНҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҢ№—Ҡ’©ӮЙ‘г•\ӮіӮкӮй•җ–еӮЖӮөӮДүhӮҰӮҪҒBӮіӮзӮЙүН“аҢ№ҺҒӮ©ӮзӮНҗОҗмҢ№ҺҒҒAҚb”гҢ№ҺҒҒAҸн—ӨҢ№ҺҒҒAүә–мҢ№ҺҒҒi‘«—ҳҺҒҒjҒAҸг–мҢ№ҺҒҒiҗV“cҺҒҒjӮИӮЗӮӘ•Ә”hӮөӮДӮўӮйҒBҗЫ’ГҚ‘Ӯр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪҗЫ’ГҢ№ҺҒӮ©ӮзӮН‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒA”ь”ZҢ№ҺҒӮ»ӮМ‘јӮӘ•Ә”hӮөӮДӮЁӮиҒAӮўӮёӮкӮаҗҙҳaҢ№ҺҒҲк–еӮЕӮ ӮиҒAӮўӮнӮдӮйҒu•җүЖҢ№ҺҒҒvӮЕӮ ӮйҒB
җҙҳaҢ№ҺҒҲИҠOӮЙ•җүЖӮЖӮИӮБӮҪҢ№ҺҒӮЖӮөӮДӮНҒAҚөүгҢ№ҺҒӮМҢ№—ZӮр‘cӮЖӮ·ӮйҒu—Z—¬ҚөүгҢ№ҺҒҒvӮӘӮ ӮйҒBҚөүгҢ№ҺҒӮМ•җүЖӮЖӮөӮДҢn•ҲӮр“`ӮҰӮҪ‘г•\ӮНҒAҗЫ’ГҚ‘ӮрҠо”ХӮЖӮөӮҪ“n•УҺҒӮЖӮ»ӮМ•Ә—¬ӮМҸјүYҺҒӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAүF‘ҪҢ№ҺҒӮМ’ҶӮЕ•җүЖӮЖӮөӮДӢЯҚ]Қ‘ӮрҠо”ХӮЖӮөӮҪҢn“қӮНӢЯҚ]Ң№ҺҒҒiҚІҚІ–ШҢ№ҺҒҒjӮЖҸМӮөҒAҚІҒX–ШҺҒӮЖӮөӮД—L—Н•җҺm’cӮЙҗ¬’·ӮөӮДӮўӮӯҒB
’ҶүӣӢM‘°ӮЖӮөӮДүhӮҰӮҪҢ№ҺҒӮЖӮөӮД‘әҸг“VҚcӮМҚcҺqӮр‘cӮЖӮ·Ӯй‘әҸгҢ№ҺҒӮӘӮ ӮйҒB“ҜӮ¶Ң№ҺҒӮЕӮаҢцӢЁӮЖӮөӮД”ЙүhӮ·ӮйҢn“қӮвҒA•җҺmӮвҗ_ҠҜӮЖӮИӮйҢn“қӮЙ•КӮкӮйӮМӮНҒAҗӯҺЎҸоҗЁӮвҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйҺТҒA•к•ыӮМҗЁ—НӮвҗg•ӘӮӘӮ»ӮМҢгӮМҠҜ“rӮЙ‘еӮ«ӮӯҚ¶үEӮ·ӮйҲЧӮЕӮ ӮйҒB“БӮЙ“VҚcӮМҚcҺqӮӘҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒAҒuҲкҗўӮМҢ№ҺҒҒvӮЖӮўӮўҒA”CҠҜӮМҸгӮЕ‘еӮўӮЙ—DӢцӮіӮкӮҪҒBҚc‘·ӮЙҺҠӮБӮДҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒu“сҗўӮМҢ№ҺҒҒvӮЖӮўӮўҒAҲкҗўӮМҢ№ҺҒӮжӮиӮаүЖҢn“IӮЙӮН•s—ҳӮр–ЦӮБӮҪҒB
•ҪҲАҢгҠъҲИҚ~ҒAҚcҲКҢpҸіӮЖӮНҠЦӮнӮиӮМӮИӮўҚcҺqҚcҸ—ӮҪӮҝӮНҸoүЖӮ·ӮйҠө—бӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪӮҪӮЯҒAҺ’җ©Ң№ҺҒӮНӮЩӮЖӮсӮЗ“rҗвӮҰӮДӮўӮҪҒBҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙ“ьӮБӮДҲкүЖӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҒiҚL”ҰүЖҒjӮӘҒAӮ»ӮкӮрҚЕҢгӮЙҢ№ҺҒҺ’—^ӮН“rҗвӮҰӮҪҒB
Ң№ҺҒӮМҲк——
Ң№ҺҒӮН‘S•”ӮЕ21ӮМ—¬”hҒiҒu“сҸ\Ҳк—¬ҒvҺQҸЖҒjӮӘӮ ӮйӮЖӮіӮкӮйӮӘҒAӮ»ӮМӮӨӮҝ18—¬ӮрҲИүәӮЙҺҰӮ·ҒB
ҚөүгҢ№ҺҒ
52‘гҚөүг“VҚcӮМҺq‘·ҒBҸЪҚЧӮНҒuҚөүгҢ№ҺҒҒvӮрҺQҸЖҒB
Қөүг“VҚcӮН‘ҪӮӯӮМҚcҺqҚcҸ—ӮЙҢ№ҺҒҗ©ӮрҺ’ӮиҗbҗРҚ~үәӮіӮ№ӮҪҒBӮұӮМ“аҒAҢ№җMҒEҢ№ҸнҒEҢ№—ZӮНҚ¶‘еҗbӮЖӮИӮиҒA•ҪҲАҺһ‘гҸүҠъӮЙ’©’мӮМҲк‘еҗЁ—НӮрӮИӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҢ№—ZӮМҢn“қӮН’n•ыӮЙ“y’…ӮЖӮөӮД•җүЖӮЖӮИӮБӮҪҒB
ҺҒ‘°ҒF“n•УҺҒҒAҸјүYҺҒҒAҠ—’rҺҒӮИӮЗ
ҚөүгҢ№ҺҒ Ңnҗ}
Қөүг“VҚcҸ”ҚcҺqҒEҚcҸ—Ңn•Ҳ
Ҹ—ҺqӮНҗ”ӮрҢАӮБӮДӢLҚЪҒB
“ъ–{ӮМ‘ж52‘г“VҚc
Қөүг“VҚc
“ъ–{ӮМ‘ж54‘г“VҚc
җm–ҫ“VҚcҒ@Қөүг“VҚcӮМ‘ж“сҚcҺq
ҸG—ЗҗeүӨ
ӢЖ—ЗҗeүӨ
’ү—ЗҗeүӨ
Ҡо—ЗҗeүӨ
Ҹ~үӨ
Ң№җMҒ@Ң№җM—¬ӮЦ
Ң№ҚOҒ@Ң№ҚO—¬ӮЦ
Ң№ҸнҒ@Ң№Ҹн—¬ӮЦ
Ң№’иҒ[Ң№ҺҠҒ[Ң№Ӣ“Ғ[Ң№ҸҮ
Ң№–ҫҒ@Ң№–ҫ—¬ӮЦ
Ң№җ¶Ғ[Ң№үБҒ[Ң№•Ӯ
Ғ@Ғ@Ғ@Ң№Ң©
2020”N01ҢҺ18“ъ
җҙҳaҢ№ҺҒ
җҙҳaҢ№ҺҒҒiӮ№ӮўӮнӮ°ӮсӮ¶Ғj
‘ж56‘гҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨӮр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№ҺҒҺҒ‘°ӮЕҒAҺ’җ©Қc‘°ӮМҲкӮВҒBҗ©ҒiғJғoғlҒjӮН’©җbҒB

үЖ–дҒ@Қщ—і’_Ғi‘г•\“IӮИүЖ–дҒj
Ғ@Ғ@Ғ@ҠeҒAҢ№ҺҒӮЙӮжӮБӮДҲЩӮИӮйҒB
–{җ©
Ң№’©җb
үЖ‘c
‘ж56‘гҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨ
Һн•К
Қc•К
Ҹoҗg’n
җЫ’ГҚ‘
’ҳ–јӮИҗl•Ё
җҙҳaҢ№ҺҒӮМҗl•ЁҲк——ҺQҸЖ
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
җЫ’ГҢ№ҺҒ
‘еҳaҢ№ҺҒ
үН“аҢ№ҺҒ
Ӯ»ӮМ‘јӮМҺx—¬ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҺеӮИҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҺQҸЖ
ҠT—v
Ң№ҺҒӮЙӮН‘cӮЖӮ·Ӯй“VҚc•КӮЙ21ӮМ—¬”hҒiҢ№ҺҒ“сҸ\Ҳк—¬ҒjӮӘӮ ӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮНӮ»ӮМӮӨӮҝӮМҲкӮВӮЕҗҙҳa“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҺҒ‘°ӮЕӮ ӮйҒB
җҙҳa“VҚcӮМҚcҺqӮМӮӨӮҝ4җlҒA‘·ӮМүӨӮМӮӨӮҝ12җlӮӘҗbҗРҚ~үәӮөӮДҢ№ҺҒӮрҸМӮөӮҪҒB’ҶӮЕӮа‘жҳZҚcҺq’еҸғҗeүӨӮМҺqҒEҢoҠоүӨҒiҢ№ҢoҠоҒjӮМҺq‘·ӮӘ’ҳӮөӮӯ”ЙүhӮөӮҪҒB
’ҶӢүӢM‘°ӮЕӮ ӮБӮҪҢoҠоӮМҺqҒEҢ№–һ’ҮҒi‘Ҫ“c–һ’ҮҒjӮНҒA“ЎҢҙ–kүЖӮМҗЫҠЦҗӯҺЎӮМҠm—§ӮЙӢҰ—НӮөӮД’ҶүӣӮЙӮЁӮҜӮй•җ–еӮЖӮөӮДӮМ’nҲКӮр’zӮ«ҒAҗЫ’ГҚ‘җм•УҢS‘Ҫ“cӮМ’nӮЙ•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮД”ЮӮМҺqӮЕӮ Ӯй—ҠҢхҒA—ҠҗeҒA—ҠҗMӮзӮа•ғӮЖ“Ҝ—lӮЙ“ЎҢҙҗЫҠЦүЖӮЙҺdӮҰӮДҗЁ—НӮрҠg‘еӮөӮҪҒBӮМӮҝӮЙҺе—¬ӮЖӮИӮй—ҠҗM—¬ӮМүН“аҢ№ҺҒӮӘ“ҢҚ‘ӮМ•җҺm’cӮрҺx”zүәӮЙ’uӮўӮД‘д“ӘӮөҒAҢ№—Ҡ’©ӮМ‘гӮЙ•җ–еӮМ“Ҹ—АӮЖӮөӮДҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮ«ҒA•җүЖҗӯҢ ӮрҠm—§ӮөӮҪҒB
Ӯ»ӮМҢгӮМҺq‘·ӮНҒA’„—¬ӮӘҢ№ҺҒҸ«ҢRӮв‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮЖӮөӮД•җүЖҗӯҢ ӮрҺеҚЙӮөӮҪӮЩӮ©ҒAҲк–еӮ©ӮзӮаҺзҢм‘е–јӮвҚ‘җlӮӘҸoӮҪҒBӮЬӮҪҲк•”ӮНҢцӢЁӮЖӮИӮиҒA“°ҸгүЖӮЖӮөӮД’|“аүЖӮӘҸoӮҪҒB
ҸoҺ©
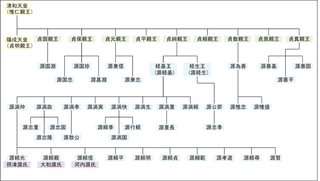
ҸүҠъҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ—ӘҢnҗ}ҒiҢ№–һ’ҮӮМҺqӮЬӮЕҒj
Ҳк”КӮЙ•җүЖӮЖӮөӮД’mӮзӮкӮйҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӢNҢ№ӮНҒAҗҙҳa“VҚcӮМ‘жҳZҚcҺq’еҸғҗeүӨӮМҺqӮЕӮ ӮйҢoҠоүӨҒiҳZ‘·үӨҒjӮӘҗbҗРҚ~үәӮЙӮжӮиҢ№җ©ӮрҺ’ӮиҢ№ҢoҠоӮЖ–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮЙ‘kӮйҒB
—zҗ¬Ң№ҺҒҗа
ҢoҠоүӨӮЙӮВӮўӮДҒA’еҸғҗeүӨӮМҺqӮЕӮНӮИӮӯ’еҸғҗeүӨӮМҢZ—zҗ¬“VҚcӮМҺqҒEҢі•ҪҗeүӨӮМҺqӮЕӮ ӮйӮЖӮ·Ӯй—zҗ¬Ң№ҺҒҗаӮӘӮ ӮйҒBӮұӮМҸoҺ©ҳ_‘ҲӮНҺАҸШӮӘӮЕӮ«ӮёҢҲ’…ӮНӮВӮўӮДӮўӮИӮўҒB
ӮұӮМ—zҗ¬Ң№ҺҒҗаӮН–ҫҺЎӮМ—рҺjҠwҺТҗҜ–мҚPӮӘҒwҺjҠwҺGҺҸҒxӮЙ”ӯ•\ӮөӮҪҳ_•¶ҒuҳZ‘·үӨғnҗҙҳaҢ№ҺҒғj”сғUғӢғmҚlҒvӮЙӮЁӮўӮД’сҸҘӮөӮҪҗаӮЕҒAҒuҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ‘cӮНҺАӮНҗҙҳa“VҚcӮЕӮНӮИӮӯ—zҗ¬“VҚcӮЕӮ ӮйӮӘҒA–\ҢNӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮй—zҗ¬’йӮМ–јӮрҠҘӮ№ӮёҗҙҳaҢ№ҺҒӮр–јҸжӮБӮҪҒvӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBҗОҗҙҗ…”Ә”ҰӢ{вKҠҜ“c’ҶүЖ•¶Ҹ‘ӮМ’ҶӮЙҢ№—ҠҗMӮӘ—_“cҺR—ЛҒiүһҗ_“VҚc—ЛҒjӮЙ”[ӮЯӮҪӮЖҸМӮ·ӮйүiҸіҢі”NҚҗ•¶ӮЙҒuҗжҗlҗV”ӯҒA‘ҙҗжҢoҠоҒA‘ҙҗжҢі•ҪҗeүӨҒA‘ҙҗж—zҗ¬“VҚcҒA‘ҙҗжҗҙҳa“VҚcҒvӮЖ–ҫӢLӮөӮДӮ ӮйӮұӮЖӮӘҚӘӢ’ӮЕӮ ӮйҒB ”ӯ•\“–ҺһӮН”g–дӮр“ҠӮ°Ӯ©ӮҜӮҪӮаӮМӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒA’КҗаӮМҗҙҳaҢ№ҺҒҗаӮр•ўӮөӮҪӮи’·Ӯӯҳ_‘ҲӮЙӮИӮБӮҪӮиӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ӯ»ӮМҢгҒA’|“а—қҺOӮӘүiҸіҢі”NҚҗ•¶ӮрҚm’иӮ·Ӯй[1]ӮЖҒAҸҜҺiҚ_ҒAҗҷӢҙ—І’jҒAүң•xҢh”VҒAҠС’BҗlҒAҢі–Ш‘Ч—YҒA–мҢыҺАӮИӮЗҺxҺқҺТӮӘ‘қӮҰ—L—НӮИүјҗаӮЖӮИӮБӮҪҒB Ҳк•ыӮЕ•уүкҺх’j[2][3]ҒAҗФҚвҚP–ҫ[4]ӮИӮЗӢҢ—ҲӮМҢn•ҲӮӘ‘Г“–ӮЖӮ·Ӯй—§ҸкӮаӮ ӮиҒAҢҲ’…ӮНӮВӮўӮДӮўӮИӮўҒB
Һ^җ¬ӮМ—§ҸкӮЕӮаҗҜ–мҗаӮ»ӮМӮЬӮЬӮЕӮНӮИӮӯҒA’|“аӮН—zҗ¬“VҚcӮМ–\ҢN‘ңӮр•җҺmӮМүЖӮЖӮөӮДӮУӮіӮнӮөӮўӮаӮМӮЖ‘ЁӮҰӮДӮўӮйҒB
ӮЬӮҪҢoҠоҒE’еҸғҗeүӨҒEҢі•ҪҗeүӨӮИӮЗӮМ”N‘гӮЕҳ_Ӯ¶ӮйӮаӮМ[3][5]ӮаӮ ӮйҒBӮҪӮҫӮөҗФҚвӮЙӮжӮБӮДҒAҺj—ҝҗ«ӮМҸгӮЕ–в‘иӮИӮўӮЖӮўӮҰӮИӮўҢnҗ}Һ‘—ҝӮӘҺg—pӮіӮкӮДӮўӮйӮЖҺw“EӮіӮкӮДӮўӮйҒB җФҚвӮНҒA“–ҺһӮМҚc‘°ӮМҸ–ҲК—бҒEҺҒҺЭӮИӮЗӮ©ӮзҗҙҳaҢ№ҺҒҗаӮӘ‘Г“–ӮЖӮ·ӮйҒBӮЬӮҪҒwҢ ӢLҒxӮЙҲш—pӮіӮкӮДӮўӮй“V—п7”NҒi953”NҒjӮМүӨҺҒҺЭ•sҗіҺ–ҢҸӮЙҢ»ӮкӮйҒAҗҙҳa“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮз—zҗ¬“VҚcҺq‘·ӮрҚјҸМӮөӮҪӮЖӮөӮД”ұӮ№ӮзӮкӮҪҢ№Ңo’үӮрҢoҠоӮ ӮйӮўӮНӮ»ӮМҢZ’нӮЖҗ„’иӮөҒA—ҠҗMӮӘҠ蕶ӮЕ—zҗ¬“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНҗ^ҺАӮЕӮ ӮйӮЖҺе’ЈӮөӮД–ј—_үс•ңӮрҗ}ӮБӮҪӮЖүрҺЯӮ·ӮйҒB
ҺК–{ӮЕӮ ӮиҚҗ•¶ӮМ— –КӮЙҚZҗіӮөӮҪӮЖ’AҸ‘Ӯ«ӮӘӮ ӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA•уүкҺх’jӮНӮ»ӮМҗMңЯҗ«ӮрӢ^ӮБӮДӮўӮйҒBҲк•ыҒAҲА“cҢіӢvӮНҗҜ–мҗаӮМҚlҸШӮрҚm’иӮ·ӮйҒAӮҪӮҫӮөҲк‘wҢө–§ӮИҺj—ҝ”б”»ӮӘ•K—vӮЖӮ·ӮйҒBӢ`Қ]ҸІ•vӮаҚЎҚlҸШӮ·Ӯй—]—TӮНӮИӮўӮӘҢ№—ҠҗMӮМҚмӮЙҠФҲбӮўӮИӮўӮЖӮ·Ӯй[6]ҒBҗФҚвӮНҗжҚsҢӨӢҶӮ©ӮзҢгҗўӮМӢUҚмӮЕӮИӮўӮұӮЖӮНҠmҺАӮҫӮӘҢ№—ҠҗMӮЙӮжӮйҚмҲЧӮӘӮ ӮиҺАҚЫӮЖҲЩӮИӮйӮЖӮөӮДӮўӮйҒB
ӮИӮЁҢoҠоӮӘҗҙҳaҢ№ҺҒӮЕӮа—zҗ¬Ң№ҺҒӮЕӮаҒA•җҺmӮМүЖӮЖӮИӮБӮҪҢn“қӮМҗ«ҺҝӮЙҲбӮўӮНӮИӮў[4]ҒBӮЬӮҪҒuҗҙҳaҢ№ҺҒҒvӮНҚLӮӯ–јӮӘ’mӮзӮкӮіӮзӮЙ–јҸМӮЕ–{ҺҝӮН•ПӮнӮзӮИӮўӮҪӮЯҒAҒu—zҗ¬Ң№ҺҒҒvӮЦ–јҸМӮр•ПӮҰӮй•K—vӮНӮИӮўӮЖӮ·ӮйҲУҢ©[7]ӮаӮ ӮйҒB
Ңn•Ҳ
җҙҳaҢ№ҺҒҗаҒFҗҙҳa“VҚcҒ|’еҸғҗeүӨҒ|Ң№ҢoҠоҒ|Ң№–һ’Ү
—zҗ¬Ң№ҺҒҗаҒFҗҙҳa“VҚcҒ|—zҗ¬“VҚcҒ|Ңі•ҪҗeүӨҒ|Ң№ҢoҠоҒ|Ң№–һ’ҮҒ@Ғ@
—рҺj
•җҺm’cӮМҢ`җ¬
ҢoҠоӮМ–јҗХӮрҢpӮўӮҫҢ№–һ’ҮӮН“ЎҢҙҗЫҠЦүЖӮЙҺdӮҰӮДҠe’nӮМҺу—МӮр—р”CҒAҗЫ’ГҚ‘җм•УҢS‘Ҫ“cҒiҢ» •әҢЙҢ§җмҗјҺs‘Ҫ“cҒjӮр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮДҢ№ҺҒ•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBҺр“Ы“¶Һq‘ЮҺЎӮИӮЗӮЕ—L–јӮИ–һ’ҮӮМ’·’jҒEҢ№—ҠҢхӮаҗЫ’ГҚ‘ӮЙӢ’“_Ӯр’uӮўӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҗЫ’ГҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBҗЫ’ГҢ№ҺҒӮМ’ҶӮЕӮа–{Ӣ’ӮЕӮ Ӯй‘Ҫ“cӮрҢpҸіӮөӮҪ’„—¬Ң№—ҠҚjҒi—ҠҢхӮМ‘·ҒjӮМҢn“қӮр‘Ҫ“cҢ№ҺҒӮЖӮўӮӨҒB–һ’ҮӮМҺҹ’jҒEҢ№—ҠҗeӮМҢn“қӮН‘еҳaҚ‘үF–мҒiҢ»“Ю—ЗҢ§ҒjӮр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮ©Ӯз‘еҳaҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҒAҺO’jҒEҢ№—ҠҗMӮМҢn“қӮНүН“аҚ‘’ЩҲдҒiҢ»‘еҚг•{үHүg–мҺs’ЩҲдҒjӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзүН“аҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒB
Ң№ҺҒҲк‘°ӮМ‘ҲӮў
Ң№–һ’ҮӮМҺqӮМ’ҶӮЕӮа“БӮЙҺO’jӮМҢ№—ҠҗMӮНҒA’·ҢіҢі”NҒi1028”NҒj–[‘ҚҺOғJҚ‘ҒiҸг‘ҚҚ‘ҒAүә‘ҚҚ‘ҒAҲА–[Қ‘ҒjӮЕӢNӮ«ӮҪ•Ҫ’үҸнӮМ—җҒi’·ҢіӮМ—җҒjӮр•Ҫ’иӮ·ӮйӮИӮЗӮМ•җҢчӮрҺҰӮ·ҒBӮЬӮҪ—ҠҗMӮМҺqҒE—ҠӢ`ӮНҚN•Ҫ5”NҒi1062”NҒjӮ©Ӯз—ӨүңҚ‘үңҳZҢSӮЙ”ШӢ’Ӯ·ӮйҳШҺъӮМ’·ҒEҲА”{ҺҒӮр“ўӮҝҒi‘OӢг”NӮМ–рҒjҒA—ҠӢ`ӮМҺqҒE”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖӮНҒA“Ҝ‘°ӮМҢ№Қ‘–[ҒAҢ№ҸdҸ@ӮЖҚҮҗнӮрҢJӮиҚLӮ°ҒAҠ°ҺЎҢі”NҒi1087”NҒjӮЙӮНҸoүHҚ‘ӮМҳШҺъ’·ҒEҗҙҢҙҺҒӮМ“а•ҙӮрҺыӮЯӮДҒiҢгҺO”NӮМ–рҒjҗә–]ӮрҚӮӮЯҒA—ҠҗM—¬ӮМүН“аҢ№ҺҒӮН“ҢҚ‘ӮЙ‘«Ҡ|Ӯ©ӮиӮрҺқӮВӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒBүН“аҢ№ҺҒӮНӮұӮМӮжӮӨӮЙ•җ–јӮрҸгӮ°ҒAӮ»ӮкӮЬӮЕӮМҗҙҳaҢ№ҺҒҸҺ—¬ӮЕӮ ӮБӮҪ’nҲКӮ©Ӯз’„—¬ӮМ’nҲКӮрҺ–ҺАҸгҗиӮЯӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮИӢ»—ІӮНҺһӮМҢ —НҺТ”’үН–@ҚcӮМҢxүъӮрҸөӮ«ҒAүН“аҢ№ҺҒӮН—}ҲіӮіӮкӮҪ[8]ҒiӮҪӮҫӮөҒAҢӨӢҶӮМҗi“WӮЕҢ©’јӮөӮӘӮіӮкӮДӮўӮйҒjҒB
үН“аҢ№ҺҒӮӘҗЫ’ГҢ№ҺҒӮМӮжӮӨӮЙӢһ“sӮрҠҲ“®•‘‘дӮЙӮ№Ӯё”В“ҢӮрӢ’“_ӮЖӮөӮҪӮМӮНҒAҢZӮМҢ№—ҠҢхҒAҢ№—ҠҗeӮӘ“ЎҢҙ“№’·ӮЙ‘ӨӢЯӮЖӮөӮДҺdӮҰӮҪӮМӮЙ‘ОӮөҒA—ҠҗMӮНҸг–мүоӮвҸн—ӨүоӮИӮЗү“•ыӮЕҺы“ьӮМҸӯӮИӮў“ҢҚ‘Һу—МӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ Ӯй[9]ҒBӮөӮ©ӮөҒAҸгӢLӮМӮжӮӨӮЙ•җҢчӮрҸdӮЛҒAӢ`үЖҒAӢ`ҚjҒi”ь”ZҺзҒjҒAӢ`ҢхҒiҗV—…ҺOҳYҒjҢZ’нӮМҚ ӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒҚЕ‘еӮМҗЁ—НӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҒiӮҪӮҫӮөҒAӢ`үЖӮЖӢ`ҚjӮМ’ҮӮНҲ«ӮӯҒAӢ`ҚjӮН’ҶүӣӮЕҸёҗiӮрҸdӮЛӮҪҒBҒjҒBӮұӮМҚ ҒAҢ№ҺҒҸҺ—¬ӮНҚ‘ӮМүәӢүҠҜҗlӮрҺ«ӮөҒA’n•ыӮМ‘‘ҠҜӮИӮЗӮЖӮИӮйӮұӮЖӮЙӮжӮиҗЁ—НӮр’zӮўӮДӮўӮБӮҪҒB
ӮөӮ©ӮөҒAӢ`үЖӮМ”У”NӮЙҺҹ’jӮМӢ`җeӮӘ’©’мӮЙ”ҪҚRӮөӮҪӮҪӮЯӢ`үЖӮНӢкӢ«ӮЙӮҪӮҪӮіӮкҒAүН“аҢ№ҺҒӮЙүAӮиӮӘҢ©ӮҰҺnӮЯӮйҒiӢ`үЖӮМ’·’jӮН‘ҒҗўӮөӮДӮўӮҪҒjҒBӮЬӮҪҒA’нӮМҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхҒiҸн—ӨҢ№ҺҒҒAҚb”гҢ№ҺҒӮМ‘cҒjӮЖҺl’jӮМҚrүБүк“ь“№Ӣ`Қ‘ҒiҸг–мҢ№ҺҒҒAүә–мҢ№ҺҒӮМ‘cҒjӮӘүГҸіҢі”NҒi1106”NҒjӮЙҸн—ӨҚҮҗнӮрҲшӮ«ӢNӮұӮөҒA—јҺТӮӘ’әҠЁӮрҺуӮҜӮДӮөӮЬӮӨҒBӮіӮзӮЙ“Vҗm2”NҒi1109”NҒjҒAӢ`үЖӮМҺҖҢгӮЙүЖ“ВӮрҢpҸіӮөүh–јӮрҢЦӮБӮҪҒAӢ`үЖӮМҺO’jҢ№Ӣ`’үӮӘҲГҺEӮіӮкҒA“–ҸүҺ–ҢҸӮМҺе”ЖӮЖӮіӮкӮҪ’нӮМӢ`ҚjҒi”ь”ZҺзҒjӮӘҒA”’үН–@ҚcӮМ–ҪӮрҺуӮҜӮҪҢ№Ӣ`җeӮМҺqҢ№ҲЧӢ`ӮЖҢ№ҢхҚ‘Ғi”ь”ZҢ№ҺҒҒjӮМ“ў”°ӮрҺуӮҜӮДүу–ЕҒAӮЬӮҪҺ–ҢҸҢгҗ^”ЖҗlӮӘҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙӮИӮйӮИӮЗҒAүН“аҢ№ҺҒ“а•”ӮМ•Ә—фӮН–ҫ”’ӮЙӮИӮиҒAҢ җЁӮНӮөӮОӮзӮӯҺё’ДӮөӮҪҒBӮұӮМ”wҢiӮЙӮНҒAүН“аҢ№ҺҒӮӘӢ’ӮиҸҠӮЙӮөӮДӮўӮҪҗЫҠЦүЖӮМҗЫҠЦҗӯҺЎӮ©ӮзҒA”’үН–@ҚcӮМү@җӯӮЦӮМҲЪҚsӮӘӮ ӮБӮҪҒB
җЫҠЦүЖӮЖү@ӮМ‘О—§
Ң№Ӣ`’үӮМҢгӮрҢpӮўӮҫҢ№ҲЧӢ`ӮН”’үН–@ҚcӮЙӢЯҺҳӮөӮҪӮӘҒAҺ©җgҒAҳY“}ҒA”Ә’jҒE’Бҗј”ӘҳYҲЧ’©ӮзӮМ—җҚsӮЕҗM—pӮрҺёӮБӮҪӮҪӮЯҒAҗЫҠЦүЖӮЦҗЪӢЯӮөӮҪҒBҲк•ыӮЕ’·’jӮМҢ№Ӣ`’©ӮН“мҠЦ“ҢӮЙүәҢьӮөӮДҗЁ—НӮрҗLӮОӮөҒA”’үН–@ҚcӮЙҺdӮҰӮД•ғӮЖӮН•КҚs“®ӮрӮЖӮБӮҪҒBӮұӮМҚЫҒA“–ҺһӮМ•җ‘ ҺзҒE“ЎҢҙҗM—ҠӮЙҗЪӢЯӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӢ`’©ӮНҒAӢ`’үӮМ’нӮЕӮ ӮйҸг–мҚ‘ӮЖүә–мҚ‘ӮЙҸҠ—МӮр—LӮ·ӮйҢ№Ӣ`Қ‘ӮЖӮаҢӢӮФӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөҠЦ“ҢӮЕ—НӮрӮВӮҜҒAӮіӮзӮЙү@ӮМүeӢҝүәӮЕӢһ“sӮЦ•ңӢAӮөӮҪҒBҲк•ыҒA•ғҒEҲЧӢ`ӮНӢ`’©ӮМ’нҒEҢ№Ӣ`Ң«ӮрӢ`’©ӮМҺx”zӮМӢyӮОӮИӮў–kҠЦ“ҢӮЦ”hҢӯӮөӮҪҒB’Ғ•ғҺҒӮМ‘ҲӮўӮаӮ©Ӯ©ӮнӮБӮДӢ`Ң«ӮНӢ`’©ӮМ’·’jҒEӢ`•ҪӮЖ‘О—§ӮөӮҪӮӘҒAӢvҺх2”NҒi1155”NҒjӮМ‘е‘ ҚҮҗнӮЕӢ`Ң«ӮӘ“ўҺҖҒAӢ`•Ҫ‘ӨӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪүН“аҢ№ҺҒӮМ“а•ҙӮМҲк•ыӮЕҒA”’үН–@ҚcӮв’№үH–@ҚcӮМ’һҲӨӮрҺуӮҜӮҪҲЙҗЁ•ҪҺҒӮМ•Ҫҗіҗ·ҒE’үҗ·•ғҺqҒA”ь”ZҢ№ҺҒӮМҢ№Ңх•ЫҒEҢхҸ@•ғҺqӮзӮӘ•ңӢ»ӮөҒA•җ–еӮМ’ҶӮЕүН“аҢ№ҺҒӮМҗЁ—НӮН‘Ҡ‘О“IӮЙ’бүәӮөӮДӮўӮБӮҪҒB
Ң№ҲЧӢ`ӮЖӢ`’©ӮМ‘О—§ӮН•ЫҢіҢі”NҒi1156”NҒjӮМ•ЫҢіӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДҢҲ’…Ӯ·ӮйҒB•ғӮв’нӮрҸҲҢYӮөӮҪӢ`’©ӮНҒA“ҜӮ¶ӮӯҢг”’үН–@Қc‘ӨӮЙӮВӮўӮҪүә–мҢ№ҺҒӮМ‘«—ҳӢ`ҚNӮӘӢ}җАӮөӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAҲк‘°ӮрҲі“|ӮөӮДүН“аҢ№ҺҒӮМ‘Қ—МӮМҚАӮЙӮВӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөӢһ“sӮЕӮНҒAҗMҗјҲк–еҒE“сҸр“VҚcҗeҗӯ”hҒEҢг”’үНү@җӯ”hӮЖӮўӮӨғOғӢҒ[ғvӮМ“C—§ҒiӮДӮўӮиӮВҒjӮӘӢNӮұӮиҒA•ҪҺЎҢі”NҒi1160”NҒjҒA“ЎҢҙҗM—ҠӮЖҢӢӮсӮЕӮўӮҪӢ`’©ӮНҢг”’үН–@ҚcӮр—H•ВӮө•ҪҺЎӮМ—җӮрӢNӮұӮ·ҒBҲкҺһ“VүәӮрүдӮӘ•ЁӮЙӮөӮҪӢ`’©ӮҫӮБӮҪӮӘҒA•Ҫҗҙҗ·ӮзӮӘ”й–§— ӮЙ–@ҚcӮзӮрӢ~ҸoӮөӮҪӮұӮЖӮЕҢ`җЁӢt“]ҒA”s‘ЮӮөӮДӢһӮр—ҺӮҝӮД“ҢҚ‘ӮЦҢьӮ©ӮӨҒBӮөӮ©ӮөҒA“№’ҶӮЕ• җSӮМҠҷ“cҗӯҗҙӮМдnҒiӮөӮгӮӨӮЖҒjӮЙӮ ӮҪӮй”ц’ЈҚ‘ӮМ’·“c’ү’vӮМҺиӮЙӮ©Ӯ©ӮБӮДҺEҠQӮіӮкҒAҢ№Ңх•ЫӮзӮаҢг”’үН–@ҚcӮЙӮжӮижnҺEҒiӮҝӮгӮӨӮіӮВҒjӮіӮкӮҪҒB
Ң№•ҪҚҮҗн
ҺЎҸі4”NҒi1180”NҒjҒA•ҪҺҒҗӯҢ ӮЕӮМҚcҲКҢpҸіӮМ•s–һӮ©Ӯз”Ҫ—җӮрҠйҗ}ӮөӮҪҲИҗmүӨӮЙҢ№—ҠҗӯҒiҗЫ’ГҢ№ҺҒҒjӮӘӢҰ—НӮ·ӮйҒiҲИҗmүӨӮМӢ“•әҒjҒBӮұӮМ—җӮНҺё”sӮ·ӮйӮӘҢF–мӮЙҗцӮсӮЕӮўӮҪӢ`’©ӮМ’нӮМҢ№ҚsүЖӮзӮӘҲИҗmүӨӮМ—ЯҺ|Ӯр‘SҚ‘ӮЙ“`ӮҰӮйӮЖҒAүН“аҢ№ҺҒӮМҢ№—Ҡ’©ҒAҢ№ҠуӢ`Ғi“yҚІҠҘҺТҒjҒAҢ№”Н—ҠҒAҢ№Ӣ`ү~ҒAҢ№Ӣ`ҢoӮзҢZ’нӮвҒAҢ№Ӣ`’©ӮМ’нӮМҢ№Ӣ`Ң«ӮМҺqӮЕӮ ӮиҒA—Ҡ’©ӮМҸ]ҢZ’нӮЙӮ ӮҪӮйҢ№Ӣ`’ҮҒi–Ш‘\ҺҹҳYӢ`’ҮҒjҒAҢ№Ӣ`ҢхӮМҺq‘·ӮМ•җ“cҗMӢ`ҒEҲА“cӢ`’иҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒAҺR–{Ӣ`ҢoҒE”җ–ШӢ`Ң“ҒiӢЯҚ]Ң№ҺҒҒjҒAӢ`Қ‘ӮМҺq‘·ӮМ‘«—ҳӢ`җҙҒiүә–мҢ№ҺҒҒjҒAҗV“cҺҒҸҺ—¬ӮМҺR–јӢ`”НҒA—ўҢ©Ӣ`җ¬ҒAӮ»ӮөӮДҗV“cӢ`ҸdҒiҸг–мҢ№ҺҒҒjҒAҗЫ’ГҢ№ҺҒӮЕӮНҒAҢ№—ҠҚjӮр‘cӮЖӮ·Ӯй’„—¬‘Ҫ“cҚsҚjҒi‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒjҒAҢ№—ҠҚjӮМ’нҚ‘–[Ӯр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№Ңх’·Ғi”ь”ZҢ№ҺҒҒjҒA‘еҳaҢ№ҺҒӮЕӮНҒAҢ№җeҺЎӮзӮӘҠe’nӮЕӢ“•әӮөҒA‘ӯӮЙҢ№•ҪҚҮҗнӮЖҢДӮОӮкӮйҺЎҸіҒEҺхүiӮМ—җӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҒB
“–ҸүӮН•ҪүЖӮӘҢ№ҺҒӮрҲі“|ӮөӮДӮЁӮиҒA—Ҡ’©ӮМ’нӮМҠуӢ`ӮӘ”sҺҖӮөӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҺҹ‘жӮЙҢ`җЁӮӘӢt“]ӮөӮД•ҪүЖӮНҢ№Ӣ`’ҮӮЙӢһ“sӮр’ЗӮнӮкӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒAҢ№Ӣ`’ҮҢRӮЖҢ№—Ҡ’©ҢRҒE•ҪүЖӮМҺOӮВ”bӮЖӮИӮБӮҪӮӘ—Ҡ’©ҢRӮӘҲі“|ӮөӮДӮўӮ«ҒAҺхүi3”NҒi1184”NҒjӮЙҲҫ’ГӮМҗнӮўӮЕӢ`’ҮҢRӮрҒAҢі—п2”NҒi1185”NҒjӮЙ’dғmүYӮМҗнӮўӮЕ•ҪүЖӮр–ЕӮЪӮөӮД—Ҡ’©ҢRӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪҒB
Ҡҷ‘qҺһ‘г
•ҪүЖӮМ’З“ўӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪ—Ҡ’©ӮНҒA—җӮМ’ҶӮЕ‘јӮМҢ№ҺҒҲк–еҒiҢ№Ӣ`ҚLҒEҚІ’|ҸGӢ`ҒiҸн—ӨҢ№ҺҒҒjҒAҗV“cӢ`ҸdҒiҸг–мҢ№ҺҒҒjҒA•җ“cҗMӢ`ҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒA‘Ҫ“cҚsҚjҒi‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒjҒA’нӮМҢ№Ӣ`ҢoҒEҢ№”Н—ҠҒjӮр–Е–SӮвҗҠ‘ЮӮіӮ№ҒAүңҸB“ЎҢҙҺҒӮр“ўӮҝҗЁ—НҠо”ХӮрҢЕӮЯӮҪҒB•җүЖҗӯҢ ӮМ‘д“ӘӮрҢҷӮўӮ»ӮМҗЁҲРӮр—}җ§ӮөӮДӮ«ӮҪҢг”’үН–@ҚcӮӘ•цҢдӮ·ӮйӮЖҒAҢҡӢv3”NҒi1192”NҒjӮЙҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙ”CӮәӮзӮкҒAҚЎ“ъӮЕӮўӮӨҠҷ‘q–Ӣ•{ӮӘҗ¬—§ӮөӮҪҒBӮұӮкӮЙӮжӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮӘ•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЕӮ ӮйӮЖ–јҺАӢӨӮЙ”FӮЯӮзӮкӮҪҒB
ӮҪӮҫӮөҢ№—Ҡ’©ӮМҢn“қӮНҒA—Ҡ’©ӮМҺqҒEҢ№ҺА’©ӮӘҢZҢ№—ҠүЖӮМҺqҒEҢцӢЕӮЙҺEҠQӮіӮкӮйҒBӮ»ӮМҢцӢЕӮа•ЯӮзӮҰӮзӮкӮДҸҲҢYҒAҢцӢЕӮМҲЩ•к’нҒE‘TӢЕӮаүБ’SӮр–вӮнӮкҺEӮіӮкҒAӮіӮзӮЙ‘TӢЕӮМ“Ҝ•кҢZҒEүhҺАӮӘҗтҗeҚtӮМ—җӮЙ—i—§ӮіӮкӮйӮӘ—җӮӘҺё”sӮөҺ©ҠQҒAӮ»ӮөӮД’jҢn’jҺqӮЕҚЕҢгӮЬӮЕҺcӮБӮДӮўӮҪ—Ҡ’©ҸҺҺqҒE’еӢЕӮӘ“V•ҹ2”NҒi1231”NҒjӮЙҺҖӢҺӮөӮД’fҗвҒAӮЬӮҪ’jҢnҸ—ҺqӮЕӮа—ҠүЖӮМ–әҒE’|ҢдҸҠӮӘ1234”NҺҖҺYӮЙӮжӮиҺҖӢҺӮөӮҪӮұӮЖӮЕҒAҠ®‘SӮЙ’fҗвӮөӮҪҒB
ӮЬӮҪҒAҠҷ‘q–Ӣ•{ӮЙӮЁӮўӮДҢ№ҺҒҲк–еӮНҒAҢҢ“қӮвҢчҗСӮИӮЗӮЙӮжӮиҢ№җ©ӮрҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӢ–ӮіӮкӮйҒuҢд–е—tҒvӮЖҒAҢ№җ©ӮрҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ“KӮнӮёҒA–јҺҡӮрҸМӮ·ӮйӮаӮМӮЙӢж•КӮіӮкӮҪҒBҢд–е—tӮЙӮНҗM”Z•ҪүкҺҒҒiҗM”ZҢ№ҺҒҒjҒA‘е“аҺҒҒiҗM”ZҢ№ҺҒҒjҒAҲА“cҺҒҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒAүБүк”ьҺҒҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjӮИӮЗӮМҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮМҢn“қҒA‘«—ҳҺҒҒAҺR–јҺҒӮИӮЗӮМҢ№Ӣ`Қ‘ӮМҢn“қӮӘ–јӮрҳAӮЛӮҪӮӘҒA•ҪүкҺҒҒA‘е“аҺҒӮНҒAҸіӢv3”NҒi1221”NҒjӮМҸіӢvӮМ—җӮЙӮжӮи“ҫҸ@үЖӮЙ”sӮк–v—ҺӮөӮҪҒB
Һә’¬Һһ‘гҲИҚ~
Ҡҷ‘q–Ӣ•{––ҠъӮМҚ¬—җҠъӮЙ“ӘҠpӮр•\ӮөӮҪҒAҢ№Ӣ`Қ‘ӮМҺҹ’jҒE‘«—ҳӢ`ҚNӮр‘cӮЖӮ·Ӯй‘«—ҳҺҒӮМ“Ҹ—АҒE‘«—ҳ‘ёҺҒӮНҒAҢ№Ӣ`Қ‘ӮМ’·’jҒEҗV“cӢ`ҸdӮр‘cӮЖӮ·ӮйҗV“cӢ`’еӮзӮМ‘ОҚRҗЁ—НӮр‘ЕӮҝ”jӮиҒA•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЖӮөӮД1338”NӮЙҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙ”CӮ¶ӮзӮкҺә’¬–Ӣ•{ӮрҠJӮӯҒB‘«—ҳӢ`–һӮНҗҙҳaҢ№ҺҒҸoҗgҺТӮЖӮөӮДҸүӮЯӮДҢ№ҺҒ’·ҺТӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢгӮМҸ«ҢRӮӘҢ№ҺҒ’·ҺТӮЖӮИӮй“№ӮрҠJӮўӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒA‘ёҺҒӮМҺq‘·ӮНҠҷ‘qҢц•ыҒAҢГүНҢц•ыҒAҸ¬Ӣ|Ңц•ыҒA–xүzҢц•ыҒAҚдҢц•ыҒAҲў”gҢц•ыӮИӮЗӮЙ•КӮкӮҪҒB
ӮЬӮҪҒA‘«—ҳҺҒҸҺ—¬ӮЕҒuҢдҲкүЖҒvӮЖӮіӮкӮҪӢg—ЗҺҒҒEҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒҒAҒuҺOҠЗ—МҒvӮМҺz”gҺҒҒEҚЧҗмҺҒҒAҒuҺlҗEҒvӮМҲкҗFҺҒӮМ‘јҒAҺR–јҺҒҒiҗV“cҺҒҸҺ—¬ҒjҒA“yҠтҺҒҒi”ь”ZҢ№ҺҒҒjӮӘ’ҶүӣӮЕ‘д“ӘӮөҒA’n•ыӮЕӮНӢгҸB’T‘иӮвҸxүНҒEү“Қ]ҺзҢмӮр—р”CӮөӮҪҚЎҗмҺҒҒiӢg—ЗҺҒҸҺ—¬ҒjҒAүңҸB’T‘иӮМ‘еҚиҺҒҒiҺz”gҺҒҸҺ—¬ҒjҒAүHҸB’T‘иӮМҚЕҸгҺҒҒiҺz”gҺҒҸҺ—¬ҒjӮӘҗЁ—НӮрҗLӮОӮөӮҪҒB
Ӯ»ӮМҢгҒAҗнҚ‘Һһ‘гӮЙӮНҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ––ебӮрҸМӮөӮДүЖҠiӮрҢЦ’ЈӮ·ӮйҺТӮаҸoӮДӮ«ӮҪҒB җҙҳaҢ№ҺҒӮрҸМӮөӮДӮўӮйӢЯҗў‘е–јӮМ‘ҪӮӯӮНҒAӮ»ӮМҺ–ҺАӮӘ—рҺjҠw“IӮЙҸШ–ҫӮіӮкӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBӮҝӮИӮЭӮЙ•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЕӮ ӮйҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМҺТӮөӮ©ӮИӮкӮИӮўӮЖӮўӮӨҗаӮӘӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA“ЎҢҙ—ҠҢoӮЖӮўӮБӮҪҗж—бӮӘ‘¶ҚЭӮөҒAҗD“cҗM’·ӮаҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙҸA”CӮ·ӮйүВ”\җ«ӮӘӮ ӮБӮҪҒiҺOҗEҗ„”C–в‘иҒjҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒAҢ»ҚЭӮЕӮНӮұӮМҗаӮН‘ӯҗаӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB
‘ж56‘гҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨӮр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№ҺҒҺҒ‘°ӮЕҒAҺ’җ©Қc‘°ӮМҲкӮВҒBҗ©ҒiғJғoғlҒjӮН’©җbҒB

үЖ–дҒ@Қщ—і’_Ғi‘г•\“IӮИүЖ–дҒj
Ғ@Ғ@Ғ@ҠeҒAҢ№ҺҒӮЙӮжӮБӮДҲЩӮИӮйҒB
–{җ©
Ң№’©җb
үЖ‘c
‘ж56‘гҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨ
Һн•К
Қc•К
Ҹoҗg’n
җЫ’ГҚ‘
’ҳ–јӮИҗl•Ё
җҙҳaҢ№ҺҒӮМҗl•ЁҲк——ҺQҸЖ
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
җЫ’ГҢ№ҺҒ
‘еҳaҢ№ҺҒ
үН“аҢ№ҺҒ
Ӯ»ӮМ‘јӮМҺx—¬ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҺеӮИҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҺQҸЖ
ҠT—v
Ң№ҺҒӮЙӮН‘cӮЖӮ·Ӯй“VҚc•КӮЙ21ӮМ—¬”hҒiҢ№ҺҒ“сҸ\Ҳк—¬ҒjӮӘӮ ӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮНӮ»ӮМӮӨӮҝӮМҲкӮВӮЕҗҙҳa“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҺҒ‘°ӮЕӮ ӮйҒB
җҙҳa“VҚcӮМҚcҺqӮМӮӨӮҝ4җlҒA‘·ӮМүӨӮМӮӨӮҝ12җlӮӘҗbҗРҚ~үәӮөӮДҢ№ҺҒӮрҸМӮөӮҪҒB’ҶӮЕӮа‘жҳZҚcҺq’еҸғҗeүӨӮМҺqҒEҢoҠоүӨҒiҢ№ҢoҠоҒjӮМҺq‘·ӮӘ’ҳӮөӮӯ”ЙүhӮөӮҪҒB
’ҶӢүӢM‘°ӮЕӮ ӮБӮҪҢoҠоӮМҺqҒEҢ№–һ’ҮҒi‘Ҫ“c–һ’ҮҒjӮНҒA“ЎҢҙ–kүЖӮМҗЫҠЦҗӯҺЎӮМҠm—§ӮЙӢҰ—НӮөӮД’ҶүӣӮЙӮЁӮҜӮй•җ–еӮЖӮөӮДӮМ’nҲКӮр’zӮ«ҒAҗЫ’ГҚ‘җм•УҢS‘Ҫ“cӮМ’nӮЙ•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮД”ЮӮМҺqӮЕӮ Ӯй—ҠҢхҒA—ҠҗeҒA—ҠҗMӮзӮа•ғӮЖ“Ҝ—lӮЙ“ЎҢҙҗЫҠЦүЖӮЙҺdӮҰӮДҗЁ—НӮрҠg‘еӮөӮҪҒBӮМӮҝӮЙҺе—¬ӮЖӮИӮй—ҠҗM—¬ӮМүН“аҢ№ҺҒӮӘ“ҢҚ‘ӮМ•җҺm’cӮрҺx”zүәӮЙ’uӮўӮД‘д“ӘӮөҒAҢ№—Ҡ’©ӮМ‘гӮЙ•җ–еӮМ“Ҹ—АӮЖӮөӮДҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮ«ҒA•җүЖҗӯҢ ӮрҠm—§ӮөӮҪҒB
Ӯ»ӮМҢгӮМҺq‘·ӮНҒA’„—¬ӮӘҢ№ҺҒҸ«ҢRӮв‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮЖӮөӮД•җүЖҗӯҢ ӮрҺеҚЙӮөӮҪӮЩӮ©ҒAҲк–еӮ©ӮзӮаҺзҢм‘е–јӮвҚ‘җlӮӘҸoӮҪҒBӮЬӮҪҲк•”ӮНҢцӢЁӮЖӮИӮиҒA“°ҸгүЖӮЖӮөӮД’|“аүЖӮӘҸoӮҪҒB
ҸoҺ©
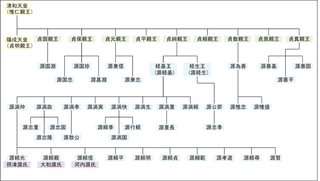
ҸүҠъҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ—ӘҢnҗ}ҒiҢ№–һ’ҮӮМҺqӮЬӮЕҒj
Ҳк”КӮЙ•җүЖӮЖӮөӮД’mӮзӮкӮйҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӢNҢ№ӮНҒAҗҙҳa“VҚcӮМ‘жҳZҚcҺq’еҸғҗeүӨӮМҺqӮЕӮ ӮйҢoҠоүӨҒiҳZ‘·үӨҒjӮӘҗbҗРҚ~үәӮЙӮжӮиҢ№җ©ӮрҺ’ӮиҢ№ҢoҠоӮЖ–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮЙ‘kӮйҒB
—zҗ¬Ң№ҺҒҗа
ҢoҠоүӨӮЙӮВӮўӮДҒA’еҸғҗeүӨӮМҺqӮЕӮНӮИӮӯ’еҸғҗeүӨӮМҢZ—zҗ¬“VҚcӮМҺqҒEҢі•ҪҗeүӨӮМҺqӮЕӮ ӮйӮЖӮ·Ӯй—zҗ¬Ң№ҺҒҗаӮӘӮ ӮйҒBӮұӮМҸoҺ©ҳ_‘ҲӮНҺАҸШӮӘӮЕӮ«ӮёҢҲ’…ӮНӮВӮўӮДӮўӮИӮўҒB
ӮұӮМ—zҗ¬Ң№ҺҒҗаӮН–ҫҺЎӮМ—рҺjҠwҺТҗҜ–мҚPӮӘҒwҺjҠwҺGҺҸҒxӮЙ”ӯ•\ӮөӮҪҳ_•¶ҒuҳZ‘·үӨғnҗҙҳaҢ№ҺҒғj”сғUғӢғmҚlҒvӮЙӮЁӮўӮД’сҸҘӮөӮҪҗаӮЕҒAҒuҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ‘cӮНҺАӮНҗҙҳa“VҚcӮЕӮНӮИӮӯ—zҗ¬“VҚcӮЕӮ ӮйӮӘҒA–\ҢNӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮй—zҗ¬’йӮМ–јӮрҠҘӮ№ӮёҗҙҳaҢ№ҺҒӮр–јҸжӮБӮҪҒvӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBҗОҗҙҗ…”Ә”ҰӢ{вKҠҜ“c’ҶүЖ•¶Ҹ‘ӮМ’ҶӮЙҢ№—ҠҗMӮӘ—_“cҺR—ЛҒiүһҗ_“VҚc—ЛҒjӮЙ”[ӮЯӮҪӮЖҸМӮ·ӮйүiҸіҢі”NҚҗ•¶ӮЙҒuҗжҗlҗV”ӯҒA‘ҙҗжҢoҠоҒA‘ҙҗжҢі•ҪҗeүӨҒA‘ҙҗж—zҗ¬“VҚcҒA‘ҙҗжҗҙҳa“VҚcҒvӮЖ–ҫӢLӮөӮДӮ ӮйӮұӮЖӮӘҚӘӢ’ӮЕӮ ӮйҒB ”ӯ•\“–ҺһӮН”g–дӮр“ҠӮ°Ӯ©ӮҜӮҪӮаӮМӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒA’КҗаӮМҗҙҳaҢ№ҺҒҗаӮр•ўӮөӮҪӮи’·Ӯӯҳ_‘ҲӮЙӮИӮБӮҪӮиӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ӯ»ӮМҢгҒA’|“а—қҺOӮӘүiҸіҢі”NҚҗ•¶ӮрҚm’иӮ·Ӯй[1]ӮЖҒAҸҜҺiҚ_ҒAҗҷӢҙ—І’jҒAүң•xҢh”VҒAҠС’BҗlҒAҢі–Ш‘Ч—YҒA–мҢыҺАӮИӮЗҺxҺқҺТӮӘ‘қӮҰ—L—НӮИүјҗаӮЖӮИӮБӮҪҒB Ҳк•ыӮЕ•уүкҺх’j[2][3]ҒAҗФҚвҚP–ҫ[4]ӮИӮЗӢҢ—ҲӮМҢn•ҲӮӘ‘Г“–ӮЖӮ·Ӯй—§ҸкӮаӮ ӮиҒAҢҲ’…ӮНӮВӮўӮДӮўӮИӮўҒB
Һ^җ¬ӮМ—§ҸкӮЕӮаҗҜ–мҗаӮ»ӮМӮЬӮЬӮЕӮНӮИӮӯҒA’|“аӮН—zҗ¬“VҚcӮМ–\ҢN‘ңӮр•җҺmӮМүЖӮЖӮөӮДӮУӮіӮнӮөӮўӮаӮМӮЖ‘ЁӮҰӮДӮўӮйҒB
ӮЬӮҪҢoҠоҒE’еҸғҗeүӨҒEҢі•ҪҗeүӨӮИӮЗӮМ”N‘гӮЕҳ_Ӯ¶ӮйӮаӮМ[3][5]ӮаӮ ӮйҒBӮҪӮҫӮөҗФҚвӮЙӮжӮБӮДҒAҺj—ҝҗ«ӮМҸгӮЕ–в‘иӮИӮўӮЖӮўӮҰӮИӮўҢnҗ}Һ‘—ҝӮӘҺg—pӮіӮкӮДӮўӮйӮЖҺw“EӮіӮкӮДӮўӮйҒB җФҚвӮНҒA“–ҺһӮМҚc‘°ӮМҸ–ҲК—бҒEҺҒҺЭӮИӮЗӮ©ӮзҗҙҳaҢ№ҺҒҗаӮӘ‘Г“–ӮЖӮ·ӮйҒBӮЬӮҪҒwҢ ӢLҒxӮЙҲш—pӮіӮкӮДӮўӮй“V—п7”NҒi953”NҒjӮМүӨҺҒҺЭ•sҗіҺ–ҢҸӮЙҢ»ӮкӮйҒAҗҙҳa“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮз—zҗ¬“VҚcҺq‘·ӮрҚјҸМӮөӮҪӮЖӮөӮД”ұӮ№ӮзӮкӮҪҢ№Ңo’үӮрҢoҠоӮ ӮйӮўӮНӮ»ӮМҢZ’нӮЖҗ„’иӮөҒA—ҠҗMӮӘҠ蕶ӮЕ—zҗ¬“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНҗ^ҺАӮЕӮ ӮйӮЖҺе’ЈӮөӮД–ј—_үс•ңӮрҗ}ӮБӮҪӮЖүрҺЯӮ·ӮйҒB
ҺК–{ӮЕӮ ӮиҚҗ•¶ӮМ— –КӮЙҚZҗіӮөӮҪӮЖ’AҸ‘Ӯ«ӮӘӮ ӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA•уүкҺх’jӮНӮ»ӮМҗMңЯҗ«ӮрӢ^ӮБӮДӮўӮйҒBҲк•ыҒAҲА“cҢіӢvӮНҗҜ–мҗаӮМҚlҸШӮрҚm’иӮ·ӮйҒAӮҪӮҫӮөҲк‘wҢө–§ӮИҺj—ҝ”б”»ӮӘ•K—vӮЖӮ·ӮйҒBӢ`Қ]ҸІ•vӮаҚЎҚlҸШӮ·Ӯй—]—TӮНӮИӮўӮӘҢ№—ҠҗMӮМҚмӮЙҠФҲбӮўӮИӮўӮЖӮ·Ӯй[6]ҒBҗФҚвӮНҗжҚsҢӨӢҶӮ©ӮзҢгҗўӮМӢUҚмӮЕӮИӮўӮұӮЖӮНҠmҺАӮҫӮӘҢ№—ҠҗMӮЙӮжӮйҚмҲЧӮӘӮ ӮиҺАҚЫӮЖҲЩӮИӮйӮЖӮөӮДӮўӮйҒB
ӮИӮЁҢoҠоӮӘҗҙҳaҢ№ҺҒӮЕӮа—zҗ¬Ң№ҺҒӮЕӮаҒA•җҺmӮМүЖӮЖӮИӮБӮҪҢn“қӮМҗ«ҺҝӮЙҲбӮўӮНӮИӮў[4]ҒBӮЬӮҪҒuҗҙҳaҢ№ҺҒҒvӮНҚLӮӯ–јӮӘ’mӮзӮкӮіӮзӮЙ–јҸМӮЕ–{ҺҝӮН•ПӮнӮзӮИӮўӮҪӮЯҒAҒu—zҗ¬Ң№ҺҒҒvӮЦ–јҸМӮр•ПӮҰӮй•K—vӮНӮИӮўӮЖӮ·ӮйҲУҢ©[7]ӮаӮ ӮйҒB
Ңn•Ҳ
җҙҳaҢ№ҺҒҗаҒFҗҙҳa“VҚcҒ|’еҸғҗeүӨҒ|Ң№ҢoҠоҒ|Ң№–һ’Ү
—zҗ¬Ң№ҺҒҗаҒFҗҙҳa“VҚcҒ|—zҗ¬“VҚcҒ|Ңі•ҪҗeүӨҒ|Ң№ҢoҠоҒ|Ң№–һ’ҮҒ@Ғ@
—рҺj
•җҺm’cӮМҢ`җ¬
ҢoҠоӮМ–јҗХӮрҢpӮўӮҫҢ№–һ’ҮӮН“ЎҢҙҗЫҠЦүЖӮЙҺdӮҰӮДҠe’nӮМҺу—МӮр—р”CҒAҗЫ’ГҚ‘җм•УҢS‘Ҫ“cҒiҢ» •әҢЙҢ§җмҗјҺs‘Ҫ“cҒjӮр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮДҢ№ҺҒ•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBҺр“Ы“¶Һq‘ЮҺЎӮИӮЗӮЕ—L–јӮИ–һ’ҮӮМ’·’jҒEҢ№—ҠҢхӮаҗЫ’ГҚ‘ӮЙӢ’“_Ӯр’uӮўӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҗЫ’ГҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBҗЫ’ГҢ№ҺҒӮМ’ҶӮЕӮа–{Ӣ’ӮЕӮ Ӯй‘Ҫ“cӮрҢpҸіӮөӮҪ’„—¬Ң№—ҠҚjҒi—ҠҢхӮМ‘·ҒjӮМҢn“қӮр‘Ҫ“cҢ№ҺҒӮЖӮўӮӨҒB–һ’ҮӮМҺҹ’jҒEҢ№—ҠҗeӮМҢn“қӮН‘еҳaҚ‘үF–мҒiҢ»“Ю—ЗҢ§ҒjӮр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮ©Ӯз‘еҳaҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҒAҺO’jҒEҢ№—ҠҗMӮМҢn“қӮНүН“аҚ‘’ЩҲдҒiҢ»‘еҚг•{үHүg–мҺs’ЩҲдҒjӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзүН“аҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒB
Ң№ҺҒҲк‘°ӮМ‘ҲӮў
Ң№–һ’ҮӮМҺqӮМ’ҶӮЕӮа“БӮЙҺO’jӮМҢ№—ҠҗMӮНҒA’·ҢіҢі”NҒi1028”NҒj–[‘ҚҺOғJҚ‘ҒiҸг‘ҚҚ‘ҒAүә‘ҚҚ‘ҒAҲА–[Қ‘ҒjӮЕӢNӮ«ӮҪ•Ҫ’үҸнӮМ—җҒi’·ҢіӮМ—җҒjӮр•Ҫ’иӮ·ӮйӮИӮЗӮМ•җҢчӮрҺҰӮ·ҒBӮЬӮҪ—ҠҗMӮМҺqҒE—ҠӢ`ӮНҚN•Ҫ5”NҒi1062”NҒjӮ©Ӯз—ӨүңҚ‘үңҳZҢSӮЙ”ШӢ’Ӯ·ӮйҳШҺъӮМ’·ҒEҲА”{ҺҒӮр“ўӮҝҒi‘OӢг”NӮМ–рҒjҒA—ҠӢ`ӮМҺqҒE”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖӮНҒA“Ҝ‘°ӮМҢ№Қ‘–[ҒAҢ№ҸdҸ@ӮЖҚҮҗнӮрҢJӮиҚLӮ°ҒAҠ°ҺЎҢі”NҒi1087”NҒjӮЙӮНҸoүHҚ‘ӮМҳШҺъ’·ҒEҗҙҢҙҺҒӮМ“а•ҙӮрҺыӮЯӮДҒiҢгҺO”NӮМ–рҒjҗә–]ӮрҚӮӮЯҒA—ҠҗM—¬ӮМүН“аҢ№ҺҒӮН“ҢҚ‘ӮЙ‘«Ҡ|Ӯ©ӮиӮрҺқӮВӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒBүН“аҢ№ҺҒӮНӮұӮМӮжӮӨӮЙ•җ–јӮрҸгӮ°ҒAӮ»ӮкӮЬӮЕӮМҗҙҳaҢ№ҺҒҸҺ—¬ӮЕӮ ӮБӮҪ’nҲКӮ©Ӯз’„—¬ӮМ’nҲКӮрҺ–ҺАҸгҗиӮЯӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮИӢ»—ІӮНҺһӮМҢ —НҺТ”’үН–@ҚcӮМҢxүъӮрҸөӮ«ҒAүН“аҢ№ҺҒӮН—}ҲіӮіӮкӮҪ[8]ҒiӮҪӮҫӮөҒAҢӨӢҶӮМҗi“WӮЕҢ©’јӮөӮӘӮіӮкӮДӮўӮйҒjҒB
үН“аҢ№ҺҒӮӘҗЫ’ГҢ№ҺҒӮМӮжӮӨӮЙӢһ“sӮрҠҲ“®•‘‘дӮЙӮ№Ӯё”В“ҢӮрӢ’“_ӮЖӮөӮҪӮМӮНҒAҢZӮМҢ№—ҠҢхҒAҢ№—ҠҗeӮӘ“ЎҢҙ“№’·ӮЙ‘ӨӢЯӮЖӮөӮДҺdӮҰӮҪӮМӮЙ‘ОӮөҒA—ҠҗMӮНҸг–мүоӮвҸн—ӨүоӮИӮЗү“•ыӮЕҺы“ьӮМҸӯӮИӮў“ҢҚ‘Һу—МӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ Ӯй[9]ҒBӮөӮ©ӮөҒAҸгӢLӮМӮжӮӨӮЙ•җҢчӮрҸdӮЛҒAӢ`үЖҒAӢ`ҚjҒi”ь”ZҺзҒjҒAӢ`ҢхҒiҗV—…ҺOҳYҒjҢZ’нӮМҚ ӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒҚЕ‘еӮМҗЁ—НӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҒiӮҪӮҫӮөҒAӢ`үЖӮЖӢ`ҚjӮМ’ҮӮНҲ«ӮӯҒAӢ`ҚjӮН’ҶүӣӮЕҸёҗiӮрҸdӮЛӮҪҒBҒjҒBӮұӮМҚ ҒAҢ№ҺҒҸҺ—¬ӮНҚ‘ӮМүәӢүҠҜҗlӮрҺ«ӮөҒA’n•ыӮМ‘‘ҠҜӮИӮЗӮЖӮИӮйӮұӮЖӮЙӮжӮиҗЁ—НӮр’zӮўӮДӮўӮБӮҪҒB
ӮөӮ©ӮөҒAӢ`үЖӮМ”У”NӮЙҺҹ’jӮМӢ`җeӮӘ’©’мӮЙ”ҪҚRӮөӮҪӮҪӮЯӢ`үЖӮНӢкӢ«ӮЙӮҪӮҪӮіӮкҒAүН“аҢ№ҺҒӮЙүAӮиӮӘҢ©ӮҰҺnӮЯӮйҒiӢ`үЖӮМ’·’jӮН‘ҒҗўӮөӮДӮўӮҪҒjҒBӮЬӮҪҒA’нӮМҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхҒiҸн—ӨҢ№ҺҒҒAҚb”гҢ№ҺҒӮМ‘cҒjӮЖҺl’jӮМҚrүБүк“ь“№Ӣ`Қ‘ҒiҸг–мҢ№ҺҒҒAүә–мҢ№ҺҒӮМ‘cҒjӮӘүГҸіҢі”NҒi1106”NҒjӮЙҸн—ӨҚҮҗнӮрҲшӮ«ӢNӮұӮөҒA—јҺТӮӘ’әҠЁӮрҺуӮҜӮДӮөӮЬӮӨҒBӮіӮзӮЙ“Vҗm2”NҒi1109”NҒjҒAӢ`үЖӮМҺҖҢгӮЙүЖ“ВӮрҢpҸіӮөүh–јӮрҢЦӮБӮҪҒAӢ`үЖӮМҺO’jҢ№Ӣ`’үӮӘҲГҺEӮіӮкҒA“–ҸүҺ–ҢҸӮМҺе”ЖӮЖӮіӮкӮҪ’нӮМӢ`ҚjҒi”ь”ZҺзҒjӮӘҒA”’үН–@ҚcӮМ–ҪӮрҺуӮҜӮҪҢ№Ӣ`җeӮМҺqҢ№ҲЧӢ`ӮЖҢ№ҢхҚ‘Ғi”ь”ZҢ№ҺҒҒjӮМ“ў”°ӮрҺуӮҜӮДүу–ЕҒAӮЬӮҪҺ–ҢҸҢгҗ^”ЖҗlӮӘҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙӮИӮйӮИӮЗҒAүН“аҢ№ҺҒ“а•”ӮМ•Ә—фӮН–ҫ”’ӮЙӮИӮиҒAҢ җЁӮНӮөӮОӮзӮӯҺё’ДӮөӮҪҒBӮұӮМ”wҢiӮЙӮНҒAүН“аҢ№ҺҒӮӘӢ’ӮиҸҠӮЙӮөӮДӮўӮҪҗЫҠЦүЖӮМҗЫҠЦҗӯҺЎӮ©ӮзҒA”’үН–@ҚcӮМү@җӯӮЦӮМҲЪҚsӮӘӮ ӮБӮҪҒB
җЫҠЦүЖӮЖү@ӮМ‘О—§
Ң№Ӣ`’үӮМҢгӮрҢpӮўӮҫҢ№ҲЧӢ`ӮН”’үН–@ҚcӮЙӢЯҺҳӮөӮҪӮӘҒAҺ©җgҒAҳY“}ҒA”Ә’jҒE’Бҗј”ӘҳYҲЧ’©ӮзӮМ—җҚsӮЕҗM—pӮрҺёӮБӮҪӮҪӮЯҒAҗЫҠЦүЖӮЦҗЪӢЯӮөӮҪҒBҲк•ыӮЕ’·’jӮМҢ№Ӣ`’©ӮН“мҠЦ“ҢӮЙүәҢьӮөӮДҗЁ—НӮрҗLӮОӮөҒA”’үН–@ҚcӮЙҺdӮҰӮД•ғӮЖӮН•КҚs“®ӮрӮЖӮБӮҪҒBӮұӮМҚЫҒA“–ҺһӮМ•җ‘ ҺзҒE“ЎҢҙҗM—ҠӮЙҗЪӢЯӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӢ`’©ӮНҒAӢ`’үӮМ’нӮЕӮ ӮйҸг–мҚ‘ӮЖүә–мҚ‘ӮЙҸҠ—МӮр—LӮ·ӮйҢ№Ӣ`Қ‘ӮЖӮаҢӢӮФӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөҠЦ“ҢӮЕ—НӮрӮВӮҜҒAӮіӮзӮЙү@ӮМүeӢҝүәӮЕӢһ“sӮЦ•ңӢAӮөӮҪҒBҲк•ыҒA•ғҒEҲЧӢ`ӮНӢ`’©ӮМ’нҒEҢ№Ӣ`Ң«ӮрӢ`’©ӮМҺx”zӮМӢyӮОӮИӮў–kҠЦ“ҢӮЦ”hҢӯӮөӮҪҒB’Ғ•ғҺҒӮМ‘ҲӮўӮаӮ©Ӯ©ӮнӮБӮДӢ`Ң«ӮНӢ`’©ӮМ’·’jҒEӢ`•ҪӮЖ‘О—§ӮөӮҪӮӘҒAӢvҺх2”NҒi1155”NҒjӮМ‘е‘ ҚҮҗнӮЕӢ`Ң«ӮӘ“ўҺҖҒAӢ`•Ҫ‘ӨӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪүН“аҢ№ҺҒӮМ“а•ҙӮМҲк•ыӮЕҒA”’үН–@ҚcӮв’№үH–@ҚcӮМ’һҲӨӮрҺуӮҜӮҪҲЙҗЁ•ҪҺҒӮМ•Ҫҗіҗ·ҒE’үҗ·•ғҺqҒA”ь”ZҢ№ҺҒӮМҢ№Ңх•ЫҒEҢхҸ@•ғҺqӮзӮӘ•ңӢ»ӮөҒA•җ–еӮМ’ҶӮЕүН“аҢ№ҺҒӮМҗЁ—НӮН‘Ҡ‘О“IӮЙ’бүәӮөӮДӮўӮБӮҪҒB
Ң№ҲЧӢ`ӮЖӢ`’©ӮМ‘О—§ӮН•ЫҢіҢі”NҒi1156”NҒjӮМ•ЫҢіӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДҢҲ’…Ӯ·ӮйҒB•ғӮв’нӮрҸҲҢYӮөӮҪӢ`’©ӮНҒA“ҜӮ¶ӮӯҢг”’үН–@Қc‘ӨӮЙӮВӮўӮҪүә–мҢ№ҺҒӮМ‘«—ҳӢ`ҚNӮӘӢ}җАӮөӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAҲк‘°ӮрҲі“|ӮөӮДүН“аҢ№ҺҒӮМ‘Қ—МӮМҚАӮЙӮВӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөӢһ“sӮЕӮНҒAҗMҗјҲк–еҒE“сҸр“VҚcҗeҗӯ”hҒEҢг”’үНү@җӯ”hӮЖӮўӮӨғOғӢҒ[ғvӮМ“C—§ҒiӮДӮўӮиӮВҒjӮӘӢNӮұӮиҒA•ҪҺЎҢі”NҒi1160”NҒjҒA“ЎҢҙҗM—ҠӮЖҢӢӮсӮЕӮўӮҪӢ`’©ӮНҢг”’үН–@ҚcӮр—H•ВӮө•ҪҺЎӮМ—җӮрӢNӮұӮ·ҒBҲкҺһ“VүәӮрүдӮӘ•ЁӮЙӮөӮҪӢ`’©ӮҫӮБӮҪӮӘҒA•Ҫҗҙҗ·ӮзӮӘ”й–§— ӮЙ–@ҚcӮзӮрӢ~ҸoӮөӮҪӮұӮЖӮЕҢ`җЁӢt“]ҒA”s‘ЮӮөӮДӢһӮр—ҺӮҝӮД“ҢҚ‘ӮЦҢьӮ©ӮӨҒBӮөӮ©ӮөҒA“№’ҶӮЕ• җSӮМҠҷ“cҗӯҗҙӮМдnҒiӮөӮгӮӨӮЖҒjӮЙӮ ӮҪӮй”ц’ЈҚ‘ӮМ’·“c’ү’vӮМҺиӮЙӮ©Ӯ©ӮБӮДҺEҠQӮіӮкҒAҢ№Ңх•ЫӮзӮаҢг”’үН–@ҚcӮЙӮжӮижnҺEҒiӮҝӮгӮӨӮіӮВҒjӮіӮкӮҪҒB
Ң№•ҪҚҮҗн
ҺЎҸі4”NҒi1180”NҒjҒA•ҪҺҒҗӯҢ ӮЕӮМҚcҲКҢpҸіӮМ•s–һӮ©Ӯз”Ҫ—җӮрҠйҗ}ӮөӮҪҲИҗmүӨӮЙҢ№—ҠҗӯҒiҗЫ’ГҢ№ҺҒҒjӮӘӢҰ—НӮ·ӮйҒiҲИҗmүӨӮМӢ“•әҒjҒBӮұӮМ—җӮНҺё”sӮ·ӮйӮӘҢF–мӮЙҗцӮсӮЕӮўӮҪӢ`’©ӮМ’нӮМҢ№ҚsүЖӮзӮӘҲИҗmүӨӮМ—ЯҺ|Ӯр‘SҚ‘ӮЙ“`ӮҰӮйӮЖҒAүН“аҢ№ҺҒӮМҢ№—Ҡ’©ҒAҢ№ҠуӢ`Ғi“yҚІҠҘҺТҒjҒAҢ№”Н—ҠҒAҢ№Ӣ`ү~ҒAҢ№Ӣ`ҢoӮзҢZ’нӮвҒAҢ№Ӣ`’©ӮМ’нӮМҢ№Ӣ`Ң«ӮМҺqӮЕӮ ӮиҒA—Ҡ’©ӮМҸ]ҢZ’нӮЙӮ ӮҪӮйҢ№Ӣ`’ҮҒi–Ш‘\ҺҹҳYӢ`’ҮҒjҒAҢ№Ӣ`ҢхӮМҺq‘·ӮМ•җ“cҗMӢ`ҒEҲА“cӢ`’иҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒAҺR–{Ӣ`ҢoҒE”җ–ШӢ`Ң“ҒiӢЯҚ]Ң№ҺҒҒjҒAӢ`Қ‘ӮМҺq‘·ӮМ‘«—ҳӢ`җҙҒiүә–мҢ№ҺҒҒjҒAҗV“cҺҒҸҺ—¬ӮМҺR–јӢ`”НҒA—ўҢ©Ӣ`җ¬ҒAӮ»ӮөӮДҗV“cӢ`ҸdҒiҸг–мҢ№ҺҒҒjҒAҗЫ’ГҢ№ҺҒӮЕӮНҒAҢ№—ҠҚjӮр‘cӮЖӮ·Ӯй’„—¬‘Ҫ“cҚsҚjҒi‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒjҒAҢ№—ҠҚjӮМ’нҚ‘–[Ӯр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№Ңх’·Ғi”ь”ZҢ№ҺҒҒjҒA‘еҳaҢ№ҺҒӮЕӮНҒAҢ№җeҺЎӮзӮӘҠe’nӮЕӢ“•әӮөҒA‘ӯӮЙҢ№•ҪҚҮҗнӮЖҢДӮОӮкӮйҺЎҸіҒEҺхүiӮМ—җӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҒB
“–ҸүӮН•ҪүЖӮӘҢ№ҺҒӮрҲі“|ӮөӮДӮЁӮиҒA—Ҡ’©ӮМ’нӮМҠуӢ`ӮӘ”sҺҖӮөӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҺҹ‘жӮЙҢ`җЁӮӘӢt“]ӮөӮД•ҪүЖӮНҢ№Ӣ`’ҮӮЙӢһ“sӮр’ЗӮнӮкӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒAҢ№Ӣ`’ҮҢRӮЖҢ№—Ҡ’©ҢRҒE•ҪүЖӮМҺOӮВ”bӮЖӮИӮБӮҪӮӘ—Ҡ’©ҢRӮӘҲі“|ӮөӮДӮўӮ«ҒAҺхүi3”NҒi1184”NҒjӮЙҲҫ’ГӮМҗнӮўӮЕӢ`’ҮҢRӮрҒAҢі—п2”NҒi1185”NҒjӮЙ’dғmүYӮМҗнӮўӮЕ•ҪүЖӮр–ЕӮЪӮөӮД—Ҡ’©ҢRӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪҒB
Ҡҷ‘qҺһ‘г
•ҪүЖӮМ’З“ўӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪ—Ҡ’©ӮНҒA—җӮМ’ҶӮЕ‘јӮМҢ№ҺҒҲк–еҒiҢ№Ӣ`ҚLҒEҚІ’|ҸGӢ`ҒiҸн—ӨҢ№ҺҒҒjҒAҗV“cӢ`ҸdҒiҸг–мҢ№ҺҒҒjҒA•җ“cҗMӢ`ҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒA‘Ҫ“cҚsҚjҒi‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒjҒA’нӮМҢ№Ӣ`ҢoҒEҢ№”Н—ҠҒjӮр–Е–SӮвҗҠ‘ЮӮіӮ№ҒAүңҸB“ЎҢҙҺҒӮр“ўӮҝҗЁ—НҠо”ХӮрҢЕӮЯӮҪҒB•җүЖҗӯҢ ӮМ‘д“ӘӮрҢҷӮўӮ»ӮМҗЁҲРӮр—}җ§ӮөӮДӮ«ӮҪҢг”’үН–@ҚcӮӘ•цҢдӮ·ӮйӮЖҒAҢҡӢv3”NҒi1192”NҒjӮЙҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙ”CӮәӮзӮкҒAҚЎ“ъӮЕӮўӮӨҠҷ‘q–Ӣ•{ӮӘҗ¬—§ӮөӮҪҒBӮұӮкӮЙӮжӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮӘ•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЕӮ ӮйӮЖ–јҺАӢӨӮЙ”FӮЯӮзӮкӮҪҒB
ӮҪӮҫӮөҢ№—Ҡ’©ӮМҢn“қӮНҒA—Ҡ’©ӮМҺqҒEҢ№ҺА’©ӮӘҢZҢ№—ҠүЖӮМҺqҒEҢцӢЕӮЙҺEҠQӮіӮкӮйҒBӮ»ӮМҢцӢЕӮа•ЯӮзӮҰӮзӮкӮДҸҲҢYҒAҢцӢЕӮМҲЩ•к’нҒE‘TӢЕӮаүБ’SӮр–вӮнӮкҺEӮіӮкҒAӮіӮзӮЙ‘TӢЕӮМ“Ҝ•кҢZҒEүhҺАӮӘҗтҗeҚtӮМ—җӮЙ—i—§ӮіӮкӮйӮӘ—җӮӘҺё”sӮөҺ©ҠQҒAӮ»ӮөӮД’jҢn’jҺqӮЕҚЕҢгӮЬӮЕҺcӮБӮДӮўӮҪ—Ҡ’©ҸҺҺqҒE’еӢЕӮӘ“V•ҹ2”NҒi1231”NҒjӮЙҺҖӢҺӮөӮД’fҗвҒAӮЬӮҪ’jҢnҸ—ҺqӮЕӮа—ҠүЖӮМ–әҒE’|ҢдҸҠӮӘ1234”NҺҖҺYӮЙӮжӮиҺҖӢҺӮөӮҪӮұӮЖӮЕҒAҠ®‘SӮЙ’fҗвӮөӮҪҒB
ӮЬӮҪҒAҠҷ‘q–Ӣ•{ӮЙӮЁӮўӮДҢ№ҺҒҲк–еӮНҒAҢҢ“қӮвҢчҗСӮИӮЗӮЙӮжӮиҢ№җ©ӮрҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӢ–ӮіӮкӮйҒuҢд–е—tҒvӮЖҒAҢ№җ©ӮрҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ“KӮнӮёҒA–јҺҡӮрҸМӮ·ӮйӮаӮМӮЙӢж•КӮіӮкӮҪҒBҢд–е—tӮЙӮНҗM”Z•ҪүкҺҒҒiҗM”ZҢ№ҺҒҒjҒA‘е“аҺҒҒiҗM”ZҢ№ҺҒҒjҒAҲА“cҺҒҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒAүБүк”ьҺҒҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjӮИӮЗӮМҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮМҢn“қҒA‘«—ҳҺҒҒAҺR–јҺҒӮИӮЗӮМҢ№Ӣ`Қ‘ӮМҢn“қӮӘ–јӮрҳAӮЛӮҪӮӘҒA•ҪүкҺҒҒA‘е“аҺҒӮНҒAҸіӢv3”NҒi1221”NҒjӮМҸіӢvӮМ—җӮЙӮжӮи“ҫҸ@үЖӮЙ”sӮк–v—ҺӮөӮҪҒB
Һә’¬Һһ‘гҲИҚ~
Ҡҷ‘q–Ӣ•{––ҠъӮМҚ¬—җҠъӮЙ“ӘҠpӮр•\ӮөӮҪҒAҢ№Ӣ`Қ‘ӮМҺҹ’jҒE‘«—ҳӢ`ҚNӮр‘cӮЖӮ·Ӯй‘«—ҳҺҒӮМ“Ҹ—АҒE‘«—ҳ‘ёҺҒӮНҒAҢ№Ӣ`Қ‘ӮМ’·’jҒEҗV“cӢ`ҸdӮр‘cӮЖӮ·ӮйҗV“cӢ`’еӮзӮМ‘ОҚRҗЁ—НӮр‘ЕӮҝ”jӮиҒA•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЖӮөӮД1338”NӮЙҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙ”CӮ¶ӮзӮкҺә’¬–Ӣ•{ӮрҠJӮӯҒB‘«—ҳӢ`–һӮНҗҙҳaҢ№ҺҒҸoҗgҺТӮЖӮөӮДҸүӮЯӮДҢ№ҺҒ’·ҺТӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢгӮМҸ«ҢRӮӘҢ№ҺҒ’·ҺТӮЖӮИӮй“№ӮрҠJӮўӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒA‘ёҺҒӮМҺq‘·ӮНҠҷ‘qҢц•ыҒAҢГүНҢц•ыҒAҸ¬Ӣ|Ңц•ыҒA–xүzҢц•ыҒAҚдҢц•ыҒAҲў”gҢц•ыӮИӮЗӮЙ•КӮкӮҪҒB
ӮЬӮҪҒA‘«—ҳҺҒҸҺ—¬ӮЕҒuҢдҲкүЖҒvӮЖӮіӮкӮҪӢg—ЗҺҒҒEҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒҒAҒuҺOҠЗ—МҒvӮМҺz”gҺҒҒEҚЧҗмҺҒҒAҒuҺlҗEҒvӮМҲкҗFҺҒӮМ‘јҒAҺR–јҺҒҒiҗV“cҺҒҸҺ—¬ҒjҒA“yҠтҺҒҒi”ь”ZҢ№ҺҒҒjӮӘ’ҶүӣӮЕ‘д“ӘӮөҒA’n•ыӮЕӮНӢгҸB’T‘иӮвҸxүНҒEү“Қ]ҺзҢмӮр—р”CӮөӮҪҚЎҗмҺҒҒiӢg—ЗҺҒҸҺ—¬ҒjҒAүңҸB’T‘иӮМ‘еҚиҺҒҒiҺz”gҺҒҸҺ—¬ҒjҒAүHҸB’T‘иӮМҚЕҸгҺҒҒiҺz”gҺҒҸҺ—¬ҒjӮӘҗЁ—НӮрҗLӮОӮөӮҪҒB
Ӯ»ӮМҢгҒAҗнҚ‘Һһ‘гӮЙӮНҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ––ебӮрҸМӮөӮДүЖҠiӮрҢЦ’ЈӮ·ӮйҺТӮаҸoӮДӮ«ӮҪҒB җҙҳaҢ№ҺҒӮрҸМӮөӮДӮўӮйӢЯҗў‘е–јӮМ‘ҪӮӯӮНҒAӮ»ӮМҺ–ҺАӮӘ—рҺjҠw“IӮЙҸШ–ҫӮіӮкӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBӮҝӮИӮЭӮЙ•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЕӮ ӮйҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМҺТӮөӮ©ӮИӮкӮИӮўӮЖӮўӮӨҗаӮӘӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA“ЎҢҙ—ҠҢoӮЖӮўӮБӮҪҗж—бӮӘ‘¶ҚЭӮөҒAҗD“cҗM’·ӮаҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙҸA”CӮ·ӮйүВ”\җ«ӮӘӮ ӮБӮҪҒiҺOҗEҗ„”C–в‘иҒjҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒAҢ»ҚЭӮЕӮНӮұӮМҗаӮН‘ӯҗаӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB
2020”N01ҢҺ15“ъ
Ӣg—ЗҺҒ
Ӣg—ЗҺҒҒiӮ«ӮзӮөҒjӮНҒA“ъ–{ӮЙӮЁӮҜӮй•җҺmӮМҺҒ‘°ӮМҲкӮВӮЕӮ ӮиҒA‘г•\“IӮИӮаӮМӮЙүәӮМҺOӮВӮМ—¬ӮкӮӘӮ ӮйҒB
җҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳҺҒҺx‘°ӮМӢg—ЗҺҒҒi’·ҺҒ—¬ҒjҒBҺOүНӢg—ЗҺҒҒB
җҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳҺҒҺx‘°ӮМӢg—ЗҺҒҒiӢ`Ңp—¬ҒjҒBүңҸBҒi•җ‘ ҒjӢg—ЗҺҒҒB
җҙҳaҢ№ҺҒҲЧӢ`—¬ӮМӢg—ЗҺҒҒB“yҚІӢg—ЗҺҒҒB
Ӣg—ЗҺҒҒiҗҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳ—¬Ғj
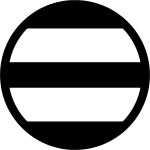
үЖ–дҒ@‘«—ҳ“сӮВҲш
–{җ©
җҙҳaҢ№ҺҒҒiүН“аҢ№ҺҒҒj
үЖ‘c
Ӣg—З’·ҺҒҒiҺOүНӢg—ЗҺҒҒj
Ӣg—ЗӢ`ҢpҒiүңҸBӢg—ЗҺҒҒj
Һн•К
•җүЖ
Һm‘°
Ҹoҗg’n
ҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSӢg—З‘‘
ҺеӮИҚӘӢ’’n
ҺOүНҚ‘
•җ‘ Қ‘
’ҳ–јӮИҗl•Ё
Ӣg—З’еӢ`
Ӣg—З—ҠҚN
Ӣg—ЗӢ`үӣ
ҸгҗҷҚjҢӣ
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
•Д‘тҸгҗҷҺҒҒi•җүЖҒЁүШ‘°Ғj
ҚЎҗмҺҒҒi•җүЖҒj
ҺӘ“cҺҒҒi•җүЖҒj
ҚrҗмҺҒҒi•җүЖҒjӮИӮЗ
–{җ©ӮНҢ№ҺҒҒBүЖҢnӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМҲкүЖҢnүН“аҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӮӯӮЮ‘«—ҳҺҒӮМҲк–еӮЕӮ ӮйҒB‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҸҺ’·ҺqҒEӢg—З’·ҺҒӮЁӮжӮСӮ»ӮМ’нҒEӢg—ЗӢ`ҢpӮжӮиҸoӮйҒBҢZҒE’·ҺҒӮМүЖҢnӮНҺOүНӢg—ЗҺҒӮЖӮИӮиҒA’нҒEӢ`ҢpӮМүЖҢnӮрүңҸBӢg—ЗҺҒӮЖӮўӮӨҒB
Ӣg—ЗҺҒӮН‘«—ҳҲк–еӮЙӮЁӮўӮД–ј–еӮЖӮіӮкҒA•ӘүЖӮМҚЎҗмҺҒӮЖӮЖӮаӮЙ‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҳAҺ}ӮЖӮөӮДӮМүЖҠiӮр—LӮөӮҪҒBӮ»ӮМҠiҺ®ӮНҒuҢдҸҠҒi‘«—ҳҸ«ҢRүЖҒjӮӘҗвӮҰӮкӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮкӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖӮЬӮЕҸҺ–ҜӮЙҢҫӮнӮкҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҢҢ–¬ӮӘҗвӮҰӮҪҚЫӮЙӮН‘«—ҳҸ@үЖӮМүЖ“ВӮрҢpҸіӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӢ–ӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҗаӮӘҚJҒiӮҝӮЬӮҪҒjӮЙӮНӮ ӮйҒB
ӮҪӮҫҒAҺOүНӮЕӮаүңҸBӮЕӮаүЖҠiӮМҚӮӮіӮЙ•җ—НӮӘ”әӮнӮёҒAүЖү^ӮН’б–АҒA‘е–јӮЖӮөӮДӮМ‘¶‘ұӮН’fӮҪӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө—јҢn“қӮНҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙүЖ–јӮрҢqӮўӮЕӮўӮйҒB
ҺOүНӢg—ЗҺҒ
Ҡҷ‘qҺһ‘гҒA‘«—ҳӢ`ҺҒӮӘҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSӢg—З‘‘ҒiҢ»ҒEҲӨ’mҢ§җј”цҺsӢg—З’¬ҒjӮМ’n“ӘҗEӮр“ҫҒAӮұӮкӮрҸҺ’·ҺqҒE’·ҺҒӮЙҸчӮБӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮй[1]ҒBӢg—З‘‘ӮМӢg—ЗӮМҢкҢ№ӮНҒA‘‘үҖ“аӮМ”Әғc–КҺRҒiӮвӮВӮЁӮаӮДӮвӮЬҒjӮЙү_•кҒi‘еҳaҢҫ—tӮЕҒuӮ«ӮзӮзҒvҒjӮМҚzҺRӮрҢГӮӯӮ©Ӯз—LӮөӮҪӮҪӮЯӮЙӮВӮҜӮзӮкӮҪӮаӮМӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮй[1]ҒB“–ҺһӮМӢg—З‘‘ӮНҢГ–оҚмҗмӮМ“ҢҗјӮЙӮаҚLӮӘӮБӮДӮўӮҪӮҪӮЯҒAҗмӮМ“ҢҗјӮрӮ»ӮкӮјӮкҒu“ҢҸрҒvҒAҒuҗјҸрҒvҒiҸйӮНҢ»ҒEҗј”цҺsҒjӮЖӢж•ӘӮөӮДҢДӮсӮЕӮўӮҪҒB’·ҺҒӮНҗјҸрӮМҗј”цҸйӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮДӮЁӮиҒA’нӮМӢ`ҢpҒiҸйӮНҢ»ҒEҗј”цҺsӢg—З’¬йo”nҒqӮЬӮҫӮзӮЯҒrҸйҺRҒjӮӘ“ҢҸрӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮҪӮЯҒA’·ҺҒӮМҢn“қӮНҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖҢДӮОӮкӮйҒBӢ`ҢpӮМҢn“қӮН‘OҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖҢДӮОӮкҒAҢгӮЙүңҸBӮЙҲЪӮБӮДӮўӮйҒB
ҸіӢvӮМ—җҲИҚ~ҒA‘«—ҳҺҒӮНҺOүНҺзҢмӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҺOүНҚ‘“аӮЙ‘ҪӮӯӮМҸҠ—МӮр“ҫӮҪӮӘҒA’·ҺҒӮНҺOүНҚ‘ӮЙ‘ШҚЭӮөӮДӮ»ӮМ’ҶӮЕӮа‘ҚҺwҠцҒEҠД“ВҢ ӮрҲПӮЛӮзӮкӮй—§ҸкӮЙӮ ӮиҒA‘«—ҳҸ@үЖӮ©Ӯзҗ[ӮўҗM—ҠӮрҺуӮҜӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮйҒB ’·ҺҒӮМҺqӢg—З–һҺҒӮН‘ҡҢҺ‘ӣ“®ӮЕҲА’B‘Чҗ·ӮЙӮӯӮЭӮөҒA–kҸрҺҒӮЙӮжӮй“ў”°ӮрҺуӮҜӮДҗнҺҖҒBӮ»ӮМҺqӢg—З’еӢ`ӮНҢіҚO3”NҒi1333”NҒjҒAҢг‘зҢн“VҚc•ыӮМҗЁ—Н“ў–ЕӮМ–ҪӮр‘СӮСӮДҸг—Ң“rҸгӮМ‘«—ҳҚӮҺҒӮӘҺOүНҚ‘ӮЙ‘ШҚЭӮөӮҪҚЫҒA’еӢ`ӮНҒu“VҚcӮЙӮВӮўӮДҠҷ‘q–Ӣ•{‘Е“|ӮМӮҪӮЯӮЙ—§ӮҝҸгӮӘӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйҒvӮЖӢӯҚdӮЙҗiҢҫӮөӮҪҒBӮұӮкӮӘҚЕҸI“IӮИҲшӮ«“SӮЖӮИӮБӮДҚӮҺҒӮНҳZ”g—…’T‘иҚUҢӮӮЙ“ҘӮЭҗШӮиҒAҠҷ‘q–Ӣ•{•цүуҢҖӮМҡ…–оҒiӮұӮӨӮөҒjӮЖӮИӮБӮҪҒB
“м–k’©Һһ‘г •ТҸW
“м–k’©Һһ‘гӮ©ӮзҺә’¬Һһ‘гӮЙӮНҒA’еӢ`ӮМҺqӢg—З–һӢ`ӮНҠПүһӮМҸп—җӮЕ‘«—ҳ’јӢ`ӮЙ–Ў•ыӮөҒA’„’j–һ’еӮЖӮЖӮаӮЙҠe’nӮр“]җнҒAҲкҺһ“IӮЙ“м’©ӮЙӮаӢAҸҮӮөӮҪҢгҒAҚЕҸI“IӮЙҺә’¬–Ӣ•{ӮЙҚ~ӮйҒB
Һә’¬Һһ‘г
Ӣg—ЗҺҒҸү‘гҒE’·ҺҒӮМүBӢҸҸҠӮЖӮөӮД’zӮ©ӮкӮҪҠЩӮНҒuҠЫҺRҢдҸҠҒvӮЖҸМӮіӮкӮҪҒBҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒӮМ—јүЖӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢдҲкүЖҒvӮЖҸМӮіӮкӮД•КҠiӮМҲөӮўӮрҺуӮҜӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAӢg—ЗҺҒ“–ҺеӮНӢһ“sӮЙӮ ӮБӮДҸ«ҢRүЖҲк–еӮЖӮөӮДӮМҠiҺ®Ӯр—LӮөҒA•]’иҸOӮМҲкҗlӮЙ‘гҒX”CӮ¶ӮзӮкӮйүЖӮЖӮөӮД–ӢҠtӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBӮЖӮӯӮЙ‘«—ҳҸ«ҢRүЖҲк–еӮМӢg—ЗҺҒӮНҺ®•]’иҸOӮЖӮөӮД‘јҺҒҸoҗgӮМҸoҗў•]’иҸOӮжӮиӮаҸdӮсӮ¶ӮзӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө‘гҒX“ҜӮ¶Қ‘ӮМҺзҢмӮрҢpӮ®ӮұӮЖӮНӮИӮӯҒAҺзҢм—МҚ‘ӮрҢ`җ¬Ӯ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB
–һӢ`ҒE–һ’е•ғҺqӮӘ–{Ӣ’’nӮМӢg—З‘‘Ӯр—ҜҺзӮЙӮөӮДӮўӮйҠФӮЙҒA–һӢ`ӮМҺl’jӢg—З‘ёӢ`ӮӘӢg—З‘‘ӮМ“ҢҸрӮрүҹ—МӮөҒA“ҢҸрӢg—ЗҺҒҒiҢгҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒҒjӮЖӮөӮДҺ©—§Ӯ·ӮйӮЖӮўӮӨҺ–ҢҸӮӘӢNӮ«ӮйҒBҲИҢгҒA‘ёӢ`ӮМ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖҒAҗјҸрӮЙҗЁ—НӮрҢА’иӮіӮкӮҪ–һ’еӮМҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖӮНҒAҢЭӮўӮЙҗі“қҗ«ӮрҺе’ЈӮөӮ ӮБӮДҸчӮзӮёҒAүһҗmӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДӮНҗјҸрүЖӮМӢg—ЗӢ`җ^ӮӘ“ҢҢRҒA“ҢҸрүЖӮМӢg—ЗӢ`“ЎӮӘҗјҢRӮЙӮ»ӮкӮјӮк‘®ӮөӮДҗнӮӨӮИӮЗҒA—јҺТӮМҺq‘·ӮН–с1җўӢIӮЙӮнӮҪӮБӮДҚR‘ҲӮрҢJӮиҚLӮ°ӮҪҒB
җнҚ‘Һһ‘г
җнҚ‘Һһ‘гӮМҺOүНӢg—ЗҺҒӮНҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`җMӮӘүiҗі5”NҒi1508”NҒjӮМ‘«—ҳӢ`вeӮМҸ«ҢR•ңӢAӮЙҢчҗСӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮөӮДҺOүНҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪӮЖӮ·Ӯйҗа[2]ӮӘӮ ӮиҒAӮЬӮҪҒAҲАҸЛҸј•ҪүЖӮМҸј•ҪҗM’үӮЙ•ОжҒӮрҺцӮҜӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒB
ӮҫӮӘҒA‘S‘МӮЖӮөӮДӮНҗЁ—НӮӘҗUӮйӮнӮИӮ©ӮБӮҪҸгӮЙҒAҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЙ•Ә—фӮөӮҪ“а•”ҚR‘ҲӮӘҺы‘©ӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒAүЖү^ӮрҲк’iӮЖ’б–АӮіӮ№ӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМҠФӮЙҒAҸҺ—¬ӮЕӮ ӮйҸxүНҺзҢмҚЎҗмҺҒӮ©ӮзӮМҲі”—ӮрҺуӮҜӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`ӢДӮМҚ ӮЕӮ ӮиҒAү“Қ]Қ‘ӮМӢ’“_ӮЕӮ ӮйҲшҠФ‘‘Ӯр’DӮнӮкӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҺOүНӮЕӮаӢg—ЗҺҒӮ©Ӯз•ОжҒӮрҺуӮҜӮй—§ҸкӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҲАҸЛҸј•ҪүЖӮӘ‘д“ӘӮ·ӮйҒBӮИӮЁҒAҸј•ҪҗҙҚNӮН“ҢҸрҸј•ҪӮМӢg—ЗҺқҗҙӮМ•ОжҒӮрҒAҸј•ҪҚL’үӮНҺқҗҙӮМ‘§ҺqӮЕӮ ӮйӢg—ЗҺқҚLӮМ•ОжҒӮрҺуӮҜӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮӘӮ ӮйҒB
ӮжӮӨӮвӮӯ“Ҝ‘°ҚR‘ҲӮМӢрӮрҢеӮБӮҪ“ҢҸрҒEҗјҸр—јүЖӮНҒA“ҢҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗҺқҚLӮӘҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`ҲАӮр—{ҺkҺqӮЙӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҢ`ӮЕҳaӢcӮрҗ¬—§ӮіӮ№ҒA’·”NӮМҚR‘ҲӮЙҸIҺ~•„Ӯр‘ЕӮБӮҪҒBӢқҳ\ҒE“V•¶Ҹү”NҠФӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӢ`ҲАӮНҚЎҗмҺҒӮЦӮМ‘ОҚRҸгҒA“ҜӮ¶ӮӯҚЎҗмҺҒӮЖҚR‘Ҳ’ҶӮЙӮ ӮБӮҪ”ц’ЈҚ‘ӮМҗD“cҺҒӮЙүБ’SӮөҒA–hүq‘Мҗ§Ӯрҗ®ӮҰӮДӮўӮӯҒBӮИӮЁҒAҚЎҗмҺҒӮМҢn•ҲӮ©ӮзҚЎҗмҺҒҗeӮМ’·Ҹ—ӮӘӢg—ЗӢ`ӢДӮМҗіҺәӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ”»–ҫӮөӮДӮўӮй‘јҒAҚЎҗмҺҒӮМҢҢӮрҲшӮўӮДӮўӮИӮў‘ӨҺәӮМҺqӮЕӮ ӮйӢ`ҲАӮӘ“ҢҸрӢg—ЗӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҗјҸрӢg—ЗӮМүЖ“ВӮрӮа–]ӮсӮЕҗјҸрӢg—ЗӮМҸdҗbӮЖ‘ҲӮБӮҪҢ`җХӮӘӮ ӮиҒAҚЎҗмҺҒӮЙӢЯӮўҸdҗbӮЙ‘ОҚRӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҺz”gҺҒӮвҗD“cҺҒӮЖҢӢӮсӮҫүВ”\җ«ӮаҺw“EӮіӮкӮДӮўӮйҒB
ӮөӮ©ӮөҒA’·”NӮМҚR‘ҲӮЕҗҠ‘ЮӮіӮ№ӮҪүЖү^ӮМүс•ңӮЬӮЕӮЙӮНҺҠӮзӮёҒA“V•¶18”NҒi1549”NҒjӮЙҚЎҗмӢ`ҢіӮМ–ТҚUӮЙ”s‘ЮӮ·ӮйҒB•ЯӮзӮҰӮзӮкӮҪӢ`ҲАӮМҗg•ҝӮНҸxүНӮЙ—}—ҜӮіӮкӮҪҒBҗјҸрӢg—ЗҺҒӮрҢpӮўӮЕӮўӮҪӢ`ҲАӮМ’нӢg—ЗӢ`ҸәӮНҒAҚЎҗмҺҒӮЙ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮаӮ ӮнӮ№ӮДҢpӮ®ӮжӮӨ–ҪӮ¶ӮзӮкҒA“ҢҗјӮМӢg—ЗҺҒӮНӮұӮӨӮөӮД“ҜҲкү»ӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҚЎҗмҺҒӮЦӮМ—к‘®җ«ӮМҚӮӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮҪӮҫӮөҒAҸ¬—СӢPӢv•FӮН“V•¶23”NҒi1554”NҒjӮЙӮНҲк’UӢ–ӮіӮкӮДӢ`ҲАӮӘ—јӢg—ЗҺҒӮрҢpӮўӮҫӮаӮМӮМҒAҚOҺЎҢі”NҒi1555”NҒjӮЙҚД“xҚЎҗмҺҒӮЙ”ҫҠшӮр–|ӮөӮҪҢӢүКҒAӢ`ҸәӮӘҢpӮўӮҫӮаӮМӮЖӮ·ӮйҗаӮрҸoӮөӮДӮўӮйҒB
ӮИӮЁҒA“–ҺһӮМҚЎҗмҺҒӮЙӮЖӮБӮДӮНӢg—ЗҺҒӮМ‘¶ҚЭӮН”YӮЭӮМҺнӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒB“V•¶18”N9ҢҺ5“ъ•tӮЕҚЎҗмӢ`ҢіӮМҸdҗbӮЕӮ Ӯй‘ҫҢҙҗбҚЦӮӘӢg—ЗӢ`ҲАӮЙҸ[ӮДӮҪҸ‘ҸуӮНҒAӢ`ҲАӮрҒuҢдү®Ң`—lҒvӮЖҢДӮсӮҫҸгӮЙҲ¶җжӮаӢ`ҲА–{җlӮЕӮНӮИӮӯҒuҗјҸрҸ”ҳVҒvӮ·ӮИӮнӮҝӢ`ҲАӮМүЖҳVҲ¶ӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBҢ»ҺАӮМҗўҠEӮЕӮНҚЎҗмҺҒӮНҸxү“ҺOӮМ3Ӯ©Қ‘ӮрҺx”zӮөӮДӢg—ЗҺҒӮрҸ]‘®үәӮЙ’uӮўӮДӮўӮйӮЙӮаҠЦӮнӮзӮёҒAҸ‘ҺD—зӮМҗўҠEӮЕӮНҗбҚЦӮНӢ`ҲАӮМ”ҶҗbҒiүЖ—ҲӮМүЖ—ҲҒjӮЖӮөӮДҗUӮй•‘ӮнӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ӮЖӮұӮлӮӘҒAүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮЕӢ`ҢіӮӘ“ўӮҝҺжӮзӮкҒAҺOүНҚ‘ӮМҺx”zӮр–ЪҺwӮ·Ҹј•ҪүЖҚNҒiӮМӮҝӮМ“ҝҗмүЖҚNҒjӮЖӢ`ҸәӮН‘О—§Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBӢ`ҸәӮН‘P–ҫ’зӮМҗнӮўӮв“Ў”g“лӮМҗнӮўӮрҢoӮДҒAүЖҚNӮЙҚ~•ҡӮ·ӮйҒBүiҳ\6”NҒi1563”NҒjҒAҺOүНҲкҢьҲкқ„ӮӘ–u”ӯӮ·ӮйӮЖҲкҢьҲкқ„•ыӮЙүБ’SӮөӮДҒAҚДӮСүЖҚNӮЖҗнӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӢ`ҸәӮН”jӮкҒAҺOүНҚ‘ӮрҸo–zӮөҒAүЖҚNӮНҗјҸрӢg—ЗүЖӮМүЖ“ВӮаӢ`ҲАӮЙ‘Ҡ‘ұӮіӮ№ӮҪҒB
Ӣ`ҸәӮНҗD“cҗM’·ӮМҺьҗщӮЙӮжӮиҒA”ц’ЈҺзҢмӮМҺz”gҺҒӮЁӮжӮСӮ»ӮМҲк–еӮМҗОӢҙҺҒӮЖ“Ҝ–ҝӮрҢӢӮФӮЬӮЕӮЙ‘ҶӮ¬’…ӮҜӮҪӮӘҒAҺz”gӢ`ӢвӮЖҗИҺҹӮрҸ„Ӯй‘ҲӮўӮрӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒBҺz”gҺҒӮаӮЬӮҪҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖҲк–е’ҶҸ«ҢRүЖӮвӢg—ЗҺҒӮЙ•АӮФ–ј‘°ӮЕӮ ӮБӮҪҒB
Қ]ҢЛҺһ‘г‘OҠъ
Қ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮНҒAӢ`ҲАӮМҺqӢ`’иӮӘҸј•ҪҗҙҚNӮМ–…Ӯр•кӮЖӮөӮДӮўӮҪҠЦҢWӮЕ“ҝҗмҺҒӮЙҺжӮи—§ӮДӮзӮкҒAӮ»ӮМҺqӢ`–нӮМ‘гӮЙҺҠӮиӢҢӢg—З‘‘“аӮЕ3,000җОӮр—МӮөӮДҒAҚӮүЖӮМүЖҠiӮр•t—^ӮіӮкӮҪҒBӮұӮкҲИҚ~ӮМӢg—ЗҺҒӮНҒAҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮМӢV“TҠЦҢWӮрҺжӮиҺdҗШӮйүЖӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйҒB
Ӣ`–нӮМҺҹӮНӢg—ЗӢ`“~ӮӘ‘Ҡ‘ұӮөӮҪҒB
Ӣ`“~ӮМ’·’jӢg—ЗӢ`үӣӮНҒAҗФ•дҺ–ҢҸҒi’үҗb‘ ҒjӮЕ’ҳ–јӮЕӮ ӮйҒBӢ`үӣӮНҒAҢіҳ\14”NҒi1701”NҒjҒAӢV“TӮМҺw“ұӮЙҠЦӮөӮД’әҺgӢАүһ–рӮМ”d–ҒҗФ•д”ЛҺеҗу–м’·ӢйӮЖӮМҠФӮЙҠmҺ·Ӯрҗ¶Ӯ¶ҒA’·ӢйӮ©Ӯз“a’ҶҗnҸқӮрҺуӮҜҒA’·ӢйӮМҗШ• ҢгҒAҢіҳ\15”NҒi1702”NҒjӮЙ‘еҗО“а‘ Ҹ•ҲИүәҗу–мӮМҲвҗbӮзӮЙӮжӮй–{ҸҠӢg—З“@ӮЦӮМ“ўӮҝ“ьӮиӮрҺуӮҜӮД“ўӮҝҺжӮзӮкӮҪҒBҢіҳ\16”NҒi1703”NҒjӮЙӮНӢ`үӣӮМ‘·ӮЙӮ ӮҪӮй“–ҺеӢg—ЗӢ`ҺьӮӘүьҲХӮіӮкӮҪҒB
Қ]ҢЛҺһ‘гҢгҠъ
Ӣ`“~ӮМҺҹ’jӢ`ҸfҒiӢ`үӣӮМ’нҒjӮН“ҢҸрҗ©Ғi“ҢҸрҺҒӮНҺә’¬Һһ‘гӮМӢg—ЗҺҒ•КҸМҒjӮр–јҸжӮБӮДҒAҺq‘·ӮаҠш–{ӮЖӮөӮДҸ«ҢRүЖӮЙҺdӮҰӮДӮўӮҪӮӘҒAӢқ•Ы17”NҒi1732”NҒjҒAӢ`ҸfӮМ‘·ӮЙ“–ӮҪӮйӢ`ӣtӮӘҒAӢ`үӣӮМүЖҢnӮӘҗвӮҰӮДӮўӮйӮұӮЖӮр—қ—RӮЙҒA“ҢҸрүЖӮ©ӮзӢg—ЗүЖӮЦӮМ•ңҗ©Ӯр–Ӣ•{ӮЙҠиӮўҸoӮДӢ–ӮіӮкӮҪҒB
ӮҪӮҫӮөӮұӮМҚДӢ»Ӣg—ЗүЖӮН•АӮЭӮМҠш–{ӮЖӮөӮДӮЕӮ ӮиҒAҚӮүЖӮМҠiҺ®ӮН—^ӮҰӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBҲИҢгҒAӢg—ЗүЖӮН–ҫҺЎҲЫҗVӮЬӮЕҠш–{ӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйҒB
—р‘г
Ӣg—З’·ҺҒ
Ӣg—З–һҺҒ
Ӣg—З’еӢ`
Ӣg—З–һӢ`
ҒiҗјҸрӢg—ЗҒjҒi“ҢҸрӢg—ЗҒj
Ӣg—З–һ’е Ғ@Ӣg—З‘ёӢ`
Ӣg—ЗҸrҺҒ Ғ@Ӣg—З’©ҺҒ
Ӣg—ЗӢ`Ҹ® Ғ@Ӣg—ЗҺқ’·
Ӣg—ЗӢ`җ^ Ғ@Ӣg—ЗҺқҸ•
Ӣg—ЗӢ`җM Ғ@Ӣg—ЗӢ`“Ў
Ӣg—ЗӢ`Ңі Ғ@Ӣg—ЗҺқҗҙ
Ӣg—ЗӢ`ӢД Ғ@Ӣg—ЗҺқҚL
Ӣg—ЗӢ`ӢҪҒ@ ҚrҗмӢ`ҚL
Ӣg—ЗӢ`ҲА
Ӣg—ЗӢ`Ҹә
Ӣg—ЗӢ`’и
Ӣg—ЗӢ`–н
Ӣg—ЗӢ`“~
Ӣg—ЗӢ`үӣ
Ӣg—ЗӢ`Һь
үңҸBҒi•җ‘ ҒjӢg—ЗҺҒ
–{җ©ӮНҢ№ҺҒҒBҺOүНӢg—ЗҺҒӮМ“ҜҢnҒB
‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҺl’jҒEӢg—ЗӢ`ҢpӮӘҒAҢZҒE’·ҺҒӮЖ“ҜӮ¶ӮӯҺOүНҚ‘Ӣg—З‘‘Ӯр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮНӮ¶ӮЬӮйҒB’·ҺҒӮӘ“Ҝ‘‘җјҸрӮЙӢ’ӮБӮҪӮМӮЙ‘ОӮөӮДӢ`ҢpӮН“ҢҸрӮр—МӮөҒA‘OҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖӮаҢДӮОӮкӮҪҒB“ҢҸрӮМҸйӮН“ҢҸрҸйӮЕҒAҸкҸҠӮНҢ»ҚЭӮМҗј”цҺsӢg—З’¬йo”nҒiӮЬӮҫӮзӮЯҒjҸйҺRӮЕӮ ӮйҒBӮҪӮҫӮө‘ё”Ъ•Ә–¬ӮЕӮНӢ`ҢpӮМҺqӢg—ЗҢoҺҒӮӘҒuҒiҗјҸрӢg—ЗӮМҒjӢg—З–һҺҒӮМҺqӮЖӮИӮБӮҪҒvҒuҚҶӢg—ЗҒiӢg—ЗӮрҚҶӮ·ҒjҒvӮЖӢLҸqӮіӮкӮДӮўӮйҒB
җҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳҺҒҺx‘°ӮМӢg—ЗҺҒҒi’·ҺҒ—¬ҒjҒBҺOүНӢg—ЗҺҒҒB
җҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳҺҒҺx‘°ӮМӢg—ЗҺҒҒiӢ`Ңp—¬ҒjҒBүңҸBҒi•җ‘ ҒjӢg—ЗҺҒҒB
җҙҳaҢ№ҺҒҲЧӢ`—¬ӮМӢg—ЗҺҒҒB“yҚІӢg—ЗҺҒҒB
Ӣg—ЗҺҒҒiҗҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳ—¬Ғj
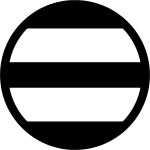
үЖ–дҒ@‘«—ҳ“сӮВҲш
–{җ©
җҙҳaҢ№ҺҒҒiүН“аҢ№ҺҒҒj
үЖ‘c
Ӣg—З’·ҺҒҒiҺOүНӢg—ЗҺҒҒj
Ӣg—ЗӢ`ҢpҒiүңҸBӢg—ЗҺҒҒj
Һн•К
•җүЖ
Һm‘°
Ҹoҗg’n
ҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSӢg—З‘‘
ҺеӮИҚӘӢ’’n
ҺOүНҚ‘
•җ‘ Қ‘
’ҳ–јӮИҗl•Ё
Ӣg—З’еӢ`
Ӣg—З—ҠҚN
Ӣg—ЗӢ`үӣ
ҸгҗҷҚjҢӣ
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
•Д‘тҸгҗҷҺҒҒi•җүЖҒЁүШ‘°Ғj
ҚЎҗмҺҒҒi•җүЖҒj
ҺӘ“cҺҒҒi•җүЖҒj
ҚrҗмҺҒҒi•җүЖҒjӮИӮЗ
–{җ©ӮНҢ№ҺҒҒBүЖҢnӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМҲкүЖҢnүН“аҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӮӯӮЮ‘«—ҳҺҒӮМҲк–еӮЕӮ ӮйҒB‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҸҺ’·ҺqҒEӢg—З’·ҺҒӮЁӮжӮСӮ»ӮМ’нҒEӢg—ЗӢ`ҢpӮжӮиҸoӮйҒBҢZҒE’·ҺҒӮМүЖҢnӮНҺOүНӢg—ЗҺҒӮЖӮИӮиҒA’нҒEӢ`ҢpӮМүЖҢnӮрүңҸBӢg—ЗҺҒӮЖӮўӮӨҒB
Ӣg—ЗҺҒӮН‘«—ҳҲк–еӮЙӮЁӮўӮД–ј–еӮЖӮіӮкҒA•ӘүЖӮМҚЎҗмҺҒӮЖӮЖӮаӮЙ‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҳAҺ}ӮЖӮөӮДӮМүЖҠiӮр—LӮөӮҪҒBӮ»ӮМҠiҺ®ӮНҒuҢдҸҠҒi‘«—ҳҸ«ҢRүЖҒjӮӘҗвӮҰӮкӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮкӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖӮЬӮЕҸҺ–ҜӮЙҢҫӮнӮкҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҢҢ–¬ӮӘҗвӮҰӮҪҚЫӮЙӮН‘«—ҳҸ@үЖӮМүЖ“ВӮрҢpҸіӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӢ–ӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҗаӮӘҚJҒiӮҝӮЬӮҪҒjӮЙӮНӮ ӮйҒB
ӮҪӮҫҒAҺOүНӮЕӮаүңҸBӮЕӮаүЖҠiӮМҚӮӮіӮЙ•җ—НӮӘ”әӮнӮёҒAүЖү^ӮН’б–АҒA‘е–јӮЖӮөӮДӮМ‘¶‘ұӮН’fӮҪӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө—јҢn“қӮНҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙүЖ–јӮрҢqӮўӮЕӮўӮйҒB
ҺOүНӢg—ЗҺҒ
Ҡҷ‘qҺһ‘гҒA‘«—ҳӢ`ҺҒӮӘҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSӢg—З‘‘ҒiҢ»ҒEҲӨ’mҢ§җј”цҺsӢg—З’¬ҒjӮМ’n“ӘҗEӮр“ҫҒAӮұӮкӮрҸҺ’·ҺqҒE’·ҺҒӮЙҸчӮБӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮй[1]ҒBӢg—З‘‘ӮМӢg—ЗӮМҢкҢ№ӮНҒA‘‘үҖ“аӮМ”Әғc–КҺRҒiӮвӮВӮЁӮаӮДӮвӮЬҒjӮЙү_•кҒi‘еҳaҢҫ—tӮЕҒuӮ«ӮзӮзҒvҒjӮМҚzҺRӮрҢГӮӯӮ©Ӯз—LӮөӮҪӮҪӮЯӮЙӮВӮҜӮзӮкӮҪӮаӮМӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮй[1]ҒB“–ҺһӮМӢg—З‘‘ӮНҢГ–оҚмҗмӮМ“ҢҗјӮЙӮаҚLӮӘӮБӮДӮўӮҪӮҪӮЯҒAҗмӮМ“ҢҗјӮрӮ»ӮкӮјӮкҒu“ҢҸрҒvҒAҒuҗјҸрҒvҒiҸйӮНҢ»ҒEҗј”цҺsҒjӮЖӢж•ӘӮөӮДҢДӮсӮЕӮўӮҪҒB’·ҺҒӮНҗјҸрӮМҗј”цҸйӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮДӮЁӮиҒA’нӮМӢ`ҢpҒiҸйӮНҢ»ҒEҗј”цҺsӢg—З’¬йo”nҒqӮЬӮҫӮзӮЯҒrҸйҺRҒjӮӘ“ҢҸрӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮҪӮЯҒA’·ҺҒӮМҢn“қӮНҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖҢДӮОӮкӮйҒBӢ`ҢpӮМҢn“қӮН‘OҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖҢДӮОӮкҒAҢгӮЙүңҸBӮЙҲЪӮБӮДӮўӮйҒB
ҸіӢvӮМ—җҲИҚ~ҒA‘«—ҳҺҒӮНҺOүНҺзҢмӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҺOүНҚ‘“аӮЙ‘ҪӮӯӮМҸҠ—МӮр“ҫӮҪӮӘҒA’·ҺҒӮНҺOүНҚ‘ӮЙ‘ШҚЭӮөӮДӮ»ӮМ’ҶӮЕӮа‘ҚҺwҠцҒEҠД“ВҢ ӮрҲПӮЛӮзӮкӮй—§ҸкӮЙӮ ӮиҒA‘«—ҳҸ@үЖӮ©Ӯзҗ[ӮўҗM—ҠӮрҺуӮҜӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮйҒB ’·ҺҒӮМҺqӢg—З–һҺҒӮН‘ҡҢҺ‘ӣ“®ӮЕҲА’B‘Чҗ·ӮЙӮӯӮЭӮөҒA–kҸрҺҒӮЙӮжӮй“ў”°ӮрҺуӮҜӮДҗнҺҖҒBӮ»ӮМҺqӢg—З’еӢ`ӮНҢіҚO3”NҒi1333”NҒjҒAҢг‘зҢн“VҚc•ыӮМҗЁ—Н“ў–ЕӮМ–ҪӮр‘СӮСӮДҸг—Ң“rҸгӮМ‘«—ҳҚӮҺҒӮӘҺOүНҚ‘ӮЙ‘ШҚЭӮөӮҪҚЫҒA’еӢ`ӮНҒu“VҚcӮЙӮВӮўӮДҠҷ‘q–Ӣ•{‘Е“|ӮМӮҪӮЯӮЙ—§ӮҝҸгӮӘӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйҒvӮЖӢӯҚdӮЙҗiҢҫӮөӮҪҒBӮұӮкӮӘҚЕҸI“IӮИҲшӮ«“SӮЖӮИӮБӮДҚӮҺҒӮНҳZ”g—…’T‘иҚUҢӮӮЙ“ҘӮЭҗШӮиҒAҠҷ‘q–Ӣ•{•цүуҢҖӮМҡ…–оҒiӮұӮӨӮөҒjӮЖӮИӮБӮҪҒB
“м–k’©Һһ‘г •ТҸW
“м–k’©Һһ‘гӮ©ӮзҺә’¬Һһ‘гӮЙӮНҒA’еӢ`ӮМҺqӢg—З–һӢ`ӮНҠПүһӮМҸп—җӮЕ‘«—ҳ’јӢ`ӮЙ–Ў•ыӮөҒA’„’j–һ’еӮЖӮЖӮаӮЙҠe’nӮр“]җнҒAҲкҺһ“IӮЙ“м’©ӮЙӮаӢAҸҮӮөӮҪҢгҒAҚЕҸI“IӮЙҺә’¬–Ӣ•{ӮЙҚ~ӮйҒB
Һә’¬Һһ‘г
Ӣg—ЗҺҒҸү‘гҒE’·ҺҒӮМүBӢҸҸҠӮЖӮөӮД’zӮ©ӮкӮҪҠЩӮНҒuҠЫҺRҢдҸҠҒvӮЖҸМӮіӮкӮҪҒBҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒӮМ—јүЖӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢдҲкүЖҒvӮЖҸМӮіӮкӮД•КҠiӮМҲөӮўӮрҺуӮҜӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAӢg—ЗҺҒ“–ҺеӮНӢһ“sӮЙӮ ӮБӮДҸ«ҢRүЖҲк–еӮЖӮөӮДӮМҠiҺ®Ӯр—LӮөҒA•]’иҸOӮМҲкҗlӮЙ‘гҒX”CӮ¶ӮзӮкӮйүЖӮЖӮөӮД–ӢҠtӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBӮЖӮӯӮЙ‘«—ҳҸ«ҢRүЖҲк–еӮМӢg—ЗҺҒӮНҺ®•]’иҸOӮЖӮөӮД‘јҺҒҸoҗgӮМҸoҗў•]’иҸOӮжӮиӮаҸdӮсӮ¶ӮзӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө‘гҒX“ҜӮ¶Қ‘ӮМҺзҢмӮрҢpӮ®ӮұӮЖӮНӮИӮӯҒAҺзҢм—МҚ‘ӮрҢ`җ¬Ӯ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB
–һӢ`ҒE–һ’е•ғҺqӮӘ–{Ӣ’’nӮМӢg—З‘‘Ӯр—ҜҺзӮЙӮөӮДӮўӮйҠФӮЙҒA–һӢ`ӮМҺl’jӢg—З‘ёӢ`ӮӘӢg—З‘‘ӮМ“ҢҸрӮрүҹ—МӮөҒA“ҢҸрӢg—ЗҺҒҒiҢгҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒҒjӮЖӮөӮДҺ©—§Ӯ·ӮйӮЖӮўӮӨҺ–ҢҸӮӘӢNӮ«ӮйҒBҲИҢгҒA‘ёӢ`ӮМ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖҒAҗјҸрӮЙҗЁ—НӮрҢА’иӮіӮкӮҪ–һ’еӮМҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖӮНҒAҢЭӮўӮЙҗі“қҗ«ӮрҺе’ЈӮөӮ ӮБӮДҸчӮзӮёҒAүһҗmӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДӮНҗјҸрүЖӮМӢg—ЗӢ`җ^ӮӘ“ҢҢRҒA“ҢҸрүЖӮМӢg—ЗӢ`“ЎӮӘҗјҢRӮЙӮ»ӮкӮјӮк‘®ӮөӮДҗнӮӨӮИӮЗҒA—јҺТӮМҺq‘·ӮН–с1җўӢIӮЙӮнӮҪӮБӮДҚR‘ҲӮрҢJӮиҚLӮ°ӮҪҒB
җнҚ‘Һһ‘г
җнҚ‘Һһ‘гӮМҺOүНӢg—ЗҺҒӮНҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`җMӮӘүiҗі5”NҒi1508”NҒjӮМ‘«—ҳӢ`вeӮМҸ«ҢR•ңӢAӮЙҢчҗСӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮөӮДҺOүНҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪӮЖӮ·Ӯйҗа[2]ӮӘӮ ӮиҒAӮЬӮҪҒAҲАҸЛҸј•ҪүЖӮМҸј•ҪҗM’үӮЙ•ОжҒӮрҺцӮҜӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒB
ӮҫӮӘҒA‘S‘МӮЖӮөӮДӮНҗЁ—НӮӘҗUӮйӮнӮИӮ©ӮБӮҪҸгӮЙҒAҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЙ•Ә—фӮөӮҪ“а•”ҚR‘ҲӮӘҺы‘©ӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒAүЖү^ӮрҲк’iӮЖ’б–АӮіӮ№ӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМҠФӮЙҒAҸҺ—¬ӮЕӮ ӮйҸxүНҺзҢмҚЎҗмҺҒӮ©ӮзӮМҲі”—ӮрҺуӮҜӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`ӢДӮМҚ ӮЕӮ ӮиҒAү“Қ]Қ‘ӮМӢ’“_ӮЕӮ ӮйҲшҠФ‘‘Ӯр’DӮнӮкӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҺOүНӮЕӮаӢg—ЗҺҒӮ©Ӯз•ОжҒӮрҺуӮҜӮй—§ҸкӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҲАҸЛҸј•ҪүЖӮӘ‘д“ӘӮ·ӮйҒBӮИӮЁҒAҸј•ҪҗҙҚNӮН“ҢҸрҸј•ҪӮМӢg—ЗҺқҗҙӮМ•ОжҒӮрҒAҸј•ҪҚL’үӮНҺқҗҙӮМ‘§ҺqӮЕӮ ӮйӢg—ЗҺқҚLӮМ•ОжҒӮрҺуӮҜӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮӘӮ ӮйҒB
ӮжӮӨӮвӮӯ“Ҝ‘°ҚR‘ҲӮМӢрӮрҢеӮБӮҪ“ҢҸрҒEҗјҸр—јүЖӮНҒA“ҢҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗҺқҚLӮӘҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`ҲАӮр—{ҺkҺqӮЙӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҢ`ӮЕҳaӢcӮрҗ¬—§ӮіӮ№ҒA’·”NӮМҚR‘ҲӮЙҸIҺ~•„Ӯр‘ЕӮБӮҪҒBӢқҳ\ҒE“V•¶Ҹү”NҠФӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӢ`ҲАӮНҚЎҗмҺҒӮЦӮМ‘ОҚRҸгҒA“ҜӮ¶ӮӯҚЎҗмҺҒӮЖҚR‘Ҳ’ҶӮЙӮ ӮБӮҪ”ц’ЈҚ‘ӮМҗD“cҺҒӮЙүБ’SӮөҒA–hүq‘Мҗ§Ӯрҗ®ӮҰӮДӮўӮӯҒBӮИӮЁҒAҚЎҗмҺҒӮМҢn•ҲӮ©ӮзҚЎҗмҺҒҗeӮМ’·Ҹ—ӮӘӢg—ЗӢ`ӢДӮМҗіҺәӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ”»–ҫӮөӮДӮўӮй‘јҒAҚЎҗмҺҒӮМҢҢӮрҲшӮўӮДӮўӮИӮў‘ӨҺәӮМҺqӮЕӮ ӮйӢ`ҲАӮӘ“ҢҸрӢg—ЗӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҗјҸрӢg—ЗӮМүЖ“ВӮрӮа–]ӮсӮЕҗјҸрӢg—ЗӮМҸdҗbӮЖ‘ҲӮБӮҪҢ`җХӮӘӮ ӮиҒAҚЎҗмҺҒӮЙӢЯӮўҸdҗbӮЙ‘ОҚRӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҺz”gҺҒӮвҗD“cҺҒӮЖҢӢӮсӮҫүВ”\җ«ӮаҺw“EӮіӮкӮДӮўӮйҒB
ӮөӮ©ӮөҒA’·”NӮМҚR‘ҲӮЕҗҠ‘ЮӮіӮ№ӮҪүЖү^ӮМүс•ңӮЬӮЕӮЙӮНҺҠӮзӮёҒA“V•¶18”NҒi1549”NҒjӮЙҚЎҗмӢ`ҢіӮМ–ТҚUӮЙ”s‘ЮӮ·ӮйҒB•ЯӮзӮҰӮзӮкӮҪӢ`ҲАӮМҗg•ҝӮНҸxүНӮЙ—}—ҜӮіӮкӮҪҒBҗјҸрӢg—ЗҺҒӮрҢpӮўӮЕӮўӮҪӢ`ҲАӮМ’нӢg—ЗӢ`ҸәӮНҒAҚЎҗмҺҒӮЙ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮаӮ ӮнӮ№ӮДҢpӮ®ӮжӮӨ–ҪӮ¶ӮзӮкҒA“ҢҗјӮМӢg—ЗҺҒӮНӮұӮӨӮөӮД“ҜҲкү»ӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҚЎҗмҺҒӮЦӮМ—к‘®җ«ӮМҚӮӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮҪӮҫӮөҒAҸ¬—СӢPӢv•FӮН“V•¶23”NҒi1554”NҒjӮЙӮНҲк’UӢ–ӮіӮкӮДӢ`ҲАӮӘ—јӢg—ЗҺҒӮрҢpӮўӮҫӮаӮМӮМҒAҚOҺЎҢі”NҒi1555”NҒjӮЙҚД“xҚЎҗмҺҒӮЙ”ҫҠшӮр–|ӮөӮҪҢӢүКҒAӢ`ҸәӮӘҢpӮўӮҫӮаӮМӮЖӮ·ӮйҗаӮрҸoӮөӮДӮўӮйҒB
ӮИӮЁҒA“–ҺһӮМҚЎҗмҺҒӮЙӮЖӮБӮДӮНӢg—ЗҺҒӮМ‘¶ҚЭӮН”YӮЭӮМҺнӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒB“V•¶18”N9ҢҺ5“ъ•tӮЕҚЎҗмӢ`ҢіӮМҸdҗbӮЕӮ Ӯй‘ҫҢҙҗбҚЦӮӘӢg—ЗӢ`ҲАӮЙҸ[ӮДӮҪҸ‘ҸуӮНҒAӢ`ҲАӮрҒuҢдү®Ң`—lҒvӮЖҢДӮсӮҫҸгӮЙҲ¶җжӮаӢ`ҲА–{җlӮЕӮНӮИӮӯҒuҗјҸрҸ”ҳVҒvӮ·ӮИӮнӮҝӢ`ҲАӮМүЖҳVҲ¶ӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBҢ»ҺАӮМҗўҠEӮЕӮНҚЎҗмҺҒӮНҸxү“ҺOӮМ3Ӯ©Қ‘ӮрҺx”zӮөӮДӢg—ЗҺҒӮрҸ]‘®үәӮЙ’uӮўӮДӮўӮйӮЙӮаҠЦӮнӮзӮёҒAҸ‘ҺD—зӮМҗўҠEӮЕӮНҗбҚЦӮНӢ`ҲАӮМ”ҶҗbҒiүЖ—ҲӮМүЖ—ҲҒjӮЖӮөӮДҗUӮй•‘ӮнӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ӮЖӮұӮлӮӘҒAүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮЕӢ`ҢіӮӘ“ўӮҝҺжӮзӮкҒAҺOүНҚ‘ӮМҺx”zӮр–ЪҺwӮ·Ҹј•ҪүЖҚNҒiӮМӮҝӮМ“ҝҗмүЖҚNҒjӮЖӢ`ҸәӮН‘О—§Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBӢ`ҸәӮН‘P–ҫ’зӮМҗнӮўӮв“Ў”g“лӮМҗнӮўӮрҢoӮДҒAүЖҚNӮЙҚ~•ҡӮ·ӮйҒBүiҳ\6”NҒi1563”NҒjҒAҺOүНҲкҢьҲкқ„ӮӘ–u”ӯӮ·ӮйӮЖҲкҢьҲкқ„•ыӮЙүБ’SӮөӮДҒAҚДӮСүЖҚNӮЖҗнӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӢ`ҸәӮН”jӮкҒAҺOүНҚ‘ӮрҸo–zӮөҒAүЖҚNӮНҗјҸрӢg—ЗүЖӮМүЖ“ВӮаӢ`ҲАӮЙ‘Ҡ‘ұӮіӮ№ӮҪҒB
Ӣ`ҸәӮНҗD“cҗM’·ӮМҺьҗщӮЙӮжӮиҒA”ц’ЈҺзҢмӮМҺz”gҺҒӮЁӮжӮСӮ»ӮМҲк–еӮМҗОӢҙҺҒӮЖ“Ҝ–ҝӮрҢӢӮФӮЬӮЕӮЙ‘ҶӮ¬’…ӮҜӮҪӮӘҒAҺz”gӢ`ӢвӮЖҗИҺҹӮрҸ„Ӯй‘ҲӮўӮрӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒBҺz”gҺҒӮаӮЬӮҪҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖҲк–е’ҶҸ«ҢRүЖӮвӢg—ЗҺҒӮЙ•АӮФ–ј‘°ӮЕӮ ӮБӮҪҒB
Қ]ҢЛҺһ‘г‘OҠъ
Қ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮНҒAӢ`ҲАӮМҺqӢ`’иӮӘҸј•ҪҗҙҚNӮМ–…Ӯр•кӮЖӮөӮДӮўӮҪҠЦҢWӮЕ“ҝҗмҺҒӮЙҺжӮи—§ӮДӮзӮкҒAӮ»ӮМҺqӢ`–нӮМ‘гӮЙҺҠӮиӢҢӢg—З‘‘“аӮЕ3,000җОӮр—МӮөӮДҒAҚӮүЖӮМүЖҠiӮр•t—^ӮіӮкӮҪҒBӮұӮкҲИҚ~ӮМӢg—ЗҺҒӮНҒAҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮМӢV“TҠЦҢWӮрҺжӮиҺdҗШӮйүЖӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйҒB
Ӣ`–нӮМҺҹӮНӢg—ЗӢ`“~ӮӘ‘Ҡ‘ұӮөӮҪҒB
Ӣ`“~ӮМ’·’jӢg—ЗӢ`үӣӮНҒAҗФ•дҺ–ҢҸҒi’үҗb‘ ҒjӮЕ’ҳ–јӮЕӮ ӮйҒBӢ`үӣӮНҒAҢіҳ\14”NҒi1701”NҒjҒAӢV“TӮМҺw“ұӮЙҠЦӮөӮД’әҺgӢАүһ–рӮМ”d–ҒҗФ•д”ЛҺеҗу–м’·ӢйӮЖӮМҠФӮЙҠmҺ·Ӯрҗ¶Ӯ¶ҒA’·ӢйӮ©Ӯз“a’ҶҗnҸқӮрҺуӮҜҒA’·ӢйӮМҗШ• ҢгҒAҢіҳ\15”NҒi1702”NҒjӮЙ‘еҗО“а‘ Ҹ•ҲИүәҗу–мӮМҲвҗbӮзӮЙӮжӮй–{ҸҠӢg—З“@ӮЦӮМ“ўӮҝ“ьӮиӮрҺуӮҜӮД“ўӮҝҺжӮзӮкӮҪҒBҢіҳ\16”NҒi1703”NҒjӮЙӮНӢ`үӣӮМ‘·ӮЙӮ ӮҪӮй“–ҺеӢg—ЗӢ`ҺьӮӘүьҲХӮіӮкӮҪҒB
Қ]ҢЛҺһ‘гҢгҠъ
Ӣ`“~ӮМҺҹ’jӢ`ҸfҒiӢ`үӣӮМ’нҒjӮН“ҢҸрҗ©Ғi“ҢҸрҺҒӮНҺә’¬Һһ‘гӮМӢg—ЗҺҒ•КҸМҒjӮр–јҸжӮБӮДҒAҺq‘·ӮаҠш–{ӮЖӮөӮДҸ«ҢRүЖӮЙҺdӮҰӮДӮўӮҪӮӘҒAӢқ•Ы17”NҒi1732”NҒjҒAӢ`ҸfӮМ‘·ӮЙ“–ӮҪӮйӢ`ӣtӮӘҒAӢ`үӣӮМүЖҢnӮӘҗвӮҰӮДӮўӮйӮұӮЖӮр—қ—RӮЙҒA“ҢҸрүЖӮ©ӮзӢg—ЗүЖӮЦӮМ•ңҗ©Ӯр–Ӣ•{ӮЙҠиӮўҸoӮДӢ–ӮіӮкӮҪҒB
ӮҪӮҫӮөӮұӮМҚДӢ»Ӣg—ЗүЖӮН•АӮЭӮМҠш–{ӮЖӮөӮДӮЕӮ ӮиҒAҚӮүЖӮМҠiҺ®ӮН—^ӮҰӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBҲИҢгҒAӢg—ЗүЖӮН–ҫҺЎҲЫҗVӮЬӮЕҠш–{ӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйҒB
—р‘г
Ӣg—З’·ҺҒ
Ӣg—З–һҺҒ
Ӣg—З’еӢ`
Ӣg—З–һӢ`
ҒiҗјҸрӢg—ЗҒjҒi“ҢҸрӢg—ЗҒj
Ӣg—З–һ’е Ғ@Ӣg—З‘ёӢ`
Ӣg—ЗҸrҺҒ Ғ@Ӣg—З’©ҺҒ
Ӣg—ЗӢ`Ҹ® Ғ@Ӣg—ЗҺқ’·
Ӣg—ЗӢ`җ^ Ғ@Ӣg—ЗҺқҸ•
Ӣg—ЗӢ`җM Ғ@Ӣg—ЗӢ`“Ў
Ӣg—ЗӢ`Ңі Ғ@Ӣg—ЗҺқҗҙ
Ӣg—ЗӢ`ӢД Ғ@Ӣg—ЗҺқҚL
Ӣg—ЗӢ`ӢҪҒ@ ҚrҗмӢ`ҚL
Ӣg—ЗӢ`ҲА
Ӣg—ЗӢ`Ҹә
Ӣg—ЗӢ`’и
Ӣg—ЗӢ`–н
Ӣg—ЗӢ`“~
Ӣg—ЗӢ`үӣ
Ӣg—ЗӢ`Һь
үңҸBҒi•җ‘ ҒjӢg—ЗҺҒ
–{җ©ӮНҢ№ҺҒҒBҺOүНӢg—ЗҺҒӮМ“ҜҢnҒB
‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҺl’jҒEӢg—ЗӢ`ҢpӮӘҒAҢZҒE’·ҺҒӮЖ“ҜӮ¶ӮӯҺOүНҚ‘Ӣg—З‘‘Ӯр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮНӮ¶ӮЬӮйҒB’·ҺҒӮӘ“Ҝ‘‘җјҸрӮЙӢ’ӮБӮҪӮМӮЙ‘ОӮөӮДӢ`ҢpӮН“ҢҸрӮр—МӮөҒA‘OҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖӮаҢДӮОӮкӮҪҒB“ҢҸрӮМҸйӮН“ҢҸрҸйӮЕҒAҸкҸҠӮНҢ»ҚЭӮМҗј”цҺsӢg—З’¬йo”nҒiӮЬӮҫӮзӮЯҒjҸйҺRӮЕӮ ӮйҒBӮҪӮҫӮө‘ё”Ъ•Ә–¬ӮЕӮНӢ`ҢpӮМҺqӢg—ЗҢoҺҒӮӘҒuҒiҗјҸрӢg—ЗӮМҒjӢg—З–һҺҒӮМҺqӮЖӮИӮБӮҪҒvҒuҚҶӢg—ЗҒiӢg—ЗӮрҚҶӮ·ҒjҒvӮЖӢLҸqӮіӮкӮДӮўӮйҒB
ҚЎҗмҺҒ
ҚЎҗмҺҒҒiӮўӮЬӮӘӮнӮөҒj
“ъ–{ӮМ•җүЖҒB
–{җ©ӮНҢ№ҺҒӮЕҒAүЖҢnӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӮРӮЖӮВүН“аҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӢӮӮЮ‘«—ҳҺҒҢдҲкүЖҒEӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЙӮ ӮҪӮйҒBӢg—ЗүЖӮН‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҗe‘°ӮЕӮ Ӯи‘«—ҳҸ@үЖӮМҢpҸіҢ Ӯр—LӮөӮДӮЁӮиҒAҺz”gүЖӮв”©ҺRүЖӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·Ӯй‘јӮМ‘«—ҳҲк–еҸ”үЖӮЖӮН•КҠiӮМ’nҲКӮЙӮ ӮБӮҪҒBҚЎҗмүЖӮНӮ»ӮМ•ӘүЖӮЖӮөӮДҒAҸxүНӮМҺзҢмӮЙ‘гҒX”C–ҪӮіӮкӮҪҒBӮіӮзӮЙү“Қ]ҺзҢмүЖӮа•Ә—¬Ӯ·ӮйҒBҸүҠъӮМ•ӘүЖӮЕӮ ӮйҚЎҗмҠЦҢыүЖӮН–Ӣ•{ӮМ•тҢцҸOӮЕӮ ӮБӮҪҒB
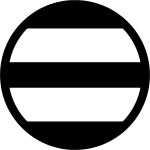
үЖ–дҒ@‘«—ҳ“сӮВҲш—ј
–{җ©
җҙҳaҢ№ҺҒӢ`үЖ—¬
үЖ‘c
ҚЎҗмҚ‘ҺҒ
Һн•К
•җүЖ
Һm‘°
Ҹoҗg’n
ҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSҚЎҗм‘‘
ҺеӮИҚӘӢ’’n
ҸxүНҚ‘
ү“Қ]Қ‘
’ҳ–јӮИҗl•Ё
ҚЎҗм—№Ҹr
ҚЎҗм”Н’ү
ҚЎҗмӢ`’ү
ҚЎҗмҺҒҗe
ҚЎҗмӢ`Ңі
ҚЎҗмҺҒҗ^
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
•iҗмҺҒҒi•җүЖҒj
–xүzҺҒҒEҗЈ–јҺҒҒi•җүЖҒj
Ҡ—ҢҙҺҒҒi•җүЖҒj
ҠT—v
‘OҸqӮМӮЖӮЁӮиҒAҚЎҗмүЖӮН‘«—ҳҲк–еӮЙӮЁӮўӮД–ј–еӮЖӮіӮкҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҗe‘°ӮЖӮөӮДӮМүЖҠiӮр—LӮөҒAҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮ©ӮзҢдҲкүЖӮЖӮөӮДӢцӮіӮкӮҪӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЙӮ ӮҪӮйҒBҒuҢдҸҠҒi‘«—ҳҸ«ҢRүЖҒjӮӘҗвӮҰӮИӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮИӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЙҒA‘«—ҳҸ@үЖҒiҺә’¬Ҹ«ҢRүЖҢn“қҒjӮМҢҢ–¬ӮӘ’fҗвӮөӮҪҸкҚҮӮЙӮНӢg—ЗүЖӮН‘«—ҳҸ@үЖӮЖҗӘҲО‘еҸ«ҢRҗEӮМҢpҸіҢ ӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·Ӯй“Б•КӮИүЖ•ҝӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮа“`ӮнӮйҒBӢg—ЗүЖӮ©ӮзӮНҺзҢмӮЁӮжӮСҠЗ—МӮвҺҳҸҠҸҠҺiӮӘ1җlӮаҸoӮДӮўӮИӮўӮМӮНӮұӮМӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒiӮұӮкӮзӮМ–рҗEӮНҒuүЖҗbӮМҺdҺ–ҒvӮЕӮ ӮиҒA‘«—ҳҸ@үЖӮМҢpҸіҢ ӮрҺқӮВүЖӮМҺТӮНҠЗ—МӮИӮЗӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйҗg•ӘӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒjҒBӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЕӮ ӮйҚЎҗмүЖӮНҺзҢмӮвҺҳҸҠҸҠҺiӮр–ұӮЯӮҪҒBҢRҢчӮЙӮжӮи•ӣҸ«ҢRӮМҸМҚҶӮрӮдӮйӮіӮкӮҪҚЎҗм”НҗӯӮМҺq”Н’үӮНүiӢқӮМ—җӮМҗнҢчӮЙӮжӮБӮДҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮ©Ӯз”ЮӮЖӮ»ӮМҺq‘·ҲИҠOӮМҚЎҗмҗ©ӮМҺg—pӮрӢЦӮ¶ӮйӮЖӮ·ӮйҒu“VүәҲк•cҺҡҒvӮМ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮҪӮҪӮЯ“ъ–{Ҡe’nӮЕүhӮҰӮДӮўӮҪҚЎҗмҗ©ӮаҸxүНҺзҢмүЖӮМӮЭӮЖӮИӮБӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA”Н’ү–vҢгӮЙҲкҺһҠъҸ@үЖӮМ’nҲКӮр‘ҲӮӨ—§ҸкӮЙӮ ӮБӮҪҸ¬ҺӯҺҒӮЙӮНӮ»ӮМҢгӮа–ңҲкӮМҚЫӮМүЖ“ВҢpҸіӮМ—LҺ‘ҠiҺТӮЖӮөӮДҚЎҗмҗ©ӮрӢ–ӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮ·ӮйҢӨӢҶӮаӮ Ӯй[1]ҒB
ҸxүНҚЎҗмүЖҒFҸxүНҺзҢмҗEӮр‘гҒXҢpҸіӮөӮҪ’„—¬ҒB–{ҚeӮЕӢLҸqҒB
ү“Қ]ҚЎҗмүЖҒF1.ӮМ•ӘүЖӮЕҒAү“Қ]ӮЙҸҠ—МӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЎҗм’еҗўҒi—№ҸrҒjӮр‘cӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҗЈ–јҺҒӮрҺQҸЖҒB
”м‘OҚЎҗмүЖҒF“ҜӮ¶Ӯӯ1.ӮМ•ӘүЖӮЕҒA”м‘OӮЙҸҠ—МӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЎҗм’ҮҸHӮр‘cӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҺқүiҺҒӮрҺQҸЖҒB
үЖ“`
Ҡҷ‘qҺһ‘г

ҚЎҗмҺҒ”ӯҸЛ’n”иҒiҲӨ’mҢ§җј”цҺsҒj
‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҸҺ’·ҺqӮЖӮөӮДӢg—ЗүЖӮрӢ»ӮөӮҪӢg—З’·ҺҒӮМ2’jӮЕӮ ӮйҚ‘ҺҒӮӘҒAӢg—ЗҺҒӮМҸҠ—МӮ©ӮзҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSҚЎҗм‘‘ҒiӮўӮЬӮӘӮнӮМӮөӮеӮӨҒAҢ»ҚЭӮМҲӨ’mҢ§җј”цҺsҚЎҗм’¬Һь•УҒjӮр•Ә—^ӮіӮкӮД–{ҠСӮЖӮөҒAҚЎҗмҺlҳYӮрҸМӮөӮҪӮМӮЙҺnӮЬӮйҒiӮ ӮйӮўӮНҚ‘ҺҒӮН’·ҺҒӮМүҷӮЕҒA—{ҺqӮЙӮИӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮӨҒjҒBҢ»ҚЭҒAҗј”цҺsҚЎҗм’¬ӮЙӮНҲӨ’mҢ§ӮЙӮжӮБӮДҢҡӮДӮзӮкӮҪҚЎҗмҺҒ”ӯҸЛ’nӮМҗО”иӮӘӮ ӮйҒB
Ӣg—ЗҺҒҒEҚЎҗмҺҒӮМ‘cӮЕӮ ӮБӮҪ’·ҺҒӮНҒA‘«—ҳүЖ‘y—МӮрҢpӮўӮҫ‘ЧҺҒӮМҢZӮЙӮ ӮҪӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒAӢg—ЗҺҒӮЙҺҹӮ®‘«—ҳҲк–еӮЖӮөӮДҸdӮ«ӮрӮИӮөҒAҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢдҲкүЖҒvӮЖҸМӮіӮкӮД•КҠiӮМҲөӮўӮрҺуӮҜӮҪӮұӮЖӮвҒAҒuҢдҸҠӮӘҗвӮҰӮкӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮкӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖӮўӮӨҸҳ—сҠПӮӘҗlҒXӮМҠФӮЙ’и’…ӮөӮҪӮМӮаҒAӮұӮӨӮөӮҪ”wҢiӮӘӮ ӮБӮДӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҢ»ҺАӮЙӮНҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮЙӮН‘ҪӮӯӮМ•КүЖӮӘ‘ҪӮӯӮ ӮиҒAӢg—ЗҺҒӮӘӮ»ӮӨӮөӮҪүЖҢnӮрүҹӮөӮМӮҜ‘«—ҳ–{үЖӮрҢpӮ°ӮйүВ”\җ«ӮНҢАӮиӮИӮӯ’бӮ©ӮБӮҪҒB
“м–k’©Һһ‘гӮ©ӮзҺә’¬Һһ‘г
Ҡҷ‘q–Ӣ•{–Е–SӮ©ӮзҢҡ•җӮМҗVҗӯӮрҢoӮйҚ ӮЙӮНҒAҚ‘ҺҒӮМ‘·ҒiҠоҺҒӮМ’·’jҒjӮЕӮ ӮйҚЎҗм—ҠҚ‘ӮӘҺlҗlӮМ’н[’ҚҺЯ 1]ӮвҺq’BӮр—ҰӮўӮД‘«—ҳ‘ёҺҒӮМ–k’©•ыӮЙ‘®ӮөҒAҠe’nӮЕҗнҢчӮрӢ“Ӯ°ӮҪҒB—ҠҚ‘ӮН’Ҷҗж‘гӮМ—җӮМҚЫӮМҸ¬–й’ҶҺRҚҮҗнӮЙӮД–kҸрҺһҚs•ыӮМ–јүz–MҺһӮр“ўӮҝҺжӮйҢчҗСӮрӢ“Ӯ°ӮҪӮӘҒA‘Ҡ–НҗмӮМҚҮҗнӮЕҺO’нӮМ—ҠҺьӮЖӢӨӮЙҗнҺҖҒA“с’нӮМ”Н–һӮаҸ¬ҺиҺwҢҙӮМҗнӮўӮЕҗнҺҖӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӮұӮкӮзӮМҢчҗСӮЙӮжӮиҒA—ҠҚ‘ӮМҺq—Ҡ’еӮН’OҢгҒE’A”nҒEҲц”ҰӮМҺзҢмӮЙ”CӮәӮзӮкӮҪҒBӮЬӮҪ—ҠҚ‘ӮМ––’нӮЕҒA‘ёҺҒӢЯӮӯӮЙҺdӮҰӮДӮўӮҪ”НҚ‘ӮаҸxүНҒEү“Қ]ӮМҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪҒB ҠПүһӮМҸп—җӮЙҚЫӮөӮДҒA”НҚ‘ӮМ’„’j”НҺҒӮН‘ёҺҒ•ыӮЙ‘®ӮөӮДҢчӮр—§ӮДҒAҸxүНҺзҢмҗEӮрҢpҸіҒB”НҺҒӮМҢn“қӮӘҚЎҗмҺҒ’„—¬ӮЖӮөӮДҸxүНҺзҢмӮрҗўҸPӮөӮҪҒBҸxүНҺзҢмӮЕӮ ӮйҚЎҗмҺҒӮНӢ«ӮрҗЪӮ·ӮйҠЦ“ҢҢц•ы—МӮрҠДҺӢӮ·Ӯй–рҠ„ӮрҸ«ҢRүЖӮ©Ӯз•үӮнӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮаӮўӮӨҒB
ҚЎҗмҺҒӮМҠфҗlӮ©ӮНҺә’¬–Ӣ•{ӮМҺҳҸҠӮМ’·ҠҜӮЙӮа”C–ҪӮіӮкӮйӮИӮЗҒAҺz”gҺҒҒE”©ҺRҺҒҒEҚЧҗмҺҒҒEҲкҗFҺҒҒEҺR–јҺҒҒEҗФҸјҺҒҒEӢһӢЙҺҒҒE“yҠтҺҒӮзӮЖӮЖӮаӮЙ–Ӣ•{ӮМҸhҳVӮМҲкҗlӮаӮВӮЖӮЯӮҪҒB
ӮЬӮҪҒA”НҺҒӮМ’нӮЕ”м‘OҺзҢмӮМ’еҗўҒi—№ҸrҒjӮНҠЗ—МӮМҚЧҗм—Ҡ”VӮЙӮжӮиӢгҸB’T‘иӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйӮЖҒA“м’©җЁ—НӮМӢӯӮ©ӮБӮҪӢгҸBӮр•Ҫ’иӮ·ӮйҺ–ӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮӘҒA‘«—ҳӢ`–һӮ©ӮзӮН—№ҸrӮМҗЁ—НӮв–јҗәӮМҚӮӮЬӮиӮрүхӮӯҺvӮнӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪ—lӮЕӮ ӮйҒBӮвӮӘӮД‘е“аӢ`ҚOӮӘӢ“•әӮ·ӮйүһүiӮМ—җӮӘ–u”ӯӮ·ӮйӮӘҒAҲкҺһӮұӮкӮЙүБ’SӮ·Ӯй“®Ӯ«ӮрҢ©Ӯ№ӮҪҠҷ‘qҢц•ыӮМ‘«—ҳҺҒ–һӮр— ӮЕ•°Ӯ«•tӮҜӮҪӮМӮӘ—№ҸrӮЕӮ ӮйҒAӮЖӮМӢ^”OӮрҠ|ӮҜӮзӮкӮҪҒB“ў”°ӮМ‘ОҸЫӮЙӮИӮйӮЖӮұӮлӮрҸгҗҷҢӣ’иӮҪӮҝӮМҸ•–ҪҠҲ“®ӮӘҺАӮрҢӢӮСҒAӢ`–һӮЦӮМҸг—ҢҺУҚЯӮЕҺНӮіӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө’ҶүӣҗӯҠEӮ©Ӯз’ЗӮнӮкӮҪӮкӮҪҸгӮЙҒAү“Қ]”јҚ‘ӮМҺзҢмӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒiҺcӮиӮМ”јҚ‘ӮМҺзҢмӮН’нӮМҚЎҗм’ҮҸHҒjҒBӮ»ӮМҺq‘·ӮНҺзҢмҗEӮрҺz”gҺҒӮЙҸчӮБӮҪҢгӮНҸxүНӮЙ“y’…ӮөҸxүНҚЎҗмүЖӮЙҺdӮҰӮҪҒB
җнҚ‘Һһ‘г
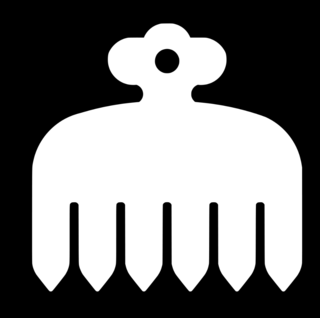
ҚЎҗмӢ`ҢіӮМ”nҲуӮЙ•`Ӯ©ӮкӮҪҗФ’№–дҒuҚЎҗмҗФ’№Ғv
җнҚ‘Һһ‘гӮМ15җўӢI––ӮЙҺҠӮиҒA”Ң•ғҲЙҗЁҗ·ҺһҒi–kҸр‘Ғү_ҒjӮМҸ•ӮҜӮЕүЖ“В‘ҲӮўӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪҺҒҗeӮНҒA–S•ғӢ`’үӮМ‘гӮЙ“ЪҚБӮөӮДӮўӮҪү“Қ]ӮЦӮМҚДҗNҚUӮрҺҺӮЭӮҪҒBӮ»ӮМҢӢүКҒA“G‘ОӮ·ӮйҺz”gҺҒӮр”rӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮДү“Қ]ҺзҢмҗEӮрҠl“ҫӮ·ӮйҒBӮЬӮҪҒAҚb”гҚ‘ӮМ—җҚ‘Ҹу‘ФӮЙүо“ьӮөҒAҚb”гҗјҢSӮМҚ‘ҸO‘еҲдҺҒӮрҸ]‘®ӮіӮ№ӮДӮўӮйҒB—МҚ‘“қҺЎӮЙӮЁӮўӮДӮН•ӘҚ‘–@ҒuҚЎҗмүј–ј–Ъҳ^ҒvӮр’иӮЯӮДҒAҚЎҗмҺҒӮрҗнҚ‘‘е–јӮЙ”ӯ“WӮіӮ№ӮҪҒBҸx•{ӮЙӮН—вҗтҲЧҳaӮИӮЗҗн—җӮр”рӮҜӮҪҢцүЖӮӘүәҢьӮөҒA•¶ү»“IӮЙӮаү~ҸnӮөӮҪҺһ‘гӮрҢ}ӮҰӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB
ҺҒҗe–vҢгӮНҗіҺәҺхҢj“тӮӘ’„’jҒEҺҒӢPӮрҢгҢ©ӮөӮҪҒB“V•¶5”NҒi1536”NҒj3ҢҺ17“ъӮЙҺҒӢPҒE•FҢЬҳYӮӘҺҖӢҺӮ·ӮйӮЖҒAҺҒӢPӮМ’нӮЕҸoүЖӮөӮДӮўӮҪҢәҚLҢb’TӮЖҗсҠxҸі–FӮМҠФӮЕүЖ“В‘ҲӮўҒuүФ‘qӮМ—җҒvӮӘ–u”ӯӮ·ӮйҒBүФ‘qӮМ—җӮНҗсҠxҸі–FӮӘҗ§ӮөҒAҚЎҗмӢ`ҢіӮЖүь–јӮөӮДҚЎҗмүЖӮМ“–ҺеӮЖӮИӮйҒBӢ`ҢіҠъӮЙӮНӮ»ӮкӮЬӮЕ“G‘ОӮөӮДӮўӮҪҚb”гӮМ•җ“cҺҒӮЖҳa–rӮөӮДҚbҸx“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкҒAӮұӮкӮЙӮжӮиҚЎҗмҺҒӮЖ‘Ҡ–НӮМҢг–kҸрҺҒӮЖӮМҠЦҢWӮрҲ«ү»ӮіӮ№ҒAҒuүН“ҢӮМ—җҒvӮрҲшӮ«ӢNӮұӮ·ҒBүН“ҢӮМ—җӮН•җ“cҺҒӮМ“–ҺеҒE•җ“cҗ°җMҒiҗMҢәҒjӮМ’ҮүоӮаӮ ӮиҚЎҗмҒEҢг–kҸрҺҒҠФӮЕӮН“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкҒAӮіӮзӮЙ•җ“cҺҒӮЖҢг–kҸрҺҒӮМҠФӮЕӮаҚb‘Ҡ“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкӮДӮЁӮиҒAҺOҺТӮМҠЦҢWӮНҒAҚb‘ҠҸxҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮЙ”ӯ“WӮ·ӮйҒB
Ӣ`ҢіӮНҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮр”wҢiӮЙҺOүНҗiҸoӮЙ—НӮр’ҚӮ¬ҒAҺг‘Мү»ӮөӮҪҺOүНҚ‘ӮМҸј•ҪҺҒӮрҸ]‘®ӮіӮ№ӮҪӮЩӮ©ҒA“ҜӮ¶Ӯӯ”ц’ЈӮМҗD“cҺҒӮЖҒuҲАҸйҚҮҗнҒvҒuҸ¬“ӨҚвӮМҗнӮўҒvӮИӮЗӮрҗнӮўҒAҺOүНӮ©ӮзҗD“cҺҒӮр’чӮЯҸoӮ·ӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪҒBҸј•ҪҺҒӮМ“–ҺеӮЕӮ ӮйҸј•ҪҢіҚNҒi“ҝҗмүЖҚNҒjӮН–Ӣ•{ӮМ•тҢцҸOӮЕҸxүНҚЎҗмҺҒӮМҸdҗbӮЕӮаӮ ӮБӮҪҚЎҗмҠЦҢыүЖӮ©ӮзҗіҺәӮрҢ}ӮҰӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДҒAҸxүНҒEү“Қ]ҒEҺOүНӮМ3Ӯ©Қ‘ӮрҺx”zӮ·ӮйҸгӮЙ”ц’ЈӮМҲк•”Ӯр—LӮ·ӮйӮӘҒA1560”NҒiүiҳ\3”NҒj5ҢҺ19“ъӮЙүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮЕҗD“cҗM’·ӮЙ–{җwӮрҸPҢӮӮіӮкҒA”sҺҖӮөӮҪҒB
Ӣ`ҢіӮМҗХӮрҢpӮўӮҫҺҒҗ^ӮМ‘гӮЙӮНҒAҺOүНүӘҚиҸйӮЕҸј•ҪҢіҚNӮӘҺ©—§Ӯ·ӮйӮИӮЗҺx”z—МҚ‘ӮМ“®—hӮрҸөӮ«ҒAҗbҸ]Қ‘җlӮҪӮҝӮМҚЎҗм—Ј”ҪӮр—U”ӯӮ·ӮйҒBҺҒҗ^ӮӘҺ©ӮзҸoҗwӮөӮҪ‘ў”ҪҢRҗӘ”°җнӮЕӮНҒAҺOүН•у”СҢSӮЙӮЁӮўӮДҸј•ҪҢRӮЙ‘е”sӮ·ӮйҒBӮвӮӘӮДӢg“cҸйӮрҺёҠЧӮөҒAҺOүНӮМҺx”zҢ Ӯа‘rҺёӮ·ӮйҒB
Қb”гӮМ•җ“cҺҒӮНҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮр”wҢiӮЙүzҢгҚ‘ӮМ’·”цҢiҢХҒiҸгҗҷҢӘҗMҒjӮЖҗм’Ҷ“ҮӮМҗнӮўӮрҢJӮиҚLӮ°ӮДӮўӮҪӮӘҒAҗм’Ҷ“ҮӮМҗнӮўӮНүiҳ\4”NҒi1561”NҒjӮМҢ_Ӣ@ӮЙҸI‘§Ӯ·ӮйҒBҚЎҗмҺҒҗ^ӮМ–…ӮЕӮ Ӯй—дҸјү@ӮН•җ“cҗMҢәӮМ’„’jҒEӢ`җMӮЙүЕӮ¬ҒAӮұӮМҚҘҲчӮЙӮжӮиҚbҸx“Ҝ–ҝӮӘҗ¬—§ӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA•җ“cүЖӮЕӮНүiҳ\8”NҒi1565”NҒjӮЙӢ`җMӮМ–d”ҪӮӘ”ӯҠoӮө—H•ВӮіӮкҒAүiҳ\10”NҒi1567”NҒj10ҢҺ19“ъӮЙҺҖӢҺӮ·ӮйӢ`җMҺ–ҢҸӮӘ”ӯҗ¶ҒB—дҸјү@ӮаҸx•{ӮЦ‘—ҠТӮіӮкҚbҸxҠЦҢWӮНҢҜҲ«ү»ҒBӮіӮзӮЙ•җ“cүЖӮЕӮНҗMҢәҺl’jӮМҗz–KҸҹ—ҠҒi•җ“cҸҹ—ҠҒjӮӘҗўҺqӮЖӮИӮиҒAҸҹ—ҠӮМҺәӮЙҗD“cҗM’·ӮМ—{Ҹ—ӮрҢ}ӮҰҠЦҢWӮрҺқӮВӮжӮӨӮЙӮИӮйӮИӮЗҒAҺҹ‘жӮЙҚЎҗмӮЖӮМ“G‘О“IҺpҗЁӮрҢ©Ӯ№ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB
үiҳ\11”NҒi1568”NҒj––ӮЙ•җ“cҗMҢәӮН“ҝҗмҺҒӮЖ“Ҝ–ҝӮөҒAҚЎҗм—МҚ‘ӮЦӮМҗNҚUӮрҠJҺnӮ·ӮйҒiҸxүНҗNҚUҒjҒB•җ“cҺҒӮМҸxүНҗNҚUӮЙ‘ОӮөӮДҢг–kҸрҺҒӮНҚЎҗмӮЙүБҗЁӮөҒAӮұӮкӮЙӮжӮиҚb‘Ҡ“Ҝ–ҝӮа”j’]ӮөӮҪҒBҚЎҗмҺҒӮНҗ””NӮМҠФӮЙ—МҚ‘ҸxүНӮЖҺOүНӮр•җ“cҺҒӮЖ“ҝҗмҺҒҒiҸј•ҪҺҒүьӮЯҒjӮЙӮжӮБӮД“ҢҗјӮ©ӮзҸuӮӯҠФӮЙҗШӮиҠlӮзӮкӮҪ[’ҚҺЯ 2]ҒB1568”NҒiүiҳ\11”NҒjҒAү“Қ]ӮЙ’ЗӮў—§ӮДӮзӮкӮҪҺҒҗ^ӮНҒAҚЕҢгӮМӢ’“_Ҡ|җмҸйӮр“ҝҗмҢRӮМҗОҗмүЖҗ¬ӮЙ–ҫӮҜ“nӮөҒAҠ|җмҸйҺеӮМ’©”д“Ю‘Ч’©“ҷӮЖӢӨӮЙ–kҸрҺҒӮр—ҠӮБӮДҸ¬“cҢҙӮЙ‘ЮӢҺҒBҗнҚ‘‘е–јӮЖӮөӮДӮМҚЎҗмҺҒӮНүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮ©Ӯз8”NӮЕ–Е–SӮөҒAҸxүНӮН•җ“c—МҚ‘ү»ӮіӮкӮйҒB
Қ]ҢЛҺһ‘г

ҠПҗтҺӣҒi“ҢӢһ“sҗҷ•АӢжҒj
ҺҒҗ^ӮНӢИҗЬӮрҢoӮД“ҝҗмүЖҚNӮМ”ЭҢмӮрҺуӮҜӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒAӢЯҚ]Қ‘–мҸFҢSҒiҢ»ҒEҺ үкҢ§–мҸFҺsҒjӮЙ500җОӮМ’mҚs’nӮӘҲА“gӮіӮкӮҪҒBҺҒҗ^ӮМ’„‘·ҒE’ј–[ӮНҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮЙҸoҺdӮөӮДҚӮүЖҗEҒiүңҚӮүЖҒjӮЙҸAӮ«ҒAҸG’үҒEүЖҢхҒEүЖҚjӮМҺO‘гӮЙӮнӮҪӮБӮД’©’мӮЖӮМҢрҸВӮИӮЗӮЙ–z‘–ӮөӮҪҒB1645”NҒiҗі•Ы2”NҒjҒAӢһ“sӮЦӮМҺgҺТӮр–ұӮЯӮДүЖҚNӮЦӮМҒu“ҢҸЖӢ{ҒvҚҶҗйүәӮр“ҫӮҪҢчӮЙӮжӮиҒAүЖҢхӮ©Ӯз•җ‘ Қ‘‘Ҫ–ҖҢSҲд‘җ‘әҒiҢ»ҒE“ҢӢһ“sҗҷ•АӢжҒjӮИӮЗ500җОӮМ’mҚsӮрүБ‘қӮіӮкҒAүЖҳ\ӮН“sҚҮ1000җОӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒB’ј–[ӮМҠҜҲКӮНҚЎҗмүЖ—р‘гӮЕҚЕӮаҚӮӮўҚ¶ӢЯүqҸӯҸ«ӮЬӮЕҸёӮиҒAҺq‘·Ӯ©ӮзӮН’ҶӢ»ӮМ‘cӮЖӢВӮӘӮкӮҪҒB
ҚӮүЖҠш–{ӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮөӮҪҚ]ҢЛҺһ‘гӮМҚЎҗмүЖӮЕӮНҒA11җlӮМ“–ҺеӮМӮӨӮҝҒA’ј–[ҒEҺҒ–rҒEӢ`‘ЧҒEӢ`ҸІҒEӢ`—pҒE”НҸ–ӮМ6җlӮӘҚӮүЖҗEӮЙҸAӮўӮДӮўӮйҒB–Ӣ––ӮМ“–ҺеҒE”НҸ–ӮНҒAҚӮүЖҸoҗgҺТӮЖӮөӮД—BҲкҺб”NҠсӮЙҸA”CӮөҒAҠҜҢRӮЖӮМҚuҳaҒEҚ]ҢЛҸйӮМҠJҸйӮЙҚЫӮөӮДҗs—НӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯө–ҫҺЎҲЫҗVҢгӮНҒA‘јӮМҺm‘°ӮЖ“ҜӮ¶ӮӯүЖҳ\ӮрҺёӮБӮД–v—ҺӮөӮҪӮӨӮҰҒAҲкҗl‘§ҺqӮЕӮ ӮйҸiҗlӮЙӮаҗж—§ӮҪӮкӮҪҒB1887”NҒi–ҫҺЎ20”NҒjҒA”НҸ–ӮМҺҖӮЙӮжӮБӮДҚЎҗмҺҒӮНҗвүЖӮөӮҪҒB
Қ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮЁӮҜӮйҚЎҗмҺҒӮМ•м’сҺӣӮНҒAҗҷ•АӢжҚЎҗмӮМ•уҺмҺRҠПҗтҺӣҒi‘Ӯ“ҙҸ@ҒjҒAҗҷ•АӢжҳa“cӮМдЭҸ№ҺR’·ү„ҺӣҒi‘Ӯ“ҙҸ@ҒjӮЕӮ ӮйҒBҠПҗтҺӣӮЙӮ ӮйҚЎҗмҺҒ—Э‘гӮМ•жӮН“ҢӢһ“sҺw’иӢҢҗХӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮИӮЁҒAҠПҗтҺӣӮМҸZҸҠӮЕӮ ӮйҒuҚЎҗмҒvӮНҒAӮұӮМ’nӮӘҚЎҗмүЖӮМ’mҚs’nӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮҝӮИӮсӮЕӮўӮйҒB
ӮИӮЁҒAҺҒҗ^ӮМҺҹ’jӮМҚӮӢvӮа“ҝҗмҸG’үӮЙҸoҺdӮөҒA•iҗмҺҒӮрҸМӮөӮД[’ҚҺЯ 3]–{үЖӮЖӮЖӮаӮЙҚӮүЖӮЙ—сӮөӮҪҒB
Ңn•Ҳ
Ң№Ӣ`үЖ
Ң№Ӣ`Қ‘
‘«—ҳӢ`ҚN
‘«—ҳӢ`Ң“
‘«—ҳӢ`ҺҒ
Ӣg—З’·ҺҒ
ҚЎҗмҚ‘ҺҒ
ҚЎҗмҠоҺҒ
ҚЎҗм”НҚ‘
ҚЎҗм”НҺҒ
ҒiҸxүНүЖҒj
ҚЎҗм‘Ч”Н
ҚЎҗм”Н’ү
ҚЎҗмӢ`’ү
ҚЎҗмҺҒҗe
ҚЎҗмӢ`Ңі
“ъ–{ӮМ•җүЖҒB
–{җ©ӮНҢ№ҺҒӮЕҒAүЖҢnӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӮРӮЖӮВүН“аҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӢӮӮЮ‘«—ҳҺҒҢдҲкүЖҒEӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЙӮ ӮҪӮйҒBӢg—ЗүЖӮН‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҗe‘°ӮЕӮ Ӯи‘«—ҳҸ@үЖӮМҢpҸіҢ Ӯр—LӮөӮДӮЁӮиҒAҺz”gүЖӮв”©ҺRүЖӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·Ӯй‘јӮМ‘«—ҳҲк–еҸ”үЖӮЖӮН•КҠiӮМ’nҲКӮЙӮ ӮБӮҪҒBҚЎҗмүЖӮНӮ»ӮМ•ӘүЖӮЖӮөӮДҒAҸxүНӮМҺзҢмӮЙ‘гҒX”C–ҪӮіӮкӮҪҒBӮіӮзӮЙү“Қ]ҺзҢмүЖӮа•Ә—¬Ӯ·ӮйҒBҸүҠъӮМ•ӘүЖӮЕӮ ӮйҚЎҗмҠЦҢыүЖӮН–Ӣ•{ӮМ•тҢцҸOӮЕӮ ӮБӮҪҒB
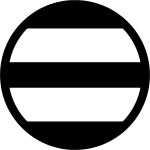
үЖ–дҒ@‘«—ҳ“сӮВҲш—ј
–{җ©
җҙҳaҢ№ҺҒӢ`үЖ—¬
үЖ‘c
ҚЎҗмҚ‘ҺҒ
Һн•К
•җүЖ
Һm‘°
Ҹoҗg’n
ҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSҚЎҗм‘‘
ҺеӮИҚӘӢ’’n
ҸxүНҚ‘
ү“Қ]Қ‘
’ҳ–јӮИҗl•Ё
ҚЎҗм—№Ҹr
ҚЎҗм”Н’ү
ҚЎҗмӢ`’ү
ҚЎҗмҺҒҗe
ҚЎҗмӢ`Ңі
ҚЎҗмҺҒҗ^
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
•iҗмҺҒҒi•җүЖҒj
–xүzҺҒҒEҗЈ–јҺҒҒi•җүЖҒj
Ҡ—ҢҙҺҒҒi•җүЖҒj
ҠT—v
‘OҸqӮМӮЖӮЁӮиҒAҚЎҗмүЖӮН‘«—ҳҲк–еӮЙӮЁӮўӮД–ј–еӮЖӮіӮкҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҗe‘°ӮЖӮөӮДӮМүЖҠiӮр—LӮөҒAҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮ©ӮзҢдҲкүЖӮЖӮөӮДӢцӮіӮкӮҪӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЙӮ ӮҪӮйҒBҒuҢдҸҠҒi‘«—ҳҸ«ҢRүЖҒjӮӘҗвӮҰӮИӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮИӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЙҒA‘«—ҳҸ@үЖҒiҺә’¬Ҹ«ҢRүЖҢn“қҒjӮМҢҢ–¬ӮӘ’fҗвӮөӮҪҸкҚҮӮЙӮНӢg—ЗүЖӮН‘«—ҳҸ@үЖӮЖҗӘҲО‘еҸ«ҢRҗEӮМҢpҸіҢ ӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·Ӯй“Б•КӮИүЖ•ҝӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮа“`ӮнӮйҒBӢg—ЗүЖӮ©ӮзӮНҺзҢмӮЁӮжӮСҠЗ—МӮвҺҳҸҠҸҠҺiӮӘ1җlӮаҸoӮДӮўӮИӮўӮМӮНӮұӮМӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒiӮұӮкӮзӮМ–рҗEӮНҒuүЖҗbӮМҺdҺ–ҒvӮЕӮ ӮиҒA‘«—ҳҸ@үЖӮМҢpҸіҢ ӮрҺқӮВүЖӮМҺТӮНҠЗ—МӮИӮЗӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйҗg•ӘӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒjҒBӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЕӮ ӮйҚЎҗмүЖӮНҺзҢмӮвҺҳҸҠҸҠҺiӮр–ұӮЯӮҪҒBҢRҢчӮЙӮжӮи•ӣҸ«ҢRӮМҸМҚҶӮрӮдӮйӮіӮкӮҪҚЎҗм”НҗӯӮМҺq”Н’үӮНүiӢқӮМ—җӮМҗнҢчӮЙӮжӮБӮДҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮ©Ӯз”ЮӮЖӮ»ӮМҺq‘·ҲИҠOӮМҚЎҗмҗ©ӮМҺg—pӮрӢЦӮ¶ӮйӮЖӮ·ӮйҒu“VүәҲк•cҺҡҒvӮМ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮҪӮҪӮЯ“ъ–{Ҡe’nӮЕүhӮҰӮДӮўӮҪҚЎҗмҗ©ӮаҸxүНҺзҢмүЖӮМӮЭӮЖӮИӮБӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA”Н’ү–vҢгӮЙҲкҺһҠъҸ@үЖӮМ’nҲКӮр‘ҲӮӨ—§ҸкӮЙӮ ӮБӮҪҸ¬ҺӯҺҒӮЙӮНӮ»ӮМҢгӮа–ңҲкӮМҚЫӮМүЖ“ВҢpҸіӮМ—LҺ‘ҠiҺТӮЖӮөӮДҚЎҗмҗ©ӮрӢ–ӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮ·ӮйҢӨӢҶӮаӮ Ӯй[1]ҒB
ҸxүНҚЎҗмүЖҒFҸxүНҺзҢмҗEӮр‘гҒXҢpҸіӮөӮҪ’„—¬ҒB–{ҚeӮЕӢLҸqҒB
ү“Қ]ҚЎҗмүЖҒF1.ӮМ•ӘүЖӮЕҒAү“Қ]ӮЙҸҠ—МӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЎҗм’еҗўҒi—№ҸrҒjӮр‘cӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҗЈ–јҺҒӮрҺQҸЖҒB
”м‘OҚЎҗмүЖҒF“ҜӮ¶Ӯӯ1.ӮМ•ӘүЖӮЕҒA”м‘OӮЙҸҠ—МӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЎҗм’ҮҸHӮр‘cӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҺқүiҺҒӮрҺQҸЖҒB
үЖ“`
Ҡҷ‘qҺһ‘г

ҚЎҗмҺҒ”ӯҸЛ’n”иҒiҲӨ’mҢ§җј”цҺsҒj
‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҸҺ’·ҺqӮЖӮөӮДӢg—ЗүЖӮрӢ»ӮөӮҪӢg—З’·ҺҒӮМ2’jӮЕӮ ӮйҚ‘ҺҒӮӘҒAӢg—ЗҺҒӮМҸҠ—МӮ©ӮзҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSҚЎҗм‘‘ҒiӮўӮЬӮӘӮнӮМӮөӮеӮӨҒAҢ»ҚЭӮМҲӨ’mҢ§җј”цҺsҚЎҗм’¬Һь•УҒjӮр•Ә—^ӮіӮкӮД–{ҠСӮЖӮөҒAҚЎҗмҺlҳYӮрҸМӮөӮҪӮМӮЙҺnӮЬӮйҒiӮ ӮйӮўӮНҚ‘ҺҒӮН’·ҺҒӮМүҷӮЕҒA—{ҺqӮЙӮИӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮӨҒjҒBҢ»ҚЭҒAҗј”цҺsҚЎҗм’¬ӮЙӮНҲӨ’mҢ§ӮЙӮжӮБӮДҢҡӮДӮзӮкӮҪҚЎҗмҺҒ”ӯҸЛ’nӮМҗО”иӮӘӮ ӮйҒB
Ӣg—ЗҺҒҒEҚЎҗмҺҒӮМ‘cӮЕӮ ӮБӮҪ’·ҺҒӮНҒA‘«—ҳүЖ‘y—МӮрҢpӮўӮҫ‘ЧҺҒӮМҢZӮЙӮ ӮҪӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒAӢg—ЗҺҒӮЙҺҹӮ®‘«—ҳҲк–еӮЖӮөӮДҸdӮ«ӮрӮИӮөҒAҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢдҲкүЖҒvӮЖҸМӮіӮкӮД•КҠiӮМҲөӮўӮрҺуӮҜӮҪӮұӮЖӮвҒAҒuҢдҸҠӮӘҗвӮҰӮкӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮкӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖӮўӮӨҸҳ—сҠПӮӘҗlҒXӮМҠФӮЙ’и’…ӮөӮҪӮМӮаҒAӮұӮӨӮөӮҪ”wҢiӮӘӮ ӮБӮДӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҢ»ҺАӮЙӮНҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮЙӮН‘ҪӮӯӮМ•КүЖӮӘ‘ҪӮӯӮ ӮиҒAӢg—ЗҺҒӮӘӮ»ӮӨӮөӮҪүЖҢnӮрүҹӮөӮМӮҜ‘«—ҳ–{үЖӮрҢpӮ°ӮйүВ”\җ«ӮНҢАӮиӮИӮӯ’бӮ©ӮБӮҪҒB
“м–k’©Һһ‘гӮ©ӮзҺә’¬Һһ‘г
Ҡҷ‘q–Ӣ•{–Е–SӮ©ӮзҢҡ•җӮМҗVҗӯӮрҢoӮйҚ ӮЙӮНҒAҚ‘ҺҒӮМ‘·ҒiҠоҺҒӮМ’·’jҒjӮЕӮ ӮйҚЎҗм—ҠҚ‘ӮӘҺlҗlӮМ’н[’ҚҺЯ 1]ӮвҺq’BӮр—ҰӮўӮД‘«—ҳ‘ёҺҒӮМ–k’©•ыӮЙ‘®ӮөҒAҠe’nӮЕҗнҢчӮрӢ“Ӯ°ӮҪҒB—ҠҚ‘ӮН’Ҷҗж‘гӮМ—җӮМҚЫӮМҸ¬–й’ҶҺRҚҮҗнӮЙӮД–kҸрҺһҚs•ыӮМ–јүz–MҺһӮр“ўӮҝҺжӮйҢчҗСӮрӢ“Ӯ°ӮҪӮӘҒA‘Ҡ–НҗмӮМҚҮҗнӮЕҺO’нӮМ—ҠҺьӮЖӢӨӮЙҗнҺҖҒA“с’нӮМ”Н–һӮаҸ¬ҺиҺwҢҙӮМҗнӮўӮЕҗнҺҖӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӮұӮкӮзӮМҢчҗСӮЙӮжӮиҒA—ҠҚ‘ӮМҺq—Ҡ’еӮН’OҢгҒE’A”nҒEҲц”ҰӮМҺзҢмӮЙ”CӮәӮзӮкӮҪҒBӮЬӮҪ—ҠҚ‘ӮМ––’нӮЕҒA‘ёҺҒӢЯӮӯӮЙҺdӮҰӮДӮўӮҪ”НҚ‘ӮаҸxүНҒEү“Қ]ӮМҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪҒB ҠПүһӮМҸп—җӮЙҚЫӮөӮДҒA”НҚ‘ӮМ’„’j”НҺҒӮН‘ёҺҒ•ыӮЙ‘®ӮөӮДҢчӮр—§ӮДҒAҸxүНҺзҢмҗEӮрҢpҸіҒB”НҺҒӮМҢn“қӮӘҚЎҗмҺҒ’„—¬ӮЖӮөӮДҸxүНҺзҢмӮрҗўҸPӮөӮҪҒBҸxүНҺзҢмӮЕӮ ӮйҚЎҗмҺҒӮНӢ«ӮрҗЪӮ·ӮйҠЦ“ҢҢц•ы—МӮрҠДҺӢӮ·Ӯй–рҠ„ӮрҸ«ҢRүЖӮ©Ӯз•үӮнӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮаӮўӮӨҒB
ҚЎҗмҺҒӮМҠфҗlӮ©ӮНҺә’¬–Ӣ•{ӮМҺҳҸҠӮМ’·ҠҜӮЙӮа”C–ҪӮіӮкӮйӮИӮЗҒAҺz”gҺҒҒE”©ҺRҺҒҒEҚЧҗмҺҒҒEҲкҗFҺҒҒEҺR–јҺҒҒEҗФҸјҺҒҒEӢһӢЙҺҒҒE“yҠтҺҒӮзӮЖӮЖӮаӮЙ–Ӣ•{ӮМҸhҳVӮМҲкҗlӮаӮВӮЖӮЯӮҪҒB
ӮЬӮҪҒA”НҺҒӮМ’нӮЕ”м‘OҺзҢмӮМ’еҗўҒi—№ҸrҒjӮНҠЗ—МӮМҚЧҗм—Ҡ”VӮЙӮжӮиӢгҸB’T‘иӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйӮЖҒA“м’©җЁ—НӮМӢӯӮ©ӮБӮҪӢгҸBӮр•Ҫ’иӮ·ӮйҺ–ӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮӘҒA‘«—ҳӢ`–һӮ©ӮзӮН—№ҸrӮМҗЁ—НӮв–јҗәӮМҚӮӮЬӮиӮрүхӮӯҺvӮнӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪ—lӮЕӮ ӮйҒBӮвӮӘӮД‘е“аӢ`ҚOӮӘӢ“•әӮ·ӮйүһүiӮМ—җӮӘ–u”ӯӮ·ӮйӮӘҒAҲкҺһӮұӮкӮЙүБ’SӮ·Ӯй“®Ӯ«ӮрҢ©Ӯ№ӮҪҠҷ‘qҢц•ыӮМ‘«—ҳҺҒ–һӮр— ӮЕ•°Ӯ«•tӮҜӮҪӮМӮӘ—№ҸrӮЕӮ ӮйҒAӮЖӮМӢ^”OӮрҠ|ӮҜӮзӮкӮҪҒB“ў”°ӮМ‘ОҸЫӮЙӮИӮйӮЖӮұӮлӮрҸгҗҷҢӣ’иӮҪӮҝӮМҸ•–ҪҠҲ“®ӮӘҺАӮрҢӢӮСҒAӢ`–һӮЦӮМҸг—ҢҺУҚЯӮЕҺНӮіӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө’ҶүӣҗӯҠEӮ©Ӯз’ЗӮнӮкӮҪӮкӮҪҸгӮЙҒAү“Қ]”јҚ‘ӮМҺзҢмӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒiҺcӮиӮМ”јҚ‘ӮМҺзҢмӮН’нӮМҚЎҗм’ҮҸHҒjҒBӮ»ӮМҺq‘·ӮНҺзҢмҗEӮрҺz”gҺҒӮЙҸчӮБӮҪҢгӮНҸxүНӮЙ“y’…ӮөҸxүНҚЎҗмүЖӮЙҺdӮҰӮҪҒB
җнҚ‘Һһ‘г
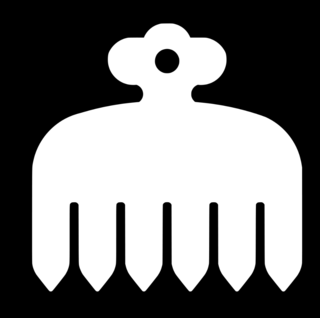
ҚЎҗмӢ`ҢіӮМ”nҲуӮЙ•`Ӯ©ӮкӮҪҗФ’№–дҒuҚЎҗмҗФ’№Ғv
җнҚ‘Һһ‘гӮМ15җўӢI––ӮЙҺҠӮиҒA”Ң•ғҲЙҗЁҗ·ҺһҒi–kҸр‘Ғү_ҒjӮМҸ•ӮҜӮЕүЖ“В‘ҲӮўӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪҺҒҗeӮНҒA–S•ғӢ`’үӮМ‘гӮЙ“ЪҚБӮөӮДӮўӮҪү“Қ]ӮЦӮМҚДҗNҚUӮрҺҺӮЭӮҪҒBӮ»ӮМҢӢүКҒA“G‘ОӮ·ӮйҺz”gҺҒӮр”rӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮДү“Қ]ҺзҢмҗEӮрҠl“ҫӮ·ӮйҒBӮЬӮҪҒAҚb”гҚ‘ӮМ—җҚ‘Ҹу‘ФӮЙүо“ьӮөҒAҚb”гҗјҢSӮМҚ‘ҸO‘еҲдҺҒӮрҸ]‘®ӮіӮ№ӮДӮўӮйҒB—МҚ‘“қҺЎӮЙӮЁӮўӮДӮН•ӘҚ‘–@ҒuҚЎҗмүј–ј–Ъҳ^ҒvӮр’иӮЯӮДҒAҚЎҗмҺҒӮрҗнҚ‘‘е–јӮЙ”ӯ“WӮіӮ№ӮҪҒBҸx•{ӮЙӮН—вҗтҲЧҳaӮИӮЗҗн—җӮр”рӮҜӮҪҢцүЖӮӘүәҢьӮөҒA•¶ү»“IӮЙӮаү~ҸnӮөӮҪҺһ‘гӮрҢ}ӮҰӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB
ҺҒҗe–vҢгӮНҗіҺәҺхҢj“тӮӘ’„’jҒEҺҒӢPӮрҢгҢ©ӮөӮҪҒB“V•¶5”NҒi1536”NҒj3ҢҺ17“ъӮЙҺҒӢPҒE•FҢЬҳYӮӘҺҖӢҺӮ·ӮйӮЖҒAҺҒӢPӮМ’нӮЕҸoүЖӮөӮДӮўӮҪҢәҚLҢb’TӮЖҗсҠxҸі–FӮМҠФӮЕүЖ“В‘ҲӮўҒuүФ‘qӮМ—җҒvӮӘ–u”ӯӮ·ӮйҒBүФ‘qӮМ—җӮНҗсҠxҸі–FӮӘҗ§ӮөҒAҚЎҗмӢ`ҢіӮЖүь–јӮөӮДҚЎҗмүЖӮМ“–ҺеӮЖӮИӮйҒBӢ`ҢіҠъӮЙӮНӮ»ӮкӮЬӮЕ“G‘ОӮөӮДӮўӮҪҚb”гӮМ•җ“cҺҒӮЖҳa–rӮөӮДҚbҸx“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкҒAӮұӮкӮЙӮжӮиҚЎҗмҺҒӮЖ‘Ҡ–НӮМҢг–kҸрҺҒӮЖӮМҠЦҢWӮрҲ«ү»ӮіӮ№ҒAҒuүН“ҢӮМ—җҒvӮрҲшӮ«ӢNӮұӮ·ҒBүН“ҢӮМ—җӮН•җ“cҺҒӮМ“–ҺеҒE•җ“cҗ°җMҒiҗMҢәҒjӮМ’ҮүоӮаӮ ӮиҚЎҗмҒEҢг–kҸрҺҒҠФӮЕӮН“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкҒAӮіӮзӮЙ•җ“cҺҒӮЖҢг–kҸрҺҒӮМҠФӮЕӮаҚb‘Ҡ“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкӮДӮЁӮиҒAҺOҺТӮМҠЦҢWӮНҒAҚb‘ҠҸxҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮЙ”ӯ“WӮ·ӮйҒB
Ӣ`ҢіӮНҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮр”wҢiӮЙҺOүНҗiҸoӮЙ—НӮр’ҚӮ¬ҒAҺг‘Мү»ӮөӮҪҺOүНҚ‘ӮМҸј•ҪҺҒӮрҸ]‘®ӮіӮ№ӮҪӮЩӮ©ҒA“ҜӮ¶Ӯӯ”ц’ЈӮМҗD“cҺҒӮЖҒuҲАҸйҚҮҗнҒvҒuҸ¬“ӨҚвӮМҗнӮўҒvӮИӮЗӮрҗнӮўҒAҺOүНӮ©ӮзҗD“cҺҒӮр’чӮЯҸoӮ·ӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪҒBҸј•ҪҺҒӮМ“–ҺеӮЕӮ ӮйҸј•ҪҢіҚNҒi“ҝҗмүЖҚNҒjӮН–Ӣ•{ӮМ•тҢцҸOӮЕҸxүНҚЎҗмҺҒӮМҸdҗbӮЕӮаӮ ӮБӮҪҚЎҗмҠЦҢыүЖӮ©ӮзҗіҺәӮрҢ}ӮҰӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДҒAҸxүНҒEү“Қ]ҒEҺOүНӮМ3Ӯ©Қ‘ӮрҺx”zӮ·ӮйҸгӮЙ”ц’ЈӮМҲк•”Ӯр—LӮ·ӮйӮӘҒA1560”NҒiүiҳ\3”NҒj5ҢҺ19“ъӮЙүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮЕҗD“cҗM’·ӮЙ–{җwӮрҸPҢӮӮіӮкҒA”sҺҖӮөӮҪҒB
Ӣ`ҢіӮМҗХӮрҢpӮўӮҫҺҒҗ^ӮМ‘гӮЙӮНҒAҺOүНүӘҚиҸйӮЕҸј•ҪҢіҚNӮӘҺ©—§Ӯ·ӮйӮИӮЗҺx”z—МҚ‘ӮМ“®—hӮрҸөӮ«ҒAҗbҸ]Қ‘җlӮҪӮҝӮМҚЎҗм—Ј”ҪӮр—U”ӯӮ·ӮйҒBҺҒҗ^ӮӘҺ©ӮзҸoҗwӮөӮҪ‘ў”ҪҢRҗӘ”°җнӮЕӮНҒAҺOүН•у”СҢSӮЙӮЁӮўӮДҸј•ҪҢRӮЙ‘е”sӮ·ӮйҒBӮвӮӘӮДӢg“cҸйӮрҺёҠЧӮөҒAҺOүНӮМҺx”zҢ Ӯа‘rҺёӮ·ӮйҒB
Қb”гӮМ•җ“cҺҒӮНҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮр”wҢiӮЙүzҢгҚ‘ӮМ’·”цҢiҢХҒiҸгҗҷҢӘҗMҒjӮЖҗм’Ҷ“ҮӮМҗнӮўӮрҢJӮиҚLӮ°ӮДӮўӮҪӮӘҒAҗм’Ҷ“ҮӮМҗнӮўӮНүiҳ\4”NҒi1561”NҒjӮМҢ_Ӣ@ӮЙҸI‘§Ӯ·ӮйҒBҚЎҗмҺҒҗ^ӮМ–…ӮЕӮ Ӯй—дҸјү@ӮН•җ“cҗMҢәӮМ’„’jҒEӢ`җMӮЙүЕӮ¬ҒAӮұӮМҚҘҲчӮЙӮжӮиҚbҸx“Ҝ–ҝӮӘҗ¬—§ӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA•җ“cүЖӮЕӮНүiҳ\8”NҒi1565”NҒjӮЙӢ`җMӮМ–d”ҪӮӘ”ӯҠoӮө—H•ВӮіӮкҒAүiҳ\10”NҒi1567”NҒj10ҢҺ19“ъӮЙҺҖӢҺӮ·ӮйӢ`җMҺ–ҢҸӮӘ”ӯҗ¶ҒB—дҸјү@ӮаҸx•{ӮЦ‘—ҠТӮіӮкҚbҸxҠЦҢWӮНҢҜҲ«ү»ҒBӮіӮзӮЙ•җ“cүЖӮЕӮНҗMҢәҺl’jӮМҗz–KҸҹ—ҠҒi•җ“cҸҹ—ҠҒjӮӘҗўҺqӮЖӮИӮиҒAҸҹ—ҠӮМҺәӮЙҗD“cҗM’·ӮМ—{Ҹ—ӮрҢ}ӮҰҠЦҢWӮрҺқӮВӮжӮӨӮЙӮИӮйӮИӮЗҒAҺҹ‘жӮЙҚЎҗмӮЖӮМ“G‘О“IҺpҗЁӮрҢ©Ӯ№ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB
үiҳ\11”NҒi1568”NҒj––ӮЙ•җ“cҗMҢәӮН“ҝҗмҺҒӮЖ“Ҝ–ҝӮөҒAҚЎҗм—МҚ‘ӮЦӮМҗNҚUӮрҠJҺnӮ·ӮйҒiҸxүНҗNҚUҒjҒB•җ“cҺҒӮМҸxүНҗNҚUӮЙ‘ОӮөӮДҢг–kҸрҺҒӮНҚЎҗмӮЙүБҗЁӮөҒAӮұӮкӮЙӮжӮиҚb‘Ҡ“Ҝ–ҝӮа”j’]ӮөӮҪҒBҚЎҗмҺҒӮНҗ””NӮМҠФӮЙ—МҚ‘ҸxүНӮЖҺOүНӮр•җ“cҺҒӮЖ“ҝҗмҺҒҒiҸј•ҪҺҒүьӮЯҒjӮЙӮжӮБӮД“ҢҗјӮ©ӮзҸuӮӯҠФӮЙҗШӮиҠlӮзӮкӮҪ[’ҚҺЯ 2]ҒB1568”NҒiүiҳ\11”NҒjҒAү“Қ]ӮЙ’ЗӮў—§ӮДӮзӮкӮҪҺҒҗ^ӮНҒAҚЕҢгӮМӢ’“_Ҡ|җмҸйӮр“ҝҗмҢRӮМҗОҗмүЖҗ¬ӮЙ–ҫӮҜ“nӮөҒAҠ|җмҸйҺеӮМ’©”д“Ю‘Ч’©“ҷӮЖӢӨӮЙ–kҸрҺҒӮр—ҠӮБӮДҸ¬“cҢҙӮЙ‘ЮӢҺҒBҗнҚ‘‘е–јӮЖӮөӮДӮМҚЎҗмҺҒӮНүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮ©Ӯз8”NӮЕ–Е–SӮөҒAҸxүНӮН•җ“c—МҚ‘ү»ӮіӮкӮйҒB
Қ]ҢЛҺһ‘г

ҠПҗтҺӣҒi“ҢӢһ“sҗҷ•АӢжҒj
ҺҒҗ^ӮНӢИҗЬӮрҢoӮД“ҝҗмүЖҚNӮМ”ЭҢмӮрҺуӮҜӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒAӢЯҚ]Қ‘–мҸFҢSҒiҢ»ҒEҺ үкҢ§–мҸFҺsҒjӮЙ500җОӮМ’mҚs’nӮӘҲА“gӮіӮкӮҪҒBҺҒҗ^ӮМ’„‘·ҒE’ј–[ӮНҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮЙҸoҺdӮөӮДҚӮүЖҗEҒiүңҚӮүЖҒjӮЙҸAӮ«ҒAҸG’үҒEүЖҢхҒEүЖҚjӮМҺO‘гӮЙӮнӮҪӮБӮД’©’мӮЖӮМҢрҸВӮИӮЗӮЙ–z‘–ӮөӮҪҒB1645”NҒiҗі•Ы2”NҒjҒAӢһ“sӮЦӮМҺgҺТӮр–ұӮЯӮДүЖҚNӮЦӮМҒu“ҢҸЖӢ{ҒvҚҶҗйүәӮр“ҫӮҪҢчӮЙӮжӮиҒAүЖҢхӮ©Ӯз•җ‘ Қ‘‘Ҫ–ҖҢSҲд‘җ‘әҒiҢ»ҒE“ҢӢһ“sҗҷ•АӢжҒjӮИӮЗ500җОӮМ’mҚsӮрүБ‘қӮіӮкҒAүЖҳ\ӮН“sҚҮ1000җОӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒB’ј–[ӮМҠҜҲКӮНҚЎҗмүЖ—р‘гӮЕҚЕӮаҚӮӮўҚ¶ӢЯүqҸӯҸ«ӮЬӮЕҸёӮиҒAҺq‘·Ӯ©ӮзӮН’ҶӢ»ӮМ‘cӮЖӢВӮӘӮкӮҪҒB
ҚӮүЖҠш–{ӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮөӮҪҚ]ҢЛҺһ‘гӮМҚЎҗмүЖӮЕӮНҒA11җlӮМ“–ҺеӮМӮӨӮҝҒA’ј–[ҒEҺҒ–rҒEӢ`‘ЧҒEӢ`ҸІҒEӢ`—pҒE”НҸ–ӮМ6җlӮӘҚӮүЖҗEӮЙҸAӮўӮДӮўӮйҒB–Ӣ––ӮМ“–ҺеҒE”НҸ–ӮНҒAҚӮүЖҸoҗgҺТӮЖӮөӮД—BҲкҺб”NҠсӮЙҸA”CӮөҒAҠҜҢRӮЖӮМҚuҳaҒEҚ]ҢЛҸйӮМҠJҸйӮЙҚЫӮөӮДҗs—НӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯө–ҫҺЎҲЫҗVҢгӮНҒA‘јӮМҺm‘°ӮЖ“ҜӮ¶ӮӯүЖҳ\ӮрҺёӮБӮД–v—ҺӮөӮҪӮӨӮҰҒAҲкҗl‘§ҺqӮЕӮ ӮйҸiҗlӮЙӮаҗж—§ӮҪӮкӮҪҒB1887”NҒi–ҫҺЎ20”NҒjҒA”НҸ–ӮМҺҖӮЙӮжӮБӮДҚЎҗмҺҒӮНҗвүЖӮөӮҪҒB
Қ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮЁӮҜӮйҚЎҗмҺҒӮМ•м’сҺӣӮНҒAҗҷ•АӢжҚЎҗмӮМ•уҺмҺRҠПҗтҺӣҒi‘Ӯ“ҙҸ@ҒjҒAҗҷ•АӢжҳa“cӮМдЭҸ№ҺR’·ү„ҺӣҒi‘Ӯ“ҙҸ@ҒjӮЕӮ ӮйҒBҠПҗтҺӣӮЙӮ ӮйҚЎҗмҺҒ—Э‘гӮМ•жӮН“ҢӢһ“sҺw’иӢҢҗХӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮИӮЁҒAҠПҗтҺӣӮМҸZҸҠӮЕӮ ӮйҒuҚЎҗмҒvӮНҒAӮұӮМ’nӮӘҚЎҗмүЖӮМ’mҚs’nӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮҝӮИӮсӮЕӮўӮйҒB
ӮИӮЁҒAҺҒҗ^ӮМҺҹ’jӮМҚӮӢvӮа“ҝҗмҸG’үӮЙҸoҺdӮөҒA•iҗмҺҒӮрҸМӮөӮД[’ҚҺЯ 3]–{үЖӮЖӮЖӮаӮЙҚӮүЖӮЙ—сӮөӮҪҒB
Ңn•Ҳ
Ң№Ӣ`үЖ
Ң№Ӣ`Қ‘
‘«—ҳӢ`ҚN
‘«—ҳӢ`Ң“
‘«—ҳӢ`ҺҒ
Ӣg—З’·ҺҒ
ҚЎҗмҚ‘ҺҒ
ҚЎҗмҠоҺҒ
ҚЎҗм”НҚ‘
ҚЎҗм”НҺҒ
ҒiҸxүНүЖҒj
ҚЎҗм‘Ч”Н
ҚЎҗм”Н’ү
ҚЎҗмӢ`’ү
ҚЎҗмҺҒҗe
ҚЎҗмӢ`Ңі
2020”N01ҢҺ14“ъ
Ң№Ӣ`ҚN
Ң№Ӣ`ҚNҒ@ӮЭӮИӮаӮЖ ӮМ ӮжӮөӮвӮ·
‘«—ҳӢ`ҚNҒ@Ӯ ӮөӮ©ӮӘӮжӮөӮвӮ·

‘«—ҳҺҒӮМ‘cӮМ‘«—ҳӢ`ҚN‘ң
•ҪҲАҺһ‘г––ҠъӮМ•җҸ«ҒB
‘«—ҳҺҒӮМ‘cҒB
—Өүң”»ҠҜӮЖӮаҸМӮөӮҪҒB
“ъ–{ӮМ•ҪҲАҺһ‘гӮМ•җҺm
Һһ‘г
•ҪҲАҺһ‘гҢгҠъ
җ¶’a
‘еҺЎ2”NҒi1127”NҒj
ҺҖ–v
•ЫҢі2”N5ҢҺ29“ъҒi1157”N7ҢҺ7“ъҒj
үь–ј
Ӣ`•ЫҒЁӢ`‘ЧҒЁӢ`ҚNҒЁ“№’BҒiӮЗӮӨӮҪӮВҒj
•К–ј
‘«—ҳӢ`ҚNҒA‘«—ҳ—Өүң”»ҠҜҒA‘«—ҳ‘ җl”»ҠҜ
•жҸҠ
“И–ШҢ§‘«—ҳҺsүЖ•x’¬ӮМиfҲўҺӣ
ҠҜҲК
‘«—ҳҸҜүәҺiҗEҒA–k–К•җҺmҒAҚ¶үq–еҲСҒAҢҹ”сҲбҺgҒAҸ]ҢЬҲКүәҒA‘ җlҒA—ӨүңҺз
ҺеҢN
’№үHҸгҚc
ҺҒ‘°
үН“аҢ№ҺҒӢ`Қ‘—¬Ғi‘«—ҳҺҒҒj
•ғ•к
•ғҒFҢ№Ӣ`Қ‘ҒA•кҒFҢ№—L–[ӮМ–ә
ҢZ’н
Ӣ`ҸdҒAӢ`ҚNҒAӢG–M
ҚИ
җіҺәҒF“ЎҢҙӢG”НӮМ—{Ҹ—Ғi“ЎҢҙ”Н’үӮМ–әҒj
Һq
Ӣ`җҙҒAӢ`’·ҒAӢ`Ң“ҒAӢ`–[
җ¶ҠU
•ҪҲАҢгҠъӮЙ‘OӢг”NӮМ–рҒEҢгҺO”NӮМ–рӮЕҠҲ–фӮөӮҪҢ№Ӣ`үЖӮМҺqҒEӢ`Қ‘ӮМҺҹ’j[1]ҒB
•ғӮ©Ӯзүә–мҚ‘‘«—ҳ‘‘Ӯр‘Ҡ‘ұӮөҒA‘«—ҳӮр–јҺҡӮЖӮөӮҪҒB•ғҒEӢ`Қ‘ӮМ–{—МӮЕӮ Ӯй”Ә”Ұ‘‘Ӯр‘Ҡ‘ұӮөӮҪҲЩ•кҢZӮМӢ`ҸdӮНҒA•ғӮЖӢӨӮЙҸг–мҚ‘җV“c‘‘ӮрҠJҚӨӮөҗV“cҺҒӮМ‘cӮЖӮИӮйҒBӢ`ҚNӮН”M“c‘еӢ{Һi“ЎҢҙӢG”НӮМ—{Ҹ—ҒiҺА‘·ҒjӮрӣWӮиҒAүН“аҢ№ҺҒӮМ“Ҝ‘°Ң№Ӣ`’©ӮЖ‘ҠгЫӮМҠЦҢWӮЙӮИӮи“Ҝ–ҝӮрҢӢӮсӮЕӮўӮйҒB
ҚNҺЎҢі”NҒi1142”NҒj10ҢҺҒA’№үHҸгҚcӮӘҢҡ—§ӮөӮҪҲАҠyҺхү@ӮЙ‘«—ҳ‘‘ӮрҠсҗiҒAӢ`ҚNӮНүәҺiӮЖӮИӮБӮҪҒBӢvҲАӮМҚ ӮЙҸг—ҢӮөҒAҸҠ—МӮМҠсҗiӮӘӢ@үҸӮЖӮИӮБӮД’№үHҸгҚcӮЙ–k–К•җҺmӮЖӮөӮДҺdӮҰҒA‘ җlӮвҢҹ”сҲбҺgӮЙ”CҠҜӮөӮҪҒBӮЬӮҪ—ӨүңҺзӮЙӮа”CӮәӮзӮкҒAҒu—Өүң”»ҠҜҒvӮЖӮаҢДӮОӮкӮҪҒB
•ЫҢіҢі”NҒi1156”NҒjҒAҺҖҠъӮӘ”—ӮБӮҪ’№үH–@ҚcӮӘ“БӮЙҗM—ҠӮЕӮ«ӮйӮЖӮөӮДҢгҺ–Ӯр‘хӮөӮҪҢЬҗlӮМ•җҺmӮМ’ҶӮЙӢ`ҚNӮМ–јӮаӮ ӮБӮҪҒB–@Қc•цҢдҢгӮЙӢNӮұӮБӮҪ•ЫҢіӮМ—җӮЕӮНҒAҢ№Ӣ`’©ӮЖӢӨӮЙҢг”’үН“VҚc‘ӨӮЙ•tӮ«ҒA•Ҫҗҙҗ·ӮМ300ӢRҒAӢ`’©ӮМ200ӢRӮЙҺҹӮ®100ӢRӮрҸ]ӮҰҒA“VҚc•ыҺе—НӮЖӮөӮДҚЕ–k•ыӮМӢЯүq•ы–КӮМҺз”хӮр’S“–ӮөӮҪҒB—җҢгҒA“G•ыӮМҚ~Ҹ«ҒE•ҪүЖҚO•ғҺqӮрҸҲҢYҒBҳ_ҢчҚsҸЬӮЙӮжӮиҸё“aӮрӢ–ӮіӮкҒAҸ]ҢЬҲКүә‘е•vҲСӮЙ”CҠҜӮөӮҪҒB
Ҹ«—ҲӮрҸъ–]ӮіӮкӮҪӮӘҒA—Ӯ”N•aӮр“ҫӮД31ҚОӮЕ–vӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB
‘«—ҳӢ`ҚNҒ@Ӯ ӮөӮ©ӮӘӮжӮөӮвӮ·

‘«—ҳҺҒӮМ‘cӮМ‘«—ҳӢ`ҚN‘ң
•ҪҲАҺһ‘г––ҠъӮМ•җҸ«ҒB
‘«—ҳҺҒӮМ‘cҒB
—Өүң”»ҠҜӮЖӮаҸМӮөӮҪҒB
“ъ–{ӮМ•ҪҲАҺһ‘гӮМ•җҺm
Һһ‘г
•ҪҲАҺһ‘гҢгҠъ
җ¶’a
‘еҺЎ2”NҒi1127”NҒj
ҺҖ–v
•ЫҢі2”N5ҢҺ29“ъҒi1157”N7ҢҺ7“ъҒj
үь–ј
Ӣ`•ЫҒЁӢ`‘ЧҒЁӢ`ҚNҒЁ“№’BҒiӮЗӮӨӮҪӮВҒj
•К–ј
‘«—ҳӢ`ҚNҒA‘«—ҳ—Өүң”»ҠҜҒA‘«—ҳ‘ җl”»ҠҜ
•жҸҠ
“И–ШҢ§‘«—ҳҺsүЖ•x’¬ӮМиfҲўҺӣ
ҠҜҲК
‘«—ҳҸҜүәҺiҗEҒA–k–К•җҺmҒAҚ¶үq–еҲСҒAҢҹ”сҲбҺgҒAҸ]ҢЬҲКүәҒA‘ җlҒA—ӨүңҺз
ҺеҢN
’№үHҸгҚc
ҺҒ‘°
үН“аҢ№ҺҒӢ`Қ‘—¬Ғi‘«—ҳҺҒҒj
•ғ•к
•ғҒFҢ№Ӣ`Қ‘ҒA•кҒFҢ№—L–[ӮМ–ә
ҢZ’н
Ӣ`ҸdҒAӢ`ҚNҒAӢG–M
ҚИ
җіҺәҒF“ЎҢҙӢG”НӮМ—{Ҹ—Ғi“ЎҢҙ”Н’үӮМ–әҒj
Һq
Ӣ`җҙҒAӢ`’·ҒAӢ`Ң“ҒAӢ`–[
җ¶ҠU
•ҪҲАҢгҠъӮЙ‘OӢг”NӮМ–рҒEҢгҺO”NӮМ–рӮЕҠҲ–фӮөӮҪҢ№Ӣ`үЖӮМҺqҒEӢ`Қ‘ӮМҺҹ’j[1]ҒB
•ғӮ©Ӯзүә–мҚ‘‘«—ҳ‘‘Ӯр‘Ҡ‘ұӮөҒA‘«—ҳӮр–јҺҡӮЖӮөӮҪҒB•ғҒEӢ`Қ‘ӮМ–{—МӮЕӮ Ӯй”Ә”Ұ‘‘Ӯр‘Ҡ‘ұӮөӮҪҲЩ•кҢZӮМӢ`ҸdӮНҒA•ғӮЖӢӨӮЙҸг–мҚ‘җV“c‘‘ӮрҠJҚӨӮөҗV“cҺҒӮМ‘cӮЖӮИӮйҒBӢ`ҚNӮН”M“c‘еӢ{Һi“ЎҢҙӢG”НӮМ—{Ҹ—ҒiҺА‘·ҒjӮрӣWӮиҒAүН“аҢ№ҺҒӮМ“Ҝ‘°Ң№Ӣ`’©ӮЖ‘ҠгЫӮМҠЦҢWӮЙӮИӮи“Ҝ–ҝӮрҢӢӮсӮЕӮўӮйҒB
ҚNҺЎҢі”NҒi1142”NҒj10ҢҺҒA’№үHҸгҚcӮӘҢҡ—§ӮөӮҪҲАҠyҺхү@ӮЙ‘«—ҳ‘‘ӮрҠсҗiҒAӢ`ҚNӮНүәҺiӮЖӮИӮБӮҪҒBӢvҲАӮМҚ ӮЙҸг—ҢӮөҒAҸҠ—МӮМҠсҗiӮӘӢ@үҸӮЖӮИӮБӮД’№үHҸгҚcӮЙ–k–К•җҺmӮЖӮөӮДҺdӮҰҒA‘ җlӮвҢҹ”сҲбҺgӮЙ”CҠҜӮөӮҪҒBӮЬӮҪ—ӨүңҺзӮЙӮа”CӮәӮзӮкҒAҒu—Өүң”»ҠҜҒvӮЖӮаҢДӮОӮкӮҪҒB
•ЫҢіҢі”NҒi1156”NҒjҒAҺҖҠъӮӘ”—ӮБӮҪ’№үH–@ҚcӮӘ“БӮЙҗM—ҠӮЕӮ«ӮйӮЖӮөӮДҢгҺ–Ӯр‘хӮөӮҪҢЬҗlӮМ•җҺmӮМ’ҶӮЙӢ`ҚNӮМ–јӮаӮ ӮБӮҪҒB–@Қc•цҢдҢгӮЙӢNӮұӮБӮҪ•ЫҢіӮМ—җӮЕӮНҒAҢ№Ӣ`’©ӮЖӢӨӮЙҢг”’үН“VҚc‘ӨӮЙ•tӮ«ҒA•Ҫҗҙҗ·ӮМ300ӢRҒAӢ`’©ӮМ200ӢRӮЙҺҹӮ®100ӢRӮрҸ]ӮҰҒA“VҚc•ыҺе—НӮЖӮөӮДҚЕ–k•ыӮМӢЯүq•ы–КӮМҺз”хӮр’S“–ӮөӮҪҒB—җҢгҒA“G•ыӮМҚ~Ҹ«ҒE•ҪүЖҚO•ғҺqӮрҸҲҢYҒBҳ_ҢчҚsҸЬӮЙӮжӮиҸё“aӮрӢ–ӮіӮкҒAҸ]ҢЬҲКүә‘е•vҲСӮЙ”CҠҜӮөӮҪҒB
Ҹ«—ҲӮрҸъ–]ӮіӮкӮҪӮӘҒA—Ӯ”N•aӮр“ҫӮД31ҚОӮЕ–vӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB
”©ҺRҺҒ
”©ҺRҺҒҒiӮНӮҪӮҜӮвӮЬӮө/ӮНӮҪӮҜӮвӮЬӮӨӮ¶ҒjӮНҒA•җ‘ Қ‘Ӯр–{ҠС’nӮЖӮ·Ӯй•җүЖӮМҲк‘°ҒBҺеӮЙҠә•җ•ҪҺҒҢnӮЖҗҙҳaҢ№ҺҒҢnӮМ2үЖҢnӮӘӮ ӮйӮӘҒA—јҺТӮНҠФҗЪ“IӮИҢҢүҸҠЦҢWӮЕӮ ӮйҒiҢгҸqҒjҒB“ЗӮЭӮЙӮН‘јӮЙҒuӮНӮҪӮвӮЬҒvӮаӮ ӮйҒB
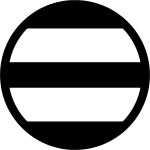
үЖ–дҒ@Ӯ ӮөӮ©ӮӘӮУӮҪӮВӮРӮ«
Ғ@Ғ@Ғ@‘«—ҳ“сӮВҲш
–{җ©
Ҡә•җ•ҪҺҒҚӮ–]үӨ—¬
җҙҳaҢ№ҺҒҒiүН“аҢ№ҺҒҒj
үЖ‘c
”©ҺRҸd”\
”©ҺRӢ`Ҹғ
Һн•К
•җүЖ
Һm‘°
Ҹoҗg’n
•җ‘ Қ‘’jеОҢS”©ҺRӢҪ
ҺеӮИҚӘӢ’’n
үН“аҚ‘ҒAӢIҲЙҚ‘
‘еҳaҚ‘ҒAүz’ҶҚ‘
”\“oҚ‘ҒA—ӨүңҚ‘
’ҳ–јӮИҗl•Ё
”©ҺRҸd’үҒA”©ҺRҚ‘җҙ
”©ҺR–һүЖҒA”©ҺRҗӯ’·
”©ҺRӢ`ҸAҒA”©ҺRӢ`‘ұ
”©ҺRӢ`ҢpҒA”©ҺRҲкҗҙ
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
ҠвҸјҺҒҒi•җүЖ ҒЁ үШ‘°Ғi’jҺЭҒjҒj
“с–{ҸјҺҒҒi•җүЖҒj
“c’ҶҺҒҒi•җүЖҒj
үН“аҸaҗмҺҒҒi•җүЖҒj
ҲАҲдҺҒҒi•җүЖҒj ӮИӮЗ
Һә’¬Һһ‘гӮЙӮН”©ҺRӢаҢбүЖӮӘ‘еҳaүF’qҢSҒEүН“аҒEӢIҲЙҒiҠЗ—МҸA”CҺһӮЙӮНҺRҸйӮаҒjӮИӮЗӮМӢE“аӮЁӮжӮСӮ»ӮМҺь•УҚ‘ӮЙҠY“–Ӯ·ӮйҸd—vӮИ’nҲжӮрҺзҢмӮЖӮөӮДҺЎӮЯҒAӮЬӮҪ–Ӣ•{ӮМҠЗ—МӮЖӮөӮДҚ‘ӮМҗӯ–ұӮрҺ·ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAүЖ“В‘ҲӮўӮЙӮжӮиҒA‘ҚҸBүЖӮЖ”цҸBүЖӮЙ•ӘӮ©ӮкӮДҒAүһҗmӮМ—җ–u”ӯӮМҲкҲцӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢгӮаҢғӮөӮӯ‘ҲӮў‘ұӮҜӮҪҒB
ӮЬӮҪҒA–k—ӨӮМүz’ҶӮМҺзҢмӮаҢ“ӮЛҒA•ӘүЖӮН”\“oӮМҺзҢмӮр‘гҒXҗўҸPӮ·ӮйҒB’ҳ–јӮИ––ебӮЖӮөӮДҺАӢЖүЖӮМ”©ҺRҲкҗҙӮӘӮўӮйҒB
ҠT—v
•ҪҲАҺһ‘гҒEҠҷ‘qҺһ‘г
Қв“Ң”Ә•ҪҺҒӮМҲк‘°ҒE’Ғ•ғҸdҚOӮМҺqӮЕӮ Ӯй’Ғ•ғҸd”\ӮӘ•җ‘ Қ‘’jеОҢS”©ҺRӢҪҒiӮНӮҪӮҜӮвӮЬӮІӮӨҒAҢ»ҚЭӮМҚйӢКҢ§җ[’JҺs”©ҺRҺь•УҒjӮЙҸҠ—МӮр“ҫӮД”©ҺRҗ©ӮрҸМӮөӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮйҒi•Ҫҗ©”©ҺRүЖҒjҒBҺЎҸіҒEҺхүiӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДҒAӮ»ӮМҺq”©ҺRҸd’үӮНҒAӮНӮ¶ӮЯӮН•ҪүЖ•ыӮЙӮВӮўӮҪӮӘҢгӮЙҢ№—Ҡ’©ӮЙҸ]ӮўҒAҲкғm’JӮМҗнӮўӮвүңҸBҚҮҗнӮИӮЗӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBҸd’үӮНӮМӮҝӮЙ–kҸрҺһҗӯӮЖ‘О—§ӮөҒAҢіӢv2”NҒi1205”NҒjӮЙ•җ‘ Қ‘“с–“җмӮЕ–kҸрӢ`ҺһӮМҢRӮЖӮМҗ퓬ӮЕ”sҺҖӮөӮҪҒi”©ҺRҸd’үӮМ—җҒjҒB
Ӯ»ӮМҢгҒAҸd’үӮМӢҢ—МӮЖ”©ҺRӮМ–јҗХӮНҒA‘«—ҳӢ`Ң“ӮМҸҺ’·ҺqҒE‘«—ҳӢ`ҸғӮӘҸd’үӮМ–ў–SҗlӮЕӮ Ӯй–kҸрҺһҗӯҸ—[’ҚҺЯ 1]ӮЖҚҘҲчӮөҒAҢpҸіӮіӮкӮҪҒBӢ`ҸғӮНӮаӮЖӮаӮЖҗV“cӢ`Ң“Ғi‘«—ҳӢ`Ң“ӮЖ“ҜжҒӮМҸ]ҢZ’нҒjӮМ–әӮЖҚҘҲчӮөҺqӮа–ЧҒiӮаӮӨҒjӮҜӮДӮўӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҚИҺqӮрӢ`җвӮөӮҪҸгӮЕӮМҢpҸіӮЕӮ ӮБӮҪ[’ҚҺЯ 2]ҒBӮұӮкӮЙӮжӮБӮДҠә•җ•ҪҺҒӮМӮРӮЖӮВ’Ғ•ғ•ҪҺҒӮМ—¬ӮкӮрӮӯӮЮ•Ҫҗ©”©ҺRҺҒӮНҸБ–ЕӮөҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӮРӮЖӮВүН“аҢ№ҺҒӮМҲкҢnҒE‘«—ҳүЖӮМҲк–еӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB
Ӣ`ҸғӮМүЖҢnҒiҢ№җ©”©ҺRүЖҒjӮН–ј–еҒE”©ҺRүЖӮМ–јҗХӮрҢpҸіӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҢгӮЙ‘«—ҳҲк–еӮМ’ҶӮЕ•КүЖҲөӮўӮМ‘«—ҳ”ц’ЈүЖҒi•җүqүЖҒAӮўӮнӮдӮйҺz”gүЖҒjӮЙҺҹӮўӮЕҚӮӮўҸҳ—сӮЙ—сӮ№ӮзӮкҒAҚЧҗмүЖӮИӮЗ‘јӮМүЖҗbӢШ•ӘүЖӮЖӮНҲЩӮИӮй‘ТӢцӮр‘«—ҳҸ@үЖӮ©ӮзҺуӮҜӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB
ӢIҲЙӮЁӮжӮСүН“аҒEүz’ҶӮМҺзҢмӮрӮЁӮЁӮЮӮЛ–ұӮЯҒA•ӘүЖӮН”\“oҺзҢмӮр–ұӮЯӮҪҒB
Һә’¬Һһ‘гҲИҚ~
•ТҸW
Ңҡ•җ3”NҒi1336”NҒjӮЙ‘«—ҳ‘ёҺҒӮӘҺә’¬–Ӣ•{Ӯр‘n—§Ӯ·ӮйӮЖҒA”©ҺRүЖӮНӮұӮкӮЬӮЕӮМҢчҗСӮЙӮжӮБӮДүz’ҶҒEүН“аҒEӢIҲЙӮМҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪҒB‘«—ҳүЖӮМ“а•ҙӮЕӮ ӮйҠПүһӮМҸп—җӮЕӮНҒAҸҺ—¬ӮМ”©ҺRҚ‘җҙӮН‘«—ҳ’јӢ`•ыӮЙ•tӮӯӮаҢгӮЙ‘ёҺҒ•ыӮЙҲЖ‘ЦӮҰӮөӮДүЖҗЁӮр•ЫӮҝҒAӮ»ӮМҲк•ыӮЕ”©ҺRүЖ’„—¬ӮМ”©ҺRҚӮҚ‘ҒEҚ‘ҺҒ•ғҺqӮНҒAҠПүһ2”NҒi1351”NҒj’јӢ`”hӮМӢg—З’еүЖӮЙ”sӮкҺ©ҠQӮөҒAҚ‘ҺҒӮМҺq“с–{ҸјҚ‘‘FӮН“с–{ҸјӮЙҲЪӮБӮҪҒiүңҸB”©ҺRүЖҒjҒB
–{—ҲӮМ’„—¬ӮЕӮ ӮйүңҸB”©ҺRүЖӮӘҗҠ‘ЮӮ·Ӯй’ҶӮЕҒA”©ҺRҚ‘җҙӮМүЖҢnҒiӢаҢбүЖҒjӮӘ”©ҺRүЖӮМ‘y—МҠiӮЖӮИӮйҒBҚ‘җҙӮНҠЦ“ҢҠЗ—МӮЙ”C–ҪӮіӮкӮД“ҢҚ‘ӮЕ“м’©•ыӮЖҗнӮӨӮӘҒAӮ»ӮМҢгҠҷ‘qҢц•ыӮМ‘«—ҳҠоҺҒӮЖ‘О—§ӮөҒAҚNҲАҢі”NҒi1361”NҒjӮЙҺёӢrӮөӮҪҒBҚ‘җҙӮНӮ»ӮМӮЬӮЬ–v—ҺӮ·ӮйӮӘҒAҚ‘җҙӮМ’нӮМ”©ҺRӢ`җ[ӮӘӮМӮҝӮЙҺзҢмӮЙ”C–ҪӮіӮк”©ҺRүЖӮрҚДӢ»ӮіӮ№ӮйҒBӢ`җ[ӮМҺqҒE”©ҺRҠоҚ‘ӮН–ҫ“ҝ2”NҒi1391”NҒjӮМ–ҫ“ҝӮМ—җӮЕҢчҗСӮрӢ“Ӯ°ӮйӮИӮЗӮөӮД‘«—ҳӢ`–һӮМҗM”CӮрҺуӮҜҒA”\“oӮМҺзҢмӮр”CӮіӮкӮйӮИӮЗҺзҢм‘е–јӮЖӮөӮД—НӮрӮВӮҜӮйҒB
үһүi5”NҒi1398”NҒjӮЙӮНҠЗ—МӮЙ”CӮ¶ӮзӮкҒA“ҜӮ¶‘«—ҳҲк–еӮМҺz”g•җүqүЖӮвҚЧҗмӢһ’ӣүЖӮЖӮЖӮаӮЙҺOҠЗ—МүЖӮЖӮөӮД–јӮрҳAӮЛӮйүЖ•ҝӮЖӮИӮБӮҪҒBҠоҚ‘ӮМҺqҒE”©ҺR–һүЖӮНӢ`–һӮЙӮН—вӢцӮіӮкӮҪӮӘҒA‘«—ҳӢ`ҺқӮМ‘гӮЙӮИӮБӮДӮ©Ӯз•\•‘‘дӮЙ•ңӢAӮөӮДҠЗ—МӮЙҸA”CӮ·ӮйҒB–һүЖӮМҺqҒE”©ҺRҺқҚ‘Ғi“ҝ–{ҒjӮНҒAҸ«ҢRҢ —НӮМӢӯү»Ӯр–Ъҳ_ӮЮ‘«—ҳӢ`ӢіӮМҠұҸВӮЙӢкӮөӮЯӮзӮкӮйӮӘҒA”©ҺRүЖӮМ“а•ҙӮр’БӮЯӮДҚЧҗмүЖӮвҺR–јүЖӮЖқhҚRҒiӮ«ӮБӮұӮӨҒjӮ·ӮйҗЁ—НӮрҲЫҺқӮөӮҪҒB
ӮөӮ©ӮөҒAҺқҚ‘ӮМҺq”©ҺRӢ`ҸAӮЖүҷ”©ҺRҗӯ’·ӮЖӮМҠФӮЕүЖ“ВӮрӮЯӮ®ӮБӮДӮМҢғӮөӮў‘ҲӮўӮӘӢNӮ«ҒAӮ»ӮкӮӘҢгӮМүһҗmӮМ—җӮМҲкҲцӮЙӮИӮБӮҪҒB•¶–ҫ9”NҒi1477”NҒjӮЙүһҗmӮМ—җӮМҸI‘§ҢгӮаӢ`ҸA—¬Ғi‘ҚҸBүЖҒjӮЖҗӯ’·—¬Ғi”цҸBүЖҒjӮН“а•ҙӮр‘ұӮҜҒAӮұӮМ‘О—§ӮН—јҚЧҗмүЖӮМ—җӮЖӢӨӮЙӢE“аӮр“аҗнҸу‘ФӮЖӮ·ӮйҺеҲцӮЖӮИӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒA”©ҺRҗӯ’·Ғi”©ҺR”цҸBүЖҒjӮв”©ҺRӢ`кҹҒi”©ҺR‘ҚҸBүЖҒjӮНҠЗ—МӮЙҸA”CӮөӮҪӮӘҒAҗнҚ‘––ҠъӮЙ—јүЖӮЕӮ»ӮкӮјӮкҒA–Ш‘т’·җӯҒi”©ҺR‘ҚҸBүЖҒjӮв—VҚІ’·ӢіҒi”©ҺR”цҸBүЖҒjӮЙӮжӮйүәҚҺҸгӮӘӢNӮұӮБӮҪҒB
үz’ҶҚ‘ӮНҺзҢм‘гӮМҗ_•ЫҺҒӮЙ’DӮнӮкҒAүН“аҚ‘Ӯа“xҒXҺзҢм‘гӮМ—VҚІҺҒӮЙӢәӮ©ӮіӮкӮҪӮӘҒA”цҸBүЖӮМӢIҲЙӮҫӮҜӮНҚЕҢгӮЬӮЕҗЁ—НӮр•ЫӮБӮҪҒBҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮЁӮўӮДӮНҠш–{ӮвҚӮүЖӮЖӮөӮДҗ”үЖӮӘҺcӮБӮҪҒB
•Ҫҗ©”©ҺRүЖ
—р‘г“–Һе
”©ҺRҸd”\ - (•Ҫҗ©”©ҺRҺҒӮМ‘c)
”©ҺRҸd’ү
”©ҺRҸd•Ы
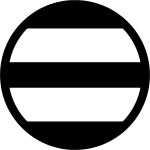
үЖ–дҒ@Ӯ ӮөӮ©ӮӘӮУӮҪӮВӮРӮ«
Ғ@Ғ@Ғ@‘«—ҳ“сӮВҲш
–{җ©
Ҡә•җ•ҪҺҒҚӮ–]үӨ—¬
җҙҳaҢ№ҺҒҒiүН“аҢ№ҺҒҒj
үЖ‘c
”©ҺRҸd”\
”©ҺRӢ`Ҹғ
Һн•К
•җүЖ
Һm‘°
Ҹoҗg’n
•җ‘ Қ‘’jеОҢS”©ҺRӢҪ
ҺеӮИҚӘӢ’’n
үН“аҚ‘ҒAӢIҲЙҚ‘
‘еҳaҚ‘ҒAүz’ҶҚ‘
”\“oҚ‘ҒA—ӨүңҚ‘
’ҳ–јӮИҗl•Ё
”©ҺRҸd’үҒA”©ҺRҚ‘җҙ
”©ҺR–һүЖҒA”©ҺRҗӯ’·
”©ҺRӢ`ҸAҒA”©ҺRӢ`‘ұ
”©ҺRӢ`ҢpҒA”©ҺRҲкҗҙ
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
ҠвҸјҺҒҒi•җүЖ ҒЁ үШ‘°Ғi’jҺЭҒjҒj
“с–{ҸјҺҒҒi•җүЖҒj
“c’ҶҺҒҒi•җүЖҒj
үН“аҸaҗмҺҒҒi•җүЖҒj
ҲАҲдҺҒҒi•җүЖҒj ӮИӮЗ
Һә’¬Һһ‘гӮЙӮН”©ҺRӢаҢбүЖӮӘ‘еҳaүF’qҢSҒEүН“аҒEӢIҲЙҒiҠЗ—МҸA”CҺһӮЙӮНҺRҸйӮаҒjӮИӮЗӮМӢE“аӮЁӮжӮСӮ»ӮМҺь•УҚ‘ӮЙҠY“–Ӯ·ӮйҸd—vӮИ’nҲжӮрҺзҢмӮЖӮөӮДҺЎӮЯҒAӮЬӮҪ–Ӣ•{ӮМҠЗ—МӮЖӮөӮДҚ‘ӮМҗӯ–ұӮрҺ·ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAүЖ“В‘ҲӮўӮЙӮжӮиҒA‘ҚҸBүЖӮЖ”цҸBүЖӮЙ•ӘӮ©ӮкӮДҒAүһҗmӮМ—җ–u”ӯӮМҲкҲцӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢгӮаҢғӮөӮӯ‘ҲӮў‘ұӮҜӮҪҒB
ӮЬӮҪҒA–k—ӨӮМүz’ҶӮМҺзҢмӮаҢ“ӮЛҒA•ӘүЖӮН”\“oӮМҺзҢмӮр‘гҒXҗўҸPӮ·ӮйҒB’ҳ–јӮИ––ебӮЖӮөӮДҺАӢЖүЖӮМ”©ҺRҲкҗҙӮӘӮўӮйҒB
ҠT—v
•ҪҲАҺһ‘гҒEҠҷ‘qҺһ‘г
Қв“Ң”Ә•ҪҺҒӮМҲк‘°ҒE’Ғ•ғҸdҚOӮМҺqӮЕӮ Ӯй’Ғ•ғҸd”\ӮӘ•җ‘ Қ‘’jеОҢS”©ҺRӢҪҒiӮНӮҪӮҜӮвӮЬӮІӮӨҒAҢ»ҚЭӮМҚйӢКҢ§җ[’JҺs”©ҺRҺь•УҒjӮЙҸҠ—МӮр“ҫӮД”©ҺRҗ©ӮрҸМӮөӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮйҒi•Ҫҗ©”©ҺRүЖҒjҒBҺЎҸіҒEҺхүiӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДҒAӮ»ӮМҺq”©ҺRҸd’үӮНҒAӮНӮ¶ӮЯӮН•ҪүЖ•ыӮЙӮВӮўӮҪӮӘҢгӮЙҢ№—Ҡ’©ӮЙҸ]ӮўҒAҲкғm’JӮМҗнӮўӮвүңҸBҚҮҗнӮИӮЗӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBҸd’үӮНӮМӮҝӮЙ–kҸрҺһҗӯӮЖ‘О—§ӮөҒAҢіӢv2”NҒi1205”NҒjӮЙ•җ‘ Қ‘“с–“җмӮЕ–kҸрӢ`ҺһӮМҢRӮЖӮМҗ퓬ӮЕ”sҺҖӮөӮҪҒi”©ҺRҸd’үӮМ—җҒjҒB
Ӯ»ӮМҢгҒAҸd’үӮМӢҢ—МӮЖ”©ҺRӮМ–јҗХӮНҒA‘«—ҳӢ`Ң“ӮМҸҺ’·ҺqҒE‘«—ҳӢ`ҸғӮӘҸd’үӮМ–ў–SҗlӮЕӮ Ӯй–kҸрҺһҗӯҸ—[’ҚҺЯ 1]ӮЖҚҘҲчӮөҒAҢpҸіӮіӮкӮҪҒBӢ`ҸғӮНӮаӮЖӮаӮЖҗV“cӢ`Ң“Ғi‘«—ҳӢ`Ң“ӮЖ“ҜжҒӮМҸ]ҢZ’нҒjӮМ–әӮЖҚҘҲчӮөҺqӮа–ЧҒiӮаӮӨҒjӮҜӮДӮўӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҚИҺqӮрӢ`җвӮөӮҪҸгӮЕӮМҢpҸіӮЕӮ ӮБӮҪ[’ҚҺЯ 2]ҒBӮұӮкӮЙӮжӮБӮДҠә•җ•ҪҺҒӮМӮРӮЖӮВ’Ғ•ғ•ҪҺҒӮМ—¬ӮкӮрӮӯӮЮ•Ҫҗ©”©ҺRҺҒӮНҸБ–ЕӮөҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӮРӮЖӮВүН“аҢ№ҺҒӮМҲкҢnҒE‘«—ҳүЖӮМҲк–еӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB
Ӣ`ҸғӮМүЖҢnҒiҢ№җ©”©ҺRүЖҒjӮН–ј–еҒE”©ҺRүЖӮМ–јҗХӮрҢpҸіӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҢгӮЙ‘«—ҳҲк–еӮМ’ҶӮЕ•КүЖҲөӮўӮМ‘«—ҳ”ц’ЈүЖҒi•җүqүЖҒAӮўӮнӮдӮйҺz”gүЖҒjӮЙҺҹӮўӮЕҚӮӮўҸҳ—сӮЙ—сӮ№ӮзӮкҒAҚЧҗмүЖӮИӮЗ‘јӮМүЖҗbӢШ•ӘүЖӮЖӮНҲЩӮИӮй‘ТӢцӮр‘«—ҳҸ@үЖӮ©ӮзҺуӮҜӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB
ӢIҲЙӮЁӮжӮСүН“аҒEүz’ҶӮМҺзҢмӮрӮЁӮЁӮЮӮЛ–ұӮЯҒA•ӘүЖӮН”\“oҺзҢмӮр–ұӮЯӮҪҒB
Һә’¬Һһ‘гҲИҚ~
•ТҸW
Ңҡ•җ3”NҒi1336”NҒjӮЙ‘«—ҳ‘ёҺҒӮӘҺә’¬–Ӣ•{Ӯр‘n—§Ӯ·ӮйӮЖҒA”©ҺRүЖӮНӮұӮкӮЬӮЕӮМҢчҗСӮЙӮжӮБӮДүz’ҶҒEүН“аҒEӢIҲЙӮМҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪҒB‘«—ҳүЖӮМ“а•ҙӮЕӮ ӮйҠПүһӮМҸп—җӮЕӮНҒAҸҺ—¬ӮМ”©ҺRҚ‘җҙӮН‘«—ҳ’јӢ`•ыӮЙ•tӮӯӮаҢгӮЙ‘ёҺҒ•ыӮЙҲЖ‘ЦӮҰӮөӮДүЖҗЁӮр•ЫӮҝҒAӮ»ӮМҲк•ыӮЕ”©ҺRүЖ’„—¬ӮМ”©ҺRҚӮҚ‘ҒEҚ‘ҺҒ•ғҺqӮНҒAҠПүһ2”NҒi1351”NҒj’јӢ`”hӮМӢg—З’еүЖӮЙ”sӮкҺ©ҠQӮөҒAҚ‘ҺҒӮМҺq“с–{ҸјҚ‘‘FӮН“с–{ҸјӮЙҲЪӮБӮҪҒiүңҸB”©ҺRүЖҒjҒB
–{—ҲӮМ’„—¬ӮЕӮ ӮйүңҸB”©ҺRүЖӮӘҗҠ‘ЮӮ·Ӯй’ҶӮЕҒA”©ҺRҚ‘җҙӮМүЖҢnҒiӢаҢбүЖҒjӮӘ”©ҺRүЖӮМ‘y—МҠiӮЖӮИӮйҒBҚ‘җҙӮНҠЦ“ҢҠЗ—МӮЙ”C–ҪӮіӮкӮД“ҢҚ‘ӮЕ“м’©•ыӮЖҗнӮӨӮӘҒAӮ»ӮМҢгҠҷ‘qҢц•ыӮМ‘«—ҳҠоҺҒӮЖ‘О—§ӮөҒAҚNҲАҢі”NҒi1361”NҒjӮЙҺёӢrӮөӮҪҒBҚ‘җҙӮНӮ»ӮМӮЬӮЬ–v—ҺӮ·ӮйӮӘҒAҚ‘җҙӮМ’нӮМ”©ҺRӢ`җ[ӮӘӮМӮҝӮЙҺзҢмӮЙ”C–ҪӮіӮк”©ҺRүЖӮрҚДӢ»ӮіӮ№ӮйҒBӢ`җ[ӮМҺqҒE”©ҺRҠоҚ‘ӮН–ҫ“ҝ2”NҒi1391”NҒjӮМ–ҫ“ҝӮМ—җӮЕҢчҗСӮрӢ“Ӯ°ӮйӮИӮЗӮөӮД‘«—ҳӢ`–һӮМҗM”CӮрҺуӮҜҒA”\“oӮМҺзҢмӮр”CӮіӮкӮйӮИӮЗҺзҢм‘е–јӮЖӮөӮД—НӮрӮВӮҜӮйҒB
үһүi5”NҒi1398”NҒjӮЙӮНҠЗ—МӮЙ”CӮ¶ӮзӮкҒA“ҜӮ¶‘«—ҳҲк–еӮМҺz”g•җүqүЖӮвҚЧҗмӢһ’ӣүЖӮЖӮЖӮаӮЙҺOҠЗ—МүЖӮЖӮөӮД–јӮрҳAӮЛӮйүЖ•ҝӮЖӮИӮБӮҪҒBҠоҚ‘ӮМҺqҒE”©ҺR–һүЖӮНӢ`–һӮЙӮН—вӢцӮіӮкӮҪӮӘҒA‘«—ҳӢ`ҺқӮМ‘гӮЙӮИӮБӮДӮ©Ӯз•\•‘‘дӮЙ•ңӢAӮөӮДҠЗ—МӮЙҸA”CӮ·ӮйҒB–һүЖӮМҺqҒE”©ҺRҺқҚ‘Ғi“ҝ–{ҒjӮНҒAҸ«ҢRҢ —НӮМӢӯү»Ӯр–Ъҳ_ӮЮ‘«—ҳӢ`ӢіӮМҠұҸВӮЙӢкӮөӮЯӮзӮкӮйӮӘҒA”©ҺRүЖӮМ“а•ҙӮр’БӮЯӮДҚЧҗмүЖӮвҺR–јүЖӮЖқhҚRҒiӮ«ӮБӮұӮӨҒjӮ·ӮйҗЁ—НӮрҲЫҺқӮөӮҪҒB
ӮөӮ©ӮөҒAҺқҚ‘ӮМҺq”©ҺRӢ`ҸAӮЖүҷ”©ҺRҗӯ’·ӮЖӮМҠФӮЕүЖ“ВӮрӮЯӮ®ӮБӮДӮМҢғӮөӮў‘ҲӮўӮӘӢNӮ«ҒAӮ»ӮкӮӘҢгӮМүһҗmӮМ—җӮМҲкҲцӮЙӮИӮБӮҪҒB•¶–ҫ9”NҒi1477”NҒjӮЙүһҗmӮМ—җӮМҸI‘§ҢгӮаӢ`ҸA—¬Ғi‘ҚҸBүЖҒjӮЖҗӯ’·—¬Ғi”цҸBүЖҒjӮН“а•ҙӮр‘ұӮҜҒAӮұӮМ‘О—§ӮН—јҚЧҗмүЖӮМ—җӮЖӢӨӮЙӢE“аӮр“аҗнҸу‘ФӮЖӮ·ӮйҺеҲцӮЖӮИӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒA”©ҺRҗӯ’·Ғi”©ҺR”цҸBүЖҒjӮв”©ҺRӢ`кҹҒi”©ҺR‘ҚҸBүЖҒjӮНҠЗ—МӮЙҸA”CӮөӮҪӮӘҒAҗнҚ‘––ҠъӮЙ—јүЖӮЕӮ»ӮкӮјӮкҒA–Ш‘т’·җӯҒi”©ҺR‘ҚҸBүЖҒjӮв—VҚІ’·ӢіҒi”©ҺR”цҸBүЖҒjӮЙӮжӮйүәҚҺҸгӮӘӢNӮұӮБӮҪҒB
үz’ҶҚ‘ӮНҺзҢм‘гӮМҗ_•ЫҺҒӮЙ’DӮнӮкҒAүН“аҚ‘Ӯа“xҒXҺзҢм‘гӮМ—VҚІҺҒӮЙӢәӮ©ӮіӮкӮҪӮӘҒA”цҸBүЖӮМӢIҲЙӮҫӮҜӮНҚЕҢгӮЬӮЕҗЁ—НӮр•ЫӮБӮҪҒBҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮЁӮўӮДӮНҠш–{ӮвҚӮүЖӮЖӮөӮДҗ”үЖӮӘҺcӮБӮҪҒB
•Ҫҗ©”©ҺRүЖ
—р‘г“–Һе
”©ҺRҸd”\ - (•Ҫҗ©”©ҺRҺҒӮМ‘c)
”©ҺRҸd’ү
”©ҺRҸd•Ы
‘hүдҺҒ
‘hүдҺҒҒiӮ»ӮӘӮӨӮ¶ҒAӮ»ӮӘӮөҒj
Ғu‘hүдҒvӮрҺҒӮМ–јӮЖӮ·ӮйҺҒ‘°ҒB
җ©ӮНҗbҒiӮЁӮЭҒjҒB

ҺҒҗ_ӮЖҗ„‘ӘӮіӮкӮйҸ@үдҚҝҸ@үд“s”дҢГҗ_ҺР
Ғi“Ю—ЗҢ§ҠҖҢҙҺsҒj
ҺҒҗ©
‘hүдҗb
ҺҒ‘c
•җ“аҸh”H
ҒiҚFҢі“VҚcӮМҢгебҒj
Һн•К
Қc•К
–{ҠС
‘еҳaҚ‘ҚӮҺsҢS‘hүд—W
’ҳ–јӮИҗl•Ё
‘hүдҲо–Ъ
‘hүд”nҺq
‘hүдүЪҲО
‘hүд“ьҺӯ
‘hүдҗФҢZ
Ңгеб
җОҗм’©җb
Ғu‘hүдҒvӮМ•\ӢL
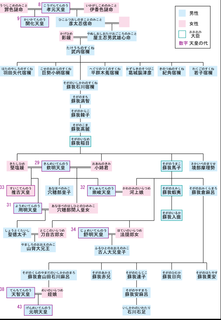
‘hүд - Ғw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒx
Ҹ@үк - ҒwҢГҺ–ӢLҒx
Ҹ@үд - Ғwҗж‘гӢҢҺ––{ӢIҒx“V‘·–{ӢIҒAҒwҸгӢ{җ№“ҝ–@үӨ’йҗаҒxҒAҒw“ъ–{ҺO‘гҺАҳ^Ғx
ҚJҠп - ҒwҢіӢ»ҺӣүҸӢN’ Ғx
ҸoҺ©
ҒwҢГҺ–ӢLҒxӮвҒw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒxӮЕӮНҒAҗ_ҢчҚcҚ@ӮМҺOҠШҗӘ”°ӮИӮЗӮЕҠҲ–фӮөӮҪ•җ“аҸh”HӮр‘cӮЖӮөӮДӮўӮйҒBӢп‘М“IӮИҠҲ“®ӮӘӢLҸqӮіӮкӮйӮМӮН6җўӢI’ҶҚ ӮМ‘hүдҲо–ЪӮ©ӮзӮЕҒAӮ»ӮкҲИ‘OӮЙҠЦӮөӮДӮНӮжӮӯ•ӘӮ©ӮБӮДӮўӮИӮўӮӘҒAүН“аӮМҗОҗмҒiҢ»ҚЭӮМ‘еҚг•{ӮМҗОҗм—¬ҲжҒAҸЪҚЧӮЙ“мүН“аҢSүН“м’¬Ҳкҗ{үкӮ ӮҪӮиӮЖ“Б’иӮіӮкӮйҗаӮаӮ ӮйҒjӮЁӮжӮСҠӢҸйҢ§‘hүд—ўҒiҢ»ҚЭӮМ“Ю—ЗҢ§ҠҖҢҙҺs‘]үд’¬Ӯ ӮҪӮиҒjӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮДӮўӮҪ“y’…ҚӢ‘°ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB ҒwҗVҗпҗ©ҺҒҳ^ҒxӮЕӮН‘hүдҺҒӮрҚc•КҒi—р‘г“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҺҒ‘°ҒjӮЙ•Ә—ЮӮөӮДӮўӮйҒB
—рҺj
үӨҢ ӮМҗEӢЖ“z‘®–ҜӮЖӮөӮДӮМ–рҠ„Ӯр’SӮБӮДӮўӮҪ“n—ҲҢnӮМҺҒ‘°ӮЖҗ[ӮўҠЦҢWӮЙӮ ӮБӮҪӮЖҢ©ӮзӮкҒA“n—ҲҗlӮМ•i•”ӮМҸW’cӮИӮЗӮӘҺқӮВ“–ҺһӮМҗжҗiӢZҸpӮӘ‘hүдҺҒӮМ‘д“ӘӮМҲкҸ•ӮЙӮИӮБӮҪӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒA•§ӢіӮӘ“`—ҲӮөӮҪҚЫӮЙӮ»ӮкӮрӮўӮҝ‘ҒӮӯҺжӮи“ьӮкӮҪӮМӮа‘hүдҺҒӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӮұӮкӮНҒA’©’мӮМҚХвJӮр”CӮіӮкӮДӮўӮҪҳAҗ©ӮМ•Ё•”ҺҒҒA’ҶҗbҺҒӮрҢЎҗ§Ӯ·ӮйҲЧӮМ–Ъ“IӮаӮ ӮБӮҪӮЖҗ„Һ@ӮіӮкӮйҒB
6җўӢIҢг”јӮЙӮНҚЎӮМ“Ю—ЗҢ§ҚӮҺsҢSӢЯ•УӮрҗЁ—НүәӮЙӮЁӮўӮДӮўӮҪӮЖҺvӮнӮкӮДӮўӮйҒB‘hүдҺҒӮӘҗӯҺЎӮМҺАҢ ӮрҸ¶Ҳ¬ӮөӮҪҺһ‘гҲИҢгҒAӮ»ӮМ’nҲжӮЙҸW’Ҷ“IӮЙ“VҚcӮМӢ{ӮӘӮЁӮ©ӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮұӮЖӮ©ӮзӮаӮӨӮ©ӮӘӮнӮкӮйҒB
‘Sҗ·Ҡъ
Ҳо–ЪӮМ‘гӮЙӮИӮйӮЖҒAүЯӢҺӮЙ‘еҗbӮрҸoӮөӮДӮўӮҪҠӢҸйҺҒӮв•ҪҢQҺҒӮНҠщӮЙ–{Ҹ@үЖӮМ–Е–SӮЙӮжӮиҗЁӮўӮрӮИӮӯӮөӮДӮЁӮиҒA‘hүдҺҒӮН‘еҳAӮМ‘е”әҺҒӮЖ•Ё•”ҺҒӮЙӮИӮзӮФҺO‘еҗЁ—НӮМҲкҠpӮЖӮИӮиҒAӮвӮӘӮД‘е”әӢа‘әӮӘҺёӢrӮ·ӮйӮЖҒA‘еҳAӮМ•Ё•”Ғi”ц—`ҒjӮЖ‘еҗbӮМ‘hүдҒiҲо–ЪҒjӮМ“с‘еҗЁ—НӮЖӮИӮйҒBӮЬӮҪҒAүЯӢҺӮМҠӢҸйҺҒӮвҢгӮМ“ЎҢҙҺҒ“Ҝ—lҒA–ә‘hүдҢҳү–•QҒAҸ¬ҺoҢNӮрӢФ–ҫ“VҚcӮЙүЕӮӘӮ№ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮи“VҚcүЖӮМҠOҗКӮЖӮИӮБӮДӮўӮӯҒi”nҺqӮМ–{ӢҸҒiғEғuғXғiҒjӮӘҠӢҸйҢ§ӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҲо–ЪӮМҚИӮНҠӢҸйҺҒӮМҸoӮЕҒAӮ»ӮМҢҢ“қӮЙҳAӮИӮйӮұӮЖӮЙӮжӮиҒA“VҚcӮЦ”ЬӮр”yҸoҸo—ҲӮйҲк‘°ӮЙҳAӮИӮБӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒjҒB
Ҳо–ЪӮНӢФ–ҫ“VҚcӮЖӮЩӮЪ“ҜҺһҠъӮЙ–vӮөҒA“с‘еҗЁ—НӮМҚ\җ}ӮНҺҹ‘гӮМ‘hүд”nҺqӮЬӮЕҲшӮ«ҢpӮӘӮкӮйӮӘҒA—p–ҫ“VҚc•цҢдҢгӮЙҢгҢpҺТӮрӮЯӮ®Ӯй‘ҲӮўӮӘӮ ӮБӮҪҒB‘hүдҺҒӮНҒAҸ¬ҺoҢNӮМҺqӮИӮӘӮзӮа•Ё•”ҺҒӮЙ—i—§ӮіӮкӮДӮўӮҪҢҠ•д•”ҚcҺqӮрҲГҺEӮөҒAҗнӮўӮЕ•Ё•”Һзү®Ӯр“ўӮҝ–ЕӮЪӮ·ӮЖҒAӮ»ӮМҢгӮН‘hүдҺҒҲИҠOӮ©ӮзӮН‘еҳAӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйҺТӮаҸoӮёҒAҗӯҢ ӮН‘hүдҺҒӮМҲкӢЙ‘Мҗ§ӮЖӮИӮйҒB
ӮұӮұӮ©Ӯзҗ’Ҹs“VҚcӮМҲГҺEӮвҒAҗ„ҢГ“VҚcӮЦӮМҠӢҸйҢ§ӮМҠ„ҸчӮМ—vӢҒҒAүЪҲОӮЙӮжӮй“VҚcӮрӮИӮўӮӘӮөӮлӮЙӮ·ӮйӮУӮйӮЬӮўҒA“ьҺӯӮЙӮжӮйҸгӢ{үӨүЖҒiҺR”w‘еҢZүӨҒjӮМ“ў–ЕҒAҸf•ғӮЕҗкҗ§җӯҺЎӮЙ”Ҫ‘ОӮ·ӮйӢ«•”–Җ—қҗЁӮМҺёӢrӮИӮЗӮМҗкүЎӮФӮиӮӘ“`ӮҰӮзӮкӮДӮЁӮиҒA‘hүдҺҒҺO‘гӮЙӮнӮҪӮБӮДҢ —НӮр—~ӮөӮўӮӘӮЬӮЬӮЙӮөӮҪӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB
ӮөӮ©Ӯө”nҺqӮМҺҖҢгӮЙҒA‘hүдҺҒӮЙ‘ОӮ·ӮйҚc‘°ӮвҸ”ҚӢ‘°ӮМ”ҪҠҙӮӘҚӮӮЬӮБӮД‘hүдҺҒӮМҗӯҺЎҠо”ХӮӘ“®—hӮөҒAӮ»ӮкӮрҚҺ•һӮөӮжӮӨӮЖӮөӮД“ьҺӯӮЙӮжӮйӢӯҢ җӯҺЎӮЙҢqӮӘӮБӮҪҒAӮЖӮўӮӨҢ©•ыӮаҸӯӮИӮ©ӮзӮёӮ ӮйҒBӮұӮкӮНҒw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒx“ҷӮЙӮжӮй‘hүдҺҒӮЙ”Ы’и“IӮИӢLҸqӮЙ‘ОӮ·Ӯй”Ҫҳ_ӮЕӮ ӮйҒB
‘еү»ӮМүьҗVӮ©Ӯзҗpҗ\ӮМ—җӮЬӮЕ •ТҸW
‘hүдҺҒӮН‘еү»ӮМүьҗVҒiүі–ӨӮМ•ПҒjӮЙӮД–ЕӮСӮҪҒAӮЖ”FҺҜӮіӮкӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўҒB
645”NӮЙ’Ҷ‘еҢZҚcҺqҒA’ҶҗbҠҷ‘«ӮзӮЙӮжӮБӮДҒA“ьҺӯӮӘҲГҺEӮіӮкӮйӮЖӮЖӮаӮЙүЪҲОӮӘҺ©ҺEӮ·ӮйҒiүі–ӨӮМ•ПҒjӮЖ‘hүдҺҒӮМҗЁ—НӮН‘е•қӮЙ’бүәӮ·ӮйӮӘҒAӮұӮкӮНӮ ӮӯӮЬӮЕӮаүЪҲОӮр’„—¬ӮЖӮ·Ӯй‘hүдҺҒҸ@–{үЖӮМ–v—ҺҒE–Е–SӮҫӮҜӮЙӮЖӮЗӮЬӮйҒBүі–ӨӮМ•ПӮЙӮНҒA–T—¬ӮЕӮ Ӯй‘hүд‘q–ғҳCҒiүЪҲОӮМ’нҒjӮМҺqӮЕӮ Ӯй‘hүд‘qҺR“cҗОҗм–ғҳCӮНҒA’Ҷ‘еҢZҚcҺqӮМӢҰ—НҺТӮЖӮөӮДҠЦӮнӮБӮДӮўӮҪҒBҗОҗм–ғҳCӮНӮұӮМҢгӮЙүE‘еҗbӮЙ”CӮ¶ӮзӮкҒA–әӮМү“’q–әӮЖ–Г–әӮр’Ҷ‘еҢZҚcҺqӮМҚ@ӮЙӮөӮДӮўӮйҒBҗОҗм–ғҳCҺ©җgӮН649”NӮЙҷlҚЯӮЕҺ©ҠQӮөҒAж§ҢҫӮөӮҪ’нӮМ‘hүд“ъҢьӮа‘еҚЙ•{ӮЙҚ¶‘JӮіӮ№ӮзӮкӮҪҒiҢы••Ӯ¶ӮЖӮМҗаӮаӮ ӮйҒjҒBӮөӮ©ӮөҒA‘јӮМ’нӮЕӮ Ӯй‘hүдҗФҢZӮЖ‘hүдҳAҺqӮНҒA“V’q“VҚcӮМҺһ‘гӮЙ‘еҗbҒiҗФҢZӮНҚ¶‘еҗbҒAҳAҺqӮНӮНӮБӮ«ӮиӮН•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮӘүE‘еҗbӮЖҗ„’иӮіӮкӮДӮўӮйҒjӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮДӮЁӮиҒA‘hүдҺҒӮНҲк’иӮМҚӮӮў’nҲКӮр•ЫҺқӮө‘ұӮҜӮДӮўӮйҒB
ҳAҺqӮН“V’q“VҚcӮМҗіҺ®ӮИ‘ҰҲКӮрҢ©ӮИӮўӮЬӮЬҺҖӢҺӮөҒAҗФҢZӮЖӮаӮӨҲкҗlӮМ’нӮЕӮ ӮйҢдҺj‘е•vӮМ‘hүдүКҲАӮНҗpҗ\ӮМ—җӮЕ‘е—FҚcҺq‘ӨӮЙӮВӮўӮД”sӮкҒAӮ»ӮкӮјӮк—¬ҚЯҒEҺ©ҠQӮЖӮИӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМүҷӮЕҳAҺqӮМҺqӮЕӮ Ӯй‘hүдҲА–ғҳCӮНҒA“V•җ“VҚcӮМҗM”CӮӘҢъӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯӮЙ‘hүдҺҒӮМҢгӮрҢpӮ¬ҒAҗОҗм’©җbӮМҗ©ҺҒӮрҺ’ӮБӮҪҒB
ӮұӮМӮжӮӨӮЙүі–ӨӮМ•ПҢгӮаҒA‘q–ғҳCӮМ‘§Һq’BӮӘӮИӮЁҗӯҺЎӮМ’ҶҗS“I—§ҸкӮЙӮЖӮЗӮЬӮиҒA‘ҠҺҹӮ®җӯ‘ҲӮЕҗҠ‘ЮӮөӮИӮӘӮзӮаӮөӮОӮзӮӯӮН‘hүдҺҒҒiҳAҺqӮМҢn“қҒjӮН‘ұӮўӮҪҒB
‘hүдҢnҗОҗм’©җb •ТҸW
‘hүдҢnҗОҗмҺҒӮНҒA”т’№Һһ‘г––ҠъӮ©Ӯз“Ю—ЗҺһ‘гӮЙҒAӮ»ӮМҢҢӮрҲшӮўӮҪ“VҚcҒiҺқ“қ“VҚcӮЖҢі–ҫ“VҚcҒjӮр”yҸoӮөӮҪҒiӮ»ӮкӮјӮкҗОҗм–ғҳCӮМ–әҒAү“’q–әӮЖ–Г–әӮӘ•кҒjҒB
ӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҒA‘hүдҗФҢZӮМҠO‘·ӮЕӮ ӮйҺR•УҚcҸ—ӮӘҒAҺқ“қ“VҚcӮЙ”rҸңӮіӮкӮҪ•vӮМ‘е’ГҚcҺqӮЙҸ}ҺҖӮөӮҪӮиҒAӮЬӮҪ•¶•җ“VҚcӮМӣlӮМҗОҗм“ҒҺq–әӮӘҒA“VҚc•цҢдҢгӮЙ–^’jӮЖӮМҠЦҢWӮрҺқӮБӮҪҺ–Ӯ©ӮзӮ»ӮМҗg•ӘӮр”Қ’DӮіӮкӮйҺ–ҢҸӮИӮЗӮаӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒBҠp“c•¶үqӮМҗаӮЙӮжӮйӮЖҒA“ҒҺq–әӮЙӮНҚLҗ¬ҒEҚLҗўӮМ2’jӮӘӮ ӮиҒA•кӮЙҳAҚАӮөӮД—јҚcҺqӮМҚc‘°ӮМҗg•ӘӮр’DӮўҒAҲЩ•кҢZ’нӮМҺсҚcҺqӮМӢЈ‘Ҳ‘ҠҺиӮр”rҸңӮөӮжӮӨӮЖӮөӮДӮМ“ЎҢҙ•s”д“ҷҒEӢkҺOҗз‘г•v•wӮМүA–dӮЖӮіӮкӮйҒB
ӮЬӮҪ–ң—tҸWӮЙӮжӮкӮОҒA“ҜӮ¶җФҢZӮМҠO‘·ӮЕӮ Ӯй•дҗПҚcҺqӮа’A”nҚcҸ—ӮЖӮМ–§’КӮӘҳIҢ©ӮөӮДҚ¶‘JӮіӮкӮҪҒB•дҗПҚcҺqӮНҒAҚKӮўӮЙӮаҺқ“қ“VҚc•цҢдҢгӮЙ’m‘ҫҗӯҠҜҺ–ӮЙҸoҗўӮөӮҪӮӘҒAҺбӮӯӮөӮД–SӮӯӮИӮБӮҪҒB
•s”д“ҷӮМҗіҚИӮНҒAҲА–ғҳCӮМ–әӮМ‘hүдҸ©ҺqҒi“ЎҢҙ•җ’q–ғҳCҒE“ЎҢҙ–[‘OҒE“ЎҢҙүFҚҮӮМ•кҒjӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМҢМӮрҲИӮДҒAӮ»ӮМ’нӮМҗОҗмҗО‘«ӮЖҺqӮМҗОҗм”N‘«ӮН’„—¬ӮМ•җ’q–ғҳCӮр‘cӮЖӮ·Ӯй“ЎҢҙ“мүЖӮЖҢӢӮСӮВӮӯӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB”N‘«ӮНҒA•җ’q–ғҳCҺҹ’jӮМ“ЎҢҙ’Ү–ғҳCӮӘҗЭ—§ӮөӮҪҺҮ”ч’Ҷ‘дӮМ‘е•JӮЖӮөӮДӮ»ӮМ•вҚІӮЙ“–ӮҪӮиҒA’Ҷ—¬ӢM‘°ӮЖӮөӮДӮИӮсӮЖӮ©Ӯ»ӮМ–Ҫ–¬Ӯр•ЫӮБӮҪҒB
җҠ‘Ю •ТҸW
ӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮМ“ЎҢҙ“мүЖӮӘ“ЎҢҙ’Ү–ғҳCӮМ—җӮЕҗҠ‘ЮӮөӮДӮөӮЬӮӨӮЖҒAҗОҗмҺҒӮа•ҪҲАӢһ‘J“sҢгӮЙ–SӮӯӮИӮБӮҪҗОҗмҗ^ҺзҒiҗіҺlҲКҸгҒEҺQӢcҒjӮрҚЕҢгӮЙҢцӢЁӮНҸoӮИӮӯӮИӮйҒBӮ»ӮМҢгҒAҢіҢcҢі”NҒi877”NҒjӮЙӮИӮБӮДҗОҗм–Ш‘әӮӘҗж‘cӮМ–јҒi‘hүдҗОҗмҒjӮрӮаӮБӮДҺq‘·ӮМҺҒӮМ–јҸМӮЖӮ·ӮйӮМӮЕӮНҒAжҒӮр”рӮҜӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮёҒAҺҖҢгӮЙҗ¶‘OӮМҺА–јӮрҠхӮсӮЕҢыӮЙӮөӮИӮў•—ҸKӮЙ”ҪӮ·ӮйӮЖӮөӮДҒAҸ@Ҡx’©җbҗ©ӮЙүьҗ©Ӯ·Ӯй[1]ҒBӮМӮҝҒAҺҒӮМ•\ӢLӮНҸ@ҠxӮ©ӮзҸ@үӘӮЙҒA“ЗӮЭӮаҒuӮ»ӮӘҒvӮ©ӮзҢP“ЗӮЭӮМҒuӮЮӮЛӮЁӮ©ҒvӮЙ•ПӮнӮБӮҪ[2]ҒB
Қ]ҢЛҺһ‘гӮМ’nүәүЖӮЕӮ ӮйҗВ–ШүЖҒiҺjҗ¶ӮИӮЗҒjҒEҺO‘оүЖҒiҸўҺg•ӣҺgҒjӮИӮЗӮӘҒAҸ@үӘҗ©ӮрҸМӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA‘hүдҺҒӮМҢҢ“қӮНҒA“ЎҢҙ•s”д“ҷӮЙүЕӮўӮЕ•җ’q–ғҳCҒE–[‘OҒEүFҚҮӮМҺO’jӮр–ЧӮҜӮҪ‘hүдҸ©ҺqӮр’КӮөӮДҢ»‘гӮЙӮа“`ӮнӮБӮДӮўӮйҒBӮИӮЁ‘јӮЙ‘hүдҺҒӮМҢҢӮрҺcӮөӮҪӮМӮНҒA‘hүдҲо–ЪӮМ–әӮЕӮ Ӯй‘hүдҢҳү–•QӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮМҢn“қӮН‘hүдҢҳү–•Q Ғ\ ҚчҲдҚcҺq Ғ\ Ӣg”х•PүӨ Ғ\ ҚcӢЙ“VҚc Ғ\ “V’q“VҚc Ғ\ ҒiҲИҢг—р‘г“VҚcҒjӮЖӮИӮйҒB
‘hүдҺҒ“n—Ҳҗlҗа
•ТҸW
–еҳe’х“сӮӘ1971”NӮЙ‘hүдҺҒ“n—ҲҗlҗаӮр’сҸҘӮөӮҪ[3][4]ҒB–еҳeӮӘ’сҸҘӮөӮҪӮМӮНүһҗ_“VҚcӮМ‘гӮЙ“n—ҲӮөӮҪҒA•SҚПӮМҚӮҠҜҒA–Ш–һ’vҒiӮаӮӯӮЬӮҝҒjӮЖ‘hүд–һ’qҒiӮЬӮҝҒjӮӘ“ҜҲкҗl•ЁӮЖӮ·ӮйҗаӮЕҒA—й–Ш–х–ҜӮвҺR”цҚKӢvӮзӮМҺxҺқ[5][6]Ӯр“ҫӮҪҲк•ыҒAүБ“ЎҢӘӢgӮвҚв–{Ӣ`ҺнӮзӮӘ”б”»[7][8]ӮөӮҪӮжӮӨӮЙҒAҺj—ҝҸгӮМ–в‘и“_ӮӘ‘ҪӮўҒBҚӘӢ’ӮӘ•sҸ\•ӘӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҺw“EӮӘӮ Ӯй[9]ҒB
–в‘и“_ӮНҗ®—қӮ·ӮйӮЖҲИүәӮМ’КӮиӮЕӮ ӮиҒA–Ш–һ’vӮЖ‘hүд–һ’qӮр“ҜҲкҗl•ЁӮЕӮ ӮйӮЖҺАҸШӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮН–в‘и“_ӮӘӮ Ӯй[10][11]ҒB
Ғu–Ш–һ’vҒvӮМ–јӮӘҢ©ӮҰӮйҒw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒxӮМүһҗ_“VҚc25”NҒiҗј—п294”NҒAҺj—ҝүрҺЯҸгӮН414”NҒjӮЖҒu–Шъ„–һ’vҒvӮМ–јӮӘҢ©ӮҰӮйҒwҺOҚ‘ҺjӢLҒx•SҚП–{ӢIӮМҠWкbүӨ21”NҒiҗј—п475”NҒjӮЖӮЕӮНҺһ‘гӮӘҲЩӮИӮй
•SҚПӮМ–ј–еҺҒ‘°ӮЕӮ Ӯй–Ш–һ’vӮӘҒAҺ©ӮзӮМҗ©ӮрҺМӮД‘hүдҺҒӮр–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮМ•sҺ©‘RӮі
“n—ҲҢnҚӢ‘°ӮӘҺ©ӮзӮМҸoҺ©Ӯрүь•ПӮ·ӮйӮМӮН8җўӢIҲИҚ~ӮЕӮ ӮйӮұӮЖ
–Шъ„–һ’vӮӘҒu“мҚsҒvӮөӮҪӮЖӮМҒwҺOҚ‘ҺjӢLҒxӮМӢLҸqӮӘӮ»ӮМӮЬӮЬҳ`Қ‘ӮЦ“n—ҲӮөӮҪӮұӮЖӮрҲУ–ЎӮөӮИӮўӮұӮЖ
•SҚПӮМ–ј–еҺҒ‘°ҸoҗgӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮзҒA‘·ӮМ–ј‘OӮӘҚӮӢе—нӮрҲУ–ЎӮ·ӮйҚӮ—нӮЕӮ ӮйӮұӮЖ
–һ’qӮМҺqӮНҠШҺqҒiӮ©ӮзӮұҒjӮЕҒAӮ»ӮМҺqҒiҲо–ЪӮМ•ғӮЙӮ ӮҪӮйҒjӮНҚӮ—нҒiӮұӮЬҒjӮЖӮўӮӨҲЩҚ‘•—ӮМ–ј‘OӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮа“n—ҲҗlҗаӮрҗ¶ӮЭҸoӮ·—vҲцӮЖӮИӮБӮДӮўӮйӮӘҒAҗ…’JҗзҸHӮНҒu‘hүдҺҒ“n—ҲҗlҗаҒvӮӘҚLӮӯҺуӮҜ“ьӮкӮзӮкӮҪ”wҢiӮр‘hүдҺҒӮрӢt‘ҜӮЖӮ·ӮйҺjҠПӮЖ“KҚҮӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҸqӮЧӮДӮўӮй[12]ҒBӮЬӮҪҒAҠШҺqӮНҒw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒxҢp‘М“VҚc24”NҸH9ҢҺӮМҸрӮМ’ҚӮЙҒu‘е“ъ–{җlӣW”ЧҸ—ҸҠҗ¶ҲЧҠШҺq–зҒvҒi‘е“ъ–{җlҒA”ЧҸ—ҒiӮЖӮИӮиӮМӮӯӮЙӮМӮЯҒjӮрӣWӮиӮДҗ¶ӮЯӮйӮрҠШҺqӮЖӮ·Ғj[’ҚҺЯ 2]ӮЖӮіӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮЙҒAҠOҚ‘җlӮЖӮМҚ¬ҢҢӮМ’КҸМӮЕӮ ӮиҒA–һ’qҠШҺqӮНҚ¬ҢҢҺҷӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮрҺҰӮ·[13]ҒB
Ғu‘hүдҒvӮрҺҒӮМ–јӮЖӮ·ӮйҺҒ‘°ҒB
җ©ӮНҗbҒiӮЁӮЭҒjҒB

ҺҒҗ_ӮЖҗ„‘ӘӮіӮкӮйҸ@үдҚҝҸ@үд“s”дҢГҗ_ҺР
Ғi“Ю—ЗҢ§ҠҖҢҙҺsҒj
ҺҒҗ©
‘hүдҗb
ҺҒ‘c
•җ“аҸh”H
ҒiҚFҢі“VҚcӮМҢгебҒj
Һн•К
Қc•К
–{ҠС
‘еҳaҚ‘ҚӮҺsҢS‘hүд—W
’ҳ–јӮИҗl•Ё
‘hүдҲо–Ъ
‘hүд”nҺq
‘hүдүЪҲО
‘hүд“ьҺӯ
‘hүдҗФҢZ
Ңгеб
җОҗм’©җb
Ғu‘hүдҒvӮМ•\ӢL
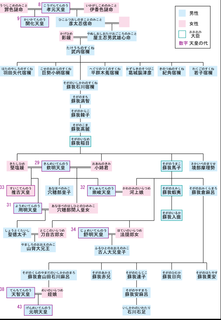
‘hүд - Ғw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒx
Ҹ@үк - ҒwҢГҺ–ӢLҒx
Ҹ@үд - Ғwҗж‘гӢҢҺ––{ӢIҒx“V‘·–{ӢIҒAҒwҸгӢ{җ№“ҝ–@үӨ’йҗаҒxҒAҒw“ъ–{ҺO‘гҺАҳ^Ғx
ҚJҠп - ҒwҢіӢ»ҺӣүҸӢN’ Ғx
ҸoҺ©
ҒwҢГҺ–ӢLҒxӮвҒw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒxӮЕӮНҒAҗ_ҢчҚcҚ@ӮМҺOҠШҗӘ”°ӮИӮЗӮЕҠҲ–фӮөӮҪ•җ“аҸh”HӮр‘cӮЖӮөӮДӮўӮйҒBӢп‘М“IӮИҠҲ“®ӮӘӢLҸqӮіӮкӮйӮМӮН6җўӢI’ҶҚ ӮМ‘hүдҲо–ЪӮ©ӮзӮЕҒAӮ»ӮкҲИ‘OӮЙҠЦӮөӮДӮНӮжӮӯ•ӘӮ©ӮБӮДӮўӮИӮўӮӘҒAүН“аӮМҗОҗмҒiҢ»ҚЭӮМ‘еҚг•{ӮМҗОҗм—¬ҲжҒAҸЪҚЧӮЙ“мүН“аҢSүН“м’¬Ҳкҗ{үкӮ ӮҪӮиӮЖ“Б’иӮіӮкӮйҗаӮаӮ ӮйҒjӮЁӮжӮСҠӢҸйҢ§‘hүд—ўҒiҢ»ҚЭӮМ“Ю—ЗҢ§ҠҖҢҙҺs‘]үд’¬Ӯ ӮҪӮиҒjӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮДӮўӮҪ“y’…ҚӢ‘°ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB ҒwҗVҗпҗ©ҺҒҳ^ҒxӮЕӮН‘hүдҺҒӮрҚc•КҒi—р‘г“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҺҒ‘°ҒjӮЙ•Ә—ЮӮөӮДӮўӮйҒB
—рҺj
үӨҢ ӮМҗEӢЖ“z‘®–ҜӮЖӮөӮДӮМ–рҠ„Ӯр’SӮБӮДӮўӮҪ“n—ҲҢnӮМҺҒ‘°ӮЖҗ[ӮўҠЦҢWӮЙӮ ӮБӮҪӮЖҢ©ӮзӮкҒA“n—ҲҗlӮМ•i•”ӮМҸW’cӮИӮЗӮӘҺқӮВ“–ҺһӮМҗжҗiӢZҸpӮӘ‘hүдҺҒӮМ‘д“ӘӮМҲкҸ•ӮЙӮИӮБӮҪӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒA•§ӢіӮӘ“`—ҲӮөӮҪҚЫӮЙӮ»ӮкӮрӮўӮҝ‘ҒӮӯҺжӮи“ьӮкӮҪӮМӮа‘hүдҺҒӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӮұӮкӮНҒA’©’мӮМҚХвJӮр”CӮіӮкӮДӮўӮҪҳAҗ©ӮМ•Ё•”ҺҒҒA’ҶҗbҺҒӮрҢЎҗ§Ӯ·ӮйҲЧӮМ–Ъ“IӮаӮ ӮБӮҪӮЖҗ„Һ@ӮіӮкӮйҒB
6җўӢIҢг”јӮЙӮНҚЎӮМ“Ю—ЗҢ§ҚӮҺsҢSӢЯ•УӮрҗЁ—НүәӮЙӮЁӮўӮДӮўӮҪӮЖҺvӮнӮкӮДӮўӮйҒB‘hүдҺҒӮӘҗӯҺЎӮМҺАҢ ӮрҸ¶Ҳ¬ӮөӮҪҺһ‘гҲИҢгҒAӮ»ӮМ’nҲжӮЙҸW’Ҷ“IӮЙ“VҚcӮМӢ{ӮӘӮЁӮ©ӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮұӮЖӮ©ӮзӮаӮӨӮ©ӮӘӮнӮкӮйҒB
‘Sҗ·Ҡъ
Ҳо–ЪӮМ‘гӮЙӮИӮйӮЖҒAүЯӢҺӮЙ‘еҗbӮрҸoӮөӮДӮўӮҪҠӢҸйҺҒӮв•ҪҢQҺҒӮНҠщӮЙ–{Ҹ@үЖӮМ–Е–SӮЙӮжӮиҗЁӮўӮрӮИӮӯӮөӮДӮЁӮиҒA‘hүдҺҒӮН‘еҳAӮМ‘е”әҺҒӮЖ•Ё•”ҺҒӮЙӮИӮзӮФҺO‘еҗЁ—НӮМҲкҠpӮЖӮИӮиҒAӮвӮӘӮД‘е”әӢа‘әӮӘҺёӢrӮ·ӮйӮЖҒA‘еҳAӮМ•Ё•”Ғi”ц—`ҒjӮЖ‘еҗbӮМ‘hүдҒiҲо–ЪҒjӮМ“с‘еҗЁ—НӮЖӮИӮйҒBӮЬӮҪҒAүЯӢҺӮМҠӢҸйҺҒӮвҢгӮМ“ЎҢҙҺҒ“Ҝ—lҒA–ә‘hүдҢҳү–•QҒAҸ¬ҺoҢNӮрӢФ–ҫ“VҚcӮЙүЕӮӘӮ№ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮи“VҚcүЖӮМҠOҗКӮЖӮИӮБӮДӮўӮӯҒi”nҺqӮМ–{ӢҸҒiғEғuғXғiҒjӮӘҠӢҸйҢ§ӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҲо–ЪӮМҚИӮНҠӢҸйҺҒӮМҸoӮЕҒAӮ»ӮМҢҢ“қӮЙҳAӮИӮйӮұӮЖӮЙӮжӮиҒA“VҚcӮЦ”ЬӮр”yҸoҸo—ҲӮйҲк‘°ӮЙҳAӮИӮБӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒjҒB
Ҳо–ЪӮНӢФ–ҫ“VҚcӮЖӮЩӮЪ“ҜҺһҠъӮЙ–vӮөҒA“с‘еҗЁ—НӮМҚ\җ}ӮНҺҹ‘гӮМ‘hүд”nҺqӮЬӮЕҲшӮ«ҢpӮӘӮкӮйӮӘҒA—p–ҫ“VҚc•цҢдҢгӮЙҢгҢpҺТӮрӮЯӮ®Ӯй‘ҲӮўӮӘӮ ӮБӮҪҒB‘hүдҺҒӮНҒAҸ¬ҺoҢNӮМҺqӮИӮӘӮзӮа•Ё•”ҺҒӮЙ—i—§ӮіӮкӮДӮўӮҪҢҠ•д•”ҚcҺqӮрҲГҺEӮөҒAҗнӮўӮЕ•Ё•”Һзү®Ӯр“ўӮҝ–ЕӮЪӮ·ӮЖҒAӮ»ӮМҢгӮН‘hүдҺҒҲИҠOӮ©ӮзӮН‘еҳAӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйҺТӮаҸoӮёҒAҗӯҢ ӮН‘hүдҺҒӮМҲкӢЙ‘Мҗ§ӮЖӮИӮйҒB
ӮұӮұӮ©Ӯзҗ’Ҹs“VҚcӮМҲГҺEӮвҒAҗ„ҢГ“VҚcӮЦӮМҠӢҸйҢ§ӮМҠ„ҸчӮМ—vӢҒҒAүЪҲОӮЙӮжӮй“VҚcӮрӮИӮўӮӘӮөӮлӮЙӮ·ӮйӮУӮйӮЬӮўҒA“ьҺӯӮЙӮжӮйҸгӢ{үӨүЖҒiҺR”w‘еҢZүӨҒjӮМ“ў–ЕҒAҸf•ғӮЕҗкҗ§җӯҺЎӮЙ”Ҫ‘ОӮ·ӮйӢ«•”–Җ—қҗЁӮМҺёӢrӮИӮЗӮМҗкүЎӮФӮиӮӘ“`ӮҰӮзӮкӮДӮЁӮиҒA‘hүдҺҒҺO‘гӮЙӮнӮҪӮБӮДҢ —НӮр—~ӮөӮўӮӘӮЬӮЬӮЙӮөӮҪӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB
ӮөӮ©Ӯө”nҺqӮМҺҖҢгӮЙҒA‘hүдҺҒӮЙ‘ОӮ·ӮйҚc‘°ӮвҸ”ҚӢ‘°ӮМ”ҪҠҙӮӘҚӮӮЬӮБӮД‘hүдҺҒӮМҗӯҺЎҠо”ХӮӘ“®—hӮөҒAӮ»ӮкӮрҚҺ•һӮөӮжӮӨӮЖӮөӮД“ьҺӯӮЙӮжӮйӢӯҢ җӯҺЎӮЙҢqӮӘӮБӮҪҒAӮЖӮўӮӨҢ©•ыӮаҸӯӮИӮ©ӮзӮёӮ ӮйҒBӮұӮкӮНҒw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒx“ҷӮЙӮжӮй‘hүдҺҒӮЙ”Ы’и“IӮИӢLҸqӮЙ‘ОӮ·Ӯй”Ҫҳ_ӮЕӮ ӮйҒB
‘еү»ӮМүьҗVӮ©Ӯзҗpҗ\ӮМ—җӮЬӮЕ •ТҸW
‘hүдҺҒӮН‘еү»ӮМүьҗVҒiүі–ӨӮМ•ПҒjӮЙӮД–ЕӮСӮҪҒAӮЖ”FҺҜӮіӮкӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўҒB
645”NӮЙ’Ҷ‘еҢZҚcҺqҒA’ҶҗbҠҷ‘«ӮзӮЙӮжӮБӮДҒA“ьҺӯӮӘҲГҺEӮіӮкӮйӮЖӮЖӮаӮЙүЪҲОӮӘҺ©ҺEӮ·ӮйҒiүі–ӨӮМ•ПҒjӮЖ‘hүдҺҒӮМҗЁ—НӮН‘е•қӮЙ’бүәӮ·ӮйӮӘҒAӮұӮкӮНӮ ӮӯӮЬӮЕӮаүЪҲОӮр’„—¬ӮЖӮ·Ӯй‘hүдҺҒҸ@–{үЖӮМ–v—ҺҒE–Е–SӮҫӮҜӮЙӮЖӮЗӮЬӮйҒBүі–ӨӮМ•ПӮЙӮНҒA–T—¬ӮЕӮ Ӯй‘hүд‘q–ғҳCҒiүЪҲОӮМ’нҒjӮМҺqӮЕӮ Ӯй‘hүд‘qҺR“cҗОҗм–ғҳCӮНҒA’Ҷ‘еҢZҚcҺqӮМӢҰ—НҺТӮЖӮөӮДҠЦӮнӮБӮДӮўӮҪҒBҗОҗм–ғҳCӮНӮұӮМҢгӮЙүE‘еҗbӮЙ”CӮ¶ӮзӮкҒA–әӮМү“’q–әӮЖ–Г–әӮр’Ҷ‘еҢZҚcҺqӮМҚ@ӮЙӮөӮДӮўӮйҒBҗОҗм–ғҳCҺ©җgӮН649”NӮЙҷlҚЯӮЕҺ©ҠQӮөҒAж§ҢҫӮөӮҪ’нӮМ‘hүд“ъҢьӮа‘еҚЙ•{ӮЙҚ¶‘JӮіӮ№ӮзӮкӮҪҒiҢы••Ӯ¶ӮЖӮМҗаӮаӮ ӮйҒjҒBӮөӮ©ӮөҒA‘јӮМ’нӮЕӮ Ӯй‘hүдҗФҢZӮЖ‘hүдҳAҺqӮНҒA“V’q“VҚcӮМҺһ‘гӮЙ‘еҗbҒiҗФҢZӮНҚ¶‘еҗbҒAҳAҺqӮНӮНӮБӮ«ӮиӮН•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮӘүE‘еҗbӮЖҗ„’иӮіӮкӮДӮўӮйҒjӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮДӮЁӮиҒA‘hүдҺҒӮНҲк’иӮМҚӮӮў’nҲКӮр•ЫҺқӮө‘ұӮҜӮДӮўӮйҒB
ҳAҺqӮН“V’q“VҚcӮМҗіҺ®ӮИ‘ҰҲКӮрҢ©ӮИӮўӮЬӮЬҺҖӢҺӮөҒAҗФҢZӮЖӮаӮӨҲкҗlӮМ’нӮЕӮ ӮйҢдҺj‘е•vӮМ‘hүдүКҲАӮНҗpҗ\ӮМ—җӮЕ‘е—FҚcҺq‘ӨӮЙӮВӮўӮД”sӮкҒAӮ»ӮкӮјӮк—¬ҚЯҒEҺ©ҠQӮЖӮИӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМүҷӮЕҳAҺqӮМҺqӮЕӮ Ӯй‘hүдҲА–ғҳCӮНҒA“V•җ“VҚcӮМҗM”CӮӘҢъӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯӮЙ‘hүдҺҒӮМҢгӮрҢpӮ¬ҒAҗОҗм’©җbӮМҗ©ҺҒӮрҺ’ӮБӮҪҒB
ӮұӮМӮжӮӨӮЙүі–ӨӮМ•ПҢгӮаҒA‘q–ғҳCӮМ‘§Һq’BӮӘӮИӮЁҗӯҺЎӮМ’ҶҗS“I—§ҸкӮЙӮЖӮЗӮЬӮиҒA‘ҠҺҹӮ®җӯ‘ҲӮЕҗҠ‘ЮӮөӮИӮӘӮзӮаӮөӮОӮзӮӯӮН‘hүдҺҒҒiҳAҺqӮМҢn“қҒjӮН‘ұӮўӮҪҒB
‘hүдҢnҗОҗм’©җb •ТҸW
‘hүдҢnҗОҗмҺҒӮНҒA”т’№Һһ‘г––ҠъӮ©Ӯз“Ю—ЗҺһ‘гӮЙҒAӮ»ӮМҢҢӮрҲшӮўӮҪ“VҚcҒiҺқ“қ“VҚcӮЖҢі–ҫ“VҚcҒjӮр”yҸoӮөӮҪҒiӮ»ӮкӮјӮкҗОҗм–ғҳCӮМ–әҒAү“’q–әӮЖ–Г–әӮӘ•кҒjҒB
ӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҒA‘hүдҗФҢZӮМҠO‘·ӮЕӮ ӮйҺR•УҚcҸ—ӮӘҒAҺқ“қ“VҚcӮЙ”rҸңӮіӮкӮҪ•vӮМ‘е’ГҚcҺqӮЙҸ}ҺҖӮөӮҪӮиҒAӮЬӮҪ•¶•җ“VҚcӮМӣlӮМҗОҗм“ҒҺq–әӮӘҒA“VҚc•цҢдҢгӮЙ–^’jӮЖӮМҠЦҢWӮрҺқӮБӮҪҺ–Ӯ©ӮзӮ»ӮМҗg•ӘӮр”Қ’DӮіӮкӮйҺ–ҢҸӮИӮЗӮаӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒBҠp“c•¶үqӮМҗаӮЙӮжӮйӮЖҒA“ҒҺq–әӮЙӮНҚLҗ¬ҒEҚLҗўӮМ2’jӮӘӮ ӮиҒA•кӮЙҳAҚАӮөӮД—јҚcҺqӮМҚc‘°ӮМҗg•ӘӮр’DӮўҒAҲЩ•кҢZ’нӮМҺсҚcҺqӮМӢЈ‘Ҳ‘ҠҺиӮр”rҸңӮөӮжӮӨӮЖӮөӮДӮМ“ЎҢҙ•s”д“ҷҒEӢkҺOҗз‘г•v•wӮМүA–dӮЖӮіӮкӮйҒB
ӮЬӮҪ–ң—tҸWӮЙӮжӮкӮОҒA“ҜӮ¶җФҢZӮМҠO‘·ӮЕӮ Ӯй•дҗПҚcҺqӮа’A”nҚcҸ—ӮЖӮМ–§’КӮӘҳIҢ©ӮөӮДҚ¶‘JӮіӮкӮҪҒB•дҗПҚcҺqӮНҒAҚKӮўӮЙӮаҺқ“қ“VҚc•цҢдҢгӮЙ’m‘ҫҗӯҠҜҺ–ӮЙҸoҗўӮөӮҪӮӘҒAҺбӮӯӮөӮД–SӮӯӮИӮБӮҪҒB
•s”д“ҷӮМҗіҚИӮНҒAҲА–ғҳCӮМ–әӮМ‘hүдҸ©ҺqҒi“ЎҢҙ•җ’q–ғҳCҒE“ЎҢҙ–[‘OҒE“ЎҢҙүFҚҮӮМ•кҒjӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМҢМӮрҲИӮДҒAӮ»ӮМ’нӮМҗОҗмҗО‘«ӮЖҺqӮМҗОҗм”N‘«ӮН’„—¬ӮМ•җ’q–ғҳCӮр‘cӮЖӮ·Ӯй“ЎҢҙ“мүЖӮЖҢӢӮСӮВӮӯӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB”N‘«ӮНҒA•җ’q–ғҳCҺҹ’jӮМ“ЎҢҙ’Ү–ғҳCӮӘҗЭ—§ӮөӮҪҺҮ”ч’Ҷ‘дӮМ‘е•JӮЖӮөӮДӮ»ӮМ•вҚІӮЙ“–ӮҪӮиҒA’Ҷ—¬ӢM‘°ӮЖӮөӮДӮИӮсӮЖӮ©Ӯ»ӮМ–Ҫ–¬Ӯр•ЫӮБӮҪҒB
җҠ‘Ю •ТҸW
ӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮМ“ЎҢҙ“мүЖӮӘ“ЎҢҙ’Ү–ғҳCӮМ—җӮЕҗҠ‘ЮӮөӮДӮөӮЬӮӨӮЖҒAҗОҗмҺҒӮа•ҪҲАӢһ‘J“sҢгӮЙ–SӮӯӮИӮБӮҪҗОҗмҗ^ҺзҒiҗіҺlҲКҸгҒEҺQӢcҒjӮрҚЕҢгӮЙҢцӢЁӮНҸoӮИӮӯӮИӮйҒBӮ»ӮМҢгҒAҢіҢcҢі”NҒi877”NҒjӮЙӮИӮБӮДҗОҗм–Ш‘әӮӘҗж‘cӮМ–јҒi‘hүдҗОҗмҒjӮрӮаӮБӮДҺq‘·ӮМҺҒӮМ–јҸМӮЖӮ·ӮйӮМӮЕӮНҒAжҒӮр”рӮҜӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮёҒAҺҖҢгӮЙҗ¶‘OӮМҺА–јӮрҠхӮсӮЕҢыӮЙӮөӮИӮў•—ҸKӮЙ”ҪӮ·ӮйӮЖӮөӮДҒAҸ@Ҡx’©җbҗ©ӮЙүьҗ©Ӯ·Ӯй[1]ҒBӮМӮҝҒAҺҒӮМ•\ӢLӮНҸ@ҠxӮ©ӮзҸ@үӘӮЙҒA“ЗӮЭӮаҒuӮ»ӮӘҒvӮ©ӮзҢP“ЗӮЭӮМҒuӮЮӮЛӮЁӮ©ҒvӮЙ•ПӮнӮБӮҪ[2]ҒB
Қ]ҢЛҺһ‘гӮМ’nүәүЖӮЕӮ ӮйҗВ–ШүЖҒiҺjҗ¶ӮИӮЗҒjҒEҺO‘оүЖҒiҸўҺg•ӣҺgҒjӮИӮЗӮӘҒAҸ@үӘҗ©ӮрҸМӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA‘hүдҺҒӮМҢҢ“қӮНҒA“ЎҢҙ•s”д“ҷӮЙүЕӮўӮЕ•җ’q–ғҳCҒE–[‘OҒEүFҚҮӮМҺO’jӮр–ЧӮҜӮҪ‘hүдҸ©ҺqӮр’КӮөӮДҢ»‘гӮЙӮа“`ӮнӮБӮДӮўӮйҒBӮИӮЁ‘јӮЙ‘hүдҺҒӮМҢҢӮрҺcӮөӮҪӮМӮНҒA‘hүдҲо–ЪӮМ–әӮЕӮ Ӯй‘hүдҢҳү–•QӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮМҢn“қӮН‘hүдҢҳү–•Q Ғ\ ҚчҲдҚcҺq Ғ\ Ӣg”х•PүӨ Ғ\ ҚcӢЙ“VҚc Ғ\ “V’q“VҚc Ғ\ ҒiҲИҢг—р‘г“VҚcҒjӮЖӮИӮйҒB
‘hүдҺҒ“n—Ҳҗlҗа
•ТҸW
–еҳe’х“сӮӘ1971”NӮЙ‘hүдҺҒ“n—ҲҗlҗаӮр’сҸҘӮөӮҪ[3][4]ҒB–еҳeӮӘ’сҸҘӮөӮҪӮМӮНүһҗ_“VҚcӮМ‘гӮЙ“n—ҲӮөӮҪҒA•SҚПӮМҚӮҠҜҒA–Ш–һ’vҒiӮаӮӯӮЬӮҝҒjӮЖ‘hүд–һ’qҒiӮЬӮҝҒjӮӘ“ҜҲкҗl•ЁӮЖӮ·ӮйҗаӮЕҒA—й–Ш–х–ҜӮвҺR”цҚKӢvӮзӮМҺxҺқ[5][6]Ӯр“ҫӮҪҲк•ыҒAүБ“ЎҢӘӢgӮвҚв–{Ӣ`ҺнӮзӮӘ”б”»[7][8]ӮөӮҪӮжӮӨӮЙҒAҺj—ҝҸгӮМ–в‘и“_ӮӘ‘ҪӮўҒBҚӘӢ’ӮӘ•sҸ\•ӘӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҺw“EӮӘӮ Ӯй[9]ҒB
–в‘и“_ӮНҗ®—қӮ·ӮйӮЖҲИүәӮМ’КӮиӮЕӮ ӮиҒA–Ш–һ’vӮЖ‘hүд–һ’qӮр“ҜҲкҗl•ЁӮЕӮ ӮйӮЖҺАҸШӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮН–в‘и“_ӮӘӮ Ӯй[10][11]ҒB
Ғu–Ш–һ’vҒvӮМ–јӮӘҢ©ӮҰӮйҒw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒxӮМүһҗ_“VҚc25”NҒiҗј—п294”NҒAҺj—ҝүрҺЯҸгӮН414”NҒjӮЖҒu–Шъ„–һ’vҒvӮМ–јӮӘҢ©ӮҰӮйҒwҺOҚ‘ҺjӢLҒx•SҚП–{ӢIӮМҠWкbүӨ21”NҒiҗј—п475”NҒjӮЖӮЕӮНҺһ‘гӮӘҲЩӮИӮй
•SҚПӮМ–ј–еҺҒ‘°ӮЕӮ Ӯй–Ш–һ’vӮӘҒAҺ©ӮзӮМҗ©ӮрҺМӮД‘hүдҺҒӮр–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮМ•sҺ©‘RӮі
“n—ҲҢnҚӢ‘°ӮӘҺ©ӮзӮМҸoҺ©Ӯрүь•ПӮ·ӮйӮМӮН8җўӢIҲИҚ~ӮЕӮ ӮйӮұӮЖ
–Шъ„–һ’vӮӘҒu“мҚsҒvӮөӮҪӮЖӮМҒwҺOҚ‘ҺjӢLҒxӮМӢLҸqӮӘӮ»ӮМӮЬӮЬҳ`Қ‘ӮЦ“n—ҲӮөӮҪӮұӮЖӮрҲУ–ЎӮөӮИӮўӮұӮЖ
•SҚПӮМ–ј–еҺҒ‘°ҸoҗgӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮзҒA‘·ӮМ–ј‘OӮӘҚӮӢе—нӮрҲУ–ЎӮ·ӮйҚӮ—нӮЕӮ ӮйӮұӮЖ
–һ’qӮМҺqӮНҠШҺqҒiӮ©ӮзӮұҒjӮЕҒAӮ»ӮМҺqҒiҲо–ЪӮМ•ғӮЙӮ ӮҪӮйҒjӮНҚӮ—нҒiӮұӮЬҒjӮЖӮўӮӨҲЩҚ‘•—ӮМ–ј‘OӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮа“n—ҲҗlҗаӮрҗ¶ӮЭҸoӮ·—vҲцӮЖӮИӮБӮДӮўӮйӮӘҒAҗ…’JҗзҸHӮНҒu‘hүдҺҒ“n—ҲҗlҗаҒvӮӘҚLӮӯҺуӮҜ“ьӮкӮзӮкӮҪ”wҢiӮр‘hүдҺҒӮрӢt‘ҜӮЖӮ·ӮйҺjҠПӮЖ“KҚҮӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҸqӮЧӮДӮўӮй[12]ҒBӮЬӮҪҒAҠШҺqӮНҒw“ъ–{Ҹ‘ӢIҒxҢp‘М“VҚc24”NҸH9ҢҺӮМҸрӮМ’ҚӮЙҒu‘е“ъ–{җlӣW”ЧҸ—ҸҠҗ¶ҲЧҠШҺq–зҒvҒi‘е“ъ–{җlҒA”ЧҸ—ҒiӮЖӮИӮиӮМӮӯӮЙӮМӮЯҒjӮрӣWӮиӮДҗ¶ӮЯӮйӮрҠШҺqӮЖӮ·Ғj[’ҚҺЯ 2]ӮЖӮіӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮЙҒAҠOҚ‘җlӮЖӮМҚ¬ҢҢӮМ’КҸМӮЕӮ ӮиҒA–һ’qҠШҺqӮНҚ¬ҢҢҺҷӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮрҺҰӮ·[13]ҒB
2020”N01ҢҺ13“ъ
җО’JҺҒ
җО’JҺҒӮНҒA“ъ–{ӮМҺҒ‘°ҒBү“Қ]җО’JҺҒҒiӮўӮөӮӘӮвӮөҒjӮЖ“yҠтҗО’JҺҒҒiӮўӮөӮҪӮЙ/ӮўӮөӮҫӮЙ/ ӮўӮөӮӘӮўҒEӮөҒjӮӘӮ ӮйҒB
ү“Қ]җО’JҺҒ
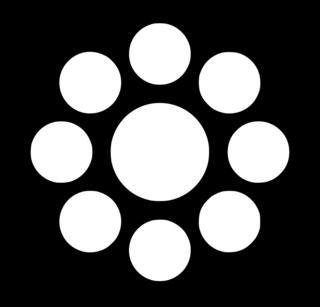
үЖ–дҒ@Ӣг—jҗҜ
–{җ©
“ЎҢҙ“мүЖҲЧҢӣ—¬“сҠK“°ҺҒҸҺ—¬
үЖ‘c
җО’Jҗӯҗҙ
Һн•К
•җүЖ
Ҹoҗg’n
ү“Қ]Қ‘ҚІ–мҢSҗјӢҪ‘‘җО’J[1]
ҺеӮИҚӘӢ’’n
ү“Қ]Қ‘ҚІ–мҢSҗјӢҪ
ҸxүНҚ‘ҲА”{ҢS‘«Ӣv•Ы[2]
’ҳ–јӮИҗl•Ё
җО’J’еҗҙ
җО’JҗҙҸ№
җО’J–sҗҙ
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
җОҠL(ҲЩ‘МҺҡ)
җОғ–’J(ҲЩ‘МҺҡ)
ү“Қ]Қ‘ҚІ–мҢSҗјӢҪҗО’JҒiҢ»ҚЭӮМҗГүӘҢ§Ҡ|җмҺsҒjӮр–{ҠСӮЖӮ·ӮйҗО’JҺҒӮН“ЎҢҙ“мүЖҲЧҢӣ—¬“сҠK“°ҺҒӮМ—¬ӮкӮр‘gӮЮӮЖӮіӮкӮйҒAҗнҚ‘Һһ‘гӮ©ӮзҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮ©ӮҜӮДӮМ•җүЖҲк‘°ҒBӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҒAҗО’JҺҒӮМ‘cӮЕӮ ӮйҗО’JҗӯҗҙӮМ‘\‘c•ғҒA“сҠK“°Қsҗ°ҲИ‘OӮМҢnҗ}ӮН–ҫӮзӮ©ӮЕӮНӮИӮӯҒAҒwҠ°үiҸ”үЖҢnҗ}“`ҒxӮЙӢ’ӮкӮОҒA“сҠK“°ҚsҸHҒiҲц”ҰҺзҒA–@–ј:ҚsӢФҒjҒ|“сҠK“°Қsҗ°Ғ|җјӢҪҚsҗҙҒ|“сҠK“°җҙ’·Ғ|җО’JҗӯҗҙӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒBҗјӢҪ–Ҝ•”Ҹӯ•гӮЖ“сҠK“°ҚsҸHӮМ–…ӮЖӮМҺqӮМ“аҒAҺҹ’jӮЕӮ ӮйҚsҗ°ӮӘ“сҠK“°ҚsҸHӮМҢгӮрҢpӮўӮҫӮЖӮіӮкҒAҗО’JҺҒӮрҸМӮөӮҪҗӯҗҙӮЙҺҠӮйӮЬӮЕүҪ“xӮа•cҺҡӮр•ПҚXӮөӮДӮЁӮиҒAҗӯҗҙҺ©җgӮН“–ҸүҗјӢҪҺҒӮрҸМӮөӮДӮўӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBҗӯҗҙӮӘ–јҺҡӮрүьӮЯӮҪӮМӮНҗО’J‘әӮЙҲЪӮиҸZӮсӮҫӮұӮЖӮЙ—R—ҲӮ·ӮйӮЖӮіӮкӮйӮӘҒAҲкҗаӮЙӮН“ҝҗмүЖҚNӮМ‘ӨҺәҒAҗјӢҪӢЗӮЙңЭӮБӮҪӮҪӮЯӮЖӮа“`ӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮИӮЁҒAҗО’JҺҒӮМҢҢ‘°ӮЕӮ ӮйҗјӢҪҺҒӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҒwҠ|җмҺsҺҸҒxӮИӮЗӮЙӢ’ӮкӮОҒAү“Қ]ҺOҸ\ҳZҗlҸOӮЙҗ”ӮҰӮзӮкҒAҺRүИүЖӮМ’n“Ә‘гӮЖӮөӮДҗјӢҪҸҜӮЙүeӢҝӮМӮ ӮБӮҪҗјӢҪҺҒӮЖҠЦҳAҗ«ӮӘҢ©ҺуӮҜӮзӮкӮйӮаӮМӮМҒA‘ӯҗаӮЙӮ ӮйҺOүНҗјӢҪҺҒӮЖӮМҠЦҳAҗ«ӮН•s–ҫӮЕӮ ӮйҒBҠо–{“IӮИүЖ–дӮНҒAү“Қ]җО’JҺҒӮМ—R—ҲӮЕӮ ӮйҗО’J‘әӮМӢгӮВӮМӢҗҗОҒi–јҺҡҗОҒAүЖ–дҗОҒAӢг—jҗОҒjӮЙӮҝӮИӮЭӢг—jҗҜӮҫӮӘҒAҢKҢҙҗӯҸdӮМҢn“қӮНҗО–ЭӢг—jҒE’З‘таbӮЕӮ ӮйӮЖӮіӮкӮйҒB
ҲА”{ҺөӢRӮЙҗ”ӮҰӮзӮкӮйҗО’JҺҒҒiҗОҠLҺҒҒjӮМҗО’JҸdҳYҚ¶үq–еӮНҒAү“Қ]җО’JҺҒӮМҲк‘°ӮЖ“`ӮҰӮзӮкҒAҚЎҗмҺҒҒE•җ“cҺҒӮЙҺdӮҰӮҪҢгҒA“ҝҗмҺҒӮЙҺdӮҰӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB
Ҳк‘°
•ТҸW
җО’Jҗӯҗҙ
ү“Қ]җО’JҺҒӮМ‘cҒB’КҸМӮНҸ\ҳYүEүq–еҒBҚЎҗмӢ`ҢіҒEҺҒҗ^ҒE“ҝҗмүЖҚNӮЙҺdӮҰӮйҒB
җО’J’еҗҙ
җӯҗҙӮМ‘·ӮЕ“ҝҗмүЖҠш–{ҒB“ҮҢҙӮМ—җӮвҢcҲАӮМ•ПӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBҚ]ҢЛ–k’¬•тҚsӮрӢОӮЯӮйҒBҗО’JҸ\‘ ӮМҺҒҗ_ӮЖӮўӮӨҗОғ–’J–ҫҗ_ӮӘҠ|җмҺsӮЙӮ ӮйҒB
җО’JҗҙҸ№
ҚІ“n•тҚsҒAҠЁ’и•тҚsҒA’·Қи•тҚsӮИӮЗӮр—р”CӮөҒA“cҸАҲУҺҹӮМҚsҗӯӮЙҗ[ӮӯҠЦ—^ӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB
җО’J–sҗҙ
җО’J’еҗҙӮМ––ебӮЕ–Ӣ––ӮМ“ҝҗмүЖҠш–{ҒBҚ]ҢЛ–k’¬•тҚsӮрӢОӮЯӮйҒBҲАҗӯӮМ‘еҚ–ӮЙҠЦ—^ӮөӮҪӮЖӮіӮкҒA‘еҳVҒEҲдҲЙ’ј•JӮМ•Рҳr“I‘¶ҚЭӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB
“yҠтҗО’JҺҒ
”ь”ZҚ‘“yҠтҢSӮМ“yҠтҺҒӮр”ӯҸЛӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҠҷ‘qҺһ‘гӮЙ“yҠтҢхҚsӮӘ”ь”ZҚ‘•ыҢ§ҢSҗО’JӮМ’n“ӘҗEӮр“ҫҒA’„ҺqҒEҚ‘ҚtӮЙ•ӘӮҜ—^ӮҰӮҪӮұӮЖӮӘҗО’JҺҒӮМҺnӮЬӮиӮЖӮіӮкӮйҒBҺә’¬Һһ‘гӮЙӮН–ҫ’qҺҒҒA”м“cҺҒӮЖӮЖӮаӮЙ•тҢцҸOӮЖӮИӮиҒAҲк‘°ӮӘҚЭӢһӮөӮҪҒB
җнҚ‘Һһ‘гӮЙҚЦ“Ў“№ҺOӮӘ‘д“ӘӮ·ӮйӮЖҗО’J‘О”nҺзӮНӮұӮкӮЙҸ]ӮӨӮӘҒA’·—ЗҗмӮМҗнӮўӮЙӮЁӮўӮД“№ҺOӮЙ–Ў•ыӮө”ь”ZӮМҗО’JҺҒӮН–Е–SӮөӮҪҒBҚЭӢһӮМҗО’JҺҒӮНҗО’JҢхҗӯӮӘҗО’J—Ҡ’CҒiҚЦ“Ў—ҳҢ«ӮМҺqҒjӮр—{ҺqӮЖӮөӮД–әӮрӣWӮ№ҒAӮ»ӮМҗО’J—Ҡ’CӮН–ҫ’qҢхҸGӮМүЖҗbӮЖӮИӮБӮҪҒBӮИӮЁҒAҢхҗӯӮМӮаӮӨҲкҗlӮМ–әӮН’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮМҗіҺәӮЕӮ ӮйҒB—Ҡ’CӮНҺRҚиӮМҗнӮўҢгӮЙ“yҚІӮЙ“ҰӮкӮДӢ`ҢZ’нӮЕӮ Ӯй’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮЙҸd—pӮіӮкӮҪӮӘҒAҢЛҺҹҗмӮМҗнӮўӮЕҗнҺҖӮөӮДӮўӮйҒB
ү“Қ]җО’JҺҒ
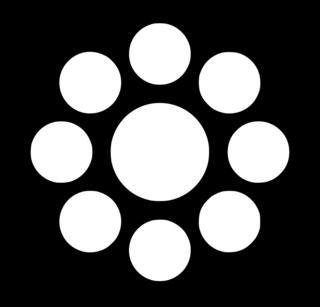
үЖ–дҒ@Ӣг—jҗҜ
–{җ©
“ЎҢҙ“мүЖҲЧҢӣ—¬“сҠK“°ҺҒҸҺ—¬
үЖ‘c
җО’Jҗӯҗҙ
Һн•К
•җүЖ
Ҹoҗg’n
ү“Қ]Қ‘ҚІ–мҢSҗјӢҪ‘‘җО’J[1]
ҺеӮИҚӘӢ’’n
ү“Қ]Қ‘ҚІ–мҢSҗјӢҪ
ҸxүНҚ‘ҲА”{ҢS‘«Ӣv•Ы[2]
’ҳ–јӮИҗl•Ё
җО’J’еҗҙ
җО’JҗҙҸ№
җО’J–sҗҙ
Һx—¬ҒA•ӘүЖ
җОҠL(ҲЩ‘МҺҡ)
җОғ–’J(ҲЩ‘МҺҡ)
ү“Қ]Қ‘ҚІ–мҢSҗјӢҪҗО’JҒiҢ»ҚЭӮМҗГүӘҢ§Ҡ|җмҺsҒjӮр–{ҠСӮЖӮ·ӮйҗО’JҺҒӮН“ЎҢҙ“мүЖҲЧҢӣ—¬“сҠK“°ҺҒӮМ—¬ӮкӮр‘gӮЮӮЖӮіӮкӮйҒAҗнҚ‘Һһ‘гӮ©ӮзҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮ©ӮҜӮДӮМ•җүЖҲк‘°ҒBӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҒAҗО’JҺҒӮМ‘cӮЕӮ ӮйҗО’JҗӯҗҙӮМ‘\‘c•ғҒA“сҠK“°Қsҗ°ҲИ‘OӮМҢnҗ}ӮН–ҫӮзӮ©ӮЕӮНӮИӮӯҒAҒwҠ°үiҸ”үЖҢnҗ}“`ҒxӮЙӢ’ӮкӮОҒA“сҠK“°ҚsҸHҒiҲц”ҰҺзҒA–@–ј:ҚsӢФҒjҒ|“сҠK“°Қsҗ°Ғ|җјӢҪҚsҗҙҒ|“сҠK“°җҙ’·Ғ|җО’JҗӯҗҙӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒBҗјӢҪ–Ҝ•”Ҹӯ•гӮЖ“сҠK“°ҚsҸHӮМ–…ӮЖӮМҺqӮМ“аҒAҺҹ’jӮЕӮ ӮйҚsҗ°ӮӘ“сҠK“°ҚsҸHӮМҢгӮрҢpӮўӮҫӮЖӮіӮкҒAҗО’JҺҒӮрҸМӮөӮҪҗӯҗҙӮЙҺҠӮйӮЬӮЕүҪ“xӮа•cҺҡӮр•ПҚXӮөӮДӮЁӮиҒAҗӯҗҙҺ©җgӮН“–ҸүҗјӢҪҺҒӮрҸМӮөӮДӮўӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBҗӯҗҙӮӘ–јҺҡӮрүьӮЯӮҪӮМӮНҗО’J‘әӮЙҲЪӮиҸZӮсӮҫӮұӮЖӮЙ—R—ҲӮ·ӮйӮЖӮіӮкӮйӮӘҒAҲкҗаӮЙӮН“ҝҗмүЖҚNӮМ‘ӨҺәҒAҗјӢҪӢЗӮЙңЭӮБӮҪӮҪӮЯӮЖӮа“`ӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮИӮЁҒAҗО’JҺҒӮМҢҢ‘°ӮЕӮ ӮйҗјӢҪҺҒӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҒwҠ|җмҺsҺҸҒxӮИӮЗӮЙӢ’ӮкӮОҒAү“Қ]ҺOҸ\ҳZҗlҸOӮЙҗ”ӮҰӮзӮкҒAҺRүИүЖӮМ’n“Ә‘гӮЖӮөӮДҗјӢҪҸҜӮЙүeӢҝӮМӮ ӮБӮҪҗјӢҪҺҒӮЖҠЦҳAҗ«ӮӘҢ©ҺуӮҜӮзӮкӮйӮаӮМӮМҒA‘ӯҗаӮЙӮ ӮйҺOүНҗјӢҪҺҒӮЖӮМҠЦҳAҗ«ӮН•s–ҫӮЕӮ ӮйҒBҠо–{“IӮИүЖ–дӮНҒAү“Қ]җО’JҺҒӮМ—R—ҲӮЕӮ ӮйҗО’J‘әӮМӢгӮВӮМӢҗҗОҒi–јҺҡҗОҒAүЖ–дҗОҒAӢг—jҗОҒjӮЙӮҝӮИӮЭӢг—jҗҜӮҫӮӘҒAҢKҢҙҗӯҸdӮМҢn“қӮНҗО–ЭӢг—jҒE’З‘таbӮЕӮ ӮйӮЖӮіӮкӮйҒB
ҲА”{ҺөӢRӮЙҗ”ӮҰӮзӮкӮйҗО’JҺҒҒiҗОҠLҺҒҒjӮМҗО’JҸdҳYҚ¶үq–еӮНҒAү“Қ]җО’JҺҒӮМҲк‘°ӮЖ“`ӮҰӮзӮкҒAҚЎҗмҺҒҒE•җ“cҺҒӮЙҺdӮҰӮҪҢгҒA“ҝҗмҺҒӮЙҺdӮҰӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB
Ҳк‘°
•ТҸW
җО’Jҗӯҗҙ
ү“Қ]җО’JҺҒӮМ‘cҒB’КҸМӮНҸ\ҳYүEүq–еҒBҚЎҗмӢ`ҢіҒEҺҒҗ^ҒE“ҝҗмүЖҚNӮЙҺdӮҰӮйҒB
җО’J’еҗҙ
җӯҗҙӮМ‘·ӮЕ“ҝҗмүЖҠш–{ҒB“ҮҢҙӮМ—җӮвҢcҲАӮМ•ПӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBҚ]ҢЛ–k’¬•тҚsӮрӢОӮЯӮйҒBҗО’JҸ\‘ ӮМҺҒҗ_ӮЖӮўӮӨҗОғ–’J–ҫҗ_ӮӘҠ|җмҺsӮЙӮ ӮйҒB
җО’JҗҙҸ№
ҚІ“n•тҚsҒAҠЁ’и•тҚsҒA’·Қи•тҚsӮИӮЗӮр—р”CӮөҒA“cҸАҲУҺҹӮМҚsҗӯӮЙҗ[ӮӯҠЦ—^ӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB
җО’J–sҗҙ
җО’J’еҗҙӮМ––ебӮЕ–Ӣ––ӮМ“ҝҗмүЖҠш–{ҒBҚ]ҢЛ–k’¬•тҚsӮрӢОӮЯӮйҒBҲАҗӯӮМ‘еҚ–ӮЙҠЦ—^ӮөӮҪӮЖӮіӮкҒA‘еҳVҒEҲдҲЙ’ј•JӮМ•Рҳr“I‘¶ҚЭӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB
“yҠтҗО’JҺҒ
”ь”ZҚ‘“yҠтҢSӮМ“yҠтҺҒӮр”ӯҸЛӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҠҷ‘qҺһ‘гӮЙ“yҠтҢхҚsӮӘ”ь”ZҚ‘•ыҢ§ҢSҗО’JӮМ’n“ӘҗEӮр“ҫҒA’„ҺqҒEҚ‘ҚtӮЙ•ӘӮҜ—^ӮҰӮҪӮұӮЖӮӘҗО’JҺҒӮМҺnӮЬӮиӮЖӮіӮкӮйҒBҺә’¬Һһ‘гӮЙӮН–ҫ’qҺҒҒA”м“cҺҒӮЖӮЖӮаӮЙ•тҢцҸOӮЖӮИӮиҒAҲк‘°ӮӘҚЭӢһӮөӮҪҒB
җнҚ‘Һһ‘гӮЙҚЦ“Ў“№ҺOӮӘ‘д“ӘӮ·ӮйӮЖҗО’J‘О”nҺзӮНӮұӮкӮЙҸ]ӮӨӮӘҒA’·—ЗҗмӮМҗнӮўӮЙӮЁӮўӮД“№ҺOӮЙ–Ў•ыӮө”ь”ZӮМҗО’JҺҒӮН–Е–SӮөӮҪҒBҚЭӢһӮМҗО’JҺҒӮНҗО’JҢхҗӯӮӘҗО’J—Ҡ’CҒiҚЦ“Ў—ҳҢ«ӮМҺqҒjӮр—{ҺqӮЖӮөӮД–әӮрӣWӮ№ҒAӮ»ӮМҗО’J—Ҡ’CӮН–ҫ’qҢхҸGӮМүЖҗbӮЖӮИӮБӮҪҒBӮИӮЁҒAҢхҗӯӮМӮаӮӨҲкҗlӮМ–әӮН’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮМҗіҺәӮЕӮ ӮйҒB—Ҡ’CӮНҺRҚиӮМҗнӮўҢгӮЙ“yҚІӮЙ“ҰӮкӮДӢ`ҢZ’нӮЕӮ Ӯй’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮЙҸd—pӮіӮкӮҪӮӘҒAҢЛҺҹҗмӮМҗнӮўӮЕҗнҺҖӮөӮДӮўӮйҒB
җО’JҢхҗӯ
җО’JҢхҗӯҒiӮўӮөӮӘӮўӮЭӮВӮЬӮіҒj
җнҚ‘Һһ‘гӮ©ӮзҲА“y“ҚҺRҺһ‘гӮЙӮ©ӮҜӮДӮМ•җҸ«ҒB
•тҢцҸOҒB
ҸoүЖӮөӮДӢу‘RҒiӮӯӮӨӮЛӮсҒjӮЖҚҶӮөҒA
җО’JӢу‘RӮМ–јӮЕӮа’mӮзӮкӮйҒB
Һһ‘г
җнҚ‘Һһ‘г - ҲА“y“ҚҺRҺһ‘г
җ¶’a
җ¶”N•sҸЪ
ҺҖ–v
–v”N•sҸЪ
үь–ј
җО’JҢхҗӯҒЁҗО’JӢу‘R
•К–ј
’КҸМҒF•ә•”‘е•гҒA–@–јҒFӢу‘R
ҠҜҲК
•ә•”‘е•г
–Ӣ•{
Һә’¬–Ӣ•{
ҺеҢN
‘«—ҳӢ`ӢPҒЁ’·Ҹ@үд•”Ңіҗe
ҺҒ‘°
җО’JҺҒ
ҚИ
җіҺәҒF•s–ҫ
ҢpҺәҒFеҗҗмҗeҸҮӮМ–ә
Һq
Ҹ—ҒiҗО’J—Ҡ’CҺәҒj
җО’JҺҒҒi’·Ҹ@үд•”ҢіҗeҺәҒj
—{ҺqҒF—Ҡ’C
—Ә—р
җО’JҺҒӮН”ь”ZҚ‘•ыҢ§ҢSҗО’J‘әҒiҢ»Ҡт•ҢҺsҗО’JҒjӮр–{ҠС’nӮЖӮөҒA“yҠтҺҒӮМҺx—¬ӮЕҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӢӮӮЮҒB
җО’JҺҒӮНӮаӮЖӮаӮЖҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮЙ‘гҒXҺdӮҰӮҪ•тҢцҸOӮМ1ӮВӮЕӮ ӮйӮӘҒAҢхҗӯӮНҺАӮНҺә’¬–Ӣ•{‘ж13‘гҸ«ҢR‘«—ҳӢ`ӢPӮМҸҺҺqӮЕӮ ӮйӮЖӮаӮіӮкҒAҗeҗӯӮр–ЪҺwӮөӮҪ‘«—ҳӢ`ӢPӮМ‘ӨӢЯӮЖӮөӮДҠҲ–фӮөӮҪҒBӮҪӮҫӮөҢхҗӯӮНӢ`ӢPӮЖӮЩӮЪ“Ҝ”N‘гӮ©ӮЮӮөӮл”N’·ӮЖҚlӮҰӮзӮкҒAҺqӮЖӮ·ӮйӮЙӮНҸӯҒX–і—қӮӘӮ ӮйӮМӮЕӮұӮкӮНҢл“`ӮЕӮ ӮлӮӨҒB
ҢхҗӯӮН’jҺqӮЙҢbӮЬӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒA“Ҝ‘°ӮМ“yҠтҺҒҺx—¬ӮМ–ҫ’qҺҒӮМүҸҺТӮЕӮ ӮйҚЦ“Ў—ҳҢ«ӮМ’·’jҒE—Ҡ’CӮр—{ҺkҺqӮЖӮөӮДҢ}ӮҰӮДҒA’·Ҹ—ӮрӣWӮзӮ№ӮҪҒBүiҳ\6”NҒi1563”NҒj ӮЙӮНеҗҗмҗe’·ӮМ’ҮүоӮЕҒAҺҹҸ—Ӯр“yҚІҚ‘ӮМҗнҚ‘‘е–јҒE’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮЙүЕӮӘӮ№ӮҪҒB
үiҳ\8”NҒi1565”NҒjҒAӢ`ӢPӮӘҸјүiӢvҸGҒEҺOҚDҺOҗlҸOӮЙҲГҺEӮіӮкӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒA–әӮМүЕӮ¬җжӮЕӮ Ӯй’·Ҹ@үд•”үЖӮр—ҠӮБӮД“yҚІӮЙ“nӮБӮҪҒBҲИҢгҒA–ә–№ӮЕӮ ӮйҢіҗeӮЙҺdӮҰҒAҺАүЖӮМҚЦ“ЎҺҒӮр—ҠӮБӮД–ҫ’qҢхҸGӮМүЖҗbӮЖӮИӮБӮҪ—Ҡ’CӮрүоӮөӮДҒAҗD“cҗM’·ӮЖӮМҺжҺҹ–рӮр–ұӮЯӮҪҒB
–v”NӮа•s–ҫӮҫӮӘҒAҒwҗО’JүЖ•¶Ҹ‘ҒxӮЙӮ Ӯй“Vҗі12”N(1584”N)•tӮҜӮМҚЧҗмҗM—ЗӮМҸ‘ҸуӮӘӢу‘RҒE—Ҡ’CӮМҳA–јӮМҲ¶–јӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒAӮұӮМҚ ӮЬӮЕӮНҗ¶‘¶ӮөӮДӮўӮҪӮжӮӨӮҫҒB
җнҚ‘Һһ‘гӮ©ӮзҲА“y“ҚҺRҺһ‘гӮЙӮ©ӮҜӮДӮМ•җҸ«ҒB
•тҢцҸOҒB
ҸoүЖӮөӮДӢу‘RҒiӮӯӮӨӮЛӮсҒjӮЖҚҶӮөҒA
җО’JӢу‘RӮМ–јӮЕӮа’mӮзӮкӮйҒB
Һһ‘г
җнҚ‘Һһ‘г - ҲА“y“ҚҺRҺһ‘г
җ¶’a
җ¶”N•sҸЪ
ҺҖ–v
–v”N•sҸЪ
үь–ј
җО’JҢхҗӯҒЁҗО’JӢу‘R
•К–ј
’КҸМҒF•ә•”‘е•гҒA–@–јҒFӢу‘R
ҠҜҲК
•ә•”‘е•г
–Ӣ•{
Һә’¬–Ӣ•{
ҺеҢN
‘«—ҳӢ`ӢPҒЁ’·Ҹ@үд•”Ңіҗe
ҺҒ‘°
җО’JҺҒ
ҚИ
җіҺәҒF•s–ҫ
ҢpҺәҒFеҗҗмҗeҸҮӮМ–ә
Һq
Ҹ—ҒiҗО’J—Ҡ’CҺәҒj
җО’JҺҒҒi’·Ҹ@үд•”ҢіҗeҺәҒj
—{ҺqҒF—Ҡ’C
—Ә—р
җО’JҺҒӮН”ь”ZҚ‘•ыҢ§ҢSҗО’J‘әҒiҢ»Ҡт•ҢҺsҗО’JҒjӮр–{ҠС’nӮЖӮөҒA“yҠтҺҒӮМҺx—¬ӮЕҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӢӮӮЮҒB
җО’JҺҒӮНӮаӮЖӮаӮЖҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮЙ‘гҒXҺdӮҰӮҪ•тҢцҸOӮМ1ӮВӮЕӮ ӮйӮӘҒAҢхҗӯӮНҺАӮНҺә’¬–Ӣ•{‘ж13‘гҸ«ҢR‘«—ҳӢ`ӢPӮМҸҺҺqӮЕӮ ӮйӮЖӮаӮіӮкҒAҗeҗӯӮр–ЪҺwӮөӮҪ‘«—ҳӢ`ӢPӮМ‘ӨӢЯӮЖӮөӮДҠҲ–фӮөӮҪҒBӮҪӮҫӮөҢхҗӯӮНӢ`ӢPӮЖӮЩӮЪ“Ҝ”N‘гӮ©ӮЮӮөӮл”N’·ӮЖҚlӮҰӮзӮкҒAҺqӮЖӮ·ӮйӮЙӮНҸӯҒX–і—қӮӘӮ ӮйӮМӮЕӮұӮкӮНҢл“`ӮЕӮ ӮлӮӨҒB
ҢхҗӯӮН’jҺqӮЙҢbӮЬӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒA“Ҝ‘°ӮМ“yҠтҺҒҺx—¬ӮМ–ҫ’qҺҒӮМүҸҺТӮЕӮ ӮйҚЦ“Ў—ҳҢ«ӮМ’·’jҒE—Ҡ’CӮр—{ҺkҺqӮЖӮөӮДҢ}ӮҰӮДҒA’·Ҹ—ӮрӣWӮзӮ№ӮҪҒBүiҳ\6”NҒi1563”NҒj ӮЙӮНеҗҗмҗe’·ӮМ’ҮүоӮЕҒAҺҹҸ—Ӯр“yҚІҚ‘ӮМҗнҚ‘‘е–јҒE’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮЙүЕӮӘӮ№ӮҪҒB
үiҳ\8”NҒi1565”NҒjҒAӢ`ӢPӮӘҸјүiӢvҸGҒEҺOҚDҺOҗlҸOӮЙҲГҺEӮіӮкӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒA–әӮМүЕӮ¬җжӮЕӮ Ӯй’·Ҹ@үд•”үЖӮр—ҠӮБӮД“yҚІӮЙ“nӮБӮҪҒBҲИҢгҒA–ә–№ӮЕӮ ӮйҢіҗeӮЙҺdӮҰҒAҺАүЖӮМҚЦ“ЎҺҒӮр—ҠӮБӮД–ҫ’qҢхҸGӮМүЖҗbӮЖӮИӮБӮҪ—Ҡ’CӮрүоӮөӮДҒAҗD“cҗM’·ӮЖӮМҺжҺҹ–рӮр–ұӮЯӮҪҒB
–v”NӮа•s–ҫӮҫӮӘҒAҒwҗО’JүЖ•¶Ҹ‘ҒxӮЙӮ Ӯй“Vҗі12”N(1584”N)•tӮҜӮМҚЧҗмҗM—ЗӮМҸ‘ҸуӮӘӢу‘RҒE—Ҡ’CӮМҳA–јӮМҲ¶–јӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒAӮұӮМҚ ӮЬӮЕӮНҗ¶‘¶ӮөӮДӮўӮҪӮжӮӨӮҫҒB
’·Ҹ@үд•”җMҗe
’·Ҹ@үд•”җMҗe(ӮҝӮеӮӨӮ»Ӯ©ӮЧӮМӮФӮҝӮ©)
ҲА“y“ҚҺRҺһ‘гӮМ•җҸ«ҒB
“yҚІҚ‘ӮМҗнҚ‘‘е–јҒE’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮМ’„’jӮЕӮ ӮБӮҪҒB

—ҺҚҮ–FҠфүж
Һһ‘г
ҲА“y“ҚҺRҺһ‘г
җ¶’a
үiҳ\8”NҒi1565”NҒj
ҺҖ–v
“Vҗі14”N12ҢҺ12“ъҒi1587”N1ҢҺ20“ъҒj
үь–ј
җз—YҠЫҒi—c–јҒjҒЁ’·Ҹ@үд•”җMҗe
•К–ј
үј–јҒF–нҺOҳY
үъ–ј
“V•бҺӣҸнҸw‘T’и–е
•жҸҠ
ҚӮ–мҺRҒBҚӮ’mҢ§ҚӮ’mҺsӮМ“V•бҺӣ
ҺеҢN
’·Ҹ@үд•”Ңіҗe
ҺҒ‘°
’·Ҹ@үд•”ҺҒ
•ғ•к
•ғҒF’·Ҹ@үд•”ҢіҗeҒA•кҒFҢіҗe•vҗlҒiҗО’JҢхҗӯӮМ–әҒj
ҢZ’н
’·Ҹ@үд•”җMҗe
ҚҒҗмҗeҳa
’Г–мҗe’ү
’·Ҹ@үд•”җ·җe
үEӢЯ‘е•v
’·Ҹ@үд•”ҚN–L
Ҹ—ҒiҲкҸр“аҗӯҺәҒj
Ҹ—ҒiӢg—ЗҗeҺАҺәҒj
Ҹ—ҒiҚІ’|җe’јҺәҒj
Ҹ—ҒiӢgҸјҸ\Қ¶үq–еҺәҒj
ҚИ
җіҺәҒFҗО’J•vҗl (җО’J—Ҡ’CӮМ–ә)
Һq
Ҹ—Ғi’·Ҹ@үд•”җ·җeҗіҺәҒj
җ¶ҠU
Ҹoҗ¶ӮЖҠҲ–ф
үiҳ\8”NҒi1565”NҒjҒA“yҚІҚ‘ӮМҗнҚ‘‘е–јҒE’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮМ’„’jӮЖӮөӮД’aҗ¶ҒB•кӮНҢіҗeӮМҗіҺәӮЕ‘«—ҳӢ`ӢPӮМүЖҗbҒEҗО’JҢхҗӯӮМ–әҒi–ҫ’qҢхҸGӮМүЖҗbҒEҚЦ“Ў—ҳҺOӮМҲЩ•ғ–…ҒjҒB
—cҸӯҺһӮ©Ӯз‘Ҹ–ҫӮЕӮ ӮБӮҪ[’ҚҺЯ 2]ӮҪӮЯ•ғӮ©Ӯз’һҲӨӮіӮкҒA“Vҗі3”NҒi1575”NҒjӮЙҢіҗeӮӘ’Ҷ“ҮүВ”VҸ•ӮрҺgҺТӮЖӮөӮДҗD“cҗM’·ӮЖӢbӮр’КӮ¶ӮҪӮЖӮ«ҒAҗM’·ӮрүG–XҺqҗeӮЖӮөӮДҗM’·ӮМҒuҗMҒvӮр—^ӮҰӮзӮкҒAҒuҗMҗeҒvӮр–јҸжӮйҒBӮұӮМӮЖӮ«ҒAҗM’·Ӯ©ӮзҚ¶•¶ҺҡӮМ–Б“ҒӮЖ–ј”nӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҒBҢіҗeӮМҺvҳfӮЖҗM’·ӮМҗн—ӘӮӘҲк’vӮөӮҪӮаӮМӮЕҒAҢіҗeӮМҠOҢрӮМҚIӮЭӮіӮЖҒA–ҫ’qҢхҸGӮМ”ӯҗM—НӮӘӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮйҗ¬үКӮЕӮ ӮйҒBӮИӮЁҒA2013”NӮЙ”ӯҢ©ӮіӮкӮҪҒwҗО’JүЖ•¶Ҹ‘ҒxҒi—СҢҙ”ьҸpҠЩҸҠ‘ ҒjӮЙҸҠҺыӮіӮкӮҪҢіҗeӮ©ӮзҗО’J—Ҡ’CҒiҗMҗeӮМҗ¶•кӮМӢ`ҢZӮЙӮ ӮҪӮйҒjӮЙҸ[ӮДӮзӮкӮҪҸ‘ҸуӮМ’ҶӮЕӮұӮМҗMҗeӮӘҲкҺҡӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЫӮЙҗM’·ӮНҚr–Ш‘әҸdӮрҚUӮЯӮДӮўӮҪӮЖҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮЁӮиҒAҚr–Ш‘әҸdӮМ”Ҫ—җӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮҪ“Vҗі6”NҒi1578”NҒjӮЙ”д’иӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒB
Ӯ»ӮМҢгӮН•ғӮЙҸ]ӮБӮДҠe’nӮр“]җнӮөӮҪҒBҗM’·–vҢгӮМ“Vҗі13”NҒi1585”NҒjҒA’·Ҹ@үд•”ҺҒӮН–LҗbҸGӢgӮМҺlҚ‘ҚUӮЯӮЙҚ~•ҡӮөҒA–LҗbҗӯҢ ”zүәӮЕ“yҚІҲкҚ‘Ӯр—МӮ·Ӯй‘е–јӮЖӮИӮйҒB
ҢЛҺҹҗмӮМҗнӮўӮЖҚЕҠъ
“Vҗі14”N4ҢҺ5“ъҒA–LҢгӮМ‘е—FҸ@—ЩӮН–LҗbҸGӢgӮЙ‘еҚвӮЕ–КүпӮөҒA“Ү’ГӢ`ӢvӮӘ–LҢгӮЙҗi“ьӮөӮДӮ«ӮҪӮұӮЖӮр‘iӮҰӢ~үҮӮрӢҒӮЯӮҪ[4]ҒBҸGӢgӮНӮұӮкӮр—№ҸіӮөҒAҚ•“cҚFҚӮӮЙ–С—ҳӮМ•әӮр‘ҚҠҮӮіӮ№ӮДҗж”ӯӮіӮ№ҒAӮіӮзӮЙҺ]ҠтӮМҗеҗОҸGӢvӮрҺеҸ«ӮЙӮөҒA’·Ҹ@үд•”ҢіҗeҒEҗMҗeӮрүБӮҰ–LҢгӮЙҸoҗwӮр–ҪӮ¶ӮҪҒB
“Ү’ГүЖӢvӮӘ–LҢгӮЙҗN“ьӮөҒA‘е—FҺҒӮМ’Яғ–ҸйӮрҚUҢӮӮөӮҪҒB12ҢҺ11“ъҒAҗеҗОҸGӢvӮЖ’·Ҹ@үд•”җMҗeӮНҒAӮұӮкӮрӢ~үҮӮөӮжӮӨӮЖҢЛҺҹҗмӮЙҗwӮрӮөӮўӮҪҒBҗн—ӘүпӢcӮЙӮЁӮўӮДҗеҗОҸGӢvӮНҗмӮр“nӮиҚUҢӮӮ·ӮйӮЧӮ«ӮЖҺе’ЈӮөӮҪҒiҒw“yҚІ•ЁҢкҒxҒjҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮД’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮНүБҗЁӮр‘ТӮҝӮ»ӮкӮ©ӮзҚҮҗнӮЙӢyӮФӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйӮЖӮөӮДҒAҗеҗОӮМҚмҗнӮЙ”Ҫ‘ОӮрӮөӮҪӮӘҒiҒwҢіҗeӢLҒxҒw“yҚІ•ЁҢкҒxҒj[6]ҒAҗеҗОӮН•·Ӯ«“ьӮкӮёҒAҸ\үН‘¶•ЫӮаҗеҗОӮЙ“Ҝ’ІӮөӮҪҒBӮұӮМӮҪӮЯҗмӮр“nӮБӮДҸoҗwӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиҗ퓬ӮН12ҢҺ12“ъӮМ—[•ыӮ©Ӯз13“ъӮЙӮ©ӮҜӮДҚsӮнӮкӮҪ[7]ҒBҗMҗeӮНҗеҗОӮМҢҲ’иӮр”б”»ӮөҒAүЖҗbӮЙ‘ОӮөӮДҒuҗMҗeҒA–ҫ“ъӮН“ўҺҖӮЖ’иӮЯӮҪӮиҒBҚЎ“ъӮМҢR•]’иӮЕҢRҠДҒEҗеҗОҸGӢvӮМҲꑶӮЙӮжӮБӮДҒA–ҫ“ъҒAҗмӮрүzӮҰӮДҗнӮӨӮЖҢҲӮЬӮиӮҪӮиҒB’nҢ`ӮМ—ҳӮрҚlӮҰӮйӮЙҒAӮұӮМ•ыӮжӮиҗмӮр“nӮйҺ–ҒAг©ӮЙ—ХӮЮҢПӮМӮІӮЖӮөҒB‘SӮӯӮМҺ©–ЕӮЖ“ҜӮ¶ҒvӮЖ“fӮ«ҺМӮДӮҪӮЖӮўӮӨҒiҒw“yҚІ•ЁҢкҒxҒjҒB
ҚҮҗн“–“ъҒAҗжҗwӮМҗеҗОӮМ•”‘аӮӘҗ^ӮБҗжӮЙ”s‘–ӮөӮҪӮҪӮЯҒA’·Ҹ@үд•”ӮМ3җзӮМ•әӮӘҗV”[‘е‘V—әӮМ5җзӮМ•әӮЖҗ퓬Ҹу‘ФӮЙӮИӮБӮҪӮӘҒAҢіҗeӮЖҗMҗeӮН—җҗнӮМ’ҶӮЙ—ЈӮкӮОӮИӮкӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҢіҗeӮН—ҺӮҝӮМӮСӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪӮӘҒAҗMҗeӮН’Ҷ’Г—ҜҗмҢҙӮЙ—ҜӮЬӮБӮҪӮаӮМӮМҒA—й–Ш‘е‘VӮЙ“ўӮҪӮкӮҪ[8]ҒBӢқ”N22ҒBҗMҗeӮНҢK–ј‘ҫҳNҚ¶үq–еӮЙ‘ЮӢpӮр‘ЈӮіӮкӮҪӮӘҲшӮ©ӮёӨҺlҺЪҺOҗЎӮМ‘е’·“ҒӮрҗUӮйӮў8җlӮрҺaӮи•ҡӮ№ӮҪҒB“GӮӘӢЯӮӯӮЙҠсӮБӮДӮӯӮйӮЖ’·“ҒӮрҺМӮДҒAҚЎ“xӮН‘ҫ“ҒӮЕ6җlӮрҺaӮи•ҡӮ№ӮҪӮЖӮіӮкӮйҒiҒwҢіҗeӢLҒxҒj[9]ҒBҗMҗeӮЙҸ]ӮБӮДӮўӮҪ700җlӮа“ўҺҖӮЙӮөҒAҸ\үН‘¶•ЫӮаҗнҺҖӮөҒA’Яғ–ҸйӮа—ҺҸйӮөӮҪ[8]ҒB
җнҢгҒAҢіҗeӮНҗMҗeӮМҗнҺҖӮр”ЯӮөӮЭҒA’J’үҗҹӮрҺgҺТӮЖӮөӮД“Ү’ГӮМҗwӮЙҢӯӮнӮөҒAҗMҗeӮМҲвҠ[ӮрӮұӮўҺуӮҜӮДҒAҚӮ–мҺRӮМүңӮМү@ӮЙ”[ӮЯӮҪӮӘҒAӮМӮҝӮЙ•ӘҚңӮөӮДҚӮ’mҺs’·•lӮМ“V•бҺӣӮЙ–„‘’ӮөӮҪ[10]ҒB
җl•ЁҒEҲнҳb
җMҗeӮН•¶•җӮЙ—DӮк—зӢVҗіӮөӮӯҒA•ғҒEҢіҗeӮНҗMҗeӮМҸ«—ҲӮр‘еӮўӮЙҸъ–]ӮөҒAӮЬӮҪүЖҗbӮв“yҚІҚ‘ӮМ–ҜӮ©ӮзӮМҗl–]ӮаҢъӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮнӮкӮй[11]ҒBҢіҗeӮНҗMҗeӮМӮҪӮЯӮЙҲк—¬ӮМҠw–вҒE•җҢ|ӮМҺtӮрӢE“аӮИӮЗү“Қ‘Ӯ©ӮзҸөӮўӮДүpҚЛӢіҲзӮрҺ{ӮөҒA’·Ҹ@үд•”үЖӮМӮіӮзӮИӮй”eӢЖӮр‘хӮөӮДӮўӮҪҒB—§”hӮИҺб•җҺТӮЙҗ¬’·ӮөӮҪҗMҗeӮрҢіҗeӮНҒAҒuһж噲Ғi‘OҠҝӮМҸү‘гҚc’йҒE—«–MӮМ• җSӮМҚӢҢҶҒjӮЙӮа—тӮйӮЬӮўҒvӮЖҺ©–қӮөҠъ‘ТӮрҠсӮ№ӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒBҗD“cҗM’·ӮНҗMҗeӮМү\Ӯр•·ӮўӮҪӮЖӮ«ҒAҺ©ӮзӮМ—{ҺqӮЙҢ}ӮҰӮҪӮўӮЖҸqӮЧӮҪӮЖӮўӮӨҲнҳbӮаӮ ӮйҒB
җg’·ӮНҒu”wӮМҚӮӮіҳZҺЪҲкҗЎҒi–с184cmҒjҒvҒA—e–eӮНҒuҗF”’ӮӯҸ_ҳaӮЙӮөӮДҒvўҺҢӮ·ӮӯӮИӮӯ—зӢVӮ ӮиӮДҢөӮИӮзӮёЈӮЖӢLӮіӮкҒA’m—EҢ“”хӮМ•җҸ«ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮнӮкӮйҒiҒw“yҚІ•ЁҢкҒxҒj[10]ҒB‘–Ӯи’өӮСӮЕ2ҠФҒi–с4mҒjӮр”тӮСүzӮҰҒA”тӮСӮИӮӘӮз“ҒӮр”ІӮӯӮұӮЖӮаӮЕӮ«ӮҪӮЖӮўӮӨ[12]ҒBҒwғtғҚғCғX“ъ–{ҺjҒxӮЙӮжӮйӮЖҒAғLғҠғXғgӢі“ьҗMӮрҚlӮҰӮДӮўӮҪӮЖӮіӮкӮйЎ
ҢіҗeӮМҗMҗeӮЦӮМҠъ‘ТӮӘ‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪӮҪӮЯӨҗнҺҖӮөӮҪӮұӮЖӮМ‘ЕҢӮӮа‘еӮ«ӮӯӨүӘ–LӮЙӢAӮБӮҪҢіҗeӮМҗ¶ҠҲӮНӨӮұӮкҲИҢгҲк•ПӮөӮҪӮЖӮіӮкӮй[13]ҒBҗMҗeӮМ‘ҒӮ·Ӯ¬ӮйҺҖӮНҒAҢгҢpҺТӮЖӮөӮДҲзӮДҸгӮ°ӮДӮўӮҪҢіҗeӮЙӮЖӮБӮД”Я’QӮӘӢӯӮӯҒA•ПӮнӮиүКӮДӮҪҺpӮЕ•ғӮМҢіӮЦӢAӮБӮДӮ«ӮҪҗMҗeӮр’јҺӢҸo—ҲӮёҒAӢғӮ«•цӮкӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮЬӮҪҗMҗeӮҫӮҜӮЕӮИӮӯ’·Ҹ@үд•”үЖӮр”w•үӮБӮД—§ӮВҺбӮўҗlҚЮӮМ‘ҪӮӯӮӘҗнҺҖӮөӮҪҺ–ӮаӮ ӮиҒAӮұӮкӮжӮиҢгҒA’·Ҹ@үд•”ҺҒӮНҗнҺҖӮөӮҪүЖҗb’cӮМҚДҢҡӮЙӮЁӮҜӮйүЖҗbҠФӮМжyӮўӮвҢгҢpҺТ‘ӣ“®ӮЙӮжӮБӮДҸҷҒXӮЙҗҠҺгӮөӮДӮўӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBҢіҗeӮМҗMҗeӮЙ‘ОӮ·ӮйҲӨҸоӮН•АҒXӮИӮзӮКӮаӮМӮӘӮ ӮиҒAҗMҗeӮЙӮ ӮБӮҪ—BҲкӮМҸ—ҺҷҒiҗ·җeӮЙӮЖӮБӮД–ГӮЙӮ ӮҪӮйҒjӮрҒAҗVӮҪӮЙҢгҢpҺТӮЖӮөӮҪҗ·җeӮМҗіҺәӮЖӮөӮДӣWӮнӮ№ӮйӮұӮЖӮЕҒAҗMҗeӮМҢҢ“қӮр’·Ҹ@үд•”ҺҒ“–ҺеӮЙ‘ұӮ©Ӯ№ӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮЩӮЗӮЕӮ ӮйҒB
ҲА“y“ҚҺRҺһ‘гӮМ•җҸ«ҒB
“yҚІҚ‘ӮМҗнҚ‘‘е–јҒE’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮМ’„’jӮЕӮ ӮБӮҪҒB

—ҺҚҮ–FҠфүж
Һһ‘г
ҲА“y“ҚҺRҺһ‘г
җ¶’a
үiҳ\8”NҒi1565”NҒj
ҺҖ–v
“Vҗі14”N12ҢҺ12“ъҒi1587”N1ҢҺ20“ъҒj
үь–ј
җз—YҠЫҒi—c–јҒjҒЁ’·Ҹ@үд•”җMҗe
•К–ј
үј–јҒF–нҺOҳY
үъ–ј
“V•бҺӣҸнҸw‘T’и–е
•жҸҠ
ҚӮ–мҺRҒBҚӮ’mҢ§ҚӮ’mҺsӮМ“V•бҺӣ
ҺеҢN
’·Ҹ@үд•”Ңіҗe
ҺҒ‘°
’·Ҹ@үд•”ҺҒ
•ғ•к
•ғҒF’·Ҹ@үд•”ҢіҗeҒA•кҒFҢіҗe•vҗlҒiҗО’JҢхҗӯӮМ–әҒj
ҢZ’н
’·Ҹ@үд•”җMҗe
ҚҒҗмҗeҳa
’Г–мҗe’ү
’·Ҹ@үд•”җ·җe
үEӢЯ‘е•v
’·Ҹ@үд•”ҚN–L
Ҹ—ҒiҲкҸр“аҗӯҺәҒj
Ҹ—ҒiӢg—ЗҗeҺАҺәҒj
Ҹ—ҒiҚІ’|җe’јҺәҒj
Ҹ—ҒiӢgҸјҸ\Қ¶үq–еҺәҒj
ҚИ
җіҺәҒFҗО’J•vҗl (җО’J—Ҡ’CӮМ–ә)
Һq
Ҹ—Ғi’·Ҹ@үд•”җ·җeҗіҺәҒj
җ¶ҠU
Ҹoҗ¶ӮЖҠҲ–ф
үiҳ\8”NҒi1565”NҒjҒA“yҚІҚ‘ӮМҗнҚ‘‘е–јҒE’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮМ’„’jӮЖӮөӮД’aҗ¶ҒB•кӮНҢіҗeӮМҗіҺәӮЕ‘«—ҳӢ`ӢPӮМүЖҗbҒEҗО’JҢхҗӯӮМ–әҒi–ҫ’qҢхҸGӮМүЖҗbҒEҚЦ“Ў—ҳҺOӮМҲЩ•ғ–…ҒjҒB
—cҸӯҺһӮ©Ӯз‘Ҹ–ҫӮЕӮ ӮБӮҪ[’ҚҺЯ 2]ӮҪӮЯ•ғӮ©Ӯз’һҲӨӮіӮкҒA“Vҗі3”NҒi1575”NҒjӮЙҢіҗeӮӘ’Ҷ“ҮүВ”VҸ•ӮрҺgҺТӮЖӮөӮДҗD“cҗM’·ӮЖӢbӮр’КӮ¶ӮҪӮЖӮ«ҒAҗM’·ӮрүG–XҺqҗeӮЖӮөӮДҗM’·ӮМҒuҗMҒvӮр—^ӮҰӮзӮкҒAҒuҗMҗeҒvӮр–јҸжӮйҒBӮұӮМӮЖӮ«ҒAҗM’·Ӯ©ӮзҚ¶•¶ҺҡӮМ–Б“ҒӮЖ–ј”nӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҒBҢіҗeӮМҺvҳfӮЖҗM’·ӮМҗн—ӘӮӘҲк’vӮөӮҪӮаӮМӮЕҒAҢіҗeӮМҠOҢрӮМҚIӮЭӮіӮЖҒA–ҫ’qҢхҸGӮМ”ӯҗM—НӮӘӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮйҗ¬үКӮЕӮ ӮйҒBӮИӮЁҒA2013”NӮЙ”ӯҢ©ӮіӮкӮҪҒwҗО’JүЖ•¶Ҹ‘ҒxҒi—СҢҙ”ьҸpҠЩҸҠ‘ ҒjӮЙҸҠҺыӮіӮкӮҪҢіҗeӮ©ӮзҗО’J—Ҡ’CҒiҗMҗeӮМҗ¶•кӮМӢ`ҢZӮЙӮ ӮҪӮйҒjӮЙҸ[ӮДӮзӮкӮҪҸ‘ҸуӮМ’ҶӮЕӮұӮМҗMҗeӮӘҲкҺҡӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЫӮЙҗM’·ӮНҚr–Ш‘әҸdӮрҚUӮЯӮДӮўӮҪӮЖҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮЁӮиҒAҚr–Ш‘әҸdӮМ”Ҫ—җӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮҪ“Vҗі6”NҒi1578”NҒjӮЙ”д’иӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒB
Ӯ»ӮМҢгӮН•ғӮЙҸ]ӮБӮДҠe’nӮр“]җнӮөӮҪҒBҗM’·–vҢгӮМ“Vҗі13”NҒi1585”NҒjҒA’·Ҹ@үд•”ҺҒӮН–LҗbҸGӢgӮМҺlҚ‘ҚUӮЯӮЙҚ~•ҡӮөҒA–LҗbҗӯҢ ”zүәӮЕ“yҚІҲкҚ‘Ӯр—МӮ·Ӯй‘е–јӮЖӮИӮйҒB
ҢЛҺҹҗмӮМҗнӮўӮЖҚЕҠъ
“Vҗі14”N4ҢҺ5“ъҒA–LҢгӮМ‘е—FҸ@—ЩӮН–LҗbҸGӢgӮЙ‘еҚвӮЕ–КүпӮөҒA“Ү’ГӢ`ӢvӮӘ–LҢгӮЙҗi“ьӮөӮДӮ«ӮҪӮұӮЖӮр‘iӮҰӢ~үҮӮрӢҒӮЯӮҪ[4]ҒBҸGӢgӮНӮұӮкӮр—№ҸіӮөҒAҚ•“cҚFҚӮӮЙ–С—ҳӮМ•әӮр‘ҚҠҮӮіӮ№ӮДҗж”ӯӮіӮ№ҒAӮіӮзӮЙҺ]ҠтӮМҗеҗОҸGӢvӮрҺеҸ«ӮЙӮөҒA’·Ҹ@үд•”ҢіҗeҒEҗMҗeӮрүБӮҰ–LҢгӮЙҸoҗwӮр–ҪӮ¶ӮҪҒB
“Ү’ГүЖӢvӮӘ–LҢгӮЙҗN“ьӮөҒA‘е—FҺҒӮМ’Яғ–ҸйӮрҚUҢӮӮөӮҪҒB12ҢҺ11“ъҒAҗеҗОҸGӢvӮЖ’·Ҹ@үд•”җMҗeӮНҒAӮұӮкӮрӢ~үҮӮөӮжӮӨӮЖҢЛҺҹҗмӮЙҗwӮрӮөӮўӮҪҒBҗн—ӘүпӢcӮЙӮЁӮўӮДҗеҗОҸGӢvӮНҗмӮр“nӮиҚUҢӮӮ·ӮйӮЧӮ«ӮЖҺе’ЈӮөӮҪҒiҒw“yҚІ•ЁҢкҒxҒjҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮД’·Ҹ@үд•”ҢіҗeӮНүБҗЁӮр‘ТӮҝӮ»ӮкӮ©ӮзҚҮҗнӮЙӢyӮФӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйӮЖӮөӮДҒAҗеҗОӮМҚмҗнӮЙ”Ҫ‘ОӮрӮөӮҪӮӘҒiҒwҢіҗeӢLҒxҒw“yҚІ•ЁҢкҒxҒj[6]ҒAҗеҗОӮН•·Ӯ«“ьӮкӮёҒAҸ\үН‘¶•ЫӮаҗеҗОӮЙ“Ҝ’ІӮөӮҪҒBӮұӮМӮҪӮЯҗмӮр“nӮБӮДҸoҗwӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиҗ퓬ӮН12ҢҺ12“ъӮМ—[•ыӮ©Ӯз13“ъӮЙӮ©ӮҜӮДҚsӮнӮкӮҪ[7]ҒBҗMҗeӮНҗеҗОӮМҢҲ’иӮр”б”»ӮөҒAүЖҗbӮЙ‘ОӮөӮДҒuҗMҗeҒA–ҫ“ъӮН“ўҺҖӮЖ’иӮЯӮҪӮиҒBҚЎ“ъӮМҢR•]’иӮЕҢRҠДҒEҗеҗОҸGӢvӮМҲꑶӮЙӮжӮБӮДҒA–ҫ“ъҒAҗмӮрүzӮҰӮДҗнӮӨӮЖҢҲӮЬӮиӮҪӮиҒB’nҢ`ӮМ—ҳӮрҚlӮҰӮйӮЙҒAӮұӮМ•ыӮжӮиҗмӮр“nӮйҺ–ҒAг©ӮЙ—ХӮЮҢПӮМӮІӮЖӮөҒB‘SӮӯӮМҺ©–ЕӮЖ“ҜӮ¶ҒvӮЖ“fӮ«ҺМӮДӮҪӮЖӮўӮӨҒiҒw“yҚІ•ЁҢкҒxҒjҒB
ҚҮҗн“–“ъҒAҗжҗwӮМҗеҗОӮМ•”‘аӮӘҗ^ӮБҗжӮЙ”s‘–ӮөӮҪӮҪӮЯҒA’·Ҹ@үд•”ӮМ3җзӮМ•әӮӘҗV”[‘е‘V—әӮМ5җзӮМ•әӮЖҗ퓬Ҹу‘ФӮЙӮИӮБӮҪӮӘҒAҢіҗeӮЖҗMҗeӮН—җҗнӮМ’ҶӮЙ—ЈӮкӮОӮИӮкӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҢіҗeӮН—ҺӮҝӮМӮСӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪӮӘҒAҗMҗeӮН’Ҷ’Г—ҜҗмҢҙӮЙ—ҜӮЬӮБӮҪӮаӮМӮМҒA—й–Ш‘е‘VӮЙ“ўӮҪӮкӮҪ[8]ҒBӢқ”N22ҒBҗMҗeӮНҢK–ј‘ҫҳNҚ¶үq–еӮЙ‘ЮӢpӮр‘ЈӮіӮкӮҪӮӘҲшӮ©ӮёӨҺlҺЪҺOҗЎӮМ‘е’·“ҒӮрҗUӮйӮў8җlӮрҺaӮи•ҡӮ№ӮҪҒB“GӮӘӢЯӮӯӮЙҠсӮБӮДӮӯӮйӮЖ’·“ҒӮрҺМӮДҒAҚЎ“xӮН‘ҫ“ҒӮЕ6җlӮрҺaӮи•ҡӮ№ӮҪӮЖӮіӮкӮйҒiҒwҢіҗeӢLҒxҒj[9]ҒBҗMҗeӮЙҸ]ӮБӮДӮўӮҪ700җlӮа“ўҺҖӮЙӮөҒAҸ\үН‘¶•ЫӮаҗнҺҖӮөҒA’Яғ–ҸйӮа—ҺҸйӮөӮҪ[8]ҒB
җнҢгҒAҢіҗeӮНҗMҗeӮМҗнҺҖӮр”ЯӮөӮЭҒA’J’үҗҹӮрҺgҺТӮЖӮөӮД“Ү’ГӮМҗwӮЙҢӯӮнӮөҒAҗMҗeӮМҲвҠ[ӮрӮұӮўҺуӮҜӮДҒAҚӮ–мҺRӮМүңӮМү@ӮЙ”[ӮЯӮҪӮӘҒAӮМӮҝӮЙ•ӘҚңӮөӮДҚӮ’mҺs’·•lӮМ“V•бҺӣӮЙ–„‘’ӮөӮҪ[10]ҒB
җl•ЁҒEҲнҳb
җMҗeӮН•¶•җӮЙ—DӮк—зӢVҗіӮөӮӯҒA•ғҒEҢіҗeӮНҗMҗeӮМҸ«—ҲӮр‘еӮўӮЙҸъ–]ӮөҒAӮЬӮҪүЖҗbӮв“yҚІҚ‘ӮМ–ҜӮ©ӮзӮМҗl–]ӮаҢъӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮнӮкӮй[11]ҒBҢіҗeӮНҗMҗeӮМӮҪӮЯӮЙҲк—¬ӮМҠw–вҒE•җҢ|ӮМҺtӮрӢE“аӮИӮЗү“Қ‘Ӯ©ӮзҸөӮўӮДүpҚЛӢіҲзӮрҺ{ӮөҒA’·Ҹ@үд•”үЖӮМӮіӮзӮИӮй”eӢЖӮр‘хӮөӮДӮўӮҪҒB—§”hӮИҺб•җҺТӮЙҗ¬’·ӮөӮҪҗMҗeӮрҢіҗeӮНҒAҒuһж噲Ғi‘OҠҝӮМҸү‘гҚc’йҒE—«–MӮМ• җSӮМҚӢҢҶҒjӮЙӮа—тӮйӮЬӮўҒvӮЖҺ©–қӮөҠъ‘ТӮрҠсӮ№ӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒBҗD“cҗM’·ӮНҗMҗeӮМү\Ӯр•·ӮўӮҪӮЖӮ«ҒAҺ©ӮзӮМ—{ҺqӮЙҢ}ӮҰӮҪӮўӮЖҸqӮЧӮҪӮЖӮўӮӨҲнҳbӮаӮ ӮйҒB
җg’·ӮНҒu”wӮМҚӮӮіҳZҺЪҲкҗЎҒi–с184cmҒjҒvҒA—e–eӮНҒuҗF”’ӮӯҸ_ҳaӮЙӮөӮДҒvўҺҢӮ·ӮӯӮИӮӯ—зӢVӮ ӮиӮДҢөӮИӮзӮёЈӮЖӢLӮіӮкҒA’m—EҢ“”хӮМ•җҸ«ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮнӮкӮйҒiҒw“yҚІ•ЁҢкҒxҒj[10]ҒB‘–Ӯи’өӮСӮЕ2ҠФҒi–с4mҒjӮр”тӮСүzӮҰҒA”тӮСӮИӮӘӮз“ҒӮр”ІӮӯӮұӮЖӮаӮЕӮ«ӮҪӮЖӮўӮӨ[12]ҒBҒwғtғҚғCғX“ъ–{ҺjҒxӮЙӮжӮйӮЖҒAғLғҠғXғgӢі“ьҗMӮрҚlӮҰӮДӮўӮҪӮЖӮіӮкӮйЎ
ҢіҗeӮМҗMҗeӮЦӮМҠъ‘ТӮӘ‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪӮҪӮЯӨҗнҺҖӮөӮҪӮұӮЖӮМ‘ЕҢӮӮа‘еӮ«ӮӯӨүӘ–LӮЙӢAӮБӮҪҢіҗeӮМҗ¶ҠҲӮНӨӮұӮкҲИҢгҲк•ПӮөӮҪӮЖӮіӮкӮй[13]ҒBҗMҗeӮМ‘ҒӮ·Ӯ¬ӮйҺҖӮНҒAҢгҢpҺТӮЖӮөӮДҲзӮДҸгӮ°ӮДӮўӮҪҢіҗeӮЙӮЖӮБӮД”Я’QӮӘӢӯӮӯҒA•ПӮнӮиүКӮДӮҪҺpӮЕ•ғӮМҢіӮЦӢAӮБӮДӮ«ӮҪҗMҗeӮр’јҺӢҸo—ҲӮёҒAӢғӮ«•цӮкӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮЬӮҪҗMҗeӮҫӮҜӮЕӮИӮӯ’·Ҹ@үд•”үЖӮр”w•үӮБӮД—§ӮВҺбӮўҗlҚЮӮМ‘ҪӮӯӮӘҗнҺҖӮөӮҪҺ–ӮаӮ ӮиҒAӮұӮкӮжӮиҢгҒA’·Ҹ@үд•”ҺҒӮНҗнҺҖӮөӮҪүЖҗb’cӮМҚДҢҡӮЙӮЁӮҜӮйүЖҗbҠФӮМжyӮўӮвҢгҢpҺТ‘ӣ“®ӮЙӮжӮБӮДҸҷҒXӮЙҗҠҺгӮөӮДӮўӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBҢіҗeӮМҗMҗeӮЙ‘ОӮ·ӮйҲӨҸоӮН•АҒXӮИӮзӮКӮаӮМӮӘӮ ӮиҒAҗMҗeӮЙӮ ӮБӮҪ—BҲкӮМҸ—ҺҷҒiҗ·җeӮЙӮЖӮБӮД–ГӮЙӮ ӮҪӮйҒjӮрҒAҗVӮҪӮЙҢгҢpҺТӮЖӮөӮҪҗ·җeӮМҗіҺәӮЖӮөӮДӣWӮнӮ№ӮйӮұӮЖӮЕҒAҗMҗeӮМҢҢ“қӮр’·Ҹ@үд•”ҺҒ“–ҺеӮЙ‘ұӮ©Ӯ№ӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮЩӮЗӮЕӮ ӮйҒB