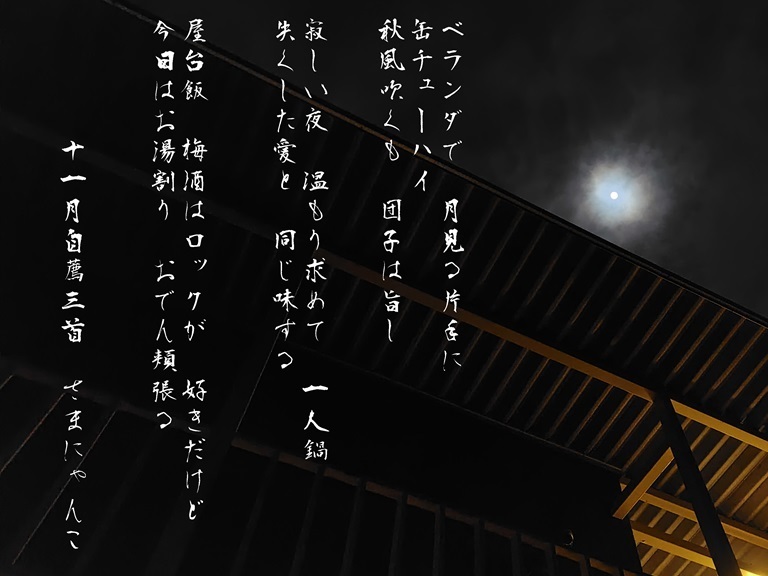新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2022年10月09日
君は過去形、僕は進行形
pixiv別名義より。
2017年9月9日00:15投稿。
※現在pixivでも掲載中です、追々pixivでは削除する予定です
ぼたぼたと雫が落ちる。
雨がアスファルトを濡らして独特の匂いがふんわりと世界を包む。
僕はナイフを自分の腹に刺しっ放しで、雨に濡れながら歩いていた。
抜いたら出てくるんだろうな。
お気に入りのコートだったのに。
黒のトレンチは、赤黒い液体で染みになっていた。
口から血が出てこないから、大したところに刺さったわけじゃないのだろう。
僕は部屋に帰って風呂場へと向かう。
止血用のタオルを手に、刺さりっ放しのナイフの引き抜くと、一気に血が噴き出して、少しふらついた。
お気に入りのコートを脱いで、シャツの上から傷口にタオルを当てる。
ぼーっとする意識を何となく保ちながら、僕は血液が止まるのを待った。
大したところに刺さっていないからだろう、暫くして血が止まったようだった。
引き抜いた時に血が噴き出しはしたが、少し噴き出した程度で止まったようだった。よかったよかった。
本当に、恐ろしいことがあるもんだ。
僕はタオルを当てたまま、先程を思い出す。
どうして君が僕を棄てたくせに、君に刺されなきゃいけないんだ。全く、酷い話もあったもんだ。
僕は血が止まった腹部の傷に、そっと指を突っ込んで見る。
僕の身体の中はどくどくと熱くて、まるでいつかの君の中みたいだ。
そう思うと、自然、僕は僕を抑えられなくなる。
君はもう、同じアパートにはいないのにね。
おしまい


2017年9月9日00:15投稿。
※現在pixivでも掲載中です、追々pixivでは削除する予定です
ぼたぼたと雫が落ちる。
雨がアスファルトを濡らして独特の匂いがふんわりと世界を包む。
僕はナイフを自分の腹に刺しっ放しで、雨に濡れながら歩いていた。
抜いたら出てくるんだろうな。
お気に入りのコートだったのに。
黒のトレンチは、赤黒い液体で染みになっていた。
口から血が出てこないから、大したところに刺さったわけじゃないのだろう。
僕は部屋に帰って風呂場へと向かう。
止血用のタオルを手に、刺さりっ放しのナイフの引き抜くと、一気に血が噴き出して、少しふらついた。
お気に入りのコートを脱いで、シャツの上から傷口にタオルを当てる。
ぼーっとする意識を何となく保ちながら、僕は血液が止まるのを待った。
大したところに刺さっていないからだろう、暫くして血が止まったようだった。
引き抜いた時に血が噴き出しはしたが、少し噴き出した程度で止まったようだった。よかったよかった。
本当に、恐ろしいことがあるもんだ。
僕はタオルを当てたまま、先程を思い出す。
どうして君が僕を棄てたくせに、君に刺されなきゃいけないんだ。全く、酷い話もあったもんだ。
僕は血が止まった腹部の傷に、そっと指を突っ込んで見る。
僕の身体の中はどくどくと熱くて、まるでいつかの君の中みたいだ。
そう思うと、自然、僕は僕を抑えられなくなる。
君はもう、同じアパートにはいないのにね。
おしまい
タグ:2017
僕は僕を忘れてしまった
pixiv別名義より。
2017年8月22日05:50投稿。
※現在pixivでも掲載中です、追々pixivでは削除する予定です
僕は壊れてしまったから
君の手で棄ててほしかったんだ
自分が壊れたことも解らなくて
蔑むような瞳が怖くて
全ての声が脳髄を蝕んで
もう
誰も彼も蔑ろだ
それなのに、
どうして心が焼き切れても
壊れていくばかりで
完全に止まってしまえないんだろう


君に恋をしたのは一体誰だったんだろうね。そんなお話。
2017年8月22日05:50投稿。
※現在pixivでも掲載中です、追々pixivでは削除する予定です
僕は壊れてしまったから
君の手で棄ててほしかったんだ
自分が壊れたことも解らなくて
蔑むような瞳が怖くて
全ての声が脳髄を蝕んで
もう
誰も彼も蔑ろだ
それなのに、
どうして心が焼き切れても
壊れていくばかりで
完全に止まってしまえないんだろう
君に恋をしたのは一体誰だったんだろうね。そんなお話。
タグ:2017
2020年05月10日
「古城を望む」
「無意味な言葉が僕の翼になる」より。
2015年04月13日投稿。
中途半端なところで切れていたので多少加筆しました、多少。
言葉の繰り返しの後、ぶっつり切れていたので。
文体、昔から変わらないなぁ、と。
これは京阪乗りながら久しぶりに創作したいなとか思いながら、今度こそ投稿するんだって書いたやつです。
それがここまで書いて放置だったので、供養供養。
いつか書き切ってみたいです。


俺は古城を望む街のスラムで生まれた。父の存在は知らない。大勢いた母の金ヅルの一人だろうと踏んでいる。
母の口癖は、
「いつかあの城から王子様が迎えにきてくれる」
だから貴方も、今に幸せな夢を見られるわ。
いつもいつも、よくもまぁそんな馬鹿げたことが言えるもんだ、と、心の中で嗤っていた。
そんな夢物語のいつかなんかより、俺にとって大事なのは、今、この飢えを忘れられて明日も生きていられる、ということだけだった。そう、俺は死んでしまいたくなかった。死んでしまいたくなかったのだ。
目の前で虫にまみれ昨日まで共に話していた人間だったもの、紅い水溜まりの中でもう誰なのかも判らなくなったもの、そんなものには決して、なりたくなかった。
だから、生きるためには、割と何でもやった。
スリは路地の向こうのあんちゃんに教わった。
闇市のじっちゃんに気に入られてナイフを握ったのは六つの誕生日のことだった。
小さな子供が好きだなんて馬鹿な大金持ちの遊びに身体も貸してやったし、それで金と旨いもんが手に入るなら、別にそれでよかった。
もし何かヘマをして命の危険を感じた時には、俺は空から逃げた。闇夜と一緒になって、置き去りにした馬鹿どもを嘲りながら罵りながら、母の待つスラムに逃げた。
あまりに怖くて帰るなり母の腕の中で泣いたこともあった。
母がいない時は、あんちゃんやじっちゃんの布団の中で一緒に眠った。あんちゃんは何にも言わずに横にいてくれたし、じっちゃんは笑って抱き締めてくれた。
きっとそれは、幸せなことだったんだと、思う。
それが俺の幼少期だった。
2015年04月13日投稿。
中途半端なところで切れていたので多少加筆しました、多少。
言葉の繰り返しの後、ぶっつり切れていたので。
文体、昔から変わらないなぁ、と。
これは京阪乗りながら久しぶりに創作したいなとか思いながら、今度こそ投稿するんだって書いたやつです。
それがここまで書いて放置だったので、供養供養。
いつか書き切ってみたいです。
俺は古城を望む街のスラムで生まれた。父の存在は知らない。大勢いた母の金ヅルの一人だろうと踏んでいる。
母の口癖は、
「いつかあの城から王子様が迎えにきてくれる」
だから貴方も、今に幸せな夢を見られるわ。
いつもいつも、よくもまぁそんな馬鹿げたことが言えるもんだ、と、心の中で嗤っていた。
そんな夢物語のいつかなんかより、俺にとって大事なのは、今、この飢えを忘れられて明日も生きていられる、ということだけだった。そう、俺は死んでしまいたくなかった。死んでしまいたくなかったのだ。
目の前で虫にまみれ昨日まで共に話していた人間だったもの、紅い水溜まりの中でもう誰なのかも判らなくなったもの、そんなものには決して、なりたくなかった。
だから、生きるためには、割と何でもやった。
スリは路地の向こうのあんちゃんに教わった。
闇市のじっちゃんに気に入られてナイフを握ったのは六つの誕生日のことだった。
小さな子供が好きだなんて馬鹿な大金持ちの遊びに身体も貸してやったし、それで金と旨いもんが手に入るなら、別にそれでよかった。
もし何かヘマをして命の危険を感じた時には、俺は空から逃げた。闇夜と一緒になって、置き去りにした馬鹿どもを嘲りながら罵りながら、母の待つスラムに逃げた。
あまりに怖くて帰るなり母の腕の中で泣いたこともあった。
母がいない時は、あんちゃんやじっちゃんの布団の中で一緒に眠った。あんちゃんは何にも言わずに横にいてくれたし、じっちゃんは笑って抱き締めてくれた。
きっとそれは、幸せなことだったんだと、思う。
それが俺の幼少期だった。
タグ:2015
「真っ黒々の」
「無意味な言葉が僕の翼になる」より。
2015年04月11日投稿。
過去メモ。
二年前ぐらいの。
一応物語カテゴリにしたけど、続かないしどっちかっていうとエッセイじみてる気がします。
そんな、始まり。


黒いものが好き。
真っ黒々な鴉が好き。
真っ暗闇のゴシックが好き。
流れる黒髪が好き。
瞬きを失った朔の夜が好き。
君が、好き。
僕は真っ黒なものが好きだった。 だから真っ黒なものは何でも欲しかったし、だから、君のことも欲しいと思った。
真っ黒なもので溢れかえれば、いつか、いつか僕も真っ黒に戻れるような気がしていたんだ。
残念ながら、君は真っ黒々とは言えなくて、どす黒いだけの、濁った何かだったのだけど。
だから僕は戻れなかった。
君と同じ、濁ったまんま。
君はいつか全てを捨ててしまうだろう。
それはちょっぴり寂しいことだけど、それよりも今、君が愛されたいと望みながら世界を吐き捨てていることの方が何倍も寂しい。万倍も悲しい。
愛されたいと思うなら、よがってないで世界を見つめてみればいい。
独り善がりの言葉では、誰も君の寂しさなんて気付かない。
取り巻きの愛撫で好がるだけでは、世界の色は計れない。
それなのに君は色を描こうとして。
泣きながら、笑って笑って描いたキャンパス、色があるのに真っ暗闇で。誰も見えない世界が沈んで。
それは本当に描いていると言えるのかな?
2015年04月11日投稿。
過去メモ。
二年前ぐらいの。
一応物語カテゴリにしたけど、続かないしどっちかっていうとエッセイじみてる気がします。
そんな、始まり。
黒いものが好き。
真っ黒々な鴉が好き。
真っ暗闇のゴシックが好き。
流れる黒髪が好き。
瞬きを失った朔の夜が好き。
君が、好き。
僕は真っ黒なものが好きだった。 だから真っ黒なものは何でも欲しかったし、だから、君のことも欲しいと思った。
真っ黒なもので溢れかえれば、いつか、いつか僕も真っ黒に戻れるような気がしていたんだ。
残念ながら、君は真っ黒々とは言えなくて、どす黒いだけの、濁った何かだったのだけど。
だから僕は戻れなかった。
君と同じ、濁ったまんま。
君はいつか全てを捨ててしまうだろう。
それはちょっぴり寂しいことだけど、それよりも今、君が愛されたいと望みながら世界を吐き捨てていることの方が何倍も寂しい。万倍も悲しい。
愛されたいと思うなら、よがってないで世界を見つめてみればいい。
独り善がりの言葉では、誰も君の寂しさなんて気付かない。
取り巻きの愛撫で好がるだけでは、世界の色は計れない。
それなのに君は色を描こうとして。
泣きながら、笑って笑って描いたキャンパス、色があるのに真っ暗闇で。誰も見えない世界が沈んで。
それは本当に描いていると言えるのかな?
タグ:2015
2020年05月09日
「ふと走り出したくなるときがある。」
「無意味な言葉が僕の翼になる」より。
2015年04月10日投稿。
過去メモ。
二年前の一月半ば。
物語は動かない。
心は届かない。
それでも、えがいてみたかった。
馬鹿な自分。


ふと走り出したくなるときがある。
人生もうどうでもいいやって、走り出して走って走って走って走って息が切れて立ち止まって。そしたら息が切れた筈なのに笑えてくるんだ。
何だか本当に愉しいもんだから、はは、はははっ、ははははははははっ、ってさ、笑い出すと止まらなくなる。 あははははははははっ、って、笑いすぎるとさ、全部全部馬鹿らしくなる。
そしたら馬鹿みたいだから笑っているのか、笑っているから馬鹿みたいに思えるのか判らなくなってきて。 すごく、寂しくなる。 あははっ、ははっ、はははははっ、ははは…、
寂しい。
寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい。
なのにそんなときに限ってさ、君がいないんだからさ。 人生って馬鹿みたいだよね。 ははははっ、
2015年04月10日投稿。
過去メモ。
二年前の一月半ば。
物語は動かない。
心は届かない。
それでも、えがいてみたかった。
馬鹿な自分。
ふと走り出したくなるときがある。
人生もうどうでもいいやって、走り出して走って走って走って走って息が切れて立ち止まって。そしたら息が切れた筈なのに笑えてくるんだ。
何だか本当に愉しいもんだから、はは、はははっ、ははははははははっ、ってさ、笑い出すと止まらなくなる。 あははははははははっ、って、笑いすぎるとさ、全部全部馬鹿らしくなる。
そしたら馬鹿みたいだから笑っているのか、笑っているから馬鹿みたいに思えるのか判らなくなってきて。 すごく、寂しくなる。 あははっ、ははっ、はははははっ、ははは…、
寂しい。
寂しい寂しい寂しい寂しい寂しい。
なのにそんなときに限ってさ、君がいないんだからさ。 人生って馬鹿みたいだよね。 ははははっ、
タグ:2015
「空は紅かった。」
「無意味な言葉が僕の翼になる」より。
2015年04月10日投稿。
過去メモ。
二年前の一月半ば。
何をしてて書いたか分からないプロローグ。
物語は動かない。
永遠に。ね。


空は紅かった。
空気は濁っていたように思うし、それを肯定するかのように息苦しかったのを覚えてる。 あんなに綺麗な空なのに、鳥は一羽もいなかった。
星は既に消えかけていて、だけど、目を凝らすとまだそこにあって。
僕は深く息を吸う。
上手く酸素が肺に取り込めない。苦しくて苦しくて、自然、息も浅くなる。
何処かで鐘が鳴った。
時計塔の鐘だ。
ごーん、ごーん、ごーん、
規則的に何度か鳴ったそれは、もう朝が近いことを告げていた。
かえろう?
僕は頬を緩める。
君に向かって。
ねぇ、かえろう?
君の声は返ってこない。
それに僕の鼓動は速くなって、ねぇ、ねぇ、ねぇってば、何度も何度も繰り返した。
本当はずっと前から分かっていたのに。
息が苦しい。
空は紅い。
君は目の前にあるはずなのに、何も返しはしなくって。
息は苦しい。
鼓動は走る。
僕は泣きそうになる。苦しくて、苦しくて、苦しくて堪らない。
ねぇ、ねぇ、ねぇってば。
僕は何度も何度も繰り返す。
そうすれば、君が答えてくれるんじゃないかって。そうすれば、君が笑ってくれるんじゃないか、って。
どんっ、 どこかで鐘が鳴る。
そして僕の後ろから、ふんわりとした声が聞こえる。
次の瞬間、鈍い痛みに僕は呼吸を忘れた。
満たされることのない肺が悲鳴を上げて軋む。 ぎしっ、ぎしぃっ、
そうして僕は、僕を失った。
空が紅い。
あぁ、もう、朝だ……。
2015年04月10日投稿。
過去メモ。
二年前の一月半ば。
何をしてて書いたか分からないプロローグ。
物語は動かない。
永遠に。ね。
空は紅かった。
空気は濁っていたように思うし、それを肯定するかのように息苦しかったのを覚えてる。 あんなに綺麗な空なのに、鳥は一羽もいなかった。
星は既に消えかけていて、だけど、目を凝らすとまだそこにあって。
僕は深く息を吸う。
上手く酸素が肺に取り込めない。苦しくて苦しくて、自然、息も浅くなる。
何処かで鐘が鳴った。
時計塔の鐘だ。
ごーん、ごーん、ごーん、
規則的に何度か鳴ったそれは、もう朝が近いことを告げていた。
かえろう?
僕は頬を緩める。
君に向かって。
ねぇ、かえろう?
君の声は返ってこない。
それに僕の鼓動は速くなって、ねぇ、ねぇ、ねぇってば、何度も何度も繰り返した。
本当はずっと前から分かっていたのに。
息が苦しい。
空は紅い。
君は目の前にあるはずなのに、何も返しはしなくって。
息は苦しい。
鼓動は走る。
僕は泣きそうになる。苦しくて、苦しくて、苦しくて堪らない。
ねぇ、ねぇ、ねぇってば。
僕は何度も何度も繰り返す。
そうすれば、君が答えてくれるんじゃないかって。そうすれば、君が笑ってくれるんじゃないか、って。
どんっ、 どこかで鐘が鳴る。
そして僕の後ろから、ふんわりとした声が聞こえる。
次の瞬間、鈍い痛みに僕は呼吸を忘れた。
満たされることのない肺が悲鳴を上げて軋む。 ぎしっ、ぎしぃっ、
そうして僕は、僕を失った。
空が紅い。
あぁ、もう、朝だ……。
タグ:2015
2020年05月06日
「鴉に恋した半魚の話」
「無意味な言葉が僕の翼になる」より。
2014年08月16日投稿。
それはそれは遠い昔の話、裏の山のそのまた裏の、ずっとずっと奥の奥、山の半ば、人の道を逸れたところにね、小さな小さな滝があってねぇ。そこには半魚が棲むと噂があってね。
誰しも其処に憧れたものさ。なんせ半魚を食べると不老長寿が手に入ると言われていたからねぇ。
ただ、本当にそんな場所があるのかすら、判らない。其処を目指して行った者は、誰一人帰らなんだんだ。
これはそんな、不思議なお話。
鴉に恋した半魚の話
半魚の肉は不老長寿の薬となる。
そんな馬鹿げた話、あるわけなかろうね。
りりは溜め息を吐いて長い黒髪を柘の櫛でといた。
さらさらと髪が舞って、りりは水面に映る自分の髪にうっとりと頬を緩ませる。
母様がいつか言っていた。美しいものを食べなさい、食はそのままお前の血肉となるのだから、美しい者を、食べなさい、と。
母様は美しい方だった。
だから、その教えを守って生きてきた。
滝に迷い込む者はおなごが多く、その人肉はほどよく甘く、あたしはそれをしっかり食した。
この美しいおなご達は、あたしの美しさになる。母様のように。
りりは長い黒髪を三つに編むと、それを何度か撫でてから、そっと大岩に寝転がった。
陽の光が身体中の鱗をきらきらと輝かせる。黒光りするその艶やかな鱗は、りりの自慢の鱗であった。
母様譲りの美しい鱗。
りりは半魚であった。
半人半魚。
人魚と言えば聞こえは言いが、所詮は化け物だ人を惑わすあやかしだなど指をさされるだけの存在だ。
りりはぼんやり目を瞑る。
滝の飛沫がきらきらと空の光を輝かせている。
水面を揺らしながらたくさんの鮒が泳いでいる。
静かな場所。滝の打つ音が心地好く耳を撫でる。
そんな場所で、りりはひとりぼっちだった。
つまんないねぇ。
半魚の肉の噂は、おなご達を引き寄せる餌でもあったが、それ故、母様の命を奪う要因にもなった。
りりは滝の真裏で母様が八つ裂きにされるのを見てしまった。
ぐちゃぐちゃに裂かれた身体をまるで魚の肉をさばくかのように小さな塊にされてしまって、一抱えほどの木箱にすっぽり収まってしまった母様。
それからずっとひとりぼっちだった。
母様を殺した男達はさして旨くはなかった。
力の強い男の筋繊維は固いばかりで食べにくかったし、内臓も苦くて食えたものじゃあなかった。
母様の肉は水の中に還してやった。
そしたらいつも一緒に泳いでた鮒供ったら、それが母様の肉だなんて知りもせずにばくばく食べちゃったもんだから、びっくりしてしまって。
でもまぁ、水に還るって、そういうことだわ。
りりは岩の上で大きく伸びをする。そして尾びれで水面を揺らして鮒を蹴散らしてから、ぼちゃんっ、川の中に潜り込んだ。
別に構やしないわ、一人だって生きていける。ただ、つまんないだけ。
水がなくちゃ生きていけないもの。滝の外に出たら私も母様のように裂かれて死んでしまうんだわ。それは不愉快だもの。だからここでいい、ここでのんびり暮らすの。
りりはきらきら揺れる水面を見上げながら思った。
暫くすると蹴散らした鮒供が戻ってきて、りりの身体に擦り寄ってくる。
りりはその鱗を優しく撫でてやってから、これでいい、これでいいんだわ、何度となくそう思った。
その時だった。
どんっ、
重たい音が、水面を貫いて耳に届く。
鮒は一斉に水底に潜ってしまった。
りりが恐る恐る顔を出すと、どんっ、また音がした。
そして何度目かのその音に、遠い空を飛んでいた黒い鳥が、翼を衝かれてばしゃんと落ちてきた。
鮒がそれに群がるので蹴散らしてから、りりはそれを拾い上げて岩の上に横たえてやる。
猟師かと思ったが、落ちた鴉を拾いに来る気配もない。
弄んだだけってことかい。
りりは無性に腹がたったが、そんなことより今は傷口を見てやらないと、そう思って翼を広げてみると、弾丸は翼の根元を折るほど深くめり込んでいて、つい、眉間に皺を寄せる。
酷いもんだねぇ、人間は。
りりが弾丸を抉り取ってやると、どろどろとした赤い液体が岩肌を伝って水面を染めていく。
あぁ、こらもうダメだね。
りりは傷口を押さえてやるけども、流れを止めてやれなくて、溜め息を吐くしかできない。
こんな小さな身体でこんなにたくさん流れちまったら、もう、ダメだろうね。
りりは傷口に触れるのを止めた。
代わりにそっと胸元に抱きしめると、苦しそうに息を吐く嘴を指の腹で優しく撫でてやった。
可哀想にねぇ、可哀想にねぇ。
人は食べるため以外に平気で生き物を殺す。生き物は愉しむための道具なんかじゃないのにねぇ。
りりはそっと頭に唇を寄せてやると、川の縁の土のあるところまで抱えて泳いでいき、そっと横たえてやった。
せめて土へお還り。
りりは最後に嘴を撫でてやってから、水の中へ帰った。
それが、昼頃のことだった。
りりが滝の裏で眠っていると、鴉が泣く声が聞こえた気がして、驚いて目を覚ました。
もう月が上っていた。そのうち星が顔を出すだろう。
りりは何となく気になって、昼頃鴉を横たえてやった場所を遠目から見やった。
何かいる!
りりはびっくりして、あまりにびっくりしたものだから、ばしゃんっ、水面を尾びれで叩いてしまって、大きな音を響かせてしまう。
やってしまった。
あれが人間で気付かれてしまったなら、自分の命はないかもしれない。もしあれが昼間、鴉を無意味に撃った人間なら、りりのことも簡単に殺してしまうのだろう。
そう思うと怖くて怖くて堪らなかったけれど、そんな気配はなくて。
りりは首を傾げた。
好奇心に負けて、水底をゆっくり這って近付いてみる。
すると、水面を揺らして人の手が差し伸べられたので、びっくりして、けれどそこには全く害意なぞ感じられなくて、りりはその手を取った。
力強く引き上げられたりりは、半魚の姿を晒してしまう。
湿った身体に土が付いて、何だか落ち着かない。
「昼間はすまなかったな」
「何がだい?」
「弾を抜いてもらって助かった。根元に深く入ったから自分では取れそうになかったから、諦めていた」
「あんた、あやかしかい」
「お前もだろう」
「……、」
りりが上体を起こすと、人の形をしたそれが、ゆっくりと抱きしめてくる。
「昼間の礼だ」
「そうかい」
誰かに抱きしめられたのなど、母様以外に初めてで、しかもその感触も久しかったものだからか、りりは心臓がだくだく打つのが感じられて、何だか落ち着かない。
「すまんが暫くここに居させてもらうぞ。あやかしとはいえ、俺は治癒に長けてない。飛べるようになるまで、だいぶ掛かるかもしれん」
「……、」
「鮒はお前の兄弟か?」
「……、いんや、ただ、食うならあたしの見てないところで食っておくれね。一緒に暮らした仲間が減るのは、心苦しいからね」
「察しがいいな」
「食べるのは生きるため仕方のないことだからねぇ」
りりは暫く腕の中にいてやった。
もぞもぞ動くとその腕は簡単に離れてしまって、少しだけ、寂しくなった。
「なぁ、あんた、名前はあるかい?」
「聞いてどうする」
「あたしはねぇ、りりってんだ。母様が付けてくれた。良い名だろう?」
りりが言うと、人の形をした鴉は、そうだな、と、りりの髪を撫ぜてきた。
それにまた、心臓がだくだく波打って。
りりは苦しくなって、ぼちゃんっ、身を捩って水の中へと戻った。
「暫くゆっくりするといい、傷が癒えるまで飛べもしないんだろう?」
りりが言うと、鴉は寂しそうな笑みを浮かべる。
「そうだな」
言って、そっぽを向いて横になった。
「その姿……、」
りりが背中に声を掛けると、鴉はひらひらと手を振った。
「あぁ、鴉は仮の姿でな、実は俺はこっちのが本当に近いんだ」
「……、」
「俺はあんたと違う。あんたみたいな綺麗な存在じゃない。半分以上、人の血が混じってんのさ」
「……、そうかい……、」
りりはそれ以上聞かなかった。
代わりに滝の裏に隠しておいた、いつぞやの食べた娘の着物を持ってくると、そっと鴉に掛けてやった。
「あんたのかい?」
「ふふふっ、だったらよかったんだけどねぇ、私はこのとおり、服なんか着やしないんだよ」
りりが笑って言うと、鴉はこっちを向いて、真っ直ぐりりを見つめてくる。
「着てみりゃいいのに。あんた、人の姿になれるだろうに、どうして」
りりはわざとらしく肩を竦める。
そしてばしゃんと尾びれで水面を叩くと、
「あたしはこれが気に入ってんのさ」
言ってから、逃げるようにその場を離れた。
滝の裏に戻っても、だくだく波打つ心臓が抑えきれなくて、苦しくて。
眠れそうにもないのに、りりは無理矢理目を瞑った。
数日、鴉は満足に動けやしないようで、ただ人の形のまんま、ずっと横たわっていた。
りりがそっと鮒を置いてやっておくと、暫くしたらそれはいなくなっていた。
毎日毎日りりは鮒を置いてやっていた。それだけしか、してやれることが見つからない自分が悔しかった。
ある日りりが滝の裏で眠っていると、ばさりっ、翼の音が聞こえて、ぼんやりと目を開けた。
大きな翼を背中に、人の形をした鴉は寂しそうに笑ってりりの頭を撫ぜてきた。
「ほら、そこで見つけた」
「あぁ、綺麗だねぇ」
簪。ここにくるおなご達はいつも簡素なそれだったから、こんなにきらきら飾りのついた簪見たことがなくて、りりはうっとりそれを見つめた。
「あんた、綺麗な髪だからな、たまにでいい、付けるといい」
水の中じゃ要らないかもしれないがな。
鴉は言うと、そっとりりから離れた。
りりは何となく、その意味を悟る。
寂しいねぇ、寂しいねぇ。
いつの間にか川縁にあんたがいるのが普通になっちまっていたよ。
それを口にすることができなくて、代わりに、りりはそっと髪を束ねると、たどたどしい手付きで簪を差してみる。
すると鴉が近付いてきて、前から後ろに手をやって、それを直してくれた。
「ありがとうねぇ」
りりは水面に映る自分の髪を見つめて、うっとりとした。
きらきら飾りが綺麗で、嬉しくなって、りりはそっと簪に触れてそれを揺らした。
「やっぱり似合う」
「そうかい?」
「最後にあんたがそれを付けてるのが見れて良かったよ」
「ふふふっ、あんた変わってるねぇ」
「変わってやしないさ、鴉はきらきら綺麗なもんが好きなんだ」
言うと、鴉はりりの頬の鱗を、そっと撫ぜる。
「あんた、そこらの宝石以上に綺麗だぜ」
「ふふふっ、あんた、硝子の欠片にだってそう思うんだろう?」
「……、」
「もう撃たれないように気を付けなね」
りりは言うと、そっと額に口付けてやった。
そして指の腹で唇を撫ぜてやってから、もう一度、ありがとねぇ、言って、鴉の唇を撫ぜたその指で簪を揺らした。
鴉は何も言わなかった。
翼をばさりと広げてから何度か羽ばたくと、初めて見た時の小さな姿になって、そのまま滝の外へと消えた。
りりが見送ると、黒い点はすぐに空の向こうに消えてしまった。
りりは簪を外して、そっと唇を落とす。
そうさね、水と空じゃあ、あまりに世界が違いすぎるってもんさね。
りりは溜め息を吐いて、そっと、桐の箱に簪をしまうのだった。
おしまい


2014年08月16日投稿。
それはそれは遠い昔の話、裏の山のそのまた裏の、ずっとずっと奥の奥、山の半ば、人の道を逸れたところにね、小さな小さな滝があってねぇ。そこには半魚が棲むと噂があってね。
誰しも其処に憧れたものさ。なんせ半魚を食べると不老長寿が手に入ると言われていたからねぇ。
ただ、本当にそんな場所があるのかすら、判らない。其処を目指して行った者は、誰一人帰らなんだんだ。
これはそんな、不思議なお話。
鴉に恋した半魚の話
半魚の肉は不老長寿の薬となる。
そんな馬鹿げた話、あるわけなかろうね。
りりは溜め息を吐いて長い黒髪を柘の櫛でといた。
さらさらと髪が舞って、りりは水面に映る自分の髪にうっとりと頬を緩ませる。
母様がいつか言っていた。美しいものを食べなさい、食はそのままお前の血肉となるのだから、美しい者を、食べなさい、と。
母様は美しい方だった。
だから、その教えを守って生きてきた。
滝に迷い込む者はおなごが多く、その人肉はほどよく甘く、あたしはそれをしっかり食した。
この美しいおなご達は、あたしの美しさになる。母様のように。
りりは長い黒髪を三つに編むと、それを何度か撫でてから、そっと大岩に寝転がった。
陽の光が身体中の鱗をきらきらと輝かせる。黒光りするその艶やかな鱗は、りりの自慢の鱗であった。
母様譲りの美しい鱗。
りりは半魚であった。
半人半魚。
人魚と言えば聞こえは言いが、所詮は化け物だ人を惑わすあやかしだなど指をさされるだけの存在だ。
りりはぼんやり目を瞑る。
滝の飛沫がきらきらと空の光を輝かせている。
水面を揺らしながらたくさんの鮒が泳いでいる。
静かな場所。滝の打つ音が心地好く耳を撫でる。
そんな場所で、りりはひとりぼっちだった。
つまんないねぇ。
半魚の肉の噂は、おなご達を引き寄せる餌でもあったが、それ故、母様の命を奪う要因にもなった。
りりは滝の真裏で母様が八つ裂きにされるのを見てしまった。
ぐちゃぐちゃに裂かれた身体をまるで魚の肉をさばくかのように小さな塊にされてしまって、一抱えほどの木箱にすっぽり収まってしまった母様。
それからずっとひとりぼっちだった。
母様を殺した男達はさして旨くはなかった。
力の強い男の筋繊維は固いばかりで食べにくかったし、内臓も苦くて食えたものじゃあなかった。
母様の肉は水の中に還してやった。
そしたらいつも一緒に泳いでた鮒供ったら、それが母様の肉だなんて知りもせずにばくばく食べちゃったもんだから、びっくりしてしまって。
でもまぁ、水に還るって、そういうことだわ。
りりは岩の上で大きく伸びをする。そして尾びれで水面を揺らして鮒を蹴散らしてから、ぼちゃんっ、川の中に潜り込んだ。
別に構やしないわ、一人だって生きていける。ただ、つまんないだけ。
水がなくちゃ生きていけないもの。滝の外に出たら私も母様のように裂かれて死んでしまうんだわ。それは不愉快だもの。だからここでいい、ここでのんびり暮らすの。
りりはきらきら揺れる水面を見上げながら思った。
暫くすると蹴散らした鮒供が戻ってきて、りりの身体に擦り寄ってくる。
りりはその鱗を優しく撫でてやってから、これでいい、これでいいんだわ、何度となくそう思った。
その時だった。
どんっ、
重たい音が、水面を貫いて耳に届く。
鮒は一斉に水底に潜ってしまった。
りりが恐る恐る顔を出すと、どんっ、また音がした。
そして何度目かのその音に、遠い空を飛んでいた黒い鳥が、翼を衝かれてばしゃんと落ちてきた。
鮒がそれに群がるので蹴散らしてから、りりはそれを拾い上げて岩の上に横たえてやる。
猟師かと思ったが、落ちた鴉を拾いに来る気配もない。
弄んだだけってことかい。
りりは無性に腹がたったが、そんなことより今は傷口を見てやらないと、そう思って翼を広げてみると、弾丸は翼の根元を折るほど深くめり込んでいて、つい、眉間に皺を寄せる。
酷いもんだねぇ、人間は。
りりが弾丸を抉り取ってやると、どろどろとした赤い液体が岩肌を伝って水面を染めていく。
あぁ、こらもうダメだね。
りりは傷口を押さえてやるけども、流れを止めてやれなくて、溜め息を吐くしかできない。
こんな小さな身体でこんなにたくさん流れちまったら、もう、ダメだろうね。
りりは傷口に触れるのを止めた。
代わりにそっと胸元に抱きしめると、苦しそうに息を吐く嘴を指の腹で優しく撫でてやった。
可哀想にねぇ、可哀想にねぇ。
人は食べるため以外に平気で生き物を殺す。生き物は愉しむための道具なんかじゃないのにねぇ。
りりはそっと頭に唇を寄せてやると、川の縁の土のあるところまで抱えて泳いでいき、そっと横たえてやった。
せめて土へお還り。
りりは最後に嘴を撫でてやってから、水の中へ帰った。
それが、昼頃のことだった。
りりが滝の裏で眠っていると、鴉が泣く声が聞こえた気がして、驚いて目を覚ました。
もう月が上っていた。そのうち星が顔を出すだろう。
りりは何となく気になって、昼頃鴉を横たえてやった場所を遠目から見やった。
何かいる!
りりはびっくりして、あまりにびっくりしたものだから、ばしゃんっ、水面を尾びれで叩いてしまって、大きな音を響かせてしまう。
やってしまった。
あれが人間で気付かれてしまったなら、自分の命はないかもしれない。もしあれが昼間、鴉を無意味に撃った人間なら、りりのことも簡単に殺してしまうのだろう。
そう思うと怖くて怖くて堪らなかったけれど、そんな気配はなくて。
りりは首を傾げた。
好奇心に負けて、水底をゆっくり這って近付いてみる。
すると、水面を揺らして人の手が差し伸べられたので、びっくりして、けれどそこには全く害意なぞ感じられなくて、りりはその手を取った。
力強く引き上げられたりりは、半魚の姿を晒してしまう。
湿った身体に土が付いて、何だか落ち着かない。
「昼間はすまなかったな」
「何がだい?」
「弾を抜いてもらって助かった。根元に深く入ったから自分では取れそうになかったから、諦めていた」
「あんた、あやかしかい」
「お前もだろう」
「……、」
りりが上体を起こすと、人の形をしたそれが、ゆっくりと抱きしめてくる。
「昼間の礼だ」
「そうかい」
誰かに抱きしめられたのなど、母様以外に初めてで、しかもその感触も久しかったものだからか、りりは心臓がだくだく打つのが感じられて、何だか落ち着かない。
「すまんが暫くここに居させてもらうぞ。あやかしとはいえ、俺は治癒に長けてない。飛べるようになるまで、だいぶ掛かるかもしれん」
「……、」
「鮒はお前の兄弟か?」
「……、いんや、ただ、食うならあたしの見てないところで食っておくれね。一緒に暮らした仲間が減るのは、心苦しいからね」
「察しがいいな」
「食べるのは生きるため仕方のないことだからねぇ」
りりは暫く腕の中にいてやった。
もぞもぞ動くとその腕は簡単に離れてしまって、少しだけ、寂しくなった。
「なぁ、あんた、名前はあるかい?」
「聞いてどうする」
「あたしはねぇ、りりってんだ。母様が付けてくれた。良い名だろう?」
りりが言うと、人の形をした鴉は、そうだな、と、りりの髪を撫ぜてきた。
それにまた、心臓がだくだく波打って。
りりは苦しくなって、ぼちゃんっ、身を捩って水の中へと戻った。
「暫くゆっくりするといい、傷が癒えるまで飛べもしないんだろう?」
りりが言うと、鴉は寂しそうな笑みを浮かべる。
「そうだな」
言って、そっぽを向いて横になった。
「その姿……、」
りりが背中に声を掛けると、鴉はひらひらと手を振った。
「あぁ、鴉は仮の姿でな、実は俺はこっちのが本当に近いんだ」
「……、」
「俺はあんたと違う。あんたみたいな綺麗な存在じゃない。半分以上、人の血が混じってんのさ」
「……、そうかい……、」
りりはそれ以上聞かなかった。
代わりに滝の裏に隠しておいた、いつぞやの食べた娘の着物を持ってくると、そっと鴉に掛けてやった。
「あんたのかい?」
「ふふふっ、だったらよかったんだけどねぇ、私はこのとおり、服なんか着やしないんだよ」
りりが笑って言うと、鴉はこっちを向いて、真っ直ぐりりを見つめてくる。
「着てみりゃいいのに。あんた、人の姿になれるだろうに、どうして」
りりはわざとらしく肩を竦める。
そしてばしゃんと尾びれで水面を叩くと、
「あたしはこれが気に入ってんのさ」
言ってから、逃げるようにその場を離れた。
滝の裏に戻っても、だくだく波打つ心臓が抑えきれなくて、苦しくて。
眠れそうにもないのに、りりは無理矢理目を瞑った。
数日、鴉は満足に動けやしないようで、ただ人の形のまんま、ずっと横たわっていた。
りりがそっと鮒を置いてやっておくと、暫くしたらそれはいなくなっていた。
毎日毎日りりは鮒を置いてやっていた。それだけしか、してやれることが見つからない自分が悔しかった。
ある日りりが滝の裏で眠っていると、ばさりっ、翼の音が聞こえて、ぼんやりと目を開けた。
大きな翼を背中に、人の形をした鴉は寂しそうに笑ってりりの頭を撫ぜてきた。
「ほら、そこで見つけた」
「あぁ、綺麗だねぇ」
簪。ここにくるおなご達はいつも簡素なそれだったから、こんなにきらきら飾りのついた簪見たことがなくて、りりはうっとりそれを見つめた。
「あんた、綺麗な髪だからな、たまにでいい、付けるといい」
水の中じゃ要らないかもしれないがな。
鴉は言うと、そっとりりから離れた。
りりは何となく、その意味を悟る。
寂しいねぇ、寂しいねぇ。
いつの間にか川縁にあんたがいるのが普通になっちまっていたよ。
それを口にすることができなくて、代わりに、りりはそっと髪を束ねると、たどたどしい手付きで簪を差してみる。
すると鴉が近付いてきて、前から後ろに手をやって、それを直してくれた。
「ありがとうねぇ」
りりは水面に映る自分の髪を見つめて、うっとりとした。
きらきら飾りが綺麗で、嬉しくなって、りりはそっと簪に触れてそれを揺らした。
「やっぱり似合う」
「そうかい?」
「最後にあんたがそれを付けてるのが見れて良かったよ」
「ふふふっ、あんた変わってるねぇ」
「変わってやしないさ、鴉はきらきら綺麗なもんが好きなんだ」
言うと、鴉はりりの頬の鱗を、そっと撫ぜる。
「あんた、そこらの宝石以上に綺麗だぜ」
「ふふふっ、あんた、硝子の欠片にだってそう思うんだろう?」
「……、」
「もう撃たれないように気を付けなね」
りりは言うと、そっと額に口付けてやった。
そして指の腹で唇を撫ぜてやってから、もう一度、ありがとねぇ、言って、鴉の唇を撫ぜたその指で簪を揺らした。
鴉は何も言わなかった。
翼をばさりと広げてから何度か羽ばたくと、初めて見た時の小さな姿になって、そのまま滝の外へと消えた。
りりが見送ると、黒い点はすぐに空の向こうに消えてしまった。
りりは簪を外して、そっと唇を落とす。
そうさね、水と空じゃあ、あまりに世界が違いすぎるってもんさね。
りりは溜め息を吐いて、そっと、桐の箱に簪をしまうのだった。
おしまい
「大正妖怪異聞-廓座お仙-」【秋の話】
「無意味な言葉が僕の翼になる」より。
2013年11月09日投稿。
※子育て関係ありません
※昨日おっぱいの日だったみたいなので書きました
※短いです


くしゅん!
お仙は一つくしゃみをすると、隣に寝そべったその姿に目をやって、溜め息を吐いた。
「お妲、お前ね、こんな季節にそんな恰好して、風邪引いても知らないよ」
「えー?」
お仙の声に布団の上でごろりと仰向けになって、寝そべったまま上目で視線をやった。
一枚しか着ていない襦袢ははだけ、ふくよかな塊が二つとも顔を出している。
それを見てお仙は溜め息を吐いた。
「だらしないねぇ、」
「いいじゃないかお仙、アタシとアンタの仲だろう?」
そう言って身を捩ると、重力に従ってたわわなそれが左へと傾いた。
透くようなその二つは重みが手伝って、戯れにお妲が身を捩る度にふわふわと揺れ、その揺れを楽しむかのようにお妲自身も何度も身を捩った。
そんな様子を暫く横目で見ていたお仙だったが、窓の外が徐々に色を失って行くのを見て、また、溜め息を吐く。
そして膝をついたままずりずりとお妲の横にくると、一度その膨らみを優しく指先で撫でてから、ずり落ちた襦袢を引っ張って整えてやった。
そして大きなそれが苦しくないよう緩く紐を結わえると、立ち上がる。
「お妲、もう冷えるからね、夕餉には羽織ぐらい羽織って来るんだよ」
そう言って煙管をくわえるとくるりっと踵を返し、ひらひら手を振って戸の外へと出ていった。
それを半身起こして見送った後、お妲はくすりと笑う。
「お仙、アンタが風邪引いたら、アタシが温めてあげるから、ねぇ」
終わってしまう
2013年11月09日投稿。
※子育て関係ありません
※昨日おっぱいの日だったみたいなので書きました
※短いです
くしゅん!
お仙は一つくしゃみをすると、隣に寝そべったその姿に目をやって、溜め息を吐いた。
「お妲、お前ね、こんな季節にそんな恰好して、風邪引いても知らないよ」
「えー?」
お仙の声に布団の上でごろりと仰向けになって、寝そべったまま上目で視線をやった。
一枚しか着ていない襦袢ははだけ、ふくよかな塊が二つとも顔を出している。
それを見てお仙は溜め息を吐いた。
「だらしないねぇ、」
「いいじゃないかお仙、アタシとアンタの仲だろう?」
そう言って身を捩ると、重力に従ってたわわなそれが左へと傾いた。
透くようなその二つは重みが手伝って、戯れにお妲が身を捩る度にふわふわと揺れ、その揺れを楽しむかのようにお妲自身も何度も身を捩った。
そんな様子を暫く横目で見ていたお仙だったが、窓の外が徐々に色を失って行くのを見て、また、溜め息を吐く。
そして膝をついたままずりずりとお妲の横にくると、一度その膨らみを優しく指先で撫でてから、ずり落ちた襦袢を引っ張って整えてやった。
そして大きなそれが苦しくないよう緩く紐を結わえると、立ち上がる。
「お妲、もう冷えるからね、夕餉には羽織ぐらい羽織って来るんだよ」
そう言って煙管をくわえるとくるりっと踵を返し、ひらひら手を振って戸の外へと出ていった。
それを半身起こして見送った後、お妲はくすりと笑う。
「お仙、アンタが風邪引いたら、アタシが温めてあげるから、ねぇ」
終わってしまう
タグ:2013 大正妖怪異聞-廓座お仙-
「凍てつく眼球 DollsMaker」
「無意味な言葉が僕の翼になる」より。
2013年09月21日投稿。
君が眠りに落ちた宵に、僕は君を壊してしまいたいんだ。
凍てつく眼球
「ねぇ、見えないってどんな気分?」
声に目蓋を開こうとしてもそれは重く、そもそも開いたところでそこには何も存在しない。
だからただ、闇の中でそれをなぶる舌先の音を、耳に感じていた。
くちゅ、くちゅ、
「ねぇ、どうして似せて作ってるのに、同じ彩りを放ってはくれないんだろう、ねぇ」
それをなぶるのに飽きたのか、柔らかな声が降ってくる。
そして膝の上から重みが消えたかと思うと、何度かの足音の後、何かを洗う水音が室内に響いた。
それを聞いて、溜め息を吐いた。
何をそんなに御執心なんだか。
と、思うと同時、こどものような無邪気な声が、また耳に届く。
「さ、お仕事だよ」
ねぇ、君、僕を、ずっとずっと愉しませておくれ、ねぇ。


DollsMaker
2013年09月21日投稿。
君が眠りに落ちた宵に、僕は君を壊してしまいたいんだ。
凍てつく眼球
「ねぇ、見えないってどんな気分?」
声に目蓋を開こうとしてもそれは重く、そもそも開いたところでそこには何も存在しない。
だからただ、闇の中でそれをなぶる舌先の音を、耳に感じていた。
くちゅ、くちゅ、
「ねぇ、どうして似せて作ってるのに、同じ彩りを放ってはくれないんだろう、ねぇ」
それをなぶるのに飽きたのか、柔らかな声が降ってくる。
そして膝の上から重みが消えたかと思うと、何度かの足音の後、何かを洗う水音が室内に響いた。
それを聞いて、溜め息を吐いた。
何をそんなに御執心なんだか。
と、思うと同時、こどものような無邪気な声が、また耳に届く。
「さ、お仕事だよ」
ねぇ、君、僕を、ずっとずっと愉しませておくれ、ねぇ。
DollsMaker
2020年05月05日
「硬質状態」
「無意味な言葉が僕の翼になる」より。
2013年08月01日投稿。
それは息を奪うようにまとわりついて、僕の身体を蝕んでいく。
世界は濁って声が出せない。
じめじめと喉をいたぶって吐き気すら覚えるのに、僕はそこから抜け出せない。
手を伸ばすと周りは硬い壁で、そこはとても狭く感じた。
あぁ、酸素を下さい。
僕は叫んだ。
だけれど声はあぶくとなって、ぼこぼこぼこぼこ空へと消えて。
結局誰にも届かない。
息も出来ないほど苦しいのに、そこにたゆたっているという快楽。
身体が熱を帯びていて、ねっとりとした汗をかきながら。
喘ぐ。
その息すらも声帯を震わせることができないようで、また、あぶくが空へと消えていった。
あぁ、周りは硬く閉ざされていて、誰が世界をこんなにしてしまったのか。
分からないまま、熱に心を浮かせたまま、僕は、吸えもしないのに酸素を求めた。
あぁ、
誰か世界を壊して下さい。
誰か僕に酸素を下さい。
何もない場所で、僕は、僕は、僕は。
独りぼっち。
さようなら。
「高湿状態」


2013年08月01日投稿。
それは息を奪うようにまとわりついて、僕の身体を蝕んでいく。
世界は濁って声が出せない。
じめじめと喉をいたぶって吐き気すら覚えるのに、僕はそこから抜け出せない。
手を伸ばすと周りは硬い壁で、そこはとても狭く感じた。
あぁ、酸素を下さい。
僕は叫んだ。
だけれど声はあぶくとなって、ぼこぼこぼこぼこ空へと消えて。
結局誰にも届かない。
息も出来ないほど苦しいのに、そこにたゆたっているという快楽。
身体が熱を帯びていて、ねっとりとした汗をかきながら。
喘ぐ。
その息すらも声帯を震わせることができないようで、また、あぶくが空へと消えていった。
あぁ、周りは硬く閉ざされていて、誰が世界をこんなにしてしまったのか。
分からないまま、熱に心を浮かせたまま、僕は、吸えもしないのに酸素を求めた。
あぁ、
誰か世界を壊して下さい。
誰か僕に酸素を下さい。
何もない場所で、僕は、僕は、僕は。
独りぼっち。
さようなら。
「高湿状態」
タグ:2013