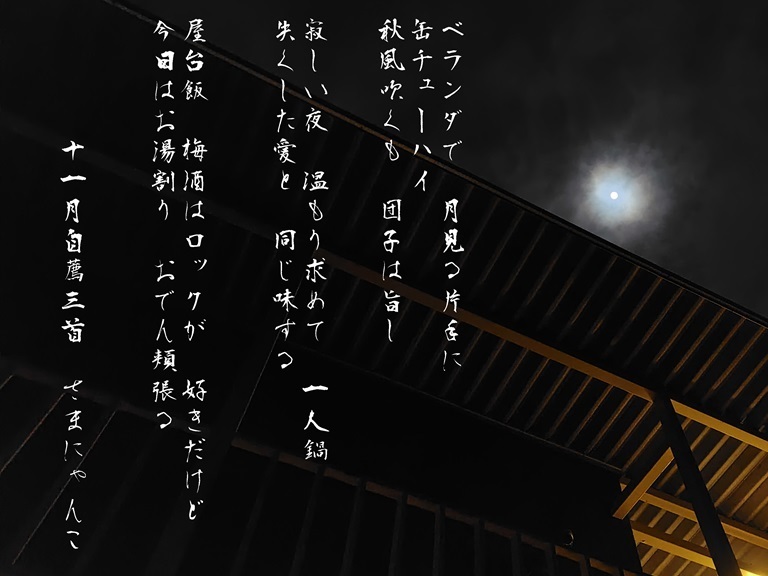2022年10月09日
僕は僕を忘れてしまった
pixiv別名義より。
2017年8月22日05:50投稿。
※現在pixivでも掲載中です、追々pixivでは削除する予定です
僕は壊れてしまったから
君の手で棄ててほしかったんだ
自分が壊れたことも解らなくて
蔑むような瞳が怖くて
全ての声が脳髄を蝕んで
もう
誰も彼も蔑ろだ
それなのに、
どうして心が焼き切れても
壊れていくばかりで
完全に止まってしまえないんだろう


君に恋をしたのは一体誰だったんだろうね。そんなお話。
蒸気で熱を帯びた工場の群れを擦り抜けて、僕は君の手を引っ張って走っていく。
君は工業地帯に不釣り合いな真っ白のワンピースを着て、追われていると言うのに笑っていた。
細い工場と工場の隙間に何とか滑り込むと、横向きになってじりじりと移動する。
君は僕に続くけれど、胸元が壁に擦れて顔を歪めながらだった。
逃げていると言うのに、ある筈のない心の臓がどくりと波打つ。
そうして工場を抜けると、そこには大量の鉄屑が積み重なって山となり、その上にはくすんだ星空が広がっていた。
「きっともう来ないよ」
君は笑って言う。
「だといいね」
僕が呆れたように返すと、君はくるくる回ってワンピースをふわふわと舞わせた。
君は自分には罪など存在しないとでも言うように笑って、手を差し出してきた。
「ねぇ、君の家を教えて」
「匿えってこと?」
嫌だな。
僕は鼻を鳴らす。
「家なんてないよ。来た道を戻れば工場の寮に戻れる。いいの? 見つかってしまうよ?」
「見つからないよ、二人で帰ろう」
君は呑気だ。
追われているということを自覚しているのだろうか。
「君を匿ったら僕は罪人だ」
「違うよ、君は迷子の女の子を保護してくれた優しい人だよ」
君は言うと、僕の手をぎゅっと握った。
僕は溜め息を吐く。
もういいや、逃げるのも疲れてしまった。
明日も仕事。早く帰って眠りたい。
ベッドに一人ばかり増えたところで狭いとも思わないだろうけれど、その柔らかな膨らみを思うと、きっと眠れないのだろうと思う。
僕は君が何処から来たのか何となく判っているけれど、敢えてそれを言及しようとは思わなかった。
君がどれほどの決意でこんな場所まで逃げてきたのかなんて知りもしないけど。
もしかしたら、本当に呑気に観光をしに来ただけなのかもしれない。
そうだとしたら、それで追われた僕は、追われ損な気がした。
「会いたかったよ」
君がぎゅっと手を握って言うのに、僕は首を傾げた。
「一目で判ったよ、君が君だって」
誰かと勘違いしているのだろう。
別にそれは珍しいことではない。
だから、ふーん、それだけ素っ気なく返して、僕はその手を振りほどいた。
「どこにいくの?」
「帰るんだよ、僕は明日も仕事なんだ」
「じゃあ、ついていくね」
「……、勝手にすれば。でももし次に見つかったら、僕はもう知らんぷりをするよ」
「また、一緒だね」
君は嬉しそうに笑って言う。
普段は間違えられることに何とも思わないのに、今は、君のその笑顔が憎々しかった。
その嬉しげな君が見つめているのは僕じゃない。
僕じゃない誰かが、僕は、憎々しくて、憎々しくて、堪らなかった。
僕は君の手を取らなかった。
君なんて知らんぷりして、歩いていく。
そんな僕に君は嬉しそうについてくる。
君は不思議だ。
そもそも、ヒトと言うのは不思議な生き物だ。
僕はそれを知っている。
だから、そんなに気にすることはないのかもしれない。
それでも僕は、君の笑顔が不思議で、不思議で、心の臓のある辺りがどくどくと苦しくなる。
そんな気持ちに気付かないふりをして、寮までの道を歩いていく。
別に引き返せば良かったのに、わざわざ違う工場の隣を選んで歩いていく。
そうして遠回りして、僕は僕の手を働く工場の隣にある寮までやってきた。
もう、皆眠っているはずだ。
僕も早く眠りたい。
そっと音を立てないように僕が入ると、するりっ、君は扉が閉まる前に一緒に入ってきた。
「君の部屋はどこ?」
嬉しそうに君はいろんな部屋の戸を見ている。
寮なんて同じ部屋の集まりなのに、君はこういう暮らしを知らないからそれが楽しくて楽しくて堪らないんだろうな。
生産させられる側に生まれなかったから、君はそんな嬉しそうに笑えるんだろうな。
僕は嗤った。
生まれたときからこの工場で働き続けることが決定していた自分は、なんて馬鹿馬鹿しい存在なのだろう。
「こっち」
あまりうろちょろされても不都合なので、僕はやっとその手を取ると、自分の部屋へと連れて入った。
寮の部屋は簡素だ。
安物のベッドと、机が一つ。椅子も安物。電気が通っているだけありがたい。
僕はぱちりと電気を点けると、着たままだった作業着を脱ぎ捨てて上半身を曝け出した。
「見ないでよ」
じっとこちらを見てくる視線が疎ましくて僕が君を睨み付けると、君は慌てて後ろを向いた。
それを見て、僕は小さく溜め息を吐いた。
僕は身体をタオルで拭ってから、腹部にある鍵穴に鍵を差し込んで、身体を開けた。
かしゃんっ、音がして、僕が開く。
無理して走ったからだろう、少し、調子がおかしい。
本当は報告して直してもらうべきなのだろうけど、直してもらって、また寿命が延びて、働く期限が増えてしまうのは、馬鹿馬鹿しかった。
僕は機械の詰まった腹に雑に油を注すと、身体を閉じてその辺にあったシャツを着た。
僕は壁に凭れて目を瞑る。
「ベッド、使えば」
「君は?」
「眠れれば、どこでもいい」
一緒に眠ってしまったら、腕の中にいる可愛らしい生き物に、心が軋んでしまいそうになる。
「調子悪いの? それとも夜の日課なの?」
君は勝手に油を拾い上げて見つめる。
「僕の身体はあまり走るのに適していないんだ。普段は工場の同じ場所で同じモノを作り続けるだけだからね」
「私のせいね」
「そうだよ」
僕は短く言う。
それに何か言いたげに君は口を開くけれど、すぐに閉じてしまった。
「眠らせてくれないか。ただでさえ人員が足りなくて工場での稼働時間がオーバーしてるんだ、多大にね。それに加えて、君に出会ったせいで身体に負荷が掛かった。一度停止しないと明日動けない」
「明日は休んでしまったら?」
君は呑気だ。
「休めるならとっくに休んでるよ。人員が足りない。僕が動かないと、ヒトが壊れてしまう。君達は直せば使える道具じゃないだろう。僕が動かないと。僕は多少なら、直せば使える」
「変なの」
「何がだよ」
眠らせてくれと言っているのに、君は壁に凭れ掛かった僕の足の上に乗ってきた。
「変だよ。君は人を気遣うことができるのに、どうして自分を気遣うことができないの?」
「……?」
君の言葉の意味が解らなくて、僕は目を細めた。
「睨まないで、責めてるわけじゃないわ」
言って、離れる。
「ベッド、借りるね。君も一緒に眠れればいいのに」
「僕はここが落ち着くんだ」
僕はここが落ち着くんだ。君の傍にいたら心が軋んで苦して苦しくて堪らないから。
僕はもう一度目を閉じた。
目を瞑ったのに、先程の工場の隙間を抜ける時の君の胸元が思い起こされて、なかなか停止してしまえなかったけど。それは、言わないことにした。
「おかえりなさい」
君はにこにこと言った。
「これで、足りる?」
僕が君に林檎を投げて寄越すと、君は嬉しそうに目を細めてから、その辺にあったタオルで軽く拭いてからそれを頬張った。
「お腹空いてたの。林檎も大好き。噛んだら口一杯に甘いのが広がるわ」
「ふーん」
林檎を丸かじりしながら、君は嬉しそうに言う。
眩しくて、僕は目を逸らした。
「残念だけど、僕に用意できるのはその程度だよ。僕に食料は不要だから、持って帰ってたら怪しまれる。君を匿って、僕は悪い奴だ」
「君がうちに来てくれたらいいのに」
「何言ってるの?」
しゃくしゃくと林檎を頬張りながら、君は何ともないかのように言う。
「うちに来てくれたら、前よりもっと大事にするわ。働き続けて、稼働時間もオーバーして、壊れてしまう。そんなのダメ。折角会えたのに、またお別れなんて寂しいわ」
君が誰のことを言っているのか判らないけれど、僕は、その見たこともない誰かがまた憎らしくなる。
同じ型番だと言うのに、工場での労働ではなくてヒトの家に配置された。それだけでも憎々しい。
それよりも憎々しいのは、僕が君を匿ったところで、君が見ているのは僕と同じ型番の誰かであって、僕じゃない。その事実だ。
そんな誰かの話なんてしないでよ。
そう言いたい。
そんな誰かの話ばかりする君なんて放り出してしまいまい。
そう思う反面、君の笑顔を手放してしまえない。
いつまでここに居座るつもりか知らないけれど、餓死する前に出ていってほしいと思う。
出ていってくれないと、僕にはたぶん、君を手放すことができなさそうだ。
僕はその気持ちを吐き出してしまいたくて、大きく息を吐いた。
機械人形は人手の足りない工場での大事な道具だった。
最初に大量受注しておけば、その分一体のコストは安くなる。
潰れたらそのストックをまた使えばいい。
僕はそんな一つだった。
同じ型番の仲間がたくさん働いていた。
ヒトが便利に生きるための道具を毎日毎日作っている。
機械が機械を作るだなんて滑稽だけれど、そうしないとヒトの暮らしは良くはならない。
僕達機械人形は、ヒトの暮らしをよくするための道具の一つだ。
工場にもヒトは何人か働いていたけれど、ヒトは一度身体と心を壊してしまったらもう戻れないらしい。消えていったヒトタチは、戻ってこなかった。
機械人形もだいぶ潰れた。
僕は昨日のスクラップ置き場を知っていた。
同じ型番のスクラップを持って、何度も捨てに行かされた。
同じモノが積み重なっていくのが怖くて、僕はいつもそれらを離して捨てていた。
僕が完全に壊れてしまったら、誰が捨てに来てくれるのだろうか。
「おかえりなさい」
少し痩せてしまった君が、今日も笑って言う。
僕はいつものように林檎を渡すと、バツが悪くなって目を逸らした。
「帰ってよ」
「どうして? 折角会えたのに、またお別れしなきゃいけないの?」
それは僕じゃないだろ。
腹立たしく思いながら、僕は鼻を鳴らした。
「ダメ。絶対に嫌。お別れするくらいなら、ここで朽ちてしまった方がマシだわ」
君が真っ直ぐ僕を見て言う。
僕はその視線が苦しくて、ベッドにごろりと横になった。
「今日は一緒に眠ってくれるのね!」
君の嬉しそうな声が聞こえる。
別に一緒に眠ろうと思ったわけじゃない。
ただ、君が僕じゃない誰かを想い続けているという事実が疎ましくて疎ましくて、それを誤魔化すために目を瞑りたかっただけだ。
ベッドで横になった僕に、君がそっと寄り添ってくる。
背中に柔らかな膨らみがあたって、ある筈のない心の臓がびくりと跳ねた。
どきどきと苦しくて、僕は眠れないままじっとしていた。
暫くすると君は呑気に寝息を立て始める。
自分ばかりが意識しているという事実を突き付けられることは、とても、しんどかった。
朝、重みを感じて目を覚ます。
いや、まだ朝じゃない。
まだ、外は暗いままだった。
僕が目を開けると、君は僕の上に馬乗りになって、じっと僕を見つめていた。
「なに?」
僕がぶっきらぼうに聞くと、君は真剣な目で言った。
「どうして? どうして君は私が判らないの?」
何を言っているのか解らない。
僕は完成してすぐにここにやってきた。
君を知っているわけがない。
そんな僕の口元を君の指が触れてくる。
何度も何度も擦ってくるその行為は、あぁ、これが愛撫というヒトがする行為なのか、と、何となく思った。
「私は一目で判ったのに。どうして君は判ってくれないの?」
僕は君を知らないよ。
けれど、言ってしまえない。
どうして? どうしてその一言が言えないんだ?
「ねぇ、逃げよう。君が壊れてしまう前に。君は私に帰ってと言った。なら、私は君を連れて帰る。今度は大事にする。本当よ」
何故だろう。
今日はその言葉を憎々しく感じることはなくて、僕は、上体を起こした。
君はすぐに抱きついてきて、唇に触れた。
僕はそれに甘んじながら、それでも、自分から返すことはしなかった。
君の柔らかな唇が何度も僕の口元に触れる。
ヒトはそれをキスと呼ぶ。知識としてインプットされてはいるけれど、実際それを受けるのはもちろん初めてのことで、僕は適切な対処の仕方が判らなかった。
判らないと、思っていた。
それなのに、何度も何度も君が唇を求めてきて、僕は、口を開いた。
舌を絡めてみる。
君はすぐに舌を絡め返して、何度か僕の舌に吸い付いてから離れた。
君の唾液が糸を引く。
僕はその不思議な糸が自分の口元と繋がっているのを、ぼんやりと眺めていた。
「帰ろう、一緒に」
「無理だよ、明日も仕事がある」
「壊れてしまったらどうするの」
「また新しいモノが届くさ」
「そうだね、工場に君の替えはきっとたくさん居るよ。君は確かに大事な人員だけど、壊れたところで、新しいモノを使えば済む。でも、私にとっては、君は君しかいないの。だから、壊れてしまうなんて、許さないんだから」
どうして?
どうしてそんな泣きそうな目で言うの?
僕はその理由を知っている気がするのに、記録に靄が掛かって、思い出せなかった。
結論から言うと、僕はほどなくして壊れてしまった。
過剰労働による内部基盤の破損。
直して使い続けることもできなくはない。けれど、破損箇所が多すぎて、コストが掛かる。
廃棄が決定した。
君が僕を盗み出して一生懸命背負って歩いていく。
壊れてしまった僕はぼんやりとした頭で、動くこともできないまま、君の背中にいた。
スクラップの山の横を延々と歩いていく。
そうまでして僕を連れていく意味が解らない。
隣はスクラップの山。
その瓦礫の中に、僕も加えてくれればいい。
そのうち燃料が尽きて、強制停止する。それで僕は、やっと、働くことから解放されるんだ。
「もうちょっとで、うちに着くから」
君が泣きそうな声で言う。
「ばか。私のばか。早くこうしていればよかった。どうしよう。まだ壊れてしまわないで。もうちょっとだから」
君の声が心地好くて、僕は、そのまま意識を手放した。


工業地帯を抜けて暫く行くと、古ぼけた家がある。
ただの家じゃない。
それは機械人形やヒトを修理する家だった。
「ただいま。おじいちゃん、やっと見つけたの。直してあげて。もうボロボロなの」
少女が泣きながら言う。
おじいちゃんと呼ばれた老人が机を指差す。
少女はそこに背負っていた青年を横たえてやると、老人に鍵を渡した。
「機械の部分が停止しかけて、ヒトの部分を圧迫してる。このままじゃ心臓が止まっちゃう。ねぇ、助けて」
老人は少女を優しく撫でると、よく見つけてきたね、と、一言、漏らすように言ってから、青年の腹に鍵を差し込んで身体を開いた。
ぎっしりと詰まった機械は、ほぼ停止していた。
停止してしまっている機械を退けると、僅かに残る人間の部位がいくつか露出する。
まだ、心臓は弱々しくだが動いている。
「型番は合わないが、仮の人工臓器に繋いでおこう。臓器が完全に停止してしまう前に壊れてしまった機械を直してしまわないと、生きている臓器まで死んでしまう」
「やだ。やだ。絶対にやだ。折角会えたのに」
「そうだね、よく見つけてきたね、いいこだ」
老人はまた少女の頭を撫でると、壊れた機械の修理に取り掛かった。


「おはよう」
君の声で目を覚ます。
身体は動かない。
首だけを何とか動かすと、工場と周辺の街並みしか知らない筈なのに、それは見覚えのある古ぼけた家の中だった。
「ごめんなさい、今は機械の電源を切ってあるの。仮の機械だから無理に稼働すると身体に負担が掛かってしまうから」
君は申し訳なさそうに目を逸らす。
「おじいちゃんが直してくれてるから、大丈夫よ」
「おじい、ちゃん……?」
僕の口から弱々しい声が出る。
どうやらまともに声も出せないらしい。
それでも、壊れてしまった後で、スクラップになるはずだったことを考えると、声が出るだけマシなのかもしれない。
「良かった……、造ったパーツ以外はちゃんと元の身体が残っていて……、造ったパーツを直すだけだから、間違えて殺してしまうこともない……。今は臓器を維持できるぎりぎりの機械しか付けてないけれど、ちゃんと、全部戻して差し替えるから、安心して」
言っていることが解らなくて、僕は首を傾げる。
「ねぇ、本当に覚えてないの?」
君は泣きそうな声で言う。
「それとも、私が大きくなっちゃったから、判らないだけなの?」
君の目からぽろりと雫が落ちる。
「君を見つけるためにいろんな工場に不法侵入して、追い掛けられて、大変だったのに、君は私を忘れてしまったんだ」
君の目から次々と雫が溢れ出すのに、僕は首以外を動かすことができなくて、拭ってあげることもできなかった。
身体に機械が埋め込み直されて、僕はベッドに移されていた。
ぎしぎしと痛む身体を起き上がらせると、君はすぐにやって来て、隣に座った。
「調子はどう?」
「それ、僕の身体がこうなってすぐにも、聞いてきた気がする」
僕が頭を撫でると、君は嬉しそうに笑った。
「ごめんなさい、ごめんなさい。君の身体がボロボロになってしまったのに、機械を埋め込んでまで生かしてしまって。怒ってる?」
「怒ってないよ」
僕は辺りを見渡した。
機械人形には型番がある。
もちろん、その型番には、元となる外見の人間がいる。
それが僕だった。
僕の身体は何度も開かれ、何度も型を取られ、それを繰り返すうちに内臓が傷んできた。
小さな女の子が駄々を捏ねた。
お兄ちゃんを殺さないで。
その言葉に、傷んだ内臓の代わりに人工臓器を埋め込んで、機械で制御し、もう一度生かされることが決まった。
僕は幸せだった。
中身を弄ばれるだけ弄ばれて死んでいく筈だったのに、もう一度、生きることができることが。
僕は女の子のために生きようと決めた。
それなのに、暫く経つと、僕を再生させたという事実を聞き付けたヒトが、僕を連れて行ってしまった。
僕はまたデータを取られる日々を送り、データが集まると廃棄される筈だった。
廃棄する前に実験をしよう。
そう言った男の声を覚えている。
脳に埋め込んであったチップを初期化し書き換えて、同じ型番が働く工場で機械人形と同じように使い続けてみよう。そうすれば、また新しいデータが手に入る。棄てるのはそれからでも遅くない。
そうして僕は気が付いたらずっと、あの工場で働く機械人形となっていた。
自分がまだ半分はヒトであるはずなのに、それを忘れてしまっていた。
それはきっと、埋め込まれたチップのせいだけではないと思う。
同じ環境で働き続けることを運命付けられて、そこから一生逃れられないのだと思うことで、自分の記憶を上書きしてしまっていたのだと思う。
逃れたいと思い続けながらそれを続けることは、心を壊してしまうからだ。僕は僕を壊してしまわないように、逃れたい、帰りたい、そういう気持ちもなかったことにした。
もう数年間、僕はずっと自分を騙しながら生きてきたんだ。
小さな女の子は、いつの間にか大きくなっていた。
「君を探せるようになったのは、去年からなの。そろそろ廃棄だ、工場から引き上げなければ、そういう噂を聞いて、君が工場で働く機械人形として使われていることが判ったの。私、仕事の合間にずっと探して、やっと、やっと会えたんだよ」
最初、嬉しそうな声で言っていたのに、いつの間にかまた、泣きそうな声になっている。
そんな君の頭を撫でると、君は泣きそうな顔で笑った。
「ずっと会いたかったの。実験の合間にいつも遊んでくれて嬉しかった。私が君にずっと恋していたことを、伝えたかった。だから幼い私はボロボロになってしまった君を無理に生かしたいと思ってしまった。折角君がまた笑ってくれたのに、すぐに君は居なくなってしまった……、」
君の目からぽろぽろと雫が溢れ出す。
「おかえりなさい、って、あの小さな部屋で言えたとき、すごく、幸せだった……。家に帰ってきてくれたわけじゃないけど、それでも、ずっとおかえりなさいって、言いたかった……。そしたら君は、林檎をくれた……。覚えてないかもしれないけど、お兄ちゃんが作ってくれたうさぎさんを食べるのが、私、大好きだったんだよ……、」
泣きながら、恥ずかしくなったのか君は真っ赤な顔でそっぽを向いた。
僕はそんな君を引き寄せると、柔らかな唇に唇を重ねた。
半開きになった口に舌を入れて絡めると、少しだけ、しょっぱくて、忘れていた筈の味覚を思い出したような気がした。
そうして僕は、この家の住人になった。
暫くは何もせずに休んでいたのだけれど、数年間働き続けていたせいか、何もせずにいることが逆にしんどくて、僕はおじいちゃんに修理を習って、手伝いをすることにした。
まだ、君をちゃんと抱きしめてあげられていないけれど、僕が昔の僕を憎々しく感じなくなった時、心から抱きしめたいと思うよ。
それまでもう少しだけ、待っていてほしいな。
おしまい


君が恋をしていたのは紛れもなく僕で、君に恋していたのは、きっと、僕だった。
2017年8月22日05:50投稿。
※現在pixivでも掲載中です、追々pixivでは削除する予定です
僕は壊れてしまったから
君の手で棄ててほしかったんだ
自分が壊れたことも解らなくて
蔑むような瞳が怖くて
全ての声が脳髄を蝕んで
もう
誰も彼も蔑ろだ
それなのに、
どうして心が焼き切れても
壊れていくばかりで
完全に止まってしまえないんだろう
君に恋をしたのは一体誰だったんだろうね。そんなお話。
蒸気で熱を帯びた工場の群れを擦り抜けて、僕は君の手を引っ張って走っていく。
君は工業地帯に不釣り合いな真っ白のワンピースを着て、追われていると言うのに笑っていた。
細い工場と工場の隙間に何とか滑り込むと、横向きになってじりじりと移動する。
君は僕に続くけれど、胸元が壁に擦れて顔を歪めながらだった。
逃げていると言うのに、ある筈のない心の臓がどくりと波打つ。
そうして工場を抜けると、そこには大量の鉄屑が積み重なって山となり、その上にはくすんだ星空が広がっていた。
「きっともう来ないよ」
君は笑って言う。
「だといいね」
僕が呆れたように返すと、君はくるくる回ってワンピースをふわふわと舞わせた。
君は自分には罪など存在しないとでも言うように笑って、手を差し出してきた。
「ねぇ、君の家を教えて」
「匿えってこと?」
嫌だな。
僕は鼻を鳴らす。
「家なんてないよ。来た道を戻れば工場の寮に戻れる。いいの? 見つかってしまうよ?」
「見つからないよ、二人で帰ろう」
君は呑気だ。
追われているということを自覚しているのだろうか。
「君を匿ったら僕は罪人だ」
「違うよ、君は迷子の女の子を保護してくれた優しい人だよ」
君は言うと、僕の手をぎゅっと握った。
僕は溜め息を吐く。
もういいや、逃げるのも疲れてしまった。
明日も仕事。早く帰って眠りたい。
ベッドに一人ばかり増えたところで狭いとも思わないだろうけれど、その柔らかな膨らみを思うと、きっと眠れないのだろうと思う。
僕は君が何処から来たのか何となく判っているけれど、敢えてそれを言及しようとは思わなかった。
君がどれほどの決意でこんな場所まで逃げてきたのかなんて知りもしないけど。
もしかしたら、本当に呑気に観光をしに来ただけなのかもしれない。
そうだとしたら、それで追われた僕は、追われ損な気がした。
「会いたかったよ」
君がぎゅっと手を握って言うのに、僕は首を傾げた。
「一目で判ったよ、君が君だって」
誰かと勘違いしているのだろう。
別にそれは珍しいことではない。
だから、ふーん、それだけ素っ気なく返して、僕はその手を振りほどいた。
「どこにいくの?」
「帰るんだよ、僕は明日も仕事なんだ」
「じゃあ、ついていくね」
「……、勝手にすれば。でももし次に見つかったら、僕はもう知らんぷりをするよ」
「また、一緒だね」
君は嬉しそうに笑って言う。
普段は間違えられることに何とも思わないのに、今は、君のその笑顔が憎々しかった。
その嬉しげな君が見つめているのは僕じゃない。
僕じゃない誰かが、僕は、憎々しくて、憎々しくて、堪らなかった。
僕は君の手を取らなかった。
君なんて知らんぷりして、歩いていく。
そんな僕に君は嬉しそうについてくる。
君は不思議だ。
そもそも、ヒトと言うのは不思議な生き物だ。
僕はそれを知っている。
だから、そんなに気にすることはないのかもしれない。
それでも僕は、君の笑顔が不思議で、不思議で、心の臓のある辺りがどくどくと苦しくなる。
そんな気持ちに気付かないふりをして、寮までの道を歩いていく。
別に引き返せば良かったのに、わざわざ違う工場の隣を選んで歩いていく。
そうして遠回りして、僕は僕の手を働く工場の隣にある寮までやってきた。
もう、皆眠っているはずだ。
僕も早く眠りたい。
そっと音を立てないように僕が入ると、するりっ、君は扉が閉まる前に一緒に入ってきた。
「君の部屋はどこ?」
嬉しそうに君はいろんな部屋の戸を見ている。
寮なんて同じ部屋の集まりなのに、君はこういう暮らしを知らないからそれが楽しくて楽しくて堪らないんだろうな。
生産させられる側に生まれなかったから、君はそんな嬉しそうに笑えるんだろうな。
僕は嗤った。
生まれたときからこの工場で働き続けることが決定していた自分は、なんて馬鹿馬鹿しい存在なのだろう。
「こっち」
あまりうろちょろされても不都合なので、僕はやっとその手を取ると、自分の部屋へと連れて入った。
寮の部屋は簡素だ。
安物のベッドと、机が一つ。椅子も安物。電気が通っているだけありがたい。
僕はぱちりと電気を点けると、着たままだった作業着を脱ぎ捨てて上半身を曝け出した。
「見ないでよ」
じっとこちらを見てくる視線が疎ましくて僕が君を睨み付けると、君は慌てて後ろを向いた。
それを見て、僕は小さく溜め息を吐いた。
僕は身体をタオルで拭ってから、腹部にある鍵穴に鍵を差し込んで、身体を開けた。
かしゃんっ、音がして、僕が開く。
無理して走ったからだろう、少し、調子がおかしい。
本当は報告して直してもらうべきなのだろうけど、直してもらって、また寿命が延びて、働く期限が増えてしまうのは、馬鹿馬鹿しかった。
僕は機械の詰まった腹に雑に油を注すと、身体を閉じてその辺にあったシャツを着た。
僕は壁に凭れて目を瞑る。
「ベッド、使えば」
「君は?」
「眠れれば、どこでもいい」
一緒に眠ってしまったら、腕の中にいる可愛らしい生き物に、心が軋んでしまいそうになる。
「調子悪いの? それとも夜の日課なの?」
君は勝手に油を拾い上げて見つめる。
「僕の身体はあまり走るのに適していないんだ。普段は工場の同じ場所で同じモノを作り続けるだけだからね」
「私のせいね」
「そうだよ」
僕は短く言う。
それに何か言いたげに君は口を開くけれど、すぐに閉じてしまった。
「眠らせてくれないか。ただでさえ人員が足りなくて工場での稼働時間がオーバーしてるんだ、多大にね。それに加えて、君に出会ったせいで身体に負荷が掛かった。一度停止しないと明日動けない」
「明日は休んでしまったら?」
君は呑気だ。
「休めるならとっくに休んでるよ。人員が足りない。僕が動かないと、ヒトが壊れてしまう。君達は直せば使える道具じゃないだろう。僕が動かないと。僕は多少なら、直せば使える」
「変なの」
「何がだよ」
眠らせてくれと言っているのに、君は壁に凭れ掛かった僕の足の上に乗ってきた。
「変だよ。君は人を気遣うことができるのに、どうして自分を気遣うことができないの?」
「……?」
君の言葉の意味が解らなくて、僕は目を細めた。
「睨まないで、責めてるわけじゃないわ」
言って、離れる。
「ベッド、借りるね。君も一緒に眠れればいいのに」
「僕はここが落ち着くんだ」
僕はここが落ち着くんだ。君の傍にいたら心が軋んで苦して苦しくて堪らないから。
僕はもう一度目を閉じた。
目を瞑ったのに、先程の工場の隙間を抜ける時の君の胸元が思い起こされて、なかなか停止してしまえなかったけど。それは、言わないことにした。
「おかえりなさい」
君はにこにこと言った。
「これで、足りる?」
僕が君に林檎を投げて寄越すと、君は嬉しそうに目を細めてから、その辺にあったタオルで軽く拭いてからそれを頬張った。
「お腹空いてたの。林檎も大好き。噛んだら口一杯に甘いのが広がるわ」
「ふーん」
林檎を丸かじりしながら、君は嬉しそうに言う。
眩しくて、僕は目を逸らした。
「残念だけど、僕に用意できるのはその程度だよ。僕に食料は不要だから、持って帰ってたら怪しまれる。君を匿って、僕は悪い奴だ」
「君がうちに来てくれたらいいのに」
「何言ってるの?」
しゃくしゃくと林檎を頬張りながら、君は何ともないかのように言う。
「うちに来てくれたら、前よりもっと大事にするわ。働き続けて、稼働時間もオーバーして、壊れてしまう。そんなのダメ。折角会えたのに、またお別れなんて寂しいわ」
君が誰のことを言っているのか判らないけれど、僕は、その見たこともない誰かがまた憎らしくなる。
同じ型番だと言うのに、工場での労働ではなくてヒトの家に配置された。それだけでも憎々しい。
それよりも憎々しいのは、僕が君を匿ったところで、君が見ているのは僕と同じ型番の誰かであって、僕じゃない。その事実だ。
そんな誰かの話なんてしないでよ。
そう言いたい。
そんな誰かの話ばかりする君なんて放り出してしまいまい。
そう思う反面、君の笑顔を手放してしまえない。
いつまでここに居座るつもりか知らないけれど、餓死する前に出ていってほしいと思う。
出ていってくれないと、僕にはたぶん、君を手放すことができなさそうだ。
僕はその気持ちを吐き出してしまいたくて、大きく息を吐いた。
機械人形は人手の足りない工場での大事な道具だった。
最初に大量受注しておけば、その分一体のコストは安くなる。
潰れたらそのストックをまた使えばいい。
僕はそんな一つだった。
同じ型番の仲間がたくさん働いていた。
ヒトが便利に生きるための道具を毎日毎日作っている。
機械が機械を作るだなんて滑稽だけれど、そうしないとヒトの暮らしは良くはならない。
僕達機械人形は、ヒトの暮らしをよくするための道具の一つだ。
工場にもヒトは何人か働いていたけれど、ヒトは一度身体と心を壊してしまったらもう戻れないらしい。消えていったヒトタチは、戻ってこなかった。
機械人形もだいぶ潰れた。
僕は昨日のスクラップ置き場を知っていた。
同じ型番のスクラップを持って、何度も捨てに行かされた。
同じモノが積み重なっていくのが怖くて、僕はいつもそれらを離して捨てていた。
僕が完全に壊れてしまったら、誰が捨てに来てくれるのだろうか。
「おかえりなさい」
少し痩せてしまった君が、今日も笑って言う。
僕はいつものように林檎を渡すと、バツが悪くなって目を逸らした。
「帰ってよ」
「どうして? 折角会えたのに、またお別れしなきゃいけないの?」
それは僕じゃないだろ。
腹立たしく思いながら、僕は鼻を鳴らした。
「ダメ。絶対に嫌。お別れするくらいなら、ここで朽ちてしまった方がマシだわ」
君が真っ直ぐ僕を見て言う。
僕はその視線が苦しくて、ベッドにごろりと横になった。
「今日は一緒に眠ってくれるのね!」
君の嬉しそうな声が聞こえる。
別に一緒に眠ろうと思ったわけじゃない。
ただ、君が僕じゃない誰かを想い続けているという事実が疎ましくて疎ましくて、それを誤魔化すために目を瞑りたかっただけだ。
ベッドで横になった僕に、君がそっと寄り添ってくる。
背中に柔らかな膨らみがあたって、ある筈のない心の臓がびくりと跳ねた。
どきどきと苦しくて、僕は眠れないままじっとしていた。
暫くすると君は呑気に寝息を立て始める。
自分ばかりが意識しているという事実を突き付けられることは、とても、しんどかった。
朝、重みを感じて目を覚ます。
いや、まだ朝じゃない。
まだ、外は暗いままだった。
僕が目を開けると、君は僕の上に馬乗りになって、じっと僕を見つめていた。
「なに?」
僕がぶっきらぼうに聞くと、君は真剣な目で言った。
「どうして? どうして君は私が判らないの?」
何を言っているのか解らない。
僕は完成してすぐにここにやってきた。
君を知っているわけがない。
そんな僕の口元を君の指が触れてくる。
何度も何度も擦ってくるその行為は、あぁ、これが愛撫というヒトがする行為なのか、と、何となく思った。
「私は一目で判ったのに。どうして君は判ってくれないの?」
僕は君を知らないよ。
けれど、言ってしまえない。
どうして? どうしてその一言が言えないんだ?
「ねぇ、逃げよう。君が壊れてしまう前に。君は私に帰ってと言った。なら、私は君を連れて帰る。今度は大事にする。本当よ」
何故だろう。
今日はその言葉を憎々しく感じることはなくて、僕は、上体を起こした。
君はすぐに抱きついてきて、唇に触れた。
僕はそれに甘んじながら、それでも、自分から返すことはしなかった。
君の柔らかな唇が何度も僕の口元に触れる。
ヒトはそれをキスと呼ぶ。知識としてインプットされてはいるけれど、実際それを受けるのはもちろん初めてのことで、僕は適切な対処の仕方が判らなかった。
判らないと、思っていた。
それなのに、何度も何度も君が唇を求めてきて、僕は、口を開いた。
舌を絡めてみる。
君はすぐに舌を絡め返して、何度か僕の舌に吸い付いてから離れた。
君の唾液が糸を引く。
僕はその不思議な糸が自分の口元と繋がっているのを、ぼんやりと眺めていた。
「帰ろう、一緒に」
「無理だよ、明日も仕事がある」
「壊れてしまったらどうするの」
「また新しいモノが届くさ」
「そうだね、工場に君の替えはきっとたくさん居るよ。君は確かに大事な人員だけど、壊れたところで、新しいモノを使えば済む。でも、私にとっては、君は君しかいないの。だから、壊れてしまうなんて、許さないんだから」
どうして?
どうしてそんな泣きそうな目で言うの?
僕はその理由を知っている気がするのに、記録に靄が掛かって、思い出せなかった。
結論から言うと、僕はほどなくして壊れてしまった。
過剰労働による内部基盤の破損。
直して使い続けることもできなくはない。けれど、破損箇所が多すぎて、コストが掛かる。
廃棄が決定した。
君が僕を盗み出して一生懸命背負って歩いていく。
壊れてしまった僕はぼんやりとした頭で、動くこともできないまま、君の背中にいた。
スクラップの山の横を延々と歩いていく。
そうまでして僕を連れていく意味が解らない。
隣はスクラップの山。
その瓦礫の中に、僕も加えてくれればいい。
そのうち燃料が尽きて、強制停止する。それで僕は、やっと、働くことから解放されるんだ。
「もうちょっとで、うちに着くから」
君が泣きそうな声で言う。
「ばか。私のばか。早くこうしていればよかった。どうしよう。まだ壊れてしまわないで。もうちょっとだから」
君の声が心地好くて、僕は、そのまま意識を手放した。
工業地帯を抜けて暫く行くと、古ぼけた家がある。
ただの家じゃない。
それは機械人形やヒトを修理する家だった。
「ただいま。おじいちゃん、やっと見つけたの。直してあげて。もうボロボロなの」
少女が泣きながら言う。
おじいちゃんと呼ばれた老人が机を指差す。
少女はそこに背負っていた青年を横たえてやると、老人に鍵を渡した。
「機械の部分が停止しかけて、ヒトの部分を圧迫してる。このままじゃ心臓が止まっちゃう。ねぇ、助けて」
老人は少女を優しく撫でると、よく見つけてきたね、と、一言、漏らすように言ってから、青年の腹に鍵を差し込んで身体を開いた。
ぎっしりと詰まった機械は、ほぼ停止していた。
停止してしまっている機械を退けると、僅かに残る人間の部位がいくつか露出する。
まだ、心臓は弱々しくだが動いている。
「型番は合わないが、仮の人工臓器に繋いでおこう。臓器が完全に停止してしまう前に壊れてしまった機械を直してしまわないと、生きている臓器まで死んでしまう」
「やだ。やだ。絶対にやだ。折角会えたのに」
「そうだね、よく見つけてきたね、いいこだ」
老人はまた少女の頭を撫でると、壊れた機械の修理に取り掛かった。
「おはよう」
君の声で目を覚ます。
身体は動かない。
首だけを何とか動かすと、工場と周辺の街並みしか知らない筈なのに、それは見覚えのある古ぼけた家の中だった。
「ごめんなさい、今は機械の電源を切ってあるの。仮の機械だから無理に稼働すると身体に負担が掛かってしまうから」
君は申し訳なさそうに目を逸らす。
「おじいちゃんが直してくれてるから、大丈夫よ」
「おじい、ちゃん……?」
僕の口から弱々しい声が出る。
どうやらまともに声も出せないらしい。
それでも、壊れてしまった後で、スクラップになるはずだったことを考えると、声が出るだけマシなのかもしれない。
「良かった……、造ったパーツ以外はちゃんと元の身体が残っていて……、造ったパーツを直すだけだから、間違えて殺してしまうこともない……。今は臓器を維持できるぎりぎりの機械しか付けてないけれど、ちゃんと、全部戻して差し替えるから、安心して」
言っていることが解らなくて、僕は首を傾げる。
「ねぇ、本当に覚えてないの?」
君は泣きそうな声で言う。
「それとも、私が大きくなっちゃったから、判らないだけなの?」
君の目からぽろりと雫が落ちる。
「君を見つけるためにいろんな工場に不法侵入して、追い掛けられて、大変だったのに、君は私を忘れてしまったんだ」
君の目から次々と雫が溢れ出すのに、僕は首以外を動かすことができなくて、拭ってあげることもできなかった。
身体に機械が埋め込み直されて、僕はベッドに移されていた。
ぎしぎしと痛む身体を起き上がらせると、君はすぐにやって来て、隣に座った。
「調子はどう?」
「それ、僕の身体がこうなってすぐにも、聞いてきた気がする」
僕が頭を撫でると、君は嬉しそうに笑った。
「ごめんなさい、ごめんなさい。君の身体がボロボロになってしまったのに、機械を埋め込んでまで生かしてしまって。怒ってる?」
「怒ってないよ」
僕は辺りを見渡した。
機械人形には型番がある。
もちろん、その型番には、元となる外見の人間がいる。
それが僕だった。
僕の身体は何度も開かれ、何度も型を取られ、それを繰り返すうちに内臓が傷んできた。
小さな女の子が駄々を捏ねた。
お兄ちゃんを殺さないで。
その言葉に、傷んだ内臓の代わりに人工臓器を埋め込んで、機械で制御し、もう一度生かされることが決まった。
僕は幸せだった。
中身を弄ばれるだけ弄ばれて死んでいく筈だったのに、もう一度、生きることができることが。
僕は女の子のために生きようと決めた。
それなのに、暫く経つと、僕を再生させたという事実を聞き付けたヒトが、僕を連れて行ってしまった。
僕はまたデータを取られる日々を送り、データが集まると廃棄される筈だった。
廃棄する前に実験をしよう。
そう言った男の声を覚えている。
脳に埋め込んであったチップを初期化し書き換えて、同じ型番が働く工場で機械人形と同じように使い続けてみよう。そうすれば、また新しいデータが手に入る。棄てるのはそれからでも遅くない。
そうして僕は気が付いたらずっと、あの工場で働く機械人形となっていた。
自分がまだ半分はヒトであるはずなのに、それを忘れてしまっていた。
それはきっと、埋め込まれたチップのせいだけではないと思う。
同じ環境で働き続けることを運命付けられて、そこから一生逃れられないのだと思うことで、自分の記憶を上書きしてしまっていたのだと思う。
逃れたいと思い続けながらそれを続けることは、心を壊してしまうからだ。僕は僕を壊してしまわないように、逃れたい、帰りたい、そういう気持ちもなかったことにした。
もう数年間、僕はずっと自分を騙しながら生きてきたんだ。
小さな女の子は、いつの間にか大きくなっていた。
「君を探せるようになったのは、去年からなの。そろそろ廃棄だ、工場から引き上げなければ、そういう噂を聞いて、君が工場で働く機械人形として使われていることが判ったの。私、仕事の合間にずっと探して、やっと、やっと会えたんだよ」
最初、嬉しそうな声で言っていたのに、いつの間にかまた、泣きそうな声になっている。
そんな君の頭を撫でると、君は泣きそうな顔で笑った。
「ずっと会いたかったの。実験の合間にいつも遊んでくれて嬉しかった。私が君にずっと恋していたことを、伝えたかった。だから幼い私はボロボロになってしまった君を無理に生かしたいと思ってしまった。折角君がまた笑ってくれたのに、すぐに君は居なくなってしまった……、」
君の目からぽろぽろと雫が溢れ出す。
「おかえりなさい、って、あの小さな部屋で言えたとき、すごく、幸せだった……。家に帰ってきてくれたわけじゃないけど、それでも、ずっとおかえりなさいって、言いたかった……。そしたら君は、林檎をくれた……。覚えてないかもしれないけど、お兄ちゃんが作ってくれたうさぎさんを食べるのが、私、大好きだったんだよ……、」
泣きながら、恥ずかしくなったのか君は真っ赤な顔でそっぽを向いた。
僕はそんな君を引き寄せると、柔らかな唇に唇を重ねた。
半開きになった口に舌を入れて絡めると、少しだけ、しょっぱくて、忘れていた筈の味覚を思い出したような気がした。
そうして僕は、この家の住人になった。
暫くは何もせずに休んでいたのだけれど、数年間働き続けていたせいか、何もせずにいることが逆にしんどくて、僕はおじいちゃんに修理を習って、手伝いをすることにした。
まだ、君をちゃんと抱きしめてあげられていないけれど、僕が昔の僕を憎々しく感じなくなった時、心から抱きしめたいと思うよ。
それまでもう少しだけ、待っていてほしいな。
おしまい
君が恋をしていたのは紛れもなく僕で、君に恋していたのは、きっと、僕だった。
タグ:2017
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11627062
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック